症例1:60歳,女性.3回の心臓カテーテル(以下心カテ)施行後,右胸背部に紅斑びらんが出現.さらに1回の心カテ施行後,右胸部に硬結,潰瘍が出現.症例2:68歳,女性.3回の心カテ施行後,右胸部に紅斑が出現.さらに2回の心カテ施行後,同部に硬結,潰瘍が出現.症例3:61歳,男性.4回の肝動脈塞栓術(transcatheter arterial embolization,以下TAE)施行後,右背部に鱗屑痂皮を伴う紅斑が出現.X線合計被曝線量は,症例1が58.5Gy,症例2が45.5Gy症例3が495.4mGy.心カテの手技には大別して冠動脈造影(coronary angiography;CAG)と経皮的冠動脈形成術(percutaneous transluminal coronary angioplasty;PTCA)がある.心カテ施行時には大量のX線が照射され,そのために放射線皮膚炎を起こす症例が1990年代後半より報告され始めた.一方,肝細胞癌に対して肝動脈造影下に行うTAEではX線照射量が少なく,放射線皮膚炎の発症はきわめて稀である.
雑誌目次
臨床皮膚科54巻5号
2000年04月発行
雑誌目次
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000
1 最近話題の皮膚疾患
Paraneoplastic pemphigus
著者: 石井美奈 , 藤原浩 , 伊藤雅章
ページ範囲:P.11 - P.13
症例:59歳,男性.1995年4月頃より,舌痛と口腔内びらんが出現.ステロイドの全身投与に反応せず,結膜炎,陰部のびらん,上肢に水疱も出現した.組織像,蛍光抗体法所見よりparaneoplastic pemphigusと診断した.縦隔腫瘍摘出後,粘膜,皮膚病変とも軽快傾向を示した.現在はプレドニゾロン,シクロスポリン内服中である.Para—neoplastic pemphigusは,1990年Anhaltらによって提唱された疾患概念である.主として血液系の悪性腫瘍を伴い,臨床的に口腔粘膜が強く侵されることが特徴的であり,組織学的所見,蛍光抗体法所見などにより診断可能である.この患者血清はdesmopla—kin 1, BPAG 1, envoplakin, periplakinなど多彩な抗原と反応する.今回,我々は患者血清がplakoglobinにも反応することを見いだした.
種痘様水疱症とEpstein-Barrウイルス感染
著者: 峰咲幸哲 , 本田まりこ , 新村眞人 , 横井清
ページ範囲:P.15 - P.20
種痘様水疱症様皮疹を繰り返し,発熱や肝機能障害などの全身症状を伴った慢性活動性Epstein-Barrウイルス感染症(chronic active Epstein-Barr virus infection:CAEBV)の14歳,男児例を報告した.顔面の丘疹の病理組織所見は,表皮から真皮中層にかけての壊死巣とそれを取り囲むように稠密な細胞浸潤がみられ,浸潤細胞の一部は大型で核異型を伴っていた.In situ hybridization法で浸潤細胞の30〜40%はEB virus—encoded small RNAs(EBER)が陽性であり,これらの陽性細胞は免疫組織化学的にCD2が陽性,CD3,CD20は陰性であったことからnatural killer細胞への感染と考えられた.なお,T細胞レセプターβ鎖Cβ1の遺伝子再構成は認めなかった.CAEBVに対する確立した治療法はなく,自験例ではこれまでプレドニゾロンや抗ウイルス剤の投与により軽快,増悪を繰り返しており,現在はプレドニゾロンおよびVP−16の併用投与により経過観察中である.
全身性形質細胞増多症とHHV−8
著者: 岡田裕之 , 加納塁 , 渡辺晋一
ページ範囲:P.21 - P.24
ヒトヘルペスウイルス8型(human herpesvirus 8,以下HHV−8)はIL−6をはじめIL−8レセプターなど各種サイトカインやケモカインの遺伝子ホモログをコードしていることから,Kaposi肉腫をはじめprimary effusion lymphoma(PEL)やCastleman病の発生に深く関与していると考えられている.われわれはCastleman病の類縁疾患とされる全身性形質細胞増多症(systemic plasmacytosis,以下SP)においてもHHV−8がその発生に関与しているかを明らかにする目的で,当科で経験したSPの4症例について組織内のHHV−8遺伝子の有無をPCR法を用いて検索した.結果は全例でHHV−8遺伝子は検出されなかった.AIDS患者にSPの報告例がないことや日本人以外での報告がきわめて少ないことなども合わせるとSPの発症にHHV−8が関与している可能性は低いと考えられた.
Pasteurella皮膚感染症—コンパニオンアニマルとのzoonosis
著者: 原弘之 , 森嶋隆文 , 荒島康友
ページ範囲:P.25 - P.29
日本大学板橋病院において過去15年間に分離されたペットのイヌ,ネコから感染したと思われるPasteurella局所化膿症12例について,臨床的,疫学的検討を行った.その結果,中高年,ことに60〜70歳代の高齢者に好発し,受傷部位は手・指が多く,次いで顔面であった.臨床像は,化膿性骨髄炎を併発した1例を除く,全例が膿瘍や蜂窩織炎を呈した.感染源としてイヌとネコからがそれぞれ6例と同数であった.分離されたPasteurella属菌は4種であり,検査技術の向上や関心が高まったためか,菌種の多様化が近年みられた.高齢化が急速に進むわが国では,ペットは家族の一員として扱う人たちが増えている.Pasteurella菌は多くの抗生物質に高い感受性を有するが,まれに死亡例も報告されており,さらに,本感染症の報告は年に25〜35%近い急激な増加を示しており,今後重要なZoonosisとして認識する必要があるものと思われた.
爪甲色素線条を呈する非メラノサイト系腫瘍
著者: 木村俊次
ページ範囲:P.30 - P.34
爪甲色素線条(以下LM)は種々の原因で生じる.腫瘍に伴うLMは従来メラノサイト系の母斑や腫瘍によるとされてきたが,少数ながら非メラノサイト系腫瘍によるLMも報告されている.今回爪下Bowen病による自験2例と,参考症例として爪下有棘細胞癌の1例およびmelanoma in situと老人性角化腫とを合併した1例を呈示するとともに,LMの組織学的背景,LMを呈する非メラノサイト系腫瘍,爪甲変形を伴うLM,Hutchinson徴候を伴うLM,メラノサイト系と非メラノサイト系の併存について考察し,LMの取り扱いと生検・手術時の注意についてもふれた.
2 皮膚疾患の病態
経皮ペプチド免疫によるメラノーマの治療
著者: 瀬尾尚宏
ページ範囲:P.37 - P.41
樹状細胞がナイーブ細胞障害性T細胞(CTL)をプライミングできる強力な抗原提示細胞であることが判明し,腫瘍関連抗原ペプチドでパルスした培養樹状細胞の担癌生体内移入による癌免疫治療法が大きく期待されている.一方皮膚にはLangerhans細胞などの樹状細胞が休止状態で多数常在しているので,これを効率的に活性化し,有効に活用できれば皮膚を介した癌免疫治療が可能となるに違いない.特にメラノーマの場合,他の腫瘍と比較して腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の中にCD8陽性のCTLが多数存在すること,TILからin vitroで抗メラノーマCTLを容易に誘導できること,さらに多数のメラノーマ関連抗原ペプチドが既に同定されていることから,免疫治療の実現可能な腫瘍であると考えられている.本稿では我々のマウス皮膚を用いたメラノーマ特異的CTLの誘導法の他,ヒトへの応用の可能性や問題点について概説する.
抗フォドリン抗体と膠原病
著者: 尹浩信
ページ範囲:P.43 - P.45
膠原病患者血清中には,自己細胞成分と反応する様々な自己抗体が検出され,疾患や病態と密接に関連することが知られている.近年,Sjögren症候群の疾患特異的な自己抗体として抗フォドリン抗体(抗α-fodrin抗体)が見いだされた.α-fodrinは生体内では脳神経細胞や心筋細胞の細胞骨格を構成する蛋白質で240kDテトラマーとして豊富に存在し,同抗体の存在はアポトーシスの同症への関与を示唆するものと考えられている.本稿では抗フォドリン抗体の膠原病における臨床的意義について最近の知見をまとめた.抗フォドリン抗体はSjögren症候群患者血清において高頻度に検出され,特異度も高いと考えられ,同症の血清学的指標になり得るものと考えられた.また新生児エリテマトーデスおよび先天性房室ブロックの血清学的指標になるものと考えられた.
薬疹におけるHHV−6
著者: 橋本公二 , 藤山幹子
ページ範囲:P.46 - P.50
Hypersensitivity syndromeは,1)比較的限られた薬剤が原因,2)原因薬剤の投与開始後2週から6週で発症,3)発熱,4)末梢血の白血球増多,5)肝機能障害,6)皮疹は斑状丘疹型で始まって紅皮症となることが多い,といった臨床的特徴をもつ重症型薬疹である.近年,ヒトヘルペスウイルスの一種で突発性発疹の原因であるHHV−6の再活性化がhypersensitivity syndromeに関与していることが明らかとなってきた.薬疹とウイルス感染が関連する新しい疾患発症機構として注目されている.
ドライスキンによる痒みのメカニズム
著者: 高森建二
ページ範囲:P.52 - P.56
痒みには抗ヒスタミン剤が有効な痒みと無効な痒みがある.ドライスキンを示す疾患の痒みには抗ヒスタミン剤が奏効しないことが多い.本稿では,ドライスキンを示す代表的疾患である老人性乾皮症の痒みメカニズムについて,表皮内神経線維との相関において推察し,動物モデルを用いて神経線維の表皮内侵入メカニズムについて考察した.
アトピー性皮膚炎とケモカイン
著者: 片桐一元 , 波多野豊
ページ範囲:P.57 - P.62
ケモカインは活性化された白血球,線維芽細胞,血管内皮細胞,上皮細胞等種々の細胞から産生され,白血球の遊走を誘導する.特に炎症局所で浸潤細胞から産生されるケモカインはautocrine,paracrine的に病態形成や維持に関与しているものと思われる.我々は,アトピー性皮膚炎患者末梢血単核球を材料としてRT-PCR法を用いてケモカインのmRNA発現を検討した.IL−8,MIP−1αの発現が充進し,RANTESの発現は健常人と差がなかった.治療前後の比較ではIL−8,MIP−1αは皮疹の改善と相関し著明に発現が低下した.同時に行ったサイトカインの発現の比較では明らかな変動は認められず,末梢血単核球の産生するケモカインはアトピー性皮膚炎の皮疹の形成に,もしくは病勢の変動に直接的に関与しているものと思われた.
3 新しい検査法と診断法
デルマトスコープの有用性—臨床的側面から
著者: 小口真司 , 斎田俊明
ページ範囲:P.65 - P.70
色素性皮膚病変に油浸オイルなどを滴下したうえで,デルマトスコープやビデオマイクロスコープを用いて拡大像を観察する方法をデルマトスコピーあるいはepilumines—cence microscopy(ELM)という.肉眼のみでは認識できない各種の所見が明瞭に観察され,診断確定に有用である.われわれは,掌蹠のメラノーマの色素斑部や早期病変がparallel ridge patternと称する独特なELM所見を高率に呈することを見いだしている.この診断法は掌蹠のみでなく,生毛部のメラノーマと色素細胞母斑の鑑別にも有用であり,基底細胞癌,脂漏性角化症,老人性色素斑,血腫などの診断や鑑別にも大いに役立つ.良性か悪性か,診断に迷うことの多い色素性病変の非侵襲的診断法として,今後,皮膚科の日常診療に広く利用されることが望まれる.
尿中単純ヘルペスウイルス抗体検査の有用性
著者: 本田まりこ , 小松崎眞 , 峰咲幸哲 , 新村眞人
ページ範囲:P.71 - P.75
尿中の単純ヘルペスウイルス(herpes simplex viruses,以下HSV)抗体価をHSVの型別,免疫グロブリン別に測定した.対象は感染HSVの型が明らかな患者57例(HSV−1 12例,HSV−2 41例,HSV−1+HSV−2 4例)とHSV感染症の既往がない血清抗体価陰性の者12例で,enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)にて尿中の抗体価を測定した.57例中HSV−1初感染者は2例,HSV−2初感染者は1例である.結果は,HSV感染症の既往がなく,しかもHSVの血清抗体価が陰性であるコントロール群では,全例尿中からHSV抗体が検出されなかったが,HSV型特異的抗原に関係なくHSV−1およびHSV−2感染者の全例に尿中の抗HSV-IgG抗体は陽性を示した.抗HSV-IgA抗体は,感染HSV型の抗原を使用した場合,HSV−1感染患者では,全例に,再発型のHSV−2感染患者では40例中35例(87.5%)に陽性を示し,型の異なる抗原ではその陽性率は低下した.HSV−1およびHSV−2の初感染患者では早期に著しい抗HSV-IgA抗体の上昇がみられた.尿中の型特異的IgA抗体が1.000以上で,IgA/IgG比が1.0以上のものは,初感染であると考えてよい.また,検出された尿中の抗HSV-IgA抗体は二量体であった.
皮膚腫瘍の超音波診断—パワードプラ法によるメラノーマの診断と鑑別
著者: 清原祥夫
ページ範囲:P.77 - P.82
皮膚腫瘍の良性・悪性の鑑別,とくにメラノーマの診断におけるパワードプラ法の有用性について検討した.最近,我々が種々の皮膚良性および悪性腫瘍の原発,巣,転移巣においてその病巣内の血流信号について超音波診断のパワードプラ法(あるいはカラードプラ法)を用いて観察したところ,良性腫瘍と悪性腫瘍の問にその流速と分布状況に違いが認められた.すなわち血流信号が悪性腫瘍の約90%に検出され,一方,良性腫瘍や表皮内癌では95%以上で検出されなかった.さらにメラノーマの原発巣および転移巣ではより高率にかつ豊富に血流信号が検出され,特徴的な分布パターンが認められた.以上から本法はその診断精度が高いだけでなく,非侵襲的で簡便なことや米粒大のin-transit転移巣のような小さな病巣の診断にも有用であることなど,メラノーマの画像診断法として優れた点が多いと思われる.
皮膚リンパ腫の最新の分類
著者: 岩月啓氏
ページ範囲:P.83 - P.89
リンパ腫分類のREAL分類と,それを基盤に改訂された新WHO分類と原発性皮膚リンパ腫の分類であるEORTC分類をとりあげ,皮膚Tリンパ腫の位置付けについて解説し,それぞれの分類における問題点について私見を述べた.さらに,最近,注目を集めているNK細胞リンパ腫とEpstein-Barrウイルス関連リンパ腫の病型を提示し,本邦におけるリンパ腫の特殊性を強調した.また,診断に苦慮することの多いAILD様T細胞リンパ腫やCastleman病についての知見を紹介した.
4 皮膚疾患治療のポイント
アトピー性皮膚炎に対するFK506軟膏(タクロリムス軟膏)使用ガイドライン
著者: 中川秀己
ページ範囲:P.93 - P.97
1999年11月24日にアトピー性皮膚炎の新しい外用薬として0.1%FK506(タクロリムス)軟膏:プロトピック®軟膏が世界に先駆けて本邦で発売された.本剤はステロイドとほぼ同等の抗炎症・抗アレルギー効果を有するとともに皮膚萎縮などのステロイド外用薬の局所的副作用がないカルシニューリン阻害薬という新しいジャンルに分類される非ステロイド系免疫抑制外用薬といえる.本剤はステロイド外用薬の連用により,局所的副作用の出現が懸念される顔面・頸部皮疹を有する患者,ステロイド外用薬の局所的副作用が既に認められる患者,ステロイド忌避の患者などに対して,積極的に使用されるものと考えられる.しかしながら,本剤は使用開始時に一過性の皮膚刺激症状が高率に認められることのほかに,血中濃度が上昇するような症例では腎機能等の定期的な検査が必要であり,皮膚科専門医が主体となり,使用していくべき薬剤であるといえる.
成人のアトピー性皮膚炎のメンタルケア
著者: 加茂登志子 , 川本恭子 , 堀川直史 , 檜垣祐子 , 有川順子 , 吉原伸子 , 川島眞
ページ範囲:P.98 - P.102
アトピー性皮膚炎は精神皮膚科学の観点から心理的要因が経過に影響を及ぼす皮膚疾患に分類されており,心理学的要因が皮膚症状の悪化と持続に重要な役割を果たす点と,itch-scratch cycleに感情的要素が大きな影響を与える点が指摘されている.15歳以上の成人のアトピー性皮膚炎患者に対するメンタルケアとしては,心理社会的ストレスに対するストレスマネージメントと,掻破行動に対する修正が重要である.さらに,掻破行動自体が心理社会的ストレスに対する不適応反応である可能性を考慮すると,ストレスマネージメントと掻破行動の修正はメンタルケアの両輪として同時にバランスよく行われる必要がある.重症例や精神疾患合併例には精神科医とのチーム医療が,また,皮膚科医が中心となってメンタルケアを行う場合は,コンサルテーション・リエゾン精神医学との技術面での交流が重要である.
嗜癖的掻破行動によるアトピー性皮膚炎の臨床像
著者: 川島眞 , 檜垣祐子 , 細谷律子 , 小林美咲
ページ範囲:P.103 - P.107
アトピー性皮膚炎において,掻破がその悪化要因となっていることは,いわゆるitch-scratch cycleとしてよく知られている.しかし最近,小林により痒み刺激によらない掻破行動の存在が明らかにされ,その行動は単なる習慣を越えて嗜癖とも言うべきものであり,嗜癖的掻破行動と命名された.その行動により誘発される皮疹は,特異な掻破行動(掻く,擦る,叩く,剥くなど)に基づくために,左右対称性,手の届く範囲に限局,境界が鮮明などの特徴がみられ,掻破の道具としての手指にも独特の症状を形成する.アトピー性皮膚炎の診療においては,掻破行動の異常による皮疹の存在に着目し,その行動異常に至る心理的要因にも踏み込んだ治療を行う必要がある.
乾癬に対するシクロスポリンの間歇投与療法
著者: 矢口均 , 小川秀興
ページ範囲:P.109 - P.113
中等症以上(PASIスコア12以上)で発症後3年以内の乾癬患者34例に対し,シクロスポリン(以下CYA)5mg/kg/日を4週間連日投与し,PASIスコアが80%以上改善した寛解症例30例を,I群:CYA5mg/kg/日を1週間内服し,1週間休薬(隔週投与法),II群:5mg/kg/日を1日内服し2日休薬(1投2休投与法),III群:3mg/kg/日の隔日投与法の3群に分け寛解後間歇的維持療法を開始し,治療開始から16週後まで,さらに50週後までのPASIスコアの変化と副作用出現頻度を各群間で比較検討した.その結果,今回検討した3群の維持療法のうちでは,CYA3mg/kg/日隔日投与法が,一定期間における総投与量が最も少なくかつ有効で,しかも副作用が少なかったことより,今回施行した寛解後維持療法の中では最も有用と思われた.
乾癬の新しいビタミンD3療法
著者: 水谷仁
ページ範囲:P.114 - P.117
乾癬に対するビタミンD3療法の位置づけと,現在開発中の新しいビタミンD3製剤について説明した.従来の低濃度のものはクリームのほかローション剤が開発され,頭皮などに有効に働くと思われる.一方,高濃度のビタミンD3製剤も申請中で,1〜2年の間に様々な化合物が製品化されてくる.高濃度製剤は低濃度製剤と違い,初期効果が高いため,ステロイドとのコンビネーション療法などで使うなど,新しい使用法の可能性を模索できるメリットがある.ローテーション療法などを用いてさらに多くの乾癬患者の治療向上が期待される.
PUVA bath-in-bath療法による尋常性乾癬の治療
著者: 安田秀美 , 山根まどか
ページ範囲:P.119 - P.122
PUVA bath療法は乾癬に対する非常に有用な治療法であるが,紫外線照射装置と浴槽を近くに併設するという設備上の問題,患者1人の1回の治療に要するメトキサレンおよび温水の量が多いという経済性の問題がある.今回,筆者らは40度程度の温水を満たした浴槽内に,約20lの0.0002%のメトキサレン溶液を入れたビニール製の袋(バスインバス®)を入れ,患者はその袋の中に10分間入浴し,全身紫外線照射装置でUVAを照射するという方法を試みた.この方法によりメトキサレンは通常の7.5分の1に,また連続使用時の浴槽内の温水使用量が削減された.この方法を,外来通院中の尋常性乾癬患者33名(男26名,女7名)に施行し,通常のPUVA bath療法とほぼ同等の効果が得られた.PUVA bath-in-bath療法の治療成績と問題点について述べた.
男性型脱毛症治療の可能性
著者: 荒瀬誠治
ページ範囲:P.123 - P.127
男性型脱毛症とは,思春期過ぎの男性の頭頂部から前頭部の硬毛が軟毛へと転換し細く短くなり(ミニチュア毛包化),成長期も短くなり,毛包のメラニン産生も減り軟毛も見え難くなり,休止期から成長期に移行しない毛包も増え,最終的には毛髪数も少なくなる変化である.毛包と男性ホルモンの関係,毛包の生物学的特性より,理論的に考えられる治療法としては,1.毛を太くする,2.毛包に直接働き毛伸長を促す,3.毛包周辺の環境改善により毛母細胞分裂を促進する,4.成長期を延長することで毛伸長を促進する,5.局所で男性ホルモン作用や活性を不活化することで進展を妨げる,などがある.個々について現在の状況を述べるとともに,売出し中のミノキシジル製剤の効能・効果,将来売り出される可能性のある5α-リダクターゼ阻害剤についても述べた.我々は本症を皮膚の個性(正常の変化)ではなく病態そのものと考え,治療に踏み出す必要がある.
全身性強皮症におけるスキン・スコア
著者: 佐藤伸一 , 竹原和彦
ページ範囲:P.129 - P.132
全身性強皮症における重症度,活動性などの病勢を正確に把握する指標が従来より求められてきた.この必要性に対して,Rodnanによるオリジナルのスキン・スコア・システムに始まった試みは,現在modified Rodnan total skin thickness score(modified Rodnan TSS)に収斂され,国際的に広く使用される指標となりつつある.このmodified Rodnan TSSは全身性強皮症の病型分類,進行度のモニタリング,新薬の効果判定などに今後重要な役割を担っていくことは疑いない.一方,modified Rodnan TSSは,今後解決すべきいくつかの問題点を有していることも事実である.本稿ではスキン・スコアの有する様々な側面についてまとめてみた.
ニトログリセリンテープによる強皮症患者の末梢循環不全の治療
著者: 関姿惠 , 秋元幸子 , 石川治
ページ範囲:P.133 - P.137
全身性強皮症患者の末梢循環不全に対するニトログリセリン製剤含有テープ(NTGテープ)貼布の効果を,サーモグラフィーを用いた手指温測定および臨床症状の変化により評価した.全身性強皮症患者25名の一側の手関節部にNTGテープを貼布した後,手指温の変化を経時的に検討し,また,12名においてNTGテープ貼布後のRaynaud現象,指尖潰瘍,自覚症状の変化を評価した.NTGテープ貼布60分後には60.0%(15/25)の患者で2℃以上の手指温上昇を認めた.温度上昇例は貼布前の手指温が健常人の手指温の平均−2SD以下に低下している例で有意に多く(p<0.01),臨床所見や罹患年数とは相関がなかった.Raynaud現象は33.3%(4/12),指尖潰瘍は44.4%(4/9),自覚症状は83.3%(10/12)の患者で改善した.NTGテープ貼布は全身性強皮症患者の末梢循環不全に対し試みる価値のある治療法と考えた.
皮膚潰瘍の近赤外線療法
著者: 戸田憲一
ページ範囲:P.138 - P.143
皮膚潰瘍の新しい治療法として近赤外線照射法を紹介した.対象は入院患者10人で,インフォームド・コンセント取得後,膠原病群,Buerger病,慢性接触皮膚炎,Werner病,糖尿病,植皮術後など多種の皮膚潰瘍21か所に,非偏光あるいは偏光の近赤外線照射装置(スーパーライザー®(SL):HA550,東京医研)を用いて,1例を除き連日照射した.照射プローブ先端より約1cm離し,100%出力,1サイクルを4〜6秒on,1〜2秒offの照射時間として,1照射野あたり7〜10分で1日1回,創面すべてに照射されることを基本とした.いずれの場合にもほとんどすべての潰瘍で傷の完全閉鎖あるいは自覚症状の改善を認めた.皮膚潰瘍外用剤単独とSLとの併用の比較臨床試験においては照射側が有意な創傷治癒促進効果を示した.副作用は軽度熱傷あるいは不快感が2名にみられたが,軽微であった.予備的基礎実験では近赤外線照射が創傷治癒関連細胞群の増殖あるいはサイトカインTGF-β産生あるいは遊走能などに対する直接的活性化を示唆する結果が得られた.皮膚潰瘍の保存的治療法の主流は現在外用剤にあることは明らかであるが,今回の結果は,本法もその一つとしてきわめて有望である可能性を示唆している.
ステロイド大量療法中の骨粗鬆症の予防
著者: 田中清
ページ範囲:P.144 - P.147
ステロイドホルモン使用中の副作用として,骨粗髪症は非常に頻度の高いものであるが,他の副作用ほどには十分認識されているとは言えない.近年DXA(dual energy X-ray absorptiometry)法を代表とする骨量測定機器の進歩により,骨量を簡便かつ正確に評価しうるようになった.また治療面でも次々に新しい治療薬が開発され,骨量低下の防止や増加が期待しうるようになってきた.ステロイド治療中・治療予定患者に対しては積極的にDXA法による骨量評価を考慮すべきである.特に大量ステロイド投与開始時は,開始後早期から骨量減少をきたす可能性があるので,早めの骨量再検,早めの治療が望まれる.
ウイルス性疣贅のモノクロロ酢酸療法
著者: 高木章好 , 梶田哲 , 豊田典明 , 山本明美
ページ範囲:P.148 - P.151
ウイルス性疣贅の一型である尋常性疣贅の中には液体窒素による凍結法などに反応せず,治療に苦慮する症例がある.今回我々はモノクロロ酢酸による腐食療法を行い,本法が安価で簡単,安全かつきわめて有効な治療と思われ報告する.方法は,少量のモノクロロ酢酸飽和水溶液を楊枝の先で直接疣贅に塗布し(疣贅上に付着した液を数回軽く突くようにして疣贅内に浸透させるが,周囲に流れないように気をつける),乾燥を確認し帰宅させ,処置した日は入浴をさける.原則とし1週間に1度の間隔で施行した.結果は,1998年1月から6月まで総数377例,男171例,女206例に施行し,最年少は2歳男児,最高齢は83歳女性であった.ほとんどの症例で著効または治癒し,不変,悪化は足底で1.8%,手背は0.6%であった.
抗菌薬の使い方
著者: 神崎寛子
ページ範囲:P.152 - P.156
皮膚科領域の感染症では臨床診断より起炎菌を比較的容易に推定することができる.主たる起炎菌はStaphylococcus aureusとStreptococcus pyogenesである.主に選択される抗菌薬はペニシリン系薬とβ-ラクタマーゼ阻害薬の合剤,新経口セフェム系薬,ペネム系薬,ニューキノロン系薬,マクロライド系薬,テトラサイクリン系薬である.ホスホマイシンは併用薬として使用される.これらの抗菌剤の抗菌スペクトラム,体内動態,使用上の注意を概説するとともに,実際の治療例をまとめた.
靴と皮膚ケア
著者: 倉片長門 , 鈴木啓之
ページ範囲:P.157 - P.159
皮膚科では鶏眼,胼胝腫,陥入爪などの足のトラブルを主訴に来院する患者を診察するが,対応に苦慮することもしばしばである.それらの患者には適切な処置を行うとともに,適合した靴の使用を指導することは治療上不可欠であり,予後を左右する重要な要因である.
ケミカルピーリング
著者: 鈴木晴恵
ページ範囲:P.160 - P.164
ケミカルピーリングは色素沈着や色素脱失,瘢痕形成などの副作用の危険から日本においてはあまり省みられなかった.レチノイン酸のrejuvenation効果が発見されたことによりprimingやmaintenance therapyが有効に行われるようになり,浅いケミカルピーリングでも効果が表れ,その効果を持続させることが可能になった.最近の盛んなマスコミでの報道とあいまって,わが国ではケミカルピーリングが人々の関心を呼んでいる.ケミカルピーリングの適応は広範でありピーリング剤も手技も種々ある.手技に習熟し,患者のホームケアの指導を徹底すれば便利で有効な治療手段の一つとなり得る.
5 皮膚科医のための臨床トピックス
アトピー性脊髄炎
著者: 堀内泉 , 吉良潤一
ページ範囲:P.169 - P.172
アトピー性皮膚炎(AD)合併脊髄炎は,1)ADが先行する,2)四肢遠位部の異常感覚(ジンジン感)を主徴とする,3)頸髄病巣が高率,4)高IgE血症,5)ダニ特異的IgEが陽性,6)髄液所見が正常,7)軽い頸髄症候が動揺しつつ長く続き,MRI上も小病巣が長く残存する,などの特徴を呈する.AD非合併脊髄炎でも高IgE血症とダニ特異的IgE陽性率が健常対照より高く,胸髄に病巣の分布が多い.したがって,高IgE血症とダニ特異的IgE陽性の一群の脊髄炎患者が存在し,AD合併例では頸髄に,非合併例では胸髄に病巣がみられることが多いと考えられる.
アトピー性皮膚炎の網膜剥離—全国調査から
著者: 平岡智之 , 樋田哲夫
ページ範囲:P.174 - P.175
アトピー性皮膚炎に伴う網膜剥離の疫学的動向と臨床的特徴を把握すべく,多施設全国調査を行った結果について述べた,33施設から合計417眼の報告が得られ,手術眼数は年々増加の傾向にあった.発症年齢は16〜25歳にピークがみられた.白内障のあるもの,または手術既往のあるものが9割を占めた.通常の網膜剥離に比べ,手術成績は不良であった.早期発見・治療に向けて,眼科,皮膚科の連携診療が重要と思われる.
シックハウス症候群(化学物質過敏症)
著者: 鳥居新平
ページ範囲:P.176 - P.178
化学物質過敏症は化学物質の大量曝露の後に再び同じ化学物質に接触した場合にみられる症状であり,次第に最初に曝露したもの以外の多種の化学物質で症状が誘発されるようになるので,多種化学物質過敏症ともいわれる.シックハウス症候群は住居に由来する汚染物質による健康被害であり,化学物質過敏症もその一部に含まれるものがある.本稿ではシックハウス症候群に含まれる化学物質過敏症について解説した.
強皮症・Sjögren症候群の病因としてのキメリズム
著者: 根岸泉 , 遠藤雪恵 , 石川治
ページ範囲:P.180 - P.181
慢性移植片対宿主病(GVHD)では,しばしば全身性強皮症(SSc)やSjögren症候群(SjS)との類似症状が発症する.最近,SSc患者の血中ならびに皮膚病変部に胎児由来単核球が同定され,発症メカニズムとしてキメリズムが注目されている.そこで,我々もSScならびにSjS患者について検討を試みたところ,SSc患者の末梢血中,SjS患者の口唇小唾液腺中に胎児由来DNA配列を検出できた.キメリズムだけで両疾患の発症メカニズムのすべてを説明することはできないが,一部の患者ではGVHD様反応による直接的な組織障害,あるいは間接的に自己免疫反応が誘導されている可能性が示唆される.
MRSA院内感染対策
著者: 宮崎義継
ページ範囲:P.182 - P.184
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌:methicillin resistant Staphylococcus aureus)の分離頻度は本邦において特に高く,多くの病院で黄色ブドウ球菌の半数前後を占めている.そのため,しばしば定着か感染症かにかかわらず主たる院内感染対策の対象として取り上げられる.MRSAは接触感染が最も重要なルートであるため,MRSA感染症か定着かの違いをみきわめたうえで,排菌量が持続的に多いMRSA感染症の患者については,これを感染源として院内播種を防ぐために日常のケアにおいて特に注意が必要である.
Kabuki make-up症候群
著者: 坂本泰子
ページ範囲:P.186 - P.187
Kabuki make-up症候群は,1981年,新川,黒木らによって確立された新しい先天性奇形症候群であり,特徴的な顔貌,精神発達遅滞,成長障害等を主微とする.本邦からの報告以降,現在は世界各国で症例が認められている.本症候群の臨床像と特徴的な顔貌からつけられた名前の由来について紹介する.
敏感肌
著者: 沼上克子 , 田上八朗
ページ範囲:P.188 - P.189
「敏感肌」とは,皮膚科学的な定義ではない.一般成人の間から発し,さらに社会的に用いられてきた名称である.その割合はかなり多いとされるが,敏感肌と診断するに足る科学的基準にはいまだ一定の見解がない.文献的には,敏感肌とは様々な外界の要因に対して皮膚に不利な反応が起こりやすい皮膚のタイプとしてとらえられていることが多い.反応の形も,目に見える接触蕁麻疹,鱗屑,紅斑のみならず,ぴりぴり感やかゆみなどの不快な感覚のみ(subjective irritation)であることもある.Subjective irritationをきたす実験的刺激物質の乳酸を用いた研究,および生体計測工学的方法を用いての敏感肌に関する研究の知見を中心に述べる.
ダイオキシン
著者: 香山不二雄
ページ範囲:P.190 - P.192
ダイオキシン類による環境汚染が,人の健康に悪影響を与えることが危惧されている.ダイオキシン類は強い毒性とともに発癌性,発生毒性,生殖異常,免疫毒性などが動物実験で報告されている.人の高度濃度曝露では,クロールアクネなどの皮膚病変が観察される.さらに児の性比の変化,子宮内膜症,甲状腺機能異常,免疫毒性に関する知見が蓄積されている.ダイオキシン類による環境汚染問題は,ダイオキシン類の発生源対策が最も重要である.ゴミ焼却場の改善や,ゴミの分別収集を進め,さらにゴミの減量化のために,包装,流通システム,リサイクルシステムの改善が重要である.
医学教育改革の方向
著者: 北島康雄
ページ範囲:P.193 - P.195
近年の分子医学を含めた医学の発展に伴って,医師になるため,また,優れた医師であり続けるためには膨大な知識量が要求されるようになった.加えて,豊かな人間性を有する医師による患者中心の医療が求められている.このために医学部学生は知識の暗記ではなく,あふれる情報の中から適切な情報を選び,理解し,問題解決に当たる能力と人間性豊かな態度を身につけなければならない.そのような教育には少人数教育,テュトーリアル教育あるいはクリニカルクラークシップを代表とする新しい合目的的なカリキュラムが開発される必要がある.一方,そのような教育を行うことができる医学部教員・臨床指導医の教育能力の開発(faculty developlnent)が要求される.
介護保険における医師・医療の役割
著者: 青柳俊
ページ範囲:P.196 - P.198
平成12年度にスタートする介護保険制度は,「医療」と「介護」が一体的に提供される仕組みとして,医師・医療の役割が非常に重要である.介護保険では,認定された介護レベルに限られた保険給付となるので,要介護認定が重要なポイントとなる.要介護認定においては医師は,1)「主治医意見書」の作成,2)審査会委員としての審査・判定などの重要な役割を担う.特に,現在の一次判定ロジックは,基礎データや分析手法に多くの問題が指摘され,要介護認定では二次判定が重要視されることから,医師の作成する「主治医意見書」は,公正かつ客観的な認定の鍵になるといえる.高齢者のQOL向上を図るためには,必要なときに必要な医療と介護サービスが提供される仕組み作りが重要であり,介護保険制度への医師の積極的関与が必要と考える.
Derm.2000
臨床と研究の狭間にて
著者: 森脇真一
ページ範囲:P.41 - P.41
昨年,アメリカのベンチュラ市で開催されたゴードン・カンファレンス(DNA修復)に参加した.総勢150名という比較的少人数の会であったが,DNA修復に関する最新の研究成果が報告され活発な討論がなされた.up-to-dateの知識を吸収でき,また自分の研究に対して多くの助言が得られ,有意義な1週間であった.参加者で所属が臨床講座なのは私だけであった.ゴードンというのはジョンズ・ホプキンス大学の化学の教授の名前であり,同じ領域で研究をしている人が少人数集まり新しく得た結果について論じあう目的で始まったもので,第1回の会議は1931年夏にバルチモアで行われたそうである.
私は色素性乾皮症などDNA修復異常で発症する遺伝性疾患が専門であるが,ここ数年,この分野の基礎研究の進歩には著しいものがあるため,日々明らかになる新しい知見をフォローするにはこのような学会への積極的な参加が必要となる.医師になって14年目であるが,6年余りを基礎の教室で過ごした経験があり,いまだ基礎研究への興味が持続している.診療の合間に少しずつではあるがDNA修復に関する実験をしており,臨床医と研究者の二足のわらじをはく毎日が続いている.皮膚科医としての業務(診療,症例検討,学生の指導など)は決しておろそかにできず,研究の時間は必ずしも十分とはいえない.夜間や休日に実験をしたり研究論文を読んだりしているが,若い院生でもない私にいつまでこのような二重生活をする体力,知力が続くであろうか.臨床医と研究者—これらを両立することははたして可能なのだろうか.基礎の講座でやっていく能力も自信もなく,かといって臨床オンリーだと専門領域の進歩からは取り残されてしまう.おそらく今後もこのようなことを考えながら,毎日が過ぎてゆくのであろう.読者の中にも臨床と研究の狭間で同じような悩みをもった皮膚科医が結構多くいるのではないだろうか.
皮膚潰瘍について/患者さんの訴え
著者: 菊池かな子 , 江畑俊哉
ページ範囲:P.51 - P.51
1999年5月まで,2年ほど病棟医長を担当させていただいた.もちろん様々な疾患の方がいらっしゃるのだが,何故か難治性皮膚潰瘍が多かった印象がある.褥瘡,静脈瘤性,糖尿病性,血管炎によるもの,膠原病性と成因は多様であった.これらに対し,保存療法,手術療法を適宜組み合わせることになる.保存療法については,bFGFなどの細胞成長因子が実際に使用可能となりつつあるのは大いに楽しみである.10年以上前,キーストーンシンポジウムで創傷治癒のセクションがあり,当時留学中だったので参加させてもらった.その当時の最先端の講演でも,多くの細胞成長因子の使用がまだ動物実験の段階であった.コストも高いことだし実用化されるのはまだまだ先だろうなと思った記憶がある.これらが実際に使用可能になるまでの現状ではTopical Hemotherapyも捨てがたい.何例か試み,以外に早く良好な肉芽形成をみた.
強皮症は私の専門でもあるので,内科より皮膚潰瘍治療を依頼される場合もあった.つい最近までの常識では,強皮症の皮膚潰瘍は保存療法のみで,手術療法は禁忌に近いとされていたと思う.人工真皮の併用により潰瘍面への分層植皮が可能になり,症例によっては相当入院期間の短縮が図られた.残念ながら,強皮症では決定的基礎治療薬がないが,対症療法の組み合わせでQOLを改善する余地は多分にあるのだ.
「手のひら,足の裏に蕁麻疹が出ませんか?」
著者: 堀川達弥
ページ範囲:P.70 - P.70
アスピリン蕁麻疹は奇妙な蕁麻疹である.通常は多種類の酸性系消炎鎮痛剤によって惹起されるが,これらに対するスクラッチテストや皮内テストでは陽性所見は得られない.またその誘発までの時間は数十分から7〜8時間までと様々である.IgE-抗原複合体などによる肥満細胞による脱顆粒が酸性系消炎鎮痛剤によって増強されるのではないかとの仮説のもとに当教室の原田晋先生らと臨床的検索を行ってきた.現在のところ食餌依存性運動誘発性アナフィラキシー患者においてアスピリン摂取後にIgE-RAST陽性の一部の食物を摂取すると蕁麻疹やアナフィラキシーが誘発されるが,食物あるいはアスピリンのみでは誘発されないということがわかってきた.
このアスピリン負荷テストを行っている間に様々なタイプの皮膚症状が誘発されることに気がついた.最も多いのは蕁麻疹タイプであるが,この他に血管神経浮腫や小紅斑がみられることもある.また蕁麻疹タイプでは頻繁に手掌,足蹠,被髪頭部に皮疹がみられることに気がついた.このため蕁麻疹患者を診察したら必ず「手のひら,足の裏に皮膚症状が出ませんか?」と尋ねるようになった.その後掌蹠に症状があり,アスピリン負荷テスト陽性になる症例を続けて経験したため「アスピリン蕁麻疹では掌蹠に症状が出るのではないか」と思った時期もあったが,しばらくしてから掌蹠に症状があるにもかかわらずアスピリン負荷で出ない症例も経験したため,必ずしもこれが正しいわけではないと考えるようになった.しかし,このアスピリン負荷で掌蹠や被髪頭部に症状が出ることが多いのはまちがいないと今も信じている.このため今も蕁麻疹患者を診察したら「痛み止めや解熱剤で蕁麻疹はひどくなりませんか? 手のひら,足の裏,頭の中に皮膚症状が出ませんか?」と尋ねている.
樹状細胞療法/臨床研究をしていて思うこと
著者: 北嶋敏之 , 秋元幸子
ページ範囲:P.76 - P.76
当科では東京大学医科学研究所を中心として発足したメラノーマに対する樹状細胞療法の臨床研究プロジェクトに参加している.原理を簡単に述べると,患者さんの樹状細胞にメラノーマの腫瘍抗原をパルスしたものを投与して抗腫瘍免疫を高めようとするものである.このプロジェクトはステージIVの患者さんが対象であるが,もちろんわが国でははじめての試みである.欧米では主としてペプチドを腫瘍抗原として使用しある程度の効果をあげているが,わが国ではHLAの関係上,腫瘍細胞溶解液を抗原として用いるのが特徴である.
先日,医科研での治療の合間にこちらでIL 2を注射しに来られた患者さんを診させていただく機会があった.調子はどうかと尋ねると案外良いとのことであった.「むこうで血をとって何回か注射してもらっている」と治療の様子を話してくれた.この患者さんの腕にIL−2を注射するたびに,まだ始まったばかりでおそらく前途は長いであろうこの治療に同意していただいたことに対する感謝の念とともに,このような患者さんのためにも,幾多の困難を乗り越え,このプロジェクトを前進させていかなければならないと思った.
小児の泣かない外来小手術
著者: 田村敦志
ページ範囲:P.82 - P.82
幼小児の小手術や生検は嫌なものである.暴れるのを防止するために,全身麻酔下で手術を行うこともあるが,麻酔に必要な検査をするのがまた局麻下の手術以上に大変になることもある.それ故,言うことを聞く年齢まで手術を引き延ばしにすることが多い.しかし,何らかの理由で不運にも幼小児の局麻下小手術を行うことになってしまった場合には,極力泣かさないようにして行っている.実際,四肢の小手術であれば4人中3人は泣かさずに終了させている.コツは,とにかく手術や注射を行うことを悟らせないことと,休みなくお話をし続けることである.泣いたり暴れたりする理由は恐怖心と痛みにあるので,この両者を与えないことが大切である.まず,明るく幼稚園のお話などをしながら,お薬を塗る(消毒する).次に問題の局麻の注射となる.お薬はちょっとしみるかもしれないことを一応伝えたうえで,大きな声で気を逸らしながら皮内針ですばやく真皮を貫通させる.この一瞬のみ痛みを感じるはずであるが,注射をされるものと思っていないので,大抵ちょっとピクッと反応するだけである.局麻薬はきわめて緩徐に注入し,麻酔の効いた範囲内で針を進めてゆく.これが最も骨の折れる作業で時間もかかる.粗な組織内で薬剤が急速に注入されないよう十分コントロールしなければならない.麻酔薬注射に時間を要するので,皮切部の皮用注射を追加しなくてもすでに効いていることが多い.麻酔さえ無痛で注射できれば終わったも同然である.それ以降の手術操作はまったく問題ない.局麻剤の注射時に看護婦さんが親切にも「ちょっと痛いけど注射だけ我慢してね!」とか言ったりすればその瞬間にこの計画は失敗に終わる.親が事前に子供に納得させるべく手術について十分な説明をしている場合も同様に無効である.「注射,痛い,我慢,針」などの恐怖用語は禁句であり,注射器や手術器械を手にしている姿は決して見られてはならない.終始,お友達の立場で休みなく話し続ける.いい大人が馬鹿らしくてやってられないと思う人には決してできない方法である.万が一バレて泣き出したら,諦めて押さえつけてでもすぐに終わらせる.
コンピュータと皮膚診療
著者: 上出康二
ページ範囲:P.102 - P.102
若い女性が「顔の傷跡を治したいのですけれど……」ここから長時間にわたる患者との問答が始まる.レーザー治療をしているあざの患者を目の前にしてレーザーの効果はどうなのだろうか?写真台帳をめくりスライドを探し,小さなリバーサルフィルムをかざしてジーと見つめうーんとうなる.術前検討でポラロイド写真をコピーしてデザインするうちに写真は鉛筆で真っ黒.学生の講義に分厚い教科書の索引を見てあちらこちらページをめくるうちに学生の目はうつろ.腎機能障害患者にアシクロビルを投与するためにクレアチニンクリアランスの計算式は?等々.もっとスマートにできないものだろうか?と考え,趣味が高じて,これらすべてをコンピュータにやってもらうようにしてしまった.患者の病名情報,皮膚疾患の要点,診療のメモ書きなどの文書データ,臨床写真,組織写真などの画像データを苦労してすべてコンピュータに放り込み,簡単に検索,表示,カラー印刷できるシステムを作成した.苦労したおかげで,これまで診察室で長時間を要した患者への説明も,机上にある21インチのモニターいっぱいに映し出された大画面の写真をみれば一目瞭然.学生の目も輝きだし,術前検討もカラープリンターに印刷あるいはモニター上で検討できる.困難な症例は電子メールで他の皮膚科医,形成外科医と検討している.しかしモニター上の画面をじっと見ていると,なにか訴えかけるものがない.皮疹のビットマップのみでは表現できない感覚的なもの,皮膚全体さらには患者をとりまく皮膚疾患特有のオーラといったものを写真上ではとらえることができない.逆に,苦労して経験して得られたものは脳に強くインプットされ決して消去できないものとなっている.今後もひとつひとつの症例を大切にして,貴重なデータを脳とハードディスクにインプットしていこうと思っている.
おまかせでお願いします
著者: 下妻道郎
ページ範囲:P.107 - P.107
何年ほど前からであろうか.タクシーに乗ると道順を確認されることが多くなったのは.行く先を告げ,さあこれで目的地に着くまでゆっくりしようと思っていると,「どのようなルートで行きましょうか.」と聞かれるのである.途中でもAかBかのあまり違いのないルートの選択をせまられる場合もしばしばである.乗客の自己決定権を尊重してくれているのだと解釈し,あれこれ考えて「それでは,Bのルートでお願いします.Aは結構混みそうですから.」そして行ってみたところ,不幸にして渋滞にまきこまれてしまい,これは自分の責任だと思わざるを得ない状況になってしまうこともよくある.「早そうなほうでお願いします.」と責任放棄をすると不愉快そうにされる場合もあり,なかなか目的地まで気が抜けない.寝ていたりボーッとしているとよい乗客とは言えないのである.
そうこうしていると,医療においてもインフォームド・コンセントの必要性が強調されるようになり,患者さんの同意を確認したり,承諾書を書いてもらう機会が増えてきた.専門性の高い医療行為を判断してもらうには,まずこちらの説明を十分理解してもらう必要がある.逆の立場になってみると,余計な負担をかけているのではないかと思うこともしばしばである.なかにはタクシーに乗って私が感じたように,「そちらもプロなんだから,よろしく頼みますよ.」と煩わしく思われている場合もあるのではないか.ここはしっかり説明する必要があると話し始めたところ,ポツリと「まあいろいろあるでしょうが,先生のいいと思う方法でお願いします.」と拍子抜けする場合など,信頼されていると解釈することにしているが実際どうなのであろうか.いずれにしろ,最適のルートで速やかに目的地に到着すればお互い満足できるのは間違いないのだが.
皮膚科医15年間の軌跡,16年目の真実
著者: 石黒直子
ページ範囲:P.117 - P.117
【MCTDとoverlap症候群】初論文のテーマである.Raynaud現象,手指の浮腫性硬化,筋力低下,腎生検での異常所見,抗RNP抗体単独高値…….当時典型的なMCTDと考えたが,今この疾患がわからない.抗RNP抗体陽性のもとに集められる種々のケース.独立疾患なのか否か.その後典型例に遭遇しない.【健康人の抗核抗体】初臨床研究のテーマである.健康人でも意外と抗核抗体陽性者がいる.抗核抗体陽性で膠原病を疑っていると依頼がくる.もちろん抗核抗体が陽性でも膠原病の症状を認めない人は経過観察としている.【接触皮膚炎と薬疹】これほど探求心を試される疾患はない.多種類の抗真菌外用剤で接触アレルギーを起こした症例では基剤中のアルコールが原因であった.熱傷様の皮疹を繰り返し幼児虐待説まででた症例は,母も投薬を忘れていたアスベリンの固定薬疹と判明した.いつも神経を研ぎすましておきたい.【除去食が奏効したAD】負荷試験まで試み,湿疹反応を確認した唯一の症例.入院でのステロイド外用にも反応しなかった5か月男児は,10歳になり皮疹を認めない.【GVHDと薬疹】輸血後の紅皮症の依頼がくると皮膚科医の判断が求められ苦渋した.今は放射線による予防が徹底し,そのストレスからは解放された.【疣と接触免疫療法】学位論文である.難治例で60%以上の治癒率を得たが,最近はほぼ100%治癒すると思っている.上司は「君は治ると信じているだろう.君の信じる気持ちが残り40%の患者の免疫を賦活化するんだ.」と……。もちろん科学的には証明できないが今日も信じて治療をする.【intermediate LE II】皮膚科医でなくては診断できないことがある.内科から検査上はさほど問題ないとして皮疹について依頼がある.生検,諸検査にて軽症型SLEと診断し治療をするがさほど進行しない症例がある.—私がしなくてはならないことは何か.これからも模索していきたい.
紫外線治療と基礎医学のはざまにて/実験机に向いながら
著者: 荒金兆典 , 米田耕造
ページ範囲:P.128 - P.128
紫外線治療を行っている.対象疾患としては炎症性皮膚疾患(アトピー性皮膚炎や乾癬をはじめ,ほぼすべての炎症性疾患を網羅する)が主である.Bath PUVA療法を治療法の中心に据え,外用PUVAやUVB療法も行う.紫外線療法は以前より広く行われており,効果は臨床的に十分評価を受けているが,その作用機序に関しては意外なほど明らかではない.炎症の発生に寄与する免疫担当細胞のアポトーシスの誘導が抗炎症的に作用していると考えるのは一面の真実であろうと思われるが,では炎症の取っかかりである,抗原(未知のことが多い)を認識する機構を抗原特異的に抑制しうるかどうかときかれれば,現時点では答える材料がない.仮にすでに確立されたアレルギー反応を,紫外線療法により抗原特異的免疫不応答状態(トレランス)に転化できれば,多くのアレルギー性皮膚疾患の長期の改善(もちろん紫外線療法のみで)が理論上可能になる.そこで,同僚とともにマウスモデルを用い紫外線照射を行う毎日である.しかし,ヒトの病態はマウスに比べ変化が豊富で,マウスで得られた結果が即ヒトに応用できるかというと疑問が残る.その大きな理由としてヒトに紫外線療法を行った際の,皮膚の免疫担当細胞の動態に関する詳細な計時的変化に関する理解が不足している点が挙げられる.よってその点を充足するために,紫外線療法により明らかに改善傾向を示す患者さんに生検をお願いすることになる.これは尋くほうも辛いが,尋かれるほうがもっと辛いと思う.この辛さというのはマウスだけを扱っていると起こり得ないものである.しかし,患者さんが生検を許可してくださった場合,この検体を無駄にはできないという思いを新たにする.私の研究はこういう声なき多くの人々に支えられていると思うと,外来診療が神聖な行為であると再認識する.
「こうたいか」って何ですか?
著者: 伊藤薫
ページ範囲:P.137 - P.137
インフォームド・コンセントということが言われているが,日常診療の中で患者さんにいかに理解してもらえるように説明するかが難しい.
例えば,患者さんに生検のことを説明した医師が「じゃあ,生検しますか」と言ってしばらくして「えっ,先生,せいけんって皮膚を切って縫うんですか」と聞かれることがある.
どうして化粧するの
著者: 小泉洋子
ページ範囲:P.151 - P.151
女性の顔面の湿疹病変は接触皮膚炎のことが多い.化粧品を変えたあとなどはそれがあやしい.化粧品を使わないでください.お薬ぬってください.落ち着いたらパッチテストしましょう.すると患者さんの多くは,えっ,お化粧しちゃいけませんか.どうして.仕事にいくので化粧しないといけないんです.
仕事に化粧が必要なら男性はどうしてしないのかしら.
HIV感染症と皮膚症状
著者: 中村晃一郎
ページ範囲:P.164 - P.164
現在,東京大学医科学研究所附属病院感染症内科(教授岩本愛吉博士)ではHIV感染症患者を専門に診察しており,とくに皮膚疾患について診療に参加する機会をいただいた.AIDSについて,最近ではややマスコミなどの報道もおさまった感があるが,依然としてHIV患者数は増加を続けている.HIVに伴う皮膚疾患としては,爪,足白癬や驚口瘡が顕著であり,また非定型抗酸菌剤に対する薬疹,脂漏性皮膚炎,好酸球性膿疱性毛嚢炎などの症状をみることが多い.これらの皮膚症状は初発症状としてみられることもあれば,経過中に出現する場合もある.Kaposi肉腫も四肢,足などにしばしば生じる皮膚症状であり,治療として液体窒素療法,ビンブラスチンの局注,手術などを行い,比較的よい経過をみている.また,皮膚にHHV 8とEBVの関連したリンパ腫を生じた症例を経験した1).
外国人移住者等も増加している昨今,患者が自身の認識なく,一般皮膚科外来を受診するケースも想定される.HIV患者への対応や皮膚症状についての認識を新たにしておく必要が感じられる.
どうやって傷は治るのか—蒼ざめたマウスをみつめて
著者: 高橋健造
ページ範囲:P.178 - P.178
ヒト遺伝子ゲノムの概要が,当初の計画よりもずいぶんと早い今年の春には明らかにされるようです.遺伝性疾患の解明にはますます拍車がかかり,複数の遺伝的素因が関与するであろう乾癬やアトピー性皮膚炎などの発症機序も着々と解き明かされていくと思われます.遺伝情報に関する爆発的な進歩は,大腸菌からヒトのゲノムに至るまでどんな遺伝子を誰が扱っても,共通の割と簡単な方法論が通用するという遺伝子工学の特徴によるところが大きいと思います.しかし個々の疾患の治療法となると,個々の病因に拮抗させる薬剤の開発や導入するための手段は,疾患や臓器ごとに大きく異なるために病因の解明ほどには容易に運びそうにはありません.そこでこれからの臨床医学,特に治療面での期待が大きいのが,臓器の再生に関する再生医学の研究で,京都大学にも再生医科学研究所が新設されました.
そんなわけで表皮組織の再生のメカニズムを探る実験を続けています.皮膚科医ならずとも,創傷や熱傷の後に皮膚が自然に再生して創部を埋めていくのは当然のことのように思われがちですが,実際には表皮や毛嚢のどの角化細胞がどのように潰瘍底に遊走し,実際の再生表皮の基底層や幹細胞を再構成するのか,今のところはっきりした回答はありません.
アトピー外来は今?
著者: 大槻マミ太郎
ページ範囲:P.184 - P.184
栃木の人は,取っつきにくいところもあるが概ね正直である,というのが県民の特徴だそうである.そのせいかどうかは定かでないが,アトピー性皮膚炎(AD)の患者も東京に比べると,un—complicatedである場合が多い.東大で外来医長をしていた頃は,初診のAD患者にはもっとも気を遣ったものだが,ここでは患者の親が頓珍漢な横槍を入れるケースは少ない.
自治医大に赴任して2年になるが,その間にADの治療現場では,随分と変化があった.“アトピービジネス”の皮膚科側からの糾弾,厚生省からの治療ガイドラインの公表,“嗜癖的掻破行動”についての認識の深まり,そして新薬タクロリムス軟膏の発売など,これらはすべてステロイド論争と様々な角度から対峙し,良識ある皮膚科医にとってはフォローの風になるであろうnew faceといえる.
基本情報
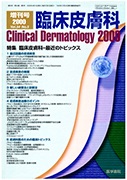
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
78巻12号(2024年11月発行)
78巻11号(2024年10月発行)
78巻10号(2024年9月発行)
78巻9号(2024年8月発行)
78巻8号(2024年7月発行)
78巻7号(2024年6月発行)
78巻6号(2024年5月発行)
78巻5号(2024年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024
78巻4号(2024年4月発行)
78巻3号(2024年3月発行)
78巻2号(2024年2月発行)
78巻1号(2024年1月発行)
77巻13号(2023年12月発行)
77巻12号(2023年11月発行)
77巻11号(2023年10月発行)
77巻10号(2023年9月発行)
77巻9号(2023年8月発行)
77巻8号(2023年7月発行)
77巻7号(2023年6月発行)
77巻6号(2023年5月発行)
77巻5号(2023年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023
77巻4号(2023年4月発行)
77巻3号(2023年3月発行)
77巻2号(2023年2月発行)
77巻1号(2023年1月発行)
76巻13号(2022年12月発行)
76巻12号(2022年11月発行)
76巻11号(2022年10月発行)
76巻10号(2022年9月発行)
76巻9号(2022年8月発行)
76巻8号(2022年7月発行)
76巻7号(2022年6月発行)
76巻6号(2022年5月発行)
76巻5号(2022年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022
76巻4号(2022年4月発行)
76巻3号(2022年3月発行)
76巻2号(2022年2月発行)
76巻1号(2022年1月発行)
75巻13号(2021年12月発行)
75巻12号(2021年11月発行)
75巻11号(2021年10月発行)
75巻10号(2021年9月発行)
75巻9号(2021年8月発行)
75巻8号(2021年7月発行)
75巻7号(2021年6月発行)
75巻6号(2021年5月発行)
75巻5号(2021年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021
75巻4号(2021年4月発行)
75巻3号(2021年3月発行)
75巻2号(2021年2月発行)
75巻1号(2021年1月発行)
74巻13号(2020年12月発行)
74巻12号(2020年11月発行)
74巻11号(2020年10月発行)
74巻10号(2020年9月発行)
74巻9号(2020年8月発行)
74巻8号(2020年7月発行)
74巻7号(2020年6月発行)
74巻6号(2020年5月発行)
74巻5号(2020年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2020 Clinical Dermatology 2020
74巻4号(2020年4月発行)
74巻3号(2020年3月発行)
74巻2号(2020年2月発行)
74巻1号(2020年1月発行)
73巻13号(2019年12月発行)
73巻12号(2019年11月発行)
73巻11号(2019年10月発行)
73巻10号(2019年9月発行)
73巻9号(2019年8月発行)
73巻8号(2019年7月発行)
73巻7号(2019年6月発行)
73巻6号(2019年5月発行)
73巻5号(2019年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2019 Clinical Dermatology 2019
73巻4号(2019年4月発行)
73巻3号(2019年3月発行)
73巻2号(2019年2月発行)
73巻1号(2019年1月発行)
72巻13号(2018年12月発行)
72巻12号(2018年11月発行)
72巻11号(2018年10月発行)
72巻10号(2018年9月発行)
72巻9号(2018年8月発行)
72巻8号(2018年7月発行)
72巻7号(2018年6月発行)
72巻6号(2018年5月発行)
72巻5号(2018年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2018 Clinical Dermatology 2018
72巻4号(2018年4月発行)
72巻3号(2018年3月発行)
72巻2号(2018年2月発行)
72巻1号(2018年1月発行)
71巻13号(2017年12月発行)
71巻12号(2017年11月発行)
71巻11号(2017年10月発行)
71巻10号(2017年9月発行)
71巻9号(2017年8月発行)
71巻8号(2017年7月発行)
71巻7号(2017年6月発行)
71巻6号(2017年5月発行)
71巻5号(2017年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2017 Clinical Dermatology 2017
71巻4号(2017年4月発行)
71巻3号(2017年3月発行)
71巻2号(2017年2月発行)
71巻1号(2017年1月発行)
70巻13号(2016年12月発行)
70巻12号(2016年11月発行)
70巻11号(2016年10月発行)
70巻10号(2016年9月発行)
70巻9号(2016年8月発行)
70巻8号(2016年7月発行)
70巻7号(2016年6月発行)
70巻6号(2016年5月発行)
70巻5号(2016年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2016 Clinical Dermatology 2016
70巻4号(2016年4月発行)
70巻3号(2016年3月発行)
70巻2号(2016年2月発行)
70巻1号(2016年1月発行)
69巻13号(2015年12月発行)
69巻12号(2015年11月発行)
69巻11号(2015年10月発行)
69巻10号(2015年9月発行)
69巻9号(2015年8月発行)
69巻8号(2015年7月発行)
69巻7号(2015年6月発行)
69巻6号(2015年5月発行)
69巻5号(2015年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2015 Clinical Dermatology 2015
69巻4号(2015年4月発行)
69巻3号(2015年3月発行)
69巻2号(2015年2月発行)
69巻1号(2015年1月発行)
68巻13号(2014年12月発行)
68巻12号(2014年11月発行)
68巻11号(2014年10月発行)
68巻10号(2014年9月発行)
68巻9号(2014年8月発行)
68巻8号(2014年7月発行)
68巻7号(2014年6月発行)
68巻6号(2014年5月発行)
68巻5号(2014年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2014 Clinical Dermatology 2014
68巻4号(2014年4月発行)
68巻3号(2014年3月発行)
68巻2号(2014年2月発行)
68巻1号(2014年1月発行)
67巻13号(2013年12月発行)
67巻12号(2013年11月発行)
67巻11号(2013年10月発行)
67巻10号(2013年9月発行)
67巻9号(2013年8月発行)
67巻8号(2013年7月発行)
67巻7号(2013年6月発行)
67巻6号(2013年5月発行)
67巻5号(2013年4月発行)
特集 最近のトピックス2013 Clinical Dermatology 2013
67巻4号(2013年4月発行)
67巻3号(2013年3月発行)
67巻2号(2013年2月発行)
67巻1号(2013年1月発行)
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
66巻11号(2012年10月発行)
66巻10号(2012年9月発行)
66巻9号(2012年8月発行)
66巻8号(2012年7月発行)
66巻7号(2012年6月発行)
66巻6号(2012年5月発行)
66巻5号(2012年4月発行)
特集 最近のトピックス2012 Clinical Dermatology 2012
66巻4号(2012年4月発行)
66巻3号(2012年3月発行)
66巻2号(2012年2月発行)
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
65巻11号(2011年10月発行)
65巻10号(2011年9月発行)
65巻9号(2011年8月発行)
65巻8号(2011年7月発行)
65巻7号(2011年6月発行)
65巻6号(2011年5月発行)
65巻5号(2011年4月発行)
特集 最近のトピックス2011 Clinical Dermatology 2011
65巻4号(2011年4月発行)
65巻3号(2011年3月発行)
65巻2号(2011年2月発行)
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
64巻12号(2010年11月発行)
64巻11号(2010年10月発行)
64巻10号(2010年9月発行)
64巻9号(2010年8月発行)
64巻8号(2010年7月発行)
64巻7号(2010年6月発行)
64巻6号(2010年5月発行)
64巻5号(2010年4月発行)
特集 最近のトピックス2010 Clinical Dermatology 2010
64巻4号(2010年4月発行)
64巻3号(2010年3月発行)
64巻2号(2010年2月発行)
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
63巻11号(2009年10月発行)
63巻10号(2009年9月発行)
63巻9号(2009年8月発行)
63巻8号(2009年7月発行)
63巻7号(2009年6月発行)
63巻6号(2009年5月発行)
63巻5号(2009年4月発行)
特集 最近のトピックス2009 Clinical Dermatology 2009
63巻4号(2009年4月発行)
63巻3号(2009年3月発行)
63巻2号(2009年2月発行)
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
62巻11号(2008年10月発行)
62巻10号(2008年9月発行)
62巻9号(2008年8月発行)
62巻8号(2008年7月発行)
62巻7号(2008年6月発行)
62巻6号(2008年5月発行)
62巻5号(2008年4月発行)
特集 最近のトピックス2008 Clinical Dermatology 2008
62巻4号(2008年4月発行)
62巻3号(2008年3月発行)
62巻2号(2008年2月発行)
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
61巻10号(2007年9月発行)
61巻9号(2007年8月発行)
61巻8号(2007年7月発行)
61巻7号(2007年6月発行)
61巻6号(2007年5月発行)
61巻5号(2007年4月発行)
特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007
61巻4号(2007年4月発行)
61巻3号(2007年3月発行)
61巻2号(2007年2月発行)
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
60巻11号(2006年10月発行)
60巻10号(2006年9月発行)
60巻9号(2006年8月発行)
60巻8号(2006年7月発行)
60巻7号(2006年6月発行)
60巻6号(2006年5月発行)
60巻4号(2006年4月発行)
60巻5号(2006年4月発行)
特集 最近のトピックス 2006 Clinical Dermatology 2006
60巻3号(2006年3月発行)
60巻2号(2006年2月発行)
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
59巻11号(2005年10月発行)
59巻10号(2005年9月発行)
59巻9号(2005年8月発行)
59巻8号(2005年7月発行)
59巻7号(2005年6月発行)
59巻6号(2005年5月発行)
59巻4号(2005年4月発行)
59巻5号(2005年4月発行)
特集 最近のトピックス2005 Clinical Dermatology 2005
59巻3号(2005年3月発行)
59巻2号(2005年2月発行)
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
58巻12号(2004年11月発行)
58巻11号(2004年10月発行)
58巻10号(2004年9月発行)
58巻9号(2004年8月発行)
58巻8号(2004年7月発行)
58巻7号(2004年6月発行)
58巻6号(2004年5月発行)
58巻4号(2004年4月発行)
58巻5号(2004年4月発行)
特集 最近のトピックス2004 Clinical Dermatology 2004
58巻3号(2004年3月発行)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
57巻10号(2003年9月発行)
57巻9号(2003年8月発行)
57巻8号(2003年7月発行)
57巻7号(2003年6月発行)
57巻6号(2003年5月発行)
57巻4号(2003年4月発行)
57巻5号(2003年4月発行)
特集 最近のトピックス2003 Clinical Dermatology 2003
57巻3号(2003年3月発行)
57巻2号(2003年2月発行)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年8月発行)
56巻8号(2002年7月発行)
56巻7号(2002年6月発行)
56巻6号(2002年5月発行)
56巻5号(2002年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2002
56巻4号(2002年4月発行)
56巻3号(2002年3月発行)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻14号(2001年12月発行)
特集 皮膚真菌症の新しい治療戦略
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
55巻9号(2001年8月発行)
55巻8号(2001年7月発行)
55巻7号(2001年6月発行)
55巻6号(2001年5月発行)
55巻5号(2001年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2001
55巻4号(2001年4月発行)
55巻3号(2001年3月発行)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
54巻10号(2000年9月発行)
54巻9号(2000年8月発行)
54巻8号(2000年7月発行)
54巻7号(2000年6月発行)
54巻6号(2000年5月発行)
54巻5号(2000年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000
54巻4号(2000年4月発行)
54巻3号(2000年3月発行)
54巻2号(2000年2月発行)
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
53巻9号(1999年8月発行)
53巻8号(1999年7月発行)
53巻7号(1999年6月発行)
53巻6号(1999年5月発行)
53巻5号(1999年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1999
53巻4号(1999年4月発行)
53巻3号(1999年3月発行)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
52巻10号(1998年9月発行)
52巻9号(1998年8月発行)
52巻8号(1998年7月発行)
52巻7号(1998年6月発行)
52巻6号(1998年5月発行)
52巻5号(1998年4月発行)
特集 最近のトピックス1998 Clinical Dermatology 1998
52巻4号(1998年4月発行)
52巻3号(1998年3月発行)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
51巻10号(1997年9月発行)
51巻9号(1997年8月発行)
51巻8号(1997年7月発行)
51巻7号(1997年6月発行)
51巻6号(1997年5月発行)
51巻5号(1997年4月発行)
特集 最近のトピックス1997 Clinical Dermatology 1997
51巻4号(1997年4月発行)
51巻3号(1997年3月発行)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
50巻10号(1996年9月発行)
50巻9号(1996年8月発行)
50巻8号(1996年7月発行)
50巻7号(1996年6月発行)
50巻6号(1996年5月発行)
50巻5号(1996年4月発行)
特集 最近のトピックス1996 Clinical Dermatology 1996
50巻4号(1996年4月発行)
50巻3号(1996年3月発行)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
49巻10号(1995年9月発行)
49巻9号(1995年8月発行)
49巻8号(1995年7月発行)
49巻7号(1995年6月発行)
49巻6号(1995年5月発行)
49巻5号(1995年4月発行)
特集 最近のトピックス1995 Clinical Dermatology 1995
49巻4号(1995年4月発行)
49巻3号(1995年3月発行)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
48巻10号(1994年9月発行)
48巻9号(1994年8月発行)
48巻8号(1994年7月発行)
48巻7号(1994年6月発行)
48巻6号(1994年5月発行)
48巻5号(1994年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1994
48巻4号(1994年4月発行)
48巻3号(1994年3月発行)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
47巻10号(1993年9月発行)
47巻9号(1993年8月発行)
47巻8号(1993年7月発行)
47巻7号(1993年6月発行)
47巻6号(1993年5月発行)
47巻5号(1993年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1993
47巻4号(1993年4月発行)
47巻3号(1993年3月発行)
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
46巻10号(1992年9月発行)
46巻9号(1992年8月発行)
46巻8号(1992年7月発行)
46巻7号(1992年6月発行)
46巻6号(1992年5月発行)
46巻5号(1992年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1992
46巻4号(1992年4月発行)
46巻3号(1992年3月発行)
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
45巻10号(1991年9月発行)
45巻9号(1991年8月発行)
45巻8号(1991年7月発行)
45巻7号(1991年6月発行)
45巻6号(1991年5月発行)
45巻5号(1991年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1991
45巻4号(1991年4月発行)
45巻3号(1991年3月発行)
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
44巻9号(1990年8月発行)
44巻8号(1990年7月発行)
44巻7号(1990年6月発行)
44巻6号(1990年5月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1990
44巻5号(1990年5月発行)
44巻4号(1990年4月発行)
44巻3号(1990年3月発行)
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
43巻9号(1989年8月発行)
43巻8号(1989年7月発行)
43巻7号(1989年6月発行)
43巻6号(1989年5月発行)
特集 臨床皮膚科—最近のトピックス
43巻5号(1989年5月発行)
43巻4号(1989年4月発行)
43巻3号(1989年3月発行)
43巻2号(1989年2月発行)
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
42巻6号(1988年6月発行)
42巻5号(1988年5月発行)
42巻4号(1988年4月発行)
42巻3号(1988年3月発行)
42巻2号(1988年2月発行)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻13号(1987年12月発行)
41巻12号(1987年11月発行)
41巻11号(1987年10月発行)
41巻10号(1987年9月発行)
41巻9号(1987年8月発行)
41巻8号(1987年7月発行)
41巻7号(1987年6月発行)
41巻6号(1987年5月発行)
41巻5号(1987年5月発行)
41巻4号(1987年4月発行)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
40巻7号(1986年7月発行)
40巻6号(1986年6月発行)
40巻5号(1986年5月発行)
40巻4号(1986年4月発行)
40巻3号(1986年3月発行)
40巻2号(1986年2月発行)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
39巻6号(1985年6月発行)
39巻5号(1985年5月発行)
39巻4号(1985年4月発行)
39巻3号(1985年3月発行)
39巻2号(1985年2月発行)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
38巻6号(1984年6月発行)
38巻5号(1984年5月発行)
38巻4号(1984年4月発行)
38巻3号(1984年3月発行)
38巻2号(1984年2月発行)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
37巻7号(1983年7月発行)
37巻6号(1983年6月発行)
37巻5号(1983年5月発行)
37巻4号(1983年4月発行)
37巻3号(1983年3月発行)
37巻2号(1983年2月発行)
37巻1号(1983年1月発行)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
36巻8号(1982年8月発行)
36巻7号(1982年7月発行)
36巻6号(1982年6月発行)
36巻5号(1982年5月発行)
36巻4号(1982年4月発行)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
35巻8号(1981年8月発行)
35巻7号(1981年7月発行)
35巻6号(1981年6月発行)
35巻5号(1981年5月発行)
35巻4号(1981年4月発行)
35巻3号(1981年3月発行)
35巻2号(1981年2月発行)
35巻1号(1981年1月発行)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
34巻6号(1980年6月発行)
34巻5号(1980年5月発行)
34巻4号(1980年4月発行)
34巻3号(1980年3月発行)
34巻2号(1980年2月発行)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
33巻6号(1979年6月発行)
33巻5号(1979年5月発行)
33巻4号(1979年4月発行)
33巻3号(1979年3月発行)
33巻2号(1979年2月発行)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
32巻5号(1978年5月発行)
32巻4号(1978年4月発行)
32巻3号(1978年3月発行)
32巻2号(1978年2月発行)
32巻1号(1978年1月発行)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
31巻5号(1977年5月発行)
31巻4号(1977年4月発行)
31巻3号(1977年3月発行)
31巻2号(1977年2月発行)
31巻1号(1977年1月発行)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
30巻5号(1976年5月発行)
30巻4号(1976年4月発行)
30巻3号(1976年3月発行)
30巻2号(1976年2月発行)
30巻1号(1976年1月発行)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
29巻5号(1975年5月発行)
29巻4号(1975年4月発行)
29巻3号(1975年3月発行)
29巻2号(1975年2月発行)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻8号(1974年8月発行)
28巻7号(1974年7月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
28巻5号(1974年5月発行)
28巻4号(1974年4月発行)
28巻3号(1974年3月発行)
28巻2号(1974年2月発行)
28巻1号(1974年1月発行)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
27巻5号(1973年5月発行)
27巻4号(1973年4月発行)
27巻3号(1973年3月発行)
27巻2号(1973年2月発行)
27巻1号(1973年1月発行)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
26巻4号(1972年4月発行)
26巻3号(1972年3月発行)
26巻2号(1972年2月発行)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻13号(1971年12月発行)
特集 小児の皮膚疾患
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
特集 基底膜
25巻6号(1971年6月発行)
25巻5号(1971年5月発行)
25巻4号(1971年4月発行)
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
24巻12号(1970年12月発行)
24巻11号(1970年11月発行)
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
24巻5号(1970年5月発行)
24巻4号(1970年4月発行)
24巻3号(1970年3月発行)
24巻2号(1970年2月発行)
24巻1号(1970年1月発行)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
23巻4号(1969年4月発行)
23巻3号(1969年3月発行)
23巻2号(1969年2月発行)
23巻1号(1969年1月発行)
