患者:51歳,男性.
初診:1998年11月10日.
雑誌目次
臨床皮膚科55巻9号
2001年08月発行
雑誌目次
カラーアトラス
Acquired digital fibrokeratoma
著者: 佐藤友隆 , 永尾圭介 , 松本博子 , 杉浦丹
ページ範囲:P.654 - P.655
原著
抗リン脂質抗体陽性のSLE患者の臨床的検討
著者: 石黒直子 , 石橋睦子 , 山本由美 , 有川順子 , 川島眞 , 内山真一郎
ページ範囲:P.657 - P.664
当科通院中のSLE患者のうち,抗リン脂質抗体陽性者について検討を加えた。SLE患者12例中5例が抗リン脂質抗体陽性であり,頭痛を4例に,一過性黒内障と多発性単神経炎を各1例に認めたが,5例とも網状皮斑や潰瘍形成,血栓性静脈炎,肢端壊疽などの血栓症を思わせるような皮膚症状は認めなかった.検査所見では,血小板減少を2例に,血小板系と凝固系の活性化所見を各3例に認めた.また,MRIで脳梗塞が2例に見いだされた.以上より一過性黒内障を認めた1例と脳梗塞が確認された2例,血小板減少症と多発性単神経炎を認めた1例の計4例を抗リン脂質抗体症候群の合併と考えた.本疾患の基礎疾患として多いSLEでの抗リン脂質抗体の検索の必要性と,陽性例では十分な問診と経過観察のうえ,血小板・凝固系の検査,頭部MRI検査の結果を踏まえて,抗血栓療法を併用すべきことを強調したい.
高齢者に発症したアナフィラクトイド紫斑
著者: 石田雅美 , 岡本玲子 , 川島眞
ページ範囲:P.665 - P.670
症例は81歳の男性,67歳の男性,61歳の女性,64歳の女性である.いずれも下肢を中心に浸潤を触れる紫斑を認めた.組織像ではleukocytoclastic vasculitisを3例に認めた.全例プレドニゾロン内服にて治療を開始した.81歳の男性では経過中に高度の蛋白尿が出現し,67歳の男性では便潜血陽性を認め,内視鏡的には特記すべき所見はなかったが,貧血が進行した.61歳の女性はCAPD(continuos ambulatory peritoneal dialysis;携帯型持続腹膜透析)中であり,発症前にMRSA腹膜炎がみられた.64歳の女性は血液透析シャントに感染したMRSAによる感染性心内膜炎の先行が疑われ,内視鏡下に下行結腸の縦走潰瘍を認めた.
今月の症例
著明なるいそうに伴って多発したvascular spiderの1例
著者: 沖田博 , 大塚勤 , 山蔭明生 , 山崎雙次
ページ範囲:P.671 - P.673
37歳,女性.約5年前から著明な体重減少を認め,神経性食欲不振症と考えられた.その頃より顔面・四肢・手掌・胸部にvascular spiderが多発してきた.検査上,貧血,血小板数低下,軽度肝機能障害,尿酸値高値,アミラーゼ高値,低蛋白血症を認めた.成長ホルモン(GH)高値,freeT3(FT3)低値であったが,血中プロゲステロン,エストラジオールは正常であった.組織学的所見では,真皮浅層に血管の増生・拡張を認め,その血管は1〜2層の内皮細胞によって構成された壁を持っていた.切除後,再発を認めていない.自験例は,神経性食欲不振症の著明なるいそうに伴って出現したvascular spiderの1例であるが,エストロゲン以外の血管増生因子がその発症にかかわっている可能性が考えられた.
症例報告
切傷のある指で熱帯魚を扱い生じたMycobacterium marinumによるfish tank granulomaの1例
著者: 草刈良之 , 原正啓 , 川村真樹 , 田上八朗
ページ範囲:P.675 - P.677
手指から前腕にかけてリンパ行性に出現した皮膚非定型抗酸菌症の1例を報告する.症例は34歳,女性.約3か月前にガラスコップの破片で右手第2指を切り,その部が徐々に腫脹してきた.同時期には熱帯魚を飼育していた.初診時,右手第2指背に潰瘍を伴う紫紅色の結節を2か所認め,その組織所見は肉芽腫性の変化であった.約2週間後に,右前腕部に出現した同様の結節から穿刺して得た黄白色調の液を小川培地(25℃)にて培養した.4週間後に得られた単一のコロニーは,表面平滑,黄色調,光発色性陽性で,Mycobacterium marinumと同定された.ミノマイシン200mg/日,および携帯カイロによる温熱療法を約2か月間継続し,皮疹は徐々に消退した.
広島県で初めて確認された日本紅斑熱の1例
著者: 河田義郎 , 浦久保直澄 , 松本光仁
ページ範囲:P.678 - P.681
広島県で初めて血清学的に確認された日本紅斑熱の症例を経験したので報告する.症例は尾道市在住の農業を営む82歳の男性.右腰背部に2個の径10mm前後の黒色痂皮を付す刺し口と,手掌・足蹠を含む全身に紅斑を伴い,40℃前後の高熱と右鼠径部リンパ節腫脹,肝・脾腫を認めた.日本紅斑熱のYH株に対する抗体価は回復期にIgMは160倍と上昇,IgGは40倍(第35病日)で半年後には640倍となった.Weil-Felix反応はOX2が20倍であった.治療はミノサイクリン200mg/日の点滴を1週間,その後3週間は半分量を経口で投与した.4日目に解熱し,1週間でリンパ節腫脹,肝・脾腫は消退した.
成人呼吸促迫症候群を併発した水痘肺炎の1例
著者: 河本博明 , 井上敏明 , 井上一郎
ページ範囲:P.682 - P.685
35歳,男性.生来健康.初診の2目前より発熱,全身に水疱が出現し急速に増加.水痘の診断で,対症療法にて外来経過観察としたが,翌日より39〜40℃台の発熱が出現し,2日後より激しい咳,胸痛,および呼吸困難も伴うようになり,3日後再診.血液ガス分析にてPaO2が32.1mmHg, O2,飽和度は65.2%と著明に低下し,高度の呼吸不全状態を示した.胸部X線にて両側肺野は全体にすりガラス状で,びまん性に小結節性陰影を認めた.成人呼吸促迫症候群(ARDS)の併発と診断し,人工呼吸器による厳重な呼吸管理およびアシクロビルなどの投与により全身状態は徐々に改善した.成人水痘の場合,病初期には軽症と考えられても,発疹出現1〜6日後に急速に咳嗽,血痰,呼吸困難を起こし,重篤なものはARDSへ移行する水痘肺炎を併発することがある.自験例は経過良好であったが,死亡例の報告もあり,厳重な対応が望まれる.
RPRカード法でプロゾーン現象の認められた第2期顕症梅毒の1例
著者: 肥後尚孝 , 中田土起丈 , 末木博彦 , 飯島正文 , 五味邦英
ページ範囲:P.687 - P.689
38歳,男性.約6か月前に感染機会あり.初診の1か月前より右手関節部に皮疹が出現し,漸次両上肢,躯幹,口囲に拡大.躯幹,両上肢に小豆大〜示指頭大,淡紅褐色,自覚症状のない紅斑が多発し,一部で環状に配列していた.口角にびらん,口囲に丘疹がみられた.初診当日のガラス板法128倍,TPHA法10,240倍.2週間後に生検を施行した.組織学的には血管周囲性に形質細胞浸潤が認められた.生検時の術前検査報告書ではRPR法陰性.当科からの連絡で施行した再検査の結果,原血清は陰性,2〜16倍希釈血清のRPR法は陽性.プロゾーン現象によるRPR法の偽陰性と判明した.
水銀軟膏による水銀皮膚炎の1例
著者: 山田佐知子 , 木花光
ページ範囲:P.690 - P.692
マーキュロクロムによる接触性皮膚炎の既往のある49歳の男性に生じた,水銀軟膏による水銀皮膚炎の1例を報告する.陰部の毛虱に対して市販の水銀軟膏を外用後,同部に重症の皮膚炎を認めただけでなく,離れた頸部,腋窩にも発赤を認めた.血液検査所見より,軽度の肝・腎障害がみられ,水銀の経皮吸収あるいは蒸散水銀の吸入による水銀中毒症状と考えた.水銀軟膏は現在も製造,販売されており,水銀皮膚炎は今後も起こりうる疾患であると再認識した.
シックハウス症候群の1例
著者: 小林康隆 , 中田良子 , 上出良一
ページ範囲:P.693 - P.696
50歳,女性.2000年3月26日,シロアリ駆除のため業者が床下にハチクサンFL®(イミダクロプリド)を撒布し,換気ファンも設置した.同日より,起居している1階室内に刺激臭を感じ,3日後より顔面から前胸部にかけて境界不明瞭なびまん性淡紅色斑,眼瞼の腫脹が生じ,心悸亢進や不安感が強く,4月7日に当科を紹介受診,一般検査にて異常を認めず,使用したシロアリ駆除剤,ホルマリン,ケーソンCGのパッチテストは48時間後,72時間後ともに陰性.心理的な面を含めた治療を行い,また実家で過ごすなど,シロアリ駆除剤との接触を断つことにより症状は軽快.1か月後,シロアリ駆除剤の異臭はほとんど消失し,心悸亢進,紅斑は消失した.以上より,シロアリ駆除剤によるシックハウス症候群と診断した.
パブロンS®中のマレイン酸カルビノキサミンによる角層下膿疱型薬疹の1例
著者: 前田知子 , 中島武之 , 宮島進 , 岡田奈津子
ページ範囲:P.697 - P.699
市販薬パブロンS®により膿疱を伴う多形滲出性紅斑を呈し,成分パッチテストによってマレイン酸カルビノキサミンによる薬疹と診断した1例を報告する.患者は58歳,女性。風邪症状が長引き,パブロンS®を2週間以上内服していた.近医受診時,腹部は膿疱を伴い紅皮症状態であったという.当科初診時には肉眼的膿疱は消失していたが,病理組織学的に角層下膿疱が認められた.プレドニン30mg/日にて治療開始し,約10日で軽快した.退院後,原因薬剤検索の目的で,成分スクラッチパッチテストを行った.抗ヒスタミン作用を有するマレイン酸カルビノキサミンにより膿疱を伴う紅斑がパッチテスト部位に誘発され,同剤による薬疹と診断した.経皮吸収を高めたスクラッチパッチテストにより,ほぼ臨床像に近い皮疹が得られ,膿疱型薬疹の薬剤検索法として有用であると思われた.
Lipophagic panniculitis of childhoodの1例
著者: 田村政昭 , 大西一徳 , 石川治
ページ範囲:P.700 - P.702
5歳の男児.初診の10か月前より左大腿に紅色調の硬い皮下のしこりが出現.その後,徐々に上肢,躯幹にも同様の皮疹が出現した.病理組織学的には脂肪小葉内に単核球,組織球,泡沫細胞,多核巨細胞が浸潤した小葉脂肪織炎の像を呈し,小児に生じたlipophagic panniculitisとした.現在,皮疹の拡大はないが,陥凹が残存している.
劇症肝炎を発症し死亡したChurg-Strauss症候群の1例
著者: 瀬川聡子 , 五十嵐泰子 , 神田憲子 , 石黒直子 , 川島眞 , 針谷正祥 , 林直諒
ページ範囲:P.703 - P.705
53歳,男性.20年前より慢性B型肝炎,2年前より気管支喘息がある.初診の1週間前より出現した下肢の紫斑,浮腫,しびれ感を主訴に当科を受診した.血中好酸球数,IgEの上昇を伴い,紫斑の病理組織像では血管周囲性に著明な好酸球浸潤と一部血管壁の破壊像を認めた.神経・筋生検を施行し,フィブリノイド変性を伴う肉芽腫性血管炎の像を確認し,Churg-Strauss症候群と診断した.皮疹は床上安静のみで速やかに消退したが,血中好酸球数が24,000/mm3まで増加し,下肢のしびれ感も持続したため,プレドニゾロン1日30mgの全身投与を開始した。検査所見,神経症状ともに改善するも,プレドニゾロンの減量中に劇症肝炎を発症し死亡した.
D—ペニシラミン投与中の汎発性強皮症患者に生じた尋常性天疱瘡の1例
著者: 慶田朋子 , 水嶋淳一 , 石黒直子 , 川島眞 , 天谷雅行
ページ範囲:P.707 - P.709
45歳,男性.汎発性強皮症に間質性肺炎を併発し,D—ペニシラミン1日300mgの内服開始約2年後に,被髪頭部を除くほぼ全身に,びらん,水疱が出現した.口腔粘膜疹も認めた.初診時の検査所見では貧血,血沈の亢進,CRP, IgGの上昇を認めた.病理組織像は基底層直上の表皮内水疱で,蛍光抗体直接法で,表皮細胞間にIgGの沈着を認め,血中抗表皮細胞間抗体は320倍,ELISA法にて抗デスモグレイン3抗体,1抗体陽性であった,薬剤中止3週後も軽快せず,プレドニゾロンの内服を開始し,約2か月で略治した.同時に,強皮症の関節拘縮の顕著な改善を認めた.
Linear IgA/IgG bullous dermatosisの1例
著者: 石神光雄 , 栗田みずほ , 田端康一 , 山西清文 , 安野洋一
ページ範囲:P.711 - P.714
Linear IgA/IgG bullous dermatosis(LAGBD)の61歳,男性例を報告する.初診の約半年前より体幹,四肢に瘙痒を伴う紅斑が出現,しだいに皮疹は環状を示し,紅斑の辺縁に沿って小水疱を生じるようになった.採取した生検組織の病理組織学的所見および蛍光抗体直接法で皮膚基底膜部にIgG, IgAの両者の線状沈着を認めたことからLAGBDと診断した.LAGBDはlinear IgA bullous dermatosisの中で基底膜部にIgGの沈着を伴う症例に対して,Zoneらにより提唱された疾患名であるが,その疾患概念について若干の文献的考察を行った.
栄養障害型表皮水疱症の2例
著者: 市川雅子 , 瀬川聡子 , 桧垣祐子 , 川島眞 , 清水宏
ページ範囲:P.715 - P.717
栄養障害型表皮水疱症の2例を報告する.症例1は52歳の女性で,初診の約半年前より四肢関節伸側に瘙痒を伴う水疱,びらん,扁平小結節が出現した.爪の変形を認め,患者の息子,父,父方の叔父とその娘にも同症あり.水疱はlamina densa直下に形成され,anchoring fibrilは減少していたが,正常なものも認められ,VII型コラーゲンの発現量はほぼ正常であった.優性栄養障害型表皮水疱症のpruriginosa型と考えられた.症例2は1歳の中国人女児で,生後10日目より四肢に水疱を繰り返すようになった.爪変形は認めない.家族歴はない.水疱はlaminadensa直下に形成され,VII型コラーゲンの発現量はほぼ正常であったが,正常なanchoring fibrilはほとんど認められず,栄養障害型表皮水疱症と診断した.
ヘリオトロープ疹のみで発症し,8年の経過で皮膚筋炎,全身性強皮症,morpheaを生じた1例
著者: 宍戸悦子 , 石黒直子 , 川島眞
ページ範囲:P.719 - P.721
65歳,女性の皮膚筋炎,全身性強皮症(以下SSc),morpheaの合併例を報告する.1988年12月にヘリオトロープ疹のみが出現し,精査するも筋炎の所見は認めなかった.1991年に両前腕の浮腫性硬化が出現し,皮膚生検にてSScの浮腫期と診断した.1992年に下肢の筋痛,1996年頃より前腕の硬化の増強と筋酵素の上昇,morpheaを認め,その間に抗RNP抗体の陽性化をみた.プレドニゾロン1日40mgの治療を開始したところ,筋炎の軽快とともに前腕,大腿の皮膚硬化の著しい改善も認めた.抗RNP抗体は,膠原病の重複にかかわる1つのマーカーと考える.
老人性血管腫様皮疹を呈したFabry病の1例
著者: 三浦龍司 , 平井昭男 , 右田友房
ページ範囲:P.722 - P.724
50歳,男性.生下時より全身の発汗低下があり,初診の約1か月前より四肢末梢のしびれ感と躯幹・両上腕の皮疹に気づき,当科を受診した.初診時,前胸部と両上腕に自覚症を欠く米粒大までの暗赤色調の光沢を有する丘疹が散在していた.組織学的に,真皮中層までの血管壁の菲薄化を伴う血管拡張像および皮下脂肪織内における血管平滑筋細胞と汗腺腺上皮細胞の空胞化を認めた.電顕的に,空胞化した細胞質内に約60A間隔の高電子密度のミエリン様物質を多数認め,Fabry病と診断した.発汗試験では,温熱発汗は正常で,ピロカルピン負荷により発汗低下を認めた.白血球中のα—galactosidase Aの値は,1.7nmol/mgP/hと低値を示した.発汗障害,末梢神経炎,軽度の蛋白尿を認め,老人性血管腫様皮疹を呈するFabry病の1例を経験したので,若干の考察を加えて報告する.
Cutaneous angiolipoleiomyomaの1例
著者: 嵯峨兵太 , 黒瀬信行
ページ範囲:P.726 - P.728
58歳,女性.初診の約1年前,左頬部の結節に気づくも放置していた.初診時,左頬部に直径12mmの自覚症状のない常色の皮下結節を触れた.下床との可動性は良好であった.病理組織学的には,真皮から皮下組織にかけての線維性被膜に覆われた腫瘍性病変であり,小血管の増生,血管周囲および間質での平滑筋の増殖を認めた.また,一部に脂肪組織の混在を認めたため,自験例をcutaneous angiolipoleiomyomaと診断した.本疾患は比較的稀であり,筆者らの検索しえた限りでは本邦報告例は見当たらなかった.
下腿に生じた浸潤性外毛根鞘癌の1例
著者: 菅原弘士 , 加藤直子 , 青柳哲 , 木村久美子 , 西川勝司
ページ範囲:P.729 - P.731
65歳,女性.右下腿に直径2.3×2.5cmの茶褐色の角化性腫瘤を呈した浸潤性外毛根鞘癌の1例を報告する.組織学的に真皮網状層下層まで腫瘍細胞増殖を示した.腫瘍胞巣の外層には集塊細胞,異常角化細胞を含むBowen病様の像があり,内層にはグリコーゲンを有する淡明細胞が増生していた.胞巣の一部では中央部が嚢腫状となり,その中に好酸性の無構造物質の充満を認めた.今回,筆者らは1985年以降15年間の浸潤性外毛根鞘癌の本邦報告例20例に自験例を加えまとめた.リンパ節転移が21例中8例,38%に認められ,3例には遠隔転移も認められた.
連載
Clinical Exercises・101—出題と解答
著者: 松永佳世子
ページ範囲:P.714 - P.714
201
ラテックスアレルギーについて正しい記載はどれか.
①ラテックスアレルギーによる死亡例の原因製品として最も多いのは天然ゴムラテックス手袋である.
海外生活16年—出会った人・学んだこと・8
著者: 神保孝一
ページ範囲:P.736 - P.736
ハーバード大学医学部皮膚科学講座のスタッフの紹介(その3)
Fitzpatrick教授のハーバード大学における最初の門下生は,Harward BadenとIrvin Freedburgであった.この2人がFitzpatrick教授の指導のもとで,ハーバード大学医学部皮膚科でスタッフとしてどのような教育を受け,成長し,その後どのような人生を歩んでいったかは,アメリカのアカデミックな領域,ことに大学における人事の一面を考える際に興味のあるものである.
まず2人は,多くの共通点を有する,例えば,ともに生粋のユダヤ系であること,ハーバード大学でレジデントの修練を受けたこと,共通の師を有し,ともにその一期生であること,同じ皮膚角化細胞の研究領域に進んだこと,しかもともにその研究領域において世界的に認められ,皮膚科学の研究雑誌としてはベストである“Journal of Investigative Dermatology”のエディターとなったことなどである.一方,異とする点としては,Badenは幼少時から経済的に苦労して育ったのに対し,Freedburgは裕福な家庭の一人息子として育った.Badenは論議の場において極めて率直に自分の意見を述べ,なかなか妥協しようとしない.他方,Freedburgはソフトに話し,周囲を見,しばしば政治的判断を加えたうえで自分の意見を述べる.また,Badenは学会などにおいても極めてストレートに自分の意見を述べる.Freedburgは石橋を叩いて逆に後退する.学会に出ていても,何をいおうとしているのか,わかりづらい場合もしばしばあった.研究論文の発表数も,Badenは原著の論文が202以上あるのに,Freedburgは88しかない.このように比較すると,BadenがFreedburgよりはるかに抜きん出て,アカデミックな領域で成功するように見えるが,現実は必ずしもそうではなかった.まずハーバード大学における教授としての就任は,Fitzpatrick教授がBadenを最初に推薦したにもかかわらず,Freedburgが先になった.この裏話としてFreedburgの叔父さんが当時,ハーバード大学の循環器科の教授であったため,強くFreedburgを推薦したという噂があった.Freedburgは,“Journal of Investigative Dermatology”のエディターになった後すぐに,アメリカで最も伝統のある医学部の1つであるニューヨーク大学の主任教授として栄転した.多くの学会賞を獲得し,日本にも土肥記念講演者として招かれた.しかるにBadenは,ハーバード大学皮膚科の教授のままであり,他大学の主任教授とはならずじまいで,多分そのままで退官するであろう.
治療
苺状血管腫に対する色素レーザー治療の効果とその限界
著者: 木下涼子 , 安田浩 , 旭正一
ページ範囲:P.733 - P.735
近年,血管腫に対する色素レーザー治療の有用性の報告がみられるようになってきたが,苺状血管腫の報告例は単純性血管腫に比べ少ない.そこで,苺状血管腫に対する色素レーザー治療の経験を報告する.症例は生後1〜7か月までの9例10部位,照射回数は1〜5回(平均2.9回),観察期間は2か月〜1年10か月であった.結果は9症例10部位のうち追跡できなかった1例を除いて,著効3例,改善4例,不変1例であった.今回,生後早期,つまり腫瘤形成前に照射を開始したものは,短い観察期間内に瘢痕を残さず消失,縮小の結果が得られた.一方,腫瘤形成後に照射を開始したものは,色調の消失はみられても,皮膚の萎縮,瘢痕が残った.よって,苺状血管腫に対しては遅くとも生後6か月以内に積極的に治療を開始するべきであり,さらには腫瘤型では扁平化と瘢痕の抑制には限界があり,レーザー治療中止時期の判断も重要になると思われた.
基本情報
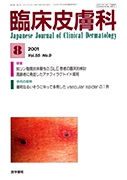
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
78巻12号(2024年11月発行)
78巻11号(2024年10月発行)
78巻10号(2024年9月発行)
78巻9号(2024年8月発行)
78巻8号(2024年7月発行)
78巻7号(2024年6月発行)
78巻6号(2024年5月発行)
78巻5号(2024年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024
78巻4号(2024年4月発行)
78巻3号(2024年3月発行)
78巻2号(2024年2月発行)
78巻1号(2024年1月発行)
77巻13号(2023年12月発行)
77巻12号(2023年11月発行)
77巻11号(2023年10月発行)
77巻10号(2023年9月発行)
77巻9号(2023年8月発行)
77巻8号(2023年7月発行)
77巻7号(2023年6月発行)
77巻6号(2023年5月発行)
77巻5号(2023年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023
77巻4号(2023年4月発行)
77巻3号(2023年3月発行)
77巻2号(2023年2月発行)
77巻1号(2023年1月発行)
76巻13号(2022年12月発行)
76巻12号(2022年11月発行)
76巻11号(2022年10月発行)
76巻10号(2022年9月発行)
76巻9号(2022年8月発行)
76巻8号(2022年7月発行)
76巻7号(2022年6月発行)
76巻6号(2022年5月発行)
76巻5号(2022年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022
76巻4号(2022年4月発行)
76巻3号(2022年3月発行)
76巻2号(2022年2月発行)
76巻1号(2022年1月発行)
75巻13号(2021年12月発行)
75巻12号(2021年11月発行)
75巻11号(2021年10月発行)
75巻10号(2021年9月発行)
75巻9号(2021年8月発行)
75巻8号(2021年7月発行)
75巻7号(2021年6月発行)
75巻6号(2021年5月発行)
75巻5号(2021年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021
75巻4号(2021年4月発行)
75巻3号(2021年3月発行)
75巻2号(2021年2月発行)
75巻1号(2021年1月発行)
74巻13号(2020年12月発行)
74巻12号(2020年11月発行)
74巻11号(2020年10月発行)
74巻10号(2020年9月発行)
74巻9号(2020年8月発行)
74巻8号(2020年7月発行)
74巻7号(2020年6月発行)
74巻6号(2020年5月発行)
74巻5号(2020年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2020 Clinical Dermatology 2020
74巻4号(2020年4月発行)
74巻3号(2020年3月発行)
74巻2号(2020年2月発行)
74巻1号(2020年1月発行)
73巻13号(2019年12月発行)
73巻12号(2019年11月発行)
73巻11号(2019年10月発行)
73巻10号(2019年9月発行)
73巻9号(2019年8月発行)
73巻8号(2019年7月発行)
73巻7号(2019年6月発行)
73巻6号(2019年5月発行)
73巻5号(2019年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2019 Clinical Dermatology 2019
73巻4号(2019年4月発行)
73巻3号(2019年3月発行)
73巻2号(2019年2月発行)
73巻1号(2019年1月発行)
72巻13号(2018年12月発行)
72巻12号(2018年11月発行)
72巻11号(2018年10月発行)
72巻10号(2018年9月発行)
72巻9号(2018年8月発行)
72巻8号(2018年7月発行)
72巻7号(2018年6月発行)
72巻6号(2018年5月発行)
72巻5号(2018年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2018 Clinical Dermatology 2018
72巻4号(2018年4月発行)
72巻3号(2018年3月発行)
72巻2号(2018年2月発行)
72巻1号(2018年1月発行)
71巻13号(2017年12月発行)
71巻12号(2017年11月発行)
71巻11号(2017年10月発行)
71巻10号(2017年9月発行)
71巻9号(2017年8月発行)
71巻8号(2017年7月発行)
71巻7号(2017年6月発行)
71巻6号(2017年5月発行)
71巻5号(2017年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2017 Clinical Dermatology 2017
71巻4号(2017年4月発行)
71巻3号(2017年3月発行)
71巻2号(2017年2月発行)
71巻1号(2017年1月発行)
70巻13号(2016年12月発行)
70巻12号(2016年11月発行)
70巻11号(2016年10月発行)
70巻10号(2016年9月発行)
70巻9号(2016年8月発行)
70巻8号(2016年7月発行)
70巻7号(2016年6月発行)
70巻6号(2016年5月発行)
70巻5号(2016年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2016 Clinical Dermatology 2016
70巻4号(2016年4月発行)
70巻3号(2016年3月発行)
70巻2号(2016年2月発行)
70巻1号(2016年1月発行)
69巻13号(2015年12月発行)
69巻12号(2015年11月発行)
69巻11号(2015年10月発行)
69巻10号(2015年9月発行)
69巻9号(2015年8月発行)
69巻8号(2015年7月発行)
69巻7号(2015年6月発行)
69巻6号(2015年5月発行)
69巻5号(2015年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2015 Clinical Dermatology 2015
69巻4号(2015年4月発行)
69巻3号(2015年3月発行)
69巻2号(2015年2月発行)
69巻1号(2015年1月発行)
68巻13号(2014年12月発行)
68巻12号(2014年11月発行)
68巻11号(2014年10月発行)
68巻10号(2014年9月発行)
68巻9号(2014年8月発行)
68巻8号(2014年7月発行)
68巻7号(2014年6月発行)
68巻6号(2014年5月発行)
68巻5号(2014年4月発行)
増刊号特集 最近のトピックス2014 Clinical Dermatology 2014
68巻4号(2014年4月発行)
68巻3号(2014年3月発行)
68巻2号(2014年2月発行)
68巻1号(2014年1月発行)
67巻13号(2013年12月発行)
67巻12号(2013年11月発行)
67巻11号(2013年10月発行)
67巻10号(2013年9月発行)
67巻9号(2013年8月発行)
67巻8号(2013年7月発行)
67巻7号(2013年6月発行)
67巻6号(2013年5月発行)
67巻5号(2013年4月発行)
特集 最近のトピックス2013 Clinical Dermatology 2013
67巻4号(2013年4月発行)
67巻3号(2013年3月発行)
67巻2号(2013年2月発行)
67巻1号(2013年1月発行)
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
66巻11号(2012年10月発行)
66巻10号(2012年9月発行)
66巻9号(2012年8月発行)
66巻8号(2012年7月発行)
66巻7号(2012年6月発行)
66巻6号(2012年5月発行)
66巻5号(2012年4月発行)
特集 最近のトピックス2012 Clinical Dermatology 2012
66巻4号(2012年4月発行)
66巻3号(2012年3月発行)
66巻2号(2012年2月発行)
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
65巻11号(2011年10月発行)
65巻10号(2011年9月発行)
65巻9号(2011年8月発行)
65巻8号(2011年7月発行)
65巻7号(2011年6月発行)
65巻6号(2011年5月発行)
65巻5号(2011年4月発行)
特集 最近のトピックス2011 Clinical Dermatology 2011
65巻4号(2011年4月発行)
65巻3号(2011年3月発行)
65巻2号(2011年2月発行)
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
64巻12号(2010年11月発行)
64巻11号(2010年10月発行)
64巻10号(2010年9月発行)
64巻9号(2010年8月発行)
64巻8号(2010年7月発行)
64巻7号(2010年6月発行)
64巻6号(2010年5月発行)
64巻5号(2010年4月発行)
特集 最近のトピックス2010 Clinical Dermatology 2010
64巻4号(2010年4月発行)
64巻3号(2010年3月発行)
64巻2号(2010年2月発行)
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
63巻11号(2009年10月発行)
63巻10号(2009年9月発行)
63巻9号(2009年8月発行)
63巻8号(2009年7月発行)
63巻7号(2009年6月発行)
63巻6号(2009年5月発行)
63巻5号(2009年4月発行)
特集 最近のトピックス2009 Clinical Dermatology 2009
63巻4号(2009年4月発行)
63巻3号(2009年3月発行)
63巻2号(2009年2月発行)
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
62巻11号(2008年10月発行)
62巻10号(2008年9月発行)
62巻9号(2008年8月発行)
62巻8号(2008年7月発行)
62巻7号(2008年6月発行)
62巻6号(2008年5月発行)
62巻5号(2008年4月発行)
特集 最近のトピックス2008 Clinical Dermatology 2008
62巻4号(2008年4月発行)
62巻3号(2008年3月発行)
62巻2号(2008年2月発行)
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
61巻10号(2007年9月発行)
61巻9号(2007年8月発行)
61巻8号(2007年7月発行)
61巻7号(2007年6月発行)
61巻6号(2007年5月発行)
61巻5号(2007年4月発行)
特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007
61巻4号(2007年4月発行)
61巻3号(2007年3月発行)
61巻2号(2007年2月発行)
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
60巻11号(2006年10月発行)
60巻10号(2006年9月発行)
60巻9号(2006年8月発行)
60巻8号(2006年7月発行)
60巻7号(2006年6月発行)
60巻6号(2006年5月発行)
60巻4号(2006年4月発行)
60巻5号(2006年4月発行)
特集 最近のトピックス 2006 Clinical Dermatology 2006
60巻3号(2006年3月発行)
60巻2号(2006年2月発行)
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
59巻11号(2005年10月発行)
59巻10号(2005年9月発行)
59巻9号(2005年8月発行)
59巻8号(2005年7月発行)
59巻7号(2005年6月発行)
59巻6号(2005年5月発行)
59巻4号(2005年4月発行)
59巻5号(2005年4月発行)
特集 最近のトピックス2005 Clinical Dermatology 2005
59巻3号(2005年3月発行)
59巻2号(2005年2月発行)
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
58巻12号(2004年11月発行)
58巻11号(2004年10月発行)
58巻10号(2004年9月発行)
58巻9号(2004年8月発行)
58巻8号(2004年7月発行)
58巻7号(2004年6月発行)
58巻6号(2004年5月発行)
58巻4号(2004年4月発行)
58巻5号(2004年4月発行)
特集 最近のトピックス2004 Clinical Dermatology 2004
58巻3号(2004年3月発行)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
57巻10号(2003年9月発行)
57巻9号(2003年8月発行)
57巻8号(2003年7月発行)
57巻7号(2003年6月発行)
57巻6号(2003年5月発行)
57巻4号(2003年4月発行)
57巻5号(2003年4月発行)
特集 最近のトピックス2003 Clinical Dermatology 2003
57巻3号(2003年3月発行)
57巻2号(2003年2月発行)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年8月発行)
56巻8号(2002年7月発行)
56巻7号(2002年6月発行)
56巻6号(2002年5月発行)
56巻5号(2002年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2002
56巻4号(2002年4月発行)
56巻3号(2002年3月発行)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻14号(2001年12月発行)
特集 皮膚真菌症の新しい治療戦略
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
55巻9号(2001年8月発行)
55巻8号(2001年7月発行)
55巻7号(2001年6月発行)
55巻6号(2001年5月発行)
55巻5号(2001年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2001
55巻4号(2001年4月発行)
55巻3号(2001年3月発行)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
54巻10号(2000年9月発行)
54巻9号(2000年8月発行)
54巻8号(2000年7月発行)
54巻7号(2000年6月発行)
54巻6号(2000年5月発行)
54巻5号(2000年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000
54巻4号(2000年4月発行)
54巻3号(2000年3月発行)
54巻2号(2000年2月発行)
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
53巻9号(1999年8月発行)
53巻8号(1999年7月発行)
53巻7号(1999年6月発行)
53巻6号(1999年5月発行)
53巻5号(1999年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1999
53巻4号(1999年4月発行)
53巻3号(1999年3月発行)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
52巻10号(1998年9月発行)
52巻9号(1998年8月発行)
52巻8号(1998年7月発行)
52巻7号(1998年6月発行)
52巻6号(1998年5月発行)
52巻5号(1998年4月発行)
特集 最近のトピックス1998 Clinical Dermatology 1998
52巻4号(1998年4月発行)
52巻3号(1998年3月発行)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
51巻10号(1997年9月発行)
51巻9号(1997年8月発行)
51巻8号(1997年7月発行)
51巻7号(1997年6月発行)
51巻6号(1997年5月発行)
51巻5号(1997年4月発行)
特集 最近のトピックス1997 Clinical Dermatology 1997
51巻4号(1997年4月発行)
51巻3号(1997年3月発行)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
50巻10号(1996年9月発行)
50巻9号(1996年8月発行)
50巻8号(1996年7月発行)
50巻7号(1996年6月発行)
50巻6号(1996年5月発行)
50巻5号(1996年4月発行)
特集 最近のトピックス1996 Clinical Dermatology 1996
50巻4号(1996年4月発行)
50巻3号(1996年3月発行)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
49巻10号(1995年9月発行)
49巻9号(1995年8月発行)
49巻8号(1995年7月発行)
49巻7号(1995年6月発行)
49巻6号(1995年5月発行)
49巻5号(1995年4月発行)
特集 最近のトピックス1995 Clinical Dermatology 1995
49巻4号(1995年4月発行)
49巻3号(1995年3月発行)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
48巻10号(1994年9月発行)
48巻9号(1994年8月発行)
48巻8号(1994年7月発行)
48巻7号(1994年6月発行)
48巻6号(1994年5月発行)
48巻5号(1994年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1994
48巻4号(1994年4月発行)
48巻3号(1994年3月発行)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
47巻10号(1993年9月発行)
47巻9号(1993年8月発行)
47巻8号(1993年7月発行)
47巻7号(1993年6月発行)
47巻6号(1993年5月発行)
47巻5号(1993年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1993
47巻4号(1993年4月発行)
47巻3号(1993年3月発行)
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
46巻10号(1992年9月発行)
46巻9号(1992年8月発行)
46巻8号(1992年7月発行)
46巻7号(1992年6月発行)
46巻6号(1992年5月発行)
46巻5号(1992年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1992
46巻4号(1992年4月発行)
46巻3号(1992年3月発行)
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
45巻10号(1991年9月発行)
45巻9号(1991年8月発行)
45巻8号(1991年7月発行)
45巻7号(1991年6月発行)
45巻6号(1991年5月発行)
45巻5号(1991年4月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1991
45巻4号(1991年4月発行)
45巻3号(1991年3月発行)
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
44巻9号(1990年8月発行)
44巻8号(1990年7月発行)
44巻7号(1990年6月発行)
44巻6号(1990年5月発行)
特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1990
44巻5号(1990年5月発行)
44巻4号(1990年4月発行)
44巻3号(1990年3月発行)
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
43巻9号(1989年8月発行)
43巻8号(1989年7月発行)
43巻7号(1989年6月発行)
43巻6号(1989年5月発行)
特集 臨床皮膚科—最近のトピックス
43巻5号(1989年5月発行)
43巻4号(1989年4月発行)
43巻3号(1989年3月発行)
43巻2号(1989年2月発行)
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
42巻6号(1988年6月発行)
42巻5号(1988年5月発行)
42巻4号(1988年4月発行)
42巻3号(1988年3月発行)
42巻2号(1988年2月発行)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻13号(1987年12月発行)
41巻12号(1987年11月発行)
41巻11号(1987年10月発行)
41巻10号(1987年9月発行)
41巻9号(1987年8月発行)
41巻8号(1987年7月発行)
41巻7号(1987年6月発行)
41巻6号(1987年5月発行)
41巻5号(1987年5月発行)
41巻4号(1987年4月発行)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
40巻7号(1986年7月発行)
40巻6号(1986年6月発行)
40巻5号(1986年5月発行)
40巻4号(1986年4月発行)
40巻3号(1986年3月発行)
40巻2号(1986年2月発行)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
39巻6号(1985年6月発行)
39巻5号(1985年5月発行)
39巻4号(1985年4月発行)
39巻3号(1985年3月発行)
39巻2号(1985年2月発行)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
38巻6号(1984年6月発行)
38巻5号(1984年5月発行)
38巻4号(1984年4月発行)
38巻3号(1984年3月発行)
38巻2号(1984年2月発行)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
37巻7号(1983年7月発行)
37巻6号(1983年6月発行)
37巻5号(1983年5月発行)
37巻4号(1983年4月発行)
37巻3号(1983年3月発行)
37巻2号(1983年2月発行)
37巻1号(1983年1月発行)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
36巻8号(1982年8月発行)
36巻7号(1982年7月発行)
36巻6号(1982年6月発行)
36巻5号(1982年5月発行)
36巻4号(1982年4月発行)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
35巻8号(1981年8月発行)
35巻7号(1981年7月発行)
35巻6号(1981年6月発行)
35巻5号(1981年5月発行)
35巻4号(1981年4月発行)
35巻3号(1981年3月発行)
35巻2号(1981年2月発行)
35巻1号(1981年1月発行)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
34巻6号(1980年6月発行)
34巻5号(1980年5月発行)
34巻4号(1980年4月発行)
34巻3号(1980年3月発行)
34巻2号(1980年2月発行)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
33巻6号(1979年6月発行)
33巻5号(1979年5月発行)
33巻4号(1979年4月発行)
33巻3号(1979年3月発行)
33巻2号(1979年2月発行)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
32巻5号(1978年5月発行)
32巻4号(1978年4月発行)
32巻3号(1978年3月発行)
32巻2号(1978年2月発行)
32巻1号(1978年1月発行)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
31巻5号(1977年5月発行)
31巻4号(1977年4月発行)
31巻3号(1977年3月発行)
31巻2号(1977年2月発行)
31巻1号(1977年1月発行)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
30巻5号(1976年5月発行)
30巻4号(1976年4月発行)
30巻3号(1976年3月発行)
30巻2号(1976年2月発行)
30巻1号(1976年1月発行)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
29巻5号(1975年5月発行)
29巻4号(1975年4月発行)
29巻3号(1975年3月発行)
29巻2号(1975年2月発行)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻8号(1974年8月発行)
28巻7号(1974年7月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
28巻5号(1974年5月発行)
28巻4号(1974年4月発行)
28巻3号(1974年3月発行)
28巻2号(1974年2月発行)
28巻1号(1974年1月発行)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
27巻5号(1973年5月発行)
27巻4号(1973年4月発行)
27巻3号(1973年3月発行)
27巻2号(1973年2月発行)
27巻1号(1973年1月発行)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
26巻4号(1972年4月発行)
26巻3号(1972年3月発行)
26巻2号(1972年2月発行)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻13号(1971年12月発行)
特集 小児の皮膚疾患
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
特集 基底膜
25巻6号(1971年6月発行)
25巻5号(1971年5月発行)
25巻4号(1971年4月発行)
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
24巻12号(1970年12月発行)
24巻11号(1970年11月発行)
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
24巻5号(1970年5月発行)
24巻4号(1970年4月発行)
24巻3号(1970年3月発行)
24巻2号(1970年2月発行)
24巻1号(1970年1月発行)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
23巻4号(1969年4月発行)
23巻3号(1969年3月発行)
23巻2号(1969年2月発行)
23巻1号(1969年1月発行)
