アルコール性肝障害に対する概念の変遷
アルコール性肝障害の発生機序については,現在もなお不明の点が多く残されており,真の成因は不明といわなければならない.歴史的にみると,大酒家に肝障害の多いことは,すでに16世紀頃より気づかれていたのであるが,その発生要因についての考え方には大きな変遷がみられている.20世紀初頭までは,大酒家に肝障害の多いことより,単純にアルコールが有害であると考えられていたが,1930年代頃より,栄養障害性肝硬変の実験的作成,栄養学の進歩などがあって,肝障害の発生はアルコールの過剰摂取に伴う栄養障害に由来するとする間接障害説が強調されるようになった,しかし,近年に到り,Rubinら1)によって,十分バランスのとれた栄養条件下でも,アルコールの過剰摂取によって肝炎・肝硬変が実験的に作成しうることが明らかにされ,アルコールの直接的障害作用が再認識されてきた里このように現在では,アルコールがなんらかの形で直接的肝障害作用を有し,栄養性因子は肝障害の発生には副次的な役割を果たすに過ぎないとの見方が大勢を占めるようになってきている.しかし,ヒト大酒家にみられる肝病変がアルコールのみの単独の障害作用に由来するのか,また,なぜアルコールが障害的に作用するかの詳細については不明のままである.
雑誌目次
medicina13巻10号
1976年10月発行
雑誌目次
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
理解のための10題
ページ範囲:P.1398 - P.1400
臓器障害,なぜ起こるか
肝臓
著者: 高田昭
ページ範囲:P.1348 - P.1349
胃と腸
著者: 田中三千雄 , 堤京子 , 竹本忠良
ページ範囲:P.1350 - P.1351
appetizerとして食膳をにぎわしているアルコール飲料は,消化管に多大の作用を及ぼしている.
胃液の分泌亢進は,その最たるものであろう,たとえば,1合の日本酒は,胃液検査法として今日広く行われているガストリン刺激法(4μg/kg,筋注)にほぼ匹敵するほどの,胃液の分泌刺激能をもっている1).また同時に,腸液の分泌2),胃腸管の蠕動運動3〜5),そして胃腸管粘膜血流量19)などにも影響を及ぼしている.
膵臓
著者: 小田正幸 , 本間達二 , 長田敦夫
ページ範囲:P.1352 - P.1353
はじめに
アルコール過飲が膵炎の原因となることは古くより知られ,最近,わが国でもアルコール膵炎は著しく増加してきている.1974年,厚生省慢性膵炎調査研究班の報告工)では,慢性膵炎のうちアルコールが関与すると思われる症例は約半数に達している.
この背景には,わが国での近年のアルコール消費量の著しい増加があると思われ,外国での報告をみても,慢性膵炎患者とアルコール消費量はほぼ正の相関が認められている.しかし,アルコール膵炎の頻度は国や民族(地理的因子,遺伝,体質),食生活(栄養因子)によって差があること,また,大酒家でも膵炎を発症しない人の方が多く,さらにアルコール膵炎とアルコール肝硬変を同時に合併することはまれであることなど,アルコールと膵との関係は疫学的事項からみても複雑である.
脳・神経・筋
著者: 古和久幸
ページ範囲:P.1354 - P.1355
アルコールによる神経・筋症状は多彩で,その発生機序も一様でなく,不明なものも少なくない.一方,アルコールの摂取量と症状の発現についても個人差があり,摂取速度,期間,全身状態,平常の食事の状況など多くの因子の関与が想定される.したがって,アルコール痛飲あるいは多飲後にみられた神経系障害では,アルコールが症状発現のtriggerになった可能性は否定はできないが,それらすべてをアルコールに起因するとは断定できない場合もある.
循環器—アルコールの急性毒性および慢性毒性の発生機序
著者: 南勝 , 安田寿一
ページ範囲:P.1356 - P.1358
はじめに
アルコールの慢性摂取と,臨床的なアルコール性心筋症との間には,経験的に相関のあることが示唆されている1)が,この病因に関して,アルコールの果たしている役割については議論の多いところである.
ここでは,長期のアルコール摂取者にしばしば合併する,ビタミンB1欠乏による脚気心2)や,ビール中の添加物であるコバルト塩過剰摂取によるコバルト心筋症3)のように原因の確定できるものを除いて,エタノール単独の心筋への影響,とくに心筋構造への影響,心機能との関わり合い,毒性発現の機序などを,急性と慢性効果に分けて考察を加えたい.
造血器
著者: 高橋隆一
ページ範囲:P.1359 - P.1361
アルコール中毒の時に,骨髄の赤芽球および幼若顆粒球の空胞形成,胃腸出血による鉄欠乏性貧血,葉酸欠乏による巨赤芽球性貧血,可逆的な鉄芽球性貧血,肝硬変症を伴う慢性溶血などの種々の型の貧血,顆粒球減少,顆粒球の動員障害および血小板減少などの多彩な血液異常の認められることが知られている1).しかし,不摂生な食事のための栄養失調症,とくにビタミン欠乏症,肝硬変症,胃潰瘍および感染症などを合併することが多いため,血液異常がアルコールの直接作用によるものか,合併症によるものかが明らかでなかった.
最近,アルコール投与実験を中心に血液学的および生化学的研究が行われ,アルコールの直接作用によってどのような血液異常が起きるかが明らかにされつつある.しかし,なぜ起こるかについては未だに一部しか明らかにされていない.わが国におけるこの方面の研究はほとんどなく,したがって文献もほとんどないが,アルコール中毒による血液異常を認めることが多くなりつつあるので,その概要を述べてみたい.
免疫機能—アルコール中毒者を中心に
著者: 土屋雅春 , 高木敏 , 吉武泰俊
ページ範囲:P.1362 - P.1363
アルコール中毒者における肝障害の発生機序については,アルコール自身による直接肝毒性1)を主とし,栄養障害等の種々の修飾因子が考えられている.しかし,中毒者の大多数は脂肪肝で,肝硬変症に進展していく者は10〜15%にすぎないとされている2),アルコール摂取量,飲酒期間,栄養状態が同じような条件下においても,一方では脂肪肝程度にとどまり,他方では,アルコール性肝硬変へ進展していくものがあることは,アルコールに対する生体の反応性の差,すなわち個体差の関与が重視される.
アルコール中毒者では,高率に細胞性免疫異常がみられており3),さらに近年,アルコール性肝障害の進展機序の一部に細胞性免疫異常の関与していることが明らかにされてきている4).本稿では,とくにアルコール中毒者の細胞性免疫を中心に述べ,アルコール性肝障害の発生機序についても考察を加える.
アルコールと代謝異常
水・電解質代謝
著者: 庵政志
ページ範囲:P.1364 - P.1365
アルコールと水・電解質バランスとの関係は,極めて身近の現象であるために各人の経験から,医師の間においてすらも見解の不一致がみられている.
糖質代謝
著者: 尾林紀雄 , 種瀬富男
ページ範囲:P.1366 - P.1367
消化管より吸収されたアルコールは,主に肝臓で代謝される.アルコール脱水素酵素と補酵素NDAによって,一部はmicrosomal ethanol oxidating system(MEOS)でNADPHによってアセトアルデヒドへと代謝される.次いでアセトアルデヒドは酢酸ないしacetyl COAに酸化され,TCA cycleに入ってCO2とH2Oへと酸化されていく.このようにアルコールが酸化されると,NAD+H→NADHへの反応がすすみ,NADH/NADが増加することになる.一方,糖代謝に関与する因子であるAMP(adenosine monophosphate)は少量のアルコールによって増加するといわれている1).
蛋白代謝
著者: 平山千里 , 古賀俊逸 , 関屋正彦
ページ範囲:P.1368 - P.1369
アルコール性肝臓病の病態のひとつに,蛋白代謝障害があげられる.たとえば,アルコール性肝炎,アルコール性肝硬変などでは,低蛋白血症をみる場合が多いが,これは蛋白栄養や蛋白代謝の障害によって成立するものである.事実,アルコール性肝臓病にみられる浮腫,腹水などは,アルコールの禁止や栄養改善によってコントロールしうることが多い.すなわち,アルコール性肝臓病における蛋白代謝の異常は,アルコールの直接または間接の障害に起因するものと考えることができる.
脂質代謝
著者: 武藤泰敏
ページ範囲:P.1370 - P.1372
アルコール摂取によって早期に,しかも最も高率に観察されるのは高脂血症と脂肪肝であり,アルコールの脂質代謝に及ぼす影響は極めて大きい.アルコールは高熱量源(7Cal/g)であるとともに,他の栄養素に先行して利用される化合物でもある.それゆえ,アルコールの代謝一般に及ぼす影響を論ずる場合には,どのような栄養状態にあるかを把握することが大切であろう.
筆者らが実際に食事調査をしたところ,毎日約1009のアルコール(清酒約5合)を連用する場合,糖質摂取量は著減するが,脂肪および蛋白質摂取量には大きな影響がないという結果が得られた(図1).このように低蛋白栄養状態がなくとも,肝障害(血清γ-GTPおよびGOT活性上昇はそれぞれ約60%と30%)ならびに高脂血症(約50%)が観察されている.
カラーグラフ
アルコール性肝障害の病理所見
著者: 岩村健一郎
ページ範囲:P.1374 - P.1375
病理学的にアルコール性肝障害を規定し得ろ特有な変化は認めろれていない.確かに国際肝臓学会において"アルコール性肝炎"とか"アルコール性肝硬変"の診断基準が提案されてはいる.だが,地理病理学的な違いも考えられることであるかろ,まずわが国におけるアルコール肝障害を臨床病理学的に検討することが大切であろう.そのような意味で,筆者が今日までに臨床の場で遭遇したた酒家における肝の病変を示すことにしよう.
日常問題になるのは,長期にわたる大酒家における肝障害である.したがって,急性アルコール中毒性肝障害であっても,その基盤には慢性障害があると考えなければならないであろう.組織学的に急性と慢性を分けることは可能であるが,臨床上,腹腔鏡にとらえろれるアルコール肝障害としては,脂肪肝,炎症所見を伴う脂肪肝,あるいは脂肪性肝硬変がある.
アルコール性疾患診断のポイント
アルコール性心筋症
著者: 小出直
ページ範囲:P.1377 - P.1377
大酒家に心筋症の多いこと,また,大酒家の心筋症患者が種々の点で他の特発性心筋症患者と異なる傾向を示すことなどから,"大酒家に発生した心筋症で大酒歴以外に明らかな心筋障害の原因の見当たらないもの"をアルコール性心筋症の名で呼び,ふつうの特発性心筋症と区別して扱うことがある.ただし,特異的な所見がないので,個々の症例について診断を下すには注意深く他疾患を除外することが極めて重要である.他方,実際的な立場からすると,重篤な心筋症に陥る前の軽症例をいかにして発見するかが,これに劣らず重要である.以下,診療の各段階を追って診断上の注意点を説明する.
アルコール性肝炎
著者: 伊藤進
ページ範囲:P.1378 - P.1379
アルコール性肝障害として,臨床的にも脂肪肝,肝硬炎のあることは理解されていたが,最近,脂肪肝が直接的に肝硬変へ移行するのではなく,その間に肝細胞の変性,壊死,炎症が存在し,これがアルコール性肝炎として肝硬変へ導きうる病像であるということがわかってきた.当初は急性アルコール性肝炎,あるいはまた,alcoholic steatonecrosis,sclerosing hyaline necrosisなどともいわれていたが,現在では,alcoholic hepatitisが最も妥当性のある術語として用いられてきた.
ここではFogarty international center proceedings No. 221)および筆者らの知見2〜5)に基づいて,その診断基準を概説し,ついで特徴的にみられるアルコール硝子体とこの肝炎の発症機構についても述べたい.
アルコール性多発神経炎
著者: 祖父江逸郎
ページ範囲:P.1380 - P.1381
アルコールは広く飲用されており,長期連用による中毒症状の発現も少なくなく,これまでにも尨大な報告がある.アルコールによる神経障害は,古くからすでに18世紀頃から知られているもので,欧米では頻度も高く重視されている.アルコール性多発神経炎は神経障害のひとつのタイプで,発現機序としてはアルコールそのものよりは,アルコール飲用者にみられる栄養障害性因子,ことにビタミン欠乏,肝障害などの関与が重視されている.
最近本邦でも,アルコール性多発神経炎の診断が注目されているので,臨床における診断上のポイントを中心に述べることにした.
アルコール性脳症
著者: 朝長正徳
ページ範囲:P.1382 - P.1383
ここでは,慢性アルコール中毒による脳症状の代表的なものについて述べる.これらは,アルコールそのものによる直接の脳障害よりも,慢性的アルコール大量飲用の結果としての栄養欠乏などによるものがほとんどであり,治療もこの点に留意してなされねばならない.
Zieve症候群
著者: 高橋善弥太
ページ範囲:P.1384 - P.1385
Zieve症候群とは,1958年Zieveが1)黄疸と溶血性貧血と高中性脂肪血症あるいは高コレステロール血症を主徴とする20例の患者を集め,新しい症候群として提唱したものである里患者はいずれも多量のアルコール飲用の後に発症し,飲酒をやめると症状は改善し,高脂血症,高コレステロール血症も2〜3週間で消失する.貧血は軽度のものが多く,便の潜血反応は陰性で,大球性のことが多い.溶血は軽度で一過性であって,尿や大便中のウロビリノーゲンの増量と網赤血球の増加によって知り得る.血漿ビリルビンは全例増加しているが,入院時の最低は1.4mg/dl,最高は43.0mg/dlに及んでいる.
多くの患者はいわゆる酒呑みであって,とくに大量に飲んだ後に発症する.食欲不振,嘔気,嘔吐,下痢,体重減少,寒気などがあり,ほとんどの例で上腹部痛がある.その程度はさまざまであるが,黄疸を伴うことから,胆石などが疑われ,開腹手術を受けることがある.白血球も増多を示すものが大部分であった.
治療の問題点
アルコール性肝障害
著者: 上野幸久
ページ範囲:P.1386 - P.1387
Lieber一派の実験的ならびに臨床的研究によって,アルコールの肝細胞障害作用が確認され,エタノールそのものがアルコール性肝障害の主要因子であり,Hartroftらのいう栄養障害は二次的因子に過ぎないという見解が現在では支配的のようである.アルコールの多飲後,黄疸の出現,GOTをはじめとする肝機能検査の著明な悪化など,肝障害の徴候の発現ないし増悪がしばしばみられることも,アルコールの直接的肝障害作用を裏づけている.
糖尿病とアルコール
著者: 伊東三夫
ページ範囲:P.1388 - P.1389
近年,わが国のアルコール消費量は増大しているといわれているが,糖尿病患者にも飲酒の機会は少なくない.筆者らの糖尿病教室に入院した男290例について,入院前の酒類摂取量を調査してみると,1日の平均アルコール摂取量が201 Cal以上であったものが62%にみられ,毎日501 CaI以上という例に限定してみても20%であった.この290例は新しく発見された糖尿病患者だけでなく,半数近くに既知糖尿病例が含まれていた.糖尿病教室では「糖尿病にはアルコールはいけないのでしょうか」,「ウイスキー,焼酎はよいといわれていますが本当でしょうか」というのが彼らの質問であった.
Krallら1)は,糖尿病患者が飲酒を制限しなければならない理由として,①ビールやワインにはアルコール分は少ないが糖質が含まれており,その分だけ糖質の摂取量が追加されることになる,②アルコールの多いウイスキー,ジン,ブランデーは少量であれば尿糖を増加させることはないが食事量が多くなりやすい,③最も注意しなければならないこととして,アルコールによってひき起こされた低血糖が酩酊もしくは急性中毒と誤認されることがある.インスリンによって起こっている低血糖の場合でも,呼気に酒気があると酩酊と誤認され,その結果,緊急処置が等閑にされるおそれがある,④アルコールは体内で糖,アセトンに転換されることはないが,その熱量は体重増加を起こしうると述べている.
アルコール性膵炎
著者: 小島国次
ページ範囲:P.1390 - P.1392
臨床の経験をもたない筆者が,「治療の問題点」という観点からアルコール性膵炎について述べることには,少し違和感があり,抵抗を感じないでもない.あるいはそのようなところに編集者の意図があるのかもしれない.そこでアルコール性膵炎の成り立ち方,細胞学的ならびに組織学的変化などの病理学的知見に基づいて原因〜増悪因子を考察してみた.
結論的にいえば,その因子は飲酒,食事(低蛋白),膵管系の狭窄と閉塞とであり,治療上必要なのは,常識的な禁酒,低蛋白の改善とともに,膵管系の濃縮分泌物の排泄除去の努力とである.
アルコール症の治療
著者: 河野裕明 , 堀井茂男 , 吉武泰俊
ページ範囲:P.1393 - P.1395
アルコール症の概念
従来アルコール症は,精神科では,その患者の「病的性格」として,内科では臓器毒性による「身体疾患」として扱われてきた.これはそれぞれアルコール症の一面の真理をついてはいるが,"人間におけるアルコール症の治療"の立場からは全く片手落ちであり,そのような一面的視野からの治療は時に逆効果さえもたらしてきた.したがって,ごく簡単に必要なアルコール症の概念を述べる.
WHOの定義によると,アルコール症とは薬物依存の中のいわゆるBarbitur-Alcohol型の疾患ということになり,下図(図1)のようなシェーマで考えられている.
大酒家への薬剤投与
著者: 重田洋介 , 石井裕正
ページ範囲:P.1396 - P.1397
アルコールは過去,現代を問わず嗜好品として,また人間関係の潤滑油として,さらには「心の憂さの捨てどころ」としてストレス解消剤の役割を果たしてきている.また,最近は人間関係,社会機構がますます複雑になってくるにつれ,精神安定剤や睡眠剤などの僕用量が著増傾向にあり,アルコールと精神安定剤などを併用する人も稀ではなくなってきている.そのようなとき,生体でアルコールと薬物がどのように作用し合い,その結果としてなにを予期すべきであろうか.本稿では,これらの点につき解説をしていきたい.
演習・X線診断学 消化管X線写真による読影のコツ・10
大腸のX線診断(その1)
著者: 吉川保雄 , 織田貫爾 , 勝田康夫
ページ範囲:P.1401 - P.1407
大腸X線検査は,胃X線検査のように,充満法,二重造影法,圧迫法の組み合わせ検査がうまくいかず,Fischer法(1923),Welin法(1955),Brown法(1969)ともっぱら二重造影法の改良に力が注がれてきた.そして,現在のところでは,二改造影法が大腸X線検査の主体である.二重造影法の利点は,何といっても,粘膜面の微細変化を直接描出できることであり,われわれは1970年以来,Brown法に基づく二重造影法が人腸の微細構造network patternをあらわすのに最も優れていることを報告してきた.そして,とくに陥凹性病変の診断に有用であることを強調してきた.
診断基準とその使い方
自己免疫性溶血性貧血
著者: 恒松徳五郎
ページ範囲:P.1410 - P.1413
はじめに
日常診療において貧血症はしばしば遭遇する症候である.貧血は骨髄での赤血球産生と末梢組織での破壊,喪失とのバランスが崩れる状態で,後者が前者を大きく上回ったときに現れる.溶血性貧血は体内での赤血球破壊が著明に亢進し,骨髄造血能(代償的亢進)で補いきれないとき発現する病態である.溶血の存在を知るにはまず貧血の発現または進行が急速である点に注目すべきである.この点は赤血球産生低下による場合,すなわち低形成または無形成骨髄による貧血と異なる.骨髄での造血が全く停止したとしても,その結果として貧血が発現するにはかなりの日数がかかるのと対照的である.溶血性貧血はかかる状態で急速に発症する例が多いが,慢性の経過をとるものでは貧血の発現は緩徐である.かかる例も存在する.溶血性貧血では破壊された赤血球が体内で処理されるという点で,体外への出血と異なる症候や検査所見を呈する.黄疸,ことに間接ビリルビンの上昇,尿,糞便中へのウロビリノーゲンの排泄増加などがそれを示す所見である.
溶血性貧血の原因には種々のものがあるが,そのうち自己免疫機序によるもの,すなわち自己免疫性溶血性貧血の診断基準について述べる.
図解病態のしくみ—消化管ホルモン・6
エンテログルカゴン代謝
著者: 石森章
ページ範囲:P.1414 - P.1415
消化管粘膜に分布し,その作用が膵グルカゴンに類似すると考えられたことから,エンテログルカゴンと命名された本物質は,免疫学的にも膵グルカゴンとある程度の交差性を示し,化学構造の上からも類似性の認あられることから,一般にsecretin familyに属すると考えられてきた.しかし最近の知見によれば,これらは単一の物質ではなく,主として小腸,大腸に分布するglucagon-like immunoreactivity(GLI)と,主としてイヌにおいて胃に分布し,膵グルカゴンと免疫学的に同一性質を示すglucagon immunoreactivity(GI)とに分類することができ,作用の上でもそれぞれ特徴のあることが明らかとなった.産生細胞として前者ではL細胞,後者ではA細胞が指摘されているが,ここではこれまでの歴史的背景や種族特異性を考慮して,主としてGLIをエンテログルカゴンとして取り扱い,場合に応じてGIについても言及することとする.
新薬の使い分け
脳卒中に対する薬剤の使い分け
著者: 海老原進一郎
ページ範囲:P.1416 - P.1417
脳卒中発作直後,後遺症の治療では,いずれも万人のコンセンサスをうる薬剤の選択はむずかしい,というのは脳卒中の特殊療法として用いられる薬剤は,その効果を臨床的に実証することがむずかしく,いままでのところ確実に有効とされるものはないからである.したがって,少なくとも筆者は,病態生理学的にその有効性が示唆されている薬剤を副作用の有無を重視し,選択して用いている,このような立場から,脳卒中に対する薬剤の使い分けについて述べる.
脳卒中の治療に用いる特殊薬剤は,脳圧下降剤,脳血管拡張剤,脳代謝賦活剤,抗凝血薬,血栓溶解剤,血小板凝集阻止剤など,その種類は多く,多岐にわたっている.そして,これらは脳卒中の種類,発作後の病態によって使い分けられる.
臨床病理医はこう読む ホルモン異常・1
甲状腺機能低下症
著者: 屋形稔
ページ範囲:P.1418 - P.1419
T3テストについて
この症例は各種甲状腺機能検査から,明らかな甲状腺機能低下症と考えられる.注意しなければならないのは,T3テストをTBC index法のごとく,レジンストリップをレジンスポンジの代わりに用いると,両法は機能亢進または低下で数値の多少が表現としては全く逆になることである.
T3テストはレジンスポンジを用いるトリオソルブテストが10年前に紹介されてからPBIに代わって普及してきた.実地医家も自ら行わなくとも,病院検査室や検査センターに血清を送って報告を得,時にこれのみで診断に供しているが,キット毎に方法も表示値も異なるから,値の読みに心しないと混同するおそれがある.T3テストの原理は,表1のごとく,甲状腺機能低下症では内因性ホルモン分泌が少ないため,甲状腺ホルモン結合蛋白(TBP)飽和度が低く,血清への摂取率が高いことを利用している.甲状腺機能亢進症では逆の関係になる.吸着物質または血清の131I-T3摂取率を測定すれば,甲状腺機能状態を知ることができるが,測定されるものが血清であるか,吸着物質であるかにより,甲状腺機能状態と数値が逆になる.
小児と隣接領域 小児外科・III
消化管出血
著者: 角田昭夫
ページ範囲:P.1420 - P.1421
小児の消化管出血にはいくつかの特徴がある.
1)量と質の特徴:成人と比べて絶対量は少なくても,容易に貧血やショックをひき起こす.下血の方が吐血より機会が多い.血液の消化管内停滞時間が短いこと,消化液との量的相対関係により,下血ではメレーナよりも血液そのものの肛門からの排出(Hematochezia)が多く,吐血もコーヒー残渣様より鮮血色のHematoemesisが多い.
皮膚病変と内科疾患
体部異形または非相称と内的病変(その2)
著者: 三浦修
ページ範囲:P.1422 - P.1423
眼
眼の外形の異常は眼瞼の状態,眼裂の広狭と顔の水平線に対する角度,眼球の大小や凹凸による眼窩部の状態などによってひき起こされる.
ECG読解のポイント
心筋梗塞と思われるが,ST上昇が一時的であった54歳男性の例
著者: 植木一義 , 太田怜
ページ範囲:P.1424 - P.1426
開業医としての特徴のひとつは,発作時の心電図がとれることではないだろうか.本症例は,発作時の心電図と経過から,梗塞と考えたが,翌日の心電図で,梗塞曲線の消失した1例である.
患者 男性54歳(昭和51年現在)
外来診療・ここが聞きたい
肺線維症を疑わせる動悸,息切れ
著者: 西崎統 , 田中元一
ページ範囲:P.1427 - P.1429
患者 O. S. 41歳 主婦.
現症 約2年前頃から関節痛があり,近医に受診し治療を受けていた.関節痛はやや軽減した.しかし,約6カ月前位から動悸,息切れが現れ,労作時は増強する.さらに最近,咳嗽,喀疾(黄色)を伴ってきた.
開業医学入門
"かぜ"のこじれ
著者: 柴田一郎
ページ範囲:P.1430 - P.1434
開業医にとって最も頭を悩ます問題のひとつに,いわゆる"かぜのこじれ"がある.およそ日本の開業医の診る患者の約半数はいわゆるかぜ症候群であると,最近なにかで読んだことがある.まず最初に,一般にかぜ症候群と呼ばれている一群の症候群とはなにか,ということについて検討してみたい.はじめに一応おことわりしておきたいことは,最近かぜ症候群について,大半の成書には,ウイルス学的検索などの実験室的検査について詳細に述べられ,個個のウイルスで起こる症候の分類まで詳しく述べられているが,筆者としては特殊なものを除き,これらの問題には立ち入らないつもりである.実際問題として,発病早期と回復期の2度にわたって検体をとり,これをさらに外注する,といっても結果が判明したときには患者は治癒してしまっている.検査結果が分かったとしても,抗ウイルス剤にっいてはABOBがわずかに有効なこと,また一部のウイルスに対してはアマンタジンに若干の効果がある程度でしかない現在,私たちとしては対症療法を行う以外に方法はないのである.
medicina CPC—下記の症例を診断してください
乏尿・吐血・発熱を主訴とし,急激な転帰をとった52歳,家婦の例
著者: 小沢安則 , 中川成之輔 , 青柳昭雄 , 岡安大仁 , 田崎義昭
ページ範囲:P.1435 - P.1446
症例 ○辺○子,52歳,家婦
主訴 乏尿,吐血および発熱.
既往歴 21歳,肺結核症に罹患,その他著患はない.
--------------------
内科門医を志す人に・トレーニング3題
著者: 涌井和夫 , 安永幸二郎 , 前田如矢
ページ範囲:P.1447 - P.1449
問題1. 膵炎について,次のうち正しいものはどれか.
A:急性膵炎時の膵の組織障害の程度は,血清アミラーゼの濃度によく反映する.したがって,膵炎の組織学的所見の重篤度を血清アミラーゼ値から推定することができる.
内科専門医を志す人に・私のプロトコール
血液疾患/循環器疾患
著者: 森川景子 , 村山正昭
ページ範囲:P.1450 - P.1452
血液疾患は将来の専門としたい領域であるので,全体としてプロトコールがこの分野に偏りすぎたきらいがある.血液疾患の研修にさいしては,血液塗抹標本を検査室まかせにしないで主治医が自分の眼で見ることが大切であると思う.1枚の標本から得られる情報はかなりあるが,白血病の場合はとくに重要である.
ひと口に骨髄性白血病細胞といっても,それぞれに症例により違うし,この白血病細胞が経過中に変わることもある.最初,穎粒のないリンパ芽球様のものが,再発時には穎粒を有する典型的な骨髄芽球となることがあるが,この症例もそうであった.
オスラー博士の生涯・42
講演「19世紀の医学の進歩」
著者: 日野原重明
ページ範囲:P.1453 - P.1455
オスラーは,50歳代になる頃から,大学における教育,診察のほかに,立会い診察や講演の依頼を受けることがますます多くなった.自分が育てた歴史クラブの毎月の例会も彼が主宰し,また喜んでこの会の話題提供者となった.
1900年の1月,ボストン医学図書館の落成式での「本と人」と題する講演を終えてわずか15日後に,彼はジョンス・ホプキンス大学の歴史クラブの例会に「19世紀の医学の進歩」と題して2時間にもわたる講演をした.
忘れられない患者・私の失敗例
MCLS
著者: 石垣四郎
ページ範囲:P.1456 - P.1456
約20年間の病院勤務と6年間の開業医生活の中には,忘れがたい印象を残して去来した幾多の子ども達の顔が浮かんでくる.昭和43年11月5日に,神戸市立中央市民病院小児科に入院してきた4ヵ月の乳児も,その1例である.この患児は入院5日前頃から咳がでていたが,4日前より38℃の発熱があり,顔色が著しく不良となった.また2日前から全身に発疹が出現し,一向に解熱の徴がないために入院してきたのである.みると全身に麻疹様紅斑があり,四肢には多形滲出性紅斑を思わせる発疹がある里手掌,足蹠はびまん性に発赤し,眼球結膜の充血も著明である.頸部にはえん豆大のリンパ節を触れる.心,肺に異常なし.肝は1cmに触れる.白血球数15000,Hb 11.1g/dl,尿蛋白陽性,尿沈渣に多数の白血球を認める.入院後は抗生物質とステロイド剤により解熱,症状はいったん軽快するが,ステロイド剤を中止すると再び症状が再燃する.指尖部の落屑も認めるようになる.3回の再燃をくりかえした後に次第に回復をした.以上の経過から,読者もおそらく直ちに診断をくだされるように,急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群(MCLS)と診断した.本疾患は前年の昭和42年に川崎富作博士により報告されたもので,小児科医の関心を惹いたものであった.入院後約1ヵ月を経過して,一般状態も良く,退院を考慮していた矢先のことである.
末梢血中に赤芽球が出現した1症例
著者: 笹村義一
ページ範囲:P.1457 - P.1457
私が医師となり,はじめて経験した死亡例は急性白血病であったが,本症例は種々教えられることが多く,またその後の私の進路に大きな影響を及ぼした忘れがたい1例であった.
34歳,男.昭和34年1月始めより易疲労性,心悸亢進を覚え,2月にはいり赤血球,白血球がともに少ないことを指摘された里2月20日より3月14日まで,某国立病院にて再生不良性貧血の診断のもとに入院,加療を受け,3月15日本院に転入院した.
基本情報
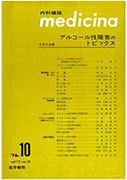
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
