臨床検査に用いられる検査材料のうち最も頻繁に使われるのはなんといっても血液である.血液には動脈血,毛細血管血と静脈血があり,検査によっては成績が著しく異なるものもある.また,検査に用いられる血液といっても,検査項目によって全血が必要なもの,血漿が必要なもの,血清が必要なもの,血球成分が必要なもの,などがある,さらに血液凝固を防ぐために加える抗凝固剤についても検査項目によっては特定の抗凝固剤に限って用いられる.このように「血液の検査」を行う場合には目的に応じた採血法が必要である.したがって,検査を依頼する場合には,それぞれの検査項目について適切な採血条件をよく知っておいてから行わなければならない.さもないと貴重な愚者の血液をむだにするばかりでなく,検査のための適切なタイミングを失うことになろう.
すべての生物学的試料に共通なことであるが,血液についても同様に,生体外にとり出されると極めて不安定であって刻々と変性してゆくものである.採血後長い間放置すると,値が著しく増減し生体内の状態を推定しえない.したがって,原則として採血後できるだけすみやかに検査を終えることが望ましい.
雑誌目次
medicina13巻12号
1976年12月発行
雑誌目次
診断篇 I.目的に応じた採血法
1.採血上とくに注意を要する検査
著者: 河合忠
ページ範囲:P.1624 - P.1628
2.血液の保存法
著者: 河合忠
ページ範囲:P.1629 - P.1631
血液の検査は,他の臨床検査と同様に,原則として,採血後できるだけすみやかに検査を終えることが望ましい.しかし,やむなく長時間血液試料を保存しなければならない場合があろう.この場合には,次に述べるように目的に応じて適切な保存法を行うことが,正しい検査成績を得るために不可欠なことである.
3.採血困難なときの対策
著者: 河合忠
ページ範囲:P.1632 - P.1633
採血法は大きく2つに分けられ,ひとつは静脈穿刺により静脈血を採取する方法であり,他のひとつは皮膚穿刺により毛細血管血を採取する方法である.次に,それぞれの場合の一般的な注意と採血困難な場合の対策についてまとめてみよう.
4.小児の採血法
著者: 西村昂三
ページ範囲:P.1634 - P.1637
小児の採血法は,周知のごとく年齢によりかなり難易の差が大であるが,乳幼児の採血が最もむずかしいのは,いうまでもない.しかし,最近は各種の検査が微量化してきたので,一昔前にくらべると小さい乳幼児から成人と同量の採血を必要とすることは少なくなってきた。換言すると,毛細管血の採血により,ほとんどすべての検査が行われるようになってきたが,完全に微量化されている施設はまだまだ少ないので,わが国の現状を考慮し,乳幼児の採血法のうち,とくに日常臨床上役立つと思われる方法について述べることにする.
II.消化器系疾患の診断技術
1.バリウムによる消化管の検査
著者: 川井啓市 , 赤坂裕三
ページ範囲:P.1640 - P.1644
バリウムによる消化管X線検査を大別すると表1のごとくである.このうち,臨床上最も重要と考えられる上部消化管スクリーニング法,胃十二指腸精密検査法および注腸検査法について述べる.これらのX線検査法については,順天堂大学白壁彦夫教授門下の秀れた業績があり,筆者らもそれを踏襲しているが,ここでは筆者らが実際に行っている方法について詳述する.
2.低緊張性十二指腸造影法
著者: 大久保忠成
ページ範囲:P.1645 - P.1649
原理
十二指腸は膵胆道系と隣接し,これと密接な関係を有するので,これらの隣接臓器の病変によってしばしば形態の変化を生ずる.しかし,十二指腸は活発な蠕動を伴うので,一般の上部消化管撮影法ではその変化をとらえることがむずかしい.Jacquemetら1,2)は1963年,アントレニールを用いて蠕動と緊張を抑制した十二指腸を選択的に造影し,その微細変化を読影して膵胆道疾患の診断に役立てることを考案し,これを低緊張性十二指腸造影法と名付けた.この方法は手技が比較的簡便なため広く用いられるようになったが,とくにVater乳頭部,膵頭部の病変の診断に適している.
3.腸吸収機能検査法
著者: 朝倉均
ページ範囲:P.1650 - P.1655
腸吸収機能検査は,食餌内容や量に問題がないのに体重減少や下痢(下痢のない吸収不良もある)を呈したとき,その消化吸収障害の程度と種類をみるため,経口的に各種物質の負荷を行って消化吸収状態を知る検査である.したがって,種々なる栄養物があり,またそのひとつの栄養素の消化吸収状態をみるため種々なる方法があるので,表1に主な検査法をあげてみた.
3大栄養素としての蛋白質,脂質,糖質の消化吸収試験はいろいろあるが,糞便中の蛋白質,資質,糖質のすべてが不消化非吸収性残存食物というわけでなく,胃液,胆汁,膵液,腸液中には種々の消化酵素,脂質なども含まれ,さらに重要なことは胃や腸などの上皮細胞が半減期2~5日という速い代謝で消化管内に剥離してくるし,また,蛋白漏出性胃腸症などの病態もあり,それらの内因性蛋白や脂質という複雑な因子も加わり,いろいろな簡便法が考えられている.
4.PSテスト
著者: 石井兼央
ページ範囲:P.1656 - P.1658
原理
慢性膵炎,膵癌などの慢性膵疾患では,膵管狭窄,腺細胞の破壊・変性によって膵液分泌障害が起こる.PSテストは膵液分泌の状態(膵外分泌機能)をしらべる検査である.
1)十二指腸液に胃液混入を避けるために胃・十二指腸二重管ゾンデを用いる.
5.ICG,BSPの検査
著者: 浪久利彦 , 小林教雄
ページ範囲:P.1659 - P.1662
肝は生体で最も大きい臓器であり,その機能には化学的な作用のみでなく,物理的な作用もある.異物排泄の過程でも,肝は異物を血中から胆汁中へ移送するのみでなく,貯蔵し,化学的な修飾を加え,代謝物を作り,あるいは蛋白との結合や解離を行ったりする,この意味で肝の排泄機能を知ることは,その広汎な機能を推察しうるものといえる.臨床的に肝の排泄機能を検査するのには,BSP試験,ICG試験,およびビリルビン負荷試験がある.
BSP試験はこの50年来行われてきたが,BSPによる重篤な副作用が報告されてから行われることが少なくなった.ICGには副作用がほとんどなく,ICG試験の成績はBSP試験とほぼ平行しているので,臨床で広く行われている.ビリルビン負荷試験は成績の解釈がむずかしいため,現在ほとんど行われていない.
6.胆のう造影法
著者: 亀田治男
ページ範囲:P.1663 - P.1665
胆道疾患の診療に際して,問診や理学的所見一般臨床検査所見などから,重要な診断の手がかりを得ることも多い.しかし,胆道疾患の診断法として最も大切なのは胆のう造影法であり,広く応用されている.胆のう造影法については,方法の選択,術式,読影などに関して,診療上問題となることも少なくないので,これらを中心にして記載することとする.
7.経皮経肝胆道造影法
著者: 大藤正雄 , 土屋幸浩
ページ範囲:P.1666 - P.1670
黄疸などの肝障害や胆道病変のために普通造影法によるX線診断が不可能の場合に,胆道を明瞭に造影し,病変を診断することを目的として経皮経肝胆道造影(PTC)が行われる.この方法は細く長い針を使用して体表から直接に肝内胆管あるいは胆のうを穿刺し,造影剤を注入して造影するものである.腹腔鏡観察下に穿刺するなど特殊の場合をのぞき,穿刺針が体壁から肝実質を貫いて胆管あるいは胆のうに刺入されるので経皮経肝胆道造影とよばれる.
本法には1921年,Bruckhardt,Mullerが行った胆のうを穿刺する方式(胆のう穿刺法)と,1937年Huard,Do-Xuan-Hopが行った肝内胆管を穿刺する方式(胆管穿刺法)とがあり,両者とも幾多の工夫・改善を経て今日に至っている.胆管穿刺法は胆のう穿刺法と比較して,造影効果が胆のう萎縮,胆のう管閉塞,胆のう摘出など胆のう病変によって左右されず,肝内胆管など上位胆管も含め病変の診断が可能である.さらに胆管穿刺法は胆汁漏出,出血などの合併症も少ないことから,現在では広く胆道外科の分野で応用されている方式であるが,最近ではX線テレビの応用によりいっそう確実で安全な手技が可能となり,予め手術準備の必要もなく内科的にも実施されるようになった.
8.肝生検
著者: 岩村健一郎
ページ範囲:P.1671 - P.1674
臨床上,肝の病理組織学的検査のために,肝組織の小片を採取することがあり,そのために行う手技を肝生検法という.
肝生検には外科的開腹術の際に行う開腹時(あるいは手術時)生検法や,経皮的に穿刺針を肝内へ刺入する針生検法があるが,日常,臨床的には針生検法がしばしば行われる.また,腹腔鏡観察下に針生検を行うことを直視下生検法というが,腹腔鏡を備える施設においてのみ行うことができる方法である.それに対して,単に体表から肋弓下あるいは肋間腔を経て行う場合には,盲生検法といっている.
III.循環器系疾患の診断技術
1.末梢静脈圧
著者: 上田慶二
ページ範囲:P.1676 - P.1677
原理
末梢静脈圧を測定する目的は右房平均圧を推定するためであり,簡便な検査法であるので右心不全の治療経過を知るため頻回に測定することが可能である.
通常,患者を仰臥位とし,胸壁中間部の高さにおいた上腕の皮静脈内へ針を挿入し,針に接続した垂直のガラス棒内の水柱の高さをもって末梢静脈圧とするが,間接的には前腕を皮静脈の緊張が消えるまで挙上し,右房の高さより前腕までの垂直距離をもって末梢静脈圧のレベルを推定することも可能である.
2.中心静脈圧
著者: 上田慶二
ページ範囲:P.1678 - P.1679
測定の原理と意義
右心房に近接する胸腔内の大静脈(上大静脈と下大静脈,さらに両側鎖骨下静脈をも含めた範囲の静脈系)の内圧を中心静脈圧(central venous pressure)と呼び,これらの静脈内にまで進めたカテーテルにより測定する.
中心静脈圧測定の目的は,右心系の充満圧(filling pressure)として重要な右房内圧を推定するにあり,その測定の意義は右房圧測定と同意義に解することができる.中心静脈圧(≒右房平均内圧)は三尖弁が正常に機能し,かつ胸腔内圧と心外膜腔内圧の正常な状態においては右心室の収縮能と拡張期コンプライアンスにより決まる右心室拡張終期圧(RVEDP)を反映するとともに,循環血液量による影響を受ける.
3.His束心電図
著者: 比江嶋一昌
ページ範囲:P.1680 - P.1684
従来,His束の興奮電位を記録する方法としては,細胞内へ0.5μ内外のガラス電極を刺入して,1個のHis束細胞の活動電位を直接記録する微小電極法と細い針や円板などの電極により,His東上の心内膜面から全体のHis東電位を記録する表面誘導法とがあり,それぞれ刺激伝導系に関する実験的な研究に用いられてきた.
一方,以前より心臓カテーテル検査時,電極カテーテルでもってHis東電位を記録せんとした試みはあったが,特殊な例を除いては,その記録がほとんど不可能であった.ところが,1969年Scherragら1)は,ちょっとした工夫によって,His東電位の安定した記録を可能にした,それ以来,この方法は短期間に世界各国に普及し,これにより臨床電気生理学の分野は急速な進歩を遂げるに至った.このように,電極カテーテルで記録されたHis東電位を,前述した表面誘導法によるものと区別する意味で,His束心電図(His bundle electrogram)と呼ぶ.
4.心カテーテル法
著者: 片山文路
ページ範囲:P.1685 - P.1688
心カテーテル法は心臓手術適応の判定に必要なばかりでなく,血行動態,心筋代謝,心筋収縮機構などの研究にも欠くことのできない検査法である.
5.心機図
著者: 小池眞弓 , 吉村正蔵
ページ範囲:P.1689 - P.1693
心臓の拍動に伴って生じる振動現象および動静脈波の視覚表示を心機図法,それにより得られた波形の記録を心機図と呼ぶ.非観血的に検査が施行可能な,いわゆる心機図には,心音図,頸動静脈波,心尖拍動波,バリストカルジオグラム,キネトカルジオグラム,その他十指にあまるものがあるが,比較的容易に検査ができることから,頸動脈波と心尖拍動波について述べる.
6.脈波検査
著者: 三島好雄
ページ範囲:P.1694 - P.1695
原理
700〜800mμの近赤外線は生体の諸組織を透過するが,血液に吸収されやすい.指先などの透過あるいは反射光を光電管や光電池にうけることにより,その部の血液量の拍動に伴う変化を光電容積脈波として記録することができる.
7.色素希釈法
著者: 香取瞭
ページ範囲:P.1696 - P.1699
血管内に色素を注入し,それが血液により希釈される過程を記録することにより循環動態を検査し,心疾患を診断する方法を色素希釈法(dye-dilution method)という.色素希釈法の応用範囲として,心拍出量の測定,循環時間の測定,心内短絡,血管短絡,弁逆流の診断と定量,中心血液量,心室内容積の測定,局所循環血液量の測定などがあげられる.
IV.呼吸器系疾患の診断技術
1.flow-volume,closing-volumeの測定
著者: 佐々木孝夫
ページ範囲:P.1702 - P.1705
flow-volume
原理
flow-volumeとは肺に空気が出入りする時の気流速度flow(l/sec)をY軸に,空気量volume(l)をX軸として表現したものである。吸気・呼気を連続的に画いた場合をflow-volume loopといい,吸気あるいは呼気の一側のみの場合,flow-volume curveという慣習がある.また,ただ単にflow-volume曲線という場合には,最大吸気位より最大努力呼気時のmaximum expiratory flow-volume curve,MEFVをさすことが多く,臨床に応用されるのも,多くはこのMEFVである.
図1に,MEFV,努力性呼気曲線(スパイログラム)およびiso-volume-pressure-flow curve(IVPF)3者の関係を示した.
2.AaD
著者: 玉谷青史 , 山林一
ページ範囲:P.1706 - P.1709
AaDとは
肺の構造をひとつの肺胞とひとつの血管から成り,肺胞気より赤血球にいたるまで拡散障害のない理想的なものと考えると,肺胞気ガス分圧と動脈血ガス分圧は等しいはずである.
しかし,実際には気道は223(約840万個)にも分かれ,おのおのの肺胞への血流分布も多様であり,解剖学的なA-Vシャントも存在する.肺胞気(平均肺胞気)と動脈血のガス分圧は等しくなく圧較差が生ずる.
3.換気力学的検査
著者: 田村昌士
ページ範囲:P.1710 - P.1712
—般に換気力学的検査とは,肺・胸郭系(横隔膜を含む)の換気運動によって変化する換気量,圧,気流の相互関係を数量的に表し,肺・胸郭系の粘性,弾性,気流抵抗,慣性などの物理学的特性を知るための検査である.その主な検査項目とその意義については表1に示してある通りであるが,日常比較的簡便に実施できる検査はスパイロメトリー,flow volume,呼吸抵抗(インピーダンス)の測定である.ここではスパイロメトリーとオッシレーション法による呼吸抵抗測定だけについて述べる.
4.気管支造影
著者: 菊池章 , 加藤敏郎
ページ範囲:P.1713 - P.1715
気管支造影は患者にとってかなりの苦痛を与え,かつ一時的にせよ肺機能の低下をきたすので,その適応は慎重にしなければならない.近位の大気管支の変化は,しばしば技術的にすぐれた断層撮影や高圧撮影によって十分な所見が得られ,その後の気管支鏡的試切や分泌物吸引によって決定的診断が得られる.したがって,これらの撮影によっても気管支内腔の変化が不明の場合に,気管支造影が必要となる。しかし,いったん造影された気管支の所見は,たとえ肺門に近い大気管支であろうとも,診断的には比較にならぬほど豊富な知見を与えてくれるので,必要と判断された際は躊躇なく実施すべきである.
気管支造影の原理は,要するにX線不透明の薬剤(造影剤)を気管経由で気管支に注入し,注入圧,造影剤の重力,呼吸運動を利用して末梢気管支まで行きわたらせ,単純X線撮影ではとらえられない気管支樹の内腔を可視化することにある.
5.肺生検
著者: 於保健吉 , 林忠清
ページ範囲:P.1716 - P.1719
原理
ここ数年間に,肺疾患,とくに肺癌の診断技術はX線写真の読影をはじめ,肺門部に発生した肺癌に対する気管支ファイバースコープの応用,末梢型の肺癌に対しては病巣擦過法,経皮肺生検法などいずれも著しい進歩を遂げた.われわれの教室における時期別にみた肺癌の診断率は表1に示すように,年々向上しているが,いずれの時期においても末梢型のものの診断率が肺門部のそれよりも低い.とくに末梢型で2cm以下の症例では,喀痰細胞診の陽性率は35%前後であり,また病巣擦過法による成績も50〜55%が限度であるので,確診率を高めるためには肺生検法によらねばならない.
肺の末梢発生の病巣に対する生検法としては,組織診あるいは細胞診のための種々な肺生検法が従来から行われているが,代表的なものは,外径2.5mmの組織診を目的としたVim-Silverman針による経皮肺検法と外径1mm前後の細い生検針を使用する細胞診を目的とした肺生検法がある.前者はしばしば重篤な合併症がみられることから,現在わが国では広く行われていない.したがって,この項では細胞診を目的とした経皮肺生検法について述べる.そのほか経気管支生検法,開胸生検があるが,ここでは省略する.
V.縦隔検査法
1.縦隔病変の検査法
著者: 吉松博
ページ範囲:P.1722 - P.1727
縦隔には心・大血管,気管・気管支,食道など重要な臓器を擁し,これら既存の臓器の病変に対する検査や診断法は,近年,著しい進歩を遂げてきた.縦隔病変にはさらに多くの縦隔腫瘍やリンパ節病変(慢性炎や癌転移など)が加わり,これら病影の鑑別と確定診断を得ることが日常臨床上,治療方針選択にあたって重要となり,症例も次第に増加を示している.
縦隔の病変に対して,従来行われてきた検査法の主なものを整理してみると,表のとおりで,胸部X線写真の各種撮影法に加え,気管支造影,食道造影,大動・静脈造影などは現在一般に広く行われ,診断上極めて有用である.通常,まず胸部X線写真を種々の組み合わせにより分析し,病影に密接した臓器の造影を加えることが確定診断に近づく重要な鍵となる.さらに内視鏡検査としては気管支鏡検査,食道鏡検査が最も一般的であるが,縦隔病変すなわち縦隔腫瘍,リンパ節病変,胸腺異常を追究する場合,これら内視鏡検査も前述のX線造影とともに間接的検査にとどまる.
VI.泌尿器系疾患の診断技術
1.尿路造影法
著者: 多田信平 , 木野雅夫 , 兼平千裕
ページ範囲:P.1730 - P.1733
尿路造影法として最も重要な位置を占め,かつ最も頻繁に現在施行されているのは排泄性尿路造影,すなわち,経静脈性腎盂造影intravenous pyelography(IVP)と呼ばれるものである.この腎盂造影の呼称は逆行性に対するものとして用いられているが,実際には腎孟の造影のみならず,腎実質,腎杯,腎盂,尿管,膀胱を造影するものであり,ことに腎実質読影の重要性を強調するため,静脈性尿路造影intravenous urography(IVU)と好んで呼ぶむきもある.
われわれの施設では,年間およそ1,500〜2,000例のIVPが行われているのに対して,逆行性腎盂造影は15例程度に過ぎない,この極端な両者の比率は最近10年来,徐々に固定化されてきた傾向であり,種々な理由が挙げられる.すなわち,①安全な造影剤が出現して,経静脈性に大量の造影剤の使用が可能になったこと,②それにより腎不全症を含め,IVPの適応症が拡大されたこと,③経皮的血管造影の発展が,逆行性腎盂造影法の適応をせばめたこと,④逆行性腎盂造影法が技術的に熟練を要し,かつ尿路感染を起こす危険の大きいこと,などである.
2.左右別腎機能検査
著者: 小沢幸雄
ページ範囲:P.1734 - P.1735
この検査は1950年,Whiteがラットで一側の腎動脈に部分的狭窄を作り,狭窄腎が健側腎に比較して,水およびNaの再吸収が著しいことを観察したのに導かれた.ヒトで腎血管性高血圧の初期には総腎機能検査に異常を示さず,左右別に腎機能を調べ,はじめてその異常を発見しうる.したがって,この検査は腎血管性高血圧をはじめ,その他の偏腎性疾患の診断,外科的適応をきめる重要なものである.そのうちよく使われる方法に,泌尿器科的なものとradioisotopeを使用するradioisotope renogramがある.
3.腎生検
著者: 木下康民
ページ範囲:P.1736 - P.1739
腎生検(以下,生検と略す)は生体腎の一部をある目的のために採取することであり,この方法による腎切片の採取は腎の臨床のみならず,研究の上にも飛躍的な進歩をもたらした.生検には経皮的な方法と開腹による手術的方法とあるが,ここでは経皮的方法について述べる.
生検の臨床的意義は光顕,電顕,螢光抗体法,あるいは細菌学的検査などあらゆる方法を用いて腎病変の拡がりや質を検討し,病変の性格を決定し,治療方針を定めるとともに,必要の都度,生検を行うことによって,経過を追究し,治療効果を評価し,予後に対する推測を可能ならしめることである.一方,研究面においても生検切片には種々の利用価値がある1).
VII.血液・造血器疾患の診断技術
1.骨髄穿刺
著者: 日野志郎
ページ範囲:P.1742 - P.1744
原理
造血機能があると思われる部位で骨髄に穿刺針を刺し,これに接続した注射筒で短時間強い陰圧を加え,骨髄組織の一部を吸引,得られた液の有核細胞数を数えたり塗抹標本を作ったり,組織小塊の圧挫標本や組織標本をこしらえて顕微鏡で検査する.
2.骨髄生検
著者: 肥後理
ページ範囲:P.1745 - P.1749
骨髄の生検というと,従来より行われてきた骨髄穿刺吸引法も一種の生検法ではあるが,穿刺法では吸引された骨髄の細胞をみるのが目的であり,本項で述べられる骨髄生検とは,骨髄を細胞学的に観察するというよりも組織学的に観察しようということである.本来,骨髄は細胞髄のほかに脂肪織,細網細胞,細網線維,血管および骨梁などよりなっており,一つの組織を構成している.一般に骨髄の状態を観察しようとするときには,細胞所見のみの観察-骨髄穿刺で十分であるが,drytapといわれる骨髄吸引不能例では全く骨髄の状態を知ることはできなかった.さらに吸引された細胞が少ないような場合,それが手技不良によるものか,低形成を意味するのか,あるいは骨髄内の線維化を意味するのかなども知りえなかった.そこで1957年頃より,骨髄を組織学的に観察しようとする試みが行われ,そのための生検法が種々考案され,この方面の研究も多くなってきた.われわれも骨髄生検針を考案して,1963年以来種々の血液疾患に骨髄生検を行ってきた.本項では,われわれの生検法を中心にして,方法および所見について述べることにする.
3.リンパ節穿刺
著者: 天木一太
ページ範囲:P.1750 - P.1752
リンパ節はいろいろの原因によって腫脹し,反応性のもの,腫瘍性のものに2大別されるが,腫瘍性のものの中には原発性のもの,転移性のものがあり,一方また,腫瘍性とも反応性とも決定しにくいものもある.そのおよその診断は臨床的にも可能であるが,確診はもっぱら病理組織学的診断に頼っている.しかしながら,リンパ節腫脹性疾患は非常に種類が多く,組織像上の所見がすべて明らかな特徴を持っているわけではないから,組織学的診断も万能ではなく,しばしば決定的診断に到達しない.その不確実さは組織標本における細胞学的所見の不足によっているのである.そこで組織所見を補うものとして細胞学的診断が役立つ.
リンパ球は細胞形態学的に著しく変貌する細胞である.リンパ球にはT cellとB cellとがあり,抗原に対して芽球化現象を起こし,小リンパ球は数十倍も大形の芽球化細胞になりうる.そして,腫瘍化した場合も小リンパ球様から大形芽球化細胞様まできわめて幅の広い特徴ある細胞形態を示す.腫瘍になっても細胞はT cell,B cellの特徴をある程度まで保持している.そして,それらはそれぞれ臨床的にも特色があるので,それらの決定は望ましいことである.
VIII.中枢神経系疾患の診断技術
1.眼底検査(螢光眼底検査を含む)
著者: 清水弘一
ページ範囲:P.1754 - P.1757
眼底検査法の器械と手技は,近年著しく高度複雑化し,古典的な倒像・直像検眼法のほか,固定式の双眼大検眼鏡や,細隙顕微鏡にゴルトマン三面鏡(角膜表面に密着させ,手で保持して使用)を組み合わせる検査法などにより,網膜の存在する眼底のほとんど全部を高倍率で検査することが可能になった.
完壁な形での眼底検査は眼科専門医に任すべきであり,非眼科医による眼底検査は不十分な形でのスクリーニングとみなすべきであるが,後者の場合,直像鏡による眼底検査法の習熟が当面の目標となる.具体的な手技は教科書にゆずり,注意すべき点のみを論じる.
2.局所脳循環—133Xe内頸動脈注入法による測定法
著者: 上村和夫 , 沓沢尚之
ページ範囲:P.1758 - P.1761
局所脳循環測定には種々の方法があるが,患者の診療を対象とした場合,1961年Lassen and Ingvarにより発表された放射性希ガス内頸動脈注入法による脳clearance法に限られるといってよいであろう一本測定法は,現在ではよりγ線量の多い133Xeが使用され,また,検出器やデータ処理技術の進歩により,最近では最小1cm平方程度の分解能を持つ測定も可能となっている1〜3).
3.脳波賦活法
著者: 高橋剛夫
ページ範囲:P.1762 - P.1767
その順序は同一ではないにしても,閉瞼安静時記録,開・閉瞼,閃光刺激,過呼吸,そして睡眠による脳波賦活が,現在広く実施されている脳波検査である.かかる脳波記録・賦活手技は成書2)にも詳述されており,すでに日常化した方法でもあり,その説明は省略したい,上述した脳波検査を注意深く行うことにより,その目的は一般には十分達せられるといっても過言ではない.ところが,てんかんなど,発作性症状を有する症例では,その誘因を考慮した,いわば特殊検査を必要とする場合が少なくない,後述の方法は,単なる開・閉瞼,閃光刺激,過呼吸以外の覚醒時に行う各種脳波賦活である.賦活効果が確認されているものだけをあげたが,Metrazol-Bemegride賦活を除いて,いずれもまだ定着した方法とはいいがたい.しかし,われわれは,そのいくつかをルーチンの検査として実施しており,稀ならず賦活効果を認めている3,4).以下,これら覚醒時の脳波賦活法について紹介し,合わせて若干の賦活脳波所見について示説する.
4.脳波の周波数分析
著者: 佐藤謙助
ページ範囲:P.1768 - P.1773
脳波の自己回帰性
ひとつの脳波の平均値からの変位が時点tでy(t)とする.これを適当な間隔Δt毎に十分多いN個測り,時点t-kΔtではyt-k=y(t-kΔt),(k=0,1,2,…)とし,分散をσy2=E〔y2t-k〕とする.ここで,E〔〕は括弧内の平均を示す.
脳波に限らず,心臓,呼吸,血圧,血流,神経,筋,種々の腺などその他の生体系の活動現象は過去から現在,さらに未来へと死の直前まで継続している.そして,刻々の現象の状態は,それ以前の活動状態の歴史に関連する部分と,しない部分とから成るが,通常,あまり遠い過去の状態とは関連しない.それで,ytはそれ以前の,たとえばM個の値yt-m,(m=1,2,…,M)との関連度amをかけたamyt-mと,関連しない偶発量ntとの総和
5.知覚誘発電位
著者: 大和田隆 , 大久保修一
ページ範囲:P.1774 - P.1779
一般的に知覚(感覚)誘発電位といわれている検査は,末梢の感覚受容器を刺激したり,末梢神経を刺激して大脳皮質に起こる反応電位を,頭皮上から電気的反応としてとらえる方法である.一般には大脳誘発電位ともいわれている.
これらは,脳の電気活動として自発活動であるところの脳波とは異なり,明らかに末梢ないしは求心路の外来刺激に応じてとらえられる大脳での電気活動であり,自発活動である脳波とは区別されるものである.
6.平衡機能検査法—めまい,平衡障害診断のために
著者: 小松崎篤
ページ範囲:P.1780 - P.1785
「めまい」の原因を考えてみると,内耳,中枢神経系,循環器系など多くの原因がある.したがって「めまい」を訴える患者は,それぞれ多くの臨床の科を訪れることになる.一方,その症状を診断,治療する立場に立つと,めまいの原因が多岐にわたっているため,ややもすれば「面倒な症状」として毛嫌いされることにもなりかねない.
幸い,めまいの予後は一般には良好で,とくに原因を確かめることもなく対症療法で解決されることが多い.
7.神経眼科的検査—とくに眼球運動の診断および検査法
著者: 石川哲
ページ範囲:P.1786 - P.1790
眼球運動を支配する神経の走行路は,脳内の種々なる部位を経由し眼に到達する一したがって,神経学に携わる神経内科医,脳外科医,精神科医などは,視覚系および瞳孔運動の経路のみならず,この眼球運動についても種々なる疾患の診断には眼球運動の知識なくしては,その診断がほとんど不可能であるとまで極言する学者もいるくらいで,眼球運動系に関するテストを熟知しておくことは日常極めて重要な事柄である.過去には,いわゆる脳神経麻痺として現れた眼筋麻痺の診断が,主として感覚面からなされる方法が支配的であったが,最近ではそれよりもさらに進み,medical electronicsを利用した詳しい眼球運動検査からsub-clinical levelまで眼球運動異常を診断する試みが世界で行われている,したがって,ここではまず外来で行われる種々なる検査を簡単に紹介し,さらに最近のME利用による検査法について若干紹介し,続いて現在どのような話題がトピックスとして取り上げられているかについて若干紹介してみることとする.
8.網膜電図
著者: 米村大蔵 , 河崎一夫
ページ範囲:P.1791 - P.1799
原理と沿革
脊椎動物眼では眼球後極側に対して角膜側が陽性の電位差(眼球のstanding potential,SP)が存在する.眼球のSPは主に網膜に由来する.眼球のSPが,光刺激の開始(on)と遮断(off)に伴って,変動することをカエルでHolmgren(1865)が発見した.この電位変動は,角膜,水晶体,房水,毛様体などを除去したいわゆる眼杯eyecupでも観察され,主に網膜から生ずる.この電位の時間的変動を描記した曲線を網膜電図electroretinogram(ERG)と呼ぶ.慣習上,電位を縦軸に,時間を横軸にとり,眼球後極側に比して角膜側がより陽性の電位変動を図では上向きの振れとして描く.EinthovenとJolly(1908)らは光刺激口開始(on)後に最初に現れた下向き(網膜SPが誠少する方向)の振れをa波,これに続く上向きの振れをb波,その後の緩徐な上向きの振れをc波,刺激光遮断(off)後の上向きの振れをd波と呼び,この命名は一般化した(図1).Granit2)は薬品に対するERGの感受性の差などに基づき,ERGを3成分(PI,PII,PIII)に分析した(図1A,B).すなわちネコにエーテルを吸入させると,まず,c波の主体をなす成分process I(PI)が消失した.
9.Computerized transverse tomography(EMI-scan)
著者: 喜多村孝一 , 山本昌昭
ページ範囲:P.1800 - P.1804
1895年,W. C. RoentgenのX-rayの発見は,当時の医学における革命的な出来事として記憶されている.爾来,X線診断学は飛躍的な進歩を遂げてきた.しかし,従来のX線写真に関する限り,透過X線のもつ情報量を十分に活用しているとはいえない.そこで,1961年Oldendorf8)は,透過X線からcomputerにより画像をつくることの可能性を実験的に示した.また実際面でも,1968年頃になり,頭部のRI scintigraphyやechoencephalographyで,既にcomputerを用いたaxial tomographyが応用されていた7).このような背景の中で,1972年Hounsfield4)により,世界ではじめてのcomputerized transverse tomography(CTTと略す)として,EMI-scanが開発されたのである.それ以来,EMI-scanはnon-invasiveな検査法として,爆発的に普及しつつあり,また機械そのものも急速に進歩している.
現在,EMI-scanner,ACTA scanner,Sirotem,⊿-scannerなど,数機種が発売されており,頭部に関する限り,CTTに対する評価は,ほぼ定まってきているようである1,2,5,6).ここでは,実用に供された世界最初のCTTであるEMI-scanを紹介するとともに,CTTの最近の機構上の進歩について述べたい.
10.気脳造影・脳室造影
著者: 玉川芳春 , 高橋睦正
ページ範囲:P.1805 - P.1807
気脳造影は腰椎穿刺あるいは大槽穿刺でクモ膜下腔に陰性造影剤を,脳室造影は外科的に側脳室前角あるいは後角穿刺を行って陰性または陽性造影剤を注入し,脳室およびクモ膜下腔の造影を得て,中枢神経疾患の診断を行う検査法である.
IX.運動器系疾患の診断技術
1.筋電図—普通筋電図と単一筋線維筋電図
著者: 広瀬和彦
ページ範囲:P.1810 - P.1814
筋電図検査は,骨格筋の活動に伴い発生する筋活動電位から,筋の状態を判定する神経・筋疾患の補助診断法である.筋の活動状態や導出電極の相違,また検査目的によりいくつかの検査法があるが,ここでは針電極を用いる日常的な普通筋電図検査を中心に記述し,今後臨床応用の普及が予想される単一筋線維筋電図法の概略についても若干触れることにする.
2.運動の筋電図
著者: 中村隆一
ページ範囲:P.1815 - P.1818
運動学での筋電図の応用は,人間の姿勢保持(体位と構えの関係),動きに際しての筋活動の様態を客観的にとらえるためのものである.
運動は筋群の活動の空間的・時間的分布により生じる生体内の力の連続的変化と,重力その他の外力とにより決定され,力学的に解析されるものである.そのため筋電図による情報を分析する前に,とりあげる運動パターンを運動分析によりとらえておく必要がある.筋活動電位が認められても,筋収縮としては静止性・求心性・遠心性の3種類が存在することには注意を要する.
3.末梢神経伝導速度
著者: 鳥居順三
ページ範囲:P.1820 - P.1823
末梢神経伝導速度の測定は,近年一般的に行われるようになってきた検査のひとつで,末梢神経障害を客観的に調べるための有力な手段である.末梢神経は腓腹神経など一部のものを除き,多くは混合神経であり,運動神経と知覚神経の両線維をもっている.
末梢神経障害のうち外傷などの場合には,これらの神経は一様におかされるが,内科的疾患の場合には運動神経線維がよりおかされる場合(たとえばギラン・バレー症候群など)と,知覚神経線維がよりおかされる場合(たとえば糖尿病性ニューロパチーなど)があり,末梢神経伝導速度も運動線維・知覚線維を別々に測定するようになってきている.
4.末梢神経生検
著者: 木下真男
ページ範囲:P.1824 - P.1825
原理
末梢神経の一部を生検して病理学的観察を加え,診断の手がかりとする.また場合によっては生化学的検索が行われることもあり得る,
5.関節穿刺
著者: 永野柾巨
ページ範囲:P.1826 - P.1827
関節病変や関節外傷の診断・治療上,重要な手技であるが,実施に当たっては合併症,とくに感染は重篤な結果をもたらすので慎重な手技を必要とする.しかし穿刺法そのものは決してむずかしいものでなく,皮下筋肉注射となんら異なるものでないことを強調したい.
6.関節鏡
著者: 渡辺正毅
ページ範囲:P.1828 - P.1830
原理
関節腔に生理食塩水を注射して,これを拡張し,套管針穿刺を行い,套管に関節鏡を挿入し,内部の現象を直接観察し,診断治療に役立てる.膝関節には,渡辺式21号関節鏡(図1)を,その他の諸関節には,渡辺式24号関節鏡を使用する.前者は直径4.9mm,套管外径6.0mm,後者は直径1.7mm,套管外径2.0で,いずれもパンチ生検・カラー写真記録が可能である.
X.アレルギー・免疫疾患の診断技術
1.アレルゲンの皮膚テスト
著者: 古谷達孝 , 山崎雙次
ページ範囲:P.1832 - P.1835
かつては,アレルギー反応は血清抗体による即時型反応と細胞性抗体による遅延型反応とに大別されていたが,最近では抗原・抗体反応の様式に基づき,周知のように下記の4型に分類されている,すなわち血清抗体による①1型アレルギー,anaphylactic type,②II型アレルギー,cytotoxic or cytolytic type,③III型アレルギー,Arthus現象,immunocomplex typeと,細胞性抗体による④IV型アレルギー,delayed typeである.これらのI〜IV型アレルギーのうち,I型アレルギーの抗体はIgE抗体(reagin)で,IV型アレルギーの抗体保有細胞はT型リンパ球であり,ともに被働性感作が可能である.
アレルゲン(抗原)の皮膚テストにより,ヒトの疾患診断に利用し得るものはI型アレルギーおよびIV型アレルギーである.
2.免疫能のスクリーニングテスト
著者: 早川浩
ページ範囲:P.1836 - P.1840
最近の臨床免疫学の発展に伴って,免疫機能の臨床的検査法も年々進歩しており,免疫不全症候群の病因と病態の解明に資するところがきわめて大きい.日進月歩のこの領域について解説しつくす余裕はないので,ここでは,日常の診療において免疫不全症候群を疑ったときにそのスクリーニングテストとして役立つ主なものを簡単に述べてみよう.おのおのについての詳細は成書を参照されたい1〜5).
XI.皮膚に関する診断技術
1.発汗試験
著者: 石原勝
ページ範囲:P.1842 - P.1844
エックリン汗腺と発汗
エックリン汗腺は口唇,陰部の一部を除く全身皮膚に200万以上存在し,出生時すでにその機能を発揮している.足底や手掌では分布密度が最も大で,400〜600/cm2,他方,背部や腰部のそれは最も小で手掌,足底の1/6以下である.
汗腺体は通常,真皮深層にあり,直径約20μの腺腔を囲む1層の壁細胞(clear cellとdark cell),その周囲の筋上皮細胞とヒアリン基底膜から成り,壁細胞から分泌された汗は汗管を上行し,汗孔から皮表に排泄される.通常,温熱あるいは精神刺激により,時に神経反射や薬物刺激によって発汗が促され,活動汗腺数の増加,個々汗腺からの汗排出量の増加をみる.発汗は手掌,足底では持続的にみられるが,その他の体部では間歇的に行われている.
2.皮膚生検
著者: 川田陽弘
ページ範囲:P.1845 - P.1847
皮膚生検は通常,皮膚の変化がどのような性格の病変か,たとえば腫瘍なのか,炎症性変化か,臨床的に決定しがたい場合とか,病原菌,たとえば深在性真菌症の培養,同定する際に行われる.
生検材料の病理組織学的検査の手順は,
XII.内視鏡とそれによる生検
1.気管支ファイバースコープ
著者: 堀江昌平
ページ範囲:P.1850 - P.1853
最近,呼吸器疾患の的確な診断のために,いろいろの検査法が開発され,急速に診断の実際面に導入応用され,新しい診断体系が確立されてきている.
気管支鏡検査においても,開発当初のせいぜい肺葉気管支までの精確度の低い肉眼的観察から,現在では器具の改良,技術の進歩により第IV次気管支におよぶ病巣の性状の精密な所見把握が可能となり,しかも気管支鏡検査は選択的細胞診,組織診,あるいは細菌検査などの,ほかの検査法に検体採取の場を提供し,他面,分泌物,喀痰の吸引,異物除去あるいは経気管支鏡的焼灼,摘出,さらに外科手術後の肺合併症の治療などの治療上の応用面にも有力な手段となってきている.
2.胃カメラ・胃ファイバースコープ
著者: 小黒八七郎
ページ範囲:P.1854 - P.1857
胃内視鏡は胃内部を直接肉眼視でき,さらに生検を行えば組織診も可能である。胃内視鏡器械の原理のあらまし,生検の実際,適応と禁忌,さらに生検成績の評価と誤診などについて検討考察を行ってみた.
3.十二指腸鏡
著者: 小林正文 , 太田安英 , 前田宏 , 井戸清仁 , 常岡健二
ページ範囲:P.1858 - P.1863
十二指腸内視鏡検査は,1958年,Hirschowitz1)のGastroduodenal Fiberscopeに始まるとされているが,今日使用されているようなFiberscopeの開発は,本邦では1968年頃から行われ,1970年には現在のscopeの原形が完成され,観察,生検,逆行性膵・胆道造影など検査手技の基本もほぼ同時に確立された.以後今日までscope・手技の改良,検査所見の分析研究が精力的に行われ,本法は十二指腸・膵・胆道疾患の診断に欠かせない検査法としてその有用性が一般に認められるに至った.本稿では十二指腸鏡の器種,検査の目的を中心に述べる.
4.EPCG—内視鏡的膵胆管造影法
著者: 大井至
ページ範囲:P.1864 - P.1866
原理と歴史的背景
EPCGは,Endoscopic Pancreatocholangiographyの略で,邦語では内視鏡的膵胆管造影法という.膵管の造影と胆管の造影を別個にあらわすには,EPGそしてECGと略する.逆行性膵胆管造影法,Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography(ERCP)の語も用いられている.
EPCGは,1969年にわが国で開発され,そして急速に全世界に普及した,十二指腸ファイバースコープを使って行う膵臓と胆管系の検査法で,非観血的に膵管を造影する画期的な方法として注目されている.さらに,胆管系を簡単にしかも十分な精度で造影する方法としても,日常診療において広く用いられている.
5.小腸ファイバースコープ
著者: 林貴雄
ページ範囲:P.1867 - P.1869
上部消化管内視鏡の著しい発達により,食道から十二指腸に至るまでは,ほとんど盲点がなく,各種の内視鏡による診断,治療が可能となった,しかし,空腸・回腸は口側からも肛側からも最も遠く,永い間,内視鏡の進入をはばんできた.この消化管の盲点に対し,1964年頃よりわれわれは日大式小腸生検器を考案し,盲目的ではあるが,小腸の吸引生検を行ってきた。しかし,直接に観察する必要性から,1970年になり十二指腸よりさらに深部に進入するための小腸ファイバーが試作され,この未知の部に対する内視鏡診断がとりあげられるようになった.
6.大腸ファイバースコープ
著者: 棟方昭博 , 金城福則 , 相沢中
ページ範囲:P.1870 - P.1871
大腸ファイバースコープは,松永らがオリンパス光学と協同で開発にとりくみ,1969年にはColonofiberscopeⅢ型機1)として完成され,現在では一般にも広く普及されている.因みに,田島の大腸内視鏡検査の全国アンケート2)によると,昭和49年1年間の大腸内視鏡検査例数は,硬式の直腸S状結腸鏡検査数約2,100例に対し,大腸ファイバースコープ検査数は9,500例となっており,今や大腸ファイバースコープ検査は特殊検査ではなく,日常の一般検査となった.教室では年間約350例の検査を行っており,本稿では教室で日常行っている大腸ファイバースコープ検査について簡単に紹介する.
7.腹腔鏡
著者: 岩村健一郎
ページ範囲:P.1872 - P.1875
腹腔鏡検査法は危険が少なく,しかも診断的価値が高い補助診断法のひとつである.その施行には技術的に熟練することを要し,また、得られた所見の判断に慣れておく努力が大切である.実際には腹腔鏡下に撮影したフィルムや腹腔鏡アトラスを数多く,かつ反復してみることによって,この検査法の効用を高めることができる.同時に本検査法の診断的価値は,施行前に患者の臨床経過およびそれまでに得られた臨床諸検査成績を検討し,この検査に期待すべき問題点を明らかにしておくことによって,さらに高められる.
8.直腸鏡
著者: 宇都宮譲二
ページ範囲:P.1876 - P.1880
適応
直腸は口腔・腔などとともに容易に診察しうる管腔であると同時に,疾患の種類や頻度の最も多い解剖学的部位でもある.大腸癌やポリープの70〜50%は直腸鏡到達部位に発生するし,潰瘍性大腸炎は100%直腸を侵す.したがって,本来一般内科・消化器科のルチーンの診察手技のひとつとして加えるべきものと考える.
本法の適応はJackman1)によれば,①肛門出血のあるもの,②指診で異常のあるもの,③成人集検とあるが,一般内科において下痢・便秘などの下部消化管症状のある例に広く行ってゆくべきであると思う.
XIII.アイソトープ診断技術
1.機能検査
著者: 木下文雄 , 久保敦司
ページ範囲:P.1882 - P.1889
脳循環動態
局所脳循環測定にはいくつかの方法があるが,133Xeによるクリアランス法が一般に用いられている.133Xe生食液を内頸動脈より注入すると脳組織に速やかに拡散し,次に血液により洗い出される.この脳からの洗い出しは脳組織を流れる血流によって決まるので,この様子を頭部に当てたシンチレーション検出器,シンチカメラなどで測定することにより局所脳循環測定が可能である.
方法 頭部にいくつかの検出器をもったシンチレーション検出器あるいはシンチカメラを設置した後,内頸動脈より133Xe生食液1〜2mCiを急速注入し,レートメータを介してペンレコーダに133Xeクリアランスカーブを記録する.
2.シンチグラム
著者: 久保敦司 , 木下文雄
ページ範囲:P.1890 - P.1898
近年,臓器シンチグラフィーの普及は目覚しいものがある.これは主に各種の新しい放射性医薬品の開発,およびシンチグラム装置の性能が著しく向上してきたことによる.放射性医薬品としては短半減核種である99mTcの種々の化合物が開発され,各臓器のシンチグラフィーの発展に貢献している,また,シンチグラム装置としては従来のシンチスキャンナーに加え,進歩の著しいシンチカメラが広く用いられてきている.さらに全身を短時間でスキャンできる全身スキャンナー,全身カメラ,およびコンピュータによるデータ処理装置も次第に普及してきており,各臓器シンチグラフィーは簡便かつ侵襲の少ない検査法として,他のRI検査同様,今後ますます臨床各方面に利用されていくであろう.
以下に臓器別にシンチグラフィーの方法および意義について述べる.
3.RIアンジオグラフィー
著者: 宮前達也
ページ範囲:P.1900 - P.1908
適当な半減期(6時間)とエネルギー(140KeV)を有する99mTcとシンチカメラの"Fortunate marriage"を契機としてRIアンジオグラフィーが誕生したわけであるが,約10年経過した今日では,とくにシンチカメラの改良がすすみ,一段と良好な画質が得られるようになった.
本稿では限られた誌面なので,とくに日常検査として役立つ方法のみに限定し,頸動脈あるいは心臓にカテーテルを挿入して行う研究段階の特殊な方法については省略する.
XIV.脈管造影法
1.心血管造影法
著者: 松山正也
ページ範囲:P.1910 - P.1916
原理
胸部単純X線撮影では心大血管の一部の輪郭は写し出されるが,心血管内腔の状態や血行動態を直接に描出することはできない.この場合,通常,X線吸収の大きな物質(造影剤)を心血管内腔に注入することによって造影し,その病態を把握しようとするものが心血管造影法であり,現在では高濃度の造影剤を直接目的部位またはその付近の部にまで進めたカテーテルを通して注入し,X線撮影を行う選択的血管心臓造影法(selective angiocardiography)が一般的である.
2.冠動脈・左心室映画造影法
著者: 山口洋
ページ範囲:P.1917 - P.1922
原理と意義
冠動脈および左心室に選択的に直接造影剤を注入して造影し,それらを映画に収め,活動している状態で病変を見定める方法である.すなわち,形態と機能を同時に把握し得る検査法であるため,冠動脈病変と左室心筋障害との関係を問題にする虚血性心疾患,あるいは心筋症の診断には最も優れた方法である.さらに僧帽弁膜症をはじめとする弁膜疾患の診断にも形態と機能の同時把握という点で,極めて精度の高い情報を提供する手段といえる.
むろん,心電図,血清酵素値の分析による診断もかなり高度な水準に達してはいるが,これらの検査法が心筋に起こった変化を見ているものであるから,冠動脈病変の診断という意味では二次的あるいは間接的診断法といわざるを得ない.さらに心筋の二次的変化も冠動脈病変がある程度以上進行し,その内腔狭窄が質的にも量的にも一定限界を越えないと,たとえ運動負荷など誘発条件を加えても,心電図上の変化として現れてこないばかりか,しばしば狭窄病変が一定限界をはるかに越えた高度なものであるにもかかわらず,心電図上変化を示さないこともある.
4.膵血管造影法
著者: 平松京一
ページ範囲:P.1928 - P.1935
膵疾患に血管造影が応用されてすでに10数年もたち,現在では一般病院でも広く行われるに至っている,膵血管造影の目的は上部消化管バリウム検査や,低緊張性十二指腸造影などからは得ることのできない情報を得ることであり,膵管造影や膵シンチグラム,さらに最近開発されたCTスキャンなどとともに,膵疾患の鑑別診断に大きな役割を持つものである.悪性腫瘍の場合には周囲の比較的大きな血管に対する浸潤や,肝転移巣の有無をも同時に知り得ることから,手術適応を含めた治療方針決定にも大いに役立つわけである.
5.消化管血管造影法
著者: 木戸長一郎
ページ範囲:P.1936 - P.1938
その意義
選択的血管撮影は,目的とする臓器に分布する大動脈分枝に,予め熱処理により先端を彎曲せしめたcatheterを挿入し,その血管分枝を造影する方法であり,1953年,Seldingerが経皮的に行う方法を発表して以来,広く行われるようになった.
血管は体内にくまなく分布するので,その性状を詳細に観察することで腫瘤の存在を知るばかりか,悪性腫瘍にあっては腫瘍血管としての異常性の存在がその病態把握を容易にする.したがって肝,腎,膵などの実質臓器には欠くことのできない検査法のひとつであるが,管腔臓器である胃や大腸の悪性腫瘍に対しても,その腫瘍の占拠部位,浸潤範囲を比較的容易に知り得るのみか,隣接臓器との関係や転移巣なども明確に理解することができる.
6.腎・副腎血管造影法
著者: 平松京一
ページ範囲:P.1939 - P.1947
腎と副腎は異なった臓器ではあるが,その位置的関係ならびに血管系の密接な関係から,ここでは両者の血管造影法を同時に述べることにする.腎の血管造影はかなり以前よりdos Santosによる経腰的直接穿刺の大動脈造影により行われていたが,Seldingerによる経皮カテーテル法によって現在行われている大動脈造影や選択的な腎の血管造影が普及し,その血管解剖からみても種々の臓器の中で最も血管造影が診断上役に立つとされている.一方,副腎についても,動脈支配の複雑さにもかかわらず,技術の進歩に伴い副腎動脈の選択的な造影が可能となり,またMaroniやBuchtによる副腎静脈血カテーテル採取法が副腎静脈法へ応用されるに至って,副腎疾患の診断は後腹膜亢気法から血管造影へとその主流が移ってきた.
7.脳血管造影法
著者: 玉川芳春 , 高橋睦正
ページ範囲:P.1948 - P.1952
脳血管造影法は脳血管に水溶性造影剤を注入し,造影剤が動脈,毛細管,静脈を循環している間に頭部撮影を行い,脳血管の性状から神経系疾患の診断を行う検査法である.
8.脊髄血管造影法
著者: 打田日出夫 , 黒田知純
ページ範囲:P.1953 - P.1956
脊髄腫瘍,脊髄の血管性病変,脊椎腫瘍が疑われたり,疼痛,間歇性跛行,麻痺などの症状が血管性病変によると考えられた場合に脊髄血管造影が適応となるが,脊髄自体とその周辺の血管を同時に造影できる脊髄動脈造影が主体をなし,硬膜外の静脈しか造影できない脊椎静脈造影は補助的診断法である.
9.四肢血管造影法
著者: 阪口周吉
ページ範囲:P.1957 - P.1960
動脈造影
適応 動脈の走向,形態異常,内腔の変化,閉塞の有無や部位,範囲,副血行の発達程度などを知るために,次のような疾患に対して行われる.
1)急性および慢性の動脈閉塞症について単なる診断よりも閉塞の範囲,run-off(閉塞部以下の末梢の血流状態)の程度,開存血管の細かい病変などを検するために行われる.
10.リンパ系造影法
著者: 入野昭三
ページ範囲:P.1961 - P.1965
リンパ系造影法Lymphographyは,リンパ管に造影剤を注入することによって,リンパ管およびリンパ節をX線的に撮影する方法であり,Kinmonth(1952)の色素注入によるリンパ管染出の成功と,直接リンパ管内造影剤注入法の確立,およびすぐれた油性造影剤の登場と相まって,その臨床応用が急速に広がり,手技の簡便さと相まって,近年,routineの一般検査法となってきている.
XV.超音波診断法
1.超音波診断法
著者: 和賀井敏夫
ページ範囲:P.1968 - P.1977
近年,超音波という一種の音波(弾性波)が臨床各分野において,種々の特色をもった診断法として利用されるようになってきた.この超音波診断法といわれるものは,広い意味における超音波応用技術の一部門である.超音波応用技術は超音波エネルギーを応用する動力的応用,すなわち強力超音波応用と,超音波を情報伝達の手段とする応用,すなわち通信的応用とに大別される.前者の動力的応用には超音波加工,超音波洗浄など,医療では超音波治療が含まれ,後者の通信的応用には超音波探傷器,魚群探知器や医療では超音波診断が含まれることになる.この中で,超音波の通信的利用は第二次大戦中ソーナーのような軍事目的に開発が進められたが,戦後これらの技術の平和利用として,探傷器や魚群探知器の開発と同時に診断的利用の研究が始められた.これは1950年頃からであり,それが近々20年の間に飛躍的進歩を遂げたわけである.この理由としては,目覚ましい発展を示した電子工学の技術を縦横に取り入れたことによることはもちろんであるが,一方,超音波診断法が現代の医学の要望にかなりの部分で答え得るという因子を持っていることがあげられる.超音波診断法の臨床的研究は,わが国が世界に先がけて着手し,1960年代はわが国の独壇場であったが,1970年に入り,諸外国,ことに米国における開発,利用が急速に進歩し,今や世界的にも診断法の領域に新しい分野としての地位を確保するまでになった.
治療篇
1.胸水・腹水・心包液・浮腫液の除去
著者: 末次勧
ページ範囲:P.1980 - P.1981
胸水・腹水・心包液・浮腫液の治療においては,まずその病因を明らかにして原因を除くことが大切である.しかし,液体の貯留が高度となって圧迫障害が認められる場合,原因療法によっても容易に液体が減少しない場合などには,対症的に器械的排除を行う必要がしばしば生ずる.
ここでは診療技術という観点から,胸水.腹水・心包液の穿刺排液法について述べる.貯留液を排除する目的は次のごとくまとめられる.①貯留液の圧迫によって起きる種々の障害(循環不全,換気機能障害など)を除く.②貯留液の吸収を促進する.すなわち,液体が長期間存在することによって起きる,二次的不可逆的機能障害(胸膜癒着・肥厚による拘束障害など)を防ぐためである.
2.非経口栄養
著者: 太村信良
ページ範囲:P.1982 - P.1984
栄養物を経口的に摂取するのが,もっとも生理的なことは,常態でも,また病態でも変わりはない.しかし,病態下では経口的に全く,あるいはほとんど栄養摂取ができない場合が少なくなく,また摂取はできても消化吸収の過程が障害されている場合もある.非経口栄養は,これらの状態の栄養管理に欠くことのできない方法である。今日では,輸液は広く行われ,それぞれ特徴をもった輸液剤も多く,患者の状態に応じて,適宜選ぶことができる.
非経口栄養は,本来避腸栄養parenteral nutritionの意味で,腸以外からの栄養補給を指すものである.
3.心拍停止に対する処置
著者: 三浦勇
ページ範囲:P.1985 - P.1988
循環が停止すれば臨床上患者は死亡したとみなされるが,もはや再出発が不可能な状態-生物学的な死亡は,これより3〜20分後に訪れる.
常温においては循環の杜絶から3分前後でまず脳皮質の細胞が,次いで約10分後には脳幹が不可逆性変化を蒙る。いわゆる脳死の状態で,精神と中枢神経の活動は永久に失われる.心筋は約20分間の無酸素状態に耐えられるが,それ以後は収縮機能を回復しえない.つまり心臓死で,絶対的な死を意味する.
4.DCショックの取り扱い
著者: 三浦勇
ページ範囲:P.1989 - P.1992
1962年,Lownらによって開発された直流除細動器(DCショック)は,心臓病治療の歴史にひとつのエポックを作ったといえる.心室細動は従来治療対象の枠外にあったが,除細動器なかんずくDCショックの出現によって確実に除去されるところとなり,心臓外科今日の隆盛をもたらし,CCU設立の技術的背景となった.一方,心房細動とその他の頻脈型不整脈に対するDCショックの偉力もまた著しい,以下DCショックの原理と装置,適応,治療の実際などについて述べる.
5.気胸に対する処置
著者: 谷本普一
ページ範囲:P.1993 - P.1996
原理
気胸とは胸腔内に空気が存在する状態をいい,その原因により,①自然気胸,②人工気胸,③外傷性気胸,④医原性気胸に分類される。気胸全体に占める比率は自然気胸が最も多く,それはさらに特発性と続発性とに分けられるが,いずれも原因はブレブの破裂によるものが多い.したがって,気胸の治療にはたえずブレブの破裂とその修復状態を考慮する必要がある.
気胸の治療方針は,①呼吸困難および胸痛の除去,②肺の再膨張,③再発の防止をはかることである.一般に患者は創痕を残す開胸術を希望しないこと,続発性の多くの患者は手術ができないような原疾患をもっていること,特発性のものは一定の年齢に達すると発症しなくなることなどにより,気胸の治療は内科的治療が主体となる.
6.窒息に対する処置
著者: 永原國彦
ページ範囲:P.1997 - P.2000
窒息(asphyxia)とは酸素の取り込みと,炭酸ガス排出との両方の障害のある状態をいう,すなわち酸素分圧が低下し,炭酸ガス分圧が上昇した状態である.その原因としては,気道の閉塞,肺ならびに肺胞,呼吸運動,胸腔,血液,外気などの異常があげられる.ここでは気道閉塞にしぼって,その処置ならびに注意すべき点につき述べる.
鼻咽腔ならびに口咽腔の閉塞に対しては,通常,下顎前推,頭部後傾法を実施し,酸素療法を行う.airwayの使用ならびにmouth-to-mouthまたはmouth-to-noseの呼気吹き込み法は有効であり,このためにSafer,Brookなどのairwayが開発されている.
7.酸素療法
著者: 古田昭一
ページ範囲:P.2001 - P.2008
酸素療法は,古くから行われている大気圧下での酸素吸入療法と,近年しだいに一般化しつつある高気圧環境下での高圧酸素療法とに分けられる,酸素療法の目的は吸気に酸素を加えてやり,低酸素状態(hypoxia)を改善することにある.体組織は予備酸素を保持することができないので,心肺機能の異常で十分な酸素供給がなされないときは,吸気に酸素を追加する必要がある.高圧酸素療法も主として,この目的に沿って使用されることが多い.しかし,適用の一部には必ずしもhypoxiaの状態ではなく,normoxiaの状態で使用し,急性hypoxiaによる可逆的中毒作用を高圧酸素効果(hyperbaric oxygenation)に期待していると考えられる治療法も含まれている.したがって,酸素療法の治療機序も一元的なものではない.酸素療法の適用の状態と治療条件,および効果の大要を表1に示した.
8.高圧酸素療法
著者: 古田昭一
ページ範囲:P.2009 - P.2016
大気圧よりも高い気圧環境のなかに患者を収容し,高濃度の酸素を投与することにより症状の改善をはかろうとする治療法を高圧酸素療法と定義することができる.高圧医学の発達の歴史は新しいものではなく,1662年,イギリスの生理学者Henshawは肺疾患の治療を目的として高圧室を作り,急性例は高圧で,慢性例は低圧で治療した.1830年代になり,フランス人によってle bain d′ air cornprimé(圧縮空気浴)と称する治療法が流行し,多くの臨床例が報告された.1878年,Paul Bertにより高圧生理学の基礎が完成され,また彼は神経系に対して高圧酸素が毒性をもつことを実証した.
高圧酸素を治療として用いたのは,1887年,Valenzvelaにより肺炎に使用されたのが最初であるとされている.1895年,Haldaneは高圧酸素がCO中毒を防止することを実験的に証明した.しかし,これらの適用が理論的な根拠を欠いたために,流行は廃れ,さらには酸素中毒に関する生理学的,薬理学的な研究が進むに従い,高圧酸素を治療に応用しようという機運は生まれない状況のまま約50年を経過した.
9.呼吸の人工管理—レスピレーター
著者: 岡田和夫
ページ範囲:P.2017 - P.2020
原理
呼吸困難,チアノーゼ,呼吸不全などで積極的に人工呼吸を施行して,肺胞まで酸素を送り込み,炭酸ガスを排泄させる方法である.従来は「鉄の肺」で代表される方式の,胸郭を外から膨張,圧迫してガスを二次的に気道から出入させる方法がとられたが,今日ではこの方法はすたれてしまい,気道に直接ガスを送り込む方式がとられ,人工的に気道に圧を加えることが第一のステップで,これが吸気となる.呼気は加圧により膨らんだ肺および胸郭の弾性によりバネが縮むようにして行われる.
救急蘇生法 人工呼吸は救急蘇生法の中で最も迅速かつ有効に施行されねばならないアメリカのSafarらが提唱したABCの手順でも,A=Airway,B=Breathe(人工呼吸),C=Circulateでみるように,呼吸の管理,すなわち気道の確保(A)と人工呼吸(B)が実施されながら循環対策(C=心マッサージ)が行われねば効果がうすいことを示している.
10.食道静脈瘤破裂時に用いる三方チューブ
著者: 二川俊二 , 杉浦光雄
ページ範囲:P.2021 - P.2023
原理と適応
食道静脈瘤破裂に対する治療に際しては,他の消化管出血に対する治療とは,著しく異なるため,出血が静脈瘤破裂によることを早急に適確かつ確実に診断を下すことが大切である.食道静脈瘤破裂の診断が確立したならば,保存的に止血を試み,できうる限り待期的手術を行うように心がけるのが原則である.
balloon tamponade法は保存的止血方法として,最も一般的な方法であり,1930年Westphalが報告して以来,種々の方法が報告されてきたが,今日,最も一般的に広く用いられている方法は,Sengstakeni-Blakemore tube(以下S-B tubeと記す)によるものである.したがって以下,S-B tubeを中心に述べる.S-B tube使用は治療の原則から考えられるべきであって,使用に先立ち,診断を確立させる要がある.
11.尿道留置カテーテルと膀胱洗浄
著者: 西浦常雄
ページ範囲:P.2024 - P.2027
原理
下部尿路に機能的あるいは器質的病変が起こり,尿流の通過障害が招来された場合,その姑息的療法として尿道留置カテーテルが行われる.
下部尿路(膀胱,尿道)の尿流通過障害は,排尿困難や尿閉などで患者自身に著しい苦痛を与えるが,尿流の停滞は尿路感染を誘発し,膀胱炎,腎盂腎炎,敗血症と進展し,高熱の持続のみならず腎実質の荒廃に連なっている事一方,下部尿路の尿流通過障害は両側の上部尿路に同時に影響を与えるという点が重要である.慢性の下部尿路尿流通過障害では,無症状の中に両側の水腎症を惹起して進行し,腎不全からさらに尿毒症に進行する.このように,下部尿路の尿流通過障害は身体に対して重大な意義を有するものである故,その原因病変の除去という根治的手段を早急に行うことが必要である.直ちに根治的手段が行えない場合に,尿流のバイパス法としての尿道留置カテーテルが必要となってくるわけである.
12.輸血—適応と輸血量
著者: 遠山博
ページ範囲:P.2028 - P.2031
「輸血の適応と輸血量」という主題はなかなかにむずかしく,限られた誌面にまとめることをためらうものであるが,その考え方を主力として論じてみたい.輸血を大きく分けて,外科的な感覚のものと内科的なものとに大別する.
13.輸血—特殊な輸血
著者: 遠山博
ページ範囲:P.2032 - P.2035
特殊な輪血といってもいろいろな観点があるであろうが,本稿では主として血液成分輸血について述べたい.真に患者が必要とする血液成分のみを与えるいわゆる"成分輸血療法"blood component therapyが急速に普及しつつあるのは御存知であろう.
14.輸血—副作用とその対策
著者: 遠山博
ページ範囲:P.2036 - P.2041
本稿では輸血によって起こる副作用のうちで,輸血血液が患者に適合しなかったり,変性を起こしていたもののみについて記述する.
15.輸液—注入液の選択と計画
著者: 飯田喜俊 , 福原吉典
ページ範囲:P.2042 - P.2047
注入液の選択と計画のたて方
輸液を行う場合として,①電解質や塩酸基平衡の異常の補正のため,②経口的に摂取できず,非経口的に電解質や栄養を補うため,③特殊な治療目的,たとえば急性腎不全や脳浮腫にマニトールを与えて改善をはかる場合などがある.それぞれ病態に応じ,必要に応じて輸液が選ばれ,計画される.
電解質の異常は大別して表1に示すものがある,この表ではそれぞれの対策についてもまとめた.しかし,実際の症例では,これらの異常のいくつかが組み合わされてひとつの病態をつくっていることが多く,対策もそれぞれに応じて対処さるべきである.一方,ある体液異常が他の異常から二次的に生じる場合もあり,この際には一次的異常を補正することによって二次的異常も正常となることもあり,一次的異常の補正のみで十分なことがある.それ故,これらの見極めのためにも患者の病態,すなわち,どのような種類の体液バランスの異常があるか,また,それら異常の間にいかなる関係があるか,などについて知る必要がある.一方,患者が非常に重篤で,詳しく病態を検討する余裕がなく,とりあえず応急的に輸液を始めることがある.この場合には,輸液を行っている間に検査データが揃うので,病態が明らかになった段階で,それに適した輸液にきりかえる.
16.輸液—小児の輸液療法
著者: 佐藤仁
ページ範囲:P.2048 - P.2050
戦後乳幼児の死亡率が激減したのは,抗生物質療法と輸液療法の発達によるところが大きい.乳幼児は成人よりも,はるかに脱水症を起こしやすく,脱水症に対して輸液療法は救命的な効果がある.したがって,小児科医はその手技に熟達するとともに,輸液療法の意義を正しく理解しておく必要がある.
かつて輸液療法の主な対象であった疫痢,消化不良性中毒症,重症アセトン血性嘔吐症(周期性嘔吐症,自家中毒症)などはほとんどなくなり,現在,輸液療法の主な対象となっている脱水症は,以前よりはかなり軽症である.したがって,これらの脱水症に対する輸液量は以前よりは少なくてよいと考える.また,腎不全に対しては腹膜灌流や血液透析が行われており,現在では腎不全に対して輸液療法を行うことはあまりないから,ここでは一般の脱水症に対する輸液療法についてのみ述べる.
17.輸液—プラスマフェレーシス
著者: 鳥居有人
ページ範囲:P.2051 - P.2053
プラスマフェレーシス(plasmapheresis)とは,1914年Abel, J. J1).らがはじめて使用した語で,血液の有形成分を元に戻して血漿だけを採取するとの意味である.彼らは動物から大量の血漿を採取する方法として発表したのであるが,第2次世界大戦で大量の血漿が必要となったため,この方法を人血に応用する考えをCo Tui2)らが1944年に発表した.しかし,当時の手技は極めて原始的なもので,ガラス瓶中に採血したものを遠沈し,血漿を抜き取るため,無菌操作の面で完全とはいえなかった.その後Plastic bagが輸血器具として用いられるようになってから,急速にplasmapheresis(以下P. Pと略す)が普及した.日本語としては血球返還採血という語旬が使われているし,血漿除去後,正常血漿を血球に混じて返還する作業をくり返すのをplasma exchange(交換血漿)と称している.
もちろん本文は治療技術としてのP. Pについて述べるのが目的であるが,現在,P. Pが実際に行われているのは臨床より血液銀行業務として血液製剤の材料を調達するためである.
18.輸液—腹水静脈還流法
著者: 島田宜浩 , 湯浅志郎
ページ範囲:P.2054 - P.2057
腹水の有無は,肝硬変症の予後を左右する重要な因子であるが,肝硬変症の腹水の大部分は,安静,食事療法や利尿剤の投与などで消失させうる.しかしながら,上記の治療に抵抗し,治癒し難い腹水を持った症例が存在し,難治性腹水といわれている.とくに,再度ないし再再度,貯溜した腹水は難治性となることが少なくない.
難治性腹水の治療として,腹水再静注法の試みは,目新しいことではないが,最近,各方面における肝疾患治療の進歩とともに,本法が再評価される気運にあるものと思われる.また,閉鎖回路で持続的に腹水を除去し,濃縮して静脈内に再静注する装置が開発され注目を浴びている.
19.腹膜および血液透析
著者: 杉野信博 , 下村旭 , 湯村和子
ページ範囲:P.2058 - P.2060
腹膜透析
原理 透析の原理は図1のごとく,セロファン嚢の中に血漿を入れ,外側にリンゲル氏液のごとき透析液を置いた場合に,よりよく理解される.透析膜は通常平均30A前後のporeが無数に開いているので,水はもちろん電解質,尿素,尿酸,クレアチニン,ブドウ糖のような小分子の物質を自由に通過させることが可能であるが,高分子の蛋白,ポリペプチド,あるいはウイルス,細菌などは全く通過しない(ただし膜に裂孔などがあれば別),したがって,膜を介する拡散(diffusion)によって血漿側から尿素,クレアチニンなどが通過するが,透析液と濃度勾配が等しい電解質はmetとしての動きはない.しかし濃度差を作った場合(たとえばカリウムは一般に透析液側に低くする),その物質は濃度の高い側から低い方へ移動する.次に透析に関与する力としては浸透(osmosis)があり,通常,透析液にブドウ糖を加えて浸透圧を上げ,高浸透圧として血漿側から水を移動させる.腹膜透析の場合,市販のものはブドウ糖濃度1.5および7%のものがあり,患者の浮腫状態から適当に混和して用いる.第3の力としては血漿側に働く陽圧であり(あるいは透析液側に陰圧を加えてもよい),超濾過(ultrafiltration)といわれ,これは血液透析において作用する力である.
20.抗癌剤の持続動脈注入法
著者: 都築俊治 , 中村康孝
ページ範囲:P.2061 - P.2063
抗癌剤の持続動脈注入法とは,抗癌剤を腫瘍の栄養動脈へ挿入したカテーテルから注入することによって抗癌剤の濃度を高め,また,副作用を軽減しようとする方法で,普通,infusion therapyといわれている.したがって,この方法の対象になるものは,癌が動脈から栄養をうけていることと栄養動脈が複数でなく,end organになっていることが必須条件である.この意味で,膵癌はこの方法の対象にはなりにくく,肝癌,肺癌,頭頸部腫瘍が対象になるが,本文では筆者の専門である肝癌について述べる.
21.RIの内用療法
著者: 橋本省三
ページ範囲:P.2064 - P.2067
現況
RIを患者の体内に経口投与,注射,穿刺,注入して行う内用療法は,治療用の放射性医薬品として販売されている131I,198Auが主である.昭和49年には131I治療用カプセル23,600mCi,液11,100mCi,注射液1,600mCiであったものが,翌年の50年には25,500mCi,5,900mCi,400mCiとなって,全体として減っており,カプセルの使用が多くなっている.198Auは25,900mCiが19,700mCiと減少傾向を示している.このことはRI内用療法は法的規制によって放射線治療病室で行われなければならず,また,看護婦などの手不足が経営上の収支を悪化させ,本法の実施に伴う当直体制,廃棄汚染物の処理などの諸経費の支出を許さなくなり,他方,その治療効果は化学療法剤などの出現と投与方法の進歩によってカバーされるようになってきたからである.
しかしながら甲状腺疾患に対する治療効果は機能亢進症,悪性腫瘍ともに秀れているので,ひき続き行われており,投与の容易なカプセルを,主として外来で投与しているものと考えられる.この点は放射線管理上問題であるが,198Auは入院を要するのでこれらの管理上の問題は少ない.半減期のことを考えると,131Iでは年間4,000例,198Auは300例程度が昨年度に行われたかと推定される.
付録
1.ME機器の安全管理
著者: 石山陽事
ページ範囲:P.2070 - P.2072
最近のME機器の進歩は,確かに医学の分野で着実にその威力を発揮しつつある.しかし一方,電子工学の急速な発展によるより高度なME機器は,使用者にとっては,それを使用することで精一ぱいのあまり,機器の性能や安全についてチェックする余裕のないのが現状といえる.結論からいえば,その原因として,患者をみる医師とパラメディカルスタッフ相互に介在する,いわゆるME機器を中心とする医療システムを医学的,工学的見地から評価し,責任管理するMEの専門的技術者が不足していることにある。最近は臨床工学(clinical engineering)という言葉が,臨床に直結したME技術の分野として使用されているが,機器や設備の拡大に伴い,機器の購入計画,および将来計画,機器の信頼性の再評価,安全管理の確保などがますます重要になり,この臨床工学を専門とする技術者の必要性にせまられている.しかしわが国では,このような専門家が各診療機関に配属されるためには,現在ではまだかなりの時間が必要なようである.したがって,ME機器に対する安全管理は機器の使用老自身が行わなければならない.
2.内視鏡器具の消毒法
著者: 亀谷麟与隆
ページ範囲:P.2073 - P.2076
消毒の意義
内視鏡器具の消毒は,病院における感染症の発生の防止上重要である.
院内感染の問題は100年以上も前から注目されている.当時,産婦に高頻度にみられた産褥熱が,出産の際の介助者の手指を介する感染によることが判明し,1847年5月に手を塩素水で洗うことをはじめたところ,産褥熱が20%付近から2%近くに減少したとの報告1)がある.
トピックス
食道癌の診断
著者: 鍋谷欣市
ページ範囲:P.1628 - P.1628
本邦における早期食道癌の集計をみると,初発症状は極めて軽微なものが多く,とくに微小癌や表層型癌では,もはや嚥下困難など従来の症状によるチェックでは不十分である.また食道癌治療成績の向上のためには,かかる微小癌や表層型癌の早期発見によって,はじめて期待されよう.
筆者は,数年来食道癌の診断面での工夫に努めてきたが,小稿では食道X線連続撮影装置とカプセル法食道擦過細胞診の開発について述べてみたい.
診療メモ
随時血圧によせて
著者: 石見善一
ページ範囲:P.1631 - P.1631
高血圧症の診断治療に際し基礎血圧が重要であり,そのために種々の工夫がこらされているが,その実測は口でいうほど簡単ではない.
最近,病院専門外来とは別に診療所で患者をみる機会を持っているが,血圧測定値の意味づけに関連して考えさせられることが多い.
脳波判読と校正電圧曲線
著者: 江部充
ページ範囲:P.1633 - P.1633
心電図や脳波のように,体表面に電極を接着して増幅器や記録器のような電子機器を使用して検査をする場合,生体での現象がこれらの機器の特性によっていろいろな制約や歪みをうけて表現されることを忘れてはいけない.とくに波形や振幅をみる場合にそれが大切である.脳波の場合,脳波計の低域周波数を決める時定数は0.3秒ということになっている.これが小さくなれば,ゆっくりとした変動の振幅が抑えられるために基線の動揺が少なくなり,一見きれいな記録がとれたように見える.しかし,徐波の振幅もまた抑えられて小さくなっている.また,高域は60Hzまでは平坦な周波数特性をもっていなければならないが,これが守られなくて低域に傾くと棘波(spike)の振幅が小さくなったり,先端が丸味をおびて小さなspikeなどを見逃すこともある,このような周波数特性の変化の原因が,装置の増幅器に由来することもあれば,記録器に由来することもある,このような周波数特性の変化を簡単に見極めるには,なんといっても校正電圧曲線(calibration curve)をよく見ることである.脳波を判読する前にまずこの曲線をながめて,その高さが正しく5mm/50μVか,先端がきれいに尖っているか,時定数が0.3秒になっているか,脳波計の全チャンネルで一列にそろっているか否かを判断しなければならない.
記録器のペン圧のちょっとした差がしばしば波形を歪ませる原因となることがある.
聴診器の使い方
著者: 石見善一
ページ範囲:P.1637 - P.1637
聴診器の使い方でまず重要なことは,聴診器自体の選択である.アメリカの教科書に悪い聴診器の例として出されているような代物を使用している方はもうあるまいが,スマートなアメリカ式のものもクレームをつけるとすればつけ得る.それはear pieceである.はじめからやわらかく耳に合致し,長時間使用しても耳の痛みを感じない,しかもear pieceの金属部の角度がうまく外聴道に一致しているものは少なく,同一聴診器でも馴れるまでにはかなりの時間を要する.各自に自由に使いこなせるものを持っていることが何より大切で,借りものの聴診器では旧式の聴診器に劣る場合も起こり得る.
聴診に際して第2に大切なことは聞こうとすることである.「心ここに在らざれば聞けども聞こえず」で,常に何を聞こうとしているかを明確にしておくことが大切である.たとえば第II音は?……強度は?……分裂は?……雑音は?と常に自問自答しながら聴診をすすめていく.
太鼓撥指の診かた
著者: 金上晴夫
ページ範囲:P.1670 - P.1670
太鼓撥指は慢性肺気腫や気管支拡張症などの慢性肺疾患の場合にしばしばみられる症状のひとつであるが,肺癌の場合にも,その合併頻度が高く,また,それが肺癌の他の症状に先がけて出現することが少なくないので重要な所見である.
本間によれば,128例の肺癌の77例(60%)に太鼓撥指が合併しているという.組織型別にみると扁平上皮癌38.4%,腺癌30%,未分化癌31.6%であるが,燕麦細胞癌には1例もみられなかったとYacoubらは述べている一また肺癌の手術後に太鼓機指が消退した症例も報告されているので,やはり見逃してはならない所見である.太鼓掻指の判定の仕方は図に示した.
聴診器の選び方
著者: 石川恭三 , 井出陽子
ページ範囲:P.1674 - P.1674
聴診器は胸壁に当てる採音部(chest piece)と,耳に挿入する挿耳部(ear piece)と,この両方を連結する部分(tubing)の3つの部分から構成されている.よい聴診器を選ぶにはそれぞれ各部の性能の良いものを選ばねばならない.ここではその要点だけを述べておく.
1)採音部(chest piece):現在,普通に使用されている聴診器には,漏斗状のOpen-bell型と,隔膜状のDiaphragma型の2つがそなわっている.
呼吸器疾患における視診のポイント
著者: 金上晴夫
ページ範囲:P.1688 - P.1688
1)顔面の腫脹:頸から顔にかけて赤く腫脹している所見は上大静脈が圧迫されている所見として重要である.この場合の腫脹あるいは浮腫は頸静脈の怒張を伴い,顔面の発赤を伴うので,腎炎の浮腫が一見蒼白なのに比べて区別できる.悪性腫瘍,とくに肺癌や縦隔リンパ節の転移を疑う所見である.
2)女性乳房:男性の乳部が女性のように肥大したもので乳首がかたい.阿部によれば高齢者の男性で女性乳房を訴えて来院した症例109例中,胸部X線検査の結果20例(25%)に肺癌を認め,また肺癌267例中,女性乳房の合併が7.5%であったと報告しているので,肺癌を疑うべき重要な所見である.女性乳房があって胸部X線写真で異常陰影を認めたら肺癌を疑って精密検査をすべきである.
動脈血の採血
著者: 河合忠
ページ範囲:P.1699 - P.1699
穿刺部位の消毒,適切な注射器を用いることは他の採血の場合と同様である.
一番問題になるのは穿刺部位の選択である.すなわち,穿刺後の血栓形成,静脈血の混入の可能性,穿刺が容易であること,などを考慮して決めなければならない.
心電図測定に関すること
著者: 石川恭三 , 柳沢厚生
ページ範囲:P.1719 - P.1719
心電図の計測には,①棘波の振幅の計測,②時間幅の計測,③軸(axis)の計測がある.そのおのおのについて若干述べてみたい.
①棘波の振幅の計測:通常の心電計は熱ペン式なので心電図波形はかなりの幅をもった線で描かれることになる.この際,振幅の計測は基線の上縁(top)から棘波の上縁(top)まで(top-to-top)か,基線の下縁(bottom)から棘波の下縁(bottom)まで(bottom-to-bottorn)を計測すべきであり,決してtop-to-bottomとか,bottom-to-topなどの計測はすべきでない.また,基線の中点(middle)から棘波の中点(middle)まで(middle-to-middle)を計測してもよい.
聴診器の使い方
著者: 石川恭三 , 金光弘
ページ範囲:P.1727 - P.1727
まず,性能のよい聴診器を用いることが第一条件である(p.62参照).ear-pieceが自分の耳孔にぴったりと当てはまり,外来雑音が十分に遮断できるように調節する.
患老の息が顔に当たらないような体位を患者にとらせる.この際,チューブをブラブラさせていないことも必要である.
診療手技のコツ
選択的血管造影におけるカテーテル操作
著者: 平松京一
ページ範囲:P.1814 - P.1814
選択的血管造影に用いるカテーテルの種類と先端の屈曲には多くの種類があり,目的とする血管によってこれらの中から適当なものを選ぶわけである.カテーテルには屈曲をつけて消毒された状態で市販されているものがあり,これをそのまま使用するか,あるいは自分でカテーテル先端の屈曲を作ってこれを使用する2つのやり方がある.
組織・細胞標本のとりかた
著者: 金子仁
ページ範囲:P.1835 - P.1835
組織の採出の仕方は,当然ながら肉眼で病変部を確かめ,その部を採出する.できれば周囲の健常部もかけて取り出すのがよい.ことに皮膚科の生検の場合は必要である.
組織の大きさは大きいほどよいが,臨床医にしてみるとなるべく小さく,患者に苦痛を与えず,後始末も簡単にできるような取り方が最も好ましいに違いないが,病理側にとってはあまり小さくて診断のつけられない標本は,たいへん困る.中には標本を作れないほど小さい材料を提出されることがある.この時は「標本作製不能」と返事をしている.喉頭部や外耳道などの耳鼻科関係を除いて,小指頭大ぐらい以上の大きさが欲しい.
組織・細胞標本のつくりかた
著者: 金子仁
ページ範囲:P.1847 - P.1847
現在,病理標本を作るのは検査技師で,標本の診断をするのは病理医である.したがって,技師の"ウデ"と病理医の"メ"が対になって,はじめて適切な診断ができる.
私はかつて,国立東京第一病院病理に勤務していた時,国立病院臨床病理共同研究班の病理幹事をしていた.私がとり上げたのは,病理の特殊染色である.東一病理で同一の未染色薄切標本を全国国立病院に送り,特殊染色を施して私の所へ送ってもらう.私がそれを1枚,1枚点検し,点数をつける.そうして技師に送り返す.このような研究方法で,技師の技術の向上を図っていた.この時私は,「病理の標本は芸術」だと感じた.同じ標本を同じ染色法で染めて,でき上がりは月とスッポンほど異なるのである.技師の"ウデ"の違いをまざまざと見せつけられた.下手な標本で病理の診断がつけられるか,こんな気持ちで,私は技師の教育に熱心になった.
組織・細胞標本のみかた
著者: 金子仁
ページ範囲:P.1956 - P.1956
病理学的検査の特徴は,成績が決してデータではなく,診断であるという点である.さらにその診断は決して数字で出るのではなく,病理医のカンと経験からつけられる点である.これが病理検査の強味であり,弱味なのである.
病理検査は,組織診であれ,細胞診であれ,1枚でも余計に標本を見,その患者の予後を臨床医といっしょに考えている病理医でなければ適切な診断はできない.単に動物実験のみに日を送っている病理学者では,患者の診断,臨床医への優れたアドバイスはできない.病理で診断したから正しいのではない大切なのは,誰が診断したかである.医師で病理学を専攻する以上,熟練した病理医であり,優秀な病理学者でなければならぬ.
胃洗浄
著者: 西崎統
ページ範囲:P.2050 - P.2050
胃洗浄は,通常経口的な毒物や食物残渣を排除するための救急技術のきめ手として重要な位置を占めている.したがって,その主な適応としては,種々の薬物中毒,幽門狭窄,胃拡張,腸閉塞などがある.
その手技であるが,その前に,取りはずしのできる義歯のあるときは嚥下する恐れがあるので,あらかじめ取りはずしておくことを忘れてはならない.
直腸指診
著者: 西崎統
ページ範囲:P.2063 - P.2063
大便異常,便通不整,下腹部痛および下血などを訴える,すべての患者に対して必ず行うべき診察である.この簡単に行える直腸指診は,直腸のみならず,ダグラス窩,前立腺,女子性器などの数多くの疾患を知り得ることができる.また,この診察は直腸鏡を行う前には,内部の状況や走行などをみておく上で欠かすことのできない診察である.ここで,もう一度,肛門,直腸部の解剖をよく理解しておく必要がある.
肛門・直腸の軸はまず前方に,ついで急に後方に曲がり,仙骨前面にそって彎曲しつつ上がる.括約筋による肛門管3cmくらい入ると膨大部になり,前面に前立腺または子宮膣部を触れる.ときには後屈子宮では膣部を触れずに,もっと深部で子宮底を触れる.
基本情報
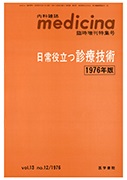
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
