Uremic toxinの研究はcentury old searchといわれるように,その研究の歴史は古い.尿に排泄されるべき物質が腎不全のために排泄されず蓄積し,それが尿毒症の病態を形成するという考えは最も明快であり,早くから研究の対象となった.しかし,尿素,フェノール,グァニジン誘導体にいたるまで多くの物質が検討されてきたが,未だ結論的なものを得ていない.これは,腎不全患者の血中から見出された物質の毒性を証明するのは,必ずしも容易なことではなく,また尿毒症症状の多くが水電解質代謝異常,酸塩基平衡の異常,エリスロポエチンなどのホルモン分泌異常などで説明可能であるため,その存在を疑わしめたためである.しかしながら人工透析が確実な腎不全の治療手段として定着するにつれ,uremic toxinの存在を疑わしめる事実が明らかになり,この研究は再び新鮮なリサーチテーマとなってきた.それは,①透析により滲透圧異常,電解質異常,酸塩基平衡異常などを是正しても改善しない症状(脳波所見,高血圧の一部,耐糖能低下,抗体産生能低下,細胞性免疫能の低下,貧血,出血傾向,骨代謝異常)がある.②血液透析例と腹膜透析例で,透析される物質の膜透過性の相違によると思われる症状の違いがある.③血液透析の週あたり頻度や透析時間,面積の相違による分子量別クリアランス曲線の違いが,やはり症状(末梢神経伝導障害など)の深さと関連するなどである.
雑誌目次
medicina13巻4号
1976年04月発行
雑誌目次
今月の主題 腎不全の病態と治療
理解のための10題
ページ範囲:P.526 - P.528
トピックス
活性型ビタミンD—その血清レベルの測定法の現状
著者: 大原憲一 , 大野丞二 , 須田立雄
ページ範囲:P.446 - P.448
はじめに
高等動物の血清Caレベルの恒常性は副甲状腺ホルモン(PTH),カルチトニン,およびビタミンDによって維持されている.近年,ビタミンDの代謝に関する研究が急速に進歩し,ビタミンDがその標的器官である十二指腸および骨組織で活性を発現するためには,まず肝臓でD3分子の側鎖にある25位の炭素が水酸化されて25-hydroxyvitamin D3〔25-OH-D3〕となり,続いて腎臓でA環の1α位の炭素が水酸化されて1α,25dihydroxyvitamin D3〔1α,25-(OH)2-D3〕に代謝されてから活性を発現することが明らかにされた(図1参照).その結果,腎臓から分泌されたこの1α,25-(OH)2-D3は標的器官の細胞のクロマチンに存在するリセプターに結合し,ビタミンD3の活性発現に必要な蛋白質の合成を促進する.このことは臨床的にも極めて重要な意味を持っており,慢性腎不全患者や抗痙攣剤を長期間服用している患者にしばしばみられるCa代謝異常と肝,腎におけるビタミンD3の活性化障害とを関連づけて考える必要がある.これらの疾患におけるCa代謝異常を正しく診断するためには,血中25-OH-D3および1α,25-(OH)2-D3のレベルを測定することが重要であるのはいうまでもない.
腎不全の成因
急性腎不全の成因と予後
著者: 小出桂三
ページ範囲:P.450 - P.452
急性腎不全とは,急激に現れた乏尿または無尿,腎機能の脱落,尿毒症などを主なる徴候とする症候群をいう.しかし,ごくまれに乏尿がない場合(非乏尿性急性腎不全)もある.
糸球体腎炎の組織分類(カラーグラフ)
著者: 三條貞三
ページ範囲:P.454 - P.455
糸球体腎炎の組織分類は微小変化群,膜性,および増殖型,局所型の4型に大別され,このうち増殖型はさらに,メサンギウム増殖型,管外型(半月形成型),膜性増殖型,メサンギウム肥厚型,硬化型の5型に区別される.このうちメサンギウム肥厚型は,軽度のものは微小変化群に,中等度のものはメサンギウム増殖型に含まれる場合が多い.
糸球体腎炎の病型と予後
著者: 三條貞三
ページ範囲:P.458 - P.459
現在まで糸球体腎炎の病型は病因,組織病変,臨床像などから分類が試みられてきたが,いずれも予後を推定するに十分なものではない.これら分類法の中で,組織病変は,その多彩な成因や症状にもかかわらず,しばしば組織病変特有の経過をとり,数年後の組織像でも幾分硬化病巣の増加する以外,ほとんど変わらない1,2).このことから,組織像に基づく腎炎の分類が最も重視されてきている.とくに光顕像以外,電子顕微鏡や螢光抗体法の適用によって組織分類も細分化され,予後との関係も一層明らかになってきている.
DICと急性腎不全
著者: 安部英
ページ範囲:P.460 - P.461
最近DIC(disseminated intravascular coagulation syndrome 汎血管内凝固症候群,あるいは脱フィブリン症候群 defibrination syndrome,消耗性凝固障害症 consumption coagulopathyともいう)が臨床各科の領域で注目されるに及んで,腎障害ことに腎不全の発症機転にこの現象の関与することが想定されるようになった.
確かに次に提示する敗血症の症例をはじめ,Shwartzman-Sanarelli現象,Waterhouse-Friderichsen症候群,Goodpasture症候群,エンドトキシン・ショック,火傷,電撃症,胎盤早期剥離,羊水塞栓,死胎子宮内停留,白血病ほか各種悪性腫瘍ことにそれの全身性転移時,蛇咬傷,薬物中毒症,異型輸血などで明らかに本症候群を呈する症例で,またいわゆる細小血管障害性溶血性貧血(microangiopathic hemolytic anemia:MHA)ないし溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome:HUS),血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic thrombopenic purpura:TTP),血栓性細小血管症(thrombotic microangiopathy)の症例で,さらには全身性,局所性エリテマトーデス(SLE,discoidal lupus erythematodes),結節性動脈周囲炎,強皮症,Wegener肉芽腫などの各種膠原病患者でDIC様症候群を示す場合に,しばしば腎障害をおこし,乏尿無尿の急性腎不全症状を呈する症例の多いことから,このDICと急性腎不全との間には何らかの発生病理学的ないし病態生理学的な関連のあることが想定される.以下,①果たしてDICが腎不全をひきおこすか,②もしおこすとすればそれはどんな機序によるか,③この場合の腎障害にはよく赤血球の溶血が論議されるが,果たしてそれがこの病変の主体であるか,④この溶血はDICと如何なる関係をもつかなど,誌面の限り考えてみたい.
糖尿病と腎不全
著者: 土屋尚義
ページ範囲:P.462 - P.463
糖尿病性腎症は,臨床的に蛋白尿を指標とすれば全糖尿病症例の約20〜30%,生検例で約65〜90%と高頻度にみられる合併症である.しかも,原疾患の予後を左右する重要な因子をなし,死因統計上,従来の昏睡や感染症に代わって近年著しく増加した血管障害死の中で,腎死は全症例の約15〜20%と重要な地位を占めている.腎症は,糖尿病の罹病期間の延長とともに発症,緩徐ながら進行して,やがては腎不全に陥る症例がしばしばである.
腎症の病理組織学的変化は,びまん性および結節性糸球体硬化像を基本病変とし,多くの例で相関して細動脈性腎硬化症を伴う1).したがって,まずこの基本病変の成因について記し,次いで経過中にしばしば挿入され,付加的に腎障害を進行・悪化させる要因について述べることにする.
代謝面からみた病態
糖代謝
著者: 中川成之輔 , 東海林隆男 , 笹岡拓雄
ページ範囲:P.464 - P.466
腎不全の糖代謝異常は,1910年代から知られた事実である.その原因はいくつかあげられてきた.主要なものは,①インスリン分泌異常,②末梢におけるインスリン感受性の低下,③インスリン拮抗物質(=uremic toxin),④肝におけるgluconeogenesisの異常,⑤growth hormone(GH),⑥高脂血症(Fredrickson分類第IV型)などである.①および④を主たる病因とする立場をとる学者は少なく,むしろ否定的になっているといってもよい.②はおおむね肯定されている.その他の項目は論議されている段階である.
腎不全が進行し,末期に達すると透析に移行され,病態生理学的修復をうける,糖代謝異常の改善が安定するまでの期間は,報告者によって異なり,一致した見解はない.筆者らは多くの病態生理学的修復が成立する時期に応じて,透析開始以後の病期区分を行いうると考えて,いくつかの指標について検討を行っており,糖代謝異常が安定するには6カ月を要すると考えているが,短いところでは,Hampers1)が2週とし,わが国の報告者で12ヵ月以上とするものもある.
脂質代謝
著者: 和田光夫
ページ範囲:P.467 - P.469
血清脂質およびリポ蛋白質代謝の概要
血清脂質の基本成分である脂肪酸は,アセチルCoAとマロニルCoAの反復縮合反応によって生成される.コレステロールの基本骨格,ステリン核はアセチルCoAからヒドロキシメチル・グルタリル(HMG)CoA,メバロン酸,スクワレンなどを経て形成され,その生合成は,血中低比重リポ蛋白質(LDL,電気泳動法のβリポ蛋白質)がHMG CoA reductaseを抑制する機序によって調節される.コレステロールのエステル化は,高比重リポ蛋白質(HDL)を反応の場としてレシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(LCAT)によって行われる.血清トリグリセリド(TG)は,脂肪酸と解糖に由来するα-グリセロ燐酸とのエステル形成反応によって,肝において生成される.合成あるいはとり込みによって肝細胞に入った脂質は,肝内合成された蛋白質(アポ蛋白質)とともに,リポ蛋白質として組み立てられ,Golgi装置に集積されたのちに血流中に分泌される.すべての脂質はリポ蛋白質として血液中に存在し,その形で代謝される.
アミノ酸代謝
著者: 川口俊介 , 前田憲志 , 斉藤明 , 小林快三
ページ範囲:P.470 - P.471
腎不全における蛋白アミノ酸代謝の特徴は,ひとつには,腎不全そのものの病態と密接に関連づけられるものと,他方,protein malnutritionの一症候にすぎないものとがある.前者としては,①腎組織の荒廃による酵素活性の低下,②尿中アミノ酸排泄異常,③腸管内吸収障害,④Insulin,growth hormoneに対するantagonismの存在,⑤尿素を初めとする種々のN含有物質の蓄積,⑥catabolismの亢進などが考えられている.後者のprotein malnutritionは,腎不全時に投与される低蛋白食と食思不振により惹起されるものであるが,従来のアミノ酸代謝異常の報告の多くが,この因子を腎不全固有の特徴であるかのように錯覚しすぎたきらいがある.また一方,現在までのアミノ酸代謝の解析は,主として血漿中のアミノ酸パターンの解析にすぎず,いわばアミノ酸の動的平衡の一断面をみているにすぎない.これに対し,Bergstromら1)は,より大きなアミノ酸プールである細胞内変化に注目して,さらに動的に代謝異常を把握しようとしている.以上のことを考慮し,腎不全時の蛋白-アミノ酸代謝について述べていきたい.
酸塩基平衡
著者: 浦壁重治 , 折田義正 , 湯浅繁一
ページ範囲:P.472 - P.473
腎不全時の酸塩基平衡障害
通常,生体内では1日50〜100mEqの水素イオン(H+)が代謝によって生じ,これを緩衝するためにHCO3-が消費される.このため腎では糸球体濾過をうけたHCO3-を完全に再吸収し,その喪失を防いでいるが,さらに腎は積極的にH+,NH3を分泌し,上記のH+を処理して消費されたHCO3-を回収,滴定酸(主としてNaH2PO4),アンモニウムイオン(NH4+)の形で50〜100mEqのH+を排泄し,酸塩基平衡を維持している(図1).
腎病変が進行し,糸球体濾過値(GFR)が25ml/min以下になると,一般に血漿HCO3-濃度が低下し始め,代謝性アシドーシスをきたすようになる.これはGFRの減少により,生体内で産生された硫酸塩,燐酸塩の濾過量が減少し,HCO3-の回収がその分だけ行われなくなるためである.このように,腎不全のアシドーシスは主として糸球体障害によるもので,retention acidosisとも呼ばれ,〔Na+〕-(〔C1-〕+〔HCO3-〕)で求められるanion gapの増加が特徴的である(図2)1).
カルシウム代謝
著者: 大野丞二 , 大原憲一
ページ範囲:P.474 - P.475
慢性腎不全患者に骨変化をきたすことは古くから知られている.最近,血液透析の普及に伴い,慢性腎不全患者の長期間生存が可能となってきており,腎不全時のCa代謝異常の問題はますますその重要性を増している.ヒトの血清Caレベルは主に副甲状腺ホルモン(PTH),ビタミンDそれにカルチトニンにより厳密に維持されている.そして腎不全時においてはPTH,ビタミンDがその中心的役割をはたしている(図1).近年,ビタミンDの代謝に関する研究は目ざましいものがあり,ビタミンD3の最終活性産物や,そのanalogの合成も可能となり,それらの臨床応用も始められてきている.
臓器面からみた臨床像
中枢神経
著者: 宮原正 , 平山隆勇 , 豊原敬三
ページ範囲:P.476 - P.477
中枢神経症状は,尿毒症における重要な臨床症状のひとつで,慢性腎炎の際にみられる脳症状についての最初の報告は,1839年,Addisonによって行われた.その後,Baker and Knutson,SchreinerあるいはTylerその他の研究者により尿毒症の精神神経症状について詳細な報告が行われたのは今世紀半ば以後である.
透析療法施行前の時代と普及後とでは,尿毒症の臨床症状に明らかな相違がみられる.透析が治療法として行われる以前の尿毒症患者には,多彩な精神神経症状が認められているが,ほぼ1962〜3年頃から,すなわち,透析が広く行われるようになってから様相が一変した.当初は不十分な透析下の延命のために精神神経症状がかえって高頻度にみられたが,透析方法の改善の結果,かつてみられたような症状に遭遇するchanceはごく稀になった.したがって,今日ではuremic encephalopathyが透析を行っていない尿毒症例にみられることは昔と変わりないが,適当な時期に透析が行われるので,高度の中枢神経症状を呈することは少ない.このように,透析により尿毒症症状の顕著な改善,生存期間の延長,さらには多数の社会復帰例がみられているが,逆に透析により惹起する,しかも上述のuremic encephalopathyと異なった中枢神経症状が認められている.
尿毒症性末梢神経障害
著者: 北岡建樹
ページ範囲:P.478 - P.479
尿毒症性末梢神経障害は,末期腎不全の経過中に認められる全身的な一症候である.これは19世紀末より臨床的に認識されていたようであるが,1961年にMarin,Hegstromらにより詳細な報告がなされて以後,透析療法および腎移植法の進歩に伴って,にわかに注目されるようになった.この神経障害の有無が透析療法開始の適応基準として,透析量適正化の指標として,さらには尿毒症性物質探索の糸口として論議されるようになり,この病態の解明は急速に進歩した.とくに慢性透析患者においては,骨代謝障害とならんでこの神経障害は治癒しにくい合併症とされ,患者の社会復帰の面からもその対策が望まれる.
高血圧
著者: 藤見惺
ページ範囲:P.480 - P.481
高血圧は慢性腎不全の病因であるのみならず,その合併症として末期腎不全のほとんど全例に認められる1).高血圧は,腎機能障害をさらに助長させる因子として腎不全患者管理上,極めて重要な病態であるが,腎以外の心・血管系にも重篤な合併症をもたらす.透析療法が発達し,尿毒症による死亡が減少した今日では,高血圧は慢性腎不全の予後を規定する最大の因子と考えられる.さらに最近では長期透析患者に進行性動脈硬化性病変が認められ問題となっている2).以上の知見からみて,慢性腎不全に伴う高血圧はコントロールされるべき病態である.本稿では両側性腎実質性障害による末期腎不全に伴う高血圧の病態生理および治療につき私見を述べる.
心膜炎
著者: 黒田満彦
ページ範囲:P.482 - P.483
心膜炎は尿毒症でしばしば遭遇する合併症であり,Brightの記載以来すでに140年になるが,治療法の進歩した最近でも慢性透析者の心タンポナーデによる死亡順位は高い1).心膜炎は未治療の尿毒症例の約半数2,3)に認められるだけでなく,安定期にある慢性透析者にも10〜16%2〜4)程度に発現している.とくに慢性透析者にみられる心膜炎が問題であるが,その発症要因や透析療法との関係など不明の点が少なくない.また,心タンポナーデは心膜炎の重大な転帰であるが,その治療方針には最近までかなりの混乱があり,高い死亡率の一因であったとも考えられる.最近の文献は治療の問題を扱つたものが多く5〜7),治療に一定の方向が得られつつある.
貧血
著者: 野村武夫
ページ範囲:P.484 - P.485
慢性腎不全には,ほとんど例外なく貧血が合併する.貧血は,GFRが正常の30%以下に低下すると現れ,BUNや血清クレアチニン値が上昇するにつれて高度になり,ヘマトクリットとBUNの間には,ある程度の逆相関が認められる1).腎不全の貧血は正色素性正球性で,白血球数と血小板数には目立った変化がないのが普通である.
出血
著者: 青木延雄
ページ範囲:P.486 - P.487
尿毒症を呈する急性および慢性腎不全患者の約半数近くに,出血傾向がみられる.症状は,軽重さまざまであり,軽度の紫斑の出現から,胃腸管あるいは中枢神経系の重篤な出血がみられる.急性腎不全の6%は出血死によるものとの報告がある.
内分泌機能
著者: 長谷川弘一 , 森井浩世
ページ範囲:P.488 - P.490
慢性腎不全患者において,内分泌機能異常に関連すると思われる種々な症候が知られている.これらは患者の生命に直接影響をもたらすような合併症ではないが,患者の精神的,社会的な面に大きな影響をおよぼすことが考えられる.そこで慢性腎不全患者,とくに血液透析中の患者における内分泌機能異常について検討した.
免疫機能
著者: 伊東義一 , 平安山英機
ページ範囲:P.492 - P.493
慢性腎不全の原因疾患は多いが,これらのうち慢性腎炎,lupus腎炎,amyloid腎症などでその発症および進展に免疫機序が関与することはよく知られている.
慢性腎不全の治療として広く行われるようになった腎移植では,その成功のカギは移植腎の拒否反応をいかに防止するかにかかっている.さらに他のひとつの治療法として広く行われている血液透析により,尿毒症の死亡率は著しい減少を示している.しかし近年,抗生剤の進歩と正しい使用法の確立によって激減した感染症による死亡が,腎不全においては未だ多く,腎不全死亡例の約20%,死因としては第2位をしめている.このようなことから,第11回人工透析研究会において,透析療法における感染症が主題として取り上げられている.ここにおいては,結核の再燃や弱毒菌による敗血症などが報告され,その討論を通じて透析患者における免疫機能の低下という問題が,改めて大きな注目をあつめた.
小児と高齢者の腎不全
小児
著者: 伊藤拓 , 川村猛
ページ範囲:P.494 - P.495
最近の医療の進歩に伴い,小児腎不全治療においても諸種薬剤,食事療法の進歩,人工透析,腎移植術の導入により,患児の完全社会復帰への期待を持つことが可能となり,その早期発見,早期治療の意義が再認識されてきている.すなわち,このような患児を最初に診療する機会の多い第一線臨床医の方々の適切な診断,処置がその予後を左右するといっても過言ではなかろう.そこでこのような場合に,なんらかの参考にしていただくことを目的として,小児腎不全臨床の概要を述べてみたい.
高齢者
著者: 古山隆
ページ範囲:P.496 - P.497
腎機能は,40歳を境に次第に低下の傾向をたどるといわれている.これはおそらく,血管系の加齢による変化に伴うネフロンの減少が原因と考えられる.高齢者における腎機能の特徴は,一言でいえば調節幅の減少と表現することができる.したがって,高齢者では,若年者では大したこともなく通り抜けられる侵襲に耐えられないし,また,水・Naの処理が十分にできず心不全に陥ることもある.さらに,腎以外の器官,とくに心・肺系にも加齢による変化が存在するから,腎との間に悪循環が成立する危険もある.
治療
抗生剤の使い方
著者: 斎藤篤
ページ範囲:P.498 - P.499
抗生剤の体外への排泄経路には腎性および腎外性があるが,とりわけ腎を介しての排泄が最も重要なことはいうまでもない.
したがって,腎不全患者に抗生剤療法を実施する場合,通常つぎの2点が問題となる.第1は高い血中濃度が長時間持続するために,無計画な連用により副作用(毒性)が出現しやすくなることであり,第2は副作用を恐れるあまりに,薬効の得られない少量程度にしか使用されないことである.
食事療法
著者: 三村信英
ページ範囲:P.500 - P.501
腎不全の食事療法は,人工透析療法の進歩と普及により,透析療法を頻回に行い,食事療法を緩和する方向にある.極端な場合には自由食を主張するものさえある.しかし,腎不全の食事療法を考える場合には,腎の病態生理および透析療法の方法,効率などが考慮されて実施されるべきである.
急性腎不全では早期に,積極的に予防的透析療法を実施することが良いとされているため,原疾患にさしつかえない限りは,全身状態の改善を主体とした食事療法を行い,透析療法の効率と回数の増加によって腎不全状態をコントロールすることである.これが予後を良好にする最大の手段である.
透析療法の現況と将来
著者: 平沢由平
ページ範囲:P.502 - P.504
本邦でも,慢性腎不全に対する透析療法の歴史は10年に近づき,透析者数は全国ですでに15,000名に達し,治療施設もほとんどの都市には存在するようになり,今や透析治療は全くルーチンのものになった.このような普及は,10年前には予想もできないことであったし,近年の普及速度は先進諸国の中でも1,2を争うものであった.これを支えたものは透析医学の間断なき進歩であるが,医療保険制度の適用も大きな役割を果たしてきたことは事実である.この治療が一応の成果をあげ,その結果として巨大化するにつれ,重要な医学的,社会的問題を提起することになってきていることは周知の通りである.医療人として考えるとき,医学的にもっと満足のゆく治療に仕上げることがまず必要であり,また,社会事情により適した透析医療の制度を確立してゆくことも急務と思われる.
家庭透析の現況と対策
著者: 上田泰 , 川口良人 , 酒井聰一 , 小板橋毅
ページ範囲:P.506 - P.508
家庭透析home dialysisが初めて試みられたのは,1963年(Boston)1),次いで1964年(Seattle,London)2)であるが,今日では腎移植と並んで慢性腎不全患者の社会復帰の積極的な手段として注目され,その地位は確立されつつある(図1).
わが国においては,透析療法が導入されて10年余経過した今日においても,家庭透析は普及せず,1975年6月現在,総透析患者数11658名に対して家庭透析患者数は94名にすぎず3),米国の30%,ヨーロッパの18.5%4)に比較して著しく遅れが目立っている.
透析患者の管理
著者: 酒井糾
ページ範囲:P.509 - P.511
近年,透析療法の進歩は,社会復帰率の高い一般壮青年の腎不全患者のみならず,幼小児,主婦,老人の腎不全患者にとっても大きな福音となりつつあるが,ともすれば延命効果を期待するだけにとどまり,多くの社会問題を生む結果ともなっている.かかる問題を解決していくには,一方において腎不全患者を減らすために現在治療中の患者のretrospective studyを行い,今後の腎疾患管理,すなわちmedical careを徹底させる上に役立て,"攻めの治療"を行うとともに,ひいては腎不全の予防策を積極的に講じていくことも必要となろう.
本稿にあっては,透析患者の管理とその問題点(合併症,死因,社会復帰)について,簡単に述べる.
移植の現況と将来
著者: 太田和夫
ページ範囲:P.513 - P.515
腎移植を支える3本の柱は,いうまでもなく免疫抑制法,組織適合性検査法,ならびに臓器保存法の研究であろう.これらの研究の現況と,臨床への応用を中心に述べる.
座談会
腎不全における治療の現状と問題点
著者: 三村信英 , 平沢由平 , 越川昭三
ページ範囲:P.516 - P.524
透析が始まってからほぼ10年,それによってもたらされた恩恵には測りしれないものがある.一方,未解決の問題,新しく起こりつつある問題も多い.透析の歴史と歩みを共にされた先生方に,問題点の所在と,その展望について語っていただいた.
--------------------
内科専門医を志す人に・トレーニング3題
著者: 安部井徹 , 宮崎元滋 , 村中日出夫
ページ範囲:P.557 - P.559
問題1.Rotor型過ビリルビン血症のBSP代謝について正しいものはどれか.
A:45分で血中停滞率は正常となるが,120分位で再上昇する.
内科専門医を志す人に・私のプロトコール
内分泌・代謝
著者: 革島恒徳 , 梅村康順
ページ範囲:P.560 - P.561
今月は,内分泌・代謝疾患5例の中から,特発性副甲状膿機能低下症の1例を供覧する.昭和46年に経験した症例であり,Ca代謝に注目して検査を進めた.副甲状腺機能検査は,測定の比較的容易な,血清Ca・P・クレァチニン,尿中Ca・Pを用いて,Ca代謝を動的に把握する方法を用いて行った.これらの検査にも限界があり,十分に考慮して判定しなければならなかった.本例にCa負荷試験,EDTA試験,Ellsworth-Howard testを行い,特発性副甲状腺機能低下症が疑われ,低Ca血症を呈する,偽性副甲状腺機能低下症,腸からのCa吸収不足の腸吸収不良症候群,腎からのCa排泄の増加をきたす細尿管性アシドーシス,Caイオンの消費をもたらす急性膵炎などの臨床症状および検査成績で除外診断を行った.最近,より正確な鑑別には,PTH負荷後の尿中サイクリックAMPの測定が行われている.
Ca代謝をつかさどるホルモンとして,PTH,カルチトニン,活性型ビタミンDがあり,PTHの測定も可能となり,近年,新しい知見が増え,また,各種ホルモンのradioimrnunoassayの測定可能により,正しい理解を持っていることが要求される.
心臓病診断へのアプローチ—問診を中心に
問診の価値
著者: 石川恭三 , 広木忠行 , 前田如矢
ページ範囲:P.562 - P.568
高度の診断手技を用いなくても,聴診器と簡単な診察でかなり正確に心臓病の診断はできるものである.そのためには一定の順序に従って診察するという習慣を身につけておくことが必要である.問診,理学的所見,検査所見などを綜合して初診時診断を下すわけであるが,とりわけ問診の仕方の上手・下手により診断の正確度が左右される.そこで,問診を中心とした心臓病診断へのアプローチの実際について鼎談を企画した.
演習・X線診断学 消化管X線写真による読影のコツ・4
二重造影法について
著者: 熊倉賢二 , 杉野吉則
ページ範囲:P.569 - P.574
消化管のX線診断は,単に撮影された写真の読影だけではすまされません.それよりも,病変が忠実にあらわれている写真をとることの方がもっと重要です.よい写真さえとれれば,診断は非常に容易になってしまうからです,それに反して,目的意識もなく慢然とX線検査をすませ,あとになって撮影した写頁を読影しようといくら一所懸命になって議論してみても,そんな写真には病変がほとんど写っていないのが普通ですから,まったく無理な話です.しかし,これは日常よくみかける風景です.読影に苦心するよりも,再険査をするなり,内視鏡検査をすべきでしょう.または,検査の失敗とみなして,検査法の検討をした方が得策でしょう.したがって,"消化管X線写真による読影のコツ"というタイトルは適切ではありません."消化管X線検査のコツ"とした方がよいでしょうこのことはぜひ忘れないで頂きたいものです.
このようなことがあるので,X線検査が終わったら,検査が十分にできたかどうか,盲点がないかどうかを検討する必要があります.また,読影にあたっては,この写真はよい写真かどうか,どの程度の病変ならあらわれる写真であるかといった検討も必要です.このような写真のでき具合の判定をしたうえで読影をしないと,大きな誤診の原因になってしまいます.前に述べたように,遠隔操作式X線TV装置でとった写真は鮮鋭度が非常にわるくなっていますから,その点は十分に考えに入れておいて下さい.
診断基準とその使い方
肝癌
著者: 遠藤康夫
ページ範囲:P.530 - P.533
肝癌,とくに原発性肝癌を主体とした診断基準を下記に示す.以下,この診断基準にある各項目に沿って,肝癌と類縁疾患との鑑別診断を日常診療に際して行うにあたり,どのような点に留意したらよいかを述べていきたい.
ベーチェット病診断基準試案
著者: 吉田赳夫
ページ範囲:P.534 - P.535
はじめに
1937年より1938年にかけて,イスタンブール大学皮膚科教授のHulusi Behçet氏は,3つの症状をそろい持った症候群を報告し,1つの疾患単位とすることを提唱した.これは,口腔内の数個のアフタと,陰部の潰瘍と眼の虹彩炎とから成り,これらが,幾年もの間,くり返し出没し,慢性の経過をとるというのであった.その後,多数の類似症例の報告があり,その異同,分類などにつき議論されたが,その原因は未詳である.ただ,これを1つの疾患として認めてゆくうちに,この症候群を呈するものの中に,同時に内臓諸臓器もまた,侵されるものが多くあることが知られてきた.そして今日では,ベーチェット病とは,全身性の多系統的疾患で,発作性に再発と増悪をくり返し,病理学的には血管病変,血管炎が共通して認められるものである,と考えられている.
図解病態のしくみ
肝炎慢性化の機序・2—肝線維化を中心に
著者: 亀谷麒与隆 , 丸山勝也 , 船津和夫
ページ範囲:P.536 - P.537
肝炎慢性化の機序につき,前回は,肝炎ウイルスと宿主の免疫能を中心に持続性肝細胞障害の機序につき述べたが,今回は慢性化のもうひとつの要因である肝の線維化,すなわち結合織増生が肝炎慢性化にどのような役割を果たしているかにつき検討してみることとする.
肝においては瘢痕の形成・線維性隔壁の形成が肝内循環障害を助長し,さらに肝細胞周囲の線維化と,それに伴う類洞の毛細血管への変貌は肝内血流の短絡など肝内微小循環系の異常を惹起して,肝細胞への著しい血流減少とともに血液-肝細胞間の物質交換の阻害を招き,その結果,肝細胞傷害は増悪し,線維化はさらに進行するという一種の悪循環に陥り,肝傷害が進展すると考えられる.このように類洞の毛細血管化,すなわち類洞直下の基底膜の形成は,肝炎の慢性化さらには肝炎の進行の重要な因子と考えられ,したがって基底膜形成の機序を知ることは肝炎慢性化の機序を窺う上に重要である.そこでここでは,実験的ラット肝線維症をモデルとした基底膜形成過程について,基底膜の形成に密接な関係があるcollagen fiberと酸性ムコ多糖の変化をとくに基底膜形成のみられるDisse腔付近において観察した所見と,それらの分解酵素であるlysosome酵素およびcollagenaseの活性の推移とを比較して述べる.
新薬の使い分け
経口糖尿病薬
著者: 堀内光
ページ範囲:P.538 - P.539
スルフォニール尿素剤,ビグアナイド剤が用いられるようになって,これらの薬剤を経口糖尿病薬,経口糖尿病用剤,経口血糖降下剤などと呼んでいる.経口投与によって糖尿病の治療に役立てようとして1955年以来用いられてきたが,未だこれらの薬剤の作用機序は十分に解明されたとはいえない.糖尿病患者の血糖値を低下させることは認められるが,これが長期に糖尿病のすべての病態を改善に導くというには困難である.本剤の適応例の選定,糖尿病病態に対する効果の判定など慎重に検討しなければならない問題を残している.
臨床病理医はこう読む 酵素検査・2
アルカリ性フォスファターゼ
著者: 玄番昭夫
ページ範囲:P.540 - P.541
アルカリ性フォスファターゼの異常高値
症例1,2はともに異常に高い血清アルカリ性フォスファターゼ活性を示しているが,このようにアルカリ性フォスファターゼ値が高くなる場合は,次のように非常に多い.
1)肝胆道疾患
小児と隣接領域
小児期に問題となる重要な尿路系疾患
著者: 大田黒和生
ページ範囲:P.542 - P.543
反復性尿路感染症
高熱と膿尿をみた場合,急性腎盂腎炎と診断するが,抗生物質の投与により下熱したにもかかわらず,膿尿改善せず,高熱発作を反覆する時には,徒らに尿中細菌の感性な薬剤を求め,各種抗生物質をくりかえし投与することを止め,尿路系になんらかの異常,ことに,尿のうっ滞,残尿の存在,尿流通過障害の有無を追求すべきである.このような症例の60〜80%に尿路系異常が発見されている事実を思い浮べてほしい,まず,行うべき検査としては,腎膀胱部単純撮影と,静脈性腎盂撮影である.造影剤(0.5〜1.0cc/kg)静注後,3,6,10分の3回撮影し,急速現像でみた結果により,必要に応じ造影剤の再度の静注(片側尿路系のうっ滞ある時),あるいは単に30,60,90分と撮影を続けてゆく.4歳以上であれば30,60分撮影後に排尿せしめ,その直後に再度撮影する.学童男児であれば斜位をとらせ,排出中の撮影を行うこともある.以上により,腎の形態,位置,尿管走行,膀胱形態,逆流現象,残尿の有無,下部尿路通過異常などを知ることが可能である.一番重要なことは腎盂・尿管,または尿管・膀胱移行部の通過障害に基づく水腎症,水腎水尿管症の発見である.早期,ことに1歳前後の乳児期に根治的な形成術が施行されると,腎機能の廃絶を予防せしめることが可能である.10歳以上まで放置されると腎形態の異常と腎機能の低下は不可逆的となる.
皮膚病変と内科疾患
皮膚の増殖性病変と内的異常(その2)
著者: 三浦修
ページ範囲:P.544 - P.545
色素細胞の増殖 本型は色素母斑または悪性黒色腫を意味し,色素斑をなすもの,丘疹や結節となるもの,腫瘤を形成するものなどがある.
正常色素細胞の増殖 獣皮様色素母斑または広範囲の色素母斑は若年時に悪性黒色腫に変ずることがあり,稀には軟脳膜にも色素細胞増殖を伴う例や水頭症の併発も知られている.
ECG読解のポイント
チアノーゼのある4歳男児の例
著者: 中尾聰子 , 太田怜
ページ範囲:P.546 - P.548
患者 4歳7ヵ月の男児
現病歴 母親33歳の時の初産で出生(帝王切開),生下時体重2260g,生後2ヵ月で無酸素発作1回,その時先天性心疾患と診断されています.その後発作なく,1歳4ヵ月で歩き始め,現在6ヵ月に1回の定期診断は受けていますが,服薬はしておりません.
外来診療・ここが聞きたい
開業医学入門
意外に多い甲状腺疾患(その2)
著者: 柴田一郎
ページ範囲:P.552 - P.556
前回には,私たちの一般内科診療所でも,甲状腺疾患の頻度は多いということ,みつけ方などについて強調したつもりであるが,甲状腺腫というものは,いくつもの病気があって,なんとなく分りにくいもの,煩雑で専門家でなければ分らないものという観念がまだまだ残っているように思われる.しかし,現在ではその分類も明確になり,分かりやすくなったし,特殊な病院でなくとも,ある程度までは見当をつけることが可能であり,どんなものを専門医に回すべきかの判断もできるようになってきた.ことに甲状腺癌は,その大部分(90%)が予後の良い癌であるとはいえ,手遅れにしてしまったのでは死亡を免れ得ない.したがって私たちは,どの患者についても常に頸部触診を怠らないようにしたい.甲状腺の病気には,主として形態学的な立場からしか診断のつけられないもの,つまり機能異常とはあまり関係のないものと,甲状腺ホルモンを主とした血液化学的諸検査,すなわち機能面の検索から診断のつく疾患群とがある.後者の疾患群のばあいさらに形態的な面をからませてゆけば,ほぼその全貌をつかむことができよう.以下,その概略を述べたいと思うが,私たちの設備ではできない検査,たとえば131I-uptake,超音波による検査,最近視床下部から発見されたTRH(Thyrotropin Releasing Hormone)に関する検査は専門家に依頼するというたて前で触れないこととする.
オスラー博士の生涯・37
講演「25年後に」(その2)
著者: 日野原重明
ページ範囲:P.577 - P.579
オスラーは1899年9月21日に母校マギル大学に招かれて「25年後に」と題する講演を行った.その際,彼は,医学原論という名の講義の中で,病理解剖や病理組織,さらには臨床内科にも橋渡しをする広範囲な領域にわたって講義をやらされ,あまりに範囲が広すぎて雑駁になり,自分でも自信をなくしていた.ちようどその時,ペンシルバニア大学から内科教授の声がかかった.それを受ける気持ちになったのは,今までよりも狭く深くつっこめる医学の分野をひき受けたいという心からだった,と述べている.
私の失敗例・忘れられない患者
"原点"を忘れぬことの大切さ
著者: 渡辺亮
ページ範囲:P.583 - P.583
最近の診断技術の向上はめざましいが,一面,私ども一般医の所へ来院する患者の80%が,問診,触.打・聴・視診で確診でき,したがって,いわゆる理学的検査の重要性や問診のむずかしさは,現代でも少しも低下していないのではないかと思う.たとえば次の例だが…….
55歳の会社員,晩婚のため,12歳の中学生の男子1人があり,87歳の老母,53歳の妻と4名の家族暮し.定年退職後,子会社に移ったが,会社が倒産し,再び転職を余儀なくされた.再転職後,激しい心身の過労が続き,不規則な食生活,睡眠不足のため,胃痛の出没,便秘,胸やけ,下痢などが続いた.大学病院内科で胃腸レントゲンの精査を受け,さらに神経科に転科後,神経症として投薬を受けているうち,便秘,身体のふらつき,左下腹膨満感が出現してきた.この時点で,一般医である私の所に相談に来院した.
診療相談室
急性,慢性膵炎の診断基準について
著者: 内藤聖二
ページ範囲:P.580 - P.581
質問 急性,慢性膵炎の診断基準,および反復性急性膵炎の治療方針についてご教示ください,また,血中アミラーゼ高値持続時期に,P・Sテストを施行してよいでしょうか. (神戸市 TK生)
洋書紹介
—R. H. Salter 著—Common Medical Emergencies A Guide for Junior Physicians, 2nd Ed.
著者: 宮川隆
ページ範囲:P.466 - P.466
研修医向けの救急入門書
内科研修を行うさいには,経過の緩慢な疾患ばかりでなく,急激に進行し,内科的あるいは外科的処置を必要とする救急疾患の診療に習熟しなければならない.このような患者の救命には一刻を争うので,あらかじめ救急処置を要する疾患について勉強しておくとともに,診療の手引きとして座右に備えておく書物が必要である.
本書は16章から成り,1)心筋硬塞,2)心拍停止,3)急性左心不全,4)深部静脈血栓症,5)肺塞栓症,6)自然気胸,7)気管支喘息,8)慢性気管支炎の急性感染による増悪,9)くも膜下出血,10)脳卒中(脳出血と脳硬塞),11)一時的無意識(失神,低血糖,てんかんなど),12)初老者の突然の錯乱,13)急性中毒(バルビツール酸中毒,ベンゾジアゼピン,サリチル酸中毒,および三環式抗うつ病薬),14)急性胃腸出血(食道静脈瘤出血を含む),15)糖尿病性ケトアシドーシス(高滲透圧性非ケトン性糖尿病昏睡を含む),および 16)低血糖の項目について,おのおの,原因,臨床症状,診断(鑑別診断),合併症および治療について,わかりやすく,実際の診療に役立つよう書かれた160頁ほどの小冊子である.
基本情報
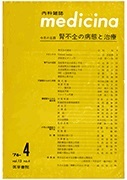
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
