はじめに
DICは以下のごとく理解されよう.
1)種々の原因による凝固系の持続的賦活:外因系では組織トロンボプラスチンにより,内因系は第XII因子の活性化により凝固が開始し,最終的にはトロンビンの持続的生成に至る.
雑誌目次
medicina14巻6号
1977年06月発行
雑誌目次
今月の主題 DICとその周辺
理解のための10題
ページ範囲:P.863 - P.865
血管内凝固の成因
DICの成因と基礎疾患
著者: 青木延雄 , 吉田信彦
ページ範囲:P.798 - P.799
血流の病態生理
著者: 磯貝行秀
ページ範囲:P.800 - P.803
はじめに
細小血管における微小血栓の多発はDICを惹起してくるが,凝固発動の機序は多様であり,一概に論ずることはできない.基本的には循環血中へのトロンビンの出現と血管閉塞が重要である.両者いずれも引き金的要因として,①細小血管内皮細胞の傷害(Hageman因子の活性化:内因性凝固機序およびカリクリノーゲン,プラスミノゲン,補体など4系列の賦活化),②組織傷害(外因性凝固機序の発動,白血球および腫瘍細胞にも組織トロンボプラスチンが多く含有されている),③血小板傷害(血小板凝集,血小板第3および第4因子,凝固第V,VIII,XII,XIII因子の放出)などと密接な関連がある1).
本稿では,上記凝固の引き金的要因との関連で,細小血管における血流の病態生理について述べてみたい.
線溶のしくみ
著者: 風間睦美
ページ範囲:P.804 - P.806
線溶系の構成
生体の止血機能を保持する諸要因のうちで,凝固系と線溶系はしばしば対比され,またそれらの相関が論じられる(図1).これらは血漿蛋白酵素の特異的連鎖反応系であって,共に最終的基質はフィブリノゲンである.線溶系の主役はプラスミンであるが,この蛋白分解酵素はフィブリノゲンやフィブリンに強い親和性をもち,フィブリン体分子のC末端より逐次これを加水分解して小分子の分解産物を生ぜしめる1,2).
生理的状態において線溶機能は一定のレベルを保ち,凝固機能や血小板機能と呼応して正常の止血機能を営むが,線溶が異常亢進すれば血流中のフィブリノゲン分解や生理的止血血栓の溶解などが異常に進行して止血能の低下をきたし,これが線溶の異常亢進による出血傾向の最大原因と目される.しかし蛋白分解酵素としてのプラスミンは,さらに他の血漿蛋白にも作用する.すなわち比較的不安定な凝固第V,第VIII因子の活性を低下せしめ,カリクレインを活性化することによってキニノゲンをキニン分解し,また血小板機能を障害するなど,生体内の線溶の亢進はフィブリン体分解のみならず,凝固系・血小板・血管系などに多面的な影響を及ぼすものである.
フィブリノゲンとFDP
著者: 高木皇輝 , 河合忠
ページ範囲:P.807 - P.809
フィブリノゲンの構造と主な性状
フィブリノゲンは血液凝固第I因子とも呼ばれ,血液凝固に関与してトロンビンによりフィブリンに転換する.フィブリノゲンは主として肝臓で生成され,正常成人血漿中には,200〜400mg/dlの割合で含まれ,生物学的半減期は4〜6日である.フィブリノゲンは分子量約340,000で図1で示すごとき分子構造をもっていると考えられている.3対のポリペプチド鎖,合計6本のポリペプチド鎖からなる化学的2量体(A)α2(B)β2γ2であり,それぞれ多くの鎖間および鎖内S-S結合により分子を形成している.構成サブユニットの分子量はそれぞれAα約70,000とBβ約60,000γ約50,000でN末端側が互いに近接している.Aα鎖が最も外殻に存在するらしく,最も早く蛋白分解酵素により分解される.
血漿フィブリノゲンは急性相反応物質の一つとして脳血管障害,心筋梗塞,悪性腫瘍,妊娠,ネフローゼ症候群,炎症などの疾患で増加して生体への外的侵襲,感染などに対する生体防御反応の一端を担っていると考えられる.また,血漿フィブリノゲンの減少または欠如があると,重篤な出血傾向を合併し,重症肝障害による合成低下でみられるほか,線溶亢進,DICなどでも消費亢進のため減少する.
診断
DICの診断基準
著者: 安部英
ページ範囲:P.810 - P.811
DICの定義
DIC(disseminated intravascular coagulation syndrome,播種性または汎発性血管内凝固症候群)とは,循環する血液の凝固性が亢進するため血管内で血液の凝固が起こって,全身各部で血栓が形成され,そのために種種の臨床症状が起こるとともに,血液の線溶活性も亢進して血栓,さらにフィブリノゲンが溶解し,このためにも各種臨床症状が起こる際,それらすべてを総括したものである.
これらの診断基準はもとより,その際の臨床症状,すなわちoozing型ないし急激な出血や血栓によるうっ血症状,さらにはショックなどとともに,その成因や発症機序に基づく特有な血液所見をも包含する必要がある.
DICの検査とすすめ方
著者: 松田保
ページ範囲:P.812 - P.813
はじめに
DIC(disseminated intravascular coagulation)は,最近ほとんどすべての臨床領域において,にわかに注目されている重要な症候群である.
本稿においては,DICの疑われる患者において,どのような検査を行い,またいかに早期に診断するかについて,簡単に述べることとする.
MHA
著者: 三輪史朗
ページ範囲:P.814 - P.815
はじめに
MHA(microangiopathic hemolytic anemia,細血管障害性溶血性貧血)の概念は1962年Brain,Dacie and Hourihane1)により提唱されたもので,末梢血中の著しい赤血球奇形と広範な細血管病変(microangiopathy)の存在により特徴づけられる溶血性貧血である.この場合にみられる奇形赤血球は赤血球の元来の正円形を失い,不規則な形を示すもので(図1),その形態的特徴からburr(いが状),spiculated(とげ状),triangular(三角状),helmet(ヘルメット状),schistocyte(分裂状),redcell fragment(破砕赤血球)などの名で呼ばれるが,最近ではschistocyteないしred cell fragmentと呼ばれるのが一般のようである.
最近ではred cell fragmentation syndrome(赤血球破砕症候群)という概念が生まれ,MHAよりもむしろ一般的になりつつある.
TTP
著者: 山田兼雄
ページ範囲:P.816 - P.817
はじめに
TTP(thrombotic thrombocytopenic purpura)は1925年Mosckowitzによりはじめて記載された,末梢動脈の血栓のたあに血小板が減少し,出血傾向をきたし,それとともに発熱,溶血性貧血,腎障害,消長する神経症状,消化器症状を主徴とする疾患である.
DICのみられる内科疾患
癌
著者: 螺良英郎 , 山下喬 , 樋口佑次
ページ範囲:P.818 - P.820
はじめに
悪性腫瘍の中でも,広範囲に浸潤あるいは転移を有する癌患者,または白血病患者において,血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation,DIC)がみられることがある.しかし,その頻度は必ずしも高率ではない.悪性腫瘍患者におけるDICには他の疾患同様,感染症あるいは肝障害などのrisk factorが存在している.したがって,癌患者の病態の把握に凝固線溶系の諸検査が必要となりつつある.悪性腫瘍におけるDICには急性で重篤な経過をとる典型的な急性型のDICと共に,出血,血栓などの症状があまり顕著でない慢性型のDICが注目されている.癌におけるDICは主に末期にみられるので,その治療は困難で予後不良のことが多い.DIC発生のrisk factorに注意することが大切である.
血液病
著者: 前川正 , 小林紀夫
ページ範囲:P.822 - P.823
はじめに
播種性血管内凝固症候群(DIC)は多数の基礎疾患の上に発現するので,各科領域で注目されている.血液疾患でも,DICを併発しやすいものがいくつかある.DICの併発は,その疾患の病像を修飾し,予後にも直接関連する点が注目されているが,中にはDICの症候が,その疾患の主要症候となる場合もある.DICは血液凝固,線溶系や血小板のみでなく,循環動態などをも含めたhemostatic balanceの破綻の結果生ずるが,これら各疾患におけるDIC発生の機序も決して一様ではない.
DICは基礎疾患による凝固亢進状態に以下のごとき引き金因子のいずれかが作用して発現すると考えられる1).
感染症
著者: 長谷川弥人 , 小林芳夫
ページ範囲:P.824 - P.825
はじめに
血管内凝固症候群(DIC)を生じやすい疾患の一つとして感染症,なかでも敗血症が注目されるようになっている.本稿では文献を参照しつつ,筆者らの経験をふまえて,いくつかの重要と考えられる点にふれてみる.
腎疾患
著者: 山田外春
ページ範囲:P.826 - P.827
はじめに
血液は先天的に付与された止血機序(血小板,凝血線溶因子,血管壁,血管周囲組織が関与)によって,心臓や血管の中では常に流動性を保っており,これによって生体は常に出血や血栓形成の危険から守られているのである.
しかし,外傷などの血管障害時には止血機序のみだれにより,生命がおびやかされるばかりでなく,機械的外傷がなくても,心因性にも止血機序の異常が生じうるし,さらに種々のmediator(刺激物質)によって,血管内で凝血・線溶因子が変化をきたし,生体がおびやかされる.
肝・胆道疾患
著者: 山本祐夫 , 𠮷村良之介
ページ範囲:P.828 - P.830
はじめに
DICは,なんらかの病的状態下で"ひき金因子"が加わり,凝固系が活性化されて生ずる一連の生体反応であるが,この時,肝で産生されるantithrombinによるthrombinの中和,肝およびRESなどでの凝固活性物質の処理などが抑制作用として働く.
凝固因子の産生低下もきたす重篤な肝障害時にDICが誘発されうる病態は,一見不思議とも思われるが,血中の凝固因子活性が低下することと血液凝固が活性化されることとは別問題であり,最近では,肝疾患に合併したDIC症例が多数報告されている.
心・血管病
著者: 中村克己
ページ範囲:P.831 - P.833
DICは,心・血管病そのものにより,あるいは心・血管における病変に伴って起こり得る.また,逆にDIC病態における一連の病変として,心・血管に変化が認められもする.このように,DICと心・血管との関連性は深いものといえるが,以下,DICの原因としての,あるいは結果としての(因果はめぐって正確には区別しがたい場合もあるが)心・血管病ないしは病変について,表における順序に従って述べてみる.
脳血管疾患
著者: 山之内博
ページ範囲:P.834 - P.835
DIC症例の背景
DIC症候群をきたし得る基礎疾患は多種多様である.悪性腫瘍,ことに消化器系臓器の癌,前立腺癌,肺癌,急性白血病,悪性リンパ腫,敗血症,重篤な感染症,ショック,産科的疾患など報告されている1,2),神経系疾患としては脳外傷,脳手術,原発性脳腫瘍,妊娠または産褥時に起こったくも膜下出血などの報告がみられる.
老年者では,DICは少なくない2,5).筆者らの検討では,連続剖検例中の約15%の症例に生前DICが認められている.そして,基礎疾患としては癌,ことに消化器系の癌,敗血症,重症感染症が多くみられた2,5).
呼吸器病
著者: 長谷川淳
ページ範囲:P.836 - P.837
呼吸器疾患におけるDICの合併頻度
呼吸器疾患にどのような頻度でDICが合併するのか,現在まだ明確ではない.昭和49年度の日本病理剖検輯報から,第1剖検診断名が呼吸器疾患であり,肺ないし他の臓器の出血,血栓,梗塞,ないし出血性素因,DICなどの記載のあった症例を全国大学病院の剖検症例(11,262症例)から抽出してみた(表1).10呼吸器疾患の症例数は1,141症例で全体の10.1%を占め,上記の種々の病態を合併した症例は272症例で1,141症例の23.8%に当たり,昭和48年度の22.5%に類似していた.DICと明確に記載されていたのは1症例のみであったが,微小血栓の存在症例,出血性素因の存在症例中には生前DICの病態を呈した症例もあったのではないかと推定される.また肺塞栓症,肺梗塞症を第1剖検病名に記載していたのは13症例であったが,他の基礎疾患の合併症として記載されていたのは199症例であり,DICは肺塞栓症の3症例,出血性素因の合併は18症例であった(表1).
肺癌におけるDICの発症頻度は対照とした胃癌の発症頻度より低く,肺塞栓・梗塞症ではより高率であることを示している表1の成績は,肺疾患でもDICの病態を示す症例があるので,経過を追った検索が必要であることを示唆している成績と考えられる.
糖尿病
著者: 阿部恒男
ページ範囲:P.838 - P.840
はじめに
糖尿病(以下DM)とは,インスリン作用不足による糖質,脂質の代謝異常と特徴的な細小血管症をきたす疾患である.近年,糖尿病治療の進歩に伴って血糖のコントロールは容易になってきたが,一方,網膜症や腎症に代表されるmicroangiopathy,ならびに心筋梗塞,脳血栓症に代表されるmacroangiopathyの発生進展が患者の予後を左右するので,臨床上きわめて重要な課題になっている.
DMは,血小板機能を含めて血液凝固能亢進と低線溶能の傾向にあることが指摘されており,これらの病態生理像がDMの血管障害の発生ないしは進展因子になっているのではないかとの報告も少なくない.また,いわゆるDICに陥ったと思われる症例報告も散見されるので,DMの一っの病態生理学的特徴とも考えられる血液凝固線溶系の態度について述べ,血管内凝固との関連性についても触れてみたい.
カラーグラフ
目でみるDIC
著者: 松田保 , 嶋田裕之
ページ範囲:P.842 - P.843
図1 26歳,男子.播種性転移癌(原発巣不明)に併発したDICの例にみられた歯肉からの出血.DICにおいて,出血は重要な症状であるが,この症例のように著しい出血傾向を示す例はむしろ少ない.
DICのみられる他領域の疾患
産婦人科領域
著者: 坂元正一 , 佐藤和雄 , 中林正雄
ページ範囲:P.846 - P.847
産婦人科領域におけるDICの特殊性
産婦人科領域(とくに妊娠分娩時)では典型的なDICが多く認められるが,それは以下の理由による.
1)妊娠中は各種の凝固因子が増加して,Shwartzman現象の準備状態と同じと考えられる.
外科領域
著者: 神前五郎 , 今岡真義
ページ範囲:P.848 - P.849
一般に,外科的にメスを加えて手術を行う際,組織の障害に伴い組織プラスミノゲン・アクチベーターや組織トロンボプラスチンが遊離され,線溶亢進や過凝固状態が惹起される.しかし,実際単なる手術操作のみでDICが惹起されることは比較的稀であって,長時間にわたる手術で大量の輸血を行ったり,手術中ショックに陥る場合を除いてはあまり認められない.ただ,基礎疾患に癌や重症感染症(endotoxemia)などがあると手術が契機となりDICが容易に惹起される.
麻酔科領域
著者: 小川龍
ページ範囲:P.850 - P.851
はじめに
日常用いられている麻酔剤や麻酔法がDICの直接の原因となることは考えにくいが,特殊な麻酔法,麻酔の合併症,手術操作がDICを誘発することがある.また時にDICやDIC準備状態の患者に外科的治療を加える必要が生ずるため,手術室やICUにおいて麻酔科医がDICの治療管理にあたることも稀ではない.そこで,外科領域のDICとの重複を避けつつ,麻酔科医の遭遇するDICについて述べる.
輸血時
著者: 川越裕也
ページ範囲:P.852 - P.854
はじめに
DICの発生は凝固因子の増量や血小板機能の亢進などが大きな要因になる1)ことは事実であるが,これらのみでは発生しない.この凝固亢進状態に加えて,これらの凝固過程を活性化する何かの作用があって初めてDICが発生するものである,この活性化作用因子をDICのtriggerないしchallengerと呼ぶ.その主なものはendotoxin,血管内溶血,組織液,抗原抗体複合体,補体,血管内皮の変化,血液粘度増加,血管内局所血流低下,蛋白分解酵素,脂質,コロイド物質などである.さて輸血時には凝固因子の流入,さらに重要なものとしてDIC triggerとなる要素を多分に含み,輸血液の状態,輸血技術,量などにより,それぞれ異なった程度にDIC発生因子の複合が生じてDICを発生する可能性を内蔵している.これらについて以下,適合輸血時の問題点,不適合輸血におけるDICについて簡単に述べる.
治療
DICの治療方針
著者: 松田道生
ページ範囲:P.855 - P.857
DICとは,腫瘍,炎症,組織の損傷,熱傷,ショックその他さまざまな病態を背景にかもし出される血管内での凝血系の活性化と,多くはそれによって招来される凝血因子の消費と血中でのレベル低下などのために,一方で腎,肺,腸管膜などに多発性の血栓を作り,他方で,対処しがたい出血傾向をみる症候群と理解される.
DICに対する治療方針はしたがって,その発生機序から分類すると理解しやすく,次のようになるであろうか.
抗線溶剤
著者: 元田憲
ページ範囲:P.858 - P.859
はじめに
DICには,常にそれを惹起する原因疾患が存在し,その排除がDIC治療の根本であることは自明の理である.しかし,実際には細菌感染,血管病変,心大動脈瘤のごとき原因除去可能なものもあるが,悪性腫瘍,白血病などその治療がほとんど不可能なものが多く,そのため凝固・線溶系の対症的是正が主役をなすことになる.
DICの発生機転はその名のとおり凝固亢進による汎発性の血管内凝固に始まり,そのためフィブリノゲンをはじめとする凝固因子の大量消費が出血性素因となって現れ,同時に,多発血栓はそれ自体二次線溶を惹起し,出血性素因となる.この2つの出血性素因が重なって,皮下のoozingから各臓器の大出血までを起こすものである.また,DIC中の生体内では,最初は凝固亢進により発生したとしても,図1のごとく病像としてわれわれが把握しうる頃には,3つのphaseが混在していると考えねばならない.
成分輸血
著者: 清水勝
ページ範囲:P.860 - P.862
はじめに
すべての輸血を行うにあたって常に考えておかねばならないことは,輸血はあくまでも補充療法であるということである.したがって,輸血の効果を最大限にあげるためには,目的とする血液成分について,下記の事柄に十分配慮することが必要とされる.
第1には,該当する成分が一般の供血者の体内においてどのくらいの量存在するかということ,第2には,採血・製剤化の過程や,保存時間・期間内に,その成分の量や活性能がどのくらい低下するかということ,第3には,その成分が患者に輸血されたとき,患者の体内での最少有効量と,体内における寿命とがどのくらいであるかということ,第4には,その成分の減少が急性にきたものか慢性にきたものかということである.これらの諸点を考えることなく輸血することは,輸血の効果を十分に期待できないばかりか,いたずらに副作用を助長するにすぎない結果となるといわざるを得ない.
演習・X線診断学 血管造影写真読影のコツ・6
胆道系疾患
著者: 古寺研一 , 平松京一
ページ範囲:P.866 - P.871
はじめに
従来胆道系のX線診断は,単純X線写真,上部消化管透視,および経口ないし経静脈的胆のう造影によって行われてきました.これらの検査は,ルーチン検査としてまず施行されるべきもので,とくに胆のう炎や胆石症などの診断には不可欠の検査であることはいうまでもありません.さらに近年になって,経皮経肝胆管造影(PTC)および内視鏡的膵胆管造影(EPCG)が開発されて,胆道系の悪性腫瘍についても,かなりの情報が得られるようになりましたが,これらのテクニックを用いてもなお,胆のう癌の術前診断はむずかしく,また炎症性疾患との鑑別もかなり困難なことがあります.
近年になって,Seldinger法により,経皮的に腹部大動脈分枝を造影するテクニックが確立され,腹部臓器の選択的血管造影が容易にかつ安全に行えるようになり,当然胆道系にも応用されるに至りました.さらに超選択的血管造影,薬理血管造影などを行うことによって,この領域の悪性腫瘍の診断の精度がかなり向上してきています.
--------------------
内科専門医を志す人に・トレーニング3題
著者: 深谷一太 , 鵜沢春生 , 依藤進
ページ範囲:P.873 - P.875
問題1. 腸管内にて増殖し,毒素を産生することにより下痢症をきたすことができるものは下記のどれか.
① 赤痢菌
連載
目でみるトレーニング
ページ範囲:P.876 - P.879
内科専門医を志す人に・私のプロトコール
POS編・その5
著者: 石村孝夫 , 山口潜
ページ範囲:P.881 - P.884
POS形式と従来形式折衷の記載
今月の提示例は,前回よりさらに一層,複雑な症例で,active problemは4つ,そのうち#3を除いては各各互いに関連性をもっている.POS形式だとこういう場合が困る.前回,POS形式では記載の前に,まず"縦割り"整理をしなくてはならないと述べたが,本例の場合は,#1のpure red cell aplasiaという基本になる大きな病気の流れがあって#2と#4はその原因および合併して生じた問題であるがために,本来,独立したactive problemとして分けてしまうことに無理があると思われる.
本例の記載は,はじめに例によって,"要約の要約"を記してあるので,#1,2,4相互の流れが理解できるが,これがなければバラバラとなって,病気の本体を見誤る恐れさえ生じてくるのである.こういう例に遭遇したとき,POSで一体,どう対処したらよいのか,私はまだいい方法が見当たらない,そこで,やむをえず一番大きなproblemである#1のみで本文を進め,その中で#2,#3…と挿入していくことにしている.これはいわば従来形式との折衷であるといえる.
診断基準とその使い方
先天性免疫不全症候群
著者: 早川浩
ページ範囲:P.885 - P.889
先天性免疫不全症候群は単一の疾患ではなく,それぞれ独立した性格をもったいろいろな疾患の総称であり,したがって,その診断基準もおのおのの疾患に独自のものがあるので,これらをすべて解説しつくすことは許された誌面ではとうていできない.ここでは厚生省特定疾患調査研究班「免疫不全症候群」(小林登班長)において試みたこれらの疾患の診断基準1)を中心に簡単に解説し,おのおのの疾患における診断上の最近の問題点を要約してみたい1〜3).
さて,先天性免疫不全症候群とは免疫反応を遂行する因子の一次的な異常により,主として感染に対する生体防御反応の不全である状態をいう1).この概念は比較的広義の概念であり,欧米でいうところのprimary immunodeficiency diseaseが主としてリンパ球系の異常による疾患に限定されているのに対し,好中球系,補体系などの先天異常による疾患も含めて考えている.このうち,primary immunodeficiency diseasesと称せられるものは表1に示したような種類に分類することが最もよく知られている.この分類はWHO推薦によるもので,免疫細胞の状態と遺伝型式とから特徴を示している.
図解病態のしくみ 高血圧シリーズ・2
高血圧症における心筋・血管平滑筋の収縮異常
著者: 青木久三
ページ範囲:P.890 - P.892
心筋・血管平滑筋の収縮・弛緩とCa2+の動態
血圧の高さを決定する心臓と血管機能は,心筋・血管平滑筋自体の固有の自動調節系,および神経系,内分泌系,レニン・アンギオテンシン系,電解質系などの外来性調節系との協調ある制御によって,主として血圧と心拍数の変動を介して,恒常性のある最適な血液循環の維持を計っている.これらは心筋・血管平滑筋の筋収縮と弛緩によるが,その機序は松田らおよび江橋らによりとくにCa2+の動態との関連において漸次解明されつつある.すなわち,筋細胞膜の興奮(活動電位,脱分極)に伴って膜のCa2+透過性が高まり,細胞外から細胞内へCa2+が流入して(Ca2+channelへのCa2+増加とslow inward Ca2+Currentの発生)細胞内Ca2+濃度が増加する.また,膜の脱分極または細胞外から流入したCa2+によって筋小胞体(細胞内Ca2+貯蔵部位)からCa2+が遊離し,細胞内遊離Ca2+濃度が増加する.このようにして増加した細胞内Ca2+はトロポニンに結合し,アクチン・ミオシンATP系を活性化し,筋は収縮(緊張,短縮)する.
臨床病理医はこう読む
肝機能検査(2)
著者: 山崎晴一朗 , 久原厚生
ページ範囲:P.894 - P.895
肝細胞障害を反映する検査
外くの肝機能検査の中から肝障害の病態把握に必要不可欠な検査を選択する場合,肝細胞障害を反映するものとしてGOTとGPT,胆路系の障害を反映するものとしてビリルビンとアルカリフォスファターゼ(Al-P),また間葉系組織の反応をみる検査としてTTTとZnTTが日常よく利用される.
本症例のごとく,トランスアミナーゼ値が著しく高く,しかもHBs抗原(+)であればB型急性ウイルス性肝炎の診断は比較的容易に下される.急性肝炎症例の多くでは,血中トランスアミナーゼ値は発病初期にはGOT>GPTであり,その後急速に血中レベルの上昇がみられ,極期にはGOT<GPTとなる.GPT値は200〜1600Uに分布し,平均値は約600Uである.その後急速に下降し,再びGOT>GPTとなり,発症後2カ月以内に正常化することが多い(図1).しかし,急性肝炎の一部(5,6%)には電撃性に経過して数日で死の転帰をとる劇症肝炎がある.
今日の食事療法
肝疾患—治療食の概略と実際
著者: 奥田邦雄 , 稲毛博実
ページ範囲:P.896 - P.897
現在の肝疾患の治療の大略は,①安静,②薬物療法,③食事療法の3つである.このうち,食事療法についても,過去幾多の議論がなされてきたが,今日の大勢は(多少の修正や批判はあるが),高蛋白,高ビタミン,高カロリー食であるが,これは食生活の極めて悪いアルコール性肝硬変症患者において得られる治療効果に基づいており,その他の肝疾患では眼に見えるような食事療法の効果はなかなか得られない.
疾患合併と薬剤
陳旧性肺結核があってステロイドを使うとき
著者: 青柳昭雄
ページ範囲:P.898 - P.899
ステロイドと結核
治療効果
副腎皮質ステロイド(ステロイド)の強力な抗炎症作用が期待されて,本剤の登場初期には,抗結核薬との併用によって肺結核の治療に応用する研究が行われた.
しかしながら,ステロイド投与群は,解熱,体重増加などの一般症状の改善や,胸部X線上空洞の閉鎖,浸潤影の吸収なども治療3ヵ月までは速やかであるが,治療6ヵ月ではその治療成績はステロイド非投与群と比べて不変で,かつ病巣の不活動化までの期間を短縮し得ず,最終判定では,通常の肺結核症の治療には有利に作用しないと結論されており,また慢性肺結核症,すなわちX線学研病型C型(線維乾酪型),F型(重症混合型)に対してステロイドを併用投与すると,悪化,死亡例が高率となることが報告されている1,2).
プライマリー・ケアの実際
腹痛の診断と急性腹症(2)
著者: 眞栄城優夫
ページ範囲:P.900 - P.903
急性腹症の鑑別診断
虫垂炎の鑑別診断
腹部全体,上腹部,あるいは臍周辺の内臓痛が,炎症の腹膜への波及とともに,壁側痛である右下腹痛として限局することが虫垂炎の特徴である.しかし,虫垂が盲腸後方に位置するときには,最初から右下腹痛として発症し,骨盤部に位置する虫垂では,膀胱症状をみることもある.普通は2歳以後にみられるが,われわれの経験した最年少者は,生後8ヵ月であった.したがって,乳児期の原因不明の発熱でも虫垂炎は疑うべきであり,試験的腹腔穿刺も活用すべきである.時には,L1,L2のgenitofemoral nerveを介しての睾丸痛が,初発痛として発症することもみられるので,副睾丸炎や睾丸捻転などと鑑別しなければならない.左側の痛みを訴えたり,内臓転位症で,虫垂が左側にあるにもかかわらず,腹痛を右側に訴えることもある.50歳以後,および学童期より前の症例では,穿孔の頻度が高い.穿孔を起こすと,39度以上の高熱となり,腹痛が軽減することもある.穿孔により,レントゲンで腹腔内遊離ガスを認めたり,血清アミラーゼの上昇すら認めることもあるので注意しなければならない.
外来診療・ここが聞きたい
内科臨床に役立つ眼科の知識
視力障害の見分け方
著者: 松井瑞夫
ページ範囲:P.908 - P.909
視力障害という訴えにはいろいろなものがあるが,問診を系統的に行うことによって,その視力障害の原因をかなりの程度まで推測することができる.ここでは,ペンライトや直像検眼鏡など限られた診断手段と問診によって,視力障害の原因を見分ける方法について述べてみよう.
心疾患の治療・今日の考え方 〈最終回〉
心疾患の緊急状態に対する処置
著者: 石川恭三 , 広木忠行 , 前田如矢
ページ範囲:P.910 - P.916
前田(司会) 本日は,このシリーズ治療篇のしめくくりとして,cardiac emergencyをとりあげたいと思います.
心臓専門医に限らず,すべての臨床家にとってcardiacemergencyは非常に大事な問題です.処置もむずかしいし,急性期の処置を誤れば予後を大きく左右します.そこでまず,頻度の多い急性の冠不全についてうかがいたいと思います.急性冠不全といえば,まず狭心症,中間型,心筋梗塞の3つが問題ですが,そのうちで急激に起こった狭心症および中間型に対しては一般的にどういう注意をすればいいでしょうか,石川先生.
天地人
産婆蛙
著者: 人
ページ範囲:P.917 - P.917
近年,公害による環境汚染の問題がやかましく云々され,やれ川魚の変態がみられたとか,やれ奇形がみられたとか報道されている.ダーウィン以来の進化論では,環境の変化による自然淘汰が動物進化のための一つの原動力になっていると説いている.
ところで,ヨーロッパの南部に普通にみられる産婆蛙という妙な習性をもった蛙がいる.この蛙は産卵の時に,雄が雌の背の上から抱いて,雌が産卵すると直ちに雄はこれを下肢に巻きつけ,雌のからだから幾分引き出して助ける動作をするため,産婆蛙と呼ばれているとのことである.卵は寒天のような物で包まれていて,雄の下肢にねばりつくわけである.このようにして,卵の紐を下肢に巻きつけた雄は,雌の産卵が終わると,雌のからだから離れて,石の下や草の蔭などにかくれて卵のおもりをするのである.やがて,卵が発育してオタマジャクシのような形にまで成長して水中に泳ぎ出ようとする時期になると,雄はおもむろに近くの池や沼に入って,オタマジャクシを水中に泳ぎ出させるらしい.この時期に,やっと雄は身軽になって自分自身の生活にもどることになる.この産婆蛙はお産まで雄雌が平等に責任をもっているわけで,これこそ"超近代的男女平等"なのかもしれない.
オスラー博士の生涯・50
ボルチモア市の火災と大学病院復興対策
著者: 日野原重明
ページ範囲:P.918 - P.920
1903年は,オスラーは結核対策とその研究および予防と治療のキャンペーンなどで多忙な1年を過ごした.そしてまた,この年にはオスラーの業績として残る2っの立派な講演をしているのである.
ここにも医療あり
語らぬ「むくろ」に聞く話—警察医23年
著者: 松野清
ページ範囲:P.922 - P.923
医師法第21条
第1例 駅前の女子寮で,未婚の31歳の女工さんが,押入れの中で出産し,血だらけになって倒れているという連絡が110番に入った.ピーポー・ピーポーと救急車が女子寮に向かい,母子を乗せてK産婦人科医院に運ばれた.K先生は後産を処理し,母は順調に経過したが,嬰児は死産として埋葬された.○○署の刑事がK医院を訪ねて,先日の母子のことをうかがいたいという.ここで刑事に医師法第21条を持ち出された.この嬰児は「死体又は妊娠四月以上の死産児」である,したがって「二十四時間以内に所轄署に届け出なければならない」.「異常」とは,死産児自体の外,四囲の状況から判断されたい.
第2例 C病院に救急車がきて,母子の薬物中毒患者が運ばれた.M院長はその家族からすでに連絡があって,直ちに診療・治療をした.母の救命には成功したが,子供は死亡した.子供には死亡診断書を書いて埋葬した,○○署の刑事がM院長に面会を求めてきた.「死体をみた場合は届けなければなるまいが,この場合は生きていたし,その後死亡したので死亡診断書で埋葬した.」
基本情報
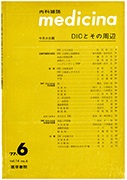
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
