現在の新抗癌剤開発の主な方向は,現存する抗癌剤の利点,すなわち有効性をより高め,一方において欠点,すなわち毒性をより少なくした類縁化合物の研究である.この場合新しい化合物が合成されると,そのもとの抗癌剤と有効性,毒性が動物実験で比較検討され,より優る結果が見出されたときに臨床研究へと導入される.また数少ないけれども従来の抗癌剤とまったく異なる性質をもつ薬剤も研究されている.本稿では,phase I,II studyの段階にある新しい抗癌剤の現況を解説する.なお誌面の限定があり,本邦で研究されている薬剤および近い将来に研究されるであろう薬剤を中心に記述したい.
雑誌目次
medicina19巻6号
1982年06月発行
雑誌目次
今月の主題 癌治療の最前線
理解のための10題
ページ範囲:P.1072 - P.1074
化学療法
ヌードマウスを用いたin vivo抗癌剤感受性テストの意義
著者: 久保田哲朗
ページ範囲:P.1004 - P.1005
ヌードマウス可移植性ヒト腫瘍を用いた実験的化学療法は1975年Povlsen & Rygaard1)の報告に端を発し,当初は個々の患者の癌組織を移植しそれぞれの腫瘍の感受性をあたかも細菌の感受性試験のように行おうとする試みがなされた.しかしながら,初回移植率が40〜50%であること2)や,継代株を樹立して感受性試験を行うまで数ヵ月を要すること3)が明らかとなり,現在のところは臨床材料を直接感受性試験に用いる方法は谷らの報告4)を除くと広くは行われていない.
一方,樹立された継代株を対象とした抗癌剤感受性試験は筆者らの成績3,5)を含めて各施設からの報告があり,米国National Cancer Instituteでは,L-1210,P-388などのマウスの腫瘍を用いた1次スクリーニングの次にヌードマウス可移植性のヒト肺・乳腺・結腸癌の代表株を用いて2次的スクリーニングを行うシステムを組み立てている.代表株によるスクリーニングにおいて問題となるのは,多種多様な組織型を有する各臓器癌が同一の抗癌剤感受性を保持しているか否かということである.
腫瘍の微小循環特性に基づいた昇圧化学療法
著者: 涌井昭 , 佐藤春彦
ページ範囲:P.1007 - P.1010
癌化学療法効果を増強する方策として,第1に,腫瘍実質に対して,第2に間質を介してのアプローチの重要性が指摘され,その考え方にそった研究が種々報告されている.前者は癌細胞自体に対する殺細胞効果増強へのアプローチであり,後者は主として,抗癌剤の癌巣到達性亢進に対する試みである.
近年,腫瘍の微小循環に関する研究により,以下の実験事実が示された2,3).
抗癌剤のtargeting
著者: 高橋俊雄 , 山口俊晴
ページ範囲:P.1012 - P.1013
癌細胞にだけ選択的に毒性を示し,正常細胞には毒性を示さない薬剤,すなわち癌選択毒性のある抗癌剤の開発が待たれているが,現在のところ満足すべき薬剤はない.そこで,新しい抗癌剤の開発に努力する一方,現在ある抗癌剤を効率よく選択的に癌病巣に到達させる試みがなされている.本稿ではその試みを,薬剤の修飾による抗癌剤のtargetingと投与法,投与経路の工夫による抗癌剤targetingの2のつ面から概説してみたい.
Transcatheter Chemo-Embolization
著者: 神前五郎 , 岡村純
ページ範囲:P.1014 - P.1015
意義,目的
従来,肝癌に対する姑息的治療としては全身投与,または動注による化学療法と肝動脈結紮術の2つがよく行われ,1年以上生存例も報告されてきた.しかし延命効果としての生存率を論ずるに足るだけの成績をあげるに至らず,肝癌の治療は大きな暗礁に乗りあげ,異なった治療の登場に期待がかけられていた.
14年前の脊髄動静脈奇形の治療,ひきつづいて消化管出血の治療のために用いられた経カテーテル動脈塞栓術(transcatheter arterial embolization;TAE)が,9年前ごろより腎癌の治療に応用されるに至った.このTAEを原発性肝癌に応用したのはGoldstein1)であるが,系統的な治療として行い,よい成績をあげているのは本邦山田ら2)である.筆者らは1979年来濃度dependentな薬剤を用いた抗癌剤one shot動注とTAEの併用(表題にあるtranscatheter chemo-embolizationのchemoは化学療法剤の動注を意味するchemoであって,化学療法剤に浸漬したあるいはそれを内包した塞栓材料を使うというchemo3)でないので,誤解されないことを望むが,とにかくこの言葉を以下TCEと略する)を非切除肝癌58例に行って1年生存率は56.2%4)と,これまでになかったよい成績があげられるようになった.
免疫療法
癌免疫研究の現状
著者: 橋本嘉幸
ページ範囲:P.1016 - P.1017
近代癌免疫の発展は1960年代初期における近交系動物の開発に伴う同系癌,さらには自己癌に対する宿主の移植免疫研究に礎を有するものと思われる.これらの研究により,化学発癌剤誘発癌およびウイルス癌には正常組織細胞には表現されていない癌特異抗原が存在することが明らかにされ,いく多の研究を通して,癌の特異抗原性の概念が確立されてきた.これに平行して,癌に抗原性があれば細菌やウイルスとのアナロジーにより,免疫学的な癌の治療法が可能かもしれないという予測のもとに,種々の形の癌免疫療法が実験的に追求され,やがて臨床の場にも持ち込まれるに至った.
一方,以上のような癌に対する免疫現象を司る宿主側の因子は何かについての解析も,上の諸研究と並行して行われ,キラーT細胞,マクロファージ,K細胞,NK細胞といった宿主細胞の関与や血清因子の効果,さらには基礎免疫学の知見の拡大による抑制性細胞や因子の発見が行われてきた.
インターフェロンの抗腫瘍性
著者: 雨貝孝 , 岸田綱太郎
ページ範囲:P.1018 - P.1020
1975年,New YorkでCantellらの生産したヒト白血球インターフェロン(IFN)を,Stranderが骨肉腫の患者に原発巣の外科的処置の後,肺転移抑制の目的で試用し有効であることが報告され,一躍IFNの抗腫瘍剤としての効果が世界の注目を集めるに至った.IFNは,1954年長野,小島によって,1957年IsaacsとLindermannによって発見された.「細胞に非特異的ウイルス抵抗性を誘導する蛋白ないし糖蛋白」である.IFNの抗腫瘍効果研究の出発点は,ウイルスで誘発された腫瘍に対して,抗ウイルスで作用をもつIFNが有効ではないかという点にあった.現在,多種多様な腫瘍患者にIFN治療が試みられつつあるが,その現状の概略と考えられるIFNの作用のメカニズムについて述べてみたい.紙数の関係で,文献1)(石田らの項)および2)を参照されたい.
monoclonal抗体と癌治療
著者: 葛巻暹
ページ範囲:P.1022 - P.1023
腫瘍が生体によって拒絶される場合は,主として細胞性免疫の働きによるという証拠が動物実験で多く得られている.これに対して液性免疫がどれほどの効果を持っているのか疑問であるとされてきた.にもかかわらず血清抗体による癌の免疫治療が試みられてきたのは,その調整や保存の容易さと,抗体の持つ特異性のためである.しかし従来の血清療法では,用いる血清が異種の動物由来であれば吸収操作が必要となり,同種の血清でも一般に抗体の力価が低く,腫瘍抗原に対する抗体としての特異性も厳密なものとはいえなかった.これらの欠点が,いまやルチーンの抗体作製法となった細胞融合法によって得られるmonoclonal抗体によって克服された.しかし,monoclonal抗体単独では腫瘍の完全な治療を期待するのは無理であるという成績が大勢を占め,monoclonal抗体を抗癌作用のある物質のcarrierとして用いるという観点から臨床への応用が具体化されつつある.
monoclonal killer T cellと癌治療
著者: 藤本重義
ページ範囲:P.1024 - P.1025
近年,細胞工学の手法の進歩にはめざましいものがあり,免疫学の分野においても免疫学的手法の技術革命として急速に脚光を浴びるようになった.その1つは,単一の特異性と均一な機能を持った単クロン性免疫細胞(monoclonal immunocyte)をin vitroで樹立,維持する手法としての細胞融合法1)(cell fusion)である.これは,免疫細胞(T細胞あるいはB細胞)と腫瘍細胞とを融合させて,免疫細胞が持つ免疫学的機能(抗体産生能やT細胞機能,たとえばヘルパーやサプレッサー機能あるいは細胞障害能など)と腫瘍細胞が持つ持続性の自律性増殖能を兼ね備えた融合細胞(hybridoma)を作ることによって,B細胞あるいはT細胞のハイブリッドクロンを大量に作ることができるようになった.他の1つは,細胞融合法と同様の目的性を持った手法で,免疫細胞(丁細胞あるいはB細胞)をTcell growth factor(TCGF)2)あるいはB cell growth factor(BCGF)を用いることによって,抗原特異的T細胞あるいはB細胞を免疫学的機能を保持したまま正常リンパ球としてin vitroで長期培養することが可能になりつつあるために,それらの細胞を増殖させてクロン化する手法である.
体液性免疫抑制因子の分析
著者: 漆崎一朗
ページ範囲:P.1026 - P.1029
生体の免疫応答の発現には,機能を異にした免疫担当細胞群,および体液中の免疫反応を抑制あるいは増強する因子などに依存する免疫の調節機構immunoregulationが関与する.癌患者の細胞性免疫能の低下は広く知られているが,その機序にも免疫抑制細胞と体液性の免疫抑制因子が働いているとされている.癌血清中の免疫複合体が免疫抑制的に働き,腫瘍関連抗原のあるものが免疫抑制細胞を誘導し,免疫抑制細胞が抑制作用を有するsoluble mediatorを遊出するなどのことは,体液性の免疫抑制因子が担癌生体の免疫能に重要な意義をもつことを示している.これまでにも血清中の免疫抑制因子については表1に示すように多くの物質が報ぜられたが,その異同性,化学的性状,作用機序および生理的意義について不明な点が少なくない.ここでは癌血清の免疫抑制因子について整理してみたい.
癌治療と抗癌免疫能
著者: 西條長宏
ページ範囲:P.1030 - P.1033
臨床における免疫機能測定の目的の1つは,これらが担癌患者の重要なprognostic factor (予後因子)になりうるか否かという点にある.一般的に担癌患者の免疫機能の検討は患者のperformance status,臨床病期,治療効果など既存のprognostic factorとの相関,あるいは直接予後との相関を分析することが大半である.近年あらゆる治療はrandomized control trialによってその効果を判定する必要に迫られてきている.randomizedcontrol trialの場合,層別化の基礎になるのは担癌患者のprognostic factorである.prognostic factorのreliabilityを向上させるには評価方法の客観性が要求される.免疫機能はすべて数値で表現しうるため,きわめて客観的な指標といえる.一方,担癌患者免疫機能は,腫瘍に対するeffector機構解析の手段として検討されつつある.この場合は自己の腫瘍増殖に直接関連性の深い腫瘍免疫機構の一部としての免疫機能であり,本稿ではこれを抗癌免疫能と呼ぶ,臨床レベルにおける免疫療法のほとんどすべては免疫adjuvantを用いた非特異的免疫療法であるが,これらの免疫adjuvant検定には,少なくとも癌細胞に対し障害性に働く免疫反応が確実に作働しているという証明が臨床においても要求される.
トピックス
レーザー治療の適応と限界
著者: 早田義博
ページ範囲:P.1034 - P.1035
最近の科学の進歩の一つはオプトエレクトロニクス(光技術)である.1960年ルビー・レーザーに始まり,固体,気体,液体,半導体レーザーなどを利用した各種レーザーが開発され,医学の部門でも癌の診断,治療へ応用され始めた.しかし未だその成績は一定していないが,これからレーザー医療を志す人にとって,いままでの経験からレーザー治療の適応と限界を推定することは意義がある.
Biological Response Modifiers(BRM)の概念
著者: 塚越茂
ページ範囲:P.1036 - P.1037
癌の治療は外科,放射線それに抗癌剤による治療法が中心となっているが,それらはいずれも癌を選択的に除去しようとする最終目標のもとに実施されている.しかし,いずれの治療法もいまだ完全なものではなく,正常組織も腫瘍組織とともに多かれ少なかれ障害を受けるのが実情であろう.したがって治療を受ける側の患者は,良好な結果を望むならば,その治療によるマイナスの影響をも同時に受けることになる.すなわち,いずれの治療法も効果と副作用の比で評価されねばならない.
これまで,担癌患者にはもともと癌に対する固有の抵抗性のあることも報告されてきている.そしてほとんどの場合これは免疫学の表現をもって示されてきた.腫瘍細胞はその表面に腫瘍特異抗原があることが報告されており,この抗原刺激に対し宿主は免疫応答を示すこともわかってきた.したがってこのような免疫応答を増強することにより治療効果を期待する試みが広く行われるようになってきている.
全身hyperthermia
著者: 山中直樹 , 加藤信夫
ページ範囲:P.1038 - P.1040
丹毒に罹患して高熱を発した後sarcomaが治癒したとの報告以来,癌に対して温熱療法が有効な治療法として注目された.その作用機構については多くの研究があるので,他書を参照されたい1〜2).
温熱療法とは治療目的をもって人為的に身体の一部または全体の温度を上昇させる治療をいう.したがって局所温熱療法と全身温熱療法(totalbody hyperthermia;T-HT)とがある.T-HTには,pyrogenの注入によるもの,体表面より加温する方法と体外循環によって身体のコアーから加温する方法とがある.
局所hyperthermia
著者: 柄川順
ページ範囲:P.1042 - P.1043
癌の温熱療法はかなり以前から試みられていたが,近年,機器の開発や生物学的研究で効果が次次と報告されるようになり,新しい臨床応用が開かれようとしている.局所加温では必要な部位に予定通りの温度にまで加温しうる装置がまだ完成しておらず,腫瘍内やその周辺組織の温度測定が侵襲的にしか行えないことと,電磁波による加温下で正確な温度を測定するのが難かしいことなどの問題点がある.
癌転移の抑制
著者: 螺良英郎 , 山下喬 , 八木正人
ページ範囲:P.1044 - P.1045
癌患者における転移
癌患者の死因一癌死は多元的要因に基づく,癌そのものの拡がり,すなわち浸潤,転移は癌死の最大要因であるが,担癌状態の進展による代謝異常や免疫異常は癌悪液質として間接的に合併症で死因につながっている.これらのなかでも転移(metastasis)は癌患者の病期とも関連し,診断および治療上の大きい指標とされている.転移は癌が悪性であるという代名詞ともなっており,その抑制に対して基礎的ならびに臨床的研究も行われているが,きわめて困難である.癌転移の抑制には直接癌細胞を除去,抑制しようとする手段と癌細胞には直接抗癌効果を示さないが,間接的に転移巣の形成を防止ないし抑制する2つの手段がある.転移の抑制を目的とした系統的な臨床成果はなく,各種癌で観察された転移抑制の散発的な成績しかみあたらない.動物実験による転移の形成と抑制に関する最近のデータも参照しつつ転移抑制の今後の検討について述べることとする.
癌治療の指標としての腫瘍マーカー
著者: 服部信
ページ範囲:P.1046 - P.1047
腫瘍マーカーの臨床応用は,腫瘍のスクリーニング,腫瘍の診断が最も一般的なものであるが,癌治療の指標としての価値も応用面の1つである.もちろん,自然は診断とか治療の指標になるようにと考えて腫瘍マーカーを生合成しているのでなく,腫瘍の本来の性格に基づいて,過剰に生成した腫瘍マーカーを逆に利用して臨床上に応用しようというわけである.当然自ら制約も生ずるのである.
集学的治療
消化器癌
著者: 岡崎伸生
ページ範囲:P.1048 - P.1049
最近では癌の治療においても,外科的療法ばかりではなく放射線療法,抗癌剤および免疫療法など,いくつかの治療手段がそれぞれ確立されつつある.癌の集学的治療の基本思想は,治療の必要な患者に対して,その病期やhost factorを考慮した上で最も適切な治療手段を選択することにある.病状によってはいくつかの治療手段が同時に採用される.また異なった治療手段を用い連続的に治療されることもある.
消化器癌においても集学的治療の概念はすでに日常の診療体系にとり入れられている.しかし,その病理組織像の大部分を占める腺癌や肝細胞癌は放射線療法や抗癌剤療法に抵抗性であるため,集学的治療の効果が十分発揮できる症例は必ずしも多くはない.本論文では,将来が期待されながらも現在なお方法論の確立されていない消化器癌の集学的治療の現状について述べたい.
肺癌
著者: 大熨泰亮
ページ範囲:P.1050 - P.1051
肺癌の集学的治療(multidisciplinary treatment)とは,その治療成績の向上を目的として,診断から治療にいたる全過程において,関連するあらゆる領域の専門家の知識を集約し,その協力体制のもとで患者の管理を行うことを意味する.肺癌治療の場において集学的作業が最も要求されるのは個々の患者についての至適治療計画を立案する過程においてである.病理組織所見,病変の解剖学的な拡がり(病期),患者のvital organ capacityに基づき,肺癌に対する手術療法,放射線療法,化学療法など個々の治療様式の信頼限界を考慮に入れた総合的な治療計画の立案が,治療成績向上の第一歩であることは論をまたない.最近では集学的治療体系の中で,それぞれの治療法が持つ利点を助長し欠点を補うことを目的に,いくつかの治療様式を組み合わせた,いわゆる合併療法(multimodal treatment)が試みられつつある.
白血病
著者: 大野竜三 , 山田一正
ページ範囲:P.1052 - P.1053
かつては不治の病とみなされていた白血病に対して,現在では単に生存期間の延長を目指すのみでなく,その完全治癒を目標とした治療が行われている.その中心をなしているのは化学療法であるが,近年,免疫療法や骨髄移植も広く施行されるようになり,抗生物質療法や成分輸血を中心とする補助療法の進歩を含めた集学的治療の結果,長期生存例も年々増加し,治癒と考えうる症例も多数存在している.
本稿では,これら集学的治療の最近の進歩を解説するとともに,白血病治療の今後のあり方についても考察する.
乳癌
著者: 冨永健
ページ範囲:P.1055 - P.1057
乳癌は最近わが国においても急増の傾向にあり,婦人悪性腫瘍の中で子宮癌,胃癌についで多くみられる疾患である.年齢分布をみると20歳台から80歳以上に及んでおり,40歳台に最も多い.しかし,近年これが50歳台に近づき始めるとともに,70歳前後の高齢者にもピークが認められはじめ,いわゆる2峯性のパターンを示すようになってきており,欧米での年齢分布に似てきている.
乳癌が多くの他臓器癌と違う点は,その内分泌依存性にあり,この特性が治療の上で大きな役割を果たしている,すなわち,その増殖は下垂体,副腎,卵巣などの臓器と密接な関係にあり,閉経前後でも癌細胞の内分泌学的性格は異なっている.近年,乳癌細胞中のestrogen receptor(ER),progesterone receptor(PgR),prolactin receptorなどが測定できるようになってから,腫瘍の内分泌依存性を予測することが可能となり,臨床的にも成果をあげている.
癌性心嚢炎
著者: 富永慶曙 , 新海哲
ページ範囲:P.1058 - P.1059
悪性腫瘍による心嚢炎としてはmesotheliomaやその他の心嚢原発のものと,他の臓器の癌の転移,浸潤によるものがある.しかし,頻度としては後者のほうが圧倒的に多く,したがって本稿も転移,浸潤による癌性心嚢炎について述べたい.
癌性心嚢炎の多くの場合は,他の種々の臓器にも同時に転移を有している末期癌である場合が多い.それゆえ的確な臨床診断がなされえぬ場合もあるが,癌性心嚢炎による心タンポナーデが致死的であることを考えれば,その診断と治療は重要である.
座談会
癌治療の進歩—基礎から臨床へ
著者: 新田和男 , 仁井谷久暢 , 中島聰總 , 西條長宏
ページ範囲:P.1061 - P.1071
新しい抗癌剤,免疫賦活剤 ニトロソウレア系/サイクロフォスファマイド/代謝拮抗剤/その他の合成剤/抗生物質/植物成分 新抗癌剤の開発とスクリーニング 開発のポイント/臨床治験への適応基準/biological response modifier(BRM)の位置づけ/効果判定基準BRMによる免疫療法の意義 近接効果は判定可能か/in vivoでの近接効果のチェック/細胞レベルでの判定法を 新しい治療法の位置づけ レーザー治療/抗癌剤の動注法とtargeting/hyperthermia phase Ⅱ study signal tumor/日本でも独自のものをPhase Ⅲ study,adjuvant study randomized trial/phase Ⅲ studyには必ずphase I,Ⅱ studyを経た薬剤を/多剤併用療法 予後を左右する因子 宿主要因/腫瘍要因/randomized studyは万能か/adjuvant chemotherapy 癌の撲滅のために/やはり早期発見と早期手術/情報の整理が必要/微小転移巣への対策
カラーグラフ 臨床医のための腎生検・6
糸球体病変・6
管内増殖性糸球体腎炎
著者: 坂口弘
ページ範囲:P.1076 - P.1077
従来,急性糸球体腎炎といわれてきたものの糸球体病変である,これと同じような症状は以下に述べる管内増殖性糸球体腎炎のほか,半月体性糸球体腎炎(crescentic GN,次回),MPGN type I(4回),dence deposit腎炎(MPGN type II),MPGN type III(5回)その他の型の糸球体腎炎でもみられるので,まとめて急性腎炎症候群(acute nephritic syndrome)と呼ばれ,どの型の糸球体腎炎であるかは腎生検によって確かめる.
このdiffuse endocapillary GNは溶連菌感染後急性糸球体腎炎に相当するもので,光顕では図1のように糸球体はすべて著しく腫大し,図2のように個々の糸球体はメサンギウム領域も毛細血管腔も腫大増殖した細胞で充満し,糸球体内の赤血球はそのため減少している.筆者らが学生のころには急性腎炎の糸球体の所見はAnschwellung(腫脹),Kernreichtuln(富核),Ischarnie(乏血)とドイツ語で教わったが,まさにその通りである.増殖した細胞は,内皮細胞,メサンギウム細胞,血中からの単球,好中球などであるが,好中球以外は光顕ではどれがどれだか識別ができないので,一括して管内増殖(endocapillary proliferation)と呼んでいる.
連載 演習
目でみるトレーニング 61
ページ範囲:P.1080 - P.1085
画像診断 心臓のCT・6
大動脈炎症候群
著者: 太田怜 , 林建男
ページ範囲:P.1086 - P.1092
大動脈炎症候群は,動脈壁の変化の強い症例では,単純心X線上,大動脈に沿った広範な石灰沈着から,それと診断できるが,そうでない症例では,かならずしも容易ではない.確診のためには,大動脈造影を行って,大動脈の狭小化をみなければならない.
大動脈炎症候群は,大動脈壁そのものが拘縮するので,内腔のみならず,外径も狭くなっている.CT検査は,単純なものでも,その検出にきわめて有利な方法である.
画像診断と臨床
今月の焦点 座談会
コンピュータで広がる医療
著者: 土肥一郎 , 三宅浩之 , 開原成允 , 浅原朗 , 坂部長正
ページ範囲:P.1102 - P.1115
坂部(司会)今日のテーマは「コンピュータで広がる医療」です.まず,各自ご自分の専門の分野を持ちながら,コンピュータのほうに進んでいったきっかけについて,土肥先生からお願いします.
講座 図解病態のしくみ 消化器疾患・27
Parenteral & Enteral Nutrition(6)—Peripheral Parenteral Nutrition
著者: 松枝啓
ページ範囲:P.1119 - P.1125
4月号では,Protein-Sparing Therapyの実際について述べた.しかし,Protein-Sparing Therapyは,3月号(vol. 19,no. 3,P. 523-527)で示したごとくMaintenance Therapyなので,治療効果には限界があり,体重減少が理想体重の10%以下などと軽度の栄養不良状態が存在する場合のみに施行されるべきであり,もしProtein-Sparing Therapyの開始より2〜3週間以内に十分な栄養の経口摂取が可能でない場合や,体重減少が理想体重の10%以上などと高度の栄養不良状態が存在する場合には,次の段階である強力な治療法としてのAnabolic Therapyを考慮すべきである.このAnabolic Therapyには,Total Parenteral Nutritionと,特殊な方法によるEnteral Hyperalimentationがあることは3月号で述べた.Total Parenteral Nutritionは,さらに末梢の静脈から投与するPeripheral Parenteral Nutritionと,中心静脈より投与するCentral Parenteral Nutritionに分類できるが(図1),今月号では,主にPeripheral Parenteral Nutritionについて述べたい.
図解病態のしくみ 臓器循環・5
肝循環—解剖,生理,病態のまとめ
著者: 須永俊明
ページ範囲:P.1127 - P.1132
肝の血管系
肝血管系の成立ち
肝の血管系は,肝動脈系と門脈系から成っている.肝動脈系は,主にceliac axisに入るが,時には,左胃動脈または上腸間膜動脈からの場合もある.主としてO2供給系である.
これに対して門脈系は,主に栄養の移送と供給が考えられる.両者が肝内sinusoidを形成して,肝静脈を経て下大静脈に入る.
異常値の出るメカニズム・50 酵素検査・10
血清LAPとCAP
著者: 玄番昭夫
ページ範囲:P.1133 - P.1139
LAPに関する混乱
ロイシンアミノペプチダーゼ(leucine amino-peptidase,LAP〈ラップ〉)とは,表のようにEC 3.4.11.1のコードNoをもつ酵素である.しかしこれまで臨床的に測定され,そして"いわゆる"LAPと呼んできた酵素はこの"真の"LAPと異なり,EC 3.4.11.2に属する酵素である.さらにEC3.4.11.3のシスチンアミノペプチダーゼ(cystine aminopeptidase,CAP〈キャップ〉)を"胎盤性"LAPと称することがあって,ますます混乱が大きくなっている,単に名称の問題だけであると臨床的にそれほど重大なものではないが,この3種類のLAP,すなわち"真の"LAP,"いわゆる"LAP,"胎盤性"LAPのもっそれぞれの臨床的意義も異なるために深刻な混乱が生じてくるのである.今回はまずこの問題の解説からはじめることにする.
"真の"LAP(これを本稿では単にLAPと呼ぶことにし,そして現在多くの臨床検査室で測定されている"いわゆる"LAPのことを,ここではアリルアミダーゼ<AA>と呼ぶことにする)とは,表に示したようにL-ロイシンアミド(あるいはL-ロイシルグリシン)を加水分解する酵素である.
外来診療・ここが聞きたい
診療基本手技
大伏在静脈カットダウン
著者: 高尾信廣
ページ範囲:P.1140 - P.1141
最近,経皮的カニュレーションの技術が普及したので,静脈切開により血管確保を行う機会が次第に少なくなってきた.しかし,まだまだ直視下で安全,確実に血管確保が行える静脈切開の必要性は多い.当科でも,とくにニューフェイスのレジデントには,その機会のあるごとに経験させるように努めている.
研修法として,まず剖検の際に5症例前後行い,次に5症例くらい介助につき,さらに指導下で3〜5症例経験を積むようにしている.そうすれば,一応独力で可能になると思われる.また,モスキート鉗子の取り扱いに慣れることも大事である.まず,図1に示すように,鉗子を手に持ち,小さな紙片をつかむ練習をし,細かな動きが可能になるようにしておく.
がん免疫振興財団シンポジウム 「末期患者に対する積極的治療」から(その2)
癌の内分泌療法の現況—乳癌を中心に
著者: 熊岡爽一
ページ範囲:P.1160 - P.1163
はじめに
癌はおしなべて悪性であり,自律性の成長をとげ,生体を倒すという認識は一般論としては正しい.しかし,成長の経過中に自然退縮したり,物理的化学的な環境の変化によって腫瘍が消失することは時に起こることである.これは温熱療法とか細菌感染によって悪性腫瘍を治癒に導こうとする試みとして応用されている.
手術不能または再発癌に対しては,放射線照射,化学療法などが行われ,これらは大なり小なり腫瘍以外の健康組織にも損傷を与えることとなる.しかし,限られた一部の癌においては,癌をとりまく環境の変化によって癌が縮小したり治癒する現象が起こる.
がん免疫振興財団シンポジウム 「末期患者に対する積極的治療」から(その3)
末期患者の取り扱い方
著者: 筒井末春
ページ範囲:P.1164 - P.1168
はじめに
死を目前に控えた末期患者は,医療スタッフであれば遭遇することが少なくないにもかかわらず,そのアプローチの仕方に関しては今日まできちんとした学問体系も築かれず,かつ医学および看護教育もなされないままで,各人の良識の判断にまかされているのが実情のようである.
欧米において死に臨む患者への対処につき学問として積極的な関心を呼ぶようになったのは,比較的新しく1960年以降のことである.
がん免疫振興財団シンポジウム 「末期患者に対する積極的治療」から(その4)
癌末期の疼痛除去について
著者: 村山良介
ページ範囲:P.1170 - P.1173
疼痛というもの1,2)
癌の末期に疼痛が一番問題となってくる.では疼痛とは何かと,あらたまって聞かれると答に窮する.ペインクリニックなるものを始めた頃,疼痛というものを簡単に考えていた.痛みというものは誰でもわかるものであり,そんな特殊なものではない.針でついたり,刃物で切った時に感じるものである,お腹が痛い,頭が痛いというのも日常経験することであると.しかし,20年たって,神経ブロックも麻薬も効かない痛みがあることがわかり,この人の痛みとは一体なんなのかと考え出すに及んで,今まで疼痛というものを本当に理解していたかを疑うようになると,いろいろな問題点が浮かんできた.臨床的に疼痛とは,「真実を語っている場合,言語またはこれに代わる方法をもって"痛い"と告げたとき,その人のもっている意識内容である.」と定義した.なぜこのようにややこしい定義をしなければならないかというと,同じ刺激たとえば針でついても痛く感じる人とそうでない人がある.これは個人的な感受性の問題といえる.また,浅い全身麻酔で手術を始めた時,血圧が上昇すると疼痛のためと説明され,一様に納得するが,全身麻酔をかけられているので疼痛は感じていない.これも痛みといわれている.疼痛を起こす刺激も疼痛といわれているのである.そこで痛みに一つの線を引いておく必要があったのである,そうしないと疼痛を語りながらすれ違いを生じてしまう.
オスラー博士の生涯・107
プラトンが描いた医術と医師 その1—1898年Johns Hopkins病院医史クラブ例会にて
著者: 日野原重明 , 仁木久恵
ページ範囲:P.1144 - P.1150
ウィリアム・オスラーは1889年にジョンス・ホプキンス大学に招かれ,病理学のウェルチなどとともに,医学部作りの中心として働いた.ジョンス・ホプキンス病院に赴任すると,すぐウェルチとともに病院の歴史クラブの例会をさかんにするように努力した.1893年の例会には上記の題でプラトンを中心に,ギリシャの医術と医師について語った.オスラーは作家や哲学者の医師論や医師批判に非常に興味をもっていたようである.
オスラーは1892年5月に,42歳で結婚したが,英国への新婚旅行中に,ロンドンで買い求めたJowett訳の「プラトンの対話」を読んだ.
天地人
女性と肩書き
著者: 越
ページ範囲:P.1143 - P.1143
先般,月面宙返りで鳴らした器械体操のオリンピック選手が,女性ボスの依怙ひいきに反発して現役を退く声明を出したことが話題になった.
この事の真相はともかく,女性は肩書がつくと矢鱈に威張りたがるものらしい.それも男性のようにふんぞり返って威張っているのが見え見えであると,却って皆にコケにされたり,オダテられて足をすくわれたり,ことは簡単であるが,女性の長はそうはいかない.表面は何くわぬ顔付きで,蔭に廻ってのイビリ,アテコスリ,意地悪と,あらゆる陰険で知能的な手段を使ってやっつけるものらしい.ターゲットにされた男性や女性こそいい面の皮で,つくづく仕事がいやになるであろう.
--------------------
ECHO
著者: 猪狩淳
ページ範囲:P.1071 - P.1071
Q 補体の不活化の温度とその意義についてお教えください(仙台市 開業,30歳)
A 補体は正常な脊椎動物の血清中に存在し,いろいろな種類の蛋白によって構成されている大きな反応系であり,試験管内では免疫粘着反応,溶解反応および補体結合反応などの抗原抗体反応に関与する.
VlA AIR MAIL
著者: 福原俊一
ページ範囲:P.1152 - P.1156
一流の研究陣,24時間体制のパラメディクス,教授も例外でない厳しい相互評価,風通しのよい上下関係など,アメリカの誇る研修システムの実際
基本情報
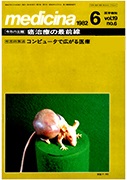
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
