内科医の現状を憂える
今日の内科医のあり方でもつとも重要な問題は,医学の社会化ということではなかろうか。現行の社会保険制度の矛盾は,いろいろの原因もあろうが,もつとも重大な原因は,従来の医者が医学の社会化ということにあまりにも無関心であり過ぎたためではなかろうか。もともと医学は善意の学問であり,医学それ自身はその当初から自分自身の社会化を考えている。それが今日の公衆衛生の発達であり,現今の文明社会はこの恩恵にもとづいて繁栄しているのである。その最たるものが急性伝染病に対する防疫であつて,これなくして現代の文明国の繁栄はまつたくあり得なかったのである。臨床医学も医学の一分野,というより古来から主役であり,善意の学問たるにちがいないのである。したがつて太古は宗教的色彩をさえおび,現在でもそれと手をつないでいる例はいくらもある。私の少年時代,医者は自ら国手をもつて任じ,国家もそれを認め,何の不安もなく人間の善意の上にあぐらをかいていたようにさえみえた。未だ多くの急性伝染病が民衆をおびやかし,医者の必要性が切実であつたからであろう。しかし防疫が完備し.ワクチンや抗生物質が発達した現在,ちようど「治にいて乱を忘れる」諺のように,民衆は次第に医者への切実な善意を忘れがちになる。そしてちようど防疫施設やワクチン注射のごとく,医者の役目を国家の制度と,化学工業による薬剤との効果に置き換えようとしている。
雑誌目次
medicina2巻4号
1965年04月発行
雑誌目次
EDITORIAL
内科医のあり方—医学の社会化を目指せ
著者: 前川孫二郎
ページ範囲:P.505 - P.507
今月の主題
悪性高血圧の本態
著者: 武内重五郎
ページ範囲:P.508 - P.511
高血圧症のうち,なぜ一部のものが悪用化するかということが問題である。現在血圧上昇による血管の負担増大(器械的影響)を重視する考え方が有力であるが.これですべてを説明しうるか否かについてはなお異論が多い……。
蛋白漏泄性胃腸症
著者: 西川光夫
ページ範囲:P.512 - P.515
アイソトープを用いる検査法の導入により,従来原因不明とされていた低蛋白血症のなかに胃腸への喪失に基因するものがあることが判明しつつある。いわゆる蛋白漏泄性胃腸症は,いかなる機序で蛋白が漏れるのであろうか……。
<話合い>蛋白漏泄性胃腸症—その発生機序と診断のすすめ方
著者: 西川光夫 , 築山義雄 , 宇佐美正暢
ページ範囲:P.516 - P.521
耳新しい病気
司会(宇佐美) 本日は,蛋白漏泄性胃腸症についてお話を願うわけでありますが,この病気は,私をも含めて一般の先生方には,耳新しいものでありまして,初めてお聞きになつた方も多いのじやないかと思います。それでまず本疾患の概念と,その歴史的展望について,西川先生から,簡単にお話し願いたいと思います。
西川 ネフローゼは昔から知られていて,尿の中に蛋白が漏れ,血清の蛋白が減つて,低蛋白血症をきたすのですが,そういう低蛋白血と体中に浮腫があつて尿に蛋白の出ていない例が,昔からある程度,気づかれていたようです。そういつた例は,尿蛋白のないネフローゼと言つたりして,原因不明のままに過ごしていたのだと思います。低蛋白血症が起こるには,食べる蛋白が少ない場合がまず考えられます。飢饉などで長い間蛋白質を食べないでおれば低蛋白血が来ます。また,せつかく蛋白質を食べても,消化,吸収が悪かつたり,または蛋白の合成の障害のために低蛋白血になります。その他,摂取も合成も正常で,外へ漏れてしまうために低蛋白が来ることがあります。漏れるものの中にはネフローゼのように有名なものもあるし,瘻孔から膿汁が絶えず出ているとか,あるいは肺から多量の喀痰が出て蛋白の減少をきたすこともある。ところが胃腸から便の中に蛋白が漏れるものがあることが最近わかつてきたわけです。
診断のポイント
構音障害
著者: 神山五郎
ページ範囲:P.523 - P.525
はじめに
構音障害という術語はまぎらわしいものである。articulation disordersとも考えられるし,dysarthriaとも考えられる。医学方面ではdysarthriaのことを指す場合が多いようである。
articulation disordersはdysarthriaを含む上位概念で,原因が何であろうとも,構音に誤りがあるすべての症状を指す。たとえば,地方で育つて方言を持つた人が東京に来れば,時にarticulation disordersといわれうる。これに反して,dysarthriaは構音器官といわれている口唇,舌,軟口蓋,咽頭,喉頭などの諸筋の障害,これらを支配する神経の障害,およびこれらの神経のさらに中枢部にある神経の障害によつて生ずる共同運動障害などに起因するarticulation disordersを指す。
便潜血反応
著者: 正宗研
ページ範囲:P.526 - P.527
消化管疾患の症状のうち,消化管出血は最も重要なものの一つなので,吐血下血のごとき顕出血はむろんのこと,潜出血の場合にもこれを他覚的に証明するために,糞便潜血反応は重要な日常の検査手技の一つとして診断学上応用されている。
坐骨神経痛
著者: 西新助
ページ範囲:P.528 - P.530
安直になりがちな痛みの診断
臨床上痛みに対処する場合には重要問題点が内蔵されているが,一般には,いわゆる神経痛ときめて安直な処理法に走りがちのようである。しかし,痛みを主訴とする者が外来患者の高い%を占めているからには,その痛みの種類を見分け,出来れば原因を正してみようとする意欲を,さらにはそれを実行に移す努力をといつたことが望まれるのは当然であるが,自覚的な痛みを他覚的にとらえることは必ずしも容易な業ではなく,また多くの患者を限られた時間内に診療せねばならない多忙な医家にとつて,それに費し得る時間には自から制約があろう。神経痛は医者では駄目だとして,いかがわしき施療に足を向かわしめる結果を招く原因は,あるいはそんなところにあろうかと思う。そんな意味から,はなはだ多く診断名として表われる坐骨神経痛を取上げてみた。
治療のポイント
ジギタリス使用の実際
著者: 細田瑳一
ページ範囲:P.531 - P.532
薬剤の種類と使用量
強心配糖体ジギタリスは,少量に過ぎては効果がなく,大量に過ぎれば生命の危険をもたらすことは周知のとおりである。適応を慎重に決定し,使用に当つては,中毒の予防に絶えず注意することが重要である。
古くから使われたジギタリス葉末も,最近の純度の高い製剤も作用機序は同じと考えられており,不純物の含有量,吸収排泄の効果速度などが,患者の固体差と共に作用の差を生ずる。また後に述べるいろいろの要素により使用量が左右される。
気管支喘息とアドレナリン,エフェドリンの使い方
著者: 光井庄太郎
ページ範囲:P.535 - P.537
対症薬として
気管支喘息の治療は原因療法と対症療法とになる。対症療法の目的は発作を早急に,しかも完全に消失させることであるが,さらに発作を予防することもできれば,その価値はいちじるしく大きい。アドレナリンおよびエフェドリンは優秀なステロイド剤が使用されるこんにちにおいてもいぜんとして重要な気管支喘息の対症薬である。
肥満の生活指導
著者: 松木駿 , 竹内由美子
ページ範囲:P.538 - P.539
肥満の害の認識
肥満者が生命保険の統計上短命であること,糖尿病,高血圧,心臓病などにかかりやすく,またかかつた場合に肥満の問題を考慮しないと,治療がなかなかやつかいであることなど,最近は一般へのPRもきいて,これを知らない人はほとんどない。しかしこれがいざ自分のこととなると,自分だけはこの問題から除外されているように錯覚しており,認識不足をいなめない。
それはなぜであるかと考えてみると,食欲のcontrolの難かしさ,肥満者自身が感じているsense of well-being(健康感と訳すのがよいと思うが,実はこの場合は誤まつた健康感である),かつぷくがよいとか,かんろくがあるという一種の肥満肯定の考えなどであろう。これに対し肥満抑制に強力に働らくのは美容上の要求である。女性の肥満が50歳未満に比較的少なく50歳を越えると急に増加する事実も美容上の抑制がとれることが大いに関係あろう。日本では男女を比べると肥満は明らかに男性に多いのに,私どもの肥満症外来を訪れる患者は大部分が若い女性である事実からも,美容上の要求がいかに強いかが判る。
慢性骨髄性白血病
著者: 木村禧代二
ページ範囲:P.540 - P.542
慢性白血病中わが国において臨床的に取り扱われる症例の多くは慢性骨髄性白血病(CML)であり,慢性淋巴性白血病(CLL)を取り扱うことはきわめてまれである。われわれの経験においても百数十例の慢性白血病例中CLLはわずか6例にすぎない。したがつて以下CMLを中心に慢性白血病の治療を記述してみたい。
グラフ
骨髄腫
著者: 長村重之
ページ範囲:P.495 - P.497
骨髄腫患者の骨髄穿刺液中に多数認められる細胞はきわめて多彩であるが,共通に認められる細胞は形質細胞ないし,形質細胞様細胞であり,一般にこれを骨髄腫細胞という。骨髄腫には骨髄に結節を形成し,骨を破壊するossales Myelomと,骨髄全体にびまん性に発生するdifuses Myelomとがあるが,いずれも形質細胞の異常増殖が認められる。したがって形質細胞性骨髄腫という名称を提唱している人もいる。
骨髄腫細胞の大きさは15〜20μで,境界の鮮明な円形ないし卵円形細胞で,一般に原形質の巾が広く好塩基性に濃染し,紫青色ないし青色を呈しており,正常の形質細胞より淡いことが多い。核は円形で通常1個であるが,分節しているもの,およびくびれを有するものもあり,多くは偏在している。核の輪廓は鮮明でクロマチン網工はきわめて繊細緻密であり.通常1個の比較的大きい核小体を有する。核小体は時に5μくらいに及ぶこともある。骨髄腫細胞の中には正常の形質細胞によく似て区別の困難なものもある。その他細網細胞および,類リンパ球に類似するものもある。したがって骨髄腫は細胞の形態学からは,1)成熟形質細胞が主体である場合一形質細胞腫,2)定型的な骨髄腫細胞が主体である場合一形質芽細胞腫 3)異型の強い形質細胞性細網細胞が主体である場合一形質細胞性細網症,4)類リンパ球が主体である場合一類リンパ球性細網細胞症に分けられる。
新しい甲状腺機能検査法—Triiodothyronine-131Iのresin sponge摂取率(Triosorb test)について
著者: 星子直躬
ページ範囲:P.498 - P.502
Hamolskyらはin vitroの血液に131I標識triiodothyronine(T3-131I)を混じて放置しておくと,T3-131Iが血漿蛋白だけでなく赤血球にも結合摂取され,甲状腺機能亢進症患者の血液では赤血球に結合摂取されるT3-131Iの量が多く反対に甲状腺機能低下症患者の血液では赤血球に結合摂取されるT3-131Iの量が少ないことを報告し,T3-131I赤血球摂取率(EU)の測定が他の甲状腺機能検査法の成績に比べ信頼性が高く,患者に131Iを投与しないですみ,比較的簡便迅速にしかもin vitroで検査し得,かつ検査成績が甲状腺剤,甲状腺ホルモン,ヨード剤,ヨード含有食品の摂取による影響をうけない優れた検査法であることを報告した。(1,2)Mitchellらは赤血球の代用としてresin spongeを使用した。in vitroで,被検血清にT3-131Iを加えた混合血清中にresin spongeを投入する。resin spongeに結合摂取されるT3-131Iの量すなわちresin spongeuptake(RSU)は甲状腺機能亢進症患者では高く,甲状腺機能正常妊婦,甲状腺機能低下症患者では低く,その成績はEUよりも優れ,操作も簡易で短時間ですみ,血清の保存も可能というように現在ではきわめて優秀な方法であることを発表した(3)。
ファースト・エイド
下血によるショック
著者: 安藤幸夫
ページ範囲:P.546 - P.549
下血は吐血と同様に消化管からの出血によつて起こり,その原因となる疾患には表に示すようにいろいろある。下血には上部消化管の出血のように吐血を伴うようなものは診断は容易で,その対策もたてやすいが,下血だけの場合は,わが国のようにまだ水洗が不完全のところでは下血に気づかないでショック状態となり,来院,あるいは診察を求められる場合が多い。一般に下血でショックをきたすようなものは大部分が上部消化管からの出血であり,そのほとんどが循環血液量の減少に起因するものである。以下,下血によるショックの救急処置について述べる。
器械の使い方
顕微鏡の種類と利用法
著者: 高橋昭三
ページ範囲:P.550 - P.551
顕微鏡は,金属用(反射型)と生物用(透過型)にわけられる。前者は,医学用としては皮膚表面の観察などに用いられるのみであり,対物レンズを通して,光を標本にあて,反射光を再び対物レンズを通して観察するものである。後者は,普通の生物用,実体,倒立型の3種にわけられる。倒立型は金属用に多い型式で,対物レンズが標本の下にある型式で,多用途大型の装置が多い。あるものは,接眼レンズで,小さいスクリーンに像を投影するようになつている。実体顕微鏡は,光学的に傾斜した2本の鏡筒よりなり,像は正立である点が特色で,倍率は150倍位までであり,解剖用,耳鼻科の手術用などに用いられる。しかし,医学の分野で最も多く用いられるのは,普通の生物用顕微鏡であるから,これを中心にして述べたい。
顕微鏡を正確に使うことは,自動車の運転よりもむずかしい。自動車なら,運転がまずければ,自分にも他人にもすぐわかるが,顕微鏡では,最高の性能を発揮させているかどうかが,自分にはわからないからである。現在,顕微鏡の改良されて来た点は,顕微鏡のレンズの改良もあるが,どうしたら面倒な操作なしに最もよい鏡検の条件をいつもだせるか,という点に集中されているといつてよいだろう。これらの諸点をみながら,手許の顕微鏡の完全な使い方のポイントを考えたい。
正常値
血糖値について
著者: 永野允
ページ範囲:P.604 - P.605
臨床的に血糖という場合は……
一般に血糖値とは血液中のブドウ糖の値を指しています。生体のなかにはブドウ糖以外にブドウ糖の代謝産物としての燐酸化された六炭糖,五炭糖を初め,数多くの糖が含まれていますし,血液中にもこれらの糖は認められています。血糖という表現(Blood sugar,Blutzucker)をしますと,これらの糖をすべて含んでもよいわけですが,臨床的に血糖という場合は血中ブドウ糖と考えるのが常識になつております。
尿中蛋白質を以前はAlbuminuriaと表現しましたが,これはProteinuriaが正しいのと同じように血液ブドウ糖はBlood sugarという表現をやめてBlood glucoseというのが正しいわけです。
メディチーナジャーナル 循環器
Digitalisの予防的投与
著者: 小沢利男
ページ範囲:P.616 - P.616
近年心臓などの大手術が盛んになるに伴つて,心疾患の手術に際しては,心不全の有無に関せず,術前にDigitalizationする傾向が多くなつたようである。Digitalisの適応はいうまでもなく,うつ血性心不全ならびに心房細動,心房性頻脈などの不整脈にあり,心不全のない限りDigitalisの使用は控えるべきであるというのが従来の一般的な考えであつた。これは主として正常心にDigitalisを投与した場合に心榑出量の減少が認められるという事実に基づくものであるが,この点からすれば術前のDigitalisの投与の可否も大いに論議のある所といわねばならぬ。しかしDigitalisの作用は,はたしてこのように健常心と不全心とで相反するものであろうか。最近心カテーテル法の長足の進歩とともに,心搏出量などの循環諸量がより正確に測定せらるるに及んでこの問題は再び各方面より検討されてきている。
すなわち,最近の研究によればDigitalisを健常心に投与した場合,心搏出量は必ずしも減少ぜず,不変の場合もまた時には増加する場合もある。従来の心搏出量が減少したという報告は,Selzerによれば,その殆んどが検査方法もしくは検査結果の検討の不備に基づくものであり,心カテーテル法を駆使した最近の報告70例をまとめた結果では,健常心の心搏出量に及ばすDigitalisの作用は一定した傾向を示さないという。
健康管理
日本人労働者の血液生理値
著者: 山本武彦
ページ範囲:P.617 - P.617
健康管理の基本的姿勢は,健康の側面からみることにある,ということについてはこの欄で述べた1)。健康管理活動の実際面において評価の基礎となるものの中で,血液諸像はとくに意義が大きいものの一つである。そのための顕著な業績の一つとして,"日本人労働者の血液生理値"2)の大成が挙げられる。さきに1962年(昭37)3月,"日本人の正常血液像"3)が小宮らの努力で脚光を浴びたが,ちようど同じ頃,企業の労働者の健康管理の分野で,とくに法の定める特殊業務に従事する人を対称とする健診法の中心である血液検査に,「ふるいわけ検査」が用いられた。その場合血液諸像の正常,異常域の限界を定めたいという強い要望があり,小宮らの大著の中でも,きわめて少ない工場労働者について,その実態を調査し実用に供し得るデーターを提供したいという学会の意向があつた。
ここで正常値といわず,生理値(physical values)といつているのは,この委員会の人たちが生理値という方が,より生物学的意味合いが強いと考えたからであり,正常値といつてもかまわないというように汲みとれる。
簡易臨床検査のやり方と評価
小児科領域における血中尿素窒素の簡易定量法
著者: 茂手木皓喜
ページ範囲:P.492 - P.492
尿素窒素の微量定量には,血清0.005〜0.01mlで行なうウンアーゼ法があり,正確性がみとめられているが,微量用の光電比色計が必要で,広く一般に簡易に行なうわけにゆかない。またごく簡易な方法としてXanthohydrolによる比濁法があるが除蛋白の必要があること,検体を大量に要することなどで,小児科むきではない。ここに紹介するユニグラフは,検体も微量ですみ,除蛋白の必要もなく,操作も至つて簡易であり,現在の簡易検査のうちでもつともすぐれたものと思われる。
ノモグラム
任意採尿のPSP排泄値より標準時間値を求めるノモグラム
著者: 阿部裕
ページ範囲:P.485 - P.485
使用法:PSP排泄値がt分でE%のとき,15分排泄値を求めるには,まず上のN字型共線図表の両側の目盛上にt分とE%をとり,直線で結び,中央斜線との交点を求める。次にこの交点と15分とを結び,この延長と右側PSP排泄値目盛線との交点を求めれば,これが15分値である。tが30分以内のときは左上部のノモグラムを同じ要領で使用してもよい。図中破線はt=29分,E=50%より15分値30%を求める例である。
臨床検査の盲点
PSP経時排泄曲線の意義
著者: 阿部裕
ページ範囲:P.601 - P.601
PSP排泄試験でえられた15,30,60,120分各排泄値が,日常臨床で全部活かして使われているだろうか。
もちろん15分値が腎血流量の簡便な指標として欠くことのできないものであることは周知のことであろう。今腎血流量をRPF,PSPの腎除去率をE,PSPの体内分布容量をVとすれば,静注t分後のPSP排泄値S(%)は
保険問答
結核の治療指針
著者: 古平義郎
ページ範囲:P.620 - P.623
質問 二次抗結核剤に対する耐性検査は社会保険として未だとりあげられないと聞いている。
しかし39年8月に衛生検査指針のうち結核菌検査指針が改正され二次抗結核剤に対する検査もその方法が示されている点から,社会保険医療としても保留のままの状態とは考えられない。以上の点からどう考えられるか
統計
日本国民の体位
著者: 滝川勝人
ページ範囲:P.522 - P.522
わが国民の体位については,栄養改善法に基づき毎年全国的な規模で行なわれている「国民栄養調査」により,その実態が明らかにされている。
戦争によつていちじるしく低下した国民の体位も,食糧事情の好転と相まつて遂年向上し,昭和28年頃にはおおむね戦前の水準にまで回復し,その後も栄養摂取水準の上昇に伴つて順調に伸びつづけている。とくに成長期における青少年の体位向上はめざましいものがある。
話題
第6回日本精神身体医学会総会およびPSMの最近の動向
著者: 長谷川直義
ページ範囲:P.561 - P.561
今年は第6回総会が東北大・九嶋勝司教授を会長として,きたる5月4日および5日の両日,仙台市において開催されることになつた。
学会準備のつごう上,1月末日に抄録を締切つたにもかかわらず,申込みの一般演題は83題に達した。これらの演題の内容を検討してみると,わが国におけるPSM研究のあゆみと最近の動向がおのずと理解される。以下,思いつくままに記してみたい。
第35回日本内科学会信越地方会感想記
著者: 古田精市
ページ範囲:P.615 - P.615
信州大学小田正幸教授主催のもとに11月15日に行なわれた本会は,前夜までの雨がすっかりあがり,晴天に恵まれた。初冬の肌寒い信州の気候にもかかわらず,早朝8時半よりすでに多数の会員が集まり,午後4時やや過ぎまで,41題の興味ある症例報告あるいは研究発表があり,なごやかな中にも活溌な討論が行なわれた。
特別講演は千葉大学三輪内科の白壁彦夫講師による"胃X線診断に関する最近の諸問題"についてで,寸刻を惜しむごとくにエネルギッシュな講演が行なわれた。わが国においては日常の臨床上最も多いと言ってよい胃腸疾患の診断法についてはわれわれ会員としても切実な,それ故にまた興味ある問題であって,氏は胃集団検診などによって集められた多数の症例にもとづいて得意とする二重造影法,圧迫法を中心に,さらに充盈法の長所を入れて,細かな所見の意味づけについても長年の手術例との対比にもとづいて実に見事にわれわれ会員に示してくれた。まずX線上に現われる粘膜の太さについては,時に粘膜襞の頭と頭とが接触して,それによって作られた襞が一見胃粘膜襞としてX線上に現われることがある点に注意を与え,このような場合には圧迫によっておのおのの襞の中に十分バリウムをすり込むことが大切である。
第6回日本老年医学会総会から
著者: 村松文男
ページ範囲:P.534 - P.534
第6回日本老年医学会総会は,昨年12月6,7の両日にわたり,初冬の東京サンケイ会館において,慶大内科,相沢豊三教授会長のもとに盛大に開催された。二日間三会場に分れ,一般演題183題,シンポジウム3題とともに,沖中東大名誉教授の特別講演,米国オークランド新陳代謝研究所所長Kinsell博士の招待講演,更に相沢教授の会長演説と,非常に多くの講演演題が取り上げられ,早朝よりおそくまで活発に討議された。
一般演題の内容は,動脈硬化に関するもの39題,高血圧関係17題,脳卒中関係16題,心機能に関するもの13題,糖尿病関係9題ほか,呼吸器,消化器,代謝関係など数多くが基礎,臨床など多方面にわたり,時間の許す限りの発言,討論がおこなわれた。特別講演としては,冲中名誉教授は,「老年者と自律神経系」と題し,自律神経系の形態および機能と老化現象との関連について,多年にわたる研究の成果を述べられ,これらの関連性を追求する一方向を示唆された。Kinsell博士は脂質代謝を中心として,その基礎および臨床面につき講演したが,ともに本総会を意義深いものにした。
症例
選択的腎動脈撮影—3.腎評の鑑別診断
著者: 田坂晧 , 竹中栄一 , 山内尚聰 , 北川龍一
ページ範囲:P.556 - P.559
前号では腎の悪性腫瘍および嚢腫について述べた。今回はこれ以外の腎疾患で腎が腫大したり腫瘤がある例で選択的腎動脈撮影からどのようなことが知りうるかを述べることにする。
他科との話合い
前立腺—肥大症とがんの診断
著者: 落合京一郎 , 日野志郎
ページ範囲:P.595 - P.600
前立腺の肥大症とがんは,2つの大きな男子の老人病であるといわれている。
肥大症もさることながら,がんの早期発見のためにこそ,内科医はつとめて直腸内触診をやるべきであると,落合教授は強調されている。
基礎医学
MEDICAL ELECTRONICS
著者: 大島正光
ページ範囲:P.606 - P.609
最近の急速な発達に伴い,Electronicsは医学の全額域に取り入れられるようになつてきた。すでに広く用いられている心電図や脳波から,病院管理の面まで,今やElectronicsなしには医学を語り得ない時代が到来しつつある。
If…
スポーツ,何一つできません—日本学士院会員東北大名誉教授 加藤豊治郎氏に聞く
著者: 長谷川泉
ページ範囲:P.562 - P.563
数・物が得意で工科志望
長谷川 生存者叙勲で賜杯をお受けになりまして,おめでとう存じます。`
先生は東大明治40年のご卒業でございますから,緒方知三郎,黒沢良臣,塩谷不二雄先生などとこ同期でいらつしやいますね。早速でございますが,もし先生が医師にならなかつたら,どんな人生コースを歩まれたとお思いになりますか。
ルポタージュ
関西医療界のユニークな存在—淀川キリスト教病院を訪ねて
著者: 張知夫
ページ範囲:P.566 - P.568
いい病院とは?
いったい"いい病院"とはなんだろう? 医師を中心とする医療チームが優秀であることや,設備のいいことが,まず不可欠の要件としてあげられる。しかし,さらに一歩つつこんで,では優秀な医師とはなにか,と考えてみると,その定義はすこぶるアイマイなものであることに気がつく。学識,技術,判断力,人格,統率力,経営の才……どれに重点をおくかによって,さまざまの"優秀な医師"があり得る。設備にしてもおなじことだ。一流ホテルなみの病院や給食を"いい設備"というのか,それとも,そんなものはどうでもよくて,医療器機や手術室の完備をさしていうのか?
定義のさだかでない要素をいくつかあつめて,それでもつて病院の優劣を判定しなければならないとすれば,これは元来ムリな注文なのかも知れない。そのうえ最近では,医療を行なう側と医療を受ける側とで,判断の基準が逆になることすらある。「キミのところはいいようだナ」とA院長がB院長にいうとき,それはB病院の経営がうまくいつているということだ。それは極端にいえば,B病院はガメツくやつてるということで,患者の立場からすればボラれているということになりかねない。
海外だより
アメリカの足
著者: 川合厚生
ページ範囲:P.564 - P.565
□自動車はぜいたく品というより必需品□
アメリカにおける自動車(自家用車)のめざましい普及については,くる前から十分予備知識を仕込んであつたから,さほど驚くことはなかつたが,公共の交通機関のあまりの未発達なことには意外の感をもたざるをえなかつた。都市間の交通はさておいて,問題は市内交通である。私の住む人口5万のこの町には,数本のバス路線があることはあるが,網の目のように張られた日本の都市のそれと比較すれば,ほとんどなきに等しい。しかも,土地はむやみと広いから,その不便さは言語に絶する。だからこそ,自家用車がこんにちのようないちじるしい発達を遂げたのかもしれない。あるいは反対に,自家用車のために,公共の交通機関の発展がおさえられてきたのかもしれない。それはともかく,自動車はここではぜいたく品ではなく,必需品であるといわれるわけが,よくわかつたような気がした。この町の人たちも,各世帯に少なくとも1台は車をそなえている。夫婦仲よく1台ずつ持ち合わせている家もある。おもしろいのは,家々の構造があたかも自動車が大事な家族の一員であるかのように,車庫が家の一部として組み入れられ,しかも,それがたいていの場合,家の正面にでんと据えられていることだ。そのかげに本屋がドァをへだててつながつている。私はこれを見て,いつか北日本で見た馬小屋と母屋が木戸1枚を境につながつている農家の構えを連想したものだ。
海外の動き
中央検査室自動化最近の動き—アメリカ臨床病理学会総会見聞記
著者: 河合忠
ページ範囲:P.570 - P.571
1964年10月17日から23日までアメリカ臨床病理学会(American Society of Clinical Pathologists)とアメリカ病理医協会(College of American Pathologists)の合同総会がフロリダ州パルハーバー市でおこなわれ,私も会員の1人として出席した。病理医から検査技術員の問題まで広範な討議があつたが,最も大きな話題はやはり中央検査室の自動化における最近の進歩であろう。わが国においても同様な動きが活溌にみられており,臨床医各位にとつても見逃すことのできない話題と思われるのでアメリカにおける現状を要約してみよう。
私の工夫
安い恒温槽の工夫
著者: 斉藤正行
ページ範囲:P.572 - P.573
今日GOT,GPT,アルカリ性リン酸酵素活性測定データなしで肝機能いかんを云々することは冒険であるとされている。また,心血管疾患の管理に抗凝固薬の投与例が日に日にふえて来ると血液凝固能の測定はやらないわけにはいかないはずである。当然時代の要求に応じてこれらの測定用試薬キットが自由に入手できるようになつたが,いずれも恒温槽を必要とし,大病院以外ではなかなか買つてもらえない。実際,医療機械店に頼むと数万円で,正確な攪拌装置つきともなると10万円近いし,大型で狭い診療所の検査机にはのらない。ところがデパートの熱帯魚の売場で買い物をして見ると数万円に相当する攪拌装置つきの美しい小型の恒温槽が何と3,500円位でただちにでき上り,その精度も0.5℃以内で日常診療には勿論,研究上にも十分役立つ。利用をおすすめする。
診断問答
左上腹部疼痛と強度の進行性頭痛を主訴とする患者の診断
著者: 高階経和
ページ範囲:P.612 - P.614
第1部
医師A—今朝は,病棟に特別変った症例もありませんが,実は,先生にお話ししようと思っていた厄介なケースがあつたんです。不幸なことに,昨夜その患者はなくなりましてね—。
医師B—病理解剖は,すみましたか?
薬のページ
TRASYLOL
著者: 佐久間昭
ページ範囲:P.560 - P.560
Trasylolはウシの耳下腺やリンパ節から抽出,分離された塩基性polypeptideであり,分子量は11,000〜12,000,16種のamino酸,約100コから成るという。等電点はpH9〜10である。
Trasylolはkallikreinの阻害剤として発展したものであるが,trypsin,plasrnin,chymotrypsinなどの蛋白分解酵素にも阻害作用を示す。したがつて,いわゆるplasma kinin類の生成阻害を示す。臨床的には急性の膵臓炎,とくに酵素活性の高い場合の治療に応用され,また,その予防にも利用される。その効果は,おそらく,kallikreinやtrypsinなどに対する阻害作用によるものと思われる。また,耳下腺炎にも応用される。
文献抄録
フィブリン溶解の治療への導入—Lancet, July '64より
著者: 外島英彦
ページ範囲:P.618 - P.619
血管閉塞の原因は数多くあるというのは疑う余地のないことだが,この症患をめぐつて脂質や食事や人種による相違や抗凝固剤やコレステロールを低下させる物質等々が論議の対象にされる中にあつて,フィブリン溶解という問題は無視される場合が多い。現在では血中に能動的フィブリン溶解機構が存在するという十分な証拠があり,フィブリン塊が血管から除去されるのはその機構の働きによるとするものはもはや推測の段階を脱したといつてよいだろう。ただここで,血液凝固とフィブリン溶解との間の動的平衝すなわち,フィブリンが時あつて血管に沈着するに違いないのだが,閉塞が起こり得ない事情の下では除去される運命をたどるというNolfの考え方を承認する必要はない。フィブリン溶解システムは生体内変化のもろもろの過程に一役を演じているのであつて,従来より血管内機能に注意を向けるあまりその役割を狭く限定しすぎてきた嫌いがある,というのが現今の趨勢的見解である。
それにしてもやはりフィブリン溶解は閉塞性血管病と重大な関連を有するものであり,治療に利用できる可能性のあることが明らかにされつつある。治療への導入には二つの方法があり,今酵素的方法,薬理的方法と称しておく。
ニュース
母子保健法制定の動き
著者:
ページ範囲:P.569 - P.569
中央児童福祉審議会の母子保健対策部会(部会長,木下正一氏)は,さる4月,厚相から諮問のあつた「未婚者,新婚者をふくめた母子保健対策」について討議をかさねていたが,3月中に4つの専門部会での結論をまとめ,厚相に答申する模様である。
母子保健対策部会での結論は,これまで保健所が中心になつて行なつていた母子保健行政を,キメ細かな行政にするため,市町村に移管すると同時に,現行の児童福祉法では,母性保健という面が欠けているので,未婚老,新婚者を含めた母と子の保健対策を一本化するため,「母子保健法」を新たに制定するという2点に重点がおかれている。
NEWS
家庭と医薬品,他
ページ範囲:P.576 - P.576
厚生省が,昭和38年10月に実施した「保健衛生基礎調査」の結果によれば,家庭と医薬品の状況はっぎのとおりである。
保健薬使用状況—保健薬を使つている者のいる世帯は,全体の36%で,事業経営世帯の47%,常用勤労者世帯の39%が多く,農業世帯は29%である。
--------------------
導尿のコツ
著者: 落合京一郎 , 日野志郎
ページ範囲:P.521 - P.521
〈潤滑剤を十分に〉
一私ども病院に勤務しているものは,たいてい,看護婦さんが導尿をするので,自分でなかなか手を出さない。ところが,開業していて,そういう患者さんが突然来られると,どうやつてよいかわからない。本でよんだ知識や,学生のとき習った知識なんかでやるんですが,どうもうまくはいらないことが多い。私,戦後しばらく開業をしておりました時の実感です。ある日,尿閉の患者が来まして,カテーテルを入れたんですが,どうしてもつかえてはいらない。しようがなくて近所の年とった開業の先生にお願いしてやっていただいたら,スポッとはいりましたね。いかにこちらの腕が悪いかを知つて恥をかきました。
その時,その先生が教えてくれたのは,まわりに潤滑剤のつけ方が足りないんだろうということでした。それから私も考えて,流動パラフィンを使うことにしたのです。注射器に流動パラフィンを入れておいて,つかえましたら,カテーテルにつないで注入します。こうやりますと,うまくはいりますね。何か他に方法はありますか。
基本情報
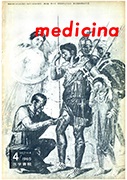
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
