医学と医療の違い
患者といえば,公衆衛生学上の潜在患者,つまり健康者らしいものまで頭にうかんでくるが,いまはそれをべつとして,診療をもとめてくる患者だけを考えても,これは大きな問題であつた。それこそ広義の社会医学,心理学,医療社会事業の範疇まで言及しなければなるまい。そしてそこに,医学と医療の相違が生じてくることになる。医学雑誌がこのような問題に視野をひろげてきたことは,たいへんな変化であり,進歩だと思う。やがて医学雑誌か医療雑誌かを区別するときが,やつてくる。こなければうそである。人はMedicinaという誌名をどのように理解しているのであろうか。
雑誌目次
medicina2巻5号
1965年05月発行
雑誌目次
EDITORIAL
患者の実態と医学および医療
著者: 野村実
ページ範囲:P.665 - P.667
今月の主題
高血圧とアンジオテンシン
著者: 山村雄一
ページ範囲:P.668 - P.671
古くから腎の病変があるときには,高血圧を伴うことが経験的に知られていた。腎性高血圧とよばれる症候群である。ところで腎の病変ということと,高血圧という症候群とはどのように結びついているかという問題は永い間わからなかつた。しかし近年にいたつて,その一部が解かれてきたといつてよい。その解決の鍵の一つがアンジオテンシン(angiotensin)である。
類白血病反応
著者: 服部絢一
ページ範囲:P.672 - P.675
白血球数が増えると,まず,白血病のみを考えがちであるが,類白血病反応をも念頭において,診断・治療をすすめたい。類白血病反応が白血病と誤診されたために基礎疾患の早期発見が見逃がされたり,死期を早めたりすることのあるのを,十分に注意しなければならない。
呼吸困難とモルヒネ
著者: 三瀬淳一
ページ範囲:P.676 - P.681
阿片から分離されるモルヒネは,たしかに急性肺浮腫などの苦痛除去には著効を示すが,すべての呼吸困難に適応するとは限らない。逆に禁忌とすべき症例も多い。呼吸困難の発生機序と,モルヒネの適応について反省した。
<話合い>Physical Diagnosis
著者: 阿部正和 , 高橋忠雄 , 日野原重明 , 小酒井望 , 佐々木智也
ページ範囲:P.682 - P.688
なにごとも"検査ばやり"の当今ではあるが,極端な検査へのもたれかかりについてはさまざまな反省と警告が,すでになされている。むしろより完全な検査を期するためにも,Physical Diagnosisの意味をさぐり,その方法を再検討することが,臨床医にとつてのこんにちの課題ではなかろうか。
診断のポイント
微熱
著者: 冨家崇雄
ページ範囲:P.689 - P.691
微熱の特性
「微熱」はいわゆる原因不明の発熱という状態の領域に属するものであつて,実地医家にとつてまことにやつかいな問題の一つである。
「微熱」とはどういう状態であるかを考えてみる。体温値としては38℃くらいまでを微熱として取り扱うという立場もあるが,微熱問題の核心となる体温の範囲は実際的には36.9〜37.0℃から37.5〜37.6℃くらいの間のものである。すなわち,統計的な正常体温分布の範囲を含んでいる点,患者の受診状態,その原因の解析の困難,などの点からみていちばん問題となり,一種独特の様相を呈する範囲である。さらにその原因が不明であるままに相当長期間微熱が継続するという特性をもつている。原病を指示すべき決定的な訴えや症状は明らかでないが,患者は一種独特な不安感を示す。不定の愁訴をもつている場合が多いが,そのおもなものは全身あるいは四肢の倦怠感,易疲労性,頭重感や頭痛,なんとなく胸苦しい感じ,腹部不快感や食欲不振,肩こり,顔面や躯幹上半部のほてり感,四肢のほてり感や冷感などである。
尿路結石と副甲状腺
著者: 藤田拓男
ページ範囲:P.692 - P.694
尿路結石と生体代謝異常
尿路結石は入類とともに古い疾患であつて,BC 5,000年と推定されているエジプトのミイラにすでに発見され化学的に分析されている。Hippocratesは尿路結石の外科的治療は専門医にまかすべきことを警告している。このことは現在も変わらぬ真理であるが,疾患の病態生理について深く考察するとともに,広く人体の全般の立場から正しい診断をくだすことを使命とする内科医にとって,尿路結石は,生体の代謝異常の重要な一つの断面として,容易に看過することのできない現象であると思われるのである。
尿路結石の85〜90%はカルシウムを含むといわれ,燐酸,炭酸,尿酸,修酸,チスチン,キサンチンなどとともに結石の主成分を構成するが,尿路結石の成立には尿中カルシウム排泄の増加のほかに,尿の種々の性状ことにpHの変化などいろいろの条件が必要なことは当然予測されるところであるが,臨床的な経験においては,原因の不明ないわゆる特発性結石がかなりの割合を占める実情である。Reddyらの238例の尿路結石症についての研究によると,85%は原因が不明であつて,11%が閉塞性腎疾患,7%が系統的疾患によるものであるという。
無酸症
ページ範囲:P.695 - P.697
治療のポイント 治療剤
ジギタリスの適応と禁忌
著者: 細田瑳一
ページ範囲:P.698 - P.699
強心配糖体ジギタリスを有効かつ安全に用いるためには,適応を十分にわきまえ,これに従つて使用しなければならない。ここではまずジギタリスの併用機序と適応禁忌について述べ使用の適切をはかる一助としたい。
生活指導
胃下垂症の生活指導
著者: 日野貞雄
ページ範囲:P.700 - P.702
胃下垂症の本態について
まずはじめに胃下垂症とはどんな疾患かということをのべておかねばならない。衆知のごとく,胃が下つているだけで胃下垂症という病名を与えるのは誤りといわねばならない。胃が下つているだけなら長胃Lang-magenというべきで,牛角胃や鈎状胃と同じように一つの胃型というべきであろう。胃下垂症の胃は下垂とともに緊張の低下をともなうことが条件になつている。つまり胃液分泌を除いた胃機能が低下しているということができる。
しかし私は胃下垂症は胃だけの病気とは考えていない。胃以外の腹腔臓器の下垂,これにともなう機能低下ということも当然ともなつている。たとえば大腸の下垂,アトニーは便秘という症状を現わし,胆嚢や腎臓の下垂は胆道ジスキネジーや遊走腎として症状を現わすことがある。
病名別による……
期外収縮
著者: 高安正夫
ページ範囲:P.703 - P.704
期外収縮の概念
期外収縮はまた早期収縮とも呼ばれ当然来たるべき周期より早期に異所性刺激により拍動をきたすもので,一般には下位中枢あるいは一般心筋より異所的に自働が発生しておこるものである。これに対して上位中枢の機能が低下して,それに比して下位中枢の自働能がこれを上廻るためにおこる補充収縮とは区別せねばならない。後者は徐脈があるか,あるいはそれより早いリズムの下位自働がみられるか,伝導がないために下位自働の収縮がみられるのに対し,期外収縮はリズムより早期に収縮がみられる。整調のリズムの間に余分の収縮がはいる場合を間入性期外収縮といわれるが,期外収縮のために正規の調律の時期には心筋が不定期にあるため1回休止するのが普通であり代償性期外収縮と呼ばれる。代償性休止があれば一拍が休止するので脈拍によつてもわかるが間入性の場合は脈拍のみではわからない。
他科と関連するもの
輸液の速度
著者: 浦壁重治
ページ範囲:P.705 - P.707
輸液計画
輸液の計画を立てるには,まず前提として患者の病歴,自他覚症,検査成績から体液異常の種類,欠乏量ないし過剰量,排泄予測量,心肺腎の予備力をつかむことが必要である。次にこれをもとにどんな輸液剤をどれだけ,どこから,どれだけの時間に輸液するかという輸液計画をねらねばならないが,ここではこの最後の問題を中心に述べてみよう。
グラフ
螢光染色による赤血球の検査
著者: 小机弘之
ページ範囲:P.654 - P.655
血液標本を螢光色素で染めると,白血球と栓球は螢光顕微鏡下で容易に螢光を放つが、正常の成熱赤血球はほとんど光らない。ところが貧血や中毒など異常のある場合の赤血球には,特有の螢光像を現わすものがある。螢光赤血球は古くより知られ(Keller & Seggel,1934),その螢光はポルフィリンの固有螢光に由来する。さらに.適当な螢光染色法を用いれば,網状赤血球1),2),3)好塩基点赤血球4),Heinz小体5)(芳香族ニトロおよびアミド化合物中毒で赤血球に出現する)などの検出が容易にできる。それらの手技はすこぶる簡単で,しかも検出能率ははなはだ高い。
螢光顕微鏡装置としては、まず強力な光源が必要で,これに青紫色系ガラスフィルターをかけ,顕微鏡では明視野集光器を用い,接眼フィルターには濃黄色系ガラスフィルターを用いる。油浸および標本の封入には最純流動パラフィンがよい。このようにして青紫色の半明視野で鏡検すれば,暗い正常赤血球もともに観察できるので,血球の計数にも便利である。
リンパ系造影法
著者: 入野昭三
ページ範囲:P.657 - P.659
リンパ系造影法はKinmonthの直接リンパ管内造影剤注入法の確立と適切な油性造影剤の出現によつて,近年その臨床応用が急速に広まり,すぐれたリンパ系異常検索法として注目をあびつつある。
まず色素patent blueを足背部栂指内側のところで皮下注射し,約30分後,青染されたリンパ管の走行に従つて1.5〜2.0cmの切開を加えてリンパ管を露出させ,スクリュー型手動注入器(図1)または微速自動注入装置を用いて,油性造影剤Lipicdol ultrafluide,あるいはPopiodol(DR-47)を,一側10ccずつ,10分間約1ccの速度で注入する。X線撮影は造影剤注入終了直後および24時間後に行なう。
光電比色計の使い方
著者: 斎藤正行
ページ範囲:P.660 - P.662
今日の医療でなくてはならぬものに検査があげられるが,その検査の必備品は光電比色計だという人もいる。それほどまでにのし上った光電比色計とはどんなものかは別頁(第70頁)にゆずるとして,その使用法を最も単純なしかし堅牢な方式(第1図)をとっている単光路直読によるLeitzの機器で説明することにする。
ファースト・エイド
心筋硬塞発作時のショック
著者: 日野原重明
ページ範囲:P.708 - P.709
心筋硬塞におけるショックの意義
心筋硬塞の急性期,すなわち,発病4週間以内に死亡するのは,聖ルカ病院の統計では約30%であるが,このなかでは最初の1週間以内の死亡が多い。
急性心筋硬塞の死亡は,発作直後のショックか,2週間以内の心臓破裂か,心室細動のためか,または急速に悪化する心不全かのいずれかであるが,このうち発病直後のショックはしばしば遭遇するものであり,またもつとも危険なものである。
器械の使い方
光電比色計の選び方
著者: 斎藤正行
ページ範囲:P.710 - P.711
光電比色計とは?
光電比色計とはある目的物質の呈色調を混在他呈色調から選別特異吸収し,さらにその目的物質の呈色波長の強さの減少を客観的,正確に指示する計測器械と定義づけられよう。ここに当然考えられる前提条件としては,第1に発色させるのに必要な化学分析基礎操作,第2に折角濃度差が正確に求められるのであるから,ピペットの正確な操作を初めとしての化学定量分析に習練していることがあげられる。したがつて単に光電比色計を一台購入してもそれら前提条件が満されてなければ本器は全く無用の長物で診療室の高価な飾り物と化してしまう。単に血液(清)や尿をそのままこの器械に入れてもほとんど何物もわれわれに語つてくれないのである。
ところが反面,化学定量分析に習練した人々にとつては本器は全く便利な存在で,大きな病院の化学検査室などでは全く奪い合いで1人の検査技師に1台はないと能率は非常に悪くなる。これは今日の血液成分の定量分析法のほとんどが測定操作の最後を本器による時代であるからである。
正常値
血小板—測定法による相違
著者: 山中学
ページ範囲:P.766 - P.768
血小板は,赤血球や白血球のように,ちやんとした血液中の有形成分の一つで,顕微鏡下にその姿をとらえることができるのに,その正常値となると人により,また測定方法によりまちまちな値が報告されている。
血小板は一旦血管外へ出ると,凝集粘着をおこし,また崩壊しやすいので,通常用いられる算定法で得られる値は,実際よりは少ないものであると考えられており,現在の測定法を用いて得られる数値のなかで,最も大なるものほど真の値に近いとさえいわれるのである。
メディチーナジャーナル 消化器
腹部症状を伴うSubacute Myelo-Optico-Neuropathy
著者: 松尾裕
ページ範囲:P.778 - P.778
米子市における昭和39年度消化器病学会秋季大会(会長石原教授)において東大中尾教授が上記の疾患について自験例90例とくに埼玉県蕨・戸田地区において多発した45例(中島病院)をもとにして特別講演を行なつたので,その概略について述べる。
本疾患は腹痛,下痢,著明な便秘,鼓腸,いちじるしい食欲不振,悪心嘔吐という腹部症状が単独あるいは組合わさつて出現し,その後脊髄炎症状主として下半身または上肢の知覚障害,運動障害,排尿障害または視力障害などが出現してくる症候群である。そしてその本態がウイルス性疾患であるのか,中毒性疾患であるのか栄養障害によるものか不明である。また外国において報告されている腹部症状を伴いやすいポリオ類似の疾患とも症状がかなり異つており,本邦に特異な疾患であると考えられている。日本では昭和36年ごろより注目され(三重大学高崎教授,山形県立病院清野博士,京都大学前川教授)以来かなり広範囲に日本各地に散発していることが明らかとなり昭和39年内科学会総シンポジウム(司会楠井教授)においてはアンケートを含めて日本各地に823例剖検24例とされ,その後も報告例がつづいている。しかし本疾患の本態が不明であり,一つの疾患単位とするか否かについても異論があり,まだ確定した名称もなく,報告者によつても,いろいろな病名によつて報告されている。したがつてこんにちその病態生理の究明が非常に期待されていたのである。
メティチーナジャーナル 代謝
Metabolic Myophathies—最近明らかにされた筋疾患
著者: 田崎義昭
ページ範囲:P.779 - P.779
近年,筋疾患の研究はいちじるしく進歩し,臨床的に興味深い知見が数多く報告されつつある。
このようなめざましい発展をとげた主な理由は,酵素学を主とした生化学的,組織化学的研究の進歩,電子顕微鏡による筋の微細構造の検討などによるものである。生化学的異常が明らかにされている筋疾患のうち,metabolic myopathiesと呼ばれているものに最近多くの関心が寄せられている。これには(I)骨格筋の解糖系代謝異常によつて起こるもの,(II)家族性周期性四肢麻痺,(III)mitochondriaの代謝異常によるものが含まれている。いずれも稀な疾患である。(I)は糖原病glycogen storage diseaseの一種で,先天的な酵素の欠損によつてグリコーゲンの代謝異常がおこり,myopathyを示すものである。このうちMcArdle病は1951年に初めて報告され,特有な筋症状を主症状としている。発病は小児期のものが多く,運動後に筋肉が有痛性の痙攣を起こす。硬直状態の筋を筋電図で調べると電気活動が完全に消失している。また上腕をマンシエツトで圧迫し,虚血状態にしておいて前腕,手の運動を行なわせ,肘静脈血の乳酸を測定すると,正常人では明らかに増加するのに,McArdle病では増加を示さない。しかも筋の硬直時にブドウ糖を静注すると症状が軽快する。
簡易臨床検査のやりかたと評価
尿中,血中ケトン体の簡易検査法
著者: 橘敏也
ページ範囲:P.652 - P.652
ケトン体検査の意義:高脂肪低含水炭素食,飢餓,糖尿病では,含水炭素の代わりに大量の脂肪が代謝にまわされる。その結果,脂肪の不完全燃焼が起こり,血中にケトン体ketone bodiesといわれるアセト酢酸,β-オキシ酢酸,アセトンが増してくる。これらケトン体が血中に増す(ケトン血症ketonemia)と血液はアシドージスに傾き,生体の機能はいちじるしく障害される。血中に増したケトン体は尿に漏れてくるので尿を検査することによつてケトン血症を知ることができる。
一般にケトン血症ではこれら新陳代謝障害のため重篤な症状を呈し,時宜をえた処置がなされないと生命は危険に瀕する。しかもそれを処置することによつてその症状のめざましい好転をきたすことができる。このようにケトン体の検査は診断と治療の確認に大きな助けとなる。しかも最近はケトン体の検査法はいちじるしく簡便化されたので,この臨床的意義の大きいケトン体の検査はもつともつと日常診療のなかにとりいれられるべきものと考える。ケトン体の検査はその目的からとりわけ敏感で,簡便なことを要する。検査法としては,こんにちnitropruside reactionがもつぱら用いられる。
ノモグラム
F. F.(濾過率)算出用ノモグラム
著者: 阿部裕
ページ範囲:P.645 - P.645
使用法:検査によつて求めたパラアミノ馬尿酸クリアランス(RPF)およびチオ硫酸ソーダクリアランス(GFR)をそれぞれ左右のスケールにとり,直線で結び中央斜線部分との交点を求めれば,これがF. F. すなわち(GFR/RPF)である。例えばRPF 600ml/minとGFR 120ml/minを結び交点を求めると0.20である。
臨床検査の盲点
1回静注によるクリアランス法
著者: 阿部裕
ページ範囲:P.777 - P.777
Van Slykeによつて提唱されたクリアランスの概念が,腎で特異的動態を示す数種の物質に応用され,腎血行動態の計測が容易に行なわれるようになつた。なかでも腎血漿流量(RPF)と糸球体透過量(GFR)は生理的意義が明瞭で,病的腎においても障害部位をよく反映した変化を示すので,現今ほとんどroutine testとして各検査室で行なわれている。
ところがクリアランスという一見高級な言葉とml/minといういかにも精密な感じを与える単位にまどわされて,何をさておいてもこの成績を信じこみ,極端な場合は少数点以下2桁まで有効数字を出している場合すらある。複雑な検査ほど検査誤差,測定誤差がはいりやすく,まして腎血漿流量,糸球体透過量など時々刻々と変化しているのであるからとうていこんな正確なデーターが出るはずはない。
統計
わが国民の栄養
著者: 滝川勝人
ページ範囲:P.712 - P.712
昭和38年度の国民1人1日当り栄養摂取量を,「国民栄養調査」の成績からみると,表1のとおりである。この栄養状態を,日本人として摂取しなければならない栄養基準量(表2,3参照)と比較してみると,ビタミンCの調理による損失を考慮すれば,含水炭素を除くほとんど全ての栄養素が不足状態にあるといえる。
食品群別摂取量においては,いま昭和30年の摂取量を100とした指数により,その年次推移をみると,図1のとおりで,食事の内容は遂年改善の方向にあり,殻類はすべての食品について減少し,いも類についても同様のことがいえる。また栄養的に重要な肉類,卵類,乳および乳製品などの動物性食品,および油脂類が著明に増加しており,全般的に殻類偏重の食生活傾向から脱却しつつあるといえる。
話題
γ-グロブリンの新しい命名法—第2回日本臨床代謝学会を聞いて
著者: 橋本信也
ページ範囲:P.772 - P.773
γ-グロブリンという名称は,1937年Tiseliusが電気泳動装置によつて血清蛋白質を5つの分画に分けることに成功したとき,易動度mobilityのもつとも遅い血清中のグロブリン分画に対し命名したものである。このものは長い間,単一の化学物質と考えられていたが,その後超遠心法や,免疫電気泳動法の導入によつて,γ-グロブリンにはいくつかの種類があり,機能もそれぞれ異なることが判つて,その不均一性heterogeneityという問題が論ぜられるようになつた。さらに近年になると,γ-グロブリンをパパインやメルカプトエタノールで分解するというような構造に関する研究が進んできて,その命名に統一性がなくなり,大きな混乱を生むに至つたのである。
1964年WHOでγ-グロブリンの命名を統一しようという試みが行なわれた。ときあたかも1965年3月7,8日第2回日本臨床代謝学会が,山村雄一教授の会長のもとに大阪で開催され,その中でガンマー・グロブリン異常症と題するシンポジウムがもたれたのである。そのシンポジウムの冒頭,京大ウィルス研の右田俊介博士はImmunoglobulinと題する講演の中で,γ-グロブリンの新命名法について解説され,聴衆に多大の感銘を与えた。
第2回思春期医学シンポジウムに出席して
著者: 江口篤寿
ページ範囲:P.702 - P.702
各科で取り組む思春期
身体面でも心理面でも,人間の一生のうちでもつとも変化の大きい時期とみられる思春期については,小児科,内科,産婦人科,泌尿器科,神経科などでとりくんでおり,また心理学の中でも重要な課題となつているので,これら各分野の研究者が一緒にあつまつて,この共通の問題について話し合いたいということから,群大・松本(産婦人科),群大・志田(泌尿器科),東大・古谷(産婦人科),東大・樋口(脳研),東大・茂手木(中検)諸博士らが発起人となって,38年11月に第1回のシンポジウムが行なわれたが,その節,特に話題の中心となつた「アクセル化」を次回のテーマにとりあげようと話し合われた。そこで39年12月5日,東京のエーザイ株式会社大ホールで行なわれた第2回の本シンポジウムでは,「思春期のアクセル化とその身体的ならびに精神的影響」についてのパネルディスカッションが企画された。これと同時に一般演題も募集されて,あつまつた演題は昨年とほば同じ21題で,所属科別には,内科6,小児科1,神経科5,産婦人科4(+1),泌尿器科2,衛生1,学校保建2(+1),外科(+1)〔カッコ内の数字は他科との共同研究〕となつていた。
北京科学シンポジウムに参加して—見たこと・考えたこと
著者: 久保全雄
ページ範囲:P.736 - P.736
シンポジウムへの不安
北京科学シンポジウムの呼びかけがあつたのは,開催前一年足らずだつた。その会議の準備期間があまりにも短かいことと,しかもその内容が,反帝国主義,反植民地主義の立場と,真に民族のためになる科学シンポジウムを,ヨーロッパ,ソ連,アメリカを除いて,文学から社会科学,自然科学を含む総合科学シンポジウムという,科学史上,かつてなかつたマンモス,シンポジウムで,参加者はかならず論文提出ということだつた。
このような莫然とした,科学シンポジウムに,どんな国からどのような学者が,どんな論文をもつて集まり,どんな形式で運営されるのか,かいもくわからず,果して成功するのかどうか,疑いをもつた。
症例
腰痛症のX線所見
腰椎椎間関節性腰痛のX線所見
著者: 恩地裕
ページ範囲:P.713 - P.715
腰背痛を起こす疾患
腰背痛という症状は臨床医ならば,内科外科を問わず,日常つねに出くわすものである。ところが,この腰背痛を起こしてくる疾患は非常に多く,その診断は専門医でも困難な場合が多い。ちなみに腰背痛を起こしてくる疾患のうち,脊椎に起因するもののだいたいを列挙してみると,変性性疾患として変形性脊椎症,骨粗鬆症,椎間板ヘルニア,椎間関節症など,炎症性疾患として脊椎カリエス,化膿性脊椎炎,リウマチ性脊椎炎など,また,転位がんを含む種々の脊椎腫瘍などが日常よく見られるものである。これらのうち,とくに腰背痛の原因として多く見られる腰椎椎間関節性腰痛について,そのレ線診断,ならびに治療について述べることにする。
腰椎椎間関節性腰痛(Facet Syndrome)は1933年GhormleyがFacet Syndromeとして報告して以来,注目されるようになつたものである。このFacet Syndromeの臨床症状は個体により,またその程度によりさまざまであるが,姿勢に関係した局在性の腰痛,従来,腰部捻挫として取り扱われたような激痛,大腿外側への牽引痛,しびれ感などを主訴とするものである。年齢的には30〜40歳がもつとも多い。Fecet Syndromeの他覚所見は,通常,第IV,第V腰椎棘突起の高さで脊椎の両側,あるいは片側に限局性の圧痛を証明することが多く,圧痛側に背筋の緊張を証明するのがふつうである。
他科との話合い
ビタミン—その適正な使い方
著者: 田崎義昭 , 吉川春寿 , 日野原重明 , 奥田邦雄
ページ範囲:P.753 - P.759
ビタミン剤が大量に生産されるようになつた今日,その生産のペースにまき込まれて乱用されているのではないか。この辺でビタミンの適正使用について反省してみよう。
基礎医学
日本人のビタミンの摂取量とビタミン剤—過剰ビタミンはどうなるか
著者: 小池五郎
ページ範囲:P.762 - P.765
臨床のお医者さんは,患者の症状の必要に応じて,あるいは患者に安心感を与えるという精神衛生上の観点から,いろいろのビタミン剤を投与する。そのときそこに含まれているビタミンの種類と量が,健康人の1日の所要量あるいは必要量に比べてどの程度のものであるか,ということを一応認識しておいたほうがよい。お医者さんご自身は,そういうビタミン剤は摂取していないことが多いだろうが,その場合,日常食においてはそれぞれのビタミンをどのくらいとつているか,ということぐらいは知つて,それと比較しながら,患者にビタミン剤を投与して,その効果を判定するという態度も必要であろう。
If…
夢をもつた研究目標を—元阪大総長成人病センター 今村荒男氏に聞く
著者: 長谷川泉
ページ範囲:P.722 - P.723
研究体制を確立したい
長谷川 勲一等瑞宝章の栄に浴されておめでとう存じます。多年,医学・教育界に尽瘁されましたことへの叙勲でたいそう意義のあることと存じます。さつそくですが,現在の医学研究の体制について,どうお考えですか。
今村 第16回日本医学会総会がすんでから感想みたいなことを書いたことがあるが,日本の医学研究に対して政府や一般の人が応援して研究費も潤沢にし生活も保障して,有能な医学者がある研究目標を相当長くゆつくり研究できるようになることを希望しますね。3年ぐらいの短期間しか研究費が出ないようではりつぱな研究はむつかしく,それをおし進めるには非常に大きな壁があるわけです。その壁を突き破るためには,相当時間をかけ,執拗にやらなければならないが,それには研究題目や方法の選びかたも必要だが,研究者が研究に没頭できるようにすることがたいせつです。研究報告はたくさんあつても,大阪の言葉でいえば,どえらい研究があまりないんで,画期的な研究を進めるには現在の体制では不満です。1人の医学者がいろんなテーマをあれこれたくさんやつて右往左往しているし,新しい方法が出るとそれを利用することだけを考えて,どつしりした研究が出ない。これは,研究者に与えられている条件がよくないからだと思うんです。
座談会
臨床病理医とはなにか—アメリカで学んだこと—日本に帰つて思うこと
著者: 小酒井望 , 米山達男 , 河合忠 , 竹田節
ページ範囲:P.726 - P.731
日本に帰つて感じたこと
小酒井(司会)きようはアメリカで臨床病理の専門医と申しますか,Clinical Pathologistという専門医の試験に通られて,その資格をおもちになつた先生方3人にお集まりいただいて,アメリカの臨床病理専門医というものは,病理なり臨床医学なりの面でどんな役割をはたしているか。それに比べてわが日本の現状はどうか。将来こういつた臨床病理専門医というものが日本でも当然育てられていかなければならないと思うんですが,その臨床病理専門医が将来の日本の臨床医学のなかでどういつたふうに育つべきか。またどんな役割をはたすべきか,そういつた未来図といつたようなものも考えながら,3人の先生方の経験を通して日本の臨床医学あるいは現在の医療といつたものに対しての,忌憚のない批判をいただけるとおもしろいと思うんですが,いかがなものでしようか。
米山 私,日本では東京第一病院でインターンをしました。そのころから小酒井先生からいろいろ教えていただいたわけです。で,インターンを終りましてから,米軍の406部隊総合医学研究所の病理に行きまして,2年おりました。そこではだいたいcytologyとtissue pathologyそれから57年にノースキャロライナのデューク大学というところへ行つて病理解剖をもう1年やりました。
海外だより
勤勉で競争意識の激しい研究者たち—ウイスコンシン大学生化学教室より
著者: 尾形悦郎
ページ範囲:P.724 - P.725
アメリカ一美しい大学都市
ウイスコンシン大学は,シカゴの北西,車で約3時間,4つの湖に囲まれた町,マヂソンにある。アメリカ一美しい大学都市,と人々はいう。事実,湖畔は,白い桟橋につながったさまざまなボート,木陰で読書する人,釣糸を垂れる人,はるか対岸に木々の間から見える州庁のドーム,葦の間を一列に進んで行くあひるたち,日の出,日沈の時,四季それぞれに飽かぬ眺めだが,ことに晩秋紅葉の時の美しさは,何に例えようもない。毎朝,大学の樹木林の中を遠まわりして研究室へ行くドライブは,異国での数少ない楽しみの一つである。
大学は,なかでも一番大きな湖,メンドウタ湖畔一帯を占める。州立大学の常として,高校卒業のだれでもが入学できるので,実に数万の学生が構内を右往左往しており,学期始めの昼時には,交通整理の巡査が立ち,大学周辺のキャフェテリアは満員で,昼ぬきとなる学生もでてくる。学期終り頃には大分淘汰され,卒業頃にはちようどよくなるという。クリスマス休暇には,この学生たちのほとんどが,サァーツとどこかへ消えてしまう。街は急に森閑となり,今度は,とり残こされたように居残っている外国人ばかりが,やたらと目につきだす。大部分が大学関係者で,日本人も二百人を越すというが,構内を歩くと,普段でも,おなじみのモンゴリアン系の風貌に何回となく,すれ違う。
私の意見
医療スペクトルと一般医
著者: 小倉敏郎
ページ範囲:P.721 - P.721
1964年のWHO特別委員会の報告は"一般医の継続的かつ綜合的治療は,個人,家族および地域社会の本来の要求に応ずるものであるから,すべての社会における医療サービスとして本質的機能を果し,かつ予知される将来に対しても,その機能を果しつづけることを確信する"とあるが,臨床医学の急激な進歩により疾病治療の様相が一変した今日,一般医の果すべき役割とは一体どんなものであろうか。
診断問答
胸骨下部の持続性疼痛を伴った患者の診断
著者: 高階経和
ページ範囲:P.774 - P.776
第1部
医師B--きようは,だいたい回診も終りましたが,ほかに珍しいケースでもありませんか?
医師A--そうですね。きようのところは,ざつとこのくらいです。
医療の自動化・2題
「診断過程の合理化」をめぐって
著者: 難波和
ページ範囲:P.780 - P.780
医療自動化の必然性
最近の日常の診療ことに診断過程を運用の面から考えるとき,つぎのような問題点があろう。
(1)周辺諸科学の進歩した理論や技術が急速に医学のなかにとりいれられ,主として臨床検査の面での諸種の業務が急増してきた。
心電図その他の自動診断機構について
著者: 野村裕
ページ範囲:P.781 - P.781
何が自動化の機運をもたらしたか
いわゆるHospital Automationの一環として,電子計算機を中心としたシステムが医療分野につぎつぎと導入されようとしている。アメリカではすでに実用化の段階にはいつているし,わが国でも以前からあつた理論的研究が,3年前にME学会の発足するころよりさらにさかんとなり,昭和40年度から文部省は電子計算機の医学への応用というテーマで全国各大学に科学研究班を組織させるほどの実状にまでいたつている。こうした機運は遅かれ早かれ一般医療機関へも滲透していくものと思われるが,何がこうした機運をもたらしたかについてここで反省してみる必要があろう。
質問と答え
50肩の治療
著者: 清原迪夫 ,
ページ範囲:P.782 - P.782
質問
46歳の男子,昨年秋ごろから右肩が痛みだし,最近ではその疼(うず)きのために,睡眠も妨げられ,衣服の着脱もできなくなり,来院しました。高単位ビタミン,ピラゾロン系薬剤,ザルブロなどを使用しましたが,著効ありません。
患者には,時期がくればなおるといつておきましたが,残る対策にはどのようなものがありましようか。(大阪市 K)
妊婦と副腎皮質ホルモンの大量投与
著者: 梅原千治
ページ範囲:P.783 - P.783
質問
最近,副腎皮質ホルモンを大量投与中の幼児に,多幸症と著明な肝腫大を認めましたが,妊婦に上記ホルモンを大量投与したさいに,胎児にいかなる変化が起こりますか?ご教示ください。
(一読者)
医学英語論文の書き方15
ニュース
議論を呼んだ新産業都市の保健計画
著者:
ページ範囲:P.734 - P.734
地域開発研究会(委員長 斎藤潔国立公衆衛生院長)は,昭和37年から,厚生科学研究費補助金の要望課題と,岡山県からの委託により,「地域開発における社会開発の策定」に関する研究を進めていたが,昨年11月末,その研究報告書を神田厚相に提出し,その後ただちに,これは神田厚相から佐藤首相にも報告された。
しかし,日本医師会は,この報告書を検討した結果,その内容には,共産主義路線による社会体制に直結する点,またはその基盤となりうる要素がきわめて多いとして,佐藤首相に対し,「この報告に盛られた考え方による社会開発の進展には全面的に反対する。政府においても,この点に関し慎重な御検討と御配慮を賜りたい」との要望書を提出した。
国民体位向上の基本的要綱案まとまる
著者:
ページ範囲:P.735 - P.735
政府は,かねてから河野国務相を中心に「国民の健康,体力増強に関する基本要綱」の作成を急いでいたが,さる12月14日,一応の原案がまとまつたので,自民党に提示したのち,党政調会で審議のうえ,党側の意向も加え,同月18日閣議で正式に決定した。
この要綱では,「国民のすべてが健康を楽しみ,ひいては労働の生産性を高め,経済発展の原動力をつちかい,国際社会における日本の躍進のいしずえを築くため,健康増進と体力増強をはかる」とその趣旨を述べている。
基本情報
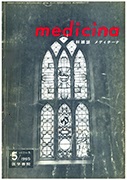
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
