腎臓の主要な機能の1つは,その排泄機能を介して,体液量や体液組成を調節したり,代謝産物や薬物などを排泄することである(図1).このような排泄機能のほかに,腎臓はまた臓器としても重要な働きをしている.腎臓は肝臓と並んで物質代謝全般に重要な役割りをはたしているばかりでなく,レニン・アンギオテンシン系,カリクレイン・キニン系,プロスタグランジン,ビタミンD3,エリトロポエチンなどのホルモンまたはオータコイドの産生臓器でもある.
腎臓を構成する基本単位はネフロンであるが,これは血管系と尿細管系とが糸球体を介在して密接に結びついたものである(図1).したがって,腎臓の機能も血行動態,糸球体濾過,尿細管機能の三者が密接な関連をもって維持されている.これら三者を含めた腎機能は腎臓自体の持つ自動調節能のほかに,神経やホルモン,オータコイドなどの体液性因子による微妙な調節機能によって調節されているのである.そこで,腎臓の機能を血行動態,糸球体濾過,尿細管機能の3つの面から基本的な事項を簡略に述べる.
雑誌目次
medicina21巻3号
1984年03月発行
雑誌目次
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
腎臓の生理学
著者: 今井正
ページ範囲:P.394 - P.398
検査の手順
尿沈渣
著者: 林康之
ページ範囲:P.400 - P.401
尿沈渣鏡検はベッドサイドテストである.採尿直後に尿定性試験紙を利用すると同時に沈渣も鏡検すべき検査項目である.鏡検による判定は慣れであって,決定できない細胞は結局のところ誰れにも判断つかぬものである.日常診療の片手間に鏡検をくりかえしていれば,外界からの混入物にしても,その診療所あるいは外来,病棟に特有のものであったりする.また,沈渣鏡検は形態分析であり,一種の探しもの的要素が強い.ということは,診療し,患者の訴えを聞いた医師が疑いを持って目的物を発見するために払う努力と,検査室で義務的に観察するのと,どちらが目的物発見の確率が高いかである.無論,前者に見落し,過誤は少ない道理である.また尿沈渣鏡検がベッドサイドで行われることにより,即座に得られる情報の価値は,翌日得られた同一情報よりは遙かに高い.以下技術的な簡易法を含めて検査手技を紹介し結果の評価を記す.
腎機能検査
著者: 椎貝達夫
ページ範囲:P.402 - P.403
「腎機能検査」の意味するところはきわめて広汎な項目であり,大きく分類しても,糸球体濾過量(GFR),腎血漿流量(RPF),尿細管機能(濃縮力,尿酸水化能等)に分れ,この各々がさらに細かく分れる.これら全般につき述べることは他書に譲り,ここでは日常の診療のなかで,①どの検査を重視すべきか,②dynamicな指標としてのとらえ方,に重点を置きたい.
画像診断
著者: 平松慶博
ページ範囲:P.404 - P.408
画像診断とは,X線写真をはじめとする種々のX線検査,超音波検査,核医学検査,さらに最近臨床に用いられはじめた核磁気共鳴(NMR)を用いた映像法などの診断法の,一つあるいはそれらのいくつかを組合わせて診断することである.最近総合画像診断ということが盛んにいわれるようになって来たが,いくつかの検査法の所見を組み合わせて判断することは,以前から行なわれて来たことであり,とくに新しい学問が形成されたわけではない.例えば,腹部単純写真1枚で診断できれば,それも立派な画像診断である.
しかし,X線CTと超音波検査の普及,NMRの出現などにより,多くの検査法をいかに有効に組み合わせるかも重要なことである.decision treeという考えはここから生れて来たものであるが,decision treeというものは,常に変化しつつあるものであり,また施設によっても,さらにそれぞれの医師の見解によってもかなり異なるものである.
本稿では各画像診断法について簡単に述べると共に,代表的な疾患におけるdecision treeの例を挙げる.
鑑別診断
糸球体腎炎
著者: 波多野道信 , 奈倉勇爾
ページ範囲:P.410 - P.411
糸球体腎炎の臨床像は蛋白尿,血尿,尿円柱などの尿異常,低蛋白血症,高脂血症,浮腫,高血圧,腎機能低下や血液凝固能異常などで,これらが組み合わさって一つの疾患をかたちづくるものである.本稿では,糸球体腎炎に共通する所見としての蛋白尿について,その病態生理について述べ,糸球体腎炎の鑑別点について述べてみたい.
間質性腎炎
著者: 宮原正 , 川村哲也
ページ範囲:P.412 - P.414
近年,各種抗生物質をはじめとする新しい薬剤の臨床応用が進むにつれ,drug hypersensitivityに基づく腎障害の頻度が増し,その免疫反応の場である腎間質の病変が注目されている.
間質性腎炎は糸球体腎炎と異なり,その主病変(炎症性細胞浸潤,浮腫,線維化)を腎間質に認める.しかし同時に,尿細管病変(変性,壊死)や尿細管の機能障害(体液,電解質,酸・塩基平衡の失調)を伴うことが多く,尿細管の機能と形態という面からも注目される疾患である.したがって今日では,tubulointerstitialnephropathyという名称が用いられることが多い.
腎盂腎炎
著者: 永瀬宗重 , 東條静夫
ページ範囲:P.416 - P.417
腎盂腎炎は一般細菌による腎盂・腎杯・腎実質の感染症である.歴史的には917年,Löhleinがpyelonephritisch Schrumpfniereの名のもとに,感染にもとづく腎病変を明らかにした時点まで遡ることができる.日常の診療活動の上で遭遇する頻度が高く,更に最近では本症の誘因として重要な膀胱尿管逆流現象(VUR)と予後不良な巣状糸球体硬化症(FGS)との関連もclose upされるに至っている1).
病原菌としては,大腸菌,肺炎桿菌,変形菌,緑膿菌が大半を占める.感染経路としては,血行性,リンパ行性,上行性感染がその大部分を占めている.誘因としては,尿路結石,尿管狭窄,VUR,留置カテーテルン等の局所的な因子と,妊娠,糖尿病,高血圧,カリウム欠乏状態などの全身的因子があげられる.臨床症状は,急性腎盂腎炎では,悪寒,戦慄,腰痛,側腹部痛等の定型的症候を呈し,その高い細菌尿の証明率からも比較的容易に診断しうるが,慢性腎盂腎炎の場合には,無床状のものから,全身倦怠感,易疲労性など不定の症状を伴うもの,あるいは消化器症状のみ強いものなどがみられ,診断には困難が伴う場合が少なくない.
ネフローゼ症候群
著者: 本田西男
ページ範囲:P.418 - P.420
ネフローゼ症候群(以下ネ症)は高度の蛋白尿,低蛋白血症を主徴し,浮腫,高脂血症を伴う症候群で,多くの原因,疾患によりおこる.その病態については,近年,腎生検の普及や腎生理学の進歩に伴い漸次明らかにされつつある.
腎血管性腎障害
著者: 国府達郎 , 高田泰治
ページ範囲:P.422 - P.424
腎血管性疾患は,持続的な高血圧を伴う疾患と持続的な高血圧を伴わない疾患に大別される(表1).前者には腎血管性高血圧の原因となる血管病変および高血圧の結果として生じる腎硬化症があり,後者には腎梗塞と腎静脈血栓症がある.
尿路閉塞性疾患
著者: 平塚義治 , 坂本公孝
ページ範囲:P.426 - P.427
尿路が閉塞をおこすと腎は種々の程度に障害されるが,閉塞をはやく発見し解除すると腎機能はかなり回復する.従ってその病態を十分理解しておくことは臨床上大切なことである.
尿路結石
著者: 高崎悦司
ページ範囲:P.428 - P.429
尿路結石の病態生理
尿路結石は尿中に存在するある種の晶質を主体として構成される凝固物であり,ほとんどが腎に発生し,その原基は尿細管のなかですでに形成されていると考えられるが,結石へと成長するのは腎杯や腎盂のなかであり,小なるものは尿とともに外部に自然排出され,大なるものが腎杯,腎盂あるいは尿管内に留って臨床症状を呈する.結石を構成する主な晶質として蓚酸,燐酸および炭酸のカルシウム塩,燐酸のマグネシウムアンモニウム塩,尿酸とその塩,シスチン,キサンチンなどがある.シスチン,キサンチン以外は正常でも尿中に,これらの晶質がしばしば過飽和に溶解しており,さらに濃度が高まると自然に析出するに至る.この濃度レベルでのそのイオン活動度積をformationproductと呼び,このレベル以下は過飽和状態ではあるが晶質の析出はおこらぬ準安定な領域(metastableregion)であり,尿中に存在する晶質析出を阻止する因子(inhibitor)の作用が想定されている(図1).また晶質が析出しない他の因子として,尿の速かな流れがある.
腎前性,腎後性腎不全
著者: 長瀬光昌
ページ範囲:P.430 - P.433
あたえられたテーマは腎前性腎不全と腎後性腎不全の鑑別である.この両者はほとんどが急性腎不全の形をとる.しかも腎前性腎不全は腎実質性腎不全へと移行するので,この点について留意することは肝要である.しかもこのばあい適切な治療により腎性腎不全への移行は予防できるので,その鑑別はすみやかに行う必要がある.
また以上の急性腎不全は必ずしも正常な腎に発症するとは限らず,軽度ないし中等度の慢性腎不全に併発したときはその診断には特別な慎重さを必要とする.
腎不全
急性腎不全—病因と早期診断
著者: 杉野信博 , 佐藤博司
ページ範囲:P.434 - P.436
病因
急性腎不全(ARF)の病因として最も多いものは腎前性であるが,近年腎毒性薬剤(とくに抗生剤,抗腫瘍剤など)による腎障害が増加して来た.表1はいずれの成書にも書かれている病因による腎前性,腎性,腎後性の分類と,それぞれの項の代表的なものを挙げた1).腎毒性の強い抗生剤としてはaminoglycoside(gentamycin,kanamycin,streptomycinなど),cephalosporine系が挙げられ,ことに腎疾患が既にある場合,幼弱児・高齢者,全身状態の不良な患者などには十分注意して使用すべきである.
急性腎不全—治療と予後
著者: 小林快三 , 小栗正光
ページ範囲:P.438 - P.439
急性腎不全の治療に対して,透析療法を使用しなかった時代には,①発症期,②乏尿期,③利尿期,④回復期という臨床経過をたどる.その時期々々に応じた原因,保存対症療法を行って,利尿のつくのをひたすらに待つといった受身の治療であった.しかし1960年代より透析療法の普及してくるにつれ,第一線の医師にとって,容易にその導入が決定されることより,急性腎不全(以下ARFと略す)の治療にたいする考え方に大きな変化をもたらした.しかしARFの病態の,早期発見と治療時期の開始がおくれれば,現在でもその死亡率は高くなることから,的確な病態の判断と,それに対する治療が予後を大きく左右することになる.そのためには,ARFの治療において,一般原則的な原因療法,保存療法を,上述の①,②の時期において,最善の処置をほどこしながら,積極療法としての透析療法導入の時期を早期に判断し,実行に移すことが最大のポイントである.
慢性腎不全—末期腎不全の病態と管理
著者: 原茂子 , 三村信英
ページ範囲:P.440 - P.442
腎機能が高度に障害されGFR(糸球体濾過量)が30%以下となると,代償不全状態(慢性腎不全)1)となり,生体のhomeostasis維持のために食事療法・薬物療法等が必要となる.さらに腎不全が進展し10%以下となると諸臓器病変による種々の臨床症状を呈し,いわゆるuremia(尿毒症,末期腎不全)1)となり,保存的療法のみでは困難となり透析療法が必要となる.しかし透析療法の発達に伴い,腎不全病態が明らかになるとともに末期腎不全の保存的管理も適切に行いうる.本稿では透析導入期症例を中心に,末期腎不全での病態とその保存的管理について述べる.
慢性腎不全—急性増悪と対策
著者: 上村旭 , 平沢由平
ページ範囲:P.444 - P.446
慢性腎不全の増悪には①腎不全を悪化させる合併症のための増悪,②原疾患の病態にもとづく腎不全の進行,の両面があり,透析療法を行わざるをえない場合も多い.しかし高齢化,複雑多様な合併症をもつ慢性腎不全患者の増加してきた現在,急性増悪期をのりきれば,しばらく維持透析療法を行わなくてもよい症例もしばしばみられ,治療可能な可逆性増悪因子に対して充分な検討と適切な治療を行い,むやみな慢性透析療法導入をさけるべきである(表1).
腎不全と薬物
著者: 折田義正 , 岡田倫之 , 阿部裕
ページ範囲:P.448 - P.451
腎不全時には感染症,高血圧,心障害,貧血,骨障害等を合併することが多く,これらに対して種々の薬物の投与が必要となる.腎は多くの薬物の主要な排泄経路であるため,体内へ薬物が蓄積する傾向にある.そのため腎不全時には副作用の出現しないよう,最適制御の一つとしての最適投薬法を確立する必要がある.最近,腎不全時には薬物の排泄障害だけでなく,吸収,分布,代謝などの障害,生体側の感受性の変化なども明らかとなって来た.本稿では,まず腎不全時の薬動力学的変化,および生体の変化について述べ,次いで腎不全時の薬物投与の実際について述べる.
透析
腹膜透析(CAPD)
著者: 太田和夫
ページ範囲:P.452 - P.453
CAPDはいうまでもなくContinuous Ambulatory Peritoneal Dialysisの略であり,日本語では持続的外来腹膜透析,携帯型腹膜透析などと訳されている.これは1976年米国のPopovich, Moncriefらにより着想されたものであり,1978年頃より一般治療として普及しはじめ,現在では欧米を中心に約18,000人の慢性腎不全患者がこの治療の恩恵を受け,家庭透析を行なっている.
血液透析
著者: 中川成之輔
ページ範囲:P.454 - P.456
血液透析の適応と導入
適応と禁忌 腎不全状態はすべて適応である.年齢と原疾患による禁忌はとくにない.ただし,長期慢性透析が予定されるものでは,治療の内容を理解できない精神疾患や痴呆状態のある場合は慎重に考慮する.乾癬や精神分裂病を適応と主張するものもあるが定説ではない.多発性骨髄腫,Goodpasture症候群,SLE,肝腎症候群の腎不全では,plasmapheresisを第一選択とするか併用する.
長期透析患者の合併症
著者: 今村典嗣 , 川口良人
ページ範囲:P.458 - P.459
透析療法の進歩は,長期生存症例を増加させているが,これに伴い合併症の存在が大きな問題となっている.ここでは,十分な透析を行うことにより,Ⅰ)改善されうる病態,Ⅱ)あまり改善が期待できない病態,Ⅲ)長期透析により惹起される新しい病態とに大別し,Ⅰ)については項目を挙げるにとどめ,Ⅱ),Ⅲ)について述べる.
質疑応答
腎不全の血圧管理をどうするか
著者: 小野山薫
ページ範囲:P.460 - P.460
高血圧に伴ってみられる腎不全は,高血圧性臓器障害の1つとしての腎機能障害(腎不全)と腎臓の種々の原発性病変(例えば糸球体腎炎,腎盂腎炎,間質性腎炎,嚢胞腎,水腎症など)が進行する過程でおこってくるそれとがある.その原因がいずれによるものであれ,高血圧は腎不全を進行させる最も大きな要因であるので血圧の管理は大変重要なこととされている.
腎不全に伴う高血圧はその発生機序から2つのタイプに大別される.1つは腎不全に起因する水・ナトリウムの貯溜が,体液量増加,循環血漿量増加,心拍出量の増加を介して,全身血管の自動調節機構(autoregulation)を作動させて抵抗血管を収縮し,血圧上昇をもたらす機序が考えられている.他の1つは腎不全によりもたらされる腎の虚血がレニン分泌を促進して,抵抗血管を収縮し,血圧上昇をもたらす機序が考えられている.前者は体液量依存性高血圧(volume dependent hypertension),後者はレニン依存性高血圧(renindependent hypertension)と呼ばれている.しかし個々の症例ではこの両方の機序が種々の割合で同時に関与している.腎不全例では水・ナトリウムは程度の差はあっても貯溜傾向を示し,一方レニン・アンジオテンシン系は体液量の貯溜に伴う抑制が不充分で,そのいずれもが血圧上昇に作用するといわれる.
悪性高血圧にβ遮断剤はどこまで増量できるか
著者: 多川斉
ページ範囲:P.461 - P.461
悪性高血圧とレニン分泌
著明な高血圧によって乳頭浮腫と細動脈の線維素性壊死を生じ急速に腎不全に進行する病態を,悪性高血圧と呼び,表に示す診断基準によって定義されている.本症は疾患単位ではなく症候群であり,本態性高血圧症のほかに,腎性高血圧など二次性高血圧症によっても起こる.悪性高血圧では一般にレニン・アンジオテンシン系が亢進している1).これは,著しい高血圧による血管病変が腎血流を減少させ,傍糸球体装置からのレニン分泌が増加するためである.レニン分泌の亢進はさらに血圧を上昇させ,悪循環が形成される.
アンギオテンシンⅠ変換酵素阻害剤の使い方
著者: 阿部功 , 尾前照雄
ページ範囲:P.462 - P.462
アンギオテンシンI変換酵素阻害剤(CEI)は,アンギオテンシンⅠ(AⅠ)から強力な昇圧物質であるアンギオテンシンⅡ(AⅡ)への変換を阻害すると同時に,降圧系ホルモンであるキニンの不活化を抑制する.したがって理論的には昇圧系の抑制と降圧系の活性化により降圧作用を発揮することになる.経口投与可能なCEIとして最初に開発されたカプトプリルは現在臨床的に応用されており,治験成績も豊富であるので,以下カプトプリルについて述べる.
膠原病腎障害のステロイド療法—用量,増減の目安
著者: 長沢俊彦
ページ範囲:P.463 - P.463
ループス腎炎
ループス腎炎のステロイド療法は,表に示す3つのパラメーターを参考にして,初期用量とその後の増減を決定する,これらの3つの異常すべてを備えている例には,プレドニソロン(PSL)40〜60mg/日で治療を開始するか,まずパルス療法を行なってその後療法としてPSL経口投与を行ってもよい.この初期大量投与期間は2カ月が限度と考える.
2カ月の時点で,これらの所見,とくに腎症候が改善してきていれば,2週間に5mgずつ減量する.2カ月の時点で,腎症候は改善しても免疫所見の改善のみられない例に対して,さらに初期投与量の継続や投与量を増やすことは,合併症の頻度を増す危険性があるので好ましくない.むしろ,免疫抑制薬の併用か,血清γ-globulinや血清IC量の高い例では血漿交換など,他の免疫抑制療法を加えるほうがよい.
ステロイド投与中に発熱をみたらどうするか
著者: 酒井紀 , 金井達也
ページ範囲:P.464 - P.464
腎臓病のなかでステロイド療法が適応となる主な疾患は,ネフローゼ症候群を呈する一次性糸球体疾患をはじめ,腎症状を伴なう膠原病やその近縁疾患,特にループス腎炎や結節性多発性動脈炎などであるが,このほか薬剤による急性間質性腎炎,稀れではあるが多発性骨髄腫やサルコイドーシスに伴う高カルシウム血症,あるいは腎移植後の拒絶反応の防止などである.
これらの腎疾患に対してステロイド投与中に発熱がみられた場合には,通常,3つの原因が考えられる.その第1は原疾患に対する長期のステロイド治療中に,ステロイド剤の重症副作用の一つである感染の誘発や感染の増悪を起こした場合.第2は原疾患のステロイド治療を中止あるいはステロイドの減量を急激に行なったために,ステロイド離脱症候群(withdrawal syndrome)をおこし,その全身症状として発熱した場合.第3は原疾患に対してステロイド治療を行なっているが,原疾患の増悪,再燃によって発熱した場合である.
糖尿病腎症の血糖調節のポイント
著者: 広瀬賢次
ページ範囲:P.465 - P.465
糖尿病性腎症(以下腎症と略す)における血糖調節は,腎症の進展を抑制する可能性に連なる点で臨床上重視される.以下その血糖調節のポイントを腎症非透析例について述べる.
腎炎患者の妊娠継続を決めるめやす
著者: 加藤暎一
ページ範囲:P.466 - P.467
妊婦死亡の半数となんらかのかかわりのある妊娠中毒症は,妊娠腎あるいはEPH-Gestosis(妊娠に関係したEdema-Proteinuria-Hypertension)と呼ばれるほどで,腎とかかわりが深い.腎疾患を有する患者が妊娠した場合には,早期から妊娠中毒症を合併する率が高く,しかも重症で,流早産の率も高く,母体の腎疾患の増悪をきたすこともある.近年多数例での機能検査と腎生検とを合せてのprospectiveおよびretrospectiveな予後調査の分析より,妊娠可能な腎炎の病型および程度が明らかになってきた.
表1は主として機能面よりの考察にもとづく1967年,表2は腎生検所見をも参考にした1981年に発表した我々の基準である.
腎機能が次第に低下する時腎生検をすべきか
著者: 大野丞二
ページ範囲:P.468 - P.468
腎機能が次第に低下する状態に接した時には先ずその腎機能低下の原因が腎前性か,腎性か,腎後性かの鑑別診断を行うことが重要である.腎前性では脱水や心不全等の合併で腎血流量の低下を来たすごとき病態が先行したり,腸管出血や代謝亢進でBUN上昇を見ることも少なくないし,腎後性で前立腺肥大症等尿流の障害を来す病態が存在する場合には先ずそれらの病態の除去を計ることが必要で,もちろん腎生検の適応ではない.
腎生検の適応となるのは進行する腎機能低下が腎性すなわち腎実質の疾患しかもびまん性腎実質疾患によってもたらされた場合である.最も腎生検の有用な疾患はネフローゼ症候群,慢性糸球体腎炎,膠原病性腎障害,原因不明のタンパク尿および血尿等であり,移植腎の病態評価の目的にも必須である.またアレルギー性間質性腎炎,急性糸球体腎炎,糖尿病性腎症,妊娠腎等の評価にも有用であるが,末期腎不全,嚢胞腎,水腎症,細菌性の急性および慢性腎盂腎炎,腎膿瘍,腎癌等は腎生検の適応とならないし,また重症高血圧や重症貧血の認められる場合も適応ではない.もちろん出血性素因を認める場合は禁忌である.
プラスマフェレーシスの適応が考えられる腎疾患
著者: 塩川優一
ページ範囲:P.469 - P.469
プラスマフェレーシスは新しい治療方法であり,現在なお研究の途上にある.
しかも,方法は現在急激に進歩しつつあり,そのために,適応疾患,実施法,その他について十分な検討が行われていない現状である.すなわち,実施方法として新鮮冷凍血漿を用いるいわゆる血漿交換(plasmaexchange)より濾過膜を用いる膜濾過法(membranefiltration)へと移りつつある.このような点を考慮しながら,実施すべきである.
活性型ビタミンD(1α(OH)D3)の投与法と検査
著者: 多久和陽 , 尾形悦郎
ページ範囲:P.470 - P.471
腎疾患の領域において活性型ビタミンD治療の適応となる疾患は主として慢性腎不全に伴なう骨病変(これらは腎性骨形成不全症renal osteodystrophyと総称される)である.血液透析の進歩,腎移植術の発展により,慢性腎不全患者の生命的予後が改善されるとともに,腎性骨形成不全症の管理は臨床的にますます重要な問題となってきている.本症の基本的な病変は組織学的には線維性骨炎(osteitis fibrosa)と骨軟化症(osteomalacia)である.近年のPTH,ビタミンDをめぐるCa内分泌学の進歩により腎性骨形成不全症の病態生理に関する理解はすすみ,二次性副甲状腺機能亢進症,活性型ビタミンDの欠乏,代謝性アシドーシスなどが本症の発症に関与することが明らかにされた.このように,慢性腎不全におけるビタミンD代謝異常の存在が明らかにされるとともに,合成活性型ビタミンDあるいはそのアナログが腎性骨形成不全症の治療に導入され,有効性が示された.現在わが国で,本症の治療に用いられている活性型ビタミンDは主として1α(OH)D3である.
腎機能を保護するための術前術後の注意
著者: 落合武徳
ページ範囲:P.472 - P.472
手術前の注意
手術前に腎機能検査を行って患者の腎機能を正確に把握し,時にかくれた腎機能障害をあきらかにしておくことは手術を安全に行うためのみならず,腎を保護する観点からも重要である.腎機能障害がある場合は手術術式の選択と限界,補液,抗生物質の選択に注意を払うことによって腎不全の発生を防止できる.術前にcheckすべき項目は一日尿量,尿比重,尿沈渣,尿蛋白,血清クレアチニン値,クレアチニン・クリアランス,PSP,血清電解質,血液ガス,acid base balanceなどである.
術前にあらかじめ脱水状態を補正し,腎血流量を増しておくことは,来るべき手術侵襲に対して腎を保護するうえで重要である.このために1日尿量を1000ml以上に保つように必要なら補液を行う.
腎移植の現状と問題点
著者: 東間紘
ページ範囲:P.474 - P.475
腎移植はこの数年著しく進歩し,臨床成績の向上には目をみはるものがある.ここでは日頃腎不全患者から相談をうける機会の多い内科医にとって,少しでも参考になればと思い,わが国の腎移植の現状についてごく簡単に記すことにしたい.
カラーグラフ 臨床医のための血液像
白血球増多症(1)
著者: 原芳邦
ページ範囲:P.478 - P.479
CBC(complete blood count)にて白血球数の増加が見られた場合,その分画を知ることはきわめて重要である.今回は顆粒球系の増加した場合を取りあげた.
グラフ 胸部X線診断の基礎
撮り方と読み方(3)
著者: 新野稔
ページ範囲:P.493 - P.500
胸部X線写真の観察方法について述べ,基礎的解説として増感紙をとりあげる.フィルム特性を最大限に発揮させるには,増感紙とX線フィルムとの組合せを考える必要があり,増感紙の作用・特性・種類ならびにその取り扱い上における注意事項にふれる.
複合心エコー図法
先天性心疾患(3)
著者: 伊東紘一 , 鈴木修 , 柳沢正義
ページ範囲:P.488 - P.490
症例3 2歳,男児
38週,3,400g自然分娩の男児.出産後まもなく口唇チアノーゼが出現し,心雑音を指摘された.生後10カ月に肺炎のため入院治療をうけている.その後哺乳も良く,チアノーゼやsquattingを認めるが,経過観察を続けていた.心音は収縮期雑音(3/6)がharshで,3LSBが最強点である.拡張期雑音なし.CTR≒58%,心電図でRVH.RAD,RA負荷所見である.Clubbing fingerを認める.
プライマリ・ケア プライマリ・ケアに必要な初期臨床研修とその現状・2
ローテート臨床研修の現状と将来像
著者: 鈴木俊一 , 箕輪良行 , 坂本健一 , 荒川洋一 , 藤井幹久 , 吉新通康 , 細田瑳一
ページ範囲:P.507 - P.514
はじめに■
医学部を卒業し毎年国家試験に合格する者は6000人を超え,研修病院の不足が訴えられている.
典型的な卒後の生活設計の一例を考えてみると以下のようになる.卒業して出身大学の内科に入局した.第一内科は消化器と内分泌が主な主題である.受け持ち患者は多くても5人,血液疾患・神経疾患は扱うことはほとんどない.第二内科・第三内科との交流もほとんどない.大学での一年の研修も終わり,当人は内視鏡の技術と糖尿病の治療には或る程度の経験もできる.2年目は医局からの派遣により市民病院での研修であった.受け持ち患者は10人を超え,疾患の種類もやや広範囲のものとなった.3年目には大学の医局にて研究活動に入った.7年後学位も得て公立の病院へ消化器内科医として勤務.10年の勤務の後,自分より若い大学の講師が部長としてきた機会に,42歳になり内科・小児科をかかげて団地入口に開業した.一般に医師の勤務様式の統計でも40代で勤務医師と開業医師の数が逆転している(図1).多くの場合専攻した科目だからということで標榜科目を決め(図2),開業することになるが,実際の患者は一般診療所または病院として受診するので,内科系老人,小児中心の診療となっており,不本意な診療となる場合もある(図3).このような不本意な専門外診療をなくすためにも,ぜひ住民一般にニードの高いプライマリ・ケア(PC)医の教育とPC医としての専門性の重要性が強調されるべきである.
講座 図解病態のしくみ びまん性肺疾息・3
間質,実質病変および肺血管病変と機能障害—肺の間質病変,実質病変と肺機能異常
著者: 堀江孝至
ページ範囲:P.517 - P.523
前回までは気道閉塞を検出するための肺機能検査についてのべてきた.今回は肺の実質,間質がびまん性に傷害された時,肺機能の面からどのようにとらえるかを主に解説し,さらに肺の血管病変に対する機能検査について簡単にのべてみる.
Oncology・3
抗腫瘍剤—Ⅱ.代謝拮抗剤(1)
著者: 北原光夫
ページ範囲:P.525 - P.530
Cytarabine(Cytosine Arabinoside,Ara-C,Cyloside®)
Ara-Cは,急性骨髄性白血病の治療に重要な進歩をあたえた抗腫瘍剤である.白血病に対して,Ara-Cの開発前まで寛解率が10〜30%程度であったものを,Ara-Cのみで30〜50%の寛解率へと長足の進歩をとげた.Ara-Cは急性骨髄性白血病に効果があるが,慢性骨髄性白血病の急性転化や急性リンパ性白血病には効果が劣ることがわかっている.また,分裂をさかんにしている細胞に効果があることを考慮すると,固形癌の治療にはむいていない抗腫瘍剤である.
小児診療のコツ・9
黄疸
著者: 川名嵩久
ページ範囲:P.531 - P.535
小児科における黄疸はほとんど新生児期および乳児期早期にみられる.大部分の新生児が生まれてまもなく生理的黄疸を,また母乳栄養のものは引き続いて母乳黄疸を経過する.
これらは特別に病気扱いをしないでよいことが多いが,これらに隠れていろいろの種類の重症の黄疸が相当の数発症する.それゆえ,いつもこれは病的黄疸ではないかと注意していなくてはならない.
演習
目でみるトレーニング 79
ページ範囲:P.481 - P.487
ベッドサイド 臨床医のための臨床薬理学マニュアル
ジゴキシン
著者: 越前宏俊 , 辻本豪三 , 石崎高志
ページ範囲:P.501 - P.505
■適応
1.禁忌の場合を除く「心不全」.
2.心拍数の早い(>100拍/分)心房細動(atrial fibrillation),心房粗動(atrial flutter).
CPC
肺結核治療後,右下腹部に腫瘤が出現,急速に増大してイレウス症状を呈した46歳男性
著者: 沢田勤也 , 鈴木勝 , 大谷彰 , 長尾啓二 , 浅田学 , 斎木茂樹 , 吉沢煕 , 奥田邦雄 , 高橋力 , 原繁 , 登政和 , 林光雄 , 石毛憲治 , 鈴木良一 , 松嵜理 , 関保雄 , 近藤洋一郎 , 岡林篤 , 金子治夫 , 蛇沢晶 , 伊藤隆 , 中村和之
ページ範囲:P.549 - P.567
本CPCはさる11月19日に旭中央病院で行われた第92回旭市・海上郡医師会 旭中央病院共催のCPCを旭中央病院の御好意により掲載させていただいたものです.
診療基本手技
胸腔穿刺,胸腔ドレーン挿入
著者: 笠井健司 , 長野博 , 西崎統
ページ範囲:P.536 - P.538
臨床研修の初期に修得しなければならないベッドサイドの必須の手技の1つとして,胸腔穿刺がある.今回はその胸膜腔への穿刺およびドレナージをとりあげ,その手技のポイントを要約してみた.当院では胸腔穿刺の場合は内科レジデント独自で,ドレーン挿入の際は胸部外科医の指導のもとに行っている.
当直医のための救急手技・泌尿器系・3
陰嚢腫脹,排尿痛,血尿,その他
著者: 村上信乃
ページ範囲:P.544 - P.545
陰嚢腫脹
陰嚢の腫脹を生ずる疾患の鑑別診断の進め方を前回と同様に図示してみた(図3).
疼痛,発熱のない場合
用手で腫脹した陰嚢を腹腔に向って圧迫することにより,腫脹がなくなれば,①鼠径ヘルニアである.緊急性はないが,外科医の診察が必要でる.
新薬情報
シスプラチン(cis-platinum)—商品名:ランダ注Randa〔日本化薬〕—制癌剤
著者: 水島裕
ページ範囲:P.546 - P.547
概略
シスプラチンは白金化合物で,ユニークな制癌剤であり,これまでのどの制癌剤とも異なった構造,異なった性質をもち,しかも強力な効果を有する.白金化合物に,抗菌作用,抗リウマチ作用などのあることが知られていたが,1960年代,大腸菌の分裂増殖をシスプラチンが抑制し,これが主としてDNA合成による作用であることが見出され,次第に悪性腫瘍の治療薬として研究が進んだ.シスプラチンは,すでに米国やヨーロッパ各国で市販され,副作用の多いことに問題はあるが,強力な抗悪性腫瘍剤として認められ,最近の制癌剤の中では,その効果が強いことで画期的なものである.
臨床メモ
肺炎の診断
著者: 北原光夫
ページ範囲:P.516 - P.516
肺炎の診断は,原因菌による分類(viral,mycoplasmal,bacterial),起こりかたによる分類(communityacquired vs hospital acquired),さらにX線・病理的分類(lobar vs interstitial)などによってなされ,治療の指針を得ることができる.
肺炎の診断と治療において有意義なポイントの1つは,肺炎が入院中に起きたか,あるいは病院の外で起きたかということである.つまり,院内感染と院外感染では原因菌が異なるからである.院外感染による肺炎の大部分は肺炎球菌とマイコプラズマによってひき起こされるが,他にインフルエンザ菌,ブドウ球菌も忘れてはならない原因菌である.溶血レンサ球菌による肺炎は稀である.グラム陰性桿菌による肺炎は院内感染が大部分であるが,肺炎桿菌(Klebsiella pneumonlae)による院外感染の肺炎があることは念頭におく必要がある.
面接法のポイント・3
面接の基礎(2)
著者: 河野友信
ページ範囲:P.542 - P.543
2)医療における人間関係
医療における人間関係は非常に重要である.その治療関係は陽性のプラシーボ効果のような好ましい効果をもたらす.逆に悪い治療関係は医療を阻害することが多い.その端的な例は医療訴訟であるが,面接場面でのことばのやりとり一つが,態度や仕草の一つひとつが治療関係に関ってくる.医療における人間関係にはつぎの5つがある.
天地人
岩倉使節団とウイーン
著者: 犬
ページ範囲:P.540 - P.541
第13回国際化学療法学会が開催されたのを機会に,7年ぶりにウイーンの都を訪れた.
欧米先進諸国の制度,文物の調査と幕末に結ばれた不平等条約改正の予備交渉を目的にした岩倉使節団一行50余名は,明治6(1873)年6月ウイーンに滞在している.欧米での学会のたびに岩倉使節団の旅路を辿って来たが,今回も学会の余暇をみて,岩倉使節団の足跡を辿っての汽車の旅を楽しんだ.
基本情報
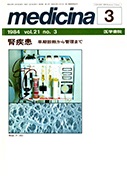
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
