本号では腎疾患をめぐる最近の進歩,話題などを中心に特集を組んでみた.いわゆる「腎臓病学」は,腎実質に病理学的所見を伴う疾患群,たとえば糸球体腎炎,間質性腎炎,糖尿病などと,いわゆる「水・電解質,酸・塩基平衡の異常」というテーマも含まれることが多い.とくに欧米でその傾向がより顕著のように思われる.たとえば,代表的な腎臓の教科書,専門書としてBrenner and Rectorの"The Kidney"(Saunders),Straus and Weltの"Diseases of the Kidney"(Little,Brown),最近出版されたSeldin and Giebischの"The Kidney;Physiology and Pathophysiology"(Raven Press)など,どれをとってもいわゆる腎臓病のみでなく,水・電解質代謝が大きなスペースを占めている.
本邦では腎臓の病気は,腎臓病学として,水・電解質代謝の調節,病態生理とはまったく別に扱う傾向があるようである.これは欧米,とくに米国と本邦でのNephrologyの臨床,研究などの歴史的な違い,また教育,研究,研修カリキュラムなどの違いによるものかもしれない.
雑誌目次
medicina22巻10号
1985年10月発行
雑誌目次
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
理解のための10題
ページ範囲:P.1826 - P.1828
EDITORIAL
腎疾患—最近の展開とトピックス
著者: 黒川清
ページ範囲:P.1730 - P.1731
糸球体腎炎:臨床と診断
溶連菌感染後腎炎
著者: 荒川正昭 , 深川光俊 , 甲田豊 , 丸山雄一郎 , 鈴木亨 , 荻野宗次郎
ページ範囲:P.1733 - P.1735
溶連菌感染後急性糸球体腎炎(Streptococcus-related, postinfectious acute glomerulonephrits or post-streptococal acute glomerulonephritis;PSAGN)は,A群β溶連菌による上気道あるいは皮膚感染の後,1〜3週間の潜伏期をおいて急性腎炎症候群(acute nephritic syndrome)を示す原発性糸球体疾患である.急性腎炎症候群とは,比較的急性に発現する血尿,蛋白尿,浮腫,高血圧,糸球体濾過値の低下などを示す症候群である.
IgA腎症
著者: 富野康日己
ページ範囲:P.1736 - P.1738
IgA腎症は,1968年フランスのBergerによって初めて報告された疾患で,わが国に高頻度に認められる慢性糸球体腎炎の1つである.その特徴的な螢光抗体法的所見は,腎糸球体メサンジウム領域へのIgAと補体C3の顆粒状沈着である.こうした螢光抗体法的所見を呈する疾患にはIgA腎症の他に,Henoch-Schoenlein紫斑病性腎炎,SLE,肝性糸球体硬化症などがあり,最近これらを一括して"IgA腎症症候群"として扱う傾向も認められる.しかし,Bergerの提唱したIgA腎症(いわゆるBerger病)は,原発性慢性糸球体腎炎の1つとして確立されており,これらの疾患とは区別される.
本稿では,"IgA腎症"の臨床的,病理組織学的特徴と治療の新しい試みについて概説する.
膜性腎症
著者: 西忠博
ページ範囲:P.1740 - P.1742
定義
膜性腎症(membranous nephropathy,以下MN)は糸球体基底膜(GBM)上皮下に広汎に(diffuse and global),免疫複合体(immune complex,以下IC)と思われる沈着物が存在することを形態的な特徴とする糸球体腎症であり,多くはネフローゼ症候群を呈する.MNの大部分(約70%)は,その病因がまったく不明で特発性(idiopathic)と呼ばれる.残りの約30%は多くの疾患や病態と関連して発現し,二次性(secondary)と呼ばれる(表)2).
ただし二次性のMNでも沈着しているICの抗原が同定されているもの(たとえばHBe-Ag,DNA)は例外的で,多くは推定によっている.以下,特発性のMNについて述べる.
リポイドネフローシス
著者: 成田光陽
ページ範囲:P.1743 - P.1745
歴史と概念
腎疾患の分類は研究者の数ほどあるといわれるが,これは大袈裟にしても,ネフローゼなる病型の取り扱いほど変遷をきわめたものは腎疾患のうちでも少ないと考えられる.
1827年Brightにより腎疾患の概念が出されてより,その本態が多元的であることが気付かれ,1905年にはMüllerによりnephritisとは異なる炎症性病変のない,変性性病変をもつブライト病をnephroseなる概念でまとめることが提唱された.
巣状糸球体硬化症(FGS)
著者: 酒井紀 , 金井達也
ページ範囲:P.1746 - P.1747
巣状糸球体硬化症(focal glomerulosclerosis;FGS)の病像は,Rich(1957年)がlipoid nephrosisと考えられた小児の剖検例のなかに,旁皮髄境界の糸球体から皮質表層に波及していく巣状糸球体硬化像を認めた20例に,糸球体硬化を伴うlipoid nephrosisの亜型と記載してから注目されるようになった.Hayslettはその後,本症を"malignant course"をたどるlipoid nephrosisの特殊病型と報告したが,1970年Churgらは本症をlipoid nephrosisとは別個に扱い,steroid抵抗性を示し,多くは腎不全へ進展する独立疾患と定義してfocal glomerulosclerosisと名づけた.
FGSはこのように特異的な巣状分葉性の糸球体硬化像を呈し,臨床的にも難治性のネフローゼ症候群を呈する疾患と考えられてきたが,しかし本症の診断には,腎生検法という制約された材料で巣状病変を診断するには限界があること,さらに,FGSの病像が他の腎疾患でも認められることなどから,本症の疾患概念に混乱が認められる.以下,一次性ネフローゼ症候群のなかで形態的にfocal segmental hyalinosis and sclerosisを呈する症例に限定して,FGSの病態像について述べることにする.
膜性増殖性腎炎(MPGN)
著者: 小林修三 , 長瀬光昌
ページ範囲:P.1748 - P.1749
膜性増殖性腎炎(membranoproliferative glomerulonephritis;MPGN)は,基本的には組織学的概念として把握されている.一方,臨床的には,治療に抵抗しつつ慢性に経過する予後不良の腎炎であり,多くがネフローゼ症候群と低補体血症を伴うことが特徴である.頻度は,原発性糸球体腎炎のうち約2%と,比較的稀な疾患である.本症は,電顕所見をもとに3型に分けられているが,以下,その中心となるtype1について述べ,最後に簡単に他の型について記載する.
全身性疾患と腎:発生病理と臨床
全身性エリテマトーデス(SLE)
著者: 長沢俊彦
ページ範囲:P.1750 - P.1751
ループス腎炎の発生病理
ループス腎炎は,流血中のDNA-抗DNA抗体を主とする免疫複合体(IC)が糸球体の内皮下,上皮下,メサンギウムのいずれか1個所,もしくは複数個所に沈着することが発症の第1段階と考えられる.SLEはB細胞の機能亢進により抗DNA抗体,その他の自己抗体の産生増加,ひいてはICの産生の亢進が根幹にある疾患であると同時に,補体によるIC可溶化能の欠陥と網内系機能不全によりIC処理能力が低下して,流血中にICが停滞しやすい条件も一方では整っている疾患である.一方,動物実験で流血中のICは,charge,sizeなどの条件さえ整えば,上皮下,内皮下,メサンギウムのいずれの部位にも沈着せしめうることも明らかにされている1).しかし,SLEの糸球体内のICがDNA-抗DNA抗体のICのみであるとはまだ言い切れないし,すべての流血中のICが糸球体に沈着するわけではない.
一方,最近膜性腎症の動物モデルを中心として,in situ IC形成説が盛んである.ループス腎炎の中にも膜性腎症型があるし,最近のモノクロナール抗DNA抗体を用いた研究では,DNAは糸球体基底膜の主要polyanionであるproteoglycanと親和性のあることが明らかにされている2).
糖尿病
著者: 大沢源吾
ページ範囲:P.1752 - P.1753
糖尿病性腎障害は病理学的な立場からみると糸球体硬化症のほか動脈硬化症,腎盂腎炎など,多彩なものが含まれるし,実際例についてみるとこれらの病変のいくつかが混在してみられることも多いが,ここでは糖尿病に特異性の高い糸球体硬化症を中心にとりあげる.
ウイルス性肝炎
著者: 小出輝
ページ範囲:P.1754 - P.1756
B型肝炎ウイルス(HBV)の関連抗原の持続陽性の慢性肝疾患患者あるいは無症候性キャリアに糸球体疾患を発症することがあり,HBV腎症と呼ばれている.
HBV感染に伴う腎症が初めて報告されたのは1971年Combesらによってである.53歳の男で血清肝炎に罹患後HBs抗原陽性が持続し,ネフローゼ症候群を呈した.腎組織所見は膜性腎症で,蛍光抗体法でIgG,C3とともに,HBs抗原の沈着を係蹄壁に認めたことから,HBs抗原が原因と考えられた.Slusarczykらは血清HBs抗原陽性の膜性腎症患者の約1/3にHBc抗原の糸球体沈着を報告し,HBc抗原が原因としている.1979年武越らは11例の小児HBV腎症について検討し,組織像はすべて膜性腎症で,血清HBs抗原は陽性であるにもかかわらず,腎にHBs抗原を検出できず,HBe抗原を証明し,原因としてのHBe抗原の重要性を強調した.次いで雨宮らはHBs抗原陽性者に伴う膜性増殖性腎炎Burkholder type IIIについて,腎糸球体にHBe抗原とともにHBs抗原の沈着を報告した.
癌,悪性リンパ腫
著者: 深川雅史 , 黒川清
ページ範囲:P.1758 - P.1760
癌,悪性リンパ腫の患者では,その経過中に治療に伴うものも含め,さまざまな腎病変が発生し(表1),その認識と管理は患者の予後にとって重要である.ここでは,その中よりいくつかを選び解説する.
痛風
著者: 原茂子 , 三村信英
ページ範囲:P.1762 - P.1763
痛風は,尿酸代謝異常に基づいて,腎障害,動脈硬化症,高脂血症などの合併症をみる全身性代謝性疾患として確立されつつある.
痛風腎による尿毒症死は,40%を占めている1).近年,高尿酸血症に対する治療法の発達により,早期より適切な治療の継続にて,腎不全への進展が予防可能となっている.本稿では,痛風腎の病態,臨床像および治療に関して述べる.
付)妊娠と腎
著者: 阿部信一
ページ範囲:P.1764 - P.1765
内科的な慢性疾患をもっている女性の妊娠をどう扱ったらよいかは,臨床家にとって重要な問題の1つである.検診,とくに検尿の普及により潜在型の慢性腎疾患が比較的早期に発見されるようになったため,このような腎疾患患者の妊娠可否の判定を内科医に依頼される機会が多くなりつつある.したがって,正常妊娠時にみられる腎を中心とした解剖学的ならびに生理学的変化について理解しておくことは,的確な判定を行うためにもきわめて大切である.
尿細管疾患:病態生理に関する進歩
遠位尿細管性アシドーシス
著者: 佐々木成
ページ範囲:P.1766 - P.1767
腎尿細管での尿酸性化能
近年,尿細管のネフロンセグメントでの尿酸性化(H分泌)の動態が明らかにされつつある1).図1にその概略をまとめたが,H分泌量は近位尿細管で最大であり,遠位尿細管のセグメントにおいてもある程度認められている.近位尿細管では分泌されたHはHCO3再吸収に使われ,遠位尿細管では分泌されたHは滴定酸,NH4となり尿中に排泄される.前者の障害が近位側(proximal)RTA(renal tubular acidosis,尿細管性アシドーシス)であり,後者の障害がdistal RTA(遠位側RTA)である.
Bartter症候群
著者: 藤田敏郎
ページ範囲:P.1768 - P.1769
1962年,NIHのBartterらによって,5歳と25歳の黒人に,高アルドステロン血症,低K血症,アルカローシス,腎の傍糸球体装置の過形成を認めた症例を,新しい症候群として最初に報告がなされた1).当初,本症候群の診断基準として,①血漿レニン活性の上昇,②アルドステロン分泌増加とそれに由来する低K血症性アルカローシス,③アンジオテンシンIIに対する昇圧反応の低下,④腎傍糸球体装置の過形成と肥大,⑤正常血圧,⑥浮腫のないこと,の6項目があげられた(表).
Bartter症候群は,二次性アルドステロン症の1つであり,アルドステロンの産生増加によって低K血症を呈する症候群である.一般に,二次性アルドステロン症は,浮腫や腹水を伴う疾患や,腎血管性高血圧症のような高血圧を伴うものが大部分を占めるが,Bartter症候群は浮腫も高血圧もないのに,レニン・アンジオテンシン・アルドステロン(R-A-A)系の亢進があるという点で,きわめて特異な疾患であるといえる.
家族性低リン血症性ビタミンD抵抗性クル病
著者: 清野佳紀
ページ範囲:P.1770 - P.1773
概念
本症は著明な低リン血症とクル病(骨軟化症)を示す,いわゆる症候群である.小児ではクル病として発見されるが,成人では骨軟化症を示す.1937年Albrightらは,本症がビタミンDに抵抗性を示す疾患であり,その結果,腸管におけるCa吸収が低下し,そのためPTHの分泌亢進をきたし,低リン血症をきたす結果,クル病を発生するという仮説をたてた.しかしながらその後,RIA法(radioimmunoassay)によりPTHを測定してみると,本症では血中PTH濃度は正常ないし軽度に上昇しているのみであり,しかも血中PTH濃度が上昇している症例では,治療として経口的にリン酸塩の投与を受けている場合が多いことが判明した.さらにArnaudら,Lewyら,Fanconiら,筆者らはすべて本症のPTH濃度を正常と報告している.
したがって現在,本症は先天的なリン転送障害が主因とされており、とくに腎尿細管と腸管におけるリン再吸収ならびに吸収障害の結果,低リン血症を発症し,クル病あるいは骨軟化症をきたす疾患と考えられている.
薬剤による腎障害
薬剤による腎障害
著者: 田部井薫 , 浅野泰
ページ範囲:P.1774 - P.1777
薬剤による腎障害で臨床的に最も頻繁に遭遇するのは抗生物質によるものであるが,注意深く観察していると,他の薬剤によるものも軽症のため見逃していることが多い.その発現形式も急性腎不全型のもののみならず,蛋白尿・ネフローゼ症候群型,慢性腎不全型,抗利尿ホルモン(ADH)の作用を修飾する型などがある.本稿ではPorter,Bennett1)の分類に従って,臨床症状から腎障害を起こす薬剤を分類してみた(表).
診断のすすめ方
血尿
著者: 黒川清
ページ範囲:P.1778 - P.1779
どのような症候,検査異常の場合でも同様であるが,血尿の患者をみた場合,現病歴,既往歴,家族歴などとともに,他にどのような症候,症状があるかについての慎重な問診,触診が重要である.ここでは血尿患者にどうアプローチするかについて概説してみよう.
血尿とは尿に赤血球が存在していることであるが,正常でも1日に尿中に約百万個位の赤血球が混在している.正常の尿検査では,uristixなどのテープでは潜血反応陰性であるが,沈渣で400×で毎視野赤血球が男性で0〜2,女性で0〜4個位までは認められる.
乏尿,無尿
著者: 菱田明
ページ範囲:P.1780 - P.1781
乏尿とは
成人の場合,尿量は通常800〜1,500ml/日である.1日尿量が400ml以下の場合,乏尿という.腎は尿量の調節を通じて体内水分量,体液浸透圧を一定に保とうとする.水分喪失量に比して相対的に水分摂取量が少ないか,腎での水排泄に障害があるとき尿量は減少する.1日尿量400ml以下を乏尿として特別扱いをするのは次の事情による.体内環境を維持する上で1日に尿中に排泄すべき溶質は成人で400〜600mOsmであるのに対し,尿最大濃縮能は1,200mOsm/kg・H2Oである.したがって,体内環境を正常に維持するには1日300〜500mlの水の排泄が必要となる.すなわち尿量が400ml以下の場合には,腎機能正常者であっても体内環境が正常に維持できないことを意味する.腎での水排泄障害による乏尿の場合に体内環境を正常に維持できないのは言うまでもない.
近年,頻回の血液検査が行われるようになり,血清クレアチニン(Pcr),血液尿素窒素(BUN)の上昇が急性腎不全発見のきっかけとなる場合も少なくない.その結果,いわゆる非乏尿性急性腎不全が急性腎不全の半数近くを占めることが明らかにされてきた.
尿路結石
著者: 池田恭治 , 福本誠二 , 松本俊夫
ページ範囲:P.1782 - P.1784
尿路結石症は,昭和50年における年間有病率が人口10万対69.4,生涯罹患率が3.96%と推定されるきわめて頻度の高い疾患である1).さらに,働き盛りの青壮年男性に多く,その再発率は5年で30%,10年で50%前後といわれており,頻回の手術と入院を余儀なくされることもある.したがって,尿路結石症を的確に診断し,適切な治療を施すことにより,その再発を防止することは,臨床的にも社会的にもきわめて重要な意義をもつ.そこで本稿では,尿路結石症の分類およびそのうちとりわけ頻度が高く問題となる特発性高Ca尿症に対して筆者らが行っている鑑別診断の進め方について具体的に述べる.
治療の進歩
腎移植—その展望
著者: 東間紘
ページ範囲:P.1788 - P.1790
ここ十数年間にわたり,目をみはるほどの進歩,発展を続けた透析療法も,このところほぼ一段落した感がある.一方,慢性腎不全治療の一方の担い手である腎移植の分野では,この数年来,Ciclosporin(CYA)やDonor-Specific Blood Tranfusion(DST)など新しい免疫抑制法の導入により画期的な進歩発展の途上にあり,かつてない興奮に包まれている.本稿では,このような腎移植の現状を今後の若干の展望を含めて報告することにしたい.
腎血管性高血圧
著者: 猿田享男
ページ範囲:P.1792 - P.1793
腎血管性高血圧は,二次性高血圧の代表的疾患であり,早期に発見して腎血管の狭窄を改善させれば,完全に治癒させうる高血圧である.それゆえ,以前より手術による腎血管再建術,腎の自家移植術さらに腎摘出術などが第1の治療法とされてきた.しかしこれまでの成績をみると,手術が施行された10〜20%の症例では血圧があまり低下せず,手術の効果がみられていない.このような症例では,腎動脈狭窄があってもその狭窄が高血圧の発症・維持と関係していないためか,高血圧となってからの期間がかなり長期となり,細動脈壁の変化など高血圧の二次的変化が進行してしまい血圧が低下し難いのか,あるいは本態性高血圧の合併例であったりする.
このように手術によっても高血圧の改善がみられぬ症例がかなりあることから,近年開発された腎血管に対する経皮的血管拡張術(percutaneous transluminal angioplasty:PTA)は侵襲が少なく,効果も良好であり,腎血管性高血圧の第1の治療法となってきた.このような治療法に加え,腎血管性高血圧における血圧上昇ときわめて密接な関係にあるレニン・アンジオテンシン(R-A)系を抑制するアンジオテンシン変換酵素阻害剤(CEI:カプトプリルなど)の登場は,内科的にもこの高血圧の治療法を大きく変えてしまった.
慢性透析療法の合併症
腎性骨異栄養症とアルミニウム中毒
著者: 久保仁 , 川口良人 , 宮原正
ページ範囲:P.1794 - P.1798
透析療法の進歩に伴い,長期透析患者が増加している今日,腎性骨異栄養症(以下RODと略す)の管理はますます重要なものとなってきている.そこで本稿では,近年明らかにされつつあるRODの発生機序,組織所見,診断,治療について述べる.
循環器系
著者: 出口隆志 , 筒井牧子 , 平沢由平
ページ範囲:P.1800 - P.1801
透析療法の発達にともない,末期腎不全の予後は明るくなったものの,透析患者での心・血管系合併症の罹患率は高く,また死因の第1位を占めている.さらに心・血管系合併症は腎不全状態からくる種々の因子の修飾をうけ,独特の病態を作りあげる.したがって,その病態把握,それに基づく管理は予後の改善のみならず,社会復帰能を高めるためにもきわめて重要となってくる.
感染症
著者: 二瓶宏 , 三村信英
ページ範囲:P.1802 - P.1803
1983年12月における人工透析研究会の調査1)によれば,同年中に死亡した4,538人の中で死因の記載のあった4,097人についてみると,心不全30.3%,脳血管障害14.2%,感染症11.0%であった.患者層の高齢化や原疾患の多様化といった問題はあるにしても,感染症への対策をなおざりにして治療成績の向上は望むべくもない.この背景に,透析患者では,細胞性・液性も含めた免疫不全状態にあること,シャント,尿路・呼吸器系など特有な感染源を有することが挙げられる.このような状況下では,炎症反応に乏しく対応が遅れやすいこと,敗血症といった重篤な感染に移行しやすいこと,治癒が遷延しやすいこと,といった特徴がみられる.
研究のトピックス:腎とホルモン
心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)
著者: 古関千寿子 , 鳥養省三 , 根東義明 , 今井正
ページ範囲:P.1804 - P.1805
分泌細胞に特徴的な顆粒を含む細胞が心房に存在することは以前より知られており,そこに酢酸によって抽出されるナトリウム利尿活性物質が存在することが,1981年DeBoldら1)によって示された.
プロスタグランディン
著者: 佐藤牧人 , 阿部圭志
ページ範囲:P.1806 - P.1807
Prostaglandin(PG)は産生部位の近くで作用する局所ホルモン(autacoids)であり,腎とくに髄質で多く産生され,腎の循環と排泄機能に関与している.腎PGはとくに腎機能が障害された際の機能維持に重要であり,臨床的にもその役割が注目される.
ビタミンD
著者: 松本俊夫
ページ範囲:P.1808 - P.1809
活性型ビタミンDとしての1,25水酸化ビタミンD〔1,25(OH)2D〕が同定されて以来,ビタミンDの代謝経路,代謝調節機構,1,25(OH)2Dの作用,さらにはその他数多くの代謝産物の同定および作用などに関する研究が著しい進展をみた.さらに,1,25(OH)2Dの受容体が腸管,腎,骨といった古典的な標的臓器のみならず,数多くの組織に存在すること,1,25(OH)2Dがカルシウム(Ca)代謝調節作用のみならず,各種の細胞の分化や,免疫系細胞の機能にも影響を及ぼすことなども近年明らかになってきた.そこで本稿では,ビタミンDの代謝調節および作用について概説するとともに,これらのトピックスについても触れてみたい.
鼎談
腎疾患—最近の展開とトピックス
著者: 荒川正昭 , 長沢俊彦 , 黒川清
ページ範囲:P.1812 - P.1825
黒川(司会) 本日は「腎疾患—最近の展開とトピックス」という話題で,日本の腎臓病,とくに糸球体腎炎を中心とした腎疾患の権威であられる荒川先生と長沢先生をお招きして,この特集を読む上で明らかにしたいいくつかの点に関して,忌憚のない意見を交換していきたいと思います.
Current topics
びまん性汎細気管支炎の独立性をめぐって
著者: 泉孝英 , 西村浩一 , 北市正則
ページ範囲:P.1864 - P.1873
びまん性汎細気管支炎(diffuse panbronchiolitis,DPB)は,最近10年ばかりの問にわが国の呼吸器科領域において広く用いられるようになった病名である1,2).本症は,"咳,痰,労作時息切れがあり,胸部X線上,粒状影と過膨張所見が認められる予後不良の疾患"であるが,DPBを独立した疾患"an independent clinical and pathological entity"であると考えるか否かについては議論の多いところである.わが国で,1つの疾患としてのDPBに議論の決着がついていないことの理由の1つに,欧米の成書,報告には本症に該当する疾患の記載がないことが挙げられる.
ここでは,まずDPBの歴史,概念と今日わが国で指摘されている問題点について紹介し,次いでDPBと関連が深いと思われる呼吸器疾患の欧米における見解の現状と,欧米におけるDPB該当疾患の有無について,欧米の呼吸器科医を対象として実施した調査成績の概要について紹介する.そして最後に,このDPBなる疾患を世界の呼吸器病学のなかに位置付けるためにはどのような努力を払うべきかについての私見を記すこととしたい.
カラーグラフ 皮膚病変のみかたとらえ方
皮膚筋炎
著者: 石川英一 , 行木弘真佐
ページ範囲:P.1830 - P.1831
概念
本症は対称的な近位部の筋力低下をきたす,横紋筋の非感染性びまん性炎症性膠原病である.皮膚症状を伴うものを皮膚筋炎,皮膚症状の明確でないものを多発性筋炎と呼ぶ傾向が強い.皮膚筋炎の特異症状として,筋脱力,筋痛(とくに大腿,上腕),CPK,アルドラーゼ,S-GOT,S-GPTの上昇とともに,ヘリオトロープ様紅斑およびGottronの症候がある.
グラフ 画像からみた鑑別診断(鼎談)
胸部X線診断の基礎
撮り方と読み方(22)
著者: 新野稔
ページ範囲:P.1852 - P.1863
肺癌の進展様式とX線像
肺門部および太い気管支粘膜から発生した癌は次の発育形式をとる.
1)管腔内発育 2)気管支壁を破壊して肺実質に向かい浸潤発育 3)1),2)を混じえた発育
演習
目でみるトレーニング(4題)
ページ範囲:P.1833 - P.1839
—内科専門医による—実践診療EXERCISE
出血傾向,貧血/全身倦怠感,心窩部痛,両眼角膜出血
著者: 赤塚祝子
ページ範囲:P.1875 - P.1878
69歳,男性,会社員.1週間前より急に下肢に皮下出血斑が出現,全身倦怠感,歩行時息切れを認めるようになった.3日前から下肢の出血斑が増強したため来院した.10年前より高血圧を指摘されているが,降圧剤は服用していない.家族歴は特記すべきことなし.
診察:身長160cm,体重54kg.栄養普通.脈拍80/分,整.血圧130/78mmHg.体温36.5℃.貧血軽度認めるが黄疸はない.表在リンパ節腫脹なし.胸部打聴診上異常なし.腹部軟,肝1横指触知,脾は触れず.下肢に点状出血斑散在,浮腫なし.深部反射正常.全身骨叩打痛あり.
講座 図解病態のしくみ 腎臓病・10
全身性疾患の腎障害
著者: 松永浩 , 黒川清
ページ範囲:P.1879 - P.1887
全身性疾患,代謝疾患を含む多彩な疾患で,また悪性腫瘍,薬剤などによっても腎の機能的,また実質性の障害がしばしばみられる.本稿ではそれらのうちで,臨床でしばしば問題となるもののいくつかについて述べる.
Oncology・22
リンパ腫(2)非ホジキン・リンパ腫
著者: 北原光夫
ページ範囲:P.1889 - P.1893
非ホジキン・リンパ腫(non-Hodgkin lymphoma,以下NHL)は単一の悪性腫瘍ではなく,むしろリンパ球の悪性変化によって出現した,いろいろな特徴をもった一群の悪性腫瘍である.したがって,自然経過,予後もおのずと異なり,治療方法もかなり異なる.
前号に述べたホジキン病は比較的はっきりと治療方針が決まっているが,NHLではそれほどはっきりしてはいないのが現状である.
臨床ウイルス学・4
自己免疫疾患とウイルス
著者: 廣瀬俊一
ページ範囲:P.1895 - P.1900
自己免疫にウイルスが関与していることは種々の動物実験からその可能性が論じられているが1),ヒトのいわゆるリウマチ性疾患にもウイルスが関係していると考えられている.その根拠としては,種々のウイルス感染の場合に狭義のリウマチ性疾患と同じ症状,すなわち,関節痛,腎炎,皮疹,低補体価のほか,動脈炎などが出現し,このような症状は自己免疫現象を伴うリウマチ性疾患である自己免疫病に多発する症状と類似したものであるからである.
また,最近は自己免疫現象を起こすのは種々の免疫細胞の質的,量的反応性の変化が原因と考えられているが2),この反応性の変化がウイルスによって誘導されたと考えられる現象が認められてきている3).したがって,これらのことから自己免疫現象にウイルスが関与しているということが相当な確実性をもって示唆されるようになってきている.
海外留学 海外留学ガイダンス
ECFMG English TestとTOEFL
著者: 大石実
ページ範囲:P.1906 - P.1909
ECFMG English Test
米国で臨床研修をするにはFMGEMSという医学の試験に加えて,英語の試験にも合格する必要がある.FMGEMSの第2日目の試験を受ける人は皆,同じ日に施行されるECFMG English Testも受験しなければならない.ECFMG English Testは約1時間の英語の試験で,年に2回,1月と7月に世界各地(日本では東京と沖縄)で施行される.
multiple-choice式の問題形式で,listening comprehension,English structure,vocabularyの3つの部分に分かれている.listening comprehensionの部分では,テープに録音してある会話などを聞き,問題用紙に印刷されている4つの答のうち1つを選ぶ.TOEFLに含まれているreading comprehensionは,ECFMG English Testでは試験時間短縮のため省略されているが,ECFMG English TestはTOEFLをもとにして作成されるので,他の部分はかなり似ている.参考書としては下記のものがあるが,TOEFLの参考書も役立つ.
診療基本手技
直腸診—前立腺の触診
著者: 永田幹男 , 西崎統
ページ範囲:P.1902 - P.1903
意義
近年,高齢化社会の到来によって老人性前立腺疾患が明らかに増加している.また前立腺炎などの患者も多く,前立腺疾患に対して関心が高まっている.前立腺疾患は問診と直腸内診によってある程度まで診断は可能である.熟練した泌尿器科医は直腸診で前立腺癌を60%診断できるといわれている.一般の臨床医ではまだ直腸診をやらないことが多く,残念ながら知識は満足ではない.
今回は直腸診—とくに前立腺疾患—について述べる.直腸診はどこでも簡単に行うことができて前立腺を触知する唯一の方法である.
一冊の本
「二十世紀旗手」—(太宰 治,浮城書店,昭和22年5月発行,80円)
著者: 川田繁
ページ範囲:P.1905 - P.1905
裏表紙に「1948.6.16著者失跡の報を見て」と私の字で記してある.小説家太宰治は,この月13日,降りしきる雨の中,玉川上水に入水し,1週間後の19日早朝,遺体が発見された.その日は奇しくも太宰満39歳の誕生日であった.「二十世紀旗手」は昭和12年に発表された小説である.この本には,本題のほかに,ダス・ゲマイネなど8つの短編が収められている.彼は戦前・戦中にも,既に多くの作品を残している.晩年,新ハムレット,正義と微笑,アルトハイデルベルヒ,教科書にも収録されている「走れメロス」(新潮,昭和15年)も.私が彼の小説にひかれたのは戦後間もないころであった.戦後の混乱のなかで私たちは,いわゆる活字文化に飢えていた.仙花紙の粗雑な本であっても飛びついた時代であった.戦いにうちひしがれ,目的と進路を見失って波に漂っている若者達にとって,感性に訴え,新鮮味にあふれ,ニヒリスティックな文体の小説は,彼等の心をとらえた.DAZAIはいまや青春文学として定着しているといわれる.当時,私もDAZAIの作品にのめりこんだ状態で過ごしていたのであった.はじらい,やさしさ,道化,与太,奉仕……これらを学ぶ,いや学ぶというよりも作品に密着し,真似ていたのではなかったか.太宰の死後既に37年,これまで数多くの太宰研究書が出ている.私も「太宰」と名のつく本の多くは買い求めては読み漁ってきた.いわば,わが青春の太宰治……であった.
感染症メモ
急性下痢症の管理
著者: 袴田啓子
ページ範囲:P.1910 - P.1911
急性下痢症の管理にあたり臨床医がすべきことは,臨床症状の評価,原因の解明,治療の必要性有無の決定および適切な治療薬剤の選択である.
診断の第一歩は十分な病歴をとることから始まる.表に示すように,病歴から診断をかなりしぼることが可能である.偽膜性腸炎はセファロスポリン,アンピシリン,クリンダマイシンが現在3大起因薬剤であるが,あらゆる抗生剤で起こる可能性があることを留意する必要がある.
面接法のポイント
栄養指導,家族および職域保健と面接
著者: 河野友信
ページ範囲:P.1912 - P.1913
1.栄養指導面接
生命体にとって栄養は最重要である.健康な生存のためにも,そして病からの回復にも,栄養は重要なのにもかかわらず,臨床栄養学はわが国の医療の中でも不毛であったし,今なお貧困である.そしてまた,食の病理がいかに多くの疾病を生んでいるか.多くの成人病や地域に偏在する病は,栄養上の問題に帰すべき場合が少なくないのである.適正な栄養はまさに医療の基本であり,健康保持と病から回復のための王道である.
数少ない紙数なので,栄養指導における面接の基本的な原則と大きな枠組についてだけ述べて,病態別の面接上の配慮や,栄養の臨床を展開する上での細かい点については触れない.
基本情報
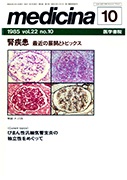
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
