"免疫とは本来疾病からまぬがれる生体現象を意味し,古くは伝染病において,疾病から回復した人々が同じ病に再び陥らないことを意味した.現在は以上のような現象をも含めて,免疫原すなわち抗原に対する生体のリンパ球およびマクロファージなど(免疫担当細胞)が担った反応(免疫応答)が何らかの形で持続している状態を総称して免疫とよんでいる"(織田・堀内・狩野・多田編:免疫学用語辞典.最新医学社,1984)."呼吸器と免疫・アレルギー"を主題とする本特集においては,"免疫"を"免疫応答を基盤とした肺における生体防御機構"として意識し,"アレルギー"を"免疫応答を基盤として惹起された気管支・肺領域における機能障害あるいは傷害に至る機序"と考えておくこととしたい.
Sir Macfarlane Burnet,Prof. PB. Medawarの共同研究"acquired immunological tolerance"に対するノーベル賞授与(1960)を契機とする近代免疫学によってもたらされた25年の成果が,まことに目覚ましい革命的産物であったことはいうまでもない.
雑誌目次
medicina23巻7号
1986年07月発行
雑誌目次
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
理解のための10題
ページ範囲:P.1226 - P.1228
editorial
呼吸器と免疫・アレルギー
著者: 泉孝英
ページ範囲:P.1116 - P.1119
免疫からみた呼吸器感染症
呼吸器における感染防御機構
著者: 安藤正幸
ページ範囲:P.1120 - P.1123
呼吸器は,ガス交換の場として直接外界の大気と接しているために,感染に対してはきわめて不利な臓器といえる.そのため呼吸器には,感染因子の侵襲を防ぐための多種多様な感染防御機構が発達している(表)が,とくに大気に接している気道表面および気道粘膜には,他臓器にみられない特殊な防御装置がそなわっている.なかでも,体液性免疫および細胞性免疫の機序による感染防御機構は,気道防御の中心的役割をなしている.
そこで本稿では,呼吸器の感染防御機構を主として免疫学的立場から,①リンパ組織および細胞による防御,②貪食系細胞による防御,③体液性免疫による防御,および,④細胞性免疫による防御に分けて概説する.なお,貪食系細胞による防御については必ずしも免疫学的に特異的な防御機構とはいえないが,免疫応答に関与している部分もあり,一括して述べる.
免疫不全と呼吸器感染症
著者: 澤木政好 , 三上理一郎 , 三笠桂一
ページ範囲:P.1124 - P.1125
感染症の発症(host-parasite relationship)において,免疫は,宿主要因としての感染防御機構の中の最も重要な部分を占めており,免疫不全と感染症については,多くの症例報告や研究報告がなされている1).定型的な免疫不全症候群やその機序などについての解説は成書にゆずり,今回は,日常の臨床面から免疫不全と呼吸器感染症について若干の検討を行いたい.
細菌性肺炎
著者: 松瀬健 , 木田厚瑞
ページ範囲:P.1126 - P.1130
肺の感染防御機構
肺は外界に開放した臓器であり,しかもきわめて血管に豊んだ構築を示している.呼吸運動に際して,常時,大気浮遊物質および微生物侵入の危険にさらされているが,これに対する防御機構も巧妙に発達している.これらは機械的,免疫学的および生化学的防御機構に大別されている(表1)1).
たとえば,Staphylococcus aureusやStreptococ-cus pneumoniaeは,健常成人の鼻咽頭粘膜に正常細菌叢として存在し得るが,これらが下気道へ落下(microaspiration)しても,粘液線毛輸送機能(mucocilliary clearance)および肺胞食細胞による貪食作用により炎症が容易に伸展波及しない仕組みになっている.しかしながら,先天的あるいは後天的原因により正常防御機構に破綻が生ずれば,病原菌の侵入,沈着,増殖を許す結果となり,下気道感染(肺炎)が成立する.このように肺炎は,宿主側(host)の防御機能と病原菌(pathogen)の間の均衡破綻が発症のtriggerになることが多い.
マイコプラズマ肺炎
著者: 須山尚史
ページ範囲:P.1132 - P.1134
マイコプラズマ肺炎とはMycoplasma Pneu-moniae(以下M.Pn.と略す)による感染症で,小児や若年成人を中心に,急性呼吸器感染症の中で大きな比重を占める疾病である.
免疫の立場から本症をみると,その発症機序が話題の中心となる.本症が一般に良好な臨床経過をたどることから,ヒトの感染における知見よりも,ハムスターやモルモットを用いた動物実験系,あるいはボランティアによるヒトでの感染実験が,その機序の解明に役立ってきた.未だ解明されていない部分も多いが,M.pn.の直接作用および間接作用に分けてこれをみるのがよい.
肺結核
著者: 久世文幸
ページ範囲:P.1136 - P.1140
一般に感染症を惹起する病原菌は,便宜的に,①細胞外寄生菌(extracellular parasites)と,②細胞内寄生菌(intracellular parasites)に分けられる.
前者はその増殖の場が貪食細胞の外にあり,通常,ブドウ球菌,レンサ球菌感染症にみられるように,急性で経過の短い化膿性炎症の形をとり,生体防御機構は好中球が主役を担い,特異的な免疫機構としては,オプソニンとして働く液性抗体(液性免疫)が補体とともに好中球の制菌,殺菌作用を助けている.
非定型抗酸菌症
著者: 久世文幸
ページ範囲:P.1141 - P.1143
結核菌以外の抗酸菌腫(非定型抗酸菌,AM)は現在多種類におよんでいるが,その病原性と本邦での現状を加味して作成したのが表である.感染症一般の現状に共通のことであるが、①日和見感染の増加と,②感染菌種の多様化がその特徴であり,抗酸菌感染症の領域もその例外ではない.
1978年以前はM. intracellulareが原因菌として90%前後を占め,M. kansasiiが7%前後,その残りをM. scrofulaceum,M. fortuitum,M. cheloneiなどがそれぞれ少数例報告されていた.しかし最近数年間の動向として,M. kansasii感染症の急激な増加と,M. szulgai,あるいは従来非病原菌とされてきたM. nonchromogenicumなどによる感染症の報告が相次いでいる.大部分は,肺結核と類似した肺の慢性感染症である.病理所見も肺結核の病理と類似しており,発症機転についても結核に準じて理解しりいるのが現状である
肺真菌症
著者: 木野稔也 , 茆原順一 , 福田康二
ページ範囲:P.1144 - P.1146
深部内臓真菌症としてわが国における頻度を剖検例からみると(この頻度は必ずしも肺真菌症を反映しているものではないが),頻度の高い順にカンジダ症,アスペルギルス症,クリプトコッカス症,ムコール症,放線菌症(アクチノミセス症),ノカルディア症の順となる(表1).
これらの病原菌の中で,アクチノミセスとノカルディアは,現在では細菌の中に分類されているが,医真菌学においては習慣上真菌として扱われることが多い.また,カンジダとアクチノミセスは,口腔・咽頭など消化器系にも常在菌として認められるので,診断上病因的意義については注意が必要である.
サイトメガロウイルス肺炎
著者: 田中健彦 , 吉澤靖之
ページ範囲:P.1147 - P.1149
ヒトサイトメガロウイルス(HCMV)は,当初子宮内胎児感染により生じる巨細胞封入体症の原因として知られていたが,最近では周産期における感染症に限らず,悪性腫瘍,臓器移植あるいはAIDSなどに伴う免疫不全に合併し,その予後を大きく左右することが明らかとなってきた.その上,正常と思われるヒトにも感染症状をきたすことが明らかとなり,HCMV感染症の多様性が注目されるようになってきた.本稿では,主として正常と思われるヒトへの肺炎を含めた感染症を述べ,その感染症の病態を免疫学的観察成績を中心に解説したい.
ニューモシスチス・カリニー肺炎
著者: 岩田猛邦 , 望月吉郎
ページ範囲:P.1150 - P.1152
Pneumocystis carinii肺炎は,Pneumocystis carinii(以下PC)という微生物によって起こる肺炎である.PCは現在のところ原虫の一種と考えられている.PCはヒトを含む哺乳動物の肺に潜在的に感染しているが,時には不顕性感染の形ではとどまらず,急に肺で増殖し重篤な肺炎をひき起こす.現在このPC肺炎は,悪性腫瘍,腎移植,膠原病などの免疫不全患者の日和見感染症の1つとして大きな問題となっている.近年,予防投与法が全国的に普及し,わが国における発症数は減少傾向を示している1).
最近,後天性免疫不全症候群(AIDS)患者の肺感染症において,PC肺炎が圧倒的多数を占めることより再び注目を集めているが,AIDS合併症に関しては他稿にゆずることとして,本稿では自験例を中心にPC肺炎を概説する.
レジオネラ感染症
著者: 朝長昭光 , 斉藤厚
ページ範囲:P.1154 - P.1155
レジオネラ感染症(Legionella infection)は,グラム陰性桿菌であるLegionella pneumophilaおよびその他のLegionella属による細菌性肺炎を主徴とするものである.
本症は1976年,米国のPhiladelphiaにおける在郷軍人会参加者に集団発生し,184名が肺炎に罹患し,29名が死亡した事例に端を発し,在郷軍人病(Legionnaires' disease)と呼称された.その後の研究で本症は過去にも存在し,また世界各国からの症例も報告され,本邦においても筆者らが1981年に第1例を報告した.
AIDSにおける肺病変
著者: 河野茂 , 斉藤厚
ページ範囲:P.1156 - P.1158
1981年米国で男性同性愛者に後天性免疫不全症候群(AIDS)が初めて報告されて以来,これまですでに15,000人を超える症例が発生し,またわが国においても,1986年2月現在で15症例の報告がなされている.本症における高リスクグループとして同性愛者,麻薬静注者,血友病患者,ハイチ人などが知られているが,最近の疫学調査では,ザイールやコンゴなどの中央アフリカから,ハイチや米国,ヨーロッパへ伝搬したものと推定されている.
1983年Montanierら1)によりリンパ節腫瘍関連ウイルス(LAV)がAIDS患者より分離され,1984年にはGalloらがHTLV-IIIを,LevyがAIDS関連レトロウイルス(ARV)を分離しレンチウイルスがAIDSの原因ウイルスとして報告され,現在のところLAV/HTLV-IIIと表記するとの申し合わせがなされている.
アレルギー性肺疾患
アレルギー性肺疾患の分類
著者: 泉孝英
ページ範囲:P.1160 - P.1161
"免疫反応を基盤として惹起された気管支・肺領域における機能障害あるいは傷害"であるアレルギー性肺疾患は,発症機序の面からはGell,Coombsの分類以来の4つのタイプ分けが行われている(図1,2).
アレルギー性肺疾患の診断
IgE(総IgEと特異的IgE)
著者: 今井弘行
ページ範囲:P.1162 - P.1163
免疫グロブリンE(IgE)を測定することによって,I型アレルギー疾患を診断し,経過を追跡することは,今では当然のこととして臨床に用いられている.しかし,血清IgEが測定可能になっても,I型アレルギーの診断を確実に下すことは容易ではない.病歴や所見を詳細に検討した上に,IgE測定で得たデータを追加してこそ,診断精度が高まる.
得られたデータを正しく評価するための問題点は,下記の2点に集約できる.
誘発試験
著者: 梅枝愛郎 , 中沢次夫
ページ範囲:P.1164 - P.1165
アレルギー性肺疾患とその起因アレルゲンの診断は,詳細な病歴聴取や諸検査で概ね可能であるが,確定診断や,近年注目されている遅発型気管支反応,さらに過敏性肺炎とその病因アレルゲン(とくに新しい場合)の診断などには,アレルゲン吸入誘発試験が不可欠である.ここでは,牧野らの吸入試験の標準法に1),筆者らの経験に基づいた施行上の注意や若干の修正を加え2,3),その施行方法について概説する.
気管支肺胞洗浄
著者: 泉孝英 , 長井苑子 , 竹内実 , 渡辺和彦 , 北市正則
ページ範囲:P.1166 - P.1171
気管支肺胞洗浄(bronchoalveolar lavage,BAL)とは,気管支ファイバースコープを亜〜亜々区域気管支に楔入し,側管から,注射器を用いて生理的食塩水50ml程度の注入回収を反復する,あるいは,サイフォンの原理を応用して100ml程度の注入回収を反復することによって,通常,200〜300mlの生理的食塩水にて対象領域を洗浄する方法である.BALによって,まず,末梢気道,肺胞腔内の細胞成分,液性成分が採取され,次いで肺胞間質内の成分が採取される(図).
Reynolds(1974)によって開発されたBALは,肺感染症における起炎菌の決定,あるいは悪性腫瘍細胞の検出手段として用いられてはいたものの,主たる目的とするところは,サルコイドーシス,過敏性肺臓炎(hypersensitivity pneumonitis,HP),特発性間質性肺炎(idiopathic pulmonary fibrosis,IPF)などを中心とするびまん性肺疾患の病態生理解明であった.しかし,最近になって,各疾患ごとのBALによって得られる液性成分,細胞成分に関する知見が増加してきたこと,また,モノクローナル抗体を用いてマクロファージ,リンパ球サブセット測定が可能になってきたことによって,BALの診断学的意義が高まってきた.
Ⅰ型アレルギーを基盤とする疾患
気管支喘息
著者: 中沢次夫
ページ範囲:P.1172 - P.1175
気管支喘息は,発作性の咳,喘鳴,呼吸困難をきたす疾患であり,①気道の広汎な狭窄,②その狭窄が可逆性であること(自然または治療により),③各種の刺激に対して気道の反応性が亢進していること(気道過敏性),と定義される.すなわち,気管支喘息は気道過敏性が基本的病因であり,これに可逆性気道狭窄という機能性変化が加わったものと考えられる.
気道狭窄は,①気管支平滑筋の攣縮,②気道炎症の結果としての気道粘膜の浮腫,腫脹,③粘液の過剰分泌による粘液栓,とで形成される.一方,このような気道狭窄をひき起こす因子としては,アレルゲンなどの特異刺激,および温度,気圧変化,匂い,運動などの非特異刺激がある.とくにアレルギー性因子は,多くの喘息患者で血中IgE値が高く,何らかのアレルゲンに対してIgE抗体を産生しやすいこと(アトピー),また既往歴や家族歴でアトピー性疾患を有することなどから,喘息病態発症に重要な役割を演じていることが想定される.したがって気管支喘息は,一種の免疫異常であるアレルギー性因子と,生理異常である気道過敏性との遺伝的関連性を併せもつ疾患としての観点から捉えられている.本稿では,気管支喘息のアレルギー的側面からみた病態生理について主に述べる.
Ⅱ型アレルギーを基盤とする疾患
Goodpasture症候群
著者: 杉山温人 , 猪熊茂子
ページ範囲:P.1176 - P.1178
1919年Goodpastureは,インフルエンザに罹患後,肺出血と急速に進行した糸球体腎炎で死亡した18歳男性の剖検例を報告した.その後,1958年にStantonとTangeはこのような肺出血に急速進行性糸球体腎炎を合併した症例をGoodpasture症候群(以下G症)と呼んだが,この両者の合併は多発性動脈炎や全身性エリテマトーデスなどでもみられるため,さらに明確な疾患概念の確立が望まれていた.1960年代になって,本症の発症機序に抗GBM(glomerular basement membrane)抗体が関与していることが証明されて以来,G症はII型アレルギーの代表的疾患として注目されている。
欧米ではG症は全腎生検中の2〜5%を占めるといわれ,男女比は2〜9:1と男性に多く,年齢は10歳代から70歳代にまで及ぶが,30歳代までの若年者に多いとされる.わが国では欧米に比べて報告例が少なく,また女性のほうに多いとする報告がみられる1).
Ⅲ型アレルギーを基盤とする疾患
特発性間質性肺炎
著者: 高田勝利 , 森下宗彦 , 山本正彦
ページ範囲:P.1180 - P.1182
特発性間質性肺炎(IIP)は,肺胞壁を主とする炎症性病変から広範に線維化して肺全体の構築を硬化・縮小する疾患である.病変は下肺野胸膜直下に起こり,漸次下肺野を上行して拡がる.本症の成立機序には免疫学的機序が関与していると推測されており,最近の知見を混じえてその関連を述べる.
Ⅳ型アレルギーを基盤とする疾患
サルコイドーシス
著者: 長井苑子
ページ範囲:P.1184 - P.1185
疾患概念,臨床所見
サルコイドーシスは,病理組織学的には乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫形成を主徴とする原因不明の全身性疾患である.ツベルクリン反応の陰性化,in vitroでの末梢血リンパ球のmitogenに対する低反応性など,種々の細胞性免疫反応の低下がみられる.一方,血清γグロブリン増加などの液性免疫反応レベルでは亢進現象が起こっているなど,多彩な免疫学的異常所見がみられるが,臨床的には易感染性,悪性腫瘍の発現率が高いなどの免疫不全の徴候を示すことはない.
男女差はなく,20歳代とくに前半が好発年齢で,小児,老人には少ない.罹患部位は全身におよぶが,肺(縦隔,肺門リンパ節,肺野;95%以上),眼(30〜40%),皮膚(5〜10%)が病変頻度の高い部位である.剖検レベルでは,肝病変,心病変もよく認められる.
いくつかのタイプのアレルギー反応が関与している疾患
過敏性肺臓炎
著者: 越智規夫
ページ範囲:P.1186 - P.1187
過敏性肺臓炎とは
有機塵に含まれるカビの胞子や動物性蛋白質などの抗原を吸い込んだ個体が免疫学的に感作され,再吸収に際して肺におけるアレルギー反応の結果,間質性肺炎を起こす一群の疾患を総括して,過敏性肺臓炎または外因性アレルギー性肺胞炎と呼ぶ.反復性の呼吸困難を主徴とするが,喘息と異なり喘鳴を伴わず発熱をみる.18世紀以来ヨーロッパで,農夫肺,醸造業者肺,鳩飼病など約20種類の職業名を冠した病名が知られてきた.近年,加湿器肺の発見により職業病の枠を超えた環境性疾患として見直され,わが国では表1のごとき報告がある.なかでも夏型過敏性肺臓炎2)は本邦特有の疾患として注目される.低分子化合物がハプテンとなり発症するイソサイアネート肺臓炎も,広義の過敏性肺臓炎として扱われる.
好酸球性肺炎
著者: 茆原順一 , 木野稔也
ページ範囲:P.1188 - P.1190
概念
好酸球性肺炎は,1969年Liebow & Carrington1)が,1952年Reeder & Goodrichの提唱したPIE症候群(pulmonary infiltration with eosinophilia)に対し,組織学的には著明な好酸球増多を呈することは同様であるが,末梢血に好酸球増多を伴わない症例もあることから,より広い新しい名称として,"eosinophilic pneumonia"と提唱したことにはじまる.たがって,肺における病態は,本症はPIE症候群と同様,肺組織の主たる炎症細胞は好酸球よりなるという共通のものであり,多少の問題点はあるかも知れないが,基本的には同一疾患概念として,本稿では一般的に用いられているPIE症候群として述べてみたい.
PIE症候群は,末梢血好酸球増多を伴い,肺浸潤影を呈する一群の症候群で,肺浸潤影を呈する組織の主たる炎症細胞は好酸球よりなることが本症の主徴である.
アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
著者: 木野稔也
ページ範囲:P.1192 - P.1194
アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(aller-gic bronchopulmonary aspergillosis;ABPA)は,アトピー性素因をもつ患者の気管支内にAspergillusが持続的に生息することによって,Gell and CoombsのI型およびIII型アレルギーが成立し発症するアレルギー性気管支肺疾患である.IV型アレルギーも同時に成立しているものと思われるが,診断にはI型アレルギー(即時型皮膚反応陽性またはIgE抗体の検出)およびIII型アレルギー(6〜8時間後を最高とする遅発型皮膚反応陽性または沈降抗体の検出)の証明で十分である.
免疫反応の関与が考えられる呼吸器疾患
塵肺症
著者: 藤村直樹
ページ範囲:P.1196 - P.1198
塵肺症は,佐渡金山では"山気",明治以後の鉱夫の間では"ヨロケ"として古くから知られた職業性疾患であったが,近年,免疫学の進歩に伴い,本症に種々の免疫異常が存在し,病変形成や病態生理に免疫学的機序が一定の役割を担っているという,免疫学的疾患としての側面が注目されるようになっている.本稿では,代表的な塵肺症である珪肺症と石綿肺につき,免疫病態生理の面から概説を試みたい.
膠原病に伴う肺病変
著者: 猪熊茂子
ページ範囲:P.1199 - P.1203
膠原病は全身多臓器障害をきたす疾患で,重要臓器の侵襲が著しければ予後を危くする.臓器障害や死因には経年的に変化がみられ,たとえば昭和48〜57年の10年間のSLEの死因は,厚生省班会議によれば,腎不全は146例中13例9%にすぎず,肺性心ないし肺高血圧を含めた肺疾患が12例とほぼ同数に増加してきている.今後は,膠原病における心肺の障害はさらに大きな問題となっていくことと思われる.
膠原病でみられる肺病変は,古くは胸膜炎,間質性肺炎が主に云々されてきたが,最近では肺血管の病変が注目されている.また,原発性の諸種肺病変と膠原病に合併したそれとの違い,同じ胸膜炎であっても各膠原病間で違いがあるかなどを含めて,発症機序などは未だ不明で,今後の課題が非常に多い分野と思われる.
肺好酸球性肉芽腫症
著者: 吉澤靖之 , 佐藤哲夫
ページ範囲:P.1204 - P.1205
1940年OtaniらおよびLichensteinらにより骨の好酸球性肉芽腫症が報告され,1951年にはFarinacciらにより骨病変を伴わない肺好酸球性肉芽腫症の存在が認められた.1953年になりLichensteinは好酸球性肉芽腫症(Eosinophilic Granuloma),Hand-Schuller-Christian病およびLetterer-Siwe病を基本的には原因不明の同一疾患であるとして,Histiocytosis Xと総称した.現在も病名については議論のあるところであり,好酸球性肉芽腫症をunifocalとmultifocalに分類し,Hand-Schuller-Christian病をmultifocalの亜群として,Letterer-Siwe病を腫瘍性の要素をもった別の疾患と分類する考え方もある.本稿で述べる好酸球性肉芽腫症は,unifocalおよびmultifocalの両者を同一疾患として扱う考え方による.
Wegener肉芽腫症
著者: 于潤江
ページ範囲:P.1206 - P.1207
概念と定義
Wegener肉芽腫症(WG)とは,全身の血管炎を伴う非特異性壊死性肉芽腫病変によって,主に上気道,肺を含む下気道,腎臓が侵される原因不明の進行性疾患である.本症は,Klinger(1931)により,化膿性鼻炎,関節症状を伴う尿毒症のため約1年の経過で死亡した症例が,結節性動脈周囲炎に類似した剖検例として報告されたのが最初である.続いてWegenerが,2度(1936,1939)にわたって,血管系および腎とともに上気道を主たる罹患部位とするのが特徴であると報告して以来,一般にWegener肉芽腫症と称されるようになったものである.Godman,Churg(1954)は,本症の病理学的特徴として3病変をあげて,本症を独立した疾患であると主張した.その3病変とは,①上気道,下気道(気管,気管支,肺)の壊死性肉芽腫,②全身性の壊死性血管炎,③糸球体腎炎,などである.
Carrington,Liebow(1966)は,腎病変を伴わない肺と皮膚のみが侵された16例の本症を報告し,これを限局型WGと称し,WGには全身型と限局型の2つの臨床病型のあることを強調した.Fauci1)(1978)は,WGの病理組織学の基盤は血管炎であることを強調した.限局型WGは全身型より予後がよい.しかし,限局型のうち全身型に進展する症例も少なくない.
肺癌
著者: 米田尚弘 , 三上理一郎 , 北村曠
ページ範囲:P.1208 - P.1210
腫瘍に対する宿主の防御機構は,1963年,Burnetによって免疫監視機構(immunological sur-veillance)の概念が提唱されて以来,腫瘍特異的キラーT細胞(CTL)が主体と考えられてきた.肺癌に対するエフェクター細胞としても,当初,CTLが関与する特異的免疫機構が注目されたが,近年,広義の宿主抵抗性を担うnatural killer(NK)細胞,マクロファージなどの関与する非特異的免疫機構が重要視されている.図1に肺癌に対する免疫監視機構の概略を示す.前者に関するパラメーターとしては,腫瘍抽出抗原を用いた遅延型皮膚反応,マクロファージ遊走阻止試験(MIT),白血球粘着阻止試験(LAI),リンパ球腫瘍混合培養(MLTC)などがあり,肺癌の抗原性と,それに対する免疫応答の存在を示すとする報告は多い.後者のパラメーターとしては,遅延型皮膚反応,PHA,ConAに対する幼若化反応,マクロファージ機能やNK細胞活性などがあるが,病期の進行に伴い低下するという報告が多い.また最近,インターロイキン2により自己腫瘍細胞などに広い細胞障害性を有するLAK細胞が報告され,両機構の中間に位置づけられる.
肺癌に対する免疫機構を経時的に観察すると,①発癌初期,②担癌期,③転移の各過程に応じて,上述のエフェクター機構が作動する.各過程の免疫能について,当教室の成績をまじえて概説したい.
薬剤性肺臓炎
著者: 茆原順一
ページ範囲:P.1212 - P.1213
近年,医学における治療学の進歩は著しいものがあり,これは多種の薬剤の新開発や,多剤併用法など投与法の進歩に負うところが多いと思われる.しかし,その一方,薬剤投与に起因する臓器障害の程度と頻度の増加も注目され,臨床上重要な点となってきている.臓器障害として,当然,肺という臓器もそのtarget organになりうるわけであるが,肺という臓器が多様な機能と構造よりなるため,その障害の発現も多種多様である1,2).
これらを大別すると,bronchial asthma(アスピリン,インドメサシンなど),hypersensitivity pneumonitis(下垂体後葉末など),PIE syndrome(ニトロフラントイン,ミノサイクリン,PASなど),interstitial pneumonitis & fibrosis(金塩,プロカインアミド,各種抗癌剤),vasculitis(SLE like syndrome)(金塩,メチルドーパ,ジギタリスなど)があげられる.これらのうち,薬剤性肺臓炎が最も臨床上重要である.
鼎談
呼吸器と免疫・アレルギー
著者: 螺良英郎 , 長井苑子 , 泉孝英
ページ範囲:P.1214 - P.1224
泉(司会)今日は,本特集"呼吸器と免疫・アレルギー"を読者の方により一層理解していただくために,お互いに年がばれてしまって具合が悪いのですけれど(笑),大体一世代ずつ違う3人が集まりまして,"呼吸器と免疫・アレルギー"というものの今日までの研究の流れを確認するとともに,残された課題についての展望を語っていきたいと思います.
私の理解からいいますと,1960年,ちょうど私が医学部を卒業した年ですが,Burnet,Medawarが,"acquired immunological tolerance"の研究によってノーベル医学賞をもらったのを契機として,新しい,いわゆる近代免疫学が始まったと思います.その前の時代は,失礼ながら中世ということになりかねないのですが,まず最初に,螺良先生の個人史というものから,お話をうかがえればと思います.
Current topics
呼吸器疾患領域におけるグルココルチコイド
著者: 泉孝英 , 田中茂 , 長井苑子
ページ範囲:P.1259 - P.1270
グルココルチコイド(glucocorticoid,GC)は,抗生物質,気管支拡張剤と並ぶ呼吸器疾患領域における治療薬の3本柱の1つである.GCの臨床応用は,Hench(1949)の慢性関節リウマチへの応用とその有効性の確認報告に始まる.呼吸器疾患領域においても,1950年頃より気管支喘息への投与が始まっており,すでに35年以上の年月が経過している1).GCの作用機序をふまえた上で,副作用の出現を抑制しつつの有効な投与法の開発は,当初より指摘されてきたことであるが,現実に,適応,投与方法,投与量の決定は経験的な知見によっているところが大きい.本稿では,GCの薬剤としての概略,作用機序2〜4)について述べるとともに,GCの適応,有効性からみた呼吸器疾患領域における応用について述べることとしたい.
カラーグラフ 皮膚病変のみかたとらえ方
悪性リンパ腫の皮膚病変
著者: 石川英一 , 二瓶義道
ページ範囲:P.1232 - P.1233
分類
皮膚の悪性リンパ腫には皮膚原発性のT細胞由来悪性リンパ腫が多いため,腫瘍細胞表面マーカーにより,T細胞由来,B細胞由来,non-T,non-B細胞由来,およびポジキン病に分ける方が一般に理解し易い.
リンパ節疾患の臨床病理
T cell型リンパ腫
著者: 片山勲
ページ範囲:P.1235 - P.1238
LSG分類(表)によれば,非ポジキンリンパ腫は3つの濾胞性リンパ腫と7つのびまん性リンパ腫の合計10項目に分類される.びまん性リンパ腫のリンパ芽球型とバーキット型はすでに本連載の前回,前々回で取りあげたが,その臨床像および病理組織像はともにきわめて特徴的であり,免疫学的にはリンパ芽球型がTcell型,バーキット型がBcell型であることなど,記憶に新しいことと思う.
残る8項目のうち,濾胞性リンパ腫は3型ともBcell型であり,多形細胞型はTcell型であるが,あとの小細胞型から大細胞型までの4型はBcell型のこともTcell型のこともある.そこで個々の症例をLSG分類する場合には,10項目のうちのどの項目に該当するかを決めたあと,もし上記の4項目のうちのいずれかである場合には,さらにBcell型であるか,T cell型であるかを免疫学的に検査(または形態学的に推定)して,たとえば"混合型リンパ腫,Bcell型(形態学的推定)"というように,免疫型を形態診断名のあとに付記することがLSG分類の正しい運用法であるとされている.その理由は,同じ分類項目でもBcell型であるかTcell型であるかに応じて,予後や治療に対する反応のうえで相当の差異が認められるからである.
グラフ 消化管造影 基本テクニックとPitfall
食道(6)—食道癌
著者: 山田明義 , 西澤護
ページ範囲:P.1240 - P.1247
各種進行癌の特性とX線像
西澤 今回が食道造影の最後になりますが,症例をみながら食道癌についてお話をうかがいます.
まずX線像の分類としては,腫瘤型,鋸歯型,漏斗型,らせん型,それ以外に表在型というふうに分かれているようですが,盛り上がりのほうから,X線の所見,特徴などについてお話ください.
内科医のための骨・関節のX線診断
(6)膠原病の骨・関節病変
著者: 水野富一
ページ範囲:P.1248 - P.1256
関節病変のX線写真の読影には前にも述べたように,A:Alignment(関節の並び) B:Bony mineralization(骨濃度) C:Cartilagenaous space(関節腔) D:Distribution(病変の分布) S:Soft tissue(軟部組織)のチェックポイントがあり,これに従って順番に読影することが正しい診断に到着する近道である1).膠原病では関節に病変の出現するものが多く,他の関節疾患との鑑別のためにも骨関節の読影にはABCDSを念頭に置く必要がある.
Forrester1)による関節炎の鑑別診断のフローチャートを表1にあげる.本稿ではリウマチ型(Rheumatoid type)とリウマチ亜型(Rheumatoid variant)について述べ,次稿にその他の関節疾患につき述べる.
演習 —内科専門医による—実践診療EXERCISE
発熱
著者: 吉村邦彦
ページ範囲:P.1257 - P.1258
53歳女性,主婦.既往歴には特記すべき事項なく,生来健康.喫煙歴,アルコール嗜癖なし,来院の10日前から38℃をこえる発熱があり,近医にて感冒の診断で解熱剤を処方されたが改善せず,発熱は持続し,咳嗽と軽度の息切れも加わるようになり来院した.
理学所見:身長154cm,体重53kg,体温39.9℃,脈拍114/分,整,呼吸数16/分,血圧120/82mmHg.意識清明,眼瞼貧血黄疸なし,表在リンパ節触知せず,心音清,胸部聴診上両側背部と右前胸部で吸気時にfine crackleを聴取した.腹部平坦,肝脾腫なし,下腿浮腫なし.神経学的所見正常.
講座 図解病態のしくみ 内分泌代謝疾患・7
甲状腺機能低下症
著者: 山本邦宏 , 斎藤公司
ページ範囲:P.1272 - P.1278
甲状腺機能低下症は,甲状腺からのホルモン分泌低下により起こされる甲状腺ホルモン(T4,T3)の不足による全身の組織の低代謝状態である.甲状腺疾患の特徴として女性に多発することが知られているが,甲状腺機能低下症でも少なくとも85%以上は女性に発症するといわれている.本症は種々の原因により起こされ,その症状も軽度なsubclinical typeから,overt typeまで広く分類され,発症年齢も出生前の母胎内の時期から老年期に亘っている.以下,種々の分類方法でまとめながらその病態のしくみを考えてみたい.
臨床ウイルス学・10
成人T細胞白血病のウイルス
著者: 小林進 , 山本直樹
ページ範囲:P.1280 - P.1285
成人T細胞白血病(Adult T-cell leukemia,ATL)は1977年に京都大学の高月(現・熊本大学医学部教授)らによって初めて独立疾患として報告された.これは主に日本の西南地方,九州に多く,地域偏在性のある独得の白血病リンパ腫である.ATLは成人,特に40歳台から60歳台が最も多く,白血病細胞の核は切れ込みや分葉の傾向があり,典型的なものでは花びら状に見える.白血病細胞はその名のようにT細胞,特にヘルパー/インデューサーの表面マーカーを保有する.患者の多くは発病すると急速に悪化の一途を辿り,衰弱が進み,最後には肺炎などを併発して死亡する.患者の約50%は半年以内に,残りのほとんども2年以内に死亡する,致命率の高い白血病である.
1980年と1981年には,それぞれ米国と日本でATL患者の末梢血からT細胞株が樹立され,今までに発見された動物のレトロウイルス(RNA型腫瘍ウイルス)のいずれとも異なるウイルスが分離された.これらのウイルス(後述のように後になり同一であることがわかった)はヒトの発癌性に直接関連することから直ちに多くのウイルス学者や血液学者の興味を引くところとなり,その病因論的研究や疫学的研究が一挙に進むことになった.その結果はこのウイルスがATLの直接的な原因であることを示すに十分なものであった.以下,ウイルスの発見に始まるこれまでの知見と,その後のATL研究の進展について述べてみたい.
海外留学 海外留学ガイダンス
英独仏語医学会話(2)—再来患者
著者: 大石実
ページ範囲:P.1288 - P.1292
ポリグロット
日本の国際的な地位が高まるにつれ,英語圏でない国との交流も必要になってきている.私もドイツ,フランス,スイス,イタリア,中国などを訪問したが,英語圏でない国ではいかに英語が役に立たないかを痛感した.英語しかできない人は英語派でしかなく,グローバルな視野をもつ真の国際派は英語プラス他の外国語ができるポリグロットを目指すべきである.
下記の本には,カナダ,イギリスなどの英語圏はもちろん,ドイツ,フランスなどの英語圏でない国への留学のしかたや,海外に留学する医師が受けられる奨学金も出ている.
新薬情報
経皮吸収型亜硝酸剤
著者: 松田隆秀 , 水島裕
ページ範囲:P.1294 - P.1295
概要
亜硝酸剤,なかでもニトログリセリン(glyceryl trinitrate,NG)は,古くより優れた抗狭心症薬として用いられてきた.また,うっ血性心不全に対し有用性が認められている.しかし,舌下錠では作用持続時間が短く,狭心症発作の予防や心不全の治療という点では,臨床的に使いやすい剤型とはいえない.近年,徐放性亜硝酸剤が開発されるとともに,Drug Delivery System(DDS)に関する研究が進み,経皮吸収型亜硝酸剤が開発され,わが国ではフランドルテープ(isosorbide dinitrate,ISDN;トーアエイヨー),バソレーター軟膏(NG;三和)がすでに発売されている(図).以下,この両薬剤を中心に解説し,発売が予定されている薬剤を紹介する.
一冊の本
「歴史」(ヘロドトス,松平千秋訳,岩波文庫,昭和46年)
著者: 長廻紘
ページ範囲:P.1287 - P.1287
若いうちは何でも読める.内容が判らなくても判ったつもりになって読める.段々年をとると時間的制約があってなかなか本を読む時間がなくなるし,読んで判らないものはすぐ投げ出す.よほど面白くないとまず読まなくなる.面白いのがよいといって漫画や推理・冒険ものばかり読むわけにもいかない.時にはsophisticated and highbrowな本も読まないといけない.そういう時に読むのは昔読んで気にいったもので,かつどこから読んでどこで終ってもよいもの,がよい.それには歴史の本がよい.但し新しい分野だと人名や地名をみただけでうんざりするから,そういうことにうんざりしない若いうちに,何回も読むに耐える本につばをつけておく.私は偶然の機会にめぐまれて,史記,三国史,読史余論,歴史(ヘロドトス),ローマ史(ギボン)などに出会い,今でも年に1回ぐらいはどれかのどこかをひもとく.
基本情報
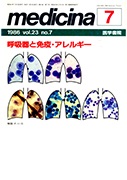
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
