Ⅰ型糖尿病の成因は現在もなお不明であるが,その研究には着実な進歩がみられている.とくにI型糖尿病モデル動物(BBラット,NODマウス)の研究は,ヒトI型糖尿病の成因の理解に大きく貢献している.そこで本稿では,ヒトにおける成績とモデル動物における成績を対比しながら,成因がどこまでわかったかについて述べる.
雑誌目次
medicina24巻1号
1987年01月発行
雑誌目次
今月の主題 糖尿病診療の現況
理解のための10題
ページ範囲:P.102 - P.104
糖尿病の診断とコントロール基準
診断基準とその根拠
著者: 佐々木陽
ページ範囲:P.18 - P.21
糖尿病は,病因論的には多様な疾患であることが明らかにされてきたが,診断基準に関しては病因のいかんを問わず,共通の基準が用いられてきた.以下,現在わが国で用いられている1982年の日本糖尿病学会の診断基準と,その背景となったWHOの診断基準について解説し,またどのような根拠からこのような基準が設定されたか,その経緯についても触れてみたい.
コントロールの指標となる検査
著者: 坂本信夫 , 佐藤祐造
ページ範囲:P.22 - P.23
糖尿病のコントロールの良否
糖尿病の病因は一元的に整理できず,臨床的に一定の特質を示す症候群と考えられているが,その特質をもたらす原因が"生体内におけるインスリン作用の不足"であることは今日疑いのないところである.したがって,糖尿病の治療(コントロール)の良否は,"インスリン作用不足による代謝異常を是正するとともに,できるだけ通常の社会生活を営みうる体力を保持させる"ことの成否を判断の根拠としなければならない.
コントロールの指標としては,血糖,グリコヘモグロビン,尿糖・ケトン体,血清脂質など代謝状態を判断するもの(化学的コントロールchemi-cal control)と,それに加えて,体重,血圧,臨床症状の程度や合併症の有無など総合的なもの(臨床的コントロールclinical control)とがある.主な指標と判定基準を表に示す.
ヘモグロビンA1,A1cの臨床的意義
著者: 老籾宗忠
ページ範囲:P.24 - P.25
HbA1あるいはHbA1cは,hemoglobin(Hb)と糖の非酵素的結合で生ずるglycosylated Hbである.Hbに糖が結合することによって陰性荷電をもち,通常のHbA0に対して電気泳動上陽極側に易動度をもつためHbA1と名付けられた.さらにイオン交換カラムを用いてHbA1を分離すると,HbA1a,HbA1b,HbA1cと,HbA1は大きく3つに分けることができる.臨床上の問題から,HbA1cがHbA1の大半(約70%)を占め,血糖変化に最も変化を受けやすいため,HbA1cがHbA1の代表のように考えられてきた.
一方,生体におけるnonenzymatic glycosylationはHbA1の存在から注目されてきたのであるが,この反応はHbのみならず広く種々の蛋白と糖との間にも生ずる反応で,Maillard反応と称され,自然界に存在する普遍的な蛋白と糖との結合反応である.たとえば,蛋白食品を加熱調理するときに生ずる褐色調への色の変化は褐変現象ともいわれ,この反応の1つである.Hbのβ鎖N端valine,あるいはlysineのε-amino基などに糖が非酵素的に結合することによってglycosylationが成立し,Schiff base結合,さらにこれがAmadori転位してketoamineになる.このSchiff base結合のものまでは可逆反応であるが,Amadori転位するとほぼ不可逆性になる(図).
糖尿病の治療と患者指導
糖尿病治療の目標
著者: 平田幸正
ページ範囲:P.26 - P.27
糖尿病のある人生の充実へ向かって
糖尿病治療の目標は,糖尿病のある人生をきわめて意義のあるものとして送ることができるということに焦点があてられると思われる.すなわち,心身ともに健康な,活動的な人生を,健常者と変わることなく長期間保持するというところに目標があるといえる.このことはquality of lifeを高め,持続させる,あるいは,よりよいquality of lifeを求めるという言葉でいい表すことができる.
すでに1925年(大正15年),R.D.Lawrenceは,"The Diabetic Life"という糖尿病患者教育用の本を発刊し,その緒言において,インスリンの発見された今日,患者は,糖尿病に関するいささかの知識を身につけ,医師とよく協力すれば,もはや糖尿病は死の病気ではない時代に入ったといえると述べた.
患者と医療スタッフとのふれあい
著者: 石垣健一
ページ範囲:P.28 - P.31
患者教育を完壁に行うことは,きわめて困難である.しかし医療スタッフは,より適正に,より有効に患者を診療すると同時に,より情熱的に患者を教育する義務がある.
どんな疾患でも,患者は正しい知識を1つでも多く求め,的確な教育指導を期待している.阿部正和氏(慈恵医大学長)の"医療は教育なり"という提唱は,まさに医療の原点である.
食事療法の効果的な指導法
著者: 泉寛治 , 吉田途男 , 萩原玲子 , 馬場耕造 , 馬渕博子
ページ範囲:P.32 - P.35
糖尿病患者の食事療法の基本原則は,血糖をコントロールし,その日内変動をできるだけ健常人に近づけ,さらに体重を標準体重の近くに維持することにより,病勢の進展や合併症の発生を阻止することである1).
糖尿病の治療は,食事療法とともに運動療法を可能な限り行い,この両者で糖尿病のコントロールが不十分なときにのみ薬物療法を追加するが,食事療法を適正に行わなければ他の治療法の効果は十分に発揮できない.このことは,最近薬物療法による副作用の問題からさらに重視されるようになった.
運動療法の具体的な指導法
著者: 藤井暁 , 中嶋千晶
ページ範囲:P.36 - P.37
糖尿病患者における運動療法は,食事療法とともに基本的なものであるとされ,事実,運動療法の継続効果について代謝面ひとつをとってみても,インスリン感受性の改善をはじめ耐糖能や脂質代謝の改善,さらには脂肪組織を中心とした減量効果などが明らかにされている1).運動療法の基本は,池田2)の指摘している"いつでも,どこでも,1人でもできる運動"であるが,患者に有効かつ安全に行わせるには,年齢,代謝異常の程度や治療法,合併症の有無など糖尿病の病状との兼ね合いで個別性を考慮した指導が望まれる.
本稿では,筆者らの運動療法教室での経験をふまえ,運動療法の実際,とくに運動指導の進め方を中心に述べてみたい.
経口血糖降下剤の使い方
著者: 三家登喜夫 , 宮村敬
ページ範囲:P.38 - P.39
インスリン治療の普及後に実用化された経口血糖降下剤は,インスリン注射の繁雑さに比べ,気楽に治療ができるということで関心が高まり,約30年の経過をへた現在でも,II型糖尿病(NIDDM)の治療に広く用いられている.この間,1970年にはUGDP(University Group of Diabetes Program)1)が,本剤の長期使用例に心血管死が高頻度に出現すると報告し,大きな波紋をなげかけた.また重症低血糖事故の報告や,ビグアナイド剤使用例における乳酸アシドーシスの発生なども指摘された.しかし現在では,経口血糖降下剤を使用する医師が,その薬理作用,使用方法,副作用などについて正しい知識をもち,注意深く使用すれば,NIDDMの治療法の1つとして有用であると考えられている.
血糖自己測定—保険適用とその実際
著者: 南信明 , 池田義雄
ページ範囲:P.40 - P.41
糖尿病のコントロールの目的は,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症などの糖尿病に特有な細小血管障害ならびに神経障害,そして動脈硬化などの合併症を防止することにある.そのためには,血糖の可能な限りの正常化が不可欠の要因とされる.
血糖を正常に近づけるための最良の手段として人工膵島が世に送り出され,糖尿病性昏睡や手術時などの短期間の血糖コントロールに大きな成果をおさめている.さらに,日常の治療に使用できるように小型化への努力も進行中である.
インスリン頻回注射法の実際
著者: 松田文子
ページ範囲:P.42 - P.43
糖尿病の合併症の進展防止には,血糖値をできるだけ正常範囲に維持することが治療の当面の目標となる.NIDDMでは食事療法や経口剤,または中間型インスリンの1日1回注射でもこの目標を達成しうることが多いが,IDDMでは中間型インスリンの1〜2回注射では不可能に近い.またIDDMでは血糖の動揺が激しく,高血糖と低血糖をくり返し起こし,一定のインスリン量では治療のできないことが多い.
IDDMに対し,できるだけ血糖値を正常に保つように,速効型,中間型,持続型インスリンを組み合わせて1日に2〜4回の頻回注射で行う治療法(頻回注射法:Multiple Injection Therapy)は,CSIIや人工膵島と同じく,インスリン強化療法と呼ばれている.従来の1回注射は,IDDMの治療としては決定的な限界があり,良好な血糖コントロールを得ることはまず不可能であり,頻回注射法は最近IDDMの通常のインスリン治療法となってきた.血糖の変動の激しい不安定型IDDMや,より厳格なコントロールを必要とする妊婦においては,日々の血糖値に合わせてインスリン量の調整が必要であり,頻回注射法に加えて,血糖自己測定の結果に基づくインスリンのスライド方式やインスリン持続注入法による治療も行われる.
インスリン皮下持続注入療法(CSII)の適応と限界
著者: 難波光義 , 垂井清一郎
ページ範囲:P.44 - P.45
CSIIの実際
インスリン皮下持続注入療法(Continuous Subcutaneous Insulin Infusion:CSII)は,強化インスリン療法1)の1つとして人工膵島開発の過程で派生した新しいインスリン治療である.携帯型ポンプ(筆者らはニプロSP-3Rを使用)を用いて,中性速効型インスリンを腹壁皮下に刺入留置した翼付針を介して,持続的に注入する.はじめてCSIIを導入する際は,全例,教育をかねて入院のうえ行う.インスリンは,たとえばノボ・アクトラピッド・ヒューマン40Rを希釈することなく用いる.これは希釈操作の誤りや汚染を防ぎ,インスリン製剤そのものの安定性を損なわないためである.注入セットの交換は原則として入浴時に行うが,少なくとも48時間に1回は更新がのぞましい.
1日注入インスリン量は,従来使用していたインスリン総量の70%を目安とする.その40〜50%を持続的な基礎注入量として,モータードライブで24時間かけて注入する(症例によっては,日中と夜間の注入速度が異なる場合もある).残り50〜60%は毎食前や軽食前に分割し,追加注入として手動操作で注入する.朝・昼・夕食に必要な注入量は症例によって異なるが,一般的には3:1:2のことが多い.導入当初は各食前後と眠前(必要があれば夜間も)の時点で血糖値を測定し,インスリン注入量の調整を行う.
糖尿病性昏睡の緊急治療
著者: 七里元亮 , 鮴谷佳和 , 山崎義光
ページ範囲:P.46 - P.48
糖尿病患者が昏睡に陥った場合,①ケトン性昏睡,②高浸透圧非ケトン性昏睡,③乳酸アシドーシス(稀な病態),④低血糖性昏睡,⑤糖尿病患者に合併する他疾患による昏睡,を念頭において鑑別する必要がある.なかでも,低血糖性昏睡(薬剤性低血糖症)との鑑別が重要,かつ緊急を要するが,一般的に,発症までの経過,低血糖症状と血糖値(50mg/dl以下)から容易に鑑別しうる.
かかる昏睡患者の治療原則は早期発見と早期治療にあり,刻々変化する患者の病態を絶えずチェックし,情報を的確に把握し適切な処置を行う必要がある.
合併症の治療と患者指導
網膜症の光凝固と硝子体手術
著者: 福田雅俊
ページ範囲:P.52 - P.53
網膜症の管理・治療は,内科医と眼科医との共同作業で行われなければならない.
網膜症がないか,あっても軽症・良性のうちは,管理・治療の主役は内科医であり,原則として全身管理の適正化により網膜症の発症・進行を阻止すべきであり,糖尿病の治療と患者指導(管理)に努めているにもかかわらず網膜症が発症・進行するときは,その管理法がこの患者にとっては適正ではないことを意味する.したがって内科医は,全身管理法の適否をチェックする意味で,常に眼底病変の動きに注意すべきである.不幸にして網膜症が悪性化(増殖化)したときは,網膜症管理の主役は眼科医に移り,後述する局所的な治療処置を眼科医は実施せねばならない.これらはより早期に実施するほど効果が大きい.したがって眼科医は,局所的処置の時期を見失わぬように眼底病変の動きをたえず注意せねばならない.
腎症患者の食事療法と指導
著者: 星充 , 中村多慶男
ページ範囲:P.55 - P.61
糖尿病で腎症を合併した症例の食事療法は,合併症のない糖尿病患者の食事療法の基本原則を守りながら,尿蛋白量,浮腫,血中尿素窒素値,食欲などの臨床像を参考に,病態改善を目的として蛋白質,食塩の制限を加味したものとする.このためには腎症の進行の程度に応じて病期を区分しておくのがよいが,腎症を発症する以前より行ってきた食事内容を若干変更することになるので,患者および家族の十分な理解が得られるよう説明と指導を行わねばならない.
腎症透析患者の管理と指導
著者: 山崎親雄 , 柴田昌雄
ページ範囲:P.62 - P.63
糖尿病人口の増加,インスリン自己注射による血糖コントロールの良好化,透析療法の一般化などにより,糖尿病性腎症(以下DM腎症)を原疾患とする血液透析(以下HD)患者の増加は著しい.日本透析療法学会の調査では,1984年に透析に導入された10,832人中,1,885人(17.4%)がDM腎症であったとされている1).
起立性低血圧と無力性膀胱の治療
著者: 姫井孟 , 宮下雄博
ページ範囲:P.64 - P.65
起立性低血圧の治療
糖尿病性自律神経障害でとくに交感神経が障害をうけると,起立時の末梢血管床における細動脈の反射性収縮が起こらず,末梢血管抵抗は低下し,静脈血の還流減少による心拍出量の減少と血圧の低下が起こる.起立により収縮期血圧が30mmHg以上降下し,何らかの症状が出る場合には治療が必要になる1).インスリン使用者では,低血糖によるふるえ,冷汗などに加えてめまいを訴える例もあり,低血糖との鑑別が必要であるが,自律神経障害が高度の例では,低血糖が無自覚に起こることがあり,注意を要する.起立性低血圧を助長する可能性のある薬剤として,tranquilizer,guanethidin,betanide,methyldopa,a-blockerなどがある.投与されていた場合は薬剤を中止し,頭部を挙上して寝ることを勧め,急激な体位の変換を避けるように指導する.腹部圧迫バンドや弾性肌着は下半身への血液貯留を防止するために用いるが,静脈血の還流障害を起こさないようにしなければならない.極度の水分制限や,長期にわたる塩分制限も,循環血液量の減少による起立性低血圧を惹起する原因になり得る2).
壊疽の病態と治療
著者: 富長将人
ページ範囲:P.66 - P.67
糖尿病性壊疽はわが国では少ないとされていたが,近年増加傾向にある.壊疽とは一般に,組織が壊死に陥った病態をいうが,糖尿病性壊疽は病因あるいはstageによっては潰瘍形成のみのこともある.ここでは,これらを総称して広く壊疽として扱うこととする.
計画妊娠と妊婦の管理
著者: 大森安恵
ページ範囲:P.68 - P.69
約5年位前までは,妊娠中糖尿病昏睡に陥り死産に終わったという既往歴をもつ糖尿病者が多かったように思う.最近は,妊娠半ばまで糖尿病の治療が放置され,糖尿病前昏睡の状態で転送されてくる症例にしばしば遭遇する.一般にわが国における糖尿病と妊娠に対する関心と対策は,まだかなり低い印象をうける.Joslin Clinicからの1つの論文によると1),1928年から1938年の間に,20歳以下で糖尿病と診断され生存していた男女症例をしらべてみると,289名中89%が結婚し,多くの症例で子どもをもっている.これは,インスリンが発見されて間もない時代に,糖尿病があっても結婚や妊娠はごく普通に行われていることの証左である.
またごく最近のアメリカでは,糖尿病性腎症のために,腎移植をうけた後,妊娠し出産した症例がすでに9例も報告されている2).糖尿病があると妊娠は難しいというのはすでにはるか過去の時代であり,現在は計画妊娠の時代であるといえる.
トピックス
ヒト・インスリン製剤の長短
著者: 中川昌一
ページ範囲:P.72 - P.73
ヒト・インスリンとは
ヒト・インスリンは本来ヒトから抽出した天然ヒト・インスリンを指すが,現在治療用として供給が始まっているのは,ヒト・インスリンとアミノ酸構成が等しいヒト型インスリン(Human sequence insulin)である.現在ヒト型インスリンを作る方法は,ヒト膵から抽出する方法の他に,化学的完全合成,ブタ・インスリンよりの転換(半合成),遺伝子工学的手法による生合成などの方法があるが,工業的に治療用として供給されている製剤は半合成(Novo社,Nordisk社,Hoechst社,日本ではNovo-小玉のみ)と生合成(EliLilly社-しおのぎ,現在はA,B鎖を生合成して化学的に結合させる方法を使用)されたもので,抽出ヒト・インスリンは原料の関係から,全合成は価格の関係から工業生産されていない.
インスリン・レセプター異常症と異常インスリン症
著者: 小林正
ページ範囲:P.74 - P.76
糖尿病は絶対的あるいは相対的インスリン作用不足による疾病であり,インスリンが分泌されていてもその作用が十分でない場合は耐糖能異常を生ずる.インスリン作用の発現には標的細胞(筋肉,脂肪,肝)のインスリンに対する反応性の異常でも惹起するが,またインスリンそのものの異常でもインスリン作用の発現が低下する.インスリン作用発現のための第一歩は,インスリン・レセプターへの結合である.したがって,標的組織のレセプターが異常であっても,インスリン側のレセプター結合部位が異常であっても,インスリン作用は低下する.このような異常をもつ患者が,稀ではあるがここ7〜8年で次々と発見され,新しい糖尿病の型としてother typesの中に含まれる.
IDDM(Ⅰ型)糖尿病の免疫療法
著者: 豊田隆謙 , 佐藤譲 , 新谷茂樹 , 手塚幸子
ページ範囲:P.78 - P.80
糖尿病の免疫に関するシンポジウムが,エドモントン(カナダ,1986年6月26日)で開催された.インスリン依存性(Ⅰ型)糖尿病〔insulin dependent(type 1)diabetes;IDDM〕の免疫異常について議論されたが,必ずしも成績が一致せず,矛盾が多く,混沌とした状況にある.それゆえ,IDDMの免疫療法は古くて新しい課題になっている.
IDDMの免疫異常についてはかなりのことが分かってきたが,焦点は膵β細胞障害過程にあてられている.体液性免疫に関しては,ラ島抗体(ICSA)あるいはインスリン抗体(ln Ab)の出現とIDDM発症と関係があり,細胞性免疫に関しては,膵β細胞障害性Tリンパ球とそれをregulateしているサプレッサーTおよびヘルパーTリンパ球に異常があり,自己免疫疾患(autoimmune disease)の1つと理解されている.したがって,免疫過程のどこを調節すれば膵β細胞障害性Tリンパ球を抑えることができるかを考えるべきである(図).
膵移植の現況と展望
著者: 高見実 , 出月康夫
ページ範囲:P.82 - P.84
膵移植の歴史は古く,すでに1893年にヒツジの膵組織片を糖尿病性昏睡の少年の皮下に異種移植したという最初の膵移植の報告がみられる.1960年に入りAzathioprine(AZA)の発見により腎・心臓などの各臓器移植の臨床応用が盛んとなり,膵移植も1966年第1例の臨床報告がなされ,すでに20年の月日が流れようとしている.本稿では,膵移植のかかえる問題点を明らかにし,わが国での臨床応用の可能性について述べてみる.
膵移植には,血管吻合を用いる膵臓移植と,内分泌腺組織であるラ島のみを移植するラ島移植の2つの方法がある.後者のラ島移植においては,純粋のラ島が多量に分離回収できる小動物では目覚ましい進歩がみられるものの,ヒトを含めた大動物では膵臓の豊富な繊維成分のため純粋なラ島が十分量分離回収できず,臨床においてはその成績はきわめて不良である.1984年6月までに166例の臨床報告があるものの,インスリン注射から完全に離脱できた症例は1例もない.現在欧米においては,前者の血管吻合を用いた膵臓移植が主体となっており,本稿でも同移植方法について述べる.
座談会
糖尿病患者のホームケアをどう指導するか
著者: 平田幸正 , 池田義雄 , 池田正毅 , 繁田幸男
ページ範囲:P.87 - P.100
繁田 本日は,「糖尿病患者のホームケアをどう指導するか」につきまして,平田先生,池田義雄先生,池田正毅先生に,いろいろお話を伺っていきたいと思います.どなたも糖尿病の大ベテランですし,患者の診療,教育についても長年のご経験があります.したがって,ホームケアについていろいろなノウハウをたくさんおもちだと思いますので,今日はそれを忌憚なくご披露いただければ幸いです.
ご承知のように,成人病というのはホームケアが非常に大事なのですが,とくに糖尿病は食事療法,運動療法,これはもうホームケアの充実がなくては事実上成り立ちません.しかも昭和56年に,わが国においてもようやくインスリンの自己注射が法的に認められました.これはもちろんそれ以前からもすでに実行されていたわけですけれども,それ以後はとくに患者が在宅でインスリン療法を行うということが急速に普及しました.61年4月には血糖自己測定が健保適用になったということで,この面でもさらにホームケアが徹底してきたということができます.
Current topics
電子内視鏡の現況
著者: 市岡四象 , 片山修 , 長谷川みち代
ページ範囲:P.137 - P.145
日本人は独創性はともかくとしても,応用力に関しては抜群の能力を持っている民族といえよう.ファイバースコープがわが国に導入された直後に,そのスコープの外側に鉗子をとりつけて胃生検に成功したのも先達であり,接眼部にTVカメラを装着してモニターTVに映像させたのも日本人である.
後述するように,当時のTVカメラは超大型で,重いし,その操作も大変だった.「いっそのこと,ファイバースコープを用いないで,TVカメラを飲み込んで直接映像を取り出すことを考えたらどうだろう」とメーカーの技術者に話したら,「等身大のTVカメラをどうやって体内に入れられますか?」と一笑に付されてしまった.
カラーグラフ 皮膚病変のみかたとらえ方
皮膚に原発する癌の臨床像
著者: 石川英一 , 二瓶義道
ページ範囲:P.106 - P.107
概念
皮膚癌には大別して,皮膚に原発するものと,皮膚以外の臓器に発生し,皮膚に転移するものとがある.本文では原発性皮膚癌について述べる.原発性皮膚癌には,(1)表皮粘膜上皮および毛包上部の重層扁平上皮に発生する有棘細胞癌,(2)脂腺,汗腺,毛包を発生母地とする皮膚付属器癌,および,(3)表皮内癌がある.さらに表皮内癌にはBowen病と乳房外Paget病の別がある.乳房Paget病は乳癌の皮膚転移と考えられるのでここでは省略する.
リンパ節疾患の臨床病理
ホジキン病
著者: 茅野秀一 , 片山勲
ページ範囲:P.117 - P.120
ホジキン病(Hodgkin's disease)は,いわば"古くて新しい病気"である.リンパ系腫瘍性疾患の歴史は,1832年Thomas Hodgkinが,系統的リンパ節腫脹と脾腫を伴い,悪液質で死亡した7症例を報告したことに始まる.以後,症例の蓄積・解析が進むにつれて,このようなリンパ系疾患群から白血病と現在の非ポジキンリンパ腫に相当するリンパ肉腫・細網肉腫が独立疾患として分離された.その残りのなかに特異な形態を呈する細胞(spezifische Zellen)の出現を特徴とする疾患群があり,これはSternbergによってリンパ肉芽腫症(Lymphogranulomatosis)と呼ばれた.現在,ホジキン病と呼ばれるものはこのリンパ肉芽腫症に相当し,spezifische Zellenのうち多核のものはReed-Sternberg細胞(RS細胞),単核のものはHodgkin細胞(HD細胞)と呼ばれることが多い.
悪性リンパ腫は,ポジキン病と非ポジキン病とに2大別されるのが一般的である.しかし,最近の急速な免疫学の進歩が非ポジキンリンパ腫研究に数々の成果をもたらしたのに対して,ホジキン病に関しては腫瘍組織中に出現するリンパ球・組織球が非腫瘍性・反応性のものであることが確立しているものの,疾患の本質に迫る腫瘍細胞(RS細胞・HD細胞)の起原については未だ不明な点が多く残されている.
グラフ 消化管造影 基本テクニックとPitfall
胃(6)—隆起性病変;境界領域病変
著者: 西俣寿人 , 西澤護
ページ範囲:P.122 - P.129
西澤 良性隆起性病変の中でポリープ,粘膜下腫瘍の他にもう1つ問題になるのは,いわゆる境界領域病変ということになります.境界領域というと,異型上皮ともいいますし,IIa subtypeともいいますし,腺腫ともいいます.境界領域病変というのは生検でGroup IIIと診断される上皮性の隆起性病変ですが,普通のポリープとか,粘膜下腫瘍に比べると,形が少し変わって,どちらかというと広基性で平板状のものが多いといわれていますが,この症例はどうでしょうか(図1).
演習
目でみるトレーニング
ページ範囲:P.109 - P.115
心電図演習【新連載】
50歳の会社員の男性が,労作時胸部圧迫感を訴えて,紹介来院した.
著者: 石村孝夫
ページ範囲:P.131 - P.134
既往歴 特記するものなし.喫煙1日30本を28年間(3年前に中止)
家族歴 父,48歳で突然死
—内科専門医による—実践診療EXERCISE
関節痛,息切れ,他
著者: 高林克日己
ページ範囲:P.147 - P.152
35歳,男性,運転手.5年前から膝関節痛があり,昨年から手指の移動性関節痛と腫脹,および朝のこわばりをみるようになった.2ヵ月前から息切れが強くなって階段を上れなくなり,また38℃の発熱をみたため,近医を受診したところ肺炎と診断され入院となった.しかし入院後も改善がなく,また右足の背屈ができなくなったため当科を紹介された.他の筋力の低下や筋痛は認めなかった.
理学所見:身長172cm,体重62kg,体温37.8℃,血圧142/78,脈拍82/分,整.結膜:貧血・黄疸なし.口腔内:異常なし.頸部:リンパ節・甲状腺を触知せず.心音:正常,呼吸音:両下肺野にVelcroラ音を聴く.腹部:異常なし.四肢:浮腫なし,右足関節背屈不能.
講座 内科診療における心身医学的アプローチ【新連載】
循環器疾患(1)—本態性高血圧,本態性低血圧,起立性低血圧
著者: 菊池長徳
ページ範囲:P.158 - P.162
よく知られているように,情動ストレスに対して敏感に反応する系として循環器があり,特に血圧はその際のよい指標となっている.このことはすでにCannonが指摘しているが,何か緊急事態に遭遇した場合,それに対処するため血液の循環を増やすことと関係しているものと思われる.この際,交感神経-副腎髄質系(カテコールアミン)の働きが主役をなしていることも,彼が動物実験で証明している.いわゆる緊急反応である.
一方,Selyeはそのストレス学説において,慢性のストレスに対して脳下垂体一副腎皮質系(コーチゾル,アルドステロンなど)が主に反応することを証明している.いずれにしても種々のストレスに対し,自律神経-内分泌が相互に関係して反応するが,血圧はこの反応状態をよく反映している.
救急 図解・救命救急治療【新連載】
心肺蘇生の新しい概念とその限界
著者: 山本保博 , 黒川顕
ページ範囲:P.164 - P.169
最近の救急センターでは,DOA(dead onarrival,入室時心肺停止患者)が目出つようになってきた.救急情報システムの発達や,救急患者に対する世間の目が厳しくなってきたためだろうか,救急隊員も心肺蘇生を施行しながら何とか医療機関に搬送しようと努力することにも理由があるのだろうか.東京においては,病院前心肺停止(prehospital cardiopulmonary arrest)患者の蘇生成功率はすでに25%を越えている.
心肺蘇生は,古くて新しい問題を多く含んでいる.胸骨を圧迫すると心臓から血液が駆出するというmechanismが,まだ十分解明されていない.それゆえ,閉胸式がよいのか,開胸式心肺蘇生にしたほうがよいのかも議論のあるところである.
症例から学ぶ抗生物質の使い方【新連載】
糖尿病に伴う尿路感染症
著者: 北原光夫
ページ範囲:P.170 - P.171
症例
58歳女性.糖尿病歴が20年あり,インスリンをNPH16U毎朝使用している.2カ月前と1カ月前に37.5℃の発熱と排尿障害を数日間認め,外来の診察ではCVAに圧痛はなかった.尿検査上,尿中に多数の白血球を証明し,尿糖は++++であった.ただちに治療を開始した.2カ月前には第1世代経口剤750mg/日を5日間投与し,尿所見も改善した.1カ月前はST合剤4錠を1回で投与し解熱していた.2回とも尿培養は大腸菌を105/ml以上認めている.今回は38℃の発熱とCVAの圧痛で救急外来を訪れている.緊急検査では無数の白血球を尿中に認めている.
循環器疾患診療メモ【新連載】
右室梗塞
著者: 山科章 , 高尾信廣
ページ範囲:P.174 - P.175
従来,急性心筋梗塞は前壁梗塞,下壁梗塞などと分類され,左室の梗塞として考えられてきた.右室については病理的には認められていても臨床的には検討されることはなかった.1970年代になりSwan-Gantzカテーテル,心エコー,心臓核医学検査の発達により右室梗塞の臨床診断が可能となり,急性心筋梗塞の中で特異な病態を示すものとされ注目されるようになった.
新薬情報
アゼプチン〔エーザイ〕 一般名:塩酸アゼラスチン—アレルギー治療剤
著者: 清川重人 , 水島裕
ページ範囲:P.154 - P.156
概略
気管支喘息および鼻アレルギーでは,気管支粘膜や鼻粘膜の肥満細胞上のIgE抗体が抗原と結合し,ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が遊離され,気道平滑筋の攣縮,気道粘液や鼻汁の分泌亢進,毛細血管透過性の亢進が起こり,喘息発作や鼻アレルギー症状が誘発されると考えられている.
アレルギー治療剤としての化学伝達物質抑制剤は,発作を抑える対症療法とは異なり,疾患発症機構に作用して発作を予防する薬剤として,これまでにインタール(DSCG),リザベン(トラニラスト),ザジデン(ケトチフェン)などが開発,臨床応用されている.アゼプチン(Azeptin,アゼラスチン)はエーザイが世界に先駆けて開発したフタラゾン誘導体であり,従来の薬剤がその作用点をSRS-A(slow reacting substance of anaphyla-xis)としてしかつかめなかったのに対し,アゼプチンはロイコトリエンを作るリポキシゲナーゼに作用しロイコトリエンの産生を抑制,さらにロイコトリエンの直接拮抗作用をも合わせもつ新しいタイプのアレルギー治療剤である.また,喘息に対してはアレルギー型の喘息はもちろんのこと,抗原抗体反応とは関係のない運動誘発喘息においても,化学伝達物質を介する気道狭窄を抑制し効果を発揮するという.
一冊の本
「遠き落日」—渡辺 淳一,角川文庫,昭和57年
著者: 相澤豊三
ページ範囲:P.173 - P.173
往々にして偉人の伝記は,その光の部分が強調され,陰の部分や人間的な側面が十分に現わされていないきらいがある.野口英世の伝記もその典型であり,「貧農の子として生まれ,米国に渡り数々の発見をし,世界に有数な医学者となる」という伝記を子供の頃から読み親しんできたのは筆者だけではないと思う.本書の著者渡辺淳一氏は整形外科医出身の作家だけに,そのような偶像崇拝的な伝記にあきたらず,外側から野口英世像を描き出すだけでなく,その体内深く分け入って骨を探るといったまさしく外科医のメスと作家のペンとの緊密な連係を物語っているようで,非常に興味深い.事実,野口英世についての日本の伝記は米国における生活の記述が十分でなく,また米国の伝記は日本における生活の記述が十分でない.本書はその両者に偏ることなく描かれている.
基本情報
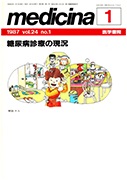
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
