老人に投薬するにさいしての注意
年をとると,循環器,消化器,脳神経,内分泌器,泌尿器など全臓器に老化現象が起こり,薬の薬理学的作用に重大な影響をきたすようになることは容易に想像できる。
従来,小児では成人に比べると薬の作用がしばしば相違することは検討されてきているが,老人と成人との相違はあまり報告されていなかつた。しかし近年人口は老齢化し,内科方面はもちろんのこと,一般外科においても老人の占める割合は多く,須藤らは一般外科患者の25%は65歳以上であると述べているほど増加したので,老人の薬剤効果とくに麻酔について深い関心がはらわれ,動物実験を初め臨床的にもかなり多くの研究がみられるようになつた。
雑誌目次
medicina3巻10号
1966年10月発行
雑誌目次
特集 老人患者を診るとき
EDITORIAL
老人と薬
著者: 石原国
ページ範囲:P.1393 - P.1395
今月の主題
老人の慢性呼吸器疾患
著者: 長沢潤
ページ範囲:P.1396 - P.1400
老人であるが故に注意を要する呼吸器疾患,老人であるが故にしばしばみられる呼吸器疾患がある。ここでは老人における慢性呼吸器疾患を生活指導,環境指導の面からとりあげてみた。
老人の心不全
著者: 小沢利男
ページ範囲:P.1401 - P.1404
わが国の死因統計によれば,心臓疾患は,中枢神経系の血管損傷,悪性新生物についで第3位となつている。これを病型別に見ると,心臓弁膜症は一般に減少傾向を示すに反し,動脈硬化性心疾患は1964年には1950年の2,5倍,その他の心筋変性も3倍以上に増加している。高齢者における心臓病は今後もますます増大することが予想せられ,臨床家にとつても大きな問題といえよう。
<話合い>老人患者の診かたと生活指導
著者: 日野原重明 , 佐々廉平 , 吉川政己
ページ範囲:P.1406 - P.1412
急速な医学の進歩は,老人人口の増加をもたらし,そのため老人患者もふえている。そして,老人の病気には老人特有の現われかたがある。老人患者を診るときの注意点,また老人が寿命を全うするだけでなく,健康に活躍するためには,どのような生活指導が必要であろうか。
基礎医学
老化の生理
著者: 相沢豊三
ページ範囲:P.1413 - P.1416
近年,本邦においても平均寿命の延長につれ老年者に関する研究はしだいに発展してきた。しかしながら,老化は生命現象とも直接的関係をもつものであり,その全面的な解明はかならずしも容易ではない。したがつてその研究も老化の本態追求の手がかりとなるべき諸現象の研究が行なわれているのが現状であり,今回はこの立場から老化の生理をとりあげてみた。
診断のポイント
老人の黄疸
著者: 高橋忠雄
ページ範囲:P.1417 - P.1418
ほかのどの病気についてもいえることかとは思うが,黄疸という症状の鑑別診断にあたつては,とくに年齢という点の考慮がきわめて大きな意義をもつている。ことに乳幼児の黄疸や,若年者に発見されるtransferase deficiencyにもとづくconstitutional jaundiceについては,その感が深い。しかし,一方老齢者での黄疸では,それ以上に診断の過誤が重大な結果をもたらすことになるので,鑑別にはきわめて慎重を要する。
老人の正常値をどう考えるか
著者: 松木駿
ページ範囲:P.1419 - P.1420
正常値と標準値
すべての医学的測定値は,それと比較して異常かどうかを決めるために,正常値が必要である。正常値は普通正常人(normal men)から得られた値であるが,正常人をどのような定義で決めるかが問題で,実際には正常と思われる人(probablynormal men)の値ということになる。病気を除外するのにどのような検査を行なつて,またどのような判定基準で正常としたかを考えると,それが真の正常人であつたかどうか自信がなくなつてしまう。病気以外にも経済状態,食事内容,ふとつているかやせているかなどの栄養状態,季節などの影響を受ける可能性のある測定値も少なくないであろう。そうなると正常値(normal value)は現段階で簡単に決めるべきものではなさそうである。しかし実際にはある基準となる値が必要であるから,それを正常値でなくて標準値(standard value)とよぶのはどうであろうか。標準値は1つの"ものさし"と考えれば,よりよいものさしができたらそれに換えてゆこう。従来正常値として報告されているものは標準値として理解して,その値が得られた対象の条件をなるべく詳細に記載しておいてほしい。年齢,性別はもとより病気を除外するための検査法や判定基準,栄養状態,経済状態を想定できるような事柄,できれば材料採取の季節などである。それらを集積すればやがて真の意味の正常値が得られるのではなかろうか。
治療のポイント
脱コレステロール剤に期待できるもの
ページ範囲:P.1423 - P.1425
主たる脱コレステロール剤についてその特性,副作用などを述べ,コレステロールを下げることが,粥状硬化性疾患の予後にどのような利点があるのかについてふれてみたい。
高齢者の胃潰瘍
著者: 中村卓次
ページ範囲:P.1426 - P.1427
高齢者の胃潰瘍の種類
最近われわれが高齢者の胃潰瘍に遭遇する機会が急速に増加してきている。これは最近の平均寿命の延長に伴い,高齢者の人口が増加していることや,診断技術の進歩によるところが大きいと考えられるが,実際に高齢者の胃潰瘍羅病率が他の年代に比し比較的高く,種々な理由で潰瘍になりやすいといわれている1,3,5)。
高齢者の胃潰瘍にはつぎの3種類のものが考えられる。(1)高齢に達してから初発し,若年者潰瘍と種々の点で異なつた特徴を有するもの。(2)若年期に初発し,難治性で老年期にいたつたもの。(3)高齢者特有の急性潰瘍。
他科との話合い
老人の骨と関節
著者: 森崎直木 , 春日豊和
ページ範囲:P.1459 - P.1465
腰や肩,膝などの痛みを訴えて内科を訪れる患者は非常に多い。このような患者のなかには,どのような骨の病気が含まれているのだろうか。レ線写真の読みかたを中心に。(グラフを併読されたい)
グラフ
老人の骨・関節障害
著者: 森崎直木
ページ範囲:P.1385 - P.1390
老年期になると骨・関節にも変性消耗現象ないしは代謝異常が現われて,そのための障害が発生する。その第1が変性消耗疾患としての変形性脊椎症,椎間板変性,変形性関節症であり,第2が代謝異常(あるいは内分泌異常)としての骨多孔症(粗鬆症Osteoporose)である。これによつて腰背痛,関節痛が起こり,あるいは歩行起居能力の減退をみるので整形外科として,重要な部門であるばかりでなく,実地医家も日常の診療上これらに関する知識を欠くことはできない。以下これらの疾患のほか,いわゆる五十肩(これも腱付着部などの消耗変性疾患とみなしうる),老人に多い骨の悪性腫瘍などについて,主としてレントゲン像を示して解説する。—なおべつに掲載した他科との話合いの項(91頁)を参考にされたい。
薬の反省
消化酵素剤
著者: 増田正典 , 細田四郎
ページ範囲:P.1432 - P.1433
ちかごろ綜合消化酵素剤というものが一つのブームのようである。国内だけでも20以上におよぶ製品が競つて発売されている。この時点において,綜合消化酵素剤の適応について再考することは意味のないことではあるまい。各種の綜合消化酵素剤のそれぞれの特性を考慮して,症例に応じたものを正しく使うように心がけるべきであり,ただ漫然と投与する愚は避けるべきであろう。
診断のポイント
妊婦の無症候性細菌尿
著者: 松田静治
ページ範囲:P.1421 - P.1422
意義と頻度
婦人の尿路は解剖学的にも生理学的にも性器との関係が密接で,外陰,腟には生理的状態においてすら,常在菌が数多く存在しているため,尿路はつねに感染の危機にさらされているといつても過言でない。事実男子に比べて婦人における尿路感染症の発生頻度は数倍にも達する。さらに加えて妊婦では尿路が妊娠により局所的な影響を強く受けるようになる。すなわち下部尿路(膀胱,尿道)は妊娠月数の進むにつれ,増大した子宮の圧迫を受け膀胱は形態的に変形をきたし,膀胱壁の弛緩が起こる。これの進んだ状態として分娩時には児頭の圧迫などの影響も加味されるから必然的に産褥期に短期間の膀胱麻痺をまねきやすい。したがつて妊婦には尿滞留などの誘因により細菌感染の機会が増加するのは当然である。しかもなお仕末の悪いことは自覚症状がほとんどないため,無症候性細菌尿といつても一般の関心をひかず,尿検査を行なわないかぎり看過されるおそれがあることである。このような潜在性の腎盂腎炎を含む妊婦の無症候性細菌尿(この場合細菌尿とは尿1ml当り菌数が105=10万以上のものをいう)はしばしばみられるもので,なかには数年間にわたり進行し,患者は腎不全症状がはつきりするまで重篤なことに気がっかずにすごしてしまうことがある。とくに注目すべきは妊娠中毒症患者に細菌尿の頻度が高い点で,これは高血圧患者に比較的高率に尿路感染症が合併しているという報告とあわせて興味深い。
治療のポイント
慢性関節リウマチ
著者: 佐々木智也
ページ範囲:P.1428 - P.1429
慢性関節リウマチの機能的予後は絶対に不良か
どのように医師が努力しても予後絶対不良の慢性疾患に対しては,本来そうであつてはならないことは承知していても,医師も神ではないので治療に対する熱意が沮喪しがちである。慢性関節リウマチrheumatoid arthritisは絶対になおらないという誤つた考えかたが広く信じられているので,この病気もある意味で医師からみはなされやすいものである。しかし,多数例についてその予後を調べてみると,初期に入院を要する程度の者のなかでも重度の身体障害者となるのは約10%にすぎず,全患者の1/3はほとんど機能障害を残さずに病勢が停止するものである。この数字は十分な治療が長期にわたつて行なわれるならば,さらによい結果に変えうるものと思われる。すでに相当程度の障害を発生した者についても,何年間かにわたり適切な治療を継続すると,機能的にいちじるしい改善のみられる事実(間 得之,1965)はこの考えかたを支持するものである。希望があるのであれば,医師はどのようにすべきであるのか。
外科にまわしてほしい高血圧
著者: 和田達雄
ページ範囲:P.1430 - P.1431
手術によつて治療できる高血圧症の種類
高血圧症はいろいろな原因によつて発生するが,このうちの相当数のものが手術によつて軽快もしくは治癒することが知られている。現在のところ外科的に治療しうる高血圧症は,つぎのように分類されると思う。
1) 内分泌性高血圧症
ファースト・エイド
器械の使い方
ネブライザーの使いかた
著者: 藤本淳
ページ範囲:P.1438 - P.1440
ネブライザーのいろいろ
ネブライザー(nebulizer)は0.5〜3μ程度の微粒子を含んだエロゾル(aero-sol)を発生せしめる器具につけられた名称で,エロゾル発生器(aerosolgenerator)ともいわれる。一般には霧吹きの原理によつて作られているが,最近では超音波を利用したものも市販されるようになつた。霧吹きの原理を応用した吸入用の粒子作製器にはネブライザーのほかに蒸気吸入器やアトマイザーとよばれているものがあり,これらは3μ以上の大きい粒子が主として含まれている。また気道に湿潤性を保持させるために吸入ガスの湿度を増加させるものとして加湿器(humidifier)がある。
上記した各種の器具はいずれも気道が外界に開放されていて,呼吸運動によりガスや微粒子が気道内に入ることを医療面に応用せんとして作られたものである。
正常値
日本人の性年齢別基礎代謝
著者: 中村正
ページ範囲:P.1468 - P.1470
基礎代謝熱量(以下基礎代謝量)は他の生理機能値と同様にかなりの個人差があり,また同一人でも日によつて5%程度の変動がある。一般に基礎代謝が体表面積によく相関する事実から(ただし熱帯では体重との相関が大きいとするGalvao1)の説もあるが),単位体表当たり値で標準値が示されていることはいうまでもない。
ところがこの場合につぎのような問題がある。基礎代謝測定実験の結果を,x軸に体表面積を,Y軸に実測代謝値をとってプロットしたとする。そこで,休表面積xと代謝yとの間に高い相関関係が認められたとしても,かならずしもxに対するyの回帰直線が座標の0点をとおるとはかぎらない。しかるに,基礎代謝量を体表当たりで表わすということはy/x=Constant,すなわち測定値の分布が全員平均点(x,y)と0点とを結ぶ直線に沿つていることを前提とした表わしかたである。厳密には,実験値をもととして,標準値は体表面積値に対する基礎代謝絶対値の回帰方程式(y=ax+b)のかたちで表わすべきである。
症例
かきの打ち子喘息—ホヤ喘息
著者: 城智彦 , 勝谷隆 , 大塚正
ページ範囲:P.1486 - P.1490
「かきの打ち子喘息」は典型的な職業病の一つで,アレルギーの原因を明らかにすることのできた数少ない喘息の一つである。広島周辺のかきのむき身作業者のあいだに数百名以上の患者がいるが,広島以外でも,かき業者や真珠養殖業者のなかに同じような機転で喘息発作を起こす人があると思われるので,広く注意を喚起したい.
心音図の読みかた(1)
機能性雑音と僧帽弁膜症の三つの症例
著者: 楠川禮造
ページ範囲:P.1481 - P.1485
心音図を読む前の準備
心音図を実際に読むにあたつてその前に,つぎの二つのことをぜひ準備しておきたい。
第1はその患者について病歴,現症,簡単な検査成績たとえば血圧,胸部X線写真,心電図などを知つておく必要がある。とくに心音は慎重に残すところなく聴診し,聴診所見によつてあらかじめ診断を樹立しておき,後で心音図を見るようにするのが望ましい。聴覚は時間的分析の点では心音図に劣るが,音調,すなわち周波数分析については心音図のはるかにおよばないすぐれた分析力をもつているからである。他の身体的所見および臨床検査成績は心音図による診断の決定に役だつばかりでなく,その疾患の程度を決定するうえにも重要である。
痛みのシリーズ・12
「いたみ」のしくみ論議
著者: 清原迪夫
ページ範囲:P.1474 - P.1476
このシリーズを連載しはじめてから,読者の方々からさまざまな質問をいただいたが,今回はその中から問題点を拾つて,対話形式でまとめてみた。
FOREIGN MEDICAL BOOKS
最近のLuisada教授の著作から
著者: 坂本二哉
ページ範囲:P.1434 - P.1435
数々の力作をやつぎばやに出版するので有名なLuisadaが,最近興味ある著作を著したので紹介することにしよう.
グラフ
痛風の臨床
著者: 吉村隆
ページ範囲:P.1382 - P.1383
痛風はいまやありきたりの関節疾患といえるが,いまだにリウマチと混同されたり,瘭疽,蜂巣織炎などの感染性疾患に誤診される場合が多い。ここでは診断に必要な特徴ある臨床像を示したが,性別,発病年齢,遺伝,体質,食習慣なども診断の助けになる。痛風は尿酸代謝異常により高尿酸血症を示し,慢性かつ進行性の全身病で,放置すれば腎不全,脳血管障害などの合併症が直接の死因となる。しかし早期に診断し,適切な治療を継続すれば病気の予後は極めて明るい。治療はcolchicine,phenylbutazoneなどで急性発作をすみやかに抑制し,probenecid,sulfinpyrazoneなどの尿酸排泄剤で代謝異常を改善せしめるが,最近ではHPP,BCPさらにα-ketophenylbutazoneなどが登場し,病勢コントロールはますます容易になつてきた。
検査データの考えかたとその対策
末梢血液中に幼弱白血球をみたとき
著者: 小宮正文
ページ範囲:P.1377 - P.1377
末梢血液中に幼弱白血球の出現してくる状態は簡単にいえば白血球の左方推移像,白血病様反応,白血病ということになる。
白血球には好中球,好酸球,好塩基球,リンパ球および単球の5種があつて,理論上ではこれら5系統の細胞について,おのおの上記3つの機転による病態が考慮される。しかし,このなかで日常もつとも遭遇しやすいのは好中球系の病態であつて,したがつて,好中球系についての知見がもつとも豊富に集められている。以下,この点を中心に記述する。
If…
当たつた単独結核腫の診定—杏雲堂病院長 塩谷卓爾氏に聞く
著者: 長谷川泉
ページ範囲:P.1442 - P.1443
医学に進むことは決められていた
長谷川 お父様もお兄様も医師でしたから人生のコースは,すでに決まつておりましたか。
塩谷 父は福島の須賀川医学校の校長をしており,そのころ後藤新平を教えました。後藤新平の名古屋時代に岡崎病院長をやりましたが,51歳で,私が3歳のときに死にました。
私の意見
Doctor-nurse relationによせて
著者: 笠間雪雄
ページ範囲:P.1444 - P.1444
病院は他の企業に比較し,とくに対人関係が重要視される職場である。種々な目的のために勤務する職員,医療を受けようとする患者,その他の人が病院に集まり,そのため人と人との接触は多く,対人関係は複雑である。また病院を構成している人間関係の綜合がその病院特有の雰囲気をかもし出す。そのうえ各部門の対人関係の不調整やtroubleは,患者へのserviceの低下はおろか,不満のはけ口として患者へのやつあたりとなつてさえ現われる危険性もある。そのため近年病院における対人関係を円滑にするため病院管理の近代化,組織の改善に努力がはらわれてきた。
病院の中核となるものは医師・看護婦間の職業的team workである。戦後このdoctor-nurserelationにも大きな変化が起こつた。看護婦は医師の従属的上下関係より技術的専門職業として認められるようになり,その地位向上の結果,職業的には医師と対等な立場に立つて医療に従事することとなつた。すなわち看護婦は総婦長をpyramidの頂点として婦長,主任看護婦,看護婦というchain of commandで結ばれ,総婦長の指揮下に各科へ配属され,看護部門を担当し,また随時配置転換される。この制度の長所は多々あるが,一方医師の側より看護婦に対して以前よりも多くの批判が出てきていることも事実である。
ゆりかごから墓場まで1冊のカルテを
著者: 児玉武伊知
ページ範囲:P.1445 - P.1445
注射の嫌いな医師
だいたい子どもに注射を多用する医師と注射を歓迎しない医師とがある。私としては注射をあまりやらない(採血はのぞいて)医師のほうが技倆は一般にすぐれていると考えたい。私も診断あるいは予後の診たてについて自信の乏しかつたころには注射を多用した思い出がある。また注射の嫌いな医師にも,一つは小児におよぼす注射の弊害について認識されている方と,もう一方は子どもが可愛いそうだからとか,あるいは子どもに泣かれるとうるさいからというタイプの先生もいられる。いずれにせよ,子どもにはなるべく注射をされない開業医が一般に繁盛しているように思うがどうであろうか。乳児でも注射をやらない医師には,診察時に十分協力してくれることを日ごろより感心している。現状では泣き声で騒々しい小児科の診察室を内科のように静かな状態に近づけてゆくのもわれわれの努力次第ではなかろうか。
私のインターン生活
4日の研修2日のバイト
著者: 山科正平
ページ範囲:P.1448 - P.1448
現在僕たちはインターン制度を拒否して,この1年間を自主的医学研修の第1年目と規定して大学内で医学研修を行なつている。よく「今年のインターンは研修医とよぶそうですね。」といわれるが,これには「今年からインターン生は存在しなくなつたのであり,新しくインターンという言葉を翻訳しなおして研修医となったのではありません。」と答えている。
この症例をどう診断する?・15
出題
ページ範囲:P.1380 - P.1380
症例
女66歳
患者は生来しごく健康で,これといつた病気にかかつたことはなかつた。しかし,健康にはよく注意するたちで,集団検診などは積極的に受けていたが,どこの異常もいわれたことはなかつた。血圧も140前後とのことである。ところが,1月2日の夜半(2時ごろ)急激な前胸部ならびに背部の圧迫感のため眠りからさめた。この胸部の不快感は胸を前後からはさみつけられるような感じであつた。発作後,約20分ぐらいで,自家用車で病院につれてこられたが,胸痛はいまだ持続し,発汗が認められていたが,チアノーゼはなかつた。入院時にオピスタン2ccが注射され,胸痛は発作後60分ぐらいで,徐々に消失している。発作前後を問わず,嘔気,嘔吐はみられなかつた。
討議
著者: 梅田博道 , 土屋雅春 , 高橋淳 , 市川平三郎 , 田崎義昭 , 和田敬
ページ範囲:P.1499 - P.1503
病理の部位が問題となる症例
梅田 和田先生が簡単だとみずから称する症例を。
和田 この症例にはごまかしがひとつもありません。ということは,お読みになつたそのものずばりです。ただしひとつだけひつかかるというのは,私がいままでみたことがない症例であるということです。それは,むずかしいという意味じやなくて,病理の部位とかそういう意味においてね。
ルポルタージュ
天理よろづ相談所憩の家を訪ねて
著者: 張知夫
ページ範囲:P.1496 - P.1498
世のなかにたくさんおられる,生活に疲れ,病に苦しむ人々におやさとに帰つていただき,その人々が心も体も共に憩うことのできる場所として作られたのが,この"憩の家"です。 —案内書より—
統計
医師の死亡
著者: 菅沼達治
ページ範囲:P.1379 - P.1379
わが国の人口動態統計には職業別の死亡統計がありますが,医師だけを抜き出した統計は,ここ10数年間集計されておりません。そこで昭和39年1月から9月までの全国の死亡票約50万枚のうちから医師の死亡票を抽出しますと692枚となつております。このうち女子は22,33歳未満の男子2であり,ここでは30歳以上の男の医師の死亡668について観察することにします。
この668名の死亡をもとにして,1年間の死亡数を推計しますと約920名になります。ここで医師の死亡率を一般国民の死亡率と比較するわけですが,医師の基礎人口は,医師法にもとづいて毎年末現在で医師の方々に届出をお願いしている「医師・歯科医師・薬剤師調査」の結果をもちいることにします。この調査はかなり完全性の高いものでありますが,きわめて高齢の方で,すでに無職となつている医師などに多少の届出もれのあることも考えられます。したがつて,表にかかげた死亡率よりは,医師の場合は多少低率となることが考えられます。30歳以上の総数では医師は一般国民よりも33%の低率であり,これを年齢別に比較しても,どの年齢層でも医師のほうが低いことが認められます。とくに30歳代の若い医師は一般国民よりも4〜5割低率であることがめだちます。それ以後の年齢でも,1〜3割低率となつています。
Bed-side Diagnosis・10
A Case of Acute Epigastric Pain in a Middle Aged Man Simulating Perforated Peptic Ulcer
著者: 和田敬
ページ範囲:P.1472 - P.1473
Dr. A, a surgical intern, picks up the telephone and calls the operator.
Dr. A "This is Dr. A speaking. Would you place* an emergency call for Dr. B? Dr. C and I will be here at Ward H. Thank you."
文献抄録
現代医学における計算機の役割とその限界—E. Goldberger:How Physicians Think, 1965, Appendix 2
著者: 浦田卓
ページ範囲:P.1478 - P.1478
はじめに:JAMAの1966年6月13日号は"現代医学と計算機"の特集をやつている。計算機シンポジウムの論文が,3篇と計算機に関する寄稿論文が7篇という,はなばなしさである。なお同じ号のJAMAの社説欄には"現代医学における計算機の役割"というテーマの論説があつて,一応この特集の"締めくくり"をしている。しかし,この"論説"を読んでみると,計算機についてある程度の予備知識がないと,ぴんとこないところがあるので,今回は,もつとわかりやすい上記の"計算機による診断"というE. Goldbergerの解説のほうを,ごく簡単に紹介したい(蒲田)。
まず,計算機の種類について簡単に紹介する。
日常診療と悪性貧血—Blood 27:599-610, May, 1966;Brit. Med 1:1149-1151, May 7, 1966
著者: 浦田卓
ページ範囲:P.1479 - P.1479
悪性貧血,つまりB12欠乏症は日常診療でそう多いものではない。しかし,そう珍しいものでもないようである。日常診療におけるその頻度は,医師の診療様式によつておおいに左右される。
まずたいせつなのは,悪性貧血の古典的三主徴,すなわち非力,舌痛,四肢のしびれとぴりぴりする感じは,もはや日常診療ではほとんど絶無といつてもよいということである。これは,近年B12または肝臓製剤が保健薬のなかに少量ながら含まれているからであろうと思われる。したがつて,われわれのみるのは,たいてい,悪性貧血のない悪性貧血症,つまり軽症のB12欠乏症がほとんどである。
話題
第7回日本精神身体医学会から
著者: 金子仁郎
ページ範囲:P.1405 - P.1405
第7回日本精神身体医学会総会は去る5月16,17日の2日間,大阪市御堂会館において,金子会長のもとに開催され,心身医学に関心をもち,治療あるいは研究をしている内科,精神科,産婦人科,外科,皮膚科,小児科など各科の医師,研究者が約500名参会し,研究発表ならびに討議を行なつた。
今回の学会では,3つのシンポジウムと77の一般演題が発表されたが,一般演題の申込数が非常に増したために,誌上発表にまわさねばならぬものがいくらかあり,さらに演説時間を5分のものと8分のものを分けねばならなかつた。このように発表数が増すことは喜ばしいことではあるが,十分な発表ならびに討議の時間が得られず,将来は演題数を制限するなど,プログラム委員会によつて検討する必要を痛感させられた。また同時に各地方の分科会をさかんにし,そのほうでも消化してもらうことも必要であると考えられる。
ニュース
中央社会保険医療協議会の動き
著者:
ページ範囲:P.1471 - P.1471
今年にはいつてから非公開で10回の全員懇談会をかさねていた中央社会保険医療協議会(中医協)は,6月末で全員懇談会をうちきり,東畑会長ら公益委員4名は,診療側,支払側との個別懇談会をひんぱんに行なつて,正式総会の開催を急いでおり,8月中には総会が開かれそうだ。
これまでの懇談会で提出された問題は,診療報酬の適正化,薬価基準の合理化,医療経営実態調査の実施,診療報酬13.5%の引上げ,歯科診療の特殊性,処方せんの調剤受付手数料50円の設定などである。これらのうち,診療側は物価・人件費の上昇に伴う診療報酬の13.5%引上げの優先審議を要求しており,一方,支払側は医療経営実態調査と薬価基準の問題の優先審議を主張し,先議争いの様相を示している。
ビジョンを欠く40年度厚生白書
著者:
ページ範囲:P.1477 - P.1477
昭和40年度厚生白書(厚生行政年次報告)が7月末発表された。今回の厚生白書には,期待されていた長期厚生行政のビジョンもあまり見られず,せつかく昭和30年代をふりかえり,40年代を展望するという企画も,画一的なものに終つてしまつている。
白書であるからには「厚生省として実行しようとしたこと,やらなければならなかつたことはこれこれであつたが,実現したのはこれだけで,その理由はこうであつた。将来はこのようにしようと思う」と国民にうつたえ,国民のあつい支援を受けながら,行政を発展させていくべきであろう。朝日新聞の社説も指摘したように,今回の白書はあまりにも自画自賛的なところが多すぎたのではあるまいか。われわれにもつとも関係の深い医療について「医療保障制度など関連制度の発展とあいまつて,国民医療はいちじるしい進展をとげている」といつていることなどが,そのよい例であろう。
今月の表紙
「スペインの薬局」
著者: 本田一二
ページ範囲:P.1480 - P.1480
ロンドンのウェルカム医学史博物館には,中世のアラブ,17世紀のイタリア,イギリスなど昔の薬局が5軒,当時そのままの器具や調度をそろえて,実物大に復元されている。
写真は,スペインのグラナダにあつた薬局を店ごと全部買い占めて,ロンドンに運び再建したもの。タナに並んだ薬品のびんは,いろんな形のものがあるが,すべて人の手で美しく彩色され,薬品名が明示されて,すこぶるカラフルである。床が,白黒ダンダラ模様なのは,アラビア人の影響であろう。
--------------------
きのう・きよう・あした
著者: 山形敞一
ページ範囲:P.1441 - P.1441
7月16日(土)昨目午後4時半,徳島空港に下り立つたときから覚悟していたことであつたが,徳島の暑熱にはさすがにまいつた。ホテルは冷房なのに扇風機が置いてあるので不思議に思つていたが,夜中の1時ごろに冷房がとまると同時に目がさめて,なんともやりきれない。窓をあけると少しは涼しいが,蚊が入つてくる。やむなく,また窓を閉め,扇風機の風力を利用して,ようやくまどろんだというしだいであつた。朝9時半に学術会議第7部会総会の会場である徳島大学医学部図書館に行くと,すぐ昨夜の暑さが話題となり,K会員のごときは夜中に水風呂に入つてみたがどうしても眠れなかつたということだつた。
午前10時から会議が始まる。さすがに冷房があるので議事もはかどる。懸案の医学部卒業後の医師(インターン,レジデント,医局員など)の教育制度と研究制度のありかたについて議論が白熱する。このためには,医学部附属病院のありかたを考えなおして,教育と研究と診療の根本体制を緊急に再検討すべきであるということに意見が一致し,秋の総会までに特別委員会設置の具体案をまとめようということになつた。正午すぎに会議をいつたん休憩して,眉山ホテルの知事招待会に行く。知事は明石と淡路島と鳴戸を結ぶ瀬戸大橋架橋の重要性を説く。世話人の徳島大学教授のK会員もさかんに必要性を強調している。現地にきてみてこれが徳島の最重要問題であつたことに気づく。
アメリカ南部の大学に留学して
著者: 飯田喜俊
ページ範囲:P.1494 - P.1495
差別反対運動の黒人指導者,キング氏の出身地
私は3年前,アメリカ南部,ジョージア州,アトランタ市のEmory大学,内科(腎臓病科)に留学する機会を得た。毎日が楽しい,なつかしいことばかりであつたがその一端をここに述べてみようと思う。
アトランタ市はジョージア州の州庁の所在地,アメリカ南東部では一番大きい,人口約百万の都市である。ジョージア州といつてもちよつとピンと来ない方もあるかも知れないが,有名なフロリダ州と接し,黒人問題で有名になつたアラバマ州の東に位置しており,以前は綿産業の中心であつた。しかし近年では自動車工業なども盛んになり,発展しつつある州である。人々はいわゆる"Southern hospitality"といつて一般に素朴かつ親切であり,私も常にat homeの気持を持つことができた。アトランタ市はこの州のほぼ中央にある。かの映画や文学でも有名になつた「風と共に去りぬ」はこの市を舞台にして展開されているのであり,かつてはここは南北戦争の中心の一つであつた。ちなみにこの『風と共に去りぬ』の著者,M.ミッチエル女史は約15年前に交通事故で死去したのであるが,その際かつぎこまれ,息をひきとつたのは私のいた病院においてであつた。また有名人といえば,最近黒人でノーベル賞をもらつたマルチン・ルーサー・キング氏はこの市の出身で今もここで牧師をしており,黒人差別反対運動でははなばなしく活躍して一やく有名になつた人である。
脳波はどんな時に撮るか—内科医の立場から
著者: 後藤文男 , 篠原幸人
ページ範囲:P.1491 - P.1493
脳波利用のために
人間の脳波がドイツの精神科医Hans Bergerによつて発見され,発表されてからすでに30余年の年月が過ぎた現在,ようやく一般内科医にも脳波検査の有用性が認められてきた感がある。脳波は脳血管写と異なり患者にストレスを与えることもなく,副作用も考えられず,ポータブル脳波計を使用すれば動かせない患者にも施行でき,大脳の機能を知る示標として内科的神経的疾患の補助診断に欠かせないものの一つとなつた。しかしまだ一部の内科医には,脳波の価値と限界についての知識に乏しく,適応でない例でも無差別に脳波検査の依頼を行なつたり,また逆に脳波が威力を発揮するような例に脳波をとらなかつたりする場合がなきにしもあらずである。そこで脳波はどんなときに撮るべきか,どのようにすれば正しく依頼できるかを考えてみることにした。
基本情報
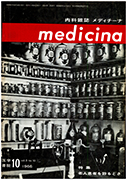
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
