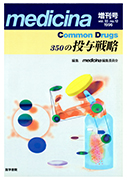文献詳細
iatrosの壺
文献概要
ベーチェット病の高熱にセファランチンが効果を示した経験を記載する.
16歳の男子高校生が,平成1年4月4日に39.1℃の発熱で受診.外来で抗生剤などが投与されたが,4月10日になっても解熱せず入院した.入院時に口蓋垂や口唇に小さなアフタがあったが,当初はベーチェット病と考えなかった.初診時の白血球数6,300ml(桿球44%,分葉球36%,好酸球0%,塩基球0%,単球5%,リンパ球15%).入院時の赤沈1時間値30mm,CRP(3+),抗核抗体(−),RA,ASO,ワ氏,抗クラミジア抗体,血液培養はいずれも(−),IgD5.0mg/dl,IgE1,208U/ml.IgE高値はスギ花粉症によるものと思われた.入院翌日の診察で,右大腿内側の径1cmの潰瘍と鼠径部リンパ節腫脹に気づいた.3日目になって,大腿部潰瘍が接する陰嚢部にもあたかも“とびひ”のように新たな潰瘍が出現した.ベーチェット病の陰部潰瘍の広がり方を知らず,伝染性膿痂疹を疑ってしまった.5日目に奈良医大皮膚科でベーチェット病と診断され,セファランチン投与を勧められた.ベーチェット病での多核白血球機能亢進,特に多核白血球の活性酸素産生能増加に対してセファランチンが抑制的に働くことから,再発性アフタ性潰瘍や眼・皮膚症状に有効であることを後になって知ったが,そのときは効果に対しては半信半疑であった.報告には30〜150mg/dayとあるが,わずか6mg/dayの投与開始の翌日から37℃台に急速に解熱したのには驚いた.6日後に再び38℃台に上昇し,ステロイドに変更したが,ベーチェット病の診断と治療方針を考える時間を得るには十分であった.平成1年10月17日にステロイドを中止し,現在にいたるまで再発はない.
16歳の男子高校生が,平成1年4月4日に39.1℃の発熱で受診.外来で抗生剤などが投与されたが,4月10日になっても解熱せず入院した.入院時に口蓋垂や口唇に小さなアフタがあったが,当初はベーチェット病と考えなかった.初診時の白血球数6,300ml(桿球44%,分葉球36%,好酸球0%,塩基球0%,単球5%,リンパ球15%).入院時の赤沈1時間値30mm,CRP(3+),抗核抗体(−),RA,ASO,ワ氏,抗クラミジア抗体,血液培養はいずれも(−),IgD5.0mg/dl,IgE1,208U/ml.IgE高値はスギ花粉症によるものと思われた.入院翌日の診察で,右大腿内側の径1cmの潰瘍と鼠径部リンパ節腫脹に気づいた.3日目になって,大腿部潰瘍が接する陰嚢部にもあたかも“とびひ”のように新たな潰瘍が出現した.ベーチェット病の陰部潰瘍の広がり方を知らず,伝染性膿痂疹を疑ってしまった.5日目に奈良医大皮膚科でベーチェット病と診断され,セファランチン投与を勧められた.ベーチェット病での多核白血球機能亢進,特に多核白血球の活性酸素産生能増加に対してセファランチンが抑制的に働くことから,再発性アフタ性潰瘍や眼・皮膚症状に有効であることを後になって知ったが,そのときは効果に対しては半信半疑であった.報告には30〜150mg/dayとあるが,わずか6mg/dayの投与開始の翌日から37℃台に急速に解熱したのには驚いた.6日後に再び38℃台に上昇し,ステロイドに変更したが,ベーチェット病の診断と治療方針を考える時間を得るには十分であった.平成1年10月17日にステロイドを中止し,現在にいたるまで再発はない.
掲載誌情報