ポイント
●心不全の臨床診断は症候と心ポンプ機能の障害の判定からなる.
●心不全の罹病者は米国では200〜300万人,わが国では50〜100万人と推定される.
●心不全発症率は米国では3〜10/1,000程度で,加齢に比例して増加する.
●原因疾患は米国では虚血性心疾患の頻度が高い.わが国では虚血性心疾患1/3,弁膜疾患1/3,その他1/3程度の比率であるが,米国型の原因疾患分布となる傾向は否めない.
●心不全の生命予後にはばらつきがあるものの,おおむね5年生存率50%程度である.直接死因として心不全自体に加え突然死が重要である.
●心不全の死亡率は,わが国では平成6年度で128.5の数値が得られている.
●心不全の死亡率は,実態が変わらなくとも統計のもととなる死亡診断書の記載法により著しく変化することが明らかである.
雑誌目次
medicina33巻5号
1996年05月発行
雑誌目次
今月の主題 心不全を見直す
理解のための40題
ページ範囲:P.983 - P.990
Introduction
臨床統計値からみた日本人の心不全—有病率,死亡率,原因疾患と頻度など
著者: 半田俊之介 , 椎名豊
ページ範囲:P.828 - P.832
最近の心不全の大規模試験から読み取るべきこと
著者: 村上知行 , 篠山重威
ページ範囲:P.834 - P.837
ポイント
●慢性心不全治療の究極的な目的は,患者の生活の質の改善と生命予後の延長である.
●交感神経,レニン-アンジオテンシン系賦活による過度なリモデリングの進展が生命予後の悪化に関連している.
●神経体液因子の作用を阻害するβ受容体遮断薬,アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬,新しいCa拮抗薬が慢性心不全治療薬として有効である.
●いわゆる強心薬は死亡率を増す危険が大きいが,種類,投与量の選択により有効なものがある.
心不全の症状予後および生命予後
著者: 渡邊正司 , 岡本洋 , 北畠顕
ページ範囲:P.838 - P.842
ポイント
●心不全の長期予後は悪性腫瘍と同様に悪い.
●冠動脈疾患による心不全の予後は拡張型心筋症に比べて悪い.
●心不全の予後規定因子として基礎疾患(冠動脈疾患か否か),左室機能(駆出率,左室拡張末期容積),運動耐容能,神経体液性因子(血漿ノルエピネフリン値,レニン活性,アンジオテンシンII値,心房性利尿ペプチド値),心室性不整脈などがある.
●アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬はあらゆる段階の心不全に対して生命予後改善効果が示され,β遮断薬,亜硝酸薬+ヒドララジン,アムロジピン,ベスナリノンについては条件つきではあるが,一部で生命予後の延長効果が示されている.
心不全とは何か
心不全とは何か
著者: 菅弘之
ページ範囲:P.844 - P.846
ポイント
●心不全は不全心と同一ではない.
●心不全は心臓が身体の代謝に必要とするに十分な心拍出量を供給することができない病態生理的状態である.
●心不全の原因は様々である.
●心筋収縮不全,心室収縮不全は心不全の原因たりうるが,必須条件ではない.
●心筋,心室収縮不全および不全心は,力学的に評価が可能であり,心拍出量低下と関連づけられる.
臨床症候から
著者: 山本啓二 , 島田和幸
ページ範囲:P.847 - P.849
ポイント
●心不全は呼吸困難,起坐呼吸,発作性夜間呼吸困難,易疲労感,心悸亢進,体重増加,乏尿,浮腫などを主徴とする一連の臨床症候群である.
●急性左心不全は左心室のポンプ機能低下による肺うっ血を特徴とする.
●起坐呼吸は心不全の末期的症状である.
●発作性夜間呼吸困難の出現は通常就寝2〜5時間後に生じる.
●右心不全で最も多い原因は左心不全をきたす疾患によるものである.
●心不全ではレニン-アンジオテンシン系が活性化され,腎でのナトリウムや水の貯留をきたす.
●右心不全の急性増悪時には胆石症,急性肝炎や他の急性腹症と誤られることがある.うっ血性心不全
循環動態および心収縮性から
著者: 木全心一
ページ範囲:P.851 - P.853
ポイント
●急性心不全の患者の病態は,肺毛細管圧と心係数(心拍出量を体表面積で割った値)で判定する.肺毛細管圧が低く,心係数が高ければ急性ポンプ失調がないと判定する.心係数が正常で,肺毛細管圧が高ければ左心不全,肺毛細管圧が高いのに心係数が低ければ心原性ショックと判定する.
●慢性心不全の病態は,左室収縮性を表す左室駆出率と運動耐容能で判定する.慢性心不全の運動耐容能は,運動量を上げたときに心係数を増せる能力と,末梢血管抵抗を下げて骨格筋に血流を増加できる能力とで規定されている.このため左室駆出率と運動耐容能とは相関せず,両者が下がっているときに慢性心不全と判定する.
循環の制御から
著者: 木之下正彦
ページ範囲:P.854 - P.856
ポイント
●心不全は心機能障害の結果生じる各種の神経体液因子が亢進する症候群である.
●心不全の悪化に関連する神経体液因子はノルエピネフリン,レニン-アンジオテンシン,エンドセリン,バゾプレッシン,TNF-αなどのサイトカインである.
●心不全の代償作用として働く神経体液因子はANP,BNP,アドレノメデュリン,ドパミン,プロスタグランディンなどである.
●心不全ではANP受容体のダウンレギュレーションが存在する.
●心不全の治療には有害な神経体液因子を阻害する薬が生命予後を改善する.
心不全の診断と重症度評価
心不全の診断と評価の進め方
著者: 弘田雄三
ページ範囲:P.858 - P.861
ポイント
●急性肺水腫,ショックの患者では,心筋梗塞,解離性大動脈瘤,肺塞栓症,急性弁不全,急性心膜・心筋炎を念頭に置き,検査と治療を同時に始める.
●慢性心不全患者の増悪時には心不全の治療とともに“増悪因子”を検索・治療する.
●慢性心不全患者の病歴では,息切れ,風邪に注意する.
●浮腫を認める患者では静脈圧を目測し,右心不全か否かを確認する.
●左心不全の診断には,胸部X線写真が重要である.
●基礎疾患の診断,病態(収縮期vs拡張期障害),障害の程度の判定には心エコーが有用である.
●重症度の判定は症状の解析によって行い,補助手段として運動負荷を実施する.
●高齢者,治療不可能な他臓器疾患(悪性腫瘍,痴呆,重症肺疾患など)を併発する患者を除き,すべての患者において基礎疾患の確定診断を行い,根治療法の有無を検索する.
臨床症状と病態評価
著者: 中村芳郎 , 継健 , 岩永亮子
ページ範囲:P.862 - P.864
ポイント
下記のポイントは本稿ならびに心不全に関する論文を読む際に,あらかじめ認識しておいていただきたい事柄である.
●心不全の定義は必ずしも明確でないまま使用されている.まず論者の立場を理解することが重要である.
●心筋以外の心臓の異常で起こった心機能異常の治療は,外科的に可能な場合が多い.
●心筋不全の多くは収縮機能障害である.
●米国の心不全の多くは虚血性心疾患に原因する.日本の現状とははなはだ異なっていることに注意が必要である.
新しい心不全ガイドラインとモニタリング
著者: 堀進悟 , 副島京子
ページ範囲:P.866 - P.868
ポイント
●心不全ガイドラインによるモニタリングの適応をまとめる.
●急性肺水腫では心電図モニターとパルスオキシメーターは必須である.
●Swan-Ganzカテーテルは治療に不応の場合,および低血圧の場合に適応となる.
●心原性ショックでは観血的血圧測定とSwan-Ganzカテーテルが必要である.
●慢性心不全では心室性不整脈が多いが,無症候性の不整脈では薬物治療の有用性が証明されていない.
●慢性心不全にルーチンにホルター心電図を施行することは適応と認められていない.
非侵襲的評価法と指標—有用性と問題点
著者: 古谷雄司 , 松﨑益徳
ページ範囲:P.869 - P.871
ポイント
●心不全が疑われる患者には,心エコー法や核医学的心室造影による左室駆出分画を測定する.
●心エコー法や核医学的心室造影により収縮機能不全と拡張機能不全を鑑別することができる.
●収縮期指標(左室駆出率)が予後の重要な規定因子である.
●僧帽弁血流シグナルから得られる拡張期指標(DT:deceleration time)はうっ血症状と関係し,収縮期指標と組み合わせることにより,詳細な予後判定が可能である.
●心臓交感神経を画像化するMIBG心筋シンチグラフィーにより,心不全の予後判定が可能である.
運動耐容能による評価
著者: 宮城匡子 , 麻野井英次
ページ範囲:P.872 - P.874
ポイント
●慢性心不全は,心機能障害に起因する症状により身体活動が制限される症候群である.
●自覚症状に基づく重症度評価法には,NYHA(New York Heart Association)旧心機能分類やSAS(specific activity scale)がある.
●SASはNYHA旧心機能分類に比し定量性に優れ,検者間の誤差も少ない.
●多段階漸増運動負荷試験により,peak VO2,AT(anaerobic threshold)などの運動耐容能指標を測定できる.
●ATは自覚症状に影響されない客観的な指標だが,重症例ほど検出率が低い.
●慢性心不全患者の身体活動能は,自覚症状と運動耐容能の両面から検討することが重要である.
心臓カテーテル法による評価—循環動態,左室造影法,収縮性の指標
著者: 石川欽司 , 稲垣雅彦
ページ範囲:P.876 - P.878
ポイント
●心不全の病態を理解するうえで,心機能の諸指標を算出しておくことは重要である.
●心エコー法など非観血的な病態観察がなされているが,心臓カテーテル法による左室圧・容積計測が左室機能評価の標準である.
●左室機能の諸指標は収縮性を表す指標と拡張能を表す指標に分類される.
●max dp/dt(左室等容収縮期圧立ち上がり一次微分値の最大値)とEF(左室駆出率,ejection fraction)が臨床上,最も有用な指標である.
神経体液性因子の臨床評価
著者: 堀正二 , 尾崎仁
ページ範囲:P.879 - P.881
ポイント
●慢性心不全患者では,代償性に交感神経系,レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAS),アルギニン・バソプレシン(AVP),エンドセリン(ET),Na利尿ペプチドなどの神経体液性因子が亢進している.
●血中ノルエピネフリン(NE),血漿レニン活性,心房性Na利尿ペプチド(ANP),脳性Na利尿ペプチド(BNP)は,慢性心不全の重症度を反映し,予後予測因子として重要である.
心不全の原因とその対応
Introduction—心不全の原因
著者: 半田俊之介 , 多田博己
ページ範囲:P.883 - P.885
ポイント
●心不全は心ポンプ機能障害による症候群である.心ポンプ機能を規定する因子として,心拍数,前負荷,後負荷および心収縮性がある.心不全の発症はこれらの中のいずれかの異常が契機となる.治療は主たる発症因子の異常の除去ないし管理を中心に考える.
●病態に相応するように心拍数,前負荷,後負荷の調節を行う.他の因子の異常の結果としての心収縮性の二次性低下は,これら負荷因子の管理・治療によりある程度まで回復することが多い.しかし,不可逆性の一次性低下の場合,例えば拡張型心筋症,広範な心筋梗塞症では回復が難しい.負荷の軽減を適切に行う.
心不全の誘発要因とその対策
著者: 茅野真男 , 横塚仁
ページ範囲:P.886 - P.889
ポイント
●心不全の誘発要因には,各医師が診ている患者層によって異なるが,不整脈,感染,急激な血圧の上昇,急性心筋梗塞,貧血,甲状腺機能亢進症,肺塞栓症,妊娠,心筋炎,弁破壊,心筋虚血が挙げられる.
●実際に多い要因としては,薬剤の中断,食塩の過剰摂取,肉体的精神的ストレスなど,患者自身の問題が多い.誘因の正確な決定には患者背景の把握が必要である.
●拡張不全が主体で心不全が発症する場合は,発症が急激なため,誘発要因が同定できないことも多い.
前負荷の管理・調節
著者: 赤石誠
ページ範囲:P.891 - P.894
ポイント
●左室にとっての前負荷とは,拡張末期容積である.静脈還流量が増大すれば前負荷が増大し,心拍出量が増加する.末梢血管抵抗が低下するような状態では,心拍出量が増加し,静脈還流,すなわち前負荷が増加する.循環血液量,体位,胸腔内圧,静脈のトーヌスも前負荷を規定する因子である.逆流性弁膜症,貧血も左室前負荷の増大をもたらす.
●心不全における前負荷の軽減は,肺うっ血の改善が主たる目的であるが,心拍出量の増大をもたらす可能性もある.前負荷を減少させるには利尿薬が第一選択である.しかし,新しい薬剤,治療法も存在する.
後負荷の管理・調節
著者: 阿部純久
ページ範囲:P.895 - P.897
ポイント
●心不全は心筋不全と同意語ではなく,心筋不全は心不全の原因の一つである.
●心不全の評価,治療に際しては,心不全の発症に関係する機械的な因子の有無,心筋不全の有無の評価が重要である.
●大動脈弁狭窄症,高血圧症など後負荷増加に伴い発症した心不全では,心筋障害が非可逆的にまで進行していることは少なく,後負荷の解除により心機能は正常化する.
●心不全に対する血管拡張療法では,生活の質および長期予後の改善を視野に入れた治療を行うことが重要である.
心収縮能の管理と治療
著者: 増田卓 , 和泉徹
ページ範囲:P.899 - P.904
ポイント
●心不全の一要因として心筋の収縮能低下が挙げられる.この心収縮能低下は同時に拡張期障害を伴いやすいことに留意すべきである.
●前負荷や後負荷の影響を受けにくい心収縮能の臨床指標として,maximal elastance(Emax)が用いられている.
●圧・容積関係を二次元的に展開すると心不全病態が簡略化され,より理解しやすくなる.
●心収縮能低下に対する管理は,基礎疾患の根治療法を図ることを基本とする.根治性が失われたと判断される場合には心症状の軽快を優先させる.
●今日,慢性心不全の治療においては,心収縮能の改善を最優先課題には掲げてはいない.むしろ,心不全の悪化防止効果が心収縮能の改善に結びつくか否かが問われている.
心拍数の管理と治療
著者: 田辺晃久
ページ範囲:P.905 - P.909
ポイント
●高頻拍性心拍異常,徐拍性心拍異常のいずれもが心不全の原因,増悪因子となる.
●高頻拍性心拍異常による心不全の原因不整脈としては,慢性持続性心房細動が多い.
●基礎疾患のある例の心房細動は,感染・発熱,過度の心負荷,過剰食塩・水分摂取,薬物内服の不良なコンプライアンスで容易に高頻拍化する.特に高齢者で影響が大きい.日常生活はこれらの誘因を避けるよう指導する.
●徐拍性不整脈で心拡大,心不全を生じた例は心ペーシングで改善しやすい.
拡張障害の管理
著者: 芹澤剛
ページ範囲:P.911 - P.913
ポイント
●拡張障害による心不全とは,左室収縮機能がほぼ正常で,なおかつ心不全症状を呈するものである.
●機械的な病態として心膜疾患,拘束性疾患がある.
●機能的な病態として高血圧性心肥大,虚血心があり,虚血による細胞内Ca++handlingの異常が原因と考えられている.
●心拍数を減少させることが治療の基本である.
高齢者における管理と治療
著者: 今井保 , 坂井誠 , 大川眞一郎
ページ範囲:P.914 - P.917
ポイント
●高齢者では心臓をはじめとする全身諸臓器の機能が低下しているため心不全を生じやすく,多臓器不全に陥りやすい.そのため若年者とは異なる特有な病態を呈する.
●主な基礎疾患として虚血性心疾患,弁膜症,高血圧性心疾患があげられる.また,先天性心疾患もさほど稀ではなく,さらに心臓以外の因子も重要である.
●誘因では感染症,心筋虚血発作,不整脈が多いが,医原性(過剰輸液,輸血,薬剤性)や治療不従順も少なくない.
●心不全の管理と治療では,まず心不全の重症度を正確に評価し,基礎疾患,誘因,合併症も考慮した治療法の選択が必要である.
●薬物療法に際しては,少量より投与を開始し,副作用の出現に注意しながら漸増して至適量を決めなくてはならない.
●薬物療法が無効の重症心不全例に対して,侵襲的治療法を行うか否かは,その治療法の可能性と限界を正しく把握し,さらに患者の社会的活動性,他臓器機能などを総合的に考慮して判断する必要がある.
成人のチアノーゼを伴う先天性心疾患
著者: 中澤誠 , 佐近琢磨 , 川越康博
ページ範囲:P.918 - P.921
ポイント
チアノーゼ性心疾患の成人例では,以下の点に留意しなければならない.
●心不全は自然歴の現れである.
●低酸素血症が基本病態で,解剖学的改善のみが根本的治療である.このため,手術やカテーテル治療の可能性を常に念頭に置いておく.
●合併症の防止に留意する.
●生活の制限は最小限にとどめ,本人のもっている循環機能で最大のQOLを引き出す.
●薬物療法は対症的で,強心剤は効果が期待できない.
心不全の管理・治療
心不全の管理・治療の基本方針
著者: 小川研一 , 飯塚昌彦
ページ範囲:P.923 - P.926
ポイント
●心不全の治療の目的は,①生命予後の改善と②生活の質(QOL:quality of life)の改善である.
●急性心不全治療はまず救命が必要で,そのためにモニター下に血行動態障害の改善を図る.
●慢性心不全の薬物治療は,アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬,利尿薬,ついでジギタリスが基本薬である.
無症状の心機能低下例の管理
著者: 安村良男 , 永田正毅
ページ範囲:P.927 - P.929
ポイント
●中等症から重症の心不全の治療には限界があり,軽症心不全の進行予防が重視されてきている.
●潜在性の心不全の早期発見に心臓超音波検査が有用である.
●特発性心筋症と免疫学的機序との関連や,心不全の進行と神経体液性因子やリモデリングとの関連が示唆されている.
●心不全の成因によらず,その進展予防にアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤が奨められる.
●軽症心不全の管理は短期的指針(左室径,血中ノルアドレナリン,不整脈など)をモニターしつつ長期的展望のもとになされる.
一般療法のポイント
著者: 秋月哲史 , 入交重雄 , 細江伸央
ページ範囲:P.930 - P.932
ポイント
●心不全の食餌療法の中心は塩分制限である.
●ベッド上臥位での安静よりも半臥位のほうが静脈還流が少なくなり前負荷が減少する.
●重症でなければ各々の運動耐容能に応じた運動・仕事を行う.
●十分量の酸素投与にもかかわらず,血中酸素濃度が低値の場合には,挿管・レスピレーターを考慮する.
薬物療法の実際—急性期ならびに急性増悪期
著者: 小川久雄
ページ範囲:P.934 - P.936
ポイント
●急性心不全の治療としては利尿薬の静注を行う.
●ニトログリセリンやisosorbide dinitrate(ISDN)の血管拡張薬も有効である.
●アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬も有効である.
●利尿薬や血管拡張薬,さらにジギタリスなどの治療によっても心不全が改善しない場合や心原性ショックの場合には,カテコラミンを点滴静注する.
●アシドーシスがあれば重炭酸ナトリウムによる補正,さらには原因疾患の治療も重要となってくる.
薬物療法の実際—慢性期
著者: 秋田穂束 , 横山光宏
ページ範囲:P.937 - P.939
ポイント
●心不全の治療目的は,血行動態,症状および運動能力の改善のみでは不十分で,さらにQOLと生命予後の改善を目指さなければならない.
●心不全の薬物治療は心不全の病態,薬物の薬理作用と体内動態を十分理解して行わなければならない.
●アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬は心不全の薬物治療の中心となるもので,生命予後の改善が期待できる.
●β遮断薬はまだ確立された心不全の薬物治療ではないが,ACE阻害薬などの無効例には注意深く試みる.
Intervention
著者: 宇井克人 , 山口徹
ページ範囲:P.940 - P.942
ポイント
●虚血性心疾患による心不全では,急性心筋梗塞に限らず経皮的冠動脈形成術(PTCA)により循環動態の改善をみることがある.
●大動脈内バルーンパンピング(IABP)は平均血圧増加・左室後負荷軽減による心拍出量増加作用および冠血流増加作用がある.
●体外限外濾過法(ECUM)は強制的に血管内水分を除去できるため,利尿の得られない心不全患者では有用な装置である.
●経皮的心肺支持装置(PCPS)は心肺機能をほぼ代用できる強力な循環補助装置であるが,基礎疾患を考慮し,その適応には十分な配慮が必要である.
外科治療
著者: 西田博 , 北村昌也 , 遠藤真弘 , 小柳仁
ページ範囲:P.944 - P.947
ポイント
●僧帽弁閉鎖不全や大動脈弁閉鎖不全では左室収縮末期容積係数(LVESVI)が100ml/m2に達する以前に手術を施行するべきである.
●左室拡張末期容積係数(LVEDVI)が150ml/m2,左室拡張末期径(LVDd)が6.8cmを越えるような症例では冠動脈バイパス術(CABG)後の心機能改善効果は乏しい.
●低左心機能の虚血性心疾患に対する待期的CABGの手術成績は良好で,左冠動脈主幹部病変や多枝病変では経皮的冠動脈形成術(PTCA)ではなくCABGを選択すべきである.
●拡張型心筋症に対する補助心臓の使用は心臓移植へのブリッジとしてのみではなく,離脱,回復をめざした治療法としての展開が注目されつつある.
心不全の治療に伴う不整脈の管理
著者: 馬場彰泰 , 三田村秀雄
ページ範囲:P.948 - P.949
ポイント
●心不全の治療により,不整脈の発生は様々に変化し得る.
●心不全例では突然死が多いが,有効な抗不整脈薬は少ない.
●致死的不整脈の出現例では,抗不整脈療法の適応となる.
●心不全例における抗不整脈療法では,アミオダロンとICDが代表的である.
リハビリテーションと運動療法
著者: 齋藤宗靖
ページ範囲:P.950 - P.952
ポイント
●心不全患者の運動制限は,肺血管床圧の上昇による息切れよりは,骨格筋の組織・生化学的変化に基づく嫌気性代謝の早期出現による下肢疲労がその原因と考えられている.
●運動トレーニングによる骨格筋の鍛錬が,運動能力の増加,ひいてはQOLの向上をもたらす可能性がある.
●最近10年来,慢性心不全患者に対する運動療法が試みられ,良好な成績が報告されている.
●従来から運動が禁忌とされた心不全患者に運動療法を施行するにあたっては,安全性に留意しながら常に研究的に行うことが必要である.
心不全改善後の生活指導
著者: 濱本紘
ページ範囲:P.953 - P.955
ポイント
●心筋梗塞発症後の再灌流療法は,急性期のみならず慢性期においても根気よく行うと,心機能改善に役立つ.
●心疾患患者の運動療法禁忌としてあげられるものに,うっ血性心不全,不安定狭心症,重篤な不整脈,広範囲梗塞などがある.
●心筋梗塞回復期における重篤な不整脈に対する抗不整脈剤の投与は,陰性変力作用などから考慮する必要があり,Ib群が安全であるが,有効性を考えるとIII群が勝っている.しかし,重篤な肺毒性を有する.
●remodelingは心筋梗塞の治癒機転として起こるが,その際のexpansionが心機能低下に大きく関与することになる.
●心筋梗塞後の心不全に対する投薬は,強心剤,利尿剤,血管拡張剤のほかに,アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤の投与が積極的に行われるようになっている.
合併症を伴う心不全の管理と治療
不整脈
著者: 飯沼宏之
ページ範囲:P.957 - P.961
ポイント
●心疾患に頻脈性不整脈が合併した際,それが引き金になって心不全症状が生じることがある.
●症状が激烈で緊急治療が必要なときは,電撃ショックないし抗不整脈薬の静注により持続性不整脈の停止を図る.
●発作停止不能のときはカテーテルアブレーション(CA)など非薬物治療を考慮する.
●緊急治療の必要度に多少のゆとりがあるときは,レートコントロール・心不全治療をまず行い,心臓に対する負荷を軽減してから不整脈停止処置をとることもある.
●不整脈停止後も再発を防ぐ目的で抗不整脈薬の投与が必要であるが,心房細動(af)以外の上室性不整脈に対してはCAが第一選択になりつつある.
●徐脈性不整脈で心不全症状を伴う場合は,最適のペーシングモードを用いた人工ペースメーカー植込みを行う.
呼吸不全
著者: 一ノ瀬正和 , 池田淳 , 白土邦男
ページ範囲:P.962 - P.964
ポイント
●呼吸不全とは室内気吸入時PaO260torr以下となる呼吸障害,またはこれに相当する呼吸障害を呈する異常状態をいう.
●慢性肺疾患による肺血管床の器質的減少および低酸素性肺血管攣縮は,肺性心(右心不全)をきたす.
●慢性気管支炎は肺気腫より肺性心をきたしやすい.
●肺性心の治療には,酸素および利尿剤の投与が有効だが,気道感染の治療や気管支拡張剤投与も重要である.
腎機能障害
著者: 青木聡 , 島井新一郎 , 高野照夫
ページ範囲:P.965 - P.967
ポイント
●腎機能障害を有する心不全の治療は腎機能障害の原因,腎機能障害の程度によりその治療法は大きく異なる.
●透析導入前の心不全患者は腎機能保持,すなわち腎血流量の保持を考えながら治療しなければならない.
●腎機能低下患者は薬物の腎からのクリアランスも低下しており,その血中濃度に注意しながら投与しなければならない.
肝機能低下
著者: 前原和平 , 丸山幸夫
ページ範囲:P.969 - P.971
ポイント
●肝硬変症では高心拍出量状態にあることが多く,総末梢血管抵抗は低下している.
●肝硬変症自体でも息切れと低酸素血症を生じ得る
●非代償性肝硬変症では腎でのナトリウム排泄能が低下している.
●非代償性肝硬変性の腹水,浮腫の治療の第1は塩分制限であり,急速な利尿は腎不全,肝性脳症を生じ得る.
妊娠
著者: 石光敏行 , 杉下靖郎
ページ範囲:P.972 - P.974
ポイント
●心不全は治療よりも予防と管理が大切である.
●妊娠に伴う生理機能変化を理解する.
●心不全の病態生理は基礎心疾患により異なり,左心不全が主体のものと右心不全を呈するものがある.
●妊娠時の診断と心機能評価は胎児にも安全な心電図と心エコー図が中心となる.
●母体だけでなく胎児への副作用も考慮して治療薬を選択する.
●問題例では分娩の前後に特別な注意が必要である.
甲状腺機能障害
著者: 中澤博江
ページ範囲:P.975 - P.977
ポイント
●心房細動を伴う心不全患者で明らかな器質性変化がない例では,甲状腺機能亢進症を疑って血中free T3(FT3),free T4(FT4),TSH(甲状腺刺激ホルモン)を測定する.
●甲状腺機能亢進症による心不全は右心不全が前景に出る.また利尿剤が著効する.
●心不全の治療とともに抗甲状腺剤を開始する.●他の心疾患による心不全に比較し,心拍数が多く,特に心房細動がある例では心室レートが200/分に及ぶ.
●甲状腺機能低下症での呼吸困難の訴えや心陰影の拡大例では,心不全との鑑別をする必要がある.
外科治療を必要とする諸疾患
著者: 木村満
ページ範囲:P.978 - P.980
ポイント
●高齢化社会を迎え,心不全患者の外科手術も増えている.
●麻酔を含め,術中の血行動態変動を減らす努力が必要である.
●New York Heart Association(NYHA)分類III度以上の心不全例では,リスク評価にかかわらず積極的な血行動態管理が必要である.
●冠疾患例で手術のリスクが高い場合は,積極的な観血的検査,さらには冠血行再建術も考慮する.
●NYHA分類II度以下の,心機能が比較的よい場合はcost-effectiveness careを考慮し,過剰な処置は控える.
カラーグラフ 塗抹標本をよく見よう・5
赤血球の異常・5
著者: 久保西一郎 , 藤田智代 , 浜田恭子 , 高橋功 , 三好勇夫
ページ範囲:P.995 - P.998
寒冷凝集素症(cold agglutinin disease)
自己免疫性溶血性貧血のほとんどは温式抗体によって生じるが,一部冷式抗体によって生じるものもある.冷式抗体には発作性寒冷ヘモグロビン尿症(paroxysmal cold hemoglobinuria)にみられるIgG型の寒冷血素と,寒冷凝集素症にみられるIgM型の寒冷凝集素とがある.図1〜3は寒冷凝集素症患者の末梢血塗抹標本である.
図1は血液を4℃に冷やして作製した塗抹標本である.抗凝固剤を加えているにもかかわらず,激しい赤血球凝集が認められる.冷式自己抗体の作用温度域は様々で,患者によって異なる.その温度域が広い場合,体温より少し低い温度でも赤血球と結合して溶血を起こす.
グラフ 高速CTによるイメージング・4
心臓領域のHelical CT
著者: 松本滋 , 原田潤太 , 多田信平
ページ範囲:P.999 - P.1005
CT診断における高速螺線型CT(複数の呼称が使われているが,本稿では以下Helical CTを使用する)の出現は,肺,肝疾患領域を中心に診断能を向上させたが,心疾患についてはどうであろうか?
本稿では,Helical CTの特徴を示し,従来型CTとの比較をまじえてHelical CTの合理的な利用法について解説する.また,超高速CTといわれる電子ビーム型CT(Electron Beam Tomography:以下EBTと略す)は1989年以来,延べ17台の導入を数えるが,Helical CTに比較すれば圧倒的に少数でもあり,汎用機としては一般的ではないと考え,紹介するのみにとどめることとする.
演習 胸部CTの読み方・11
急性呼吸不全にて救急入院した44歳の女性
著者: 由田康弘 , 山木戸道郎 , 粟井和夫
ページ範囲:P.1013 - P.1016
Case
平成6年12月上旬より咳嗽が出現し,12月下旬には呼吸困難が出現して,徐々に増悪したため,平成7年1月7日,当院に救急入院となった.体温37.8℃,呼吸数40回/分,顔面および四肢にチアノーゼを認めた.胸部X線写真にて,両側肺門を主体とした肺胞性浸潤影を認めたため,胸部CTを施行した.動脈血ガス分析は,PaO2 34.8Torr,PaCO2 31.0Torr,pH 7.464と高度の低酸素血症を認めた.WBC 12,000/m3,CRP 2.3.
図1a,bは,肺野条件の胸部CTである.
図解・病態のメカニズム—分子レベルからみた神経疾患・9
チャネル病—周期性四肢麻痺
著者: 田中恵子
ページ範囲:P.1017 - P.1021
遺伝的に筋細胞の興奮性異常をきたす疾患群は,筋膜のイオンチャネルの異常によることが明らかとなり,それぞれの疾患でチャネル遺伝子の変異が次々と報告されている.その結果,従来血清カリウム値の高低で区別されてきた高あるいは正カリウム性周期性四肢麻痺(periodic paraly-sis;PP)と低カリウム性PPは,それぞれナトリウムチャネル(Na+チャネル)1),カルシウムチャネル(Ca2+チャネル)2,3)の異常によることが明らかになり,周期性四肢麻痺という同じ症候を呈しても全く異なる病態であることが分子レベルで明らかとなった.また,ミオトニア症候群と高カリウム性周期性四肢麻痺は同じカテゴリーに属することが明らかになるなど,ミオトニアを呈する疾患群が分子遺伝学的知見に基づいて再編分類されることになった.
知っておきたい産科婦人科の疾患と知識・9
下腹痛と性感染症
著者: 宮村研二 , 廣田佳子 , 宮川勇生
ページ範囲:P.1023 - P.1026
女性が腹痛を訴えて来院した場合,常に産婦人科疾患を念頭に置く必要がある.特に,若年女性が下腹痛を主訴として受診したときには,STD(sexually transmitted diseases:性感染症)の存在を疑わなければならない.
本稿ではSTDの中でも,最近頻度が高くなってきているクラミジア感染症の症例を提示し,その診断および対応のポイントを述べる.
連載
目でみるトレーニング
ページ範囲:P.1007 - P.1012
医道そぞろ歩き—医学史の視点から・13
神聖な最高の職務とは
著者: 二宮陸雄
ページ範囲:P.1028 - P.1029
16世紀にパドヴァ大学でモンタヌスが始めたというベッドサイド教育は,意外に思われるかもしれないが,今から100年ほど前まで,アメリカでは行われなかった.医学教育はもっぱら講義だけで行われていた.アメリカで初めて本格的な臨床教育を始め,ベッドサイド教育の重要性を啓蒙したのは,フィラデルフィアのジェファスン医学校のダ・コスタである.ご承知のように,フィラデルフィアは1765年11月14日にアメリカで最初のペンシルベニア医学校が創立された町である.ダ・コスタは1864年に出版した『内科診断学』で有名な人で,この本はドイツ,イタリア,ロシヤなど各国で翻訳された.当時,アメリカでは医者の質が問われ,医学教育が盛んに論議されていた.ダ・コスタは1893年にハーヴァード大学で講演し,「法律や神学と違って,医学教育が鋭い関心と深い感情で論議されるのは,医学そのものに未だ不確定な要素が多く,また日に日に変貌しているからであろう」と述べている.
この頃,ウィリアム・オスラーは35歳でペンシルベニア大学医学部の教授になっていた.オスラーは1849年に,カナダのオンタリオ州の辺境の地ボンド・ヘッドで宣教師の9人の子の一人として生まれた.1872年にモントリオールのマギル医学校を卒業し,欧州での留学の後に,25歳で母校の教授になった.学生たちは彼をベイビー教授と呼んだ.
基本情報
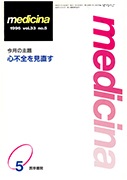
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
