ポイント
●欧米の罹患率は,人口10万当たり潰瘍性大腸炎2.1〜15.1,クローン病0.3〜8.3で,本邦の潰瘍性大腸炎1.95,クローン病0.51を大きく上回っている.
●欧米の有病率は人口10万当たり潰瘍性大腸炎43.4〜225.2,クローン病19.8〜146で,本邦の潰瘍性大腸炎18.12,クローン病5.85を大きく上回っている.
●潰瘍性大腸炎はいかなる年齢からも発症するが,20代にピークがみられる.クローン病の分布の幅は潰瘍性大腸炎より狭く,ピークはUCよりやや若い.
●潰瘍性大腸炎の死亡率は,欧米よりやや低く,クローン病は明らかに低い.
雑誌目次
medicina33巻8号
1996年08月発行
雑誌目次
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
理解のための33題
ページ範囲:P.1581 - P.1587
治療の前に知っておきたいIBDの基礎知識
日本人のIBDの疫学的特徴
著者: 棟方昭博 , 中路重之
ページ範囲:P.1442 - P.1444
IBDの病因と発症のメカニズム
著者: 馬場忠雄 , 安藤朗
ページ範囲:P.1445 - P.1449
ポイント
●潰瘍性大腸炎およびクローン病に代表される炎症性腸疾患の病因は,いまだ特定されていない.
●潰瘍性大腸炎患者の血中には,種々の自己抗体の存在が証明され,その病因に自己免疫的異常が関与している.
●クローン病は,組織学的に非乾酪性肉芽腫の形成を特徴とし,その病因の一つに単球/マクロファージの機能異常が関与している.
●腸管粘膜局所における透過性の亢進と免疫調節機構の破綻が,両疾患の病態に関与している.
IBDの経過と予後
著者: 神長憲宏 , 佐竹儀治
ページ範囲:P.1451 - P.1453
ポイント
●潰瘍性大腸炎では大部分の症例が薬物療法に反応し,長期的な予後は良好である.
●潰瘍性大腸炎における慢性持続型,頻回に再燃する再燃緩解型は手術となることが多い.
●潰瘍性大腸炎の直腸炎型,左側結腸炎型では口側へ進展する例がある.
●潰瘍性大腸炎の若年発症,全大腸炎型,慢性持続型で10年以上の経過を有する例で癌化率が高い.
●クローン病では,完全静脈栄養療法や成分栄養療法を行えば,ほとんどの症例が4週以内に緩解となるが,栄養療法を中止すると大部分の症例が2年以内で再燃をきたす.
●クローン病の炎症の活動度は,発症からの経過期間が長くなるに従って低下する.
●クローン病の累積手術率は経年的に増加を示し,発症後15年で約50%である.
●クローン病の術後の再燃もほぼ全例で認め,再手術率も40〜50%と高い.
IBD治療の目的とゴール
著者: 上野文昭
ページ範囲:P.1454 - P.1456
ポイント
●正しい治療のためには,治療の目的とゴールを設定すること,目的に合った適切な治療法を選択すること,治療効果を正しく評価できる指標を決めること,の3条件が必須である.
●IBD治療の目的は,症状の改善と良好な全身状態の維持である.
●そのためには腸管の炎症の寛解,再燃の予防,合併症の予防と治療が必要であるが,これらは直接の目的ではなく,むしろ目的達成のための手段であることに注意したい.
治療を睨んだIBDの臨床診断学
IBD診断の基本
著者: 朝倉均 , 本間照
ページ範囲:P.1457 - P.1460
ポイント
●潰瘍性大腸炎の炎症は,主として粘膜にみられ,その炎症は直腸より始まりびまん性・連続性であることを基本とするが,数%に例外がみられるので,鑑別診断は重要である.
●クローン病の炎症は消化管壁全層性で,初期病変は縦走するアフタ様病変(びらん,潰瘍)であるが,病気が進展すれば縦走潰瘍や玉石敷状所見(cobblestone appearance)を呈する.
●潰瘍性大腸炎の3大合併症(腸穿孔,腸管大量出血,中毒性巨大結腸症)は,自覚症状と他覚所見からの症候による診断が重要である.
治療方針決定のための活動度や病態の捉え方
著者: 飯塚文瑛 , 田中美紀 , 戸田潤子
ページ範囲:P.1462 - P.1470
ポイント
●鑑別診断は重要だが,当初は腸炎の重症度で対応可能である.また重症度診断については,臨床的・病像的(内視鏡像的)所見に留意する.
●罹患範囲と活動期の範囲に留意,また初回か再燃かで有効薬量が異なる.
●ステロイド治療歴については,過去の有効量と無効量(再燃時に使用していた量)に留意する.その治療は副作用の検討・対策なしに行えない.
●腸炎症状の分析と経過観察(経過表を利用)が重要.適宜治療方針の再考(方針変更,ステロイド剤の増量または漸減)を行う.
●難治例はステロイドを漸減しつつ,新しい治療・補助療法を積極的にすすめる.
●クローン病の活動度判定は,簡易なほう(IOIBD)が日常有用である.
●IBDでは,栄養不良に有効で積極的な対処を行う.
●クローン病では,狭窄・瘻孔・膿瘍・肛門部病変・小腸病変に注意する.
IBDの消化管合併症
著者: 鈴木亮一 , 永瀬肇 , 関原久彦
ページ範囲:P.1472 - P.1473
ポイント
●炎症性腸疾患の消化管合併症は,手術の適応となるものが多く,タイミングを誤ると社会復帰の遅れや生命を脅かす原因となる.
●特に穿孔は手術の絶対的適応であり,中毒性巨大結腸症は絶対的適応に準ずる.
●肛門病変はクローン病に多発し,診断の手掛りとなる.
●膿瘍・瘻孔はクローン病に特徴的な合併症であり,鑑別にも役立つ.
IBDにおける発癌—内視鏡診断とサーベイランス
著者: 長廻紘 , 藤盛孝博 , 戸田潤子
ページ範囲:P.1474 - P.1478
ポイント
●長期経過したIBDにおけるcolitic cancerの発生頻度は12.5%(5/40)であったとの報告がある1).一般の大腸癌の頻度や年齢で比較すると,長期経過IBD,特に潰瘍性大腸炎は大腸癌のhigh risk groupといえる.
●潰瘍性大腸炎におけるcolitic cancerは,①多発癌が多い,②平坦で浸潤性,境界不明瞭と特異な肉眼型を示す,③未分化癌が多い,④dysplasiaを伴うものが多い,などの特徴があげられる.
●微細な形態診断学的根拠を基にした内視鏡検査は,colitic cancerの早期診断に貢献できるであろう.
潰瘍性大腸炎の画像診断
著者: 五十嵐正広 , 小林清典 , 勝又伴栄
ページ範囲:P.1480 - P.1485
ポイント
●潰瘍性大腸炎(UC)は,炎症の時期によって画像が異なる.
●典型例では,直腸から口側に連続したびまん性の炎症がみられる.
●急性期には,前処置の下剤や検査手技で病状を悪化させることがあるので注意が必要である.
●臨床症状や内視鏡所見により重症度を判定し,治療法を選択する.
●緩解期には,萎縮した粘膜や炎症性ポリープを伴うものがあり,経過不明な症例では他疾患との鑑別診断も重要である.
クローン病の画像診断
著者: 杉野吉則 , 今井裕 , 日比紀文
ページ範囲:P.1486 - P.1490
ポイント
●クローン病の画像診断はほぼ確立されており,的確な検査が行われればほぼ確診がつけられる.診断が難しいものとしては,アフタ様病変のみからなる病像や,他の炎症性腸疾患(腸結核や潰瘍性大腸炎など)と紛らわしい病像を呈するものなどである.
●画像検査に際しては,クローン病と診断するだけにとどまらず,病変の罹患範囲や潰瘍の程度を明らかにし,病変の進行度や活動性を知って治療方針を決めたり,治療の効果を判定することが重要である.特に,高度の狭窄や難治性の瘻孔は外科的治療の対象となるので,X線で確実に表さなければならない.
免疫学的検査の治療的意義
著者: 渡辺守
ページ範囲:P.1491 - P.1493
ポイント
●潰瘍性大腸炎およびクローン病では,ともに単に消化管のみの疾患でなく,全身性の免疫異常が存在するが,その免疫学的発症機序は全く異なる.
●炎症が慢性化すれば両疾患ともに,活性化された浸潤細胞からの炎症惹起物質による非特異的な炎症像が主体となるため,免疫学的検査においては同様の結果となり,両疾患の鑑別診断および治療法の選択に有用なものはほとんどない.
●免疫学的異常の追究から,炎症性腸疾患に対する新しい治療法,例えば免疫抑制剤の使用,白血球除去療法,抗CD4およびTNF抗体療法などが開発されてきたのは事実であり,今後もその追究は続けられるべきである.
IBD治療の基本薬
サラゾスルファピリジン—これからも標準薬か
著者: 小林清典 , 勝又伴栄 , 五十嵐正広
ページ範囲:P.1495 - P.1499
ポイント
●Salazosulfapyridine(SASP)は,sulfapyridine(SP)と5-aminosalicylic acid(5-ASA)のアゾ化合物である.
●SASPは,軽症〜中等症の潰瘍性大腸炎に対する第一選択の治療薬であり,大腸病変主体のクローン病においても有効性が確認されている.
●SASPは,副作用の発現頻度が高いことが問題である.SASPのなかで,非特異的抗炎症作用を有する5-ASAが有効成分とされ,副作用の多くはSPによるものと考えられている.そこでSPを除いた5-ASA製剤が開発され,SASPと同等の治療効果が確認されている.
●今後5-ASA製剤は,SASPの不耐例のみならず,軽症から中等症の潰瘍性大腸炎およびクローン病の治療に活用されていくものと考えられる.
5-ASA—治療体系は果たして変わるか
著者: 里見匡迫 , 山村誠 , 木下隆弘
ページ範囲:P.1500 - P.1504
ポイント
●5-ASAは,salazosulphapyridine(サラゾピリン®)の抗炎症作用の有効成分とされている.単独の経口投与では,急速に上部消化管から吸収されるため効果がない.このため5-ASAをコーティングするか,他のものと結合させて吸収を遅延させるようにした製剤が用いられている.
●5-ASA製剤は,欧米では既に潰瘍性大腸炎の軽症・中等症の緩解導入および緩解維持の目的のために広く用いられている.対象と目的はサラゾピリン®と同様であり,効果もほぼ同じで,比較的副作用が少ないとされている.
●5-ASA製剤が炎症性腸疾患の現在の治療体系を変えるとは考えられないが,副作用の少ない点から,使いやすい薬剤として今後用いられることが多くなるであろう.
副腎皮質ステロイド—いつ,どのように用いるか
著者: 蘆田知史 , 栄浪克也 , 高後裕
ページ範囲:P.1505 - P.1508
ポイント
●潰瘍性大腸炎に対するステロイドの強力静注療法は高い緩解導入率を有しているが,手術適応の判定を見誤らないことが重要である.
●潰瘍性大腸炎においてステロイドを局所投与(注腸投与)する場合,投与量の約40%は全身的に吸収されることが知られており,他の投与法と同様,副作用の発現に注意が必要である.
●ステロイドの経口投与を行う場合,潰瘍性大腸炎,クローン病の両者の場合において,少量を持続的に投与しても有意な緩解期間の延長は報告されていないことを念頭に置くべきである.
免疫抑制剤はIBD治療の“first-line drug”か
著者: 岩男泰 , 渡辺守 , 日比紀文
ページ範囲:P.1510 - P.1511
ポイント
●IBDは免疫学的異常が病態に関与しており,それを踏まえたうえで免疫抑制剤の投与が行われる.
●他の薬剤に比べ副作用が強く,投与後は厳重な経過観察が必要である.
●免疫抑制剤の適応は,ステロイド離脱困難例,難治例,頻回再燃例の緩解維持である.クローン病では難治性の瘻孔も適応になる.
●6-MP,アザチオプリンは長期投与の報告も多く,少量投与では比較的安全性も高い.
●シクロスポリンやメトトレキサートの評価は定まっていないが,難治例などで効果が期待される.
止痢剤・鎮痙剤・抗生物質をどう用いるか
著者: 柳川健
ページ範囲:P.1512 - P.1514
ポイント
●止痢剤・鎮痙剤は,特に重症例の炎症性腸疾患(IBD)に重篤な合併症であるtoxicmegacolonを引き起こすことがあるので注意が必要である.
●クローン病(CD)において,閉塞や狭窄病変が疑われる場合には止痢剤・鎮痙剤を使ってはならない.
●腹腔内感染を合併する場合には,広域スペクトラムの抗生物質を用いる必要がある.
●Primary therapyとしての抗生物質の効果は潰瘍性大腸炎(UC)では否定されている(フラジール®).しかし大腸型CDで,特に瘻孔を有する場合,メトロニダゾールが有効である.
●メトロニダゾールは副作用が比較的多く,特に末梢神経障害の出現に注意する.
IBDの栄養管理と在宅管理
栄養療法は主役か,脇役か
著者: 樋渡信夫
ページ範囲:P.1515 - P.1517
ポイント
●重症型潰瘍性大腸炎における中心静脈栄養(TPN)は,栄養状態を改善・維持しながら,たとえ手術に移行しても,より安全に行えることを目的にした補助療法である.経腸栄養(EN)の適応はない.
●活動期クローン病に対しては,栄養療法単独でも80〜90%の症例で緩解導入が可能であり,primary therapyとしての効果が認められている.
●緩解維持,あるいは軽い再燃に対して,在宅経腸栄養法(HEN)か,薬物療法かは,個々の患者の背景や希望,過去の治療歴やその反応を参考にして選択する.
IBD患者の生活指導について
著者: 高添正和
ページ範囲:P.1519 - P.1521
ポイント
●診断確定時や長期フォロー中の説明に際して慎重に対処せねばならない.
●炎症性腸疾患の長期医療管理はcure and careが主体であるため,患者の実生活の問題点への積極的なアプローチが必要である.
●生活面では食生活,社会生活,学校生活,結婚,妊娠,出産などが問題となる.
●炎症性腸疾患でストーマや腸瘻が存在したり,小腸病変の存在により経管栄養を施行せざるを得ない場合には,直腸膀胱障害や小腸機能障害の認定対象となる.
●成分栄養剤を用いた経管栄養法は,在宅医療の対象である.
クローン病のprimary therapyとしての成分栄養法
著者: 大林隆晴 , 大瀬亨 , 星野恵津夫
ページ範囲:P.1522 - P.1524
ポイント
●成分栄養法は,クローン病の初期治療としてのみならず,再発防止のためにも有用な治療法であり,その効果はステロイド療法と比べ勝るとも劣らない.
●その適用においては,味や日常生活の制限の問題など若干の難があるが,副作用の発現は少なく,クローン病治療の第一選択となり得る.
●成分栄養法は,様々な投与方法・投与量で行われているが,患者の体格・活動性に見合う十分な投与量が必要である.
●患者の生活背景を考慮した無理のない投与法を選択することにより,快適な社会生活が可能となる.
クローン病における完全静脈栄養の適応と限界
著者: 正田良介 , 松枝啓
ページ範囲:P.1525 - P.1527
ポイント
●完全静脈栄養は,クローン病の急性期腸管病変自体を改善する.
●成分経腸栄養に比較して,その治療効果がより高いわけではない.
●経腸栄養に比較して,経済性・安全性・簡便性などでは劣る.
●完全静脈栄養の絶対適応とされていた短腸症候群・狭窄・瘻孔を持つ症例でも,他の治療法が行われるようになってきている.
●完全静脈栄養の絶対適応は減少しつつも,極端な短腸症候群,経腸栄養不応例などは確実に存在している.
●完全静脈栄養から経腸栄養への移行は,可能ならでき得る限り早期に行う.
内科治療の限界と外科治療
潰瘍性大腸炎の外科治療—いつ考慮するか
著者: 今村幹雄 , 中嶋裕人
ページ範囲:P.1528 - P.1530
ポイント
●結腸全摘,直腸粘膜抜去兼回腸嚢肛門吻合術(IPAA)のような手術により,潰瘍性大腸炎の手術成績は非常に向上した.
●保存的治療の限界を認識し,機をみて外科治療を選択すべきである.
●手術を考慮すべきタイミングは以下のごとくである.①全大腸炎型で長期(7年以上)にわたり再燃緩解を繰り返す難治例,②小児では保存的治療期間が2年を越える場合,③強力静注療法が有効でない場合,④ステロイド治療の限界やステロイド離脱困難を生じた場合,⑤中毒性巨大結腸症などの重篤な合併症を生じた場合.
クローン病の外科治療—何を対象とするか
著者: 福島恒男 , 山本雅由 , 山内毅 , 杉田昭 , 藤井義郎
ページ範囲:P.1531 - P.1533
ポイント
●クローン病の外科治療は,狭窄,閉塞,瘻孔,腫瘍,成長障害,肛門病変などに対して行われる.
●狭窄に対しては狭窄形成術,肛門病変に対してはシートン法など侵襲の少ない手術が選択されている.
IBDに対する腹腔鏡下手術—適応と限界
著者: 渡邊昌彦 , 日比紀文 , 北島政樹
ページ範囲:P.1534 - P.1535
ポイント
●腹腔鏡下手術は創が小さく,術後創痛は軽微で腸蠕動の再開が早く,癒着も最小限にとどめることができる.
●腹腔鏡下手術は運動制限が少なく,早期の社会復帰が可能で美容上優れている.
●主病変が小腸のクローン病や潰瘍性大腸炎は適応となる.一方,病変が広範囲なもの,開腹術の既往があるもの,活動期にある炎症性腸疾患は腹腔鏡下手術の適応から除外される.
特殊治療の理論的背景と将来展望
全身的影響の少ないステロイドによる局所療法
著者: 押谷伸英 , 北野厚生 , 小林絢三
ページ範囲:P.1536 - P.1537
ポイント
●中等症ないし軽症の左側大腸炎型あるいは直腸炎型潰瘍性大腸炎は,注腸療法の適応となる.
●局所療法であっても従来のステロイド剤では,長期間あるいは投与量が多い場合には,全身的副作用が出現する.
●全身的影響の少ないステロイド剤として,難吸収性薬剤およびアンテドラッグがある.
●合併症を有する潰瘍性大腸炎において,アンテドラッグが有用である.
新しい免疫療法
著者: 日比紀文 , 岡本晋 , 中澤敦
ページ範囲:P.1538 - P.1540
ポイント
●現在使用されている6-MPやシクロスポリンなどの免疫抑制剤は,リンパ球全体に対し抑制的に働くものが多く,全身の免疫能の低下が問題となる.
●このため,作用の対象をリンパ球の特定のサブセット,例えばヘルパーT細胞やそれらが産生するサイトカインなどに絞った,新しい免疫抑制療法の開発が試みられている.
●ヘルパーT細胞を標的とするものとしては,クローン病における腸管粘膜内活性化CD4陽性細胞に対する抗CD4抗体やCD4 analogueがある.
●サイトカインを対象とするものとしては,炎症性サイトカインの抑制剤投与と炎症抑制性サイトカインの投与の2通りの方法があるが,なかでも,抗TNF-α抗体はクローン病に対する新しい治療法として注目されている.
潰瘍性大腸炎の白血球除去療法
著者: 大西国夫 , 澤田康史 , 下山孝
ページ範囲:P.1541 - P.1544
ポイント
●潰瘍性大腸炎は若年者に好発し,主として粘膜下層を侵す大腸の特発性・非特異性の難治性炎症性疾患である.
●炎症性腸疾患は,広い意味での自己免疫疾患であると考えられている.
●組織像でみられるように,好中球,形質細胞,リンパ球などの白血球が活性化,増加している.
病態に応じたIBDの治療
潰瘍性大腸炎の治療戦略
著者: 牧山和也 , 岩本美智子 , 野元健行
ページ範囲:P.1546 - P.1549
ポイント
●潰瘍性大腸炎(以下,UC)の長期経過パターンを,コントロールの難易性から4つの型に分類できる.
●UCの大腸粘膜局所では,過剰なsystemic inflammatory immune responseが引き起こされている.
●UC治療のポイントは,初発時のステロイドを主体とした強力な初期治療である.さらに,中断のない緩解維持療法,手術が必要な患者のタイミングよい選択,QOLを保つための患者教育と患者管理を的確に行う.
●新しい薬物治療の戦略は,活性酸素産生と代謝機構,サイトカイン・ケモカインの産生機構,接着分子発現機構の抑制と制御がターゲットになっている.
ステロイド抵抗性/依存性の潰瘍性大腸炎
著者: 山崎日出雄
ページ範囲:P.1550 - P.1551
ポイント
●潰瘍性大腸炎重症・激症例には,強力静注療法や動注療法などのステロイド全身投与が施行されるが,無効例は緊急手術の適応とすべきである.
●アザチオプリンや6-MPは,ステロイド依存性症例に対しステロイド減量・離脱効果を有する.
●アザチオプリンや6-MPの副作用として,骨髄抑制(特に白血球減少や無顆粒球症),膵炎,脱毛などに注意する必要がある.
クローン病の治療戦略
著者: 大原信 , 北洞哲治 , 林篤
ページ範囲:P.1552 - P.1555
ポイント
●治療の基本は腸管の炎症を抑え,栄養状態を改善させる内科的治療である.
●病態からみて,抗原の除去と栄養の改善をはかる栄養療法,生体の免疫異常を是正し,炎症を抑える薬物療法が選択される.
●栄養療法,薬物療法,厚生省特定疾患調査研究班の治療指針案を基盤に行われるが,画一的な治療法はなく,その病態,病状を考慮し適切に選択することが肝要である.
●外科治療は小範囲切除や狭窄形成術にとどめ,できるだけ内科的治療を続ける考え方が近年優勢となりつつあり,腹腔鏡下手術も試みられ始めている.
会陰部クローン病の保存的治療と外科治療
著者: 鈴木公孝 , 武藤徹一郎
ページ範囲:P.1556 - P.1557
ポイント
●会陰部クローン病は,大きく一次性,二次性,随伴性に分類される.
●一次性病変には裂肛,深掘れ潰瘍などが含まれ,栄養療法や薬物療法で軽快することが多い.
●痔瘻の2/3は通常の低位筋間痔瘻であり,根治手術(laying open)により治癒することが多い.
●複雑な高位痔瘻は二次性病変であり,切開排膿,シートン法が適応である.
●二次性病変である直腸膣瘻に対し,advancement flapを経膣的に用いる方法は有効である.
●随伴性病変である痔核の手術適応については今後の課題である.
妊娠・授乳時のIBD治療
著者: 杉浦弘和 , 宮岡正明 , 斉藤利彦
ページ範囲:P.1558 - P.1559
ポイント
●IBD患者での妊娠は可能であり,妊娠を諦めたり,積極的な避任は不要である.
●IBD患者の妊娠は,寛解期に勧めるのが望ましい.
●常用量のサラゾピリン®やステロイド剤は,胎児への影響は少ない.
●授乳中のステロイド剤は児に対する影響が少ないとされているが,サラゾピリン®では,児への影響があるという報告もみられるため,慎重に投与すべきである.
●妊娠・授乳を希望するIBD患者には,服薬継続のメリットとデメリットを十分に説明することが大切である.
高齢者IBD患者の治療と問題点
著者: 金城福則
ページ範囲:P.1560 - P.1561
ポイント
●潰瘍性大腸炎で,60歳以上の発症は約10%である.
●病変の範囲は全大腸炎型が少なく,直腸・左側結腸に限局した病変が多い.
●再燃緩解型が少なく,初回発作型が多い.
●手術例では穿孔を原因とするものが多い.
●経過中の死亡率が高い.
●虚血性大腸炎,感染性大腸炎などとの鑑別を,糞便検査や前処置なしの直腸・S状結腸内視鏡検査で迅速に行う.
●治療は厚生省難治性炎症性腸管障害調査研究班による治療指針改訂案に準じて行う.
●外科的治療の適応を的確に判断する.
IBDの消化管外合併症とその治療
著者: 柴田実
ページ範囲:P.1562 - P.1564
ポイント
●IBDは多彩な合併症を呈するため,腸管病変を主体とした全身疾患と捉えることができる.
●大腸の病変では免疫異常に関連した合併症が多く,小腸の病変では吸収障害などの生理学的異常に関連した合併症が多い.
●コルチコステロイドやサラゾスルファピリジンの投与による医原性合併症も存在する.
●合併症と腸管病変の出現時期は必ずしも一致しておらず,合併症がIBD発見の契機になることもある.
クリニカル・ワークショップ
IBD治療における内科と外科のインタープレー
著者: 飯塚文瑛 , 日比紀文 , 杉田昭 , 上野文昭
ページ範囲:P.1565 - P.1579
上野(司会) IBDの治療法が次々と開発され,多様化するに従い,臨床の現場では治療法の選択に迷うこともかえって多くなりつつあります.本日は,日頃お互い気心の知れた内科と外科の先生方をお迎えして,それぞれの信念と哲学に基づいた治療法について大いにdebateをしていただきたいと思います.
今日は症例を2例用意しました.教科書的な通り一辺の治療法ではなく,活きた治療法に関する討論をすすめていただきたいと思います.
カラーグラフ 塗抹標本をよく見よう・8
リンパ球の異常・1
著者: 久保西一郎 , 藤田智代 , 浜田恭子 , 高橋功 , 三好勇夫
ページ範囲:P.1593 - P.1596
正常リンパ球
図1は,末梢血塗抹標本で見られる正常リンパ球である.図1aは小型リンパ球,図1bは大型リンパ球をそれぞれ示している.リンパ球は末梢血白血球の分類上,約30〜40%をしめる.正常人の白血球数を4,000〜8,000/mm3とすると,その絶対数は約1,200〜3,200/mm3くらいとなる.末梢血中のリンパ球の大部分(75〜80%)はTリンパ球で,15〜20%はBリンパ球と考えられている.残りの約5%はTでもないBでもない,いわゆるnon T/non B(null cell)タイプのリンパ球と考えられている.このnon T/non Bリンパ球は,図1bで示した大型で細胞質の中に顆粒を有する細胞(large granular lymphocyte)で,naturalkiller活性を持っていると考えられている.図1bをよく見るとazur顆粒があるのだが,分かっていただけるだろうか.
グラフ 高速CTによるイメージング・7
肺の実質性病変
著者: 鈴木孝司 , 甲田英一 , 平松京一
ページ範囲:P.1605 - P.1610
高速CTの長所は,短時間で多数の連続したデータを得ることができるところにあると考えられる.この長所を生かし,肺の病変に対してもいろいろな試み1)がなされている.特に肺実質の腫瘍性病変や気管支病変に対する応用はかなり広いものがある.これらについては,本連載で国立がんセンターの小室先生,栃木県立がんセンターの森先生が詳しく解説されると思うので,この項では肺の実質性病変を広い意味に解釈し,お二人の先生が言及されないと思われるその他の肺病変の中で,高速CTが有用と思われた症例を供覧する.もし重複があった場合はご容赦願いたい.
図解・病態のメカニズム—分子レベルからみた神経疾患・12
ミトコンドリア脳筋症
著者: 米田誠
ページ範囲:P.1615 - P.1619
ミトコンドリア脳筋症は,生体のエネルギープラントであるミトコンドリアの酸化的リン酸化系(電子伝達系とATP合成酵素)の遺伝的障害によって,神経・筋を主体とした多彩な症状を呈する疾患群である.網膜色素変性症・外眼筋麻痺・心伝導障害を主徴とするKearns-Sayre症候群(KSS),小児の脳卒中様発作・乳酸アシドーシスを主徴とするMELAS症候群(mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes),ミオクロヌスてんかん・小脳失調・痴呆を主徴とするMERRF症候群(myoclonus epilepsy as-sociated with ragged-red fibers)が三大病型とみなされているが,これらのほかにも各種の臨床型が認められている.神経・筋以外の症状を主体とする病型も多く見いだされているため,ここでは広くミトコンドリア病という名称を用いる.
近年の分子遺伝学的解析によって,これらの各種臨床型における特異的ミトコンドリア遺伝子(mtDNA)変異の存在が明らかになってきた1〜3).mtDNAは染色体上の核遺伝子とは大きく異なるいくつかの遺伝学的特徴をそなえており,ミトコンドリア病の特異な病態を規定している.
知っておきたい産科婦人科の疾患と知識・12
肥満,月経異常と多嚢胞性卵巣症候群
著者: 楢原久司 , 江藤靖子 , 宮川勇生
ページ範囲:P.1621 - P.1624
多嚢胞性卵巣症候群(polycystic ovary syn-drome:PCOS)は生殖年齢女性の約3%にみられ,排卵障害による月経異常や不妊,さらには多毛,にきび,肥満などの臨床症状を呈する症候群である.本邦では,肥満はPCOSの約20%に認められ,肥満のPCOSは非肥満のPCOSに比べて約2倍不妊となる率が高い.一方,肥満女性には月経異常の頻度が高いことが知られているが,PCOSの月経異常と,肥満ではあるがPCOSではない(非PCOS肥満)女性の月経異常が,同一の病態を共有しているかどうかについては一定した見解が得られていない.
本稿では,PCOSの症例を呈示し,病態生理および肥満との関連について概説する.また,内科医として遭遇する機会が多い肥満患者に月経異常が合併した際,PCOSを含めどのような臨床上の問題点があるのかを,産婦人科医の立場から述べてみたい.
Drug Information 副作用情報・5
薬剤性ショック(3)—プロスタグランジン製剤投与後のショック死例
著者: 浜六郎
ページ範囲:P.1625 - P.1627
今回は,薬剤性ショック(1)でも簡単に紹介した例を詳細に述べたい.重症のCOPD(慢性閉塞性呼吸器障害)の患者に二次的に生じた偽性腸閉塞(排便困難)に対してプロスタグランジン製剤を使用し(適応外),発熱・血圧上昇,投与終了後解熱,血圧の低下をきたし,ショック状態となって,心肺停止後,いったん蘇生したが,4ヵ月後に死亡した例である.医師が訴えられ,最近判決が下され,医師が敗訴している.
医道そぞろ歩き—医学史の視点から・16
権威に挑戦したヴェサリウス
著者: 二宮陸雄
ページ範囲:P.1628 - P.1629
「人体構造論』(ファブリカ)の出版の後,ヴェサリウスはガレノス批判のゆえに権威者たちに非難され,四面楚歌のただ中に身を置く羽目になった.パリ時代の師シルビウスも,師と思うな,と書いてきた.この極めて実証的な記述解剖書が西欧の医師たちに与えた衝撃が消えやらぬ翌年の1544年に,ヴェサリウスはパドヴァ大学を去り,ベルギーのシャルル5世の宮廷臨床医の道を選んだ.
ヴェサリウスは『ファブリカ』の中で,長い間欧州全域で疑問のない権威を保っていたガレノスの解剖学の誤りを指摘した.そして遠慮がちな言い回しではあったが,「ガレノスはかなり空想的である」とか,ガレノスの解剖書である「身体各部の役割について」が「空想的でないことを願う」とか,「ガレノスの無数の教義が全く信頼しがたいとは言わないが」とか,果ては「ガレノスは人体解剖をしたことがない」とさえ書いた.
連載
目でみるトレーニング
ページ範囲:P.1597 - P.1603
基本情報
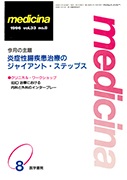
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
