最初この企画を見たとき,これは大変難しいことを依頼された,と感じた.現在,分子生物学の飛躍的な進歩により,多くの疾患の原因が明らかにされ,分子病態に沿った治療法が考案されつつある.既に一部は臨床応用され,効果をあげていることが新聞などで報道されているので,耳にしていることと思う.また,なかには患者からその内容について質問された経験をお持ちの方も多いであろう.したがって,遺伝子工学を理解することは臨床医にとって重要であるのは間違いない.
だが,重要であることと理解できる,あるいは馴染みがあるということとは別であって,多くの臨床医の方は,遺伝子工学を理解する必要などないよ,と思われていることであろう.筆者も初めて遺伝子工学の実験を行うのに(10年程前になるが),従来の実験手法との違いに驚き,遺伝子工学を理解するのに苦労した(幸い,わからないまま実験を行っているうちに,完全ではないが理解できるようになり現在に至っているが).しかし,遺伝子工学の方法は理解できなくとも,そこから得られた果実は,実地診療のためにも臨床医が食べる必要がある.本特集がその手助けになれば幸いである.
雑誌目次
medicina34巻12号
1997年11月発行
雑誌目次
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
理解のための26題
ページ範囲:P.2211 - P.2216
Editorial
臨床医にとっての遺伝子工学とは
著者: 森下竜一
ページ範囲:P.2066 - P.2067
遺伝子の基礎知識
染色体の構造と遺伝子
著者: 服巻保幸
ページ範囲:P.2068 - P.2074
生物の遺伝情報を担う構造物を染色体(クロモソーム)と呼ぶが,大腸菌などの原核細胞では遺伝情報が塩基配列として刻み込まれているDNAはほとんど裸の状態で存在している.しかし酵母からヒトに至る真核生物の細胞では,染色体はより複雑な構造をとっている.つまりDNAだけでなく,組織によらず均一なヒストン蛋白質と一部組織ごとに異なるノンヒストン蛋白質やRNAから成り,このような染色体の構成成分を染色質(クロマチン)と呼ぶ.本来,染色体は細胞周期のM期(分裂期)に凝縮してみられる棒状の構造体を示し,それ以外の間期に核内に分散してみられる塩基性色素で染まる物質をクロマチン(染色質)と呼んでいた.このクロマチンがM期に凝集して染色体を形作ることになるが,現在では染色体という言葉は細胞周期の時期によらず用いられ,特に染色体の構成成分を意識した場合,クロマチンという言葉が用いられることが多い.ここでは染色体の基本構造やゲノムと遺伝子との関係,ならびにクロマチンと転写や複製との関係について説明する.
遺伝子の構造と機能
著者: 藤澤順一
ページ範囲:P.2076 - P.2079
ゲノムと遺伝子
現在,世界的な規模でのゲノムプロジェクトが着実に進行し,これまでに10種類以上の生命体の全ゲノム構造が明らかとなっている.そのほとんどが,病原性微生物をはじめとする原核生物のゲノム構造であるが,ワクチンや化学療法剤開発における意義はいうまでもなく,約半数の機能不明の仮想的遺伝子を含めた1,000種類足らずの遺伝子の機能で生命活動を説明し得る状況になったことのインパクトは大きい.
ヒトのゲノムはハプロイドあたり約3×109塩基対(bp)存在し,はじめてそのゲノム構造が明らかとなった生命体Haemophilus influenzae(1.8×106bp)の2,000倍にも達するが,そのなかでRNAとして転写される領域,すなわち遺伝子領域はたかだか10%に満たないとされている.残りのゲノム配列の大部分は,いわゆるjunk DNAで,個体レベルあるいは進化レベルでの遺伝子組み換えや遺伝子重複に関与している.
転写因子
著者: 河邊拓己 , 岡本尚
ページ範囲:P.2081 - P.2085
一般に,遺伝情報はDNAに蓄えられており,そこから情報を引き出す最初のステップが,DNAからRNAへの転写である.転写は核内で行われ,転写された遺伝情報は,細胞質でリボソームとトランスファーRNA(tRNA)の働きによりアミノ酸配列へと翻訳され,実に様々な蛋白質が合成される.DNAからRNAへの転写を行うために用意された蛋白質群を転写因子と呼んでいる.ここでは,主に高等動物細胞における転写について述べる.
遺伝子の変異と疾患の発症
著者: 山縣和也 , 松沢佑次
ページ範囲:P.2086 - P.2088
遺伝性鎌状赤血球貧血の原因が異常ヘモグロビンであると判明したのが,特定の蛋白質分子の異常により疾患が発症することが明らかになった最初の報告であるという.その後も,血友病における凝固因子,フェニルケトン尿症におけるフェニルアラニンヒドロキシラーゼなどのように,いくつかの遺伝病においては生化学的な欠損が発見され,疾患の発症原因が同定された.しかし,大部分の遺伝病においてはその生化学的異常は不明であり,分子生物学の技術が発展する以前には,ヒトの疾患において遺伝子異常を解明することは大変困難であった.
分子生物学の著しい発展により,疾患の原因は蛋白質レベルから遺伝子レベルで解明されるようになった.現在,遺伝子データベースには5,000以上の疾患遺伝子座がマップされている.注目すべきことは,生化学的な異常が同定される以前に原因遺伝子を同定する手法が開発されたことである.筋ジストロフィーのジストロフィンや,cystic fibrosisにおけるCFTR(cystic fibrosis transmembrane conductor regulator),若年発症成人型糖尿病におけるHNF遺伝子などはそのよい例である.
ベッドサイドで可能な遺伝子診断
遺伝子診断概論:遺伝子解析と診断
著者: 田中一
ページ範囲:P.2090 - P.2093
分子遺伝学の長足の進歩を背景に,近年,遺伝子解析・遺伝子診断が爆発的普及をみせている.最近は研究機関の基礎的研究にとどまらず,疾患によっては第一線の実地診療において日常的検査として様々な診断レベルで応用されるに至っており,民間の臨床検査施設でも解析可能な遺伝子項目が増えつつある.
一概に遺伝子診断といっても,その対象はメンデル型遺伝形式を示す単一遺伝子病から,生活習慣病に代表されるような多因子遺伝病,癌などの体細胞遺伝子病,染色体異常,感染症,個体識別にまで多岐にわたっている.単一遺伝子病は,Victor A. McKusickによるMenderian Inheritance in Manと呼ばれるカタログに詳細が収録されているが,最近はサイバースペースの隆盛により,インターネット経由でいつどこからでもこれらの情報を入手することが可能となっている.このオンラインで検索可能なカタログはOMIM(Online Menderian Inheritance in Man)と呼ばれ,米国のNCBI(National Center for Biotechnology Information)によりホームページ(http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/)の維持管理が行われている.
心疾患解析
著者: 広井知歳 , 木村彰方 , 永井良三
ページ範囲:P.2096 - P.2099
最近数年間の分子遺伝学的解析により,心疾患領域においても,永らく原因不明とされていた遺伝性心筋症や遺伝性不整脈の原因の一部が明らかにされてきている(表1).これら遺伝性心疾患を診断するためには患者およびその家族を対象として,既知の原因遺伝子を検索し,遺伝子内変異を同定するのが一般的である.本稿では,特にその解析が進んでいる家族性肥大型心筋症,家族性QT延長症候群を中心に,現在までに明らかにされている原因遺伝子について最近の知見を概説する.
内分泌代謝領域
著者: 高橋義彦 , 門脇孝
ページ範囲:P.2100 - P.2103
PCR(polymerase chain reaction)法によって,遺伝子異常による疾病が多数明らかにされ,その変異の同定に至るまでの過程が以前より速まってきた.特に内分泌代謝領域では,ホルモンの異常あるいはその受容体の異常,輸送蛋白の異常などが,種々の内分泌学的負荷試験や血中代謝産物の解析により臨床的に特定され,それが実際の遺伝子解析に結びついて多くの成果が上げられている.この領域における遺伝子異常のすべてをカバーはできないが,概ね以下のように分類されよう.
高血圧解析
著者: 勝谷友宏 , 檜垣實男 , 荻原俊男
ページ範囲:P.2104 - P.2107
高血圧症は臨床医が最も高頻度に接する疾患であり,日本には約3,000万人の患者が存在する.利尿剤しかなかった昔とは異なり,非常に多くの種類の降圧薬が市販され,あらゆる診療科で「血圧が高いですね.ではこのお薬を飲んでください」という光景がごく一般のものとなっている.しかし,食塩過剰摂取や喫煙が高血圧の増悪因子であることはよく知られているが,「高血圧」の原因はいまだ不明であり「本態性高血圧症」の病名を冠するものが9割以上を占めているのが現実である.高血圧に遺伝が関与することは理解されていても,それを診断補助に用いたり,患者への説明に用いられた方はほとんどないのではないだろうか.この5〜6年の間の急速な分子生物学的手法の進歩により,この「高血圧」という多因子遺伝性疾患が少しずつ解明されつつある.本稿では,病気を起こす原因遺伝子が明らかにされた「遺伝性高血圧」の紹介とその臨床像の特徴,また本態性高血圧症に罹患しやすくなると考えられる「疾患感受性遺伝子」の解析の現状について述べる.
腎疾患解析
著者: 桑原道雄 , 丸茂文昭
ページ範囲:P.2108 - P.2110
遺伝子工学の進歩によって,腎疾患においても疾患発症の原因となっている遺伝子異常が次々と同定されつつある.これらの主な疾患を表1に示した.
内分泌疾患解析
著者: 藤原裕和 , 巽圭太 , 網野信行
ページ範囲:P.2112 - P.2114
内分泌系において,情報の伝達を担うのはホルモンである.paracrine(傍分泌),autocrine(自己分泌)あるいはneuroendocrine(神経内分泌)などの概念の確立とともに,内分泌およびホルモンの概念も大きく変化してきている.古典的には,内分泌器官でホルモン産生が行われ,血中に分泌,血流を介して標的器官に達したホルモンは,そのホルモンに特異的な受容体に結合し,標的器官内ではこれに対する反応が進み機能が発揮される.
この一連の情報伝達のそれぞれの過程で,遺伝子異常に基づく疾患が最近明らかになってきた.表1に,病因が遺伝子レベルで明らかにされた内分泌疾患をあげた1).本稿では,筆者の研究室で世界に先駆けて病因を遺伝子レベルで明らかにした例を3例紹介する.いずれも先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)を呈する疾患で,放置すると重篤な知能・発育の低下を招くが,早期(生後3ヵ月以内)からの治療により発症は予防できる.
動脈硬化症の遺伝子診断
著者: 一瀬白帝
ページ範囲:P.2117 - P.2119
動脈硬化症の中で臨床的に最も問題となるのは粥状硬化症で,その程度が軽い時期は無症状であるが,年月を経て次第に動脈内腔の狭小化が高度になると虚血症状が顕著になる.例えば脳梗塞,心筋梗塞,間欠性跛行症・下肢の壊死など,粥状硬化の起きた動脈によって還流される領域の虚血症状が引き起こされる.
粥状硬化症の成因としては「障害反応説」が定説となっており1),その発生と進展には血管壁の障害に対する細胞遊走・増殖と脂質・細胞外マトリックス代謝が主役を演じ,内腔閉塞には血栓形成や血管攣縮も重要な役割を果たす.粥状硬化は健常人でも10代から発生して緩徐に進行するので,それ自体は加齢現象の一部とも考えられる.しかし食生活の欧米化とともに,比較的若年でも臨床症状を呈する症例が増加しつつあるので,死に至る「生活習慣病」として進行防止の努力が肝要である.
遺伝子工学の臨床への応用 基礎知識—遺伝子工学とは?
トランスジェニック技術
著者: 宮崎純一
ページ範囲:P.2120 - P.2123
マウス受精卵にDNAを導入することにより,外来遺伝子を染色体に取り込ませたトランスジェニックマウスが初めて報告されてから10数年経つが,この技術は改良されて,様々な遺伝子を発現させることに成功してきた.トランスジェニックマウスにより,遺伝子の役割を,動物の発生・成長過程を含めて個体で研究することが可能になり,実際,複雑な生命現象の解析に大きな威力を発揮してきた.このトランスジェニック技術はマウスのみならず,ラット,ウサギ,ヤギなどにも応用されてきたが,一般的にはマウスを用いることが多いので,ここではトランスジェニックマウス作製法について概説するとともに,その医学研究への応用例を示す.
ノックアウト技術
著者: 深水昭吉
ページ範囲:P.2125 - P.2128
ノックアウトマウス作製
ノックアウト技術は,遺伝子の機能を個体レベルで解析しようとする方法の一つで,現在様々な分野(発生,内分泌,転写,癌)で応用されている.この技術の出発点は,多分化能を有するマウス胚性幹細胞(embryonicstem cell:ES細胞)のin vitroでの継代培養を可能にしたことであった1).
遺伝子ノックアウトマウス作製の第一段階は,ES細胞レベルにおいて相同組み換えによって目的の遺伝子を欠損させることである.導入した遺伝子が染色体に組み込まれる確率は103から104に1個程度であるから,遺伝子が導入されたものを選ぶための選別(positive selection)が必要である.ネオマイシン(neo)は蛋白質合成を阻害することによって細胞を死に至らしめる.neo耐性(aminoglycoside phosphotransferase)遺伝子はneoをリン酸化することによって,この蛋白質合成阻害作用を和らげる.よって,導入DNA内にneo耐性遺伝子を組み込んで発現させれば,導入したDNAが染色体に取り込まれた細胞のみを生き残らせることができる.
生体への遺伝子導入の方法
著者: 山野智基 , 金田安史
ページ範囲:P.2130 - P.2133
遺伝子治療は難治性疾患に対する画期的な治療法として1990年代に大きな期待を集めて登場した.しかし日本では,本格的な臨床治験は行われておらず,また遺伝子治療先進国である米国でも従来の治療にとって代わるだけの評価は得られていない.現在の遺伝子治療における最大の問題点は結局のところ,生体への遺伝子導入法が確立していないことに尽きる.すなわち現在の技術では,①目的とする組織にのみ遺伝子を導入すること,②高い効率で遺伝子を導入し長期に遺伝子発現を持続させること,③導入した遺伝子発現をコントロールすること,はできておらず,これらを克服するために遺伝子導入ベクターの開発・改良とともに,発現ベクターの研究も進められている.
本稿では,ウイルスベクターとして現在最も広く用いられているレトロウイルスベクター,アデノウイルスベクター,選択的な遺伝子組み込み機能を持つAAV(adeno-associated virus:アデノ随伴ウイルス)ベクターを取り上げ,また非ウイルスベクターとしてリポソーム法,そして大阪大学で開発されたHVJ(hemagglutinating virus of Japan:センダイウイルス)リポソーム法,レセプター介在性遺伝子導入法などについて述べ,最後に発現ベクターについて簡単に触れる.
疾患解析への応用
自己免疫疾患
著者: 改正恒康
ページ範囲:P.2134 - P.2135
ヒト自己免疫疾患の病因に関しては,まだまだ不明な点が多い.しかも遺伝的背景および複数の病因が絡むと考えられるので,解析は非常に困難である.一方,マウスにも種々の自己免疫疾患を呈するモデルが存在するが,近年その機構の一部が解明され,ヒト自己免疫疾患の病因解明に有用な情報が提供されてきている.また古典的なモデルに加えて,トランスジェニックマウス,ノックアウトマウスのなかで自己免疫様の病態を引き起こすことが時に観察される.当然のことながら,遺伝子工学的に異常な状況を作成しているので,直接ヒト自己免疫疾患に結びつくのかは明らかではないが,病態の理解にとって貴重な情報であることは疑う余地がない.ここでは,自己免疫様病態を引き起こす変異マウスをいくつかのグループにまとめて概説してみたい(表1).
血液疾患
著者: 平井久丸 , 本田浩章
ページ範囲:P.2136 - P.2138
Philadelphia染色体(Ph1染色体)は,慢性骨髄性白血病(CML)の90〜95%,急性リンパ性白血病(ALL)の10〜20%に認められる染色体異常である.これは9番染色体と22番染色体との相互転座t(9;22)(q34;q11)により生じ,この結果,9番染色体上のc-abl遺伝子と22番染色体上のbcr遺伝子との融合遺伝子産物p210bcr/ablが産生される1).P210bcr/ablは正常のc-abl遺伝子産物に比べて高いチロシンリン酸化能を持ち,この増強されたチロシンキナーゼ活性が白血病の発症に関与していると考えられている2).しかし,p210bcr/ablが実際に白血病の原因遺伝子であるかどうかを確かめるためには,逆に生体内で発現させることにより白血病が発症するかどうかを検討する必要がある.この目的のためには,個体内で特定の遺伝子を発現させることができるトランスジェニックマウスの手法が適している.ここでは,筆者らが作製したp210bcr/ablトランスジェニックマウスについて紹介する.
消化器疾患
著者: 浅部伸一 , 井廻道夫
ページ範囲:P.2139 - P.2141
近年,消化器分野の疾患においても遺伝子工学的手法を用いた研究が盛んに行われている.胃潰瘍や潰瘍性大腸炎などの病態解明,肝炎ウイルス,Helicobacter pyloriなどの感染症と病態との関連,大腸癌,膵癌,胃癌,肝癌などにおける遺伝子異常の研究など,多くの疾患で遺伝子レベルでの解析が行われており,診断と治療に応用されている.ここでは肝炎ウイルスを中心に疾患解析の現状を概説したい.
呼吸器疾患
著者: 菊地利明 , 貫和敏博
ページ範囲:P.2142 - P.2144
近年種々の疾患について,その原因遺伝子の発見がなされているが,こと呼吸器疾患に限ってみると,その責任遺伝子がわかっている単一遺伝子病は,α1アンチトリプシン(α1 AT)欠損症とcysticfibrosis(嚢胞性線維症)のみである.肺癌,気管支喘息,気管支拡張症,サルコイドーシス,および原発性肺高血圧症の一部に遺伝性が考えられているものの,その遺伝の本体は不明である(気管支喘息の責任遺伝子が発見されたという情報があるが,まだ論文発表はされていない).そこで本稿では,一般的な肺気腫の病態の理解に重要なα1 AT欠損症について述べることにする.
老化
著者: 名倉潤 , 三木哲郎
ページ範囲:P.2146 - P.2148
1970年に特異的な部位を切断する制限酵素が発見され,1973年に組み換えDNA技術が確立して以来,遺伝子工学は医学,生物学のほとんどの分野において欠くことのできない技術となった.老化研究もその例外ではなく,ほとんどの老化研究に遺伝子工学が使用されている.
そこで本項では,種々の老化研究による知見とそれに基づいた老化に対する統合的な概念,および最近のトピックスとして,老化の代表的モデル疾患であるWerner症候群原因遺伝子単離とその後の研究を中心に紹介する.
発癌解析
著者: 野田朝男
ページ範囲:P.2150 - P.2152
発癌解析においては,これまで2つの異なった観点からのアプローチが取られることが多かった.第一は癌細胞における遺伝子変異解析であり,第二は遺伝性の癌の連鎖解析である.しかし,癌化に関与する遺伝子が多数同定され,発癌過程ではいくつかの遺伝子の異常が多段階的に蓄積されることが明らかとなるに従って,この2つのアプローチは現在では個々の遺伝子変異の事例でも相互に検討されるようになってきている.本稿では,癌化を一連の遺伝子の変化に伴って起こる正常細胞の増殖破綻過程であるとして,その要因を解説する.
疾患治療への遺伝子工学の応用:遺伝子治療に向けて 日本での現状
遺伝子治療の現状
著者: 小澤敬也
ページ範囲:P.2155 - P.2159
遺伝子工学の進歩は,分子病態の解明や遺伝子診断にとどまらず,その技術を治療にまで活かそうという遺伝子治療の発想を生み出してきた.本格的な遺伝子治療は,1989年の遺伝子マーキング臨床研究に引き続き,アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症を対象として1990年9月に米国NIHでスタートした.対象疾患はこのような難治性の遺伝性疾患(そのなかでも当面はシンプルな単一遺伝子病が対象)だけでなく,様々なアイデアのもとに遺伝子操作を利用した治療法が工夫され,癌やエイズなどの生命が脅かされる疾患も含められるようになった.
それに伴い,遺伝子治療に対する社会の関心と期待も一段と高まってきている.ここ数年の間に予想を超える勢いで臨床研究が進められ,何らかの目的で遺伝子の投与を受けた患者数は1995年12月の調査では1,062例,1996年6月には1,537例,同年12月には2,103例に急増してきている1).国別では米国がやはり圧倒的に多く,そのうち1,700例以上を占めている.対象疾患は癌が1,446例(68%)で一番多く,次いでHIV感染症390例(18%),嚢胞性線維症176例(8%)などとなっている.なお,表1に米国の臨床プロトコールを示す2).
先天性疾患の遺伝子治療—アデノシンデアミナーゼ欠損症を中心に
著者: 﨑山幸雄
ページ範囲:P.2160 - P.2161
1990年9月,米国国立衛生研究所(NationalInstitute of Health:NIH)のブーレイス博士らのグループが,酵素補充療法中のアデノシンデアミナーゼ(adenosine deaminase:ADA)欠損症の女児例に,ヒトへの初めての遺伝子治療を行った1).筆者らは同博士との共同研究で,ADA欠損症に対する遺伝子治療臨床研究を1995年8月から開始している.
HIV感染症に対する遺伝子治療
著者: 松下修三
ページ範囲:P.2163 - P.2165
ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus type-1:HIV-1)感染症に対する遺伝子治療には2つのストラテジーがある1).1つは標的細胞に抗ウイルス遺伝子を入れて細胞レベルで感染抵抗性にする方法で,もう1つはHIVに対する細胞性免疫を強化する方法である.筆者らの計画は後者の方法で,平成9年5月,文部省および厚生省の了承を得た.しかしその後,米国のベクター製造プラントで増殖可能レトロウイルス(replication competent retrovirus:RCR)が検出されるロットがあることがわかり,薬事審議会の遺伝子治療用医薬品調査会で再審議されることとなった.レトロウイルスベクターを用いる限り,ある確率でRCRが出現すると考えられ,どのような基準でRCR混入が否定されたものを安全とするのかが明確にされるべきだと考えられる.
癌の遺伝子治療:癌抑制遺伝子療法
著者: 藤原俊義 , 田中紀章
ページ範囲:P.2167 - P.2169
最近の分子生物学的解析により,癌は癌関連遺伝子の異常が多段階的に集積した結果生じた遺伝子病であるという概念が定着しつつある.実際に切除標本を用いた検索で,前癌病変から進行癌に至る各段階での癌遺伝子の活性化や癌抑制遺伝子の不活化など,複数の遺伝子異常が検出されている.癌抑制遺伝子は,正常な状態では遺伝子転写,細胞分裂,DNA修複などに働いており,変異や欠失などの異常が生じることで癌化に寄与している.なかでも,p53遺伝子産物は転写調節因子として細胞周期やアポトーシス誘導に関する多くの関連遺伝子を制御しており,トランスフェクションの実験系では,正常なp53遺伝子導入による癌細胞の増殖抑制やアポトーシス細胞死が認められる1).さらにp53は,抗癌剤や放射線によるアポトーシスの過程でも重要であることが明らかになってきており,p53遺伝子の異常は癌細胞の抗癌剤耐性のメカニズムの一つと考えられる2).
本稿では,このp53遺伝子を分子標的とした遺伝子治療の可能性について概説する.
癌の遺伝子治療:免疫遺伝子治療
著者: 谷憲三朗
ページ範囲:P.2171 - P.2176
近年の癌・白血病に対する治療法の進歩にはめざましいものがあるが,一方でいまだに治療抵抗症例も多く,悪性腫瘍は過去十数年以上も日本人の死因の第1位になっている.現在まで,これらの手術療法,化学療法や放射線療法などの主要な治療が有効でない症例群に対して,いくつかの新しい治療法が開発されてきており,遺伝子治療もこのうちの一つである.
癌に対する遺伝子治療法としては表1に示すような遺伝子治療プロトコールが,現在計画もしくは実施されている.これらは方法論的に大きく2つに分けられる.すなわち,癌細胞に直接的に遺伝子導入することによって治療を行う方法と,癌細胞以外に遺伝子導入をすることで間接的に治療を行う方法が検討されてきている.前者は従来の癌治療法の方向性と類似しており,その抗腫瘍効果には期待が持てるものの,現在の方法論ではまだ正確な腫瘍細胞の標的化が困難であるため,非腫瘍細胞への副作用の出現も懸念される.一方後者では,患者自身の免疫機構を利用しており,腫瘍細胞の標的化が現在の技術水準でも可能と考えられ,実用性が高いものと考えられる.
これからの遺伝子治療
循環器疾患の遺伝子治療
著者: 米満吉和 , 古森公浩 , 杉町圭蔵
ページ範囲:P.2177 - P.2179
心疾患,脳血管疾患など,動脈硬化に起因する疾病は国民死亡原因の第1位であり,その対策は急務である.循環器疾患において,臓器不全に陥る最大の原因は血管内腔の閉塞とそれに続発する臓器虚血であり,局所的な血管内腔の狭小化を制御する手段の確立,また虚血による臓器機能低下の回復が重要となる.また動脈硬化促進因子の制御も,発生予防上重要である.
これまで多くの薬剤や血管内治療法が確立され,一定の成績を治めているものの十分な効果をあげているとは言い難い.近年,遺伝子治療によるこれらの問題の解決が期待されているが,臨床応用にはいくつかの越えるべきハードルがある.本稿では循環器領域,特に血管壁内膜肥厚と虚血性疾患の遺伝子治療研究の現状と今後の課題について概説する.
自己免疫疾患(リウマチ)の遺伝子治療
著者: 冨田哲也 , 越智隆弘
ページ範囲:P.2180 - P.2183
慢性関節リウマチ(RA)は関節を主座とする慢性炎症性の疾患であるが,その治療については,近年のRAの病因・病態解明の著しい進歩により変化しつつある.非ステロイド系抗炎症剤,遅効性の抗リウマチ薬に加え,最近では抗TNF-α抗体,抗IL-6受容体抗体,抗Fas抗体などの生物製剤の高い有効率が報告されている.さらに,RA病変部位で過剰に発現している炎症関連蛋白を遺伝子レベルで抑制しようとする遺伝子医薬に関する研究も進みつつある.本稿では,筆者らの用いているHVJ-リポソーム法1)を中心にRAに対する遺伝子治療の可能性について述べる.
脳疾患の遺伝子治療
著者: 夏目敦至 , 吉田純
ページ範囲:P.2184 - P.2187
脳の解剖,生理機能の複雑さゆえに,脳疾患には現在の薬物療法,手術療法では不十分であるものが少なくなく,新しい治療法として遺伝子治療が期待されている.ここ10年間の急速な分子生物学の発展は,一部の脳疾患に対する遺伝子治療を現実にした.まず,1992年に悪性脳腫瘍に対してNIH(米国立衛生研究所)でherpes simplex virus-thymidine kinase(HSV-TK)/ganciclovir(GCV)を用いる自殺遺伝子治療が試みられた.脳は以下の特殊性のために,遺伝子治療を有利にも不利にもしている.
脳は血液脳関門により他臓器より隔絶されているclosed cavityであるため,各種遺伝子導入ベクターを脳内に局注してもベクターあるいは導入遺伝子が他臓器に影響を及ぼす可能性が低いことや,脳は分化を終えた非分裂細胞からなる組織であり,レトロウイルスベクター,リポソームなどで遺伝子発現されないことである.本稿では,脳疾患の遺伝子治療に焦点をあてるが,紙面の都合上,限られた疾患の遺伝子治療の概念に触れる.詳細については,文末に取り上げる文献を参照されたい.
腎疾患の遺伝子治療
著者: 冨田奈留也 , 檜垣實男 , 荻原俊男
ページ範囲:P.2188 - P.2190
遺伝子治療とは,遺伝子導入技術に基づき遺伝子を外部より補充することによる治療法を意味する.対象疾患としては単一の遺伝子欠損症が第一に考えられ,腎疾患においてはAlport症候群,多脳胞腎などがそれらの疾患にあてはまることになる.しかし現在のところ,上記2疾患は遺伝子治療の対象とは考えられていない.現状では,対象としては主に糸球体硬化病変を有する疾患があげられ,遺伝子導入が盛んに行われている.糸球体硬化病変の進展をいかにして抑制するかということで,オリゴヌクレオチドや遺伝子の導入によりメサンギウム細胞の増殖や,細胞外マトリックス産生の抑制を目指した治療法が現在の主流となっている.
遺伝子工学のトピックス
核酸医薬の臨床応用
著者: 青木元邦 , 森下竜一 , 檜垣實男 , 荻原俊男
ページ範囲:P.2191 - P.2193
分子生物学の進歩は,従来の医療では治療困難であった疾患に対し遺伝子治療という新しい治療法を与え,その流れは循環器領域にも及びつつある.遺伝子治療の一つの方法は,核酸合成機で作製されるアンチセンスオリゴヌクレオタイド(アンチセンスオリゴ)であり,新しい核酸医薬という薬物療法の概念を作った.この核酸医薬の新しい仲間として,おとり(デコイ)型核酸医薬やリボザイムが開発されてきて注目を集めている.
クローン技術
著者: 小関良宏
ページ範囲:P.2195 - P.2197
「クローン」とは,「1つの生物体から由来する同じ遺伝子情報を持った生物の集団」ということと「それを無限に増やせる」という2つの条件を満たすものと考えることができる.しかし,これまで遺伝子操作において最も重要であった生物体,すなわちin vivoにおける外来DNA断片を含んだ「クローン」の考えかたは,PCR(polymerase chain reaction)法の開発によって大きく変化した.両端の塩基配列がわかっていれば,それらの配列に対するプライマーを用いて,PCRによってその両端に挟まれるDNA領域を無限に増幅することができるようになったためである.またinverse PCRなどを用いれば,その配列の外側部分,すなわちその配列の近傍のDNA領域を増幅することも可能である.すなわち,塩基配列が一部分わかっていれば,生物の助けを借りなくとも,PCR法によってDNA断片の「クローン」はinvitroで手軽に無限に増幅して得られるようになった.このため,塩基配列の相同性をプローブとして,vivoクローンをスクリーニングすることは少なくなりつつある.
ジーンタイトレーション
著者: 松川直道 ,
ページ範囲:P.2198 - P.2201
多くの疾患は,遺伝因子と環境因子が組み合わされて引き起こされる.線維性嚢胞症やDuchenne型筋ジストロフィーなど遺伝因子が単一な疾患もあるが,高血圧,動脈硬化,糖尿病に代表されるように,多くの場合は多因子疾患である.これら多因子疾患の原因遺伝子を決定するには,大きく2つの方法論が考えられる.
一つは疾患モデル動物やヒトの疾患家系において,広くゲノム全体をカバーするマイクロサテライトのような遺伝子マーカーとその表現型との相関をみるか,またあらかじめ候補となる原因遺伝子を定めRFLPを調べるようなanalytic experimentである.この場合,原因候補遺伝子が絞り込まれたとしても,そのlocusとリンクしている他の遺伝因子の影響も受けうるなど,その遺伝子と疾患との直接的な因果関係が証明できない欠点がある.これに対してもう一つの方法論として考えられるのが,特定の遺伝子のみを選択的に不活化することによりその遺伝子機能を調べるsynthetic experimentであり,1990年にSmithiesらのグループが最初に成功1)して以来,ジーンターゲティングとして現在では広く普及している.その利用法もnull変異を作るにとどまらず,遺伝子の置換,挿入など様々な変異を導入することが可能である.
遺伝子工学を利用した医薬品開発
著者: 宮崎洋
ページ範囲:P.2202 - P.2204
バイオテクノロジーの中核をなす遺伝子工学の発達は,医薬品開発に飛躍的な発展をもたらしてきた.なかでも遺伝子工学の利用によって,ヒトの体内に微量しか存在しない蛋白性生理活性物質の遺伝子組み換え型が大量に得られるようになり,その医薬品化が成功したことは特筆に値する.
世界初の組み換え医薬品は,1982年(わが国では1986年)に発売されたインスリンである.その後,成長ホルモン,インターフェロン,組織プラスミノーゲンアクチベーター(TPA:血栓溶解剤),エリスロポエチン(EPO:赤血球増多因子),顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF:好中球増多因子)などの組み換え医薬品が登場し,これまでにわが国で10種類以上もの組み換え医薬品が臨床応用されている(表1).さらに現在,組み換え医薬品の候補となる様々な組み換え蛋白質の薬理効果が動物実験や臨床試験で検討されている.本稿では,これらの中から,血球の分化に重要な役割を担っているEPO,G-CSF,および筆者らが最近クローニングしたトロンボポエチン(TPO:血小板増多因子)を具体的事例としてあげ,遺伝子工学を利用した医薬品開発について概説する.
リボザイム
著者: 菊池洋
ページ範囲:P.2205 - P.2207
分子生物学では遺伝子DNAからそのコピーであるRNAができ,その情報に従って蛋白質ができることが,生きていることの基本であると教えている.多くの遺伝子が調和を保ち,適宜うまく発現されていることにより,生物は快適に時を過ごしていると思われる.しかし,遺伝子が変異を持っていたり,ウイルスなど外来遺伝子に侵入されたりして,この調和が乱されると,時に重篤な疾患となる.この遺伝子発現のステップにかかわる疾患としては,癌,遺伝病,ウイルス疾患などが含まれるが,その多くは根本的な治療法が確立されていない.悪い遺伝子を発現させないようにする一つの方法として,悪いDNAから読まれた悪いRNAを見分けて分解してしまえばよい,という方法が考えられる.そのためには非常に特異性の高いRNA分解酵素が必要とされる.そのようなRNA分解酵素が1980年代に発見され,現在,任意の標的のみを切断するような設計も可能となってきた1).
このRNA分解酵素は「リボザイム(ribozyme)」と呼ばれている.リボザイムは,RNA分解酵素ではあるが,それ自身蛋白質ではなく,RNAからできている.本稿では,リボザイムの発見から,その設計法,および医療への応用研究の現状について紹介したい.
カラーグラフ 感染症グローバリゼーション・8
消化器系寄生原虫性疾患(2)—最近話題になっている消化管原虫症
著者: 西山利正
ページ範囲:P.2223 - P.2226
前回は消化管原虫の中で最も病原性が強く,頻度も高い赤痢アメーバ症について述べたが,今回は最近話題になっている消化器系寄生原虫であるランブル鞭毛虫(Giardia intestinalis;従来G.lambliaと呼ばれていた),クリプトスポリジウム(Cryptosporidium parvum),大腸バランチジウム(Balantidium coli),プラストシスチス・ホミニス(Blastocystis hominis)について述べる.これらの原虫症は,一般的にはそれほど強い症状を呈さないが,後天性免疫不全症候群(AIDS),移植後の免疫抑制剤を投与されているような免疫能の低下しているヒト,小児などに感染した場合に,時に重篤な感染症を起こすことがあるので注意する必要がある.
連載
目でみるトレーニング
ページ範囲:P.2229 - P.2234
図解・病態のメカニズム 腎疾患・11
ACE gene polymorphism
著者: 坪井伸夫 , 吉田裕明
ページ範囲:P.2235 - P.2238
われわれ内科医が日常診療において取り扱う疾患の多くは“common disease”と呼ばれ,様々な遺伝的素因を兼ね備えた個人が様々な環境因子に曝露することによって発症する多因子疾患であると考えられる.すなわち同じ環境因子に曝露しても,疾患を発症する個人と発症しない個人がおり,また同じ疾患に罹患しても,その重症度・予後は個人により大きく異なる.遺伝子多型(gene polymorphism)は,このような疾患と個人差という現象を説明しうる有力なファクターの一つと考えられている.
内科医が知っておきたい小児科学・最近の話題・11
小児科からみた不登校
著者: 衛藤隆
ページ範囲:P.2239 - P.2241
不登校とは?
学校に行かない(あるいは行きたいのだけれども行けない)子どもは,一体いつからいたのだろうか.まだ日本が貧しかった頃には,貧困が理由で学校に行けない子どもたちは存在した.しかし,このような経済的な事由がないにもかかわらず,どうしても学校に行きたくない,行けない,行かないという状況がいつの間にか目立つようになり,登校拒否と称されるようになった.
昭和30年代にこのような名称が広く用いられたかどうか定かではないが,筆者の同学年の仲間にもこの状態に該当する児童・生徒がいたことを記憶している.必ずしも本人が積極的に登校を拒否するという明確な意志を持っているとは限らないので,登校拒否という名称は不適当であるという考えかたが広まり,いつしか不登校という現象を記述する用語が用いられるようになった.
演習 腹部CTの読みかた・6
発熱を主訴とした64歳の女性
著者: 岩田美郎
ページ範囲:P.2242 - P.2250
Case
64歳,女性.主訴:発熱.
9日前より38℃の発熱を生じ悪寒,右季肋部痛を伴っていた.経過観察していたが,1日に1回は高熱を生じ改善傾向のみられないことより近医へ入院した.抗生剤を使用するも解熱しないため,当院に転院となった.
Drug Information 副作用情報・20
薬剤性血液障害(1)—白血球減少・無顆粒球症(その1)
著者: 浜六郎
ページ範囲:P.2253 - P.2256
血液障害,特に無顆粒球症は,生命にかかわる重大な薬剤性反応の1つである.このシリーズでは,すでにH2ブロッカーによる血液障害について解説した.また,クロラムフェニコールによる再生不良性貧血は社会的な問題にもなり,アメリカではこの問題を通じて,血液学者のWintrobeらの提唱で医師会に薬剤性血液障害の登録システムが発足し,薬剤による副作用モニタリングの先駆け的な存在となった.
これから何回かは,薬剤性血液障害について解説する.今回はまず,白血球系の異常について述べたい.
日常診療に必要なHIV感染の知識・5
HIV感染症における日和見感染症の診断・治療・予防
著者: 安岡彰
ページ範囲:P.2257 - P.2260
HIV感染症の治療においては,HIVに対する抗ウイルス治療と,日和見感染/悪性腫瘍の治療が,車の両輪のごとく並立して重要である.HIV陽性者にみられる日和見感染症は,日常臨床でよくみられる感染症とは病原体のスペクトラムや病態が大きく異なることから,大胆な視点の切り替えが必要である.表1にAIDSの診断基準にリストされている病原体をあげたが,単純ヘルペス,一般細菌(肺炎球菌,インフルエンザ菌など),結核菌,カンジダ以外は,一般臨床上は比較的稀な病原体である.これらの疾患が患者の免疫状態,一般的には末梢血CD4陽性細胞数に応じて,高頻度に繰り返し発症してくる.
CHEC-TIE—よい医師—患者関係づくりのために・11
末期の患者が診療への疑問や不安を表明したとき
著者: 箕輪良行 , 柏井昭良 , 竹中直美
ページ範囲:P.2262 - P.2263
症例 鎮痛と減黄のほかに有効な治療法がない再発胃癌例
49歳のカトウさんは進行性胃癌の切除術を受けて約1年後に,肝門部リンパ節の局所再発を起こした.軽度の背部痛を自覚し始めて,CA19-9の上昇傾向があり,CTで診断された.病気については入院・手術時の主治医から告知されていた.子供2人で4人暮らし,会社の重役という立場もあり,少しずつ身辺整理を始めていた.
次第に増強してきた背部痛にはボルタレン坐薬®が有効で,除痛して眠れた.2カ月後に黄疸が出現した.肝門部リンパ節の腫大による閉塞性障害で,入院してPTCDを行った.その後胆道内にステントを留置して内瘻化したところ,奏功してデータもすべて正常化した.退院の目処もたった.
医道そぞろ歩き—医学史の視点から・31
心電図学の創始者エイントーフェン
著者: 二宮陸雄
ページ範囲:P.2264 - P.2265
心臓の搏動に伴う電気的変化に気づき,これを記録する試みは19世紀の中頃に始められた.1843年にはイタリアのマッテウッチがハトの心臓の電位変化を観察し,ドイツのケーリケルらがカエルの神経筋肉標本を心臓の上に置くと収縮することを発見している.1878年には,イギリスで毛細管電流計を使って心臓の活動電流が記録されているし,1887年には,ロンドンでワラーが自宅に研究室を作って体表の電極から心臓の活動電流を記録した.しかし,当時使われていた毛細管(水銀)電流計は精度が低く,心臓の活動電流以外の変化も加わって,計算補正を行っても真の心電図を得ることは難しかった.
エイントーフェンがユトレヒト大学で医学の学位を得たのはワラーの研究が始まった頃である.父はインドネシア派遣軍の医師で,現地人との間に4人の子をもうけ,妻の死後オランダ女性と結婚して,6人の子が生まれた.その1人がエイントーフェンである.やがて母は子供たちを連れて帰国し,エイントーフェンはユトレヒト大学で医学を学んだ.この入学資格に必要なギリシア,ラテン語の学習はエイントーフェンに終生にわたる深い西洋古典への関心を植えつけ,折りにふれて古典の1節を暗唱してみせたという.冗談が好きで,率直で真摯な人であった.
medicina Conference・23
上腹部痛と嘔気を訴えた24歳の女性
著者: 雨森正記 , 川上恵基 , 三宅直樹 , 井上雅史 , 福田勝美 , 松本恒司 , 山内宏哲 , 太田敬治 , 田村忠雄
ページ範囲:P.2266 - P.2275
症例=24歳,女性,事務員.
主訴:上腹部痛,嘔気.
既往歴:14歳時に十二指腸潰瘍,22歳時に急性虫垂炎,多発性卵巣嚢腫.
基本情報
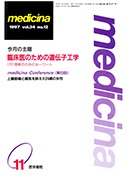
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
