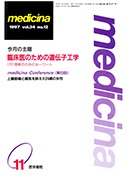文献詳細
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
疾患治療への遺伝子工学の応用:遺伝子治療に向けて 日本での現状
文献概要
遺伝子工学の進歩は,分子病態の解明や遺伝子診断にとどまらず,その技術を治療にまで活かそうという遺伝子治療の発想を生み出してきた.本格的な遺伝子治療は,1989年の遺伝子マーキング臨床研究に引き続き,アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症を対象として1990年9月に米国NIHでスタートした.対象疾患はこのような難治性の遺伝性疾患(そのなかでも当面はシンプルな単一遺伝子病が対象)だけでなく,様々なアイデアのもとに遺伝子操作を利用した治療法が工夫され,癌やエイズなどの生命が脅かされる疾患も含められるようになった.
それに伴い,遺伝子治療に対する社会の関心と期待も一段と高まってきている.ここ数年の間に予想を超える勢いで臨床研究が進められ,何らかの目的で遺伝子の投与を受けた患者数は1995年12月の調査では1,062例,1996年6月には1,537例,同年12月には2,103例に急増してきている1).国別では米国がやはり圧倒的に多く,そのうち1,700例以上を占めている.対象疾患は癌が1,446例(68%)で一番多く,次いでHIV感染症390例(18%),嚢胞性線維症176例(8%)などとなっている.なお,表1に米国の臨床プロトコールを示す2).
それに伴い,遺伝子治療に対する社会の関心と期待も一段と高まってきている.ここ数年の間に予想を超える勢いで臨床研究が進められ,何らかの目的で遺伝子の投与を受けた患者数は1995年12月の調査では1,062例,1996年6月には1,537例,同年12月には2,103例に急増してきている1).国別では米国がやはり圧倒的に多く,そのうち1,700例以上を占めている.対象疾患は癌が1,446例(68%)で一番多く,次いでHIV感染症390例(18%),嚢胞性線維症176例(8%)などとなっている.なお,表1に米国の臨床プロトコールを示す2).
掲載誌情報