あ
悪性中皮腫…167
雑誌目次
medicina41巻12号
2004年11月発行
雑誌目次
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
総論
はじめに
著者: 黒崎喜久
ページ範囲:P.6 - P.7
放射線関連の画像診断というと,単純X線写真,CT,MR,超音波,核医学検査,などいろいろなmodalityがある.それらのなかで単純撮影をどのように位置付けているかは医師の世代によって異なるようである.画像診断を専門とする放射線科医を考えてみても,単純X線写真に対する姿勢は2大別される.一つは単純X線写真の意義を熱く語るタイプである.このタイプは一般にCTが導入される前に卒後研修を受けている年配者である.単純X線写真の意義を強調するあまり若手放射線科医師に煙たがられることもある.もう一つのタイプはCT,MR,超音波でトレーニングを受けた世代であり,単純X線写真への関心は決して高いとはいえない.放射線科以外の診療科の若手の医師も後者のタイプに属する.
特殊な医療機関を除けば,普段実施されている画像診断検査のなかで圧倒的に多いのは依然として単純X線写真である.このように日常臨床に定着している単純X線写真が正しく活用されているかというと,疑問もある.検査伝票を書けば,予約なしで直ちに施行される簡便かつ安価な検査であるので,「単純X線写真で何が見たいのか?」という明確な目的を確認せずに,習慣的に単純X線写真のオーダーが行われていないか? 撮影された単純X線写真を丹念に読影して,その所見を誰が見てもわかるように診療録に記録しているか? 単純X線写真の結果が次に行うべき画像検査の選択や治療方針の決定などに適切に反映されているか? 読者には是非これらの点を一度チェックしてほしい.
CR(computed radiography)画像―CR画像を活用するための基礎知識
著者: 堂領和彦
ページ範囲:P.8 - P.15
CR画像の原理・基礎
1. デジタルとアナログ
従来,一般撮影領域における診断は,アナログフィルムが主流であった.近年,デジタル技術の進歩に伴い,CR(computed radiography)が主流となりつつある.そこで,まずアナログ画像およびデジタル画像の違いについて述べる.
アナログ画像とは,図1(a)に示すように空間的に連続的なデータ(光の強さ)をいう.デジタル画像とは,図1(b)に示すように連続的なデータに区切り,区切られた範囲のデータ値を飛び飛びの数値列で表現することである.データを区切ることをサンプリングあるいは標本化といい,数値列で表現することを量子化という.デジタル画像を評価する際,できるだけオリジナルに近い画像に近づけるには,図1(a,b)の比較からも理解できるように空間をできるだけ細かく区切り(画素サイズを小さくする),データ値を細かくきざめばよいことになる.この区切り方でデジタルデータの空間分解能と濃度分解能が決定する.デジタル化レベルを粗くとりすぎると図2のようにモザイク画像となったり,等高線が出る画像となってしまう.しかし,むやみに細分化することは,データ量が多くなるだけで経済的,運用的に非効率となる.
頭部・頭頸部
頭蓋骨―MR・CT時代に知っておくべき単純X線撮影所見
著者: 小野由子 , 西井規子 , 阿部香代子
ページ範囲:P.18 - P.25
正常解剖と撮影のコツ
頭部単純X線撮影は,一昔前まで頭部の画像診断のなかで,まず最初の検査としてさまざまな病態を知る手段であった.MR/CTが一般的な検査法となり,頭蓋内の病変が容易に捉えられるようになって頭部単純X線写真のもつ意味が大きく変わってきた.単純X線写真の利用は,一つは外傷での骨折の診断を別とすれば,少なくとも単純X線撮影で病変の有無を評価するのではなく,骨変化や石灰化などから病変の性質や疾患の鑑別に利用することである.もう一つの大事な点は,CTで有用な情報を得るためのスライス断面の決定に利用することである.MR/CTとも,とにかく撮像すれば何らかの重要な情報は得られるが,手術あるいは内科的治療のために,病変の部位・範囲・性質をすべて表し,必要な情報を一度に全部引き出すことが一番効果的,経済的な方法である.そのために,特にCTでのsingle sliceの場合の撮像面の決定は単純撮影であるscout viewから行うわけであるから,頭蓋から見た脳構造の位置的関係を十分に理解しておくことがスライス像を理解することになる.
MR・CTに対しての頭部単純X線像は正面側面だけでなく,場合によってはStenvers, Schüllerその他,従来からの撮影法が有用あるいは必要なことがあるが,ここでは誌面の関係から側面(図1),正面(図2)を基本として,Towne, Waterなどとりつきやすい画像のみに限って画像を供覧する.
側頭骨―CT・MRI時代における単純X線写真の意義
著者: 小玉隆男
ページ範囲:P.26 - P.32
単純X線撮影の意義
側頭骨の画像診断を扱った最近の代表的なテキストでは,単純X線写真はほとんど取り上げられておらず,CTやMRIを中心とした画像診断プロトコールが示されているものが多い1).非常に微小な構造の診断を要求されるこの領域において,単純X線撮影の意義が乏しくなったことを示していると思われる.ただ,一部の総説では,スクリーニング的な目的での単純X線撮影の必要性が触れられている.わが国においても,耳科的疾患の診断におけるfirst stepの一つとして,多くの施設で単純X線写真が撮られている現状もある.側頭骨の単純X線撮影がもつ意義は,施設によってある程度異なると思われる.CTやMRIのない病院や医院では,大きな異常を除外する目的で単純写真が撮像されていることが少なくないようである.一方,CTやMRIが可能な施設においても,少なからず単純X線写真が撮像されている.症状や理学的所見からCTやMRIによる評価が必要と考えられる,あるいはこれらの検査が予定されている患者に対して,とりあえず単純写真を撮っておくという考え方には,医療経済やX線被曝の観点から問題があると考えているが,単純X線写真の所見もふまえてCTやMRIの適否を決定するということもあるようだ.
単純X線撮影や断層撮影がCT以上に有用な状況としては,人工内耳や人工中耳の術中・術後評価が挙げられる.実効スライス厚を薄くできるMDCTの普及によってかなり改善されたとはいえ,CTにおける金属アーチファクトは一つの問題である(後述).また,CTまでは必要としないが乳突蜂巣の発達・含気などを評価しておきたいという状況もある.子どもの急性・滲出性中耳炎の予後判定,鼓膜チューブ留置の期間,鼓膜穿孔のない伝音・混合難聴耳の中耳炎の関与推定,急性中耳炎に伴う合併症の可能性推定などが挙げられる.
副鼻腔―単純X線検査の適応と限界
著者: 川波哲 , 青木隆敏 , 興梠征典
ページ範囲:P.33 - P.41
単純X線撮影の意義
CT/MRIの普及した近年,副鼻腔領域における単純X線検査の精査的役割は従来と比べて減じている.しかし,その長い歴史と簡便性のため,単純X線検査は診断の出発点として現在も日常的に施行され,まだまだ臨床家にとっても馴染みが深い.副鼻腔領域の単純X線検査では,X線束の方向や骨同士の重なりに伴って生じる死角を減じるために複数方向の撮影を組み合わせるが,より詳細な検討が必要なときには,さらに次の診断ステップのCT/MRIへ進むべきである.適応や限界を踏まえて単純X線検査を適切に利用し,CT/MRIと上手に使い分けることは,無駄な検査を減らし,被曝低減や経済的利点にもつながるものと思われる.
撮影のコツ
副鼻腔の単純X線検査には数多くの撮影方法があるが,通常はWaters撮影とCaldwell撮影もしくは側面撮影を撮影し,場合によってその他の撮像(軸位撮影,Rhese撮影,眼窩撮影,Towne撮影など)を追加する.重要な所見の一つである鏡面形成(air-fluid level)を見逃さないために,副鼻腔の単純X線検査は立位または坐位で行うのが好ましい.
咽頭・喉頭―CT・MRIの時代での意義
著者: 中山圭子 , 赤土みゆき , 井上佑一
ページ範囲:P.42 - P.48
単純X線写真撮影の意義
咽頭・喉頭領域では現在CTやMRIが中心で,一般に単純X線写真の役割はきわめて少なくなっているのが現状である.しかしながら,迅速な撮影が要求される救急領域や小児では単純X線写真が行われることが多い.アデノイドのサイズの評価,異物,クループや急性喉頭蓋炎,気管切開後のカニューレの位置の確認で単純X線撮影が使用されている.また,頸椎や頭部,胸部の単純X線写真で偶然,咽頭・喉頭の病変が発見されることも少なくない.これらの点から,咽頭・喉頭の単純X線写真の知識を習得しておくことは重要である.
撮影のコツ
咽頭・喉頭領域は,内腔の空気と軟部組織のコントラストが明瞭になるように撮影または処理することが重要である.CRがなかった頃は低電圧で焦点を縮小させたり,前頸部にウェッジ用のフィルターをのせて軟部の厚さを均一にして撮影していた.頸椎の単純X線写真では通常,立位で撮影するが,咽頭・喉頭の単純X線写真では体動の影響を受けやすいので一般に臥位で撮影する.
胸部
胸部単純X線撮影―正常解剖と読影のコツ
著者: 三角茂樹 , 庄司友和 , 佐藤雅史
ページ範囲:P.50 - P.60
胸部単純X線撮影の意義
胸部単純撮影ほど疾患のスクリーニング検査に優れている画像診断法はない.簡便かつ安価で,読影の処理能力にもずば抜けている.そのためわが国においては,医療施設で頻用されるのみならず,学生の定期健康診断にも胸部撮影が行われるほど普及している.胸部CTの出現により,その診断精度に関しての限界も囁かれてはいるものの,その簡便性において,当分の間は臨床の現場で見捨てられることはないであろう.また医療被曝の面からみても,他の放射線検査とは比較にならないほど微量であり,胸部単純写真の被曝線量は自然放射能による年間被曝量の数分の一とされている.この点からも,放射線画像検査の唯一の欠点である放射線被曝量は,胸部写真から得られる情報と比較すれば全く問題にならないといえる.空気という気体で満たされ十分に膨らんだ肺臓内に起きる多くの病変は,炎症であれ腫瘍であれ,正常肺との強いコントラスト差により,前処置なしに,容易に異常陰影として描出されてくる.そのため,空気(陰性造影剤)で満たされた肺臓は,カルシウムなど(陽性造影剤)で構成される骨組織とともに,単純撮影には理想的な臓器といえる.
わが国で広く行われている胸部検診を考えればわかるように,胸部単純撮影は老若年者を問わず健康管理にはきわめて有用な検査法である.特に結核の蔓延していた時期に,わが国独自で開発した間接撮影装置による胸部検診が発達している.このロールフィルムを使用した撮影装置は移動可能の組立式装置や大型自動車にも設置可能なため,被検者を移動することなしに効率良く多数の撮影を短時間のうちに処理できる.そして胸部の間接写真は,直接撮影と比べてその診断能において決して劣るものではなく,特に処理能力において,ロール状に巻かれていたフィルムを観察装置で巻取りながらの読影は,短時間で読影処理が可能な点からも検診には大変に有用な診断モダリティである.
無気肺―肺葉性無気肺を中心に
著者: 芦澤和人 , 上谷雅孝 , 林邦昭
ページ範囲:P.62 - P.71
典型的な症例
58歳,男性,扁平上皮癌.
正面像(a)で,左上肺野内側に肺野濃度の上昇がみられるが,その外側の境界は不鮮明でありfade outしたような印象を受ける(後述する右上葉無気肺のX線像とは異なることに注目).肺門部陰影や大動脈辺縁はやや不鮮明であり(シルエットサイン陽性),横隔膜の挙上もみられる.側面像(b)では,大葉間裂は前方に偏位し前胸壁に対して平行である(矢印).
経験の少ない医師にとっては,正面像のみでは一見肺炎と誤診される可能性がある(実際,前医では肺炎の診断で治療されていたようである).側面像で,無気肺のX線所見のなかで最も重要な葉間裂の偏位を確認することで,左上葉無気肺と診断可能である.なお,正面像で無気肺部外側の境界が不鮮明なのは,偏位した葉間裂がX線束に対して斜方向に走行するためであることがCTで理解される(c,矢頭).
肺水腫―画像所見から読みとる肺の循環動態
著者: 酒井文和
ページ範囲:P.72 - P.78
典型的な症例
慢性腎不全の増悪,呼吸困難,起座呼吸にて入院.立位胸部正面像では,心陰影の拡大(黒矢印)と上肺野の血管陰影の増強,右優位の肺門部近傍を中心とする浸潤影やすりガラス陰影(白矢印)がみられ,いわゆる蝶形分布を示している.このために肺門部の血管陰影の輪郭は不鮮明化している(hilar haze).また両側胸水による肋骨横隔膜角の鈍化(黒矢頭)と上下葉間の葉間胸水による陰影(白矢頭)がみられる.またいわゆるvascular pedicle width(両端矢印)は増大し,循環血液量の増加を示している.典型的なvolume overloadおよび心不全による心原性肺水腫の所見である.
肺水腫の診療における画像診断の役割は,その検出,肺水腫の病因の鑑別,肺水腫の程度の評価,経過や治療効果の評価,他疾患との鑑別などである.このためには,患者の臨床症状をよく把握することは必須である.またICUなどでは,ポータブル撮影などの条件の悪い単純撮影のみでの診断を迫られることも多く,ポータブル撮影写真によく慣れる必要があるとともに,単純撮影の限界もわきまえなければならない.さらにその病因の診断にあたっては,循環動態を把握することは重要であり,画像所見からもその症例の循環動態を表す指標を読みとり,肺水腫発生の病態生理まで遡って画像所見を解釈することが必要になる.
胸水―的確に胸部写真から胸水貯留を診断するコツ
著者: 小林健
ページ範囲:P.80 - P.87
典型的な症例
正面像で,右下肺野の肋骨横隔膜角(costophrenic angle)の鈍化を認め,外側は上方へ弓状に滑らかに先細りしていく.これは三日月兆候(meniscus appearance)と呼ばれ,典型的な胸水貯留を示す単純X線写真の所見として広く知られている.胸水貯留では肺との境界は明瞭で尾側は均一な濃度となり,本来横隔膜下に透見できる右下葉の血管が全く見ることができない.小葉間裂も平滑に肥厚し三日月兆候と連続している.小葉間裂にも胸水貯留が指摘可能である.右下肺野の透過性が低下している所見は,大葉間裂や背側に貯留した胸水を見ていると考えられる.
胸水貯留はさまざまな原因で胸腔内に液体貯留をきたすものであるが,少量の場合には聴診や打診では発見できず,胸部単純X線写真は胸水の診断にきわめて有用である.また,胸水量の推定,治療などに伴う胸水の変化の観察にも簡便で有力な診断法となる.
しかし,ある程度以上の量の胸水で典型的な画像所見をとる場合には判断に困ることはないと思われるが,非典型的な画像所見をとる場合や少量の胸水を診断する場合,多量の胸水と無気肺の鑑別には注意を要する.本稿では,以上の点を中心に胸水の単純X線写真について述べる.
気胸―見落とし・誤診を減らす撮影法と読影
著者: 小野修一
ページ範囲:P.88 - P.96
典型的な症例
症例1:27歳,男性.
初発症状:突然の呼吸困難,背部痛.
立位,吸気位の胸部単純X線写真を提示した(図1).気胸は,左側肺野末梢の空気濃度の陰影としてみられる.同部は,肺野血管影の欠如,透過性の亢進を呈し,やや縮んだ肺の濃度はわずかに高く,気胸との間に臓側胸膜で縁取られた円弧状の境界面を形成している.一般に元々低い空気濃度の肺とより低い空気濃度の気胸であるので,少量の気胸を濃度の差として捉えることは難しいことが多く,この円弧状陰影と肺野血管影の欠如が有力な情報を与える.本症例では,肺野縦隔側にも気胸があり,肺野と境界面を形成,中央陰影の外側にmedial stripe sign(90ページ,「知っておきたいサイン」参照)を形成している.
気胸は,種々の原因により胸膜腔に空気が貯留した状態を指す.全く無症状のものから非常に重篤で予後不良の経過をたどるものまであり,急速に進行するものもあるため,初診時の画像診断,特に単純X線写真の役割は重要である.多量の気胸はまず見落とされることはないが,比較的少量の場合,時に診断が難しく見落とされることがある.本稿は,気胸の診断で,見落とし,誤診を減らすための撮影法と,その画像所見,診断・治療に必要な情報を得るための臨床的事項について概説する.
感染性肺炎―単純X線写真でどこまで診断に近づけるか
著者: 阿部克己 , 小須田茂 , 鎌田憲子 , 酒井文和
ページ範囲:P.98 - P.109
典型的な症例
胸部単純X線写真正面像で,心陰影に重なり左肺下葉に区域性に分布する境界不鮮明,内部不均一な浸潤影とその周囲に斑状影が認められる(矢印).浸潤影は斑状影が融合したものと想像される.この症例は,ブドウ球菌による市中感染性の気管支肺炎であるが,咳嗽,発熱,血液検査から呼吸器感染症が示唆され,これに単純X線写真での病変の分布が区域性であること,小葉大の斑状影とそれらが融合したと考えられる内部不均一な浸潤影から気管支肺炎と診断できるが,このパターンを示す他の起因微生物の鑑別は画像所見のみでは困難である.この症例は,たまたまCTが行われているが,この症例も含め一般に市中肺炎ではCTの胸部単純写真に付加する情報はない.
胸部単純X線写真は,症状や検査所見とともに肺炎の有無の診断に用いられる.肺の感染症の起因微生物は細菌,ウイルス,結核,真菌,リケッチア,クラミジア,原虫などがあり,これらの感染の強さや宿主の免疫状態,治療内容により同じ微生物による感染でも異なった病態をとる.一般にこれらの起因微生物の同定は,症状や検査所見および単純X線写真からは困難で,治療は細菌学的あるいは免疫学的検査による起因微生物の同定に基づいた抗菌薬の選択が最善であるが,実際には困難なことも多く,起因微生物不明のまま経験的に行われること(エンピリック治療)も多い.日本呼吸器学会の肺炎診療のガイドライン(以下,ガイドライン)1)では,肺炎を症状や検査所見および単純X線写真により重症度別に分類し,それぞれの起因微生物をカバーする抗菌薬を選択するとしている.しかし,臨床の場では抗菌薬の有効な選択のために,画像から考えられる起因微生物が求められることもある.
結核・非結核性抗酸菌症―知っておくべき画像のポイント
著者: 高橋雅士 , 新田哲久 , 村田喜代史
ページ範囲:P.110 - P.116
典型的な症例
右上肺野外側に,浸潤影,すりガラス陰影を認める.陰影の内部には高濃度の粒状陰影が散在する(長い矢印).また空洞性変化を疑わせる透亮像(短い矢印)を包含する.肺門に連続する線状陰影を認め(矢頭),気管支壁の肥厚が疑われる.陰影は,通常の肺炎像に比較すると,陰影の強弱が多彩であり,また基本的にコントラストの高い“かたい”陰影である.これらのコントラストの高い陰影は,乾酪壊死物質の腔内貯留という二次結核の基本的病理像に一致する典型的な胸部単純X線写真像である.肺胞腔,肺胞管,細気管支を高吸収の乾酪壊死物質が充満し,周囲肺野とは比較的,境界が鮮明な高濃度の陰影を形成する.拡がりは,肺胞管レベルから小葉レベルまで多彩であり,これらが混在して,病変の陰影の強弱が多彩となる.空洞や気管支壁肥厚も結核を強く疑わせる所見である.
CT(b)では,小葉内で分岐する高コントラストの微細な分岐線状陰影(白矢印),粒状陰影(矢印),空洞性病変,など,多彩な病変を認める.
1997年,日本の結核の新登録患者は42,715人と38年ぶりに上昇に転じ,罹患率も10万対33.9と43年ぶりに上昇を示したことを受けて,厚生労働省が結核の非常事態宣言を出したことは記憶に新しい.その後数年は,これらの値は再び下降傾向にあるが,日本の結核罹患率(2002年)は,いまだに対10万人あたり25.8人であり,これは他の欧米先進国の4.5~10.1人と比べると,明らかに多い数値である.また,塗抹陽性患者の全結核患者における割合は,45.1%ときわめて高い割合を示している事実に対しても,われわれは認識を新たにする必要がある.一方,人口の高齢化,疾病構造の変化による潜在的な免疫不全患者の増加,外国人流入者の増加などの社会的要因が加わり,結核症は日常診療において必ず鑑別診断に含まれる感染症の一つになっている.結核の診断は画像診断でなされるものではなく,患者の自他覚所見やその他の種々の臨床所見を総合して初めて,その疑いが浮上するものである.しかし,結核を主治医が疑うようになる契機として,結核のいくつかの特徴的な画像を知っておくことは重要であり,さらに胸部画像診断の出発点でもある胸部単純X線写真におけるそれらの特徴を知っておくことは有益である.非結核性抗酸菌は,抗酸菌症の全体のなかでの施設別の割合では,結核療養所よりも一般病院で菌が分離される比率が高いことが知られており,一般病院でより問題となりうる抗酸菌症である.結核症例の画像との類似点,相違点を簡単に述べる.
肺結節と間違えやすい正常構造や病変―偽病変を作らないために
著者: 古村慎二 , 黒崎喜久
ページ範囲:P.118 - P.123
典型的な症例
正面像で,円形の結節(図a矢印)が右鎖骨のすぐ足側に見える.これに相当する陰影は側面像で肺内にはない.正面像を見直すと,この陰影は右側の第1肋骨と肋軟骨の結合部に重なって下方に突出している.側面像では,前胸壁から肺に向かって突出する半球状の陰影(図b矢印)がある.
この陰影の本体は第1肋軟骨の骨化である.第1肋骨との結合部の肋軟骨の骨化が強いと,この症例のように肺結節と紛らわしいことがある.第1肋軟骨との位置関係に気付けば,診断は正面像のみで容易である.ただし,右上葉の結節が正面像でこの部位にほぼ重なることもあるので,疑問が残る場合には側面像を追加して両者の鑑別を行うべきである.
肺癌の死亡者数は増加の一途をたどり,1998年には男女合わせた全体で癌死の第1位となった.撮影目的の如何を問わず,胸部単純X線写真の読影では肺癌を疑う陰影がないかどうか注意深い読影が要求される.各診療科の医師が胸部単純X線写真で肺結節を疑って胸部CT検査を依頼する症例のなかには,胸部単純X線写真のみで肺腫瘍以外のものであると診断できるものもある.不必要な放射線被曝を避ける観点からも,胸部単純X線写真で肺結節と間違えやすい病変や正常構造を理解しておくことは重要である.
肺癌―肺癌にみられやすい単純X線所見について
著者: 立石宇貴秀 , 楠本昌彦 , 荒井保明
ページ範囲:P.124 - P.130
典型的な症例
症例:77歳女性,検診で胸部異常陰影を指摘された.
所見:単純X線の正面像(図1a)で右中肺野にスピクラを伴う辺縁不明瞭な結節陰影を認める.肺門部,縦隔にリンパ節腫脹はみられない.また,胸水は認められない.
解説:典型的な高分化肺腺癌の所見である.スピクラ(図1b:拡大像,図1c:CT像)は棘状の辺縁を特徴づける所見で,肺実質内への浸潤か随伴する線維化を示す.結節陰影の辺縁は不整,分葉状,不明瞭,棘状などと表現される.これらの所見は確定診断の根拠になるほど信頼性はないが,悪性を示唆する所見となりうる.右上葉切除が施行され,中心に虚脱性線維性瘢痕を有する肺胞置換性増殖を示す高分化肺腺癌で,気管支を巻き込んでいた.
肺癌における単純X線の読影は,多彩な陰影パターンの定義と非特異的所見により複雑な作業といえる.本稿では肺癌にみられる頻度の高い代表的な単純X線パターンについて,病理学的背景を踏まえいっそうわかりやすく呈示することに努めた.
良性肺腫瘍と腫瘍類似疾患―各良性疾患の特徴
著者: 藤本公則
ページ範囲:P.132 - P.142
典型的な症例
症例は30歳,女性.検診時の胸部単純X線写真正面像で,右下肺野の上部に約3cm大の円形不透過影(腫瘤影)を認めた(図a矢印).腫瘤影の辺縁は平滑,周囲肺野との境界は明瞭で,血管影の集束や連続性は認めない.内部のX線透過性は,中心部より辺縁寄りがやや良好で,明らかな石灰化影は指摘できない.CTでは,中葉に辺縁平滑,境界明瞭な腫瘤影がみられる.内部のX線吸収値は不均等で,高吸収値を示す微細石灰化が介在し,辺縁部には脂肪を示唆する低吸収域(図b矢印)も混在している.以上より,過誤腫と思われたが,増大傾向にあったため腫瘤摘出術を施行し,chondromatous hamartomaの病理診断を得た.
比較的若い成人女性にみられた増大傾向を有する,辺縁平滑,境界明瞭な円形陰影で,単純X線写真からは過誤腫,硬化性血管腫のような良性結節が考えられた.この症例のように臨床的事項や単純X線写真で,悪性より良性腫瘍を考えさせる所見(後述:「読影のポイント」参照)があるが,各所見は悪性腫瘍でもみられることがあるため,これらを組み合わせて鑑別の一助とせねばならない.また,悪性腫瘍のみならず,各良性疾患の特徴を知っておく必要がある.
良性肺腫瘍の肺腫瘍全体に占める割合は2~7%とされるが,この頻度の差は,その定義の違いによると思われる.また,腫瘍類似疾患となると,定義は曖昧で,多彩な病態,病変が含まれることにもなる.そこで,本稿では,国際保健機関(WHO)による肺・胸膜腫瘍の組織分類に基づいて,肺良性腫瘍および腫瘍類似疾患を抜粋して記載した(表1).各疾患とも稀であるため,このなかから比較的遭遇する可能性の高い疾患,結節影ないし腫瘤影を形成する疾患および特徴的な画像を呈する疾患を選び,胸部単純X線写真,X線CT像を主体に呈示し解説する.
縦隔腫瘍―単純X線写真で絞る鑑別診断
著者: 高橋直幹 , 藪内英剛 , 本田浩
ページ範囲:P.144 - P.149
典型的な症例
胸部単純X線写真正面像(a)で肺門部のレベルで,心陰影左側に接した腫瘤影を認める(黒矢印).境界は明瞭で,心陰影と上下端でなだらかに連続している.また,下行大動脈とのシルエット・サインは陰性で,傍脊椎線との連続性もないので,前縦隔由来の腫瘤と考えられる.また,左中肺野には内側は境界明瞭で,外側が境界不明瞭な腫瘤影がみられる(白矢印).また,左横隔膜は波状になっており(矢頭),いずれも胸膜腫瘤も疑われる.
側面像(b)で前縦隔に濃度上昇がみられ,腫瘤が前縦隔に位置することが確認できる.また,横隔膜は正面像同様波状になっている(矢頭).
胸膜播種を伴った前縦隔腫瘤の所見であり,胸腺腫や胸腺癌が第一に考えられる.鑑別としては悪性胚細胞腫や肺癌なども挙げられる.
びまん性肺疾患―パターン分類によるアプローチ
著者: 審良正則
ページ範囲:P.150 - P.157
典型的な症例
症例1:特発性間質性肺炎(usual interstitial pneumonia:UIP).69歳男性.1年前より労作時息切れ,乾性咳が出現し,徐々に増強してきた.胸部単純X線像では全肺野にわたって粗い網目状陰影が広がっているが,分布は下肺末梢優位である.肺門陰影と縦隔陰影の輪郭はきわめて不鮮明で,肋骨横隔膜角の輪郭も不鮮明である.下肺野では直径3~5mmで,壁の厚さ1~2mmの輪状影が入り混じって蜂の巣のような陰影を呈している.いわゆる蜂窩状陰影である.下肺の容積は減少し,上肺野ではブラもみられる.胸部CTでは蜂窩肺が明瞭で牽引性気管支拡張像もみられる. 症例2:BOOP(bronchiolitis obliterans organizing pneumonia).66歳女性.2カ月前より微熱が出現し,胸部単純X線上異常影が認められた.各種抗生物質使用にても改善せず,陰影に移動性が認められた.胸部単純X線像では両側肺野末梢性に均等な浸潤影が認められる.陰影内に空洞や気管支透亮像は認められない.胸水やリンパ節腫大もみられない.胸部CTでは胸膜下に非区域性の浸潤影とすりガラス様陰影が認められる.両側性,肺末梢性,移動性の肺胞性陰影で,臨床所見とあわせると好酸球性肺炎とBOOPが最も考えられる.両者は画像上鑑別困難である.Churg-Strauss syndromeも画像所見は一致しているが,末梢血好酸球増多と喘息症状はみられなかった.X線像からは肺胞上皮癌やリンパ腫も考えられるが,臨床経過(移動性陰影)からは否定的である.肺炎や肺結核,肺梗塞,肺胞出血,Wegener肉芽腫症なども鑑別に挙げられるが,臨床所見と陰影の移動性から考えにくい.肺吸虫症でも末梢性の移動性浸潤影がみられることがある.
びまん性肺疾患の画像診断にHRCTは非常に有用であるが,その画像診断の第一歩は胸部単純X線写真である.びまん性肺疾患の胸部単純X線写真の読影には,いわゆる肺胞性パターンと間質性パターンの2つの基本的パターンに分けて読影することが有用である.これらのパターンに病変分布のパターンと急性か慢性かの経過を加えることによって鑑別診断を絞ることができる.
塵肺―珪肺とアスベスト肺
著者: 荒川浩明
ページ範囲:P.158 - P.168
典型的な症例
【症例1】 64歳男性.25年間,削岩夫をしていた.患者はすでに退職している.
胸部単純X線写真(図1)では,両側肺野に多数の粒状影を認める.粒は上肺野に多く,癒合傾向を示している.比較的均一な大きさと考えられる.特に密度の高い部分では,大きな塊状巣を形成しているのがわかる(矢印).これが塵肺の大陰影,英語圏では,progressive massive fibrosis(PMF)と呼ばれるもので,塵肺の線維化巣である.もう一つ,両側肺門が腫大しており,いわゆるBHL (bilateral hilar lymphadenopathy)といわれる所見を呈している.
【症例2】 66歳男性.解体業に従事していた.患者はすでに退職しており,特に症状もない.
胸部単純X線写真(図2a)では一見問題ないように見える.しかし,両側の側胸部,肩甲骨が重なるあたりなどに肋骨陰影の内側に線状の陰影が認められる(矢印).さらに,肺野の陰影が所々増強しているように感じられる.こうした一連の所見は胸膜の肥厚があることを意味する.
CT写真の縦隔条件(図2b)では,両側の胸膜に沿ってうっすらと肥厚が認められる(矢印).一部で石灰化が認められるので,単純X線写真よりわかりやすい.
これは胸膜プラークの所見であり,両側性であること,職業上アスベスト曝露の可能性のある職業に従事していたことなどから,アスベストプラークと考えられる.
もし,片側にしかこうした所見がなければ結核性胸膜炎の跡などが考えられる.
塵肺の診断は,①しかるべき粉塵曝露歴,②胸部単純X線写真での塵肺陰影の存在,の二点が必須項目である.病理学的な塵肺所見の有無は問われない.したがって,塵肺の診断には胸部単純X線写真が不可欠である.
胸部外傷―胸部外傷患者の単純撮影をどう読影するか~ピットフォールを含めて
著者: 水沼仁孝 , 加藤弘毅 , 利安隆史
ページ範囲:P.170 - P.177
典型的な症例
症例は65歳男性,2004/04/20 11:30受傷の交通外傷.
12:34撮影の胸部単純X線写真では,左肺野のX線透過性の低下を認めるが左肺の虚脱はない.よくみると,左第4肋骨以下の肋骨外側に多発骨折を認める.左肺野のX線透過性は,この多発肋骨骨折による血胸であることがわかる.
胸部外傷で最も多いのが肋骨骨折である.これは骨折時に肺や肋間動静脈を損傷して気胸や血気胸を起こしやすく,また,肺挫傷や肺裂傷,時に心損傷や肝損傷も引き起こす.一つの肋骨が2カ所以上折れ,それが多発する場合には奇異呼吸をきたす,いわゆるflail chestとなり,急速に状態は悪化する.初療時に肋骨骨折のみと考えて,その後の観察を怠り,急激な血胸の進展や気胸の増大を見過ごすこともあり,頻回な観察が必要である.
本稿では肋骨骨折を中心に血気胸,肺損傷,大動脈損傷,横隔膜損傷などについて述べる.
ポータブル胸部単純X線写真の読影法―いかに正確な情報を抽出するか
著者: 栗原泰之
ページ範囲:P.178 - P.186
典型的な症例
ポータブル撮影装置による胸部単純X線写真(以下,ポータブル写真)には,さまざまなカテーテルやチューブが描出されていることが多い.これらのカテーテルやチューブは適切に挿入されていないと,機能しないだけではなく予想もしない合併症を招くこととなる.
写真の心臓手術後の患者には,Swan-Ganzカテーテル,気管内挿管チューブ,左胸腔内チューブ,そして経鼻胃管が挿入されているが,経鼻胃管は食道ではなく気管内挿管チューブと同じ気管を通って,その先端は右下葉気管支末梢に位置している(矢印).このままでは経鼻胃管として機能しないのはもちろん,無気肺,肺炎あるいは気胸などの重大な合併症を招きかねないので直ちに抜去する必要がある.
本邦ではあまり聞き慣れない言葉であるが,集中治療室や救急救命センターの患者に対して施行されるモニタリングのためのX線写真のことをintensive care radiologyとかintensive care imagingとかcritical care radiologyと呼び,広範囲をカバーする画像診断である.そのなかで最も多いのが,ポータブル胸部X線写真(以下,ポータブル写真)である.
ポータブル写真は種々の制約があるものの,呼吸状態のみならず全身の水分量の評価もでき,きわめて情報量の豊富なモニタリングデバイスである.系統的で客観的なポータブル写真読影法と臨床情報の付き合わせから,かなり正確な病態把握が可能であると筆者は考えている.またカテーテルやチューブの不適切な挿入による医原性合併症を未然に防ぐことも可能であり,security controlのうえでもその重要性が増している.
こうしたintensive care imagingが,実は中規模,大規模病院のX線診断のうち大きな割合を占めている.当院でもポータブル写真は,胸部単純X線写真の15%前後に達しており,全単純X線写真のうち10%に上っている.大量のポータブル写真から迅速に的確な画像情報を抽出する必要があるのだが,ポータブル写真という特異な写真であること,有所見率がきわめて高いこと,読影の担い手がきわめて多忙である集中治療室の主治医に任せられていることなどのため,多くの施設において個々のポータブル写真から正確な情報が十分抽出はされていないのが実情であろう.
本稿では,ポータブル写真の読影に少しでも役立つように,実際の画像を中心に論を進めたい.
心大血管疾患―単純X線撮影でここまで読める
著者: 佐久間亨 , 原田潤太
ページ範囲:P.188 - P.193
典型的な症例
正面像(a)で心血管陰影の右縁上部は上行大動脈の狭窄後拡張のため突出している(矢印).左室の拡大がないため心左縁下部の張り出しはない.
側面像では,心陰影の中央にリング状の石灰化を認める(矢印).この石灰化は大動脈弁の石灰化を示している.石灰化が著しいほど弁狭窄の程度が高いとされており大動脈弁狭窄を示唆する.狭窄に伴う圧負荷がかかるため求心性の左室肥大をきたすが,大動脈閉鎖不全と異なり,容量負荷がかからないため左室の拡張をきたさない.
CT,MRI,超音波など各種の非侵襲的検査法の発達はめざましいものがあり,心疾患の画像診断法としても大きな役割を占めている.しかし胸部X線撮影はより簡便で,かつ肺血管,心大血管の形状,心房・心室などに関しての情報が得られ,いまだその重要性に変化はない.本稿では胸部単純X線撮影で知ることのできる心大血管系の異常に関して,代表的疾患の画像を紹介し,注目すべき点を挙げて解説する.
乳腺疾患―マンモグラフィでここまで読める
著者: 遠藤登喜子
ページ範囲:P.194 - P.202
典型的な症例
【症例1】 脂肪性乳房の右乳房外上部に,楕円形の腫瘤が認められ,さまざまな長さと太さを示すスピキュラを伴っている.腫瘤の境界および辺縁を観察すると,スピキュラとスピキュラの間には微細鋸歯状の毛羽立ちが,腫瘤から皮膚までには幅のある淡い陰影増強が,皮膚には肥厚と引きつれが認められる.線維成分の豊富な,周囲組織に浸潤する典型的浸潤性乳癌の像である.
【症例2】 右乳房上部に陰影の増強と,糸ミミズのような石灰化が多数認められる.中には線状のみならず,分枝した石灰化も混在し,その幅も長さもさまざまである.また,周辺には,無数の非常に細かい不整形石灰化も認められる.乳管内癌の増殖・壊死による石灰化と判断できる.
乳腺疾患の診断における単純X線撮影(マンモグラフィ)の役割は大きい.診療においてのみならずスクリーニングにおいても,2004年4月からは乳がん検診での中心的役割を担うものとして位置付けられている1).
腹部
腹部単純X線撮影―これだけは知っておきたい腹部単純X線正常像
著者: 稲岡努 , 山田有則 , 油野民雄
ページ範囲:P.204 - P.208
腹部単純X線撮影の意義
診断機器の発達,普及により腹部領域の診断において超音波,CT,MRI,核医学などの検査が容易に実施できるようになった.しかし,単純X線写真は急性期,慢性期の疾患を問わず腹部領域の診断において依然として重要な位置を占めている.単純X線写真は腹部全体を把握するのに適し,それのみで診断が可能なこともあるが,次に続く超音波,CT,MRI,核医学などの検査への道標として重要な役割を果たしている.また,CT,MRIを読影する際にも多くの情報を提供し,見返して初めて異常所見に気付かされることも少なくない.単純X線写真は,空気,脂肪,水,金属濃度から成り立つ画像であり,すべての異常を観察することは不可能であるが,そのコントラストの成因,正常X線解剖を学習し,常に意識しながら読影することにより多くの異常所見が拾えるようになる.
撮影のポイント
腹部単純X線写真において最も基本的な撮影体位は背臥位前後方向撮影である.背臥位では腹厚が平均化し,腹部全体のコントラストが良好となる.また,腹部の臓器や腫瘤が後腹膜腔の脂肪を圧排し,辺縁をより良好に描出する.立位前後方向撮影を同時に撮影した場合には体位による所見の変化,移動を知ることができる.
腸閉塞―部位と原因,血行障害の有無を見きわめる
著者: 坂本力
ページ範囲:P.210 - P.219
典型的な症例
機械性腸閉塞には腸管の血行障害を伴わない腸閉塞(単純性腸閉塞)と血行障害を伴う腸閉塞(絞扼性腸閉塞)がある.図1は血行障害を伴わない腸閉塞である.立位(a)は拡張腸管(空腸)の鏡面形成(air-fluid level),背臥位(b)は腸管ループがhair pin appearanceを示す.図2の背臥位の腹単は血行障害を伴う腸閉塞で,頻回の嘔吐のためガスが少なく,骨盤腔は均一軟部組織濃度(骨盤腔暗影)を示す〔この所見は造影CT(b)では腸液で満たされた小腸,腸壁は造影されない.扇状に広がる腸間膜の浮腫,間膜根部は捻転している〕.
腹部単純X線写真は簡便,無侵襲,安価で腹部全体が網羅でき,急性腹症には欠くことができない.特にガス像の異常を示す腸閉塞は最も診断が容易であるが,閉塞部位と閉塞の原因を診断することは困難なことが多い.特に閉塞腸管が血行障害を伴うか否かは予後に影響し,必ず診断しなければならない.血行障害を伴う腸閉塞は腹部単純X線写真で次の所見があれば推測できる.①多量の腹水の出現,②腸液で満たされ拡張腸管が偽腫瘍(pseudotumor sign)としてみえたり,あるいは骨盤腔を占拠した所見(骨盤腔暗影),③壁肥厚を示す腸管とその腸管が体位で形を変えない(腸管ループの固定).閉塞の原因を知るためにCT検査は欠かせない.
腹膜腔遊離ガス(free air)―腹膜腔遊離ガスを見落とさないために
著者: 鬼塚英雄 , 山口健
ページ範囲:P.220 - P.227
典型的な症例
腹部膨満の新生児の背臥位腹部単純写真である.一般に小児においては胸部に対し腹部の割合が成人のそれより大きいが,本症例の割合は異常と思われる.また腹部全体には楕円形の透亮像が広がっており,周辺では腹壁の軟部組織と明瞭に境されているのがわかる(矢印).これは大量の空気が腹腔内に充満しているためである.肝外側に入り込んだ遊離ガスによって肝辺縁が写し出されている(白矢頭).さらに肝表面の空気により肝と前腹壁の間にある肝鎌状間膜が,右上腹部から下腹部正中に向かって走る細い線状の陰影として描出されている(黒矢頭).この大きな楕円形の透亮像とその中を走る索状の陰影がラグビーのボールに似ていることからfootball signといわれる.大量の遊離ガスが腹腔内に充満している所見であり,特に新生児の消化管穿孔(胃穿孔が多い)によく認められる.
腹腔内遊離ガスは開腹術後など特殊な場合を除き,消化管穿孔の重要なX線所見であり,急性腹症の際に撮影された腹部単純写真では,遊離ガスの有無が重要なキーとなることが多い.ここでは遊離ガスの検出に必要な撮影法,X線所見ならびにいくつかの鑑別診断について述べる.
腹部異常ガス―その原因と読影のポイント
著者: 後閑武彦 , 信澤宏 , 宗近宏次
ページ範囲:P.228 - P.233
典型的な症例
立位腹部単純X線写真で,右上腹部に空気-液面形成を伴った異常ガス像がみられる(矢印).このガス像に連続し,線状のガス像が連続している(矢頭).部位から考えて,このガス像の由来は胆囊,腸管,右腎などの可能性があるが,矢頭は胆囊の輪郭(胆囊壁内ガス),矢印は胆囊内腔のガスと考えると胆囊の形態と一致し,気腫性胆囊炎と診断される.
気腫性胆囊炎は胆囊腔,胆囊壁,胆囊周囲にガスが認められる急性胆囊炎の特殊型である.一般の胆囊炎と異なり,男性に多い.無胆石例も多く,糖尿病に合併することが多い.穿孔率が通常の急性胆囊炎の5倍あり,死亡率も高いので,早期の治療が必要である.腹部X線所見の特徴は胆囊壁内ガスであるが,その判定が困難なときにはCTが役立つ1).
本稿では腹部単純X線写真でみられる腸管外ガス像のうち,腹膜腔遊離ガスを除いた異常ガス像について解説を行う.この異常ガス像は,腹部単純X線写真で特徴的な所見を示すものもあり,早期発見の手がかりとなることも少なくない.また,早急な治療を有する病態が関係することが多く,早期発見の臨床的意義は高い.
腹部石灰化をどう読むか―多様な所見を理解する
著者: 西井規子 , 桑鶴良平 , 三橋紀夫
ページ範囲:P.234 - P.241
典型的な症例
腹部単純X線写真で石灰化を認めたとき,その局在や形状から成因を推測できるが,臓器の重なりのため単純写真だけで診断を確定することは困難なことも多い.
症例は64歳,男性.胃泡に重なるように帯状に分布する小石灰化の集簇を認める. 両側の腎門部,左腎陰影のやや内側下方,小骨盤内にも多数の石灰化を認める.そのほか,下腹部に散在する結節状の高濃度領域も認められる.
これらはCT上,膵石(①),両側腎結石(②,④),左尿管結石(③),右尿管膀胱移行部結石(⑤)および腸管憩室や虫垂内に残存したバリウム(矢頭)であった.石灰化に比べてバリウムのX線透過性は低く,石灰化よりも高濃度で認められることが多い.
現在の画像診断は主にCTやMRIを中心として行われており,単純X線写真はそれらの前にスクリーニングとして撮影されることが多い.単純X線写真の利点として,胸部や腹部の全体像を一枚の写真で見ることができ,異常があればその概略を把握しやすい,ということがある.ここで述べる石灰化は単純X線写真で高濃度に描出され,検出感度は比較的高い.CTと単純X線写真では空間分解能が異なるが,X線で描出される石灰化病変はほぼ組織像に一致する.また,形状や分布の把握はCTよりも単純X線写真のほうが容易なことがある.腹部の石灰化には,単純写真のみでは成因や病態がよくわからないもの,臨床的にあまり意義をもたないと判断できるものから,疾患そのものや疾患の重症度を示唆するものまで含まれる.これらの多様な所見の理解は,病態の把握や次の検査法を選択するうえで有用である.
骨格系
軀幹骨格(脊椎,骨盤,股関節,肩関節)の単純X線写真―正常解剖と読影のコツ
著者: 藤川章
ページ範囲:P.244 - P.249
単純X線写真の名前は“単純”だが,三次元の物を平面上に凝縮するので,写真上に現れた形状は複雑なことが多い.異常所見を見つけるためには,正常解剖の知識と指先確認を用いて“影絵”のようなX線写真の所見を一つひとつ読み解くことが日々の診療では重要となる.目的によって撮影法やその組み合わせは多岐にわたるが,日常臨床で使用する頻度の高いものを選んで異常を見つけるための正常所見の概要を解説する.
四肢の単純X線撮影―正常解剖と読影のコツ
著者: 玉川光春 , 晴山雅人
ページ範囲:P.250 - P.259
単純X線撮影の意義
近年,四肢関節領域のMRIの重要性は明らかで多用されるが,骨折や奇形,変形性関節症などの重症度判定はX線写真で成される.ここでは,複雑で疾患の多い関節の単純X線撮影を中心に,実際に四肢関節の疾患が疑われる場合,疾患ごとの有効な撮像法をリストアップし,X線写真の注目点について解説した.関節の形状や可動性は個人差が大きいため,異常の発見には左右を撮像し比較することが重要である.なお骨腫瘍の撮像に関しては言及していないが,長管骨の場合は病変の存在する骨の正面像と側面像の二方向の撮像が基本である.
病変と紛らわしい正常変異―偽病変を作らないために
著者: 藤本肇
ページ範囲:P.260 - P.266
典型的な症例
52歳男性の腹部単純X線写真正面像で,仙骨に重なる円形の石灰化陰影がある(図1a矢印).一見して尿管結石を思わせるが,CTを参照するとこの病変は仙骨の内部に存在するのが判明する(図1b矢印).
この陰影の本体は仙骨内に発生した内骨腫(骨島)である.日常診療でしばしば遭遇する正常変異の一つであり,骨盤周囲や肋骨に好発する.辺縁明瞭で均一な硬化像を呈すること,撮影体位によらず位置が変わらないこと,正常骨梁との連続性が認められることなどを考慮すれば容易に診断可能であるが,時にCTによる確認を要することがある.
骨格系の正常変異にはさまざまなものが知られている.これらの多くは単純写真で認められるものである.
本稿では,特に骨腫瘍あるいは骨折などと誤診されやすい正常変異を取り上げ,診断の要点を解説する.
骨膜反応―病変の発見と診断へのアプローチ
著者: 原澤有美
ページ範囲:P.268 - P.272
典型的な症例
下腿の脛骨,腓骨の骨幹部には骨皮質に沿って上下に連続した多層性,波状の石灰化像が認められる.骨膜反応の所見である.この症例は数年来,下腿静脈瘤と診断されており,下腿のびまん性腫脹が増強して疼痛があるため受診した.年余にわたる静脈うっ滞の持続に伴う骨膜反応は,このような連続性多層性~波状充実性骨膜反応を呈するのが典型的である.
骨膜反応(periosteal reaction)または,骨膜新生(periosteal new born formation)は,骨病変や骨近傍の軟部組織病変に対する非特異的な骨膜の反応で,画像上は骨皮質の外側に沿った石灰化像として検出される.骨膜反応を分析することによる骨軟部疾患の特異的な鑑別診断は必ずしも容易ではないが,骨膜反応を検出することによって病変の発見,診断の契機に繋がることも多い.
内科系診療を中心とした日常臨床の場では,原発性骨腫瘍に遭遇する機会は少なく,骨関節症状を主訴とする症例は必ずしも多くない.しかし,全身性疾患や内科的疾患の症例に合併する骨関節症状や,画像検査で遭遇する骨関節所見に注目する着眼点の一つとして認識しておく必要があると考える.
骨折―見逃さないためのポイント
著者: 館悦子 , 佐志隆士
ページ範囲:P.274 - P.280
典型的な症例
13歳男性.左足の痛みがあり受診.部活動でテニスをしている.左足の単純X線写真では明らかな骨折線を指摘できないが,第3中足骨にわずかに骨膜反応がみられる(図1a,b矢印).
MRIでは,第3中足骨骨髄および骨周囲の軟部組織の信号変化が明瞭に観察される(図1c~f矢印).スポーツ歴,部位,画像所見など典型的な疲労骨折である.
骨折とは,外力によって生理的な骨構造の連続性が断たれた状態をいう.骨折の大部分は,患者自身が外傷を自覚し,骨折部の疼痛を訴えて受診する.診察で骨折が疑われた場合,最初に行われる検査が単純X線写真撮影である.単純写真で,ひと目でわかるような骨折は,診断することに限ればほとんど問題にはならない.しかし,微細な骨折や単純X線写真ではっきりしないような骨折の場合には,知識の有無により診断できるかどうかに差が出てくる.本稿では,骨折の診断・治療を専門としていない方々が,特にひと目ではわかりにくい骨折を診断するための一助となることを目標としたい.
骨腫瘍―症例から学ぶ骨腫瘍とその鑑別疾患
著者: 松島理士 , 福田国彦
ページ範囲:P.281 - P.287
典型的な症例
皮質骨不整症候群(cortical irregularity syndrome)
cortical irregularity syndromeは,腫瘍性病変との鑑別が重要となる骨格筋の腱付着部のストレスに起因する変化である1).若年者の大腿骨遠位骨幹端内側後面の腓腹筋内側頭ないし大内転筋の腱付着部に好発する.単純X線写真上,症例のような長管骨骨幹端に骨皮質の菲薄化と境界明瞭な硬化縁を伴う囊胞状の溶骨性変化を示す.若年者で無症状,単純写真で上記のような典型像を呈するときはさらなる検査は不要である.疼痛や非典型的な画像所見を呈するときはMRIによる精査が必要で,本症例では疼痛の原因となる外側半月板断裂が認められた.加齢とともに硬化性変化を呈し溶骨性変化は消失する.基本的には画像で診断が可能であり,放置可能な疾患であるため,この部位にこのような所見を若年者に認めた場合には,この生理的皮質骨不整を考えるべきである.
症例提示設問 骨腫瘍を含めた骨軟部領域の診断においても単純X線写真は最初に行われる検査である.本稿では臨床現場の臨場感を感じながら読み・学んでいただくために,実際の症例の単純X線写真を呈示し,クイズ形式にて執筆した.
骨転移―単純X線写真で見逃さないために
著者: 青木純
ページ範囲:P.288 - P.293
典型的な症例
図1は76歳男性の左肩正面像である.肺癌の既往があり,鎖骨骨折をきたした.X線像では鎖骨中央に骨吸収像が2カ所みられ,一方(矢印)が病的骨折を伴っている.多発病変であることがまず転移性腫瘍を示唆するが,個々の骨吸収の辺縁も不整(いわゆる浸潤像,permeated pattern)であり,悪性腫瘍を強く示唆する.
図2は72歳男性の右股関節正面像である.膀胱癌全摘後放射線治療中の患者である.骨盤部のX線写真で右大腿骨転子間と座骨に骨硬化像が偶然発見された(矢印).同部位に特に症状はない.骨硬化の内部は比較的均一であり,辺縁は淡く外側に消退(fading)している.典型的な硬化性骨転移の像である.
本稿は「単純X線写真の読み方・使い方」の企画の一環であるが,骨転移の診断,特にスクリーニングにおける単純X線写真の果たす役割は少ない.所見としては,先に挙げた不整形の骨吸収像や淡い骨硬化像あるいは両者の混在の像であるが,担癌患者にこのようなX線所見がみられる場合には臨床的にほぼ診断のついていることが多い.すなわち,骨転移の確認といった意味合いが強い.早期治療につながる早期診断のためには,骨シンチグラムやMRIあるいは最近ではFDG-PETが有用である.本稿では,単純X線写真の読影に際して有用と思われる骨転移の一般的知識と,知っていて役に立つと思われるいくつかのポイントを挙げる.
骨粗鬆症・骨軟化症―合併症としての骨折の有無を確認する
著者: 高尾正一郎 , 上谷雅孝
ページ範囲:P.294 - P.301
典型的な症例
全体的に骨梁は粗造である.両側大腿骨の彎曲(bowing)があり,左大腿骨頸部内側にLooser's zone (pseudofracture)を認める.骨盤骨や大腿骨の腱・靱帯付着部には過剰な骨化を認める.
骨減少(osteopenia)は単純X線写真上,骨のX線透過性の亢進として認識される.単純X線写真で認識できる骨減少は30~50%以上の骨量低下で,軽度のものは診断が難しい.最近は骨量の定量評価(骨塩定量)が一般的に行われるようになり,単純X線診断よりも正確で信頼性のある診断が可能になっている.全身性骨減少の最も多い原因は,骨粗鬆症,骨軟化症,副甲状腺機能亢進症であるが,これらの診断は臨床所見で明らかなことが多い.したがって,単純X線撮影は,診断そのものよりもそれに伴う合併症の診断に重点が置かれるべきである.本稿では,骨粗鬆症および骨軟化症の基本的概念,特徴的なX線所見と診断のポイントについて論ずる.
変形性脊椎症,椎間板ヘルニア,脊柱管狭窄症,脊椎領域の骨化症―的確な治療方針を立てるために
著者: 辰野聡
ページ範囲:P.302 - P.307
典型的な症例
明らかな誘因なく左前腕から示指~環指のしびれ感が6カ月前から徐々に増悪している.脱力はない.
頸椎正面像(図1a)で左C6/7椎間における鉤椎関節の退行性変化が疑われる(a:矢印).側面像(図1b)ではC4の下位終板,C5,C6の上下終板,C7の上位終板の牽引性骨棘形成(b:矢頭)が認められるが,椎間腔は正常に保たれ,椎前部軟部組織の厚さと脊柱管の前後径も正常範囲内で靱帯骨化もみられない.骨破壊性病変は認められない.左前斜位像(図1c)上,C6/7椎間孔はC7の鉤状突起部の骨棘形成(c:矢印)によって狭小化している.左C7神経根障害の原因として一致する.
中年以降では脊椎退行性変化の多くは無症候であり,画像所見は神経所見と一致して初めて有意となるが,本例では両者に矛盾がなく,これ以上の画像診断は行われなかった.
慢性腎不全と骨関節病変―慢性腎不全マネジメントに欠かせないポイント
著者: 工藤祥
ページ範囲:P.308 - P.315
典型的な症例
図1 35歳女性,透析歴8年,頭部顔面側面像
骨濃度は全体的に低下し,頭蓋冠部はびまん性に小顆粒状影のいわゆるsalt and pepper appearanceを呈している.上顎骨,下顎骨では個々の歯根周囲に本来みられるべき歯槽硬線(lamina dura)が消失している.いずれも二次性副甲状腺機能亢進症による骨吸収の所見である.
図2 53歳女性,透析歴12年,右手正面像
骨皮質および骨梁の吸収があり,骨は淡く,皮質・髄質の境界が不明瞭となっている.特に第2基節骨撓骨側の骨膜下骨吸収(矢頭)が顕著であり,軟骨下骨吸収(矢印)もみられる.第一末節骨も吸収され,小さくなっているようである.さらに,指間動脈に多数の石灰化がみられる.いずれも二次性副甲状腺機能亢進症に特徴的な所見である.
慢性腎不全に関連する骨・関節・軟部の病変は多様であるが,最も典型的とされるのは腎性骨異栄養症(renal osteodystrophy)と総称される病態であり,これには二次性副甲状腺機能亢進症(図1~4),骨粗鬆症,骨硬化(図5),骨軟化症(図6,7),くる病(図8),軟部・血管の石灰化(図2)などが含まれる.また,長期の透析に関連してはアミロイド沈着症(図9~11),破壊性脊椎関節症(図11),アルミニウム骨症,結晶沈着症,腱断裂などがあり,骨・軟部感染症や骨壊死の合併もある.
代謝・内分泌疾患と骨関節病変―特徴的骨変化を読む
著者: 藤澤英文 , 櫛橋民生
ページ範囲:P.316 - P.322
典型的な症例
手関節の単純X線正面撮影で,尺骨端は,杯状陥凹(cupping)を示し,幅広い(flaring).予備石灰化層は不鮮明で,刷毛状不整化(fraying)を認める.橈骨骨幹端にも刷毛状不整化を認める.成長板間隙は開大している.
膝関節の単純X線正面撮影では,予備石灰化層は消失し,骨幹端は不整で,横径が拡大している.これらは成長板の骨化障害による所見である.
骨は全体的に骨濃度が低下しており,骨量減少(osteopenia)の状態である.本症例は抗てんかん薬を服用しており,薬剤性のくる病である.
膠原病と骨関節病変―単純X線所見が決め手になる関節炎の診断
著者: 苫米地牧子 , 江原茂
ページ範囲:P.324 - P.330
典型的な症例
62歳,女性.両手関節の腫脹と疼痛を訴えて来院.手の単純X線撮影が施行された.図はその写真である(図1a).手関節部の軟部組織の腫脹は明らかである.また遠位橈尺関節と手根中央関節裂隙が狭小化している.
手関節部の拡大像(図1b)では,特に尺骨茎状突起の周囲に軟部組織の腫脹が著しく,また茎状突起尺側に侵食(erosion)を認める.さらに中手指節関節の拡大像(図1c)では,関節辺縁部皮質の輪郭が不明瞭化となっている.このような軽微な骨侵食は,第2~5中手指節関節のいずれでも認められる.これらはいずれも慢性化した滑膜炎の所見である.関節リウマチのこのような典型的所見の特異性は高い.
血液・造血器疾患と骨関節病変―単純X線写真から多くを読みとるクセをつける
著者: 篠崎健史 , 藤田晃史 , 杉本英治
ページ範囲:P.332 - P.339
典型的な症例
64歳,女性.頭蓋骨正面(図1a),側面像(図1b)にて頭蓋冠に境界明瞭,多発性,円形,辺縁の硬化性変化のない透亮性変化(punched-out lesion)を認める(矢印).また下顎骨にも同様の所見を認める(矢頭).40歳以上の成人で,このような所見を認めた場合,転移性骨腫瘍か形質細胞骨髄腫(多発性骨髄腫と形質細胞腫の総称)をまず考える.形質細胞骨髄腫は転移性骨腫瘍に比べて,下顎骨が侵される頻度が非常に高く,また大きさが比較的揃っていることが多い.
本症例は60歳代,頭蓋冠,下顎骨の多発性punched-out lesionを認め,形質細胞骨髄腫(多発性骨髄腫)と診断された.
骨関節疾患というと整形外科的疾患をまず思い浮かべるが,代謝疾患,内分泌疾患,血液疾患,その他多くの臓器や全身性の疾患に伴い変化が生じることを忘れてはならない.またCT,MRI検査が全盛であるが,簡便かつ安価な単純X線写真(以下,単純写真)から非常に多くの情報が得られる点は,胸部単純写真と同様であり,必ずCT,MRI画像と単純写真は比較しながら読影する必要がある.今回は,血液・造血器疾患の骨関節病変の画像診断について,腫瘍性病変と非腫瘍性病変に分けて解説する.
結晶沈着疾患―痛風,偽痛風,石灰化腱板炎の診断と治療
著者: 西村浩 , 濱田哲矢
ページ範囲:P.340 - P.345
典型的な症例
図1 慢性の痛風性関節炎(a:40歳男性,b:43歳男性)
いずれの例においても右母趾中足趾節関節に偏在性の軟部組織腫脹がみられる(矢印).bでは一部石灰化を伴っている.関節裂隙はaでは若干狭小化がみられるが,bでは狭小化はほとんど認められない.中足骨にはいずれの例でも比較的境界明瞭なびらんを認め,ややわかりにくいがoverhanging edges(矢頭)が認められる.
結晶沈着誘発関節症(crystal induced arthritis)とは,生体または軟骨の代謝異常によって析出した無機塩の結晶が関節腔に遊離し白血球に貪食されて関節内の滑膜,軟骨などに沈着して起こる関節炎のことである.
原因となる結晶には,尿酸ナトリウム結晶(痛風),ピロリン酸カルシウム(偽痛風),リン酸カルシウムの一種であるハイドロオキシアパタイト(石灰化腱板炎など),シュウ酸カルシウムなどがある(表1).本稿では,代表的な痛風,偽痛風,石灰化腱板炎の3疾患に絞って解説する.なお,尿酸ナトリウム結晶以外は,関節軟骨に石灰化がみられるために画像所見や病理学的用語としての軟骨石灰化症(chondrocalcinosis)とも呼ばれるが,結晶沈着症以外にも軟骨に石灰化をきたすことがあるため鑑別診断上注意が必要である(表2).
軟部組織疾患―CT,MRIといかに組み合わせるか
著者: 青木隆敏 , 川波哲 , 興梠征典
ページ範囲:P.346 - P.352
典型的な症例
20歳代の女性.頸部単純X線側面像で,後頸部の軟部組織に種々の大きさの円形ないしリング状の石灰化が認められる(a).MRIT2強調横断像では頸椎の背側~左側に著明な高信号を示す腫瘤(矢頭)がみられ,腫瘤内部には単純X線写真での石灰化に相当する円形低信号(矢印)が認められる(b).
この症例の単純X線写真で認められる円形やリング状の石灰化は静脈石であり,拡張した血管腔内の石灰化した血栓を示す.深在性の血管腫を単純X線写真で指摘することは困難なことが多いが,本例のように複数の集簇する静脈石を捉えることができれば,単純X線写真のみで特異的診断が可能である.
基本情報
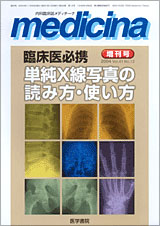
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
