CT・MRIの最近の進歩
CTおよびMRIは,装置およびソフトの開発とコンピュータ能力の向上が合わさり日々進歩している.特に最近では医療機器メーカーの開発努力により,その進歩が早まっていると感じられる.本稿では,最近10年程度のCT,MR装置の進歩を述べ,次に両者の使い分けについて解説していきたい.
雑誌目次
medicina46巻12号
2009年11月発行
雑誌目次
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
正常解剖アトラス
頭部/頸部/肺/縦隔/腹部/骨盤
ページ範囲:P.6 - P.17
CT・MRIの動向
CT・MRIの最近の進歩,モダリティ選択
著者: 渡邉嘉之
ページ範囲:P.18 - P.25
脳 総論
読影の基本とポイント
著者: 岩下孝弥 , 平井俊範
ページ範囲:P.28 - P.32
脳のMRI読影について
MRIは頭部領域の画像診断において中心的な検査法である.一般にMRIはCTと比較して中枢神経病変の描出に優れており,ペースメーカー装着者などの検査禁忌例を除けば,多くの疾患において第一選択の画像診断法である.
MR画像の読影は,①異常所見の拾い上げ,②異常所見の解釈,③鑑別診断,の順に行う(図1).これらにおいて,正常MR像を把握すること,アーチファクトかどうか判断できること,MR信号強度を解釈すること,は適切な画像診断に必須である.
各論
基底核・視床
著者: 井田正博 , 日野圭子 , 萬直哉 , 菅原俊祐 , 久保優子 , 川口祐子
ページ範囲:P.33 - P.43
■基底核
「大脳基底核(basal ganglia)」とは終脳の深部灰白質で,前脳基底部の線条体(striatum)〔尾状核(caudate nucleus)と被殻(putamen)〕と淡蒼球(globus pallidus),間脳の視床下核(subthalamic nucleus)および中脳の黒質(substantia nigra)からなる(図1).「中心灰白質(central gray matter)」は,これら基底核と間脳の視床を含める(視床は大脳基底核には含まれない注釈1, 2)1).基底核は大脳皮質や視床と相互の神経回路を形成し,運動の調節機能(興奮と抑制)を司る〔錐体外路系(extra pyramidal tract)〕.その障害は①運動低下をきたすParkinson病や,②振戦,アテトーゼなどの不随意運動の原因となる.
視床は間脳由来の中心灰白質で,大脳基底核には含まれない.ただし,大脳皮質や基底核と密な神経線維連絡があり,大脳皮質-基底核-視床-大脳皮質のフィードバックループを形成する(直接経路,間接経路;後述図4)2).視床の外側腹側核,前腹側核,背側内側核は運動のコントロールに関連する.その他,感覚,記憶,情動,眼球運動などの多くの機能を中継,連合する.
海馬
著者: 松末英司 , 藤井進也 , 小川敏英
ページ範囲:P.44 - P.50
海馬と扁桃体
側頭葉内側部を構成する重要な構造として海馬と扁桃体がある1~4).扁桃体,その内側下部にある迂回回,海馬頭部の内側領域をあわせた領域は鈎とも呼ばれる(図1~3).
海馬はアンモン角と歯状回からなり,隣接する海馬台,海馬采を含めて海馬体と呼ばれる.これらは記憶にかかわる機能と関連が深い.アンモン角は細胞構築の差異によりCA1~CA4に分けられる.アンモン角と連続する皮質である海馬台は海馬傍回の上面を構成する(図1~4).海馬が関連する記憶にかかわる神経回路はPapezの回路と呼ばれ,アンモン角,海馬台の錐体細胞からの遠心性線維が,海馬采→脳弓→乳頭体→乳頭視床路→視床前核→帯状回後部→帯状束→海馬傍回→海馬体に戻る.海馬の前端に近接してみられる扁桃体は,下角の前上壁をなすアーモンド型の灰白質構造であり(図1~3),情動反応の処理と記憶において主要な役割をもつとされる.扁桃体は主に6つの核からなるが,機能的には皮質内側扁桃体群と基底外側扁桃体群に分けられる.扁桃体が関連する感情にかかわる回路はYakovlevの回路と呼ばれ,扁桃体→視床内側核→前頭葉眼窩面皮質→側頭葉皮質前部→扁桃体に戻る.
下垂体・視床下部・傍鞍部
著者: 木村有喜男 , 佐藤典子
ページ範囲:P.51 - P.57
この領域には,生体の恒常性の維持に重要な内分泌機能を担っている下垂体-視床下部系をはじめ,視交叉,海綿静脈洞,Willis動脈輪など複雑な構造が含まれている.本稿では,下垂体を中心とした正常MRI像を概説し,代表的な疾患について症例を提示する.
脳幹・小脳
著者: 木下俊文 , 木下富美子
ページ範囲:P.58 - P.64
正常解剖1,2)(図1)
脳幹は,延髄,橋および中脳の3つの部分に分かれる.脳幹の頭側には間脳(視床)があり,尾側では脊髄につながる.橋および中脳の背側部は発生学的に古く,被蓋部と呼ばれ,脳神経核を含んでいる.小脳は脳幹の背側に位置し,正中の虫部と一対の半球よりなる.小脳は中脳・橋・延髄とおのおの上・中・下小脳脚でつながっている.小脳と橋の間には第四脳室が存在し,中脳水道を介して第三脳室と交通する.第四脳室からは両外側にあるLuschka孔と正中下部にあるMagendie孔によりくも膜下腔につながる.脳幹,小脳周囲には小脳延髄槽,小脳橋角槽などの脳槽があり,このうち小脳橋角槽は小脳と脳幹部で形成されるくも膜下腔で,橋と延髄の接合部より出る顔面神経や内耳神経が走行する.
脳幹部では,さまざまな神経線維が神経核を介しながら,縦走・横走する.運動系の伝導路として最も重要なものに皮質脊髄路が挙げられる.皮質脊髄路は線維が延髄錐体を走行することから錐体路とも呼ばれる.中脳では大脳脚を,橋では橋底部を,延髄では錐体を下行する.その他の橋の縦走線維としては,皮質核路(別名,皮質延髄路)と皮質橋路がある.皮質核路は大脳皮質から迷走神経核や舌下神経核といった主に延髄の脳神経運動核に至る経路である.また,皮質橋路は大脳皮質から橋に下行する縦走線維で,橋核で橋小脳路に中継される.橋小脳路は中小脳脚を通って対側の小脳皮質に至る.
大脳白質
著者: 中村尚子 , 赤澤健太郎 , 山田惠 , 西村恒彦
ページ範囲:P.65 - P.72
大脳白質は有髄線維を多く含むため,肉眼的に皮質と比べて白くみえる.CTやMRIで観察すると,一見均質な左右対称性の単純な構造にみえるかもしれないが,解剖学的には神経線維の束が交錯し合った複雑な形態をしている.その大まかな構造を知っておくことは,画像診断においてきわめて重要である.また,白質は脳の容積のかなりの部分を占めており,さまざまな疾患が生じることが知られている.
本稿では,白質の種類や解剖を中心に概説を行う.
大脳皮質
著者: 日向野修一 , 麦倉俊司 , 梅津篤司 , 加藤裕美子 , 高橋昭喜
ページ範囲:P.73 - P.81
正常解剖
●大脳の表在解剖1)(図1a,b)
大脳半球は正中の大脳縦裂により左右の半球に分けられる.それぞれの大脳半球は中心溝,Sylvius裂,頭頂後頭溝により前頭葉,頭頂葉,側頭葉,後頭葉,島葉に分けられる.
前頭葉は,後縁は中心溝によって頭頂葉と,下後部はSylvius裂後枝により側頭葉と境される.外側面では,中心溝の前にこれと平行して中心前溝があり,ここから前方に向かって横走する2本の上・下前頭溝がある.これらの脳溝により,中心前回,上・中・下前頭回の4つの脳回に分けられる.中心前回は一次運動野にあたる.下前頭回はSylvius裂の前水平枝と前上行枝により,眼窩部,三角部,弁蓋部に分けられる.
頭蓋冠・髄膜
著者: 土屋一洋
ページ範囲:P.82 - P.89
正常解剖
●頭蓋冠
頭蓋腔を円盤状に被うのが頭蓋冠(calvaria)である.頭蓋のうち,顔面骨や頭蓋底を除いた部分で,頭頂骨と前頭骨・側頭骨・後頭骨の鱗部からなる.緻密質からなる外板と内板の間に,海綿質からなる板間層がある3層構造になっている.
外板の表面は平滑で,帽状腱膜がこれを被う.板間層には各所に静脈を容れた板間管があり,外板または内板に開口する.また,板間層には骨髄が存在し,そのMRIでの信号強度は年齢などで変化する.すなわち,赤色髄が占めるとT1強調像で低信号を示し,これは1歳以下では正常所見である.その後おおむね7歳前後まで,脂肪髄化に伴い次第に高信号化する(図1).赤色髄はGd造影剤で増強効果を示す.内板の内面は各種の凹凸がある.これには脳回による指圧痕,脳溝による脳隆起,硬膜の動静脈による動・静脈溝,硬膜静脈洞による上矢状洞溝や横洞溝などがある(図2).
脳血管
著者: 朝日公一 , 鈴木通真 , 青木茂樹
ページ範囲:P.90 - P.98
血管・血流の情報は,脳疾患,特に脳血管障害の診断に欠くことができない情報で,従来から脳腫瘍・脳血管障害などにおいてカテーテルを用いた選択的脳血管造影が広く行われていた.しかし,その合併症の頻度は高く,症状で観察した報告で0.5%,MRIの拡散強調像で観察すると2割程度の検査で異常が出現したという報告もあり,血管内治療は別として,その適応は術前や血管障害に限られてきている.
血管造影の適応を限定できるようになった背景には,CT,MRIの進歩で血管の情報が頭蓋内でも非侵襲的に得られるようになったことが大きい.
特にMRAは非侵襲的に頭蓋内の血管の詳細を知ることができ,その臨床的有用性は高い.また,通常の断層像でも血管に注目すればかなりの情報が得られることも知っておく必要がある.
頭頸部 総論
読影の基本とポイント
著者: 豊田圭子
ページ範囲:P.100 - P.104
CTとMRIの部位別・疾患別の選択の指針
頭頸部は頭蓋底から胸郭入口部までの領域を指すが,細分すると,頭蓋底,眼窩,側頭骨,鼻・副鼻腔,咽頭,喉頭,口腔,大唾液腺,甲状腺・副甲状腺,リンパ組織である.その第一の診断法は,耳鏡,喉頭鏡,鼻鏡などを用いた視診法と頸部触診法である.これらで診断がつけられ,さらに質的診断や進達度診断のため,画像検査が施行される.頭頸部における読影の手順は,中枢神経系や腹部領域など,そのほかの領域と基本的に同じである.しかし頭頸部では,病変の進展により大きく治療方針が異なるので,進達度診断が重要である.症状が著明な,しかし視診・触診で診断がつかない例でも,画像診断は行われる(例えば異物誤飲).
また,頭頸部は症状と所見が一致しやすい領域であるので,症状から上記のそれぞれの領域を細かく画像を撮像する.具体的な画像の選択方法は後述する(表1).
各論
側頭骨
著者: 長縄慎二
ページ範囲:P.105 - P.111
側頭骨の画像診断には一般にCTおよびMRIが用いられる.側頭骨領域の特徴としては,立体的に複雑な構造であることと,各構造自体が小さく空間分解能の高い撮影が要求されるという点である.CTは骨構造の微細な変化の描出に優れ,MRIは軟部組織コントラストの変化検出に優れる.後頭蓋窩および内耳道については,CTでは周囲の厚い骨によるX線の線質変化(beam hardening artifact)によって詳細な検討が困難であるので,MRIを用いるのが一般的である.また内耳についても,形態異常と内部石灰化や空気の有無のほかはMRIを用いるのがよい.例えば,外傷後の骨折線や迷路気腫の検出についてはCTのほうが優れるが,迷路内の軟部組織の検出にはMRIが優れる.中耳および外耳については,外耳道骨壁や耳小骨,顔面神経管などの描出に優れるCTを用いることが多いが,外耳道腫瘍の進展範囲や中耳真珠腫の性状把握にはMRIも用いられる.側頭骨領域の画像診断で重要なことは,まず画像そのものが診断に値するような適切な撮影がなされているかどうかを判定することである.不十分な条件で撮影された画像は,この領域を専門とする画像診断医にとっても読影が難しく,ましてこの領域の画像を見慣れない諸家にとっては評価がきわめて困難である.次に適切に撮影された画像で,正常解剖を習熟し,さらには代表的疾患の典型像を知っておくことである.
内科医がこの領域の画像を目にするのは,めまい,顔面神経麻痺,頭痛,耳痛,難聴,耳鳴りなどの症状をもった患者の場合と思われる.この領域の症状が全身疾患の一症候として現れることもあるので,内科医もある程度は側頭骨領域の画像診断を知っておく必要がある.本稿では,最新の装置を用いて得られたCT像とMRI像によって,まず側頭骨領域の正常解剖を習熟し,ついで上述の症状を呈する代表的な疾患の画像を提示する.
頭蓋底
著者: 佐藤陽介 , 藤田晃史 , 杉本英治
ページ範囲:P.112 - P.122
当然ながら頭蓋底を直接観察することはできない.その病変を疑うきっかけは,症状や画像に頼るところが大きい.頭蓋底は頭蓋内と頭蓋外の境界で,脳神経が頭蓋外に出るときに必ず通る領域である.そのため,この領域の病変の症状の多くは脳神経の異常として認められる.また,画像による頭蓋底病変の存在診断,広がり診断は治療方針の決定に重要であるが,この領域の解剖は複雑で,不慣れな場合は画像の解釈にも苦労することも多い.
本稿では,症状と関連する画像所見(CT,MRI)を中心に,正常解剖,頻度の高い疾患,見落とすと重大な結果につながる疾患を中心に取り上げた.
唾液腺・甲状腺
著者: 高橋直也
ページ範囲:P.123 - P.128
唾液腺と甲状腺は表在に位置するため,触診や超音波検査が有用である.CT・MRIの役割は主に病変の由来や局在を明らかにすることにある.本稿では,痛みや腫瘤などの症状をきたす疾患を中心に解説する.
咽頭・喉頭
著者: 池田耕士 , 前原稔 , 播磨洋子 , 澤田敏
ページ範囲:P.129 - P.135
正常解剖
咽頭とは全長約12~15cmの管状臓器で,上・中・下の3腔に分けられる.喉頭とは咽頭と気管の狭間にある(図1).
頸部リンパ節
著者: 河津俊幸 , 吉浦一紀
ページ範囲:P.136 - P.139
正常解剖
全身に800個あるリンパ節のうち,300個は頸部に存在するといわれている.
頸部リンパ節の分類に関しては,解剖学的分類とともに頭頸部癌取扱い規約やACHNSO(Academy's Committee for Head and Neck Surgery and Oncology)など,いくつかの分類法が提唱されているが,決まった見解はない.本稿では基本的に頭頸部癌取扱い規約1)の分類に則り解説を進めていく.図1および以下にその分類を示す.
頸椎
著者: 大久保敏之
ページ範囲:P.140 - P.149
正常解剖
頸椎では,単純X線撮影がまずスクリーニングとして施行されることが多く,CT,MRIを精密検査として使用することが多い.MRIでは,その高いコントラスト分解能によって,前処置なく脊髄,くも膜下腔,脊髄神経根が明瞭に描出できるので,頸椎,頸髄の領域では最も重要な検査法である.
胸部 総論
読影の基本とポイント
著者: 村田喜代史
ページ範囲:P.152 - P.155
胸部における画像診断法の選択の指針
胸部は単純X線写真が依然として重要な役割を占める数少ない領域の1つである.簡便性やX線被曝量の低さに加えて,胸部全体の変化を概観できる利点をもつが,精密な形態診断は断層像であるCTが中心になる.要は,X線写真とCTを組み合わせながら,いかに最小のX線被曝で,最大の情報を得るかを考えることが重要ということになる.なお,現時点では,胸部MRIはCTを補足する役割と位置づけられる.
胸部CTでは,通常,肺野条件と縦隔条件の画像シリーズが再構成されるので,全スライスを正常構造の連続性に注意しながらレビューして,肺野あるいは縦隔胸壁内の異常をとらえる.肺野の病変の有無をとらえるだけなら,5~7mm厚の通常CTでも可能であるが,びまん性肺疾患で肺二次小葉レベルの精密形態診断を行うためには,1~2mm厚の高分解能CT(high-resolution computed tomography:HRCT)が必要である.また,肺癌の形態診断も通常HRCTを用いて行われる.
各論
肺胞・肺小葉・肺間質
著者: 野間恵之 , 田口善夫 , 小橋陽一郎 , 伊藤春海
ページ範囲:P.156 - P.163
肺野に出現する異常陰影を正確に読影するためには,肺の基本構造である小葉の理解と,種々の異常所見が小葉とどう関連しているかを読み解くことが重要である.したがって,本稿においては,まず肺の基本構造である小葉について整理し,さらに,病変がHRCT(high-resolution CT)で小葉とどう関連して把握されるのかを,いくつかの典型例とその病理像を示しながら解説する.
気管・気管支・細気管支
著者: 松山直弘 , 芦澤和人
ページ範囲:P.164 - P.170
正常解剖
●気管
輪状軟骨下縁から気管分岐部までの長さ約12cm,径約2cmの管腔臓器である.食道の前方で胸腔内に入り椎体前方を下降する.通常,第6胸椎のレベルで左右の気管支に分岐する.気管壁は前方および側方を軟骨部,後方を膜様部と呼ぶ.前者は16~20個の馬蹄形の気管軟骨により,後者は平滑筋と弾性線維により構成されている.
肺の動静脈
著者: 栗原泰之
ページ範囲:P.171 - P.177
正常解剖
中枢側の肺動脈と肺静脈は胸部単純X線写真上,肺門陰影を形成する重要な要素である.肺門の大きさを左右する陰影である肺底肺動脈(下肺動脈幹)は,右中間気管支幹外側では正常では15mm以下,第8肋骨の幅とほぼ同じである.左肺門は左肺動脈が左主気管支を乗り越えてから葉間肺動脈として下行するために,左肺門のほうが高く位置する.
肺動脈は末梢では気管支に伴走するが,中枢の分岐パターンにはバリエーションがみられる.
縦隔・胸腺
著者: 松尾有香 , 酒井文和 , 木村文子
ページ範囲:P.178 - P.188
正常解剖と生理的変化
●正常解剖
縦隔は左右の胸腔の間に位置し,前方は胸骨,後方は胸椎,下方は横隔膜で囲まれ,上方は頸部へ連続している.
縦隔のX線学的区分は,従来よりFelsonの胸部単純写真側面像での区分により理解されている1).この区分では,気管の前縁から心陰影の後縁を結ぶ線を前縦隔と中縦隔の境界とし,椎体前縁の1cm後方を中縦隔と後縦隔の境界としている.現在ではCTにより正常構造の位置を把握し,前縦隔を心大血管の前外側,中縦隔を気管・食道周囲,後縦隔を傍椎体領域としている(Sone, et al2)による区分).
肺のリンパ管・リンパ節
著者: 渡辺尚史 , 高橋康二
ページ範囲:P.189 - P.195
正常解剖
●肺のリンパ管の解剖
肺のリンパ管は存在部位により,胸膜に分布する表在性リンパ管と内部に存在する深在性リンパ管に大別される.深在性リンパ管はさらに小葉間結合織内のリンパ管,肺静脈・気管支・肺動脈に伴うものに分類される1,2).
胸膜下リンパ毛細血管内のリンパは,主に小葉周辺部のリンパ管を介して一本の集合リンパ管に運ばれ,区域間や肺葉間の肺静脈に伴う集合リンパ管を介して肺門部に注ぐ.ごく一部は,小葉間結合織内の集合リンパ管を経て,肺動脈・気管支に伴うリンパ管に流入してから,肺門部に到達する経路,すなわち表在性から深在性リンパ管に注ぐ経路が存在している(胎児で発達,成人は肺底部にわずかに認められる)(図1).
また,胸膜下リンパ管への色素注入法による解剖学的検討と,肺癌切除例における転移リンパ節分布の検討から,肺から縦隔への直接リンパ経路の存在が考えられている.
胸膜
著者: 負門克典
ページ範囲:P.196 - P.202
正常解剖と画像
●正常解剖
胸膜は薄い漿膜で,肺を覆う臓側胸膜と胸壁内面・縦隔・横隔膜を覆う壁側胸膜の2つからなり,両者は肺門を介して連続的に移行している.胸膜で囲まれたスペースが胸腔であり,内部に肺を格納する.正常の状態では,臓側胸膜で覆われた肺が入り込めない閉鎖腔が肋骨横隔膜陥凹(costodiaphragmatic recess)尾側に存在しており,同部では壁側胸膜同士が接することになる.胸部単純X線撮影で認識される肋骨横隔膜角とは肺下端に対応しており,胸腔は閉鎖腔としてさらにその下方まで伸びていることを忘れてはならない.
肺門下部では臓側胸膜と壁側胸膜が飜転して肺靱帯が形成されており,これにより肺下葉は縦隔側に固定されている.前後方向に2枚の胸膜が存在する索状の狭い間隙にはリンパ組織(肺癌取扱い規約の#9肺靱帯リンパ節)と結合織がはさまっている.
心臓・心囊
著者: 市川泰崇
ページ範囲:P.203 - P.211
正常解剖(図1~4)
心臓は心膜に包まれ,人の握り拳大で,重量は250~350gである.心臓の下端部はやや尖り,心尖と呼ばれる.心臓内部は右心房,右心室,左心房,左心室の4つの部屋に分かれる.房・室および左右心室を隔てる境界に一致して,心臓の表面に溝がみられる.心房と心室の間の溝は房室間溝と呼ばれる.心室の前面と後面には縦走する溝があり,前室間溝・後室間溝と呼ばれる.右心房は心臓の右上部を占め,後方の上下に上大静脈と下大静脈が注ぐ.右心耳は上大静脈の基部から左前方に向かって突出する.心房中隔には浅い卵円形の凹みがあり,卵円窩と呼ばれる.三尖弁は前尖・後尖・中隔尖からなる.右心室は心臓の最下部を占め,内面に多数の肉柱がみられる.心室中隔は右心室に向かって膨隆する.心室中隔の大部分は筋性で厚いが,中隔上部の小部分は薄く膜様で,膜性部と呼ばれる.肺動脈弁口は右心室の前上部に位置する.左心房は心臓の後上部にあり,後壁上部に左右肺から2本ずつ肺静脈が開口する.左心耳は肺動脈起始部の左方に位置する.左心室の内面には右心室と同様に多数の肉柱がみられ,前壁と下壁には強大な乳頭筋(前乳頭筋・後乳頭筋)が突出する.僧帽弁は2個の弁尖(前尖・後尖)からなる.大動脈弁と肺動脈弁は同様の形状をもち,3枚の半月弁からなる.
冠動脈は右冠動脈と左冠動脈からなる.右冠動脈は大動脈起始部腹側の右冠動脈洞から分岐し,右房室間溝に沿って走行する.左冠動脈は大動脈起始部左背側の左冠動脈洞より起始し,左冠動脈前下行枝と左冠動脈回旋枝に分岐する.分岐するまでを左主幹部と呼ぶ.分岐した左冠動脈前下行枝は前室間溝,左冠動脈回旋枝は左房室間溝に沿って走行する.冠動脈の各セグメントの名称については,AHA(American Heart Association)の分類が一般的に使用される.心臓の静脈の大部分は冠状静脈洞に集まり,右心房に注ぐ.冠状静脈洞の開口部は,下大静脈口と三尖弁口との間に位置する.
心臓を包む結合組織性の膜を心膜という.心膜は,心臓表面を覆う臓側心膜と,胸膜と接する壁側心膜より構成される.両者に囲まれた空間が心膜腔であり,心膜腔には正常でも50ml以下の心囊液が存在する.
食道・横隔膜
著者: 門澤秀一
ページ範囲:P.212 - P.220
■食道
正常解剖(図1)
食道は咽頭と胃を結ぶ25~30cmの筋性の管腔臓器で,食道癌取扱い規約では食道入口部(輪状軟骨下縁のレベル)から胸骨上縁(内視鏡では門歯から約18cm)までを頸部食道,胸骨上縁から気管分岐部下縁(門歯から約24cm)までを胸部上部食道,気管分岐部下縁から食道胃接合部(門歯から約40cm)を2等分した上半分(門歯から約32cmまで)を胸部中部食道,下半分を胸部下部食道に区分している.
食道は頸部では気管と椎体の間を,胸部では椎体の左前方の後縦隔を下行し,食道裂孔(第11胸椎レベル)から水平方向に向きを変えながら腹腔に入る.腹部食道は円錐状にゆるやかに拡張しながら胃噴門へ移行する.
胸部の大血管:大動脈弓と大静脈
著者: 岡田宗正 , 松永尚文
ページ範囲:P.221 - P.231
胸部の大動脈
●発生異常
胎児の大動脈は,左右1対の背側大動脈(dorsal aorta)で,背側大動脈弓は第1大動脈弓を形成し,腹側大動脈(ventral aorta)へ移行する.左右の腹側大動脈は合流し,大動脈囊(aortic sac)を形成する.以後,鰓弓の発生に伴い腹側大動脈と背側大動脈との間に左右6対の大動脈弓が異時的に形成されるが,最終的には正常の大動脈弓は左第4弓と連続する背側大動脈からなり,第3弓は両側頸動脈,右第4弓は腕頭動脈および右鎖骨下動脈起始部,第6弓は肺動脈となり,左大動脈弓が正常の形態となる.
大動脈弓の発生異常は,Edwardsの模式図“仮想両側大動脈弓両側動脈管(hypothetic double aortic arch with bilateral ducti arteriosi)”という概念から(図1),吸収および残存形態から種々の大動脈弓異常が説明される1).
先天性大動脈異常の分類には,①大動脈弓の位置(右側,左側または両側),②上部下行大動脈の位置(右側または左側),③動脈管の位置(右側か左側),④弓部分枝の分岐パターンにより,以下のように分類される.
胸郭・胸椎
著者: 名嘉山哲雄 , 井上佑一 , 三木幸雄
ページ範囲:P.232 - P.243
正常解剖
胸壁などの軟部組織を除く骨性構造の正常解剖について記載する.
●胸郭(図1~4)
骨性胸郭は12個の胸椎,12対の肋骨と肋軟骨,胸骨で構成される.前方では肋軟骨が肋骨弓を形成する.上位7対の肋軟骨は胸骨と関節する.第1~2肋骨は胸椎柄の肋骨切痕と関節し,第3~7肋骨は胸骨体部の肋骨切痕と関節する.第8~10肋軟骨は1つ上位の肋骨と関節する肋軟骨間関節を形成する.後方では肋骨と胸椎が関節する.胸骨は3部分からなり,上方から胸骨柄,胸骨体部,剣状突起に分かれる.柄部の上方正中部に頸切痕,上方外側に鎖骨切痕が存在し,鎖骨切痕部で鎖骨と関節する.胸鎖関節は関節円板をもつ滑膜関節で前方に全胸鎖骨靱帯,その外側下方に肋鎖靱帯が存在する.頸切痕の上方を鎖骨間靱帯が走行し,鎖骨を連結する.その下方に第1~2肋骨との関節部である肋骨切痕が存在する.胸骨角部は胸骨柄と体部の結合部分が前方に突出する部分である.体部上外側に第2肋骨と関節する肋骨切痕が存在する.下方に第3~7肋骨との関節部である肋骨切痕が存在し,第1胸肋関節は軟骨結合であり,関節腔は存在しない.第2~7胸肋関節内には関節腔があり,関節内胸肋関節靱帯が存在する.前方には前放射状胸肋靱帯が存在する.肋骨は大きく分け,頭部,頸部,体部から構成される.肋骨の前方には硝子軟骨である肋軟骨が存在する.第3~10肋骨では肋骨頭部に胸骨の肋骨窩との関節部である上下肋骨頭関節面が存在し,肋骨頭稜で境される.第1,2,11,12肋骨頭部では単一の肋骨頭関節面である.頸部の外側後方に肋横突関節部である肋骨結節が存在する.体部の尖端には肋軟骨との関節部分が存在する.第1肋骨体部上面には,鎖骨下静脈溝と前斜角筋結節が存在する.第2肋骨体部上面には前鋸筋による結節が存在する.
乳腺
著者: 五十嵐隆朗 , 戸崎光宏 , 福田国彦
ページ範囲:P.244 - P.248
正常解剖と生理的変化
乳房には,体表面から皮膚,皮下脂肪組織,浅在筋膜浅葉,乳腺,浅在筋膜深葉,乳腺後脂肪組織,大胸筋が順に存在する.成人女性の乳腺(図1)は約15~20の乳腺葉からなる.各乳腺葉の体積は均一ではない.乳腺葉は乳汁産生能を有する終末乳管小葉単位(terminal duct lobular units:TDLU)と乳汁を乳頭へ導く乳管からなる.各乳腺葉からの乳管がそれぞれ乳頭に開口するが,開口直前に紡錘状に拡張する領域がみられ,乳管洞と呼ばれる.生殖可能年齢にある女性の乳腺組織はエストロゲンとプロゲステロンに反応する.エストロゲンは新たな乳管形成や既存の乳管の延長などを促進し,これにより結合組織の量や弾力性が増加し,脂肪組織の沈着,血管分布の増大が生じる.プロゲステロンは小葉の形成を刺激する.乳腺実質は加齢とともに萎縮し,脂肪組織に置換され,周囲結合織の線維化がみられるようになる.
腹部 総論
読影の基本とポイント
著者: 齋田幸久
ページ範囲:P.250 - P.253
CTとMRIの使い分け
腹部には多数の臓器が存在し,肝,胆,膵,胃腸管,腎尿路系,骨盤生殖器系など,多彩である.想定される臓器と疾患によって,それぞれの検査の進め方は異なり,CT,MRIの使い分けも要求される.
国内には,X線CT装置が数多く備えられ,検査の施行とその診断評価が比較的簡便であることから,まずCTが選択される傾向にある.腹部全体を網羅的に把握して客観的に評価できる点で優れている.ただし,CTは常にX線被曝を伴う.CTによる腹部の被曝量は単純X線検査のおよそ10倍を優に超え,100倍に迫る.一方,MRIにX線被曝はなく,その濃度分解能はCTに比べ圧倒的に優れている.ただし,装置が高価で,しかも検査時間がCTに比べて長く,その画像評価もCTのように単純ではない.
各論
肝臓
著者: 塚原嘉典 , 角谷眞澄
ページ範囲:P.254 - P.262
正常解剖(図1)
右の上腹部で横隔膜下面の凹みに存在している.肝後面の上部はbare areaと呼ばれ,腹膜を欠くため,肝は横隔膜に接している.肝鎌状靱帯により大きく解剖学的左葉と右葉とに区分される.また,胆囊窩と下大静脈を結ぶ線(Cantlie's line)により外科的な左葉と右葉とに分けられ,この線上に中肝静脈が走行する.
門脈本幹は肝門部で右枝と左枝に分かれ,右枝はさらに前区域枝と後区域枝とに分かれる.肝動脈は,固有肝動脈から左肝動脈と右肝動脈とに分かれる.右肝動脈も前区域枝と後区域枝とに分かれ,肝内の動脈は門脈に伴走する.肝内胆管も門脈に伴走する.
脾臓・脾静脈
著者: 冨永理人 , 市川智章 , 荒木力
ページ範囲:P.263 - P.269
正常解剖
脾臓(spleen)は人体最大のリンパ性器官であり,腹腔内の左上隅の横隔膜と左腎の間に存在する.第9~11肋骨の高さにあり,その長軸は左第10肋間と平行している.形態はやや扁平な楕円形で,横隔膜面は凸面をなし,胃,膵尾部,左腎に向かう臓側面は凹面をなしている.また,脾門は臓側面にあり,脾動静脈と神経の出入り部位となる(図1).脾臓は,長さが約10cm,幅約7cm,厚さ約3cmで,重さは75~200gであり,15歳前後にピークに達する.
胆道:胆管・胆囊
著者: 香田渉 , 蒲田敏文 , 松井修
ページ範囲:P.270 - P.277
正常解剖
●胆道系の正常解剖(図1~4)
胆道とは,肝細胞から分泌された胆汁が十二指腸に流出するまでの全経路を指すが,胆道癌取扱い規約では肝外胆道系を意味し,肝外胆管,胆囊,乳頭部に区分される(図1)1).
肝外胆管は,肝門部胆管,上部胆管,中部胆管および下部胆管に区分される.肝門部胆管は,左側は外側区と内側区の合流部から,右側は前枝と後枝の合流部から左右肝管合流部下縁までとされ,さらに右肝管,左肝管,上部胆管で囲まれる部位は肝管合流部とされる(図2).上部および中部胆管は,肝門部胆管の下縁から膵上縁までの部分を2等分して区分され,下部胆管は膵上縁から十二指腸壁を貫通するまでの部分とされる.解剖学的には肝左葉から出た左肝管と右葉から出た右肝管が肝門部で合流し総肝管となり,その下方で胆囊管と合流し総胆管となるが(図3),胆道癌取扱い規約では,胆管の区分として総肝管,総胆管という解剖学的な名称は用いない.
膵臓
著者: 入江裕之
ページ範囲:P.278 - P.286
正常解剖と正常膵のCT・MRI
●正常解剖
膵は十二指腸下行脚~水平脚,上行結腸,下行結腸と同様,前腎傍腔に存在する後腹膜臓器であり(図1),内外分泌機能を有する腺組織である.膵癌取扱い規約では頭部,体部,尾部に分類され,門脈左縁より右側が膵頭部,左側が膵体尾部であり,さらに膵体尾部は二等分して体部と尾部に分けられる(図2).解剖学的にはその他,頸部,鈎部があり,頸部は上腸間膜静脈と脾静脈の合流部の腹側にあたる領域を指し,鈎部は頭部の左下縁で上腸間膜静脈の背側に位置する.頸部,鈎部ともに膵癌取扱い規約では頭部に含まれる.
膵頭部,体部は前面が壁側腹膜に覆われ,後面が前腎筋膜に隣接し,純粋に後腹膜に存在するのに対して,尾部は脾腎間膜内に存在し,前後面ともに腹膜で囲まれ,腹腔内に存在する.体尾部の前面には小網と呼ばれる腹膜腔が存在する.横行結腸間膜は頭部前面に付着して体尾部方向に横走し,小腸間膜は横行結腸間膜の後層から連続して頭部前面より起始し,鈎部前面を横走下行する(図3).これらの間膜は種々の膵病変の進展経路となるため重要である.
胃・十二指腸
著者: 水口昌伸 , 鈴木宗村 , 工藤祥
ページ範囲:P.287 - P.293
従来,胃・十二指腸に対するCT,MRI検査の主な目的は,消化管原発の悪性腫瘍(図1a)の他臓器浸潤や転移の術前評価と経過観察であった.近年,multidetector row CT(多列検出器CT:以下,MDCT)が普及し,高速で詳細なデータ収集が可能となり,種々の画像作成ソフトが開発されたことにより,ワークステーション上でのデータ再構築が可能となった.これにより,腸管の任意の断面の作成(図1b)や血管との重ね合わせ像(図1c)での観察など手術のシミュレーションに耐えうる画像が短時間で作成できるようになっている.また,立体視(いわゆるバーチャルエンドスコープ)が可能になり,検診への応用も検討されている.MRIにおいては撮像の高速化により空間および組織分解能が向上している.また,拡散強調像が腹部でも撮像可能となり,消化管の悪性腫瘍の検出や転移,播種病変の検出に有用である.
小腸・大腸・直腸
著者: 市川太郎
ページ範囲:P.294 - P.303
正常解剖
一般に消化管疾患の診断は,消化管造影や内視鏡によりなされる.それは,現代の消化管診断の主たる目的が早期の癌を見つけることにあるからである.しかしながら,消化管疾患の裾野は広く,CTあるいはMRIでの診断が優先される病変も数多い.さらに最近の断層画像の進歩は著しく,以前にはこれらの検査の適応と思われなかった病変に対しても施行され,一定の評価が得られているものもある.
小腸,大腸,直腸は,現在では特別の前処置や工夫を行わなくても断層画像での描出ができる.しかし,それは詳細に粘膜面が診断できるといった段階ではない.また,詳細に粘膜を診断するまでではないものの,消化管腫瘍の描出などを主たる検査目的とする場合は,あらかじめ下剤を投与する,消化管内にガスを注入しておく,造影剤を飲用させておくなどの前処置が行われることもある.しかしながら,他疾患の検索,腹部の不定愁訴,急性腹症などで検査を行う場合,前処置なしに施行されることが一般的であり,これらの検査で消化管疾患が見つかることも数多い.したがって,こういった通常の検査画像からでも消化管にも注意して読影する習慣が必要である.
腹膜・腸間膜
著者: 高司亮 , 松本俊郎 , 森宣
ページ範囲:P.304 - P.311
腹膜・腸間膜は,さまざまな腫瘍性病変および炎症性病変の重要な波及経路となりうることから,CTを中心とした画像診断を正確に行うには,これらの正常解剖の知識が必須となる.
腸間膜はその複雑な解剖学的特徴から,従来のCT横断像のみでは十分に評価ができないことも少なくなかった.近年,multidetector-row CT(MDCT)の普及により,1mm-sliceなどのthin-sliceでの多断面再構成像による評価が可能となり,各間膜や腹膜コンパートメントの認識が十分可能となった.
本稿では腸間膜の正常解剖とその代表的疾患について,主にMDCTで撮像された症例の供覧を中心に概説する.
副腎・後腹膜・腹部の大血管
著者: 後閑武彦
ページ範囲:P.312 - P.323
後腹膜腔は,前腎筋膜(anterior renal fascia),後腎筋膜(posterior renal fascia),外側円錐筋膜(lateroconal fascia)により3腔に分けられる(図1).腎周囲腔(perirenal space)は,前腎筋膜と後腎筋膜で囲まれる腔であり,腎,腎周囲脂肪組織,副腎を入れる.前腎筋膜と後腎筋膜は外側で外側円錐筋膜に移行する.前腎傍腔(anterior pararenal space)は,壁側腹膜と前腎筋膜,外側円錐筋膜で囲まれた領域で,膵,上行・下行結腸,十二指腸の下行・水平・上行脚が含まれる.後腎傍腔(posterior pararenal space)は,腹側を後腎筋膜と外側円錐筋膜で,背側を腹横筋膜で囲まれた領域であり,脂肪組織のみで実質臓器は含まない(図2).
副腎は,右側は右腎上極のやや上方で,下大静脈後方,肝右葉内側,右横隔膜脚の外側に位置する.左副腎は左腎前内側で,膵尾部の後方,左横隔膜脚の外側に位置する.左副腎は右側に比べ,やや下方に位置する.副腎はCTやMRIの横断像で逆Y字型,逆V字型,三角形,線状,三射状などの形態を示すが,頭側では線状,中央部では逆Y字型,尾側では逆V字~三射状を示すことが多い(図3).MRIではT1強調像で肝と同程度かやや低信号,T2強調像で肝とほぼ等信号を示す(図4).
腹部大動脈は,大動脈裂口部から左右の総腸骨動脈に分岐するまでをいう.主な分枝として,第12胸椎下縁から第1腰椎の高さで腹腔動脈,続いて上腸間膜動脈,左右の腎動脈,下腸間膜動脈を分枝する.下大静脈は左右の総腸骨静脈が第4~5腰椎の高さで合流し,椎体の右前方を走行し,右心房に合流する(図5).
腎臓
著者: 秋田大宇 , 陣崎雅弘
ページ範囲:P.324 - P.332
正常解剖(図1,2)
腎臓は後腹膜に位置する代表的臓器の1つである.後腹膜のなかで脂肪組織に包まれており,それを腎周囲腔と呼ぶ.腎周囲腔の前後には前傍腎腔と後傍腎腔があり,それぞれGerota筋膜前葉とGerota筋膜後葉により腎周囲腔と境されている.
腎臓は通常左右1個ずつ存在し,右腎は左腎より尾側に位置する.しかし,片腎の先天性欠損や馬蹄腎(左右の腎臓が腹部大動脈,下大静脈の前方で癒合,図3)などの正常変異もある.また,骨盤腎や胸腔内腎など位置の変異を認める場合もある.さらに腎動静脈が流入,流出する腎門は通常前方内側を向いているが,回転異常によりさまざまな方向を向くことがある.特に腹側を向くことが多い.
尿管・膀胱
著者: 稲田悠紀 , 松木充 , 鳴海善文
ページ範囲:P.333 - P.339
正常解剖
●尿管
尿管は腎盂から連続する長さ約30cm,径約5mmの管腔臓器である.大腰筋の腹側を下内側に走行し,生殖(卵巣,精巣)動静脈の背面を横走する.小骨盤腔では総腸骨動脈と交叉して腹側を通り,仙腸関節付近まで下行すると正中方向に曲がり,膀胱後壁を正中から約2.5cmのところで斜め前方に貫いて終わる.尿管には生理的狭窄が3カ所〔①腎盂尿管移行部(ureteropelvic junction:UPJ),②総腸骨動静脈との交叉部,③尿管膀胱移行部(ureterovesical junction:UVJ)〕存在し,尿管結石が嵌頓しやすい部位である(図1).
子宮
著者: 安藤理奈 , 藤谷哲也 , 今岡いずみ , 村上卓道
ページ範囲:P.340 - P.346
正常解剖
●一般的事項
子宮は膀胱背側,直腸腹側に位置している.子宮を覆う腹膜(=子宮広間膜)は,膀胱子宮窩と直腸子宮窩(=Douglas窩)という2つの腔を形成する.この腔は腹水が貯留するスペースとして,あるいは悪性腫瘍の腹膜播種をきたす部位として重要である.
子宮は西洋梨型で,子宮体部,子宮頸部および両者の移行部である子宮峡部からなる.
卵巣
著者: 田村綾子
ページ範囲:P.347 - P.357
正常解剖
●解剖
卵巣は子宮の両側に1つずつ認められる.卵巣窩は外腸骨動静脈の腹側,尿管の背側に位置する.卵巣は卵巣固有索,卵巣提索,卵巣間膜により支持されている.子宮広間膜の背側で,子宮角の卵管付着部に卵巣固有索(ovarian ligament)によって付着する.広間膜は外側で卵巣提索(suspensory ligament)となって骨盤壁に達し,卵巣を保持する.卵巣動静脈や神経はここを通る.卵巣間膜(mesovarium)は卵巣腹側を覆う二重の腹膜で,卵巣前縁から広間膜後葉に連続する.卵巣間膜の卵巣への付着部が卵巣門であり,血管と神経,リンパ管が通る.卵巣門以外の卵巣表面は腹腔に露出している.
卵巣は大動脈から直接分枝する卵巣動脈,子宮動脈卵巣枝の2つの動脈血流が流入する.卵巣動脈と子宮動脈は卵巣間膜内で吻合する.卵巣静脈は動脈に伴走する.広間膜内で子宮静脈と吻合し,右卵巣静脈は下大静脈へ,左卵巣静脈は左腎静脈へ流入する.
卵巣は卵胞を含む表層部の皮質と血管の豊富な中心部の髄質からなり,白膜に覆われる.皮質には卵胞のほかに豊富な間質も含む.生殖可能年齢では皮質が大部分を占める.
前立腺・男性生殖器
著者: 北島一宏 , 楫靖
ページ範囲:P.358 - P.364
正常解剖およびCT/MRIでの正常像
男性生殖器の疾患に対しては,CTよりも軟部組織コントラスト分解能に優れ,被曝もないMRIが用いられることが多い.本稿もMRIを中心に概説する.
腹壁・骨盤壁
著者: 吉松俊治 , 浅尾千秋
ページ範囲:P.365 - P.370
正常解剖
腹壁を構成する浅腹筋には外側群の側腹筋と内側群の前腹筋がある.前腹筋には前腹壁の正中部に左右の腹直筋があり,恥骨からでて白線内に入り込む小さい錐体筋がある.側腹筋は浅層より外腹斜筋,内腹斜筋,腹横筋の3層の筋群よりなり,上中腹部では脂肪により3層の分離は良好であるが,下腹部では分離が不良となる.
側腹筋はその広い面状をなす腱膜で両側の腹直筋を包み,固有の結合組織である腹直筋鞘を形成する.腹直筋上部中部では,外腹斜筋腱膜は腹直筋鞘前葉を,内腹斜筋腱膜は前後に分かれて前葉と後葉を,腹横筋腱膜は腹直筋鞘後葉を形成する.臍輪より数cm下方の腹直筋下部では,側腹筋腱膜はすべて腹直筋鞘前葉を形成し,後葉は欠如する.腹直筋鞘後葉の消失する部分が弓状線である(図1).
腰椎・腰筋
著者: 堀正明 , 寺田一志 , 荒木力
ページ範囲:P.371 - P.377
正常解剖
腰椎に限らず,脊椎の解剖は大きく前方成分(椎体および椎間板),後方成分(椎弓や関節突起),脊椎周囲組織(周囲の筋など)に分けて考えると理解しやすい(図1).腰椎は5つの椎体からなる.また,頸椎,胸椎レベルと異なり,脊髄はL1~2レベルまで脊髄円錘となり,それより尾側では馬尾が連続する.椎体の両側に大腰筋を認め,後方成分背側には棘筋や胸最長筋を認める.
骨軟部 総論
読影の基本とポイント
著者: 新津守
ページ範囲:P.380 - P.383
骨病変の画像診断の第一選択は,単純X線写真であることに異論はないであろう.近年では超音波が高性能化し,単純X線写真では描出されない肋骨などの骨折を超音波で描出する試みも報告1)されているが,その普及(多くは整形外科医が外来で実施すると思われる)には今しばらく時間がかかりそうである.また,微細な骨折線や椎骨や手足の骨,顔面骨など複雑な形状の骨の骨折描出にはCT,特にMDCTによる薄スライスや多方向再構成画像が有用なのは周知のことと思われる(図1).
本稿ではMRIについてその有用性,撮像法の工夫について述べる.
各論
肩関節の解剖
著者: 野崎太希 , 新津守 , 齋田幸久
ページ範囲:P.384 - P.389
肩関節(肩甲上腕関節)は西洋梨状の陥凹をもつ関節窩(glenoid fossa)と,その約3倍の関節軟骨の広がりをもつ上腕骨頭(humeral head)から構成される球関節である.生体内において最大の可動域をもつことが特徴であるが,関節窩が上腕骨頭に対して小さく,関節の不安定性があることが弱点であり,最も脱臼を起こしやすい関節となっている.そのために関節唇(glenoid labrum),上腕骨頭の約2倍の表面積をもつ関節包,関節上腕靱帯をはじめとする靱帯,腱板(rotator cuff)などの軟部組織が補強・支持する構造となっている.表層にあり,触れることのできる筋肉をアウターマッスル,深層にある筋肉をインナーマッスルと呼ぶ言い方があるが,肩関節において腱板を構成する筋肉はインナーマッスルに相当し,関節のstabilizerとして機能している.ほかの関節とは異なるこういった特徴を有するために,一般的に肩関節の解剖,MRIの読影は難しい印象をもたれている.したがって,本稿では肩関節のMRI解剖においてポイントとなる構造について解説する.
肩関節の疾患
著者: 佐々木泰輔 , 山本祐司
ページ範囲:P.390 - P.395
一般的に関節疾患はMRIのよい適応だが,筆者のまわりの画像診断医には肩関節のMRIを不得手とする者が多い.その原因を推定すると,まず解剖がやや複雑で正常変異も多いこと,膝などに比べると構造が小さく損傷機序も複雑なこと,などが挙げられる.
本稿では,肩MRIの読影の基本について簡潔に説明したい.取り上げる疾患も,腱板損傷,脱臼,スポーツ外傷に限定し,損傷の細かな分類や亜型についてはあえて触れないのでご容赦いただきたい.なお,提示する症例は関節鏡や手術で診断が確認されたものである.
手関節
著者: 植野映子
ページ範囲:P.396 - P.401
MRI正常像と手の関節の解剖,機能
手の関節は多数の関節により構成される(表1).「手関節」と「手の関節」はあくまで別の名称であり,「手関節」とは橈骨手根関節,手根間関節,豆状三角骨関節を一括したもの,「手の関節」は手のなかにあるすべての関節のことである.手関節の運動は屈曲(掌屈),伸展(背屈),外転(撓屈),内転(尺屈)のほか,回外・回内運動が加わることが特徴的である.指関節などをはじめとして高い巧緻性が求められる関節でもある.個々の関節の構成は非常にシンプルであるが,多数の関節が集合することで巧緻運動を可能にしている.別の見かたをすれば,狭い領域に多数の構造がひしめく関節でもあり(図1~3),解剖はとっつきづらい印象が否めないかもしれない.
股関節
著者: 中西克之
ページ範囲:P.402 - P.409
股関節は,球形の大腿骨頭とそれを包み込む臼蓋で強固に結合する最大の関節である.寛骨臼と臼蓋唇により骨頭の2/3が包み込まれ,ball and socket constitutionとも呼ばれる.関節可動域は肩関節に比べて制限されるが,関節の安定性と体重の支持において重要な役割を果たしている.近年,高精細なMRIやCTで詳細な画像が得られるようになり,画像診断を施行するにあたり,関節の特性と正確な解剖知識を得ておく必要がある.図1に高精細MR像とシェーマの対比を示す.
上述したように大腿骨頭の2/3が臼蓋唇により包み込まれるため,関節裂隙は狭く,大腿骨頭側の関節軟骨と臼蓋側の関節軟骨が分離してみえないこともしばしばある.本例では股関節を牽引して関節裂隙を広げ,両側関節軟骨を分離して描出していることに留意されたい.MRIで脂肪抑制画像を用いると関節軟骨が高信号に描出され表面を追跡しやすくなる.臼蓋と大腿骨頭を結合させる役割で大腿骨頭靱帯がある.臼蓋側ではその靱帯の周囲に月状窩と呼ばれる脂肪が存在し,関節軟骨は存在しない.臼蓋の辺縁部分に関節唇が存在する.関節唇は膝関節における半月板と同様,線維軟骨であり,低信号に描出され,楔状の構造を呈する.
膝関節の解剖
著者: 稲岡努
ページ範囲:P.410 - P.414
正常解剖
膝関節は人体最大の加重関節であり,最大の長管骨である大腿骨と次に大きい脛骨によって構成される.また,前方には最大の種子骨である膝蓋骨が関節包内に存在し,大腿骨と膝蓋大腿関節を形成している.脛骨の外側部には腓骨が位置するが,関節包内には存在しない.大腿骨遠位端と脛骨近位端の関節面には硝子軟骨からなる厚い関節軟骨が広がっている.膝蓋大腿関節は外側部に広いV字状を呈し,関節面には同様に厚い関節軟骨が広がっている.
膝関節内および周囲には多くの軟部支持組織が存在する.内側側副靱帯,外側側副靱帯を含む外側支持組織,前・後十字靱帯,半月板が臨床的に重要である.内側側副靱帯は,膝関節の内側部を縦走する靱帯であり,浅層と深層とに分けられる.浅層は大腿骨内顆から起こり,脛骨骨幹端の内側部に付着する.深層は浅層の直下に存在している.深層は内側半月板辺縁と強固に付着し,半月板と大腿骨,半月板と脛骨とを結ぶため,それぞれmeniscofemoral ligament,meniscotibial ligament とも呼ばれる(図1).また,膝関節内側部の表層には縫工筋,薄筋,半腱様筋腱,半膜様筋腱が下降し,脛骨上端の内側部に付着している(図2).膝関節外側部には,外側側副靱帯を含めた外側支持組織が存在し,内側部と比べて複雑な構造になっている.外側側副靱帯は,大腿骨外顆から腓骨頭へと広がり,下端は関節包から離れている.その表層では前方に腸脛靱帯,後方には大腿二頭筋腱が下降し,脛骨外側部および腓骨頭に付着している(図3).
膝関節の疾患
著者: 神島保
ページ範囲:P.415 - P.419
変形性関節症(図1)
変形性関節症は軟骨の軟化に始まる疾患である.関節構造とそれにかかる荷重のバランスが崩れることにより生じる.初期の病理は関節軟骨の変性とそれに伴う修復像であり,軟骨細胞の消失と細線維化や軟骨細胞集合化が認められる.さらに進むと軟骨に裂隙が生じ,軟骨欠損部に線維軟骨が形成される.軟骨が完全に磨耗すると関節裂隙は狭小化し,軟骨下骨が露出,軟骨下骨の硬化,骨内囊胞形成が画像で認められる.骨棘や遊離体形成も特徴的である.滑膜に強い炎症を伴うことは稀である.
軟部腫瘍
著者: 玉川光春 , 晴山雅人
ページ範囲:P.420 - P.434
正常解剖
大腿・下腿の横断像を示す(図1,2).大腿の筋を含む大腿筋膜は,外側で厚く腸脛靱帯を形成する.鼠径部で大腿前面の大腿筋膜の穴が伏在裂孔で,大伏在静脈などが通過する.大腿筋膜の内外後側から大腿骨に向かい,内側筋間中隔と外側筋間中隔,半膜様筋と大内転筋を分ける3枚の中隔が存在する.これにより,筋は前方,後方,内側筋膜区分に分けられる.前方には伸筋群である大腿四頭筋(大腿直筋,内側広筋,外側広筋,中間広筋)と縫工筋,後方には屈筋群(ハムストリング)である大腿二頭筋,半腱様筋,半膜様筋,内側には内転筋群の薄筋,恥骨筋,短内転筋,長内転筋,大内転筋が存在する.大腿動脈は前方筋膜区分内にあり,坐骨神経は後方筋膜区分内にある.
下腿の筋膜は大腿筋膜が膝窩筋膜となり,連続的に下腿筋膜に移行する.下腿筋膜は前後筋間中隔が腓骨に付着し,脛骨と腓骨の間の骨間膜で前方,外側,後方筋膜区分に分かれる.後方筋膜区は深横筋膜で,浅層筋群と深層筋群に分かれる.前方には伸筋群の前脛骨筋,長指伸筋,長母指伸筋があり,前脛骨動静脈,深腓骨神経が含まれ,外側では腓骨筋群の長・短腓骨筋,腓骨動脈からの枝,浅腓骨神経が含まれる.後方筋膜区分は深横筋膜により分けられ,浅層筋群には下腿三頭筋(腓腹筋,ヒラメ筋)と足底筋,深層筋群には膝窩筋,後腓骨筋,長母指屈筋,長指屈筋があり,後脛骨動静脈,腓骨動静脈,脛骨神経が含まれる.
骨腫瘍
著者: 高尾正一郎 , 原田太平 , 上野淳二
ページ範囲:P.435 - P.442
骨腫瘍の診断は年齢・性別などの臨床情報と単純X線所見が重要であるが,近年はこれに加えてCTおよびMRIが広く応用されるようになった.これらの画像診断は,単純X線写真で描出困難な病変の発見や,病変範囲の正確な決定およびstaging,病変の質的診断に有用な情報を提供する.本稿では,MRIを中心に骨腫瘍の診断における画像診断の応用を述べる.
基本情報
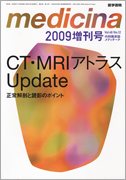
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
