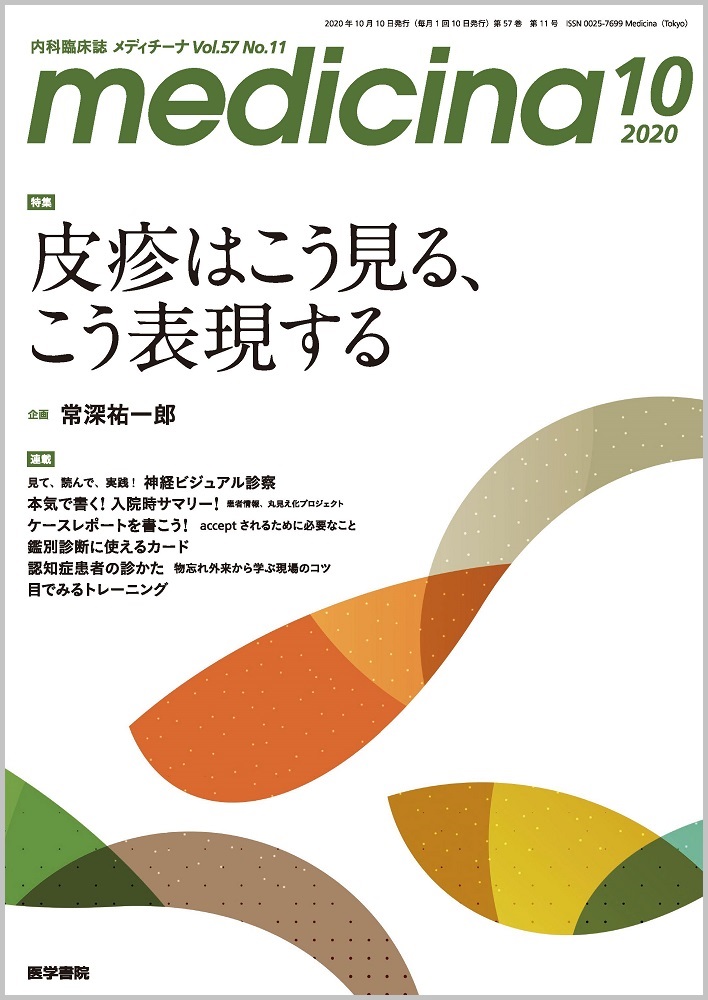文献詳細
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
よく見る皮膚疾患を発疹レベルで理解する 〈血管・血流障害〉
文献概要
▶疾患の概要
定義 本疾患は1806年Heberdenが最初に報告し,のちにSchönleinが関節痛との関連性を,またHenochが消化器症状と腎障害の合併を報告したことで疾患概念が確立し,Henoch-Schönlein紫斑病と呼称されていた1).真皮小血管や腎糸球体にIgAや補体が沈着し,患者血中にIgA抗体の免疫複合体が存在することが証明され,原発性血管炎の名称と定義についての合意形成を目的としたChapel Hill Consensus Conferenceにおいて1994年に公表されたChapel Hill分類(CHCC1994)でその定義が示された2).2012年の改定Chapel Hill分類(CHCC2012)ではeponymが排除されたために,IgA血管炎へ名称変更された3).この分類では,“IgA1抗体優位の免疫複合体の沈着を伴い,小血管特に毛細血管,細静脈,細動脈に及ぶ血管炎で,もっぱら皮膚や消化管を侵し関節炎を生じ,IgA腎症と区別をつけがたい糸球体腎炎を生じることがある”とされ3),免疫複合体性小型血管炎に分類された.IgA血管炎による腎障害は紫斑病性腎炎と呼称されている.
疫学 IgA血管炎は上気道感染が先行することが多く,それを反映してか秋から冬に多い.小児に多く4〜7歳がピークであり,男女比は1.2〜1.8とされる.発症率は小児で10万人につき約20人,成人で約1〜2人である.
定義 本疾患は1806年Heberdenが最初に報告し,のちにSchönleinが関節痛との関連性を,またHenochが消化器症状と腎障害の合併を報告したことで疾患概念が確立し,Henoch-Schönlein紫斑病と呼称されていた1).真皮小血管や腎糸球体にIgAや補体が沈着し,患者血中にIgA抗体の免疫複合体が存在することが証明され,原発性血管炎の名称と定義についての合意形成を目的としたChapel Hill Consensus Conferenceにおいて1994年に公表されたChapel Hill分類(CHCC1994)でその定義が示された2).2012年の改定Chapel Hill分類(CHCC2012)ではeponymが排除されたために,IgA血管炎へ名称変更された3).この分類では,“IgA1抗体優位の免疫複合体の沈着を伴い,小血管特に毛細血管,細静脈,細動脈に及ぶ血管炎で,もっぱら皮膚や消化管を侵し関節炎を生じ,IgA腎症と区別をつけがたい糸球体腎炎を生じることがある”とされ3),免疫複合体性小型血管炎に分類された.IgA血管炎による腎障害は紫斑病性腎炎と呼称されている.
疫学 IgA血管炎は上気道感染が先行することが多く,それを反映してか秋から冬に多い.小児に多く4〜7歳がピークであり,男女比は1.2〜1.8とされる.発症率は小児で10万人につき約20人,成人で約1〜2人である.
参考文献
1)渕上達夫:IgA血管炎.日本臨牀75:993-997, 2017
2)Jennette JC, et al:Nomenclature of systemic vasculitides. Arthritis Rheum 37:187-192, 1994
3)Jennette JC et al:2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum 65:1-11, 2013
4)川名誠司,陳 科榮:第5章 皮膚血管炎へのアプローチ.皮膚血管炎,p54,医学書院,2013
5)有村義宏:血管炎症候群.成人病と生活習慣病47:1150-1156, 2017
6)川上民裕:IgA血管炎(旧名Henoch-Schönlein紫斑病).宮坂信之(編):別冊日本臨床 新領域別症候群シリーズNo.34 免疫症候群(第2版)Ⅰ,pp799-803,日本臨牀社,2015
掲載誌情報