一口に医師といってもさまざまなありようだ.専門分野の多様性は言うまでもなく,働く場所においても,開業医,地域病院の医師,あらゆる分野の医師を抱え最先端を自負する大規模病院,そして大学病院がある.腎臓内科の中の一専門分野においても,基礎研究者,統計を扱う疫学の研究者,臨床医などさまざまである.さらに時代によって急激な変化があり,その変化の速度は増している.地域病院の中で腎臓内科医として働いている一臨床医を取り上げてみても,腎臓内科の中の多くの分野,移植,血液透析,腹膜透析,手術関連,腎病理,水電解質などの中の一分野のみに特化している医師は少なく,さらに腎臓内科のみに特化せず,腎臓・内分泌科,腎臓・糖尿病科,腎臓・膠原病・感染症科,腎臓・循環器科,腎臓・血液内科などを標榜し,二股三股もかけて働いている人が少なくない.化学療法の進歩によって腫瘍科との連携も必要とされるようになってきている.また,昨年からはCOVID-19によって思いがけない変化が起きている.COVID-19対策も引き受けてその中心になって働いている医師も多いのではないか.COVID-19時代の真っ只中にあって今までと変わりなく目の前の患者さんに没頭して忙しく日々を過ごしているうちに,気がついてみると浦島太郎になっていたということになりはしないだろうかと,ふと心配になることもあるのは私だけであろうか.
一医師に与えられた時間は限られている.生活もある生身の人間だ.今までは治療法がなく見落としていても患者さんに不利益はなく,逆に診断できても患者さんにとってあまり利益はないという病気が最近の進歩で治るようになった,かつては「見落としてもよかった病気」が今や「見落としてはいけない病気」になった,また原因不明であった病気に「病名」がつけられ治療法が与えられた,などという情報をいかにつかむか.そういう情報が気軽に入る環境をいかに作るか.目の前の患者さんに没頭して日々過ごしていても最新情報を自然に簡単に短時間で知りたいという医師は多いのではないか.競争社会であっても医療現場においては競争原理を働かせずに情報と知識を分かち合う臨床現場であってほしい.患者さんに役に立ち治療に応用できる実践的知識および具体的な治療法を知り,患者さんにより役に立つ臨床医でありたいと願う医師,現場が忙しくても基本と進歩を理解し患者さんに還元する喜びがほしいという医師をわかりやすく助けてくれる雑誌が欲しい.
雑誌目次
medicina58巻10号
2021年09月発行
雑誌目次
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
扉 フリーアクセス
著者: 藤田芳郎
ページ範囲:P.1502 - P.1503
腎機能の評価
腎機能のさまざまな評価法,また腎機能障害を早期に診断するための新たなバイオマーカーについて教えてください
著者: 藤田陽子 , 今井直彦
ページ範囲:P.1508 - P.1511
Point
◎血清クレアチニン(Cr)やeGFRcreat(クレアチニンによる推定糸球体濾過量)は,筋肉量や蛋白質摂取量によって変化しうるが,シスタチンCやeGFRcys(シスタチンCによる推定糸球体濾過量)はそれらの影響を受けにくい.
◎eGFRcreat値は,慢性腎臓病の重症度分類に用いるために算出する値であり,各個人の体型にあったGFR推定値ではない.よって,薬物投与設計では用いない.
◎Cockcroft-Gault式による推定クレアチニンクリアランス(CCr)は,各個人の体型にあったCCr推定値となるため,薬剤投与設計で用いられる.
急性腎障害の診断と治療
血清クレアチニン上昇をみたときどう行動すべきでしょうか? 急性腎障害の予防,診断,治療のコツを教えてください
著者: 森久保悟 , 今井直彦
ページ範囲:P.1512 - P.1516
Point
◎腎機能障害をみた際は,腎形態,尿量推移,体重推移,直近のクレアチニン推移などから急性腎障害(AKI)と慢性腎臓病(CKD)を鑑別する.
◎緊急透析の適応は,各種パラメーター(代謝性アシドーシス,高カリウム血症,心不全など)だけでなく,その後の臨床経過を予想し判断する.
◎AKIの治療の基本は,腎機能が改善するまで,血圧・体液量を適正に保ち続けることである.
高血圧
高血圧の治療目標,具体的な治療・薬剤選択について教えてください
著者: 平和伸仁
ページ範囲:P.1517 - P.1520
Point
◎高血圧の治療目的は,脳心血管病の発症や死亡を減らし,患者の生命予後に加えてQOLを改善させることである.
◎降圧目標は,既存の疾患の有無により異なり,75歳未満の成人では130/80 mmHg未満である.
◎高血圧の治療は,生活習慣の修正(非薬物療法)および薬物療法により行う.
◎血圧が高くなくても生活習慣を適正化することにより,高血圧の発症を予防することが大切である.
◎積極的な適応となる病態がなければ,降圧薬はCa拮抗薬,アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB),アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬,あるいは少量の利尿薬を第一選択薬として用いる.
二次性高血圧の原因として多い原発性アルドステロン症を非専門医が見落とさないようにするコツとその治療を教えてください
著者: 尾関良則 , 柴田洋孝
ページ範囲:P.1521 - P.1524
Point
◎原発性アルドステロン症の早期診断のためには,有病率の高い疾患群において積極的なスクリーニング検査が重要である.
◎スクリーニング検査が陽性であれば機能確認検査を実施する.機能確認検査のなかでカプトプリル負荷試験は簡易かつ短時間で実施できるため外来でも実施可能である.
◎血中アルドステロン濃度測定が2021年4月から新規検査法に変更となったため,カットオフ値の見直しなど今後の対応が求められる.
◎薬物療法において,ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬は現在3剤使用可能であり,2型糖尿病患者において腎機能障害の進行抑制が期待できる新たなMR拮抗薬が現在臨床試験中である.
よく出会う糸球体疾患の治療の実際
IgA腎症の診断と治療の実際を教えてください
著者: 片渕律子
ページ範囲:P.1525 - P.1528
Point
◎IgA腎症は,腎生検によってのみ診断され,糸球体へのIgAの優位な沈着がみられる腎炎と定義される.
◎IgA腎症の治療法は臨床病理学的重症度,組織の活動性に応じて個別に決定する.
◎一日尿蛋白>0.5 gかつ尿中赤血球>10/HPFを呈し,活動性病変を有する症例には積極的にステロイドパルス療法を行う.
◎上気道炎後に肉眼的血尿を繰り返す症例には扁桃摘出術を考慮する.
膜性腎症の診断と治療の留意点は何でしょうか?治療開始時期など具体的な治療のコツを教えてください
著者: 横山仁 , 古市賢吾
ページ範囲:P.1529 - P.1532
Point
◎膜性腎症の77.9%が一次性であり,一次性ネフローゼ症候群の36.8%を占め,高齢層での発症頻度が高い.
◎係蹄上皮細胞上のM型ホスホリパーゼA2受容体などの各種自己抗原とそれに対する抗体の同定が診断において重要である.
◎自己抗体力価は治療効果の判定に有用であり,治療抵抗性を推測するうえでは抗体サブクラス(IgG4優位性)および補体活性化経路(レクチン経路の活性化)が参考になる.
◎レニン・アンジオテンシン系阻害薬などを含む支持・保存的療法もしくはステロイド単独あるいは免疫抑制薬併用のいずれかを臨床病理学的所見に基づき開始する.
ネフローゼ症候群に対する生物学的製剤の治療の適応と効果について教えてください
著者: 勝野敬之
ページ範囲:P.1533 - P.1537
Point
◎ネフローゼ症候群は,大量の尿蛋白漏出と低蛋白(低アルブミン)血症を特徴とする症候群である.急性腎障害を呈する症例も多く,浮腫,脂質異常症,血栓症,易感染性などさまざまな病態を合併する.
◎ネフローゼ症候群はステロイド治療を基本とするが,易再発性,依存性および抵抗性によるステロイド積算使用量の増大が懸念される.またシクロスポリンの長期使用による腎毒性も問題点である.
◎頻回再発型/ステロイド依存性の微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS)に対し,リツキシマブは再発回数の減少やステロイドおよび免疫抑制薬の減量を可能とする.
◎膜性腎症に対するリツキシマブの寛解導入効果が臨床試験などで報告されており,治療選択肢の一つとなりうる.
◎ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ治療は,長期的な治療戦略や安全性など今後明らかにされるべき点も多い.日常臨床においては,保険適用にも留意して診療に当たる必要がある.
糖尿病と腎障害
糖尿病性腎臓病(DKD)の診断と最新治療について教えてください
著者: 滝山由美
ページ範囲:P.1538 - P.1541
Point
◎糖尿病性腎臓病(DKD)の診断には,尿中アルブミン,eGFR(シスタチンC)を測定し,尿検査を施行(沈査を含む),糖尿病網膜症併発の有無から,まずは,non-DKDの鑑別診断後,腎症病期を確定する.
◎糖尿病性腎臓病には,正常アルブミン尿を呈しながら,eGFRが急速低下する非典型例が存在するため,eGFRの経過観察が重要である.加齢,高血圧,動脈硬化,脂質異常症などが病態に関与する.
◎血糖コントロールは,網膜症,神経障害など糖尿病性細小血管障害の予防・進行阻止に重要であるが,腎症に対しては,降圧薬,RAAS阻害薬,SGLT2阻害薬などの腎血行動態改善を標的にした治療がより効果的と言える.
感染症
腹膜透析における腹膜炎の診断と治療について教えてください
著者: 伊藤恭彦 , 鬼無洋
ページ範囲:P.1542 - P.1545
Point
◎初期対応として重要なことは,細菌学的検査のための検体を採取したら,その結果を待たず早期より治療を始めることである.
◎適切な抗菌薬を推奨された期間投与する.
◎診断に苦慮する内因性腹膜炎,結核性腹膜炎,真菌性腹膜炎の予後が悪いので注意する.
◎腹膜炎の予防,特に内視鏡前の予防投与を忘れないようにする.
腎移植における感染管理についての最新情報(ワクチンなども含めて)を教えてください
著者: 嶋田啓基 , 長浜正彦
ページ範囲:P.1546 - P.1549
Point
◎腎移植後感染症の診療に際しては,移植後の時間によって変化する免疫抑制状態の変化(net state of immunosuppression:NSI)と,それに関連する疫学的特徴(epidemiologic exposure)を把握することが重要となる.
◎ワクチン接種による感染症予防が腎予後や生命予後を改善することが示されており,適切な時期にワクチン接種を行うことが重要である.
◎移植後特有の感染症(CMV感染症,BKV腎症,尿路感染症)について理解し,早期診断,早期治療を行う必要がある.
膠原病
強皮症診療の基本と腎クリーゼの対処について教えてください
著者: 桑名正隆
ページ範囲:P.1550 - P.1554
Point
◎全身性強皮症を早期に捉えるための徴候としてRaynaud現象,手指腫脹,爪郭毛細血管異常,爪上皮出血点がある.
◎全身性強皮症の臓器障害や予後の予測にはびまん皮膚硬化型,限局皮膚硬化型の病型分類が用いられる.
◎腎クリーゼのリスク因子として罹病期間4年以内の早期びまん皮膚硬化型,抗RNAポリメラーゼⅢ抗体,先行する心疾患やステロイド投与がある.
◎アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬の導入により腎クリーゼの短期死亡は減少したが,さらなる予後改善には早期診断,治療介入が不可欠である.
見逃しやすいSAPHO症候群の診断と最新治療について教えてください
著者: 岸本暢将 , 辻成佳
ページ範囲:P.1556 - P.1559
Point
◎SAPHO症候群は,Synovitis-Acne-Pustulosis-Hyperostosis Osteitisの頭文字をとったさまざまな疾患を含む概念で,皮膚所見に加え,特に前胸部(胸部・鎖骨を中心)に生じる無菌性の硬化性もしくは肥大性骨関節病変を引き起こす.
◎本邦では皮膚症状の80%以上が掌蹠膿疱症であり,その治療薬として生物学的製剤のIL-23阻害薬が2018年SAPHO症候群の亜型である掌蹠膿疱症(PPP)/掌蹠膿疱症性骨関節炎(pustulotic arthro-osteitis:PAO)に対して世界で初めて使用可能となった.
全身性エリテマトーデス診療の基本と最新治療を教えてください
著者: 木戸口元気 , 岡田正人
ページ範囲:P.1560 - P.1565
Point
◎膠原病診療の基本は「病態診断→除外診断→臨床診断→治療・フォローアップ」である.
◎臨床経過,検査所見から,腎組織型を予測する.ループス腎炎の組織型に応じて,免疫抑制治療の適応を判断する.
◎活動性のループス腎炎に対するベリムマブの有用性を証明した大規模RCTが2020年に報告された.標準療法への追加が検討される.
ANCA関連血管炎(GPA,MPA,EGPA)の診療の基本と最新治療を教えてください
著者: 田巻弘道
ページ範囲:P.1566 - P.1570
Point
◎ANCA関連血管炎は多発血管炎性肉芽腫症(GPA),顕微鏡的多発血管炎(MPA),好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)の3つを含む疾患概念であり,中〜小型の壊死性血管炎である.
◎GPAでは中〜小型の壊死性血管炎に加えて,血管外の壊死性肉芽腫性炎症が特徴的であり,EGPAは中〜小型の壊死性血管炎に加えて,好酸球性の炎症を伴うことが特徴的である.
◎ANCA関連血管炎の診断においては,同様の症状を呈するような感染症の除外が重要となってくる.
◎GPAとMPAは,同様の薬剤を用いて治療をされるのに対して,EGPAはこれら2疾患とは異なる薬剤を用いて治療することもある.
◎GPA/MPAに対してC5a受容体拮抗薬は効果が期待でき,今後ステロイドを用いない治療もできるようになってくる可能性がある.
IgG4関連疾患の診断と最新の治療について教えてください
著者: 水島伊知郎 , 川野充弘
ページ範囲:P.1572 - P.1578
Point
◎IgG4関連疾患(IgG4-RD)は,多くの臓器を標的とし,高度な免疫細胞浸潤かつ/もしくは線維化により臓器機能障害をきたす慢性全身性疾患である.
◎IgG4-RDでは,唾液腺,涙腺・眼窩,膵臓,胆道,後腹膜・動脈周囲,肺などに加え,腎臓も主要な罹患臓器であり,IgG4関連腎臓病(IgG4-RKD)と呼ばれる.
◎IgG4-RKDの診断は,臨床像,血清所見,画像所見,病理所見などを総合的に勘案して行う必要があり,わが国のIgG4-RKD診断基準や,ACR/EULAR分類基準を用いる.
◎IgG4-RKDはステロイド治療に良好に反応するが,治療前の腎機能障害の改善は一定程度にとどまり,慢性の機能障害を遺しうる.
痛風の尿酸降下療法:薬剤選択と血清尿酸値の治療目標値について教えてください
著者: 谷口敦夫
ページ範囲:P.1580 - P.1584
Point
◎病因について,「痛風は高尿酸血症の合併症の一つである」あるいは「痛風は尿酸塩結晶による関節炎を繰り返す疾患である」という考え方では,痛風における尿酸降下療法の意義は理解しにくい.
◎「痛風は関節内に尿酸塩結晶が持続的に沈着する疾患である」という考え方に基づき,痛風の尿酸降下療法を進めるのが適切である.
◎薬物による尿酸降下療法では,適応症例の選択,治療目標値,薬剤の選択,治療開始時期,治療期間を考慮する必要がある.
補体関連疾患
補体の基礎および補体関連疾患の診断と抗補体薬による最新の治療について教えてください
著者: 堀内孝彦
ページ範囲:P.1586 - P.1589
Point
◎補体を選択的に阻害する抗補体薬が次々に開発されている.
◎抗補体薬の適応疾患が広がるに伴って,補体関連疾患という疾患概念が確立されつつある.
◎補体は難解であるため多くの臨床医に敬遠されてきたが,今や知っておくべき分野の一つになった.
非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)を見逃さないようにする早期診断の注意点と治療の留意点を教えてください
著者: 池田洋一郎
ページ範囲:P.1590 - P.1594
Point
◎非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)は血小板減少,微小血管症性溶血性貧血,急性腎障害の3徴を満たす急性の疾患である.
◎aHUSは主に補体関連分子の先天的あるいは後天的な異常によって発症する.
◎aHUSの治療は血漿交換または補体阻害薬が第一選択となる.
腫瘍・血液疾患とその周辺疾患と腎臓
onconephrologyとは何か,またがん薬物療法における腎機能の正しい評価法と薬物投与量の調節の仕方を教えてください
著者: 和田健彦
ページ範囲:P.1595 - P.1599
Point
◎onconephrologyは,がん患者にみられる腎臓の諸問題,腎臓病患者に発生するがんの諸問題に関する幅広い分野を取り扱う新しい学際的領域である.
◎腎機能障害患者に対して薬剤の効果を最大限に引き出しつつ安全に抗がん薬を投与するために,薬物動態および主要な排泄経路となる腎臓の機能を正確に評価する方法を知り,状況に応じて使い分けることができるとよい.
◎抗がん薬には体格を考慮した投与量が設定されているものと,そうでないものが存在し,それぞれの場合に用いる腎機能評価法が異なることに注意が必要である.
Castleman病,TAFRO症候群,POEMS症候群の診断と治療について最新の情報を教えてください
著者: 中世古知昭 , 大和田千桂子 , 渡部玲子
ページ範囲:P.1600 - P.1604
Point
◎TAFRO症候群,POEMS症候群でリンパ節腫大を認める場合,生検にてCastleman病の病理組織像を呈することがある.
◎本邦におけるCastleman病は多くが特発性多中心性Castleman病(iMCD)であり,中等症以上の症例ではトシリズマブが適応となる.
◎TAFRO症候群は最近本邦から提唱された疾患概念であり,多くの点においてiMCDとは異なる臨床像を呈する.治療としてはステロイドが第一選択である.
◎POEMS症候群では,多発性骨髄腫に準じた治療として,サリドマイドや自家造血幹細胞移植が奏効する.
骨髄腫関連の腎障害やMGRSの診断と最新の治療を教えてください
著者: 水野真一
ページ範囲:P.1605 - P.1609
Point
◎多発性骨髄腫の診断にはCRAB症状が重要であり,血清遊離軽鎖検査もM蛋白のスクリーニング検査として優れている.
◎腎不全でもほぼすべての骨髄腫の新規薬は使用可能であり,ダラツムマブを併用した治療が期待されている.
◎MGRS(monoclonal gammopathy of renal significance)の診断には腎生検は必須であり,M蛋白を産生している細胞をターゲットにした化学療法が推奨される.
水・電解質
カリウム摂取低下は高血圧を引き起こす? その機序を教えてください.またミネラルコルチコイド受容体の多彩な作用について最新の知見を教えてください
著者: 柴田茂
ページ範囲:P.1610 - P.1614
Point
◎1日のカリウム(K)摂取量と高血圧や心血管イベント発症の間には負の相関関係がある.
◎K摂取低下に伴う血圧の上昇には,遠位尿細管に発現するNa-Cl共輸送体の関与が報告されている.
◎ミネラルコルチコイド受容体(MR)の電解質作用には食塩の再吸収とK排泄があり,両者のバランスは遠位尿細管と集合管の協調的作用により調節されている.
◎MRの負の作用として心血管疾患や慢性腎臓病の進展作用があり,臨床研究からMR拮抗薬の臓器保護作用が明らかにされている.
皮膚や骨などの血液中以外でのナトリウムの役割や骨粗鬆症・高血圧・感染症との関係などの興味深い最近の知見を教えてください
著者: 木戸口慧 , 北田研人 , 西山成
ページ範囲:P.1616 - P.1619
Point
◎従来,血液中と組織中のナトリウム濃度は平衡化されると考えられてきた.
◎しかしながら,皮膚などにおいて組織局所にナトリウムの制御機構が存在し,血液中と組織中のナトリウム濃度は平衡化されていないことが証明されている.
◎皮膚局所におけるナトリウムの制御機構は,体液保持,高血圧,感染症などと関連している.
◎骨や骨髄局所におけるナトリウム制御機構は,骨芽細胞や破骨細胞の機能を変化させ,骨量に影響を与えることが報告されている.
血中リン濃度の制御機構および関連疾患と治療について教えてください
著者: 杉山絋基 , 宮本賢一
ページ範囲:P.1620 - P.1623
Point
◎血中リン濃度を正常に維持する機構は,腎近位尿細管のリン再吸収機構を中心に機能している.
◎副甲状腺ホルモン(PTH)および線維芽細胞増殖因子23(FGF23)は,腎臓に作用してリン利尿を促進させる.
◎低リン血症(慢性)は,通常,腎臓でのリン再吸収能の低下に起因している.
◎高リン血症(慢性)は,進行した慢性腎臓病や透析患者における心血管障害の重要な危険因子である.
酸-塩基平衡
心不全のフロセミド治療中にHCO3−,PaCO2が上昇した場合の治療と,高度の乳酸アシドーシス患者を診たときの対処について教えてください
著者: 田中竜馬
ページ範囲:P.1624 - P.1627
Question 1
心不全のフロセミド治療中にHCO3−が上昇し代償的にPaCO2が上昇してきた場合にはどのような治療を行えばよいでしょうか?
利尿薬やその他の新薬の有効性と注意すべき副作用
「尿が出ない!」だから利尿薬を投与する?利尿薬投与の基本と最新の使用法について教えてください
著者: 緒方聖友 , 谷澤雅彦 , 柴垣有吾
ページ範囲:P.1628 - P.1634
Point
◎利尿薬の作用機序を理解する.
◎ループ利尿薬をもとに各疾患での利尿薬のPK/PDについて理解する.
◎利尿薬抵抗性への対応理解を深める.
心不全やAKIにANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)を投与すべきか否か? またその効果はあるのか? について教えてください
著者: 山田博之 , 横井秀基
ページ範囲:P.1636 - P.1640
Point
◎心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は,心房の進展に応じて分泌されるペプチドホルモンで,心臓,腎臓,血管などでさまざまな作用をもたらす.
◎心不全の観点では,ANPはその強力な利尿作用によって心不全治療には大いに寄与するが,予後の改善効果はエビデンスレベルとして高いとは言えない.
◎AKIの観点では,腎代替療法の導入率を改善させる可能性がランダム化比較試験(RCT)により示されている.ただし,サンプルサイズやバイアスリスクなどの点で有効性が確立されていると言えず,さらに大規模でバイアスリスクの低いRCTが望まれる.
SGLT2阻害薬とMR拮抗薬の有用性について教えてください
著者: 木戸口慧 , 西山成
ページ範囲:P.1641 - P.1646
Point
◎SGLT(sodium-glucose co-transporter)は近位尿細管における糖の再吸収に携わるトランスポーターであり,SGLT2阻害薬はこれを抑制することにより血糖降下作用を発揮する薬剤である.
◎SGLT2阻害薬は多彩な研究で心保護および腎保護作用が実証されており,この効果は非糖尿病患者でも認められることから,血糖降下作用とは一部独立した臓器保護効果があることが示唆されている.
◎ミネラルコルチコイド受容体(MR)は慢性的な塩分摂取,肥満,糖尿病などによりリガンド非依存的に活性化し,臓器障害に関わることが示されている.
◎新規に開発されたMR拮抗薬であるエサキセレノンやフィネレノンはステロイド骨格をもたず,MRへの選択性が高いことから,副作用を軽減しつつ臓器保護効果を示すことが期待されている.
「HIF-PH阻害薬の光と影」の本当のところを教えてください
著者: 濱野高行
ページ範囲:P.1647 - P.1650
Point
◎腎不全患者の貧血のすべてが腎性貧血ではなく,薬剤性貧血やvolume overloadによる希釈性貧血,さらには骨髄異形成症候群やがんに伴う貧血も多く,HIF-PH(低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素)阻害薬の適応ではないものもある.
◎腎性貧血のうちでも,鉄が囲い込みされるような炎症状態ではエリスロポエチン製剤抵抗性となるが,そのような症例でHIF-PH阻害薬を使うことで,貧血の管理が容易になり輸血が減る.
◎HIF-PH阻害薬はヘプシジンを下げるので,鉄の腸管からの吸収は改善し鉄の投与は静注にこだわる必要はなくなるが,その副作用抑制の観点からも鉄欠乏に対して適宜鉄を補充することが肝要である.
◎透析患者の治験の結果では,ロキサデュスタット群ではダルベポエチン群よりも血栓塞栓症の発生が多かった.バダデュスタットの保存期のランダム化比較試験では,バダデュスタット群ではダルベポエチン群よりも主要な心血管イベント(MACE)が有意に多かった.
◎HIF-PH阻害薬の腎機能保護効果に期待がかかるが,一方で長期投与による眼に対する影響や肺高血圧や血管石灰化に対する危惧もある.また悪性腫瘍に対する影響など不明な点が多く,今後の研究が待たれる.
遺伝性腎疾患
遺伝学的検査をすべき成人の遺伝性腎疾患について教えてください
著者: 堀之内智子 , 野津寛大
ページ範囲:P.1651 - P.1654
Point
◎遺伝性腎疾患は多岐にわたるが,臨床診断が困難な場合,臨床情報と遺伝学的検査を併せて検討することで正確な診断につながることがある.
◎特に,疾患特異的な治療が存在する常染色体優性多発性囊胞腎(ADPKD)やFabry病およびレニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬が有効であるAlport症候群などではできるだけ早期の正確な診断が重要である.
◎近年,次世代シークエンサーの進歩により,網羅的にさまざまな遺伝学的検査を行うことが可能となっている.
◎遺伝学的検査に際しては,各種ガイドラインや指針の趣旨をよく理解しておく必要がある.
ミトコンドリア腎症とは? その診断と治療について教えてください
著者: 今澤俊之
ページ範囲:P.1655 - P.1659
Point
◎ミトコンドリア腎症は,核DNAもしくはミトコンドリアDNA変異による遺伝性疾患である.
◎腎病理でのミトコンドリアの質的・数的異常が診断のきっかけとなる.
◎診断のための補助的方法はあるものの,最終診断には遺伝学的検査を行うことが望まれる.
◎遺伝子診断に基づいた効果的治療が可能となりつつある.
連載 読んだら,ちょいあて! POCUSのススメ・6
皮膚・皮下病変のPOCUS
著者: 太田智行
ページ範囲:P.1491 - P.1497
日当直などでも,皮膚や皮下病変に対する診療機会は少なくありません.皮膚・皮下病変は視診だけで判断できることもありますが,POCUSを実践することで精査が可能になります.患者説明や治療の方針を決める際に役立つことも多いので,積極的に利用してください.
【症例】41歳男性.顎の下の腫瘤には以前から気づいていた.先週から少し大きくなってきたので(図1),気になって週末の救急外来を受診した.
主治医の介入でこれだけ変わる! 内科疾患のリハビリテーション・1【新連載】
リハビリ・運動療法の必要性と基本知識
内科疾患でリハビリ・運動療法が必要なわけ
著者: 上月正博
ページ範囲:P.1660 - P.1664
高齢化が進み,内科治療で何とか内臓機能を維持できても,足腰が弱って生活範囲が狭くなってくる患者.体力がどんどん低下する患者.家族の介護負担が増え,施設転院を余儀なくされる患者.このような患者が多くみられる時代になってきた.
リハビリテーション(以下,リハビリ)は,もはやリハビリ科医やリハビリ関連職種のみのものではない.内科医の日常診療にも最新のリハビリを取り込んでいく時代になった.本連載の内容を実践すれば,担当した患者の生活機能や運動機能を改善し,生命予後を延長することも可能になり,さらなる“名医”としての成功が約束されるだろう.ぜひ,最後までお付き合いいただきたい.
ここが知りたい! 欲張り神経病巣診断・6
脳出血④皮質下出血〜意識障害と麻痺〜
著者: 難波雄亮
ページ範囲:P.1665 - P.1668
前回まで,脳出血には好発部位があること,運動障害や感覚障害をきたす脳出血について勉強してきましたが,意識レベルが悪くなる,注意力が散漫になる場合はどうでしょうか?
今回は,意識障害と高次脳機能障害の原因となる大脳皮質領域の障害について,一緒に勉強していきましょう!
目でみるトレーニング
書評
—奥田 真弘 監修 村阪 敏規 執筆 妹尾 昌幸 執筆協力—医薬品情報のひきだし フリーアクセス
著者: 葉山達也
ページ範囲:P.1615 - P.1615
医薬品情報業務(DI業務)は,薬物療法の最適化に必要な情報を扱う.一見,質疑への対応に目を奪われがちだが,薬剤師業務の変遷に伴ってDI業務も「評価」「整理」「周知」「適正使用の推進」など,大きく変化してきた.以前,評者は「DI業務は薬剤師の病棟業務や各専門領域業務の『監督』であり,病棟業務は与えられた情報に基づいて具体的に戦略を実行する“player”」という図式を勝手に描いていた.しかし,近年の対人業務へのシフトに伴って,DI業務も情報を評価,取捨選択し具体的な処方設計に携わる“player”の1人として活躍が期待されている.
本書には76の事例が章に相当する8つのひきだし(1.薬学的な思考,2.換算,3.服薬タイミング,4.小児,5.腎機能,6.在宅医療,7.粉砕・一包化・簡易懸濁法,8.安定性・製剤特性)に収載されている.まさに現場目線の痒いところに手が届く内容である.臨床でよく遭遇する「問い」を発端にして,情報を提供するに至るまでのアプローチを視覚的に記載しているため,非常に理解しやすい.アプローチの内容は主に,①情報根拠(添付文書,論文),②根拠(現象)に付随する知識,③同効薬との比較,④関連性が高い予備的なクリニカルクエスチョン(現象に関連するもの,薬剤に関連するもの)で構成されており,これまでのやり方で得た情報にさらに厚みをもたせることができる.
—八重樫 牧人,佐藤 暁幸 監修 亀田総合病院 編—総合内科マニュアル第2版 フリーアクセス
著者: 森川暢
ページ範囲:P.1635 - P.1635
ついに『総合内科マニュアル(亀マニュ)』が改訂された.実は,私は亀マニュのファンだ.医師3年目のときに総合診療の後期研修を始めたが,本当に右も左もわからなかった.多少は内科の知識をもっている自信があったが,それは粉々に打ち砕かれた.かといって,同期や先輩のようにUpToDate®を紐解き知識を増やすような甲斐性もなく,仕事にひたすら追われていた.
当時,私は常に2つのマニュアルをポケットに入れていた.1つは『診察エッセンシャルズ』という診断学に特化したマニュアルであった.しかし,内科マネジメントについても同様にマニュアルが必要であった.結果的に,私が選んだ相棒は亀マニュだった.ベットサイドで診療し,亀マニュを見るという日々をひたすら繰り返した.いつしか,亀マニュは自分の血肉となり携帯はしなくなった.ただ,その後の自分の内科マネジメントの原則や原理は亀マニュが基本となっていることに変わりはない.そして,今回の改訂である.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1498 - P.1501
読者アンケート
ページ範囲:P.1675 - P.1675
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1676 - P.1677
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.1678 - P.1678
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1679 - P.1679
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.1680 - P.1680
基本情報
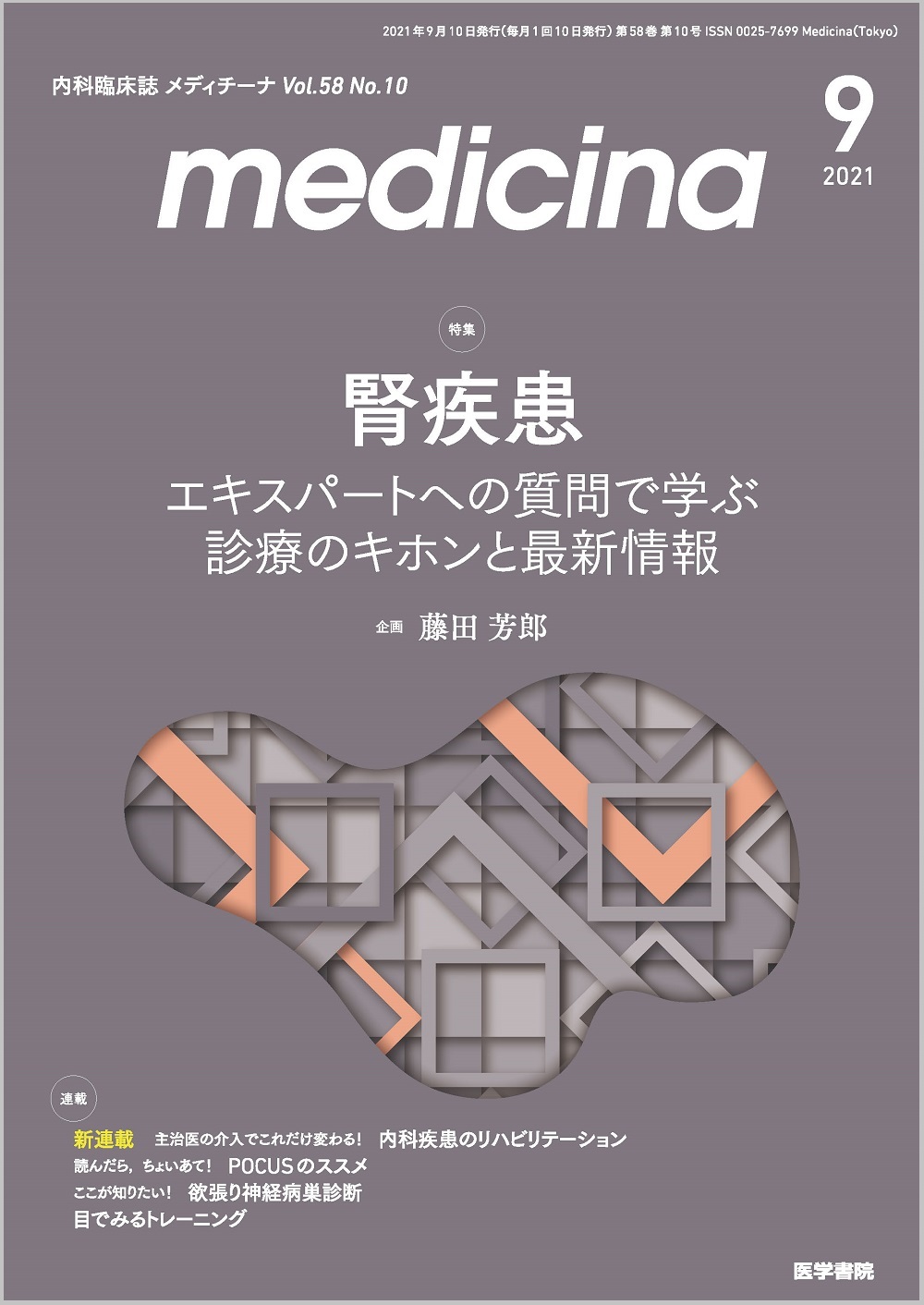
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
