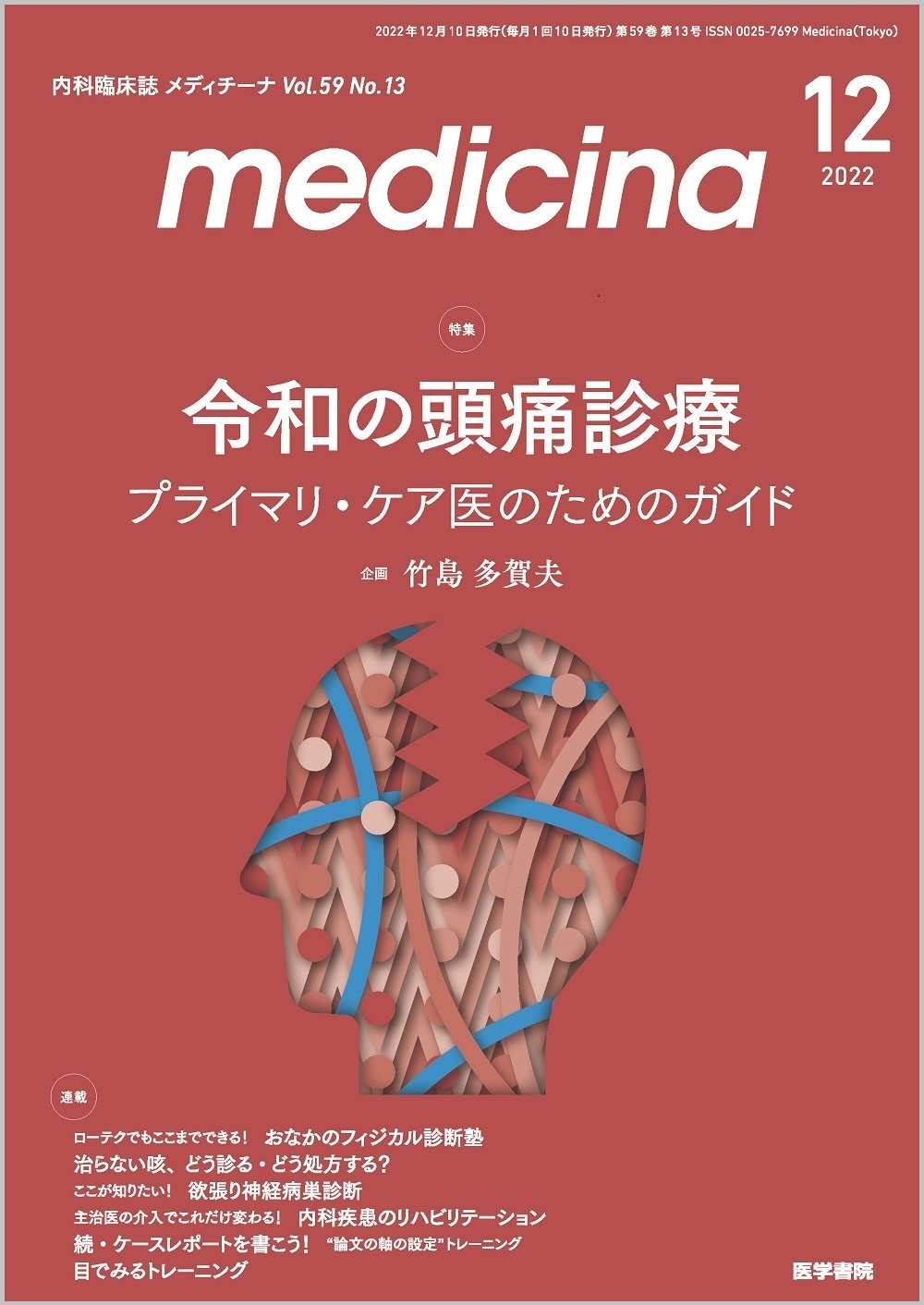文献詳細
連載 主治医の介入でこれだけ変わる! 内科疾患のリハビリテーション・16
疾患別リハビリ・運動療法の実際
文献概要
脳血管障害は,わが国の死亡原因では悪性新生物,心疾患,老衰に次いで第4位を占める1).また,脳血管障害は,要介護となる原因では認知症に次いで第2位である2).脳血管障害は,脳梗塞,脳出血,くも膜下出血の3つに分類されるが,わが国では脳血管障害の約75%は脳梗塞である.脳硬塞は,ラクナ梗塞,アテローム血栓性脳梗塞,心原性脳塞栓症に分類される.
脳血管障害に対する急性期治療の進歩により死亡率は減少したが,後遺障害を伴う慢性期脳血管障害患者は増加しており,リハビリテーション(以下,リハビリ)治療の重要性が増している.特に医療機関の退院後に地域で行われる生活期(維持期)のリハビリは,地域包括ケアの観点からも今後一層必要になると予想され,本誌の読者が関与する機会が多くなると考えられる.そこで本稿では,脳血管障害に対する生活期のリハビリ・運動療法を解説する.
脳血管障害に対する急性期治療の進歩により死亡率は減少したが,後遺障害を伴う慢性期脳血管障害患者は増加しており,リハビリテーション(以下,リハビリ)治療の重要性が増している.特に医療機関の退院後に地域で行われる生活期(維持期)のリハビリは,地域包括ケアの観点からも今後一層必要になると予想され,本誌の読者が関与する機会が多くなると考えられる.そこで本稿では,脳血管障害に対する生活期のリハビリ・運動療法を解説する.
参考文献
1)厚生労働省:令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/dl/gaikyouR2.pdf(2022年8月閲覧)
2)厚生労働省:2019年国民生活基礎調査の概況. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html(2022年8月閲覧)
3)渡邉裕志:脳卒中.上月正博(編):あなたも名医! 日常診療に取り入れよう! 継続できる内科疾患のリハビリ・運動療法,pp 134-142,日本医事新報社,2022.
4)宮越浩一:リハビリテーションにおけるリスク管理の必要性と対策.亀田メディカルセンターリハビリテーション科リハビリテーション室(編):リハビリテーションリスク管理ハンドブック 第4版,pp 2-13,メジカルビュー社,2020
5)日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会:脳卒中治療ガイドライン2021.協和企画,2021.
6)幸田 剣,田島文博:脳血管障害.久保俊一,水間正澄(総編集):生活期のリハビリテーション医学・医療テキスト,pp 91-113,医学書院,2020
7)横山絵里子:脳血管障害リハビリテーションの概要.千田富義,髙見彰淑(編):リハ実践テクニック脳卒中 第3版,pp 23-28,メジカルビュー社,2017
掲載誌情報