消化器領域には非常に多くの臓器が含まれるとともに,炎症性疾患から悪性腫瘍まで病態も幅広く,同じような症状であっても,診断がまったく異なる状況も存在します.もちろん,「お腹の調子が悪い」といった患者さんの漠然とした訴えを,病歴聴取や身体診察から丁寧に紐解いて鑑別診断を立てていく作業が必要なことも多く,ただ単にCTを撮ればいつでも何でもなんとかなるというものではありません.すなわち,病態生理や診断方法に関して,医師は常に知識をアップデートしていなくてはなりません.なかには,新しく開発されたモダリティや新規の検査方法も含め,日進月歩の医療技術がいつの間にか導入されていることも少なくありません.さらに,数多くの診療ガイドラインが存在することも含め,日頃の自分の診療が旧態依然のものになっていないか? もう時代遅れなのではないか? 実は,なかなか振り返ってみることすらできていないこともあるかと思います.
自身がガイドライン作成に携わった経験から言えることは,新たなエビデンスの創出に伴い,ガイドラインはどんどんアップデートを重ねており,5年前の知識はいつしか古びた,錆びれたものとなり,せっかく学んだ知識であっても,あっという間に古くなっていることが往々にしてあるということでした.もちろん,自分が得意とする臓器や領域の知識のアップデートはきっと,自然と目につき耳にするものと思います.しかし,それほど関心をもっていない領域については,ついつい見落としがちで,気付かないまま時が過ぎていくような気もします.もちろん,学会に参加することで新たな知見を身につける機会もあることでしょう.しかし,それだけでは患者さんに最新の知見を届けることはできません.
雑誌目次
medicina60巻1号
2023年01月発行
雑誌目次
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
扉 フリーアクセス
著者: 横江正道
ページ範囲:P.10 - P.11
症候
「お腹の調子が悪い」患者をどう診るか?
著者: 横江正道
ページ範囲:P.16 - P.21
Point
◎患者の「お腹の調子が悪い」という漠然とした訴えをひもとくには,診断推論を効かせた症状に関する質問,病歴聴取が重要である.
◎消化器は1つの系統(システム)であり,痛みの局在をはっきりさせられないことも多い.
◎検査は,鑑別診断の裏づけとして必要なものだけを行う.その際,検査の長所・短所,感度・特異度を勘案して選択することが大切である.
急性腹症
著者: 小澤尚弥
ページ範囲:P.22 - P.26
『急性腹症ガイドライン』が2015年に出版されたが,急性腹症は複数疾患を含む概念であり,悪性腫瘍と比べると体系的に学ぶ機会も少なく,診療の標準化は進んでいない分野である.急性腹症の分野における最近のアップデートとして,小腸閉塞・大腸閉塞・急性虫垂炎を例に挙げて解説する.
便秘症
著者: 緒方智樹 , 結束貴臣 , 中島淳
ページ範囲:P.28 - P.33
疾患概要
わが国の2016年度の国民生活基礎調査によると,便秘の有訴者数は2〜5%程度と言われている.男性(2.5%)よりも女性(4.6%)に多い傾向を示しており,加齢により有病率が増加している.ただし,慢性便秘症に限定した疫学調査は行われていないのが現状である.また,一般に「便秘」という言葉は観念的に使用されることが多く,その正確な定義を考えることは少ない.日本国内や海外では便秘を客観的に捉えるために定義付けが行われている.日本での便秘の診療の基本となっている『慢性便秘症診療ガイドライン2017』1)では,“本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態”と定義されている.
一方,海外では,2016年に発表されたRome Ⅳ基準2)の中で機能性便秘は,“排便困難,排便回数が少ない,または排便が不完全であるといった有症状の機能性腸疾患”と定義されている.
急性下痢—原因不明,新型コロナウイルスも含めて
著者: 辛島遼 , 小林拓
ページ範囲:P.34 - P.40
下痢は一般によくみられる症状で,「1日に3回以上の軟便もしくは水様便」と定義される1).急性下痢は「水分量,頻度が増加し14日以内に続いている便」,慢性下痢は「水分量,頻度が増加し28日以上続く便」と定義される2).さまざまな原因があるものの世界共通の健康問題であり,毎年約130万人の死亡を誘発し3),発症,死亡はともに特に乳幼児に多いと報告されている4).
ピロリ菌感染症—ピロリ菌感染症の“今”を理解する
著者: 間部克裕 , 津田桃子 , 久保公利
ページ範囲:P.41 - P.45
ピロリ菌が発見されてから既に40年が経過し,消化性潰瘍や胃癌など胃十二指腸疾患の概念・診断・予防・治療は大きく変化した.既に常識となったピロリ菌であるが,さまざまな進歩や変化があり複雑な保険適用の問題もある.そこで本稿ではピロリ菌感染症のこれまでと“今”について概説し,感染診断,除菌治療,除菌判定検査についてまとめたい.
胸やけ・胃もたれなどの上腹部不定愁訴
著者: 浅岡大介
ページ範囲:P.46 - P.50
医療機関を受診する患者で,胃が痛い,胃が重い,おなかが張る,ムカムカする,胃液が上がってくるなどの上部消化管に起因する自覚症状を訴える患者は多くみられる.このようなさまざまな上腹部不定愁訴は「胃痛」「胃もたれ」「腹部膨満感」「胸やけ」「呑酸」症状として存在し,現在もなお医療現場で使われているが,患者の自覚症状も1つとは限らず,複数の症状を同時に呈することも少なくない.患者も厳密にこれらの上腹部症状を正確に区別して表現しているという確証もなく,例えば胸やけを訴える患者によっては,胸部の不快感,あるいは上腹部不快感の要素を含んでいることもある.また,これらの上腹部不定愁訴について,聴取する医師によって考え方や診断にばらつきがあることも少なくない.このような胸やけ・胃もたれなどの上腹部症状について,近年改訂された機能性消化管疾患の国際基準であるRome Ⅳや機能性ディスペプシアという疾患概念の提唱により整理されつつある.本稿では,胸やけ・胃もたれなどの上腹部症状に対する診断・治療について概説する.
悪心・嘔吐,食欲不振
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.52 - P.56
症例1
(Scene 1)
80歳男性
Alzheimer型認知症があり要介護4で施設入居している.来院前日から嘔吐が始まり,来院まで6回ほど嘔吐し施設職員が救急要請し搬送となる.嘔吐以外の訴えや随伴症状は認めない.バイタルサインは安定している.身体診察で明らかな異常は見つけられない.
Q. この患者の嘔吐の鑑別診断をどのように進めるか?
疾患
食道癌
著者: 丹羽由紀子
ページ範囲:P.57 - P.61
食道癌の内視鏡診断の進歩
食道表在癌の大部分は自覚症状がなく,その発見契機は90%以上が内視鏡である.一方,食道表在癌の内視鏡診断は難しく,わずかな発赤や陥凹,隆起に注目して詳細に観察することが必要である.ヨード染色は食道表在癌発見に有用だが,胸焼けなどの副作用があり,また食道炎を惹起するためルーチンには使用できない.近年急速に普及したnarrow band imaging(NBI)やflexible spectral imaging color enhancement(FICE)は被検者に負担をかけることなく,食道扁平上皮癌を効率よく発見することができる.また,これらの画像強調内視鏡を併用した拡大内視鏡観察は鑑別診断,深達度診断に応用されている.
2011年に発表された日本食道学会拡大内視鏡分類1)におけるType B1,B2,B3それぞれが深達度T1a-EP〜LPM,T1a-MM〜T1b-SM1,T1b-SM22)に相当しているとしている.またAVA(avascular area)-small,AVA- middle,AVA-largeの順に深達度T1a-EP〜LPM,T1a-MM〜T1b-SM1,T1b-SM2に相当するとし,B1血管のみで構成されるAVAの深達度はT1a-EP〜LPMに相当するとした(表1).このように,日本食道学会拡大内視鏡分類の表現法は内視鏡のエキスパートでなくても表現できるため,多くの内視鏡医が深達度診断の議論に加われる共通の言語として広く浸透した3).
胃食道逆流症
著者: 夏目まこと
ページ範囲:P.62 - P.69
胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease:GERD)は食道粘膜障害や逆流症状を起こす疾患であり,良性疾患であるもののQOLに大きく影響することから臨床で重要な疾患となっている.2015年に新しい酸抑制薬であるカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)の登場により新たな知見が報告され,GERDの日常臨床治療に組み込まれたことから,2021年に『胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン』が改訂された.そこで,GERDの概念,ガイドラインの刊行によるGERDの診療の変化,ピロリ菌除菌後にみられるGERDについて述べる.
機能性ディスペプシア—これだけでわかる 機能性ディスペプシア診療はどう進化したか?
著者: 山本さゆり , 小笠原尚高 , 春日井邦夫
ページ範囲:P.70 - P.75
2013年に機能性ディスペプシア(functional dyspepsia:FD)が保険診療名として初めて承認され,2014年に『機能性消化管診療ガイドライン—機能性ディスペプシア』(以下,ガイドライン)第1版が,そして,2021年に第2版が発刊された.本稿ではFD診療のこれまでの流れを踏まえつつ,最新の動向や診療のこつを述べたい.
胃・十二指腸潰瘍(消化性潰瘍)
著者: 伊藤恵介
ページ範囲:P.76 - P.81
本邦における消化性潰瘍の罹患数は減少傾向を示しており,厚生労働省の統計によると,胃潰瘍および十二指腸潰瘍の推計患者総数は1996年13万4,000人であったところが,2008年5万7,300人,2020年には1万4,300人と減少の一途を辿っており,この20数年間で約1/10となっている1).
消化性潰瘍の主な原因は
胃癌・早期胃癌(EMR/ESD)—胃癌治療10年の変化〜『胃癌治療ガイドライン』第3版と第6版の比較から
著者: 早川俊輔 , 佐川弘之 , 瀧口修司
ページ範囲:P.82 - P.87
胃癌治療は日進月歩で進んでおり,特に手術療法や化学療法に関しては10年前の治療法とは大きく異なっている.『胃癌診療ガイドライン』第3版(2010年10月改訂)と第6版(2021年7月改訂)の治療アルゴリズムを比較すると,この10年間で治療選択肢は増加したが,逆に言えば複雑化したとも言える.本稿では第3版と第6版の治療法を比較し,胃癌治療の進歩に焦点を当てていく.
十二指腸癌(十二指腸腫瘍)
著者: 光永豊 , 菊池大輔 , 布袋屋修
ページ範囲:P.88 - P.92
ひと昔前に「十二指腸癌」と言ったら,概ねそのイメージは決まっており,あまり見ない癌,よくわからないけれども治療がややこしい病気という印象だった.ようするに,希少癌であり,あまり注目されてはいなかったのである.そもそも十二指腸の疾患自体が重要視されるような時代ではなく,上部消化管内視鏡時に十二指腸の観察はそれほど力を入れなくていいよ,と教えられた内視鏡医がまだ多いはずである.実際に,胃では定型的な観察法は多く存在するものの,十二指腸に関しては定型的な観察法すら確立していないのが現状である.しかしここへ来て,十二指腸の上皮性腫瘍の発見率が明らかに増加している1〜3).その原因やリスクファクターなども明らかになっていないが,内視鏡機器の進歩や内視鏡医の関心の高まりに加え,ヘリコバクターピロリ陰性時代の到来が関連していることが考えられている.2021年には国内で初めて『十二指腸癌診療ガイドライン』が発刊され4),いよいよ十二指腸腫瘍を避けては通れない時代がやってきている.本稿では,このあまり馴染みのない十二指腸上皮性腫瘍の種類や治療法につき概説する.
大腸癌
著者: 上原圭
ページ範囲:P.98 - P.103
日本人の2人に1人が患うと言われる悪性新生物のなかでも,大腸癌の発生頻度は高く,年齢調整罹患率は男性では肺癌,胃癌,前立腺癌に次ぐ第4位,女性では乳癌に次ぐ第2位であり,死亡率は男性では肺癌に次ぐ第2位,女性では第1位となっている.筆者が大腸癌診療に関わるようになった25年前には,使用できる抗がん剤はフルオロウラシルとマイトマイシンのみで,切除不能がんにおける平均余命は約1年とされていた.近年,内視鏡外科手術の進歩,抗がん剤および分子標的薬,免疫治療といった治療の進歩は著しく,ステージⅡ/Ⅲ結腸癌の5年全生存率は90%に近づき,切除不能進行再発大腸癌の全生存率の中央値は約3年に迫っている.
大腸癌の標準治療は大腸癌研究会で作成された『大腸癌治療ガイドライン2022年版』にまとめられており1),約2年に一度のアップデートがされている.しかし,治療は日進月歩で進歩しており,昨日までの常識が今日は非常識ということは常に起こりうることである.本稿では,最近の新しい常識や今後の常識となりそうなホットな話題をいくつか紹介する.
大腸ポリープ
著者: 蟹江浩
ページ範囲:P.104 - P.107
本稿のテーマは「大腸ポリープ」であるが,いわゆる大腸ポリープだけではなく,表面型を含めた腫瘍性病変を対象とし,腺腫・早期癌・ポリポーシスなどの「大腸局在性病変」すべてが対象となる.
2014年に日本消化器病学会において『大腸ポリープ診療ガイドライン』1)(以下,初版)が刊行され,6年間で新たに蓄積されたエビデンスに基づき『大腸ポリープ診療ガイドライン2020改訂第2版』2)(以下,ガイドライン第2版)が刊行された.
大腸憩室症—日常診療においてアップデートすべき大腸憩室に関する5項目
著者: 山田英司 , 野中敬 , 小松達司
ページ範囲:P.108 - P.111
大腸憩室および関連疾患は近年も増加している.本邦においては2017年に『大腸憩室症(憩室出血・憩室炎)ガイドライン』1)(以下,ガイドライン)が刊行され,これまで常識とされてきた大腸憩室症に関する疫学,診断,治療,発病予防などが見直されるきっかけとなった.本項では,筆者の考える日常診療においてアップデートすべき大腸憩室に関する5つの項目を列挙し解説する.
炎症性腸疾患(IBD)
著者: 長坂光夫
ページ範囲:P.112 - P.117
潰瘍性大腸炎,Crohn病を主とする炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease:IBD)は原因不明の難治性疾患であり,その患者数は近年増加の一途を辿る.かつてのIBDの治療は食事・栄養療法が主体であったが,その後サラゾスルファピリジン(salazosulfapyridine:SASP),5-アミノサリチル酸(5-aminosalicylic acid:5-ASA)製剤,副腎皮質ステロイド薬(ステロイド)を主体とする薬物療法,そして現在はさまざまな分子標的薬へと移行した.新たな治療薬によりIBDの治療目標は症状の緩和から内視鏡的粘膜治癒1,2),そして組織学的治癒へとハードルが上がったといえる.診断機器はX線造影検査から内視鏡,カプセル内視鏡3〜5),バルーン内視鏡6〜8),そしてCT enterograph,MR enterography(MRE)へ,バイオマーカーとして赤血球沈降速度(赤沈),C反応性蛋白(C reactive protein:CRP)に加えて便カルプロテクチン,ロイシンリッチα2グリコプロテイン(Leucine-rich alpha 2 glycoprotein:LRG)など,新規の検査法や新薬の開発によりIBDの診断・治療はこの10年で大きな変遷を遂げた.
過敏性腸症候群
著者: 田中由佳里
ページ範囲:P.118 - P.121
過敏性腸症候群(IBS)は繰り返す腹痛や,それに伴う便性状や排便回数の変化を伴う機能性消化管疾患である.IBSの症状トリガーにストレスが関連することが示唆されており,脳腸相関が病態の軸とされている.
本邦でのIBSの有病率は約10%とされ,臨床現場で頻回に出会う消化器疾患の1つである.米国の有病率と大きくは変わらない.ストレス反応に関連する副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH,視床下部)が消化管の運動や感覚亢進を引き起こすことがわかってきた.さらに近年IBSのコホート調査や,粘膜微小炎症や腸内細菌の研究なども進み,感染性腸炎後にIBSに進展するという感染性腸炎後IBS(post-infectious IBS:PI-IBS)という病態も知られてきた.
急性虫垂炎—診断と治療(WSESエルサレムガイドラインより)
著者: 新宮優二
ページ範囲:P.122 - P.125
今より約20年前,右下腹部痛を訴え同部に触診上所見があれば,直ちに虫垂炎を疑い,手術(開腹)を行っていた.そして,当時いわゆる“散らす”という保存的治療は,将来の再発リスクを許容せざるを得ない特別な社会的理由がなければ選択されない治療方針であった.
近年では,虫垂炎診断だけでなく炎症程度の評価が可能となり,それに合わせて治療方針も,保存的治療,非侵襲的な手術(腹腔鏡下手術など),保存的治療からの計画的待機的手術など,多様化している.そのなかで,2015年に初めてWorld Society of Emergency Surgery(WSES)により急性虫垂炎の診療ガイドライン(WSESエルサレムガイドライン,2020年初回改訂1))が策定され,虫垂炎治療の方向性が示された.
B型肝炎,C型肝炎
著者: 長谷川泉
ページ範囲:P.127 - P.132
B型肝炎,C型肝炎は肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV,hepatitis C virus:HCV)による感染症である.慢性感染者では炎症は緩徐に進行し,高率に肝硬変や肝細胞癌(hepatocellular carcinoma:HCC)を発症する.HCCはわが国の死亡者数が第5位の癌である1).発癌の有無にかかわらず,いったん線維化が進行し肝機能が破綻すると,時に致命的ともなる肝疾患関連合併症を発症する.肝炎ウイルスを制御・駆除する目的は,こうした肝発癌および肝疾患関連死を抑止し患者のQOLを改善することにある.全世界で推定3億5,400万人がHBVまたはHCVに感染しているといわれ,WHOは2030年までにこれらの肝炎ウイルスの撲滅に向けての目標を設定・修正し,国単位で自国に即した目標を達成するよう勧告している2).本稿ではB型肝炎,C型肝炎について,治療の変遷および今後の展望について概説する.
NAFLD/NASH
著者: 角田圭雄 , 中島淳 , 米田政志
ページ範囲:P.133 - P.137
非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)は肝酵素異常で紹介された際に遭遇する頻度の最も高い疾患で,国内で約2,200万人が罹患している.肝細胞癌(HCC)では従来肝炎ウイルスが主因であったが,現在は肝炎ウイルス以外のアルコールやメタボリックシンドローム,糖尿病などによる代謝性肝疾患の増加が著しい.米国肝臓病学会2012年のガイドラインに基づきNAFLDは非アルコール性脂肪肝(nonalcoholic fatty liver:NAFL)と非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis:NASH)に分類された.国内では2014年に初めて『NAFLD/NASH診療ガイドライン』(以下,ガイドライン)が発表された.2020年にガイドライン改訂第2版が発表されたが,近年はNAFLDの予後規定因子が肝線維化の程度であることが明らかとなり,高度肝線維化例を見逃すことなく肝臓専門医へ紹介し,早期の治療やHCCのサーベイランスに繋げることが重視される.また治療に関して大きなイノベーションはないが,ガイドライン2020では糖尿病合併例に対しては,SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)の投与が推奨されるようになった.本稿ではNAFLD/NASHの診断および治療について「10年前の常識が現在の非常識!?」となっている現状について概説したい.
肝細胞癌治療—最新の話題
著者: 日下部篤宣
ページ範囲:P.138 - P.143
肝細胞癌の治療としては,従来,肝切除や穿刺局所療法,interventional radiology(IVR)治療が主流であり,薬物療法としては10年前にはソラフェニブ1剤しかエビデンスのある薬剤は存在しなかった.しかし近年,薬物療法の発達が目覚ましく,今日では免疫チェックポイント阻害薬併用レジメンを含めた6レジメンが使用可能となっている.本稿では2021年秋に改訂された日本肝臓学会の『肝癌診療ガイドライン2021年度版(第5版)』(以下,ガイドライン第5版)の治療アルゴリズムの内容をもとに,肝細胞癌治療に関する最新の話題(特に薬物療法を中心に)について述べていく.
胆石症,急性胆囊炎,急性胆管炎
著者: 桐山勢生
ページ範囲:P.144 - P.148
胆石症は,消化器疾患の代表的なcommon diseaseの1つであるが,結石の存在部位により,胆囊結石,総胆管結石,肝内胆管結石に分けられる.胆囊結石の多く(60〜80%)は無症状で,治療(胆摘術)を行う意義は少ないとされている.また肝内胆管結石も近年は無症状例が増加しているが,肝内胆管癌や肝萎縮,胆道狭窄や拡張がなければ経過観察が推奨されている1).一方,総胆管結石に対しては,無症状であっても胆管炎のリスクがあり治療を行うことが推奨されている1).このように,胆石症は,実際に治療の対象となるのは,無症状で発見される一部の総胆管結石症例を除き,何らかの症状をきたした症例となるが,特に急性胆囊炎・胆管炎を併発すると,急性期に適切な対応が必要とされ,臨床的に重要な疾患といえる.
急性胆囊炎,胆管炎の診療ガイドラインは,本邦では2005年に日本語版第1版が発刊され2),2007年には日本発の国際版診療ガイドラインとして『Tokyo Guidelines 2007(TG07)』が発表された3).その後,新たなエビデンスに基づいてアップデートが重ねられ,さらに2013年にTG134),2018年にはTG18と改訂され5),それに従って日本語版も現在第3版に改訂されている6).
胆道癌
著者: 宮部勝之
ページ範囲:P.150 - P.155
本邦における胆道癌の罹患数は,がん全体で13位,死亡数では6位のがん腫1)であり,各種がん腫のなかで比較的稀な難治性がんとして位置づけられる.胆道癌は肝内胆管癌,肝外胆管癌,十二指腸乳頭部癌,胆囊癌に分類される.近年,2019年に『胆道癌診療ガイドライン第3版』が発刊され,2021年には『胆道癌取扱い規約第7版』発刊のほか,『十二指腸乳頭腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術ガイドライン』の新たな作成が行われた.そのほか,肝内胆管癌に対しては,日本肝癌研究会を中心として『肝内胆管癌ガイドライン2021年版』が作成された.本稿ではこれらのガイドラインや取扱い規約の内容を基本としながら,現在まで明らかになった知見を概説する.
急性膵炎,慢性膵炎
著者: 白井邦博
ページ範囲:P.157 - P.164
ガイドラインは,実臨床の現場で意思決定に重要な役割を果たし,質の高い標準的治療を提供している.本稿では,『急性膵炎診療ガイドライン2021年第5版』と『慢性膵炎ガイドライン2021年第3版』の改訂ポイントから,最近の流れについて解説する.
膵癌
著者: 林香月
ページ範囲:P.165 - P.169
膵癌の統計や予後
膵管から発生した浸潤性膵管癌が一般的に膵癌と呼ばれている.その他の膵腫瘍には腺房細胞癌,膵神経内分泌腫瘍,膵管内乳頭状粘液腫瘍(IPMN),粘液性囊胞腫瘍(MCN),漿液性囊胞腫瘍(SCN),充実性偽乳頭状腫瘍(SPN),退形成性膵癌などがある.
本邦の膵癌死亡者数は,2019年には36,356人,2020年には37,677人と増加傾向を示し,肺癌,大腸癌,胃癌に次ぐ第4位であった.米国では膵癌死亡者数は2030年までに第2位になることが予想されており1),本邦でも同様の傾向が危惧されている.
Column
最新の内視鏡診断法(内視鏡光源,NBI,TXI,RDI,AI診断)に関する知見
著者: 藤吉俊尚 , 山口丈夫
ページ範囲:P.94 - P.96
内視鏡光源
2020年にオリンパス社からLED搭載の新型内視鏡システム(EVIS X1)が発売された.EVIS X1はred(赤),green(緑),blue(青),violet(紫)にamber(琥珀)を加えた5つのLEDを採用している.amberを搭載したことで,より自然な色表現を可能にし,白色光,狭帯域光観察(narrow band imaging:NBI)をはじめ,構造色彩強調機能(texture and color enhancement imaging:TXI),赤色光観察(red dichromatic imaging:RDI)などの新しい画像強調観察が可能となった.
筆者が内視鏡を触り始めた頃(2007年)の画質は,HD(1280 px×720 px)ですらなかったが,この最新の内視鏡光源(EVIS X1)は4K解像度(3840 px×2160 px)で観察することができる(図1).テレビ放送の世界で4Kや8K画質と進化しているように,内視鏡の画質も技術革新が進んでいる.
連載 ローテクでもここまでできる! おなかのフィジカル診断塾・10
—おなかが膨満している その3—肝囊胞のフィジカル—腹部膨満+αの症状に注目
著者: 中野弘康
ページ範囲:P.1 - P.5
今回も,おなかをみること(+α)が診断に役立つ症例をご紹介します.“腹部膨満”を訴える患者さんをみたら,常におなかを真横から見る姿勢が大切ですが,今回はおなか以外(+α)のフィジカルにも注目してみてください.
治らない咳,どう診る・どう処方する?・13
間質性肺炎の咳嗽・喀痰
著者: 中島啓
ページ範囲:P.172 - P.177
ポイント
・まず原疾患の進行であるかを評価する.原疾患の進行があれば,原疾患の治療を行う.
・ステロイドや免疫抑制薬を投与している間質性肺炎患者の場合は,細菌,抗酸菌.アスペルギルスなど感染症の合併有無を評価する.
・感染症以外の並存疾患[咳喘息,胃食道逆流症(GERD),慢性閉塞性肺疾患(COPD),後鼻漏など]の有無も評価する.特発性肺線維症(IPF)の患者ではGERDの合併率が高いとされている.
・上記に当てはまらない場合は,間質性肺炎自体による咳嗽として対症療法の強化を行う.
ここが知りたい! 欲張り神経病巣診断・20
ふらつきや飲み込みにくさ—Wallenberg症候群/症候性頸動脈狭窄症の内科的治療
著者: 難波雄亮
ページ範囲:P.178 - P.183
脳幹には狭い空間にさまざまな神経が走行しています.大脳皮質から脳幹を通り手足に行き渡るため,例えば錐体路障害ではほんのわずかな病変でも強い障害が生じることもあります.また,脳梗塞の場合,神経所見で異常があってもMRIで病変が映りづらいこともよく経験します.それでは,今回はさまざまな症状をきたす延髄の病変について見ていきましょう.
主治医の介入でこれだけ変わる! 内科疾患のリハビリテーション・17
疾患別リハビリ・運動療法の実際
摂食嚥下障害
著者: 上月正博
ページ範囲:P.184 - P.191
超高齢社会を迎え,日常診療のなかで摂食嚥下障害の対応に苦慮する場面が増えている.摂食嚥下障害は,日常の診療で身近な問題であるにもかかわらず,その対応を学ぶ機会はなかなかない.本稿では,摂食嚥下を専門としない医療者にも役に立つ摂食嚥下障害に対する生活期のリハビリテーション(以下,リハビリ)・運動療法を解説する.
医学古書を紐解く・1【新連載】
古書から何を学ぶか—『危く誤診せんとした経験集』『最終講義』『誤診』
著者: 綿貫聡
ページ範囲:P.192 - P.195
症例経験から学ぶ
私が診断エラーに関心を抱いた一番最初のきっかけは,初期研修医の頃から愛読していた福井大学の寺澤秀一先生の『研修医当直御法度—症例帖』(三輪書店)の中に描かれていた「症例経験の振り返りから何を学ぶか?」という視点だったように思う.
こうした本が過去にもあったのだろうかと思い調べてみると,かなり昔まで遡ることができ,1937年に医界展望社という出版社から『危く誤診せんとした経験集』(梅室純三,金原作輔 編)という症例集が出版されていた1).目次には「心臓喘息を気管支喘息に」「血液培養陰性のチフス患者」「診断に先入観は禁物」といった,現代でも発生しかねない症例が並んでいる.各著者は「こういった経験は,他の人にも起こり得るのではないか」という意識で自験例を紹介されていた.
目でみるトレーニング
information
千里ライフサイエンスセミナーT5「バイオインフォマティクスの最前線」 フリーアクセス
ページ範囲:P.21 - P.21
第4回日本周麻酔期看護医学会学術集会のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.69 - P.69
書評
—杉崎 陽一郎 著・監修 小島 俊輔,佐藤 宏行,高麗 謙吾 著—循環器のトビラ—循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ フリーアクセス
著者: 平岡栄治
ページ範囲:P.27 - P.27
循環器は非専門医にとって恐怖の分野ではなかろうか.非専門医の気持ちを代弁するなら,「緊急を要する可能性もあり,手を出せない」,「自分がしたことで,よくないことが生じたら(そのせいではないときでも)どうしよう」であろう.著者・監修者の杉崎先生は,循環器のトビラは「開けなきゃいけないけど,ちょっと二の足を踏む」重厚なトビラと表現され,そういうことを少しでも払しょくするために,循環器内科医と非専門医の共通言語になりうることを目的として本書を企画された.内容はエビデンスやガイドラインに沿っており,さらに著者らの豊富な経験のもとわかりやすく書かれている良書である.
本書は急性冠症候群(ACS),安定冠動脈疾患(CAD),心不全,不整脈,下肢閉塞性動脈疾患,周術期などに関する14章から成り立つ.第1章で取り上げられているACSは,非専門医もよく遭遇し循環器内科医に適切にコンサルトすべき疾患で,専門医と非専門医が共通概念で動く必要度が高い.心電図でSTが上昇していればST上昇型心筋梗塞で「door-to-baloon time 90分を目指し循環器医コール」,と非専門医は比較的行動がとりやすい.一方,困るのが心電図でSTが上がっていないときである.それについて,リスクに分けたマネジメントが解説されている.すなわち,誰がみても不安定な患者,例えば,胸痛が持続,胸痛が再発,血行動態が不安定,STが下がりっぱなし(進行性の虚血,左主幹部病変による虚血や後壁梗塞ですぐに心臓カテーテルが必要),不安定な不整脈などはすぐに冠動脈造影を行い,一見落ち着いていてもGRACEスコアなどで点数が高い高リスク群は24時間以内など早期に冠動脈造影を行う,といった具合である.こういったことが共通概念になっていると,非専門医はとてもやりやすい.専門医と非専門医が共有しておくべきことが各章にまとまっている.非専門医はこういったことを知っておき,専門医にアセスメントとプランをある程度述べることができるように本書を熟読することをお勧めする.
—長野 広之 著—ジェネラリストのための内科診断キーフレーズ フリーアクセス
著者: 原田拓
ページ範囲:P.97 - P.97
著者の長野広之先生は,現在,日本病院総合診療医学会若手医師部会副代表,日本プライマリ・ケア連合学会若手医師部門病院総合医チーム2代目代表を務められています.キャリアとしては上田剛士先生のいらっしゃる洛和会丸太町病院で研鑽を積まれた後,現在は在宅臨床をしつつ京大大学院医療経済学分野の博士課程で研究に邁進され,SNSでも積極的に情報を発信されているという,臨床も教育も研究もすべてできる,まさにこれからの総合診療医を牽引される先生です.こうしたバックグラウンドから生み出される,アウトプット特集,腎盂腎炎特集,在宅医療×病院特集と,現場最前線で臨床に取り組む医師の琴線に触れる雑誌特集企画を連発されている長野先生の著書が面白くないわけがない,ということで読ませていただきました.
本書は医学書院の総合臨床誌『medicina』で好評を博した鑑別診断の連載企画が基になっており,一言で言うと,「即日で鑑別診断能力の数も質も向上する」,そんな構成に思えました.さまざまな診断カンファレンスで無双の強さを示す長野先生が,その経験から導き出された「数多ある情報から診断につながる特異的な情報をピックアップする」という視点で執筆された,日常診療で役立つ内容になっています.
—新見 正則,田村 朋子 著—フローチャート糖尿病漢方薬—漢方でインスリンは出ません! フリーアクセス
著者: 松本一成
ページ範囲:P.171 - P.171
私は長年,糖尿病専門医として診療をしてきましたが,これまで漢方薬にはあまり関心がありませんでした.それは,漢方薬には糖尿病患者さんの血糖値を下げる効果が期待できなかったからです.実は本書の表紙にも,「漢方でインスリンは出ません!」と書いてあります.それでは,なぜ糖尿病漢方薬の本が上梓されたのだろうと思いながら本書を読んでみました.
本書のフローチャートは自覚症状別に並んでいます.食欲・女性・疲れ・運動・便秘・合併症・その他という具合です.このフローチャートに沿って調べてみると,例えば「がっちりタイプの女性の更年期不調」には補中益気湯を1回2.5g,1日3回,2カ月を目安に継続,と記載されています.したがって,患者さんの自覚症状から推奨される漢方薬の種類・用量・投薬期間が簡単にわかります.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.6 - P.8
読者アンケート
ページ範囲:P.203 - P.203
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.204 - P.205
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.206 - P.206
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.207 - P.207
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.208 - P.208
基本情報
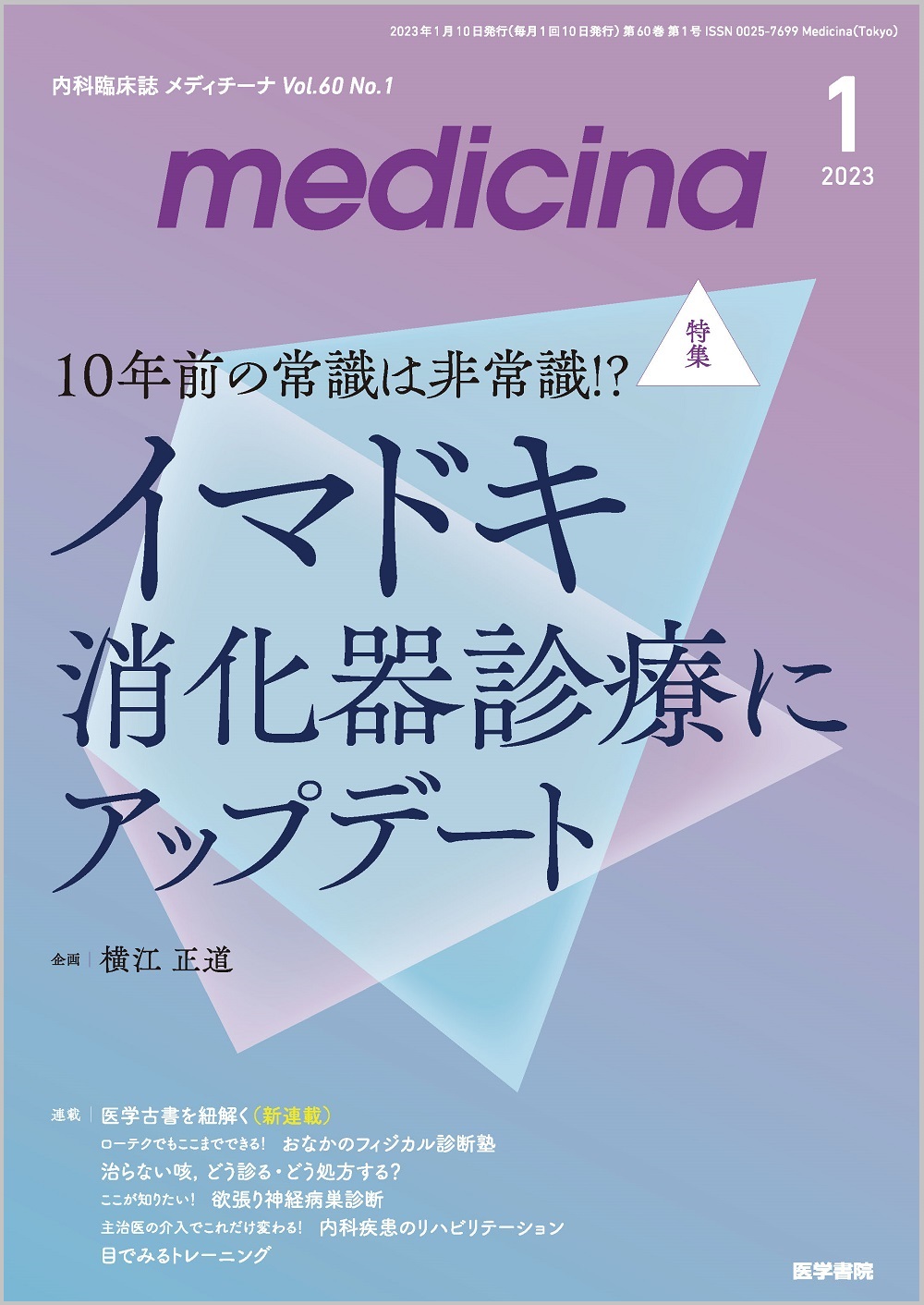
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
