髪の毛の匂いを嗅ぎあって 「くさいなあ」ってふざけあって
くだらないの中に愛が 人は笑うように生きる
「くだらないの中に」 星野 源
雑誌目次
medicina60巻11号
2023年10月発行
雑誌目次
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
扉 フリーアクセス
著者: 松村真司
ページ範囲:P.1760 - P.1761
座談会
AI時代に診察室での患者と医師の会話はどう変わる?
著者: 石川翔吾 , 川添愛 , 尾藤誠司 , 松村真司
ページ範囲:P.1762 - P.1767
診療中に患者さんから受ける質問にうまく答えられなかったり,コミュニケーションエラーが生じることも多々あります.一方,近年ではChatGPTなど自然言語を生成するAIチャットサービスの登場により,情報収集や情報説明のあり方も少しずつ変わってきています.このようなAI時代での医師と患者とのコミュニケーションについて,未来予想も踏まえてお話しいただきました.(松村)
そもそも論
Question 1 内科はどんな問題を扱ってくれる科でしょうか?
著者: 山田康博
ページ範囲:P.1768 - P.1769
ひとまず返答
内科は,成人の健康問題を扱う診療科です.幅広い健康問題について,診断し治療と管理を行います.また,疾病の予防にも関わります.診断のためには病歴を聴取し,身体診察やさまざまな検査を用います.治療内容は多岐にわたりますが,外科のような手術はほとんど行いません.治療には緩和医療が含まれることがあります.必要に応じて適切な診療科と連携して診療を行います.
Question 2 内科は何歳から受診できるのですか?
著者: 山田康博
ページ範囲:P.1770 - P.1771
ひとまず返答
一般的に内科は15歳以上を対象としています.ただ地域の医療資源の状況や,それぞれの内科医の特性によって小児医療への関与の程度はさまざまです.小児の予防接種は診断・治療とは別途に行う場合があります.他診療科への連携を行うことも内科医の役割の1つです.また,先天性疾患の診療においては,小児の成長に伴って小児科医と内科医が連携をとりながら医療を行うこともあります.このように,年齢による対象患者の原則はありますが,患者さんによっては内科医が対応することもありますので,なぜそのような疑問をもったか教えてください.
Question 3 私は特に何の症状もありませんが,それって健康ってことですよね?
著者: 黒木史仁 , 本村和久
ページ範囲:P.1773 - P.1775
ひとまず返答
一般に,症状がない人は,健康であることが多いです.しかし,健康かどうかは症状の有無だけで判断せず,心理・社会的な面も含めて判断します.また,症状のない状態でも,隠れた健康上の問題やリスクが存在する可能性があり,特定の病気や状態が進行する前は症状が現れないこともあります.そのため,症状がない場合でも,定期的な健康診断を受けることや,健康的な生活習慣を維持することをお勧めします.
Question 4 検査の正常値と異常値はどうやって決めているのですか?
著者: 本村和久
ページ範囲:P.1776 - P.1777
ひとまず返答
正常値については,大規模なデータを収集し,そのデータから平均値や標準偏差などの統計的な指標を計算して決める方法(身長など)や,臨床研究に基づいて,健康への影響を考えて正常値と異常値を決定する方法(血圧など)などがあります.また,個別の患者の特性や状態(健康状態や年齢,性別,妊娠などの要素)によっても,検査の正常値と異常値が変化する場合があり,特定の状況や文脈に応じて,適切な基準を使用することが重要です.
Question 5 健康診断は何を診断しているのですか?
著者: 安藤明美
ページ範囲:P.1778 - P.1779
ひとまず返答
健康診断は,健康維持やさまざまな病気の早期発見,生活習慣による病気を予防するために,法律に基づいて実施されるものです.問診(既往歴,職務歴,自・他覚症状などの確認),身体測定,視力・聴力検査,血圧測定,便・尿検査,胸部X線,血液検査などを行います.これらにより,糖尿病や脂質異常症なども,自覚症状がない早期の段階で発見することができます.さらに生活習慣の改善が必要な状態かなども診断しています.
Question 6 どういう状態になったら「死んだ」と言えるのですか?
著者: 今永光彦
ページ範囲:P.1781 - P.1783
ひとまず返答
「死んだ」という状態は,医学的な見地から言うと,呼吸・心臓・脳の全機能が完全に停止して生き返ることが不可能な状態のことを指します.死亡診断をする際には,医師は聴診器で呼吸と心臓が止まっていることを確認します.また,脳の全機能が停止していることを確認するために目にライトを当てて瞳孔が開いていること,光に対する反応がないことを確認します.医師はこれら3つの確認を行って「死んだ」と診断します.
Question 7 ぽっくり死にたいのですが,どうするのがよいですか?
著者: 今永光彦
ページ範囲:P.1784 - P.1785
ひとまず返答
いわゆるPPK(ピンピンコロリ)ですね.残念ながら,これをしたらぽっくり死ねるということはなかなかないですね.ただし,寝たきりにならずに亡くなる直前まで元気にしていたいというのであれば,足腰が弱らないようにすることが大事でしょうね.普段から運動を心掛けることは重要だと思いますよ.
Question 8 “長生き”するためには,何に注意すればよいですか?
著者: 木村琢磨
ページ範囲:P.1786 - P.1788
ひとまず返答
“長生き”するためには,身体を動かして暴飲暴食を避け,適切な栄養を摂ることを無理のない範囲で続けましょう.糖尿病などの生活習慣病があれば,その状態を改善・安定させましょう.健康診断やがん検診を受け,歯科受診し,怪我や事故に気を付けることも肝要です.寿命は予測が難しい面も多いですが,無理せず可能な範囲で規則正しい生活を心がけ,前向きに毎日を過ごしましょう.
簡単そうで難しい質問
Question 9 血圧って何ですか? 血圧が高いのはなぜいけないのですか?
著者: 有田卓人
ページ範囲:P.1790 - P.1791
ひとまず返答
「血圧」とは,心臓から送り出された血液が,血管の内壁を押す力(圧力)のことを言います.血圧は心臓が送り出す血液の量と血管(動脈)の抵抗によって決まります.血圧が高いこと自体による自覚症状は何もないことが多いですが,虚血性心疾患,脳卒中,慢性腎臓病などの発症原因となるので臨床的にはその管理が大事な状態です.高血圧症は生活習慣病の1つとされており,男女共に最も患者数が多い疾患として考えられています.
Question 10 血圧は1日何回測ればいいですか?
著者: 有田卓人
ページ範囲:P.1792 - P.1793
ひとまず返答
血圧は1日のなかでも変化するので毎日決まった時間に測定しましょう.基本的には起床後と就寝前の2回とされています.朝は起きて1時間以内,トイレを済ませ,食事や薬を飲む前に座って1〜2分程度安静にした後に測ります.就寝前にも座って1〜2分程度安静にした後に測るのが通常です.血圧測定は,正しいタイミングと姿勢で測定し,記録を残すようにしましょう.
Question 11 脈拍をみることでどんなことがわかるのですか?
著者: 林智史
ページ範囲:P.1794 - P.1795
ひとまず返答
脈拍とは心臓が拍動する回数のことで,1分間の回数で表します.通常であれば安静時に,規則的なリズムであれば1分間に60〜100回未満であることが多いです.回数については,脱水状態や緊張するといった交感神経が刺激される状態だと脈拍は速くなり,就寝時や安静状態といった副交感神経が刺激される状態では遅くなります.リズム不整や異常な脈拍数だと判断したらまずは12誘導心電図を実施して波形を確認し,心臓の問題か,その他の問題かを判断します.
Question 12 体温って何を表わしていますか? 私の平熱は何℃ですか?
著者: 林智史
ページ範囲:P.1796 - P.1797
ひとまず返答
体温は,体内の代謝活動や炎症反応,ストレス反応など,身体の状態を示す指標の1つです.体温は常に35℃台半ば〜37℃台前半に保たれています1).この範囲であれば体の状態は良好と考えることができます.体温は視床下部の体温調節中枢でセットポイントとして制御されています.セットポイントというのは,身体が自然に維持しようとする体温レベルのことで,例えば感染症だとセットポイントが高くなり,発熱します.感染症が改善すると,セットポイントが元に戻り体温も正常化していきます.
平熱は人それぞれなのでなんとも言えませんが,体温は常に35℃台半ば〜37℃台前半に保たれていますので,この範囲内にあると思います.
Question 13 パルスオキシメーターは何を測っているのですか? 95%以下だと救急車を呼んだほうがいいと言われたので心配です.
著者: 林智史
ページ範囲:P.1798 - P.1799
ひとまず返答
酸素は生命を維持するために必要です.酸素は血液の成分であるヘモグロビンと結びつくと鮮やかな赤色になります.パルスオキシメーターはこの赤色の度合いを見て,酸素飽和度(SpO2)を計算しています.正常値は96〜99%とされていますが,SpO2が95%以下でも無症状なら異常とは見なさないことが多いです.また血流が悪いと正確に測定できず,低温や高温でも値がずれることが知られています.そのため呼吸器症状を含めた全身症状と合わせて考えるので,95%以下だから危険というわけではありません.
Question 14 動脈硬化って何ですか? どうすれば治りますか?
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.1800 - P.1801
ひとまず返答
心臓から全身に血液,酸素,栄養を送るのが動脈です.その内腔が狭くなり,詰まりやすくなるのが動脈硬化です.下水管を掃除しないとたまに詰まりますよね.血圧,血糖値,コレステロール値などが高い状態が続くことや喫煙で似た様なことが動脈に起こります.心臓や脳の細胞を養う動脈が詰まるとその先の細胞が死に重篤な状態になります.血圧,血糖値,コレステロール値を適切な値までコントロールして禁煙すれば,動脈硬化の進行は予防できます.すでにある動脈硬化は治らないかもしれないですが,進行を予防していきましょう.
Question 15 血液ドロドロ,サラサラってよく聞きますが,それってどういう状態ですか?
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.1802 - P.1803
ひとまず返答
どういう状態でしょう,医学的定義はたぶんないと思います(笑).おそらく血管が詰まりやすい,詰まりにくい血液の状態をわかりやすくイメージする表現だと思います.血液中の血糖値や脂質の値が高い状態が続くと血管が詰まりやすくなるので,それを「ドロドロ」と表現したのかと思います.一方,脳や心臓を養う血管が詰まりそうな,あるいは詰まったことがある人は血液が固まりにくいような治療を受けている場合があります.このような治療をしていると出血の際,血が止まりにくい状態になるので,それを「サラサラ」と表現したのかと思います.
Question 16 がんはなぜ転移するのですか?
著者: 竹内麻理
ページ範囲:P.1804 - P.1805
ひとまず返答
普通の細胞は一定の数以上には増えないように制御されています.けれども,がん細胞では,増殖と抑制のコントロールがうまくいかなくなり,増殖してしまいます.このがん細胞が血液やリンパの流れに乗って遠くの臓器やリンパ節に運ばれ,そこで新たに塊をつくることがあります.これを転移といいます.そもそも異常に増殖したり転移したりする性質をもつ腫瘍を「がん」と呼び,他の良性の腫瘍と区別しています.がんがなぜ転移するのかは,まだ完全には解明されていないのが現状です.
Question 17 睡眠は8時間はとらないと体に悪いですよね? 何時間寝ればよいでしょうか?
著者: 都留あゆみ , 松井健太郎
ページ範囲:P.1806 - P.1808
ひとまず返答
必要な睡眠時間は人それぞれ違いますし,同じ人でも年を重ねるごとに変化しますので,一概に何時間寝ればよい,とお答えすることはできません.慢性的な睡眠不足により身体的・精神的不調が生じやすいことがわかっているため,睡眠不足になりがちな若い世代は8時間程度の睡眠時間をとったほうがよいとされています.一方で,高齢になると必要な睡眠時間が短くなる傾向があり,実際に眠れる時間よりも長く床に就くと不眠の原因となることもあるため,注意が必要です.
Question 18 尿って何ですか? どのくらいの尿の出方が正常なのでしょうか?
著者: 安田隆
ページ範囲:P.1810 - P.1812
ひとまず返答
尿とは体内の老廃物などの不要なものや水分や食塩などで余分な分を水とともに体外へ捨てるために腎臓で作られているものです.人間は日々,さまざまなものを食べ,飲み,そして老廃物ができますが,一定状態を維持するために余分な分のほとんどは尿として体外に排泄されます.その量は1日に1〜2L程度です.残念ながらどの程度の尿量が健康によいのかはわかっていませんが,1日に1〜2L程度の尿量が出るように飲水を心がけることが勧められます.
Question 19 便って何ですか? どんな便が正常ですか?
著者: 横江正道
ページ範囲:P.1814 - P.1816
ひとまず返答
「便」には,小便と大便があります.小便は尿道から排出される液体物で,いわゆる尿のことを指し,一般的にはおしっこと呼ばれます.一方,大便は,肛門から排出される固体〜液体物で,いわゆる,「うんち」「うんこ」と呼ばれるものです.今回は,このうんち,うんこのお話をします.どんな便が正常かと言えば,適度に形が整った固体便が正常だと考えられています(図1a).
現在の医療においては,Bristol便形状スケール1)のタイプ3〜5の便が正常便とされています(表1).
Question 20 食べてなければ排便はないはずなのに,なぜ出るのですか?
著者: 横江正道
ページ範囲:P.1817 - P.1819
ひとまず返答
食事を食べなくても便(うんこ・うんち)は出ます.なぜならば,便は食べ物の残骸だけではないからです.
日本うんこ学会1)の会長で消化器外科医である石井洋介先生によると,うんちの組成で一番多いのは水分で,全体の8割程度を占め,残りの2割には,腸内細菌,食べカス(主に食物繊維),腸粘膜などが含まれています.うんちの5〜10%が「腸粘膜の細胞」で,腸の中では腸の細胞はわずか2日という驚異的なスピードで生まれ変わり,皮膚で垢ができるのと同じ仕組みで連日10g以上の“垢”が発生しています2).
Question 21 血管の中でなぜ血は固まらないのですか? なのになぜ血栓ができるのですか?
著者: 宮崎仁
ページ範囲:P.1820 - P.1821
ひとまず返答
血液が固まることを医学用語では「凝固」と呼びます.正常な状態では,血管の中で血液は凝固せず循環しています.その理由は血管の内側にある血管内皮の細胞に,血栓を防ぐためのさまざまな物質が存在しており,血管の中では凝固が起きないように厳重な制御を行っているからです.一方,血管,血流,血液成分のいずれかに異常が生じると,この制御は破綻します.その結果,血管内で不要な血栓がつくられ,病的な状態である血栓症が発生します.
Question 22 ワクチンってなぜ効果があるのですか? 副反応のないワクチンはなぜないのですか?
著者: 中山久仁子
ページ範囲:P.1822 - P.1824
ひとまず返答
ワクチンは病原体の一部または似た成分からできています.ワクチンを接種すると,その成分に対して,体の中に免疫ができます.その後に本物の病原体が体内に入ってきたときに,ワクチンによってできた免疫が発動し,病原体が増えて病気になるのを予防したり,重症になることを予防したりします.
副反応のないワクチンはありません.ワクチンは注射で接種すると,痛みや腫れがあったり,免疫への影響で,だるくなったり熱が出ることがあります.これらの反応は,体の免疫が刺激されたことによって起こりますが,2,3日で治まることがほとんどです.
診療編 〈診察・検査〉
Question 23 聴診器では何の音を聴いているのですか?
著者: 北村大
ページ範囲:P.1826 - P.1827
ひとまず返答
聴診器は,医師や看護師が患者の体内の音を聴くために使っています.主に使用するのは,心臓や肺,腸などの臓器の音を聴くときです.例えば,心臓であれば鼓動の音のリズムや雑音を聞いて病気がないか判断します.リズムは一定か,速さは適当か,心音のタイミングや強さ,聴かれる部位は適当か,過剰な心音はないか,心臓の弁の異常や血流に関連した心雑音などを聴取することで,不整脈や弁膜症,心拡大,心臓も関連した全身の病気を見つけることができます.肺であれば気道や気管支,肺から呼吸をするときに聴こえる音で,肺や気管支の病気がないかを判断します.肺炎や気管支炎,気管支喘息といった病気だけでなく,肺に水の溜まった肺水腫や,肺に穴が空いた気胸などを見つけることができます.腸の音は腸の動きやガスの移動に関する音が聴こえて,腸の病気がないかを判断します.腸が詰まってしまう腸閉塞がみつかることがあります.
Question 24 内科の先生はおなかを触って何をしているんですか?
著者: 平島修
ページ範囲:P.1828 - P.1829
ひとまず返答
おなかに限ったことではありませんが,患者さんに手を当てて診察をする目的は大きく2つ,病気を探すために情報を収集すること,診断後の治療の経過を追うことです.そのなかでも特におなかを触って診察すること(腹部の触診)で,痛みの範囲を特定すること,しこりを特定すること,肝臓や脾臓といった臓器の腫れがないかを確認することができます.腹部の触診によって特定の疾患を断定できるものではありませんが,腹部エコー検査やCT検査といった詳しい検査を行うべきかの参考になります.また,触診による痛みの消失は食事を再開する判断に役立ちます.
Question 25 心臓に雑音があるって言われましたが,それってどういうことですか?
著者: 角田那由香
ページ範囲:P.1830 - P.1832
ひとまず返答
心臓は全身に血液を循環させるポンプとして働いており,4つの部屋と,部屋の出口に4つの弁が付いています(図1).この“弁”は,逆流防止の機能を備えており,弁のお陰で血液は一方向のみに流れています.弁が壊れて血液の流れに異常が起こると,聴診器で心臓の雑音が聴こえます.しかし,心疾患以外にも貧血や感染症,甲状腺の異常が原因のことや,健常若年者でも雑音を聴取することはあり,原因精査には専門医の診察が必要です.
Question 26 心電図って,何がわかるんですか?
著者: 角田那由香
ページ範囲:P.1833 - P.1835
ひとまず返答
心臓は,心臓の筋肉(以下,「心筋」と略します)の中に電気が流れることで動いています.体の表面から心臓の電気の流れをグラフに記録したものが心電図で,心臓の動き方が反映されます.不整脈といった心臓が拍動するリズムや速さの異常,心筋梗塞といった心筋が酸欠になっている状態,心筋症などが心電図の異常として現れます.なかには症状を自覚している瞬間の心電図でないと診断が難しいものもあり,症状があるときの心電図が診断に有用です.
Question 27 レントゲン写真って,なんで体の中が見えるのですか?
著者: 朝日公一
ページ範囲:P.1836 - P.1839
ひとまず返答
レントゲン写真はX線が体内の組織や構造に吸収され,異なる組織の密度や厚さにより,吸収度が変化し,それが写真上で陰影として現れます.骨はX線をよく吸収するため白く,肺や軟部組織はあまり吸収しないため暗く映ります.これにより,内部の骨や臓器,異常な影,病変などが視覚的に捉えられます.症状や疾患の評価のためレントゲン写真を撮影します.
Question 28 超音波検査って何をみているのですか? CTとどう違うのですか?
著者: 亀田徹
ページ範囲:P.1840 - P.1842
ひとまず返答
超音波検査は超音波という耳に聞こえない音波を用いて体中を観察する検査です.ジェルを介して探触子(プローブ)を体に当て,超音波を体内へ伝搬させ,体内のある部位で反射して,超音波が探触子に戻ってくるまでの時間を測定します.その時間をもとに反射体までの距離が求められ,そこから白黒の画像が作られます.一方,CTとはcomputed tomography(コンピューター断層撮影)の略で,身体の周りからX線を当て,体を通過したX線情報をコンピュータで解析することで断層画像(輪切りの画像)を得る検査です.
Question 29 CTとMRIの違いは何ですか?
著者: 朝日公一
ページ範囲:P.1844 - P.1847
ひとまず返答
CTとMRIは,異なる原理に基づいて体内の画像を作成する医療検査法です.CTはX線を使用し,断層画像を生成します.骨や組織の形状がよくわかり,出血や骨折の検出に適しています.一方,MRIは磁気と無線波を使用し,組織の水分や病変の情報を提供します.脳や脊髄,関節,内臓の詳細な構造や病変の評価に優れています.
Question 30 尿検査では何をみているのですか?
著者: 太良史郎
ページ範囲:P.1848 - P.1849
ひとまず返答
尿は体内での代謝の結果生じた老廃物が,腎臓を通して水分とともに排泄されたものです.尿を検査することで,腎臓についての情報のほか,体の代謝の状態や老廃物が蓄積していないか,老廃物の排泄機能が低下していないかといった身体の情報を得ることができます1,2).また尿の通り道である,腎臓・尿管・膀胱・尿道までの病気についての情報も得られます.
Question 31 血液検査でわかるものをすべて調べてください.詳しく血液検査をすれば健康かどうかわかりますよね?
著者: 太良史郎
ページ範囲:P.1850 - P.1851
ひとまず返答
血液検査項目は膨大であり,できる検査をすべて行うことは現実的ではありません.また血液検査で異常がないこと=健康というわけでもありません.あなたの健康問題に対して一緒に考えていきたいと思いますので,よろしければ,網羅的に血液検査を実施したい理由について教えていただけますか?
Question 32 アレルギーだと思うのですが,アレルゲンを全部調べてくれますか?
著者: 星哲哉
ページ範囲:P.1852 - P.1854
ひとまず返答
(以下は「Chat GPT」による回答です)
申し訳ありませんが,アレルギーに関するすべての情報を提供することはできません.アレルギーは非常に広範なトピックであり,さまざまな種類のアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)や症状,診断方法,治療法などが存在します.アレルギーに関する情報をより具体的に知りたい場合は,特定のアレルギーについての質問や関心事を教えていただくと,より具体的な情報を提供できるかと思います.
Question 33 こんなに調子が悪いのに,検査ではなんともないと言われました.どうすればよいですか?
著者: 星哲哉
ページ範囲:P.1855 - P.1857
ひとまず返答
(以下は「Chat GPT」による回答です)
1.一時的な問題:症状が一時的なものであり,検査時には既に回復していた可能性があります.もし症状が再発しない限り,特別な治療は必要ありません.ただし,症状が継続する場合は,医師に再度相談してください.
2.健康的な範囲内の変動:人間の体は日々変化しています.検査結果が正常範囲内でも,一時的な体の変化や個人差による調子の変動があります.このような場合,自己管理や生活習慣の見直しを行うことで改善する可能性があります.
3.他の要因による症状:症状が身体的な問題ではなく,ストレスや不安,うつ病,睡眠障害などの精神的な要因によるものかもしれません.これらの症状は検査では見つけにくい場合があります.心理的な健康状態を改善するために,心理療法やストレス管理の方法を試してみることができます.
Question 34 がんが心配です.どんな検査をするのが一番いいですか?
著者: 奈良江梨子 , 公平誠
ページ範囲:P.1858 - P.1860
ひとまず返答
がんの検査にはいろいろとありますが,すべての検査が必要なわけではありません.自覚症状,過去の病歴,現在の病気,家族歴,生活習慣(喫煙や飲酒,職業など)などに基づいて,適切な検査を受けることが推奨されます.また,どんな検査を受けるかは,目的によっても異なります.一般的な検査は,がんのスクリーニング検査,症状に基づく検査,がんのリスクに基づく検査です.現在自覚症状はないけれど,がんが心配な方は,有効性が確立した対策型がん検診を受けることが推奨されます.わが国では,市区町村が行う住民健診が該当します.対象となっていたら,定期的にがん検診を受けましょう.
Question 35 健診で測った腫瘍マーカーの値が少し高いと言われました.がんではないでしょうか?
著者: 奈良江梨子 , 公平誠
ページ範囲:P.1861 - P.1863
ひとまず返答
健診の腫瘍マーカーが高いことが,必ずしもがんであるとは限りません.腫瘍マーカーは,がんの種類によって特徴的に産生される物質であり,がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます.がん細胞の数や,がん細胞が産生する物質の量が多くなると値が高くなるため,腫瘍量が少ない早期がんではほとんど血中に増加せず,健診において有用性の確立した腫瘍マーカーはありません.一方,加齢や喫煙,感染症,糖尿病など良性疾患でも異常値となることがあるため,腫瘍マーカーはあくまでもがん診断の補助として活用されるべきであり,がんかどうかは画像検査などほかの検査と合わせて医師が総合的に判断します.
Question 36 コロナの検査が陰性なら大丈夫なんじゃないですか? 仕事に行っていいですよね?
著者: 尾田正仁 , 森伸晃
ページ範囲:P.1864 - P.1865
ひとまず返答
新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)の検査で陰性の結果が出たということは,「その検査を行った時点では感染が確認できなかった」という意味になります.また,検査のタイミングや検査の種類によっては新型コロナに感染していたとしても偽陰性と結果が返ってくることがあります.したがって,陰性の結果が出れば大丈夫,つまり新型コロナに感染していないというわけではありません.検査が陰性で仕事に行く場合でもマスクを着用する,手洗いを行う,他者と適切な距離を保つなど感染症対策を行うことが重要です.
Question 37 コロナの抗原検査とPCR検査とはどこが違うんですか?
著者: 尾田正仁 , 森伸晃
ページ範囲:P.1866 - P.1867
ひとまず返答
新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)の抗原検査とPCR検査は,その目的と方法に違いがあります.PCR検査はウイルスの遺伝情報を検出し,特に発症2日前から発症6日程度までの感染初期に高い精度で結果を得ることができます.これに対して,抗原検査は新型コロナに特有の蛋白質を検出します.抗原検査の特徴としては,短時間で結果が出るという利点がありますが,PCR検査に比べて検出率は劣るとされています.したがって,抗原検査やPCR検査の選択は検査の目的や時間の制約などの状況によります.
〈予防・治療〉
Question 38 運動は1日何分やれば十分でしょうか?
著者: 岡崎研太郎
ページ範囲:P.1868 - P.1870
ひとまず返答
一般的には,1日30分程度の運動が健康に良いとされています.ただし,減量,骨粗鬆症の予防,認知症の予防,血糖値の低下,心機能の維持,筋力の維持などの目標によっても,推奨される適切な運動時間は異なってくるでしょう.
また,運動の種類によっても,運動の強度が異なるため,運動時間や効果は変わってきます.○○さんの健康状態や周囲の状況,環境も考慮したうえで,運動の種類と強度から適切な運動時間を考えてみてはどうでしょうか.
Question 39 食事も運動も気を付けているのに、なぜ体重が減らないんですか?
著者: 岡崎研太郎
ページ範囲:P.1872 - P.1873
ひとまず返答
一般的には,体重は摂取カロリーと消費カロリーの差で決まります.体重が減らないということは,消費カロリーと摂取カロリーが同じか,摂取カロリーのほうが多いことが考えられます.体重を減らすには,消費カロリーを増やすか摂取カロリーを減らすことが有効です.まずは,現在の食習慣と運動習慣について,医療者とともに見直してみることを勧めます.そうすることで,あなたに最適な減量作戦が立てられると思います.
Question 40 お酒は飲みすぎるといけないと言われますが,どのくらいなら大丈夫ですか?
著者: 加藤篤之 , 川口満理奈 , 大塚文男
ページ範囲:P.1874 - P.1877
ひとまず返答
飲酒量については,1日の平均飲酒量が増えれば増えるほど,がん,高血圧,脳出血,脂質異常症などを発症するリスクが上がると言われています1).生活習慣病を防ぐためには飲酒量は少なければ少ないほどよいと言えます.生活習慣病がない場合でも,男性の場合はビール500mL 1缶程度(日本酒1合,焼酎100mL,7%チューハイ350mL 1缶),女性の場合は男性の1/2〜2/3程度に抑えるほうがよいと思います.
Question 41 サプリメントは飲んでいいですか? 飲んだほうがいいですか?
著者: 副島佳晃 , 川口満理奈 , 大塚文男
ページ範囲:P.1878 - P.1880
ひとまず返答
サプリメントは適切に使用することで,普段の食事だけでは摂取することが難しい栄養素を補うことができる場合があります.しかしながら,あくまで食事,運動,休養の質を高めるものとして補助的に使用することが重要です.医薬品とは異なるため,安全性や有効性に十分に注意し,自己判断での複数種類のサプリメントの利用や医薬品との併用は避ける必要があります.使用する場合には使用状況を記録して,不調を感じたらすぐに使用を中止して医療機関を受診しましょう.
Question 42 ボケないためには,何をすればよいですか?
著者: 坂戸慶一郎
ページ範囲:P.1881 - P.1883
ひとまず返答
運動をすることは,さまざまな病気の予防にも役立ちますし,認知症予防にも良いのではないかと言われています.また,バランスの良い食生活を心がけましょう.頭を使う作業も良いと思います.日常生活で新しいことにチャレンジしたり,新聞や本を読んだりすることで,脳の活性化につながります.人と話したり交流したりすることで,社交性を高めることが,認知症予防にも良さそうです.
また,高血圧症や糖尿病などの生活習慣病は認知症の危険性が高まると言われています1).それらの薬を飲めば認知症を防げるということではないですが,食事療法・運動療法と必要な薬物療法などをして,さまざまな病気を防ぎたいですね.
残念ながら認知症予防について研究で明確な成果が出ているものはないのですが,さまざまな生活上の工夫をすることが良さそうですよ.
Question 43 健康診断のオプションは何を追加すればよいですか?
著者: 宮崎景
ページ範囲:P.1885 - P.1887
ひとまず返答
事前に聞いていただきありがとうございます.健康診断のオプションに載っている項目は,必ずしもすべてお勧めというわけではありません.必要のない検査を受けて,かえって〇〇さんにとって害になる場合もあります.具体的にどの項目が良いかは年齢と性別,癌家系かどうか?などによって変わりますので調べてみましょう.
(時間的にその場で調べるのが難しければ,「次回受診日までに,〇〇さんにお勧めの項目をしっかり調べておきますので宿題とさせてください」と持ち帰る)
Question 44 健診でピロリ菌抗体が陽性と言われました.どうすればよいですか?
著者: 宮崎景
ページ範囲:P.1888 - P.1889
ひとまず返答
ピロリ菌抗体検査だけでは,必ずしもピロリ菌がいると確定したわけではありません.仮にピロリ菌がいたとして,どのように対処したいかのご希望に応じて,精密検査を進めるか,何もせずに様子をみるかを相談したいと思います.まずはピロリ菌がいたとしたら,何が問題かについてお話ししましょう.
Question 45 妊娠しているかもしれません.薬を飲んでも大丈夫ですか?
著者: 明石芽未 , 岩田智子 , 鳴本敬一郎
ページ範囲:P.1891 - P.1893
ひとまず返答
「妊娠しているかも」と思った理由があったのですね.仮に妊娠していた場合,妊娠週数や薬の種類によって薬による胎児へのリスクが変わります.妊娠2〜3週末までは妊娠が継続されていれば胎児に薬の影響が残らない時期,妊娠4〜12週末までは胎児の薬剤感受性が高く奇形(催奇形性)が問題になる時期,妊娠13週以降は胎児の機能的異常や発育(胎児毒性)が問題になる時期です1).これらのリスクを踏まえて妊娠中でも必要な薬を内服することは可能です.どうするか一緒に考えていきましょう.
Question 46 血圧の薬は死ぬまで飲まないといけないと言われました.本当ですか?
著者: 一戸由美子
ページ範囲:P.1894 - P.1895
ひとまず返答
高血圧は風邪とは違って,薬を飲んで数日で治ってしまう病気ではありませんので,服用を続ける必要があります.血圧を下げる薬は効果が切れると血圧は元の状態に戻り,上昇してきます.ですから薬を飲み続け血圧を良い状態に保つことが大切です.しかし,高血圧は生活習慣病と言われるように,血圧を高くするような生活習慣を改善することで,血圧が低下し経過によっては降圧薬を減量や中止できる場合もあります.
Question 47 コレステロールの薬はいつ(どのタイミングで)飲めばよいですか?
著者: 一戸由美子
ページ範囲:P.1896 - P.1897
ひとまず返答
コレステロールの薬にはいくつか種類があり,飲む回数やタイミングが異なりますので,医師の指示通りに服薬いただくのが基本となります.薬は肝臓でのコレステロールの合成を抑えますが,コレステロールは夜間に合成されるため,一般的には夕方に飲んだほうが効果が高いと言われています.
Question 48 認知症にならないための薬がほしいです.よい薬はありますか?
著者: 木村琢磨
ページ範囲:P.1899 - P.1901
ひとまず返答
残念ながら,現在,認知症の予防に効果があるお薬はありません.認知症の発症を高める可能性がある糖尿病や高血圧,脂質異常症の方は,必要に応じてお薬を飲み安定させることが,認知症の予防にある程度,期待できます.特に病気のない方は,お薬よりも適度な身体活動や禁煙,バランスのよい食事,過度の飲酒を控えることが肝要と考えられます.
Question 49 睡眠薬がほしいです.友達がこの薬は軽いから安全と言っていました.処方してくれませんか?
著者: 松井健太郎
ページ範囲:P.1902 - P.1904
ひとまず返答
睡眠薬の処方は,それが本当に必要であると判断されたときにのみ行います.まず,○○さんの睡眠問題について詳しく教えてください.一時的なものなのか,それとも長きにわたるものなのか.その問題が日常生活にどのような影響を及ぼしているか.何か特定のきっかけがあったのかもしれません.
睡眠薬によっては依存のリスクがありますし,その他の健康問題を引き起こす可能性もあります.ご友人のアドバイスはありがたいのですが,必ずしも○○さんに適しているわけではないかもしれません.
Question 50 以前処方してもらってとっておいた薬が家にあります.飲んでいいですか?
著者: 三澤美和
ページ範囲:P.1905 - P.1907
ひとまず返答
病院や診療所で処方される薬は,製造の段階で3〜5年経っても効き目が変わらないように,品質管理してつくられています.市販の薬は外箱に使用期限が書いてあるので自分で確認できます.使用期限の目安はあくまで正しい保管方法で置いてあった場合です.お薬は「そのとき,最適なもの」を医師が患者さんに処方しているので,「今の自分に合うものかどうか」はわかりません.できれば長期間置いているものは一度医師や薬剤師に聞いてから使用してください.
Question 51 以前この抗生剤でよくなったのに,なぜ今回は処方してくれないのですか?
著者: 三澤美和
ページ範囲:P.1908 - P.1910
ひとまず返答
抗生剤(=正確には抗菌薬)は,細菌(ばい菌)を殺す薬です.喉が痛い,鼻水が出る,咳が出るなどの症状に代表される「風邪」は細菌ではなく,ウイルスが原因なので抗菌薬を使っても治りません.風邪は体に入ったウイルスを自分の免疫力で治す病気です.抗菌薬を使うときは「風邪」ではなく,「細菌(ばい菌)」の感染が考えられるときなので,いつも抗菌薬が必要とは限らないんです.
Question 52 漢方薬には副作用はないから安心ですか?
著者: 樫尾明彦
ページ範囲:P.1911 - P.1913
ひとまず返答
漢方薬も薬であるため,頻度は少ないですが,副作用が起こる可能性があります.副作用を防ぐためには,自己判断で服用する量を調整せず,正しく服用しましょう.また副作用が出てしまったら,すぐに服用をやめて医師または薬剤師に相談してください.
(AIである「PERPLEXITY」による返答です)
Question 53 お薬が多すぎるので減らしたいです.どうすればよいですか?
著者: 矢吹拓
ページ範囲:P.1914 - P.1915
ひとまず返答
お薬の減らし方は,まずは主治医と相談することが重要です.主治医は◯◯さんの病状について詳しく知っているので,適切な判断ができます.お薬のなかには必要不可欠なものもありますので,自己判断で減らすのは避けましょう.主治医とのコミュニケーションを大切にし,症状やお薬の効果について正直に話すことで,最適なお薬の調整が可能になります.
医療制度編
Question 54 オンライン診療はなぜ反対する人がいるのですか?
著者: 吉田伸
ページ範囲:P.1919 - P.1921
ひとまず返答
オンライン診療を新しい診療形態としてみた場合には,どのような方にどのように用いれば効果や安全が保証されるかがわかりません.また,対面でないことによって患者満足度が下がったり,接続に手間や機器の購入が必要であったり,診療単価も下がってしまったりするというように,医師側が考えるからではないでしょうか.
Question 55 どうして予約したのにこんなに待たなければいけないのですか?
著者: 髙橋啓悟 , 吉田伸
ページ範囲:P.1922 - P.1924
ひとまず返答
予約いただいているのにお待たせすることになって申し訳ありません.診察がいつになるのかと不安に思われたでしょうか?
Question 56 平日は仕事があるので病院に行けません.救急の時間に行っていいですか?
著者: 菅長麗依
ページ範囲:P.1925 - P.1927
ひとまず返答
平日以外にも,週末や夕方〜夜間に一般診療を行っている医療機関はあります.受診理由に緊急性がない場合は,一般診療の受診をお勧めします.救急診療は原則的に命に関わる患者さんの対応が優先されるため,緊急性の高くない患者さんは後回しになります.また,時間外加算が課されて受診料も高くなります.お勤めの会社に産業医がいる場合は,ぜひ相談してみてください.
Question 57 なぜ自由に病院に行けないのですか? どうして紹介状を持ってこないと診てくれないのですか?
著者: 菅長麗依
ページ範囲:P.1928 - P.1930
ひとまず返答
日本の国民皆保険制度上,日常的な健康問題については,患者さんは医療機関を自由に選んで紹介状なしで受診することが可能です.しかし,専門的または高度な医療が必要な場合で総合病院などの大病院へ受診する際は,医療情報の適切な共有や効果的な治療を行うために,初めに受診した診療所などの医療機関からの紹介状が必要とされています.
実際に,患者さんが日常的な健康問題で大病院を受診することで,待ち時間が増加したり大病院が本来担うべき医療に支障が出たりすることなどが問題視されています.現在,国も医療機関の役割分担の必要性を提唱しており,紹介状なしで大病院を受診した場合は,救急や自由診療の場合を除いて,特別料金が課される仕組みになっています.
Question 58 入院になるかどうかは誰が決めているのですか?
著者: 鈴木智之 , 和田幹生
ページ範囲:P.1931 - P.1933
ひとまず返答
入院は疾患などの健康問題を改善するための重要な方法になります.しかし,入院にはメリットだけではなく,入院中に認知機能や日常動作能力を低下させてしまうといったデメリットもあります.○○さんの健康状態を改善するためには疾患そのものだけでなく,家族や社会的背景,さらに心理面も併せて意識することが必要です.入院を含めた医療の方針は,私たち医療者側と○○さん・ご家族などでともに決めるものになります.
Question 59 どういう状態になったら退院できますか?
著者: 浦田恵里 , 三原雅人
ページ範囲:P.1934 - P.1935
ひとまず返答
退院のことが気になるのはどうしてでしょうか? ご自宅のことが心配であれば,外出や外泊の調整をすることは可能です.入院してから体力が落ちてしまい退院が不安だと感じている場合は,介護保険などのサービスを利用することもできます.これから医師だけでなく看護師や薬剤師,リハビリスタッフなど多職種で,○○さんの退院をサポートします.何かお悩みごとがあれば一緒に解決策を考えますので,詳しくお話を聞かせてもらえませんか?
Question 60 セカンドオピニオンを受けるにはどうすればよいですか?担当の先生は気を悪くしませんか?
著者: 富田詩織
ページ範囲:P.1936 - P.1937
ひとまず返答
担当医が気分を害するのではないかと心配されているのですね.今医療の世界ではセカンドオピニオンは広く浸透していて,どの医師であっても当たり前の患者さんの権利として受け入れています.セカンドオピニオンを受けたい場合には,現在の担当医に率直に「〇〇病院でセカンドオピニオンを受けたいと思っているので紹介状をお願いします」と,希望を伝えてください.何か大層な理由をつける必要もありません.それによってあなたの治療が不利益を被るようなこともありませんから,安心して申し出てくださいね.
Question 61 食欲がないのでビタミン剤がほしいのに,どうして処方してくれないんですか?
著者: 富田詩織
ページ範囲:P.1939 - P.1941
ひとまず返答
食欲がないことでビタミン不足になることを心配されているのですね.食欲がなくてなかなか栄養があるものを食べられなくても,体にはビタミンの貯蓄がありますから,すぐにビタミンが不足して何らかの異常が起こってしまうことは多くありません.またビタミン剤は,「栄養補給」という意味合いでの処方は保険適用にならないことが,今から10年ほど前に決まりました.ですから「すぐに補充しなくては」と焦らずに,まずはなぜ食欲が出ないのかについて一緒に調べていきましょう.
Question 62 保険が利く薬と利かない薬は何が違うのですか?
著者: 平山陽子
ページ範囲:P.1942 - P.1943
ひとまず返答
保険が利くお薬(保険薬)は,医師が必要と判断した場合に処方されます.保険が利かない薬(市販薬)は,基本的に患者さんが自分の判断で薬局で購入し,症状に合わせて使うものです1).含まれている成分は保険薬に比べると少なめで安全な量です.
Question 63 ジェネリック医薬品って何ですか? 飲んでも大丈夫ですか?
著者: 平山陽子
ページ範囲:P.1944 - P.1945
ひとまず返答
後発医薬品(=ジェネリック医薬品)とは,先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される,先発医薬品と同じ有効成分,同じ効能・効果をもつ医薬品のことです.作っている会社が変わるので商品名は変わりますが,効果や副作用は基本的には変わりません.先発医薬品よりも安価なので,国としても使用を推進しています.
Question 64 治療費がかかりすぎて生活が苦しいです.どうすればよいですか?
著者: 舟越光彦
ページ範囲:P.1946 - P.1948
ひとまず返答
治療費の負担が大変なのですね.それなら,検査の項目を減らしてみましょう.高額なお薬でも変更できないものがありますが,削減できるものは減らしてみましょう.
Question 65 医師を目指しています.医師免許はどのようにして与えられるのですか?
著者: 武田裕子
ページ範囲:P.1949 - P.1951
ひとまず返答
まず,医学部または医科大学に入学します.日本の場合は6年制で,医師に求められる知識や技術,態度を修得する教育を受けます.すべての課程修了後に医師国家試験を受験し,合格すると医師の資格がある者として国に登録されます.それを「医籍登録」と言い,登録が完了すると「医師免許証」が交付されます.近年では,海外の医学部に進学する例も増えていますが,日本の医師国家試験受験資格を得られるかどうかは注意が必要です1).
Question 66 「学会のため休診」とありましたが,学会って何をしているところですか?
著者: 矢吹拓
ページ範囲:P.1952 - P.1953
ひとまず返答
学会とは,医師や医療関係者などが集まり,最新の医学知識や研究成果を共有する場です.学会では,専門分野の最新情報や治療の進歩についての講演やシンポジウム,症例報告,研究発表などが行われます.医師は学会を通じて専門分野における知識を深め,自身の診療に反映させることができます.休診の理由は,医師が学会に参加して情報収集や医療の向上を図るためであり,患者さんに対してよりよい医療を提供するための活動の1つです.
Question 67 専門医って何ですか? 認定医と専門医では何が違うのですか?
著者: 矢吹拓
ページ範囲:P.1954 - P.1955
ひとまず返答
認定医や専門医とは,各専門領域の学会や学術団体が定める資格であり,一定の基準をクリアした医師に与えられます.一定の基準は学会によって異なりますが,規定の診療経験やカリキュラム以外に,学術的な報告や研究論文,筆記試験,面接などの専門医試験に合格することです.専門医と認定医の違いについてですが,そもそも学術団体によっては「認定医」を設けていないこともあります.一般に「専門医」とは,初期臨床研修を修了後に規定の専門研修を受けて専門医試験に合格した医師に与えられる資格で,3年間の研修期間を経て取得するのが一般です.「認定医」は「専門医」よりも資格取得要件が簡易であり,所定の研修期間は不要であることが多いです.
Question 68 医師の間では,どのような意見が正しいとみなされるのですか?
著者: 矢吹拓
ページ範囲:P.1956 - P.1957
ひとまず返答
医学の進歩によって,医療における最善の方法は絶えず変化しています.現在,多くの医師は,医学的なエビデンス(科学的根拠)に基づいて診療を行うことを正しい医療と考えるようになっています.これは「エビデンスに基づく医療(evidence based medicine:EBM)」と呼ばれています.EBMでは科学的根拠を1つの判断軸として,それに加えて患者さんの希望や周囲の状況,臨床医の経験を統合して方針を相談していきます.そのため,同じ状況でも判断が異なることもありますし,結果として医師の間でも意見の違いが生じることもあるでしょう.医師は科学的根拠を重視しがちであり,根拠に乏しい選択は好まない傾向にあると思います.
説明・回答にまつわるエトセトラ
伝える力
著者: 大野毎子
ページ範囲:P.1789 - P.1789
師長の眼差し
研修医1年目に,病棟で入院患者の家族に病状説明を行った.指導医と事前に打ち合わせ,患者さんの経過,診断,治療,今後の見込みなどを説明した.私は面接を終え,過不足なく説明できたと思っていた.しかし,それを見ていた看護師長が私に笑顔で声をかけてくれた.「先生の説明は,立て板に水なんですよね.」私が説明の際に,早口になっており,患者家族は説明が腑に落ちず,置いてけぼりになっていることをしっかり教えてくれた.このフィードバックは卒後30年目を迎えた今も心に残っている.
その後から,内容だけでなく伝え方を考えるようになった.それには,話す環境のこと,また,冒頭は来所への謝意の表明,自分や同席者の紹介,最後はまとめを入れるというような話の進め方のこと,句読点を意識して話す,強調するときは相手の目を見る,紙に文字や図を書いて説明するなどの話し方の工夫が含まれる1).最後はまとめをしたあと「質問やご心配なことはないですか?」といって相手の言葉を待つ.話し方では,研修医のころは無言の時間をうまく使えなかった.今はゆっくり話して間を置くようにしている.このほうが一度に多くの情報を提供するより,伝わるという実感がある.「間」は患者や家族が聞いたことを消化する時間でもあり,それぞれが自分の意見をまとめている貴重な時間でもある.あれ以降,私の面接では当時の師長の代わりにもう一人の自分が,自分の面接を見ており,相手に伝わったかどうかを点検している.
身体診察が患者に語るもの
著者: 金城光代
ページ範囲:P.1809 - P.1809
60代後半の外国人男性が総合内科外来を予約外受診した.2週間の湿性咳嗽を主訴に受診した救急外来では,肺炎随伴胸水として胸水穿刺と抗菌薬治療が開始された.その後,専科では担当医から詳しいCT所見の説明と胸水の原因となりうる背景疾患の可能性について詳しい説明がなされた.胸水穿刺後のフォローは2週間後に予定されていた.半年前の定期検診を自国で受けたが問題はなく,大きな既往のない非喫煙者である.日本と自国を行き来する大きな組織のVIPという立場の方である.
予定外来よりも5日前に総合内科外来を受診されたのは,咳が続くため,何か原因がほかにあり得るのかを心配されていた.
難治の慢性疾患につきあうのは誰?
著者: 川島篤志
ページ範囲:P.1843 - P.1843
「この病気って治らないのですか?」こんな質問をされたら,皆さんはどう答えますか?
病院の新患外来の胸部異常陰影精査で,偶然見つかってしまうやっかいな疾患に非結核性抗酸菌症(nontuberculous mycobacteria:NTM)があります.この疾患に遭遇したとき(疑い例含めて),皆さんはどうされていますか? その後の対応は適切になされていますか? 患者さんは困っていたり,悩んでいたりしませんか?
「治るんですか?」
著者: 清田雅智
ページ範囲:P.1884 - P.1884
その患者さんは30代の男性であったが,近医で撮影されたCTで頸部,鼠径部のリンパ節腫脹がありリンパ腫ではないかと紹介された.既往歴では,近医の救急外来に,胸痛や頭痛などの症状で頻回に受診して,器質的な問題はないと指摘され続けていたため不安障害も併存していると推察されていた.診察すると明らかな重症アトピー性皮膚炎があるが,本人はステロイドに対する抵抗感が強く,プレドニゾロンの内服は絶対にしたくないと言っている.さらに数10万円する“医療機器”を自ら購入して自己治療していたが治らないとも言っていた.話してみて少し理解能力が低い印象があるものの,独身で定職には就いており普通に会話は成立していた.後に精神科医に評価をしていただいたときに養育手帳Bを保持している発達障害があることがわかったが,既往歴を聞いても語ってもらえなかったので当時は強迫症の要素があるとだけ理解していた.
彼は,以前にステロイドの外用や内服を皮膚科で処方されたことがあり,よくならないといって中断になった経緯があった.このため副作用も気にしていた.
自分はどうしてこんなに体調が悪いのですか?―『ドクターショッピング』をする患者さん
著者: 米本崇子 , 塚田(哲翁)弥生
ページ範囲:P.1890 - P.1890
患者さんは体調に関する不安・疑問が解決されないと,次から次へと複数医療機関を受診する,いわゆる『ドクターショッピング』行動につながります.採血・画像診断結果,診療情報提供書をもって受診される『セカンドオピニオン』とは違い,前医の診療内容がまったくわからないところから手探りの診察となり,かつ,わかりやすい病名では説明できないことが多く,大変困ります.
そのような患者さんを診察するときには,いつも以上に患者さんに寄り添い,丁寧に説明を行うことが必要です.深呼吸をして,主訴の聴取から長時間になると覚悟を決めてから,診察室に呼び入れましょう.
「腰にご先祖様の霊が憑いて困っている」と相談されたら―物語能力の使い方
著者: 宮崎仁
ページ範囲:P.1898 - P.1898
「センセイ,腰になぁ,ご先祖様の霊が憑いてしまって困っとるのよ.何とかならんもんかねぇ」
夏のある日のこと,九十歳にもうすぐ手が届くキクさんという患者さんが,私の診察室にやって来て,そう言いました.
看取りで医師ができること
著者: 宮本翔平 , 塩尻俊明
ページ範囲:P.1938 - P.1938
私が初めて看取りを経験したのは,初期研修1年目の4月のことだった.当時その研修病院は完全主治医制をとっており,休日でも夜間でもまずは担当医のPHSに連絡が来るような状況だった.夜2時頃,心拍が伸びてきていると連絡を受け,上級医に連絡を取りながら急いで病院へ向かった.病室に入ると,すでに家族はベッドの周りに集まっており,家族の視線は「医師」である私に集まった.「先生,この人のためにしてあげられることはありますか?」と聞かれ,当時の私は何も答えることはできなかった.結局,心拍が停止し上級医が来院して死亡確認するまで,私は病室の中で置物のように待っていることしかできなかった.
家族の「最期に何かしてあげたい」という思いに対しどう答えたらよかっただろうか.1つは,患者さんと家族が過ごす最後の時間を大事にしてあげるべきであったと今となっては思う.患者さんと家族にとって,患者さんの死に立ち会うという人生の大事なイベントにおいて医師というのは直接の関係者ではない.医師として患者さんにできることがそれ以上ないのであれば,せめて病室の外に出て患者さんと家族だけの時間をつくってあげるべきであったと思う.
連載 知らないとヤバい! リウマチ・膠原病のアレやコレ・2
RA治療中のヤバい病態 その②「間質性肺疾患」
著者: 猪飼浩樹
ページ範囲:P.1958 - P.1965
関節リウマチ(rheumatoid arthritis:RA)は有病率0.5〜1%であり1),非常に患者数の多い疾患である.そのためプライマリ・ケア医やジェネラリストが知っておくと患者アウトカムが向上する事象は多い.
今回は,RAの経過中に注意すべき病態である「間質性肺疾患(interstitial lung disease:ILD)」について解説し,知っておくと患者アウトカムに直結するポイントを整理したい.自分自身でRAの診療を行っていなくとも,RAを併存している患者をみた場合には,前回解説した「メトトレキサート(MTX)によるさまざまな毒性(特に血球減少)が起きていないかどうか」と同様に,「ILDがないかどうか」は気をつけたいポイントである.
ここが知りたい! 欲張り神経病巣診断・28
手がしびれる! 脳梗塞?—手の末梢神経障害②/手根管症候群の診断と身体診察
著者: 難波雄亮
ページ範囲:P.1966 - P.1970
手根管症候群では夜間や明け方の手のしびれを訴えることが多いですが,手のしびれをきたす疾患でほかにも注意すべき疾患があります.手の末梢神経障害では手根管症候群の次に多い疾患です.肘を中心に,丁寧に問診と診察をすれば診断しやすいです.それでは症例をみていきましょう.
事例から学ぶ 糖尿病のコーチングマインド・3
伝える—患者自身の取り組みを尊重する
著者: 金子由梨 , 佐藤文彦 , 松澤陽子 , 石井均
ページ範囲:P.1971 - P.1975
症例提示
64歳男性,20年前より2型糖尿病.身長160cm,体重79kg,BMI 31
病歴:強化インスリン療法に変更し,3回の教育入院を繰り返すが,HbA1cは8〜9%であった.4回目の入院を担当したことを契機にその後の治療に関わるようになる.
糖尿病合併症:単純網膜症,腎症2期,末梢神経障害
明日から主治医! 外国人診療のススメ・7
外国人の生活習慣病
著者: 高柳喜代子
ページ範囲:P.1977 - P.1981
CASE
内科後期研修医(翔太)と家庭医(松本)が,「まつもとクリニック」の内科外来で…
翔太)松本先生! 先週,初診で来た50代のミャンマー人のアウンさんという男性,「だるい,口が乾く」というので採血したところ,HbA1cが11.6%もあります…….どうしましょう…….今日結果を聞きに来るのですが,どこかにすぐに糖尿病教育入院させなくちゃですよね?
松本)アウンさんは,これまでに糖尿病を指摘されたことはあったのかしら?
翔太)いえ,それが日本に6年も住んでいるのに,一度も採血したことがないと言っていました.収縮期血圧も145mmHgを超えていたし,LDLコレステロールも180mg/dL以上あって,肥満体型,ザ・メタボって感じなのに…….
松本)日本人は健診を受けるのが当たり前と思っているかもしれないけど,実は外国ではそれほど一般的ではないの.高血圧症や脂質異常症はあまり症状もないから,疾患に気づかない人も多いし,生活習慣病として予防するという考えもあまり浸透していないのよ.
翔太)でも僕,外国人に栄養指導とか,言葉が通じなかったり文化が違ったりして無理かなと思うし,そもそもちゃんと定期的に通ってくれるか不安です…….
松本)仕事だってあるし,いきなり入院と言われたらきっと戸惑うでしょう.外国人に生活指導をして定期通院に導き,改善結果を出すためには,いくつかコツがあるの.アウンさんが来る前に,テクニックをちょっと伝授するね.
ERの片隅で・7
ティッシュ山積みサイン
著者: 関根一朗
ページ範囲:P.1982 - P.1983
土曜の夕方、赤い夕日が救急車搬入口をスポットライトのように照らしている。ER内で救急搬送を告げるアナウンスが流れた。「10分後、救急車入ります。43歳男性、テニスの片付け中に回転性めまいを生じ、救急要請。麻痺や嘔吐なし。」
間もなくして、首にタオルをかけたスポーツウェアの男性が救急隊のストレッチャーで搬入された。「こんなめまいは初めてです。熱中症ですかね?」と言う男性に、担当する研修医は挨拶をして、神経診察を始めた。搬入直前に復習した眼振誘発試験でも有意な眼振はなく、MRIで中枢性めまいを精査する方針にしたようだ。
医学古書を紐解く・10
オスラー博士から日野原先生へ 受け継がれていく“平静と情熱の心”【後編】—Osler W. 『Aequanimitas』/日野原重明,仁木久恵(訳)『平静の心』
著者: 陶山恭博
ページ範囲:P.1984 - P.1987
Aequanimitasから平静の心へ
オスラー博士(Sir William Osler)の言葉と精神に強烈なインスピレーションを受け,その教育への情熱を受け継いだ日野原重明先生は,『Aequanimitas』を日本語に翻訳することを決意した.そして,同書の第3版から15篇を選び,さらに米国オスラー協会会員のKeynesがまとめたオスラー博士の講演集『Selected Writings of Sir William Osler』1)から3篇を追加し,合計18篇から成る『平静の心』が誕生した2).追加されたのは,オスラー博士が終生座右に置いた愛読書とその著者を紹介した「Sir Thomas Browne(トマス・ブラウン卿)」,医学生へのメッセージとして「Aequanimitas」と双璧を成す1913年4月20日のエール大学における講演「A way of Life(生き方)」,そして,オスラー博士の最後の講演となった1919年5月の英国古典学会の会長講演であり,オスラー博士の思想の統括と言うべき医学のサイエンスとアート論“Medicine is an art based on science”を格調高い文章で纏めた「The Old Humanities and the New Science(古き人文学と新しい科学)」だ.
『平静の心』の出版は単なる翻訳作業ではなく,10年もの歳月を要した情熱そのものだった.オスラー博士の講演・記述にはギリシャ・ローマの古典,旧約・新約聖書,中世〜近世にわたる欧米の文学や哲学,シェイクスピアの作品などからの引用がたびたび登場していた.こうした日本人には馴染みの薄い背景知識や出典を把握するために,日野原先生は英米文学に詳しい聖路加看護大学(現・聖路加国際大学)の仁木久恵教授と共訳を進め,オックスフォード大学のボドリアン図書館やマギル大学医学部のオスラー図書館にも足を運んだ.その過程は本誌『medicina』での日野原先生の長期連載「オスラー博士の生涯」(1972年8月号〜1982年11月号まで,全112回)でも紹介されている.例えば,エッセイ「Aequanimitas」は本連載の第80回で初めて日本語に翻訳され,当初,“心の平静”と訳されていた3).
目でみるトレーニング
書評
—岩田健太郎 編集—シン・感染症999の謎—Shin・999 Wonders of Infectious Diseases フリーアクセス
著者: 賀来満夫
ページ範囲:P.1825 - P.1825
2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症は世界的に流行する規模の感染症:パンデミックとなり,世界全体が混乱に陥いることとなった.わが国において,5類となった現在においても,再び感染が増加しつつあり,あらためて新興感染症のもつ脅威,怖さが浮き彫りとなっている.
このような未曽有な新型コロナウイルス感染症流行時に,わが国を代表する感染症専門医である神戸大学大学院医学系研究科微生物感染症学講座感染症治療学分野の岩田健太郎教授により編集された『シン・感染症999の謎』が刊行された.
—𠮷村 長久,山崎 祥光 編—トラブルを未然に防ぐカルテの書き方 フリーアクセス
著者: 川崎誠治
ページ範囲:P.1871 - P.1871
本書は,北野病院の𠮷村長久院長と山崎祥光弁護士の編集で上梓されたものである.適切なカルテ記載の重要性を認識し,もともと関心をもっていらっしゃった𠮷村院長が,医師の資格もあり臨床経験もおもちの山崎弁護士にカルテ記載に関する講演を数多く依頼してきた.その講演の内容が土台となったのが本書である.このお二人の組み合わせこそが,独特の視点をもつ本書の出版を可能にしたと言える.北野病院医療安全管理室の先生方と山崎弁護士が中心になり著述されているが,本書を読むと,「カルテ記載のない事柄はなかったことになる」ということがあらためて強く認識される.そのほかに,「何となくそうではないか」,あるいはぼんやりと「どうなのだろう」と思っていたいくつかのことが明瞭に説明・記述されており,大変参考になる.以下に例を挙げる.
・カルテと異なり,忌憚のない意見交換の場であるカンファレンスや医療安全事例検討会などの議事録は開示の義務はない(むしろ開示すべきではない).それと関連して開示・非開示の書類の区別を医療機関内できちんと定めておくべきである.
—野木 真将・橋本 忠幸・松尾 貴公・岡本 武士 著—チーフレジデント直伝!—デキる指導医になる70の方法—研修医教育・マネジメント・リーダーシップ・評価法の極意 フリーアクセス
著者: 志水太郎
ページ範囲:P.1918 - P.1918
本邦初,チーフレジデント視座からの指導医向けテキスト
本書の役割は,巻末の対談で野木真将先生が仰っている「みんなの(リーダー育成のための解決法に対しての)共通認識を広げ,育てるツールとして役立ってほしい(p.331)」という言葉に集約されていると感じます.日米の伝統的なチーフレジデント制度をもつ研修病院でチーフレジデントを経られたメンバーらが,指導医として,ミドルレベルのマネジャーとして,教育者としてどのようなことに気を付けながら診療・教育・マネジメントを実践していけばよいかを指南してくださっています.しかし,押しつけのような形ではなく,ソフトな語り口調で,“研修教育をしたことがない”“自信がない”という読者の皆さまにも,入りやすい構成になっているのではないかと思います.
本書で評者が個人的にお勧めしたい章はたくさんあります.以下列挙すると,カンファレンスを盛り上げるためのコツは?(p.70),病棟などで少人数相手の指導で役立つポイントは?(p.96),EBMをどうやって教えれば良いか?(p.102),せっかく作ったカリキュラムがうまく共有されてないときの良い対処方法(p.179),当直表をどのように作成,調整したら良いですか?(p.228),医学生を上手に勧誘するコツは?(p.251),採用過程でのアドバイスはありますか?(p.254)……このように,他書にない“痒い所に手が届く”“それ,興味ある!”指導医向けの内容が満載です.Think-pair-shareやEPA(Entrustable Professional Activity),Bloom's taxonomyなど,経験値のある指導医たちが多く踏襲していると思われる重要な概念の共有まで行き届いていて,とても勉強になると思います.その他,忙しい臨床現場で効率的に教えるコツ(p.26),多くの指導医が直面するであろう世代間ギャップをどのように考えるかの章(p.34),うつ(p.277),やBurnout(p.283)への対処,医学教育を学ぶプログラムの紹介(p.296)なども,多くの指導医たちのサポートになるのではないでしょうか.書評タイトルに記載したように,役職として責任あるレジデントを束ねるミドルマネジャーらが集結して記述された指導医指南書は,評者の調べる限りこれまで日本にはなかったのではないかと思います.新世代の後輩たちを指導する立場のすべての指導医たちにお薦めの,珠玉の一冊です.
—中島 俊 著—入職1年目から現場で活かせる!—こころが動く医療コミュニケーション読本 フリーアクセス
著者: 竹林崇
ページ範囲:P.1976 - P.1976
医療において,コミュニケーションは基盤となる知識および技術である.どれだけ確実性の高い医療技術があったとしても,それを施術してその後のサポートを行う医療従事者に対する納得と信頼を得られなければ,対象者はそれらの技術は選ばないかもしれない.また仮に選んだとしても,医療従事者に対する不信は,対象者の心身の予後を悪化させる可能性もある.これらの観点から,医療者がコミュニケーションを学ぶことは,エビデンスや知識・技術を学ぶことと同様,非常に重要なものであると考えている.
しかしながら,医療者におけるコミュニケーションについては,養成校などでも特化した授業が少なく,また経験的に実施してきた先人も多いため,エビデンスを基盤としたコミュニケーション技術に対する教育はいまだに確立されていない.一方,情報化の時代がさらに加速する昨今,医療事故やミスに関する報道が一気に加熱することで医療に対する対象者の不信感が過去に比べて膨らんだという社会的背景もあり,コミュニケーションや接遇に対する必要性がより一層重視されている.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1754 - P.1758
読者アンケート
ページ範囲:P.1995 - P.1995
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1996 - P.1997
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.1998 - P.1998
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1999 - P.1999
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.2000 - P.2000
基本情報
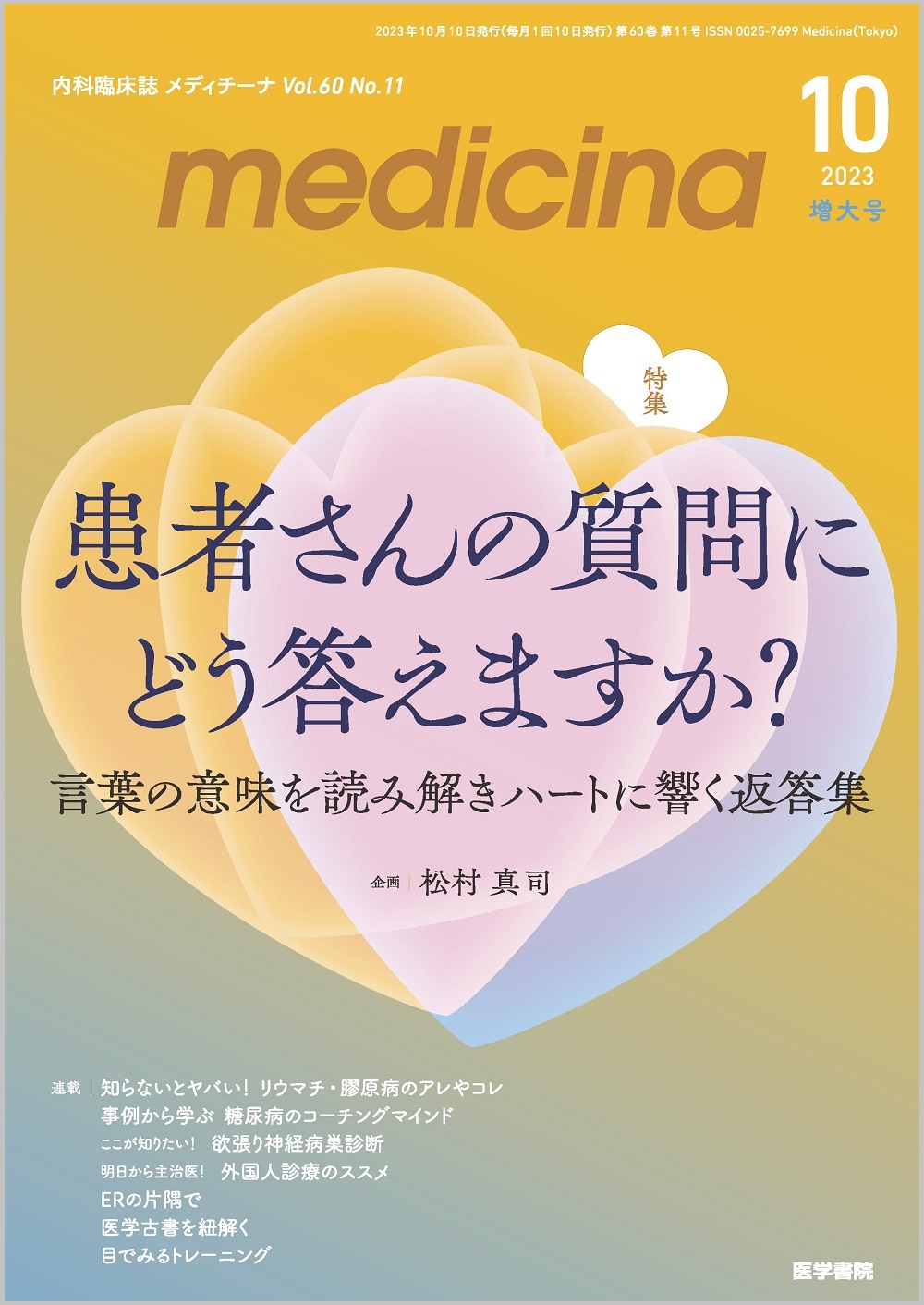
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
