本特集で取り扱う慢性疾患とは治療や経過が長期に及ぶ疾患の総称であり,高血圧や糖尿病,脂質異常症といった生活習慣病や,慢性心不全,喘息,慢性閉塞性肺疾患(COPD),慢性腎臓病(CKD),肝硬変,認知症,骨粗鬆症などが挙げられる.また,本特集では症候として不眠や便秘,そしてワクチンやがん検診などのヘルスメンテナンスも含めて解説している.これら一つ一つは非常にcommonで読者の皆様も診る機会が多いと思われるが,適切な診療を継続することは難しいと私は感じている.その理由はいくつか挙げられる.
雑誌目次
medicina60巻2号
2023年02月発行
雑誌目次
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
座談会
慢性疾患を診るのに必要な視点とは?—求められる“複眼的”診療
著者: 長野広之 , 大浦誠 , 松島和樹
ページ範囲:P.226 - P.233
治療や経過が長期にわたる慢性疾患診療には,急性疾患診療と異なる難しさがあります.一方で,特有の面白さもあります.本日は入院・外来・在宅と幅広い臨床現場で慢性疾患を診ているお二人の先生と,慢性疾患で考えるべきポイントについて幅広く議論できればと思います.(長野)
総論
慢性疾患のケアバンドルって何ですか?
著者: 松島和樹
ページ範囲:P.234 - P.238
Point
◎エビデンスが確立したケアを3〜5個まとめたものをケアバンドルと呼ぶ.
◎ケアバンドルは医療の質やEBMの面からみても有用である.
◎慢性疾患のケアバンドルを施設単位で作成するとよい.
慢性疾患のマルチモビディティは外来でどう意識したらいいですか?
著者: 大浦誠
ページ範囲:P.240 - P.243
Point
◎多疾患併存状態(マルチモビディティ:マルモ)への介入は,患者のできそうなこと(capacity)を支援し,患者負担(treatment burden)を軽減することが求められる.
◎その介入のバランスを患者と意思決定していくために有用なバランスモデルを紹介する.
慢性疾患に対する患者のモチベーションを上げるにはどうすればいいですか?
著者: 小澤秀浩 , 小坂鎮太郎
ページ範囲:P.244 - P.248
Point
◎慢性疾患の管理は,患者のセルフケアを支えることが重要である.
◎個人の能力やモチベーションに合わせた伴走型医療を提供する.
◎患者の行動変容を促すには,動機付け面接(MI)が有効なことが多い.
◎伴走型医療を実施するには,医療従事者の経験価値(EX)が豊かである必要がある.
高血圧
高齢患者では高血圧の目標値をどう決めたらいいですか?
著者: 渡辺綾 , 會田哲朗
ページ範囲:P.250 - P.253
Point
◎高齢者の降圧目標は余命や併存疾患,フレイルや認知機能を評価し検討する.
◎SPRINT試験,STEP試験の組入基準に該当する高齢者には,収縮期血圧130 mmHg未満の厳格な降圧管理も検討する.
◎フレイルや認知機能を定期的に評価し,過度な降圧治療を見直す.
Ca拮抗薬をよく使うのですが,注意することはありますか?
著者: 片山皓太
ページ範囲:P.254 - P.256
Point
◎慢性腎臓病(CKD)患者には,L型Ca拮抗薬処方よりもT/L型やN/L型を優先的に考える.
◎過降圧に気を付けて,少量からの投与を心がける.
◎グレープフルーツジュースのほか,相互作用する薬がないか,お薬手帳を確認する.
◎浮腫,逆流性食道炎,便秘,歯肉増生をみたらCa拮抗薬の副作用を疑う.
Ca拮抗薬,ACE阻害薬/ARB,さらにはサイアザイド系利尿薬を使用しても降圧目標に達しない場合,どうしたらよいですか?
著者: 石瀬裕子 , 本田優希
ページ範囲:P.258 - P.263
Point
◎治療抵抗性高血圧では,服薬アドヒアランス,生活習慣,外因物質の関与などを確認したうえで,二次性高血圧の可能性を考慮する.
◎二次性高血圧の診断のためには,病歴の聴取,随伴症状の確認,身体所見の評価が必須である.
◎二次性高血圧の背景疾患は年齢によって重点的に想定すべき疾患が異なる.
◎原発性アルドステロン症は特異的な所見に乏しく,本態性高血圧症と鑑別が困難であるため,より一層の注意が必要である.
◎治療抵抗性高血圧にはミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)の追加を考慮する.
脂質異常症
脂質異常症の一次予防としての薬物療法はどんな患者にするべきですか?
著者: 横田雄也 , 松下明
ページ範囲:P.265 - P.270
Point
◎一次予防としての脂質異常症の治療目的は,心血管疾患(CVD)発症を予防し,生命予後を改善することである.
◎一次予防は非薬物療法が中心であり,薬物療法の一次予防効果は限定的である.
◎家族性高コレステロール血症(FH)は早期診断・早期治療が生命予後改善に重要である.
◎生命予後改善を目的とした一次予防の場合,FHや糖尿病,慢性腎臓病,末梢動脈疾患がない患者において,60〜79歳の男性で,10年間のCVD発症リスクが20%を超える場合に,スタチン療法を考慮する.
◎最終的には,shared decision making(SDM)を実践して治療方針を決定する.
スタチン以外の脂質異常症の薬は実際使いますか?
著者: 水谷肇
ページ範囲:P.271 - P.274
Point
◎一次予防では治療の絶対的な管理目標を定めることは困難なので,スタチンの投与を検討する患者もいるが,追加の治療は不要である.
◎80歳以下の二次予防では全例ストロングスタチン(ロスバスタチン)の内服を行うが,二次予防の追加治療に関しては,心血管イベントリスクが高いと考えられる症例についてエゼチミブ(ゼチーア®)の追加投与を検討してもよい.
◎副作用でスタチンが内服できない高リスクの患者には,エゼチミブ投与が強く推奨されている.PCSK9阻害薬を検討する場合は専門医にコンサルトする.
◎高トリグリセリド(TG)は500 mg/dLを超えない限りは原則治療しない.二次予防としてスタチンを内服したうえでTGが高い場合,イコサペント酸エチルの投与を検討してもよい.心血管イベントリスクが高いと考えられる患者の第一選択はスタチンであり,フィブラート系薬との併用は行わない.
糖尿病
高齢患者にSGLT2阻害薬,GLP-1受容体作動薬は使うべきですか?
著者: 國友耕太郎 , 吉村文孝
ページ範囲:P.275 - P.278
Point
◎慢性心不全がある場合,SGLT2阻害薬はよい適応となる.
◎動脈硬化性心血管疾患・慢性腎臓病の既往がある場合,SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬は,両者ともによい適応となる.
◎高齢の糖尿病患者は,サルコペニア・認知機能低下・フレイルになりやすいため,ADL・認知機能・服薬アドヒアランスなどを考慮し,個々に薬剤選択をする必要がある.
DPP-4阻害薬はどんな人に何を目標に使うべきですか?
著者: 宮松弥生 , 谷崎隆太郎
ページ範囲:P.279 - P.282
Point
◎DPP-4阻害薬の臨床効果はそれぞれの薬剤で大きな差はない.多くは腎代謝だが,リナグリプチンとテネリグリプチンは腎不全でも用量調節が不要である.
◎近年はGLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬の心血管予後改善効果が明らかとなり,米国糖尿病学会(ADA)では心血管リスクの高い患者に対しては,これらの薬剤が禁忌ではない場合にDPP-4阻害薬よりもGLP-1受容体作動薬もしくはSGLT2阻害薬が推奨されている.
◎心血管リスクの高い患者であっても,GLP-1受容体作動薬およびSGLT2阻害薬が腎機能障害や副作用,アドヒアランスの問題で使用しづらい場合には,DPP-4阻害薬はメトホルミンに次ぐ第二選択薬として使用される.
高齢患者の糖尿病治療の目標は何ですか?
著者: 合田建
ページ範囲:P.283 - P.286
Point
◎糖尿病の治療目標は「血糖コントロール」だけではなく,個々人の人生の目標,QOLをともに考えていくことが重要である.
◎血糖コントロールの目標は重篤な低血糖イベントを回避しつつ,長期的な合併症を最小限に抑えることである.
◎貧血の回復期や溶血性貧血,肝硬変,透析患者などにおいて,血糖コントロールの指標としてHbA1c値は適さない.
◎血糖目標値は定期的に,患者とともに見直す必要がある.
糖尿病の血管障害ってどう診断,フォローすればいいですか?
著者: 山里一志
ページ範囲:P.287 - P.290
Point
◎糖尿病性神経障害の約半数は自覚症状なく進行するため,早期発見とフットケアが重要である.
◎糖尿病性神経障害のスクリーニングには,10 gモノフィラメント試験と128 Hz音叉による振動覚が有用である.
◎下肢閉塞性動脈硬化症では,約半数が典型的な間歇性跛行を呈さないため,血管危険因子を有する患者では,足関節上腕血圧比(ankle-brachial index:ABI)によるスクリーニングが重要である.
喘息,COPD
喘息とCOPDの吸入薬はたくさんありますが,高齢患者にはどれがおすすめですか?
著者: 森川昇
ページ範囲:P.291 - P.295
Point
◎喘息のkye drugは吸入ステロイド(ICS),COPDのkye drugは長時間作用性抗コリン薬(LAMA)である.
◎吸入薬のエビデンスは多数あるが,実臨床で診る患者と臨床試験に組み入れられている患者では背景が異なることがある.
◎吸入薬ではアドヒアランス維持とデバイス選択が重要になる.
◎高齢者ではアドヒアランス維持のため,1日1回吸入がデバイス1つで可能な吸入薬を選択することが多い.
◎吸入力が低下した症例ではDPI(dry powder inhaler)は使用困難なことが多い.
◎患者ごとに適切な吸入デバイスを決めるためには,医療者自身が吸入デバイスの特性を熟知する必要がある.
COPD
喘息のコントロールが悪いとき,生物学的製剤は考慮すべきですか? その前に考えておくことはありますか?
著者: 吉松由貴
ページ範囲:P.297 - P.302
Point
◎生物学的製剤は難治性/重症喘息の特定の患者に適応のある注射薬である.
◎難治性とされる多くの症例は,既存の治療や併存症の見直しで改善が得られる.
◎特に生活指導や服薬アドヒアランスに関しては主治医のていねいな関わりが求められる.
◎喘息の管理に難渋する場合は,早めに専門科へ紹介することが望ましい.
患者に禁煙してもらうにはどうしたらいいですか?
著者: 豊田喜弘
ページ範囲:P.303 - P.306
Point
◎禁煙はCOPD患者に対する必須の治療介入であるが,禁煙に消極的または拒否的な患者は少なくない.
◎禁煙に消極的な患者へ動機づけ面接法で介入すると,抵抗感を高めずに動機を引き出していくことができる.
◎禁煙指導は決して一筋縄にいくものではないが,医療者自身のコミュニケーションスキルやレジリエンスを高める絶好の機会である.
COPD患者でHOTを導入するタイミングはいつですか? 導入する際は何に注意すればいいですか?
著者: 江原淳
ページ範囲:P.307 - P.310
Point
◎在宅酸素療法(HOT)が生命予後を改善するのは,重度の安静時低酸素を伴う場合である.
◎中等度の安静時低酸素や運動時のみの低酸素に対して,HOTが生命予後や入院,QOLを改善することは示されていない.
◎医学的メリットと器材を導入・管理する物理的かつ金銭的負担をもとにHOTの導入を検討する.
慢性心不全
心不全にSGLT2阻害薬,ARNIって使わないといけないですか?
著者: 平松由布季
ページ範囲:P.311 - P.316
Point
◎stage C以上(有症状)のHFrEFには,ARNIとSGLT2阻害薬はクラス1で推奨されている.
◎stage C以上(有症状)のHFmrEF, HFpEFには,SGLT2阻害薬のみクラス2aで推奨されている.
◎stage B(無症状)では,ARNIもSGLT2阻害薬もまだ推奨がない.
◎ARNIやSGLT2阻害薬を開始するかどうかは,効果の大きさ,副作用,費用などの情報を提供したうえで,患者と共有意思決定を行う.
慢性心不全の増悪を防ぐにはどうすればいいですか?
著者: 小野雅敬 , 官澤洋平
ページ範囲:P.318 - P.325
Point
◎ハードエンドポイントである生命予後改善のみならず,ソフトエンドポイントである再入院予防も大切な治療目標となる.
◎患者本人の理解や価値観を尊重した臨床決定や,患者や家族の積極的な参加を促し支援することも重要である.
◎高齢者では特に併存疾患管理や心臓リハビリテーション,多職種連携が重要となる.
◎再入院は退院後早期に多く,移行期ケアに最大の注意を払う.
心房細動
心房細動でDOACは使ったほうがいいですか? DOACの注意点はありますか?
著者: 石塚晃介
ページ範囲:P.326 - P.330
Point
◎直接経口抗凝固薬(DOAC)は総じてワルファリンよりも出血リスクが低い傾向にあり,適応も広がっているが,投与回数や副作用リスク,併用薬,コスト,患者の好みなどの視点から抗凝固薬を選択すべきである.
◎機械弁患者や重度の腎障害・肝障害,妊婦患者ではDOACは使用すべきではない.
◎高齢者の抗凝固療法は年齢だけで判断しない.
◎フレイルな高齢者では,抗凝固療法に関しては臨床倫理4分割法を用いて多因子を1つずつ吟味し,医療者(多職種),患者・家族,介護者で方針を決定することが重要である.
心房細動でアブレーションを意識する場面はどんなときですか?
著者: 眞柴貴久 , 大森崇史
ページ範囲:P.331 - P.335
Point
◎心房細動患者は国内で実に100万人に上ると言われている.プライマリ・ケアの現場でも遭遇するcommonな疾患であり,死亡率,脳卒中,心不全,認知症のリスクを増加させる.
◎カテーテルアブレーションは抗不整脈薬よりも洞調律維持率が高く,QOLの改善,運動耐容能の改善が見込まれ,特に発作性心房細動で有効である.
◎症状の有無,年齢,心房細動のタイプによって洞調律化維持の妥当性が決定される.カテーテルアブレーションの急性期リスクを説明したうえでshared decision making(共同意思決定)を行う必要がある.
認知症
認知症治療薬は何を目的に使えばいいですか?
著者: 山藤光一郎 , 宮上泰樹
ページ範囲:P.336 - P.340
Point
◎認知症治療薬使用の目的は,認知症症状進行抑制による患者と家族のQOL維持である.
◎中核症状および周辺症状を抑えることを念頭に適切な薬剤を選択・継続し,中止は慎重に検討する.
◎Alzheimer型認知症の重症度,および患者の呈している症状を評価して,薬剤を使い分ける.
認知症予防やBPSDの非薬物療法で使えるものはありますか?
著者: 松本朋樹
ページ範囲:P.341 - P.344
Point
◎認知症の予防,精神症状に対する非薬物療法の研究はエビデンスの質が高いものは少ない.
◎認知症予防は,背景因子を理解したうえで運動,栄養療法,血管リスクの治療が挙げられる.
◎認知症における精神症状の非薬物療法はさまざまなものが挙げられるが,質の面からさらなる研究が望まれる.
認知症ではAlzheimer病以外はどう診断し,何を注意すればいいですか?
著者: 松原知康
ページ範囲:P.345 - P.348
Point
◎Lewy小体型認知症は全身病である.認知機能障害以外の症状に注目する.
◎Lewy小体型認知症は全例ではないが,コリンエステラーゼ阻害薬が著効するケースがある.
◎診療の過程では,治療可能な認知症の原因の検索も忘れずに行う.
消化器
便秘の患者で考えないといけないことはありますか? また,下剤の使い分けを教えてください
著者: 大西崇平 , 工藤仁隆
ページ範囲:P.349 - P.353
Point
◎便秘は命に関わる危険性がある.
◎機能性便秘と診断する前に除外すべき疾患がある.
◎便秘の治療薬は近年さまざまな治療薬が出現しており,患者の病態や基礎疾患に応じて使い分ける必要がある.
GERD,消化性潰瘍,潰瘍予防で投与しているPPIはいつまで続ければいいですか?
著者: 木下慶一郎 , 明保洋之
ページ範囲:P.354 - P.358
Point
◎プロトンポンプ阻害薬(PPI)の長期投与に関連する有害事象を把握し,漫然とPPIを投与しない.
◎軽症の胃食道逆流症(GERD)や非びらん性胃食道逆流症(NERD)に対するPPIは症状改善すれば中止,改善しない場合は酸逆流以外の病態を考える.
◎
◎NSAIDs長期内服患者でもリスク因子がなければ,予防的PPIは不要である可能性あり.
肝硬変
肝硬変の患者では何に注意してフォローすればいいですか?
著者: 菊川翔馬 , 天野雅之
ページ範囲:P.359 - P.363
Point
◎リスク因子のある患者では,軽微なサインも拾い上げ積極的に肝硬変を疑おう.
◎肝硬変で生じやすい合併症を把握し,定期的にスクリーニングしよう.
◎肝腫瘤発見時や合併症管理に難渋する場合は速やかに肝臓専門医に紹介しよう.
慢性腎不全
慢性腎不全の患者を診る際に注意することを教えてください
著者: 田代温 , 近藤敬太
ページ範囲:P.365 - P.370
Point
◎慢性腎不全(CKF)とは「数カ月ないし数年にわたって持続的に腎予備能力が低下し,その結果腎機能不全に至って体液の量・質的恒常性が維持できなくなり,多彩な症状を呈する症候群」である.
◎CKFの状態になると,腎機能が正常に戻ることはない.腎不全進行抑制・死亡率低下のために,血圧管理,貧血管理,電解質管理,食事療法が必要である.
◎CKFの状態にならないようにすることも重要である.慢性腎臓病(CKD)を早期に発見し治療介入できれば,CKFの状態に至らず,治癒も十分期待できる.
◎アルブミン尿は腎機能の予後規定因子であり,蛋白尿に対する早期介入することが腎不全抑制にとって重要である.
腎性貧血はなぜ治療しないといけないんですか? 薬の使い分けはありますか?
著者: 中村仁彦 , 山下駿
ページ範囲:P.371 - P.375
Point
◎腎性貧血は,慢性腎臓病(CKD)患者における重要な合併症の1つである.
◎心腎貧血症候群を防ぐために,腎性貧血を治療・管理する.
◎腎性貧血は,エリスロポエチン産生低下だけでなく鉄欠乏など複数の因子が関与する.
◎腎性貧血に対して目標Hb値を設定し,赤血球造血刺激因子製剤(ESA)の投与を開始する.
◎近年,経口薬である低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(HIF-PH)阻害薬が使用されるようになった.
骨粗鬆症
骨粗鬆症の治療は超高齢者でも導入すべきですか? 薬の使い分けはありますか?
著者: 原田拓
ページ範囲:P.376 - P.379
Point
◎骨粗鬆症は一次予防も二次予防も過小診断と過小治療が多い.
◎股関節骨折や椎体骨折はQOLや機能に与える影響が強く,予後が1〜2年くらいの人でも予防投与が選択肢に挙がる.
◎経口ビスホスホネート製剤投与時に押さえておくべきポイントは,腎機能と食道疾患と坐位保持と内服方法の4点である.
骨密度が検査できない場合,骨粗鬆症は診断できますか? フォローの骨密度の測定は必要ですか?
著者: 松本百奈美 , 原田侑典
ページ範囲:P.380 - P.384
Point
◎骨粗鬆症の診断・治療の目的は骨折の予防,骨折によるADL・QOLの低下防止である.骨密度測定検査(BMD)が目的になってはいけない.
◎BMDを使用しないスコアリング方法を用いて,骨粗鬆症のリスクを評価することができる.
◎病歴・身体所見から骨粗鬆症リスクの程度を判断し,介入で予防効果が期待できる場合は積極的治療を検討する.
◎フォローのBMDの施行間隔の根拠は明確ではない.治療開始後のBMDは意義がないとされている.
◎骨粗鬆症治療薬はアドヒアランス不良であるため,アドヒアランス向上に努めることも重要である.
ビスホスホネート製剤は5年以上続けるべきですか?
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.386 - P.390
Point
◎閉経後骨粗鬆症において,骨密度を主体としたgoal-directed treatmentが提唱されており,治療薬選択の一助となる.
◎ビスホスホネート製剤は使用後5年以内であれば,非定型大腿骨骨折リスクよりも脆弱性骨折リスク低減効果のほうが明らかに有益である.
◎ビスホスホネート製剤を5年以上使用することもできるが,継続するかdrug holidayを設けるかどうかは患者ごとのリスクに応じて検討する.
◎drug holidayの期間はビスホスホネート製剤の各薬剤で異なるが,休薬中も評価は繰り返す必要がある.
サルコペニア
高齢のサルコペニア患者はどうすればいいですか? どうやったら体重が増えますか?
著者: 森川暢 , 豊島孝幸
ページ範囲:P.391 - P.396
Point
◎AWGS2019の評価指標を用いることで診療所や地域でも診断が可能である.
◎サルコペニアのスクリーニングにはフレイルや低栄養診断の指標も有用である.
◎サルコペニア予防・治療は栄養と運動をセットで行うことでより効果的である.
◎ICFの観点で評価し,適切な治療とリハビリ栄養を開始することが重要である.
不眠症
不眠症のTipsあれこれ—複雑だからこそ状況別にまとめました
著者: 柴﨑俊一
ページ範囲:P.398 - P.403
Point
◎入院で新規の不眠症をみたら,非高齢者では夜間の医療介入をなるべく避け,高齢者ならせん妄を見つけることが最初の一歩.
◎外来で慢性の不眠症状の訴えを聞いたら,時間の確保が難しい外来では「複数回の外来に分けて診断・初期治療」が現実的.
◎患者指導にリーフレットを使うことで時間節約! インターネットにさまざまなよいものが公開されている.
◎睡眠薬はベンゾジアゼピン系を避けても,完全な安全・安心ではない.出口を意識し,漫然とした処方は避けたい.
◎よくならない「不眠症」では,ほかの睡眠障害との鑑別も必要であり,専門家への紹介を検討する.
ヘルスメンテナンス
予防やスクリーニングなどのヘルスメンテナンスは高齢者でも行うべきですか?
著者: 細川旬 , 小杉俊介
ページ範囲:P.404 - P.408
Point
◎高齢者の予防医学では,利益より不利益が上回りやすい特徴がある.
◎帯状疱疹不活化ワクチンは,50歳以上に接種することが推奨されている.
◎悪性腫瘍スクリーニングは,高齢者に対して不利益が大きくなる可能性があるため,本人や家族などと情報共有しながら方針決定をしていくことが重要である.
連載 ローテクでもここまでできる! おなかのフィジカル診断塾・11
—お腹が膨満している その4—腹水のフィジカル—病歴と視診・打診から腹水貯留をみつけよう!
著者: 中野弘康
ページ範囲:P.209 - P.212
腹部膨満のケースを3回続けて提示してきましたが,いかがでしたか.復習ですが,“腹部膨満”から導き出される鑑別診断は,ずばり6F+αです.すなわち,Fatty(皮下脂肪=肥満),Fetus(胎児=妊娠),Fluid(液体=腹水),Flatus(腸管ガス=腸閉塞や軸捻転),Feces(便=便秘),Fatal growth(腹腔内悪性腫瘍)+尿閉であると理解します.
今回は,“Fluid”の貯留に伴って腹部膨満がみられたケースを提示します.
治らない咳,どう診る・どう処方する?・14【最終回】
肺がんの咳嗽・喀痰
著者: 中島啓
ページ範囲:P.410 - P.413
ポイント
・肺がん患者の咳嗽では,まず肺がん進行に伴う合併症の有無(中枢気道狭窄,がん性胸膜炎,がん性リンパ管症,閉塞性肺炎など)を評価する.
・次に感染性肺炎,薬剤性肺障害,放射線肺炎の可能性を考慮する.
・最後に,COPD,間質性肺炎などの並存疾患,慢性咳嗽の原因となる他疾患の可能性を考える.
・いずれにも当てはまらなければ対症療法の強化を行う.
ここが知りたい! 欲張り神経病巣診断・21
頭が痛くて眼が変な方向を向いてる!? 外眼筋麻痺の臨床②/眼瞼下垂の鑑別
著者: 難波雄亮
ページ範囲:P.414 - P.419
突然の頭痛をきたし,その後意識障害をきたしたときには,脳出血を想像するかと思います.意識障害があっても,病巣部位を想定するのに必要な神経所見はとれます.特に眼の症状がある場合,視診で大まかな病巣部位がわかります.くも膜下出血のある場合,患者さんをあまり刺激せずに(脳動脈瘤の再破裂をきたさないよう)診察することは重要です.
それでは,今回は実際の写真を交えながら病巣を想定していきましょう.
医学古書を紐解く・2
漫才のように面白い教科書—Felson B『Chest Roentgenology』
著者: 仲田和正
ページ範囲:P.420 - P.421
私が好きな医学古書として,まずは『Chest Roentgenology』を紹介したい.これは1973年に出版されたBenjamin Felsonによる教科書(初版)で,私は1978年に医学部を卒業したが,研修医1年目に通読した.とにかく“漫才のように面白く,かつ為になる”という代物である.Felsonはシルエットサイン(silhouette sign)を発表した医師として知られている.
主治医の介入でこれだけ変わる! 内科疾患のリハビリテーション・18
疾患別リハビリ・運動療法の実際
サルコペニア・フレイル
著者: 上月正博
ページ範囲:P.423 - P.428
サルコペニア(sarcopenia)はRosenbergによってギリシャ語のsarx(筋肉)とpenia(減少)からの造語を用いて1989年に提唱された.筋量の減少により身体機能低下,入院リスク,死亡リスクが高まること,またこれに伴う握力や歩行速度の低下が臨床上重要であることが明らかとなり,2010年にはEWGSOP(European Working Group on Sarcopenia in Older People)がサルコペニアを「進行性かつ全身性の筋量および筋力の低下であり,身体機能障害,QOL低下,死のリスクを伴うもの」と定義づけるコンセンサスを発表した1).サルコペニアの最も重要な要因としては加齢が挙げられ,危険因子としては,活動量不足,疾患(代謝疾患,消耗性疾患など),栄養不良が挙げられる.
一方,フレイル(frailty)は,「加齢に伴って身体機能,精神認知機能,社会性が低下し,全般的な活動性が減少した状態」を指す.フレイルは,加齢に伴う「衰え」を多面的(身体的,精神認知的,社会的)に捉えた概念であり,健康(robust)と要介護状態(disability)の中間として位置づけることができる(図1)2).つまり,フレイルは要介護状態の前段階(pre-disabled state)と考えられる.身体機能低下,精神認知機能低下,社会機能低下はいずれも密接に関連しており,1つの機能低下がほかの機能低下を次々に引き起こす〔フレイルの悪循環(vicious cycle of frailty)〕.すなわち,筋力が低下すると歩行機能が低下して外出の機会が減り,社会的に閉じこもり状態となり,ついには認知機能まで低下する.
目でみるトレーニング
information
『ジェネラリストのための内科診断キーフレーズ』発刊1周年記念セミナー内科診断に「キーフレーズ」を実装する!明日からの臨床に役立つTips フリーアクセス
ページ範囲:P.249 - P.249
書評
—鈴木 慎吾 著—続・外来診療の型—苦手な主訴にも同じ診断アプローチ! フリーアクセス
著者: 岩田健太郎
ページ範囲:P.239 - P.239
「守破離」という言葉がある.修業における成長過程を示したもので,まずは師匠や流派の方法を忠実に「守」り,この型をあえて「破」って能力を発展させ,さらに「離」れて自分のスタイルを確立させていく,というものだ. 日本の外来診療教育にはこのような「守破離」がない.というか「守」がそもそもない.米国で内科研修を受けた僕はこのことをいつも不満に思っていた.昨今は初期研修にも一般外来研修が組み込まれ,外来診療教育に力を入れている施設も増えてきたが,それでも多くの研修医たちは外来診療の「型」を教わることなく,ときに指導医の外来診療の見様見真似,ときにロールモデル「ゼロ」のままで悪戦苦闘している.したがって,その多くは「型なし」のままで我流に陥るのだ.
—森田 達也,木澤 義之 監修 西 智弘,松本 禎久,森 雅紀,山口 崇 編—緩和ケアレジデントマニュアル 第2版 フリーアクセス
著者: 柏木秀行
ページ範囲:P.257 - P.257
レジデントマニュアルシリーズと聞けば,「片手で持てて,ポケットに入るけど,ちょっと厚めのマニュアルね」と多くの人がイメージする.そのくらい,各領域に抜群の信頼性を備えた診療マニュアルとして位置付けられ,定番中の定番だろう.そんなレジデントマニュアルに,緩和ケアが仲間入りしたのが2016年であった.初版も緩和ケアにかかわる幅広い論点を網羅していたが,さらに充実したというのが第2版を手にとっての感想である.
緩和ケアもここ数年で大きく変化した.心不全をはじめとした非がん疾患をも対象とし,今後の症状緩和のアプローチが変わっていくような薬剤も出てきた.こういったアップデートをふんだんに盛り込んだのが第2版である.緩和ケアに関するマニュアルも増えてきたが,網羅性という点において間違いなく最強であろう.そう考えると分厚さも,「これだけのことを網羅しておいて,よくこの厚さに抑えたものだ」と感じられる.
—小坂 鎮太郎,松村 真司 編—外来・病棟・地域をつなぐ—ケア移行実践ガイド フリーアクセス
著者: 淺香えみ子
ページ範囲:P.296 - P.296
疾病や傷害によって日常生活の継続が困難になった生活者たる人を速やかに元の生活に戻すことを目標にケアをする看護師は,「継続看護」としてその人へのケアをつなげています.これは,施設内外の部署,施設間によらず意識されており,生活支援をすることに看護の専門性を説明するゆえんもここにあります.
この度発刊された本書は,この視座と同じものが医師の役割のなかで説明されています.患者の治療は生活の再獲得に向かう手段であり,その効果を最大化するうえで現行の医療・社会・福祉の構造特性によって生じる「つなぎ」の効率性を考える必要があることを国内外の情報をもとに解説されています.
—𠮷村 長久,山崎 祥光 編—トラブルを未然に防ぐカルテの書き方 フリーアクセス
著者: 松村由美
ページ範囲:P.364 - P.364
本書は,𠮷村長久氏と山崎祥光氏の共同編集によるものです.𠮷村氏は,京大眼科教授から北野病院病院長になられました.山崎氏は,京大医学部卒業後,同大学での研修医を経て,同大学法科大学院で学び,現在は弁護士として活躍されています.𠮷村氏は管理者として,山崎氏は弁護士として,カルテ記載の重要性を痛感され,本書を企画されたのだろうと思います.私も,医療安全管理者として,カルテ記載がいかに重要かを知っています.重要性を認識している3名に共通することは,「痛い目」を経験しているということかもしれません.
病院管理者,医療側弁護士,医療安全管理者は,あらゆるトラブルを経験します.私も,臨床医のまま一生を終えていたら経験しなかったようなことを経験してきました.その経験のなかで,ぜひ,スタッフに伝えたいと思ったことが「カルテの書き方」です.今まで,私がこの十数年,経験的に学んだことが,本書では,コンパクトでありつつ,豊富な根拠を示したうえで記載されています.本書はどの部分から読んでも,1つひとつの話題や内容が完結しているために,カルテ記載について気になったときに読むということもできます.また,時間のあるときにパラパラとめくって,斜め読みするだけでも,十分勉強になります.医局に数冊置いておくと有用であること間違いなしです.
—山下 武志 編—心研印 心電図判読ドリル フリーアクセス
著者: 井上博
ページ範囲:P.409 - P.409
「心電図が読めるようになるにはどうしたらよいですか?」という質問はいつの時代にもある.小生が現役時代,医学生や研修医諸君に答えていたことは,「まず何でもよいから一通り心電図の本を読んで基本的事項を理解し,その後は一例一例の心電図を読んで専門家に教えてもらう」であった.本書の編者はまさに同じことを序文で述べている.しかし周囲に心電図の専門家が必ずしもいるとは限らない.そのような場合どうすればよいか? この難題に応えてくれるのが本書である.心臓血管研究所の山下武志先生とその5人のお弟子さんの手で上梓された.
基礎編(小手調べ)7例,実践編(いよいよ本番)43例の計50例から成る.まず簡単な病歴と心電図が提示され,多肢選択形式で質問に対する回答を読者が考えるという形式である.解答としては心電図所見の場合もあれば,疾患名の場合もある.解説では心電図所見がていねい(重要な部分にはアンダーライン)に説明され,必要に応じて胸部X線写真,冠動脈造影,心エコー図などが示され,読者の理解を容易にする工夫がされている.心電図や,提示されている画像は鮮明で見やすい.解説に続いてLearning Pointとして,その心電図所見で注意すべき要点が示され,最後に深く学びたい読者のために参考文献が引用されている.本編に続いて逆引き疾患目次があり,心電図所見,疾患名から検索できるようになっている.最後にLearning Pointのまとめが50例分示され,心電図所見のカルテへの記載例が英語で示されている.痒いところに手が届く工夫が随所になされている.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.214 - P.217
読者アンケート
ページ範囲:P.435 - P.435
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.436 - P.437
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.438 - P.438
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.439 - P.439
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.440 - P.440
基本情報
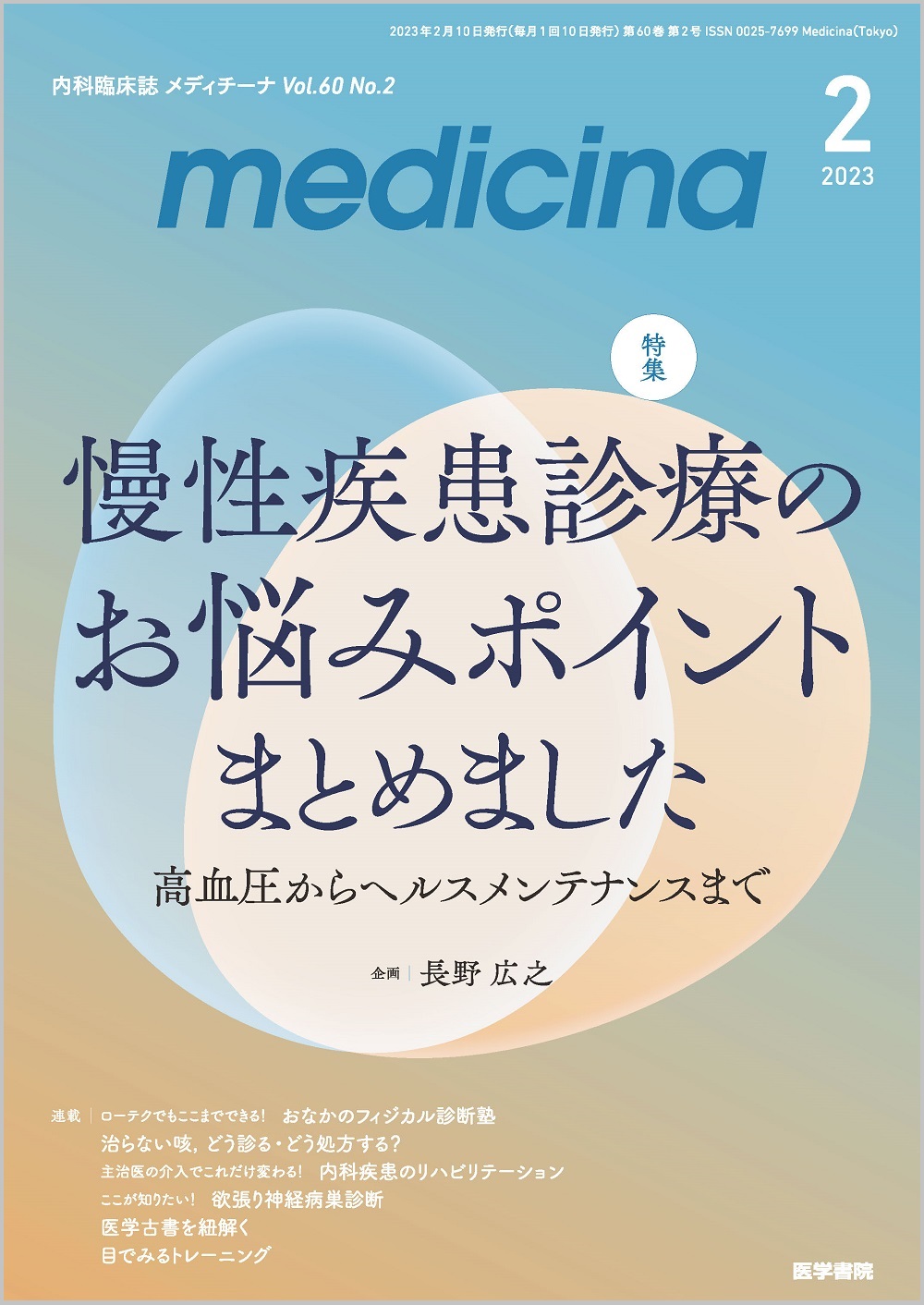
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
