マイナーエマージェンシーとは,「ショック」「脳出血」「心筋梗塞」「急性腹症」以外の病態を指すと言われています.医療者にとってちょっとしたこと(マイナーな状態)ではあっても,患者さんはどうしてよいのかわからず困り果てて外来を受診されます.
例えば,深夜2時頃に眠っていたところ,急に鼻から血が出て出血が止まらず困り,家族に連れられ医療機関に直接自家用車で受診した患者さんがいるとします.そんなとき,医療者として「自分の専門外だから」「院内に耳鼻咽喉科医がいないから」と断るのは簡単かもしれませんが,患者さんは次にどうすればよいかわからずより困ってしまいます.
雑誌目次
medicina60巻4号
2023年04月発行
雑誌目次
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
扉 フリーアクセス
著者: 小淵岳恒
ページ範囲:P.7 - P.7
Ⅰ.眼のエマージェンシー
眼が赤いんですけど,どうすればいいですか?—流行性角結膜炎を見逃すな!
著者: 山中俊祐
ページ範囲:P.10 - P.14
POINT
●Red eye診察で見逃してはならない疾患は,①緑内障,②角膜化学熱傷,③淋菌性・流行性角結膜炎の3つである.
●角膜化学熱傷(特にアルカリ性)はすぐに洗浄を! 角膜表面が弱アルカリ性になるまで!
●流行性角結膜炎(EKC)は伝播力が強いため,学校,職場などで流行していないかを確認することが診断の一助となる.
●EKCが疑われたら適切な患者指導を行うとともに,コメディカルと連携して院内の感染予防に努める.
コンタクトを使っていますが,眼が赤くて痛いんです—緑膿菌感染症,角膜潰瘍を見逃すな!
著者: 山中俊祐
ページ範囲:P.16 - P.19
POINT
●コンタクトレンズ関連細菌性角結膜炎は失明するリスクがある.
●できれば当日の眼科紹介が望ましい.
●緑膿菌をスペクトラムに含めた抗菌薬投与を検討する.
眼が赤くて,腫れて熱もあるんです—眼窩膿瘍,眼窩周囲蜂窩織炎を見逃すな!
著者: 神川洋平
ページ範囲:P.20 - P.23
POINT
●眼窩周囲蜂窩織炎は比較的軽微な感染症だが,近日中の眼科フォローが必要である.
●眼窩蜂窩織炎は眼窩内の重篤な感染症であり,速やかな眼科コンサルトが必要である.
●眼窩・副鼻腔CTが診断の助けとなる.それでも判別困難なら眼窩蜂窩織炎に準じて対応する.
夜になって,眼が痛くて涙が止まりません—紫外線による電気性眼炎を見逃すな!
著者: 岩村晃
ページ範囲:P.25 - P.27
POINT
●電気性眼炎は紫外線曝露から時間が経ってから受診するため日中の生活歴を聴取する.
●眼痛が強く,眼の観察ができないときは点眼麻酔薬を使用して観察する.
●電気性眼炎自体は自然軽快が得られるが,再発予防の指導が重要である.
眼にボールが当たって,うまく見えません—結膜下出血と眼球破裂・前房出血を見極めろ!
著者: 東裕之
ページ範囲:P.28 - P.31
POINT
●受傷機転・ぶつかった物をしっかり確認する.
●眼球への強い衝撃が加わっていれば,眼球破裂の可能性は否定せずに愛護的に対応する.
●外傷に伴う結膜下出血を認めても,前房出血・眼球破裂の有無の確認は忘れずに.
●眼球破裂の可能性は容易に否定しないように.
●眼球破裂が疑われれば眼球に圧がかからないように眼球を保護する.
眼に何か入りました①—角結膜異物の除去法をマスターせよ!
著者: 水野晴貴
ページ範囲:P.33 - P.35
POINT
●処置・観察前に局所点眼麻酔薬の使用を忘れない!
●上眼瞼の裏もしっかり観察しよう.
●異物の種類によって対応が異なるため,受傷機転を確認し,具体的なフォローアップの方針を検討する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
眼に何か入りました②—化学性結膜炎はコンサルトする前に対処せよ!
著者: 安藤裕貴
ページ範囲:P.36 - P.40
POINT
●目の痛みを訴える患者への最初の質問は“眼に何か入りましたか?”である.
●化学性結膜炎を疑ったら,その物質の特定に努める.
●化学物質への曝露が判明している場合は,評価が可能になるまで最低10分間灌流を継続する.
Ⅱ.鼻のエマージェンシー
鼻血が出て止まらないんです—専門医を呼ぶ前にまず自分で止めてみよう!
著者: 泉玲央
ページ範囲:P.42 - P.46
POINT
●鼻出血を見たら,まず迅速な対応が必要かどうかを判断する.
●活動性の鼻出血には,鼻翼圧迫法を試みる.
●鼻翼圧迫法後も出血が持続する場合は,前方パッキングを試み,それでも止血しない場合や後方出血が疑われる場合は,耳鼻咽喉科にコンサルトする.
●前方パッキングで止血できた場合には,3〜5日以内に耳鼻咽喉科を受診するよう指示し,帰宅させる.
子どもが鼻の中に何かを入れました—鼻腔異物除去をマスターせよ!
著者: 高橋優二 , 梅木寛 , 宗謙次
ページ範囲:P.48 - P.53
POINT
●片側性の膿性鼻汁は鼻腔異物を疑うサインである.
●異物除去の際には固定が大事である.
●耳鼻咽喉科に紹介すべき危険な異物を知る.
●異物除去で最も注意すべき合併症は気道異物である.
●異物の種類によって摘出法は異なること知る.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
鼻折れてません?—眼窩底吹き抜け骨折を見逃すな!
著者: 西田成
ページ範囲:P.54 - P.58
POINT
●顔面外傷では,鼻骨骨折と眼窩底吹き抜け骨折を疑う.両者はしばしば合併する.
●顔面の外傷で骨折を疑った場合,X線ではなくCTを撮影する.
●複視や嘔吐,高度な眼球運動障害を伴う症例ではwhite eyed blowout fractureを疑う.
膿性の鼻汁が続きます—抗菌薬の処方のタイミングは?
著者: 小山佳祐
ページ範囲:P.59 - P.63
POINT
●膿性鼻汁,悪臭,頭痛・顔面部痛といった症状で副鼻腔炎に気づくことができる.
●治癒しない場合に備え,初回抗菌薬処方時には鼻腔培養検査を検討する.
●内服・点滴治療で症状改善が期待できるが,手術治療が必要な例もある.
●強い疼痛,腫脹,視力・視野障害がある場合には専門医にコンサルトを!
Ⅲ.耳のエマージェンシー
耳の中に入った物が取れないんです—耳内異物除去法をマスターせよ!
著者: 千々和可怜
ページ範囲:P.66 - P.70
POINT
●異物の大きさ・性状,症状は,その後の処置を行ううえで重要な要素である.
●慢性中耳炎など鼓膜穿孔のリスクファクターである疾患の既往の有無を確認する.
●耳洗浄は異物の種類によっては禁忌である.
●摘出が難しいと判断した場合,ガラス片など鋭利な異物である場合,外耳道や鼓膜に外傷のある場合は,耳鼻咽喉科にコンサルトする.
耳の中に虫が入って出てこないんです—耳の中の虫ってどうやって取り出すの?
著者: 吉田英人
ページ範囲:P.72 - P.75
POINT
●外耳道の解剖と有生物異物の特徴を理解する.
●有生物異物のときは,キシロカイン® やオイルを用いて動きを止めてから除去を試みる.
●深部に入り込んだ有生物の除去は,耳鼻咽喉科へのコンサルテーションを考慮する.
耳が痛くて,吐き気がします—耳介周辺の帯状疱疹を見逃すな!
著者: 前田啓佑
ページ範囲:P.76 - P.81
POINT
●Ramsay Hunt症候群は顔面神経での水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化による,①耳介部帯状疱疹,②顔面神経麻痺,③内耳神経症状を呈する症候群である.
●3徴すべてが揃っていなくても,Ramsay Hunt症候群が疑われる場合には早期に抗ウイルス薬,ステロイドの治療を開始する.
●顔面神経麻痺,聴力障害,帯状疱疹後疼痛など後遺症が生じる場合があるので,耳鼻咽喉科へは早めに紹介する.
打撲後,音がよく聞こえません—鼓膜損傷を見逃すな!
著者: 岡本昌之
ページ範囲:P.82 - P.85
POINT
●外傷性鼓膜穿孔の原因は,耳かきなどによる直達性外傷と,耳への平手打ちや打撲などによる介達性穿孔がある.
●穿孔は鼓膜下半分に生じることが多く,耳介を後上方に牽引して鼓膜下方をしっかり観察する.
●外傷性鼓膜穿孔は自然閉鎖することが多く,それに伴い聴力なども回復する.
●抗菌薬は内服による予防投与を行い,耳内に感染がある場合には点耳薬も併用する.
●自然閉鎖しない場合にはトラフェルミンを用いた鼓膜再生治療が保険適用となっている.
Ⅳ.のどのエマージェンシー
のどに何か刺さりました—魚骨除去法をマスターせよ!
著者: 宮岡慎一 , 髙橋仁
ページ範囲:P.88 - P.91
POINT
●魚骨異物は日本を含むアジア圏では全年齢層で起こりうる,ありふれた病態である.
●魚骨異物を訴える患者のうち,実際に魚骨が認められる患者は約20%とそれほど多くない.
●口腔内から観察できる魚骨は容易に摘出できる.
●魚骨が確認できないが症状が軽く飲水・食事が可能であれば,48時間を目安に再受診のタイミングなどを明確に示したうえで自宅経過観察とする.
●症状が重く,嚥下・呼吸困難がある場合は,頸部CTや鼻咽頭ファイバースコープで観察・摘出を試みる.
●魚骨を確認したものの除去できない場合は,基本的には耳鼻咽喉科コンサルトが必要となる.魚骨が食道にある場合には内視鏡医師へのコンサルトを検討する.
のどが腫れて痛いんです—扁桃周囲膿瘍を見逃すな!
著者: 垣内駿吾
ページ範囲:P.92 - P.96
POINT
●コロナ禍の咽頭痛は,致死的疾患を見逃さないために咽頭を見なくても確認できるred flagを探すことが重要である.
●咽頭痛の対症療法は,単回のステロイド内服が効くかもしれない.
●扁桃周囲膿瘍の画像的評価は造影CTだけでなく,エコーでもできる.
のどが痛くて,うまく話せず,飲み込めません—急性喉頭蓋炎・咽後膿瘍を見逃すな!
著者: 小迫拓矢
ページ範囲:P.98 - P.103
POINT
●「咽頭痛」を訴える患者では,「killer sore throat」を鑑別に挙げて診察する.
●上気道閉塞を疑う身体所見を見逃さない.上気道閉塞を疑えば大勢で対応する.
●急性喉頭蓋炎,咽後膿瘍の特徴的なX線所見を見逃さない.
おじいちゃんが何か飲み込んだみたいです—ボタン電池・PTP誤飲に要注意!
著者: 伊禮奏子
ページ範囲:P.104 - P.108
POINT
●異物誤飲の症例に遭遇した場合,まず気道閉塞の有無,異物の形状および種類,誤飲の時間を聴取する.
●ボタン電池やPTPなどの鋭利な異物の誤飲は消化管穿孔のリスクが高く,早急に専門科による内視鏡的除去が必要である.
●X線検査で異物が特定できない場合,誤飲した異物が危険なものでないことが確実である場合は,追加検査をせず経過観察も可能である.
Ⅴ.歯科口腔のエマージェンシー
顎が外れました—顎関節脱臼の整復法をマスターせよ!
著者: 田中惇也
ページ範囲:P.110 - P.115
POINT
●骨折を伴う顎関節脱臼は専門医にコンサルトする.
●Hippocrates法で整復を行うときは,患者に口を閉じてもらうと整復しやすい.
●術者の手が噛まれるリスクがあるときや術者が慣れているときは,口腔外法やシリンジ法での整復も考慮する.
●整復後,再脱臼しないように固定と患者指導を行う.
歯が欠けました—歯の破折,歯の脱臼を見極めろ!
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.117 - P.121
POINT
●歯牙外傷があればCTも用いて顔面外傷として総合評価する.
●歯牙外傷は完全脱臼,歯冠破折,歯根破折を鑑別する.
●完全脱臼の脱落歯は来院前から生理食塩水のコップに入れる.保存状態が良ければ深夜受診で翌朝コンサルトでもよい.
●破折は評価ができれば,処置は口腔外科医へ任せてよい.コンサルトも急がない.
唇にブツブツが出たんです—それは口唇ヘルペス? 口角炎?
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.122 - P.126
POINT
●単純ヘルペスウイルス(HSV)が起こす口唇ヘルペス,ヘルペス性歯肉口内炎,カポジ水痘様発疹症を臨床診断すべし.
●口唇ヘルペスは十分な説明が必須,内服の抗ウイルス薬が選択的,抗ウイルス薬の軟膏や皮膚科コンサルトは不要.
●PIT療法(patient-initiated-treatment)を含め,必要に応じて抗ウイルス薬の処方ができるようになること.
Ⅵ.皮膚のエマージェンシー
体にブツブツが出たんです①—アナフィラキシーを見逃すな!
著者: 石井義洋
ページ範囲:P.128 - P.132
POINT
●蕁麻疹をみたら,アナフィラキシーを除外する.
●アナフィラキシーを疑ったときは,アレルゲンの曝露歴と発症までの時間経過,臓器症状を確認する.
●臓器症状は,通常,複数同時に認めるが,初期には典型的な症状が揃わないこともある.
●アナフィラキシーを疑ったときには,アドレナリン筋注を躊躇しない.
体にブツブツが出たんです②—Stevens-Johnson症候群(SJS)を見逃すな!
著者: 石井義洋
ページ範囲:P.133 - P.137
POINT
●薬疹を見逃さないためには常に薬疹を疑い,薬歴を正確にとる.
●薬疹を疑ったときには,常に生命に関わる重症薬疹を考慮して,早期サインを見逃さない.
●Stevens-Johnson症候群(SJS)や中毒性表皮壊死症(TEN)を疑ったときには皮膚科だけでなく,眼粘膜病変の評価のために眼科にも相談する.
急に顔が腫れました—顔面の皮膚疾患を見極めろ!
著者: 笠松宏至
ページ範囲:P.138 - P.142
POINT
●皮膚のみに留まる丹毒と,深部病変を有する顔面蜂窩織炎を鑑別する.
●帯状疱疹では眼科・耳鼻咽喉科領域の異常がないか,髄膜炎・脳炎の徴候がないか確認する.
●繰り返す,原因のわからない接触皮膚炎は後日,専門科にコンサルトする.
●気道緊急を要する顔面腫脹として,血管性浮腫の対処法を押さえる.
子どもに急にブツブツが出たんです—小児独特の発疹を見極めろ!
著者: 塩住忠春 , 宮本雄気
ページ範囲:P.143 - P.151
POINT
●見逃してはいけない皮疹を見逃さない.
●学校感染症など公衆衛生上重要な皮疹を見極める.
●困った時に相談しやすいよう,地域の医療機関と良好な関係を築く.
足が急に腫れました,熱もあるんです—蜂窩織炎 vs 壊死性筋膜炎を見極めろ!
著者: 勢理客晶子
ページ範囲:P.153 - P.157
POINT
●皮膚所見と不釣り合いな痛みのある患者をみた場合は注意しよう.
●来院から6時間以内に外科的デブリドマンを行う.
●早期のデブリドマンに向けて,医療スタッフ全員が緊急疾患であることを認識しよう.
爪周りから膿が出ます—陥入爪の初期対応をマスターせよ!
著者: 宮前誠
ページ範囲:P.158 - P.162
POINT
●陥入爪は抗菌薬や軟膏だけでは治らない.爪の陥入をいかに解除するかが重要である.
●安易な爪切りは行わない.爪を切らない対処方法を理解する.
●爪脱臼に対するSchiller法を理解する.
Ⅶ.整形外科のエマージェンシー
肩が痛くて,外れたのかもしれません—肩関節の脱臼整復法を学ぼう!
著者: 林実
ページ範囲:P.164 - P.168
POINT
●脱臼に合併する骨折を見逃さない.骨折を合併している場合は整形外科にコンサルトする.
●十分な鎮痛が徒手整復成功のカギである.最も簡単な鎮痛方法は関節内リドカイン注射である.
●整復後は三角巾とバストバンドで固定して,整形外科への受診を指示する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
指が引っかかって変な方向に曲がりました—IP関節の脱臼整復法を学ぼう!
著者: 田下大輔
ページ範囲:P.170 - P.174
POINT
●IP関節脱臼はその方向によって背側脱臼(dorsal dislocation),側方脱臼(lateral dislocation),掌側脱臼(volar dislocation)に分類される.
●合併する手指骨骨折の程度が大きい場合や開放性骨折を伴う場合,また腱や骨片の関節内陥入などにより整復困難である場合は速やかに整形外科へのコンサルテーションが必要となる.
●背側脱臼の整復はただ単に引っ張るのではなく,関節をわずかに伸展させたのちに元の位置まで戻す外力を加えながらゆるやかに屈曲させることがコツである.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
子どもの肩が上がらなくなりました—肘内障の整復法を学ぼう!
著者: 秦龍彦
ページ範囲:P.176 - P.179
POINT
●急に片手を使いたがらない病歴があれば,commonな肘内障を疑う.
●「手を引っ張られた」という病歴聴取が役立つが,「寝返りを打った後から」という例もある.
●転倒に伴うものであれば骨折の可能性に注意する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
足をくじいて歩けません—足関節にまつわる落とし穴を学ぼう!
著者: 狩野謙一
ページ範囲:P.180 - P.184
POINT
●X線撮像するかどうかはまずはOttawa足外傷ルールを使う.
●Ottawa足外傷ルールでは骨折は完全否定できない.
●捻挫にはRICE+Nで対処する.
●足首が痛い患者では腓骨遠位と第5中足骨の診察を忘れない.
膝を捻って歩けません—膝関節にまつわる落とし穴を学ぼう!
著者: 海透優太
ページ範囲:P.185 - P.189
POINT
●整形外科外傷領域で鑑別を絞っていくためには,問診とエピソードが重要である.
●膝関節液貯留は,確実に診断できるようになっておきたい身体所見である.
●膝関節穿刺を実施する際は,自施設のルールを必ず確認する.
●正確な診断は難しくても,適切なマネジメントが行うことが大切である.
三角巾,松葉杖が上手に使えません—いまさら聞けない使い方
著者: 野々山忠芳
ページ範囲:P.190 - P.194
POINT
●患者の自己管理能力(松葉杖であれば荷重コントロール,三角巾の装着方法の習得)を加味して処方する.
●三角巾の使用の際は肩関節を包み込むように装着する.
●松葉杖処方では転倒のリスクを考慮し,十分な練習・指導をする必要がある.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
Ⅷ.泌尿器科のエマージェンシー
おしっこが出なくなりました—尿閉—導尿・バルーンを入れるときのコツ
著者: 多賀峰克
ページ範囲:P.196 - P.200
POINT
●排尿障害の原因を考える.
●急性尿閉には間欠的導尿を,それ以外には尿道カテーテル留置を検討する.
●男性の場合,体幹に対して直角に陰茎を牽引把持する.
●尿道留置カテーテルは,基本的には根元まで挿入し固定水を注入する.
急に左下腹部が痛くなりました—精巣以外の痛みを訴えたときに注意!
著者: 階戸尊
ページ範囲:P.201 - P.205
POINT
●精巣捻転は時間との勝負! 典型例はもちろん,よくある非典型例についても知っておく.
●腹部疾患を疑った際には必ず精巣捻転を鑑別に挙げ,陰部も診察することをルーティンにする.
●少しでも疑った場合には,身体診察に加えてエコー検査を使用する.正常例とともに精巣捻転で見える像について理解する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
わき腹が痛い,七転八倒の痛みです—尿管結石にまつわるエトセトラ
著者: 野田透
ページ範囲:P.206 - P.211
POINT
●尿管結石が疑わしい症状の人でも,必ず,尿管結石以外の疾患の可能性も考える.
●疼痛処置だけで帰宅させてはいけない尿管結石患者を見逃さない.
実は危険がいっぱい泌尿器感染症—早めに対応しないと敗血症に!
著者: 和田亨
ページ範囲:P.212 - P.216
POINT
●敗血症へ一直線! 恐ろしい泌尿器感染症.
●腎盂腎炎のCT検査はどこまで必要?
●いつも悩ましい高齢者の発熱診療.
Ⅸ.動物のエマージェンシー
飼いイヌに手を咬まれました—動物に咬まれたときはどうするの?
著者: 岩田和佳奈
ページ範囲:P.218 - P.223
POINT
●感染を防ぐことが大事! まずは洗浄・デブリードマンをしっかりとしよう.
●縫合するかしないかは感染リスクと整容面を天秤にかけて決めよう.
●咬傷後の感染リスクは,ネコ>ヒト>イヌ! ネコは感染必発! パスツレラ感染に注意を.
●破傷風予防も忘れずにやろう.
山でダニに咬まれたかもしれません—山での昆虫咬傷について学ぼう!
著者: 石本貴美
ページ範囲:P.225 - P.229
POINT
●マダニの生体を知り,どうして容易に外れないのかを知ろう.
●発熱の鑑別疾患に,マダニ類媒介感染症がある.
●マダニ類媒介感染症に対する一番の予防は「マダニを付着させない」ことである.
●マダニ除去にティックツイスター® を使用してみよう.
海で何かに刺された,何か踏みました—海での海洋生物による外傷を学ぼう!
著者: 四本仁寛
ページ範囲:P.231 - P.235
POINT
●クラゲ刺傷の疼痛には患部をお湯で温めることが有効だが,冷却でも効果があるとの報告もある.
●海洋生物刺傷ではほとんどが局所のみの症状だが,アナフィラキシーをきたすことがある.
●オコゼ,ゴンズイ,エイ,カサゴ刺傷の疼痛にはお湯で温めることが有効である.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
ハチに刺されました!—ハチ刺されの初期対応,アナフィラキシーに注意
著者: 辻本佳久
ページ範囲:P.236 - P.240
POINT
●まずはアナフィラキシーを起こしていないか確認する.
●アナフィラキシーを疑った場合,0.1%アドレナリン0.01mg/kg(最大量:成人0.5mg,小児0.3mg)を大腿前外側に筋肉注射する.
●アナフィラキシーを起こした患者には,アドレナリン自己注射薬(エピペン®)の使い方を指導し処方する.
Ⅹ.神経・環境・中毒のエマージェンシー
体が冷たいんです,動けないです—低体温症の初期対応を学ぼう!
著者: 茂見瞭
ページ範囲:P.242 - P.245
POINT
●体が冷たい,体温計で体温が測れないなど低体温症を疑う場合には深部体温を測定する.
●気道・呼吸・循環の安定化と重症度に応じた復温を同時進行で行う.
●一次性低体温症と決めつけずに,二次性低体温症の可能性を常に考慮し感染,神経/内分泌疾患,外傷などの原因検索を怠らない.
やけどして,水ぶくれができました—軽症熱傷の初期対応を学ぼう!
著者: 峯岸芳樹
ページ範囲:P.246 - P.250
POINT
●受診前に問い合わせがあれば,患部の十分な冷却を指示する.
●受傷機転の問診から熱傷深度を早期に見極める.
●熱傷による水疱膜を除去するタイミングは受傷からの時期・創面の状況から判断する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
キャンプをしていて頭が痛くなりました—一見軽症に見えるCO中毒を見逃すな!
著者: 永井秀哉
ページ範囲:P.251 - P.255
POINT
●化石燃料(ガス,炭,石油,ガソリンなど)を燃焼させるときは,常に一酸化炭素中毒を招く危険を孕んでいる.啓発と予防が最も重要である.
●酸素投与が重要(高濃度酸素投与,CPAP,ネーザルハイフロー,高気圧酸素).
●遅発性脳症を起こすことがあり,長期的な予後やQOLの低下を招く.
●中等症以上では心筋障害の合併が多く,予後を悪化させる.
風邪薬をたくさん飲んでしまいました—薬物中毒でも早めの対応が必要なものも
著者: 安宅伸人
ページ範囲:P.256 - P.259
POINT
●アセトアミノフェン中毒は,前臨床毒性期,肝障害期,肝不全期,回復期に分類される.
●初期対応は,ABCDの安定化を行い,その時点で対応が困難であれば早急に救急医などの手助けが必要となる.
●N-アセチルシステイン(NAC)の投与は経口投与と静脈投与があり,それぞれの利点と欠点がある.
なかなか眠れず,睡眠薬をたくさん飲んでしまいました—睡眠薬過量内服の初期対応を学ぼう
著者: 西川佳友 , 鈴木優子 , 森川華也子
ページ範囲:P.260 - P.263
POINT
●睡眠薬過量内服の治療はABCを保ちつつ,対症療法がメインとなる.
●複数種類の薬物を過量内服する例も多く,本人・家族や救急隊からの情報収集に努める.
●内服直後の“全身状態良好”に騙されない.中毒は後から悪化する.
●Tipsをマスターし,睡眠薬過量内服診療に強くなろう.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
子どもがおばあちゃんのお薬を飲んでしまいました—小児の薬物中毒は1錠でも危ない!
著者: 矢島つかさ
ページ範囲:P.265 - P.269
POINT
●薬物誤飲が疑われる小児へのアプローチは,まず気道,呼吸,循環の初期評価と安定化,そして神経学的問題の評価と治療から始める.
●虐待の可能性も考慮する.
●中毒治療は,支持療法が治療の柱.除染や排泄促進などの治療法もあるが,あまり強いエビデンスはないのが現状である.
呼吸回数が多くなり,手がしびれるんです—ペーパーバッグ法はもう古い!
著者: 福本雄太
ページ範囲:P.270 - P.273
POINT
●過換気症候群の背景に隠れた疾患を見逃さないために,発作の誘因となったエピソードに注目する.
●患者が安心するように語りかけ,呼吸法を指導することで過換気発作の改善を図る.
●ペーパーバッグ法は低酸素血症の危険があるため行わない.
近所の人からもらったキノコを食べたら気分が悪くなりました—採らない,食べない,配らない!
著者: 小川史朗
ページ範囲:P.274 - P.278
POINT
●植物による中毒の発生は秋(9〜11月)が約半数を占める.
●野生植物は種々のアルカロイドなど毒性物質を含み,微量でも多様な症状をきたす.
●植物の現物や写真,患者のトキシドロームに基づいて原因植物・毒性物質を特定する.
●中毒の成書などに加え,日本中毒情報センターなど相談先を作っておくことが重要.
●野生植物は「採らない,食べない,配らない!」患者への教育的な情報提供も忘れずに.
Ⅺ.マイナー外傷でのエマージェンシー
釣り針が刺さって抜けません—上手な外し方を身に付けよう!
著者: 清水晶 , 武部弘太郎
ページ範囲:P.280 - P.284
POINT
●釣り針にはカエシが付いており,引っ張るだけでは簡単に抜けない.
●釣り針の種類,創部の状態を見て抜去方法を選択する.
●釣り針の種類が不明な場合はX線写真で確認する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
すねをぶつけてケガをしました—下腿裂傷の対応は慎重に
著者: 浦邊亮太朗
ページ範囲:P.286 - P.290
POINT
●下腿は皮膚・皮下組織が薄く,創傷治癒が遷延しやすい部位であるため,下腿裂傷の初療は慎重を要する.
●広範な組織欠損や骨折,深部組織の損傷が疑われる場合は,形成外科もしくは整形外科など専門医へのコンサルトが望ましい.
●土壌や水場での受傷は感染のリスクが高いため,丁寧に洗浄,処置を行い,抗菌薬の投与を行う.
●下腿は創傷治癒が遷延しやすい部位であるため,深くまで到達していた裂傷や,縫合後の緊張が強い場合は14日前後で抜糸を行うと安全である.
子どもが頭をぶつけました—小児の頭部外傷にCTは必要?
著者: 成山美々
ページ範囲:P.291 - P.296
POINT
●CTを撮るべきかどうかはPECARNルールに沿って考えてみよう.
●最終的には受傷機転,受傷後の経過,保護者の不安の強さなど総合的に考慮する.
●帰宅前の説明が大事! 帰宅後の過ごし方,どんなときに再診が必要かを説明しよう.
Ⅻ.マイナーエマージェンシーのエコー活用術
こんなに役立つ超音波—まさかショック? びっくりどうしよう?
著者: 瀬良誠
ページ範囲:P.298 - P.303
POINT
●ショックを認識する.
●よくわからないときはとりあえず「サルも聴診器」.
●ショックにエコーで対応する.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
こんなところにも超音波①内科編—在宅でも使いこなせるとイイね!
著者: 岩見有希子
ページ範囲:P.305 - P.307
POINT
●蜂窩織炎が疑われる時にエコーを当てて膿瘍がないか確認してみよう.
●蜂窩織炎治療中にエコーを当てて膿瘍形成がないか経過をフォローすることができる.
●尿量低下が主訴のときに膀胱にエコーを当てて尿閉がないかをまずは見てみよう.
●膀胱容量をエコーを用いて計算することができる.
*本論文中、関連する動画を見ることができます(公開期間:2026年3月31日まで公開)。
こんなところにも超音波②小さい外傷編—X線を撮る前に使えるとイイね!
著者: 小淵岳恒
ページ範囲:P.309 - P.313
POINT
●肋骨骨折は打撲にて生じることが多いが,高齢者では軽微な理由(くしゃみなど)でも生じるため,内科外来に「胸痛」で受診することもある.
●肋骨骨折の診断においてCT検査は最も有効であるが,基本的には臨床診断になることが多く,X線検査で見逃すことが多い.
●内科医(整形外科非専門医)であっても,胸部の痛いところにちょっとエコープローブを当てるだけでその場で診断が可能である.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.2 - P.5
索引 フリーアクセス
ページ範囲:P.314 - P.317
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.318 - P.318
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.319 - P.319
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.320 - P.320
基本情報
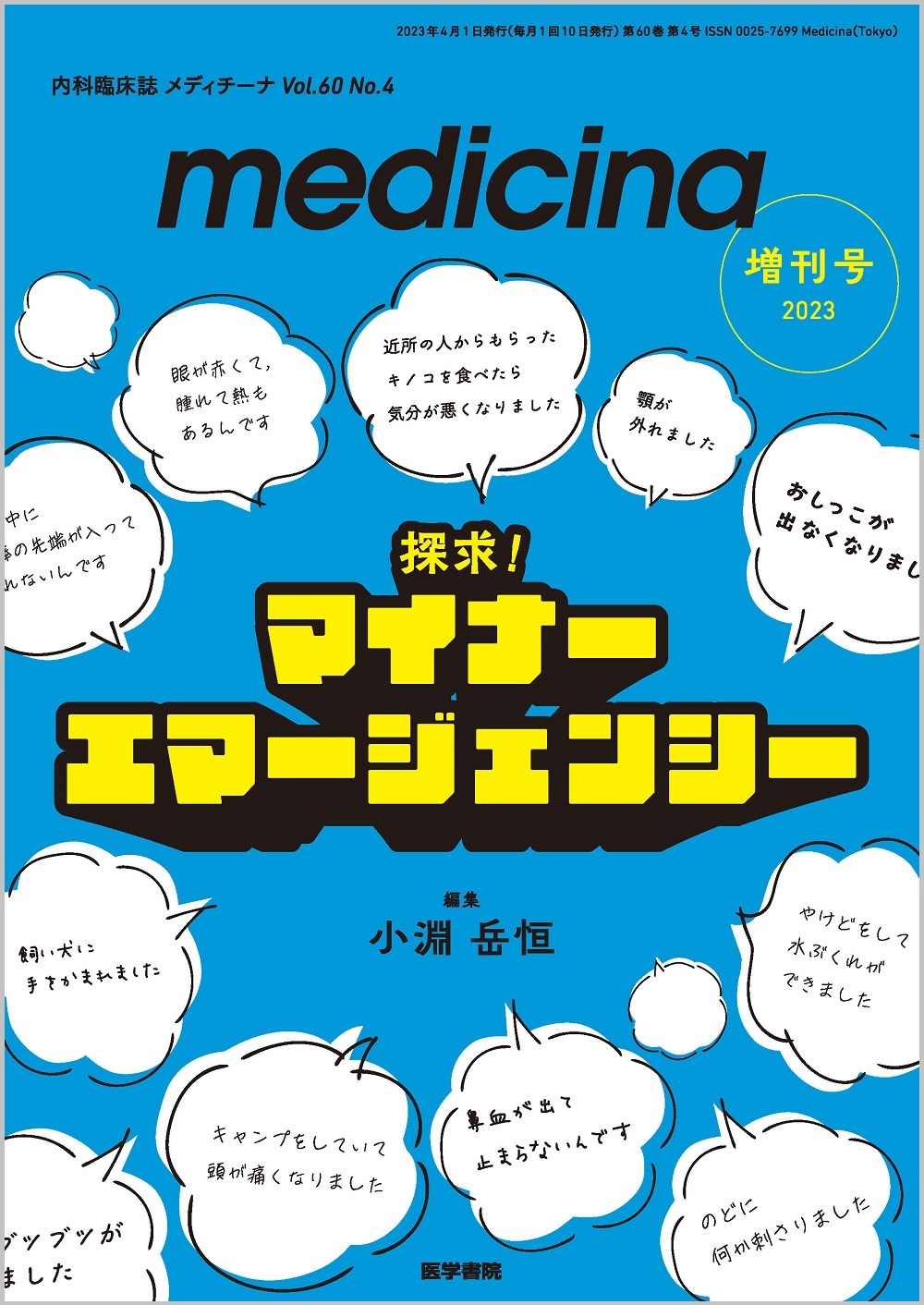
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
