2023年末〜2024年を迎え,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の出現から5年目に突入した.
この感染症に対し,人類は現代医学の総力を投入し,わずか数年のうちに新規のワクチンと治療薬を複数開発し,また重症化の病態や感染様式も詳細に解明され,大規模臨床試験を通じて治療戦略も見出されている.
雑誌目次
medicina61巻3号
2024年03月発行
雑誌目次
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
特集にあたって フリーアクセス
著者: 岡秀昭
ページ範囲:P.418 - P.419
座談会
コロナ禍で露呈したわが国の感染症(科学)リテラシーとその改善に向けて
著者: 知念実希人 , 岡秀昭 , 忽那賢志
ページ範囲:P.426 - P.434
新型コロナウイルス感染症(以下,コロナ)は5類感染症への移行という大きな節目を迎え,コモンディジーズの1つとなりました.本日は,コロナ禍初期から情報を発信しながら重症患者を診てこられた忽那先生と,開業医という立場から情報を発信されてきた知念先生のお二人に,それぞれの視点からコロナ禍を振り返っていただくとともに,コモンディジーズとなったコロナの今後や次のパンデミックへの備えについて話し合っていきたいと思います.(岡)
どこでもみれる? 5類感染症
新型コロナウイルス感染症 5類化以降の治療
著者: 忽那賢志
ページ範囲:P.436 - P.440
Point
◎新型コロナウイルス感染症の治療法は,ウイルス増殖期に抗ウイルス薬を,炎症反応が過剰に起こる時期に抗炎症薬を使用することが重要である.
◎現在,重症化する感染者の割合は激減しており,複数の抗ウイルス薬(レムデシビル,モルヌピラビル,ニルマトレルビル/リトナビル,エンシトレルビル)が承認されている.また,重症例ではデキサメタゾン,バリシチニブ,トシリズマブなどの抗炎症薬が使用される.
◎治療の有効性は,オミクロン株の拡大やワクチン接種の進展により変化しているため,最新の臨床研究に基づく治療法の適用が必要である.
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌による感染症の診断・治療—感染症と定着をいかに区別するか?
著者: 小野大輔
ページ範囲:P.442 - P.445
Point
◎カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)とカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌(CPE)の定義,違いについて理解する.
◎検出されたCREが感染症の原因菌であるのか,感染を引き起こしていない定着であるのかは,臨床経過から判断する.
◎CREが検出された場合には,感染対策およびカルバペネマーゼ産生の確認検査を実施する.
◎薬剤耐性菌の診断・治療について考えるときには,海外との疫学や使用できる抗菌薬の違いについても考慮する.
◎治療が難しい薬剤耐性菌であるCREによる感染症の診療においては,感染か定着かの判断やソースコントロールなどの一般感染症診療における原則はより一層重要である.
HIV感染症の診断・治療—プライマリ・ケア医も知っておきたい検査や治療薬のアップデート
著者: 塚田訓久
ページ範囲:P.446 - P.450
Point
◎早期に診断され抗HIV療法を継続すれば生命予後は良好である.
◎抗HIV療法により血中ウイルス量が抑制された状態を維持していれば新たな感染源にならない.
◎「HIV感染症の診断」「抗HIV療法で安定したHIV陽性者の合併症診療」はプライマリ・ケア医の役割である.
見逃してはならない細菌性髄膜炎(侵襲性肺炎球菌感染症)—診断・治療・予防のコツから届け出の基準まで
著者: 渋江寧
ページ範囲:P.451 - P.455
Point
◎細菌性髄膜炎は早期診断・早期治療が重要であり,臨床経過で疑い,まず血液培養を採取する.
◎細菌性髄膜炎を疑ってから抗菌薬治療開始まで1時間以内を目指す.
◎血液,髄液などの無菌部位から肺炎球菌が検出された場合は侵襲性肺炎球菌感染症と認識して5類感染症として届け出る.
増えている梅毒の診断・治療—ステルイズ® の使い方を中心に
著者: 谷崎隆太郎
ページ範囲:P.456 - P.459
Point
◎トレポネーマ(Tp)検査陽性であれば梅毒の可能性が高いが,現在の感染と過去の感染を区別できないため,現在の疾患活動性の有無と治療効果判定には非Tp検査(主にrapid plasma reagin:RPR)を用いる.
◎神経梅毒を合併していない早期梅毒の標準治療はペニシリンGベンザチン(ステルイズ®)240万単位を単回筋注し,後期梅毒の場合は同量を1週間空けて合計3回筋注する.
◎治療開始後,治療前値から1/4以上RPRが低下すれば治療成功と考えるが,再上昇する場合には再感染の可能性を,なかなか低下しない場合にはHIV感染症合併や神経梅毒合併の可能性を考慮する.
これから増える!? 知っておきたい麻疹の診断・治療
著者: 上山伸也
ページ範囲:P.460 - P.462
Point
◎麻疹は臨床診断で検査前確率を上げることが重要である.そのうえでPCR検査による確定診断を行う.
◎ワクチン接種歴があると修飾麻疹となり診断が困難となるため,疑わしければ積極的に保健所と相談する.
◎麻疹は世界的に再流行している.インバウンドの増加に伴う国内での再流行には注意を要する.
◎麻疹の治療は基本的に対症療法であり,ビタミンAやリバビリンの効果は限定的であるため予防が重要である.
感染症新薬アップデートと感染症
国内でのイミペネム・レレバクタムの適正使用とは?
著者: 西村翔
ページ範囲:P.463 - P.467
Point
◎イミペネム・レレバクタムは既存のイミペネムと新規βラクタマーゼ阻害薬であるレレバクタムの合剤である.
◎抗菌活性の観点からは,イミペネムと比較して,KPC型カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌とカルバペネマーゼ非依存性難治耐性緑膿菌においてアドバンテージがある.
◎国内のカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌で最も頻度の高いカルバペネマーゼは,イミペネム・レレバクタムが無効なIMP型であり,KPC型はほとんど認めない.したがって,イミペネム・レレバクタムを腸内細菌目細菌感染症において使用すべき機会は限られており,主に難治耐性緑膿菌感染症において有用な抗菌薬である.
◎イミペネム・レレバクタムは,既存薬だとコリスチンやアミノグリコシド系しか選択できない難治耐性緑膿菌感染症において,既存薬よりも臨床予後を改善し,かつ腎障害の頻度を低下させることができる.
◎難治耐性緑膿菌感染症では,同じく有用な新規βラクタマーゼ阻害薬の合剤の先行薬であるセフトロザン・タゾバクタムの感受性が確認されているのであれば,両剤の比較試験がない現状では,より臨床実績の豊富なセフトロザン・タゾバクタムをイミペネム・レレバクタムよりも優先して使用すべきである.
イサブコナゾールの特徴—他の抗糸状菌作用を有するアゾール系抗真菌薬との違い
著者: 冲中敬二
ページ範囲:P.468 - P.472
Point
◎イサブコナゾール(ISCZ)はポサコナゾール(PSCZ)と同様にムーコル属をカバーする.
◎ISCZはボリコナゾール(VRCZ)やPSCZより肝機能障害などの副作用が少ないと報告されている.
◎ISCZはVRCZ,PSCZとの違いを理解したうえで処方する(臓器移行性,薬物相互作用,腎障害時の投与経路,経口吸収率など).
◎ISCZは広いスペクトラムを有する抗真菌薬であり適正使用に注意する.
フィダキソマイシンとCDI—ガイドラインの改訂ポイントを中心に
著者: 森伸晃
ページ範囲:P.473 - P.478
Point
◎
◎
◎CDIの再発例もしくは再発リスクのある患者ではフィダキソマイシンの使用を検討する.
2023年新見解に基づく肺MAC症治療とアミカシンリポソーム吸入用懸濁液
著者: 倉原優
ページ範囲:P.480 - P.484
Point
◎近年,肺
◎2023年に肺非結核性抗酸菌(NTM)症の治療に関する新見解が日本結核・非結核性抗酸菌症学会から発出され,これに基づいて標準治療を適用すべきである.
◎排菌陰性化が得られにくい症例(難治例)にアミカシンリポソーム吸入用懸濁液は有効である.
◎アミカシンリポソーム吸入用懸濁液を処方すると高額療養費制度の支払い上限額に到達するため,事前に自己負担額がどの程度か患者と相談しながら用いる.
コモンディジーズと感染症アップデート
市中肺炎アップデート
著者: 友田義崇
ページ範囲:P.486 - P.489
Point
◎新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は市中肺炎の一般的な原因微生物となった.
◎抗菌薬治療の投与期間は短縮される傾向にある.
◎重症肺炎に対するステロイドは有効かもしれない.
尿路感染症アップデート
著者: 三村一行
ページ範囲:P.490 - P.493
Point
◎尿路感染症は単純性尿路感染症と複雑性尿路感染症に分類され,両群においては推定される起因菌が異なる.
◎初期抗菌薬は,推定される起因菌と地域ごとの抗菌薬感受性(ローカルファクター),疾患の重症度を考慮して決定する.
◎合併症がない場合,単純性尿路感染症では7日以下,複雑性尿路感染症の場合には10〜14日間の抗菌薬治療期間が一般的には推奨される.
◎複雑性尿路感染症においても,患者背景によっては7日間の短期治療を行う妥当性を担保するエビデンスが蓄積されてきている.
皮膚軟部組織感染症アップデート
著者: 西田裕介
ページ範囲:P.494 - P.498
Point
◎蜂窩織炎は真皮深部〜皮下組織の炎症のため紅斑の境界が不明瞭であるのに対し,丹毒は表在真皮の炎症のため紅斑の境界が比較的明瞭になる.
◎原因微生物はA群β溶血性レンサ球菌と黄色ブドウ球菌が大半であるが,特殊な病歴がある場合は稀な微生物も関与する.
◎一般的に蜂窩織炎は軽症であることが多く,初期治療の段階でのメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)カバーは不要である.
◎壊死性軟部組織炎を除外するのに有用な所見は乏しく,見た目に釣り合わない強い痛みを訴える場合や,バイタルが不安定な場合は外科系診療科への相談を行う.
カテーテル関連血流感染症アップデート
著者: 松永直久
ページ範囲:P.500 - P.503
Point
◎新型コロナウイルス感染症の影響で米国では中心静脈カテーテル関連血流感染症(CLABSI)が増加したが,わが国ではサーベイランス上明らかな影響はみられなかった.
◎CLABSIを起こしにくい因子として,単内腔カテーテルが挙げられている.
◎末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)のほうが従来の中心静脈カテーテル(CICC)より血流感染症の頻度が低いことを示す報告が,最近発表されている(ただし,いずれも単施設の後ろ向き研究).
◎カテーテルの逆血を用いた培養検査と静脈から直接採取した血液を用いた培養検査の陽性化までの時間差(DTP)はカテーテル関連血流感染症(CRBSI)の診断に有用だが,黄色ブドウ球菌とカンジダ属菌では良好な結果は得られなかった.
◎コアグラーゼ陰性ブドウ球菌によるCRBSIに対して,低リスク者では抗菌薬投与が不要である可能性が示唆されており,今後の研究が待たれる.
ガイドラインアップデート
結核—疫学の変化,多剤耐性菌の現状について
著者: 佐々木結花
ページ範囲:P.504 - P.507
Point
◎新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け,世界の結核対策は後退し,結核患者発見が進まず,結核死亡者数が増加した.
◎本邦の結核罹患率(人口10万対)は2022年に8.2となり,結核低蔓延状態を維持している.
◎2023年1〜9月まででは,20歳台の結核患者数が急増している.
◎本邦では,2023年5月に超多剤耐性結核菌の定義が,WHOに準じて「イソニアジド+リファンピシンに加えて,レボフロキサシンあるいはモキシフロキサシンのいずれかのキノロン系薬に耐性を有し,かつ,ベダキリンないしはリネゾリドのいずれかに耐性を有する菌」と変更された.
◎世界的には治療の短期化が進んでいるが,本邦では健康保険のもとで投与できない薬剤があるために実施できない.
感染性心内膜炎—修正Duke診断基準を中心に
著者: 山本舜悟
ページ範囲:P.508 - P.513
Point
◎2023年に改訂された診断基準では,PET/CTや心臓CTが組み込まれるようになった.
◎抗菌薬開始から4日間以内に解熱しても感染性心内膜炎を除外できるわけではなく,4日間未満の抗菌薬治療で再発がなければ除外できることが明確になった.
◎臨床状況が許せば,感染性心内膜炎の治療でも静注薬から経口薬への変更は安全で有効である.
敗血症—集中治療医の視点から
著者: 竹内晋太郎 , 太田啓介
ページ範囲:P.514 - P.519
Point
◎敗血症のスクリーニングツールはさまざまなものがあるが,quick SOFA(qSOFA)は本来,予測死亡率として策定されたものであり,単独で用いないほうがよい.
◎ショックを伴わない敗血症の可能性がある患者には,敗血症と認識されて3時間以内に抗菌薬を投与するとよい.SSCG2016ではショックがなくとも1時間以内の抗菌薬投与が推奨されたが,抗菌薬の不要な投与が増えるなどの有害事象がある.
◎昇圧薬の投与は中心静脈が確保されるまで待つのでなく,末梢静脈から投与を開始することで平均血圧65 mmHgをより早く達成できる.
◎集中治療室に滞在している間も,患者だけでなく,家族のケアや退院後の生活を見据えた治療計画を立てる必要がある.
◎日本版SSCG2020の独自項目として,体温管理,集中治療後症候群(PICS)/ICU-AW(ICU-acquired weakness)や神経集中治療などがある.
骨髄炎—ガイドラインの改訂があった糖尿病性足感染症を中心に
著者: 川村隆之
ページ範囲:P.520 - P.524
Point
◎糖尿病性足感染症/骨髄炎の診断根拠や微生物学的評価が最重要である.
◎抗菌薬治療の原則は狭域抗菌薬から開始するescalation戦略である.
◎最新のガイドラインで推奨されている治療期間を把握する.
◎外科的処置の必要性を症例ごとに判断する.
薬剤耐性(AMR)と抗菌薬適正使用支援(AS)
著者: 加藤英明
ページ範囲:P.526 - P.529
Point
◎日本の薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)が国の主導で策定され,耐性菌検出率と抗菌薬使用量の数値目標が設定された.
◎感染対策向上加算1,2の取得要件として感染管理部門に抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を作り各種モニタリングや臨床への介入を行うことが求められる.
◎ASTには責任を持つ薬剤師の配置と活動時間の確保が必要である.ASTリーダーは抗菌薬適正使用支援の意義を病院全体に示していく必要がある.
ワクチンアップデート
新型コロナワクチン—令和5年秋開始接種時点のQ&A
著者: 守屋章成
ページ範囲:P.530 - P.534
本稿では,2023年12月末時点での新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(以下,新型コロナワクチン)に関する疑問点をQ&A形式で整理したい.
肺炎球菌ワクチン—PPSV23,PCV13の効果の違いと使い分け
著者: 三村一行
ページ範囲:P.535 - P.539
Point
◎肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV)は単独接種ではワクチン含有血清型の侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)にのみワクチン効果を認めるが,インフルエンザワクチンと併用することでIPD以外の肺炎球菌感染症にも予防効果が得られる.
◎肺炎球菌結合型ワクチン(PCV)は単独接種においてIPD以外にも菌血症を伴わない肺炎球菌性肺炎や免疫機能低下例についても有効性を示し,集団免疫効果も期待できるワクチンである.
◎近年,非ワクチン含有血清型による肺炎球菌感染症の増加(血清型置換)が問題となっている.
◎連続接種に関しては,初回にPCVを接種し,その1年後を目安にPPSV接種を行うと免疫原性が高まり,より高い臨床効果が得られる.
帯状疱疹ワクチン—生ワクチン,サブユニットワクチンの効果の違いと使い分け
著者: 西田裕介
ページ範囲:P.540 - P.543
Point
◎小児への水痘ワクチンの定期接種により水痘帯状疱疹ウイルスの自然曝露が減少し,高齢者の帯状疱疹が増加した.
◎2016年に50歳以上の帯状疱疹の予防を目的に乾燥弱毒生水痘ワクチンの適応が拡大され,2018年にアジュバンド添加サブユニット帯状疱疹ワクチンが承認された.
◎サブユニットワクチンは生ワクチンに比べ帯状疱疹発症予防効果に優れるうえに,生ワクチンが接種できない免疫不全患者にも接種可能になった.
ブレイクスルーと感染症
関節リウマチに対する生物学的製剤と感染症
著者: 山室亮介 , 萩野昇
ページ範囲:P.544 - P.548
Point
◎関節リウマチにおける生物学的製剤にはモノクローナル抗体と融合蛋白製剤がある.
◎モノクローナル抗体の主な標的はTNF-αとIL-6受容体,融合蛋白製剤は組換え部分がTNF受容体およびCTLA-4である.
◎生物学的製剤使用中の患者の診察においては進行した感染症が存在していても症状は軽度にみえることがあるので,毎回の外来で詳細な病歴聴取と身体診察を行うことが重要である.
◎一般細菌以外における留意点としてTNF阻害薬は抗酸菌をはじめとする細胞内寄生菌の感染,抗IL-6受容体抗体では消化管穿孔のリスクが高いことが挙げられる.
糖尿病治療の進歩と感染症
著者: 岩田健太郎
ページ範囲:P.550 - P.553
Point
◎糖尿病患者は「易感染性」である.具体的にどの感染症のリスクが高いか把握しておくとよい.
◎特に多いのは尿路感染症だ.無症候性細菌尿は尿路感染症のリスクである.ただし,抗菌薬投与でそのリスクはヘッジできない.
◎足感染症予防のために,患者や医師による足の観察が重要である.感染時は,皮膚や潰瘍表面のスワブ培養は採ってはならない.
◎SGLT2阻害薬の服用で尿路感染などが増える可能性がある.
免疫チェックポイント阻害薬と感染症
著者: 武田孝一
ページ範囲:P.554 - P.559
Point
◎免疫チェックポイント阻害薬の機序と,その特異的な副作用である免疫関連有害事象(irAE)を理解する.
◎免疫チェックポイント阻害薬そのものに感染症リスクは(おそらく)ないが,合併したirAEに対してステロイド/免疫抑制薬/生物学的製剤を使用した場合は,(特に細胞性免疫不全状態の)感染症に注意する.
◎irAEのうち,臨床像が感染症に類似するものが複数存在する.
新型コロナミミック
主治医のCOVID-19罹患後に高度低酸素血症と肺炎をきたした一例
著者: 島田侑祐 , 志水太郎
ページ範囲:P.564 - P.568
症例
65歳,女性.
現病歴 既往や内服歴なく,元気に生活をしていた.転倒による左大腿骨転子下骨折で入院となり,すぐに観血的整復固定術を実施された.術後経過は良好であり,X−55日に回復期リハビリ病棟へ転棟し,その後も順調に院内でリハビリが進んでいた.
COVID-19流行初期に発熱・非定型肺炎で転院搬送された一例
著者: 前田正
ページ範囲:P.569 - P.571
症例
症例 62歳,男性.
現病歴 2週間前,サプリメントを内服後に全身の皮疹にて近医皮膚科を受診し,経過観察となっていた.その後,発熱と体動困難が増悪したため前医に搬送され,重度の脱水所見とCT所見で非定型肺炎との鑑別を要する間質性陰影を認めた.当時の流行状況から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による肺炎が疑われたため,精査加療目的にて当院へ転院となった.
連載 日常診療で役立つ 皮膚科治療薬の選びかた・使いかた・3
ERの片隅で・12【最終回】
ありがとうを繰り返す救急医
著者: 関根一朗
ページ範囲:P.572 - P.573
「搬送、お疲れさまです。雨降り出したんですね。」日曜日の午後10時、救急搬送でERに入ってきた救急隊員の服が濡れているのを見て、救急医関根が救急隊員に話しかけている。「急に降り始めました。風も強くて、今夜は冷えますね。」搬送を終えた救急隊員は雨に濡れた帽子に手を当てながら答える。
walk-in受診した症例を診ていた研修医が、関根のところに相談に来た。「3歳男児、急性上気道炎の疑いです。昨日から鼻汁と咳嗽があり、本日発熱したため受診されました。診察では異常所見はありませんでした。緊急性はなさそうなので、平日に小児科を受診するように指示しようと思います。」関根が答えた。「なるほど。確かに症状の経過からは緊急性はなさそうだね。一緒に診察してみようか。」
明日から主治医! 外国人診療のススメ・12
プライマリ・ケアクリニックにおける外国人診療の現状:精神科との境界領域
著者: 高柳喜代子
ページ範囲:P.574 - P.579
CASE
内科後期研修医(翔太)が「まつもとクリニック」の内科外来で,家庭医(松本)と…
翔太)はぁ…
松本)翔太先生,どうしたの,ため息なんかついちゃって.
翔太)松本先生….実は,K医療センターから治療継続を依頼された方がいて.
松本)どんな患者さん?
翔太)2年前に単身で日本に働きに来た40代のネパール人コック,タパさんという方です.消化器系の愁訴が多くて,いろいろ検査されているんですが,これといった異常がなくて.でも本人は納得してくれないんです.
松本)ドクターショッピングもしているかしら?
翔太)どうしてわかるんですか!? これまでにかかった病院の診察券を見せてもらったんですが,2年で5カ所も受診されていました.これってメンタル不調ですよね,苦手だなぁ….
松本)なるほど,persistent physical spymptoms(PPS)ね.診断名がつくことを治療のゴールにせず,日常生活を少しでもよく過ごせるような別のアプローチが必要かもしれないわ.
ここが知りたい! 欲張り神経病巣診断・33
顔が痛い! 歯の病気? 顔面の神経痛/三叉神経痛の原因と治療
著者: 難波雄亮
ページ範囲:P.580 - P.585
患者さんが顔面の痛みを訴えるとき,顔の表面に異常がない場合には歯科疾患を疑う人は多いです.歯科を受診しても痛みの原因がわからず,原因不明の痛みとして長期間放置されたり,また抜歯されたりしてしまうケースも昔はみかけました.顔に皮疹があり,神経髄節に異常を認めれば帯状疱疹の可能性もありますが,歯科疾患以外でほかに顔の痛みの原因となるものには何があるでしょうか? それでは,その一例を一緒に勉強していきましょう.
知らないとヤバい! リウマチ・膠原病のアレやコレ・7
リウマチにおける知らないとヤバい“足”のアレやコレ—足から始まる関節リウマチって実は多いんです
著者: 猪飼浩樹
ページ範囲:P.587 - P.594
本連載では,リウマチ・膠原病診療における緊急病態,知っておかないと重篤な状態となりうる事象について取り扱っている.リウマチ・膠原病診療は専門性が高い面もあるが,専門医に必ずしも受診していない患者も多い.その背景には,専門医が少ない地域性の問題や,高齢などの理由で専門医への通院が困難であるといった多くの要因がある.関節リウマチ(rheumatoid arthritis:RA)や膠原病を併存症としてもっている患者を診る機会のあるすべての医師において注意すべき見逃したくない,ヤバい病態について学ぶ連載である.
目でみるトレーニング
書評
—森 望 著—老いをみつめる脳科学 フリーアクセス
著者: 白澤卓二
ページ範囲:P.425 - P.425
私と森先生のお付き合いは長く,私が東京都老人総合研究所(今の東京都健康長寿医療センター研究所)で分子遺伝学の部長,森先生が国立長寿医療研究センターの研究部長を務めている頃からの長い学友である.ともに,日本基礎老化学会で脳の老化のメカニズムを違った角度から研究していた.私は,アルツハイマー病の病理学からスタートして,脳の正常老化プロセスがどのようにアルツハイマー病という病気によりダメージを受けるかを研究していたのに対して,森先生はむしろ神経科学(ニューロサイエンス)の生理学基盤を深掘りして理解することにより,正常老化と病的老化の違いを探究していたと記憶している.森先生が2004年に長崎大学に栄転されたときには,解剖学の教授で赴任したという話を聞いて,神経科学の先生がどうして解剖学の教授の道を選んだのか不思議に思ったが,今回の『老いをみつめる脳科学』を一読して,脳を3次元的に理解できないと,神経科学の発展だけでは解決できない問題が神経疾患には数多く残されていて,その知識基盤を固めるために解剖学の教授として長崎大学に赴任されたのだと確信した.私も2007年には,東京都老人総合研究所から順天堂大学に移り,加齢制御学という新しい分野の研究を開始した.アルツハイマー病や認知症を脳の加齢制御プロセス異常であるという新たな視点から,アルツハイマー病の治療や予防に突破口を開こうとしたためだ.
サイエンスでの発見は,どの論文も大きなジグソーパズルの1つのピースに過ぎないと1990年に免疫学から分子病理学に転向したときから学んできた.森先生もおそらく,私と同様の考えで研究を続けてきたに違いない.今回,森先生が出版された本を拝見すると,これまでに発見されたサイエンスのピースからどのように「脳」や「精神」や「心」が,再構築できるかという内容になっている.1980年に医学に分子生物学が導入され,分子から病気の原因や病態を解明する医学研究が主流となった.2003年にはヒトゲノムが解読され,ヒトの設計図が明らかになると,ヒトの発生や病気の多くは,ヒトゲノム情報からのアプローチで解決するのではないかと期待されたが,残念ながら多くの神経変性疾患はいくつかの原因遺伝子が解明されたにもかかわらず,根本的治療法が確立されていないのが現状である.
—坂本 史衣 著—感染対策60のQ&A フリーアクセス
著者: 伊東直哉
ページ範囲:P.435 - P.435
坂本史衣先生といえば,言わずと知れた「感染管理のプロフェッショナル」です.感染症業界の人ならば,まずその名を知らない人はいないのではないでしょうか? 知らなかったらモグリです.「感染管理ならば,感染症内科医もやっているでしょ? 専門でしょ?」と,思われるかもしれませんが,チッチッチ,それは違うのです.あくまでもわれわれ感染症内科医は,感染症「診療」の専門家であって,「感染管理」の専門家ではないのです(一部に両方に深い見識と経験を持つ稀有な存在もいますが).坂本先生は,学会活動や多くの著書を通じて,長きにわたって日本の感染管理を牽引されてきました.私自身も,実際に坂本先生の講演や著書で感染管理を学んできた熱心なファンの一人です.そのような師匠的存在の坂本先生の著書の書評を書かせていただくことはとても光栄なことで,とてもとても嬉しいことなのです.
さて,『感染対策60のQ&A』ですが,前著『感染対策40の鉄則』よりもさらに読みやすく進化しており,感染管理の実務担当者の新たなバイブル本の1つになると確信しています.
—矢野 寿一,笠原 敬 監修 小川 吉彦 著—ケースで学ぶ抗菌薬選択の考え方—耐性と抗菌メカニズムの理解で深掘りする フリーアクセス
著者: 林俊誠
ページ範囲:P.485 - P.485
感染症診療のマニュアル本は持っているし,一般的な感染症はだいたい治療できている.とは言え,もしも耐性菌やそれに対する抗菌薬選択について聞かれたら,スムーズに答えられるほど詳しいわけでもない.いっそ専門書を読んでみたいけど,読める自信もない.見慣れない・聞き慣れない菌は,微生物学の本を読んでもしっくりこない.そんなあなたがギャップを乗り越えステップアップするのにおすすめなのが本書である.
第1章は薬剤耐性の総論である.「MICの数字を横読みする」「CEZを使用し続けても,そのMSSAはMRSAにはなりません」など,耐性菌に対する抗菌薬選択に欠かせない基礎知識が満載だ.続く第2章は臨床で主に使用される抗菌薬に対する耐性機序の解説で,ここまでをじっくり読んでも2時間程度で理解できるのが嬉しい.最もよく出合うβ-ラクタマーゼについては特に図が豊富なので,この分野について初めて読む場合でもイメージしやすい.また,AmpCの「心変わり」や複雑怪奇なカルバペネマーゼがわかりやすく解説されてもいる.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.414 - P.416
読者アンケート
ページ範囲:P.603 - P.603
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.604 - P.605
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.606 - P.606
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.607 - P.607
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.608 - P.608
基本情報
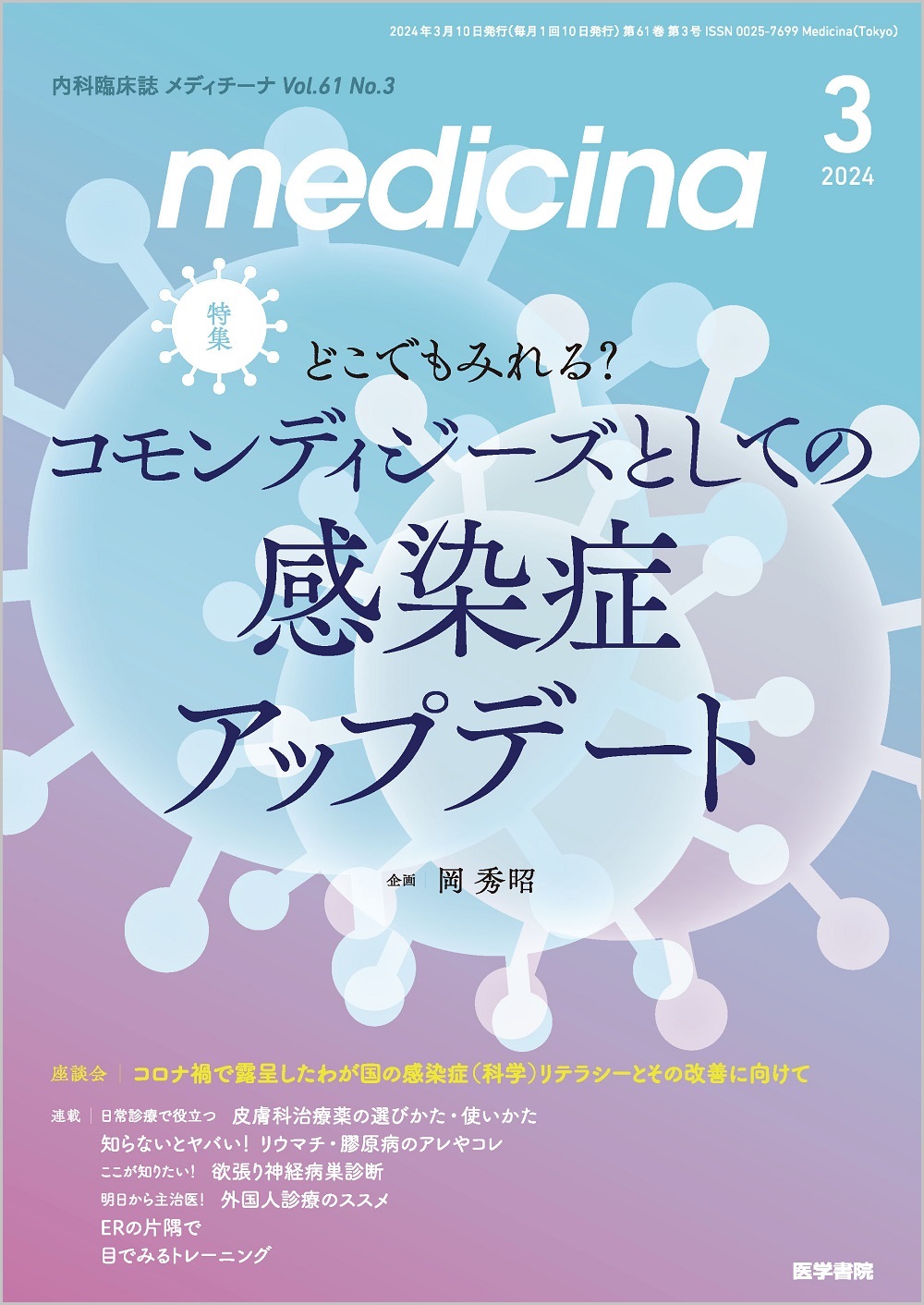
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
