今回は,プライマリ・ケア医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かたについての特集を企画させていただきました.私は脳神経内科医として約30年間にわたって救急を含めた臨床の場で診療に当たっています.そのなかで,「しびれ」,「ふるえ」,「めまい」は最もありふれた患者の訴えである一方で,最も対応に苦慮する訴えであると感じています.また,「しびれ」,「ふるえ」,「めまい」への対応は,人口の高齢化もあり増すばかりです.プライマリ・ケア医の先生方にとっても,「しびれ」,「ふるえ」,「めまい」の診療は必須であるにもかかわらず,敬遠される分野であると思います.
患者の訴えるそれらの症状は多彩な症候を含んでおり,背景となる疾患もさまざまです.「年のせい」,「心配ない」,「異常ありません」として,ゴミ箱的に片付けられる例も多いのではないかと考えられますが,一方で生命や神経機能に重大な影響を及ぼす病態,緊急に対応を必要とする疾患が紛れている可能性は十分にあります.画像診断を含めた検査技術の進歩により,ベットサイドでの診察だけで「しびれ」,「ふるえ」,「めまい」の診断を下す機会は少なくなりつつあります.しかしながら,「しびれ」,「ふるえ」,「めまい」は問診とベットサイドの診察のみでその多くが診断できると言っても過言ではありません.
雑誌目次
medicina61巻7号
2024年06月発行
雑誌目次
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
特集にあたって フリーアクセス
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1010 - P.1011
しびれの診かた
患者の訴える「しびれ」とは何か?—しびれの評価にはまず病歴聴取が重要
著者: 安藤孝志
ページ範囲:P.1016 - P.1021
Point
◎病歴聴取に先立ち,ABC(Airway:気道,Breathing:呼吸,Circulation:循環)が安定しているかどうかをまず確認する.
◎「しびれ」という表現がどのような症状を指すのか具体的に明らかにする.
◎しびれの発症様式から背景に存在する病態を,分布から神経系における病変部位をそれぞれ推測する.
◎聴取した臨床情報を基に鑑別診断を想起し,診断を確定させるためにどの神経診察や検査に重点を置くかを決定する.
しびれの分布から考えること—中枢性と末梢性の見分け方は?/「ピリピリする」と患者が訴える場合はどのような疾患を考えるか?
著者: 千田譲
ページ範囲:P.1022 - P.1028
Point
◎脳神経系の診察というと,「打鍵器や音叉を使いこなさなければ」と思い苦手意識を持ってしまいがちだが,実は少しの知識と問診や視診を組み合わせることで確定診断に迫ることができる.
◎脳血管障害,頚椎・頚髄症,ニューロパチーで,しびれの出現様式が異なる.
◎しびれの部位が,単部位なのか,バラバラなのか(patchy),左右対称型なのか(手袋・靴下型か靴下型のみか)を確認しつつ,それぞれ鑑別すべき背景疾患を想起していく.
しびれの原因疾患とその病態は?—手根管症候群,変形性脊椎症,末梢神経障害,脳血管障害,むずむず脚症候群などを中心に
著者: 加藤隼康 , 杉浦真
ページ範囲:P.1029 - P.1032
Point
◎しびれの発生には末梢神経から脳の感覚野までが関連しており,手根管症候群や変形性脊椎症,糖尿病性ニューロパチー,脳血管障害,むずむず脚症候群など,さまざまな疾患が原因となりうる.
◎しびれの分布は障害された神経や脳の部位によって異なる.手袋靴下型や片側性,対側性,局在性などの分布の特徴と,それに対応する神経や脳の部位について理解する必要がある.
◎しびれの原因となる疾患は多岐にわたるため,診断や鑑別には頻度の高い疾患の病態と特徴的な症状を理解することが鑑別診断に重要である.
しびれの診断に必要な神経学的診察や検査法—腱反射,表在覚・深部覚の診かた/神経伝導速度検査,針筋電図などの検査法
著者: 石原健司
ページ範囲:P.1034 - P.1039
Point
◎感覚障害の評価では,障害の程度とともに,障害の範囲を正確に調べることが必要である.
◎腱反射の評価では,関節の動きよりも,筋の収縮の有無,程度を確認する.
◎画像検査は,感覚障害の分布,運動症状(筋力低下の分布,腱反射の強弱など)から病変部位を推定してオーダーする.
◎電気生理学的検査は,しびれを呈する疾患の診断に有用であるが,症候を踏まえたうえで結果を解釈する.
「診断のつかないしびれ」に対する対処法—高齢者の訴えるしびれや原因不明のしびれにはどのように対応すべきか?
著者: 岩瀬環
ページ範囲:P.1040 - P.1043
Point
◎高齢者のしびれへの対処は,加齢性変化を知ることから始まる.
◎高齢者は頚髄薄束の有髄神経線維が脱落している.
◎一次感覚ニューロンは最も長い細胞で,加齢に対して選択的に脆弱である.
◎下肢からの一次感覚ニューロンの障害は,腰部脊柱管狭窄症と無関係ではない.
◎感覚受容器は加齢により減少する.
しびれの治療—末梢神経障害(神経障害性疼痛)の治療を中心に
著者: 吉川正章 , 小池春樹
ページ範囲:P.1046 - P.1049
Point
◎神経障害性疼痛の原因は多岐にわたる.
◎診断には詳細な病歴聴取と神経学的評価を含めた診察が重要である.
◎個々の患者に適した治療薬を選択し,患者のQOL向上を目指す.
ふるえの診かた
患者の訴える「ふるえ」とは何か?—「ふるえ」にはどのような病態,症候が含まれているのか?
著者: 和座雅浩
ページ範囲:P.1051 - P.1057
Point
◎ふるえを主訴とする疾患は,本態性振戦やParkinson病が代表的であるが,これらの脳神経疾患以外にも全身疾患でも認めることがある.
◎ふるえの原因や病態を鑑別するためには,まず丁寧な問診と視診が重要である.
◎指鼻試験や渦巻き書きテストは,ふるえの特徴や治療効果を簡便に評価することができ,プライマリ・ケアにおいて有用である.
ふるえの分類と特徴—不随意運動,てんかん発作との違いは何か
著者: 倉重毅志
ページ範囲:P.1058 - P.1061
Point
◎「ふるえ」は自分の意思にかかわらず体が勝手に動いてしまう症状であり,生理的なものと病的なものがある.
◎「ふるえ」は通常は意識清明のときに出現するが,意識障害に伴う場合には「ふるえ」の診断価値は高く生命予後にかかわる可能性が高い.
◎「ふるえ」は中枢神経内のリズム形成回路網の活動による二次運動ニューロンの動的な興奮に脊髄反射回路の活動が加わることで生じる.
◎「ふるえ」の鑑別には静止時かどうか,および振戦の周期が重要である.
◎「ふるえ」は生理的な振戦であることも多く,脳神経疾患にこだわらないことも重要である.
ふるえの原因疾患と診断—本態性振戦,パーキンソニズムに関連した振戦,心因性振戦を中心に
著者: 曽根淳
ページ範囲:P.1062 - P.1067
Point
◎2018年に,国際パーキンソン運動障害協会(International Parkinson and Movement Disorder Society:IPMDS)によって新たな振戦の分類基準が発表された.
◎新しい分類基準では,本態性振戦(essential tremor:ET)が再定義され,“ET plus”(ジストニア,運動失調,パーキンソニズムなどの追加の神経学的症状を伴うET)の概念が導入された.
◎随意運動中の振戦の抑制は,Parkinson病における静止時振戦の特徴である.
◎心因性振戦には診断基準はなく,診断は慎重な病歴と神経学的検査に基づいて行われる.特徴として,変動性,注意散漫性,同調性,一貫性などがある.振戦の始まりは通常突然であり,振戦の振幅,周波数,方向にはばらつきがある.
ふるえの治療—本態性振戦(老人性振戦)はどう治療する?/病態を考慮した治療薬の選び方
著者: 伊藤瑞規 , 千田麻友美 , 水谷泰彰
ページ範囲:P.1068 - P.1071
Point
◎本態性振戦の治療には,内服療法,ボツリヌス毒素療法,手術療法があり,どの治療を選択するかは,振戦による日常生活や社会生活への影響を考慮し判断する.
◎内服療法の第一選択薬は,β交感神経遮断薬のアロチノロール,プロプラノロールと抗てんかん薬のプリミドンで,第二選択薬として,ベンゾジアゼピン系薬,抗てんかん薬や抗精神病薬などが用いられる.
◎手術療法は,非侵襲的治療の効果が不十分で,振戦のために日常生活や社会生活に困難を認める場合に適応となり,脳深部刺激療法,ラジオ波温熱凝固術,MRガイド下集束超音波治療がある.
めまいの診かた
患者の訴える「めまい」とは何か?—急性めまいに対する新しいアプローチ
著者: 赤木明生
ページ範囲:P.1072 - P.1076
Point
◎急性めまいへの新しいアプローチ“ATTEST”では,特にTT(timing and trigger)が重要である.
◎急性めまいへのアプローチでは致死性疾患の除外が重要である.
◎急性めまいへのアプローチでは,正確な病歴聴取と身体診察が基本である.
めまいの分類—末梢性めまいを中心に
著者: 陸雄一
ページ範囲:P.1077 - P.1080
Point
◎めまいには回転性めまい(vertigo)と浮動感(dizziness)とがある.どちらになるかは末梢性か中枢性かではなく,前庭感覚路の障害パターンによって決まる.
◎本稿では前庭や前庭神経の障害で起こるものを末梢性めまい,脳幹や小脳などの脳実質病変で起こるものを中枢性めまいと定義する.
◎薬剤,アルコール,加齢などさまざまな全身要因で起こるめまいを知っておく.
緊急対応を要するめまい—鑑別のコツと要点,直ちに行うべき検査,対応法は?
著者: 藤田浩司
ページ範囲:P.1081 - P.1084
Point
◎突然発症のめまいで,高齢または血管危険因子を背景とする場合,中枢性めまいを示唆する症候を認める場合などは,脳卒中を疑う.
◎中枢性めまいの背景として小脳,脳幹の病変を考える.血管では後方循環系のうち,椎骨動脈,後下小脳動脈,脳底動脈,上小脳動脈,前下小脳動脈などの病変を考える.
◎後方循環系の脳梗塞の評価のためには頭部MRIを行う.ただし,後方循環系の脳梗塞は超急性期にMRIで偽陰性となりうるため,初回MRIで陰性でも必要に応じてフォローアップ検査を行う.
中枢性めまいと末梢性めまいの鑑別—眼振所見の診かた,Romberg test/耳性と非耳性をどう鑑別する?
著者: 加藤優弥 , 岩井克成
ページ範囲:P.1086 - P.1092
Point
◎めまいの病巣ごとに誘発因子や随伴症状,眼振所見を押さえておき,症状から病巣の推定を行う.
◎Romberg testは脊髄後索障害の有無の評価に有用である.
◎前庭性のめまいが除外できたら,小脳失調やその他の脳神経障害について神経診察を行う.
◎良性発作性頭位めまい症(BPPV)や前庭神経炎,Ménière病などの代表的な疾患の特徴を押さえておく.
失神の診断と原因疾患の鑑別—起立性低血圧,血管迷走神経反射性失神の診断/てんかん,心原性失神とどう鑑別する?
著者: 池田知雅
ページ範囲:P.1093 - P.1096
Point
◎失神の鑑別には詳細な病歴聴取が重要である.
◎長期生命予後の観点から,心原性失神の可能性を念頭に診療に当たるべきである.
◎てんかんでなくても全身性けいれんを発症するけいれん性失神がある.
◎起立性低血圧では薬剤誘発性の頻度が高いため,必ず服薬歴を確認する.
見落とされがちなめまいの鑑別—持続性知覚性姿勢誘発めまい,片頭痛関連めまい,前庭性発作症,Barré-Lieou症候群などを中心に
著者: 井口正寛
ページ範囲:P.1097 - P.1100
Point
◎比較的稀なめまいとして,持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD),片頭痛関連めまい,前庭性発作症,Barré-Lieou症候群などがある.
◎PPPDは比較的新しい概念で,多くの場合,先行するめまいへの不適切な適応により生じると考えられる.
◎前庭性片頭痛は,前庭症状を伴う片頭痛であり,片頭痛の診断がきちんとなされなければならない.しばしば頭位性めまいであるため,良性発作性頭位めまい症と誤診しないように注意する.
◎前庭性発作症は,日に何度も繰り返す,短時間のめまい発作であり,カルバマゼピンが奏功する.
◎Barré-Lieou症候群は,後頭部を中心とした頭痛,頭部の回旋で生じるめまい,耳鳴,かすみ眼などの自覚症状を生じる後頚部交感神経症候群とされるが,疾患概念には議論がある.
めまいの画像診断
著者: 櫻井圭太
ページ範囲:P.1101 - P.1104
Point
◎CTは短時間での検査実施が可能であり,粗大な病変の確認などスクリーニングに適する.
◎ただし,CTの検出感度は高いとは言えず,脳幹梗塞など小さな病変の検出には適していない.
◎MRIは検査時間が長いものの,急性期の梗塞,脳動脈解離など種々の病態の検出に有用である.
◎CT,MRIそれぞれの長所と短所を理解し,臨床経過から推測される病態に応じた画像検査の選択を行う必要がある.
末梢性めまいの治療—急性期に効果的な治療薬,抗めまい薬はどう使い分ける?/慢性的なめまい症状に対する治療は?/「部位の診断がつかないめまい感」にどう対処する?
著者: 服部綾 , 服部学
ページ範囲:P.1106 - P.1110
Point
◎めまいの急性期には,対症療法を早めに開始することで,診察や鑑別診断も容易になる.
◎めまいの診察においては患者の不安を取り除くことが大切である.
◎良性発作性頭位めまい症(BPPV)の耳石置換法の有効性は高く,プライマリ・ケアの場でも役に立つ.
中枢性めまいの治療—脳血管障害によるめまいの急性期治療と慢性期治療/脳動脈狭窄症,脳動脈硬化症による慢性的なめまいはどう治療する?
著者: 小林麗
ページ範囲:P.1111 - P.1114
Point
◎めまいが症状の主体である脳血管障害では,多くの場合で病変部位は脳幹,小脳であり,責任血管は椎骨脳底動脈である.
◎椎骨脳底動脈領域の脳血管障害では,進行すると重篤な転帰に至る場合があり迅速な診断と治療開始が重要である.
◎椎骨脳底動脈循環不全はめまいの原因となる重要な病態の1つである.
◎慢性的なめまいを伴う脳血管障害では,高血圧,脂質異常の治療などの内科的管理が重要である.
しびれ,ふるえ,めまいなど多彩な神経症状を呈する疾患の診かた
脳血管障害のしびれ,ふるえ,めまい
著者: 田村拓也
ページ範囲:P.1116 - P.1120
Point
◎突然・急性発症のしびれ,ふるえ,めまいではまず脳血管障害を念頭に置く.
◎しびれ,ふるえ,めまい以外の随伴する神経症候(麻痺,運動失調,眼球運動障害など)を見逃さない.
◎しびれ,ふるえ,めまいのみを呈する急性期脳血管障害が存在することに注意する.
◎慢性期脳血管障害に伴うしびれ,ふるえ,めまいが存在し,それぞれの発生機序に応じた治療が必要である.
Parkinson病のしびれ,ふるえ,めまい—その出現メカニズムと対応法は?
著者: 池中建介
ページ範囲:P.1121 - P.1124
Point
◎Parkinson病(PD)のしびれにおいては,高用量レボドパによるビタミンB6低下に伴う末梢神経障害の有無を考える必要がある.
◎PDのふるえで最も重要なものは,じっとしていて動作をしていないときに起こる静止時振戦である.
◎PD患者が「ふらつく」と表現する際に,起立性低血圧が起こっていないかを調べる必要がある.
多発性硬化症と視神経脊髄炎スペクトラム障害のしびれ,ふるえ,めまい—その出現メカニズムと対応法は?
著者: 安井敬三 , 両角佐織 , 荒木周
ページ範囲:P.1125 - P.1130
Point
◎脱髄疾患は再発が特徴で,軽微な症状のときには受診しないこともあるので,きちんと病歴を聴取することが重要である.
◎急性または亜急性に出現した神経症状に合致する新規病巣を認めた場合は,専門医に紹介する.
◎無症候性病変が検診などで初めて指摘されることがあり,その場合も専門医に相談するとよい.
精神・心理的な要因に影響されたしびれ,ふるえ,めまい—心因性の問題と機能性神経障害の考え方
著者: 西原真理
ページ範囲:P.1132 - P.1136
Point
◎「心因性」という言葉はあまり治療的でないことが多く,なるべく使用しない.
◎機能性神経障害は幅広い概念であり,心理学的要因の修飾なども含めた脳機能の変化が基になっていると考える.
◎機能性神経障害は除外診断で考えるのではなく,基本的には陽性徴候から診断するべきである.
◎機能性神経障害は精神障害と併存することも多く,身体症状症や変換症との関係も検討すべきである.
◎脳神経内科医による診療そのものが治療的であり意義深く,また心理教育やリハビリテーションを含めた集学的治療が望まれる.
小児期,思春期のめまい—精神的要因? 器質的疾患?
著者: 宮原弘明
ページ範囲:P.1138 - P.1141
Point
◎小児ではめまいの訴えを正確に受け止め,評価できるかが重要である.
◎小児期,思春期のめまいの原因としては良性発作性めまい,片頭痛関連めまい,起立性調節障害が多い.
◎脳腫瘍や頭部外傷などの見逃すと重大な疾患が潜んでいる場合がある.
しびれ,ふるえ,めまいをきたす薬剤,薬物—器質的疾患との鑑別法と対処法は?
著者: 林祐一 , 西田承平 , 鈴木昭夫
ページ範囲:P.1142 - P.1146
Point
◎問診では,薬剤歴や経過の確認が必要である.
◎お薬手帳などの薬剤情報の入手が必要である.
◎薬剤以外の疾患との鑑別が重要である.
◎薬剤性であれば,薬剤の漸減中止と対症療法,代替薬への変更が重要である.
COVID-19感染によるしびれ,ふるえ,めまい
著者: 大野陽哉 , 下畑享良
ページ範囲:P.1147 - P.1151
Point
◎COVID-19による「しびれ」をきたす疾患として,small fiber neuropathy,Guillain-Barré症候群,脳梗塞などがある.
◎COVID-19による「ふるえ」には,自己免疫性や代謝性,機能性などの病態を背景とする振戦やミオクローヌスがある.
◎COVID-19の「めまい」には,前庭機能障害のほか,感染に伴う全身症状が関与している可能性がある.
Column
患者の訴える“しびれ”とは何か?
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1021 - P.1021
「しびれ(痺れ)」を訴えて脳神経内科を受診する患者は非常に多い.「しびれ」は日常語であるが,漠然とした曖昧な表現でもある.脳神経内科的には感覚障害や感覚異常を指すことが多いが,患者は必ずしもこれらを訴えているとは限らず,筋力低下を「しびれ」と訴えたり,痛みを「しびれ」と訴える例も多い.一過性脳虚血発作で一時的な脱力があると「手がしびれた」と訴えることが多く,Parkinson病による振戦や筋強剛を「しびれ」と訴える患者,小脳失調による巧緻運動障害を「しびれ」と訴える患者,関節リウマチによる手指のこわばりを「しびれ」と訴える患者もしばしば経験する.「しびれ」を訴える患者の診察ポイントは非常に多岐にわたるので,問診のコツ,神経学的所見の取り方,日常診療で頻度の高い鑑別疾患について理解していただきたい.
しびれの診察は問診が重要
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1028 - P.1028
患者の訴える「しびれ」の内容は多彩で捉えにくい場合が多く,診断には具体的な問診がきわめて重要である.問診で「しびれ」の内容を理解し,ある程度鑑別診断をつけなければ,いくら慎重に診察,検査をしても「しびれ」の多くは原因を特定することはできないと言っても過言ではなく,逆に神経学的所見をとる前に問診で大体の診断がつくことも多い.「しびれ」の問診で重要な点は,患者の訴える「しびれ」が感覚障害であるかどうかをまず確認し,その性状を具体的に把握することである.患者が訴える感覚障害の具体的な内容は「ビリビリする」「ジンジンする」,「チクチクする」,「ほてる」,「感覚が鈍い」などがあり,「触ると痛い」などの痛みの要素を伴うこともある.これらが混在していたり,問診では判別が難しかったりすることもあり,神経学的な用語を正確に使うことを意識するよりも,患者の訴えを理解し,具体的に記載するほうが有用である.
しびれイコール脳神経内科?
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1033 - P.1033
しびれがあるというだけで脳神経内科に紹介されてくる患者は多いが,実際には整形外科,血管外科,内分泌内科,婦人科,心療内科的な治療を要することも多く,脳神経内科的な専門治療を要する疾患であることはそれほど多くない.しびれの部位が神経支配に一致していない場合や,神経伝導速度検査や種々の画像検査を駆使しても異常が見つからない場合には,神経症や仮面うつ病,更年期障害,自律神経失調症なども疑わなければならず,最近はストレスや神経症の転換性障害による顔面や全身のしびれを訴える患者も多い.神経障害の有無を鑑別するのが脳神経内科医の仕事であるが,最初から適切な科へ紹介することが重要であることは言うまでもないので,まず鑑別診断をしっかり行っていただきたい.また,しびれを訴えたというだけで,ビタミンB12製剤やビタミンE製剤が漫然と長期投与されている患者をしばしば経験するが,まず適切な鑑別診断を行ってから投与することが重要である.
しびれの表現とカルテ記載
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1039 - P.1039
しびれを言葉で表現するのは患者にとっても非常に難しい.下肢のしびれを主訴に来院した患者に「どんな感じのしびれですか?」と問うと,「しびれるんです」と答えるので,「具体的にはどんな感じですか?」と再度問うと「しびれるんです」と答えるので,「ビリビリするのですか?」と問うても「しびれるんです」,と堂々巡りになってお互いにムッとしてしまったことがある.患者自身もうまく表現できず,とにかく感じがおかしいということを一生懸命訴えるのであるが,もう少し具体的に言ってくれるとこちらもわかりやすいと感じることも多い.「足の裏がもつもつする」,「指先がつんつんする」,「手のひらがうようよする」と訴えた患者もいた.カルテには,できるだけ近い表現を推定して補足しつつ,患者の訴えをある程度そのままの表現で記載するようにしている.
「しびれは歳のせいです」
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1044 - P.1044
「しびれ」の診断はしばしば難しく,原因不明としてしまう場合も実際には多い.特に高齢者においては「歳のせいですよ」と言ってうやむやになっている症例も多いと思われるが,筆者の脳神経内科外来でも,原因不明で「歳のせいですから心配ないですよ」と言ってしまうことが恥ずかしながらしばしばある.しびれの背景は脊柱管狭窄症,絞扼性神経障害,末梢循環障害,自律神経障害など多彩であろうが,高齢者であればいくつかの原因が複合している場合もあると思われる.高齢者では振動覚が軽度に低下していることは通常みられ,これはまさに「歳のせい」であると考えている.「検査しても特に異常はありませんので,心配のないしびれ,歳のせいだと思います」と説明すると,「歳のせいとはなんだ!」と怒る患者や,腑に落ちないで怪訝そうな表情をする患者もいる.「歳のせいですよ」とはどの診療科でも使われる便利な表現だと思われるが,頭部CT検査で年齢相応の脳萎縮が見られた場合に,「年齢相応の脳萎縮ですから心配ありません」と説明するのも同様であろう.
患者の訴える“ふるえ”とは何か?
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1057 - P.1057
「ふるえ」を訴えて脳神経内科を受診する患者は多いが,「振戦」であるとは限らず,一方で振戦を「けいれんする」と訴える患者も多い.振戦を「ピクピクする」,「ブルブルする」と訴えることもある.てんかん発作によるけいれんを患者や目撃者は「ふるえる」と表現することもあるので注意が必要である.振戦以外の不随意運動(ミオクローヌスやバリスムなど)を「ふるえる」と訴えることもある.患者が訴える「ふるえ」の内容が振戦を指すのか,それ以外の症候を指すのかをまず鑑別しなければならないが,そのためには問診と視診が重要である.
本態性振戦や老人性振戦のサポート
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1061 - P.1061
本態性振戦や老人性振戦は生命予後に影響することはないが,人前で手がふるえて字が書けない,酒が注げない,周囲の視線が気になる,など社会生活上の問題で悩んでいる症例は多い.治療は対症療法になることが多く,完全には抑制できない場合が多いが,患者にとってふるえが大変なストレスであり,人前に出るのを極端に嫌がる場合もある.精神的緊張や不安により増強するため,心療内科や精神科で投薬を受けている患者や,抗不安薬を持っているだけで安心して症状が改善するという患者もいる.アルコール摂取が有効であることを経験的に自覚し,アルコール中毒になってしまったという症例もあり,それぐらい患者にとってはふるえが苦痛である.投薬で効果がなくても心理的サポートを含めた継続的な対応が重要となる症例もあることを強調しておきたい.
ふるえとけいれん
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1067 - P.1067
振戦のことを「けいれん」と訴える患者が比較的多いが,患者が「けいれんする」と訴えると「てんかん」をまず鑑別疾患に挙げることが多いと思われる.「手がけいれんする」,「昨日けいれんした」と訴えられ,てんかんの疑いと先入観をもって問診していたら,すぐに振戦であることがわかったという経験はしばしばある.一方で,単純部分発作のてんかん患者で振戦様のけいれん発作が持続することがあるので,このような症例では問診だけでは生理的振戦と誤る可能性はある.非医療従事者のなかには本態性振戦や老人性振戦をてんかんと勘違いされる方もいるが,患者が「けいれんする」と訴えると「てんかんの疑い」と考えてすぐに脳神経内科に紹介してくる先生もいるので注意していただきたい.
患者の訴える“めまい”とは何か?
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1076 - P.1076
「めまい」という訴えはかなり曖昧な表現であり,一方でありふれた愁訴の1つである.「目が回る」,「目がくらむ」,「ふらふらする」など多彩な症状を患者は一様に「めまい」と訴える.「めまい」を訴えたというだけで脳神経内科に紹介されてくる患者が多いが,めまいの原因には耳鼻咽喉科疾患も多いことは言うまでもなく,脳外科疾患,精神疾患,眼科疾患,貧血,循環器疾患,自律神経失調症や更年期障害,栄養失調,脱水,薬剤性など多岐にわたり,すべての診療科に関連すると言っても過言ではない.めまいの原因は不明であることも多いが,生命にかかわる重大な病態が関連している可能性もあり,慎重な対応が必要である.めまいの検査には誘発眼振検査(頭位変換眼振検査)や聴力検査などの耳鼻咽喉科的検査,重心動揺検査などの平衡機能検査も重要であるが,詳細は成書に譲り,本特集では外来での簡単な鑑別のコツを中心に述べていただいた.
めまい患者の対応は難しい?
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1080 - P.1080
めまい患者を問診していると,非常に詳細に症状や経過を語る患者や,神経質な患者,めまいの内容がうまく説明できずにまわりくどく話す患者など多彩である.概して,めまいを訴える患者はその自覚するめまいが重篤で何とかしてほしい旨を切々と訴えたり,脳血管障害を非常に心配している傾向がある.「検査では異常ありませんから,心配ありません」と言っても納得しない患者は多いが,めまいは心理的な要因によっても改善したり悪化したりするので,患者の訴えにできる限り理解を示すことも重要であると思われる.
緊急を要するめまいの鑑別は重要
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1084 - P.1084
めまいを訴える患者の診察では,まず脳神経疾患が鑑別に挙がるであろうが,多くの病院でCTやMRIが常時撮影できるとは限らず,脳神経内科医や脳神経外科医が常駐している施設も多くはない.めまいの鑑別診断の誤りは,適切な検査法適用の遅れ,重篤な全身疾患の見逃し,CTやMRI撮影中の急変といった救急場面での事故にもつながる.医師であれば,科や専門性を問わず,病歴や身体所見によるめまいの鑑別診断に習熟する必要があることは言うまでもない.高額な検査機器がなくても,ハンマーさえあれば最低限の神経診療はできることを強調したい.
問診の重要性
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1092 - P.1092
「神経学的診察のスクリーニング法はない」とはよく言われる言葉だが,「的確な問診をすれば,神経学的診察の前に神経疾患の8割は診断がつく」とも言われる.問診ですべてがわかるわけではないが,ある程度疾患を絞り込むことができ,時にはほぼ診断をつけることが可能である.今回の特集で述べられた内容のなかには「当たり前のことじゃないか」と思われるものもあるだろうが,このありふれた知識が医師の診断能力向上,患者と家族の満足につながる.また,臨床の限られた時間のなかで,診療効率やリスクマネジメントなど患者の利益に直接結びつく観点からも,問診というありふれた推測材料は,しびれ,ふるえ,めまいの診察においても重要視すべきである.
くずかごの中の地雷
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1096 - P.1096
めまいの原因の多くは良性疾患であり,経過観察や対症療法で次第に改善するが,頻度は低いが見逃してはならない疾患が隠れている点に留意しなければならない.症状の程度と原因疾患の重症度は相関しないことが多く,末梢性めまいのほうが,脳血管障害などの生命に危険がある中枢性めまいより重篤感があることも多い.一方で,全身倦怠感や頭重感などの不定愁訴とともにめまいを訴えることや,更年期障害に伴ってめまいを訴えることも多いため,「めまいは放っておいてもいずれ治る」と言われたり,「めまいは病気のくずかご」とも言われたりする.しかしながら,めまいには「くずかごの中の地雷」と考えられる,見落とすと死に至る疾患がある.複視や構音障害,失調など脳幹・小脳症状を伴っていれば見落とすことはないであろうが,時に明らかな神経症候を伴わないで脳幹や小脳に病変を生じている症例がある.筆者の経験上,「突然に発症して頭痛を伴うめまい」は神経診療のなかで最も怖いことを強調しておきたい(脳幹梗塞,小脳出血,くも膜下出血が隠れている!).
小脳梗塞は要注意
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1105 - P.1105
めまいを訴える患者において,小脳梗塞が見逃されることは稀ではない.教科書的には病変と同側の失調を呈するが,失調が明らかでない症例も多い.小脳梗塞ではRomberg徴候が陰性であること,脳神経症状を認めないことも理解しておく必要がある.小脳出血であれば頭部CTで容易に診断可能であるが,梗塞病変は急性期にはCTでは異常を認めない.急性期に診断するためにはMRIが必要であるが,すべての施設でMRIを常に撮影できるわけではない.筆者も,「頭部CTで異常はなく,脳神経症状や失調を認めないので末梢性めまいだろう」と診断し,耳鼻咽喉科に紹介した症例が後日のCT再検やMRIで小脳梗塞が判明して冷や汗をかいた経験は恥ずかしながら何度もある.このような症例を経験すると,急性期のめまいの診断には,神経学的所見を認めなくてもMRIは必須であると感じる.
Wallenberg症候群を見逃すな!
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1120 - P.1120
めまいを訴える患者において,頻度は高くないが絶対に見逃してはならない疾患がWallenberg症候群である.延髄外側の梗塞によりめまいを生じ,錐体路は障害されないので運動麻痺は呈さない.診断にはMRIが必須であるが,特徴的な神経症候を理解していれば容易に診断可能である.筆者も救急外来や耳鼻咽喉科からのめまい患者のコンサルトで,「頭部CTで異常はなく,運動麻痺もないが念のため診察してほしい」と依頼され,神経学的診察のみで,「Wallenberg症候群だと思います.MRIで延髄外側梗塞があるはずです」と伝え,実際にMRI画像で病変を認めて,“どや顔”をした経験が何度もある.
患者観察はきわめて重要
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1124 - P.1124
しびれ,ふるえ,めまいの診察に限らず,脳神経内科医にとって,診察室に入ってくる患者の様子を観察することはきわめて重要であり,患者が診察室に入ってきて,向かい合って座り,問診を始めるまでの数秒〜数十秒の間に得られる情報は膨大な量である.患者が診察室に入ってくる貴重な瞬間に姿勢,歩容,表情,不随意運動,失調などを観察することが可能であり,時には診察室に入ってきた瞬間に診断がつくこともある.患者が診察室に入って来るとき,あるいは出て行くときにコンピュータ画面に向かって記録や処方を打ち込んでいて貴重な瞬間を見落とすことがあってはならない.また,どの診療科であっても当然のことであるが,患者が診察室に入ってくるときにアイコンタクトを含めて相手としっかり向き合うことは,その後の問診,診察を含めて医師-患者関係を築くうえできわめて重要な第一歩であることは言うまでもない.
しびれ,ふるえ,めまいの神経内科診察
著者: 岩崎靖
ページ範囲:P.1146 - P.1146
「しびれ,ふるえ,めまいを診る際に,短時間で正確な診断や病変部位の特定ができるようなコツはないですか?」という質問を他科の先生や研修医から受ける機会は多い.「そんな便利なコツはありません.神経疾患が疑われたら脳神経内科に紹介してください」と答えているが,もう少し問診,神経所見を取って,鑑別診断をしてから脳神経内科に紹介してほしいと感じることもある.しかしながら,神経疾患を否定することが脳神経内科医の重要な仕事であるから,問診票や紹介状をみただけで「神経疾患ではありません」と言って断ったり他科に回すことはせず,一度は診察をするようにしている.診察の結果,「神経学的所見に異常を認めません」「神経疾患は否定的です」と患者や紹介してきた先生に伝えることも脳神経内科医の重要な責務であると考えている.
連載 日常診療で役立つ 皮膚科治療薬の選びかた・使いかた・6
抗ヒスタミン薬② 薬剤の選びかたと副作用
著者: 松田光弘
ページ範囲:P.1001 - P.1005
Q問題
図11)の蕁麻疹に処方する薬剤はどれが良い?
a クロルフェニラミン(ポララミン®) b オロパタジン(アレロック®) c フェキソフェナジン(アレグラ®)
ケースでみる 心理学×医療コミュニケーション!・1【新連載】
認知行動療法をコミュニケーションに活かすうえで最も大切なこと
著者: 五十嵐友里
ページ範囲:P.1152 - P.1155
自己紹介とご挨拶
私は公認心理師・臨床心理士として大学病院神経精神科で臨床業務に従事し,さまざまな医療チームや多職種との協働のなかで,身体疾患患者さんやそのご家族への心理的ケアに取り組んでいます.多様な患者さん・ご家族に合ったより良い対応を,第一線に立って日々模索する医療者の皆様の姿に,本当に頭が下がる思いで過ごしてきました.心理学は,人の日々の営みを理解する枠組みを提供してくれます.そんな心理学の力を日々の医療コミュニケーションに生かす工夫を紹介していけたら嬉しいです.
明日から主治医! 外国人診療のススメ・15【最終回】
外国人診療とチーム医療
著者: 沢田貴志
ページ範囲:P.1156 - P.1159
CASE
総合診療科の研修医(大樹)と指導医(朋子)が外来で…
大樹)先ほど胃腸炎で受診した30代女性ですけど,紛争から逃れてきた少数民族の方だそうで,乳児の世話もしていてかなり大変そうです.
朋子)ひょっとして健康保険もないのかな?
大樹)はい,現在難民申請をしているようですが,ビザが3カ月しか出ていないので国民健康保険には入れないみたいです.
看護師)大変です! さっきの女性の連れている赤ちゃん,なんとなく気になってお母さんに声をかけていたのですが,待合室で泣いたら唇が紫色になっちゃいました.
朋子)ほんとだわ.それに,すごい心雑音.すぐに小児科の先生を呼んで.あと心エコーの手配を.
ここが知りたい! 欲張り神経病巣診断・36
頭が痛いな,脳出血? え,神経痛? 頭皮の神経痛/後頭部の表在神経の走行・大後頭神経痛の症状
著者: 難波雄亮
ページ範囲:P.1160 - P.1164
患者さんが「頭が痛い」と訴えたとき,原因として真っ先に脳卒中が鑑別に挙がると思います.ただし,頭蓋内疾患以外にも問診と診察をしっかりしないと区別がつかない頭痛があります.本連載の第33回(本誌61巻3号掲載)で取り上げた三叉神経痛もその1つです.今回は,それ以外にも後頭部周辺の痛みをきたす疾患について勉強していきましょう!
知らないとヤバい! リウマチ・膠原病のアレやコレ・9
ちょっと待った! それって本当にヘバーデン結節ですか?—見逃すとヤバい関節炎との鑑別
著者: 猪飼浩樹
ページ範囲:P.1165 - P.1172
本連載では,リウマチ・膠原病診療における緊急病態,知っておかないと重篤な状態となりうる事象について取り扱う.リウマチ・膠原病診療は専門性が高い面もあるが,専門医に必ずしも受診していない患者も多い.その背景には,専門医が少ない地域性の問題や,高齢などの理由で専門医への通院が困難であるなどの多くの要因がある.
これまで本連載では,関節リウマチ(RA)治療中のヤバい病態としてさまざまなもの(血球減少,間質性肺炎,頸椎病変,単関節炎など),および前回は緊急性のある疾患として抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎を取り扱ってきた.ぜひ今までの回もご覧いただきたい.
目でみるトレーニング
書評
—塩尻 俊明 監修/杉田 陽一郎 執筆—病態生理と神経解剖からアプローチする—レジデントのための神経診療 フリーアクセス
著者: 江原淳
ページ範囲:P.1131 - P.1131
神経診療は難しく,苦手意識のある医師は多い.
なぜ難しく苦手と感じるのか.1つに,神経領域の幅広さがあると思う.解剖学的にも,脳,脊髄,末梢神経,神経筋接合部,筋などと多彩であり,病態的にも血管障害,感染症,自己免疫,変性など幅が広く,その組み合わせで膨大な疾患が存在する.誰しもその疾患数や領域の広さに圧倒され,特に神経内科を専門領域とする者以外にとってこれをすべて勉強しきることは無理だ,専門科に任せようという気持ちになるのもわからなくはない.
—福武 敏夫 著—神経症状の診かた・考えかた 第3版—General Neurologyのすすめ フリーアクセス
著者: 宮岡等
ページ範囲:P.1137 - P.1137
評者は精神科医である.精神科医になって3,4年目のころ,今から約40年も前になるが,身体疾患に起因する意識障害であるせん妄,認知症,統合失調症治療薬による錐体外路症状,心理面の原因で身体症状を呈する転換性障害などに出合って,精神科医もある程度の神経内科(現在の脳神経内科)の知識が不可欠であると考えた.当時の私のバイブルは故・本多虔夫先生が単独執筆された『神経病へのアプローチ』(医学書院)であった.所属教室の主任教授に頼み,週1回程度であったが,しばらくの間,本多先生の下で研修を受け,臨床家はこうあるべきという姿勢も学んだ.
それ以後,自分が精神科教員の立場となり,わかりやすいテキストを探しているなか,みつけたのが本書である.著者は初版の序で「遺伝学や生化学などのいわゆる高度医療の側面には触れていない.それらを高速道路建設に例えると,本書は街中(まちなか)の交通渋滞に対処するものである」,第3版の序では「『街中の交通渋滞対処』が『高速道路建設』に役立つ」,「予断や理屈に捉われないで,患者の症状を観察し,自ら一歩深く考えることが今なお臨床医に求められていると思う」と強調しており,評者が教えられてきた医療観を再確認させられた.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1006 - P.1009
読者アンケート
ページ範囲:P.1179 - P.1179
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1180 - P.1181
購読申し込み書 フリーアクセス
ページ範囲:P.1182 - P.1182
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1183 - P.1183
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.1184 - P.1184
基本情報
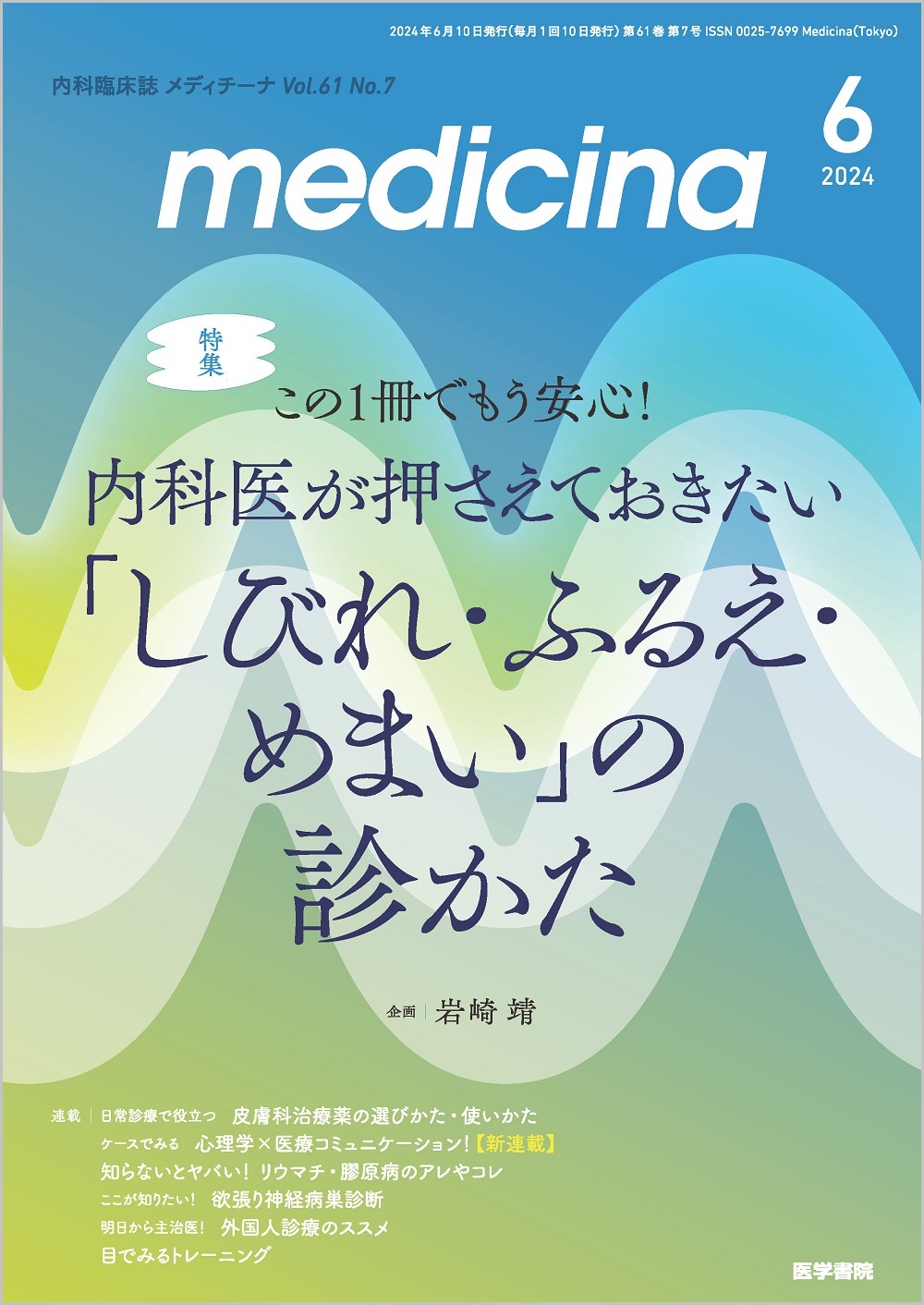
バックナンバー
61巻13号(2024年12月発行)
特集 喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date
61巻12号(2024年11月発行)
特集 消化器症候への実践的アプローチ
61巻11号(2024年10月発行)
増大号特集 続・Quality Indicatorの実装とその改善—日々の診療に役立つ診療評価指標
61巻10号(2024年9月発行)
特集 内科医が知っておくべきICU・ERでの薬の使い方
61巻9号(2024年8月発行)
特集 リウマチ膠原病疾患Up To Date!—押さえておきたい最新の診断と治療
61巻8号(2024年7月発行)
特集 “とりあえずスタチン”から脱却!—動脈硬化性疾患一次予防・最新の考え方
61巻7号(2024年6月発行)
特集 この1冊でもう安心!—内科医が押さえておきたい「しびれ・ふるえ・めまい」の診かた
61巻6号(2024年5月発行)
特集 睡眠にまつわる疑問にすべて答えます!—あなたの患者の睡眠中に何かが起きているかもしれない
61巻5号(2024年4月発行)
特集 腎機能を考慮した内科疾患の診療
61巻4号(2024年4月発行)
増刊号 内科医のための臨床問題集
61巻3号(2024年3月発行)
特集 どこでもみれる?—コモンディジーズとしての感染症アップデート
61巻2号(2024年2月発行)
特集 今どきの手技を見直し,医療処置でのトラブルを防ぐ—経験値ごとの気をつけるべき合併症や工夫
61巻1号(2024年1月発行)
特集 その知見は臨床を変える?—エキスパートが解説! 内科における最新論文
60巻13号(2023年12月発行)
特集 一般医家のための—DOAC時代の心房細動診療
60巻12号(2023年11月発行)
特集 内科医が遭遇する皮膚疾患フロントライン—「皮疹」は現場で起きている!
60巻11号(2023年10月発行)
増大号特集 患者さんの質問にどう答えますか?—言葉の意味を読み解きハートに響く返答集
60巻10号(2023年9月発行)
特集 ミミッカー症例からいかに学ぶか
60巻9号(2023年8月発行)
特集 症例から読み解く—高齢者診療ステップアップ
60巻8号(2023年7月発行)
特集 浮腫と脱水—Q&Aで学ぶジェネラリストのための体液量異常診療
60巻7号(2023年6月発行)
特集 整形外科プライマリ・ケア—内科医が知りたい整形外科疾患のすべて
60巻6号(2023年5月発行)
特集 Common diseaseの処方箋ファイル—臨床経過から学ぶ20症例
60巻5号(2023年4月発行)
特集 臨床医からみたPOCT
60巻4号(2023年4月発行)
増刊号 探求!マイナーエマージェンシー
60巻3号(2023年3月発行)
特集 令和の脳卒中ディベート10番勝負—脳卒中治療ガイドライン2021とその先を識る
60巻2号(2023年2月発行)
特集 慢性疾患診療のお悩みポイントまとめました—高血圧からヘルスメンテナンスまで
60巻1号(2023年1月発行)
特集 10年前の常識は非常識!?—イマドキ消化器診療にアップデート
59巻13号(2022年12月発行)
特集 令和の頭痛診療—プライマリ・ケア医のためのガイド
59巻12号(2022年11月発行)
特集 避けて通れない心不全診療—総合内科力・循環器力を鍛えよう!
59巻11号(2022年10月発行)
増大号特集 これからもスタンダード!—Quality Indicatorの診療への実装—生活習慣病を中心に
59巻10号(2022年9月発行)
特集 ちょっと待って,その痛み大丈夫?—“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ
59巻9号(2022年8月発行)
特集 不安を自信に変える心電図トレーニング—専門医のtipsを詰め込んだ50問
59巻8号(2022年7月発行)
特集 日常診療に潜む臨床検査のピットフォールを回避せよ
59巻7号(2022年6月発行)
特集 抗菌薬の使い方—敵はコロナだけにあらず! 今こそ基本に立ち返る
59巻6号(2022年5月発行)
特集 ジェネラリストの羅針盤—医学部では教わらなかった28のクエスチョン
59巻5号(2022年4月発行)
特集 症例から学ぶ—電解質と体液量管理のベストアンサー
59巻4号(2022年4月発行)
増刊号 フィジカル大全
59巻3号(2022年3月発行)
特集 成人が必要とするワクチン—生涯を通した予防接種の重要性
59巻2号(2022年2月発行)
特集 意外と知らない? 外用薬・自己注射薬—外来診療での適“剤”適所
59巻1号(2022年1月発行)
特集 クリニカルクエスチョンで学ぶ糖尿病治療薬—糖尿病治療の新しい潮流
58巻13号(2021年12月発行)
特集 血液疾患をプライマリ・ケアではどこまで診て,どのように専門医と連携をとるべきか?
58巻12号(2021年11月発行)
特集 外来で役立つAha!クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?
58巻11号(2021年10月発行)
特集 鑑別診断を意識した—非専門医のための胸部画像診断
58巻10号(2021年9月発行)
特集 腎疾患—エキスパートへの質問で学ぶ診療のキホンと最新情報
58巻9号(2021年8月発行)
特集 日常診療で内分泌疾患を見逃さない!
58巻8号(2021年7月発行)
特集 ジェネラリスト・漢方—とっておきの漢方活用術
58巻7号(2021年6月発行)
特集 “のど・はな・みみ”の内科学
58巻6号(2021年5月発行)
特集 デジタル内科学の勃興—オンライン診療,AI,治療用アプリ
58巻5号(2021年4月発行)
特集 その考えはもう古い!—最新・感染症診療
58巻4号(2021年4月発行)
増刊号 救急診療 好手と悪手
58巻3号(2021年3月発行)
特集 いまさら聞けない! 肝胆膵疾患—みなさんのギモンに答えます
58巻2号(2021年2月発行)
特集 外来で出会うアレルギー疾患—Total Allergist入門
58巻1号(2021年1月発行)
特集 エキスパートに学ぶ—最新の循環器治療薬の使い方
57巻13号(2020年12月発行)
特集 プライマリ・ケアにおける神経症候へのアプローチ
57巻12号(2020年11月発行)
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
57巻11号(2020年10月発行)
特集 皮疹はこう見る,こう表現する
57巻10号(2020年9月発行)
特集 循環器診療2020—どこまで攻めて,どこから引くか?
57巻9号(2020年8月発行)
特集 患者満足度の高い便秘診療
57巻8号(2020年7月発行)
特集 真夏の診察室
57巻7号(2020年6月発行)
特集 運動・スポーツ×内科—内科医に求められるスポーツ医学とは
57巻6号(2020年5月発行)
特集 教えて! 健診/検診“ホントのところ”—エビデンスを知り,何を伝えるか
57巻5号(2020年4月発行)
特集 デキル内科医のコンサルト—専門医が教える隠れたエッセンス
57巻4号(2020年4月発行)
増刊号 早わかり診療ガイドライン100—エッセンス&リアルワールド
57巻3号(2020年3月発行)
特集 症状・治療歴から考える—薬の副作用の診断プロセス問題集60題
57巻2号(2020年2月発行)
特集 臨床に役立つ解剖・生理学
57巻1号(2020年1月発行)
特集 今の流れに乗り遅れない!—プライマリ・ケアでの呼吸器疾患の診かた・薬の使いかた
56巻13号(2019年12月発行)
特集 プライマリ・ケアのための—ポリファーマシー「超」整理法
56巻12号(2019年11月発行)
特集 内科医が押さえておくべき—検査の考えかたと落とし穴
56巻11号(2019年10月発行)
特集 不明熱を不明にしないために—実践から考えるケーススタディ
56巻10号(2019年9月発行)
特集 脱・「とりあえずCT」!—スマートな腹痛診療
56巻9号(2019年8月発行)
特集 みんなが知っておきたい透析診療—透析のキホンと患者の診かた
56巻8号(2019年7月発行)
特集 一歩踏み込んだ—内科エマージェンシーのトリセツ
56巻7号(2019年6月発行)
特集 抗菌薬をアップデートせよ!—耐性菌に立ち向かう! 適正化の手法から新薬の使い分けまで
56巻6号(2019年5月発行)
特集 糖尿病診療の“Q”—現場の疑問に答えます
56巻5号(2019年4月発行)
特集 しまった!日常診療のリアルから学ぶ—エラー症例問題集
56巻4号(2019年4月発行)
増刊号 一人でも慌てない!—「こんなときどうする?」の処方箋85
56巻3号(2019年3月発行)
特集 TPOで読み解く心電図
56巻2号(2019年2月発行)
特集 抗血栓療法のジレンマ—予防すべきは血栓か,出血か?
56巻1号(2019年1月発行)
特集 枠組みとケースから考える—消化器薬の選び方・使い方
55巻13号(2018年12月発行)
特集 これからの心不全診療への最新アプローチ—予防からチーム医療・先進医療まで
55巻12号(2018年11月発行)
特集 内科医のための「ちょいあて」エコー—POCUSのススメ
55巻11号(2018年10月発行)
特集 どんとこい! 内科医が支える—エンド・オブ・ライフ
55巻10号(2018年9月発行)
特集 クリティカル・ケアを極める—一歩進んだ総合内科医を目指して
55巻9号(2018年8月発行)
特集 もっともっとフィジカル!—黒帯級の技とパール
55巻8号(2018年7月発行)
特集 血液疾患を見逃さないために—プライマリ・ケアと専門医コンサルトのタイミング
55巻7号(2018年6月発行)
特集 ここさえ分かれば—輸液・水・電解質
55巻6号(2018年5月発行)
特集 プロブレムから学ぶ感染症診療—すぐに役立つ厳選シナリオ30選
55巻5号(2018年4月発行)
特集 明日のために解くべし!—総合内科問題集
55巻4号(2018年4月発行)
増刊号 プライマリ・ケアでおさえておきたい—重要薬・頻用薬
55巻3号(2018年3月発行)
特集 —クリニカル・クエスチョンで学ぶ—循環器薬の使い方
55巻2号(2018年2月発行)
特集 —デキる内科医の—神経内科コンサルト
55巻1号(2018年1月発行)
特集 気管支喘息・COPD診療に強くなる
54巻13号(2017年12月発行)
特集 骨関節内科
54巻12号(2017年11月発行)
特集 救急外来で役立つ!—意識障害の診かた—“あたま”と“からだ”で考える
54巻11号(2017年10月発行)
特集 自信をもって対応する—虚血性心疾患
54巻10号(2017年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール3
54巻9号(2017年8月発行)
特集 皮膚疾患が治らない!—皮膚科医が教える“次の一手”
54巻8号(2017年7月発行)
特集 がん診療—内科医が知りたい30のエッセンス
54巻7号(2017年6月発行)
特集 外来診療必読エビデンス—日米比較で考える内科Standards of Excellence
54巻6号(2017年5月発行)
特集 プライマリ・ケア医のための消化器症候学
54巻5号(2017年4月発行)
特集 —症候別 すぐ役に立つ—救急画像診断—いつ撮る? どう見る?
54巻4号(2017年4月発行)
増刊号 総合内科医の必修臨床問題182問
54巻3号(2017年3月発行)
特集 トリコになる不整脈—診断と治療のすべて!
54巻2号(2017年2月発行)
特集 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
54巻1号(2017年1月発行)
特集 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
53巻13号(2016年12月発行)
特集 内分泌疾患を診きわめる
53巻12号(2016年11月発行)
特集 どうする? メンタルな問題—精神症状に対して内科医ができること
53巻11号(2016年10月発行)
特集 主治医として診る高血圧診療
53巻10号(2016年9月発行)
特集 超高齢時代の内科診療
53巻9号(2016年8月発行)
特集 誰も教えてくれなかった—慢性便秘の診かた
53巻8号(2016年7月発行)
特集 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
53巻7号(2016年6月発行)
特集 抗菌薬の考え方,使い方—ホントのところを聞いてみました
53巻6号(2016年5月発行)
特集 内科救急サバイバルブック—院内救急&地域でのマネジメント
53巻5号(2016年4月発行)
特集 心電図を詠む—心に残る24症例から
53巻4号(2016年4月発行)
増刊号 内科診断の道しるべ—その症候、どう診る どう考える
53巻3号(2016年3月発行)
特集 内科医がになう骨粗鬆症—診療と生活指導の最新情報
53巻2号(2016年2月発行)
特集 脳卒中はこう診る—新ガイドラインで何が変わったか
53巻1号(2016年1月発行)
特集 糖尿病治療薬Update—適正使用に向けて
52巻13号(2015年12月発行)
特集 抗血栓療法—おさえておきたい最新のエッセンス
52巻12号(2015年11月発行)
特集 外来で診るリンパ腫・骨髄腫—治癒または長期共存を目指して
52巻11号(2015年10月発行)
特集 いまアレルギー外来がおもしろい—安全で効果の高い治療を使いこなす
52巻10号(2015年9月発行)
特集 内科プライマリケアのための消化器診療Update
52巻9号(2015年8月発行)
特集 外来で出会う呼吸器common疾患
52巻8号(2015年7月発行)
特集 自信がもてる頭痛診療
52巻7号(2015年6月発行)
特集 心不全クロニクル—患者の人生に寄り添いながら診る
52巻6号(2015年5月発行)
特集 感染症診療 それ,ホント?
52巻5号(2015年4月発行)
特集 救急疾患,重症はこうして見極める—いつまでもヤブと思うなよ!
52巻4号(2015年4月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第9集
52巻3号(2015年3月発行)
特集 がんを診る
52巻2号(2015年2月発行)
特集 ウイルス肝炎の薬物治療—変わりゆく治療戦略
52巻1号(2015年1月発行)
特集 循環器薬up to date 2015
51巻13号(2014年12月発行)
特集 最新情報をおさえる!—臨床栄養の活用ガイド
51巻12号(2014年11月発行)
特集 関節リウマチ・膠原病—症例で学ぶ診断と治療
51巻11号(2014年11月発行)
増刊号 CT・MRI—“戦略的”活用ガイド
51巻10号(2014年10月発行)
特集 すぐ役に立つ—呼吸器薬の標準的使い方
51巻9号(2014年9月発行)
特集 ここが知りたい循環器診療―パールとピットフォール
51巻8号(2014年8月発行)
特集 糖尿病患者を診る―治療と兼科のポイント
51巻7号(2014年7月発行)
特集 神経診察―そのポイントと次の一手
51巻6号(2014年6月発行)
特集 炎症性腸疾患攻略の手引き―これだけは知っておきたい!
51巻5号(2014年5月発行)
特集 内科医のための皮疹の診かたのロジック
51巻4号(2014年4月発行)
特集 虚血性心疾患up to date―内科医によるトータルマネジメント
51巻3号(2014年3月発行)
特集 もう見逃さない!迷わない!―非血液専門医のための血液診療
51巻2号(2014年2月発行)
特集 診て考えて実践する―水・電解質管理と輸液
51巻1号(2014年1月発行)
特集 消化器薬―新時代の治療指針
50巻13号(2013年12月発行)
特集 不整脈の診断と治療―ポイントをおさえよう
50巻12号(2013年11月発行)
特集 新時代の肺炎診療
50巻11号(2013年11月発行)
特集 内科診療にガイドラインを生かす
50巻10号(2013年10月発行)
特集 内分泌疾患に強くなる
50巻9号(2013年9月発行)
特集 内科医のためのクリニカル・パール2
50巻8号(2013年8月発行)
特集 今日から役立つ高血圧診療のノウハウ
50巻7号(2013年7月発行)
特集 “実践的”抗菌薬の使い方―その本質を理解する
50巻6号(2013年6月発行)
特集 最新の動脈硬化診療―どう診断し,どう治療するか?
50巻5号(2013年5月発行)
特集 胃食道逆流症(GERD)―“胸やけ”を診療する
50巻4号(2013年4月発行)
特集 エマージェンシーの予兆を察知する―リスクを評価し危機に備える
50巻3号(2013年3月発行)
特集 免疫反応と疾患
50巻2号(2013年2月発行)
特集 大きく変貌した脳梗塞の診断と治療
50巻1号(2013年1月発行)
特集 進化し続ける内科診療―世界が認めたブレイクスルー
49巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 急性心不全への挑戦
49巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 連携して診る腎疾患―タイムリーな紹介から患者マネジメントまで
49巻11号(2012年11月発行)
特集 いま,内科薬はこう使う
49巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識
49巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 内科診断の本道―病歴と身体診察情報からどこまでわかるか?
49巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 痛風・高尿酸血症診療の新展開
49巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 肝硬変update―より良き診療のために
49巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 新規経口抗凝固薬の光と影
49巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 糖尿病治療薬2012―皆が知りたい新しい治療A to Z
49巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 神経内科エマージェンシー―日常臨床でどこまで対応できるか
49巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 内科医のための気管支喘息とCOPD診療
49巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 下痢と便秘―今日的アプローチ
49巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 外してならない循環器薬の使い方 2012
48巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 “がん診療”を内科医が担う時代
48巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 内科診療に役立つメンズヘルス
48巻11号(2011年11月発行)
特集 内科 疾患インストラクションガイド―何をどう説明するか
48巻10号(2011年10月発行)
今月の主題 一般内科医がみる血液疾患―血液専門医との効率的な連携のために
48巻9号(2011年9月発行)
今月の主題 視ないで診る消化器疾患―考える内科医のアプローチ
48巻8号(2011年8月発行)
今月の主題 神経疾患common diseaseの診かた―内科医のためのminimum requirement
48巻7号(2011年7月発行)
今月の主題 内科疾患の予防戦略
48巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 睡眠呼吸障害の克服―内科医が知っておきたい病態・症状・関連疾患
48巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 脂質異常症―動脈硬化症を予防するためのStrategy
48巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 緊急画像トラブルシューティング―内科医のためのPearlとPitfall
48巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 臨床栄養Update 2011
48巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 関節リウマチを疑ったら―診断・治療のUpdateと鑑別すべき膠原病
48巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 皮膚から内科疾患を疑う
47巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 これ血液悪性疾患?自分の守備範囲?―非専門医のための見分け方
47巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 糖尿病診療Update―いま何が変わりつつあるのか
47巻11号(2010年10月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第8集
47巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori―関連疾患と除菌療法のインパクト
47巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 虚血性心疾患―プライマリケアは内科医が担う
47巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 呼吸不全の診療
47巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 高血圧診療―わかっていること・わからないこと
47巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 酸塩基・電解質―日常で出くわす異常の診かた
47巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 ワンランク上の内科エマージェンシー―もうだまされない! 非典型例から最新知識まで
47巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 抗菌薬の使い方を究める
47巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎―日常診療のポイント
47巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患を疑ったら,こう診る!
47巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 ズバリ! 見えてくる不整脈
46巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 腎臓病診療のエッセンス
46巻12号(2009年11月発行)
特集 CT・MRIアトラス Update―正常解剖と読影のポイント
46巻11号(2009年11月発行)
今月の主題 脳卒中の征圧をめざして
46巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 一般内科診療における呼吸器薬の使い方
46巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 内科医のためのクリニカル・パール―診療のキーポイントと心にのこる症例
46巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 ガイドラインを基盤とした心不全の個別診療
46巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 一般内科診療に役立つ消化器内視鏡ガイド―コンサルテーションのポイントから最新知識まで
46巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 内分泌疾患を診るこつ
46巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 肺血栓塞栓症 見逃さず迅速かつ的確な対応を
46巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 苦手感染症の克服
46巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 膵炎のマネジメント―急性膵炎・慢性膵炎・自己免疫性膵炎
46巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 訴え・症状から考える神経所見のとり方
46巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2009
45巻13号(2008年12月発行)
特集 目でみる診療基本手技
45巻12号(2008年12月発行)
今月の主題 末梢血検査異常 何を考え,どう対応するか
45巻11号(2008年11月発行)
今月の主題 浮腫をどう診るか
45巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 内科の基本 肺炎をきわめる
45巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 Multiple problemsの治療戦略
45巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 内科医のためのがん診療Update
45巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 主治医として診る後期高齢者
45巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 実践! 糖尿病診療
45巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と機能性腸疾患─病態の理解と求められる対応
45巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 一般内科医が診る循環器疾患―3大病態を把握する
45巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 内科医が診る骨粗鬆症
45巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 しびれと痛み 患者の“何か変な感じ”をどう受け止め,応じていくか
45巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 プライマリケア医が主役―膠原病・関節リウマチの早期診断・早期治療
44巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 内科外来でみるウィメンズ・ヘルス
44巻12号(2007年11月発行)
特集 一般医のためのエコー活用法
44巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ
44巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 最新ガイドラインに基づく喘息とCOPDの診療
44巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方Update
44巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 動脈硬化のトータルマネジメント
44巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 内科医が診る睡眠障害
44巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 認知症のプライマリケア
44巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎 実地診療A to Z
44巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー2007 鬼門を克服する
44巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 日常診療・当直のための酸塩基平衡,水・電解質,輸液
44巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 症例からみる肺疾患のCT画像
44巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 高血圧の臨床―焦点の合った個別診療へ向けて
43巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 理解しよう! 下痢と便秘
43巻12号(2006年11月発行)
特集 Common Disease インストラクションマニュアル―患者に何をどう説明するか
43巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 頭痛治療の疑問を解決する
43巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 皮膚から見つける内科疾患
43巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2006
43巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 消化器内視鏡治療の現在
43巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 血液腫瘍はどこまで治し得るのか
43巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 ベッドサイドの免疫学-免疫疾患に強くなるために
43巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養―プランニングとその実践
43巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 抗菌薬を使いこなそう!―実地臨床での正しい選択と投与法
43巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腎・尿路疾患―一般診療から専門診療へ
43巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 ブレインアタック2006―t-PA時代の診断と治療
43巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 糖尿病の臨床―基礎知識を実践に生かす
42巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 急性冠症候群へのアプローチ
42巻12号(2005年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第7集
42巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 内科医が知っておくべき がん治療
42巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい呼吸器薬の使い方
42巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 アルコールと内科疾患
42巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 胆膵疾患はこう診る―緊急処置からフォローアップまで
42巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 臨床で出遭う内分泌疾患
42巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 内科emergency―爆弾を踏まない!
42巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 内科医が診る関節リウマチ
42巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 これだけは知っておきたい不整脈の診かたと治療のポイント
42巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 Digital時代の脳神経画像診断
42巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 肥満症―診断・治療の新展開
42巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 日常診療で診るGERD(胃食道逆流症)
41巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 ミネラルと骨代謝異常と骨粗鬆症
41巻12号(2004年11月発行)
特集 臨床医必携 単純X線写真の読み方・使い方
41巻11号(2004年11月発行)
今月の主題 慢性心不全を最近の知見から整理する―病態生理から治療まで
41巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 肝疾患の疑問に答える―研修医と内科医のために
41巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 内科レッド・フラッグサイン―よくある症候から危険を見抜く
41巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 内科医が診るしびれと痛み
41巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 臨床医のための呼吸調節と障害
41巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 血栓症の予防と治療
41巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 臨床行動に結びつく検査戦略
41巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 内科コモンプロブレム
41巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 アレルギー診療Update
41巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 腹部疾患をエコーで診る
41巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 高血圧診療のエビデンスと個別的治療―主治医の役割とジレンマ
40巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 肺炎
40巻12号(2003年11月発行)
特集 臨床研修コアスキル
40巻11号(2003年11月発行)
今月の主題 水・電解質と輸液
40巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 前期高齢者・後期高齢者を診る
40巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 消化器疾患のエビデンスとエキスパート・オピニオン
40巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2003
40巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 ブレイン アタック―超急性期から維持期まで
40巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚科的スキル
40巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 一般医も診る血液疾患
40巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 緊急時に画像診断を使いこなす
40巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 糖尿病にどう対処するか
40巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 臓器感染と抗菌薬のえらび方
40巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 内科医と虚血性心疾患
39巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 内科臨床における“こころ”と“からだ”
39巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 画像でせまる呼吸器疾患
39巻11号(2002年10月発行)
増刊号 内科医が使う薬の副作用・相互作用
39巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 一般医も診なければならないB型・C型肝炎
39巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な血管疾患診療の知識
39巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント
39巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 わかりやすい不整脈診療
39巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 頭痛とめまい—外来診療ガイド
39巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 腸疾患診療のノウハウ
39巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 動脈硬化と高脂血症
39巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 わかりやすいゲノム・再生医療の基礎・現状・展望
39巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 臨床栄養Update
39巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方 2002
38巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 内科医のためのレディース・クリニックII
38巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 腎・尿路系疾患を診る
38巻11号(2001年10月発行)
増刊号 CT・MRIアトラス—正常解剖と読影のポイント
38巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 新しい概念に基づいた慢性心不全診療
38巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 内科医ができる癌患者への対応
38巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 Cognitive Disorder—内科医が知っておくべき認知機能障害
38巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 内科医が知っておきたい外科的治療のUpdate
38巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 臨床に活かす免疫学
38巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 動きながら考える内科エマージェンシー
38巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 Geriatrics—高齢者のQOLをみる医療
38巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 内科医が診るリウマチ
38巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Hematological malignancy—診断と治療の現状と展望
38巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 抗菌薬マネジメント—細菌感染症治療の基礎と実践
37巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 糖尿病と合併症へのアプローチ
37巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方 2001
37巻11号(2000年10月発行)
増刊号 臨床医のための最新エコー法
37巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 肺炎—市中感染と院内感染
37巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 「考える」診断学—病歴と診察のEBM
37巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 2000
37巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 ブレインアタック Brain attack
37巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 症例から学ぶ水電解質・酸塩基平衡異常
37巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 血栓症と抗血栓薬
37巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 内科医のための皮膚所見の診かた
37巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 高血圧の診療—新しい話題
37巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 アレルギー診療の実際
37巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 急性冠症候群
36巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 Evidenceに基づいた内科疾患の予防
36巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 内科医のためのCT
36巻11号(1999年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第6集
36巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 見逃しやすい内分泌疾患
36巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 下痢と便秘
36巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 ニューロパチーとミオパチー
36巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 不整脈患者のマネジメント
36巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 慢性呼吸不全に必要な基礎知識
36巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 高齢者医療—現状と展望
36巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 検査異常から考える血液疾患
36巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
36巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 肝疾患診療 1999
36巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 抗菌薬の適切な使い方
35巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 内科evidenceは果たしてあるのか
35巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 糖尿病の患者を受け持ったら
35巻11号(1998年10月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
35巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 膠原病・リウマチ性疾患
35巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 腹部エコーToday
35巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 循環器疾患の低侵襲治療
35巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 腎・尿路系の問題とマネジメント
35巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 カルシウム・骨代謝異常症と骨粗鬆症
35巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 内科医がよく遭遇する血管疾患
35巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 狭心症—日常臨床へのExpertise
35巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な癌のマネジメント
35巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 経静脈・経腸栄養療法のストラテジー
35巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 自己免疫性肝疾患のNew Wave
34巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 脳卒中プラクティス
34巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 臨床医のための遺伝子工学
34巻11号(1997年10月発行)
増刊号 内科医のMRIとのつきあいかた
34巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 肺炎と肺臓炎
34巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 外来診療でここまでできる
34巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1997
34巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 頭痛とめまいの外来診療
34巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 白血病—日常の診療に必要な知識
34巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 日常臨床にみる水・電解質と酸塩基平衡
34巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 高血圧の治療—新しい時代を迎えて
34巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 消化器疾患の低侵襲治療手技
34巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の最近の考え方と治療
34巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 臓器感染症へのアプローチ
33巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 内分泌疾患の検査
33巻12号(1996年11月発行)
増刊号 Common Drugs 350の投与戦略
33巻11号(1996年11月発行)
今月の主題 心エコーToday
33巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 内科医のための痴呆の最新知識
33巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 レディースクリニック
33巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患治療のジャイアント・ステップス
33巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 血栓症とDIC
33巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 内科医のためのInterventional Radiology
33巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心不全を見直す
33巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 皮膚科から内科医へのアドバイス
33巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 肝疾患Q&A
33巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 糖尿病臨床の最先端
33巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 抗生物質をどう使うか
32巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチとリウマチ周辺疾患
32巻12号(1995年11月発行)
増刊号 Common Disease 200の治療戦略
32巻11号(1995年11月発行)
今月の主題 脳卒中
32巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 見えてきた腎疾患
32巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 呼吸器疾患の画像診断
32巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 急性心筋梗塞Q&A
32巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 高齢者医療の新しい視点
32巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 内科臨床における心身医療
32巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 不整脈診療のための心電図の見方
32巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 脂質代謝と動脈硬化
32巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 免疫学の理解とその臨床
32巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 小児疾患とキャリーオーバー診療
32巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の画像診断
31巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 狭心症—診断と治療の進歩
31巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 呼吸器薬の使い方
31巻11号(1994年10月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第5集
31巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
31巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 水電解質・酸塩基平衡の調節とその異常
31巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 神経疾患の画像診断
31巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 1994
31巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 臨床医のための栄養ガイダンス
31巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 外科から内科へのメッセージ
31巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 First-line検査
31巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 臨床医のための血液疾患の理解
31巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 内分泌疾患診療と研究の最前線
31巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 消化器疾患の治療法—1994年の再評価
30巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
30巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 閉塞性肺疾患の診断と治療
30巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 膠原病—診断へのアプローチと最新の治療法
30巻10号(1993年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたいX線写真読影のポイント
30巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 消化性潰瘍治療の新展開
30巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 糖尿病 1993
30巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方 1993
30巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 心不全診療の新たな展開
30巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 症例にみる血液浄化療法の進歩
30巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 白血病—研究と診療の最新情報
30巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎ABC
30巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内科疾患患者の生活指導
30巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 出血傾向の臨床
29巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 神経症候—リアルタイムの診療
29巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 臨床医のためのわかりやすい免疫学
29巻11号(1992年10月発行)
増刊号 図解 診療基本手技 第2集
29巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 心電図の読み方から不整脈診療へ
29巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 肝硬変から肝細胞癌へ—臨床医の正しい診療のために
29巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 胸部X線からの肺疾患の診断と治療
29巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 虚血性心疾患Today
29巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 内科医のためのCT・MRI
29巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 よくわかる水・電解質と酸塩基平衡
29巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 Common Diseases リアルタイムの診断・治療手順
29巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 高脂血症の日常診療
29巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 胆道系疾患1992
29巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方 '92
28巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 高血圧治療の実際と新たな展開
28巻12号(1991年11月発行)
今月の主題 よくわかる内分泌疾患
28巻11号(1991年10月発行)
増刊号 わかりやすいエコー法の臨床
28巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 臓器感染症と抗生物質の選択
28巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 大腸疾患診療の新時代
28巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 心不全へのアプローチ
28巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 リンパ系疾患の臨床
28巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 輸液療法の実際
28巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
28巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方—その効果と限界
28巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 最新の肺癌診療
28巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 アレルギー疾患診療の実際
28巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 不整脈診療プラクティス
27巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 STROKE—脳卒中診療のポイント
27巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 膠原病—活動性の評価と治療の選択
27巻11号(1990年10月発行)
今月の主題 ベッドサイドの痴呆学
27巻10号(1990年9月発行)
増刊号 内科エマージェンシーと救急手技
27巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎1990
27巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
27巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
27巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 わかりやすい心電図の臨床
27巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 呼吸不全の臨床
27巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療
27巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 臨床医のための免疫学
27巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 消化器診療のcontroversy
27巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 再灌流療法時代の急性心筋梗塞診療
26巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 痛みの診断とその対策
26巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 凝固・線溶系の臨床1989
26巻11号(1989年10月発行)
今月の主題 水・電解質と酸塩基平衡
26巻10号(1989年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント 第4集
26巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
26巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 膵・胆道疾患の臨床
26巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 内科エマージェンシー
26巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 糖尿病マネージメントUpdate
26巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 内科医のための他科疾患プライマリ・ケア
26巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 輸血の実際と血液製剤
26巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 高脂血症と動脈硬化
26巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 内科医のための癌治療のオリエンテーション
26巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 新しい不整脈診療
25巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸液・栄養療法
25巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 腎疾患診療の実際
25巻11号(1988年10月発行)
今月の主題 抗生物質の使い方
25巻10号(1988年9月発行)
増刊号 診断基準とその使い方
25巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 カルシウム代謝と骨
25巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 老人診療のポイント
25巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 高血圧治療のポイント
25巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 リウマチとその周辺
25巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 肝炎への新しいアプローチ
25巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 今日の心不全診療
25巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化性潰瘍とその周辺
25巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症性肺疾患へのアプローチ
25巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 白血病とリンパ腫
24巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 免疫不全とAIDS
24巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 脳卒中up-to-date
24巻11号(1987年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患の最前線
24巻10号(1987年9月発行)
増刊号 これだけは知っておきたい薬の使い方
24巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
24巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 膠原病診療の実際
24巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 肝・胆・膵疾患の画像診断
24巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 循環器疾患の画像診断
24巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
24巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
24巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 甲状腺疾患—up-to-date
24巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患とその周辺—診断と治療
24巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
23巻13号(1986年12月発行)
臨時増刊特集 図解 診療基本手技
23巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 血流障害と血栓・塞栓症
23巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 意識障害へのアプローチ
23巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 感染症の動向と抗生物質
23巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 狭心症—各種治療手段の適応
23巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 内科医のための小児診療のコツ
23巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 呼吸器と免疫・アレルギー
23巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 体液・電解質補正の実際
23巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 水電解質と酸塩基平衡
23巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 消化器薬の使い方
23巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 アルコール障害
23巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 止血機構とその異常
23巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 不整脈診療の実際
22巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 めまいの臨床
22巻12号(1985年12月発行)
臨時増刊特集 エコー法の現況
22巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 生体防御と感染症
22巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 腎疾患—最近の展開とトピックス
22巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 白血病—最新の知見と治療の進歩
22巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の治療
22巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 抗炎症剤の進歩と使い方
22巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎—現況と展望
22巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 免疫反応と臓器疾患
22巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 胆道疾患診療のトピックス
22巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 内分泌疾患の新たな展開
22巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 筋疾患とその周辺
22巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 心不全診療の動向
21巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
21巻12号(1984年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第3集
21巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 脳血管障害のトピックス
21巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 リンパ系疾患へのアプローチ
21巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 膠原病—最新の知識
21巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 下痢と腸疾患
21巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 循環器薬の使い方
21巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 糖尿病診療の実際
21巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の異常
21巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 気管支喘息—病態から治療まで
21巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 腎疾患—早期診断から管理まで
21巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 中枢神経系の感染症
21巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 新しい栄養療法
20巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍—その基礎と臨床のすべて
20巻12号(1983年12月発行)
臨時増刊特集 問題となるケースの治療のポイント
20巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 各種病態における抗生物質の使い方
20巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 血小板の臨床
20巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 肝硬変と肝癌
20巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 臨床医のための神経内科学
20巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 不整脈のトピックス
20巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 内科医に必要な救急治療
20巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 水と電解質
20巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 膵疾患診療のトピックス
20巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 呼吸不全—その実態と治療
20巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 免疫からみた腸疾患
20巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞のハイライト
19巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な泌尿器科の知識
19巻12号(1982年12月発行)
臨時増刊特集 目でみるトレーニング―新作問題248題とその解説
19巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 高血圧症—今日の知識
19巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 自律神経失調症—心身症としての考え方・扱い方
19巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 腎疾患診療のトピックス
19巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 実地医に必要な臨床検査のベース
19巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 カルシウム代謝の基礎と臨床
19巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
19巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 血清リポ蛋白の異常
19巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 狭心症とその周辺
19巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 リハビリテーションの現況
19巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 感染症と免疫
19巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 内分泌疾患—今日の知識
18巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 肺機能検査から疾患肺へ
18巻12号(1981年11月発行)
臨時増刊特集 臨床医のためのCTスキャン
18巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 白血病—最新の概念と治療
18巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 脳循環の基礎と臨床
18巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 ウイルス肝炎のトピックス
18巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 心エコー法の現況
18巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 腹部エコー法の現況—癌診断を中心に
18巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 膠原病—最近の考え方
18巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 出血とその対策
18巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 臨床栄養学—最近の進歩
18巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 肺癌—最近の知識
18巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 心不全の動向
18巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 糖尿病診療の現況
17巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 内科医に必要な脳神経外科の知識
17巻12号(1980年11月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
17巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 高血圧症—最近の動向と展望
17巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 感染症—治療の実際
17巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 膵と胆道疾患
17巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 今日の血液形態学
17巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 アレルギーの現況
17巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 慢性肝炎をめぐる諸問題
17巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 甲状腺疾患診療の進歩
17巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 最近の腎疾患の基礎と臨床
17巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肺の炎症性疾患—最近の動向
17巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 末梢性ニューロパチー
17巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 心膜疾患の臨床
16巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの基礎と臨床
16巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 血管炎とその臨床
16巻11号(1979年10月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい検査のポイント 第2集
16巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 酸塩基平衡の実際
16巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 内科医に必要な精神科の知識
16巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 腸疾患の臨床
16巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 癌と免疫
16巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 血栓とその臨床
16巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 胃癌とその周辺
16巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 肺機能検査の実際
16巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 臨床家のための輸血学
16巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 パーキンソン病とその周辺
16巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 心筋症—その展望
15巻13号(1978年12月発行)
今月の主題 リポ蛋白—最近の知識
15巻12号(1978年12月発行)
臨時増刊特集 これだけは知っておきたい治療のポイント 第2集
15巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 デルマドローム—内科疾患と皮膚病変
15巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 人工透析か腎移植か
15巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 肝疾患のトピックス
15巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 慢性骨髄増殖症候群
15巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 実地医のための臨床細菌学
15巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 免疫診断法と免疫療法
15巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化・吸収の基礎と臨床
15巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 新しい糖尿病の臨床
15巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 胸痛の診かた・とらえかた
15巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
15巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 急性期脳卒中の臨床
14巻13号(1977年12月発行)
今月の主題 知っておきたい骨・関節疾患の診かた
14巻12号(1977年12月発行)
臨時増刊特集 診断基準とその使い方
14巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 呼吸不全とその管理
14巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 高血圧の問題点と最近の治療
14巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 浮腫と臨床
14巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 癌治療の最前線
14巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 腹痛の診かた・とらえかた
14巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 DICとその周辺
14巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 めまいの基礎と臨床
14巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 内分泌疾患診断の進歩
14巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 熱性疾患への臨床的アプローチ
14巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 消化器癌のトピックス
14巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 心筋梗塞—今日の問題点
13巻13号(1976年12月発行)
今月の主題 ミオパチー最近の進歩
13巻12号(1976年12月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
13巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 電解質異常のすべて
13巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 アルコール性障害のトピックス
13巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 リンパ組織の基礎と臨床
13巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 知っておきたいリハビリテーションの技術
13巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 内科疾患としての先天性代謝異常
13巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 肺のびまん性陰影をめぐって
13巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 痛みとその対策
13巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 腎不全の病態と治療
13巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 内科医に必要な末梢血管病変の知識
13巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 胆道疾患—診療の実際
13巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 不整脈のハイライト
12巻13号(1975年12月発行)
今月の主題 SLE—成因から治療まで
12巻12号(1975年11月発行)
今月の主題 肺癌—その理解と対処のために
12巻11号(1975年10月発行)
今月の主題 感染症としてのB型肝炎
12巻10号(1975年9月発行)
今月の主題 アレルギーのトピックス
12巻9号(1975年8月発行)
今月の主題 甲状腺疾患のすべて
12巻8号(1975年7月発行)
今月の主題 感染症—最近の話題
12巻7号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管潰瘍—診断および治療の現況
12巻6号(1975年5月発行)
今月の主題 出血傾向の新知識
12巻5号(1975年4月発行)
今月の主題 糖尿病への新たなる対処
12巻4号(1975年3月発行)
特集 これだけは知っておきたい検査のポイント
12巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 心身症からみた症候群
12巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 血液ガスの基礎と臨床
12巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 意識障害への新しいアプローチ
11巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 喘息の本質から治療まで
11巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 神経内科の動き
11巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 手術適応の問題点
11巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 腎疾患のトピックス
11巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 内科医に必要なバイオプシー
11巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 肝硬変—今日の視点
11巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の臨床
11巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 臨床心電図のキーポイント
11巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 高脂血症の意味するもの
11巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 貧血の現況
11巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 酸・塩基平衡異常—その日常臨床とのつながり
11巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 新しい臓器相関のとらえ方
10巻13号(1973年12月発行)
今月の主題 最近の老人病—臨床とその特異性
10巻12号(1973年11月発行)
特集 これだけは知っておきたい治療のポイント
10巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 高血圧とその周辺
10巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 膵疾患診断法
10巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 慢性関節リウマチ(RA)の新しいプロフィール
10巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 転換期に立つ検診
10巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 化学療法剤—現状とその使い方
10巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 問診
10巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 消化管ホルモンの臨床
10巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 内科最近の話題
10巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内科領域における輸液と輸血
10巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 冠硬化症の新しい知見
10巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 新鮮脳卒中
9巻13号(1972年12月発行)
今月の主題
9巻12号(1972年11月発行)
今月の主題
9巻11号(1972年10月発行)
今月の主題
9巻10号(1972年9月発行)
今月の主題
9巻9号(1972年8月発行)
今月の主題
9巻8号(1972年7月発行)
今月の主題
9巻7号(1972年7月発行)
特集 これだけは知っておきたい診断のポイント
9巻6号(1972年6月発行)
今月の主題
9巻5号(1972年5月発行)
今月の主題
9巻4号(1972年4月発行)
今月の主題
9巻3号(1972年3月発行)
今月の主題
9巻2号(1972年2月発行)
今月の主題
9巻1号(1972年1月発行)
今月の主題
8巻13号(1971年12月発行)
今月の主題
8巻12号(1971年11月発行)
今月の主題
8巻11号(1971年10月発行)
今月の主題
8巻10号(1971年9月発行)
今月の主題
8巻9号(1971年8月発行)
今月の主題
8巻8号(1971年7月発行)
今月の主題
8巻7号(1971年6月発行)
今月の主題
8巻6号(1971年5月発行)
臨時増刊特集 身体所見のとり方と診断のすすめ方
8巻5号(1971年5月発行)
今月の主題
8巻4号(1971年4月発行)
今月の主題
8巻3号(1971年3月発行)
今月の主題
8巻2号(1971年2月発行)
今月の主題
8巻1号(1971年1月発行)
今月の主題
7巻13号(1970年12月発行)
今月の主題
7巻12号(1970年11月発行)
今月の主題
7巻11号(1970年10月発行)
7巻10号(1970年9月発行)
今月の主題
7巻9号(1970年8月発行)
今月の主題
7巻8号(1970年7月発行)
今月の主題
7巻7号(1970年6月発行)
今月の主題
7巻6号(1970年5月発行)
臨時増刊特集 日常役立つ診療技術
7巻5号(1970年5月発行)
今月の主題
7巻4号(1970年4月発行)
今月の主題
7巻3号(1970年3月発行)
今月の主題
7巻2号(1970年2月発行)
今月の主題
7巻1号(1970年1月発行)
今月の主題
6巻12号(1969年12月発行)
今月の主題
6巻11号(1969年11月発行)
今月の主題
6巻10号(1969年10月発行)
今月の主題
6巻9号(1969年9月発行)
今月の主題
6巻8号(1969年8月発行)
今月の主題
6巻7号(1969年7月発行)
今月の主題
6巻6号(1969年6月発行)
今月の主題
6巻5号(1969年5月発行)
今月の主題
6巻4号(1969年4月発行)
今月の主題
6巻3号(1969年3月発行)
今月の主題
6巻2号(1969年2月発行)
今月の主題
6巻1号(1969年1月発行)
今月の主題
5巻12号(1968年12月発行)
5巻11号(1968年11月発行)
5巻10号(1968年10月発行)
5巻9号(1968年9月発行)
5巻8号(1968年8月発行)
5巻7号(1968年7月発行)
5巻6号(1968年6月発行)
特集 くすりの新しい使いかた
5巻5号(1968年5月発行)
5巻4号(1968年4月発行)
5巻3号(1968年3月発行)
5巻2号(1968年2月発行)
5巻1号(1968年1月発行)
特集 古い治療から新しい治療へ
4巻12号(1967年12月発行)
特集 病歴
4巻11号(1967年11月発行)
4巻10号(1967年10月発行)
4巻9号(1967年9月発行)
4巻8号(1967年8月発行)
4巻7号(1967年7月発行)
4巻6号(1967年6月発行)
4巻5号(1967年5月発行)
4巻4号(1967年4月発行)
4巻3号(1967年3月発行)
4巻2号(1967年2月発行)
特集 尿糖
4巻1号(1967年1月発行)
3巻12号(1966年12月発行)
今月の主題
3巻11号(1966年11月発行)
今月の主題
3巻10号(1966年10月発行)
特集 老人患者を診るとき
3巻9号(1966年9月発行)
今月の主題
3巻8号(1966年8月発行)
今月の主題
3巻7号(1966年7月発行)
今月の主題
3巻6号(1966年6月発行)
特集 蛋白尿
3巻5号(1966年5月発行)
今月の主題
3巻4号(1966年4月発行)
今月の主題
3巻3号(1966年3月発行)
今月の主題
3巻2号(1966年2月発行)
今月の主題
3巻1号(1966年1月発行)
今月の主題
