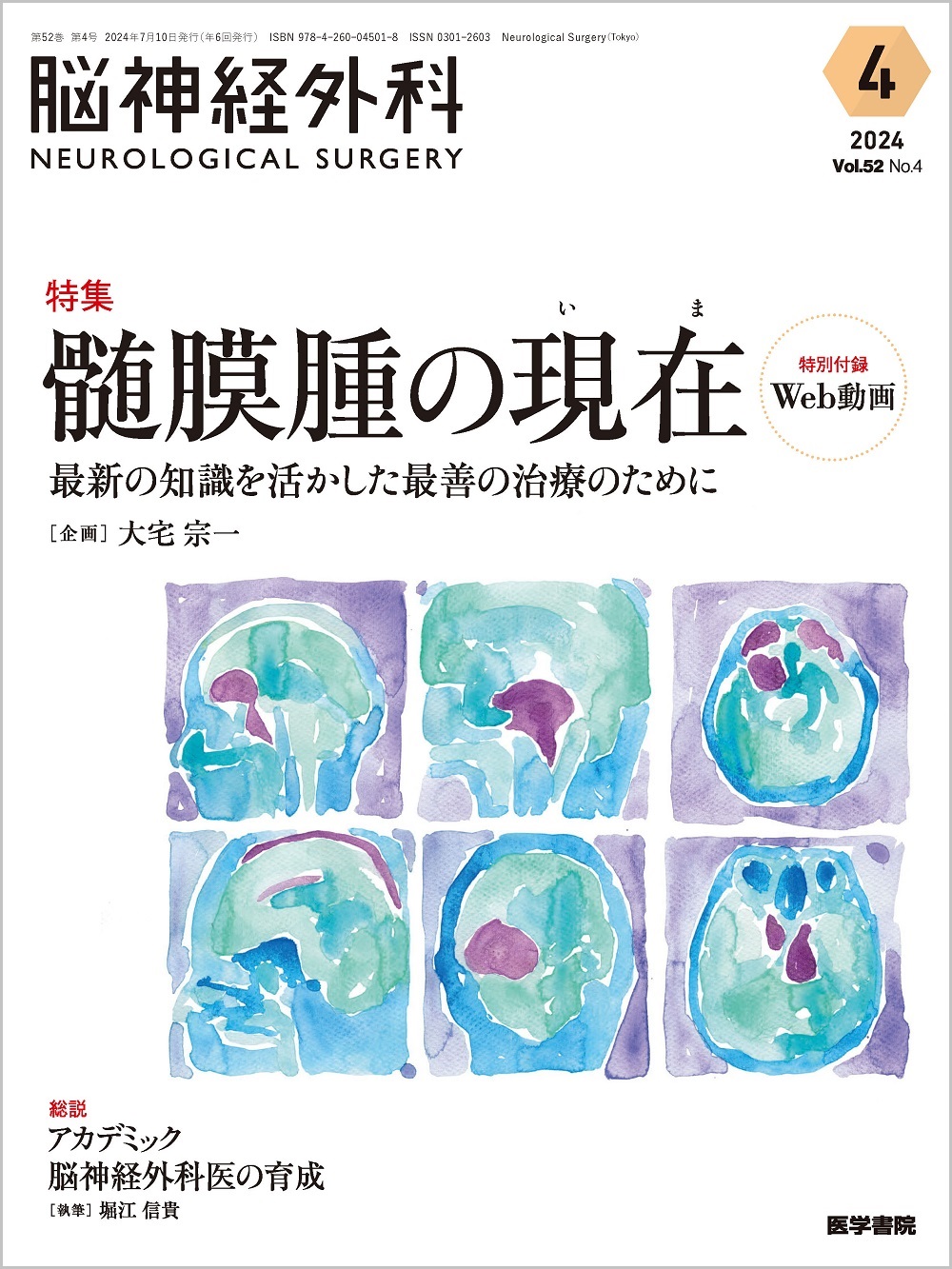文献詳細
文献概要
総説
アカデミック脳神経外科医の育成
著者: 堀江信貴1
所属機関: 1広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科学
ページ範囲:P.867 - P.875
文献購入ページに移動トランスレーショナルリサーチの概念は,21世紀初頭に国際的な研究トレンドとして導入された.本邦の医学研究においても研究成果を臨床現場に迅速に適用することの重要性が認識されるようになり,2000年代当初より日本政府や学術機関は,トランスレーショナルリサーチの推進に力を入れ始め,科学技術振興機構(Japan Science and Technology Agency:JST)や厚生労働省などの公的機関が基礎研究から臨床応用までのプロセスをサポートするプログラムや資金提供を開始した.また,多くの大学や研究所ではトランスレーショナルリサーチセンターやプログラムが設立され,基礎科学者と臨床医との間の協力を促進する体制が整えられた.これらの整備により,本邦においても新しい治療法や診断法の開発が加速したと言える.国際的な研究連携も重要な要素であり,本邦の研究者は世界中の研究機関や企業との共同研究を通じて,グローバルな研究ネットワークを構築することが推進されている.このような公的機関の取り組みによりゲノム編集技術やiPS(induced pluripotent stem)細胞(人工多能性幹細胞)などの革新的な技術を活用したトランスレーショナルリサーチが活発に行われていることは周知のとおりであり,個別化医療や再生医療など,次世代の医療を牽引する分野での応用が期待されている.
一方で,本邦における学術的競争力が世界的に低下していることは大きな懸念事項である(Fig. 1)1).Nature誌でも“Numbers of young scientists declining in Japan”という記事を載せており,特に中小研究施設における基礎研究への研究資金拡充の必要性を述べている2).脳神経外科領域においてもこのトレンドは顕著であり,海外のそれとは大きく異なる本邦の脳神経外科医の研修システム,業務内容についての特異性が影響しているものと考えられる.特に大学病院などアカデミックセンターの医師は,診療だけでなく明日の医療を開発するための研究や次代を担う医師・医療従事者を育成するための教育をその役割として担っている.現在進行形の医師の働き方改革による診療を主対象とする労働時間の削減によって,結果的に研究や教育を行う余裕が減り,本邦の医学研究・医学教育の質が低下することは避けねばならない.脳神経外科の父と言われているHarvey Cushing(1869〜1939年)はacademic surgeonについて7原則(Table 1)を示しているが,その内容は現在においても異論を唱える者は少ないと思われる.すなわち,生体の内部,疾患の患部を直接観察でき,自分のスキルにより病変を治療できるのは外科医のみの特権であり,それ故に自分のスキルの向上は言うまでもなく,その上にアカデミズムを重ねることで,より高次元の外科医になれると言える.
本稿では,臨床医におけるアカデミズムの意義について,特に本邦における脳神経外科医の現状を踏まえ,今後の課題につき概説する.
参考文献
掲載誌情報