It has been cause of the deepest sorrow to hear of the unexpected, sudden dis-appearance of my good friend, Prof. Yasushi Nakamura, on October 18th 1956, owing to cerebral haemorrhage.
It was hardly possible for me to believe that my distinguished Colleague, Pro-fessor of Ophthalmology at the Nippon Medical College since 1928, had left us! Just the month before I had again the pleasure of spending many happy hours with him during my visit to Japan, where he organized so kindly and perfectly my programme.
雑誌目次
臨床眼科11巻4号
1957年04月発行
雑誌目次
故中村康教授追悼号
追悼の辞
著者:
ページ範囲:P.541 - P.566
グラフ
在りし日の中村康教授
ページ範囲:P.531 - P.534
原著
低照度に於ける視標の認識域について
著者: 宮田正治
ページ範囲:P.571 - P.574
緒言
暗順応状態での最小光度及種々なる低照度に於ける視標の認識能力域が,眼の高さの水平面上に於いて如何なる深度を有するかを実験し,その数値を形態的に作図し観察せんとす。
某自動車工場從業員に於ける眼筋運動負荷試験成績
著者: 瀨尾孝之
ページ範囲:P.575 - P.580
曩に松原広氏はメトロノームによる眼筋運動負荷試験を試みて,同試験が疲労誘発試験並びに眼精疲労の補助診断として有意義である事を述べているが,偶々我が教室が某自動車工場の依頼を受けて工場従業員の有害光線(特に紫外線)被曝による障害の実態調査を行う事になり,著者も其の一員として近点測定による調節力検査を分坦する機会を得,予てより興味を抱き自験を望んでいた同試験を追加実験として施行する事が出来たので其の結果を此処に報告致し度いと思う。
皮角について
著者: 中泉行信
ページ範囲:P.580 - P.582
皮角の定義というものは獸角に似た円錐形の突起を皮膚に生ずるものであつて,これには真性のものと偽性のものとに分けられる。真性には良性の腫瘍として発生するものと母斑をもととして発生するものと,伝染性疾患や機械的化学的の刺戟をもととして発生するものとがある。しかしいずれも孤立性に発生し,形も定形的な円錐形もしくわこれに似た形をとるものが多い。真の獸角の様に表面に横溝と縦溝とを有していて,円錐形であるけれども発育するにつれて彎曲するのが普通である。色は暗褐色又は褐色を呈して先端は変色して汚い紅色を帯びてくる。又多くのものは堅いが中には柔かいものがある。尚自発痛はないのが原則である。
皮角という疾患は比較的まれな疾患であり,医学中央雑誌や眼科雑誌を調べてみても報告は少い。特に我が国の眼科では報告例が少いのである。1912年以来報告された23例の中,やや詳細な記載のあるものは石丸・鹿野・疋田・岩館・緒方の5例にすぎないのである。
結膜上皮細胞内の色素顆粒に就て
著者: 吉永幸子
ページ範囲:P.583 - P.587
I.緒言
Virus学の進歩に伴い結膜分泌物の細胞学は,結膜或は角膜疾患の診断上重要視されるに至つたのは当然である。さて結膜の擦過塗抹標本及び分泌物中の上皮細胞内に「ギムザ」染色にて一見P氏小体類似顆粒が存在することは,既に多くの人々によつて報告されている。従つてP氏小体検索上,上皮細胞内に見られる類似顆粒との鑑別に注意を促されている。即ち越智氏は「ウンナア,パツペンハイム」氏染色にて暗緑色,或は殆んど緑色を呈する小体を細胞内又は細胞外に散在的に或は集的団に存在することを認めている。本顆粒は270例の内11例に見られ,その出現機転は炎症等の如き動機により増殖する事が認められると述べている。脇坂氏は「トラコーマ」顆粒内細胞を塗抹標本により形態的に研究した際,「トラコーマ」にコツホ,ウイークス氏桿菌結膜炎を併発せるものゝ分泌物中にある上皮細胞内に多数の黄褐色色素顆粒を発見し,本染色体は炎症によつて本来色素顆粒を産出すべき傾向特性を有する細胞が,この際色素顆粒を産出し来るものならんと述べ,変性とは無関係であろうと云つている。小口,馬島氏も「トラコーマ」分泌物中の上皮細胞内に屡々黄褐色の色素顆粒を認め,普通の「メラニン」に相当したものであり,或るものは「リポクローム」類似のものにして,「メラニン」とは階級的の差異であろうと述べている。
パイフエル氏菌性結膜炎の統計的観察
著者: 河瀬澄男
ページ範囲:P.587 - P.589
緒言
Pfeiffer氏Influenza菌は所謂インフルエンザの病原的価値は現在消極的で眼科領域に於いては従来Koch-Weeks氏菌との異同に就いてのみ多くの興味が持たれて来た。併しながら眼分泌物の顕微鏡的診断の際,屡々本菌に遭遇し,且つその患者の臨床症状も特定の所見を呈し,且つ経過も短時目に治癒する事に気付いたので我々の外来に於ける1年間の患者に就いて臨床所見を総合的に観察し聊か見るべき成績を得た。
春季カタル患者の結膜嚢内細菌とpHに就いて
著者: 小口昌美 , 右田省三
ページ範囲:P.590 - P.592
緒言
春季カタルの分泌物を鏡検する場合屡々気付くことは,塗抹標本中に細菌が少いことである。殊に急性者季カタルの場合,殆んど標本中に細菌を認めぬことは注目に値するであらう。
従つて急性春季カタルの診断に際し,標本に細菌の少いことは,好酸球の有無と同様一つの診断の目標となる位である。即ち標本中に細菌を多数認めた場合,急性春季カタルの診断の反証と考えてよい時が屡々である。
春季カタル患者の鼻粘膜に就いて
著者: 小口昌美 , 河瀬澄男
ページ範囲:P.592 - P.594
1.緒言
春季カタルの本態に就いては結膜のアレルギー性炎症説は異論のないところである。私共はそのアレルゲンに獣いて花粉を最も有力なるものとし種々実験を重ねた結果,又全国の本患者の統計を観察した結果,花粉感作説は最早確定的のものであるとの結論に達した。其後花粉感作説の基盤をなすものに当然体質の問題を取上げねばならないが此のグレンツゲビートの一つとして鼻粘膜の態度を究明することになつた。花粉感作が結膜粘膜のみに限局すると言う考えはおかしなことで当然他の粘膜殊に近接臓器として鼻粘膜等の所見を究明することが花粉感作説を側面より説明することになるのである。春季カタルの文献中扁桃腺等の所見を調査したものはあるが,鼻粘膜それ自身を問題にしたものはない。私共は春季カタル患者17例の鼻粘膜を調査して聊か成績を得たので報告する次第である。
結膜嚢内分泌物のリゾチームの実験的研究
著者: 河瀬澄男 , 根本祐
ページ範囲:P.595 - P.598
緒言
前眼部は,空気中に曝露せられているので直接的に数多くの細菌侵入の門戸となる。而して,涙液は,多数の細菌を機械的に洗い出すのみならず,或る程度の殺菌作用を具備しそれに依り細菌の発育を或る程度阻止するものと考えられた。此の非特異性溶菌作用の存在を発見したのは,A.Flemming & Allison (1922)である。彼は鼻汁唾液卵白等にもこれを認め此の物質を始めて「リゾチーム」と名付けた。扨て,溶菌性酵素「リゾチーム」(以下「リ」と略す)の研究ば,A.Fle-mming9)(1922)以来K. Meyer,Anderson,Findlay1)等が行つているが,本邦に於ける臨床的分野では,耳鼻科領域に於ける穏明寺氏11)の研究を見るのみで,眼科領域では未だその業績はないのである。
今回,私等は,健康群,トラコーマ群,瘢痕性トラコーマ群,眼瞼結膜炎群,春季カタル群,流行性角結膜炎群,角膜疾患群,涙器疾患群の結膜嚢内分泌物の「リ」量を調査し少しく知見を得たので,茲に発表する次第である。
流行性角結膜炎の病名論
著者: 小口昌美
ページ範囲:P.599 - P.601
流行性角結膜炎(以下流角と略)の病名に就いて検討を加え度いと思う。その理由は此病名の解釈に二つの異つた解釈がなされているからである。従つて統計上或は疫学上にて多少の困乱が生ずるのは当然である。此問題に就いては先に萩野教授が日本医事新報(昭和28年)に流角の診断と題して種々の角度より検討されている。併しその後Virus学の進歩により流角のVirusも明確になりつゝあるので流角の病名に就いて再検討をする次第である。本邦の最近の報告を見ても流角の罹患が乳幼児にあるかないかの二通りの解釈が行われている。外国にては流角と診断したものに就いては乳幼児の罹患は殆んど問題外の感がある。そこで流角の病名の解釈に就いて文献を挙げ,それに批判を加え度いと思う。
中村教授生前の角膜移植業績より
著者: 樋田敏夫
ページ範囲:P.601 - P.604
中村教授が,透光体,眼底に疾患を有せず,只単に角膜溷濁を有するが為に,暗黒に悩む儘に放置されて居る失明患者に再生の光を与えんと角膜移植に注目され,昭和16年該研究を開始され,昨31年10月卒然として不帰の客となられる迄途中,大平洋戦争,大学の焼失,疎開による研究の中断等幾多の障碍を乗り越えられつつ,眼科学会に角膜移植という偉大な業績を残された事は既に御承知の事と思う。此の間昭和25年には「基礎的研究より臨床的応用」なる演題の特別講演をされた外,機に応じ,時を得て,或いは臨床眼科学会に集談会に,或いは手術叢書に発表され,今や角膜移植は眼科一般の常識となり,各所に於て実施せられる様になり,幾多の失明患者に再生の悦びを与えて居るのである。角膜移植なる大綱に就いては既に中村教授の著書もあり,又報告も多数見られるので,改めて,詳細に亘り述べる事は必要としないが,偶々恩師中村康教授の計に当り追悼号が編輯されるを聞き,故教授が生前実施された偉大なる業績を偲び,その御遺志を奉ずる意味に於て御存命中の移植成績を纒め,二,三感ずる所があつたので之を此の機会に発表し,恩師に続き更に奮起一番研究を続けんとする我々教室員の参考に資せんとするものである。
中村教授在世中の角膜移植例総数は403例(男291例,女112例)
角膜脂肪変性組織所見3例に就いて
著者: 清水由規
ページ範囲:P.605 - P.608
角膜脂肪変性は比較的稀有なる疾患として報告されて居りますが,今迄本症は角膜全層を得るが如き角膜移植の手術の適応とはならなかつた為,従来の諸報告に於いても生体角膜脂肪変性の全層に互つての組織的検索を行つた報告はありません。当教室に於ては,角膜移植に当つて本疾患の角膜全層を得,その組織的検索を行い先に当教室中村陽氏はその結果を報告して居りますが,その後3例の角膜脂肪変性の全層角膜片を得る機会を得ましたので追加報告致します。
材料は角膜移植時に採りたる角膜中央部4〜6粍直径の角膜全層を,10%ホルマリンに固定し氷結切片にし,ヘマトキシリン,及びスダンⅢで染色した。
角膜ヘルペスに於けるリーゼンガング氏環の3例に就て
著者: 吉永幸子
ページ範囲:P.608 - P.612
I.緒言
角膜ヘルペスの臨床像は多種多様であつて現在に於ては円板状角膜炎,樹枝状角膜炎及び糸状角膜炎等が一般に認められている。之の角膜ヘルペスは1920年Wilhelm Gruter氏がヘルペスより採取したる材料を以て家兎角膜に接種し,人間と同様の変化を起させることに成功して以来角膜ヘルペスは,一種のVirus性疾患と見做されるに至つた。就中円板状の角膜溷濁を特徴とする円板状角膜炎は1901年E. Fuchs氏によつて独立した眼疾患として命名されて以来数多くの報告がなされている。しかし其の病因に就ては外傷,痘毒,蜂毒,枯草菌或は結核アレルギー等色々な報告があつて,未だ決定したとは考えられない。杉田氏はこの円板状角膜炎の本態を追究し新しい所信を述べている。即ち氏によると家兎角膜の実験により,円板状角膜炎の特異な臨床像は角膜を一種のコロイド膜としてリーゼンガング氏現象を基本とした基質蛋白質の沈澱輪により成立するものである。又Virus毒素による実験の結果,固定した円板状角膜炎の臨床像を認めている。之はVirus毒素の病巣産生物質が蛋白質に作用し,異種蛋白質の相接触せる現象として共に沈澱せるものと考え,之が円板状を呈しているのはコロイド板内に於ける異種コロイド電解質の拡散像としてリーゼンガング氏現象を具現したものである。
塩化ビニール安定剤によると思われた表層角膜炎
著者: 根本祐 , 右田省三
ページ範囲:P.613 - P.616
緒言
薬物に依る角膜障碍の報告は既に多数例を見るが,近来化学工業の発達に伴い益々其の機会が多くなるのは当然の事と思われる。私共は,最近同一某化学工場から数人の同様な表層角膜炎の患者が多発したのに気付いた。そして種々調査した結果,塩化ビニール安定剤による角膜障碍であることを確める事が出来たので茲に報告する次第である。
而して,此ゝに述べる塩化ビニール安定剤とは其の一種類の錫系安定剤である。その製造工程は第1表の如くにして,錫とナトリウムの合金にBuBr2を加えBu2SnB12としてそれにラニン酸ソーダを加えBr2を取つてBu2SuLr2とし,又苛性ソーダを加えBu2SnOとするものである。又Bu2SnBr2は不安定で温度により蒸化して粉末のBu2SnCl2となるのである。この3種類成分を錫系塩化安定剤として製品化するものである。
耳畸形を伴つた角膜輪部皮様腫
著者: 河瀨澄男
ページ範囲:P.616 - P.619
1.緒言
眼部皮様腫は臨床的組織学的に稀有なものではなく1852年RybaがDermoidなる名を冠して以来多数の報告例を見る。尚Ryba以前にMau-chart (1748)により『眼球表面に現われ且つ之れに長髪を伴う腫脹』として報告されたのが始めで次いでCazeles (1766)は『毛髪を伴い角膜縁に跨る腫瘍』に就て報告した。又本態に関してはTrichosis bulbiと謂い或いはLipoma crinosumと呼ばれ又久しい間Warzeと称せられていた。本邦では明治20年甲野氏の報告を嚆矢として55例を数え,而して報告されないものが又多数あると思われる。又屡々他の諸種先天異常合併の報告例は26を算する。最近私は角膜輪部皮様腫に種々の先天異常を合併した一例を経験したので追加報告する次第である。
虹彩紋理の一観察
著者: 須沢光雄
ページ範囲:P.619 - P.621
緒言
虹彩紋理に就いての報告は眼科学的或は人類学的方面よりしても少ない。
虹彩紋理は周知の如く人種,個人,年齡的に相違するもので,これが精密な分類は困難なるも,その大要の分類を行うに大体二つの方法が考えられる。
本邦人胎児黄斑部の発育過程について(Ⅰ)
著者: 佐伯譲
ページ範囲:P.622 - P.632
緒言
動物網膜の発育過程については内外を問わず幾多の研究があるが,人眼網膜特に黄斑部の発育についての研究は比較的少く,外国にてはChievi-tz, Seefelder, Mann等の研究が代表的のものであり,本邦にては最近中村教授の概説及び市川氏の研究があり,市川氏はその細胞の発育過程について詳細に報告した。文献に依れば成人黄斑部の呈する形態は胎生時より存在するものではない様である。然らば黄斑部は胎生時にはどの様な形態の変化過程を辿るのであろうか。これについて私は本邦胎児を用い検索し若干の知見を得たので報告する。
人胎児網膜発生過程に於ける組織化学的研究
著者: 中山恭四郎
ページ範囲:P.635 - P.644
緒言
網膜視機能の発現機転については古来解剖組織学・生理学・生化学等各方面よりの幾多の研究があるが未だその詳細については解明された状態とは云えない。吾教室に於てはこの数年来恩師故中村康教授御指導の下に教室を挙げて網膜構造と視機能発現につき視力・網膜電流・緑内障等の研究と平行して胎生学的研究を行つて来て多大の成果を納めつつある。就中胎生学的研究については故中村康教授は既に自ら眼科領域の発生学につき広範該博なる論文を表わされてその概要を明らかにされた。教室の研究課題として意図する範囲も又極めて広く殆ど眼科領域の全域にわたつているものでその完成の曉はこの方面の進歩に括目すべき貢献をなすものと期待される。
一方近時医学・生物学の分野に於て新に生体内の新事実を解明し長足の進歩をなしつつあるものの中に組織化学なる領域がある。即ち夫々自らの分野の中で著しい発展を遂げた生化学及び解剖組織学の間を連結する組織化学は組織或は細胞内に於ける一定化学物質を化学的処置法によりそれが組織内にあるがままの形で染め出しその所在と在り方を究明し更にはそれが細胞内エネルギー代謝と如何なる関係にあるかを解決して細胞内物質代謝の様相を把握しようとするのである。
網膜電流に就いて—補遣 其の二
著者: 広瀨東一郎 , 平岡寅次郞
ページ範囲:P.644 - P.647
第1章 緒言
さきに著者は人生体眼に於ける網膜活動電流に就き,其の基礎的,臨床的研究結果を総括し,或は特異的なるものに就き実験結果を述べて来たが本稿に於ては小口氏病の網膜活動電流に就き述べたいと考える。
周知の如く,小口氏病は明治39年小口忠太教授が発見報告以来,明暗順応時に於ける特異な眼底変化(中村—水尾氏現象)と暗順応経過曲線の特徴とに依り諸学者の注目するところとなり,幾多の研究がなされているが,其の本態は今尚推論の域を脱しない。
緑内障患者に於ける虹視の出現率に就いて
著者: 清水貞男
ページ範囲:P.647 - P.651
緑内障患者に虹視の現われる事に就いては,既に古くから知られている所でありますが,此の度教室に於ける緑内障研究の一端として,まとめる機会を得ましたので此処に発表させて戴く事に致します。
春季カタル及び老人性白内障患者の血清総Ca量に関する研究
著者: 根本祐 , 永井誠一
ページ範囲:P.653 - P.657
緒言
春季カタルの発病に就ては,アレルゲンの侵襲は勿論であるが,其の基盤をなすものは体質が大に影響する事は充分想像されるのである。私共は今回其の体質研究の一部として,血清中総Ca量を柳沢氏法に依り測定した。
春季カタルの血清Ca量に就てはつとに Woodsの報告があり,Ca量の減少を認め且つ非経口的のCa療法を有効であると述べている。又本邦に於ては,高橋氏が,5例の春季カタルに就て測定し,Ca量が健康人より多いものが少からずと報告した。
緑内障様主訴症例に就て
著者: 魵沢甲造
ページ範囲:P.657 - P.660
緑内障診断が極めて困難なるものだけに,其の誤診も亦比較的多いと云わなければならない。
私は当院外来患者中,緑内障様主訴により,未検査のまま,一般医に於て,緑内障或は疑似と診断された無手術症例28例に就て,是が如何なる主訴並に病状を呈しているものかを検索し,得る処があつたので茲に報告する。
Schlemm氏管内墨汁注入に依る導出管の観察(正常人眼)
著者: 高橋龍生
ページ範囲:P.660 - P.664
緒言
房水流出路に関する研究はLeberの所謂前房隅角Schlemm氏管(以下Sch氏管と略)経由説以幾来多の業績があり,Sch氏管導出路に就てはMaggiore, Teobaldはじめ内外に其の研究は数多い。更にAscher (1942)の房水静脈観察以来鞏膜面静脈に房水流出を実証する研究,又Sch氏管と房水静脈との関連に就てもThomassen,Bakkan, Goldmann, Greaves, Asthon,高橋(昭28)岸本,宮田等の臨床的或は組織学的の研究がなされて居る。色素材螢光物質,neoprenelatex等を用いる研究も多い,私は先に主として家兎眼に依つてインヂコカルミン前房注入により房水流出路の観察を行つたが,今回屍体人眼球のSch氏管内に墨汁を注入して房水流出路の観察を行つて得たる所を此処に発表する。本実験は故中村教授の御指導に依るものであるが,今回恩師追悼号の発行に当り,研究未だ中途なるを顧みず,誌上にのせて報恩の一端となす所である。
不幸の転帰をとつた眼窩腫瘍(Glioblastoma multiforme)の1例
著者: 中山恭四郞
ページ範囲:P.665 - P.668
眼窩腫瘍は現在に於ては必ずしも稀な疾患ではないが今回私は極めて急激な経過を取り再度の手術を行うも再発を繰返し遂に悪液質の為不幸の転帰をとつた1例を経験したので茲に報告する次第である。
眼結核の血清カルボール反応に就て
著者: 吉永幸子
ページ範囲:P.668 - P.677
I.緒言
眼結核の臨床診断の困難なことは周知の通りであつて,従来概ね推定と消去法に依るの外はない。推定とは全身の結核の有無の判定の結果眼結核とする場合であり,消去法とは他原因となる可き疾患を順次抹殺してその結果眼結核と診断する場合であるが,何れにしても両者共診断の適中率は相当あるとしても断定的なことは中々困難である。最後は組織学的所見或は菌培養に依るの外はないのが現状である。しかし組織学所見と菌培養の点,眼組織の場合その病巣の所在によつては不可能の場合があり,ために結核の確実な臨床診断法が要望される所似である。そこで結核の血清学的診断法を見るに特異的免疫反応と血清の膠質化学的変化を利用した方法がある。前者の一つとして近来Middelbrook Dubos反応として眼科領域にては血清並びに前房水を用いて結核に特異的に反応し眼結核の診断にその価値は重大なりとするものがあるが,一方鹿野氏等は前房水の本反応を以て結核と断定することは早計であると警告している。
次に血清の膠質化学的反応として種々のものがあるが,本学皮膚科教授丸山千里氏のカルボール反応が結核に撰択的に反応することが報告され,結核の診断に劃期的な役割を呈したことは周知のことである。私は眼結核と思われるものに就て,その血清のカルボール反応を実施してみたので報告する次第である。
Penicillin点眼迅速反応について
著者: 初田博司
ページ範囲:P.678 - P.679
緒言
Pアナフイラキシーの予防診断を目的として河東氏は点眼反応及び皮内反応の比較を試み,個体のPアレルギー状態の強さに応じて,安全と思われる診断用のP点眼液の濃度を想定した。若しも安全にして簡易な点眼反応が,皮内反応と同程度に上述の予防診断に役立つならば,臨床上大いに利用さるべきものであり,其の価値は大きいものである。私は先頃から河東氏の方法によりP点眼反応が皮内反応とどの程度一致するかについて検討を試みて来たが,現在迄の結果につき報告したいと思う。
アイソトープの眼科治療学的応用—其の2 翼状片に対する応用
著者: 中泉行信
ページ範囲:P.680 - P.683
1.緒言
最近,眼科領域に於いて人工放射性同位元素による放射線治療が漸く行われ眼科治療に新しい分野が開拓されてきている。眼科疾患特に角膜疾患に対してはすでに長い間エツクス線及びラヂウムによるγ線及びβ線等の放射線療法や紫外線,赤外線,ヂアテルミー超音波等が用いられてきた。
放射線療法としては放射線が角膜を通し深層に達して水晶体の退化現象を起し白内障を来たすおそれがある為に,表在効果があり深層効果のないものが望まれるのである。即ちβ線は透過力が少いために放射線によつておきる水晶体の退化現象を防ぐ事が可能なわけである。アイソトープの生産が可能になる迄はβ線は主としてラヂウムやラドン等の天然放射性物質から得て来た。しかし角膜疾患にラドンapplicatorを用いる場合にはラドンの半減期が3.81日という短期間であるのでラドンを定期的に補充しなければならず又γ線に対する保護措置が常に必要であるのであまり用いられてはいなかつた。
眼疾患に対する5-オキシン錠の効果
著者: 菅原淳 , 浜田正和
ページ範囲:P.683 - P.687
緒言
5—オキシアントラニール酸は副腎摘出動物の肝グリコーゲンを正常に保ち尿中クレアチニン,尿素の減少を抑え血中残余窒素の増加を抑えて正常値に近く維持する作用があり,また肝機能を亢進し利尿,血糖調整,解毒の作用があると云われ,未だ其の作用が充分に明らかにせられていないが,トリプトフアンの中間代謝物質であつてキノニミンカルボン酸との間に可逆平衡のあることが認められており,微量で以て著明な生理作用を有するものであるらしい。5-オキシン錠(ゾンネボード製薬)は其の一錠中に5-オキシアントラニール酸の0.3mgとアントラニール酸の5mgを含有する製剤であつて他にビタミンB1 B2 B6が含まれている。最近私共は本剤の提供を受けて数種の眼疾患に使用し,一定の疾患群では驚くべき治効を認めたので其の大要を報告するものである。
科手術に於けるウインタミンの使用経験
著者: 臼井都夫
ページ範囲:P.687 - P.692
緒言
1950年,フランスのRhone-Poulence研究所で合成された自律神経安定剤クロールプロマジンは,1951年,H.Laboritが,之を主体とする多くの薬剤を用いて,臨床的にはじめて人工冬眠麻酔に成功して以来,今日まで内科,外科,精神科,産婦人科,耳鼻咽喉科,皮膚科,眼科等の各領域に於て広く応用されて来た。
本剤を眼科領域に於ける手術の麻酔にはじめて使用したのは,Dejean及びJauhmes (1954)等であつて,我が国に於ては,1955年,植村によつてはじめて報告されて以来,多くの人々の報告が見られる。
熔接工の眼検診成績
著者: 初田博司 , 市川達 , 中村陽 , 中山恭四郎 , 平岡寅次郎 , 瀨尾孝之 , 鈴木鋿司
ページ範囲:P.693 - P.695
最近工場に於ける有害放射線の障碍が注目され,労働者の要請もあつて,各地で調査が行われている。私共は労働省の調査とは別個に某熔接工場の依頼により,熔接工の眼機能を検診する機会を得た。此種の調査は,周到な注意と,長期間に亘る観察によつて成果を得るものであるのは勿論であるが,調査方法の差異によつて成績に相違を来し,過つた結果を得る危険も存在すると考えられるので,今後の調査の参考にもなれば幸と思い,唯一回の調査成績のみであるが,発表する次第である。
有害光線被曝従業者の眼検診成績
著者: 市川達 , 中山恭四郎 , 瀨尾孝之 , 鈴木鋿司 , 小林幹雄
ページ範囲:P.697 - P.701
有害放射線の障碍に関する報告は以前より少なくなく,眼科的疾患については既に著明なものが確認されている。特に最近関係者の間に於て,注目を受け此の方面の研究が盛に行われているが,未だ日浅くその全貌は明かでないのみならず,寧ろ混乱を来して居る様である。その原因は,此の種研究の多くは単なる実験的研究であつたり,実態調査に於てもその放射線の性状を明かにしたものは少ない為と考えられる。
私共は今回某工場に於てカーバイト電炉と滓炉との有害放射線量の測定を行い,その作業者の眼機能の一部を検査する機会を得た。その結果は此の方面の研究を解決するものでは勿論ないが,今後の研究の基礎的資料として有意義と信じ報告する。
カルピノールに関する研究(其の1)—点眼縮瞳薬カルピノール液の取扱上の注意に就て
著者: 南熊太
ページ範囲:P.701 - P.707
緒言
点眼縮瞳薬「カルピノール」は,合成の縮瞳,眼圧低下剤でCarbaminoilcholin chloridなる化学組成を有し,縮瞳薬の極度に払底し,エゼリン,ピロカルピン等の品切れにて緑内障治療に困却を来していた所も相当多かつたろうと思われる昭和22年4月,大阪大学に於て行われた日本医学会眼科分科会の際に厚生省に申請されて田辺製薬株式会社から,発売することになつたものにして,此の眼科分科会席上,庄司教授から一般会員にも縮瞳点眼薬としでPilocarpin, Eserinの代用に充分なることを紹介されている。
其の後此のCalpinolは点眼用としては縮瞳,眼圧低下作用等に就て色々の実験が色々の人々により行われ,報告されている。
談話室
欧米旅日記(その1)
著者: 萩原朗
ページ範囲:P.710 - P.716
1昨年11月3日日航で羽田空港を飛立ち,米国を始めとして英,仏,独,瑞(西)和,丁,瑞(典),諾,伊10カ国を廻つて,昨年10月17日羽田に帰着致しました。中泉主幹から何か帰朝の挨拶を書くようにとのことでありましたので,格別纒つたお話しもありませんが,只通つて来た道順を竝べる程度で,想い出すまゝに禿筆を走らせることに致します。
私の1カ年間の外遊が決つたのは,1昨年の初めのことでしたが,種々の都合で上記のように11月の上旬まで延びました。その時,私は,1カ年間世界を廻るとしたら,果して東へ向つて出発した方がよいか,或は西へ向つた方がよいかを考えて見ました。11月と云えば所謂向寒の季節です。聞けば米国は,極寒の季節でも,室内は常に日本の5,6月頃の気温に保たれて居るとのこと。それに引換えて欧洲は,暖房の点では米国にはとても及ばない。そうして見れば,寒い間を米国で過し,暖かくなつてから欧洲を廻つたら快適であろうと,そんな横着な考え方が,先ず私の心をぐんぐん米国の方へ引張りました。次に米国は何と云つても当代随一の勢いのよい国です。この国の施設を見て置けば,欧洲へ渡つてから,各国の施設を落着いて批判することが出来るだろう。又米国は暮すにも旅行するにも金の要る国である。
ロンドン便り抄(その1)
著者: 中島章 , 佐藤勉
ページ範囲:P.717 - P.719
9月19日
お元気ですごしですか。私もあとロンドン上陸を待つばかりになりました。私の乗つて居るカントン号以後の英船はスエズ運河国有の件のためにケープタウンを廻る事になり,英仏人のパイロツトはスエズ運河から引揚げてしまいましたから,私は全くすべり込みとゆうわけです。スエズでの上陸は許されないと思い,カイロ行きはすつかり断念して居ましたところが,9月14日の夜船がスエズに着くとエジプト人が乗込んで来て,上陸が出来るとゆうので,早速手続をしました。エジプト人は特に日本人には大変好意的で親切に見物について説明してくれました。
15日早朝上陸して砂漠を80〜90キロメートルの速度でドライヴしてカイロに入りました。有名なカイロの博物館で例のTout Ankh Amenの遺物をみて,その精細な古代文化に全く驚きました。午後Tobgy教授のプライベートオフイスを訪ねました。Tobgy教授は非常に親切で野寄君のhand funds cameraの話をした所が,出来るだけ早く1台送つてくれ,3月のエジプト眼科学会で報告して宣伝してやると言つて居りました。角膜刀と前戻手術の本とその英訳とを贈呈しました。教授が患者を見終えるのを待つて町のレストランえ行き,純エジプト料理を御馳走になりながら色々話をしました。久しぶりでおいしいエジプト米を喰べながら,三井さんがエジプトえ来られた時の話なでを聞きました。
基本情報
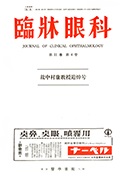
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
