脳梗塞と脳出血の患者について障害脳動脈と眼底所見の関連性を検討し,以下の結果を得た。
(1)穿通枝系動脈の脳梗塞患者と脳出血患者では高血圧症の合併率が高かった。穿通枝系脳梗塞患者の多くは罹病期間8年以上の高血圧症を合併し,穿通枝系脳出血患者の多くは高度の高血圧症を合併していた。
(2)脳梗塞患者の眼底所見のうち,網膜動脈硬化性変化Ⅱ度以上の出現頻度は穿通枝系脳梗塞患者で高く,皮質枝系脳梗塞患者では低かった。特に高血圧症の罹病期間が8年以上の穿通枝系脳梗塞患者で高く,高血圧症を合併しない皮質枝系脳梗塞患者で低かった。
また高血圧性変化Ⅱ度以上の出現頻度は皮質枝系脳梗塞患者に比べて穿通枝系脳梗塞患者の方がやや高かった。しかし,網膜動脈硬化性変化ほど両脳梗塞患者間に差はなかった。
(3)穿通枝系脳出血患者の眼底所見のうち,高血圧性変化Ⅱ度以上の出現頻度はいずれの脳梗塞患者よりもはるかに高く,特に高度の高血圧症合併例では高かった。しかし,網膜動脈硬化性変化Ⅱ度以上の出現頻度は高くなかった。
以上の結果から,次の結論を得た。
(1)眼底の網膜動脈硬化性変化は長期間の高血圧症を共通の因子として,穿通枝系脳梗塞には関連性をしめすが,皮質枝系脳梗塞には関連性をしめさない。
(2)眼底の高血圧性変化は高度高血圧症を共通の因子として穿通枝系脳出血に関連性をしめす。
(3)眼底検査は脳動脈のうち,穿通枝系動脈の病変を推察するうえで臨床上,有力な手段である。
雑誌目次
臨床眼科36巻6号
1982年06月発行
雑誌目次
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
学会原著
脳卒中における障害脳動脈と眼底所見の関連性について
著者: 中尾雄三
ページ範囲:P.545 - P.549
眼瞼・眼窩腫瘍における細胞診について
著者: 麻薙薫 , 石川清 , 中村泰久 , 堀内文男
ページ範囲:P.551 - P.555
1975年より108例の眼瞼,眼窩部腫瘤に対し,穿刺吸引細胞診を行い,その結果を病理組織所見と対比検討を行い,以下の結果を得た。
(1)病理組織学的に悪性腫瘍と診断された症例に行った細胞診において,class IV, Vの悪性腫瘍細胞は76.396認められ,悪性を疑うclass IIIの異型細胞は18.4%に認められた。
(2)細胞診による悪性腫瘍の病理組織像の推定は68.4%に可能であった。
(3)病理組織学的に良性と診断された症例ではclass IV, Vの誤陽性はなく,class I,IIのものが84.2%であった。
(4)細胞診による良性腫瘍の病理組織像の推定は44.7%に可能であった。
したがって本法は腫瘍の良性,悪性の診断のみならず,かなりの高率で組織像をも推定できるため治療方針を決定する上で重要な検査法である。
眼瞼部悪性腫瘍の治療について
著者: 吉田博 , 松田久美子 , 坂上英 , 黒木悟 , 村上順子 , 中野可古
ページ範囲:P.557 - P.560
1979年7月より1981年6月までの最近2年間に広範な眼瞼部悪性腫瘍と診断し治療を行った8症例につき検討し報告した。
腫瘍が上もしくは下眼瞼全体に広がっていたものが6例,上下両眼瞼にわたっていたものが1例,上眼瞼から眼球壁に及んでいたものが1例であった。病理組織所見では扁平上皮癌4例,基底細胞癌2例,脂腺癌2例であった。治療は手術療法を原則として,眼瞼形成術を併用した腫瘍摘出術を6例に施行し,腫瘍摘出術に眼球摘出術を併用したものが1例であった。術後に後療法として放射線療法を3例に施行した。
川崎病における眼病変の臨床像
著者: 大野重昭 , 宮島輝英 , 樋口真琴 , 吉田篤 , 松田英彦 , 佐伯義人 , 富樫武弘
ページ範囲:P.561 - P.566
川崎病(小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群,MCLS)における眼症状の詳細を知る目的でprospective studyを行い,本症にて小児科を受診した患者15例を無作意にえらんで眼科検査を行った。その結果,球結膜充血が93%,虹彩毛様体炎が73%と高頻度にみられたほか,表層性角膜炎が20%,硝子体混濁が14%,そして結膜下出血が7%の患者に認められた。しかし毛様充血や網膜血管炎,網脈絡膜炎は本病患者ではみられなかった。結膜充血および虹彩毛様体炎は全例両眼性であり,しかも病日の経過とともに両眼が同一経過をたどり左右差はみられなかった。両眼の主要症状は病口,赤沈値,CRPとの間に有意の相関を示した。本症でみられた眼症状の予後は良好で重篤な合併症は認められなかった。これらの成績をもとに,川崎病における眼病変の臨床像について考察を加えた。
シェーグレン病の眼科的治療に関する研究—第1報涙液膜のbreak-up timeおよび粘性剤点眼液の影響
著者: 宮川公博
ページ範囲:P.567 - P.571
シェーグレン病における乾性角結膜炎の治療を目的として,粘性剤を含有する人工涙液を作製した。作製にあたり,患者の涙液膜を安定に保つため,最適粘性剤濃度を検討した。0%,0.1%,0.3%,0.4% hydroxyethyl celluloseおよび1%,3%chondroi—tin sulfateを点眼し,その前後の涙液膜のbreak-up timeを測定して検討を行った。従来のbreak-up time測定法では,涙液量の少ない乾性角結膜炎患者の涙液膜に影響が大きいため,必要最少量のfluorcsceinを使用する変法を用いた。
患者のbreak-up timeは正常者に比し有意に短縮していた。点眼後のbreak-up timeは粘性剤濃度の高いものほど延長していたが,0.3%と0.4%のhydroxycthyl celluloseでは有意差がなかった。3%chondroitin sulfate,点眼後は特に強く延長し,正常者と有意差が認められなかった。
シェーグレン病の乾性角結膜炎患者の涙液膜を安定に保つため,人工涙液には適量の粘性剤を含有させる必要がある。
スギ花粉症治療薬の定量的効果判定
著者: 三国郁夫 , 外川国人 , 水島規子
ページ範囲:P.573 - P.576
通年性のスギ花粉症患者10例に,非発作期に誘発試験を行い,0.08%Ketotifen®点眼薬の定量的効果判定を行った。有効率は80%であった。点眼時一過性のしみる感じが30%にあった。
異常な臨床像を示した症例を含む急性出血性結膜炎の流行について
著者: 青木功喜 , 加藤道夫 , 大塚秀勇 , 石井慶蔵 , 中園直樹 , 宇田川素子
ページ範囲:P.577 - P.581
1981年2月に一眼科診療所において2週間余の期間に臨床的に急性出血性結膜炎(AHC)と推定される84例の多発を経験した。このうち63例についてはウイルス分離と組血清による中和試験を行い,ウイルス分離は不成功であったが,血清学的にEV70感染と決定できた。
この多発は血清学的所見および疫学的所見から同一伝播鎖によるものと推定できた。角膜潰瘍,虹彩炎を伴ったEV70感染としては異常と思われる症例が初発例であったことがまず注目される。次にアデノウイルス感染を血清学的に否定したうえで,少数であるが血清学的に低応答または無応答の症例が認められた。この多発において諸眼症状,耳前リンパ腺症の頻度を観察したが,若年者より60歳以上の高年者で低率で,殊にAHCの特微的症状である結膜下出血では有意差がみられ,特に高年者における不全型例の存在が指摘でき,感染防止などの面からも論じた。
酵素抗体法による単純ヘルペスウイルスのIDU感受性試験の試み
著者: 吉田秀人 , 坂田広志 , 日山昇 , 近藤英明 , 岩本俊之
ページ範囲:P.583 - P.586
角膜ヘルペス患者から分離したherpes simplex virus (HSV)17株について,酵素抗体直接法を利用したIDU感受性試験を行い,つぎのような結果が得られた。
(1) HSV 17株の全例で,5μg/ml以下のIDU感受性が認められた。
(2)螢光抗体法に比べて,操作時間が長くなるという欠点はあるが,通常の光学顕微鏡による観察が可能である。また,永久保存もできるという長所がある。
(3)技術操作は簡単で,臨床的応用は十分に可能と考えられる。
新しい抗真菌剤ketoconazole (KW−1414)内服による角膜真菌症2例の治療経験
著者: 石橋康久
ページ範囲:P.587 - P.592
48歳女性の右眼,および44歳男性の左眼に認められた2例の角膜真菌症に対して新しく開発された抗真菌剤であるketoconazoleの内服療法を試みた。第1例では1日300mgから100mgを内服し,治療57日間,総量13,000mgで眼前手動弁であった視力が矯正0.6に回復し,潰瘍も消失,淡い混濁を残して治癒した。第2例でも1日300mgから100mgを内服し,治療20日間,総臆4,700mgで,矯正0.6であった視力が矯正1.2まで改善し,極く淡い混濁を残して治癒した。両者とも薬剤の重篤な副作用は認められなかった。なお第2例より分離されたFusarium solaniに対するketoconazoleのMICを測定した結果250μg/mlであった。また同菌をウサギ角膜に接種し治療群と対照群に分け,1日1回100mgの内服を治療群に行った結果,治療群は対照群に比較して炎症の程度がやや低くなる傾向のあることがわかった。
Graph pen digitizerによる生体角膜内皮細胞面積測定—その3水晶体嚢外摘出眼と人工水晶体移植眼の経時的変化
著者: 鈴木一成 , 深尾隆三 , 池田定嗣 , 永田誠 , 瀬川義朗
ページ範囲:P.593 - P.597
specular microscopeおよびdigitizer法を用いて,水晶体嚢外摘出14眼,Shear—ing lens挿入17眼およびiridocapsular lens挿入13眼の術前,術後1,3,6カ月目の角膜内皮細胞の形態的変化について経時的に検討した。
(1)平均細胞面積は嚢外摘出眼,人工水晶体挿入眼とも1ヵ月以内に拡大し,1ヵ月以後から6ヵ月目まではほとんど不変であった。
(2)平均細胞面積の増加率は嚢外摘出眼,Shearinglens挿入眼,iridocapsular lens挿入の角膜内皮—人工レンズ非接触眼,iridocapsular lens挿入の角膜内皮—人工レンズ接触眼の順に増加していた。
(3)人工水晶体挿入時,角膜内皮に接触したのはShearing lens 1眼(6%),irido—capsular lens 5眼(38%)であった。
(4)嚢外摘出眼,Shearing lens挿入眼,iridocapsular lens挿入の非接触眼は大型細胞の出現と細胞面積のばらつきが少なく,それに比しiridocapsular lens挿入の接触眼は大型細胞の高率な出現と細胞面債のばらつきが著明であった。
Posner-Schlossman症候群の角膜内皮について
著者: 川俣達男 , 岩下正美 , 村松隆次 , 浜田嶺次郎
ページ範囲:P.599 - P.603
Posner-Schlossman症候群患者15名の角膜の厚さと角膜内皮細胞の形態計測を行い次の結果を得た。
(1)患眼と健眼の細胞面積には有意差(Pく0.001)を認め,発作回数と相関して細胞面積は増大した。
(2)患眼と健眼の細胞周長も面積と同様右意差(P<0.001)を認めた。
(3)角膜の厚さ,形状係数では患眼と健眼および正常眼の間に有意差は認めなかった。
出生時デスメ膜破裂と角膜内皮細胞
著者: 矢野眞知子 , 神鳥高世 , 佐藤孜 , 谷島輝雄
ページ範囲:P.605 - P.609
片眼のデスメ膜に皺襞があり,鉗子分娩の既往のある8症例および鉗子分娩既往のない8症例,合計16症例の臨床所見,角膜内皮細胞の形態計測の結果を報告した。鉗子既往例では,鉗子既往のない例と比較すると,視力不良の例が多く,角膜乱視が高度な例が多かった。強主径線とデスメ膜皺襞との関係は鉗子既往例では平行となっている例が多く,既往のない例では一定ではなかった。
角膜中央部の内皮細胞をspecular microscopeで写真撮影し,画像解析装置で面積測定した結果,全例患眼の内皮細胞面積は,健限より拡大していた。内皮細胞面積は,鉗子既往の有無による差はなく,視力,角膜乱視,角膜厚との間に相関はみられなかった。
炭酸ガスレーザーによる角膜手術について
著者: 中路裕 , 池部均 , 井上節 , 田村邦嘉 , 佐々本研二 , 小玉裕司 , 糸井素一
ページ範囲:P.611 - P.614
家兎角膜を用い,炭酸ガスレーザーとサーモペンシルによる角膜熱形成術を行い,角膜形状の変化と形態学的変化を比較した。
その結果,両者同等に角膜を変形させることができた。また適切な条件を没定すれば,炭酸ガスレーザーは臨床的に角膜熱形成術に使用できる可能性があると考えられた。
人工水晶体移植術と角膜内皮障害について
著者: 松浦みち子 , 木崎宏史 , 高橋春男 , 深道義尚
ページ範囲:P.615 - P.619
人に水晶体移植術後の角膜内皮障害を水晶体全摘出術および二つの術式ごとに比較してみた。
術後3ヵ月における細胞密度の減少率は,水晶体全摘出術では11%,超枠波乳化吸引術(KPE)は13%, KPE後に後房レンズ挿入したものでは15%,計画的嚢外摘出術では18%,計画的嚢外摘出術後に後房レンズ挿入したものでは19%であった。
これより,人工水晶体挿入による角膜内皮障害はほとんどないものと考えられた。また,KPEと計画的嚢外摘出術では角膜内皮障害に関してはKPEの方がすぐれていた。
混合感染を伴うヘルペス性角膜炎の検討
著者: 北川和子 , 山村敏明 , 佐々木一之
ページ範囲:P.625 - P.631
金沢医科大学眼科外来を1979年,1980年の2年間に受診した角膜ヘルペス患者27例について,細菌の分離同定および薬剤感受性の検討を行い,47例の角膜潰瘍眼,159例の健常眼よりの分離菌との比較を試み以下の結論を得た。
(1)角膜ヘルペス患者27例中13例が培養陽性であり,そのうち6例が混合感染と考えられた。混合感染例の起炎菌はStaphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, StreptoceccusPneumoniae,α—StrePtecoccus, Diphtheroid, Moraxellaなどであり,いずれも適切な抗生剤の投与が治癒を促進した。
(2)対象眼より最も多く分離されたものはStaphylococcus epidernzidisであり,そのEM耐性株の占める比率は角膜ヘルペス群が最も高く,ついで角膜潰瘍群,健常群の順であった。
(3)角膜ヘルペス眼における混合感染の診断は病歴・角膜所見・培養結果(菌種およびコロニー数)・治療効果などにより総合的に行うことが必要であり,経過中には細菌培養および薬剤感受性をくりかえし行うことが治療の上できわめて重要とおもわれる。
学術展示
外転神経麻痺で発症した硬膜海綿静脈洞瘻
著者: 照林宏之 , 田村邦嘉 , 薗田桂子
ページ範囲:P.632 - P.633
緒言海綿静脈洞内の静脈圧上昇により,眼症状を示すことは,よく知られている。さらに初発症状が眼症状のみであることも比較的多い。しかし,この原因疾患の中で,硬膜海綿静脈洞瘻は非常にまれなものである。1966年にCastaigneら1)により初めて報告されて以来,30例あまりしか報告されていない。われわれの経験した硬膜海綿静脈洞瘻の1例は,初発症状が外転神経麻痺であること,約1年の経過観察にて自然治癒傾向を示したことの点で興味がもたれここに報告する。
症例:65歳,女性。
頭蓋Hyperostosisに伴う視野変化
著者: 大久保潔 , 藤井啓誠 , 溝上国義 , 諌山義正
ページ範囲:P.634 - P.635
頭蓋Hyperostosisに伴う視野変化についての報告例は少なく,特に視野変化の特徴および進行のパターンについての報告はみられない。
今回我々は4例の頭蓋Hyperostosis症例において,それぞれの視野変化を示し,共通した特徴および視野障害の進行のパターンについて分析し報告する。
Tonic pupilにおける周波数特性
著者: 新富芳子 , 粂田信一 , 長田廉平 , 加瀬学
ページ範囲:P.636 - P.637
Tonic pupilを呈する症例の全身的臨床像には多くの変動がみられ,腱反射異常を伴う定型的Adie症候群の他,近年は多様な全身疾患との合併が報告されている1〜3)。我々は先にこれらtonic pupilの瞳孔運動障害の経時的変化を比較し,定型的Adie症候群と全身疾患に伴うtonic pupilとの発生機序の相違を推定した4)。今回は,その発生機序をさらに検討するためインパルス光刺激による対光反応パターンをシステム工学的に解析した。
対象と方法片眼性の定型的Adie症候群7名,全身疾患に伴うtonic pupil 5名(polyneuropathy 2名,vi—ral cncepharitis 1名,varicella 1名,syringomyelia 1名),対照として正常人におけるトロピカマイド点限前後の瞳孔運動を測定した。測定には赤外線電子瞳孔計を用い,ハロゲンを光源とし角膜面1lux, 100msecの光刺激による間接対光反応を記録した。その波形をフーリェ変換し,周波数特性をボード線図で表わし,瞳孔運動系の伝達函数を推定した(図1)。
視神経乳頭部腫瘍の2症例
著者: 有田達生 , 岡村良一
ページ範囲:P.638 - P.639
視神経乳頭の血管腫は比較的まれである。視神経乳頭の血管腫と思われる2症例を経験したので報告する。
症例1:30歳の主婦。数年来,右視力低下を自覚していたが,頭痛,めまいがおこり,歩行障害もきたしたため,熊大脳外科受診。CTにて左小脳半球に広範な,ほとんどenhanceされていないlow density areaがあり,右視神経乳頭部に腫瘤が認められたため,当科を紹介された。その後,小脳腫瘍の全摘術を受け,組織診でan—gioblastomaと診断された。他に全身的な合併症は認められていない。
糖尿病性網膜症に対する汎網膜光凝固術の効果について(予報)
著者: 能美俊典 , 渡辺正樹 , 松浦啓之 , 山本由香里 , 瀬戸川朝一
ページ範囲:P.640 - P.641
1960年ルビーレーザー装置が実用化されて以来,その眼科領域への応用が幾多の先人によってなされ,ことに増加傾向にある糖尿病性網膜症に対する治療効果が多数報告されている。従来,重症糖尿病性網膜症に対して病巣凝固が行われたが,病変の進行阻止効果は少なく,最近は網膜全体に侵襲を及ぼす汎網膜光凝固療法(以下PR.Pと略)による治療効果が検討されている1,2)。当科でも先に報告した例3)に加え,新たにPRPを行ったPRP症例についてその効果を検討した。
対象は1979年10月以後当科を受診しPRPを行い,3カ月以上経過観察ができた症例とした。性別では,男13例20眼,女23例36眼,計36例56眼である。年齢は26〜74歳(平均54歳),糖尿病歴は1〜33年(平均12年),経過観察期間は最短3カ月,最長18カ月(平均8カ月)である。適応例としては,網膜中間周辺部に広範な毛細血管非灌流域があり,かつその近位の毛細血管拡張・透過性亢進の強い活性病変を示すもの,比較的大きい静脈のうっ血い拡張・コイル状〜結節状変形などいわゆる前増殖期性病変を有するも,いまだ血管新生を認めないものなど単純型網膜症20眼と乳頭・網膜上に新生血管を有する増殖型網膜症36眼を対象とした。
糖尿病患者における白内障手術の遠隔成績
著者: 三木正毅 , 鈴木まち子 , 近藤武久
ページ範囲:P.642 - P.643
糖尿病患者の白内障手術においては,出血,炎症や感染などの危険性が高く,また糖尿病性網膜症を進行させる場合があるなどの理由で,一般に慎重な適応の決定や,術前術後のコントロールが必要であるといわれる。われわれはその実態を把握し今後の研究の基礎にしようとして,まず視力予後を中心に,本調査を行った。対象としたのは,1976年4月から1977年12月の間に白内障手術を行った症例で,糖尿病と診断されていた患老61例100眼のうち,長期観察ができた29例50眼で,4年以上経過観察したものが22例38眼になる。
表1に糖尿病性網膜症を認めない症例の術後矯正視力を挙げるが,最終視力で0.5以上のものが92%で,経過中明らかな網膜症の発生をみたものはなかった。表2は単純型網膜症の術後矯正視力で,網膜症のない例と大差はなく,最終視力0.5以上が81%である。この中には嚢外摘出術を施行した例が1眼含まれている。以上の症例のうち,術直後に前房出血を認めたもの3眼と術後前眼部炎症が強かったもの3眼があるが,最終視力には余り関係があるとはいえず,緑内障等大きな併発症は認めていない。また入院時の血糖値と炎症や出血,最終視力との間にも相関は認めていない。これに反して増殖型網膜症は,術後視力が悪く,0.5以上が35%と多くが視力不良例で,最終視力でみると,更に低下し0.5以上は1例のみとなっている。
糖尿病眼底管理方式に関する研究
著者: 福田雅俊 , 小室優一
ページ範囲:P.644 - P.645
緒言糖尿病性網膜症(以下網膜症と略す)の経過を比較検討する場合,眼底写真の比較により客観的に判定する方式をとることが近年盛んとなってきたが,網膜症の経過を追跡する記録手段としては,螢光眼底造影検査による方式(以下螢光と略す)と,単純なカラー眼服底写真による方式(以下カラーと略す)があり,両方式の差を検討した報告はほとんどない。筆者らは近年約300名の網膜症の経過を螢光とカラーの両方式によって2年間追跡する機会があり,両方式の比較を試みたのでここに報告する。
実験方法内科医による全身管理が十分行われている糖尿病患者286名(東大第三内科159名,東京女子医大糖尿病センター127名)の約400眼を対象に,螢光とカラーの両方式により定期的に眼底所見を記録し,2年間追跡した。螢光は初診時・(実験開始時)と12カ月後,18カ月後,24カ月後の4回記録し,毎回右限よりフルオレセインソジウム(10%)5cc静注直後から約3分間に後極部乳頭・黄斑を中心に15枚,次に左眼を引続き約3分間に15枚撮影した。カラーは初診時と6カ月後,12カ月後,18カ月後,24カ月後の5回記録し,毎回両眼共にAirlie分類指定1)に準じた後極部6枚を撮影した。
糖尿病性網膜症における眼循環動態—II.循環量に関する臨床的検討
著者: 山本保範 , 西川憲清 , 中川成則 , 竹本環 , 福田全克 , 別所建夫
ページ範囲:P.646 - P.647
緒言我々は先に超音波血流計を用い,眼動脈流速脈波を得,その解析から,内頸動脈の狭窄・閉塞例では,糖尿病性網膜症に進行が見られることを報告した1)。このことは,macroangiopathyが網膜症の経過に何らかの影響を与えることを示している。そこで,今回は網膜症に影響を与える眼循環状態をより正確に把握するため,眼動脈流速脈波に加え,眼動脈拍動容積を計測することにより循環鍋の面からも検討した。
方法超音波Doppler血流計(日立メディコ社EUB−3D)およびサウンドスペクトログラフ(リオン社SG−07)を使用し,眼動脈血流音を流速脈波として描き解析した。またOphthalmodynamography (Boucke社ODG−350型)(図1)を使用し,眼窩カプセルにて眼窩全体を圧迫して得られる最大脈拍振幅と,検量拍動装置で50μlの人工的拍動を眼窩代用容積に加えることにより得られる検量容積振幅との比から,眼動脈拍動容積を求めた。
Saccadic reaction timeに関する研究—精神薄弱,びまん性大脳萎縮および頭頂葉障害例について
著者: 福島正文
ページ範囲:P.648 - P.648
緒言固視反射で行う衝動性眼球運動は突然の視標の動きに対して視覚系だけで行う視性衝動運動と聴覚刺激で発動し視標を捕える聴性衝動運動に分けることができる。この2種類の衝動性眼球運動潜時(saccadic reac—tiontime:以下SRTと略す)は求心性経路や知覚認知過程の違いにより正常被検者でも異なることは既に報告した1)。今回,これらの正常SRTをもとに精神薄弱,びまん性大脳萎縮および頭頂葉障害例における視性と聴性SRTを比較検討した。
方法衝動性眼球運動は左右10°へのcccentricとcen—teringの4通りを視性と聴性に分け行った。視性衝動運動は浜松テレビ視標運動誘発装置を用い,聴性衝動運動はクリック音をヘッドホンで両耳同時に聞かせtrig—gcrとした。記録はDC-EOGを用い,増幅後storageoscilloscopeに描記した。これを写真撮影し,分析はTalos digikitizerとNEC PC−8001マイクロコンピューターシステムにて行った。検定はT検定を用いた。
Myotonic dystrophyの眼球運動異常について
著者: 郡司隆一 , 桐渕利次 , 丸尾敏夫
ページ範囲:P.649 - P.649
Myotonic dystrophyは遺伝性の全身系統疾患で,眼科的には,白内障,眼瞼下垂,眼球陥凹,低眼圧,瞳孔異常,眼球運動障害および網膜病変など多彩な症状を呈することが知られている1,2)。全身所見や眼所見では白内障や網膜病変について詳細な報告がなされているが,眼球異常についてのくわしい報告は少ない。Myotonicdystrophyに伴う眼球運動異常は比較的まれとされているが,眼球運動障害がある場合には内転障害からはじまって進行性の全眼筋麻痺3)の形をとるとされている。
今回われわれは,両眼の内転障害を示したMyotonicdystrophyの2症例を経験したのでここに報告する。
連載 眼科図譜・295
Argon laser iridotomy
著者: 白土城照 , 山本哲也 , 北沢克明
ページ範囲:P.542 - P.543
緒言閉塞隅角緑内障に対するレーザー虹彩切開術は,非観血的に前後房間に交通路を形成する優れた方法であり,既に我々は本法が日本人の茶褐色虹彩でも十分に有用である事を報告している1〜3)。今回我々は対象例を増やし殊にその合併症について検討を加えたので報告する。
対象および方法対象は閉塞隅角緑内障59例68眼で,原発閉塞隅角緑内障57例66眼(急性発作9眼),続発閉塞隅角緑内障2例2眼であり,術後観察期間は1ヵ月〜1年10ヵ月である。
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(7)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斉藤仁男
ページ範囲:P.652 - P.653
13.眼書一流之秘伝
古写本に記された年代には秘伝などの授受によって書き込まれるものと,その書きとめられたものが後世において書写相伝された時に記される書写年代とがある。眼科諸流派の秘伝書においてもこの原本成立年代と書写相伝年代の異なるものがままある。「眼書一流之秘伝」はそうした類に入る古写本である。
「眼書一流之秘伝」は36葉全1冊,横長本で,淡青色手漉和紙に達筆な平仮名にて丹念に記述された古写本である。各見出しの文末識語年代には天正5年,文禄元年,慶長9年および元和3年等の年号が記されているが,この写本が実際に書かれた年代は筆跡,朱墨の濃淡等の具合から元和3年以降の書写と思われる。
臨床報告
視神経疾患における視覚の疲労現象とサングラス処方への応用
著者: 大沼貴弘 , 田上勇作 , 諫山義正
ページ範囲:P.655 - P.658
視力の回復した視神経疾患患者に対し,レーザー干渉縞視力を経時的に5分間測定した。
高輝度下(平均輝度1500cd/m2)では全例に経時的な視力の低下が観察されたが,Ttibinger静的中心視野,VECPにおける障害程度の相関は認められなかった。
またJIS規格による一般事務の適正照度に相当する平均輝度250cd/m2においても36例中6例に低下が観察された。この6例に対し,疲労現象の軽減を目的としたサングラスの処方を行ったところ,患者の訴えが少なくなり,視神経疾患患者の日常の視作業を容易に遂行する上で,臨床的に極めて有用と考えられた。
水俣病にみられるsquare wave jerks
著者: 石川哲 , 向野和雄 , 村田悦子 , 山上晴子 , 鵜飼一彦 , 岡村良一 , 皆良田研介
ページ範囲:P.659 - P.664
典型的な水俣病(MD)患者10例と,ほぼ同年齢の正常者10名について,赤外線光電素子を装着した眼鏡を利用し,固視微動を中心とする眼球運動をphoto-electricな方法で記録し分析した。固視標は横8mm,縦15mmの光源を眼前2mに置き,暗所,点灯,filter挿入により,対数的に固視標の光を変化させながら記録した結果,次のような事実が判明した。
患者全例にsquare wave jerks (SWJ)が,暗所および明所でみられた。正常者で認めた例は10例中4名で,しかも3例は暗黒時のみ認められた。患者のSWJの持続時間(dura—tion)は正常者より有意に延長していた。頻数(frequency)は,正常者より頻発し,固視標の光が強くなれば増加する傾向を示した。また,振幅(amplitude)は,暗所においては正常者の2倍近くであり,固視標が明るくなるに従って,抑制されていく傾向にあった。今回最も興味のあった事実は,共働性ではないdisjugate SWJの検出である。1眼は大きなsaccadeの後,stair caseでfoveationを行うもので,他眼はそのsaccadeの向きは同じであるが,中心窩に戻る動きはsmoothな眼球運動成分に加えて,最後にfoveatingsaccadeで補正されるという,disjugateな運動である。この異常波形は10例中6例に認められた。
Pneumatonograph®用sensor固定装置の試作とその使用成績
著者: 小鹿倉寛 , 塩谷容子 , 高橋信久 , 近藤邦彦
ページ範囲:P.665 - P.668
従来,検者の手持ちで測定が行われていたAlcon Applanation PneumaticTonometer (PneumatonographD)のsensor固定装置を試作し,正常眼の眼圧測定に試用した結果,眼圧測定値の安定性と精度の向上と,測定時の被検者と検者の双方の緊張と疲労の軽減をもたらすことができ,臨床的に有用なことを確認した。
さらに,本固定装置の使用の有無での測定値とGoldmann Applanation Tonometerでの測定値について比較検討を行った。
GROUP DISCUSSION
眼先天異常
著者: 馬嶋昭生
ページ範囲:P.669 - P.675
1.高度の上眼瞼欠損を示したGoldenhar症候群の1例
Goldenhar症候群の眼症状には,三主徴の一つであるepibulbar dermoidまたはlipodermoidの他様々なものがあるが,高度の上眼瞼欠損により角膜障害を来した報告は少ない。
症例1生後1日目,男児,第2子,妊娠分娩に異常なく,家族歴にも特記すべきことはなかった。全身状態も良好であった。
基本情報
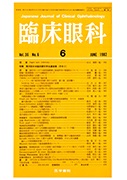
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
