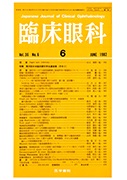文献詳細
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
学会原著
文献概要
金沢医科大学眼科外来を1979年,1980年の2年間に受診した角膜ヘルペス患者27例について,細菌の分離同定および薬剤感受性の検討を行い,47例の角膜潰瘍眼,159例の健常眼よりの分離菌との比較を試み以下の結論を得た。
(1)角膜ヘルペス患者27例中13例が培養陽性であり,そのうち6例が混合感染と考えられた。混合感染例の起炎菌はStaphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, StreptoceccusPneumoniae,α—StrePtecoccus, Diphtheroid, Moraxellaなどであり,いずれも適切な抗生剤の投与が治癒を促進した。
(2)対象眼より最も多く分離されたものはStaphylococcus epidernzidisであり,そのEM耐性株の占める比率は角膜ヘルペス群が最も高く,ついで角膜潰瘍群,健常群の順であった。
(3)角膜ヘルペス眼における混合感染の診断は病歴・角膜所見・培養結果(菌種およびコロニー数)・治療効果などにより総合的に行うことが必要であり,経過中には細菌培養および薬剤感受性をくりかえし行うことが治療の上できわめて重要とおもわれる。
(1)角膜ヘルペス患者27例中13例が培養陽性であり,そのうち6例が混合感染と考えられた。混合感染例の起炎菌はStaphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, StreptoceccusPneumoniae,α—StrePtecoccus, Diphtheroid, Moraxellaなどであり,いずれも適切な抗生剤の投与が治癒を促進した。
(2)対象眼より最も多く分離されたものはStaphylococcus epidernzidisであり,そのEM耐性株の占める比率は角膜ヘルペス群が最も高く,ついで角膜潰瘍群,健常群の順であった。
(3)角膜ヘルペス眼における混合感染の診断は病歴・角膜所見・培養結果(菌種およびコロニー数)・治療効果などにより総合的に行うことが必要であり,経過中には細菌培養および薬剤感受性をくりかえし行うことが治療の上できわめて重要とおもわれる。
掲載誌情報