当大学における白内障手術患者から凍結法によって摘出して得た水晶体80眼について水晶体重量,水分量,電解質(Na+,K+),糖および糖アルコール(Fructose, Sorbitol,Glucose, Inositol)およびうち30眼についてAldose reductase activityを測定し,次の結果を得た。
(1)成熟期(老人性および糖尿病性白内障)で著明なNa+,Na/K比,含水率の上昇,K+の減少が認められた。水晶体重量はいずれも変化がなかった。
(2) Glucoseは成熟期に多く,未熟期に少なく,Inositolはこれと正反対の変動を示した。SorbitolとFructoseは未熟期に多く認められ,「老人」と「糖尿病」の比は2分の1〜3分の1であった。成熟期になるとSorbitolとFructoseはほとんど認められなくなった。
(3)未熟期「老人」にGlucose 50g経口負荷を行ったところ,水晶体中の糖および糖アルコールは,糖負荷を行わなかった症例に比し,有意差は生じなかったが,すべてに増加を示した。
(4)「老人」未熟期においては糖負荷の有無にかかわらず,水晶体内においてGlucose量の多いものほどFructose+Sorbitol量も多かった。
(5)水晶体Aldose reductase活性は成熟期には低下しているが,未熟期では「老人」に最も高く,有意差はないが「糖尿病」がこれに次いで高かった。
雑誌目次
臨床眼科36巻7号
1982年07月発行
雑誌目次
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
学会原著
老人性白内障における糖および糖アルコールについて
著者: 藤原隆明 , 尾羽澤大 , 三国郁夫 , 長尾玉子 , 佐藤薫 , 山本佑二郎
ページ範囲:P.687 - P.692
ヒト先天性白内障水晶体の組織学的検討
著者: 浜井保名 , 高橋茂樹
ページ範囲:P.693 - P.698
白内障手術(水晶体全摘出術)によって得られた5例6眼の先天性白内障水晶体の組織所見について,光学顕微鏡および電子顕微鏡にて検討した。
症例のうちわけは核白内障1例1眼,層間白内障1例2眼,皮質および点状白内障1例1眼,全白内障2例2眼である。
先天性白内障水晶体の混濁部は白内障の種類により異なっていたが,水晶体細胞の病的変化は類似していた。
混濁部位は異なっていても,各症例に共通して観察された組織学的所見は,bowの存在部位が赤道部より核におよんでいたこと,脱核現象の遅延,細胞内micro-organelleの残存などであった。
これらのことからヒト先天性白内障では,水晶体の栄養障害,蛋白合成の異常,酵素活性低下など何らかの原因による成長の遅れが考えられる。
Buerger病が原因と思われる急性緑内障の1症例
著者: 川端啓子 , 天日和子 , 対馬信子
ページ範囲:P.699 - P.702
malignant glaucoma (direct lens block angle closure glaucoma)と思われる急性緑内障の1例について報告した。症例は38歳男性で15年前よりBuerger病に罹患し,左側下肢を切断している。眼底,結膜の充血怒張,虹彩切除後の著しいぶどう膜炎の状態からBuerger病(閉塞性血栓血管炎)による網脈絡膜の循環障害がこの急性緑内障発作の原因と推定した。
後極部裂孔を有する網膜剥離眼の特徴—黄斑部孔以外の症例について
著者: 坪井俊児 , 井上恵美子 , 額田朋経 , 恵美和幸
ページ範囲:P.703 - P.707
後極部に裂孔を有する網膜剥離で,黄斑部孔以外の症例12例12眼を検討した。発生頻度は,網膜剥離全体の2.4%であった。これらは,性格の異なる3群に分れた。I群は傍血管小裂孔を伴い,高度近視眼で著明な後部ぶどう腫を認めた。II群は比較的大型の馬蹄型裂孔を伴うもので,これらも高度近視眼であったが,中間部(周辺部)裂孔との境界症例と思われた。III群では高度近視は認めなかったが,血管病変に合併するものであった。12例とも程度の差はあれ,硝子体牽引を認めた。裂孔周囲の硝子体牽引が,黄斑部孔との相異点であり,治療成績を左右する原因になりうるものと思われた。
レーザー散乱光によるヒト水晶体核蛋白粒子の直径計測
著者: 馬嶋慶直 , 湯浅英治 , 田中豊一 , 西尾泉
ページ範囲:P.709 - P.712
He-Neレーザー光を水晶体核に集束し,その散乱光より,核蛋白粒子の直径を測定した。白色家兎の実験にて,本法が可能であることを確認し,22眼のヒト水晶体核に適用した。スリットランプマイクロスコープにて,その色相に従って混濁核を五つのgradeに分類し,grade 0を正常核,grade 1は淡白色,grade 2は白黄色,grade 3は黄色,grade4はかつ色混濁核とした。各gradeの水晶体核にレーザー光をfocusさせ,その蛋白粒子直径を算出したところ,grade 0では1.12μ,grade 1は1.45μ,grade 2は2.24μ,grade 3は2.76μ,grade 4は2.46μとなり,gradeの上昇に伴い,直径の増加を示した。この粒子直径の増大は,核蛋白の重合の進行を示唆するものと考えられる。我々の用いた装置は,MTFの安全基準ともなったAmerican National Standardに照らして十分安全であり,測定後,視機能低下の愁訴はなく,色ウサギによる照射実験にても,組織学的に障害はみられなかった。白内障発生の予知および発生因子の研究に,本法は有力な手段となると考えられる。
Binkhorst 2loop lens挿入結果とレンズ固定について
著者: 西興史 , 植村恭子 , 西素子 , 細川久子
ページ範囲:P.713 - P.718
1979年10月〜1981年6月の間に,Binkhorst 2loop lensを挿入した46人48眼について統計的観察と,レンズ固定の分析を行った。臨床上問題となった合併症は脱臼の2眼4.2%で観血的に整復し,縮瞳剤の点眼を続行している。レンズが確実に固定されているもの44眼91.7%,レンズと嚢とが癒着していないと思えるもの,4眼8.3%で,この後者4眼と,少なくとも術後数日間は,全例縮瞳剤を与えて,虹彩支持に頼らねばならないのが,このレンズの最も神経を使うところであり欠点といえる。主に嚢内摘出後挿入する,iris medallion lensと比較するとレンズ固定はより確実であり角膜内皮損傷もより少ない。ループと嚢との癒着は,残留した前嚢が後嚢と触れる位置の水晶体上皮細胞の増殖によるものと思われた。現時点で使用に耐えうる人工水晶体の一つと思われるが,わずかであれ,なお脱臼が起りうるので,Shearing型のものが主流になっていくと考えられる。
眼圧調整機構としての微動調節の研究
著者: 小林明美 , 鈴村昭弘
ページ範囲:P.719 - P.723
本研究では調節機能に眼圧調整機能の存在することを明らかにする目的で,β遮断剤(Befunolol hydrochloride)を中心に,その影響を検討した。
その結果,眼圧下降例および房水流出率改善例に微動調節の改善したものが多くみられ,特に高眼圧群により強くその傾向を認めた。このことから,微動調節は眼圧調整機能としての作用の存在が考えられた。
さらに高眼圧症と緑内障とでは,微動調節の眼圧調整機能としての作用の役割に,相違が考えられた。
急性閉塞隅角緑内障における虹彩萎縮の臨床的意義
著者: 松村美代 , 沖波聡 , 原山憲治 , 大熊正人
ページ範囲:P.725 - P.729
急性閉塞隅角緑内障151眼を対象に,虹彩萎縮の発生状況およびその臨床的意義を検討した。虹彩萎縮は年齢の高いほど,また発作持続時間の長いほど発生率が高い。乳頭がpaleで虹彩萎縮のあるものは一般に予後の悪いことが多く,乳頭がpaleでも虹彩萎縮のないものでは予後のよいこともある。虹彩萎縮が存在すれば,比較的強い急性緑内障発作であり,かなり持続時間も長く,予後も悪い可能性が大きいという一つの目安になると思われる。
虹彩萎縮発生率と同様に,初回手術による眼圧調整率は処置までの時間によく相関するが,手術までの時間とは直接関係しない。急性緑内障の予後をよくするためには,虹彩萎縮がおこりにくく,術後の眼圧コントロールの良好な12時間以内に処置をすることが重要であるが,手術そのものを特に急ぐ必要はない。
緑内障性視機能障害と色識別能—特にごく初期例について
著者: 関伶子 , 阿部春樹 , 岩田和雄
ページ範囲:P.731 - P.736
緑内障にみられる色識別能力の異常が,高眼圧症の時期にすでにつかまえうるのか,それとも緑内障となって初めて出現するものか,初期の網膜神経線維層欠損のどの時期にどの様な異常がみられるかを検討するため,コントロールとして正常眼31例46眼,高眼圧症5例10眼および網膜神経線維層欠損の種々の程度の緑内障83例100眼で,Farns—worth-Munsell 100—Hue Testを施行した。
その結果,色識別能力の異常は網膜神経線維層欠損が中等度以上に進行した湖崎分類Hb期以上で,青緑障害を主として必発し,網膜神経線維層欠損が進行するに従い青黄障害となる結果を得た。しかし高眼圧症や湖崎分類IIb期以前の緑内障では有意の異常はみられなかった。これはDranceらの高眼圧症眼で,青緑,青黄障害を伴う色覚障害を認める例は,将来視野障害を来たすという報告と相容れず,その原因についても検討した。
アルゴンレーザーによる開放隅角緑内障の治療(III)—照射直後の眼圧変動について
著者: 田邊吉彦 , 原田敬志 , 浅野隆 , 安間正子 , 稲川寿夫
ページ範囲:P.737 - P.742
薬物治療不良の種々な開放隅角緑内障40眼のtrabeculaeにlaser照射を行い,1時間毎に眼圧測定した。trabeculae 120°にわたって照射したもの14眼.180°にわたったもの18眼,360°にわたったもの8眼の照射後眼圧変動パターンは,基本的には三つの群の間に大差はなかったが,360°照射群では眼圧上昇とflareの増加が120°群に比べて著明であった。
照射後の眼圧上昇には種々の要因が考えられるがPGEの増加がその一つであると思われるデータが得られた。
開放隅角緑内障のlaser治療は計画的に120°ずつ間隔をおき3回に分けて行う方が360°1度に行うよりよいと推論した。
トラベクレクトミー術後の脈絡膜剥離発生について
著者: 内野允 , 吉田公雄 , 江川知子 , 安田典子 , 永楽皓人 , 神力忍 , 景山万里子
ページ範囲:P.743 - P.748
Trabeculectomyと白内障手術の術後経過を観察し術後の脈絡膜剥離発症の様態を調べた。Trabeculectomyでは27眼中15眼56%に脈絡膜剥離の発症がみられたが,白内障手術では74眼中3眼4%に認められたのみであった。Trabeculectomy後多くは2〜4日目に発症し,10日間ほど継続して急速に消褪した。前房深度の平均減少率は発症眼で44%,非発症眼でわずか1%であり,眼圧の平均値は前者で2.8mm,後者で6.4mmHgであった。手術による隅角部組織切除片の大きさと脈絡膜剥離発症との間に相関は認められなかった。発症した全例は散瞳薬とステロイドで治療し,手術的操作は必要とせず重篤な合併症へ進展するものはなかった。脈絡膜剥離の発症には手術による炎症と低眼圧が不可欠因子であるのはもちろんであるが,Trabeculectomy後の発症眼では非発症眼にくらべ,浅前房,低眼圧の程度が極めて強いことから,濾過口形成がこれに最も大きく関与しているものと考える。術後精密に検査をすればTrabeculectomy後の脈絡膜剥離発生は,今までに報告されているものよりはるかに頻度の高いものであることを強調したい。
トラベクレクトミーの奏効機序
著者: 門田裕子 , 沖坂重邦 , 稲垣有司 , 百瀬皓 , 樋渡正五
ページ範囲:P.749 - P.754
原発開放隅角,原発閉塞隅角,先天,続発,嚢性緑内障計69眼を対象に,採取した組織片にトラベクルムを含んでいることを光顕下で確認し,術後1カ月から3年までの経過を観察した。
手術方法はトラベクルムを含むたて長の強角膜片を切除,強膜弁の縫合を十分に行った。術後の眼圧コントロール良好例は95.7%であった。
術後濾過瘢痕を形成したもの27.5%,このうち眼圧コントロール良好のもの94.6%であった。術後濾過瘢痕を形成しなかったもの,観察中に消失したものは72.5%で,このうち眼圧コントロール良好のもの96%であった。濾過瘢痕形成の有無による眼圧コントロールの差は認められなかった。
トラベクレクトミーの奏効機序として結膜下への濾過のみでなく,脈絡膜外隙への房水流出路も考慮すべきであると考えた。
白内障手術早期教育の試み
著者: 平原将好 , 吉村利規 , 黒田純一 , 楫野郁夫 , 倉淵信哉 , 小西則子 , 仲河正博 , 宮野恭子 , 大八木康夫 , 三木敏照 , 上野山謙四郎
ページ範囲:P.755 - P.757
眼科入局2年目に,顕微鏡下白内障手術を,経験者の指導下で,40症例集中的に行った。以後年間10数例程度経験した。その結果は次のとおりであった。
(1)40症例教育期間中の硝子体脱出は,平均5.7%であった。
(2)40症例以後は,平均5.3%であった。
(3)術後視力0.5以上得られたものは,65%であった。
(4)1976年から'80年末までに行われた白内障手術合計1,212眼のうち749眼が,教育目的に使用された。
眼内レンズ手術の増加と視力予後
著者: 越智利行 , 矢田清身 , 桜井やよい , 岡田裕 , 稲富誠 , 深道義尚
ページ範囲:P.759 - P.763
1980年1月より1981年6月までに当教室で行われた白内障手術460例607眼につき,6カ月毎の3期に分け手術方法の推移,合併症,視力予後について検討した。
(1)当教室において近年全摘術が減少し,KPEを用いた嚢外摘出術が増加し,さらに人工水晶体挿入例が増加している。
(2)人工水晶体挿入例では,患者の平均年令は次第に高齢化の傾向にある。
(3)使用した人工水晶体は後房レンズが主流となってきており,3期では95%が後房レンズであった。
(4)人工水晶体挿入例の術中術後の合併症も全摘術と比較し,特に問題となるものはみられない。
(5)人工水晶体挿入例では術後早期より良好な視力が得られた。
角膜内皮障害,人工水晶体の耐用性など種々な問題はあるものの,KPEと後房レンズ挿入の組み合わせは,将来増加して行くと考えられる。
Dipivalyl epinephrine点眼薬の緑内障治療における評価
著者: 東郁郎 , 中島正之 , 西田哲夫
ページ範囲:P.769 - P.773
用時溶解型dipivalyl epinephrine (DPE)点限薬の臨床効果およびこれとβ—遮断剤との併用効果について検討したところ,次のような結論を得た。
(1) DPE点眼液の眼圧下降作用はdose-responseの関係を示し,0.05%が臨床応用できる下限の濃度であった。
(2)散瞳作用もdose-responseの関係を示し,瞳孔径に有意な変化を及ぼさない濃度の上限は0.05%であった。
(3) DPE 1回点眼による副作用として,点眼時の一過性の眼刺激感(しみる)を認めたが,l-epinephrineより軽度であった。
(4) Timolol点眼後DPE点眼群ではDPEの減圧効果は認められず,DPE点眼後timolol点眼群でtimololの有意な減圧効果を認めた。
以上から,DPE点眼薬は0.05%を主にして,臨床応用すれば,緑内障治療に有用と思われる。
Befunolol点眼における眼圧下降効果とその副作用—原発開放隅角緑内障,高眼圧症を対象とする検討
著者: 南波久斌 , 新家真 , 小室苑 , 高瀬正彌 , 谷島輝雄 , 澤充
ページ範囲:P.775 - P.781
Befunolol点眼液を,原発開放隅角緑内障11例,高眼圧症7例,計18例に投与し,次の結果を得た。
(1)8週間の二重盲検試験において,0,25,0.5,1%いずれのBefunololも有意の眼圧下降を示した。1年以上の長期投与においても,有意の眼圧下降が保持された。
(2)二年以上の経過において涙液リゾチーム濃度,角膜内皮細胞面積には,有意な変化は見られなかった。
(3)脈拍は投与後1カ月までは減少したが,その後は投与前の水準まで回復した。瞳孔径,全身血圧には,変化は見られなかった。
(4) Befunolol投与により,軽度の刺激感,頭痛,結膜充血,角膜びらんが数例に出現した。また,アレルギー性眼瞼炎が1例出現した。
Tilted disc syndromeに関する研究—変視症について
著者: 張由美
ページ範囲:P.782 - P.789
従来報告をみないtilted disc syndromeに伴う変視症について検討した.対象はtilted disc syndromeを呈する52名86眼とした。この中,変視症を自覚した7名10眼を含む38名65眼につき,螢光眼底撮影を施行した。
(1)65眼中14眼(21.5%)では黄斑部付近にある下方ぶどう腫の辺縁の一部に,斑状または帯状をなす顆粒状の過螢光が認められた。この顆粒状過螢光は色素上皮層が主に障害されるものから脈絡膜毛細血管板の萎縮まで,程度の違う変化であった。
(2)変視症のある10眼は前述した顆粒状過螢光のある14眼の中に含まれた。この10眼中8眼では経過中に変視症は消失した。このうちの3眼は顆粒状過螢光の中に一部螢光のleakageがみられ,leakageの消失に従って,変視症の症状の改善が認められた。したがって,tilted disc syndromeに伴う変視症の原因は単なるぶどう腫の形態的変化による網膜像の歪みよりも,ぶどう腫により生じた網膜色素上皮層の障害に起因する一過性の網膜浮腫によると思われた。
(3)変視症の発症年齢および病態より,本症は漿液性中心性網脈絡膜症と同様であるが,両者の相異点は本症では広範囲の色素上皮層の障害が基板にあることと考えた。
(4)網膜皺襞は9名12眼に認められたが,変視症と直接の関係はなかった。
(5)変視症はtilted disc syndromeの合併症の一つと考えて良いと思われた。
学術展示
同名半盲の臨床
著者: 太田玄一郎 , 瀬早苗 , 田地野正勝 , 井街譲
ページ範囲:P.790 - P.791
緒言頭蓋内病変における視覚路の障害では,視索より上位の障害で同名性半盲があらわれ,視野の形態やその他の神経症状を合わせて考えることにより,障害部位の推定の一助となりうる。今回,我々は同名性半盲症例について解析を行ったので報告する。
解析対象対象は1974年5月〜1981年4月までの7年間に本院外来を受診した患者総数32,005名の内,同名性半盲を示した138名である。
眼組織抽出液による合成非吸収性縫合糸の分解について
著者: 早坂征次 , 石黒誠一 , 塩野貴
ページ範囲:P.792 - P.793
緒言眼科手術時にナイロン糸,ダクロン糸,プロリーン糸は非吸収性縫合糸として,またフロロカーボンは人工眼内レンズのループとして用いられている。だが,ナイロン糸は眼内で分解されるとの報告1,2)がみられる。そこで,これら合成縫合糸が本当に分解されるか否か。分解に関与する要因は何か。また,その要因はどの眼組織に多いか等を検討した。
実験方法(1)人工眼内レンズ固定のために用いたナイロン糸を1年後にとり,その表面を観察した。(2)牛眼各組織を0.02M燐酸緩衝液中でホモジナイズし,遠心しその上澄をとり,硫安分画し,非透析画分を抽出液とした。この抽出液に,ナイロン糸(6—ナイロン,アルコン社),ダクロン糸(アルコン社),プロリーン糸(polypropylene,エチコン社),フロロカーボン(東洋コンタクトレンズ社)を入れ,37℃で12時間インキュベートし,反応終了後,縫合糸をよく洗い,その表面を走査電顕で観察した。
入院患者の治療効果判定
著者: 石崎道治 , 千葉桂三 , 平岡利彦 , 横田章夫
ページ範囲:P.794 - P.795
1974年7月独協医大病院開設以来7年になる。そこで,いままでに行ってきた眼科診療を顧みる時期にきていると思われる。しかし全疾患は極めて多岐にわたるため,以下に述べる6疾患を対象とし,果たしてどの程度入院治療効果をあげ,どの点が不十分で改善の余地があるか検討した。
対象は開設より1981年6月までの入院患者1,433名中,白内障607名,緑内障182名,網膜剥離100名,視神経炎34名,ぶどう膜炎36名,斜視70名とした。入院中,退院後の経過をカルテより調査し,各疾患ごとに定めた基準により治療効果の判定を行った。
眼鏡処方の現況と医療行為としての認識に関する調査成績
著者: 宮本吉郎
ページ範囲:P.796 - P.797
これからの適切な眼科医療を確立するための一助として,眼鏡コンタクトレンズ(CL)の処方に関係したアンケート調査を行った。
調査対象と方法18歳以上の男女に10項目37の質問を備えたアンケートに回答してもらった資料をコンピューターで集計,解析した。有効回答者は男2,380名(10代=241,20代=907,30代=753,40代=302,50代=161,60代以上=16),女1,500名(10代=406,20代=559,30代=309,40代=151,50代=66,60代以上=9)計3,880名である。
視覚誘発脳波による視的学習利得の研究—脳および視神経の器質的疾患と機能的疾患における後期成分の消長
著者: 市橋進
ページ範囲:P.798 - P.798
緒言視覚誘発脳波の後期成分のP200(Vertex Potential)およびP300成分が,視的学習利得を反映することを正常人について先に報告した1)。今回は視的学習という点での病態である脳または視神経に器質的あるいは機能的障害のある疾患群について,この誘発脳波がどのように影響されるかを観察し,その意義を明らかにする。
実験方法刺激方法は,前報の実験2の条件で行い,VEPの導出と加算は前報通りである。データ処理は,P200成分については刺激後約200msecの頂点潜時とN1—P2(P200)振幅を測定し,P300成分は,振幅の個人差が大きいために頂点潜時の計測のみを行った。
タイ国の失明対策の現況—プライマリ・アイ・ケア推進計画について
著者: 紺山和一 , 赤松恒彦
ページ範囲:P.799 - P.799
我々は昨年の臨床眼科学会において,タイ国における失明防止対策について報告した1)。今回はその後の進行状態についてプライマリ・アイ・ケアを中心とした動きについて述べてみたい。また同時に試験的に実施して来た地方病院眼科モニタリング制度として提出された月間報告に基づいて得た失明原因および白内障・緑内障手術の実態について報告してみたい。
タイ国失明対策の基本戦略 前回にも述べた通り,man power developmentが基本戦略の中心であり,外科医の眼科教育,地方出身の看護婦の眼科教育を行い,各地方に4名の下級保健従事者を眼科技術員として現地で教育し,医師1,看護婦2,技術員4の比率でのチームを作り,県レベル(第2次レベル)の眼科医療サービスを行う。
脳血管障害と視野異常—内頸動脈閉塞症および中大脳動脈閉塞症
著者: 前田修司 , 薄葉澄夫 , 長田乾
ページ範囲:P.800 - P.801
緒言内頸動脈(ICA)およびその分枝である中大脳動脈(MCA)は眼球から視放線へ至る視路への血液供給を行っているため,その閉塞により高頻度に眼症状が発現することが知られている1,2)。同名性視野欠損はその中で最も主要なものであり内頸動脈閉塞症(ICAO)の11〜52%1〜3)に,中大脳動脈閉塞症(MCAO)の19〜68%3〜5)にみられ,特に視野下半部の障害が強いとされているが6,7),その視野欠損の形態に関しての報告は未だない。今回は,視野異常の発現頻度,欠損の形より両者の比較を行った。
対象脳血管撮影で確認された視野検査可能なICAO 27例(男26例,女1例),MCAO 38例(男32例,女6例)である。不完全閉塞や他の視路疾患を合併しているものは除外した。
Cross-Tralk消去機能をもったEOG自動測定装置の開発
著者: 久保賢倫 , 伊月宣之
ページ範囲:P.802 - P.803
眼球の運動や常在電位をElectro-oculogram (EOG)で検査する場合には,他眼からの電位の影響すなわちcross-talkが問題になる。左右の眼が共働運動している場合または左右の常在電位が等しい場合には,cross-talkは大きな問題にはならない。しかし,そうでない場合にはcross-talkを消去して測定しなければ誤った解析結果がえられる1,2,4)。
眼球運動測定時にはcross-talkはfeed back法で消去できる。常在電位の変動測定時には消去は各々のEOGのピーク値だけで行えばよいので,測定のデジタル化にて症例毎にcross-talkを自動的に消去できる3)。そこで今回,マイクロコンピュータ(マイコン)を利用してcross-talkを消去でき,またEOG時間曲線を短時間で測定しグラフとして表示もできる装置を開発した。
問診情報から眼疾患を予想するシステムにおけるオフィスコンピューターの応用
著者: 湖崎克 , 佐野充 , 奥沢康正
ページ範囲:P.804 - P.805
緒言われわれは,眼科におけるコンピュータの現実的な応用方法として,従来から健保請求のレセプト打ち出し機として普及しているオフィスコンピューターの容量の余裕を利用し,眼科診療内容の向上と能率化を目的として,問診内容を入力し,予想される眼疾患および必要な検査を出力するプログラムを検討した。このうち指示された検査の内の,一次検査のみは受付の段階から医師の診察までの間に実施されておれば,能率の向上は著しいはずである。
全眼球炎の統計的観察
著者: 秦野寛 , 磯部裕 , 佐々木隆敏 , 田中直彦
ページ範囲:P.806 - P.807
細菌および真菌による全眼球炎は重篤で,化学療法の発達した今日でも,なおその予後が極めて不良な眼感染症である。今回我々は過去11年間に経験した本症35例35眼についての統計的観察を行い,あわせて早期診断の一助としてグラム陰性菌のエンドトキシン検出試験であるリムルステストを一部の症例に試み,その意義について検討した。
(1)誘因(表1):35例35眼の感染経路よりみた内訳は外傷性14眼,術後感染14眼,軽移性6眼,不明1眼であり,さらにそれぞれの内訳をみると外傷性は全て穿孔性外傷で,うち8眼が眼内異物によるものであった。術後感染は13眼が緑内障濾過手術後発感染,1眼が白内障全摘術後発感染であり,術後から発症までの期間は最短1年4カ月,最長18年で,平均9年3カ月であった。転移性は2例が膀胱炎由来のものと考えられ,残り4例の原発病巣は不明であった。糖尿病の合併は外傷性0,術後感染1,転移性2例で合併率は全体で9%であった。性別については,男性21眼女性14眼で3対2と男性優位で,さらに誘因別にみると外傷性は大半が男性で,術後感染は男女同数,転移性は女性が多いという傾向を示した。
Cefmetazole sodium (CMZ)の人眼前房内移行濃度の検討
著者: 野々村正博 , 山上潔 , 村田幹夫 , 松山秀一 , 伊藤信一
ページ範囲:P.808 - P.809
緒言Cefmetazole sodium (CMZ)は,新しく開発されたセファマイシン系抗生物質で,広抗い菌スペクトラムと強力な抗菌作用から,その臨床的応用が期待されている1)。
一般に,抗生物質の使用にあたっては,その組織内移行を考慮しなければならないが,従来,人眼についての検討は少ない2〜8)。
眼感染症におけるopportunistic pathogenとしての嫌気性菌とその病態に関する検討
著者: 永井重夫 , 大石正夫
ページ範囲:P.810 - P.811
緒言近年,各種細菌感染症において,従来,弱毒菌とされていた無芽胞嫌気性菌が,いわゆるopportunis—tic pathogenとして高頻度に分離され,感染症における嫌気性菌の役割が次第に明らかにされつつある。今回,我々は眼感染症患者より検出された嫌気性菌について,その病因的意義を検討した。
方法1976年来,新潟大学眼科感染症クリニックにおいて,患者の眼脂,膿,角膜擦過物などの検体を採取し,当大学中検細菌検査室にて培養,分離して,検出菌の年次的推移を調べた。そして,これら嫌気性菌の総検出菌および好気性菌に対する比率を検討した。次いで,1979年,1980年の2カ年における疾患別菌検出率を調べ,さらに嫌気性菌単独および好気性菌との複数菌検出症例について検討した。菌の同定は,1980年の24株について,東京総合臨床検査センターに依頼した。
連載 眼科図譜・296
Gaucher病兄弟の眼所見
著者: 佐々木隆弥 , 清水幸夫 , 塚原重雄
ページ範囲:P.684 - P.685
緒言
Gaucher病(以下G病)とは,類脂質代謝障害の一つでGlucocerebrosidaseの欠損のためGlucocerebrosideが主として網内系組織に沈着する常染色体劣性遺伝を示す疾患である。
眼科的な異常所見として臨床的には,眼球運動障害,特異な瞼裂斑,硝子体混濁,網膜出血,網膜浮腫,黄斑周囲輪状変性,岡辺部綱膜の小点状白斑,cherry red spot病理組織学的には結膜,毛様体,脈絡膜のGaucher,細胞の存在が報告されている。
臨床報告
術後経過よりみた外斜視に対するParksの量定の検討
著者: 根本龍司 , 松田恭一 , 根本加代子 , 門脇文子
ページ範囲:P.812 - P.816
外斜視31例の手術成績を調査し,その結果からParksの量定法を検討した。
(1)術前の眼位は−28〜−35prism dioptersに最も多く分布していた。術後眼位は+1〜−3と−19〜−23prism dioptersにピークをもつ二峰性の分布を示していた。
(2)術後6〜12カ月目での治癒状態はFairが最も多かったが,これには術後の残余角(10prism diopters以上)が影響すると思われた。
(3)間歓性外斜視における矯正係数は平均0.76±0.31で,恒常性外斜視のそれは0.93±0.33であったが,両者は危険率10%で有意の差があるとはいえなかった。
(4)術後の期間と眼位の変化との間には,y=1/b ln x-ln a/bの関係があり,術後眼位および手術効果を検討するには良い指標となった。
(5)矯正係数のバラツキの原因として,術者の斜視手術に対する熟練度,術式の不統一が考えられ,今後考慮されるべき点であった。
(6)今回の症例では,Parksの量定は全体としてやや低矯正の傾向にあり,内直筋短縮を1mm多く行っても良いと考えられた。
Aicardi症候群の1例
著者: 唐木剛 , 太田一郎
ページ範囲:P.817 - P.821
我々は脳梁欠損・点頭てんかん・特異な網脈絡膜症を備えたAicardi症候群1例を経験し,本症例が他の全身奇形を伴わず,視反応も良好であることから,Aicardi症候群の最も基本的な症例と考え報告した。
また特異な網脈絡膜症について,その局在・障害の部位について文献的に検討し,発生学的見地も加えて,胎生10週以後6カ月までの間に網膜色素上皮および脈絡膜になんらかの原因で変化がおこることにより生ずると考えた。
実質型角膜ヘルペスの免疫療法—第3報levamisole®による臨床効果とくに長期観察例を中心に
著者: 加藤富士子 , 大野重昭 , 松田英彦
ページ範囲:P.822 - P.827
実質型角膜ヘルペス患者28例を対象としてL-tetramisolc (levamisole®)による免疫療法を行い,4年以上経過を観察しえた長期観察例も含め,本療法の臨床効果および問題点について検討した。
投与量は1週間450mgの3投4休法,あるいは1週間150mgの1投6休法にて行い,最短3カ月から最長1年5カ月間の薬剤投与を行った。
視力の改善したものは3カ月後68%,6カ月後73%,1年後61%であったが,症状別に検討した結果からは潰瘍を伴った軽度浮腫群に著効例が多かった。
再発率は1年後19%,2年後27%,3年後33%,4年後20%であり,IDU・steroid併用療法に比べ低率を示した。
副作用は発熱・発疹・掻痒感・臭覚異常・腹痛などで,いずれも投薬中止にて治まり,無顆粒球症はみられなかった。
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(8)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斉藤仁男
ページ範囲:P.828 - P.829
15.実相院流一流一巻
古来,病に悩める人々の神仏信仰は殊に厚かった様であるが,そうした信仰の"場"となったのが神社や寺院である。眼科諸流派の中でも馬嶋流(明眼院),根来流(根来不動院),あるいは医王山高田寺,雲州一畑薬師の流派等,そこで創められたと伝えられる眼病治療も僧侶によるものが多く,寺社との関係も深かった様である。実相院流もそうした寺院等から興った流派とも思われるが,その伝えられる秘伝書「一流一巻」を掲出する。
この「一流一巻」という秘伝書は実相院流の秘伝を伝えたものであると巻末に書かれているが,実相院流についてはその起源,創始者等調査及ぼず明らかでない。ちなみに,大事典(平凡社)には摂家門跡の一つに実相院がある。その条下に『天台宗寺門派の大本山,実相院門跡,又は岩倉門跡と称す。京都府愛宕岩倉にあり,寛喜年間(1229〜1231)浄基の建立。浄基は関白近衛基通の曽孫,鷹司兼基の子で,出家して実相院と称し,天台の座主となった人』とあるが,本書と実相院流派との関係は審かではない。
GROUP DISCUSSION
地域予防眼科研究会
著者: 小暮文雄 , 赤松恒彦
ページ範囲:P.831 - P.834
第一回研究会,昭和56年11月23日Am9:00〜12:00会場帝国ホテル鶴の間,出席者数108名。世話人独協医大小暮による当研究会設立趣意説明が行われた。この研究会の内容をよく理解していただくために,その内容を紹介しておく。
この会は失明防止公衆衛生眼科研究会との名称で発会する予定であったが,研究会の目的を名称にわかりやすくのせることにし,地域予防眼科(Community and Pre—ventive Ophthalmology)とした。
眼感染症
著者: 北野周作
ページ範囲:P.835 - P.838
1.流行性角結膜炎の院内感染
流行性角結膜炎(以下,E.K.C.)は,感染力が強く,春より初夏にかけ外来をにぎわせる。入院患者に発生した場合,早期に隔離,退院させることにより,院内感染,流行を引き起こさずにすむことがほとんどであった。
今回我々は,入院患者1名にE.K,Cを発症した段階で病棟を閉鎖したにもかかわらず,全入院患者中の14名(約27%)の発症を引き起こし,二週間の病棟閉鎖をよぎなくされた一連の経過について報告すると共に,E.K.Cの院内感染の予防について検討を加えた。
基本情報
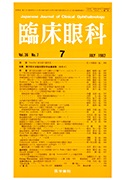
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
