交感性眼炎とVogt—小柳—原田症候群に発生した脈絡膜新生血管について病理組織学的に検討した。
脈絡膜新生血管は交感性眼炎では鋸状縁付近に,Vogt—小柳—原田症候群ではとくに赤道部から周辺部にかけて認められた。いずれも脈絡膜の細胞浸潤が強いか,または炎症が長期にわたって持続した部位であった。綱辺部から鋸状縁付近は乳頭周囲および黄斑部とともにぶどう膜炎における脈絡膜新生血管の好発部位とみなされる。
ぶどう膜炎における脈絡膜新生血管は脈絡膜毛細管板から発生する可能性が強く,その発生誘因として,炎症細胞の浸潤によっておこる脈絡膜毛細管板とBruch膜の障害が関係しているものと思われた。
脈絡膜新生血管の発生と網膜色素上皮細胞の増殖との間に表裏一体の密接な関係が認められた。その前後関係として,脈絡膜新生血管が発生すると,それに続いて網膜色素上皮細胞が増殖して新生血管を取り囲む場合と,脈絡膜の炎症に対する組織反応として網膜色素上皮細胞が増殖し,それが2次的に脈絡膜新生血管の発生を促す場合の二通りの可能性が考えられた。
雑誌目次
臨床眼科36巻9号
1982年09月発行
雑誌目次
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
学会原著
交感性眼炎およびVogt—小柳—原田症候群における脈絡膜新生血管—病理組織学的研究
著者: 猪俣孟 , 嶺井真理子 , 谷口慶晃 , 川田芳里
ページ範囲:P.1023 - P.1031
重症糖尿病性網膜症の治療における蛍光虹彩造影(FIA)の有用性について
著者: 福島茂 , 林英之 , 大島健司
ページ範囲:P.1033 - P.1039
重症糖尿病性網膜症51例100眼に対して汎網膜光凝固療法,網膜冷凍凝固療法,硝子体手術を行い,その治療前および治療後6ヵ月目に螢光虹彩造影(FIA)を行った。結果は以下の通りであった。
(1)細隙灯検査にて虹彩ルベオージスを認めたものは27眼であったが,FIAにて94眼に螢光色素の漏出を認めた。(2) FIA所見は網膜症重度度とくに網膜剥離の合併をよく反映した。(3)35眼に光凝固を施行したが,眼底所見とFIA所見の軽快は並行せず,また血管新生緑内障の発生はなかった。(4)11眼に網膜冷凍凝固を施行したが,眼底所見の軽快例はなく,FIA増悪眼2眼に血管新生緑内障の発生をみた。(5)21眼に硝子体手術を施行したが,眼底所見は9眼で軽快し,4眼で増悪した。術前,術後を通して網膜剥離を認めた4眼に新たに血管新生緑内障を認めた。術前のFIAと血管新生緑内障の間に相関はみられなかった。
全層角膜移植の統計的観察—順天堂大学における最近24年間の症例について
著者: 上田俊介 , 中安清夫 , 江本一郎 , 南修一郎 , 中馬祐一 , 金井淳 , 中島章
ページ範囲:P.1041 - P.1045
1958年から1981年6月までに順天堂大学眼科学教室で行った全層角膜移植8171眼の術後混濁原因等につき検討を加えた。
(1)全層角膜移植術全体の透明治癒率は71%であった。
(2)角膜白斑例のうち,術前の内皮障害の著明なもの,混濁範囲の大きいものの結果は不良で,術後侵入血管の多少と透明治癒率との間に有意の関係は無かった。
(3)移植片反応は全体の27.4%に発症し,うち約30%が混濁結果に終わった。
(4)円錐角膜例における移植片反応は24.6%に発症し,その61%が術後3ヵ月までに,94%が術後1年までに起き,術後6ヵ月以上で起きた移植片反応では混濁結果に終わるものは少なかった。また角膜提供者の年齢が高くなるに従い,移植片反応出現率は箸明に上昇した。
角膜ヘルペスに対するhuman fibroblast interferonの効果および必要点眼回数
著者: 塩田洋 , 山根伸太 , 藤田善史
ページ範囲:P.1047 - P.1051
角膜ヘルペスに対するhuman fibroblast interferon (Hu IFN—β)の効果および必要点眼回数を兎を用いて検討し,次の様な結果ならびに結論を得た。
(1) Human fibroblast interferonは,家兎角膜ヘルペスに対し発症防止効果を持っていた。
(2) Human fibroblast interferonは,家兎角膜ヘルペスにおいてでき上がった潰瘍に対する治療効果は無かった。
(3)1日3回の点限による発症防止効果は,1日10回の点眼による効果と等しかった。
(4) Human fibroblast interferonを人の角膜ヘルペスに応用する際,106IU/mlを用いる場合には1日3回位の点眼回数が妥当ではないかと思われる。
糖尿病性網膜症での血管床閉塞域と視野の相関
著者: 蓮沼敏行 , 村岡兼光 , 北川道隆 , 仁木高志 , 辻健一 , 粟根裕
ページ範囲:P.1053 - P.1063
糖尿病性網膜症で網膜血管床閉塞がその基本的病変であると証明された事実を踏まえ,血管床が閉塞している網膜の機能についての検索を行った。我々は糖尿病性網膜症で,広範囲螢光造影と良質な動的量的視野の両者が得られた57例80眼について検討し,その結果,ほぼ正常の視野を示す第I群16眼,2/I・3/Iのイソプターが異常を示す第II群25眼,4/Iが異常を示す第III群28眼,4/Vまでも異常を示す第IV群11眼の4群に大別した。
第I群から第Ⅲ群までは,視野異常の程度と血管床閉塞の面積とに正の相関があった。そして各々の症例で視野のイソプターと螢光造影の前管床閉塞域とを重ねて比較検討すると,両者の範囲が凹凸の形を含め相似していた。第Iから第III群では,網膜血管床が閉塞している部位でも4/Vのイソプターの視野はよく保存されていた。第IV群は視神経炎等があり,検索時点では網膜血管床閉塞と視野異常の密接な相関はなかった。
以上血管床閉塞域の網膜では血流が非常に少ないにもかかわらず,視機能を完全には失っていない。この事実は,血管床閉塞域がhypoxic focusであり網膜症を悪性化させる主原因である,とする従来の説と合致していた。
β—遮断剤の眼圧下降効果とくにtimololならびにcarteololの比較
著者: 堀江武 , 高橋修 , 白土城照 , 北沢克明
ページ範囲:P.1065 - P.1070
新しく開発された,相異なる二つの交感神経β—受容体遮断剤であるtimololとcarteololの眼圧下降効果の強度比について,open studyと二重盲検交叉法を用いて比較検討し,以下の結果を得た。
(1)高眼圧症ならびに原発開放隅角緑内障患者を対象とし,open studyにより,0.25%timololと1%carteololを6週間ずつ計12週間timololからcarteololへの順で点眼し,その眼圧下降効果を比較検討したところ,両者の効果は同等であった。
(2)高眼圧症ならびに原発開放隅角緑内障患者を対象とし,open studyにより,0.5%timololと2%carteololを各々6週間ずつ計12週間timololからcarteololへの順で点眼し,その眼圧下降効果を比較したところ,その効果は0.5%timololの方が2%carteololより大であった。
(3)高眼圧症ならびに原発開放隅角緑内障患者を対象とし,二重盲検交叉法により,O.5%timololと2%carteololを4週ずつ8週間点眼し,眼圧下降効果を比較したところ,両者は同等であった。
(4)0.5%timololと2%carteololの眼圧下降効果が,opcn studyと二重盲検交叉法による試験で相異なったことの原因については,二つの試験方法のprotocol,とくに点眼期間および症例数の違い等による可能性は否定できないが,真の原因は不明である。
エタンブトール中毒の眼科的副作用の統計的観察
著者: 栃久保哲男 , 橘川真弓 , 大垣節子 , 渡辺博 , 渡辺ひろみ , 大岡良子
ページ範囲:P.1071 - P.1078
先に我々はEB中毒性視神経症前症例4例について報告したが,今回1979年4月から1981年7月までの2年3ヵ月間に,東邦大学付属大森病院限科外来を受診したEB服用患者100例を対象とし,経過観察を行った。EB中毒性視神経症と診断された患者は,外来48例中4例(8.3%),内科入院52例中10例(19.2%),計100例中14例(14%)である。発症群14例を対照群,すなわち対象例100例中発症群14例を除いた残り86例中から定期的に眼科的および内科的に各検査の施行された入院患者より19例を選び,これと比較検討し,統計的観察を行った結果,発症群と対照群において投与量および投与期間についてはDose-Response関係が必ずしも成り立たないこと,また眼科的副作用の発症と結核病巣の広がり,炎症所見,排菌の有無等,結核の重症度とは,あまり有意な関係は認められなかった。しかし,本症発症例において今回,赤血球数,ヘモグロビン1直,ヘマトクリット値が比較的低値を示し,有意差を認め,このことは本症発症に関字する一因子になりうると考えた。
垂直眼球運動系の検討—第4報視床血管障害28例の検討
著者: 関本幸子 , 稲垣昌泰 , 鈴木利根 , 石川弘 , 後藤昇 , 金子満雄
ページ範囲:P.1079 - P.1084
視床病変で出現した28例の垂直眼球運動異常の臨床症候に対応する病変局在について検討を行い,以下の結論を得た。
(1)上方注視麻痺および上方下方注視麻痺は視床背側外側核後部傷害例に多い。
(2)上方下方注視麻痺は視床外へ病巣の広がりをもつ例が多い。
(3)下方注視麻痺は視床穿通動脈流域の両側の病変で出現した。
後天性色覚異常のFarnsworth-Munsell 100hue testによる検討
著者: 北原健二
ページ範囲:P.1085 - P.1089
後天性色覚異常のFarnsworth-Munsell 100—hue testのパターン分析に関して,全色相を4分割し,象限IからIVまでとした。そして,それぞれの象限に関して,その偏差点の小計を分割線を回転させながら1周期にわたって求めた。それらの値をSI(n),SIII(n),SIII(n)ならびにSIV(n)とし,{SI(n)+SIII(n)}—{SII(n)+SIV(n)}に着目し,この値を総偏差点(ST)で割った値をA (n)とおくと,この関数A (n)が,Farnsworth-Munsell100—hue testのパターン解析の一方法となることを提唱した。
片眼性先天性二色型第二色覚異常の1例—第1報選択的順応法による各錐体系のスペクトル感度の測定
著者: 岡島修 , 岡本道香 , 小沢哲麿
ページ範囲:P.1091 - P.1095
右眼がdeuteranopia,左眼がほぼ正常に近い色覚の女性症例を報告する。症例の右眼は仮性同色表,色相配列検査およびanomaloscopcでdeuteranopiaと判定され,左眼は石原表を除いた諸検査で正常と判定された。本症例の父親はdeuteranopiaであった。
正常者群,deuteranopia群および本症例の両眼の各錐体系のスペクトル感度を,Waldの選択的順応法によって測定し,次の結果を得た。
(1) deuteranopia群では,正常者群と比べて緑錐体系の感度が有意に低下していた。
(2)本症例の右眼の各錐体系のスペクトル感度は,いずれもdeuteranopia群の95%信頼区間内に含まれた。
(3)本症例の左眼の緑錐体系のスペクトル感度は,正常域よりやや低下していた。
以上の結果,本症例の右眼はdeuteranopia,左眼は軽度緑錐体系異常と診断された。
Behçet病患者の血清補体系—Immune complexとの関係
著者: 小暮美津子 , 島川真知子 , 大野弓子
ページ範囲:P.1096 - P.1100
Behçet病患者44例(96検体)を対象に,血清補体価,補体蛋白およびその阻害物質,circulating immune complexの値を測定し,これら相互の関係および臨床経過との関連性を検討して以下の結果を得た。
(1)本症患者の血清補体価,補体蛋白量(C3,C4,Factor B),補体阻害物質(CI in—activator,α1—antitrypsin)の平均値は健常対照にくらべて有意に高値であったが,変動幅も大きかった。
(2)補体蛋白最とその阻害物質はともに高補体群に高い傾向がみられ,補体の活性化は低補体血清に高頻度に認められた。
(3)本症患者のIC陽性率は36.5%であった。IC陽性率は本症の活動期に増加し,病変の出現部位との間に相関はなく,むしろ発症後の経過年数と関連して出現していた。
(4)低補体血清中のIC陽性率は高い傾向がみられた。
眼科サーモグラフィの研究—種々の観察方法について
著者: 蒲山俊夫
ページ範囲:P.1101 - P.1107
サーモグラフィを眼科臨床検査に応用する目的で,サーモグラフィによる種々の観察方法について検討を行った。
(1)単純検査法:画像拡大法およびコンピュータ画像処理観察法によって,サーモグラフィによる前眼部の表在性微細病変の検出が可能になった。
(2)負荷検査法:眼球内部および眼窩内の深在性病変に対しては,持続開瞼負荷後の経時温度変化検査法および冷却負荷後の温度回復検査法を用いることによって,病態をサーモグラフィでつかむことができた。
眼科サーモグラフィは上記の方法を用いることにより,臨床上広範囲の眼疾患に適応でき,診断学上,きわめて利用価値のある検査法である。
毛様体解離によるhypotony maculopathyの治療法について—臨床的,組織学的検討
著者: 直原修一 , 丹羽子郎 , 舩橋正員
ページ範囲:P.1109 - P.1115
鈍的眼外傷3例と緑内障手術後の1例に毛様体解離を伴うhypotony maculo—pathyが発症し,いずれも保存療法が無効で,3例は解離部に対してのargon laser照射で,1例は縫合手術により改善が得られ,毛様体解離の閉鎖には両法とも有効と思われた。
Argon laser照射は解離範開約45度以下の3例に有効で,照射2週間後に急激な眼圧上昇とともに臨床症状の改善が得られた。
有色家兎による実験では,縫合手術3日後には虹彩根部と角膜は密着し,角膜内皮細胞が虹彩上に連続してみられた。Argon laser照射3日後には凝固部に線維素の析出とともに細胞増殖像が観察され,14日後には結合組織により解離部の閉塞がみられた。
以上のように,臨床例4例および有色家兎による実験成績より,毛様体解離に伴うhy—potony maculopathyに対して,縫合手術,argon leser照射は,その奏効機序よりともに有効であると思われた。
急性後極部びまん性脈絡膜炎
著者: 吉岡久春
ページ範囲:P.1121 - P.1127
急性後極部びまん性脈絡膜炎の4例を報告し,(1)本病は漿液性円盤状黄斑部網膜剥離を来たす一連の疾患として,(2)網膜色素上皮レベルからの螢光漏出点が多発する一連の疾患として考慮さるべきである。
そして本病の病態は脈絡膜の前毛細血管細動脈の原発性急性非閉塞性炎症により,脈絡膜毛細血管の透過性亢進を来たし,これにより二次的に網膜色素上皮細胞にある外血液網膜柵を破綻し,続発性網膜剥離を来したものと考えた。
長期間持続した外傷性低眼圧の臨床的検討
著者: 森野智英子 , 難波彰一 , 北庄司清子 , 泉谷昌利 , 松山道郎
ページ範囲:P.1129 - P.1133
(1)長期間(最短1ヵ月,最長2年4ヵ月)低眼圧を持続した眼球打撲症5例を,1年以上follow upし,その臨床経過を観察した。
(2)隅角検査で5例中4例にcyclodialysisが認められ,1例にはangle recessionがみられたが,はっきりしたcyclodialysisは発見できなかった。
(3)5例ともに,長期間高度の低眼圧が持続した後,突然,毛様充血,あるいは前房混濁を伴った眼圧上昇がおこり,数日で正常眼圧に改善され,以後,眼圧は正常範囲内にコントロールされている。
(4)以上の臨床経過より推して,眼球打撲後長期間持続する低眼圧の主要因子として,cyclodialysisの発現に伴って続発する房水排出の促進を推定した。また,これらの低眼圧症候群の改善は,経過中に発生した炎症性反応による房水過剰流出路の閉鎖に起因するものと考えた。
盲人歩行誘導に関する研究(その1)
著者: 山本覚次
ページ範囲:P.1134 - P.1136
盲人の歩行誘導について,色々な研究または着想が発表されているが,未だ十分とは考えられない。著者は某盲学校の生徒のアンケートを基礎として盲人の歩行に便利な誘導器具の開発を試み,色々な試行作誤をくりかえした後,磁気センサーを用いて,磁気歩行誘導の実験を行い,盲人を使用して,その有効性について実証した。
経年性後部硝子体剥離—1,077正常眼の分析
著者: 高橋正孝
ページ範囲:P.1137 - P.1141
606名,1,077正常眼の硝子体を細隙灯顕微鏡法により観察し次の結果を得た。
(1)硝子体の剥離率は,加齢とともに8%(40歳代),22%(50歳代),43%(60歳代),71%(70歳代),85%(80歳代)と上昇する。
(2)40歳未満における後硝子体剥離は451眼中わずか1眼で,これは例外的なものと見なされる。
(3)男女差はなく,剥離は右眼に先行する傾向があり,剥離率は左眼より右眼がわずかに高い。
(4)完全後硝子体剥離率と部分硝子体剥離率はそれぞれ21%と2%で,後者は前者の約1/10と比率が小さい。
(5)正常眼の硝子体剥離は上象限から起り,下象限へとひろがる。
(6)増殖型糖尿病性網膜症を例にとり,部分硝子体剥離の頻度について正常眼との比較を行ったところ,前者では有意に高いことが証明された。
両眼開放と他眼遮閉での屈折度変化
著者: 牧野弘之 , 魚里博 , 畑健一 , 西信元嗣 , 中尾主一
ページ範囲:P.1143 - P.1147
Objective Automated Refraction (Dioptron II®)を用いて,同一被検者に対して,両眼開放測定と他眼遮閉測定を行い,測定法の違いによる屈折度の差を検討した。我我は,6歳より15歳までの裸眼視力1.0未満の生徒よりアトランダムに抽出した各学年約50〜100名を被検者として選んだ。
両眼開放と片眼遮閉と測定条件を変えることにより,球面屈折度では平均−0.3D,乱視度数においては平均一0.1Dの変化を示した。この両者でのそれぞれの変化は,P<0.05で有意差を認めた。各年代における,球面度数,乱視度数のその変化の量は,ほぼ同程度であった。乱視軸については,有意ある差は認めなかった。
静的量的視野計測(CPブラケット)の解析能力について
著者: 井上洋一 , 井上トヨ子
ページ範囲:P.1149 - P.1154
CPブラケットによる成績を解析する上で,正常CPの基準について検討した結果,No 31ではマ盲点の1ポイントを除く,異常ポイント1個,No 32ではマ盲点1個を除く異常ポイント2個が,正常CPと判定された。
CPへ影響する要因としては,上眼瞼・レンズ矯正・瞳孔径など,これまでの視野検査上注意すべき点の外,検査への対応度,すなわち初回に現われ,2回目以後に消失する異常性で,この練習効果は無視できない要因として注目された。
No 31,32による376眼のCPによると,初回正常CPと出た115眼中,2回目も正常CPが得られたもの94眼(81.7%),異常CP 21眼(18.3%)であった。また,初回異常CPの検出された261眼については,2回目正常CPは97眼(37.2%),2回目に異常CPの検出されたものは164眼(62.8%)であった。これらの臨床的な結果からCPブラケットによる解析能力の臨床的な長所,欠点を述べた。
Cathode ray tube (CRT)使用者の眼精疲労について
著者: 栗本晋二 , 岩崎常人 , 野村恒民 , 相良久美 , 野呂影勇 , 山本栄
ページ範囲:P.1155 - P.1160
Cathode ray tube (CRT)端末を用いた作業を高年者,中年者,若年者に行わせ視機能への影響,また各世代層による相違を調節機能を主として検討した。高年者(58歳〜65歳)5名,中年者(38歳〜41歳)5名,若年者(19歳〜21歳)7名にCRT端末を用いた氏名探索作業を2時間行わせ,作業前後および安静2時間後の調節機能をAccommodopolyrecorderを用いて測定した。
その結果,高・中年者では平均2cmの調節近点距離の延長がみられ,安静2時間後で作業前の近点距離に近づいた。若年者では有意な変化は認められなかった。調節時間は各年齢層とも作業前後に有意な差を検出することはできなかったが,高・中年者では作業後延長する傾向をみた。Accommodogram patternについても若年層では作業負荷によるパターン変化はなかったが,高・中年者ではパターン変化を認めた。
以上のことより,高齢化するほどCRT作業の影響は大であったといえる。
人工透析患者の眼障害—視力障害について
著者: 矢野啓子 , 上田萬利子
ページ範囲:P.1161 - P.1165
長期人工透析患者の眼障害に関する研究の一環として,透析期間6ヵ月以上の慢性腎不全患者136例272眼を対象として視力障害について検討し,次のような結果を得た。
(1)86%は0.5以上の視力を保持していたが,7.7%に0.1未満の高度視力障害が認められた。
(2)視力障害の原因は,視力0.1未満では糖尿病性網膜症が48%,中心静脈閉塞症が24%を占め,視力0.1〜0.4では糖尿病性網膜症が38%,黄斑変性が31%を占めた。
(3)症例中,一過性の視力低下,色覚異常,ERGの消失をきたした例を2例経験した。
眼内悪性リンパ腫によるぶどう膜炎
著者: 宇山昌延 , 山下秀明 , 加賀典雄 , 大熊紘 , 越生晶
ページ範囲:P.1166 - P.1171
最近10年間に,組織診断の行われた眼内に初発した悪性リンパ腫を4例7眼経験した。患者は中・高齢者で,激しいぶどう膜炎を示し,とくに黄白色の広範囲に拡がる網膜・脈絡膜の濃厚な滲出斑,多量のみぢん状硝子体混濁を主症状とし,やがて虹彩後癒着,虹彩rubeosisと血管新生性緑内障を合併し,数ヵ月で視力が失われた。1例は前房蓄膿と虹彩結節,球結膜下腫瘤,眼球突出を示した。
この時期には何ら全身症状がなく診断は確定しなかったが,数ヵ月おくれて多中心性に全身に悪性リンパ腫の症状があらわれた。2例は全身哀弱で死亡した。死後剖検(2例),皮膚結節の生検(1例),摘出眼球の検査(2例)により,ぶどう膜炎の原因が2例はlymphocytic lymphoma,2例はhistiocytic lymphoma (reticulum cell sarcoma)であることが判明した。腫瘍細胞はlymphocytic lymphomaではぶどう膜に,histiocytic lymphomaでは網膜に浸潤していた。
最初の3例は診断困難で失明したが,最近の1例は房水の細胞診を行って本症であることを確認し,眼部へ放射線療法(4,000rads)を行い消炎しえた。
本症が疑われる原因不明の難治のぶどう膜炎には前房水,または硝子体の細胞診を行い早期に診断を確定し,眼部へ放射線療法を行うのが眼球を救いうる手段としてすすめられる。
学術展示
網膜赤道部変性といわゆる網脈絡膜萎縮巣
著者: 佐藤清祐 , 西山愛子 , 嶺崎育世 , 高村悦子 , 中野由宇子
ページ範囲:P.1172 - P.1173
緒言著者らの赤道部変性の螢光造影所見1,2)では色素上皮の異常を反映する変性巣内の顆粒状過螢光と変性巣およびその周囲における網膜血管閉塞が90%以上の高率に見られ,その他網膜血管からの漏出,微細血管瘤形成等が見られたが,はじめはこれらの所見を赤道部変性の発生病理とどう結びつけるかは明確には理解しえなかった。その後螢光造影検査を多くの例に行った結果,上記螢光像所見はおそらく原発性の網脈絡膜炎とそれに続発する網膜血管炎を示唆すると考えるようになった。また赤道部変性患者の眼底を注意深く観察していると,網脈絡膜炎の痕と考えられるいわゆる網脈絡膜萎縮巣を見出すことが多いのに気付いていた。この点からも赤道部変性と網脈絡膜萎縮巣との間に病因論的に関連がありそうだと考え,この点を確めるため両者の関連性を統計学的に検討したところ,興味ある結果を得たので報告する。
対象と方法対象は赤道部変性で経過を観察している118名,222眼である。網脈絡膜萎縮はSchepensらが網脈絡膜炎の痕と規定しているChorioretinal scar(網脈絡膜瘢痕)を主体とするが,それと共にSchepensらがFocal pigment proliferation(限局性色素増殖巣とでも訳すべきか)と呼んでいる変化をも加えてある。前者は網脈絡膜の韮薄化を主体とした萎縮性瘢痕であり,後者は色素増殖の著明な増殖性瘢痕であると理解してよいので,両者を同列に扱った。
網膜色素変性症における眼球常存電位と副腎皮質ホルモンの日内変動
著者: 玉井信 , 福与貴秀 , 清沢源弘
ページ範囲:P.1174 - P.1175
緒言さまざまな生体機能にはリズムがあり,その組合せにより生命が保持されている。生体リズム最大の同調因子(Zeitgeber)は光である。近年光受容器である視細胞外節の再生もその例外でないことが明らかになった1,2)。更にその再生機構および視細胞全体を支えている色素上皮細胞の活動性を反映する眼球常存電位(Sp)にも日周性リズムが存在する3,4)。今回Spの日内変動とともに細胞の糖質代謝,電解質代謝に最も大きく影響する副腎皮質ホルモンの血中濃度の目内変動を正常者,定型的網膜色素変性症患者,下垂体機能異常者で観察した。
方法および症例Spの測定方法は先に報告した4)。血中副腎皮質ホルモンとしてコーチゾールを測定した。Spの測定に先立ち採血し大塚アッセイ研(徳島)に依頼しRIA PEG法(栄研イムノケミカル)にて測定した。正常者6名(25歳より50歳,男5名女1名)呈色素変性症患者5名(18歳より55歳,男4名,女1名)はERG;測定不能,EOG:平坦型,中心視力:0,4以上,視野:20°前後の人を選んだ。遺伝型はいずれも劣性遺伝であった。下垂体機能異常者2名(いずれも女子)はクッシング症候群により下垂体全摘出術を受けた者1名(デキサメサゾン1.5mg投与)とシーハン症候群1名(ステロイド剤投与なし)でいずれも本院内科に入院中である。
中心性滲出性網脈絡膜症に対する光凝固治験
著者: 井上暁二 , 追中松芳 , 調枝寛治 , 長谷部治之
ページ範囲:P.1176 - P.1177
Neovascular macropathyの治療としては光凝固療法が屯要な位置をしめるが,この光凝固療法の適応と効果については議論の多いところである。今回,著者らは中心性滲出性網脈絡膜症(Rieger)にアルゴン・レザー光凝固を行い,良好な結果が得られたので,反省点とともにその概要を報告する。
対象は1978年1月より80年12月までの3年間に,広大眼科に受診した中心性滲出性綱脈絡膜症の19例19眼のうち,光凝固治療に応じた7例7眼である。
老人性白内障手術後の網膜剥離
著者: 加藤秋成 , 太田陽一 , 斉藤啓子 , 竹内忍 , 中谷玲子 , 加藤綾子
ページ範囲:P.1178 - P.1179
白内障手術後の網膜剥離は,重大な術後合併症の一つであるが,その原因には不明な点が多い。これまで本邦において,母集団を網膜剥離側においた無水晶体限網膜剥離に対する報告は少なからずあるが,白内障手術後の集団をも考慮した基礎的資料は少ない。今回我々は老人性白内障全摘出術後の網膜剥離発生率と,無水晶体眼網膜剥離発生に関連する因子につき検討した。
調査対象は,(1)1975年1月から1981年3月までの問に,当院で手術した40歳以上の老人性白内障全摘出術1,022眼(男413,女609,以下白内障群とする),(2)1975年1月から1981年9月まで当院で手術した裂孔原性網膜剥離1,019眼のうち,無水晶体眼網膜剥離を含まない40歳以上の非外傷性網膜剥離466眼(男232,女234,以下網膜剥離群とする),(3)上記(2)の期間に当院で手術した無水晶体眼網膜剥離64眼のうち,40歳以上の老人性白内障手術後の42眼(男33,女9,以下無水晶体眼網膜剥離群とする)。
網膜色素変性症の病勢進行を遅らせる目的で製作した眼鏡レンズの紹介(第1報)
著者: 戸塚清 , 高山秀隆 , 谷野洸
ページ範囲:P.1180 - P.1181
網膜色素変性症は,遺伝子の異常に基づく進行性の変性疾患である。古来多くの治療法が考えられているが,いずれもその効果は思わしくない。我々はこの疾患を全治させようというようなことは考えないが,進行性を幾分でも遅らせる方途はないかと考えた。このような観点のもとに,過去の文献を渉猟して行く中に,1眼を長期間被覆して置くと,病勢の進行が,まだ確証はないが,防げそうだという内容の幾編かの報告を見出した。すなわち動物実験では,たとえばラットで,そのロドプシンの最大吸収波長に相応する可視光を,連続して3日間照射すると,視細胞の外節と内節の分離現象が見られるようになり,これは非可逆的な変化である1,2)。
また人間では,ハーバード大学のBersonが,永年にわたって一つの信念を持って,この方面の研究を継続している。彼は初期の網膜色素変性症患者において,光を遮蔽すると網膜視細胞の変性の進行が緩やかになる可能性を示し,この考えに則って,不透明な強膜コンタクトレンズを作り,これを一つの治療法として,患者の1眼に装着して見た3,4)。
余の方法による網膜色素変性症の治療成績について
著者: 広瀬金之助
ページ範囲:P.1182 - P.1183
緒言網膜色素変性症の治療に関しては古くから種種なる療法が発表されているが,有効的確の療法が現在も未だない。三國1)は薬物的,臓器ホルモン的,理学的,手術的療法等に分けて効果のあったと称する報告例を手際よく紹介しているのでくわしい事はそれに譲る事とするが,次々に発表された新しい療法も,追試して報告者のいうごとき効果がなかったためか自然に廃たれてしまうかにみえる。手術療法において特にその感が深い。
著者は以前某大学脳外科学教室で,視交叉附近の病変による視神経萎縮にイミダリンの皮下注射が有効だとの話をきいていた。大学奉職中には至難であったが,毎日患者に接して診療観察を行いうる身分になったので,視神経萎縮および種々なる網脈絡膜萎縮にイミダリン球後注射を行う事を決意した。けだし,皮下注射に比して球後注射は量が少なくてもより強力に,より長く作用すると考えたからである。著者は過去19年間これら諸疾患に試みて,みるべき効果を挙げたと信ずる。この報告はその第1報である。
連載 眼科図譜・298
硝子体内播種を示した転移性網膜腫瘍
著者: 加賀典雄 , 牧浦正直 , 平松君恵
ページ範囲:P.1020 - P.1021
悪性腫瘍の眼内転移は葡萄膜にみられることが多く,網膜に転移するのは極めて稀とされている。今回我々は胃癌患者で外科的手術を受けた後,全身各所に転移を生じ,同時に網膜に転移巣と思われる滲出性病巣を来たした症例を経験したので報告する。
症例:39歳,女性。
臨床報告
進行性錐・杆体変性症の2例
著者: 山名忠己 , 伊藤久太郎 , 船田雅之 , 藤永博
ページ範囲:P.1184 - P.1189
9歳で初診した22歳の進行性錐・杆体変性症の1例を報告した。あわせて逆網膜色素変性症と診断された1例を報告し,色覚,暗順応,螢光眼底所見,ERG,ERP,EOGなどの精神物理学的,電気生理学的検索の結果を比較した。
その結果,いずれも進行性の錐体,杆体の変性疾患で,錐体の障害が杆体の障害よりもより優位であり,cone-rod dystrophy (progressive cone-rod degeneration)と考えられた。
眼内フィラリア迷入の1症例
著者: 佐竹成子 , 矢ヶ崎克哉
ページ範囲:P.1195 - P.1199
奄美大島出身で69歳の男性の右眼前房内に寄生虫を認め,手術的に摘出除去した。虫体は,すでに死亡しており,死後長期間を経ているため,外表層のクチクラ(Cuti—cula)のみを残して,内臓はすべて消失していた。しかし,クチクラの形態,患者の出身地,生活歴より,フィラリア(おそらくWuchereria bancrofti)と診断した。術前,術後共眼内に炎症症状は認められず,全身状態にも異常はなかった。
眼科手術学会
眼内手術と血液網膜柵
著者: 三宅謙作 , 朝倉当子
ページ範囲:P.1190 - P.1193
みかけ上正常眼底で術後1年以上を経過した白内障嚢内摘出(ICCE)眼121眼,諸種対緑内障手術眼26眼の血液網膜柵の状態をvitreous fiuorophotomctryで調べた。ICCEの術後1年の群では70眼中32眼(46%),3年の群では60眼中18眼(30%)に血液網膜柵の破壊がみられ,いずれの群でも手術時の年齢が高い程,高率に破壊が起っていた。一方,対緑内障手術眼では術後平均8.6年で26眼中6眼(23%),ICCEに比べ低率であった。これらの破壊頻度は,正常群に比べ有意に高率であった(ICCE 1年p<0.005,3年p<0.05,緑内障p<0.1)。破壊の背景となる因子およびその意義について二,三の考察をなした。
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(10)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斉藤仁男
ページ範囲:P.1200 - P.1201
19.玉泉房流書伝集
この流派の古写本に挙げられている書名には玉泉流,玉泉房流,玉泉坊流,玉仙流等いろいろあるが内容は大同小異である。
眼科諸流派の興りを考察する場合,寺院との係りを探ってみることが多いが"玉泉"という名のつく寺には伊豆下田にあるタウンゼント・ハリスで有名な玉泉寺,中国湖北省當隋陽県玉泉山の山麓にある玉泉寺(隋の開皇12年天台大師が隋の煬帝晉王広に請うて建立)等があり,中国ではその後,玉泉の名は天台宗の異称として用いられるようになったといわれる。また馬島流分派には五流五家があって,その五家の中に玉泉坊という一家が含まれている。「玉泉房流書伝集」が前記と係りがあるや否や不明であるが,本書に伝えられる記述によって玉泉房流眼科を窺知してみよう。
GROUP DISCUSSION
ブドウ膜研究会
著者: 増田寛次郎
ページ範囲:P.1203 - P.1204
た時もあったが,小さな部屋であるためにお互いに身近かに感じられて,質問,討論が活発に行われた事は大変結構だと思った。18題の演題の他に今回は中国ハルビン医科大学附属第2病院の景崇徳先生の特別講演も組んだ。時間をややオーバーしたけれども司会者,講演者,質問者の協力により最後の18演題まで終える事ができた。ある一つのテーマにしぼって研究会を開く事も良いけれど,今回のように一般公募の形で研究会を進める事も多くの人々にブドウ膜炎に対する興味を持ってもらう意味で大切なことだと思う。
最初の演題は「Acute retinal necrosisの一例」であった。昨年の臨眼のグループディスカッションにおいてのテーマであった桐沢型ブドウ膜炎の定義,診断,治療などが討議されたが今回も大いに論議をよんだ。浦山氏らの桐沢型ブドウ膜炎とPriseらのbilateral acute retinalnecrosisの異同はまだはっきりされていないが,ほぼ同じ疾患を見ているものと思う。今回も治療に抵抗して予後が非常に悪い症例の呈示であった。このような例に対して大量のステロイド療法とか,網膜剥離手術が成功したという症例の追加報告などがあった。これからも本病の本体,診断,および治療に関しての研究が必要であろう。第2と特別講演は交感性眼炎についてであるが,最近交感性眼炎をみる例はほとんどないけれど,過去の症例についての分析が報告された。
基本情報
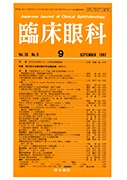
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
