人工水晶体挿入後2〜3年で角膜内皮障害を認めた4症例を経時的に観察し以下の結果を得た。(1) specular microscopeにより最後に観察しえた角膜内皮のaveragecell densityは400〜500/mm2, average cell areaは2,000〜2,500μm2であった。(2)症例2および症例3のフルオ前房水角膜移行係数(kc・ac)は各々0.23, 1.49(hr−1),分配係数(rac)は各々0.83, 0.74の値を得た。(3)全層角膜移植を行った2症例の被移植片および摘出人工水晶体の走査電顕的検索では露出したデスメ膜の網状線維性構造と島状に残存した角膜内皮の細胞間接合部の破壊像を認めた。また人工水晶体のレンズ表面に細胞の付着像は認めなかった。
雑誌目次
臨床眼科37巻2号
1983年02月発行
雑誌目次
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
学会原著
後房レンズ挿入眼で観察した血液房水柵破壊とその交感性反応
著者: 三宅謙作 , 朝倉当子 , 三浦花
ページ範囲:P.117 - P.121
白内障乳化吸引後に,後房人工水晶体を挿入した眼の血液房水柵の破壊とその他眼の血液房水柵の交感性反応を術後1日,1週および4週において細隙灯式fluorophoto—metryで検討した。同時に,手術眼に局所投与したindomethacinのこれら柵破壊に対する効果も二重盲検的に調べた。手術眼ではindomethacinは術後1週と4週においてplaceboと比較して有意に血液房水柵の破壊を抑制したが,それらの他眼の交感性反応では検査全期間を通じ,placeboとの間に有意差を認めなかった。手術後1日,1週および4週で交感性反応の大きさを比較すると,術後1日が有意に大きかった。さらに術後1日の交感性反応は,手術眼の血液房水柵の破壊の大きさに比例した大きさで起こったが,術後1週と4週では手術眼の破壊の大きさとは無関係に起こった。手術に際して起こる血液房水柵破壊の交感性反応は,手術時の術眼の柵破壊の大きさが最も関連があるように考えられ,これが術後一定期間残存する症例があった。手術眼から他眼への交感性反応伝達のメカニズムについて二,三の考察を行った。
眼炎症におけるロイコトリエンの役割—第1報実験的ぶどう膜炎に対する抗SRS-A剤の効果
著者: 砂田昭信 , 金恵媛 , 宮永嘉隆
ページ範囲:P.123 - P.129
生体の炎症や免疫反応に深くかかわっている物質の一つとして,ロイコトリエン(LTs=SRS-A)の存在がクローズアップされて来ているが,眼炎症にLTsがどのように関与しているかは未だ解明されていない。
今回,抗SRS-A作用を持つとされるKC−404を用いて,ウサギの実験的ぶどう膜炎がどのように抑制されるかを検討して次の結果を得た。
(1)卵白アルブミンをウサギの硝子体中に注入して起こさせたぶどう膜炎に対しては,かなり有意の抗炎症効果が認められた。
(2)牛血清アルブミン注入によるアルサス型ぶどう膜炎に対しては炎症が強すぎたためか,コントロールとの間にはっきりとした有意差は認められなかった。
(3) Carrageeninをウサギの硝子体中に注入して起こさせたぶどう膜炎に対しては,効果を比較検討するほどの炎症が起こらなかった。
以上より,眼炎症においてもロイコトリエンの関与があろうことが示唆された。
ベーチェット病におけるインターフェロンシステムの研究
著者: 大野重昭 , 小竹聡 , 松田英彦 , 藤井暢弘 , 皆川知紀
ページ範囲:P.131 - P.136
ベーチェット病におけるインターフェロン(IFN)システムを検索するため,36例の本病患者より51検体のリンパ球試料を得,IFN産生の動態やリンパ球の反応性についてしらべた。その結果,本病患者の末梢血リンパ球は単培養のみで高力価のIFN—γを産生し,眼発作期にはこれが有意に低下した。IFN—γ活性は患者の性別や病型,HLA-B5の有無との間には有意の関係を示さず,いずれも高い活性を示した。IFN—γ産生細胞の起源は患者の末梢血Tリンパ球であり,マクロファージの添加によって産生は増強されなかった。本病患者のCon A誘発IFN—γは対照より増強していたが,HSVによるIFN—α産生は著変を示さなかった。
IFNシステムは生体の免疫応答調節因子として本病の病因,病態生理と密接に関連していることが考えられる。
原田病の経過についての検討—ステロイド大量投与例と非投与例の比較
著者: 山本倬司 , 早川薫 , 秦野寛 , 鎌田光二 , 佐々木隆敏
ページ範囲:P.137 - P.142
原田病に対するステロイド全身大量投与による治療法(以下大量療法と略す)の評値を改めて行うために,その施行例19例と,非投与の8例の臨床経過を比較し,検討を行った。その結果,大量療法を行った19例中11例が,非投与8例中1例が遷延型となった。大量療法を行った群に遷延型となったものが多かった。
網膜静脈閉塞症に対する治療法—特に線溶療法と光凝固療法の応用について
著者: 岩船裕一 , 村田幹夫 , 吉本弘志
ページ範囲:P.143 - P.148
網膜静脈閉塞症に対し,線溶活性剤urokinase初回量10万単位を使用し,その後光凝固療法を併用してその治療効果をみた。
(1)10万単位投与にて線溶亢進状態を示すPT, aPTTの有意の延長があり,血液粘稠度も低下した。
(2)光凝固療法併用にて視力改善率75.9%, 0.6以上の症例が53.1%と良好な結果を得た。
以上より,urokinaseをもってする線溶療法は有効な治療法であるが,それのみで改善の得られない例ではすみやかに適応を決定し,光凝固療法を比較的早期に併用することにより,視力の予後に関しても良好な結果が得られることが判明した。
中心性漿液性網脈絡膜症に対する光凝固治療と網膜感度
著者: 松野公利 , 春田龍吾 , 三村治 , 可児一孝 , 下奥仁
ページ範囲:P.149 - P.153
(1)中心性漿液性網脈絡膜症13例にアルゴンレーザー光凝固を行い,眼底視野計を用いて,凝固斑および,その周囲の網膜感度を測定した。
(2)13例中12例において,凝固部の網膜感度の低下が認められた。
(3)凝固後,凝固部の周囲では凝固の影響によって,感度は一時低下し,再び上昇し正常に復した。
(4)凝固後,凝固部の感度は大きく低下し,1週間目頃から回復傾向を示すものがみられるが,この回復は3〜4週間目頃には停止し,正常感度までには戻らなかった。
(5)アルゴンレーザー光凝固による網膜の機能障害は,決して無視できるものではなく,その使用にあたっては常にこのことを念頭に入れておかなくてはならない。
難治性網膜剥離に対する磁性体応用法の開発
著者: 浦山晃 , 早川真人 , 田中泰雄 , 山木邦比古 , 桜木章三
ページ範囲:P.155 - P.158
巨大裂孔を有する網膜剥離に対する新しい治療として,磁性体応用法を考案した。その原理は,軟性磁性体の特性をもった金属(パーマロイメタル)を封入したガラス球を硝子体内に挿入し,後極寄り裂孔縁近くまで誘導し,予め強膜上に縫いつけた磁石(希土類磁石)との間に網膜を挾みこんで圧着させ,剥離網膜の復位を計るものである。家兎眼球内のガラス球が長期間無害であることを確かめた上で,臨床実験をも行ったが,まだ成功例は得られていない。
試作眼内光凝固装置による治療
著者: 檀上真次 , 田中康夫 , 山本保範 , 石本一郎 , 西川憲清 , 額田朋経 , 田野保雄 , 眞鍋禮三
ページ範囲:P.159 - P.162
試作したキセノン眼内光凝固装置を用い,硝子体手術中に眼内光凝固を行ったPDR 21眼(施行群)と行わなかった54眼(非施行群)とを比較検討した。
視力予後は,施行群が非施行群より,2段階以上の視力悪化例は少なかった。
施行群では,非施行群に比べ,虹彩ルベオーシスの発生,悪化は少なく,血管新生性緑内障の発生も少なかった。
硝子体手術中の眼内光凝固は,術後の虹彩ルベオーシス,血管新生経緑内障の発生の予防に効果があった。
糖尿病性網膜症における硝子体出血の予後
著者: 安藤伸朗 , 関伶子
ページ範囲:P.163 - P.168
(1)当科糖尿病外来で管理し,硝子体出血発症後6カ月以上観察できた58例80眼について,硝子体出血後の視力・網膜症の予後および予後に関する因子について検討した。
(2)硝子体出血眼の最終視力は0.3未満のものが80眼中43眼(53.8%)であった。
(3)硝子体出血80眼中,牽引性網膜剥離38眼(47.5%),吸収されない硝子体出血9眼(11.3%)。
(4)硝子体出血は3カ月以内81.5%,6カ月以内に90.7%が吸収された(大出血44眼中)。
(5)硝子体出血眼で,視力および網膜症の予後に関与する因子は,以下のごとくであった。
1)新生血管の部位:NVDはNVEより予後不良。2)新生血管の大きさ:新生血管の大きさが大きいもの程予後不良。3)硝子体出血の程度:大出血は小出血より予後不良。4)硝子体出血の型:網膜前型は硝子体型より予後不良。5) PRP:出血前PRP可能例は出血後のPRPや,非施行例より予後良好。
糖尿病性網膜症の新生血管および網膜血管床に対する光凝固療法の効果について
著者: 能美俊典 , 渡辺正樹 , 松浦啓之 , 山本由香里 , 瀬戸川朝一
ページ範囲:P.169 - P.174
重症型糖尿病性網膜症患者18例中27眼について光凝固を行い,その前後の螢光眼底像を比較し,毛細血管非灌流野の状態および新生血管に対する光凝固療法の効果を検討した。
(1)毛細血管非灌流野において毛細血管再造影を認めたものは27眼中20眼で,再疎通型を示したものは20眼中17眼,再形成型は14眼であった。再疎通型は光凝固による循環改善効果を示すと考えた。
(2)増殖型15眼について光凝固後その網膜新生血管の72.4%が,また乳頭新生血管は57.1%が消失・縮小し,光凝固は網膜新生血管により効果を示した。
また以上の結果を検討して,光凝固の適応時期・手技について少考を加えた。
単性緑内障における自律神経機能の研究—β—遮断剤点眼液の影響
著者: 大垣節子 , 橘川真弓 , 杤久保哲男
ページ範囲:P.175 - P.180
単性緑内障と診断された61症例(男性31例,女性30例)を対象とし,自律神経機能検査の一つであるMicrovibration (以下MVと略記)ならびに心理テストを行いβ—遮断剤点眼液の影響を検討した。
今回,β—遮断剤使用例と未使用例との間に眼圧の有意な差は認められなかったが,眼圧とMV,心理テストでは一部関連を認めた。
MVにより単性緑内障では交感神経緊張型が多く,しかもβ—遮断剤使用により副交感神経緊張型に移行する症例が多くあることからβ—遮断剤点眼液による自律神経機能への影響が推測され,また緑内障の成因の一つとして交感神経系の関与が示唆された。
糖尿病性網膜症の初期病変について—蛍光眼底造影法による研究
著者: 山名泰生
ページ範囲:P.185 - P.193
九大病院内科で治療中の糖尿病患者のうち,1977年10月から1982年3月までに当科糖尿病外来を受診し,検眼鏡的に網膜症を認めなかった166人,272眼を対象に螢光眼底造影を行い,糖尿病性網膜症の螢光眼底造影法による初発病変ならびに初期病変の推移について検討し以下の結果を得た。
(1)螢光眼底造影法により得られた異常所見は以下の五つであり,螢光漏出は163眼に,限局性拡張は124眼に,充盈欠損は55眼に,小点状螢光は33眼に,毛細血管瘤は29眼にみられた。このうち少なくともひとつ以上の異常所見がみられたのは272眼中181眼(66.5%)であった。
(2)2回以上繰り返し螢光眼底造影を行った症例の所見とそれらの統計学的な検討から,螢光漏出,限局性拡張,充盈欠損,小点状螢光,毛細血管瘤の順序で異常所見は発現してくる。
(3)各異常所見をもつ患者群の平均罹病年数には統計学的に有意差はみられなかった。
アルゴンレーザーによる開放隅角緑内障の治療(Ⅳ)—若年緑内障へのlaser trabeculoplasty
著者: 田邊吉彦 , 浅野隆 , 原田敬志
ページ範囲:P.195 - P.199
薬物コントロール困難の若年緑内障11例14眼にlaser trabeculoplasty (LTP)を行い,5例7眼で眼圧コントロールに成功,5例5眼で不成功,残る1例は1眼で成功,1眼で不成功であり,その成功と不成功の比は各々50%であった。
LTPにおけるlaser照射範囲は3例3眼が120°照射,6例6眼は180°照射,3例5眼は360°照射であった。そうして120°および180°照射例では成功率はいずれも33%であったが,360°照射の3例5眼はすべて成功している。それ故,この成功率はまだ上昇する可能性は強い。
LTP後,1度低下した眼圧が再上昇し,4週程してやっと落着き,以後安定した眼圧のコントロールを示す例があり,効果の判定には1カ月待つ必要がある。
原発開放隅角緑内障の初期視野異常の改善に関与する眼圧レベルの検討
著者: 勝島晴美
ページ範囲:P.200 - P.205
60歳以下の原発開放隅角緑内障で,初期視野異常の検出された46眼を対象として,視野の改善に関与すると思われる眼圧レベルについて検討した。観察期間は平均3年で,その間にのべ248眼の動的視野計測を行った。
視野の改善は48眼(19.3%)に認められた。視野検査前3カ月間の平均眼圧と,視野改善との間に,相関は認められなかったが,改善例の眼圧はすべて24mmHg以下であり,その71%は21mmHg以下であった。
視野の悪化は83眼(33.5%)に認められ,3カ月間の平均眼圧との間に強い相関が認められた。特に,Bjerrum areaに暗点の検出されている症例では眼圧との相関が強い。このような症例では視野の悪化を防ぐために,少なくとも20mmHg以下にコントロールすべきである。
視野の改善には,3カ月間よりもさらに長期間の眼圧コントロール値が関与している可能性もあり,また,個体差も考慮されるべき因子であると思われる。
内頸動脈閉塞症に続発する緑内障—Ⅱ.血管外科不適応例に対する検討
著者: 西川憲清 , 玉田玲子 , 松本聖子 , 張野正誉 , 竹本環 , 日山英子 , 山本保範 , 石本一郎 , 福田全克
ページ範囲:P.206 - P.209
内頸動脈閉塞症に続発する虹彩ルベオーシスが,trabeculectomyまたは,汎光凝固術によって消失した。
trabeculectomyすることにより,眼圧が下降し眼動脈圧と眼圧との圧差が拡大し,眼内循環が改善したと考えられた。また,汎光凝固は網膜を間引くことにより,hypoxiaに対応していると考えられた。
これらの手段により,続発緑内障の発生を予防できた。
学術展示
網膜血管異常を伴うVitreoretinopathyの2例
著者: 鈴木美佐子 , 松木恒生 , 平井香織 , 油井恵美子 , 近藤聖一
ページ範囲:P.212 - P.213
緒言瘢痕期未熟児網膜症類似の網膜血管形成異常とvitreoretinopathyを来たす疾患についてはいまだはっきりしたclinical entityが確立していないが,若年性網膜剥離との関連もあって興味が持たれるところである。今回我々は本疾患と思われる2症例を経験し,5年間にわたって経過観察できたので若干の文献的考察を加えて報告する。
症例症例1は11歳女児。生下時体重は3,260gで酸素投与の既往はない。視力はV.d.=0.04(0.1×—10.0D),V.s.=0.1(0.2×−4.0D)で右方視時に水平性眼振が出現するが,前眼部・水晶体には異常所見が見られない。眼底は両眼とも軽度汚穢色で牽引乳頭が見られ,また網膜血管は柳枝状に分岐しながら直線的走行をなしている。耳側周辺での血管終末部は帯状に異常分岐してこれより周辺では無血管野となっており黄斑外方ではこの無血管野が後極部へ向かってV字型に彎入している。これらの変化は右眼に特に強く,さらに右黄斑外側部に至る領域に黄白色滲出斑,色素沈着,線維性増殖物が認められる(図1)。螢光撮影上,耳側血管終末部には色素の漏出,血管吻合が見られ,特に黄斑外側から周辺に至る領域では色素漏出,組織染が強い(図2,3)。後部硝子体は両眼とも完全に剥離し耳側と下鼻側に硝子体網膜癒着を認める。
Retinal macroaneurysmの臨床像について
著者: 鷹尾良枝 , 直原修一 , 丹羽子郎 , 舩橋正員
ページ範囲:P.214 - P.215
1973年Robertsonは,網膜の小動脈にみられる孤立性の動脈瘤を一つのclinical entityとして考え,retinalmacroaneurysmと呼ぶことを提唱した。その臨床的特微として,①第3分枝以内の網膜小動脈に存在し,②限局性の網膜出血と浸出斑を伴い,③高血圧症,動脈硬化症のある高齢者に多く,④自然寛解の傾向があるという4点を挙げた。その後多くの症例が報告され,Robertsonの提唱した典型的な症例以外にも,種々の病像を示すものがあることが指摘された。今回われわれは本症を19症例20眼経験し,その臨床所見と経過について過去の報告と比較検討し,若干の知見をえたので報告する。
アルゴンレーザーによる経強膜光凝固の臨床応用について
著者: 河野望
ページ範囲:P.216 - P.217
緒言網膜裂孔に対する光凝固は主に,経瞳孔光凝固が行われている。我々は周辺部の病変や,中間透光体混濁のため,経瞳孔光凝固の困難な症例に対して,経強膜的に網脈絡膜を凝固する新しいアプローチを開発した。さらに今回,臨床応用に先だち日本猿を使用し,その効果および安全性を検討した上で臨床応用を行った。すなわち網膜周辺部に裂孔を有する9例9眼に対し,経強膜光凝固を行い,検眼鏡的に色素の増加を伴う瘢痕形成を確認した。
装置Nidek Arレーザー光凝固装置AC−3500Gを改作した1)もので,発振器からレーザー光を石英モノフィラメントファイバーで先端のプローベに誘導し,プローベ先端のTipより照射する。Tipは前極部用(径600μm,直針)と,後極部用(径300μm,曲針)の2種であり,容易に交換可能である。実施に際しては,双眼倒像鏡観察下で図1のように行った。
ぶどう膜炎症状を示した小児の網膜芽細胞腫の症例—前房内浮遊細胞および硝子体混濁の細胞学的検索の意義
著者: 山下秀明 , 宇山昌延 , 文元章能 , 本間哲
ページ範囲:P.218 - P.219
緒言網膜芽細胞腫がぶどう膜炎様症状を示すことがあり,その場合は診断が非常に困難となる。今回,小児に発症した原因不明の難治ぶどう膜炎の治療中に前房内浮遊細胞および硝子体中滲出物の細胞学的検索を行って網膜芽細胞腫と診断された症例を経験したので報告する。
症例10歳男児。1980年3月,右眼充血血に気づくも放置,5月に視力低下を自覚し某医受診,眼内炎の診断のもとに抗生剤,ステロイドの大量投与を受けたが軽快しないので,1980年5月20日当科受診した。初診時,矯正視力右0.3,左1.5,眼圧右49mmHg,左20mmHg。右眼所見;中等度毛様充血,前房水は大型滲出物を含み混濁,虹彩上に灰白色の円形の塊状滲出物を多数認めた。更に硝子体中に濃厚な惨出物と,網膜に白色の滲出物を認めた。強力な眼圧降下薬物治療を開始した。その後前房混濁が増悪し前戸蓄膿を認めたため(図1),7月10日と11月5日の2回前房水を採取し電顕にて細胞を観察したところ,悪性腫瘍細胞を認めたので1981年1月7日よりCo60を150rads,10回照射した。前房水混濁と虹彩上滲出物はほぼ消失したが,水晶体混濁が出現した。5月中旬より再び前房水混濁と虹彩上滲出物の出現をみ,7月29日前房水採取と同時に硝子体手術の上,水晶体吸引と硝子体滲出物を採取し,細胞診を行い,その結果,網膜芽細胞腫の診断を得た。
Sex-linked juvenile retinoschisisの一家系
著者: 河合功
ページ範囲:P.220 - P.221
緒言X染色体劣性遺伝を示す先天性網膜分離症は,特異な遺伝形式と臨床像から,若年者の黄斑部ジストロフィー群の主要な病型の一つと考えられるようになってきた1)。
今回,著者は,先天性網膜分離症の一家系3症例を経験し,螢光眼底撮影にて血管異常を認めたので,諸検査とあわせて報告する。
急性骨髄性白血病にみられた黄斑部脈絡膜新生血管
著者: 松野亨規 , 吉岡久春
ページ範囲:P.222 - P.223
緒言白血病にみられる眼底病変としてLeibreichが網膜炎の報告をして以来種々の眼底所見の記載があるが,最近急性骨髄性白血病患者の片眼に従来報告のない脈絡膜由来の新生血管を認めた症例を経験したのでここに報告する。
症例16歳女性。初診1982年2月5目。
網膜全剥離眼のEER (Electrically Evoked Response)
著者: 三宅養三 , 安藤文隆 , 太田一郎
ページ範囲:P.224 - P.225
緒言近年硝子体手術の導入に伴い極めて難治な網膜剥離も解剖的復位が可能となりつつある。手術は長時間を要し患者の負担も大きい。このような症例に対して術後の視機能予後を占い手術の適応を決めることは大変重要である。
網膜全剥離眼(以後TRDと略)ではERG (electro—retinogram)は一般に消失型となり手術予後を占うことはできない。VER (visual evoked response)も視細胞機能に強い影響を受けTRDでは強い異常を呈する。一方,眼球の電気刺激により誘発され後頭部より記録されるEER (electrically evoked response)1)はその網膜での引き金となる層がERG, VERとは異なり視細胞より中枢網膜と考えられるため2〜4),視細胞機能が脱落したTRDにおいて,その機能不全に陥った視細胞の影響を受けずに残余視機能を評値することが可能と考えられる。
向精神薬服用患者におけるERGの障害
著者: 森敏郎 , 尾上正軒 , 白井淳一 , 田沢豊 , 佐藤敬司 , 切替辰哉
ページ範囲:P.226 - P.227
緒言向精神薬の副作用の一つとして眼障害があり,時には網膜色素変性症などの網膜障害も生じることが報告されている。そこで今回は,向精神薬服用患者のERG・a, b, c波と律動様小波を測定することにより,これらの変化と薬物服用量との関係を検討し,向精神薬の網膜各層におよぼす影響を電気生理学的に調べた。
対象および方法対象は,岩手医大神経精神科に入院している眼科疾患の既往のない精神分裂病患者20名(男15名,女5名)40眼で,患者の平均年齢は34.0歳(21〜61歳)である。これらの対象の眼底は,検眼鏡要上いずれも正常である。向精神薬の平均服用期間は5.0年(1カ月〜11年)である。また,服用している向精神薬の種類は単一薬剤ではなく,各例でそれぞれ数種類にわたっているので,クロルプロマジン量に換算して服用量を算出した。
露出を自動化したフォトスリットランプの開発
著者: 金上貞夫 , 清水昊幸 , 柿沢弘一郎 , 平野隆 , 小池近司
ページ範囲:P.228 - P.229
緒言フォトスリット撮影の適正露光量の選び方は,スリット幅などの条件の変化に応じながら設定するが,これには熟練と経験を要する。我々はこの問題を解決するため自動露出装置を内蔵し,併せて独創的な光学系をもつフォトスリットランプを開発した。
自動露光の方法センサーによりスリット幅を検出し,コントロールユニットにより露光量の基本条件を設定する。光量は実験機による臨床撮影の結果,最適となる条件により決定した。この基本条件にカメラ絞り,開口絞り,倍率,カメラバックの種類などによる総合条件を加えスリット撮影の露光量を計算し,さらに撮影目的によって選んだ被写体の明るさに応じた補正を行い適正露光を自動設定する。カメラ絞りは選択式で,条件に合わない場合はブザーが鳴り,絞り補正の方向をコントロールパネル上にLEDで表示する。
片眼性網膜血管異常を呈した未熟児の1例
著者: 佐貫眞木子 , 小沢勝子
ページ範囲:P.230 - P.231
緒言未熟児網膜症としては特異な所見を片眼に呈した未熟児の1例を経験した。未熟児網膜症以外の因子が加わっていると推定し類似疾患や全身異常につき考察した。本例は早期にステロイド投与をうけており,実験的に立証されたステロイド誘発網膜症1)と網膜血管像が類似している点に注目すべきである。
症例在胎34週6日膜生下時体重1,560gのSFDの男児である。持続性低血糖のため生後4日から7日まで計7mgのプレドニゾロンを投与された。生後10日には低血糖は改善した(図1)。他に全身異常は認めなかった。生後14日に眼底検査目的にて当院小児科より眼科を紹介された。右眼底は後極部は正常,耳側周辺に無血管領域と血管分岐過多を認めた(図2)。左眼底は耳側から上方に広範な浮腫状無血管領域が黄斑部近くまであり,後極部血管は著明な怒張蛇行を呈した。また血管吻合が末端部のみならず後極側にも認められ,網膜硝子体出血もみられた(図3)。右眼は生後22日に境界線が形成されたが生後2カ月には自然に消腿した。左眼は出血が吸収され,血管の怒張蛇行が軽減し血管走行が直線化する一方,血管終末部の異常分岐はさらに増加し,生後25日には境界線形成をみた。生後28日に境界線上に硝子体への発芽がみられた。
連載 眼科図譜・303
Soft contact lenses装用後に発生した慢性乳頭増殖性結膜炎の症例
著者: 青木功喜 , 実藤誠
ページ範囲:P.106 - P.107
Allansmith1)がgiant papillary conjunctivitis (GPC)を報告してから5年の歳月が過ぎているがわが国からのGPCの報告は少ない。我々はGPCの組織所見についてはすでに報告2)したので今回は臨床像を中心に症例を供覧する。
対象:札幌市内の二つの眼科診療所において1981年1年間に受診した1年以上soft contact lenses (SCL)装用した1,083名について結膜を細隙灯顕微鏡検査を行いGPCを36名(3.3%)に認めた(表1)。そのうちの4例を供覧する。
--------------------
Charles L. Schepens-Retinal Detachment and Allied Diseases (2 vols.)
著者: 清水弘一
ページ範囲:P.168 - P.168
眼科の関係者すべてがながらく待望していたSche—pensの剥離の本が遂に出た。明かるいグレーの表紙に鮮かな青と赤の文字と模様の押された2冊本で,合せて厚さ7.5cm,目方4.8kgの大冊である。氏が網膜剥離に専念するようになって40年,ボストンのEye and EarInfirmary病院で網膜外来Retina Serviceを世界ではじめて開設してから36年になり,本書にはひとつの専門分野を歴史と共に作りあげた氏の知識と智恵が込められていると見られるのである。
網膜剥離を題名とはしているが,裂孔原性(特発性)剥離をその主対象とし,また,アカデミックな病因論よりも診断と治療とに圧倒的に大きな比重が置かれている。本書全体の7割が手術で2割が検査というページ配分だが,これは,剥離の理論的な面を前のVitreoretinalDisorders (Tolentino, Schepens & Freeman著,659pp.,Saunders, 1976)でたっぷり論じてあるからということらしい。逆に云えば,今度のこの本を読むほどの人は前著を既に卒業している筈ということかとも思われるのである。
臨床報告
ズームフォトスリットランプ(Nikon FS 2)の使用経験
著者: 原和彦 , 千代田和正 , 出口達也
ページ範囲:P.232 - P.235
従来のフォトスリットランプは,倍率変換やステレオ撮影時に,レンズの交換やアダプター装着の必要があり操作が繁雑であった。これらの問題点を補うズーム式変倍装置,ビームスプリッター切り換え式ステレオ撮影装置,背景照明用光ファイバー照明などを備えたフォトスリットランプを使用する機会を得て,臨床的に有用と思われたので使用経験について報告する。しかし,絞り系を備えていないため焦点深度が浅く,隅角撮影などにはやや解像力が不足であるなどの問題点もみられる。
Blowout fractureの経上顎洞および経眼窩整復について
著者: 沖波聡 , 小林博 , 柏井聡 , 本田孔士 , 後藤まゆき , 細見泰敏 , 松岡出
ページ範囲:P.237 - P.240
1972〜1981年の10年間に,blowout fractureの症例に対して,経上顎洞法(11例)と,経眼窩法(21例)で手術を行い,その成績を比較検討した。両者とも約70%で複視の消失が見られれたが,眼球陥凹に対しては,ほとんど効果が見られなかった。経上顎洞法は術野が広く,眼窩底骨折部への嵌頓組織の整復が行いやすく,もっと試みてよい方法と考える。
新しい抗ヘルペス剤Acyclovir®による治療成績—特にIDU耐性,実質性角膜炎に対する有効性について
著者: 千原悦夫 , 松田晴子 , 遠谷茂
ページ範囲:P.241 - P.245
樹枝状角膜潰瘍あるいは星状角膜潰瘍の8眼(6例)と実質病変を伴うヘルペス性角膜炎7眼(6例),計15眼に対してAcyclovir®〔9—(2—hydroxyethoxymethyl) guanine〕による治療を試み良好な結果を得た。樹枝状あるいは星状角膜潰瘍の患者は全例が治癒し,潰瘍が消失するまでの平均日数はわずか2,8日であった。IDU耐性と考えられる樹枝状角膜潰瘍の2眼に対してもAcyclovir®は著効を示した。実質性角膜炎を伴う7眼に対するAcyclovir®の効果も比較的良好で5眼において10日以内に潰瘍が消失し,角膜炎の軽快が認められた。
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(14)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斉藤仁男
ページ範囲:P.246 - P.247
23.眼科大秘伝保濟新流
わが国江戸時代の眼科諸流派の秘伝書には種々の流派名が付けられているが,いずれも原は中国古医方眼科を祖述したものが多く,その内容の根本的差異は少ない。ただ,より日本人に適合する医療に近づけるために少しでも他より優れた治療方法なり,薬物処方などを創意工夫してきたと思われる。そこに一流一派が興り諸流派が生れたものと考えられる。
眼科古写本の中には諸流派の秘伝書を抜萃して一つの秘伝書となしているものもある。「眼病門眼目一巻」という眼科古写本には鷹取氏の眼目秘伝,ホスミー流秘伝,真嶋一流の秘伝(寛永元年)あるいは且來村常念寺伝方等を集めて一書としている。しかし,こうした類の古写本には原本を後世になって書写相伝したものが多い。
GROUP DISCUSSION
超音波
著者: 山本由記雄
ページ範囲:P.249 - P.252
1.振動子改良に関する考察
セラミックと高分子圧電膜で後者の優秀性を確認し,圧電膜に周波数,直径,焦点距離などの多様変化を与え,最適の条件を探求しようと試みた。
基本情報
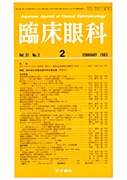
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
