両眼先天白内障の手術施行例31例について眼振随伴の有無により2群に分け,視力予後に関係するいくつかの因子について検討した。眼振をともなわぬ群は発症が遅く,随伴する眼異常も少なく,手術および光学的矯正が遅れても予後は良好であった。眼振をともなう群は発症が早く,随伴する眼異常の頻度も高く,眼振が発生してから治療を施行しても予後は不良であった。眼振は白内障によるvisual deprivationにて起こるとの考えをもとに早期手術,早期光学的矯正を行い,眼振の発生をみなかった5例を報告した。
雑誌目次
臨床眼科37巻8号
1983年08月発行
雑誌目次
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
学会原著
翼状片の病態に対する生化学的アプローチ—SDS—ゲル,125I標識レクチンを用いた糖タンパクの分析
著者: 上原文行 , 村松喬 , 小澤政之 , 大庭紀雄
ページ範囲:P.1049 - P.1053
翼状片および結膜組織をホモゲナイズ,超遠心分離した後,Fairbanksの系で,SDS—ゲル電気泳動を行い,クーマジーブルーを用いたタンパク染色,およびクロラミンT法により125I標識したレクチン(Con A, WGA, UEA−1, PNA)を用いて糖タンパクの検出を行い,両者の比較検討を行った。上清に関しては,翼状片と結膜とでは異なったパンドは検出されなかったが,沈渣では翼状片頭部に特異的な分子量36,000のCon Aと反応するバンドが検出されるとともに,コラーゲンのγ鎖を表わしていると考えられる30万のバンドが翼状片に強く検出された。後者においては,翼状片組織での架橋形成の増大が示唆された。
硝子体抽出液に対し,病理学的ならびに血清学的検索を行った桐沢型ぶどう膜炎の1例
著者: 月本伸子 , 高塚忠宏 , 上谷弥子 , 秋草正子 , 遠藤雄三
ページ範囲:P.1055 - P.1061
桐沢型ぶどう膜炎の症例に硝子体手術を行い,得られた硝子体の沈渣ならびに上清に対し組織学的およびウイルス抗体についての検索を行った。
(1)組織学的検索では一般のぶどう膜炎と同様の所見が観察されたが.核内封入体.ウイルス顆粒は認められなかった。
(2)硝子体液のHSV抗体価は1:128と上昇,型分類ではII型であった。
(3)これらの結果ならびに家族歴より,本症例はHSV II型の眼局所への感染である可能性が示唆された。
抗生物質のヒト眼内移行に関する実験的研究
著者: 有本啓三 , 村尾とし子 , 天野了一
ページ範囲:P.1063 - P.1067
セフェム系抗生物質Cefmetazole sodium (CMZ),ペニシリン系抗生物質TA—058,アミノ配糖体抗生物質KW−1070(Fortimicin)のIS剤について房水内および涙液内への移行性を検討した。その結果房水中への移行率はCMZ2〜20%TA−058 1〜20%,KW−1070 10〜50%で,涙液中への移行率はCMZ2〜15%,TA−058 2〜15%,KW−107020〜90%で,CMZとTA−058はほぼ同程度,KW−1070はCMZやTA−058より高い値をしめした。抗生物質の房水および涙液内移行は,血清中濃度よりほぼ予測でき,眼感染症に対する抗生物質の選択が容易となった。
春季カタルの涙液IgE
著者: 中川やよい , 多田玲 , 山本保範 , 若野育子 , 湯浅武之助
ページ範囲:P.1069 - P.1072
春季カタル患者の涙液IgEは,その増悪期には高値を示すことが明らかにされているが,同様の重症度を示す患者間にもかなりの涙液IgE 値の相違がみとめられる。このような現象を説明するために同一患者の涙液を希釈法により反復採取し,涙液IgE量の推移をみることにより,結膜におけるIgE産生の実態を把握しようと試みた。また血清と涙液でIgEとalbuminを同時に測定することにより,涙液IgEの由来すなわら局所産生によるものと炎症による血管外漏出によるものとの比率を検討した。IgEはPRIST法,albuminはsingle radial immunodiffusion法によって測定した。
その結果,同一例においては角膜症状の消長と涙液IgEの増減はよく一致していた。また輪部型のような春季カタルでも軽症例に属するものでは,涙液IgE 値は他の型と比較して低値であった。さらに結膜アレルギー患者10例中8例で,結膜局所でのIgE産生をみとめたが,涙液IgEの局所産生と血管外漏出によるものの比率は症例により非常に差異が大きいことが明らかになった。
関節リウマチに合併したSjögren症候群の治療
著者: 右田三紀子 , 川島健 , 吉野槇一 , 森田悦子 , 柿崎秀子 , 河瀬澄男
ページ範囲:P.1073 - P.1076
関節リウマチを合併したSjögren病患者99症例に点眼療法,内服療法を試み,その臨床的効果を検討した。
(1)6カ月の頻回点眼療法のみを行った群では,乾燥症状の一時的な改善は多くの症例でみられたが,持続的な寛解を示した症例は1割以下であった。
(2)点眼療法に加えてprednisoloneを投与した群では全身症状の強い症例ではその著明な改善をみたものもあったが,乾燥所見の改善はやはり1割程度に留まった。また,副作用の発現した症例が3割に認められた。
(3)点眼療法に加え,bromhexine 48mg/dayを投与した群では投与後6週の時点では7割近くの症例で乾燥症状の何らかの改善を認め,かつ涙液中のlysozyme値は著明に増加した(P<0.01)。その後乾燥所見は症例によって寛解と増悪をくり返したが,6カ月後の現時点においては投与開始時点と比較し,48%の症例で他覚的所見の改善を認めている。
以上より,(1)対症療法としての点眼療法は一時的にはかなりの症例で有効である事。(2)全身症状の強いものに対しては,prednisoloneが有効な事もあるが,副作用の発現頻度も大きい事。(3) Bromhexineは,RAを合併したSjögren病の乾燥症状に対しては有効であり,その効果の判定材料として涙液中のIysozyme 値が適当である事が考えられた。
ウイルス性結膜炎の臨床疫学的研究—感染経路を中心として
著者: 青木功喜 , 加藤道夫 , 大塚秀男 , 石井慶蔵 , 中園直樹 , 高橋美由起 , 陳振武 , 林金祈
ページ範囲:P.1077 - P.1081
1979年から1982年6月までにウイルス性結膜炎と診断した1,067名について臨床疫学的検討を加えた。院内感染は26.8%〜41.5劣の頻度にて発生し,その主感染源の一つに眼科外来小手術と老人があげられた。家族内感染は新患が再患に較べて多く,流行時に家族内において流行性,非流行性の判断が極めて難しい事を示しえた。プールにおける結膜炎の多くは塩素による刺激症状であり,ウイルス感染ではAd3とAd4によるものがみられ,Ad8によるものは見出す事ができなかった。これはプールでの感染源として眼より大便のウイルス排出を重視する必要を物語るかもしれない。院内感染における老人,家族内感染における乳幼児と母親,プールにおける学童に今後注意する必要があり,眼科専門医としては結膜炎における流行性の患者の選別と共に,サーベイランスにおける情報提供を行う事が大切である。またこのためには臨床所見のみならず病原決定を併行させて行う事が有用であろう。
硝子体フルオロフォトメトリーの臨床的応用
著者: 米谷新 , 稲葉茂 , 沼賀哲郎 , 山崎伸一 , 堀内知光
ページ範囲:P.1083 - P.1087
硝子体フルオロフォトメーター(Fluoromet model 120, Xanar社)を人眼に適用し,コントロール眼,中心性網膜炎,原田病,ベーチェット病,眼サルコイドーシス,糖尿病性網膜症,網膜静脈閉塞症の各症例計119眼で10%フルオレセイン—Naを体重kg当り7mgを静注し,1時間後に測定を行った。
前部・中部・後部硝子体の各3点における測定結果を推計学的に検討し,それぞれの疾患で特徴的な螢光色素の硝子体内濃度分布のあることが理解された(表1)。
螢光眼底撮影上網膜下に螢光漏出が認められる原田病などでは硝子体内への螢光漏出は観察されなかった。一方,血管炎を伴う葡萄膜炎では中部・後部硝子体への有意の螢光漏出が見られた。また全身の血管変化を伴う,網膜静脈閉塞症では前部・後部硝子体に有意の螢光漏出があり,糖尿病性網膜症では前部・中部・後部硝子体全ての部分で有意の螢光増強が観察された。これらの事実より螢光色素の硝子体内漏出には孟1管因子,特に内血液網膜柵の破壊が大きく関与していることが結論される。
飛蚊症の臨床的研究
著者: 荻野誠周 , 山岸和矢 , 山川良治
ページ範囲:P.1089 - P.1093
飛蚊症を主訴とする285例367眼の飛蚊症の原因は全て硝子体混濁であったが,加齢による硝子体変性が351眼とほとんどを占め,うち320眼に後部硝子体分離が存在した。乳頭前環がもっとも飛蚊症の原因となりやすく,線維性混濁,硝子体細胞,赤血球,剥離網膜前線維膜や黄斑前環が原因となっていた。後部硝子体分離を伴う飛蚊症の発症年齢は60歳代前半にピークを示したが,男性と中等度以上の近視は明らかに早発化因子であり,後者では好発年齢が約15年若かった。後部硝子体分離を伴う320眼(男性71眼,女性249眼)の合併症として,類嚢胞黄斑変性22眼6.9%,網膜前線維膜97眼30.3%,牽引性網膜裂孔20眼6.3%,硝子体網膜出血28眼8.8%,光視症48眼(lightening streak 41眼,後部硝子体剥離時閃光7眼)15.0%および格子状変性24眼7.5%がみられた。類嚢胞黄斑変性は女性に著しく好発(女性は20眼8.0%,男性は2眼2.8%)し,牽引性網膜裂孔は男性に好発(男性は11眼15.5%女性は9眼3.6%)した。硝子体網膜出血はその10眼35.9%に牽引性網膜裂孔を合併していた。
飛蚊症眼の硝子体変化
著者: 村上喜三雄 , 高橋正孝
ページ範囲:P.1095 - P.1098
出血性・炎症性変化がないにもかかわらず飛蚊症を訴える334名,425眼の硝子体変化を細隙灯顕微鏡法により観察し,次の結果を得た。
(1)飛蚊症を訴える患者は2:1の割合で女性に多く,右眼に多い傾向があった。
(2)飛蚊症を訴える眼の72%に後部硝子体剥離を認め,ことに50歳以上では87%に見られた。
(3)硝子体が剥離している眼の飛蚊症の主因は後硝子膜上の有形の混濁であった。またゲルの収縮が進行すると飛蚊症が自覚されなくなる傾向がみられた。
(4)硝子体剥離がなくて飛蚊症を訴える眼では,先天性の線維,あるいは加齢によるゲルの融解に伴う変性線維の混濁を自覚していた。
VDT作業とpaper作業における眼精疲労の比較検討
著者: 栗本晋二 , 岩崎常人 , 野村恒民 , 野呂影勇 , 山本栄 , 小松原明哲
ページ範囲:P.1099 - P.1104
Visual Display Terminal (VDT)を用いた作業者と,一般事務作業者(Paper作業者)の眼精疲労を比較するため調節機能を指針として検討した。
被験者33例には物名探索作業を2時間行わせ,作業による調節機能の変化をAccommodopolyrecorderとIn frared optometerで測定した。作業後,VDT作業者では調節近点と調節緊張時間に有意な低下を認め,Paper作業者には有意差を認めなかった。特にVDT作業者の中でも小文字のディスプレイを使用した群に著名な低下をみた。微動調節運動については,VDT作業者,Paper作業者ともに変化が認められた。しかしVDT作業者の変化が著しかった。
これらのことより,VDT作業はPaper作業に比べ,調節機能に与える影響は大であり,眼精疲労を発症しやすいことが示唆された。
高周波直線電子走査式超音波診断装置の眼科臨床応用
著者: 太根節直 , 小松章 , 神野順子
ページ範囲:P.1105 - P.1108
今回試用した10MHzは高速リニア電子スキャン超音波診断装置は,従来の眼科用高速機械スキャン装置に比べ,多くの症例において,分解能や階調性の点で優れていることが確認され,振動,騒音もなく,熟練を要せず,簡易,迅速な操作性に優れていた。更に電子的操作により眼内計測にも便利で,Bモード断層像の動的解析や,Aモード同時表示による組織鑑別(tissue differentiation)も可能であった。以上の諸特性をそなえた本装置は眼科の臨床診断上にも十分有用と考えられた。
Logarithmic amplificationを用いた最新の超音波診断装置TRISCANによる眼内膜様病変のtissue characterizationについて
著者: 馬場幸夫 , 益山芳正 , 小山田義貴 , 高橋信 , 林田中 , 澤田惇
ページ範囲:P.1109 - P.1113
眼科領域における最新の超音波診断装置TRISCANを用い眼内膜様病変の検索を行った。TRISCANは附属のカリパー装置によりBモードで組織間の距離や大きさをmm単位でデジタル表示でき,topographic echographyにきわめて有用であった。また本装置に用いられているAモードのS-curved amplificationとIogarithmic amplificationによるquantitative echographyを行い,その結果,S-curved amplificationよりもdynamicrangeが40dBおよび25dBのlogarithmic amplificationによる鑑別診断の方がより有用であることがわかった。
網膜赤道部変性と網脈絡膜瘢痕の中間型
著者: 佐藤清祐 , 西山愛子 , 嶺崎育世 , 高村悦子 , 酒井道子 , 中野由宇子
ページ範囲:P.1115 - P.1120
一つの病変で赤道部変性と網脈絡膜瘢痕双力の判定基準の幾つかを共有するものを両者の中間型とし,これについて記述した。中間型は検眼鏡所見を主に細隙灯顕微鏡所見を加味して以下のように分類した。
I.赤道部変性であるが,著明な色素増殖のため色素増殖性の網脈絡膜瘢痕の外観を示すもの。
II.基本が網脈絡膜瘢痕。a.小さい色素増殖性瘢痕が赤道部に帯状に集合し,赤道部変性様の外観を呈するもの。b.網脈絡膜瘢痕だが,また非定型的赤道部変性ともみなしうるもの。
III.赤道部変性と網脈絡膜瘢痕とが混在するもの。a.上記2病変が隣接して存在するもの。b.広い網脈絡膜瘢痕の中に赤道部変性が存在するもの。
なお赤道部変性と網脈絡膜瘢痕の螢光像の特長,すなわち若年者の典型的な赤道部変性では検眼鏡的には鮮明な境界が螢光像上は全く不鮮明であり,一方網脈絡膜瘢痕では検眼鏡的と同様螢光像上も境界鮮明であるという特長を参考にすることにより,中間型の判定をより確実に行うことができた。
赤道部変性患者201例,349眼について中間型をしらべた結果,I型は2例2眼に2個,II-aは4例5眼に11個,II-bは9例10眼に11個,III-aは9例(うち他の型との重複3例)9眼に11個,III-bは3例4眼中に4個,計27例30眼に39個見られた。
年齢的には中間型はほとんどが30代以上に見られ,30代以上の総数136例の17%に見られた。
Basic concepts and clinical evaluation of the Peritest automatic and semi-automatic perimeter
著者: L.Greve
ページ範囲:P.1133 - P.1136
厚生省研究班新分類による未熟児網膜症の活動期から瘢痕期への推移と今後の対策について
著者: 田中純子 , 馬嶋昭生 , 加藤寿江 , 鎌尾憲明
ページ範囲:P.1137 - P.1142
名市大未熟児病棟で管理された出生体重2,500g未満の低出生体重児のうち,1970年1月から1975年6月1でに生れた470例(A群)と,1977年1月から1981年7月までの272例(B群)を対象として,厚生省未熟児網膜症研究班の新しい診断基準に基づいて,活動期から瘢痕期への推移を検討し,次の結果を得た。
(1)極小未熟児の増加に伴い,重症網膜症が増加し,瘢痕を残すものも増加している。
(2)白色瘢痕組織のない瘢痕期1度aは0度に近い性格である。
(3)活動期2期まで進行したものは3期以上に比べて有意に瘢痕期0度が多く,3期中期まで進行したものは1度bとなるものが有意に多かった。
(4)活動期2期および3期初期まで進行したものは最終活動期の持続期間が長い程瘢痕が事高度となる。
(5)活動期から瘢痕期への移行についてA群とB群はほとんど差がない。
(6)現在名市大では全身的管理の向上がみられず,眼科的管理能力も限界に達しているので,今後は極小未熟児の出生防止とさらに一層の全身管理技術の向上や網膜症の発生,進行の防止対策の検討が必要である。
学術展示
横浜南部地域に多発した結膜掻痒症に関する研究
著者: 磯辺雅子 , 上杉エリ子 , 福吉泉
ページ範囲:P.1146 - P.1147
緒言1979年に大量のスギ花粉が飛散し多数のスギ花粉アレルギー患者が発生した。3年目にあたる今年(1982年)はスギ花粉産生周期では花粉増加年にあたる。しかも1981年7-8月の月平均気温が高かったため,今年は1979年を凌ぐほど大量のスギ花粉空中飛散量とスギ花粉症の増加とが予測1)されていた。
横浜南部の新興住宅地に位置する当院には1982年早春(主として2-3月)に116名もの結膜掻痒の患者が来院した。これらの42%はアレルギー性鼻炎症状を合併しておりステロイド剤点眼・抗ヒスタミン剤内服により自・他覚症状は消失した。我々はこの結膜掻痒症をスギ花粉症と想定し,アレルゲン特異的IgE抗体測定を中心に免疫学的検査を行った。
抗生剤の結膜下注射による腎毒性に関する研究—Gentamicinの成績
著者: 永井重夫 , 大石正夫 , 黒澤明充
ページ範囲:P.1148 - P.1149
緒言抗生剤の結膜下注射は,眼科化学療法を高める上に,きわめてすぐれた投与法である。結膜下注射により,高い眼内濃度がえられるからである。ただし,結膜下注射では,眼局所に与える障害に加えて,全身臓器に及ぼす影響を無視することはできない,アミノ配糖体系抗生剤であるneomycinの結膜下注射による全身血中への移行は,筋注時に匹敵するという報告もある1)。
そこで,アミノ配糖体系の一つであるgentamicin(GMと略)の腎毒性について,結膜下注射単独,筋注ないし静注の併用,さらにcefazolin (CEZと略)結膜下注射の併用時における腎機能ならびに腎組織像を検討した。
シェーグレン症候群における抗SS-AおよびB抗体について
著者: 中澤君代 , 植田達子 , 杉田由紀子
ページ範囲:P.1150 - P.1151
緒言シェーグレン症候群(以下SSと略)は,外分泌腺の慢性炎症性疾患であるが,最近はその病型について,乾燥単独症候群sicca complex aloneといわれている一次性SSとRA等自己免疫疾患を合併した二次性SSとに大別されている。SSの成因としては,種々の自己抗体が証明され,細胞性免疫異常が発現することより自己免疫学的背景が示唆されている。膠原病に出現する抗核抗体は(図1)のごとく分類されているが,1975年AlspaughとTanら1)により報告された抗非ピストン核蛋白抗体である抗SS-AおよびSS-B抗体は,SSに特異的な沈降抗体とされており,今回検討する機会を得たので報告する。
方法厚生省シェーグレン病班の診断基準で確言参例に該当した当外来通院患者45名およびリューマチ外来通院治療中の慢性関節リューマチ患者40名に対し,抗SS—A・SS-B抗体の検索とSchirmer's test, rosebengal染色,涙液内リゾチーム濃度測定,その他の血清学的検査を行い,さらに自覚症状について検討した。SS患者の内わけは,一次性SS 27名,二次性SS 18名である。シルマーテストはシルマーI法を行い両眼の和の値をとり,rosebengal染色は角膜と界側・耳側球結膜の染色度をその程度によりそれぞれscore 0〜3に分類し,両眼scoreの和の値をとった。
ワニの涙症候群の涙液分泌機構について
著者: 木村伸子 , 大野研一 , 岡田恒治 , 篠原淳子 , 河本道次 , 内田隆治
ページ範囲:P.1152 - P.1153
緒言食事の時に流涙のおこる現象はワニの涙症候群1)と呼ばれ,本現象は末梢性顔面神経麻痺に伴う後天性のものが大部分であり2〜4),先天性のものでは文献土に記載された例は極めて少数であり,しかもこれまでの先天性のほとんどすべての報告例は眼球運動障害を伴っている。前回5)我々は先天性で眼球運動に異常のない症例を報告した。今回更に眼球運動障害を伴わない先天性のもの1例と後天性のもの1例を経験し,これらの症例について種々検索を行い,体症候群の発生機序について検討し,いまだ不明の点が多いとされている涙液の分泌機構の解明の一助としたいと考え,ここに報告する。
症例1:5歳男児。生後10ヵ月頃より食事の時,両眼より流涙に気付き,泣く時にも両眼より流涙を認めた。既往歴は,母親は妊娠中,特別異常はなく,分娩は在胎39週,正常分娩で,現在までの発育は良好で外傷,顔面神経麻痺の既往はない。眼科的所見は視力V.d.=0.5(0.8×+1.0D.〇cyl.−2.0D.A.180°),V.s.=0.4(0.7×+0.50D.〇cy1.−1.5D.A.180°)であった。シノプチスコーフでは,他覚的斜視角−5°,自覚的斜視角−6°であった。眼球運動は両眼共,各方向に障害は認められなかった。涙道検査で両眼共,通過障害はなかった。全身的所見では先天異常は認められず,神経学的に反射は正常で病的反射は認められなかった。
生体高分子の角膜内皮細胞に及ぼす影響—その組織学的研究
著者: 池部均 , 小玉裕司 , 中路裕 , 佐々本研二
ページ範囲:P.1154 - P.1155
緒言最近,眼内手術に種々の生体高分子が使用されている。今回われわれは,シルコ社のコンドロイチン硫酸(以下CDSと略す),ファルマシア社のピアルロン酸ナトリウム(Healon®),および生化学工業のピアルロン酸ナトリウム(以下SPHと略す),を家兎前房内に注入し,角膜内皮細胞に及ぼす影響を形態学的に検索し,若干の知見を得たので報告する。
実験方法実験に使用した生体高分予は,CDS (平均分子量4万),Healon®(平均分子量160万),およびSPH(平均分子量83万)である。CDSはコンドロイチン硫酸を主成分とする50%溶液,SPH, Healon®はピアルロン酸ナトリウムの1%溶液である。これらはいずれも生食とpH 7.2のリン酸緩衝液でとかしてある。その浸透圧比はCDSが4.2,SPH, Hcalon®がほぼ1.0,pHは実測値でCDSが6.3,SPH, Healon®,が7.3である。実験には,体前約2.0kgの白色家兎を24羽用い,前房内注人の方法は27G注射針2本で,角膜輪部の2時と10時の位置より前房を穿刺し,一方より生体高分子を注入しつつ,他方より前房内容を吸引した。注入量と吸引量はそれぞれ0.3mlとし,操作中は前房深度ができるだけ一定となるようにした。注人後6時間,48時間,1週および1ヵ月経過して眼球を摘出し,角膜組織切片を光顕および電顕にて観察した。観察部位は角膜中央部と下方周辺部とした。
各種縫合糸の補体価に及ぼす影響について
著者: 石田常康 , 古賀道之 , 河島敏夫
ページ範囲:P.1156 - P.1157
緒言補体はclassicalまたはahernative pathwayを介して病原微生物などの異物を排除する働きをもっている。我々はさきに治療または検査薬剤のなかにも血液との直接の接触により補体系を活性化するものがあるという事を報告した1,2)。今回は各種縫合糸について検討した。
方法選んだ縫合糸は1.Catgut plain,2. Catgutmild chromic,3.PGA (ポリグリコール酸),4.Po—lyglactin 910, 5 PVA (ポリビニールアルコール),6Silk, 7 Polyester, 8 Coatcd polyester 9 Nylon (以下数字でもって略す。)で,1から5までは吸収性,6から9までは非吸収性である。太さ5-0,長さ30cmの縫合糸をそれぞれ細かに裁断し,被検血清0.5mlに浸し,37℃30分間インクユベートし,それぞれの血清のCH50価(Mayer 50%溶血法),CIq,C4, C3, C5およびC9の各成分蛋白埴(一元免疫拡散法),一部免疫複合体(CIq solid-phase EIA法)等を測定し,更にC3およびC5の活性測定(溶血話性法)および免疫電気泳動法を加えた。なお縫合糸の太さおよびインクユベートする時間は予備実験の結果から決めた。
中医学的四診簡略記録用紙による辨証について
著者: 酒谷信一 , 宇山健 , 奥平喜惟 , 黒瀬芳俊 , 宮崎栄一
ページ範囲:P.1158 - P.1159
緒言近年,漢方方剤がエキス剤として簡便に用いることができ,薬価基準にもかなり多数のものが収載されて,眼科臨床でもそれらを投薬する機会が増大しているようである。投薬の基準として病名あるいは症候別の使用方法が示されているが,眼科領域での投与指針となるような記載は極めて少ない。本来,漢方薬は病名に対応して選択するのではなく,患者の状態を症候から分折し,いわゆる「証」を決定して処方を選ぶべきものである。このような処方決定に至る過程に,日本漢方的ないわゆる"方証相対"という考え方と,中医学的ないわゆる"辨証施治"というアプローチがあるが,眼科疾患に対する後者の方法については,わが国の文献にはいまだみられない。今回,眼科臨床で用いやすい中医学的な辨証方法を考案する第一段階として.簡易四診記録用紙を作製し,それを用いた臨床応用の結果について報告する。
愛知県内盲学校在籍者の重複障害について
著者: 唐木剛 , 太田一郎 , 薗部光子 , 尾川尚子 , 田辺竹彦
ページ範囲:P.1160 - P.1161
緒言我々は,愛知県心身障害者コロニー中央病院において,多くの重度視覚障害児を診ているが,最近その中で重複障害を有する児の占める割合が増加している傾向を感じ,一連の愛知県における重度複覚障害児の実態調査を行ってきた。今回そのうちの一つとして,就学前の重度視覚障害児と比較するために,愛知県内の盲学校在籍者について,重複障害の程度・範囲を検討したので報告する。
方法愛知県内の2校の盲学校の小中等部に在籍の156名(男子89名,女子67名)について,担任教諭もしくは養護教諭にアンケート用紙の記入を依頼し,それを集計した(1982年3月現在)。
連載 眼科図譜・309
網膜芽細胞腫の自然寛解の2症例
著者: 小松真理 , 箕田健生
ページ範囲:P.1040 - P.1041
緒言
網膜芽細胞腫の中に自然寛解例のあることは良く知られているが,過去の本邦における報告は,いずれも片眼の摘出後の病理組織検索あるいは家族歴から網膜芽細胞腫の診断がついた症例であった1)。しかし,このような裏づけのない症例の中に,その1臨床所見から網膜芽細胞腫の自然寛解と診断され,経過観察によっても拡大増殖傾向の無い,良性腫瘍としての態度をとる症例が存在し,こうした例においては治療を急ぐことなくまず経過観察することが必要であると思われるので,その臨床像について報告する。
--------------------
第37回日本臨床眼科学会総会
ページ範囲:P.1122 - P.1129
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(20)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斉藤仁男
ページ範囲:P.1162 - P.1163
29.黒滝流眼病療治
秘伝書の書名には流派名を冠する場合が多く,一般的には天真流とか南蛮流,あるいは八幡流という様な相伝者個人名とは別の名称が付けられているが,一子相伝の場合でも相伝者自身の名前をとって何々流とした例も少なくない様である。この黒滝流もその類と思われる。
「黒滝流眼病療治伝」は黒滝源意,黒滝源達によってその秘法が伝えられたものである。
臨床報告
後天性Duane症候群の1例
著者: 後藤晋 , 久保田伸枝 , 丸尾敏夫
ページ範囲:P.1165 - P.1168
2歳,女子の後天性に発症したと思われるDuane症候群の1例を報告した。外傷などの原因がなく後天性に発症し,典型的なDuane II型を示した症例はこれまでの文献にみられない。左眼内転障害および外斜視,それによる頭位異常があり,左眼外直筋後転によって内転障害を軽減させ,外斜視および頭位異常を治癒せしめた。
片眼性網膜色素変性症の1例
著者: 西田祥藏 , 渥美一成
ページ範囲:P.1169 - P.1173
63歳女に見られた片眼性網膜色素変性症について検討した。
本症を原発性片眼性網膜色素変性症と診断するためには両眼性網膜色素変性症の不全型および二次性網膜色素変性症との鑑別が重要である。眼底所見,視野および暗順応検査などの臨床検査所見に加えるにERG,EOGなどの電気生理学的検査が不可欠で,他眼に網膜色素変性症に関連した異常所見がなく,更に既往歴から二次性網膜色素変性症を除外しなければならない。また可能な限り長期間の観察も必要である。
今回の症例は患眼が眼底所見の他に視野,暗順応,ERG, EOG検査で定型的網膜色素変性症の所見を示し,他眼はERG, EOGを含めて全く正常で,感染や外傷などの既往歴も見られないので原発性片眼性網膜色素変性症と診断した。
Bacillus cereus全眼球炎
著者: 大石正夫 , 永井重夫
ページ範囲:P.1175 - P.1178
33歳,男性,左眼穿孔性外傷後に発症したBacillus cereus全眼球炎の症例を報告した。B.ctreusは抗生剤感受性が特異的で,PC系,Cephem系のβ—lactam剤には抵抗性,EMには高感受性であった。本症例にはEMの全身投与により,視力の改善はみられなかったが全眼球炎は消炎せしめて,化療効果がみとめられた。
β—lactam剤の使用頻度の多い今日,B.cereus感染症はopportunistic infectionの一つとして,薬剤選択上注意しなければならないことを述べた。
透析療法中の糖尿病患者の網膜症について
著者: 吉富健志 , 石橋達朗 , 山名泰生 , 大西克尚 , 谷口慶晃 , 寿尚義 , 岡義祐
ページ範囲:P.1179 - P.1184
透析療法中の糖尿病性網膜症患者10例20眼について,その透析導入前後の経過を臨床的に検討し,次のような結果を得た。
(1)腎機能低下のある糖尿病患者の網膜症は,進行したものが多い。
(2)透析導入直後に眼底出事血の増多を示した例は,眼底透見可能例の87.5%を占め,この原因としてheparinの関与を考えた。
(3)腎機能低下を伴う糖尿病性網膜症に対しても,早期の光凝固は有効に思われた。
したがって,糖尿病性網膜症の管理にあたっては,眼科医としても患者の腎機能には十分な注意を払って,網膜症が急速に進行する可能性がある場合には早期に汎網膜光凝同術等の治療を行うべきであると考えだ。
網膜芽細胞腫の自然寛解いわゆるretinomaについて
著者: 小松真理 , 箕田健生
ページ範囲:P.1185 - P.1189
網膜芽細胞腫の自然寛解と思われる2症例を報告した。患者は両眼性散発性の5歳3ヵ月の女児および片眼性散発性の4歳3ヵ月男児で,それぞれ1年5ヵ月,9カ月の観察期間中に腫瘍増殖がまったく見られなかった。これらの腫瘍に共通した特微は①境界鮮明な円形または楕円形の灰白色の病巣,②限局性網脈絡膜萎縮石灰化,色素沈着等を伴っている,③年長児に発症しているという点であり,これらの所見はGallieらの提唱するRetinomaの臨床像に一致した。
糖尿病性網膜症とヘモグロビンA1との関係—その推移と変動について
著者: 半田幸子 , 高橋祥子
ページ範囲:P.1191 - P.1195
糖尿病者135名のヘモグロビンA1,(HbA1)の変動と糖尿病性網膜症の推移との関連について検討し次の結果を得た。
(1)6ヵ月以上の経過を観察しえた非網膜症者と網膜症者間でのHb A1の個体内変動はp<0.01で後者が大きく,Hb A1の平均値は前者7.56±1.09%,後者9.51±1.34%で後者のHbA1は前者のそれに比べて高く(p<0.01),その変動の位置も有意に高かった。
(2)光凝固未施行の網膜症で観察期間内での網膜症に改善のみられる者および不変の者と,その所見に悪化の傾向がある者とに二分し,両群間のHbA1の個体内変動を求めると,p<0.05で後者が大きく,またその平均値は前者8. 69.±1.29%,後者10.13±1.75%で後若のHbA1は前者に比べて高く(p<0.05),その変動7)位置は有意に高い値であった。
(3)光凝固施行後の網膜症について.施行前後の網膜症の推移を改善,不変,悪化と区別し,各々のグループ間でHb A1の個体内変動と平均値の差を比べてみたが有意差はなかった。
これらの結果から,糖尿病性網膜症の発生,進展を阻止するためにはその発生因子の一つであるHb A1の適正化に努める事が重要であるが光凝固施行後の網膜症ではその推移とHb A1との関係は明らかでないものがあると結論できる。
後天色覚異常用仮性同色表の製作に関する研究 フリーアクセス
著者: 田邊詔子 , 深見嘉一郎 , 市川宏
ページ範囲:P.1197 - P.1202
「標準色覚検査表第2部後天異常用」を製作し,その内容の紹介と共に,製作の基礎となった臨床的,実験的根拠を述べた。
青黄異常は,中心性網脈絡膜症58眼中43眼に検出され,この結果はAO-HRR表の青黄異常用表やパネルD−15による検出成績とよく一致した。
赤緑異常はエタンブトール視神経症24眼中19眼,視神経萎縮7眼全例に検出された。
本表の青黄異常検出表,赤緑異常検出表は,ごく軽い異常まで鋭敏に検出することができる。ただし,後天色覚異常は先天色覚異常と違って,一元的に診断あるいは判定できるものではない。後天異常においては,青黄異常と赤緑異常が互いに独立でなく,正常と軽い異常の区別も劃然となしえないからである。
なお,本表の青黄異常検出表によって,先天性第三異常も検出することができる。
GROUP DISCUSSION
視野
著者: 大鳥利文
ページ範囲:P.1203 - P.1208
1.網膜中心外部位の波長特性に関する研究
目的:さきに,われわれは色光情報処理機構の解明,またcolor perimeterにより,これを臨床的に応用するための基礎実験として,中心外部位におけるStilesのπ5機構体について報告した。今回.網膜中心部より10°までの部位における短波長および中波長に感度の良い機構体のthroshold versus intensity curve (t.v.i.曲線)を測定し,各機構体の波長特性ならびに感度分布について検討した。
方法:測定装置としてMaxwell視光学系を使用し,Stilesの2色閾値法に基づいて,検査光として視角1°で波長480nmの単色光を使用し,背景光は視角10°で波長590nmとし,threshold versus intensity curve (t.v.i.曲線)を測定した。このt.v.i.曲線に基づき,各機構体の感度分布を求めた。
コンタクトレンズ
著者: 曲谷久雄
ページ範囲:P.1209 - P.1211
本年は臨床眼科学会において9年振りにCLグループディスカッションが開かれた。六甲山を背にした神戸ポートアイランドの国際会議場で9月17日約200名が参加し盛大に行われた。
集まった演題も14題に及んだ。できるだけ討論の時間を持てるように心掛けた心積りであったが参会者の満足が得られるかどうかの不安もあった。神戸大眼科教室の方々の周到な準備の下に円滑に進行し多数の参加と活発な討論もあり盛会裡に終了したことは誠に喜ばしいことであった。
基本情報
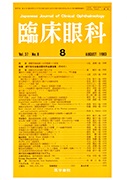
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
