シンナー中毒患者の眼症状について検討を加えた.症例は視覚系に異常を認めた5例と更に病理解剖例1例と精神症状により県立せりがや園を受診した14例の合計20例である.更に動物実験として,ラットに亜急性の実験,ビーグル犬に対して慢性実験を行い人の所見と比較した.その結果はほとんど同一であり,基本はシンナー中に含まれるトルエンによる中毒であることが明らかにされた.その所見は基本的に,眼,大脳,小脳,末梢神経に認められる,optic-cerebral-cerebellar-peripheral neuropathyとしてまとめられ,1日約5時間の吸入で11.3gを4年以上吸入すると眼症のみでなく上述の症候群が発症する可能性があることを述べた.
雑誌目次
臨床眼科39巻3号
1985年03月発行
雑誌目次
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
特別講演
学会原著
Proliferative vitreoretinopathy手術におけるbuckleの役割
著者: 松下卓郎 , 清水昊幸
ページ範囲:P.257 - P.260
Membrane peeling手技を用いて手術した赤道部裂孔によるproliferativevitreoretinopathy (PVR)においてのbuckleの役割の評価をするため,自験対象例を2群に分け検討した.硝子体手術単独群8例8眼は既存のbuckleには手をつけず,裂孔閉鎖を眼内冷凍凝固とair tamponadeのみで行った.一方,Buckle併用群14例14眼は硝子体手術と同時に裂孔閉鎖のためのbuckleとencirclingを確実なものに置き換えたものである.硝子体手術単独群8眼のうち復位は1眼のみ(治癒率13%),であり,7眼はairが抜けると再剥離した.裂孔周辺側の牽引が取りきれなかったためと考えられる.それに対して,buckle併用群の14眼では9眼が復位し(治癒率64%),非復位例は裂孔不明など5眼であった.赤道部裂孔によるPVRにおいては,硝子体側からの牽引をvitrectomy単独で除去できる保証はなく,強膜側からのbuckleによる牽引除去は治癒に導く不可欠の要素と考えられた.
CO2レーザー光による網膜下液排除
著者: 芳賀照行 , 千代田和正 , 塞河江豊 , 鈴木弘子
ページ範囲:P.261 - P.264
網膜剥離手術の網膜下液排除にCO2レーザー光を用いた.
(1)手術方法は強膜を切開して脈絡膜を露出した後,CO2レーザー光を照射し網膜下液を排出する方法である.
(2)動物実験で,CO2レーザー光は出血をきたさずに脈絡膜が穿孔でき,しかも網膜下液に吸収されるため網膜を障害せず,安全に網膜下液排除が行えることを確認した.
(3)裂孔原性網膜剥離18眼,牽引性網膜剥離2眼の計20眼の網膜剥離手術に応用し,合併症を起こさず全例で十分な網膜下液排除が行われた.
(4)安全かつ確実に網膜下液排除を行うことができる有用な操作と考えられた.
順天堂大学伊豆長岡病院新生児集中治療室(NICU)における未熟児網膜症の現状およびその予防について
著者: 稲垣有司 , 田中稔 , 加藤和男 , 中島章 , 本多節 , 柴田隆
ページ範囲:P.265 - P.270
順天堂伊豆長岡病院新生児集中治療室,(NICU)で,1982年4月の開設より1983年12月までに管理された低出生体重児217例中40例(18.4%)に未熟児網膜症が発症し,1例両眼4度の瘢痕となった.1983年度の静岡県東部地区(芝川町・富士宮市を除く)における発症率は,約0.25(32/13,000)%であった.
出生体重1,500〜1,999gにもかかわらず,特発性呼吸窮迫症候群(IRDS)および無呼吸発作にて挿管を行った症例は高率(54.5%)に発症しており,これらの症例は1,500g未満と同様に注意深くfollow upする必要があると考えられた.
超未熟児己(1,000g未満)の新生児死亡率が低下し,超未熟児の占める割合が7%(15/217)と増加したが,混合型Ⅱ型の発症率に増加傾向はなかった.低出生体重児の母親の約半数が,流早産の既往あるいは今回の妊娠経過の異常を伴っていたことから,未熟児出生の予防のためにもこのような状態にある妊婦に対する妊娠中の異常の早期発見,早期治療に関する啓蒙の必要性を感じた.
超未熟児における網膜症の進行に関与する全身諸因子の検討
著者: 加藤寿江 , 馬嶋昭生 , 鎌尾憲明 , 田中純子
ページ範囲:P.271 - P.275
1975年1月から1983年12月までに名市大末熟児病棟(NICU)で管理された低出生体重児は525例であり,このうち多胎児を除いた超未熟児は37例(7.0%)であった.これら超未熟児を対象として網膜症の発生・進行と全身諸因子との関連性について検討し,以下の結果を得た.
(1)名市大NICUでは1975年〜1977年と比べ,1978年以降超未熟児が増加している.
(2)超未熟児では網膜症発生率は100%である.
(3)超未熟児の増加に伴って,重症網膜症も増加している.
(4)網膜症の進行は,酸素投与期間および交換輸血以外の全身諸因子とは関連性はない.
(5)進行度は児の個体差が大きく関与し,全身状態のみからでは進行を推定することは困難である.
(6)失明防止のためには,早期からの厳重な眼科的管理,適切な治療が必要である.
網膜芽細胞腫のレクチン結合部の組織細胞化学的検討
著者: 秋山理津子 , 小林修 , 馬詰良比占 , 徳田久弥 , 箕田健生 , 高田邦昭 , 平野寛
ページ範囲:P.277 - P.282
特定の糖構造と特異的に結合する糖結合蛋白であるレクチンを用いて,網膜芽細胞腫におけるレクチン結合パターンを,光顕ならびに電顕下で,組織細胞化学的に検索し,正常家兎網膜およびヒト網膜の場合と比較検討した.
正常家兎網膜では,peanut agglutinin (PNA)は杆錐体層,外顆粒層,Ricinus communisagglutinin (RCA)は外顆粒層.内境界膜,神経線維層,wheat germ agglutinin (WGA)は杆錐体層,concanavalin A (ConA)は全層にわたってそれぞれ反応陽性であった.
正常ヒト網膜では,WGAは杆錐体層に強陽性,ConAは全層にわたり陽性反応を呈した.
網膜芽細胞腫では分化型,未分化型共にWGAとConAとが陽性であった.ロゼット形成細胞では,組胞膜に反応陽性であり,特にロゼット中心に一致して強陽性であった.
以上の結果から,特にWGAを用いた場合.網膜芽細胞腫と視細胞に共通の糖鎖構造が存在することが示唆された.
成人にみられた網膜芽細胞腫の1例
著者: 矢吹利子 , 岩下正美 , 古野史郎 , 松尾治亘
ページ範囲:P.283 - P.288
網膜芽細胞腫の成人例は稀であり,手拳大ほどの著明な眼球の伸展拡大と眼球突出を来たした報告例は,文献的に調べえた限りでは,わずか2例のみであった.自験例は視力低下と視野障害を訴え,左眼内腫瘍の診断を受けたが,約2年半来院せず放置していたところ眼球打撲を契機とし,腫瘍の急速な発育によって眼球の伸展拡大と著明な眼球突出を来たした21歳男子の症例である.CT検査では,著明に拡大した左眼球は眼窩をほぼ充満し,上顎洞内への浸潤が認められた.全身的には転移病変はなく,放射線治療の後に,上顎洞部分切除を含む眼窩内容除去術を行った.病理組織学的には未分化型綱膜芽細胞腫であった.現在術後9カ月を経過するが,再発および転移の微候は認められていない.
人眼ERP(Early Receptor Potential)の臨床的研究—第16報二,三の眼疾患における単色閃光ERP所見
著者: 玉井嗣彦 , 和田秀文 , 北川康介 , 割石三郎 , 上野脩幸 , 野田幸作 , 岸茂 , 豊田英治 , 伊与田加寿 , 竹村恵 , 佐々木徹 , 内田邦子
ページ範囲:P.293 - P.298
(1)赤色盲(12歳,男性)の場合,緑色,青色閃光ERPには一正常者と比べて有意の振幅変化はみられなかったが,赤色閃光ERPにおいて明らかな振幅(R1-R2)の減弱がみられた.緑色盲(6歳,男性)の場合には,赤色,青色閃光ERPには有意の変化はみられなかったが,緑色閃光ERPにおいて明らかな振幅の減弱がみられた.
(2)錐体ジストロフィー(25歳,女性)の場合,赤色,緑色,青色の各閃光ERPにおいて,著しい振幅の減弱が観察された.
(3)網膜色素変性症(65歳,女性)の場合,ERGはnonrecordableであったが,いわゆる"dissociation phenomenon"として,赤色,緑色,青色の各閃光ERPは減弱を示すものの認められた.
(4)これより,視細胞外節レベルでの錐体機能障害の把握にこの種の単色閃光ERPは有用であると思われる.
網膜疾患の電気生理学的分析—Stargardt病—黄色斑眼底群
著者: 若林謙二 , 米村大蔵 , 河崎一夫
ページ範囲:P.299 - P.303
(1) Stargardt病一黄色斑眼底群で,高浸透圧応答およびDiamox応答(網膜色素上皮由来の薬物誘発応答)所見によって網膜色素上皮の障害が示唆され,この知見は本症の主病変が網膜色素上皮にあるという組織学的知見を支持する新しい電気生理学的所見である.
(2)我々の薬物誘発応答(高浸透圧応答およびDiamox応答)によって検出された本症の網膜色素上皮障害の程度は,Nobleの検眼鏡的分類(Ⅰ〜Ⅳ群)におけるfleckのひろがりの程度によく対応した.
網膜色素変性症の眼底所見と病期—無色素変性症と脈絡膜毛細血管板萎縮について
著者: 飯島裕幸 , 岡島修 , 岡本道香 , 平戸孝明
ページ範囲:P.305 - P.309
63例の定型的および無色素性網膜色素変性症(以下PRDと略)を主に螢光眼底造影上の脈絡膜毛細血管板萎縮像(以下CCAと略)に基づいて4群に分類し他の臨床所見との相関を調べた.第1群は無色素性PRD,第2群はCCAを認めない定型的PRD,第3群は視神経乳頭径大以下の小型のCCAを認める定型的PRD,第4群は視神経乳頭径大以上の大型のCCAを散在性あるいは融合性に認める定型的PRDである.以上の分類は,遺伝型式および発症時期とは明らかな相関を有せず発症後の期間,視力,視野,色素異常と相関しており,本症の病期を反映すると考えられた.
老人性黄斑円孔—その2経過観察結果と尿中estrogen
著者: 湯沢美都子 , 松井瑞夫
ページ範囲:P.311 - P.315
初診時に片眼あるいは両眼に老人性特発性黄斑円孔がみとめられた36症例(うら40眼に円孔がみとめられた)と円孔の前段階の病変を疑った9症例(片眼円孔症例の対側眼をふくめると50眼)について,検眼鏡検査,細隙灯顕微鏡検査,螢光眼底造影法によって経過観察を行った.また,円孔を有する21症例について,1日尿中のestrogenを測定した.これらの観察結果から,以下の結論が得られた.
(1)初診時黄斑嚢胞をみとめた7眼中4眼57%と,臍状病巣をみとめた3眼中1眼33%に,経過観察中に円孔の発生を確認できた.このことから,円孔形成の前段階としては黄斑嚢胞に最も注意すべきと結論した.
(2)円孔発生時円孔縁に付着していたopeculumが,その後発生した後部硝子体剥離の際に後硝子体膜に付着した例や,後に円孔縁から分離して門孔底に付着した例が観察されたことから,硝子体牽引は円孔の完成には関与していても,円孔発生の主要因ではないと推論した.
(3) opeculumが分離せずに再付着した例,円孔底に組織増殖が発生した例などが観察され,一度形成された円孔がその後不明瞭になる場合もあることが明らかとなった.
(4)1日尿中estrogenは女性19症例中13例68%が正常範囲にあり,estrogenレベルと円孔発生との間には,密接な関係はみとめられないと考えられた.
硝子体出血をきたした老人性円盤状黄斑変性症の2例
著者: 山之内夘一 , 坂本英世 , 田村充弘
ページ範囲:P.317 - P.321
老人性円盤状黄斑変性症から硝子体出血を起した2症例3眼について述べた. この中,第1例右眼は黄斑部のmottlingから,浮腫,漿液性ついで出血性網膜色素上皮剥離,硝子体出血,円盤状黄斑変性とGassの述べた進行様式を示した.第2例左眼も,途中からであるが,第1例に準じた進展を示した.
第1例は両眼にウロキナーゼの硝子体内注入を行い,さらに右眼は水晶体摘出と前部硝子体切除を行ったが,結局は失明に終った.第2例はウロキナーゼの点滴静注が行われた.結果的には,観血的治療より,非観血的治療が好ましいことになるが,こうした出血を起す段階で,出血を防止する手段を講じることの必要性を痛感する.
我々の外来で見られ,3ケ月以上follow upできた老人性円盤状黄斑変性症は,14例20眼で,硝子体出血を見たものは2例3眼である.
いわゆるEales病について
著者: 佐藤圭子 , 白木邦彦 , 井上一紀 , 三木徳彦 , 巽陽一
ページ範囲:P.322 - P.329
(1)いわゆるEales病と診断された34例53眼について報告した.これは本邦における最多症例数で,経過観察し得た症例(その中,光凝固症例23例32眼,硝子体手術例4例4眼)は全例予後良好であった.早期に発見し,十分に光凝固を行えば良好な結果が得られるものと思われた.
(2) Eales病は網膜周辺部における血管閉塞性の疾患と考えられ,血液学的検査にてfibrinopeptide Aは正常範囲,fibrinopeptide Bβ15-42は明らかに高値を示す症例を認めた.
学術展示
隅角支持レンズの隅角所見と角膜乱視
著者: 蓮沼敏行 , 大木隆太郎
ページ範囲:P.334 - P.335
緒言 近年白内障手術において眼内レンズが多く用いられるようになってきたが,隅角支持レンズのフレキシブルループが隅角でどのような形態をとっているかについての知見は少ない.我々は経時的に角膜曲率を測定し,隅角を観察・写真記録することでフレキシブルループの隅角での挙動を明らかにしようとした.
材料および方法 29例31眼に12.5mmのシムコタイプ(SAC−3型:24眼),ケルマンⅡタイプ(MT−3型:7眼)の眼内レンズを一次移植し,平均38週間観察した(最短11週・最長69週).眼内レンズ挿入前に角膜乱視を測定し,術後も経時的に自覚的屈折と角膜乱視を測定した.そして角膜乱視および隅角所見,挿入された眼内レンズの方向,写真上で判定した角膜横径などの相互関係について検討した.
Argon laserを用いた後発白内障切開術
著者: 小峯輝男 , 加藤桂一郎
ページ範囲:P.336 - P.337
緒言 後発白内障を非観血的に切開する方法として,最近Nd;YAG laserが導入され,良好な成績を挙げているが,この装置を持つ眼科施設は限られている. 一方argon laser装置は比較的多くの施設に普及し,多くの眼科医が経験している.Lunde1)はargon laserを用いた後発自内障切開術を報告しているが,筆者らも試みた.
人工水晶体挿入患者の術後経過観察—自覚症状の分析
著者: 今泉信一郎 , 今泉博雄 , 吉田顕照 , 岡安成尚
ページ範囲:P.338 - P.339
緒言 近年,白内障術後矯正として従来より用いられている眼鏡やコンタクトレンズより,視機能1,2)が優れている人工水晶体(IOL)挿入患者が増えてきている.それに伴いIOL挿入度数の計算方法および予想度数が問題となっており,計算方法はほぼ満足のいくものが報告されている.術後の予想矯正度数の選択は種々の問題があると思われるが,その報告はなく,また,その決定権が現在の所,医師側にゆだねられている.
今回,患者側から見た術後矯正度数の満足の度合を,IOL挿入者の術後経過観察として,自覚症状と他覚症状とを比較検討し,IOL挿入度数の選択を試み,併せて術後合併症の発生頻度について検討を加えてみた.
Posterior lenticonusの治療経験
著者: 印南素子 , 泉田仁美 , 吉田博 , 樺澤泉
ページ範囲:P.340 - P.341
緒言Posterior lenticonus (後円錐水晶体)は,水晶体の後嚢と皮質が楕円もしくは円形に硝子体側に突出した水晶体の形態異常である.比較的稀な疾患であるが,CrouchとParksは小児の21症例にもおよぶ視力低下や弱視についての治療経験を報告している1).今回,我々は典型的と思われるposterior lenticonusの1例を経験し治療を行う機会を得たのでここに報告する.
症例3歳,女児.
癩患者の白内障手術
著者: 井上慎三 , 岡村和子 , 佐々木秀樹 , 松村香代子
ページ範囲:P.342 - P.343
癲疾患ではぶどう膜炎,強膜炎,兎眼性角膜炎により視力障害が起こる.ぶどう膜炎による併発白内障に加えて高齢化による老人性白内障が進行し視力低下を来した患者が増加してきた.癲療養所に於ける水晶体全摘出術の手術成績を報告する.
患者は多摩全生園,大島青松園,粟生楽泉園,東北新生園,駿河療養所,神山復生病院,身延深敬園,松丘保養所に入所している300名378眼である.手術は1974年12月から1982年10月までに大島,粟生および多磨で行った.駿河,東北,身延,神山,松丘の患者は多磨に転園して手術を行った.各療養所における入所者総数は2,750名(男性1,727名,女性1,023名,1983年4月現在),平均年齢は60.06歳であった.病型はL型2,014名,T型166名その他62名.平均年齢が60歳を越えていて,老人性病変の増加があり癲自体の治療に加えて老人病対策が必要となってきている,各療養所別の手術眼数および病型は(表1)で示す.L型の患者が96%を占めている.手術患者の男女比は患者総数の比率と同様に3対1で男性が多い.
ヒト後房レンズ移植眼の病理組織学的検索
著者: 重光利朗 , 馬嶋慶直
ページ範囲:P.344 - P.345
緒言 ヒト人工水晶体移植眼の病理学的検索は米国などにおいては報告があるが,本邦においては谷口らの報告1)のみである.我々は後房レンズ(Kratz type)移植術後1年3カ月で死亡した人眼を用いて,その病理学的所見から偽水晶体眼における病態を検索した.
症例 患者は90歳女性.1982年1月25日初診時視力は右=s.L.(+) 左=0.3 (n.c.).1982年11月16日P-ECCE後PC-IOL移植術実施(ヒアルロン酸Na使用).1983年3月25日視力右=(0.7×IOL〓cyl−3.0D→)左=0.4(n.c.)。1984年2月14日胃癌にて死亡.
検索方法 光学顕微鏡(連続切片)による検索は,通常染色としてH.E染色,PAS反応を行い,免疫組織化学的検索(PAP法)はS-100,Lysozyme,α1-anti-trypsin,Fibronectinで実施した.電子顕微鏡は透過型電顕と走査型電顕を用いた.
白内障術後における長期装用コンタクトレンズの問題点
著者: 湖崎弘 , 稲葉昌丸 , 高藤時夫 , 西川博彰
ページ範囲:P.346 - P.347
緒言 最近の日本では社会の高年齢化に伴って無水晶体眼人口が急増しており,その視力矯正法が眼科医の重要課題となりつつある.
従来の眼鏡による矯正法は視野,色覚,見え方の点でコンタクトレンズに及ばず,装用者の社会活動に大きな制約が生ずる.また,眼内レンズはそれ単独での視力,および安全性の点で問題があり,現時点での白内障術後矯正法としては連続装用コンタクトレンズがもっとも現実的である.
我々はその実用性を確かめるため)に,過去5年にわたり自内障術後(KPE主体)眼に連続装用コンタクトレンズを処方し,その経過を観察したので,その問題点について報告する.
各種白内障手術後の手術侵襲の定量化と術式間の比較—50%修復回復時間および平均破壊時間
著者: 瀬戸千尋 , 箕田健生 , 高瀬正弥
ページ範囲:P.348 - P.349
緒言 白内障手術は,近年目覚ましく進歩し水晶体嚢内摘出術(ICCE)から水晶体嚢外摘出術(ECCE),超音波乳化吸引術(KPE)さらには人工水晶体(IOL)移植まで行われるようになってきている.これら種々の術式での眼に対する侵襲についての比較検討の報告がいくつか認められるが1〜5),分析方法にいくつかの問題点が残っている.フルオレセイン静注30分後,前房—血液フルオレセイン濃度比を用いて血液房水柵(BAB)透過性を比較するため,白内障手術術式による前房体積因子の消去を行えば,異なる術式および手術者間での比較が定量的に可能となると考え時間因子を解析方法にとりいれ,各術式間について比較検討したので報告する.
対象および術式 養育院眼科において白内障手術を行ったICCE5例(72.5±5.1歳),ECCE6例(74.9±4.9歳),KPE6例(68.2+4.4歳),ECCE+IOL 12例(72.2+4.8歳),KPE+IOL 16例(69.8+7.2歳)の5群を対象とLた.
虹彩悪性黒色腫の1例
著者: 江口秀一郎 , 堀貞夫 , 箕田健生
ページ範囲:P.350 - P.351
緒言 葡萄膜に原発する悪性黒色腫は,脈絡膜より発生するものが多く,虹彩に原発するものは稀である1).今回我々は虹彩面上に多数の褐色腫瘍が散在し,隅角への浸潤,眼圧上昇がみられ臨床的に悪性黒色腫と診断され,眼球摘出した症例の組織学的検索を行ったので報告する.
症例:21歳女性(病歴番号58-3392).
虹彩に発生したreactive lymphoid hyperplasia
著者: 斉藤学 , 田川義継 , 竹内勉 , 大野重昭
ページ範囲:P.352 - P.353
近年,眼科領域において,reactive lymphoid hyperpla-siaの症例が報告されているが,その発生部位としては,眼窩・結膜などの報告が多く,虹彩にみられたものはきわめて少ない.今回我々は,虹彩腫瘍の診断のもとに生検を行い,虹彩におけるreactive lymphoid hyper-plasiaと考えられた症例を経験したので報告する.
症例40歳男性.1983年5月頃より右視矇感出現するも放置していた.その後視矇感が次第に増強し,同年10月近医受診し,右眼の虹彩炎,続発緑内障,および虹彩の異常を指摘され,同年10月31日当科初診.初診時,視力右眼0.1(矯正不能),左眼1.2.眼圧右眼62mmHg,左眼16mmHg.右眼に角膜後面沈着物,前房出血,前房微塵を多数認め,虹彩は全周にわたり肥厚し,瞳孔縁には多数の腫瘍状隆起がみられた(図1).瞳孔径は3.5mmで対光反応は,直接・間接反応共ほぼ消失し,散瞳剤・縮瞳剤にもほとんど反応がみられなかった.隅角部は開放隅角で結節等はみられなかった.中間透光体には異常なく,眼底にも緑内障性乳頭陥凹を認める以外に著変はみられなかった.左眼は前眼部・中間透光体・眼底共特に異常はみられなかった.家族歴,既往歴に特記すべきことはなかった.全身的検査では,血液学的検査および同一般生化学的検査に異常はみられなかった.
強直性脊椎炎に原田病を伴った1症例
著者: 張由美
ページ範囲:P.354 - P.355
緒言 強直性脊椎炎はぶどう膜炎と関係深い疾患として知られている.台湾においてもぶどう膜炎の中に頻度の高いものと見られている1).今回我々はHLAB 27の典型的な強直性脊椎炎の症例に両眼のぶどう膜炎を発病し,眼症状および全身所見より原田病と診断した1症例を経験したので,報告する.
連載 眼科図譜・328
新しい硝子体写真撮影法
著者: 大久保彰 , 大久保好子 , 金上貞夫 , 清水昊幸
ページ範囲:P.242 - P.243
緒言 眼球における最大の組織である硝子体は,99%が水であるため透明度が高く,光反帰率が低いため写真撮影は非常に困難であった.この度我々は,自動露出フォトスリットランプ・超高感度カラーフィルム・Gold-mann三面鏡を用いて硝子体の写真撮影を行い,この方法によれば誰でも比較的容易に硝子休写真撮影ができると思われたのでその方法を紹介し,撮影した硝子体写真を供覧する.
方法 自動露出フォトスリットランプ(興和SC−6),超高感度カラーフィルム(フジクローム1600プロフェショナルD),Goldmann三面鏡(Ocular instruments社製Universal Lens)を用いて硝子体写真撮影を行った.
臨床報告
自動露出フォトスリットランプと超高感度カラーフィルムを用いた硝子体写真撮影
著者: 大久保彰 , 大久保好子 , 金上貞夫 , 清水昊幸
ページ範囲:P.357 - P.361
自動露出フォトスリットランプ・超高感度カラーフィルム・Goldmann三面鏡を用いた硝子体写真撮影法を紹介した.
(1)自動露出フォトスリットランプ(興和SC-6)の撮影条性は,AutoではASA 400,Manualでは3-5の条件が適当であった.
(2)フジクローム1600プロフェッショナルDの使用によって,従来のASA 400フィルムの2倍増感法に比較してカラーバランス・画質の優れた,より鮮明な硝子体写真の撮影が可能となった.現像条件はPZ現像でISO 1600が適当であった.
(3)前面コーティングのGoldmann三面鏡を用いると,レンズの表面反射が減じ,硝子体写真撮影が行いやすかった.
以上の方法を用いることにより硝子体写真撮影は比較的容易になり,硝子体所見のより客観的記録法である写真撮影が眼底撮影や前眼部撮影のように眼科の慣用撮影法となる道が開かれた.
九大眼科における交感性眼炎の統計的観察
著者: 讃井浩喜 , 向野利彦 , 猪俣孟
ページ範囲:P.367 - P.371
昭和21年(1946年)から58年(1983年)までの九大眼科における交感性眼炎を統計学的に観察し次のような結果を得た.
(1)交感性眼炎の総数は45例であり,最近10年は減少傾向であった.
(2)原因として外傷と手術はそれぞれ68%,32%であった.
(3)発症頻度は穿孔性眼外傷後0.34%であり,手術後0.056%であった.
(4)患者は20歳代男性に最も多く,10歳未満は最も少なかった.
(5)患者の81%は,外傷あるいは手術後3カ月以内に発症していた.
(6)眼外傷では強角膜穿孔が最も多く,毛様体部損傷を伴う症例が多かった.
(7)ステロイド治療により視力の予後はよく起交感眼も保存的療法が主体となっていた.
Terrien's marginal corneal degenerationの1例
著者: 広瀬茂人 , 大野重昭 , 田中邦枝
ページ範囲:P.373 - P.376
Terrien's marginal corneal degenerationの1例につき報告した.症例は30歳の男性で,主訴は軽度の左眼異物感であった.右角膜には上方周辺実質の混濁と表層の血管侵人が認められ,左角膜は上方周辺角膜の菲薄化が認められた.7年間の経過観察中に角膜上皮の欠損などの異常は全く観察されなかったが,両眼ともに上方周辺部の菲薄化は徐々に進行し近視性乱視を示すに至った.
Ocular dippingについて
著者: 西田幸子 , 中野直樹 , 石川弘 , 北野周作
ページ範囲:P.377 - P.380
両眼が正中位からゆっくり下転し,急速にもとに戻り,側方への動きも伴うことを特微とするocular dippingの2症例を報告した.発生機序として,上方注視障害と下方注視抑制の解除に,上位中枢からの抑制の解除が加わり生じたものと考えられた.責任病巣は間脳・中脳移行部が最も関係が深いと思われた.
標準色覚検査表第1部(SPP−1)の検討—(3)分類表の評価
著者: 深見嘉一郎 , 島本史郎 , 石黒裕之
ページ範囲:P.381 - P.385
標準色覚検査表第1部(SPP−1)の分類表について検討した.
検査対象は本報告の第1部,第2部と同じ411名の先天色覚異常である.
第1異常に関しては,分類表全5表とも非常に良い成績を示している.第2異常では,分類表全5表中3表は非常に良い成績を示したが,残りの2表は分類不能となるものが多い.しかし,全5表にて類型を判断する限りにおいて,大部分のものは分類できる.
第1色覚(P)は100%正しく分類できる.
第1色弱(PA)は91.0%正しく分類できる.
第2色盲(D)は99.3%正しく分類できる.
第2色弱(DA)は97.2%正しく分類できる.
全体で97.6%正しく分類できる.
アノマロスコープの分類との不一致率は,PAで1例(2.3%),DAでは3例(1.7%)であった.この第1,第2異常が逆に判定されるものはすべて軽度である.重度のものはこのように逆に判定されることなく,全ては正しく判定される.
以上の結果から,SPP−1の分類表の分類能力は優れていると判断できる.
カラー臨床報告
黄斑部に渦静脈を認めた2症例
著者: 大野広子 , 松尾信彦 , 白神史雄 , 大野敦史 , 岡部史朗 , 岡本繁
ページ範囲:P.363 - P.366
17歳女性,43歳女性の右眼黄斑部に大型の渦静脈と考えられる脈絡膜静脈を認めた.それは,渦静脈分枝部,渦静脈部,強膜入口部等の渦静脈各部の特徴をもった形態を示していた.赤道部の渦静脈は,健眼に比べて小型でかつ少数であった.また,患眼に近視が強く視力障害を認めた.このことから,黄斑部の渦静脈の存在が近視の発生に関与している可能性があると考えた.
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(39)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斉藤仁男
ページ範囲:P.386 - P.387
48.眼目秘伝書
古写本の眼科秘伝書には書名がない場合が多く,記述の内容も眼目論(病論),薬性論,眼目見様之次第,能毒,禁忌,好物および薬物処方等を挙げているのが通例であるが,すべてこのパターンというわけではない.こうしたところが古写本眼科秘伝書の特徴の一つであろうか,序論,本論,各論といった順序で記述されている成書と異なっている.つまり秘伝書は理論より実地を重視して述べられているものが多く,掲出の秘伝書もそうした類のものである.
本書はその末尾に"寛文八年申暦二月廿一日,観弘書之"と識されているのみで,何れの流派の眼科を伝えたものか明らかでないが,この頃の眼科を伝えたものと思われる.
GROUP DISCUSSION
弱視・斜視
著者: 中川喬 , 有本秀樹 , 山本節 , 野崎尚志 , 田淵昭雄
ページ範囲:P.388 - P.392
1.先天性上斜筋欠損と思われる1例
我々は先天性の上斜筋形成不全あるいは欠損と思われる1例を経験したので報告する。
症例は12歳女児,術前他覚的斜視角は左眼(健眼)固視,遠見5△×T,R/L30△,眼球運動は右眼上斜筋の遅動および下斜筋の過動を呈し,頭位異常としては「左かしげ」約20°が認められ,BHTTは陽性,Maddox dou-ble rod testでは廻旋偏位はなかった。他覚的斜視角に対しプリズムを中和すると上下の複視が自覚され,上下方向の網膜異常対応が示唆された。手術効果を予測するためにプリズムを用いて斜視角を中和し,手術直前まで7日間装用させたところ,複視(±)でときどき正常な両眼視も認められた。他覚的斜視角を全矯正する目的で,第1回手術として,右眼上斜筋縫縮を予定した。術中,上直筋の耳側で上斜筋の起始部を探索するも上斜筋は見つからず,さらに上直筋の鼻側も探索したが,上斜筋は認められなかったため,術式を右眼下斜筋後転8mmに変更した。術後R/L20△が残り,残余斜視角に対しプリズムを中和すると,初回手術前同様,上下の複視が自覚された。複視が自覚されない範囲で最大の矯正をするため,節2回の手術として,右眼上直筋後転4mmを施行した。術後R/L8△となり,Bagoliniの線条レンズでは異常融像が認められ,頭位の異常も「左かしげ」約10°に改善された。
小児眼科
著者: 湖崎克
ページ範囲:P.393 - P.396
1.小児のアレルギー性結膜炎と春季カタルとの比較
中川・他(大阪逓信病院) (目的)春季カタルとアレルギー性結膜炎の患者の両者が本来同一の疾患と考えてよいかどうかについて検討した.
(方法)既往歴,合併症,増悪季節,アレルゲン,血清IgE,血清RASTなどから小児における春季カタルとアレルギー性結膜炎との相違の有無について検討し,同時に成人例とも比較を行った.
基本情報
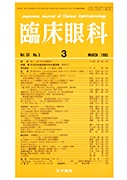
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
