原発開放隅角緑内障(以下POAG)の極初期病態を追及することにより,従来考えられてきたいわゆるPOAGというものは単なるみかけ上のentityにすぎず,その本態は著しく異なったものであることを明らかにした.そして得られた諸データをもとにPOAGの発症に関する最も妥当な考え方として以下の仮説を提唱した.
(1) POAGは前房隅角のmeshworkを初発の場とするものではない.
(2)中枢性の眼圧上昇をもって初発する.従来知られているmeshworkの病変は眼圧上昇によって惹起された続発性病変で,これが原因となって更に眼圧が上昇する.
(3)眼圧上昇が持続すれば基本的には何らかの視神経障害が必発する.
(4)高眼圧症(OH)の約90%に視神経障害がくる.これらはすべて広義のPOAGである.そのうちとくに視神経障害が著明となるもののみが,いわゆるPOAGに相当する.
(5)視神経障害の軽重は篩板部の圧に対する易障害性の程度によって決まる.易障害性の高いものは低眼圧でもおかされ,難障害性のものは高眼圧が続いてもおかされ難い.いわゆるPOAGはその中間の易障害性をもつものである.
(6)易障害性は一つの篩板の内でも部位により異なるし,個体差も大きい.
(7)易障害性の本態は次の3要素より成り立つ.
1)眼圧上昇に伴う篩板の脆弱化による後方湾曲と,軸索の支持力低下.
2)篩板の上,下耳側部の軸索孔の結合織のうすいこと,孔も大きいこと.
3)篩板直後で,有髄で著しく重くなった有髄神経が1)が原因で支えを失って下鼻 側につよく屈曲しこの力が軸索孔を横くずれさせる方向に働き,軸索をしめつげる. 特に3)は飾板の軸索孔を横くずれにっぶす原動力として重要な位澱を占める. 以上から将来は中枢性の眼圧コントロールが治療の本質となることであろうし,すでに飾板に軸索支持力の低下の始まっている場合は,節板後に始まる有髄視神経を下鼻側に屈曲しないように水平に支える形成手術が主体となるものと思われる.それが不能の現在,可能なかぎり早期から眼圧を十分に下降せしめその支持力の低下を防ぐのが最良の策で,初期暗点が出現するまで待つ現行の方法では著しく遅きに失し,進行を停止せしめえないことに留意されねばならない.
雑誌目次
臨床眼科39巻4号
1985年04月発行
雑誌目次
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
特別講演
原発開放隅角緑内障の初期病態
著者: 岩田和雄
ページ範囲:P.407 - P.424
学会原著
高安病での網膜血管床閉塞と動静脈吻合の形成過程
著者: 田中隆行 , 逸見知弘 , 粟根裕
ページ範囲:P.425 - P.431
過去8年間の高安病患者7症例14眼に螢光眼底造影を行い,網膜血管床が慢性に閉塞に至る過程を検索した.この過程には,動静脈吻合の関係しない毛細血管の特発性の閉塞(14眼)と,動静脈吻合が形成された後に続発する閉塞とがあった.この動静脈吻合には優先血行路(14眼),動静脈交差部での吻合(6眼)の2種類があった.これらの動静脈吻合の形成には,その周囲および末梢の血管床閉塞が先行することを必要としなかった.すなわち形成された動静脈吻合は網膜血管床閉塞を併発するものの,発症に関しては動静脈吻合と網膜血管床閉塞は独立した病態であると結論された.
糖尿病性網膜症の黄斑部機能
著者: 鈴木隆次郎 , 平岡利彦 , 横田章夫 , 太田裕子
ページ範囲:P.433 - P.437
糖尿病性網膜症の視機能異常には,綱膜症のみならず,視神経症による因子と思われる変化が含まれていた.これらの因子を分析し,網膜症早期の視機能変化と黄斑部浮腫の検出方法について検討した.
黄斑部に浮腫のない群では,視力,photostress recovery timeはいずれも正常であったが,色覚異常を示す例が見られた.
黄斑部浮腫のある群では,色覚異常の程度とともにphotostress recovery timeも延長していた.
proliferative retinopathyでは,photostress recovery timeも著明に延長し,中心CFFの低下例が見られた.
以上の点より,黄斑部浮腫群,特にproliferative retinopathyには視神経症による因子も関与していると考えられた.
糖尿病性網膜症に対するクリプトンとアルゴンレーザー光凝固の比較
著者: 岡野正 , 米谷新 , 村岡兼光 , 岸章治 , 沼賀哲郎
ページ範囲:P.439 - P.443
糖尿病性網膜症光凝固例489眼にレーザー光凝固治療を行い,赤色クリプトンレーザー例171眼と青緑色アルゴンレーザー例318眼について,平均8.5カ月の経過と治療成績を比較した.
糖尿病性網膜症の治療上,赤色クリプトンレーザーは従来の青緑色アンゴンレーザーと少なくとも同等の臨床効果を有し,術後の後部硝子体剥離化が少なく,硝子体牽引性障害の発生が低率であった.光凝固後の眼内臨床像の改善例はクリプトン群では77%,アルゴン群では76%であり,悪化例はクリプトン群15%,アルゴン16%で,ともにほとんど同率であった.光凝固後の矯正視力は,両群とも類似の分布を示した.両群とも,術中術直後の特記すべき合併症は生じなかった.
光凝固前に後部硝子体の剥離がなかった例(クリプトン群,アルゴン群ともに107眼)で光凝固後に不完全あるいは完全に硝子体が剥離した頻度は,クリプトン群では19%で,アルゴン群の53%より有意に低率であった.これに関して,光凝固後に新たに発生した硝子体牽引性出血例は,クリプトン群では11%でアルゴン群の19%より少なかった.また,光凝固前にすでにあった硝子体出血が光凝固後に持続・増強したものは,クリプトン群で23%,アルゴン群で31%あった.牽引性網膜剥離もクリプトン群の方が少ない傾向を示した.
以上から,赤色クリプトンレーザー光凝固は,特に眼底の汎網膜光凝固には有用な方法であるといえる.
クラミディア-トラコマティス眼感染症の臨床疫学的ならびに病因的研究
著者: 青木功喜 , 田中宣彦 , 能戸清 , 時田広 , 音無克彦 , 長谷川一郎 , 小野弘光 , 天日一光 , 沼崎啓 , 諸星輝明 , 千葉峻三 , 中尾亨 , 野田明
ページ範囲:P.445 - P.449
1983年11月からの6カ月間における札幌市のクラミディア眼感染症について検討を加えた.第一にクラミディアが子宮頸部に3/78(3.8%)に分離され,妊婦における新生児結膜炎予防の対策が必要である.第二に新生児結膜炎の8/30(27%)からクラミディアが確認され,新生児結膜炎の重症の型では注意しておく必要がある.第三に成人で急性濾胞性片眼性結膜炎の症例の3/5(60%)にChlamydia trachomatisが証明され,いわゆるsexually transmitted disease(STD)としての存在が推測された.第四にtrachoma Ⅳ期の患者群においては,14/34(41.2%)でenzymelinked immunosorbent assay(ELISA)によってIgG抗体が証明された.
クラミディア眼感染症は上記の事実から,新生児結膜炎,成人のsexually transmitteddiseaseおよび老人における瘢痕性結膜において,重要な役割を占めており,今後病因的検索を背景としてさらに臨床疫学の研究が必要である.
角膜真菌症に対するmiconazole点滴静注療法
著者: 石橋康久 , 松本雄二郎 , 武井一夫
ページ範囲:P.451 - P.454
44歳男性の左眼および53歳男性の左眼に認められた角膜真菌症に対してmico-nazoleの点滴静注療法を行った.この療法により病変は4〜5日目から改善傾向を示し,3週間,24,600mgの投与により治癒した.第1例では0.04であった視力が1.0となり,第2例では0.05から0.5に回復した.投与中に血清の中性脂肪およびリン脂質の価が上昇したが,投与終了後は速やかに正常値に復し,それ以外の副作用は認められなかった.
Harboyan症候群(遺伝性角膜内皮ジストロフィー)の家族例
著者: 熊谷俊一 , 渡辺敏明 , 白井淳一 , 小野寺毅 , 田澤豊 , 根本聰彦
ページ範囲:P.455 - P.459
内皮性角膜ジストロフィー,進行性の感音性難聴,常染色体劣性遺伝を呈する兄(18歳)と妹(15歳)の家族性発症例を経験したので報告する.本症例は1971年Harboyanらが示したいわゆるHarboyan症候群と同類の症例であり,本邦で初めての報告と思われる.
両症例の角膜所見としては,実質の著明な浮腫が特徴的であり,正常の約2倍の厚さであった.両症例に対し治療としてそれぞれ片眼に全層角膜移植術を施行し,いったんは透明癒着して視力の改善が得られたが,免疫反応が発現し(角膜移植術後,兄58日目,妹238日目)水疱性角膜症の状態になった.免疫反応による移植角膜片の内皮細胞の傷害が,角膜の透明化を得られなかった原因であろうと推察された.
実質型角膜ヘルペスにおけるステロイド非投与例の検討
著者: 北川和子 , 佐々木一之 , 高橋信夫 , 都築春美
ページ範囲:P.461 - P.465
39例40眼の実質型角膜ヘルペスに対し,ステロイド投与を行わず抗ヘルペス剤を中心とする治療を試み,以下の成績を得た.
(1) IDUのみで軽快傾向のみられたものは22例23眼(59%)であり,残りの症例にはF3T, IDC, Ara-A等を投与した.
(2)上記の治療に抵抗性であったもの,再発を繰り返した症例に対しては,レバミゾールの内服を併用した.投与量は週1回100mgとし,10〜17週用いた.
(3)中断の1例を除く全例に軽快をみ,33例(87%)で視力の改善がみられた.初診より治癒までの期間は平均70日であった.
(4)治癒と判定後の平均観察期間は15.6カ月で,この期間内における再発は27.3%であった.
角膜移植片の知覚回復について
著者: 木下茂 , 大園澄江 , 浜野孝 , 下村嘉一 , 西田輝夫 , 真鍋禮三
ページ範囲:P.466 - P.467
角膜移植片中央部の知覚は角膜移植後1年のあいだ消失または極端な低下を示し,術後1年半から2年頃より徐々に回復しはじめた.この角膜知覚繊維の再生から推察すると,移植片は角膜移植後最低1年間は神経繊維と隔絶されたneurotrophicな状態にあると想像された.
前房フルオロフォトメトリーによる眼内レンズ挿入眼の侵襲と予後
著者: 河合憲司 , 直原修一 , 船橋正員 , 早野三郎
ページ範囲:P.469 - P.472
眼内レンズ挿入後の20例(嚢内法(ICCE)後虹彩支持レンズ4例4眼,嚢外法(ECCE)後後房レンズ16例17眼)を対象として,術後血液房水柵の経時的変化を前房フルオロフォトメトリーならびに虹彩螢光血管撮影により,虹彩毛様体への侵襲と程度を検討した.10%フルオレセインNa液10mg/kg体重静注5分,60分,120分後の前房内フルオレセイン濃度を測定し,非手術眼を対照として比較した.(1)術後1週〜3カ月は眼内レンズ挿入眼の前房内フルオレセイン濃度はコントロール眼より高値であるが,経時的に低下し術後9カ月〜1年で両者の間の差は縮小し,60分値における濃度比は1となった.このことより,少なくとも血液房水柵の修復は9カ月〜1年要するものと推定した.(2)手術時年齢60歳以下と以上では,前者に前房内フルオレセイン濃度が低い傾向にあった.(3)虹彩支持レンズ挿入眼の症例は術後1年半〜7年で,コントロール眼との差を認めなかった.(4) Cystoid macular edema,術後早期に炎症を認めた症例では,5〜15分の初期前房内フルオレセイン濃度が著しく高かった.(5)臨床的に前房フルオロフォトメトリーを5分〜60分測定することにより,虹彩毛様体への侵襲による血液房水柵の傷害を察知できることが示唆された.
円錐角膜に見られるボーマン膜断裂の臨床的意義について
著者: 伊藤弘子 , 鈴木君代 , 冨田隆之 , 﨑元卓
ページ範囲:P.477 - P.481
円錐角膜でみられる角膜の形状変化を,細隙灯顕微鏡で観察されるボーマン膜断裂の変化に注目し,その関係について検討した.過去5年間に当科外来を訪れ,円錐角膜と診断された患者151名のうち,ボーマン膜断裂を認めたものが約40%あり,その変化を初期は棍棒状,中期は樹枝状,後期は網目状と分類した.その結果,樹枝状の時期を過ぎると角膜の形状変化が急速に進行し,網目状の時期になると角膜移植術を余儀無くされるために,樹枝状の時点で角膜熱形成術を施行することが望ましい.
白内障摘出術による眼球光学系の変化
著者: 大野高子
ページ範囲:P.483 - P.487
合併症を認めなかった67人83眼の白内障手術前後の屈折要素の変化,とくに眼軸長の変化を検討し,以下の結果を得た.
(1)術前眼軸長が23.50mm以下の群(43眼)では,術前眼軸長と術後の眼軸長変化に相関を認めなかった(r=−0.04,p>0.05).術前眼軸長が23.50mmを超える群(40眼)では,術前眼軸長と術後の眼軸長短縮に有意の相関を認めた(r=0.50,p<0.005).
(2)術後の眼軸長変化は白内障のタイプには無関係で,手術法(嚢内法,嚢外法)による差も認めなかった(p>0.05).
(3)術前前房深度,水晶体厚および手術による角膜屈折力の変化は術後の眼軸長変化と相関を示さなかった(p>0.05).
(4)術後1カ月目とそれ以降(平均9カ月目)の眼軸長を49眼において検討した結果,両群間に有意差を認めず,このことから合併症のない白内障術後において眼軸長はほぼ1カ月で安定化するものと考えられた.
(5)以上の結果より,とくに近視眼における人工水晶体度数決定に際しては,水晶体摘出による眼軸長短縮を考慮する必要があると考えられた.
各種後房レンズの術後固定状況
著者: 荻原博実 , 松永浩一 , 谷口重雄 , 深道義尚
ページ範囲:P.489 - P.493
3種の角度付き後房レンズ,すなわちSinskeyレンズ,Cループレンズ,Kratzレンズ移植眼について,その固定状況を特にレンズの中心ずれ(decentration)の面から比較し,更に視機能についても検討し以下の結果を得た.
(1) Decentrationは0〜3.0mmまでであった.
(2) sulcus-sulcus固定で,decentrationは最小であった.
(3) bag-bag, sulcus-sulcus固定共に3種のレンズによるdecentration分布に差はみられなかったが,bag-sulcus固定では,Cループレンズの方が,Sinskeyレンズよりdecentrationが小さい傾向にあった.
(4) Decentrationと視力および円柱レンズとは無関係であった.
学術展示
リポ多糖体とぶどう膜炎
著者: 砂川光子 , 沖波聡
ページ範囲:P.496 - P.497
緒言 グラム陰性菌の内毒素であるリポ多糖体(LPS)は,Bリンパ球増殖の非特異的な刺激を含め,生体に様々な反応をひきおこす1).眼科的にも,LPSはぶどう膜炎を誘発する事が知られている2〜4).今回,われわれはぶどう膜炎患者の血清中の抗LPS抗体価を測定し,ぶどう膜炎におけるLPSの役割について検討した.
未熟児網膜症の双眼倒像眼底撮影
著者: 山本節 , 鶴岡祥彦 , 湖崎克
ページ範囲:P.498 - P.499
緒言 未熟児の救命率が向上するにしたがって,未熟児を保育している病院,施設では未熟児の眼底検査が次第にルーチン化されてきている.一方,検査法の面でも双眼倒像鏡,強膜圧迫子を用いた網膜周辺部の眼底検査,倒像眼底撮影法1),螢光眼底検査法などの開発,進歩により,未熟児の眼底検査は一層正確な所見を把握できるようになった.そこで網膜症の進行程度や分類2),眼底所見の記録上,眼底撮影は欠かすことができないものとして,その必要性が高まっている.
今度,旭光学およびAlcon社からカメラ付双眼倒像鏡OPC(Ophthalmoscope with camera)が開発され試用する機会を得たので,網膜症に対する撮影法とともに,臨床上の効果について報告する.
テクニカルパン2415フィルムの赤色光眼底撮影への応用
著者: 内藤毅 , 猪本康代 , 兼松誠二
ページ範囲:P.500 - P.501
緒言 単色光眼底撮影法は用いる光の波長により,眼底の種々の深さの層を撮影することができ多方面で応用されている.とくに脈絡膜血管の観察には赤色光を用いると,図1に示す原理1)でより詳細な所見を得ることができる.
従来,赤色光眼底撮影にはトライXパン,プラスXパンなどが用いられてきたが,今回テクニカルパン2415フィルム(以下テクニカルパン)を用い比較検討した.
エタンブトール投与症例の血清亜鉛値
著者: 原田景子 , 岩田美雪 , 原田敬志
ページ範囲:P.502 - P.503
緒言 Ethambutol (以下EBと略記)は1960年米国レダリー社で開発され,第2次抗結核剤として広く用いられ,卓越した効果を発揮している.しかし1962年Carrにより眼科的副作用が報告され,以来現在までEB視神経症の報告が続いている.また近年は重症例の報告が散見され,早期発見と発生の予防が望まれている.最近亜鉛欠乏が中毒性球後神視経炎の原因ではないかとする報告1)があり,今回EB投与症例の血清亜鉛値を測定したので報告する.
一般診療所における赤道部変性等の早期発見の試み
著者: 佐藤清祐
ページ範囲:P.504 - P.505
緒言 網膜剥離はその前段階の変化である赤道部変性や網膜孔に対し必要な時期に適切な処置を行えば,大多数で発病を予防しうる.しかし現在この前段階変化の早期発見に関する予防医学的対策はほとんどない.著者はこの両変化の早期発見を目的として一般外来患者において散瞳しないまま周辺部眼底の検査に努めて来たので,その結果を報告する.
多発性骨髄腫における眼底変化と血液粘度
著者: 船坂芳江 , 松田久美子 , 高橋克仁 , 葦沢由美子
ページ範囲:P.506 - P.507
緒言 Hyperviscosity症候群を呈した多発性骨髄腫2例について回転平板式粘度計を使用し,化学療法前後の眼所見と血液粘度の変化を観察した.
症例 151歳女性.
脱臼水晶体摘出術および硝子体切除術後に見られた黄斑部脈絡膜新生血管の1例
著者: 阿久根秀樹 , 長崎比呂志 , 宮田典男
ページ範囲:P.508 - P.509
緒言 水晶体摘出後の黄斑部変化としてはcystoidmacular edemaやhypotony maculopathyがよく知られている.我々は硝子体切除術を併用した水晶体全摘出術後,黄斑部に脈絡膜由来と思われる新生血管を認めた症例を経験したのでここに報告する.
症例 55歳,男性.
硝子体螢光測定による糖尿病性網膜症の臨床的研究—第2報 インスリン治療の血液網膜柵に及ぼす影響
著者: 安藤伸朗
ページ範囲:P.510 - P.511
糖尿病性網膜症は,糖尿病における高血糖を含む代謝異常の結果惹き起こされるということは周知の事実である.よって糖尿病治療は厳格な血糖調節が原則である.一方,長期間調節不良の糖尿病患者に,インスリン投与により急速な血糖正常化をはかると,網膜症の増悪がみられるという事例が最近数多く報告されている1〜3).糖尿病治療に際し,血糖の正常化は第一目標であるが,そのために網膜症を悪化させてはならない.しかし,そのための最良の血糖調節法は確立されていないのが現状である.今回,この問題の解決のための一手段として,硝子体螢光測定(vitreous fluorophotometry:以下VFPと略す)を用いてインスリン治療の血液網膜柵に与える影響について検討した.
VFP値の測定は既に報告したが4),Xanar fluorophoto-meter modal 120を用い,フルオレセイン色素静注前,静注後1時間でVFP値の測定,フルオレセイン静注量は7mg/kgである.静注1時間後に得られた,二峰性の螢光曲線の前後のピークの中間点のVFP値から,静注前の同位置のVFP値(水晶体自発螢光によるspreadfunction)を除したものをVFP値と定めた.
最近2年間のレーザー光凝固術の統計的観察
著者: 清水敬子 , 戸張幾生
ページ範囲:P.512 - P.513
緒言 当科でのレーザー光凝固術は,1982年5月より1984年4月までの2年間に,延べ1,800回(1,270眼)となる.これらを疾患別に,統計的観察よりうかがえた臨床的特徴を報告する.
正常眼における後部硝子体分離の頻度—屈折度・年齢・性との関係について
著者: 小林博 , 荻野誠周
ページ範囲:P.514 - P.515
緒言 後部硝子体分離は,網膜裂孔の発生に関連した重要な現象と考えられ,また,その頻度に関しては,現在までにいくつかの報告がある1〜5).しかし,後部硝子体分離の発生と年齢,屈折度および性の関連についての分析はほとんど行われていない.今回,われわれは,正常眼に対して後部硝子体分離および硝子体の変性について観察し,その頻度を報告するとともに,年齢・屈折度・性の影響について分析を行った.
Simulationによるkinetic vitreous fluorophotometryの研究—Ⅲ.裂孔原性網膜剥離の血液網膜関門透過性
著者: 小椋祐一郎 , 塚原陽子 , 斉藤伊三雄 , 近藤武久
ページ範囲:P.516 - P.517
緒言 Vitreous fluorophotometryのデータをcomputerを用いて解析することにより,血液網膜関門の透過性を内方向(脈絡脈→硝子体)と外方向(硝子体→脈絡膜)とに区別して算出することが可能である1,2).その方法を用いて,裂孔原性網膜剥離における血液網膜関門の透過性の変化について検討を加えたので,ここに報告する.
YAG-レーザーの硝子体切除への応用—動物実験での網膜に対する影響について
著者: 余敏子 , 善利豊子 , 原和彦
ページ範囲:P.518 - P.519
緒言 YAG-レーザーを硝子体切除に応用した場合の網膜障害については,現在のところ一致した見解が得られていない.今回我々はレーザーの焦点が網膜面から何mm離れていれば,眼底に影響なく照射可能か,またそれ以内の距離に近づいたときの眼底障害についても検討を加えた.
連載 眼科図譜・329
多発性内分泌腺腫症Ⅱb型での角膜神経肥厚
著者: 大路正人 , 東晶子 , 清水芳樹 , 木下茂
ページ範囲:P.404 - P.405
我々は多発性内分泌腺腫症Ⅱb型(以下MENⅡb)の1例を経験した.MENⅡbはWilliams1), Schimke2),Gorlin3)らによりひとつのclinical entityとして提唱された疾患であるが,そのclinical entityとは粘膜神経腫に甲状腺髄様癌,副腎褐色細胞腫のいずれかあるいはその両者を合併し,他に全身所見としてMarfan様体型,凹足,脊柱の後彎や側彎,肥厚した口唇(bumpy lip),ヒスタミンの皮内反応の異常などを認めるというものである.眼科的には著明に肥厚した角膜内神経線維,結膜の神経腫,眼瞼の神経腫による肥厚および外反,涙液の分泌減少.涙点の鼻側変移などの報告がなされている4).MENⅡbは非常に稀な疾患で,本邦では約10例の報告を数えるにすぎず,眼科的領域での詳細な記載は我々の知る限りなされていない.
症例は20歳の女性で眼球乾燥感を主訴として外科から紹介され眼科を受診した.幼少期より著明に肥厚した口唇(図1).多数の結節のある舌が認められていた.1979年に甲状腺髄様癌のため甲状腺摘出術,1984年,副腎褐色細胞腫のため両側副腎摘出術を施行された.現病としては,視力,眼圧は正常で,中間透光体および眼底には異常を認めなかった.角膜は透明であったが,神経線維が著明に肥厚していた(図2).この神経線維は角膜輪部で太いtrunkとして8〜10本認められ,角膜実質のほぼ中央の深さで輪部より進入し,放射線状に分枝しながら進行し,角膜中央部に近づくにつれて上皮側にむかっていた(図3).結膜には神経腫と考えられる病変が数カ所に認められた.眼瞼の軽度肥厚は認められたが眼瞼外反は認められなかった.角膜知覚はCochet-Bonnetの知覚計で測定し,左右ともに55mmと正常範囲であった.角膜中央部の厚さばVIDA 55(VIDA祉製)で測定し,右534μm,左525μmと正常範囲であつた.シルマー試験は5分値が左右とも6mmと正常ド限を示した.以上のことより本症例では角膜内神経線維は肥厚を示したが機能的異常は認めないと考えられた.
臨床報告
YAGレーザーによる眼内レンズ障害実験
著者: 浅野良弘 , 水野勝義
ページ範囲:P.521 - P.523
Nd-YAGレーザーによる後発白内障切裂時の合併症であるIOLの破損を実験的に作り,表面を走査型電子顕微鏡で観察した.
PMMA製レンズでは,照射エネルギー,パルス数に応じて大きさの異なる欠損がみられた.この欠損は直径20〜125μmの円形を示し,内部は放射状で,また熱により形成されたと考えられる滑らかな面が観察された.照射点の深さによってはこの欠損を中心にして長さ1mmにも及ぶcrackがみられた.
ガラス製レンズでは,同様の照射エネルギーの差による形態の差以外に,レンズ全体にcrackが入り脱落するのが観察された.
従来,Nd-YAGレーザーによるIOLの欠損は視機能に影響を及ぼさなかったと報告されてきたが,照射法によっては影響を及ぼす欠損ができる可能性があり,慎重な照射を要する.
ガラス製IOLでは,レンズ全体が破損する可能性があり,Nd-YAGレーザーの使用は不適当である事が再確認された.
Aicardi症候群の1症例
著者: 渡辺英臣 , 松尾信彦 , 白神史雄 , 大野広子 , 伊豫田邦昭 , 村上政江
ページ範囲:P.525 - P.529
生後2カ月より異常脳波を伴う屈曲性痙攣が出現したAicardi症候群の女児を報告した.CTで脳梁欠損,X線にて第11胸椎に蝶形椎を認めた.生後4カ月時,右小眼球,両視神経乳頭欠損,両眼に境界鮮明黄白色の網膜脈絡膜病巣の散在,左眼後極部に限局性浮腫状病巣を認めた.螢光眼底上両眼に共通な病巣はwindow defectと部分的脈絡膜血管充盈欠損像,左眼浮腫状病巣はpoolingを呈した.前者は網膜色素上皮と脈絡膜の萎縮,後者は網膜色素上皮剥離と考えた.
強膜アプローチによる網膜剥離手術—不成功例の検討
著者: 本田孔士
ページ範囲:P.531 - P.535
1976年から1981年までの6年間に経験したコンベンショナルな網膜剥離手術の不治18症例,19眼について検討した.その中には,現在の硝子体手術の技法をもってすれば復位せしめえたであろうと考えられるものが10例あった.その他,手術拒否による不治,手術すべきでなかった続発性剥離に手をつけた不成功が1例,重症の脈絡膜剥離のため途中で治療を断念したものが2例,復位手術不成功ながら約1年後に網膜が自然復位した2例,全身状態の悪化から眼科手術が不可能になった1例などがあった.これらの不治例には術前の視機能の悪いものが多かったが,硝子体手術を合わせれば非常に高率の網膜復位が可能となった現在,術後の視機能をより高く保つ術式の開発と選択,その見透しに基づいて手術の適応をいう時代に来ているとの考えを述べた.
傍乳頭部外生網膜血管腫(juxtapapillary exophytic retinal angioma)
著者: 原田敬志 , 水野計彦 , 山崎淳 , 富安誠志
ページ範囲:P.537 - P.541
Von Hippel病のうちでも病型として珍しいjuxtapapiliary exophytic retinalangiomaを30歳女性の右眼に認めたので報告した.腫瘍は鼻側傍乳頭で11時から4時まで拡がり1/2乳頭径ほどで,扁平で淡赤色の色調を示した.螢光眼底上色素の腫瘍部への流入は動脈相でなされたことが確認された.
自動視野計(Topcon SBP-1000)の使用経験
著者: 貫名香枝 , 時枝延枝 , 村上裕美 , 西峪美恵子 , 西植茂晴 , 可児一孝
ページ範囲:P.543 - P.547
我々の開発した自動視野計(Topcon SBP-1000)を臨床に使用し,ゴールドマン視野計による動的視野と比較した.緑内障,視神経疾患,半盲,網膜疾患,その他の例において,視野異常をよく検出することができ,特に,初期の視野異常の検出に優れていた.
本視野計には,閾上刺激による静的測定と閾値測定の豊富なプログラムがあり,また,自動的な測定の他,任意の部位を細かく測定することもできる.短時間でスクリーニングと詳細な測定が可能で,臨床的に有用な視野計である.
網膜色素変性症と診断されていた進行例を含むX染色体若年網膜分離症の一家系
著者: 早川むつ子 , 細田ゆり , 中島章 , 百瀬隆行
ページ範囲:P.549 - P.553
若年網膜分離症の典型的所見を有する3兄弟と,網膜色素変性症と診断されていた母方の祖父について報告した.
祖父例は高度な視力・視野異常を有し,夜盲の自覚があり,眼底には不正形の色素斑が多数出現していた.さらに,周辺部網膜の樹枝状白色線や網膜から硝子体側へ隆起するu字状の半透明膜様物も認められた.後者の所見から原発性の網膜色素変性症は否定され,またGoldmann-Favre病は遺伝形式が異なる点で否定された.過去の報告例を検討した結果,祖父例は若年網膜分離症のsevere typeの進行例の特徴と一致しており,自験例の家系はX染色体劣性遺伝形式を示す若年網膜分離症であると結論された.X染色体若年網膜分離症の予後は比較的良好とされているが,一方では失明の報告もあり,自験例は本症の予後が老齢期においては必ずしも楽観できるものではない事を示す家系といえる.
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(40)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斎藤仁男
ページ範囲:P.554 - P.555
49.四十八膜并五色闇目口伝抄
「闇目口伝抄」という本は伝説的存在と思われるほど過去のものとなったが,中川壺山輯「本朝医家古籍考」(昭和7年,新松堂刊)に『此書ハ明応8年ノ写本ナリ,眼科ノ書ナリ云々』とあり,本書の成立は,田代三喜(導道,範翁,1465〜)が医方書を携えて逗留の中国(明)より帰えった明応7年(1498)の翌年,即ち明応8年(1499)に遡り,馬島流眼科においては,その第8世了円法印の代に相当し,尾張馬島薬師寺の宗慈坊重常が大智坊と称され,眼医者として活躍していた.北野社,松梅院禅豫の日記,明応2年2月の条に,『馬島大智坊目薬二包被送申候』(副島種經氏資料)と記されているが,馬島大智坊の活動振りが窺える.本書は本邦眼療書名中,最も古いものであろうといわれているが,その伝本すら極めて少なく,永禄13年観善写といわれるものの写本(岩波図書総目録収載),永禄13年11月写と識される写本(千葉大眼科蔵)等の古写本が現在伝えられているにすぎない.ここに掲出のものは内題に「四十八膜并五色闇目口,風眼目薬」と書かれ,慶長20年(1615)の日付のある写本であるが,原著者,相伝者は何れも不明であり,後世における慶長本の写しと思われる.
この写本は35葉,全1冊(23.8×16.8cm)の和装本で,片仮名交りであるが本文は漢字体で書かれ,眼病図などは素描である.内容は前半19葉に"内外薬種以加減可療養㕝"後半15葉には"薬種処方"について述べ,その前者には48種の眼病名それぞれに淡彩色の眼病絵図を描き,簡単な薬種療法,個々に眼病の病因をのべている。
GROUP DISCUSSION
眼先天異常
著者: 馬嶋昭生
ページ範囲:P.556 - P.558
1.Ochratoxin Aによる眼形成異常に関する研究.強角膜Sclerocorneaの発生学的考察
白井正一郎・大鹿智・馬嶋昭生(名市大)
妊娠7日のJcl:ICRマウス腹腔内にochratoxin Aを2または3mg/kg投与し.妊娠10,12,14,16,18日に胎仔をとり出して,眼部を組織学的に観察した.眼杯前縁部が角膜裏面に接するように存在し,角膜実質を形成する間葉系組織中に血管が認められ,強角膜に相当すると考えられる所見を得た.眼杯外板との組織相互作用の障害により,角膜内皮や実質となる間葉系組織が強膜様組織へと分化し,強角膜が成立すると推定した.
基本情報
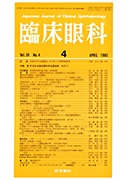
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
