(1)わが国ではもちろん,近年,世界中で近視が増加している.とくに若年者に増えているのは,おそらく近業に関係があると推定される.
(2)増えているのは軽度ないし中等度の近視であって,強度近視とは別物とする意見もある.しかし今回の成績から,近視の本態を2種類に区別することは不自然であるといえる.
(3)電気生理学的ならびに病理学的に,近視の毛様体,脈絡膜の障害が示されている.
(4)近視度ともっとも密接に関係するのは,硝子体腔の延長であって,このことは強度近視のみでなく,軽度近視にもみられる事実がある.
(5) vitreous fluorophotometryによって,近視における血液毛様体柵の障害が初めて明らかにされた.これは近視の程度ときわめてよく相関し,近視の初発症状と思われる.
(6)血液毛様体柵の障害が何故起こるのか不明であるが,その引き金となるのは持続調節であることが推定される.
雑誌目次
臨床眼科39巻5号
1985年05月発行
雑誌目次
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
特別講演
近視眼のvitreo-retino-ciliary barrier
著者: 保坂明郎
ページ範囲:P.569 - P.578
学会原著
先天性第3色盲不完全型の一家系
著者: 市川宏 , 三宅養三 , 市川一夫
ページ範囲:P.579 - P.583
我々は先に先天性第3色盲の一家系例を報告したが,今回更に先天性第3色盲不完全型の一家系を経験し,本症の特性をより明らかにすることができたのでここに報告する.
この家系には発端者(女性)とその父,妹の3名の不完全型第3色盲患者があり,常染色体優性遺伝を認めた.この家系内に視神経疾患をもつ患者は見いだされなかった.
家系内の第3色盲患者はすべて良い視力をもち,調べえた範囲で眼疾もなく,色覚検査で赤緑色覚異常を伴わない純粋な第3色覚異常所見を示した.
発端者について,ERG検査ではnormal responseを示したが,黄色背景光下のblueERGはnonrecordableであった.心理物理的検査としてスベクトル比視感度と,Waldの選択色順応法による錐体の分離と二色閾値法(tvi曲線)とTransient Tritanopia Effectの測定を行い,tvi曲線で青錐体系がわずかに機能している以外完全型第3色盲と同じように青錐体系が機能していない結果を得た.
特異な色覚異常を呈した兄妹
著者: 神立敦 , 北原博 , 北原健二
ページ範囲:P.585 - P.588
高度の視力障害,羞明,先天性眼球振盪を伴った強度の色覚異常を有する兄妹について検索した.
両症例の視力は両眼ともに0.1(0.1)であったが,眼底には異常がみられなかった.各種色覚検査表で強度異常が示され,色相配列検査では赤緑異常様のパターンを呈した.
兄の4°部位における暗順応下スペクトル感度からはCIE暗所視比視感度類似の反応が得られた.また,中心部位における白色順応下スペクトル感度測定の結果,錐体系の反応が得られたが.正常者と比較し長波長側で感度の低下がみられた.しかしながら,第1色弱例のものよりは長波長側で感度は良好であった.Rayleigh均等において赤-緑の混色目盛りは赤側に移行がみられたが,単色目盛りは第1色弱と比較し大きな値を呈した.
以上の結果から,本症例は杆体系および錐体系の反応を有するものの,特に赤および緑錐体の視色素のoptical densityの減少によるincomplete achromatopsiaの一種と推察した.
後部硝子体剥離層の微細構造—動物モデルの作成
著者: 原彰 , , J.Ryan
ページ範囲:P.589 - P.592
象兎にビトレクトミーを行い,BSS液で硝子体腔を満たし液化硝子体を人工的に形成すると.部分後部硝子体剥離が生じた.硝子体剥離は全例共硝子体皮質内で起こり,内境界膜直上から起こった例は無かった.硝子体皮質に液化硝子体の流入路としての裂孔形成が無かった事から,硝子体剥離の発生機序として,まず液化硝子体が必要条件であるが,硝子体皮質の裂孔形成は必要ではないと考えられた.液化硝子体のみが主因となって誘発する後部硝子体の可能性が論議された.一般に硝子体皮質のコラージェン層は,網膜面に層状に配列されている事が後部硝子体剥離を引き起こす基本構造のようであった.
後部硝子体剥離眼のvitreous fluorophotometry
著者: 萱沢文男 , 三宅謙作 , 草田英嗣 , 吉川隆男
ページ範囲:P.593 - P.598
経年性後部硝子体剥離が,フルオレセイン-Naの硝子体内へのinwardおよびoutward transportにどのような影響を与えるかを知る目的で,vitreous fluorophotometryを行った.
方法としてinward transportは,色素静注1時間値で,outward transportは,硝子体螢光濃度が最高値となった時点での血漿内freeフルオレセイン濃度と,硝子体螢光濃度の比(Cs/Cv)を指標として判定した.
(1)色素静注1時間後の後部硝子体および中部硝子体螢光濃度は,後部硝子体剥離眼において有意に高く,特に中部硝子体値で著明であった.螢光濃度の上昇は,血液-網膜関門の透過性亢進によるものではなく,液化硝子体によるフルオレセイン粒子の拡散速度の増大によるものと考えられた.一方,前部硝子体値は有意差はなかった.
(2) Outward transportの指標としてのCs/Cvは,有意差がみられなかった.
硝子体性状はvitreous fluorophotometryの結果を判定する上で,常に考慮に入れねばならない問題と考えられた.
乳頭周囲領域の拡大と陥凹を伴う視神経乳頭部先天異常
著者: 東範行 , 植村恭夫
ページ範囲:P.599 - P.605
視神経コロボーマ,乳頭周囲ぶどう腫,朝顔症候群およびこれに類似する乳頭形成異常45眼につき乳頭近傍の諸病変を比較検討した.陥凹部周囲の輪状,および下方の舌状の網膜脈絡膜萎縮病変は各異常に高率に認められ,硝子体中の索状物は低率であるが共通に認められた.これらの症例の中にはおのおのの異常の境界例と思われるものがあり,かつ症例によっては諸病変が少しずつ異なることよりこれらの異常は連続性があることが強く推測された.これらは発生機転の程度が違うものか発生時期にずれがあるのかは明らかではないが同一スペクトラム上にあるものと思われた.
糖尿病性網膜症のvitreous fluorophotometry
著者: 藤井正満 , 能美俊典 , 渡辺正樹 , 金森美智子 , 古瀬なな子 , 瀬戸川朝一
ページ範囲:P.607 - P.612
糖尿病性網膜症115例211眼を病期別に分類して,vitreous fluorophotometryを行い,次の結果が得られた.(1)各病期とも年代別vitreous fluorophotometry値(以下VF値)は,正常眼と同様,高齢になるにつれて増加する傾向にあった.(2) Scott 0期およびScott Ⅰa-Ⅱa期(50歳代を除く)の年代別VF値は,正常眼と比較すると全例高値を示したが,t検定では有意差を認めなかった.(3) Scott Ⅲa-Ⅲb期とScott Ⅳ-Ⅴ期の年代別VF値は,Scott Ⅰa-Ⅱa期の50歳代を含め正常眼と比較すると有意に高値であり,病期の進展につれ血液網膜柵の障害は増大する傾向を示した.(4)罹病期間別VF値は,Scott 0期,ScottⅠa-Ⅱa期,ScettⅣ-Ⅴ期では,罹病期間が長くなるほど増加する傾向にあった.(5) ScottⅢa-Ⅲb期の罹病期間別VF値は,罹病期問が長くなるほど増加傾向にあったが10年以上では減少を認めた.(6)治療別VF値は,ScottⅣ-Ⅴ期を除く各病期では,インスリン療法が最も高値で,以下,内服療法,食餌運動療法,未治療の順であり,ScottⅢ期まではインスリン依存型糖尿病患者において,血液網膜柵の障害が最も大きいことが思惟された.
黄斑円孔による網膜剥離に対する硝子体手術の予後とその適応
著者: 山岸和矢 , 西村晋 , 荻野誠周 , 永田誠
ページ範囲:P.613 - P.617
黄斑円孔による網膜剥離に対してvitrectomyとgas tamponadeを施行し,術後6カ月以上最長2年にわたり経過観察を行った24眼について検討した.
(1)硝子体手術のみで復位したのは15眼63%で光凝固を追加し復位したのを含めると20眼83%がジアテルミー凝固やbucklingを施行せず復位した.
(2)本術式は残った視機能をより良く残すことができ,絶対暗点や変視症も自覚せず,ジアテルミー凝固を行った症例より術後視力は良かった.
(3)本術式のみで復位した15眼中4眼は経過観察中に細隙灯顕微鏡で黄斑円孔が認められなくなり,比較暗点も縮小した.
(4)本術式による復位率は後強膜ぶどう腫や網脈絡膜萎縮の程度には差はなく,−14D以下で広範剥離の症例では100%であった.復位率の悪い症例は後極部限局性の扁平剥離で−7D以上の症例であった.
(5)本術式はジアテルミー凝固とbuckling法に比べ手術時間も短く,手術眼への侵襲も少なく,黄斑円孔による網膜剥離に第一選択として行って良い術式である.
硝子体手術後失明した糖尿病性牽引性網膜剥離眼の検討
著者: 高塚忠宏 , 上谷彌子 , 秋草正子 , 月本伸子
ページ範囲:P.623 - P.626
1981年3月より1984年3月までの間に硝子体手術を行った128眼の糖尿病性牽引性網膜剥離症例中19眼(14.8%)が,術後に失明しているので,これら失明例の失明原因ならびにその予防法について検討した.
19眼中,術中に網膜が復位しえなかった症例は4眼(21.1%)であり,その内3眼は,活動期のT型もしくはY型全網膜剥離例であった.
術中に網膜を復位しえた15眼中8眼(53.3%)は網膜剥離の再発から,また,5眼(33.3%)は血管新生緑内障から失明に至っている.しかもこれら13眼中6眼(46.2%)では,術後の硝子体腔中への再出血が網膜剥離もしくは血管新生緑内障発生のきっかけとなっている.
これらの結果より,T型もしくはY型全網膜剥離例では,網膜相互の癒着が強固になる以前に硝子体手術を行うべきであり,術後の頑固な再出血が予測される症例ならびに,術後の硝子体腔中のフィブリン析出等の炎症性変化が再網膜剥離を誘発すると思われる症例では硝子体切除後にシリコンオイルを硝子体腔中に注入し,再出血ならびに炎症性変化の起こる"場"をなくすことが必要であると考える.
緑内障性視神経乳頭の循環動態(続報)—眼圧変動時の検討
著者: 関伶子 , 岩田和雄
ページ範囲:P.627 - P.632
視神経乳頭の上下Bjerrum領線維集積部に,眼圧上昇により,緑内障性軸索障害の原因となるような部位特異的循環障害が発生するか否かを追究する目的で,神経線維層(NFL)に異常がないか,あっても極初期〜初期の軽度のNFL欠損を伴う7例7眼の緑内障について,眼圧上昇時と下降時の乳頭の同時立体螢光写真による三次元的解析を行い,次の結果を得た.
(1)充盈欠損は①眼圧上昇時と下降時で質的,量的に差はなく,②既存のNFL欠損に一致する陥凹底内にのみみられ,③NFL欠損がわずかに存在しても陥凹拡大のない例や,NFL欠損の存在しない例ではみられなかった.
(2)螢光漏出は①網目状血管と集合小静脈にみられ,②眼圧上昇で発生し,下降に伴い減少または消失した.③網目状血管からの漏出は陥凹底内のNFL欠損に一致した充盈欠損部にのみみられ,集合小静脈からの漏出はNFL欠損のない例でもみられた.④漏出の後で,新たにNFL欠損の発生する例はなかった.
以上の結果から,眼圧が上昇しても,乳頭のBjerrum領線維相当部に部位特異性微小循環障害は発生しないこと,充盈欠損は既存のNFL欠損に伴う異常であることが明かとなった.
したがって,従来,充盈欠損は軸索障害の原因となる一次的所見とみなされる傾向が強かったが,むしろ二次的変化にすぎないことを強く示唆する結果となった.
開放隅角緑内障の対比視力
著者: 磯松幸雅
ページ範囲:P.633 - P.636
原発開放隅角緑内障(以下POAG)の中心窩視機能を簡単に検査する目的で,市川・長南式対比視力表により対比視力を測定し次の結果を得た.
(1) POAGでは対比視力の低下がみられ,病期の進んだ症例ほど低下が強かった.
(2)偽緑内障でも対比視力の低下がみられた.
(3)高眼圧症では対比視力の低下はみられなかった.
(4)緑内障の視機能検査に対比視力測定は有効である.
学術展示
重症型眼サルコイドーシスと硝子体切除術
著者: 橋本和彦 , 宮久保純子 , 多田博行 , 堀内知光
ページ範囲:P.638 - P.639
緒言 眼サルコイドーシスは一般に予後良好な疾患とされているが,時に炎症が持続して,高度の硝子体混濁,血管新生,硝子体出血を起こし,併発白内障や続発性緑内障を合併して重篤な視機能障害に至る例がある.我々は過去5年間に経験した眼サルコイドーシス153例の内,このような重症型3例4眼に対してpars planavitrectomy (経毛様体扁平部硝子体切除術)を行い,その結果大幅に視力を改善しえた.さらに,術後の経過を長期間観察したところ視力は安定し,葡萄膜炎そのものも鎮静化する方向に向かった.
症例 症例1(K.T.54-0285):58歳女子.初診時より硝子体混濁がつよく,白内障が併発していた.右0.04(n.c.),左0.1(n.c.)の視力であったが,経過中に硝子体混濁と併発白内障が増強したために,右眼にvitrectomyおよびlensectomyを施行し,左眼にも6カ月後に同様の手術を行った(図1).術後,サルコイドーシスの大きな炎症発作は無く,現在にいたるまでステロイド点眼のみで充分にコントロールされている.
硝子体手術用電磁式眼内マグネットの試作
著者: 三木徳彦
ページ範囲:P.640 - P.641
緒言 眼内鉄片異物の摘出方法として,硝子体手術法は従来のマグネット法に比して,はるかに予後が良好であると報告してきた1,2).しかしながら,硝子体鉗子で異物をつかみ摘出するのは技術的に簡単なことではない.そこで,この摘出を容易にするため,硝子体手術時の使用に便利な電磁式眼内マグネットを作製したので報告する.
本装置の特徴 硝子体手術用電磁式眼内マグネットは眼内挿入チップの長さを30mm,太さを,20G (ゲージ)と16Gの2種類とした.20Gは最大10g,16Gは最大30gの鉄片を持ち上げることができる.磁力の強さは,本体のスイッチにより強,弱(2:1)に,またフットスイッチより,強,弱(2:1)の,それぞれ2段に切り換えが可能である.灌流付きハンドピースも作製した.ハンドピースの直径は13mm,全長170mm,重さは,60gで,硝子体手術時の操作に適していた.
凍結乾燥硬膜による強膜内ポケット法
著者: 河井克仁 , 鈴木庸一 , 越智利行 , 木下雅夫 , 深道義尚
ページ範囲:P.642 - P.643
緒言 上斜筋付着部の裂孔による網膜剥離に対し,上斜筋の切腱・scleral infoldingや太いPlombeを置くことは,術後外眼筋の機能不全の発生が考えられる.今回我々は輪部より16mm後方で,11°30'の裂孔による右眼の網膜剥離の2症例を経験した.この2症例に対し,外眼筋機能を確保するために上斜筋および上直筋を切離せず凍結乾燥硬膜Lyodura®を埋没させる強膜内po-cket法を施行し,予後良好な結果を得たのでその術式について報告した.
網膜下液の粘度と臨床所見との関係
著者: 松田久美子 , 船坂芳江 , 樺澤泉
ページ範囲:P.644 - P.645
緒言 網膜下液の粘度は,これまでの著者ら1,2)ならびにHammerら3)の測定によると,血清よりは粘稠で,液化硝子体とは同程度からそれ以上に粘稠なものまでであった.この粘度と臨床所見さらにその構成成分との関連性について検討した.
方法 実験材料として,網膜下液は手術時の排液創にテフロン針を当てがい吸引採取したものの内,混入赤血球が1×104/mm3以下のものを用いた.血清および摘出眼球より得た液化硝子体と上記網膜下液は,室温で3,000回転5分間遠心後の上清を用いた.粘度は円錐平板型回転式粘度計(東京計器社製E型)により,37℃,0.5mlの液量で測定した.網膜下液の上清が0.5ml以上あった25例は原液の粘度を,0.5ml未満の54例については生理食塩水による5倍希釈液の粘度を測定した.臨床所見と粘度との関連性については多変量解析で検討した.構成成分のうち,ヒアルロン酸はJourdianらの方法,蛋白質はLowry-Folin法,グリコペプチドはフェノール硫酸法で測定した.
胞状網膜剥離について
著者: 原彰 , 清水由規 , 川村俊彦 , 浅田洋
ページ範囲:P.646 - P.647
胞状網膜剥離(bullous retinal detachment)という疾患は1973年Gass1)の報告により名付けられた疾患である.しかし本疾患の臨床的特徴および病態発生機序を検討すると,中心性網膜炎の異型または激症型と考える者1〜3),あるいは中心性網膜炎とは別個の疾患と考え,むしろ多巣性に発生する網膜色素上皮症と考える者4,5),uveal effusionが眼底後極に発生し中心性網膜炎様の症状をとると考える者7)等々,胞状網膜剥離に対する呼称,病態の捕え方が異なり議論の絶えない疾患である.どのような病名が正しく本疾患の病像をとらえているのか今後の症例数の蓄積により解明されることと思われる.今回我々はいわゆる胞状網膜剥離または異型中心性網膜炎の3症例を経験し多少の考按を加えてみた.すなわち胞状網膜剥離には中心性網膜炎に近い臨床像を示すものから多巣性網膜色素上皮症の臨床像を示すものまであり,胞状網膜剥離の原因を一つの病態に求めなくても良いのではないかと考按した.
症例 1:47歳男子(#0576).
Vitrectomyを要した増殖性硝子体網膜症の検討
著者: 加藤秋成 , 太田陽一 , 新井真理
ページ範囲:P.648 - P.649
緒言 近年,増殖性硝子体網膜症(以下PVR)に対し硝子体手術が導入され,難治性網膜剥離の治療成績が向上している.しかし,いかに技術的な向上があろうとも,ひとたびPVRを発症すると,PVRの無い一般的な網膜剥離に比べ,その治療成績は格段に悪い.それゆえ,網膜剥離手術をする上でPVRを発症させない様にするにはどうしたらいいのか,という問題を考えるために,硝子体手術を要したPVRの症例を検討した.
方法 対象は裂孔原性網膜剥離により,初回,当院ならびに他院で網膜剥離手術を受け,その後C-11)以上のPVRとなり,当院で1981年より1984年4月までに硝子体手術を受けた80眼である.また,macular puckerの症例は除外した.以上の症例につきPVR発症に関すると思われる事項を検討し,また手術結果を検討した.なお比較対照には当院で同時期に初回手術をした裂孔原性網膜剥離のうち,PVRを除いた399眼を用いた.
側頭動脈炎による後部虚血性視神経症の1例
著者: 小沢勝子 , 滝昌弘 , 古田節子
ページ範囲:P.650 - P.651
緒言 側頭動脈炎(以下TA)により発症した後部虚血性視神経症(以下PION)の報告は本邦ではみられない.早期のステロイド治療が博効を呈したTAによるPIONの1例を報告する.
症例 64歳男性.1983年11月14日初診.右眼が2カ月前から暗く見え近医で経過観察中であったが,2日前から右眼視力低下のため当科へ紹介された.既往歴は22歳左湿性肋膜炎,40歳右肺結核.52歳発熱,頭痛,赤沈亢進,CRP陽性で当院内科へ入院してステロイド剤で軽快,54歳他病院にて腹部大動脈炎で人工血管移植術,59歳汎下垂体機能低下症にて当院内科入院,以後コーチゾン25mg/日内服.60歳に高血圧症発症し降圧剤を時々服用.初診時視力右光覚,左1.5(n.c.),眼圧は両眼とも18.9mmHg.右眼の直接対光反応減弱.眼底は左右とも乳頭正常でH0S1.眼底血圧は右56.9/40.6mm-Hg,左59.4/43.3mmHg.右浅側頭動脈は触知困難.赤沈は75mm/1h,100mm/2hと亢進,白血球数12,500/mm3と多く,血小板数36.1×104/mm3,フィブリノーゲン470mg/dlと高値.
重症筋無力症の瞳孔
著者: 山本俊一 , 石川哲
ページ範囲:P.652 - P.653
緒言 重症筋無力症(以下MG)では,瞳孔異常がないとされているが,これに反対の報告もある.MGの瞳孔に関して,瞳孔の下縁にスリット状の光を当てつづけることによって起こる瞳孔振動,edge light pupil osci-llation (以下ELPO),その周期,Pupil Cycle Time (以下PCT)に注目した.図1上段に振動の様子を模式的に示した.この刺激方法は,核上性の因子も含まれると考えられ,より生理的である.
当初,我々はMGのELPOについて,速度分析を行った1).その際,症例数が少ないので統計的検討を行わなかったが,MGの瞳孔に関し以下の印象をうけた.一つはLeporeの報告2)に反して正常とあまり差がない様であり,二つにはELPOが惹起されにくい例が多かったことである.そこで今回は症例を増やし,これらについて検討した.
若年性糖尿病患者における調節異常
著者: 難波龍人 , 名畑目薫 , 石井真紀子 , 鵜飼一彦 , 石川哲
ページ範囲:P.654 - P.655
緒言 糖尿病患者の調節について,現在,近視化あるいは遠視化,痙攣あるいは麻痺であるなどという説がある.また,血糖値との関係についても血糖値が高ければ近視化し,血糖値が下がれば正常化するといわれている.しかし,調節の動特性についての研究は一切ない.今回,視力良好で調節力の十分な若年性糖尿病患者について調節の動特性および振幅とそれらと血糖値との関連性を研究したところ興味ある結果を得たのでここに報告する.
対象 11歳〜43歳の視力良好で調節力を有する若年性糖尿病患者30名を対象とした.インスリン治療中のもの16名,内服治療中のもの4名,食事療法中のもの10名で,男17名,女13名である.糖尿病性網膜症の存在するものは7名であるが,硝子体出血のため片眼測定不能であった1例を除き視力は良好である.腎障害を有するものは1名で,神経症状を有するものはなかった.これらを血糖値が200mg/dl以上のI群17名と200mg/dl未満のII群13名とに分けた.性別,年齢などを考慮した正常者を対照とした.
Open loop刺激による対光反応について—鼻側および耳側網膜刺激による直接および間接反応の検討と半盲患者への応用
著者: 白川慎爾 , 長谷川幸子 , 石川哲
ページ範囲:P.656 - P.657
緒言 Open loop刺激を用いた瞳孔の対光反応についての研究は近年数多くなされており,closed loop刺激と比較して刺激量が安定していることなどよりその有用性が示されている.今回我々はopen loop刺激の赤外線電子瞳孔計を用いて,正常者の鼻側網膜および耳側網膜刺激を行い,対光反応の直接および間接反応について調べた.また後頭葉障害による同名半盲を呈している患者6名について同様の検査を行い半盲性瞳孔硬直の有無,および正常者との比較について調べた.
方法 対象とした被検者は眼疾患の既往のない正常者16名(男性8名,女性8名)で,年齢は20〜31歳(平均年齢26歳)と後頭葉障害による同名半盲患者6名である.これらの患者はすべて典型的同名半盲を呈しており,かつ黄斑回避も認められた.用いた装置はopen loop刺激の単眼用赤外線電子瞳孔計で光刺激装置と測定用カメラが分離しているため直接,間接反応がとれるように設計してある光刺激は2000trolandで刺激時間は0.5sec,中心窩より鼻側および耳側へそれぞれ5°の位置で直径5°の範囲で刺激を行った.15分間の暗順応後,直接および間接反応をそれぞれ3回ずつ残像が残らないように一定の間隔をおきながら測定した.測定に関しては瞳孔反応が安定している時間帯,昼食後1時間を除く午前9時から午後3時の間で測定した.
異常頭位を伴う先天性眼振の治療 artifizielle Divergenz von Cüppersについて
著者: 大月洋 , 渡辺好政 , 江木邦晃 , 平松美佐子 , 中山緑子 , 生田全
ページ範囲:P.658 - P.659
緒言 artifizielle Divergenzという概念は,1969年Cüppers1,2)が先天性眼振にみられる異常頭位の矯正のひとつとして発表したものである.この方法で治療した2症例について報告する.
症例 症例1:9歳女児,両眼視下,遠見で頭を40°左へ回転させる頭位がみられる.遠見視力は,この頭位で0.4,一方左方視0.2,正面視0.2,単眼視では,固視眼が外転位の頭位をとる.近見では異常頭位(‐),視力は注視方向には関係なく1.0,斜位(‐),斜視(‐).両眼視機能;異常頭位では線条レンズで融像可,近見立体視(Titmus);5/9,2/3.眼振は水平方向で,振巾は左眼の方が大きくPendelとRuckが混在.ENG;両眼視下,遠見では両眼共通の注視方向で著明に眼振が抑制される所見(‐)であるが,あえていえば,右30°付近が該当(図1).一方,単眼視では固視眼が内転位で著しく抑制され,近見ではさらに強い抑制が認められた.遠見よりも近見で著しく眼振が抑制されることから,プリズムで内よせ融像を惹起させれば,遠見でも近見と同様の眼振の抑制が得られ異常頭位も消失すると考え,異常頭位での内転位眼の左眼にプリズムを基底外方に装用させた.
連載 眼科図譜・330
結膜乳頭腫の1例
著者: 青木功喜 , 藤岡保範
ページ範囲:P.566 - P.567
Human papilloma virus (HPV)によって結膜に乳頭腫が発生することはHogan1)によって報告されているが,稀な疾患である.結膜に発生する乳頭腫にはinfec-tiousとnoninfectiousのものがあることをWilsonとOslerが指摘している2).我々は若年者にみられた結膜乳頭腫を経験したので供覧する.
症例127歳,M.I.(59-01685).1年前より左眼瞼の内側に腫瘤を自覚していたが,漸次増大し異物感も強くなったので,1984年2月9日に初診,視力は1.2で,眼内にも異常所見は認められなかった.
臨床報告
糖尿病性牽引性網膜剥離に対する硝子体手術後のフィブリン析出
著者: 玉田玲子 , 切通彰 , 佐藤勝 , 西川憲清 , 田野保雄
ページ範囲:P.661 - P.665
糖尿病性牽引性網膜剥離に対する硝子体手術67眼のうち,26眼(39%)に術後眼内へのフィブリン析出を認めた.フィブリン析出は眼外冷凍凝固,糖尿病のコントロール不良,腎機能障害,フィブリノーゲン高値,網膜症の活動性が高いことが要因として考えられた.術後フィブリン析出の対策として,術前に十分な光凝固を行い網膜症を抑制すること,術中のアドレナリン添加眼内灌流液の使用と眼外冷凍凝固の抑制が有効である.
隅角色素沈着を伴った緑内障に対するレーザー隅角形成術
著者: 金谷いく子 , 溝上国義
ページ範囲:P.667 - P.670
種々の原因による虹彩色素脱出および隅角色素沈着を伴った続発緑内障7例7眼に対し,アルゴンおよびクリプトンレーザーによるレーザー隅角形成術(LTP)を行い,その有効性について検討した.照射出力についてはbubble reflexをめやすにし,各症例ごとに決定した.その結果全例に有効な結果を得,とくに眼圧上昇後期間の短い例で劇的な効果をみた.またレーザー照射前後の色素沈着の差異とアルゴン,クリプトンによるLTPの有効性に対する比較検討から,その奏効機序は瘢痕収縮による線維柱帯の開大と色素のwash outによるものが考えられた.
左下眼瞼に発育した眼窩原発悪性リンパ腫の1例
著者: 伊東由紀子 , 横山健二郎 , 伊藤晃 , 増井恒夫
ページ範囲:P.671 - P.674
85歳の婦人で左下眼瞼に巨大な暗紫色の腫瘍がみられ,生検の結果,悪性リンパ腫と診断された1例を報告する.高齢のため発症後も無処置のまま放置されたため,初診時には巨大な腫瘍に増大しており開眼も不可能であった.生検標本により組織学的には,非ホジキンリンパ腫に属するびまん性リンパ腫.小細胞型と診断された.
化学療法(vincristineとprednisoloneの併用)で著効を示した.本症の様な高齢で入院加療の困難な症例においても化学療法を行えば,かなりの延命効果があると考える.
極小未熟児における未熟児網膜症—重症型未熟児網膜症の予後と治療における問題点
著者: 上田佳代 , 山名敏子 , 西村みえ子 , 近藤乾
ページ範囲:P.675 - P.679
1980年9月1日から1983年12月31日までに福岡市立こども病院NICUで経験した出生体重1,500g未満の極小未熟児69例について網膜症発生状況を検討し,さらに重症型網膜症の臨床所見,治療,予後について検討した.
(1)網膜症を発生したのは38例(55.0%),そのうち重症型網膜症は7例(10.1%)であった.
(2)重症型は全例在胎28週以下,出生体重1,000g未満で,人工換気療法を受けていた.
(3)重症型の早期診断は,網膜血管先端の位置が耳側では黄斑部から3.5乳頭径以内,鼻側では乳頭縁から6乳頭径以内で,血管先端に異常吻合,走行異常,軽度の怒張が認められれば,これを重症型と診断してよい.
(4)重症型の治療は,光凝固が第一選択で,診断がつき次第すみやかに開始し,境界部と無血管帯を十分に凝固することが重要である.また,治療によりいったん寛解した網膜症が再燃する場合があり,注意すべきである.
天井懸垂型眼底撮影装置の工夫
著者: 唐木剛 , 長坂智子 , 水上寧彦 , 太田一郎 , 堀口正之 , 三宅三平
ページ範囲:P.681 - P.683
小児を対象として眼底写真撮影を正確に行うため,抑制帯や吸入麻酔を用い仰臥位とした上で,検眼ユニットの支柱を利用して懸垂した眼底カメラを用い,眼底を撮影する方法を工夫し報告したが,今回,さらにこれを無影灯の支持装置を用いて天井懸垂型の眼底撮影装置に改良して,カメラを任意の高さで止めることができ広い可動性を得て,より容易に眼底を撮影することが可能となった.
手術ノート
初心者のための安全な眼内レンズ手術(1)
著者: 上野山謙四郎
ページ範囲:P.684 - P.685
白内障術者にとりIOLはもはや避けて通れない.和医大も最近PC-IOLを手術教育に取り入れた.方針は下記のとおりで,熟練者とかなり異なるが,初心者への安全対策を第一としている.何よりも侵襲の少ない白内障手術が前提となることを忘れてはならない.
文庫の窓から
眼科諸流派の秘伝書(41)
著者: 中泉行信 , 中泉行史 , 斎藤仁男
ページ範囲:P.686 - P.687
50.眼目図解(仮称)
この書名は外題簽に書かれたものを掲げたのであるが,これは後世において書店などで仮につけられたものと思われる.本書には内題もみられないが,項目の一つに"眼目図解"という見出し項目があり,これが書名として付けられたのではないかと考えられる.この書名からすると,今日の眼病図解,手術図解と云った感じがするが,本書は一般的眼科治療書である.
この古写本はおよそ30葉,全1冊(27×19.5cm)よりなり,片仮名混じりの和文で記述され,内容の見出し項目を次の様に掲げている.
GROUP DISCUSSION
葡萄膜炎
著者: 青木功喜
ページ範囲:P.688 - P.690
1.ぶどう膜炎における角膜内皮障害
○小川剛史・中川洋一・猪本康代・三村康男 (徳島大)〔討論〕
船橋(東急病院):卵が先か鶏が先かという問題と似ていますが,角膜内皮が障害されてそこへ白血球が遊走して来たと考えられませんか.この問題を解決するには光学顕微鏡による白血球の決定を要します.あえてこれを施行されなかった理由をお尋ねします.
小川:本実験では免疫原性ぶどう膜炎を惹起したときの観察であり,白血球の遊走はArthus型反応に由来するものです.白血球のみでなく他の組織障害性因子も前房内に出現します.したがってlysosomal enzymeなどにより軽度障害された部に白血球が付着し,内皮障害を増強させることが一番考えやすいと思います.しかし光学切片では白血球が内皮を障害している像は認められず,やはり透過電顕レベルの観察が必要と考えられます.
基本情報
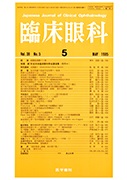
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
