(17-レセ1-11) スリットスキャン型角膜形状解析装置ORBSCANを用いて,正常角膜25眼を対象に,角膜中心から等距離の点の角膜屈折力分布曲線をフーリエ解析することにより,球面成分,正乱視成分,1次成分(非対称成分),3次以上の高次不正成分を分離定量化した。角膜前面の球面成分は48.07D,正乱視成分は0.66D,1次成分は1.18D,3次以上成分は0.06Dで,角膜後面の球面成分は−6.55D,正乱視成分は0.16D,1次成分は0.38D,3次以上成分は0.01Dであった。前面においても後面においても,非対称性を表す1次成分は正乱視を上回る値となっており,角膜の光学において不正乱視は重要な役割を持っている可能性がある。角膜後面の形状を解析することは,全角膜の屈折面としての機能を理解する上で意義がある。
雑誌目次
臨床眼科52巻6号
1998年06月発行
雑誌目次
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
学会原著
網脈絡膜に多発性の肉芽腫を生じたサルコイドーシスの1例
著者: 熊谷麻美 , 堀田喜裕 , 井出あゆみ , 貞松良成 , 早川むつ子 , 中安清夫 , 金井淳 , 前田佳代 , 植木純 , 田村尚亮 , 福地義之助
ページ範囲:P.1007 - P.1010
(17-P2-11) 18歳男性が,鈍性外傷を契機とした右眼の霧視と視力低下で受診した。矯正視力は右0.4,左1.2。前眼部は正常で,両眼底に網脈絡膜の肉芽腫が多発し,右眼には網膜静脈分枝閉塞症様の出血があった。全身的検索でサルコイドーシスと診断した。プレドニゾロン全身投与で7か月後に肉芽腫が消失し,右眼視力が回復した。
小切開眼内レンズの偏位と後発白内障の関係
著者: 吉田紳一郎 , 小原喜隆 , 西尾正哉 , 藤掛福美
ページ範囲:P.1011 - P.1015
(18-レセ2-29) 小切開眼内レンズ(以下,IOL)の偏位(傾斜と偏心)と後発白内障を前眼部画像解析装置EAS1OOOを用いて定量し,その関係について検討した。その結果,IOLの偏位はシリコーンIOLでは術後1か月から術後6か月まで強く生じていた。しかしその後減少し,術後3年では各IOLの間に差をみなかった。後発白内障の混濁はシリコーンIOLでは術後3か月から1年まで有意差を認めた。一方,PMMAIOLでは術後1年以後,混濁は上昇した。偏心と後発白内障の相関は術後1年においてアクリルIOLでみられた。
画像処理による中心性漿液性網脈絡膜症の脈絡膜血管病変検出の試み
著者: 古嶋尚 , 古嶋正俊 , 中塚和夫
ページ範囲:P.1016 - P.1018
(18-D-24) 中心性漿液性網脈絡膜症(CSR)の脈絡膜血管病変の検出を,螢光眼底造影(FAG)とカラーリバーサルの画像処理から試みた。対象はCSR群が全例黄斑部を含む網膜剥離のある14名14眼で,健常群が眼疾患のない11名11眼である。方法はカラーリバーサル,FAG動脈相早期をデジタル化し,(1)黄斑部を中心とした乳頭径を直径とする領域,(2)CSR群の剥離領域の脈絡膜平均輝度を算出した。また,(3 CSR群の(1)を①漏出点が算出領域内にある群と②ない群に分けて,平均輝度を比較した。その結果,CSR群の脈絡膜平均輝度は健常群よりも有意に高く,さらにCSR群で漏出点算出領域内の脈絡膜平均輝度が,漏出点算出領域外の平均輝度よりも有意に高かった。以上から,この画像処理のCSRのFAG脈絡膜平均輝度は脈絡膜病変を反映する可能性が示された。
網膜前黄斑線維症のOCT所見
著者: 丸山泰弘 , 大谷倫裕 , 岸章治
ページ範囲:P.1019 - P.1022
(18-D-28) 網膜前黄斑線維症19眼の網膜断面を光学的干渉断層計OCTで観察した。中心窩の厚さは,正常値150μmが300〜650μmに肥厚していた。中心窩の陥凹は15眼で消失し,黄斑網膜がドーム状に膨隆していた。偽円孔のある4眼では,中心窩周囲の網膜が肥厚し,中心窩が円筒形の急峻な陥凹を呈した。肥厚した網膜では,浮腫と液体貯留を示す低反射が外層に顕著であった。本症は網膜表面だけの病変ではなく,網膜外層に液体貯留があり,網膜に肥厚がある三次元的な疾患であることが明らかになった。
加齢性黄斑変性に対する光凝固と参考にした螢光眼底造影所見
著者: 沢美喜 , 張野正誉 , 上村穂高 , 岩橋佳子
ページ範囲:P.1023 - P.1027
(18D-30) 加齢性黄斑変性症例で中心窩外に脈絡膜新生血管が存在した37例38眼のうち,光凝固施行時にフルオレセイン螢光眼底造影(FA)またはインドシアニングリーン螢光眼底造影(IA)のいずれを参考にしたかについて,FAでCNVの存在を確認できたgroup 1と確認できなかったgroup 2に分け,その凝固成績を検討した。光凝固後平均観察期間21.4か月(6〜55か月)の凝固成功率は,group 1で96%(24/25眼),group 2は54%(7/13眼),IAを参考にした割合はgroup 1で40%,group 2は100%であった。IAは光凝固の参考所見として,FAで確認できなかった場合はもちろん,FAで確認できた場合でも有用な例があった。IAは極力全例に施行すべきであると思われた。
無縫合白内障手術後の外傷性無虹彩症の1例
著者: 木内裕美子 , 小森秀樹 , 井本昌子 , 亀田知加子 , 竹中久 , 王孝福 , 前野貴俊 , 満田久年 , 真野富也
ページ範囲:P.1028 - P.1030
(18-P2-5) 80歳男性が右眼に自己閉鎖創白内障手術と眼内レンズ挿入術を受けた。その3か月後に転倒して右顔面と眼球を打撲した。前房は維持され,白内障の術創は閉鎖していた。前房出血と硝子体出血に対して硝子体手術を行った。水晶体嚢と眼内レンズは定位置にあったが,無虹彩であった。受傷の際に虹彩が自己閉鎖創から脱出し,同時に角膜創が再閉鎖したと考えられた。
二次元有限要素モデルによる鈍的眼外傷のシミュレーション
著者: 矢部比呂夫 , 滝澤裕一 , 川口龍平
ページ範囲:P.1031 - P.1034
(18-G409-28) 汎用パーソナルコンピュータ上で稼働することができる眼球の2次元有限要素モデルを作成した。このモデルを用いて鈍的眼外傷のシミュレーションを行ったところ,実際の臨床像に近似した応力状態の変化がみられた。今後,眼組織の正確な材料定数や境界条件を確立することが課題である。
新しい乱視矯正術—白内障同時手術
著者: 対馬一仁 , 清水公也
ページ範囲:P.1035 - P.1037
(18-P2-53) 1.0D以上の直乱視がある白内障11眼に,輪部減張切開術と耳側角膜一面小切開白内障手術を行った。術前の角膜乱視は2.0±0.8Dで,術後3か月での屈折乱視は0.5±0.5Dであった。角膜内皮細胞密度は9.2%減少し,全例で1.0以上の矯正視力が得られた。乱視軸の回転,過矯正,角膜穿孔などの合併症はなかった。本術式は,強い直乱視のある白内障に対して,安全で容易,かつ有効である。
角膜形状の評価におけるオフサルモメーターとビデオケラトスコープとの相関
著者: 草野暢子 , 北澤世志博 , 佐々木秀次 , 所敬
ページ範囲:P.1039 - P.1041
(17-レセ1-9) Littmann型オフサルモメーターの強主経線と弱主経線の中間値(D)と,TMS−1の7本目のマイヤーリングの平均角膜屈折力(D)との相関関係を検討した。対象は35名69眼,屈折度−0.50〜−26.00D,角膜乱視度0〜3.75D。2機種の全症例の測定値は1次式に回帰され,その相関係数はO.958で強い相関があった(p<0.001)。さらに対象を角膜乱視により3群に分け(0以上0.75D未満,0.75以上1.50D未満,1.50D以上)同様の検討を行った結果,各群の相関係数もそれぞれ0.952,0.959,0.947で強い相関がみられた(p<0.001)。角膜中央部の形状評価では,2機種の測定値を同等に考えることができ,角膜乱視度は考慮しなくてよいと思われた。
網膜中心静脈閉塞症でoptociliary veinsが生じた症例
著者: 神野早苗 , 池田尚弘 , 三村治
ページ範囲:P.1043 - P.1045
(17-D-13) 過去5年間に兵庫医科大学眼科を初診したCRVO69例70眼のうち,乳頭部に生じるoptociliaryveinsと視力予後について検討した。経過中にoptociliary veinsを生じたのは12眼で,うち2段階以上視力改善したものは3眼,不変は6眼,悪化は3眼であった。Optociliary veins非存在群で経過を追えた54眼のうち,視力改善があったもの9眼,不変が32眼,悪化が13眼で両者に有意差はなかった。フルオレセイン螢光造影で,0ptociliary veinsは静脈相にて造影され,網膜より脈絡膜への血流方向を示した。Optociliary veinsは網膜中心静脈の灌流側副路として発達すると考えられるが,視力改善には関係しない。
両眼発症まで長期間を要したレーベル病の2症例
著者: 落合篤也 , 斉藤紀子 , 加島陽二 , 石川弘
ページ範囲:P.1047 - P.1050
(17-G402-9) 片眼の発症から他眼の発症まで,長期間を要したレーベル病の2症例を報告した。症例1は家族歴のある17歳男性で,右眼の発症17か月後に左眼に発症した。症例2は家族歴はないが大量飲酒歴のある48歳男性で,頭部外傷後に左眼が発症し,16か月後に右眼に発症した。両者ともレーベル病に特徴的な眼底所見を示し,ミトコンドリアDNA検査で11778番塩基対の変異が検出された。レーベル病はさまざまな発症様式があり,両眼発症まで長期間を要する症例もあることから,注意深い経過観察が必要である。
悪性リンパ腫の寛解期に生じた浸潤性視神経症
著者: 飯野直樹 , 久保田芳美 , 渡辺博 , 朽久保哲男
ページ範囲:P.1051 - P.1054
(17-G402-11) 70歳男性の右眼に視力低下が突発した。3年8か月前に非Hodgkinリンパ腫と診断され,化学療法と放射線治療で完全寛解の状態にあった。右眼矯正視力は0.08であり,乳頭が発赤腫脹していた。浸潤性視神経症と診断し,全身ステロイド剤投与と視神経部への放射線照射を行い,4週後に視力は0.8に回復した。3週後に視力が再び0.01に低下し,乳頭浮腫が再発した。放射線照射を行ったが,最終視力は0.1であった。悪性リンパ腫では寛解期でも浸潤性視神経症が起こりうることと,再発が多いことを示す症例である。
北九州市内19病院眼科における視覚障害者の実態調査(第1報)—視覚障害者と日常生活訓練
著者: 高橋広
ページ範囲:P.1055 - P.1058
(17-G402-13) 北九州市内19病院眼科に1997年2月に受診した22,117名を調査し,602名(2.7%)が視覚障害者であった。これらの患者の眼疾患の第1位は糖尿病網膜症で,以下,網脈絡膜萎縮,緑内障,網膜色素変性症の順で,身体障害者手帳該当者は75%であったが,実際には54%しか所持していなかった。日常生活訓練経験者は9%のみであったが,18歳未満では87%が盲学校や療育センターで,65歳以上は全身合併症のための病院リハビリテーション施設で訓練を受けていた。訓練希望者は41%,18歳未満では96%,18歳から64歳でも半数が希望しており,ロービジョンケア対象者が多数病院に通院していることが判明した。今後積極的にプライマリロービジョンケアを行う必要がある。
眼瞼結膜下に生じた汗腺嚢腫の1例
著者: 千葉可芽里 , 向井田泰子 , 小野貞英 , 田澤豊
ページ範囲:P.1059 - P.1061
(17-G409-3) 眼瞼結膜下に生じた汗腺嚢腫と思われる1例を経験した。症例は38歳,男性。右下眼瞼の軽度の腫脹を主訴に受診した。初診時,右下眼瞼結膜の円蓋部の中央に約12×10mmの腫瘤があり,同側の上眼瞼結膜にも類似の病変がみられた。下眼瞼結膜下の腫瘤の全摘出を行い,手術後の病理組織診では汗腺嚢腫と診断された。本症例は皮膚上皮性の嚢胞が瞼結膜下に生じた稀な例と思われた。
極低出生体重児における未熟児網膜症の検討
著者: 十川治恵 , 山下啓行 , 榊保堅 , 梶原真人 , 田村充弘
ページ範囲:P.1063 - P.1066
(17-P1-18) 1990年から1996年の7年間に、大分県立病院眼科で診察した出生体重1,500g未満の極低出生体重児(生存例)313例を対象とし,未熟児網膜症(ROP)の発症率,治療率,予後および合併症につき検討した。発症率は134例(42.8%)であった。治療はアルゴンレーザー光凝固を26例(8.3%)に行い,2例には冷凍凝固を追加した。治療開始は31週以降であった。25例(99.7%)は,grade 1以下の瘢痕を残すのみとなった。ROPを発症した極低出生体重児の屈折は,非発症群に比べ近視傾向を示した。眼位異常は19例(6.1%)であり高頻度であった。脳室周囲白質軟化症や脳室内出血がある超低出生体重児ではROPを伴うことが多く,眼位異常例もみられた。
加齢黄斑変性滲出型瘢痕期における固視点の視機能
著者: 藤田京子
ページ範囲:P.1067 - P.1069
(17-P1-22) 両眼性加齢黄斑変性滲出型瘢痕期の20例20眼に対し,走査レーザー検眼鏡を用いた微小視野検査(microperimetry)を行い,固視点の位置,および固視点の網膜感度を調べた。20例中遠見矯正視力0.1以上を有する11例では,中心窩から固視点までの距離が1乳頭径以内,または固視領域の網膜感度が10dB以上であり,9例(82%)で両方の条件を満たした。これらの条件はロービジョンエイドを行う際の視機能の評価として利用できると思われた。
加齢黄斑変性における後部硝子体剥離の発生頻度
著者: 横江志保 , 白神史雄 , 高須逸平 , 大月洋 , 尾嶋有美
ページ範囲:P.1071 - P.1074
(17-P1-23) 加齢黄斑変性(AMD)と後部硝子体剥離(PVD)との関連について検討した。対象は無治療のAMD74例(AMD群)と,性と年齢をマッチさせた対照74例(対照群)である。その結果AMD群と対照群,患眼と健眼(片眼性AMD60例),活動病巣と瘢痕病巣との間のいずれにおいてもPVDの発生率に有意差はなかった。また初診時活動性がみられ,6か月以上経過観察を行った症例44例について,PVD群とnon PVD群の間で視力変化,終診時の視力分布,活動性を持続した症例と経過観察中に瘢痕化した症例について検討したが,いずれにおいても有意差はなかった。以上より,今回の検討ではAMDと後部硝子体皮質との明らかな関連は証明されなかった。
原田病における網膜神経線維層厚の変化
著者: 大山夏子 , 国松志保 , 鈴木康之 , 大原國俊
ページ範囲:P.1075 - P.1079
(17-P2-15) 走査レーザー眼底観察鏡(NFA)を用いて,原田病における網膜神経線維層厚(NFLT)と臨床所見との関連について検討した。対象は原田病の3例6眼で,全例にステロイド大量点滴療法(prednisolone換算で200mgより漸減)を施行した。NFLTは,全周平均値(μm)において6眼中6眼では有意差はなかったが,6眼中5眼で治療による漿液性網膜剥離の改善に伴ったNFLTの減少をみた。原田病では漿液性網膜剥離と乳頭周囲浮腫による網膜神経線維層の浮種を併発しており,病状の改善がNFLTの変化として反映されると考えられた。
パーソナルコンピュータによるフリッカー視野計測
著者: 綾仁立 , 福原潤 , 田中史恵 , 湯川英一 , 西信元嗣
ページ範囲:P.1082 - P.1085
(17-P2-34) パーソナルコンピュータに点滅する視標を提示してフリッカー視野を測定する方法を開発した。20Hzの視標が固視点とその上下,左右4方向8点の計9部位に提示され,時間変調閾値を測定する。40歳台の正常被験者1眼について,極限法と恒常法で評価した。時間変調閾値は,上昇系列と下降系列で異なる値を示した。再現性のある測定値を得ることは困難であった。コンピュータの性能を向上させることで,この方式の実用化が可能になると期待される。
視神経異常を伴った両眼性第一次硝子体過形成遺残の1例
著者: 柳原順代 , 山野勝也 , 河野剛也 , 三木徳彦 , 田中あけみ , 矢野善久
ページ範囲:P.1087 - P.1090
(17-P3-3) 両眼白色瞳孔を呈した4か月男児の両眼に浅前房,虹彩後癒着,白内障,水晶体後方の白色集塊物がみられた。超音波検査で両眼硝子体腔内に腫瘍様陰影がみられ,網膜芽細胞腫が疑われたが,MRIで水晶体から連なる索状物が描出され,後に腫瘍様陰影も縮小したため,両眼性第一次硝子体過形成遺残と診断した。MRIで視交叉,視索は描出されず,軽度難聴が示唆されたため,Norrie病の散発例の可能性も考え,Norrie病責任遺伝子の異常の検索を試みたが,ほとんどの異常が報告されている部位は正常であった。本症例は遺伝歴がないため,Norrie病との診断には遺伝子異常の検出が必要であり,現在さらに検索中である。
僻地病院である五島列島富江病院と丹後半島弥栄病院の眼科外来患者の特徴
著者: 高原誠治 , 大平明弘 , 雨宮次生 , 松尾彰
ページ範囲:P.1091 - P.1094
(17P-3-9) 弥栄病院と富江病院のそれぞれの眼科外来を,1996年8月〜10月に受診した患者の臨床像を比較した。外来患者の年齢分布は,富江では70歳にピークがあったが,弥栄では1歳〜20歳までと70歳代の2峰性のピークを示した。疾患については弥栄は冨江に比べ角膜異物,先天性鼻涙管閉塞,霰粒腫,麦粒腫,眼球打撲が有意に多く,翼状片,糖尿病網膜症,結膜炎が有意に少なかった(χ2検定<O.01)。また網膜色素変性が富江で4人(人口約7千人),弥栄で3人(人口約6千人)と,ともに高率に認められた。今回この比較研究から僻地眼科受診患者にも疾患傾向があり,その地域の歴史,産業,風土,病院の性格などにより特徴付けられていることがわかった。
失明初期患者のケア
著者: 齋藤和代 , 安積淳 , 藤澤久美子 , 山本節
ページ範囲:P.1095 - P.1098
(17-P3-20) 入院中の失明初期患者に対し,家庭への社会復帰を可能にするため,さまざまな援助を行った。症例は抗リン脂質抗体症候群の37歳女性と増殖糖尿病網膜症の49歳男性であった。両者とも両眼完全失明状態で離床できなかった。定期的に訪床し,患者の失明受容の状態把握を行い,簡単な日常生活訓練および歩行訓練を行った。結果的に両者とも,家人の助けを受けながら家庭生活および簡単な社会生活が営める状態となった。医療サイドが失明初期患者とその家族に積極的に関わることは,患者の社会復帰に重要であり,医療から福祉への“つなぎ”をより確実なものにする。
帯状角膜変性症の姉妹例
著者: 北田浩美 , 小野純治 , 貞松良成 , 中安清夫 , 金井淳
ページ範囲:P.1099 - P.1102
(18-レセ1-2) 両眼に帯状角膜変性症と白内障を認めた81歳女性(症例1),78歳女性(症例2)について,角膜変性部を手術的に採取,電子顕微鏡による微細構造の観察と元素分析および,病理組織標本にてカルシウムの存在を確認した。諸検査を施行するも続発性要因は認められなかった。続発性要因を認めない帯状角膜変性症は孤発例でも稀であるが,本症例は姉妹であり,帯状角膜変性症の遺伝的発現の可能性を示唆する上でも興味深いと考えられた。
原発閉塞隅角緑内障において術後併発症として生じた悪性緑内障の3例
著者: 渡部大介 , 谷原秀信 , 本庄恵 , 稲谷大 , 本田孔士
ページ範囲:P.1103 - P.1107
(18-レセ2-16) 原発閉塞隅角緑内障眼に対する手術治療後に生じた悪性緑内障3例の臨床像とその対処をまとめた。全例で術前にレーザー虹彩切開術により瞳孔ブロックは解除されていた。きっかけとなった手術治療は,2例においてPEA+IOL+トラベクロトミー+隅角癒着解離術+虹彩切除術の同時手術,1例でPEA+IOLであった。YAGレーザー後嚢切開術および前部硝子体切開術を施行したが,器質的隅角癒着や生理的房水流出路障害のために,さらに手術治療手段が追加・併用された。
イソプロピルウノプロストンの長期併用効果の検討
著者: 小池美香子 , 山形忍 , 忍田拓哉 , 久保田久世 , 土屋裕介 , 杤久保哲男
ページ範囲:P.1109 - P.1113
(18-レセ2-22) 既存抗緑内障点眼薬使用中の緑内障症例(61例109眼)に対して,イソプロピルウノプロストン点眼薬を追加併用し,平均16.7か月までの眼圧の推移を病型,併用薬別に検討した。併用開始後,ほとんどの群で眼圧は徐々に下降し,有意な下降効果を示したが原発開放隅角緑内障,正常眼圧緑内障では12か月頃から徐々に眼圧が併用開始前に戻る傾向がみられた。特にβ遮断薬使用例に追加併用した場合にその傾向が強かった。本剤を追加薬剤として,眼圧下降効果を期待する場合,併用薬の作用機序を考慮し,その組み合わせや長期効果について留意すべきことが示唆された。
アクリルレンズ2種類の嚢内固定に関する検討
著者: 吉村正美 , 宮田章 , 泉幸子 , 石井克憲 , 稲富誠 , 小出良平
ページ範囲:P.1115 - P.1118
(18-レセ2-23) 光学径の異なる2種類のアクリル眼内レンズを各30眼に嚢内固定し,術後6か月間の経過を比較した。使用しンズは,MA60BMとMA30BAで,光学部直径は各6.0mmと5.5mm,角膜切開創幅は各4.1mmと3.8mmである。術後の前房フしア値は両者間に差がなく,前房深度は両者ともに術後1か月後に安定した。術後視力,眼内レンズの傾きと偏位に有意差はなかった。同じレンズを用いての全長と圧縮加重による全長の変化実験は,眼内レンズが固定後1か月以降に安定する所見を示した。嚢内固定したアクリル眼内レンズは,術後3か月以降に安定すると総合判定された。
眼科未治療の牽引性網膜剥離を伴う増殖糖尿病網膜症の硝子体手術成績
著者: 高橋一則 , 小林史樹 , 筑田眞
ページ範囲:P.1119 - P.1121
(18-D-19) 術前の光凝固未施行で,硝子体手術を施行した牽引性網膜剥離を伴う増殖糖尿病網膜症18例19眼についての手術成績を検討した。15眼には通常の硝子体手術を,4眼には二段階硝子体手術を行った。術前の黄斑部剥離および牽引は13眼(68%)にみられた。通常の方法では,初回手術での医原性網膜裂孔が12眼(80%),液—空気置換を13眼(87%)で必要とし,術後の増殖性硝子体網膜症(PVR)を5眼(33%)に発症したのに対し,二段階法では術中医原性裂孔,PVRの発生はなかった。また術後視力0.1以上は,通常の方法3眼(20%),二段階法3眼(75%)であった。症例によっては,二段階硝子体手術は有効である。
増殖糖尿病網膜症の硝子体手術における水晶体の処理法と術後合併症
著者: 李才源 , 佐藤幸裕 , 清水雅子 , 島田宏之
ページ範囲:P.1123 - P.1126
(18-D-21) 過去3年間に硝子体手術を行い,術後6か月以上追跡できた糖尿病網膜症299眼を検索した。171眼(57%)では水晶体を温存した。128眼(43%)では前または後嚢を残して水晶体を摘出した。両群の間に,術後の虹彩新生血管または血管新生緑内障の頻度に差はなかった。この所見は,術前に硝子体出血のみがある例,線維血管膜がある例,牽引性網膜剥離のある例で差はなかった。硝子体再出血は水晶体を温存した群で有意に多かった。硝子体腔を空気で置換した例には眼内レンズ挿入術を同時に行ったが,同様に良好な結果が得られ,前眼部合併症も少なく,有用な方法であると考えられた。
エゴグラムからみた中心性漿液性網脈絡膜症
著者: 清水敬子 , 戸張幾生 , 筒井末春
ページ範囲:P.1127 - P.1129
(18-D-23) 自我状態を評価するエゴグラム・チェック・リストを使って,中心性漿液性網脈絡膜症34例を検索した。すべて男性であり,非再発性23例,再発性11例であった。平均エゴグラムは,再発群が非再発群よりも,AC (順応した子供)が有意に高値を示した(p<0.01)。FC (自由な子供)よりもACが高いものと,ACが5点以上の場合をAC優位型と定義した。この頻度は非再発群で6例(26%),再発群で9例(82%)であり,有意差があった(p<0.01)。本症の再発性は,非再発性よりも,自我状態の歪みがあることが示された。
ICG螢光造影による加齢性黄斑変性の脈絡膜新生血管分類とその視力予後
著者: 西口和輝 , 尾花明 , 郷渡有子 , 松本宗明 , 柳原順代 , 白木邦彦 , 三木徳彦
ページ範囲:P.1131 - P.1134
(18-D501-4) フルオレセイン螢光造影で,隠れた脈絡膜新生血管を有した加齢性黄斑変性症例109例122眼(年齢50〜91歳,平均69.1±9.4歳)のインドシアニングリーン螢光造影所見を,Guyerらの分類にしたがって過螢光部の大きさから,focal spots, plaquesおよび両者が混在するcombination lesionsに分類した。各分類の頻度は,focal spots 39眼(32%),plaques 67眼(55%),combination lesions11眼(9%)で,Guyerらの報告とほぼ一致した。1年以上の自然経過群と光凝固術実施群において,各分類の視力予後,光凝固術の成績を検討したが,各分類間に統計学的な有意差はなかった。視力予後には新生血管の位置や活動性(activity)が影響した。
糖尿病黄斑浮腫に対するトリプル手術後の屈折変化
著者: 西垣士郎 , 喜田有紀 , 内田英哉 , 岩城正佳 , 舘奈保子 , 荻野誠周
ページ範囲:P.1135 - P.1137
(18-D501-16) 糖尿病黄斑浮腫29眼に対して,硝子体手術,水晶体除去,眼内レンズ挿入の同時手術(トリプル手術)を行い,予測屈折値と術後屈折値を検索した。結果は,白内障摘出と眼内レンズ挿入のみを行った70眼(単独手術)と比較した。両群とも,手術の1か月後には近視化した。以後,単独手術群では遠視化の傾向を示したが,トリプル手術群では屈折値にほとんど変化がなかった。手術後の角膜屈折力は両群間に有意な差はなかった。トリプル手術では,浮腫の軽減に伴って眼軸長が復元することが遠視化が起こらない理由であると推定された。
眼サルコイドーシス診断の問題点
著者: 秋田恵子 , 矢口智恵美 , 大原國俊 , 吾妻安良太 , 高橋卓夫 , 阿部信二 , 工藤翔二
ページ範囲:P.1139 - P.1141
(18-G402-9) 眼サルコイドーシスの確定診断群と疑診群について全身検査項目を比較検討した。対象は1996年に当眼科を初診し,眼サルコイドーシスが疑われた25例で,サルコイドーシスの診断基準により診断が確定した11例と疑診者14例である。両群の間に眼所見の内容とその頻度に差はなかった。気管支肺胞洗浄(BAL)のリンパ球比率とCD4/CD8は両群ともに上昇していた。疑診群では,血清ACE,胸部X線,CTの異常を示す症例が有意に少なかった。眼所見からサルコイドーシスが強く疑われながら確診できない疑診例が多く,眼サルコイドーシスの診断基準の再検討が必要であると考えられた。
糖尿病網膜症の進展に関与する因子としての血清リポ蛋白(a)の検討
著者: 大垣修一 , 松岡徹 , 長谷川榮一
ページ範囲:P.1143 - P.1145
(18-P1-10) 過去2年間に受診した糖尿病患者57例について血清リポ蛋白(a)を測定した。経過観察中に網膜症が進展または当初から増殖網膜症があるものを進展群とした。リポ蛋白(a)値は,進展群で非進展群よりも有意に高値であった(p=0.0001)。血清リポ蛋白(a)が高いとき,糖尿病網膜症が進展しや手ずい状態にあると結論された。
コーツ病様病変および網膜新生血管を合併した網膜色素変性症の1例
著者: 森脇光康 , 白木邦彦 , 柳原順代 , 萩原善行 , 三木徳彦
ページ範囲:P.1147 - P.1150
(18-P1-35) コーツ病様血管病変を合併した24歳,女性の網膜色素変性症の1例を報告した。両眼底に骨小体様色素沈着が血管アーケードから赤道部にかけてみられた。また下方周辺部に滲出性の網膜剥離がみられ,同部に網膜血管の拡張蛇行および硝子体中へ立ち上がる網膜新生血管がみられた。網膜電位図は記録不能,視野検査は求心性の狭窄,内部イソプターの沈下がみられた。フルオレセイン螢光造影では後期に黄斑部および乳頭周囲の網膜血管,周辺部異常血管,網膜新生血管から色素漏出がみられ,異常血管から周辺部にかけて無血管領域がみられた。異常血管の周辺部に存在する無血管野が,新生血管の発生に関与したものと考えた。
人間ドックにおける緑内障のスクリーニングテスト
著者: 宮内修 , 伊藤彰 , 佐野信昭 , 前田知里 , 渡部美博
ページ範囲:P.1151 - P.1154
(18-P3-20) 人間ドックを受診した7,242人に対して,2方法による緑内障のスクリーニングを行った。2,639人には,無散瞳眼底カメラによる眼底写真から,緑内障性の視神経乳頭の緑内障性変化または網膜神経線維層欠損を検索した。他の4,603人には,圧平式眼圧測定,隅角検査,散瞳眼底検査を行い,その1項目以上が異常のときを陽性とした。緑内障の検出率は量前群で0.19%,後群で1.15%であった。検出された緑内障は,開放隅角型が7割以上,閉塞隅角型が約2割であった。以上から,緑内障の検出には,眼底撮影だけでは不十分であり,細隙灯顕微鏡検査,眼圧測定、隅角検査,特に散瞳下の乳頭の立体観察が重要であると結論される。
糖尿病性血管新生緑内障の他眼の予後
著者: 吉川順子 , 小田仁 , 堀田一樹 , 吉野啓 , 大久保敏男 , 平形明人 , 樋田哲夫
ページ範囲:P.1155 - P.1159
(18-P3-22) 糖尿病網膜症による血管新生緑内障が片眼にある24例の経過を,平均31か月検索した。他眼には,増殖前糖尿病網膜症が4眼(17%),増殖網膜症が20眼(83%),隅角新生血管が7眼(29%),網膜光凝固の既往が16眼(67%),白内障手術の既往が7眼(29%),硝子体手術の既往が3眼(13%)にあった。1眼を除いた全眼に,初回または追加治療として汎網膜光凝固が行われた。白内障手術を8眼に,硝子体手術を9眼に行った。これら他眼には,当初から隅角新生血管があった7眼中4眼に,経過中に新生血管緑内障が生じた。当初に隅角新生血管のない17眼には血管新生緑内障の発症はなかった。片眼に血管新生緑内障があっても,汎網膜光凝固を行うことで他眼の発症を回避できると解釈された。
ぶどう膜炎患者の白内障手術に対する10L挿入術の全国アンケート調査
著者: 門田遊 , 有馬加津子 , 池田英子 , 吉村浩一 , 疋田直文 , 望月學
ページ範囲:P.1160 - P.1163
(19-レセ1-10) ぶどう膜炎患者の白内障に対する眼内レンズ(IOL)挿入術が,本邦でどの程度行われているかアンケート調査を行った。調査対象は,全国の各大学病院および主要眼科病院139施設で,1997年1月にアンケート用紙を郵送した。回答率は77%(107/139施設)であった。IOL挿入術を行っている施設は99%(96/97施設)で,適応は61%が全てのぶどう膜炎に対し行っていたが,32%はベーチェット病を除外していた。IOLの種類はPMMA,ヘパリン処理およびアクリルレンズがほぼ同等に挿入されていた。全国の多くの施設でIOL挿入が行われていることが明らかになったが,予後の検討が必要と考えられた。
未熟児網膜症瘢痕期の裂孔原性網膜剥離
著者: 川端紀穂 , 田中稔 , 小林康彦 , 篠原光太郎 , 邱彗
ページ範囲:P.1164 - P.1166
(19-c-4) 未熟児網膜症の瘢痕期に発症した網膜剥離6例を過去17年間に経験した。すべて片眼性であり,年齢は9歳から33歳,平均17歳であった。未熟児網膜症の急性期の治療が2例で行われていた。裂孔の位置は全例で耳側にあり,多発裂孔が多かった。全例に手術を行い,4例では再手術を必要とし,最終的な復位が3眼で得られた。網膜裂孔は未熟児網膜症の急性期に行われた網膜凝固が原因である例があった。初回の網膜陥凹術で復位しても,前部増殖硝子体症または多発性の新裂孔の形成がときにあり,長期の経過観察が必要である。
家族性滲出性硝子体網膜症に併発した乾癬性ぶどう膜炎の1例
著者: 菅原浩美 , 山口雅彦 , 佐藤直樹 , 中島亜子 , 山木邦比古 , 櫻木章三
ページ範囲:P.1171 - P.1175
(19レセ1-4) 58歳女性が右眼の眼痛で受診した。27年前から尋常性乾癬に罹患している。IgA腎症が11年前に生じ,その2年後に乾癬性関節炎が起こった。1年前に糖尿病が発症した。右眼には急性前部ぶどう膜炎の所見があった。HLA-B27は陰性であった。両眼に家族性滲出性硝子体網膜症があった。副腎ステロイド剤の点眼と全身投与でぶどう膜炎は7か月後に寛解した。乾癬,IgA腎症,ぶどう膜炎に共通した発症要因としてサイトカインの関与が疑われた。
連載 今月の話題
OCTの臨床応用
著者: 岸章治
ページ範囲:P.991 - P.995
検眼鏡所見が組織学的にどう対応するかを知ることは,われわれ眼科医の夢であった。OCTは、眼底の断面を光学顕微鏡切片に近い形で画像化する。OCTにより,「光学生体組織学」というべき眼底疾患学の新しい分野の開拓が可能になった。
眼の組織・病理アトラス・140
木村病
著者: 猪俣孟
ページ範囲:P.996 - P.997
木村病Kimura's diseaseは,1948年に木村,吉村,石川が「淋巴組織増生を伴う異常肉芽」として最初に報告した疾患で,若年者の顔面や頭皮に発症し,血管の増生と好酸球の浸潤を伴う腫瘤である。眼窩内,涙腺,眼瞼にも発症する(図1)。末梢血の好酸球増多および血清IgEの増加を伴うことがある。
本症は,良性の炎症性腫瘤で,中国や日本から,軟部組織の好酸球性肉芽腫eosinophilic granulomaあるいは好酸球性濾胞症eosinophilic folliculosisとして発表されてきた。1969年のWellsらの報告以来,好酸球増多を伴ったリンパ組織増生(木村病)subcutaneous angiolymphoid hyperplasia with eosino-philia (ALHE)(Kimura's disease)の名称が定着している。
眼科手術のテクニック・103
トラベクロトミー—トラベクロトームの回転に伴う併発症(その2)
著者: 寺内博夫
ページ範囲:P.1000 - P.1001
前回に引き続いてロトームの回転に伴う併発症のうち,穿刺術が必要となった広範囲のデスメ膜下血腫の1例について解説する。
図1はtrabeculotomy術後3日目に,デスメ膜下血腫の穿刺術を行った例の術中写真である(写真の下方が12時に相当する)。
他科との連携 送った患者・送られた患者・4
皮膚生検で確定診断が得られたサルコイドーシス
著者: 松浦範子 , 蒲原毅 , 高野雅彦
ページ範囲:P.1176 - P.1177
サルコイドーシスは初発症状として差明感,霧視などの眼症状を訴え,眼科を受診するケースが多いが,眼所見のみで早期診断を確定するのは困難な場合がある。今回,皮膚生検によりサルコイドーシスの確定診断が得られた1症例について述べる。
症例:64歳,女性。1997年2月頃左眼に飛蚊症が出現し,4月に近医を受診した。点眼薬を処方されたが改善せず,5月には飛蚊症が悪化した。6月から両眼充血,羞明が出現し,7月には左眼視力が低下してきたため近医を受診した。原因不明の両ぶどう膜炎で7月29日当科を初診した。初診時視力は右1.0(1.2×+0.37D cyl−1.25DAx65°),左0.8(n.c.)であった。豚脂様角膜後面沈着物が両眼にみられ,前房にはフレア1+,細胞2+がみられた。ケッペ結節は右眼の2時,5時方向に,また左眼には虹彩全周にみられた。隅角にはテント状周辺虹彩前癒着がみられた。両眼底には動脈のみの白鞘化,黄白色の滲出斑,硝子体混濁がみられた(図1)。
今月の表紙
網膜色素条症(angioid streaks)
著者: 宇山昌延
ページ範囲:P.999 - P.999
全身の弾性線維,膠原線維を侵す系統疾患の部分症状が眼底にあらわれる。Bruch膜の主構成要素は弾性線維と膠原線維であるから,それが変性する結果,Bruch膜に断裂や亀裂を生じる。その部の上の網膜色素上皮は萎縮したり反応性に増殖する。それが眼底では視神経乳頭縁から稲妻状に走る黒色や黄白色の線として見え,色素線条と呼ばれる。赤道部の網膜は黒ずんだ顆粒状を示し,梨子地状眼底を示すことが多い。身体では屈伸運動が多い部の皮膚(側頸部,肘窩,膝窩など)がなめし皮状に見え,弾力線維性仮性黄色腫になる。全身症状がそろうとGranblad-Strandberg症候群と呼ばれる。色素線条が中心窩に延びると脈絡膜新生血管を生じやすく,加齢黄斑変性様の病変を生じる。また,鈍傷を受けると脈絡膜から網膜下へ大量の出血を生じやすい。
臨床報告
副腎皮質ステロイド薬投与後に生じた多発性後極部網膜色素上皮症の1症例
著者: 高嶋隆行 , 大野京子 , 森嶋直人
ページ範囲:P.1179 - P.1184
55歳の女性が健康診断で尿蛋白を発見され,腎生検でIgA腎症と診断された。ステロイド治療開始前の診察では,矯正視力は良好で,網膜色素上皮剥離が両眼に散在していた。プレドニゾロン内服を1日量40mgで開始した。その2週後に視力低下を自覚した。両眼に網膜色素上皮の拡大と漿液性網膜剥離が発見された。クリプトン赤による光凝固は無効であった。プレドニゾロンを漸減し,投与開始から10週後に1日量が10mgになった頃から視力が改善し,網膜剥離が軽減した。本症はステロイド薬の全身投与で誘発された多発性後極部網膜色素上皮症であると考えられた。
硝子体手術後の眼内レンズ二次挿入
著者: 大山芳子 , 平形明人 , 堀田一樹 , 篠田啓 , 大山光子 , 三木大二郎 , 山岡青女 , 樋田哲夫
ページ範囲:P.1185 - P.1189
硝子体手術後の無水晶体眼に対し眼内レンズ二次挿入術を行った,10例10眼の術中・術後合併症について検討した。原疾患は,増殖糖尿病網膜症5眼,増殖性硝子体網膜症1眼,裂孔原性網膜剥離3眼(穿孔性眼外傷後2眼,巨大裂孔網膜剥離1眼),黄斑円孔網膜剥離1眼であった。眼内レンズ二次挿入後,裂孔原性網膜剥離2眼,黄斑円孔網膜剥離1眼に網膜再剥離が生じた。このうち2眼は毛様溝縫着例であった。無硝子体眼では眼球の虚脱による変形を生じやすく,特に網膜剥離術後眼では,裂孔再開通による網膜再剥離の誘引となる可能性が示唆された。
黄斑部硝子体手術の合併症
著者: 後藤真里 , 舘野静香 , 輪島良平 , 白尾裕
ページ範囲:P.1190 - P.1194
過去20か月間に行った黄斑疾患に対する硝子体手術92眼の合併症を検索した。特発性黄斑円孔65眼での合併症は,術中の周辺部網膜裂孔1脹,術後の裂孔原性網膜剥離3眼,術後の脈絡膜出血と硝子体出血各1眼,黄斑円孔の再発1眼,周辺視野欠損3眼であった。嚢胞様黄斑浮腫5眼では,術後に裂孔原性網膜剥離が2眼に生じた。黄斑下血腫7眼では,網膜色素上皮欠損が3眼,裂孔原性網膜剥離と網膜静脈分枝閉塞症が各1眼に生じた。黄斑前膜13眼と外傷性黄斑円孔2眼では硝子体手術による合併症はなかった。黄斑疾患に対する硝子体手術では,医原性網膜裂孔を作らないような配慮が必要であり,術前と術中に硝子体基底部を十分に検索することが望まれる。黄斑円孔への手術後の視野欠損は,術中に後部硝子体剥離を作成することとは無関係であった。
Peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy(PEHCR)の10例
著者: 吉武良浩 , 本松薫 , 中村多賀雄 , 上野曉史 , 石橋達朗
ページ範囲:P.1195 - P.1199
われわれは過去6年間に10例のperipheral exudative hemorrhagic choriOretinopathy (PEHCR)を経験した。本症は,黄斑外の網膜下または色素上皮下に滲出や出血が生じる高齢者の疾患であり,加齢黄斑変性症に類似する。男性7例,女性3例であり,すべて片眼性であった。年齢は60歳から80歳,平均71歳であった。7眼では硝子体出血が初発症状であり,硝子体手術後に診断が確定した。病巣は4眼で耳側周辺部にあり,4眼に加齢黄斑変性が併発していた。新生血管は,フルオレセイン螢光造影では証明できず,インドシアニングリーン螢光造影で2眼にこれが検出された。本症が硝子体出血の原因になりうることが留意されるべきである。
糖尿病硝子体手術後の残存網膜剥離が再出血に与える影響
著者: 小泉閑 , 池田恒彦 , 澤浩 , 中村富子 , 石田美幸 , 木下茂
ページ範囲:P.1201 - P.1205
過去34か月間に硝子体手術を行った増殖糖尿病網膜症206眼のうち,黄斑外牽引性網膜剥離が49眼にあった。これに対して,手術終了時に気圧伸展網膜復位術を28眼(強制復位群)に行い,21眼では硝子体腔内に灌流液が充満したままとした(自然復位群)。術後に硝子体再出血が11眼にあった。それぞれ28眼中5眼(18%)と21眼中6眼(29%)であった。49眼のうち38眼では,術前の網膜剥離が血管アーケードに囲まれる面積の半分以上を占めていた。この38眼中,術後再出血は強制復位群27眼中5眼(19%)と自然復位群11眼中6眼(55%)に起こり,両群間に有意差があった(p<0.05)。広範な牽引性網膜剥離のある増殖糖尿病網膜症への硝子体手術では,気圧伸展網膜復位術を行うことが望ましいと結論される。
基本情報
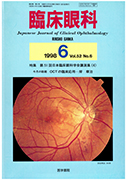
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
