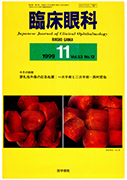文献詳細
連載 眼の組織・病理アトラス・157
文献概要
房水は前房隅角を経由して眼外へ流出する。しかし隅角陥凹angle recessが十分に開いていないと,房水流出障害が起こりやすい。隅角発育異常緑内障では,隅角陥凹の発達が悪く,そのために隅角鏡で毛様体帯の幅が狭いか,もしくは全く見えない。これは線維柱帯の発育も不十分であることを意味する。閉塞隅角緑内障では,隅角隅凹の部分だけが閉塞していても房水の流出障害を生じる。つまり,正常な房水流出には隅角隅凹がよく発育し,十分に開放していることが必要である。
よく発達した前房隅角では,線維柱帯はシュワルベ線から隅角陥凹まで広がっている。組織切片上での線維柱帯の長さは約1mmである。それを前部線維柱帯と後部線維柱帯に折半すると,シュレム管は後部線維柱帯側に存在する(図1)。シュレム管腔の幅は0.3〜0.4mmである。隅角陥凹の底部には毛様体筋の先端部が位置している。このような前房隅角の組織構築から,後部線維柱帯が経シュレム管房水流出路conventional routes of aqueous humor outflowとしても,また経ぶどう膜強膜房水流出路uveoscleral routes of aqueous humor outflowとしても重要な意義をもっていることが推測される。
よく発達した前房隅角では,線維柱帯はシュワルベ線から隅角陥凹まで広がっている。組織切片上での線維柱帯の長さは約1mmである。それを前部線維柱帯と後部線維柱帯に折半すると,シュレム管は後部線維柱帯側に存在する(図1)。シュレム管腔の幅は0.3〜0.4mmである。隅角陥凹の底部には毛様体筋の先端部が位置している。このような前房隅角の組織構築から,後部線維柱帯が経シュレム管房水流出路conventional routes of aqueous humor outflowとしても,また経ぶどう膜強膜房水流出路uveoscleral routes of aqueous humor outflowとしても重要な意義をもっていることが推測される。
掲載誌情報