(B9-1-17) 網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の急性期および陳旧期の症例に対して,光干渉断層計(OCT)で黄斑部網膜を検索し,その形態的変化について検討した。急性期の中心窩網膜厚は377±192μm(平均±標準偏差)で,視力と負の相関を示した(r=0.57,p<0.01)。BRVOの急性期では,網膜浮腫の形態から網膜外層型,網膜全層型の2型に分けられ,両者は異なる経過で推移することがわかった。陳旧期の出血側網膜厚は健側,正常者に比べ有意に減少していたが,中心窩の厚さに有意差はなかった。OCTによる黄斑部検査および網膜厚の定量化は,BRVOの病態を把握ずる上で有用な検査と考えられた。
雑誌目次
臨床眼科53巻6号
1999年06月発行
雑誌目次
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
学会原著
Heidelberg Retina Tomograph,Heidelberg Retina Flowmeterによる観察を試みた転移性脈絡膜腫瘍の1例
著者: 小田切亜弥 , 山崎芳夫
ページ範囲:P.1113 - P.1116
(P1-2-28) 筆者らは,肺原発の転移性脈絡膜腫瘍の1例に対しHeidelberg Retina Tomograph (HRT)およびHeidelberg Retina Flowmeter (HRF)を用いて,腫瘍の形状測定および組織血流測定を行った。その結果,HRTでは腫瘍の隆起範囲および表面の凹凸の様子がよく観察され,3か月後には腫瘍が増大していることが観察された。
また,HRFを用いた腫瘍部の組織血流測定では,flow,volume, velocityとも他眼の対応する網膜部位に比べ減少していた。
網膜色素上皮裂孔の光干渉断層計所見
著者: 福地俊雄 , 高橋寛二 , 伊田宜史 , 永井由巳 , 岩下憲四郎 , 宇山昌延
ページ範囲:P.1117 - P.1123
(B2-2-15) 網膜色素上皮裂孔の4症例を光干渉断層計optical coherence tomography (OCT)で観察した。発病早期には.網膜色素上皮の裂孔縁には網膜色素上皮による高反射層の断裂があり,色素上皮の欠損部は網膜色素上皮による高反射層が欠損し,その後方の脈絡膜反射は増強していた。また,色素上皮が翻転した弁の部では極めて高い反射があり,その後方の脈絡膜反射は消失していた。発病晩期には網膜色素上皮裂孔は瘢痕化したが,色素上皮の裂孔縁および弁の部は,健常な色素上皮の高反射層と同じ高反射を示して境界不鮮明であった。色素上皮の欠損していた部位は色素上皮による高反射はなく,脈絡膜反射が増強していた。網膜色素上皮裂孔による網膜色素上皮の病的変化がOCTにより断面像として明瞭に観察された。
特発性ポリープ状脈絡膜血管症のOCT所見
著者: 尾辻剛 , 福島伊知郎 , 高橋寛二 , 和田光正 , 桑原敦子 , 南部裕之 , 木本高志 , 岩下憲四郎 , 松原孝 , 松永裕史 , 宇山昌延
ページ範囲:P.1125 - P.1130
(B2-2-10) インドシアニングリーン螢光眼底造影(ICG造影)によって,特発性ポリープ状脈絡膜血管症と診断した症例9例10眼にOptical Coherence Tomography (OCT)検査を行い,異常血管の存在部位を検討した。ICG造影で車軸状に拡がる異常血管の先端がポリープ状に拡張した部をOCTで観察すると,網膜色素上皮がドーム状に隆起し,その下には中等度の反射または小さい結節状の隆起がみられ,網膜色素上皮下にポリープ状に拡張した血管が存在すると思われた。OCT所見からは,本症でみられるポリープ状の異常血管はBruch膜上で網膜色素上皮下にポリープ状に拡大した脈絡膜新生血管と思われ,本疾患は滲出性加齢黄斑変性の特殊型と考えられる。
光干渉断層計による網膜神経線維層厚と緑内障性視野障害の関係
著者: 尾﨏雅博 , 立花和也 , 後藤比奈子 , 堀越紀子 , 岡野正
ページ範囲:P.1132 - P.1138
(B5-2-20) 光干渉断層計(OCT)を用いて緑内障眼における乳頭周囲網膜神経線維層(RNFL)厚の解析を行い,視野との相関性について検討した。対象は高眼圧症患者4例4眼と緑内障患者31例47眼で,各々の症例にOCTで視神経乳頭周辺を円周状にスキャンし,動的および静的視野計測を行った。湖崎分類の平均RNFL厚の比較では,初期に差がなく,中期で有意な減少を示したが,Aulhorn分類では病期が進むごとになだらかな減少を示した。静的視野計測で得られたmean deviation(mean defect)とRNFL厚との間には有意な相関性がみられた(r=0.73〜0.88,p<0.0001)。早期の視野変化を示す緑内障眼では,blue-on-yellow視野計やslze Iの視標を用いた白色視野計の結果とOCT所見が補助診断に有用であった。
Optical coherence tomographyによる半導体レーザー誤照射の網脈絡膜障害の描出
著者: 樺澤昌 , 阿部友厚 , 安斎要 , 森圭介 , 村山耕一郎 , 米谷新
ページ範囲:P.1141 - P.1144
(P1-2-32) 半導体レーザーを開発中,右眼に誤照射された45歳,男性の1例を経験した。レーザーの波長は810nmで,出力は1.5Wであった。受傷直後より中心上方に暗点を自覚し,2日後の初診時視力は1.2であった。黄斑部直下に量輪を伴う白色斑があり,フルオレセインおよびインドシアニングリーン螢光造影検査法では白色斑に一致して螢光漏出があった。光干渉断層計(OCT)で,中心窩の網膜外層に,脈絡膜毛細血管板に及ぶ限局性の小病変が高輝度の反射で描出され,熱作用による障害が主体であると理解された。視力は良好であったが,中心窩の視細胞および色素上皮が広く障害されていることが明らかであった。
重症太陽性網膜炎の1例
著者: 林振民 , 林麗如 , 阿部恵子 , 筑田眞
ページ範囲:P.1145 - P.1149
(P1-3-1) 31歳の女性が,晴天の海岸で長時間読書したあとに左眼の変視症を自覚した。翌日他医に眼底出血を指摘され,その1か月後に受診した。左眼矯正視力は0.6であり作中心窩に黄灰色の小点があり,網膜出血,網膜下出血と光凝固斑後に好発する白色斑を伴い,これらを含む範囲に漿液性色素上皮剥離があった。太陽性網膜炎と診断した。右眼は正常であった。フルオレセイン螢光造影で,網膜神経上皮下の色素漏出と小点部の過螢光があり,走査レーザー検眼鏡の波長780nm単色光で,小点部は周囲の網膜よりも高輝度を呈した。以上の所見から,左眼の障害部位は網膜色素上皮層と脈絡膜にあると解釈した。
両眼同時白内障手術の検討
著者: 濱田麻美 , 清水公也
ページ範囲:P.1151 - P.1153
(B2-1-18) 両眼同時白内障手術の安全性と問題点を,自験例79例について検討した。全例に他の眼合併症はなく,年齢は45〜92歳,平均76歳であった。点眼麻酔による耳側角膜小切開手術を行い.折り曲げ型眼内レンズを挿入した。重篤な合併症の発生はなく,術後視力と術後炎症は片眼手術とほぼ差がなく,良好な結果が得られた。両眼同時白内障手術は,今後の白内障手術の選択肢のひとつになり得ると思われた。
超音波白内障手術におけるチップの評価
著者: 嶋浩子 , 天野浩之 , 菅敬文 , 山口智美
ページ範囲:P.1155 - P.1159
(B2-1-21) 超音波白内障手術の際のT超音波時間と角膜内皮細胞減少率の関係を三種類のチップ(NOrma30゜/Micro 30゜/Mackool30゜)を用いて比較検討した。対象は215例295眼の白内障患者である。Mackoolでは超音波時間がNormalより同等または増加したため,核破砕効率が必ずしも上がらなかった。一方,MackooはNormal, Microと比較して内皮細胞減少率は最小であった。これは,ポリイミド製インナースリーブの低い熱伝導率が創口熱傷を防いだことと,深い前房から得られる広い作業域が飛び散った核片による内皮の損傷を抑制したためと考えられた。
ヘッドマウントディスプレイ視聴とブラウン管視聴の問題点—第1報
著者: 吉村正美 , 朝広千博 , 小池昇 , 高橋春男
ページ範囲:P.1161 - P.1164
(B5-1-16) 健康な成人10名にヘッドマウントディスプレイ(HMD)とブラウン管を使って同じゲームを視聴させ,船酔いなどの症状が発現するかを検討し,その前後で視覚系と平衡感覚系を検査した。屈折はゲーム前後でHMDでは有意差があったが,変化量は小さかった。他の項目については,臨床的に問題になる所見はなかった。頭部位置の変動は,ゲーム中は巧拙に関連すると思われる被験者ごとの傾向を示した。ゲーム前後の比較では,ゲーム中の影響は残らず,大きな変化はなかった。バーチャルリアリティでの船酔いに似た現象はなく,HMDとブラウン管の間に差異はなかった。
眼科領域におけるデータ交換規約試案
著者: 川畑善之 , 内田洋人 , 直井信久 , 吉原博幸
ページ範囲:P.1165 - P.1170
(B5-1-18) 電子的な医療情報交換規約として,先日Medical Markup Language (以下,MML)および,Medical Record Image Text-Information eXchange(以下,MERIT−9と略す)が策定された。これらは汎用性を持たせる目的と策定されたばかりの規格であるため,各専門分野における細かいデータの表現方法については触れられていない。今回筆者らは,MMLに準拠した形で,細かいフォーマットの記述方式について試案を作成し,Extension for SPecial feild(ESP)と名付けた。また,これをさらに拡張する形で,眼科領域における医療情報交換規約を一部試作してみた。このような,より細かいデータの表現方法を策定することで他の医療施設のデータを電子化カルテに取り込んだり,複数施設間での電子化カルテの共有化が実現するものと考え,眼科分野向けの標準フォーマットの策定を呼びかけるものである。
網膜芽細胞腫におけるtransforming growth factor-β受容体の発現
著者: 辻英貴 , 堀江公仁子 , 小島孚允 , 山下英俊
ページ範囲:P.1171 - P.1174
(B6-1-2) 網膜芽細胞腫においてtransforming growth factor-β(TGF-β)による増殖抑制効果が喪失していることが報告されている。そのメカニズムについて検討するためTGF-βI型受容体,TGF-βII型受容体の蛋白質レベルでの発現を,網膜芽細胞腫細胞株(WERI),および実際の網膜芽細胞腫の摘出眼を用いて免疫組織学的に観察した。網膜芽細胞腫細胞株では,抗ヒトTGF-βI型受容体抗体にて蛋白質レベルの発現が観察されたが,抗ヒトTGF-βII型受容体抗体では発現はみられなかった。6例の網膜芽細胞腫摘出眼においては,抗ヒトTGF-βII型受容体抗体にて腫瘍部は染色されなかった。腫瘍部のTGF-βII型受容体の発現低下が腫瘍のTGF-β感受性低下に関与ずる可能性が示唆された。
Frequency doubling perimetryに与える近視の影響
著者: 伊藤彰 , 川端秀仁 , 藤本尚也 , 安達恵美子
ページ範囲:P.1175 - P.1179
要約 目的:新しい緑内障スクリーナーfrequency doubling perimetry(FDP)の測定結果に与える近視の影響を検討した。
対象と方法:対象は,視力良好な正視または近視の40例40眼(屈折異常の平均−4,19D,0〜−12D,平均26.9歳,23〜34歳)である。いずれも緑内障の合併はない。FDP C−20プログラム,およびハンフリー視野計Humphrey Field Analyze(HFA)30-2プログラムwhite on white perimetryを行い,結果の解析を行った。
結果:HFAのmean devlation(MD),平均感度は近視が強い群ほど低下したが,FDPのMD, patternstandard deviation(PSD),平均感度は屈折度による差は認められなかった。
結論:緑内障には近視の合併も多い。FDPに際し近視の影響を考慮に入れる必要がないことが明らかとなった。
加齢黄斑変性の中心窩脈絡膜新生血管全体のレーザー光凝固の視力予後
著者: 森隆三郎 , 湯沢美都子
ページ範囲:P.1180 - P.1184
(B9-1-6) 加齢黄斑変性の中心窩脈絡膜新生血管choroidal neovascularization (CNV)全体の光凝固を施行した66例69眼のT経過と視力の推移について検討した。凝固成功のまま推移した53眼のうち,0.1以上の視力を維持したものが25眼47%であり,凝固前と同等あるいはそれ以上の視力を得たものは42眼80%であった。Atrophic creepは大多数にみられたが,視力低下の原因にはなりにくかった。中心窩CNV閉塞後の再発は,14眼のうち凝固前と同等,あるいはそれ以上の視力を得ていたものは10眼71%であった。中心窩CNVにおいて視力の改善が期待できない症例には,凝固前の視力を維持できる可能性が高いCNV全体の光凝固は有用な治療法と考えた。
緑内障トリプル手術の術式と手術成績の検討
著者: 山口靖子 , 飯島建之 , 吉野啓 , 杉谷篤彦
ページ範囲:P.1185 - P.1188
(C4-1-18) 同一強膜創から緑内障・白内障のトリプル手術を行い,術後6か月以上経過観察できたトラベクレクトミー(レクトミー)併用群12例14眼,トラベクロトミー(ロトミー)併用群23例30眼に対し,両群間の術後成績を比較検討した。最終眼圧はレクトミー群で12.6±2.6mmHg,ロトミー群で13.3±2.6mmHgであった。ロトミー群では術後14日以内の一過性眼圧上昇が有意にみられ,レクトミー群では術後1か月以降に眼圧が上昇する症例があった。両群とも時期は異なるが,眼圧上昇のリスクを認めた。浅前房,脈絡膜剥離などの術後合併症はレクトミー群に多くみられた。ロトミー群は合併症も少なくレクトミー群と比べても最終眼圧に差がないことから,トリプル手術を行う場合は,進行例にもロトミー手術の適応が拡大できる可能性が示唆された。
アトピー性皮膚炎に伴う硝子体基底部裂孔に対する経結膜冷凍凝固術の効果
著者: 野田康雄 , 出田秀尚 , 山本悟 , 奥山美智子 , 熊丸茂
ページ範囲:P.1189 - P.1193
(B2-2-32) 過去17年間に,アトピー性皮膚炎に併発した硝子体基底部の網膜裂孔14眼に対して経結膜冷凍凝固術を行った。網膜剥離は,ないか,またはごく狭い範囲に限局していた。網膜裂孔は12眼(86%)で瘢痕化し,平均26か月の観察期間中,網膜剥離は拡大しなかった。アトピー性皮膚炎に併発した硝子体基底部の網膜裂孔には,網膜剥離があっても剥離部全体に冷凍凝固を加えれば剥離を拡大させない効果があると結論される。アトピー性皮膚炎では他の部位に裂孔が生じることがあるので,眼部の自己打撲をしないよう指導すべきである。
偽落屑症候群の隅角所見と緑内障病型
著者: 川上淳子 , 永田誠 , 松村美代
ページ範囲:P.1195 - P.1198
(B2-2-31) 偽落屑症候群213例293眼の隅角所見と緑内障病型を検討した。広隅角237眼(80.9%),狭隅角22眼(7.5%),合わせて開放隅角259眼(88.4%),閉塞隅角34眼(11.6%)であった。開放隅角緑内障は111眼(37.9%)に,閉塞隅角緑内障は34眼(11.6%)にみられた。閉塞隅角緑内障のうち混合型緑内障が13眼(38.2%)にみられた。偽落屑症候群の緑内障は,水晶体嚢性緑内障としての開放隅角緑内障だけでなく閉塞隅角緑内障もみられ,そのうちの1/3は混合型緑内障であることが明らかとなった。
抗緑内障点眼薬の単剤あるいは2剤併用の長期投与による角膜障害の出現頻度
著者: 高橋奈美子 , 籏福みどり , 西村朋子 , 細部泰雄 , 田澤豊
ページ範囲:P.1199 - P.1203
(B2-2-5) 同一薬剤を28か月間継続して点眼している緑内障154眼につき,角膜上皮障害の頻度を調査した。全例を2か月ごとに検索した。使用した薬剤は,イソプロピルウノプロストン,カルテオロール,チモロールの3種類で,単独投与群と2剤併用群に分けて検討した。角膜上皮障害の頻度は,単独投与群で12.9〜32.5%.併用群で40.0〜66.7%であり,併用群で多かった。上皮障害は同一症例で繰り返して起こる傾向があり,個々の症例での眼表面の状態がこれに関係していることが推察された。
Size Iの視標を用いたwhite-on-white視野計測とblue-on-yellow視野計測の比較
著者: 高田眞智子 , 尾﨏雅博 , 後藤比奈子 , 堀越紀子 , 岡野正
ページ範囲:P.1204 - P.1212
(B9-2-10) 早期緑内障においてwhite-on-white(W/W)視野計測(size I)とblue-on-yellow(B/Y)視野計測における異常検出感度を比較した。対象は,正常者21例21眼,高眼圧症患者12例19眼,視神経乳頭陥凹拡大を認める疑緑内障患者30例42眼,早期緑内障患者15例18眼である。全症例にW/W視野計測(size l)およびB/Y視野計測を,ハンフリー視野計の24-2プログラムを用いて行った。両視野計では,早期緑内障および疑緑内障群の平均網膜感度が正常者群より有意な感度低下を示したが,B/Y視野計に比べW/W視野計(size I)による計測で,より有意差が顕著であった。また,B/Y視野計よりW/W(size I)視野計で計測したほうが,正常者群に対する早期緑内障および疑緑内障群の確率シンボルと異常検出点における有意差がより大きくなった。W/W視野計測(size I),B/Y視野計測の短期変動(SF)は全般的に大きくなったが,W/W視野(size I)では早期緑内障群が正常者群より有意に大きかった。W/W視野計測(size I)はB/Y視野計測に比べ,早期緑内障の検出感度が高い可能性が示唆された。
広範囲の角膜潰瘍に対する強角膜移植術
著者: 榎美穂 , 近間泰一郎 , 西田輝夫
ページ範囲:P.1213 - P.1217
(C2-3-5) 通常の全層角膜移植術が不可能な広範囲の角膜潰瘍3症例に対して,強角膜を一塊として縫着する強角膜移植術を施行した。症例はいずれも潰瘍発症から長期間を経過した,穿孔か角膜ブドウ腫を伴った感染性角膜潰瘍で,本手術により視力は手動弁以下から最良矯正視力0.4から0.8までに改善した。眼圧は2例で術後上昇し,薬物治療を必要とした。フォトケラトスコープではおおむね良好な角膜形状を呈しており,また術後の内皮細胞密度は2,300から2,800cells/mm2を保っていた。シクロスポリンの投与により3症例とも現在まで拒絶反応は認めない。強角膜移植術は広範囲の角膜潰瘍に対する,視力回復を目的とした前眼部再建術の選択肢の1つとなり得る。
Photorefractive keratectomy後の自覚的屈折値と他覚的屈折値のずれ
著者: 高橋百合 , 三橋環 , 岡本加奈子 , 佐々木秀次 , 北澤世志博 , 所敬
ページ範囲:P.1218 - P.1222
(C4-2-18) Photorefractive keratectomy(PRK)術後1年の37名58眼を対象に自覚的屈折値と他覚的屈折値のずれの程度および矯正量との関係について検討した。術後1年のずれの程度(他覚的屈折値—自覚的屈折値)は,球面度数−1.42±1.15D,円柱度数−0.49±0.52Dであり,球面度数,円柱度数とも他覚的屈折値は自覚的屈折値に比べ近視側に測定された。術後の球面度数のずれと矯正量との間に有意な相関(p<0.0001)があった。球面度数のずれの原因は,矯正量が大きいほど角膜形状が非球面化するためであり,屈折矯正手術後の視力検査においては注意が必要であると思われた。
全層角膜移植手術成績
著者: 柳井亮二 , 近間泰一郎 , 西田輝夫
ページ範囲:P.1223 - P.1228
(C2-3-8) 1996年4月から1997年3月までに山口大学眼科で行った全層角膜移植術41例41眼につき手術成績を検討した。原疾患は水庖性角膜症18眼,角膜白斑8眼,円錐角膜6眼,角膜穿孔6眼,角膜潰瘍2眼,角膜熱傷1眼であった。全症例の角膜透明治癒率は85%(35/41眼)で,疾患別透明治癒率は水疱性角膜症89%(16/18眼),角膜白斑75%(6/8眼),円錐角膜100%(6/6眼),角膜穿孔67%(4/6眼)であった。当科における前回の報告(1993〜1996年)に比べ,水疱性角膜症に対する透明治癒率が改善されていた。この理由として,強角膜片保存角膜を全例使用.ドナー角膜内皮細胞の十分な術前検討,定時手術の増加,手術時間の短縮,手術時の角膜内皮細胞の保護などが考えられた。術後合併症は,拒絶反応5眼,遷延性角膜上皮欠損4眼,続発緑内障3眼,真菌感染症1眼であった。術前から涙液減少がみられた症例で有意に遷延性角膜上皮欠損を多く発症していた。透明治癒が得られなかった症例では,拒絶反応,グラフト機能不全および真菌感染症がみられた。術後最高矯正視力は85%(35/41眼)で改善されていた。
硝子体手術前後の視神経乳頭形状の変化
著者: 大橋啓一 , 春日勇三 , 羽田成彦 , 真鍋伸一 , 宮原晋介 , 山川良治
ページ範囲:P.1229 - P.1232
(C4-3-5) 硝子体手術を施行した/7眼(黄斑円孔9眼,網膜上膜5眼,糖尿病黄斑浮腫2眼,白内障術後の黄斑浮腫1眼)で術前,術後にHeidelberg Retina Tomographを用いて乳頭形状を記録重比較し,術中の硝子体操作時間,液ガス置換の有無や術中の灌流圧などとの関係を検討した。硝子体操作時間が長く,液ガス置換を行い,術中の灌流圧が高いほど,乳頭に長期間持続する変化を認めた。乳頭体積の変化の原因として,手術操作による神経線維の浮腫,乳頭部での毛細血管床の傷害による血漿成分の漏出などが考えられた。乳頭深度の増大の原因としては眼球壁の変形,神経線維に対する物理的傷害などが考えられた。硝子体手術時には可能な限り操作時間を短く作灌流圧を低く保つことが必要である。
特発性脈絡膜皺襞におけるインドシアニングリーン螢光眼底造影検査所見
著者: 蓮村直 , 米村尚子 , 平田憲 , 村田恭啓 , 根木昭
ページ範囲:P.1233 - P.1236
(P1-1-2) フルオレセイン,インドシアニングリーン同時螢光眼底造影検査(fluorescein angiography;FAindocyanine green angiography:IA)を行った特発性脈絡膜皺襞の2症例を報告した。症例1は57歳男性で,IAにおいて後極部に細かく蛇行し粗い網状を呈する脈絡膜血管異常所見がみられた。症例は63歳男性で,IAにて皺襞に一致した過螢光以外に特に異常をみなかった。今まで特発性脈絡膜綴皺襞と診断されていた症例の中に,症例1のような脈絡膜血管病変を有している可能性があり,今後とも討していく必要がある。
涙嚢鼻腔吻合術鼻外法術後の吻合孔の内視鏡所見
著者: 宮久保純子 , 宮久保寛
ページ範囲:P.1237 - P.1241
(P3-2-17) 涙嚢鼻腔吻合術(DCR)において,侵襲を少なくするためには骨窓を小さく作る必要があるが,小さすぎる胃窓は吻合孔の再閉塞の危険がある。筆者らは慢性涙嚢炎の10例10側にone flap DCRを行い,できた吻合孔を鼻腔内視鏡を使用して経時的に観察した。骨窓は平均9×10mmのものを形成し,ヌンチャク型シリコーンチューブ(N-ST)とスポンゼルまたはゼルフォームを留置した。術後1〜5か月ごろまでに吻合孔は収縮し,2例では吻合孔の中に肉芽がみられた。術中骨窓が前篩骨洞に開放した1例は再閉塞したが,残りの9例は術後平均7か月目には平均1.4×1.8mm径の円形または楕円形の吻合孔となり固定し,これらは良好な涙導機能を有した。鼻腔内視鏡の観察により,9×10mm径の骨窓を形成するDCRで,形態的にも十分な大きさの吻合孔を形成できることが明らかになった。
ウルトラパルス方式の炭酸ガスレーザーを用いた眼瞼手術
著者: 平吹佳苗 , 新美勝彦 , 那波佳月子
ページ範囲:P.1242 - P.1245
(C2-1-1) ウルトラパルス方式の炭酸ガスレーザーを使用して眼瞼手術を行った。症例は,老人性眼瞼皮膚弛緩症25眼,眼瞼下垂2眼,下眼瞼内反症2眼である。年齢は50〜79歳,平均69歳であった。レーザーは,皮膚切開,皮下組織の剥離と瞼板前組織の切除に使用した。挟瞼器を使わなくても出血量が少なく,予定線での正確な切開が可能で,創傷治癒も良好であった。
アクリルソフト眼内レンズの挿入時にみられるトラブルとその処置—挿入時合併症とその対応
著者: 矢那瀬淳一 , 栗原秀行 , 山田慎 , 譲原大輔 , 高瀬正郎 , 正田美穂 , 眞舘幸子 , 大川みどり , 荻野誠周
ページ範囲:P.1246 - P.1250
(C1-2-26) 過去29か月間にアクリルソフト眼内レンズを挿入した1,498眼の自検例を検索した。27眼(1.8%)になにかの術中の障害があった。この大部分は挿入手技に起因するものであり,光学部が開かない事例が18眼(67%)と最も多かった。挿入時の障害が術後の視機能に影響を与えたものはなかった。挿入手技を適切に選び,これに習熟することで挿入時の障害を回避することが可能であると考えられた。
糖尿病網膜症術後の失明例
著者: 松本美保 , 白川慎爾 , 庄司治代 , 佐藤美菜子 , 細川理恵 , 藤田哲
ページ範囲:P.1251 - P.1255
(P1-3-13) 1997年の1年間に硝子体手術を行った1/3眼106例を検討した。原因疾患は,糖尿病網膜症53眼,網膜剥離32眼,黄斑円孔9眼,網膜上膜6眼,網膜中心静脈閉塞症4眼,その他7眼であった。2段階以上の視力改善が78眼(69%),不変が28眼(25%),2段階以上の悪化が4眼(4%),失明が3眼(3%)であった。視力低下例は網膜剥離4眼であり,失明は糖尿病網膜症3眼であった。網膜剥離では最終的に視力が回復した。糖尿病網膜症での失明は不可逆性であり,その原因は,前部増殖性硝子体網膜症と血管新生緑内障であった。
脈絡膜コロボーマに網膜分離症様変化を合併した黄斑網膜剥離の治療経験
著者: 長野悦子 , 平形明人 , 忍足和浩 , 樋田哲夫
ページ範囲:P.1261 - P.1263
(P1-1-8) 脈絡膜コロボーマに網膜分離症様の稀な形を合併した黄斑網膜剥離の治療経過について報告した。症例は22歳,男性。両眼脈絡膜コロボーマの診断を受けていたが,1か月前からの変視症を主訴に受診した。初診時の左眼矯正視力は0.7で,脈絡膜コロボーマに接する円形の網膜分離症様の漿液性剥離と,その内部に外層網膜剥離が存在した。硝子体の液化は著明であった。視力低下が進行し,硝子体手術,意図的後部硝子体剥離作成,ガスタンポナーデを施行した。術後,視力は1.2に回復し,網膜分離症様所見と黄斑網膜剥離も消失したことにより,硝子体の牽引が病態に関与していると考えられた。
両眼の緑内障手術後に生じたuveal effusionの1例
著者: 成瀬睦子 , 島田宏之 , 春山美穂 , 浅山展也 , 川村昭之 , 湯沢美都子
ページ範囲:P.1265 - P.1268
(P1-1-9) 66歳女性の両眼の慢性閉塞隅角緑内障と白内障手術に対して,超音波水晶体乳化吸引術,眼内レンズ挿入術,線維柱帯切除術が他医で行われた。3週後に脈絡膜剥離が生じ,脈絡膜下液排液後に再発して,手術から6か月後に紹介され受診した。両眼に強膜切除術を行い,網膜剥離と脈絡膜剥離は消失した。眼軸長は正常で,小眼球ではなかった。術中に切除した強膜は肥厚しており,強膜異常による蛋白流出障害がuveal effusionの原因であると推定した。赤外螢光眼底造影で脈絡膜血管の透過性亢進があり,この所見は手術後に軽快した。非小眼球であっても強膜に異常があると緑内障手術による侵襲でuveal effusionが発症しうること,そして緑内障手術後に脈絡膜剥離が遷延するときには強膜切除術が奏効することを本症は示している。
初診時眼科未治療の増殖糖尿病網膜症患者の術後視力予後
著者: 加藤もと子 , 池尻充哉 , 四倉次郎 , 津山嘉彦
ページ範囲:P.1269 - P.1273
(P1-1-21) 初診時に眼科未治療の増殖糖尿病網膜症20例26眼の硝子体手術を過去3年間に行い,その成績を検討した。術後最高視力は22眼(84%)で2段階以上改善した。黄斑剥離がない18眼では17眼(94%)で改善し,黄斑剥離のある8眼では5眼(63%)で改善した。術後の経過中に視力の再低下が起こる症例が多く,最終視力は概して不良であった。その原因には,緑内障,白内障,黄斑変性が主であった。初診時に眼科未治療で網膜症が進行している症例にも硝子体手術が有効であるが,術後の緑内障と黄斑障害に配慮する必要があると結論される。
外傷性黄斑円孔の臨床経過
著者: 冨井厚 , 池田尚弘 , 来栖昭博 , 三村治
ページ範囲:P.1274 - P.1278
(P1-1-32) 鈍的外傷による黄斑円孔6例6眼の臨床経過を検索した。全例が男性で,年齢は10歳から28歳(平均17歳)であった。3か月以上の観察期間中,後部硝子体剥離は皆無であった。4眼で円孔は自然閉鎖し,受傷から閉鎖までの期間は2週から5か月,平均10週であった。他の2眼には円孔発症後1〜2か月後に硝子体手術を行い,円孔は閉鎖した。全6眼で視力は2段階以上改善した。今回の結果と文献から,外傷性黄斑円孔には自然寛解する事例が多いこと,そして発症から3か月を経過しても自然閉鎖しない場合には,硝子体手術を考慮すべきことが結論される。
コンフォスキャン®による角膜の計測と観察の問題点
著者: 石川隆 , 田中稔
ページ範囲:P.1279 - P.1285
(P2-1-2) 目的:コンフォーカルマイクロスコープは,角膜各層の細胞や神経などの形態学的観察が可能であり,Zスキャン装置により角膜の上皮や全層の厚さの測定ができる。これを臨床的に用い,装置の有用性と改良されるべき点を検討する。
対象と方法:コンフォスキャン(トーメイ)を使用した。対象は,20年以上のハードコンタクトレンズ装用者14眼,ステロイド大量療法中の8眼,糖尿病眼10眼,正常対照16眼である。これらについて角膜上皮と全層厚を測定し,形態学的に観察した。
結果:正常眼の角膜厚は492.9±13.1μm,角膜上皮厚は46.9±2.78μmであった。角膜厚と上皮厚は,コンタクトレンズ装用眼では,正常眼とステロイド治療眼に比べて有意に減少していた。
結論:コンフォーカルマイクロスコープで,スペキュラーマイクロスコープではできない角膜の形態を観察することができた。画質の改善,測定誤差の減少,固視点の安定化などが今後の課題である。
コンタクトレンズ装用による角膜内皮障害と安全基準
著者: 市岡博
ページ範囲:P.1286 - P.1290
(P2-1-28) 55歳以下で他の眼疾患を伴わないコンタクトレンズ装用者(1,369眼686例)の角膜内皮細胞障害につき検討した(ハードコンタクトレンズ891眼,ソフトコンタクトレンズ478眼)。細胞密度が2,000cells/Mm2以下の例を6例10眼認め,ソフトコンタクトレンズ,ハードコンタクトレンズそれぞれの典型例を供覧した。分析については単純化するために,障害程度は細胞密度のみで評価し,装用期間,1日平均使用時間の2項目につき検討した。装用期間については内皮障害との相関がなかった。1日平均装用時間も直接的相関をみなかったが,細胞密度2,500ce〜ls/mm2の症例については1日装用時間12時間以上と以下の群に有意差を認めた(pく0.001)。また,12時間以下の症例には2,500cells/mm2以下の例はなかった。コンタクトレンズ装用者は定期的に内皮検査をするべきであり,1日装用時間を12時間以下にとどめるのが望ましい。
スズメバチによる角膜刺傷の1例
著者: 清家恭三 , 澤田桂 , 渡辺牧夫 , 福島敦樹 , 上野脩幸
ページ範囲:P.1291 - P.1294
(P2-1-30) 29歳男性の左眼角膜がスズメバチに刺された。その翌日の初診時に,輪部5時の刺創と,角膜浮腫,デスメ膜皺襞があった。矯正視力は手動弁であった。併発白内障と水庖性角膜症のために視力は0.03となったが,全層角膜移櫃重水晶体摘出・眼内レンズ移植により,術後9か月に1.2の矯正視力を得た。摘出角膜の検索で,内皮細胞が菲薄化または欠損していた。正常なデスメ膜の後面にposteriorCollagenous layerがあった。
HIVプロテアーゼ阻害薬併用療法を行ったサイトメガロウイルス網膜炎の2症例
著者: 田口千香子 , 池田英子 , 疋田直文 , 望月學 , 田中健
ページ範囲:P.1295 - P.1299
(P3-1-2) 後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome:AIDS)に対してHIVプロテアーゼ阻害薬を併用したhighly active antiretroira therapy(HAART)を行い,抗サイトメガロウイルス(CMV)薬の中止後もCMV網膜炎(cytomegalovirus retinitis:CMVR)の再発を抑制できた2症例を経験した。いずれの症例もAIDSに対してHAARTを行い,CMVRに対してはガンシクロビルの全身投与を行いCMVRが鎮静化した。末梢血ウイルス量が測定限界以下となり,末梢血CD4陽性リンパ球数が症例1で55/μ1,症例2で253/μlとなった時点でガンシクロビル投与を中止し,以後半年以上CMVRの再発はない。HAARTによりAIDS患者の免疫能がある程度回復した結果抗CMV治療を行うことなくCMVRの再発予防が可能であると思われた。
活動性眼病変を合併した神経ベーチェット病の1例
著者: 山口郁子 , 清水暢夫 , 大原國俊 , 岩崎容子 , 伊東文行
ページ範囲:P.1301 - P.1304
(P3-1-15) 眼症状と同時期に発症した神経ベーチェット病の1例を経験した。症例は27歳,女性。陰部潰瘍,結節性紅斑,口腔アフタ性潰瘍,虹彩毛様体炎がみられ,完全型ベーチェット病と診断した。経過中,視力右(0.6)と低下し,両虹彩炎の増悪と右眼硝子体出血,左眼底出血,血管炎を生じた。翌日,記銘力と見当識障害を認め,髄液所見で細胞数,蛋白の増加,およびMRIのT2強調画像で右基底核に高信号域を認めた。神経ベーチェット病と診断し,プレドニン100mgから漸減療法を開始した。ステロイド大量全身投与により神経症状とともに眼症状の消退を認めたが,今後、重篤な眼発作を起こす可能性もあり,慎重な経過観察が必要と思われた。
硝子体手術により虫体が証明されたocular toxocariasisの1例
著者: 伊集院信夫 , 志水敏夫 , 福原潤 , 名和良晃 , 原嘉昭 , 西信元嗣 , 西山利正
ページ範囲:P.1305 - P.1307
(P3-1-32) 幼虫移行症の1つであるocular toxocariasisは本邦においても増加しつつある疾患であるが,この疾患の診断と治療は困難なことが多い。今回筆者らは,硝子体混濁と眼底周辺部の白色隆起性病変を認めた40歳の女性のocular toxocariasisに対し,早期に診断し硝子体手術を行った。結果,良好な術後視力が得られ,また眼球を摘出することなく硝子体手術により得られた標本にて,病理組織学的検査によりTbxocara canisが証明され確定診断に至った。
アトピー性網膜剥離に対する白内障手術を併用した強膜バックリングの手術成績
著者: 星出実香 , 石田晋 , 篠田啓 , 川島晋一 , 桂弘
ページ範囲:P.1308 - P.1311
(P1-2-17) アトピー性網膜剥離に対する初回手術として,強膜バックリングに白内障手術を併用した14例15眼を対象とし,その手術成績について検討した。白内障の術式は経角膜輪部水晶体・前部硝子体切除術(LE)3眼,水晶体吸引術(ASP)6眼,水晶体吸引術+眼内レンズ挿入術(IOL)6眼であった。全体の初回復位率は80%作最終復位率は93%であった。初回手術後再剥離を生じたのは7眼で,白内障術式別ではLE群2眼(67%),ASP群3眼(50%),IOL群2眼(33%)であった。その原因は,新裂孔5眼(毛様体雛襲部1眼,毛様体扁平部3眼,赤道部1眼),PVR 2眼であった。なお,皺襞部裂孔による再剥離はASP群であった。手術成績に関して白内障術式による明らかな差はみられず,患者のQOLを考えれば,眼内レンズ挿入の同時施行も考慮してよいと思われた。
血小板凝集能亢進の関与が疑われた網膜中心静脈閉塞症の1例
著者: 長谷川琢也 , 西村幸英 , 松下賢治 , 岡本紀夫 , 福田全克
ページ範囲:P.1312 - P.1316
(P1-2-42) 全身疾患に対し抗凝固療法中に網膜中心静脈閉塞症を発症した1例を経験した。症例は72歳の女性で,左眼の視力低下を自覚して来院した。検眼鏡および螢光眼底造影所見から、左眼下方2象限にわたる非虚血型網膜中心静脈閉塞症と診断した。血液検査では不整脈に対する抗凝固療法中であったため重血液凝固能はトロンボテスト36%と低値を示したが,血小板凝集能は著明に亢進していた。抗凝固剤を減量し抗血小板療法を持続したところ,虚血型への移行もなく左眼視力は0.2から0.6に改善した。網膜中心静脈閉塞症は抗凝固療法中にも生じることがあり,血小板凝集能亢進が疑われた場合には抗血小板持続療法が望ましいと考えられた。
嚢胞状黄斑浮腫を伴う網膜静脈分枝閉塞症に対するレーザー光凝固療法
著者: 瀧浦和子 , 湯沢美都子
ページ範囲:P.1317 - P.1320
(P1-2-47) 嚢胞状黄斑浮腫を伴う網膜静脈分枝閉塞症に対するレーザー光凝固眼の視力予後,また視力を左右する要因につき検討した。対象は光凝固を行い,1年以上経過観察した69眼である。1年後の視力改善は55%,不変36%,悪化9%であり,凝固後視力は凝固前に比べ有意に改善した(p<0.001)。また,凝固1年後に視力0.7以上になった症例は65%であった。)凝固後logMAR視力は,凝固前logMAR視力,年齢,傍中心窩毛細血管網の障害範囲と正の相関を示した(p<0.01)。凝固後視力0.7以上を得る条件は,凝固前視力0.3以上,70歳未満,傍中心窩毛細血管網の障害範囲が180度未満であった。
軽微な眼球運動障害の検出に有用な新しいelectro-oculogram検査解析法
著者: 神垣久美子 , 山田徹人 , 向野和雄 , 三橋祐美子 , 杉本朝子 , 松野彩子
ページ範囲:P.1321 - P.1326
(P2-2-20) EOGで得られた眼位信号を、新たに開発されたソフトウェア(Turbo Pascal)を用いパーソナルコンピュータ(NEC9801E)に取り込み,往復のサッカードの実際の振幅と最大速度を記録した。さらにその関係を,指数関数曲線で近似した。正常者5名では,正面位から開始する外転速度と内転位から開始する2つの外転速度に有意差はなく,また内転速度も同様の結果を得た。すなわち,EOGの欠点である眼位の偏位によるクロストークの影響を最小限に抑えることが可能となった。そこで,肉眼的には診断のつかなかった外転運動障害を疑われた症例5例に対し,同様に記録解析した。4症例は,両側もしくは片側に軽微な外転速度の低下を認め,今回の解析方法が有用なことが示された。MLF症候群を疑われた症例1例は,新たに不全注視麻痺が検出されPPRFの障害が判明した。この方法は,日常用いるEOGの記録法として,患者のデータを正常者との一般的比較ではなく,微細な眼球運動障害を同一個体のデータ上から定量的に検出することを可能にした。
白内障手術後に出現した複視についての検討
著者: 濱田麻美 , 小原真樹夫 , 清水公也
ページ範囲:P.1327 - P.1330
(P2-2-27) 点眼麻酔下での耳側角膜小切開白内障手術後に複視を訴えた6症例について眼科的に精査し,その原因を検討した。全例,上下複視があり,2症例については回旋複視を伴っていた。検査結果にて上下偏位,外方回旋,V型斜視,BHTT陽性などがみられ,これらから上斜筋麻痺が疑われた症例が3例あった。高齢者では白内障術後に,術前から存在していた上斜筋麻痺が発見される例があるが,見かけ上の眼位,眼球運動異常が明らかでなく,術前に発見されにくいことから注意を要する。
過去10年間の穿孔性眼外傷の検討
著者: 向所真規 , 吉田健一 , 岩見達也 , 堀尾和弘 , 西田保裕 , 澤田智子 , 石村博美 , 澤田修 , 山出新一 , 可児一孝 , 佐々本研二
ページ範囲:P.1331 - P.1334
(P2-2-47) 過去10年間の穿孔性眼外傷の自検例105眼104例を検索した。12歳以下の低年齢層では約半数が他人による受動的な外傷で,65歳以上の高年齢層では転倒が多かった。13歳から64歳までの青壮年層では草刈り機や金属工具などを使った作業中が多かった。これらは防護眼鏡装用で予防できたと思われた。受傷から6か月以上の56眼での視力転帰は,鋸状縁よりも後方の例で悪く,手術までに時間が経過した症例で特に不良であった。穿孔性眼外傷には早期の硝子体手術で対応することが望ましい。
上眼瞼結膜に発生した血管拡張性肉芽腫の1例
著者: 高村浩 , 川崎良 , 高橋茂樹
ページ範囲:P.1335 - P.1338
(P3-2-3) 59歳男性の上眼瞼結膜に発生した血管拡張性肉芽腫の1例を経験した。右上眼瞼結膜に4×4mm大でドーム状に隆起した赤色調の腫瘤がみられた。表面は凹凸不整で内部に係蹄様の血管がみられ,上眼瞼を反転するたびに表面から出血した。また瞼縁から腫瘤に向かって太い血管が走行していた。全身的に特に異常所見はなかった。悪性腫瘍の可能性を疑って腫瘍摘出術と冷凍凝固術を行った。
摘出した腫瘍の病理組織学的所見は,結合組織の間質のなかに多数の毛細血管が増生していた。毛細血管内および間質に多核白血球やリンパ球などの多数の炎症性細胞がみられた。悪性像はなく,血管拡張性肉芽腫と診断された。
肺・肝転移を伴った結膜悪性黒色腫の1例
著者: 岡田丈 , 栗原久美子 , 小田仁 , 平形明人 , 樋田哲夫
ページ範囲:P.1339 - P.1341
(P3-2-5) 66歳の女性が右眼の結膜腫瘍で受診した。30年前から右上眼瞼の色素沈着を自覚していた。右の上下眼瞼結膜に色素沈着を伴う分葉状の腫瘤があった。胸部X線とCTで肺転移と思われる充実性腫瘤が発見された。瞼結膜の腫瘤の生検で悪性黒色腫と診断された。眼窩内容除去術で摘出された腫瘍はそのほとんどが類上皮型であり,その大きさは20×14×17mmであった。化学療法を術後に行ったが,10か月後に肝転移のため死亡した。
涙道留置ヌンチャク型シリコーンチューブの菌検査
著者: 森寺威之 , 高木史子 , 森秀夫
ページ範囲:P.1343 - P.1346
(P3-2-14) 涙道閉塞の治療として留置したヌンチャク型シリコーンチューブの内容を,抜去後に培養し,微生物学的に検索した。対象は24眼で,チューブの留置期間は1から15か月,平均61か月であった。チューブからは17本(71%)が菌陽性であり,結膜嚢からは10眼(42%)で菌が検出された。留置期間が6か月を超えると検出率が大きかった。チューブが感染源になる可能性があり,長期間の留置には注意が必要である。
自然発症した眼窩内血腫の1症例
著者: 中嶋順子 , 石村博美 , 岩見達也 , 目加田篤 , 西田保裕
ページ範囲:P.1347 - P.1350
(P3-2-36) 56歳の女性が急激な片眼性の眼球突出を主訴として受診した。Computed tomography (CT).magnetic resonance Imaging (MRI)・脳血管造影(CAG)検査にて特発性眼窩内血腫と診断した。眼窩内血腫の原因は外傷によるものが多く,自然発症例は稀である。MRI検査では,出血の量や視神経への損傷の評価がCT検査と比較して容易であった。保存的療法が可能と判断し重ステロイド投与を行った。約20日間で血腫は消退した。血腫の診断には従来からいわれているとおりCT検査が有用であるが,治療方針の決定にはMRI検査が有用であると思われた。
特発性uveal effusionに対する硝子体手術
著者: 京兼郁江 , 安藤文隆 , 笹野久美子 , 鳥居良彦
ページ範囲:P.1351 - P.1353
(P1-3-17) 3例の特発性uveal effusion症例を硝子体切除術,経網膜網膜下液排除,液—ガス交換で治療した。強膜部分切除術+強膜開窓術が無効であった第1例に本法が成功したので,他の2症例には最初から硝子体手術を試み,全例1回の手術で網膜は復位し,視力も2段階以上回復した。3例とも経過観察期間中,再剥離はみられていない。
腎移植における眼合併症
著者: 宮原千恵 , 石井あずさ , 大西礼子 , 岩切玉代 , 堀貞夫 , 寺岡慧
ページ範囲:P.1355 - P.1358
(P2-3-12) 過去26年9か月の期間に,東京女子医科大学病院腎センター外科において腎移植を行った1,151症例中,1回の移植で生着し,眼科的に経過観察が可能であった324症例を対象として,眼合併症の出現頻度と時期についてretrospectiveに検討した。
白内障は324症例中253例(78.1%)にみられ,1年累積発症率は57.2%であった。高眼圧は24例(7.4%)にみられ,1年累積発症率は3.6%であった。眼底疾患は多発性後極部網膜色素上皮症が19例,ウイルス眼感染症が1例および中心性漿液性網脈絡膜症が6例にみられた。
賢移植患者では高率に眼合併症がみられ,また移植後早期から出現していることがわかった。
人間ドックと白内障
著者: 古谷朋子 , 門屋講司 , 林振民 , 筑田眞
ページ範囲:P.1359 - P.1362
(P3-3-4) 人間ドックの受診者445例890眼について,水晶体混濁の頻度と背景要因を検索した。男性287例,女性158例であり作年齢は21歳から84歳で,平均50.4歳であった。受診者は40歳から50歳代に極大があり,男性は女性の約2倍であった。白内障は252人(56.5%)にあり,高齢になるにつけ頻度が高く,女性にやや多かった。型別では皮質型が約7割で最も多かった。糖尿病,高血圧,貧血と白内障の間には相関はなかった。
早期緑内障眼における網膜神経線維層厚に関する検討
著者: 高橋伊満子 , 田中稔
ページ範囲:P.1363 - P.1366
(P4-3-15) 早期緑内障に関する知見を得るために,網膜神経線維層厚をNerve Fiber Analyzer GDxTMで測定した。対象は視野障害のある早期緑内障38例50眼,進行した視野障害のある緑内障16例22眼であり.年齢が一致する正常11例20眼である。検討した15のパラメータのうち、進行群で12のパラメータに正常群と比較して有意差があった。早期群では,82%に1項目以上のパラメータが異常値(p<0.05)を示したが,正常群と比較して有意差があったのは,下側のdeviation from normalとinferioraverageだけであった。緑内障症例全体に対する特異度は80%,感度は78%,早期緑内障群の感度は72%であった。以上,緑内障の早期診断に直結する結果は得られなかった。
連載 今月の話題
SLOとビデオ型カメラ装置のICG画像の違い
著者: 村山耕一郎 , 米谷新
ページ範囲:P.1097 - P.1100
インドシアニングリーン(ICG)螢光眼底造影法は加齢黄斑変性の診断には不可欠のものとなりつつあるが,現在使用されているScanning laser ophthalmoscope (SLO,ローデンストック社製)とビデオ型力メラ装置(TRC−501A,トプコン社製)では造影所見に違いがみられることがある。これは撮影機種の特性によるものであるが,特に加齢黄斑変性では新生血管の大きさや流入血管の検出など,重要な所見の読影には撮影機種の特性を理解し,判読することが重要である。
眼の組織・病理アトラス・152
水晶体と類皮嚢胞
著者: 猪俣孟 , 吉富文昭
ページ範囲:P.1102 - P.1103
水晶体と類皮嚢胞demloid cystは発生学的に似たような組織環境にある(図1,2)。それゆえに,水晶体起因性眼内炎lens-induced endophthalmitisの炎症形態と類皮嚢胞の炎症形態は非常によく類似している。
水晶体は表層外胚葉surface ectodermの一部が水晶体胞lens vesicleを形成して眼杯の前面に嵌入したものである。したがって,水晶体は水晶体細胞の基底膜である水晶体嚢に囲まれて,眼内の間質結合組織である硝子体の前面で,しかもこれも眼内の問質結合組織液である房水中に存在している。水晶体質が水晶体嚢に囲まれて存在している限り,生体は水晶体質に対して異物としての炎症反応を起こさない。しかし,穿孔性眼外傷や内眼手術で水晶体嚢が破嚢するか,もしくは過熟白内障になって水晶体質が間質結合組織である嚢外に流出すると,生体は房水中もしくは硝子体中に出た水晶体質を異物と認識して,眼内に炎症反応を生じる。
眼科手術のテクニック・114
硝子体網膜剥離術—(1)硝子体カッターを用いて(硝子体シェービング)
著者: 安藤伸朗
ページ範囲:P.1106 - P.1107
糖尿病網膜症をはじめ多くの増殖網膜症の硝子体手術を成功させるためには,増殖組織と網膜をいかに安全に,かつ確実に剥離できるかが重要である。
今回は高速回転の硝子体カッターを用いた硝子体シェービングについて述べる。
今月の表紙
傍中心窩血管拡張症
著者: 西川真平 , 玉井信
ページ範囲:P.1101 - P.1101
傍中心窩血管拡張症は,成人の黄斑部毛細血管が拡張して漏出が起こり,さらに閉塞が生じると中心視力の低下をきたす疾患である。この毛細血管の異常の発生には,先天性素因によるものと,原因不明によるものとがあると推察されている。
片眼性先天性(Group IA),片眼性特発性(Group IB),両眼性特発性後天性(Group II),周中心窩両限性特発性(Group III)に分類される(Gassの分類)。Group IA, Group IIの進行例に対しては光凝固を行うこともある。
日眼百年史こぼれ話・6
上野公園と東京大学
著者: 三島濟一
ページ範囲:P.1354 - P.1354
上野公園は博物館・美術館・芸術大学,文化会館など,日本文化の中心をなし,広い敷地,動物園,桜の名所など楽しみの中心でもあり,そこに上野公園があることが当然のこととして日本人の生活の一部になっている。しかし,もしここに現在の東京大学が建てられていたら,われわれの生活はどうなっていただろうか。
何と突拍子もないことをいうと思われるかもしれないが,実はそうなっていたかもしれないのである。
第51回日本臨床眼科学会専門別研究会1997.10.17東京
臨床報告
緑内障眼における角膜厚の検討
著者: 落合恵蔵 , 青山裕美子 , 宮崎正人 , 上野聰樹
ページ範囲:P.1370 - P.1374
原発開放隅角緑内障85眼,正常眼圧緑内障66眼,高眼圧症33眼の94名184眼で,角膜中央部の厚み(角膜厚)を測定し,眼圧,視野,病型,薬剤との関係を検索した。角膜厚の平均値は,正常眼圧緑内障で531.1μmであり,他の2群よりも有意に薄かった。原発開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障での角膜厚を平均値未満と以上の2群に分けるとき,視野障害が進行している眼では,角膜厚が平均値未満であるものが多かった。以上の結果から,病型を考慮した角膜厚測定が,病期診断に有用であると結論される。
脈絡膜新生血管に対する外科的除去術の成績
著者: 間渕文彦 , 荻野誠周 , 川村昭之 , 栗原秀行
ページ範囲:P.1375 - P.1379
中心窩下の脈絡膜新生血管膜除去術を16例16眼に行った。加齢黄斑変性症11眼,特発性新生血管黄斑症2眼,近視性新生血管黄斑症3眼である。平均10.3か月の経過観察で,視力改善が6眼,不変6眼,悪化4眼であった。術前のフルオレセインまたはインドシアニングリーン螢光眼底造影での新生血管膜の大きさは,術中で確認した新生血管膜よりも小さかった(p<0.005)。術後のフルオレセイン螢光眼底造影で網膜色素上皮障害が軽度な症例では,高度な症例よりも視力が改善していた(p<0.05)。手術による視力改善は,中心窩下の網膜色素上皮の強い障害なしに新生血管膜を除去できるような症例を選択することが重要であると思われた。
眼窩内に発生したsolitary fibrous tumorの1例
著者: 中村靖 , 大塚賢二 , 橋本雅人 , 一宮慎吾 , 佐藤昌明
ページ範囲:P.1381 - P.1384
27歳男性が,3か月前からの無痛性で緩慢に進行する左眼の内眼角部腫瘤を主訴として受診した。CTでは高吸収域があり,MRIではT1とT2強調画像の双方で低信号を示した。Gd-DPTA造影では軽度の造影効果があった。摘出した腫瘍は病理組織学的に,錯綜した膠原線維束を伴うspindle cellの増生像があった。いわゆるpatternless patternであり作免疫染色でvimentin (+),CD34(+),S-100(−)であり,solitary fibrous tumorと診断した。本疾患は,主として胸膜に発生する腫瘍であり,眼窩内に生じるのはごく稀である。
重度の視神経低形成の1例
著者: 寺尾祐子 , 仁科幸子 , 東範行
ページ範囲:P.1385 - P.1389
妊娠と分娩歴には異常がない4か月の女児が異常眼球運動を主訴として受診した。固視反応と対光反応はなかった。角膜を含む前眼部に異常はなく,視神経乳頭が両眼とも小さかった。網膜血管は後極部だけにあり,直線的で狭細であった。右眼には黄斑コロボーマ,左眼には黄斑反射が減弱し,形が不正であった。超音波検査による眼球と各部の大きさは正常範囲にあったが,両眼とも眼球後方に視神経がなかった。網膜電図は正常であったが,視覚誘発電位(VEP)は消失していた。X線検査で視神経管が細く,CTで視神経が欠如していた。頭蓋内には異常はなかった。以上の所見から,本例を無形成に近い重度の視神経低形成と診断した。
眼内レンズと後嚢との間隙にみられた高散乱性液状物質の画像診断
著者: 中泉裕子 , 佐々木洋 , 春日孝文
ページ範囲:P.1391 - P.1395
眼内レンズ(PMMAレンズ)挿入術後1年〜3年半後にIOL後面と後嚢との間に液状の貯留物質が出現した3例を報告した。3例はともに後嚢下白内障例で,糖尿病網膜症を有している。いずれも前房側,後眼部にも眼内炎症を疑わせる所見はなく,また前房深度,屈折も術後早期と変わりなく,視力,眼圧への影響もみられなかった。Scheimpflugスリット画像から液状物質が呈する光学特性は,眼内レンズ後面と後嚢の距離が長い症例ほど高かった。
特異な後発白内障の1例
著者: 樋口眞琴 , 大塚秀勇 , 村松昌裕
ページ範囲:P.1397 - P.1400
現在77歳の男性が7年前に白内障超音波乳化吸引手術と後房レンズ挿入術を受けた。当初の経過は順調であったが,左眼に特異な後発白内障が出現した。完全に嚢内固定された後房レンズと水晶体前嚢が癒着して閉鎖腔を形成し,後房レンズと後嚢との間に空隙があり,その中に乳白色の液状と塊状の混濁があった。これを摘出して組織像を検索した。赤道部には活性のある水晶体上皮細胞があり,水晶体線維は内側に向かうにつれて融解して無構造の蛋白質に変性していた。残存した水晶体上皮細胞が特殊な環境で増殖してこれらの混濁を形成したと推測された。
基本情報
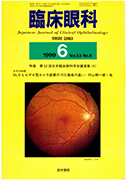
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
