(D−8PM−6) 3.2mm耳側切開による無縫合白内障手術後2年間の角膜乱視変化を,角膜切開20眼と強角膜切開20眼で比較した。軸乱視量,惹起角膜乱視絶対量ともに強角膜切開のほうが小さく,術後1年目まで角膜切開との間に有意差が認められた。術後2年目の惹起角膜乱視絶対量は,角膜切開で平均0.42(±0.24) D,強角膜切開で0.32(±0.20) Dであった。術後角膜形状変化は,強角膜切開では切開創の軽微なフラット化を認め,その後軽減したのに対し,角側切開では早期に大きな切開創のフラット化と直交するスティープ化を認め,形状変化も持続する傾向を示した。3周2mm耳側切開では,両切開ともに軽度ながら術後2年目でも手術による角膜乱視が残存して認められた。
雑誌目次
臨床眼科54巻3号
2000年03月発行
雑誌目次
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
原著
ベーチェット病における眼症状と聴覚障害の関係
著者: 阿曽香子 , 若倉雅登 , 古野久美子 , 松本美保 , 大野晃司 , 清水公也 , 岡本牧人
ページ範囲:P.309 - P.312
(D−7AM−11) 眼症状を有するベーチェット病で経過中に耳鳴,難聴をきたした8例を経験した。特徴として①眼発症1〜3年後に起こる,②眼発作を繰り返す例にみられる,③網膜血管炎などの後部発作と同時期に症状が発現する,④キーンという高い音の耳鳴から始まり難聴に進行していく、などがあった。以上のことから,聴覚障害は偶然の合併ではなく,ベーチェット病の部分症状であり,耳鼻科だけではなく,眼科でもその認識を持つ必要があると思われた。
Heidelberg Retina Tomographによる視神経乳頭解析における検者間での比較
著者: 岡田真弓 , 塚本秀利 , 岡田康志 , 二井宏紀 , 高松倫也 , 三嶋弘
ページ範囲:P.313 - P.316
(D−7PM−10) Heidelberg Retina Tomographで検索され,当科データベースに保存されている緑内障30眼の記録を,独立した2名で解析した。両名とも緑内障外来の専門医であった。解析は,disk area, cuparea, cup volume, rim voiume, maximum cup depthについて行った。全5項目について,2検者間の判定には強い相関関係(0.72〜1.00)があり,有意差はなかった。熟練した検者であれば,乳頭縁を決定する操作を手動で行っても,再現性のある結果が得られると結論される。
エキシマレーザー屈折矯正手術による角膜後面屈折力の変化
著者: 神谷和孝 , 大鹿哲郎 , 天野史郎 , 宮田和典 , 高橋哲也 , 徳永忠俊 , 吉田照宏
ページ範囲:P.317 - P.320
(G−7AM−13) エキシマレーザー屈折矯正術(PRK)を施行した15例25眼を対象に,スリットスキャン型角膜形状解析装置(OrbscanTM,Orbtek)を使用して,角膜後面屈折力の経時的変化および関連因子について検討した。術前の後面屈折力は平均−6.56Dであり,術後1週で−7.02D,1か月で−7.00D,3か月で−7.05Dと,術前に比較して有意に減少した(p<0.001,paired t-test)。この変化量は,PRK効果量の約10%に相当した。また,残存角膜厚が小さいほど後面屈折変化量は大きかった(Pearson相関係数r=0.617,p<0.OO1)。エキシマレーザー屈折矯正術は後面の屈折力にも有意な影響を与え,その変化の定量的評価にはスリットスキャン型角膜形状解析装置が有用である。
甲状腺眼症による上下斜視に対する調節糸法と従来の後転法の比較
著者: 河野玲華 , 大月洋 , 長谷部聡
ページ範囲:P.321 - P.325
(G−7PM−3) 上下直筋の後転を施行した甲状腺眼症患者20例を対象に,調節糸法(7例)と従来の後転法(13例)をretrospectiveに治療効果を比較した。単位術量あたりの矯正効果には両群間に有意な差は認められず,正面視と読書眼位における両眼単一視野獲得の割合にも差がなかった。調節糸法を施行した2例に過矯正が認められた。そのうち1例には手術筋と拮抗筋に外眼筋の肥厚,他の1例は手術直後から軽度の過矯正があった。調節糸法では,手術筋,ならびにその拮抗筋の肥厚がある場合には低矯正にとどめるように注意することが過矯正を防止する上で重要である。
黄斑剥離を伴った裂孔原性網膜剥離手術後のOCT所見
著者: 神原千浦 , 伊野田繁 , 清水由花 , 田邊和子 , 堤雅弘
ページ範囲:P.327 - P.330
(R2-8PM−19) 黄斑剥離を伴った裂孔原性網膜剥離術後27例27眼の黄斑部を,光干渉断層計(OCT)を用いて経時的に観察した。初回手術は,経強膜的手術19眼,硝子体手術8眼であった。結果は,術後検眼鏡的には復位を得ているにもかかわらず,OCT術後初回検査時に黄斑部に網膜下液が残存していた症例は,経強膜的手術で19眼中12眼(63%),硝子体手術で8眼中1眼(13%)であり,経強膜的手術後に多かった(p<0.05)。OCTは,検眼鏡でははっきりしない網膜下液を簡便に描出することが可能で,網膜剥離術後の黄斑復位の指標として有用な検査であると考えられた。
前眼部形成異常を合併した先天緑内障に対する線維柱帯切開術
著者: 野崎実穂 , 水野晋一 , 尾関年則 , 小椋祐一郎 , 山口潔 , 白井正一郎
ページ範囲:P.331 - P.334
(G−8PM−22) 前眼部形成異常を伴った先天緑内障に対して線維柱帯切開術を行った7例13眼について検討した。合併した前眼部形成異常は,強角膜症が全例にあり,後部胎生環が3例6眼,先天性ぶどう膜外反が2例3眼,Peters奇形が1例2眼,楔状虹彩異色が1例1眼であった。Peters奇形は,先天性ぶどう膜外反を伴った3例6眼では術後眼圧下降が不十分で追加手術を要し,他の4例7眼では1回の線維柱帯切開術で眼圧は下降した。Peters奇形や先天性ぶどう膜外反といった比較的重症の前眼部形成異常を伴った先天緑内障では,複数回の線維柱帯切開術を要したことから,合併する前眼部形成異常の程度によって本術式の有効性に差が生じたと考える。
血液過粘稠度症候群の症例にみられたオカルト網膜色素上皮剥離
著者: 緒方奈保子 , 高橋寛二 , 伊田宜史 , 福地俊男 , 近藤未佳
ページ範囲:P.335 - P.338
(G−8AM−6) 62歳男性が6か月前からの両眼視力低下と変視症で受診した。初診時の矯正視力は右0.5,左0.3。両眼の黄斑部に約5乳頭径大の滲出性網膜剥離があった。網膜静脈は軽度に拡張し,周辺部に網膜出血と毛細血管瘤が多発していた。光干渉断層計(OCT)による検査で,網膜剥離の外方に網膜色素上皮剥離が同定された。高ガンマグロブリン血症があり,原発性マクログロブリン血症または多発性骨髄腫による血液過粘稠度症候群と診断された。フルオレセイン蛍光眼底造影で網膜色素上皮剥離の所見がなかったのは,粘稠度の高い異常免疫グロブリン蛋白が色素上皮下に貯留していたためと解釈された。
原発閉塞隅角緑内障に対する虹彩切除術を併用した非穿孔トラベクレクトミーの手術成績
著者: 園田日出男 , 長谷部日 , 馬場恵理子 , 岩田玲子 , 新保信夫 , 山口淑美 , 岩田和雄
ページ範囲:P.339 - P.343
(G−8AM−21) 点眼やレーザー虹彩切開術で眼圧コントロールが不良な原発閉塞隅角緑内障6眼に対して,虹彩切除術を併用した非穿孔線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)を行った。必要に応じて隅角癒着解離術を併用した。術後観察期間は平均16か月であった。術前眼圧は平均29.7mmHg,術後最終眼圧は平均9.5mmHgであった。過剰濾過による一過性の合併症として,軽度の浅前房と脈絡膜剥離が1眼に生じた。虹彩切除術を併用した非穿孔線維柱帯切除術は,原発閉塞隅角緑内障に対する安全で有効な術式であると評価される。
減圧手術後に高度視機能障害が改善したうっ血乳頭を伴う小脳腫瘍症例
著者: 横川由起子 , 羽場勝彦 , 池田正人
ページ範囲:P.344 - P.347
(G−8PM−5) うっ血乳頭を伴う小脳腫瘍の術後に残存した高度の視機能障害が次第に改善した症例を経験した。症例は24歳男性,初診時視力は右0.1(n.c),左0.5(n.c.),両眼とも著明なうっ血乳頭を呈し,右眼で下半盲,左眼でマリオット盲点の拡大および鼻側下方の視野狭窄を認めた。直ちに小脳腫瘍摘出術および減圧術を施行したが、術後約2週で両眼とも視野狭窄はさらに進行し,約1か月後には乳頭は蒼白化した。しかし,以後約1年の経過で右眼視力は不変であったが,視野は初診時より改善し,左眼では視力は1.5に回復,拡大マリオット盲点は正常化,求心性狭窄も改善した。本例の経過から,うっ血乳頭による高度視機能障害も改善する場合があることがわかった。
テノン嚢内麻酔に対する前房内麻酔の付加効果
著者: 花崎秀敏
ページ範囲:P.348 - P.352
(R1-7AM−14) 他に合併症のない症例での白内障手術で,2%リドカイン1.5mlによるテノン嚢内麻酔を行い,これに前房内麻酔を追加した場合の効果と安全性を検討した。60眼を対象とした。30眼には水流核分離時にBSS Plus®を前房に注入し,他の30眼には0.5%リドカイン1mlを注入した。術後に手術全体についての疼痛の程度を10段階として聴取した。後群では前群よりも有意に疼痛は低かった。術後の眼圧,矯正視力,角膜内皮細胞密度については,両群の間に差がなかった。手術1週後の前房フレア値は後群で有意に上昇していた。テノン嚢内麻酔で麻酔効果が不十分な症例には,前房囚麻酔を追加することが有用である。
白内障術後眼に対するエキシマレーザー乱視矯正手術の臨床成績
著者: 小野恭子 , 宮田和典 , 大谷伸一郎 , 徳永忠俊 , 封馬一仁 , 天野史郎 , 大鹿哲郎
ページ範囲:P.353 - P.356
(R1-8PM−21) 白内障術後の乱視20例25眼に対してVISX社STARエキシマレーザーシステムを用いた乱視矯正術(photoastigmatic refractive keratectomy:PARK)を行い,術後6か月の経過観察を行った。自覚円柱度数は術前平均3.64±1.23ジオプター(D)から術後6か月で1.08±0.64Dと減少し,戻りもなく安定していた。等価球面度数で平均2D弱の遠視化が生じた。裸眼視力は有意に改善し,矯正視力は術直後に一時的に低下したものの,速やかに回復した。目標度数の±1.0D以内に矯正できたのは術後6か月の時点で64%であった。強い上皮下混濁,遷延性上皮欠損などの重篤な合併症はなかった。PARKは白内障術後の乱視矯正術として安全かつ有効であると考えられた。
眼中枢神経系悪性リンパ腫患者における硝子体中のインターロイキン10とインターロイキン6
著者: 政岡則夫 , 松下久美子 , 橋田正継 , 林暢紹
ページ範囲:P.357 - P.360
(R1-9AM−9) 眼中枢神経系悪性リンパ腫(以下,悪性リンパ腫)の診断における硝子体中インターロイキン(IL)10とIL-6の濃度比測定の有用性について検討した。悪性リンパ腫患者4例、ぶどう膜炎患者3例の硝子体中IL-10濃度を酵素結合免疫吸着剤測定法で,またIL-6濃度を化学発光酵素免疫測定法で測定した。ぶどう膜炎患者では全例IL-10濃度はIL-6濃度より高くなかったが,悪性リンパ腫患者は全例で高かった。のちに中枢神経系に進展した悪性リンパ腫患者2例は,頭蓋内病変を認めていない2例よりIL-10濃度が高値であった。硝子体中IL-10とIL-6の濃度比は悪性リンパ腫の診断に有用である可能性が示唆された。
中心性滲出性網脈絡膜症に対する赤外蛍光眼底造影と治療法
著者: 鈴木水音 , 安田秀彦 , 戸張幾生
ページ範囲:P.361 - P.365
(R2-7AM−7) 中心性滲出性網脈絡膜症29例30眼の治療経過を分析し,本症に対する赤外蛍光造影の有用性および治療方法について検討した。フルオレセイン蛍光造影をもとに光凝固治療を行った群(10眼)は,新生血管の閉塞は確実に得られるものの中心暗点が残り,視力予後は不良であった。赤外蛍光造影所見をもとに薬物療法を行った群(20眼)は,視力予後は良好なものの,再発が多くみられた。薬物療法群のうち,トラニラスト投与の10眼では,他の薬物療法に比較して網膜下線維増殖が少なかった。赤外蛍光造影をもとに,再発のみられる活動性のある症例には光凝固治療を考慮すべきと思われた。トラニラストは網膜下線維増殖の予防に効果的である可能性があると考えられた。
糖尿病黄斑症に対する光凝固の適応と限界
著者: 大越貴志子 , 草野良明 , 四蔵裕実 , 山口達夫
ページ範囲:P.367 - P.371
(R2-7PM−22) 糖尿病黄斑浮腫54例75眼に対して黄斑局所光凝固を行い,5年以上の長期経過を観察した。視力改善は,びまん性浮腫の48%,局所浮腫の21%で得られ,黄斑浮腫は87%で消失した。0.7以上の最終視力は35眼(47%)で得られ,その背景因子は,尿蛋白(−)(P=0.005),高度の黄斑沈着なし(P=0.01),嚢胞様浮腫なし(P=0.03)であった。0.2以下の最終視力は18眼(24%)であり,その背景因子は尿蛋白(3+以上)(P=0.002),高度または中心窩の黄斑沈着(P=0.001),嚢胞様浮腫(P=0.01)であった。光凝固前の視力が0.7以上の症例では77%が最終視力0.7以上に,0.2以下の症例では47%が最終視力0.2以下になった。以上の成績は,良好な最終視力を得るためには早期の黄斑局所光凝固が必要であること,腎症や高度の黄斑沈着が予後不良因子であることを示す。
新しい変視表M-CHARTS®による変視症の定量化の試み
著者: 松本長太 , 有村英子 , 橋本茂樹 , 高田園子 , 奥山幸子 , 下村嘉一
ページ範囲:P.373 - P.377
(R2-8AM−11) 筆者らは,変視症の定量化を目的とし新しい変視表M-CHARTS®を開発した。変視の自覚には,連続した直線による網膜面への刺激が必要である。直線を間隔の狭い点線から広い点線に変えると次第に変視は消失する。この現象を応用し,視角0.2゜から2.0゜まで間隔を変えた19種の点線からなる変視表を作成した。被検者に間隔の細かな点線から広い点線へ順に呈示し,変視が自覚されなくなった視角をもって変視量とした。変視症の症例では点線の間隔が広くなるにつれ自覚的な変視が軽減,消失した。変視の強い症例ほど点の間隔が広い点線まで変視を自覚した。M-CHARTS®は,簡便に変視を定量可能で,変視症を伴う黄斑疾患の経過観察に極めて有用である。
ハードコンタクトレンズが迷入したと思われた涙腺偽腫瘍の1例
著者: 鈴村弘隆 , 有輪六朗 , 富田香
ページ範囲:P.378 - P.380
(P−1-7) 71歳女性が左眼上眼瞼耳側の腫瘤で受診した。15年前までハードコンタクトレンズ(HCL)を使用しており,これを紛失したことが数回あった。嚢胞性腫瘤の診断でこれを摘出した。腫瘤塊の中にHCLが発見された。組織学的に、腫瘤は涙腺導管または副涙腺に由来する貯留嚢胞であった。紛失したHCLが結膜嚢に残留して結膜下に迷入し,慢性炎症などの結果涙腺導管または副涙腺を閉塞して嚢胞化したと推定された。
Wegener肉芽腫症による強膜穿孔に対し自己大腿筋膜移植術を行った1例
著者: 生杉謙吾 , 前川悟 , 福喜多光志 , 宮村昌孝 , 和田泉 , 宇治幸隆
ページ範囲:P.381 - P.384
(R2-9AM−10) 49歳男性が両眼の強膜炎と右眼角膜潰瘍で受診した。4年前に膝が腫脹し,Wegener肉芽腫症と診断され,ステロイド薬と免疫抑制薬の治療を受けていた。初診から22か月後に左眼の鼻側強膜に軟化と穿孔,硝子体脱出が生じた。強膜穿孔部に自己大腿筋膜をただちに移植した。右眼の強膜軟化部にも1か月後に同様の移植術を行った。以後11か月間,両眼とも移植片の接着は良好であり,新たな炎症は生じていない。Wegener肉芽腫症に続発した重症の壊死性強膜炎による強膜穿孔に,自己大腿筋膜移植術が有効であることを示す症例である。
眼部帯状疱疹の臨床像
著者: 安藤一彦 , 河本ひろ美
ページ範囲:P.385 - P.387
(P−1-16) 三叉神経第1枝領域の帯状疱疹87例について,眼病変の発症率と視力の経過を検索した。男性37例,女性50例で,年齢は平均61.8歳であった。眼病変の発症率は,結膜炎68%,強膜炎9%,角膜炎21%,虹彩毛様体炎20%,眼圧上昇6%であった。鼻疹(Hutchinson's sign)は15例17%にあり,鼻疹のある症例では,ない症例よりもすべての眼病変発症率が有意に高かった。眼部帯状疱疹の視力転帰は概して良好であったが,早期にアシクロビル全身投与がされなかった症例,80歳以上の高齢者,鼻疹のある症例では,眼合併症の発症が多かった。
眼窩蜂巣炎に上斜筋麻痺が合併した小児の1例
著者: 三浦孝夫 , 藤澤昇
ページ範囲:P.389 - P.391
(P−1-21) 4歳男児に高熱,両眼瞼腫脹,両眼痛が突発し,その翌日に受診した。右眼瞼に重度,左眼瞼に軽度の腫脹があった。MRI検査で両側の眼窩にびまん性の膿瘍が同定された。急性副鼻腔炎に続発した眼窩蜂巣炎と診断し,抗生物質の全身投与を開始した。その6日後に斜頸と複視が生じ,右上斜筋麻痺と診断した。以後の経過は良好であり,斜頸と複視はさらに3週後に消失した。上斜筋単独麻痺は,齢骨洞の炎症が眼窩内側壁を通じて浸潤し,総腱輪の外側で滑車神経を圧迫した結果であると推定した。
眼内レンズが裏表逆固定になった3例
著者: 平田裕也 , 喜多美穂里 , 渡部大介 , 山名隆幸
ページ範囲:P.392 - P.394
(P−1-57) アクリル眼内レンズが裏表逆の嚢内固定になつた3症例の経過を検討した。糖尿病黄斑変性を有する1例を除いて視力は改善した。術後屈折度は、術後1週で予想値よりも平均1.54D近視化していたが,2〜4か月で平均1.20Dと近視化は減少傾向を示し、以後著変なかった。前房深度は、術後13〜18か月でアクリルソフトレンズを裏表正しく嚢内固定した僚眼に比して平均14%低い値を示した。角膜内皮細胞密度の減少率は2%以下の低い値であった。1例で部分的な瞳孔捕獲を認めたが,いずれの症例でも,前房出血,遷延性虹彩炎,フィブリン反応,眼圧上昇,角膜浮腫,黄斑浮腫などの合併症,視力に影響を与える後発主内障の発生は認めなかった。
眼球打撲後に発症した中心性漿液性網脈絡膜症様症例
著者: 藤本正流 , 梅山圭以子 , 松島正史
ページ範囲:P.395 - P.399
(P−1-106) 鈍的眼球打撲が原因と思われる中心性漿液性網脈絡膜症様黄斑部変化の1例を経験した。症例は42歳男性,主訴は左眼の中心暗点で打撲直後からの発症であった。初診時視力は左眼0.3(矯正不能)で,黄斑部に2乳頭径の網膜剥離を認めた。フルオレセイン蛍光眼底写真では,造影初期に黄斑周囲に脈絡膜蛍光の低い部分を認め,斑状の過蛍光とその一部から蛍光漏出点を認めた。通常の中心性漿液性網脈絡膜症は脈絡膜循環障害が存在し,二次的に網膜色素上皮が障害され発症するとされるが,鈍的外傷の場合は打撲による脈絡膜循環障害と同時に起こった網膜色素上皮の直接障害が関与しているものと考えられた。
標的黄斑症の黄斑部機能評価
著者: 篠田啓 , 大出尚郎 , 石田晋 , 川島晋一 , 松崎忠幸 , 角田和繁 , 三田真史 , 桂弘
ページ範囲:P.401 - P.406
(P−1-141) 標的黄斑症における黄斑部機能評価を複数の検査法にて行った。中心視力が良好な3例6眼に対し,ハンフリー視野(HP)中心30度および10度,多局所網膜電図(m-ERG),走査レーザー検眼鏡による微小視野計測(SLO microperimetry)を行い,眼底所見との対応を比較検討した。いずれも検眼鏡的には中心窩領域に正常な網膜が残っており,HP10度では2例で,SLO microperimetryでは全例で中心に島状に感度良好な領域を認めた。m-ERGでは眼底所見上の病巣部で非病巣部に比して振幅の低下と潜時の延長を認めた。またHP30度、SLO microperimetry,m-ERGの結果から,眼底所見より広い範囲での機能障害の存在が推定された。
加齢黄斑変性に対する光凝固治療
著者: 廣石悟朗 , 馬場恵子 , 塩瀬聡美 , 吉田綾子 , 江島哲至 , 本多薫 , 本多貴一 , 石橋達朗 , 坂本真紀
ページ範囲:P.407 - P.412
(P−2-99) 脈絡膜新生血管が中心窩外にある加齢黄斑変性への光凝固の効果を,1997年までの5年間の自検例66例66眼について検討した。波長595nmのレーザー光凝固後,6か月以上経過が追えたものとした。視力は,改善が14眼(21%),不変29眼(44%),悪化23眼(35%)であった。脈絡膜新生血管の大きさが1乳頭面積以内の症例で有意に良好な視力が得られ,網膜色素上皮剥離と網膜下増殖組織がある症例で視力の転帰が不良な傾向があった。中心窩と新生血管の距離が500μm以上の症例で視力改善率が良い傾向があった。視力低下の自覚から光凝固までの期間,治療後の期間,光凝固実施時の視力,年齢は,視力の転帰とは無関係であった。
ステロイド懸濁液の鼻腔粘膜内注射直後に片側の網膜および脈絡膜血管塞栓がみられた1症例
著者: 高木康宏 , 木許賢一 , 今泉雅資 , 中塚和夫
ページ範囲:P.413 - P.415
(P−1-125) 49歳女性が嗅覚障害の治療として,酢酸メチルプレドニゾロン懸濁液0.5mlの左鼻腔内注射を受けた。その直後から左眼の暗黒感と複視が生じ,その10分後に眼科を受診した。左眼視力は1.2で,眼底の網膜血管末梢に多数の塞栓があり,周囲に軟性白斑があった。橙色の点状病巣が眼底後極部の深層にあり,脈絡膜血管の塞栓と診断した。1週間後,これら眼底病変は特発性に消失し,他の異常も生じなかった。鼻腔内に注射したステロイド懸濁液が血管に入り,網脈絡膜血管の塞栓を起こしたものと解釈された。
肝膿瘍を原発とした転移性眼内炎の1例
著者: 成田亜希子 , 舩田雅之 , 村田吉弘 , 飴谷有紀子 , 石野剛 , 坂谷慶子 , 井庭香織 , 玉井嗣彦
ページ範囲:P.417 - P.421
(P−2-1) 64歳男性に高熱が突発し,肝膿瘍と診断された。複数の抗生物質の投与を受けた。熱発から3日後に両眼飛蚊症と左眼視力障害が生じ,その3日後に受診した。矯正視力は,右0.6,左手動弁であり,右眼に虹彩炎,左眼に強い眼内炎の所見があった。転移性眼内炎と診断し,抗生物質の点眠結膜下注射,全身投与を行い,左眼に2度の硝子体切除術を行ったが,眼球癆に至った。肝膿瘍からKlebsiella pneumoniaeが同定された。肝膿瘍からの転移性眼内炎はグラム陰性菌によることが多く,早期診断と早期治療が必要なことを本例は示している。
YAGレーザー後嚢切開術後に生じた網膜裂孔と網膜剥離
著者: 金沢佑隆 , 大庭啓介 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.423 - P.426
(P−2-114) Nd:YAGレーザーによる後嚢切開術に,網膜裂孔と網膜剥離が5眼5例に生じた。後嚢切開術から裂孔などの発症までの間隔は,2か月が3眼,4か月と2年が各1眼であった。裂孔は,黄斑円孔3眼,弁状裂孔2眼であった。5眼中3眼に,高度近視,網膜剥離の既往,網膜変性などの危険因子があった。このような合併症の可能性のために,Nd:YAGレーザーによる後嚢切開術の前後には,十分な眼底検査が望まれる。
奈良県立医科大学における未熟児網膜症の検討
著者: 菅波絵理 , 原徳子 , 松浦豊明 , 原嘉昭 , 西信元嗣
ページ範囲:P.427 - P.431
(P−2-141) 1998年までの約14年間に眼底検査を行った低出生体重児852例での未熟児網膜症を検討した。出生体重は424gから2,492g,平均1,601gであり,在胎週数は24週から38週,平均31.8週であった。未熟児網膜症は852例中262例(30.8%)にあり,うち71例(83%)が治療を必要とした。治療を行ったのは138例中14例(10.1%)(1985〜87年),281例中28例(10.0%)(1988〜91年),266例中22例(8.3%)(1992〜95年),167例中7例(4.2%)(1996〜98年)であった。治療の結果は71例中69例(97%)で良好であった。1眼が瘢痕期2度強度,1眼が瘢痕期5度を残した0以上の結果は在胎週数,そして出生体重が少ないほど発症率が高く重症化する傾向にあり,29週以下の在胎週数と1,500g以下の出生体重のときに未熟児網膜症が急増することを示している。
連載 今月の話題
免疫不全とぶどう膜炎
著者: 望月學
ページ範囲:P.287 - P.290
サイトメガロウイルス(CMV)網膜炎は,かつてはAIDS患者の約40%に合併し、その治療に苦慮した。一方,1990年代半ばに登場したHIVプロテアーゼ阻害薬と従来の抗HIV薬を併用するhighly active antiretrovirus therapy(HAART)により,末梢血HIVウイルス量の減少とCD4陽性リンパ球数の上昇などの細胞性免疫の回復が得られるようになった。これに伴い,AIDSにおけるCMV網膜炎罹患率は半減し,さらに,CMV網膜炎の再発も著しく減じた。ごく最近,HAARTにより細胞性免疫が回復したAIDS患者のCMV網膜炎罹患眼に,CMV網膜炎の再発とは異なる硝子体炎を主症状とするぶどう膜炎(immune recovery uveitis)が生じることが話題となっている。このようなAIDSとCMV網膜炎に関する最近の話題についてレビューした。
眼の組織・病理アトラス・161
結核性脈絡網膜炎
著者: 猪俣孟
ページ範囲:P.294 - P.295
結核tuberculosisは,かつてわが国の国民病ともいわれていたが,今では患者数が激減した。しかし,老人ホームで結核が集団発生するなど高齢者結核が問題になっている。また,エイズ患者や悪性リンパ腫でステロイド薬の治療が行われた免疫不全患者にも比較的高頻度に発症している。
眼結核の多くは肺の初感染巣から結核菌が血行性にぶどう膜組織に到達して起こる二次感染によって発症する。その他に,結膜ブリクテンや網膜血管炎などは免疫反応によって生じる。
眼の遺伝病・7
ペリフェリン/RDS遺伝子異常による網膜色素変性(2)—ペリフェリン/RDSとはなにか
著者: 玉井信 , 和田裕子
ページ範囲:P.298 - P.300
網膜変性を示す動物種はイヌやヒツジなどいくつか知られているが,現在研究に広く使われているものはラット(1種類)とマウス(2種類)である。そのうちのrds (retinal degeneration slow)マウスと呼ばれるモデル動物から網膜変性の原因遺伝子peripherin/RDSが発見された。この遺伝盲マウスでは視細胞のみが生後3週目から変性しはじめ,1年以内に消失する(図1)。この動物についての研究から原因となる遺伝子はマウス17染色体にあり,視細胞外節円板膜に関係した39kDaの糖タンパク質で,牛視細胞膜タンパク質“periph-erin”と92.5%の相同性を持つことからperiph-erin/RDS蛋白または同遺伝子と呼ばれるようになった1〜3)。この糖タンパク質は346個のアミノ酸からなり,円板膜を4回貫通し,アミノ基とカルボキシル基がともに円板膜の外,すなわち視細胞の細胞質内に,また2つのループは円板内(細胞質外)に存在する(図2)。このタンパク質の機能は正確には明らかにされていないが,錐体にも桿体にも存在し,図3に示すような構造で,円板の縁に近く存在することから,円板膜の安定性に寄与しているといわれている。これと30%の相同性を持っROM1(rod outer segment membrane protein1)と呼ばれるタンパク質と協同して,その安定性に関与していると考えられる4〜6)。
眼科手術のテクニック・123
網膜剥離における周辺硝子体処理(2)
著者: 石郷岡均
ページ範囲:P.302 - P.303
5 格子状変性部の硝子体処理
周辺部の格子状変性など硝子体癒着の強い部位は,必ず前部硝子体と分離・切断しておく。前部硝子体との切断が不十分な変性部では,残存した硝子体の変性萎縮により,術後3か月以内に硝子体牽引の増強による新裂孔形成および網膜剥離再発となる可能性が高い。
格子状変性上の硝子体は液体化していることが多いが,その周囲には硝子体の強い癒着があり,この部位にかかる牽引は主に対側の前部硝子体基底部方向が中心である(図4)。
他科との連携
最近の教訓
著者: 田村正人
ページ範囲:P.442 - P.443
このたび医学書院の方から「他科との連携」で原稿依頼を受けましたが,思い浮かぶのは連携ミスで反省させられたことばかり……。「他科との連携」は取れて当たり前,取れなかったときに,場合によっては事故に結びついてしまいます。
最近の教訓を2,3……。
今月の表紙
未熟児網膜症の眼底所見
著者: 鶴岡祥彦 , 根木昭
ページ範囲:P.291 - P.292
未熟児網膜症による失明を防止する方法として光凝固治療が著効することを永田らが1968年に報告して以来,筆者らは天理よろづ相談所病院で数多くの未熟児網膜症を経過観察し,治療を必要とする重症例を選別して光凝固治療を行ってきた。当時の1例1例は,光凝固を実施する適切な時期を知り,どこをどの程度光凝固することが必要かについて経験を積むために大変貴重であった。Insidious typeとrush typeと混合型を経験し,光凝固実施時期と実施方法は症例ごとに工夫をしていた。また,臨床的情報を伝達する手段に写真撮影は重要と考え,未熟児網膜症の眼底所見を撮影するために筆者らは手持ち眼底カメラによる倒像眼底写真撮影法を開発した1)。未熟児網膜症の活動期病変の眼底写真は昭和47年(1972年)に臨床眼科に出した筆者らの論文2)が世界で最初のものであった。もちろん,倒像眼底写真撮影法で撮影されたものであった。そして筆者らが撮影した未熟児網膜症の写真はその後,未熟児網膜症活動期病変の厚生省研究班分類の基礎を作るのに貢献した。今月の表紙写真は倒像眼底写真撮影法で撮影したものである。当時この眼底所見は,なるべくその日のうちに光凝固が必要と判断され,良い視力を得るためにはこれより進行してからの光凝固は遅いと判断される時期の眼底写真であった。当時の光凝固治療の実際については「眼科マイクロサージェリー第4版」(1999年7月24日発行)に記載されている。30年を経過して,光凝固装置の光源はキセノンからレーザーに替わったが,筆者らの判断は適切であったと考えている。
第53回日本臨床眼科学会専門別研究会1999.10.10東京
Closed Eye Surgery
著者: 三宅養三
ページ範囲:P.432 - P.433
第53回日本臨床眼科学会における「専門別研究会」の1つであるClosed Eye Surgeryは10月10日(日)の午前9時から12時までホールB (1)で,満員の盛況で行われた。以下,順にその講演要旨を記す。
第1席は名古屋大学の鈴木 聰氏による「網膜色素変性症への電気的人工網膜の応用」であり,留学先のWilmer Eye Instituteでde Juan教授らと行われた研究成果の発表であった。網膜局所を電気で刺激していわゆるphospheneを感知させ視細胞が機能消失している網膜色素変性症の患者がどのようにそれを認知できるかの臨床実験であった。患者はこの実験のためにvitrectomyを受けることを受託し,医師の質問に手術による実験中にはきはき答えているのがビデオで示され,大変印象的であった。将来電気刺激による人工眼を開発するにあたり,大変貴重な実験となろう。
視野
著者: 高橋現一郎
ページ範囲:P.434 - P.436
1.Frequency doubling technologyの緑内障スク リーニング能力の検討
斉藤守(東京医大)・他
Frequency doubling technology (FDT)の緑内障スクリーニング能力につき,ハンフリー視野(HFA)測定結果と比較検討した。FDTは,Aulhorn分類2期以降のスクリーニングとして特に有用であり,HFAより早期異常が検出されたという結果であった。矯正用眼鏡の使用の有無(松本.近畿大),乱視の影響(山崎・日大)(岩瀬・多治見市民病院)につき質問があり,常用眼鏡使用による影響および乱視の影響はないとの回答があった。また,偽陽性が再検査で消失した症例があったかとの質問があり(鈴村・都立大塚),一部にそのような症例があったとの回答であった。
やさしい目で きびしい目で・3
迷路の出口
著者: 久保田伸枝
ページ範囲:P.437 - P.437
日曜日の朝,東京新聞サンデー版の「どこが違う?」と「迷路」とを解くのを楽しみにしている。
左右の2つの図の間違いを8つ見付ける「どこが違う」は,妹とどちらが早く解答できるか競争している。一方,「迷路」はかなり複雑なもので,途中で投げ出したくなるほどである。ある日,出口から逆にたどってみたら意外に簡単に解けることが分かった。
臨床報告
エキシマレーザーによる屈折矯正手術の術後成績と患者の満足度調査
著者: 越智利行
ページ範囲:P.451 - P.457
過去14か月間にエキシマレーザーによる屈折矯正手術を受けた534例1,019眼の経過を追跡した。屈折矯正角膜切除術(PRK)が626眼に行われ,角膜内皮切削形成術(LASIK)が393眼に行われた。手術時の年齢は,両群とも平均34歳である。患者の満足度の調査はアンケートによった。PRK群では術後8〜14か月,LASIK群では術後1〜7か月である。矯正精度は,予想屈折値の±1.0以内のものがPRK群では91%以上,LASIK群では98%以上であった。アンケートに対する有効回答は308例(57.5%)で得られた。84%が術後視力に対してはほぼ予想通りと回答し,92%が手術結果について満足と回答した。屈折矯正手術に対する否定的な回答はなく,半数以上が「手術は有効で医療の進歩に感謝している」と回答した。
脊髄小脳変性症の角膜内皮細胞密度と網膜電図の検討
著者: 山田教弘 , 阿部俊明 , 玉井信
ページ範囲:P.459 - P.463
脊髄小脳変性症患者63人106眼を7群に細分化し,角膜内皮細胞密度と網膜電図を検索した。白内障以外に眼疾患のない43人78眼を対照とした。患者の平均年齢は各群で40歳台から50歳台であり,各群の間に有意差はなかった。角膜内皮細胞密度は,spinocerebellar ataxia type 1(SCA1)とdentatorubropallidoluysian atrophy(DRPLA)の2群で他の群よりも有意に低下していた。網膜電図はすべての群で律動様電位(OP)1が有意に増加し,SCA1でのOP2とOP3の振幅が対照より有意に低下していた。SCA1に属する4人7眼には視神経萎縮のある症例があったが,他は検眼鏡的に網膜は正常で矯正視力も良好であったため,網膜内層に何らかの障害が存在することが推測された。
若年糖尿病患者の水晶体混濁の定量的検討
著者: 塩川あずさ , 加藤聡 , 大原こずえ , 北野滋彦 , 堀貞夫 , 湯口琢磨 , 海谷忠良
ページ範囲:P.464 - P.468
矯正視力が1.0以上で,細隙灯顕微鏡で白内障がない40歳未満の若年糖尿病患者64例64眼について,水晶体混濁を定量的に測定した。各症例での検査眼は無作為に選んだ。水晶体混濁は,Scheimpflugの原理による前眼部解析装置で定量化した。同様の条件を満たし,糖尿病のない14例23眼を対照とした。水晶体混濁は非糖尿病群よりも糖尿病群で,糖尿病群では網膜症がない群よりもある群で有意に増加していた(いずれもp<0.05)。糖尿病群での散乱光強度の積分値は,その多変量解析では,年齢と網膜症の程度と有意な相関があった(いずれもp<0.05)。以上の結果は.若年糖尿病患者では水晶体混濁が潜在的にあることと,これが網膜症の程度とともに増加することを示す。
神奈川県足柄上地区の糖尿病網膜症
著者: 岩城浩文 , 安藤展代 , 奥津紀一
ページ範囲:P.469 - P.474
足柄上医師会は,10年間にわたり神奈川県足柄上地区(人口11万人)の糖尿病患者を登録管理してきた。患者数は人口の2.1%,40歳以上人口の42%,糖尿病網膜症(以下,網膜症)の合併率は年平均10.7±0.4%であった。網膜症合併患者の年平均35.8%が安藤眼科医院を受診しており,病型(福田分類)は,A群73.3±4.3%,B群26.7±4.3%であった。1991年までの網膜症眼はそれ以降に比して低視力(0.4以下)が有意に多かった。1997年に視力0.4以下だった網膜症眼は243眼中75眼(30.9%)であり1うち48眼(64.0%)は黄斑病変による視力低下であった。243眼の網膜症(1997年)に対して,網膜光凝固術が180眼(74.1%)に,硝子体手術が9眼(3.7%)に行われていた。
網膜血管腫に続発した黄斑部網膜上膜と牽引性網膜剥離が自然寛解した1例—光干渉断層計(OCT)所見
著者: 西野和明 , 梅本亨 , 齋藤三恵子 , 齋藤一宇 , 竹田宗泰 , 奥芝詩子
ページ範囲:P.475 - P.478
67歳の男性が数か月間持続する左眼の変視症を主訴として来院した。矯正視力は0.3であった。左眼の眼底検査と光干渉断層計(OCT)にて,黄斑上膜に付着した硝子体の牽引による網膜剥離が黄斑部に確認された。耳側網膜の赤道部には孤立性の2乳頭径大の隆起した網膜血管腫がみられた。この網膜剥離による変視症を改善する目的で硝子体手術を予定していたが,初診日から40日後,矯正視力が0.7と向上したため再度眼底検査とOCT検査を行ったところ,後部硝子体剥離に伴い網膜皺襞,網膜血管の牽引は消失するとともに,黄斑部の網膜剥離も軽減し,また黄斑上膜の一部が硝子体に付着したまま剥離している所見が得られた。
カラー臨床報告
特発性脈絡膜新生血管(中心性滲出性脈絡網膜症)の光干渉断層計所見
著者: 飯田知弘 , 萩村徳一 , 佐藤拓 , 須藤勝也 , 岸章治
ページ範囲:P.445 - P.450
特発性脈絡膜新生血管(中心性滲出性脈絡網膜症)18眼を,光干渉断層計(OCT)を使って検索した。全例が片眼性であり,男6例,女12例で,年齢は21〜48歳,平均34.8歳であった。脈絡膜新生血管膜(CNM)が網膜色素上皮層の内方に土塁状に進展している断層像が8眼で得られ,これはGass分類のtype 2に相当した。8眼中6眼では,CNMの退縮に伴って,その反射が色素上皮・脈絡毛細管板の高反射層と一体化した。他の10眼では,初回の検査時から色素上皮層と一体化している紡錘形の高反射があった。全18眼中3眼で,CNMの表面が色素上皮層に連続する高反射を呈した。全18眼中15眼に検眼鏡などで漿液性網膜剥離が観察され,OCTでは17眼に網膜浮腫,9眼に網膜剥離が同定された。
基本情報
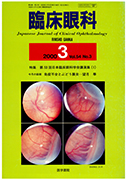
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
