(D−7PM−5) 緑内障における網膜神経線維層(RNFL)厚と静的視野との相関性について検討した。対象は正常者6例6眼,高眼圧症患者7例7眼,緑内障患者46例72眼で,光干渉断層計(OCT)による視神経乳頭周囲のRNFL厚を測定し,ハンフリー視野計のプログラム24-2の結果との相関性を調べた。
全象限のmean deviation(MD),mean sensitivity(MS)とRNFL厚との間には非線形的な関係が得られ(r=0.66〜0.68),MDが−5dB以上の視野とRNFL厚の相関性は−5dB未満の視野に比べ弱かった。上下半視野のMSとRNFL厚の関係においても前者の相関性が後者に比べ弱くなったが,早期緑内障視野では視野を細分割してRNFL厚との相関性を調べると,上耳側と下耳側で良好な相関性を示した。RNFL厚と静的視野との間には非線形的な関係がみられた。早期緑内障視野ではRNFL厚との相関性が弱いが,視野を細分割して相関性を調べることが有用であった。
雑誌目次
臨床眼科54巻5号
2000年05月発行
雑誌目次
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
原著
緑内障における網膜神経線維層厚と静的視野の関係
著者: 朝岡亮 , 尾﨏雅博 , 高田真智子 , 立花和也 , 臼井正彦
ページ範囲:P.769 - P.774
ウノプロストン(レスキュラ®)点眼によって生じた眼瞼多毛症
著者: 仙波晶子 , 豊永美江 , 西岡木綿子 , 大島裕司 , 久保田敏昭
ページ範囲:P.775 - P.778
(D−7PM−13) 緑内障治療薬としてイソプロピルウノプロストン点眼による多毛症の発症率を知るために,ウノプロストン点眼を行っている82症例157眼を対象に外眼部の観察を行った。19症例32眼(20%)に多毛症を認めた。多毛症が出現したのは,男性40症例74眼のうち6症例9眼(12%),女性42症例83眼のうち13症例23眼(28%)で,男性よりも女性に有意に多くみられた。40〜80歳台の各年齢層間にその発生頻度に差はなく,多毛症発現の割合は各年齢ともに20%前後であった。また,多毛症の割合は,イソプロピルウノプロストン単剤投与では全65眼中15眼(23%),多剤投与では全92眼中17眼(19%)であり,単剤投与での発現頻度が高い傾向にあった。
前眼部ICGを用いた房水流出経路の観察
著者: 須田雄三 , 吉田紳一郎 , 松島博之 , 藤原慎太郎 , 松井英一郎 , 菊池通晴 , 小原喜隆
ページ範囲:P.779 - P.782
(D−7PM−15) 白色家兎4頭4眼に線維柱帯切除術を行った後,前房にインドシアニングリーン(ICG)を注入し,走査型レーザー検眼鏡(SLO)で外眼部のICG造影を行った。穿孔性線維柱帯切除術では,濾過胞内にICGの貯留があったが,穿孔部周辺の上強膜静脈の造影はなかった。非穿孔性線維柱帯切除術では,強膜弁のある12時側に上強膜静脈の造影があった。この方法で房水流出路の観察が可能であった。濾過手術後早期の房水流出路は,濾過胞内圧,上強膜静脈圧,前房内圧の相互関係で決定されると推定された。
マイトマイシンC併用線維柱帯切除術における術後眼圧定量化の指標
著者: 忍田太紀 , 山崎芳夫
ページ範囲:P.785 - P.788
(D−8AM−9) 初回手術としてマイトマイシンC (MMC)併用線維柱帯切除術を施行した原発開放隅角緑内障50例61眼を対象に術後眼圧調整率,術後早期眼圧と長期予後の関係,眼圧長期予後に影響する因子について検討した。目標眼圧15mmHgとした場合,術後72か月の眼圧調整率は無治療で60.0%であった。術後1週間の平均眼圧15mmHg未満の群では15mmHg以上の群より有意に長期予後が良好であった。Cox比例hazard modelを用いた解析から無治療目標眼圧を15mmHg未満としたとき,眼圧長期予後に影響する因子としてMMC塗布時間が選択された。MMC併用線維柱帯切除術では術中の十分なMMC塗布と術後早期の眼圧を15mmHg未満にコントロールすることが重要と思われた。
円錐角膜に対する深層角膜移植術の成績
著者: 谷本誠治 , 長谷部治之 , 増本真紀子 , 廣田篤 , 今田昌輝 , 正化圭介
ページ範囲:P.789 - P.793
(D−8PM−10) 円錐角膜7例7眼に対して,角膜厚の3/4を置換する深層角膜移植術を7年余の期間に行った。年齢は平均25歳,観察期間は平均25.7か月であった。術中合併症として,デスメ膜穿孔が3眼,層間出血が1眼にあり,術後合併症として,一過性の二重前房が1眼,拒絶反応が2眼にあった。矯正視力は術前が平均0.10,術後が平均0.84であった。術後の角膜内皮細胞数は,1,750〜3,000個/mm2であった。若年者での円錐角膜に対して,深層角膜移植術は拒絶反応が少なく,長期にわたって角膜内皮が安定することから,有用な方法であると結論される。
重症筋無力症に対する胸腺摘出術の効果
著者: 中村泰介 , 河野玲華 , 山根貴司 , 松尾俊彦 , 大月洋 , 安藤陽夫
ページ範囲:P.795 - P.798
(G−7PM−4) 胸腺腫がなくステロイド薬に抵抗する眼筋型重症筋無力症4例に胸腔鏡下拡大胸腺摘出術を行った。年齢は54歳から69歳,平均62歳であった。重症筋無力症の手術までの持続期間は4か月から288か月であった。術後57か月まで経過を追跡した。全身症状は2例で治癒,2例で改善した。眼症状では,全例で眼瞼下垂が消失し,眼球偏位が改善した。複視は2例で残存し,うち1例は長期罹患例であった。以上の成績から,薬物に抵抗する眼筋型重症筋無力症に対して早期の胸腺摘出術が有効でありうることが結論される。
Alport症候群の眼内レンズ挿入術術後の期経過および前嚢の組織学的検討
著者: 後藤真里 , 大久保真司 , 石坂伸人 , 安藤佳奈子 , 山下陽子 , 柳田隆 , 武田久 , 小田恵夫
ページ範囲:P.799 - P.802
(G−7PM−9) Alport症候群の前円錐水晶体および前極白内障に対して白内障手術を行い,術後経過を長期観察し,また採取した前嚢を電顕にて検討した。症例は54歳男性で,1992年9月に左眼,1999年2月に右眼の前円錐水晶体および前極白内障に対してPEA+IOLを行った。電顕では前嚢全体が菲薄化し,亀裂様の電子密度の低い領域がみられ,前円錐水晶体は前嚢の脆弱性が原因であると考えられた。左眼のIOLは術後6年以上経過した現在でも嚢内に良好に固定されており,本症候群におけるIOL嚢内固定は問題ないと考えられた。
小児の視神経炎に網膜前出血を併発した多発性硬化症の1例
著者: 篠原泉 , 田中稔 , 篠崎久美 , 金子堅一郎
ページ範囲:P.803 - P.806
(G−8AM−15) 4歳の女児が高熱,意識障害とけいれん発作ののち複視を生じて受診した。矯正視力は右0.6,左0.7で,右眼に上斜視があり,水平眼振があった。眼底などには異常はなかった。小脳症状,滑車神経と聴神経麻痺,脳の画像診断などから多発性硬化症が疑われた。ステロイド薬の全身投与開始2週後に左眼痛が生じた。左眼に視神経乳頭炎と網膜静脈の蛇行があり,その2日後に左眼後極部一帯に網膜前出血が生じた。さらにその1か月後に右眼に視神経乳頭炎が発症した。ステロイド薬の全身投与を続けた。両眼とも最終的に寛解し,視力が回復した。左眼の網膜前出血は網膜血管炎によると解釈された。
抗リン脂質抗体症候群に伴う球後視神経炎の1例
著者: 吉田紀子 , 栗本康夫 , 吉村長久
ページ範囲:P.807 - P.811
(G−8PM−3) 31歳女性の右眼に視力低下が5日前に突発した。4年前に抗リン脂質抗体症候群と診断されている。右眼視力は手動弁で,中心暗点があった。CTとMRI検査で右視神経の腫脹があり,蛍光眼底造影で造影遅延などの異常がなく,球後視神経炎と診断した。ステロイドパルス療法開始5日後に,視力は1.2に回復した。血液の抗核抗体が陽性であり,ステロイド薬が奏効したことから,自己免疫性の球後視神経炎であると推定した。
硝子体同時手術における白内障手術の検討—遡及的研究
著者: 谷口寛恭 , 元田正憲 , 三島一晃 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.812 - P.816
(R1-7AM−11) 過去5年間の硝子体手術の際に水晶体摘出術と眼内レンズ挿入術を行った202眼を遡及的に評価した。白内障単独手術を行った308眼を対照とした。同時手術群では,一過性眼圧上昇が61眼(30%),後発白内障が48眼(24%),フィブリン析出が35眼(17%),眼内レンズ偏位が7眼(2%)にあった。対照群では,それぞれ6%,19%,1%,2%であった。同時手術ではこれらの合併症が起こりやすいが,重篤ではなく,必要があればこれを行う利点が大きいと結論される。
翼状片術後のトラニラスト点眼とアルキル化剤による再発予防の有効性の検討
著者: 笹木昇 , 安木一雄 , 福島正大
ページ範囲:P.817 - P.818
(R1-7PM−11) 翼状片術後の138症例167眼に対するトラニラスト点眼後の再発を検討した。術後全員に抗生物質・消炎鎮痛薬を1週間内服投与し,抗生物質・ステロイド薬点眼を1か月投与した。62症例76眼はアルキル化剤を追加点眼し(1群),25症例30眼はトラニラストを追加点眼し(2群),51症例61眼(再手術5眼)はアルキル化剤・トラニラストを追加点眼した(3群)。1群は5症例5眼に再発(再発率7%),2群は7症例12眼に再発(再発率40%),3群は2症例2眼に再発(再発率3%)を認めた。トラニラストは単独投与では再発予防効果がアルキル化剤に比べて弱いが,アルキル化剤と併用することで.より再発予防効果が得られることを確認した。
白内障手術による角膜不正乱視の変化
著者: 田邊樹郎 , 大鹿哲郎 , 天野史郎 , 富所敦男 , 鮫島智一 , 宮田和典
ページ範囲:P.821 - P.824
(R1-8PM−4) 角膜形状解析装置で測定した投影リング上の屈折力データ列をフーリエ変換し,角膜中心約3mmでの球面成分,正乱視成分,不正乱視成分(非対称成分,高次不正乱視成分)を分離定量する方法で,白内障手術後の角膜不正乱視を定量的に検討した。対象は老人性白内障患者60名60眼で,6.0mm強膜切開創,4.1mm強膜切開創,3.5mm強膜切開創の3群に各20眼ずつ無作為に振り分けて手術を行い,術前,術後1か月の2点で解析した。6.0mm切開創群で正乱視(p=0.026, paired t-test)と高次不正乱視成分(p=0.018)が有意に増加していたが,他の群では手術による有意な変化はみられなかった。術前からの変化量を3群間で比較したところ,高次不正乱視成分において3群間に有意差が認められ(p<0.05,一元配置分散分析),6.0mm切開創群の値が4.1mm切開創群より高い値であった(p<0.05,Bonferroni検定)。以上の結果から,創口幅により角膜正・不正乱視の惹起量が異なることが結論された。
白内障術後のモノビジョンによる満足度
著者: 井上俊洋 , 清水公也 , 新井田孝裕 , 新田任里江 , 嶺井利沙子
ページ範囲:P.825 - P.829
(R1-8PM−8) 白内障術後に眼鏡なしで生活できることを目的とし,眼内レンズの度数に左右差をつけることによるモノビジョン法を試みた。術後良好な近見および遠見裸眼視力を得た16例に対し,術前の眼優位性と術前後の立体視,融像幅を測定し,術後眼鏡の必要性との相関について検討した。術後眼鏡が不要であった症例は16例中14例(88%)であり,眼鏡を必要とした症例群に比較して両眼視機能が良好な傾向にあった。上下および回旋斜視のあった1例はモノビジョン法に対して不満足であった。眼内レンズによるモノビジョン法は老視の治療法として有効であると考えられたが,術前に両眼視機能の低い症例は慎重な適応の決定が必要である。
短眼軸長眼における2枚重ね眼内レンズ挿入術の臨床成績
著者: 今村明香 , 大鹿哲郎 , 天野史郎 , 江口秀一郎 , 恩田健 , 福山誠 , 中山幸 , 恵美和幸
ページ範囲:P.831 - P.834
(R1-8PM−13) +30ジオプトリー以上の挿入眼内レンズ度数が必要と術前に予想された短眼軸長眼6例9眼に対して,超音波水晶体乳化吸引術およびアクリルソフト眼内レンズ2枚の嚢内固定を行った。全症例において特記すべき術中合併症はなく,嚢内に2枚の眼内レンズが挿入された。術後裸眼視力,矯正視力ともに有意に改善し,また等価球面度数は正視に近づいたが,すべての症例で予想より遠視側に度数がずれた。虹彩後癒着が3眼,軽度の眼内レンズ間混濁が3眼にみられたが,術後6か月を通じてその他に特記すべき術後合併症は認めなかった。短眼軸長眼に対する2枚重ねpiggyback法は有用であるが,必要度数の正確な予想が困難で,現行の計算システムをそのまま用いると予想度数は過小評価され,術後度数は遠視側にずれる。
真菌性眼内炎の起因菌におけるフルコナゾール耐性Candida属の増加
著者: 草野良明 , 大越貴志子 , 佐久間敦之 , 安田明弘 , 折原雄一 , 山口達夫
ページ範囲:P.836 - P.840
(R1-9AM−2) 1995年から1999年までに当院眼科で精査した真菌血症20例について,起因真菌,眼内炎合併の有無,使用した抗真菌薬,予後などを調査し,1988年から1990年までの真菌血症19例と比較検討した。1988年から1990年までの19例の真菌血症の9例11眼(47%)で真菌性眼内炎を認め,起因菌はいずれもCandida albfcansであり,全例フルコナゾールもしくはミコナゾール投与にて治癒した(1例1眼で硝子体手術を併用)。一方,1995年から1999年までの真菌血症20例中,16例31眼(80%)で真菌性眼内炎を認めた。起因菌としてフルコナゾール耐性のC.albicans (2例)や,C.albicans以外のCandida属(9例)が増加し,63%で治療にアンフォテリシンB投与による治療を要した(2例3眼で硝子体手術を併用)。今回の検索により,近年,フルコナゾール耐性のC.albicansやnonalbicans candida属による真菌性眼内炎が増加していることが判明した。今後,真菌性眼内炎起因真菌の薬剤感受性を考慮した治療薬の選択がより一層大切であると思われる。
眼トキソカラ症におけるToxocaraCHEKの有用性
著者: 田口千香子 , 杉田直 , 棚成都子 , 浦野哲 , 吉村浩一 , 疋田直文 , 山川良治 , 高瀬博 , 望月學 , 赤尾信明
ページ範囲:P.841 - P.845
(R1-9AM−4) ToxocaraCHEKを用いて血清と眼内液の抗トキソカラ幼虫抗原排泄物に対する抗体を測定し,その有用性についてELISAと比較検討した。対象は眼トキソカラ症の硝子体4例,血清12例と,他のぶどう膜炎と黄斑円孔の硝子体9例を用いた。眼トキソカラ症の硝子体は4例すべて両検査法で抗体陽性であった。血清抗体陽性率は両検査間で有意差はなかったが,疑陽性率はToxocaraCHEKが高く,逆に陰性率はELISAで高かった。その中で血清抗体は陰性で,硝子体抗体のみ陽性を示したものが1例あった。また,対照群の硝子体は両検査法ですべて陰性であった。以上からToxocaraCHEKはELISAとほぼ同等の感度があり,検査は迅速かつ簡便なため有用であり,また硝子体サンプルの検査が診断率向上に有用であると考えられた。
内境界膜下血腫の除去
著者: 小原智子 , 原田隆文 , 木戸啓文 , 橋本貴夫
ページ範囲:P.849 - P.854
(V−23) 黄斑部を大きく占拠する内境界膜下血腫10例に内境界膜下血腫除去手術を施行した。手術は,硝子体切除を行ったのち,血腫上の内境界膜を剥離して血腫を吸引,除去した。10例中2例で黄斑部に円孔を認め,SF6ガスタンポナーデを施行した。また,2例で除去した膜を電顕で観察し,内境界膜であることを確認した。血腫の原因は9例が網膜細動脈瘤,1例は不明であったが,全例で合併症もなく視力の改善がみられた。内境界膜下血腫は自然吸収傾向もみられるが,症例によっては内境界膜下血腫除去手術が有効であると考えられた。
マイトマイシンCを併用した翼状片切除術の検討
著者: 坂東純子 , 鈴木智 , 横井則彦 , 稲富勉 , 佐野洋一郎 , 外園千恵 , 木下茂
ページ範囲:P.857 - P.860
(R2-9AM−1) マイトマイシンCを併用する翼状片手術を57眼54例に行った。年齢は22歳から77歳,平均60歳であった。術中に0.04%マイトマイシンCを5分間結膜下組織に作用させた。眼球運動障害のある再発例14眼には角膜上皮形成術を併用した。平均17.4±13.9か月の術後観察期間中の翼状片再発は,初回手術33眼では皆無,再手術24例では2眼にあった。初回手術の1眼に一過性の角膜潰瘍が生じた。マイトマイシンCを併用する翼状片手術は,初回および再手術例に対して有効で安全であると結論される。
糖尿病黄斑浮腫での硬性白斑の局在
著者: 大谷倫裕 , 岸章治
ページ範囲:P.861 - P.865
(R2-8PM−11)) 糖尿病黄斑浮腫への硝子体手術後,硬性白斑が中心窩に沈着した10眼に対し,それが網膜のどの層に局在するか光干渉断層計OCTによって検索した。硬性白斑は強い反射巣として描出された。硬性白斑は10眼中5眼では網膜内にあり,その前方の境界は網膜表面に接していた。この5眼の最終平均視力は0.3であった。残りの5眼では硬性白斑は網膜内だけでなく網膜下腔にも沈着しており,網膜色素上皮と一体化したプラーク状の高反射帯として観察された。これらの5眼では,術前からあるいは術後に漿液性網膜剥離が観察された。2眼では,硬性白斑を示す高反射巣が剥離した網膜と色素上皮を架橋していた。これらの5眼の最終平均視力は0.08であった。硬性白斑は主に網膜内に凝集するが,中心窩の漿液性網膜剥離を伴う例では網膜下にも沈着することがあり,視力予後が不良である。
黄斑手術における術後視力の比較
著者: 島田宏之 , 磯前貴子 , 李才源 , 佐藤幸裕
ページ範囲:P.866 - P.870
(R2-7AM−11) 特発性黄斑上膜(ERM)123眼,全層黄斑円孔(MH)76眼,滲出型加齢黄斑変性(AMD)59眼に硝子体手術を行った。術後最高視力に影響する術前要因について重回帰分析を行った結果,3疾患とも術前視力が最も高い相関を示した。視力改善は,ERM 59%,MH 78%,AMD 69%,術後0.5以上は,ERM 70%,MH 45%,AMD 22%であった。3疾患とも術後視力は有意に向上していたことから,これらの疾患に対する手術の有用性が確認された。術後に視力を維持・改善できるための術前視力は,ERM 0.9,MH 0.6,AMD 0.3と推定され,これを適応基準とするのが妥当であると考えた。
黄斑浮腫に対する硝子体手術導入後の網膜静脈分枝閉塞症新鮮例の治療と成績
著者: 馬渡祐記 , 小川邦子 , 松井淑江 , 石郷岡均 , 荻野誠周
ページ範囲:P.871 - P.874
(R2-7PM−4) 発症から6か月以内の網膜静脈分枝閉塞症に併発した黄斑浮腫に対しての治療成績を検索した。52例52眼を黄斑浮腫の程度によって3群に分け,軽度群には内服治療,中等度群にはレーザー光凝固,高度群にはレーザー光凝固と硝子体手術を行った。軽度群14眼では,0.8以上の最終矯正視力が全例で得られた。中等度群20眼では,0.7以上の視力が18眼(90%)で得られた。高度群で硝子体手術を施行した15眼では,黄斑浮腫が1〜8か月(平均4.2か月)で消失し、0.7以上の視力が7眼(53%),0.5以上の視力が12眼(80%)で得られ,全例で0.3以上の視力が得られた。高度群で手術ができなかった3眼では,最終視力は0.2以下であった,網膜静脈分枝閉塞症に併発した黄斑浮腫がレーザー光凝固で改善しない症例には,硝子体手術が有効でありうる可能性が示唆された。
水晶体嚢拡張リングの固定作用
著者: 森茂
ページ範囲:P.875 - P.878
(V−7) 水晶体嚢拡張リングを豚眼に挿入して,水晶体嚢赤道部を内視鏡と直視下で観察した。12.3mmのリングは毛様体襞部に接触し,13.0mmのものは毛様体突起部先端に接触し,14.5mmのものは毛様外溝側に位置していた。内視鏡で見た人眼では,12.3mmでは毛様体襞部に接触し,13.0mmでは毛様体溝側に位置していた。以上から,リングが毛様体に接していれば虹彩面に平行方向に固定されるので水晶体破砕吸引手術が安全に行えること,リングが毛様体溝側にあれば矢状面方向に固定されるので眼内レンズが落下する危険が少なくなると結論される。
加齢黄斑変性で自然寛解したプラーク病変
著者: 萩村徳一 , 飯田知弘 , 堀内康史 , 岸章治
ページ範囲:P.879 - P.882
(P−2-101) 加齢黄斑変性が右眼にある71歳男性を約8年間追跡した。初診から4年後に,インドシアニングリーン蛍光造影の後期像での過蛍光斑plaqueが出現した。その境界は不明瞭で,1乳頭径大であった。このplaqueは以後,緩慢に縮小し,眼底の滲出性変化も消失した。境界が不鮮明なpoorly definedpiaqueは新生血管そのものではなく,新生血管発生の場にすぎない所見である可能性がある。
特発性黄斑円孔に行った内境界膜切除術の3方法の比較検討
著者: 北岡隆 , 大庭啓介 , 雨宮次生
ページ範囲:P.883 - P.886
(V−19) 長崎大学医学部附属病院眼科で施行した連続症例23例23眼の特発性黄斑円孔の硝子体手術で,意図的内境界膜切除を3通りの違った方法で行った。鉗子で直接内境界膜を把持し切除する方法が18例18眼,ピックを使用し切除する方法が3例3眼,粘弾性物質を内境界膜下に注入する方法が2例2眼であった。鉗子で切除した症例のうち,1眼で円孔は閉鎖しなかった。ピックを使用する方法および粘弾性物質を使用する方法では,全例閉鎖した。全体の術前対数視力は−0.79±0.29で,術後対数視力は−0.37±0.29であった。閉鎖率および視力改善には有意差はなかった。最終的に切除できる内境界膜の範囲に差はなかったが,ピックもしくは粘弾性物質を使用したほうが内境界膜を一塊として切除できる範囲は広かった。
隅角後退によって引き起こされた眼圧コントロール不良であった1例
著者: 前谷悟 , 二井宏紀 , 三嶋弘 , 岸浩子
ページ範囲:P.887 - P.890
(P−1-35) 56歳男性が左眼の霧視と視野狭窄で受診した。7年前に左前眉部に鈍的外傷を受けた既往がある。2年前に左眼の高眼圧が発見された。緑内障として点眼治療を受けていたが,眼圧は下降しなかった。当科初診時の眼圧は右16mmHg,左25mmHgであった。左眼に上方から耳側に及ぶ150°の隅角後退があった。左眼に耳側下方に及ぶ視野欠損があった。レーザー隅角形成術は効果なく,線維柱帯切除術を行い,眼圧のコントロールが得られた。隅角後退のある緑内障には早期の濾過手術が望ましいことを示す症例である。
緑内障におけるfrequency doubling technologyの特性
著者: 尾﨏雅博 , 堀越紀子 , 後藤比奈子 , 田村陽子 , 岡野正
ページ範囲:P.891 - P.895
(P−1-37) Frequency doubling technology (FDT)はfrequency doubling illusionを応用した新しい視野計である。今回,緑内障における光覚閾値検査とFDTの結果の相関性について検討した。対象は正常者23例23眼,緑内障患者68例68眼で,全症例に対してハンフリー視野計(HFA)の24-2プログラムとFDTのC−20プログラムを施行した。平均測定時間はHFAが669秒,FDTが277秒であった。Mean deviation, pattern standard deviationの比較では有意な相関性を認め(r=0.79,0.86),各測定点での網膜感度の相関性は中心部より周辺部でよくなった。また,緑内障におけるFDTの異常検出率は97.1%,特異性は95.7%であった。FDTの結果では光覚閾値検査との相関性が得られたが,臨床におけるFDTの位置づけについてさらに検討する必要がある。
眼内レンズ交換手術例の検討
著者: 新村美代子 , 武田憲夫 , 古山文子 , 朴栄華
ページ範囲:P.897 - P.900
(P−1-61) 最近3年間に眼内レンズ交換手術を施行した6例6眼について検討した。初回手術後再手術までの期間は5日から4年,平均307日であった。原因は,眼軸長の測定誤差,角膜曲率半径の測定誤差,眼内レンズの用意のミス,眼内レンズ光学部の傷患者の裸眼での遠見視力への不満,患者の裸眼での近見視力への不満がそれぞれ1例ずつであった。眼内レンズ挿入術中に後嚢破損のあった2例では,眼内レンズ交換時に硝子体脱出があり,前部硝子体切除術を必要とした。手術は再手術までの期間が短いほど容易であった。眼内レンズ交換を回避するためには,眼軸長,角膜曲率半径計測の精度を高めるとともに,患者の術後裸眼視力の希望を初回手術前によく聞くことが重要である。
東京医科大学病院眼科における視神経疾患の統計的観察
著者: 小林昭子 , 小森敦子 , 田中孝男 , 原澤佳代子 , 臼井正彦
ページ範囲:P.901 - P.904
(P−1-92) 1998年までの5年間に,視野異常のある内因性視神経疾患83例を遡及的に検索した。内訳は,脱髄性疾患43例(52%),循環障害性20例(24%),薬物中毒14例(17%),遺伝性2例(2%),原因不明4例(5%)であった。特発性視神経炎が最も多かった。エタンブトールを内服中の結核患者29例中11例(38%)に視野障害があり,中毒性視神経症と診断した。特発性視神経炎では,両眼性が片眼性よりも視力転帰が不良であった。
網膜中心静脈閉塞症の黄斑浮腫に対する硝子体手術の手術成績
著者: 大音壮太郎 , 高木均 , 王英泰 , 野中淳之 , 西脇弘一 , 本田孔士
ページ範囲:P.905 - P.908
(P−1-99) 網膜中心静脈閉塞症に黄斑浮腫が生じ,視力が0.1以下の11眼に対して硝子体手術を行った。黄斑浮腫は7眼で6か月以内に消失した。視力は6眼で改善した。網膜中心静脈閉塞症が発症してから6か月以内に手術を行った7眼では5眼で視力が改善し,7か月以降の4眼では1眼で視力が改善した。この差は有意であった(p<0.05)。視力低下が強い黄斑浮腫を伴う網膜中心静脈閉塞症では,早期の硝子体手術によって浮腫の改善と視力の向上が得られることを示す症例群である。
網膜剥離手術後の長期屈折変化
著者: 川崎勉 , 出田秀尚 , 村田正敏 , 石川美智子
ページ範囲:P.909 - P.912
(P−1-119) 強膜バックル術で手術をした網膜剥離125眼の屈折要素の長期変化を検討した。術後の近視化は,エクソプラント群(20眼)では4年で回復し,インプラント群(105眼)では約1Dの近視化が10年以上続いた。角膜屈折力は術後1年以内で増加し,エクソプラント群でその平均値が0.9Dであった。インプラント群では後部硝子体剥離がない例でこれが大きかった。エクソプラント群で術直後に約2Dの乱視ベクトルが生じた。インプラント群では約1Dの乱視ベクトルが6年以上持続し,後部硝子体剥離がある例でこれが大きかった。以上から,エクソプラント群では近視化は回復するが術直後の角膜の形状変化が強いこと,インプラント群ではバックル効果が長期間持続し,約1Dの近視が10年以上続くことが結論される。
脳内多発性肉芽腫症が疑われた網脈絡膜炎の1例
著者: 安宅伸介 , 白木邦彦 , 井上一紀 , 成瀬裕恒
ページ範囲:P.913 - P.917
(P−1-133) 57歳男性が10日前からのふらつきと歩行障害で脳神経外科に入院した。MRIで脳内病変が多発していた。その6日後に左眼に飛蚊症が生じ,眼科に紹介された。矯正視力は両眼1.2,左眼に硝子体に細胞浮遊と乳頭の耳側に出血を伴う0.5乳頭径(DD)の滲出があった。滲出は2週後に1DDに拡大し,視力は0.04に低下した。脳内病巣は最盛期には150個以上あった。開頭手術でastrocyteの腫脹があったが,腫瘍ないし炎症の所見はなかった。抗生物質投与だけで,神経症状,脳内病変,眼底の滲出性病変が改善した。脳と滲出性網脈絡膜炎の病因は不明であったが,同時期に寛解したことから共通した全身病が関連していると推定された。
8歳発症の原発開放隅角緑内障例
著者: 今関亜希子 , 藤本尚也 , 川端秀仁
ページ範囲:P.919 - P.922
(P−2-59) 8歳男児が近視で眼科を受診し,乳頭陥凹の拡大が左眼に発見された。喘息とアトピー皮膚炎があり,ステロイド軟膏を使用していたが顔面には塗布していない。眼圧は右18mmHg,左19mmHgであった。左眼に鼻側下法の視野欠損があり,緑内障が疑われた。左眼圧は4か月後に22mmHgになった。点眼治療を行ったが眼圧は30mmHg台に上昇し,当科を紹介された。緑内障として点眼治療を追加したが,左眼の視野欠損が進行し,その2か月後に線維柱帯切除術を行った。以後7か月間,薬物なしで左眼圧は10mmHg台に維持され,視野欠損の進行もない。患児とその父に,緑内障の遺伝子ミオシリンの変異はなかった。このような若年でも原発開放隅角緑内障が起こりうることを示す症例である。
過去16年間における眼窩腫瘍94例の検討
著者: 荻野晴義 , 吉原睦 , 斉藤紀子 , 加島陽二 , 石川弘
ページ範囲:P.923 - P.928
(P−2-5) 1983年1月から1998年12月までの16年間に日本大学医学部附属板橋病院眼科を初診し,病理診断の確定した眼窩腫瘍94例について,病理組織的および臨床症状について検討した。最近10年間の初診患者に占める割合は年平均で0.093%であった。原発性34例1転移性11例,続発性49例であった。病理組織型では副鼻腔嚢胞が最も多く,次いで副鼻腔癌腫であった。臨床症状は眼球突出が70例と一番多く,次いで眼球運動障害の41例であった。悪性腫瘍では,19例中8例に2方向以上の眼球運動制限と視力低下をきたしている症例がみられ,このような症例では慎重な対処を要すると考えられた。
放射線療法中に一過性の著しい視力低下をきたした眼原発の悪性リンパ腫の1例
著者: 宮尾洋子 , 多田玲 , 小泉範子 , 山田英明 , 木下茂 , 池田恒彦
ページ範囲:P.929 - P.932
(P−2-80) 56歳女性が2年前からの両眼の視力低下で受診した。慢性ぶどう膜炎としてステロイド薬の全身と局所投与を受けていたが寛解しなかった。矯正視力は右0.8,左0.5であった。MRIやGaシンチを含む全身検査では異常がなぐ硝子体細胞診で眼原発の悪性リンパ腫の診断が確定した。1日2Gyの放射線照射の開始後7日目に右眼黄斑下にニボーを伴う滲出物が出現し,右視力は0,07に低下した。ステロイド薬の全身投与では滲出は消失し,13日後の右眼視力は1.0に回復した。本症では放射線照射中に病像が一過性に悪化することがあり,保存的な療法でこれが寛解する場合のあることを示す症例である。
再発を繰り返したLeber特発性星芒状神経網膜炎
著者: 川野敏夫 , 町田拓幸 , 青沼秀実
ページ範囲:P.933 - P.936
(P−2-142) 76歳女性が3日前からの両眼霧視で受診した。視力は右0.15,左0.1であった。両眼に乳頭浮腫,乳頭周囲の網膜浮腫,後極部の漿液性網膜剥離があった。全身検査には異常がなかった。初診から10日後に黄斑に星芒状白斑が出現し,Leber特発性星芒状神経網膜炎と診断した。いったん寛解した後,7か月後に右眼,4年7か月後に左眼に視力障害が再発した。初診から6年後の現在,視力は右0.81左1.2であり,治癒した状態にある。本症では再発があり得ることを示す症例である。
硝子体切除,液空気置換による黄斑下血腫移動術
著者: 木許賢一 , 高木康宏 , 松本惣一セルソ , 瀧田忠介 , 古嶋正俊 , 中塚和夫 , 蔭山誠
ページ範囲:P.937 - P.940
(P−2-104) 63歳男性に右眼の視力低下が突発した。右眼矯正視力は0.1。乳頭縁から中心窩にかけて厚い網膜下血腫があり,加齢黄斑変性によると診断した。発症3日目に硝子体切除術と液空気置換術を行った。血腫は術後3日目から下方に移動しはじめ,視力は術後1週で0.8,1か月で1.0に回復した。併存する網膜色素上皮下血腫には位置の移動はなかった。術後1か月後の黄斑部局所ERGでは,negativeb波のパターンがあり,網膜中層の機能回復が視力回復よりも遅れていることが推定された。新鮮な厚い黄斑下血腫に対して,この手術が有効であることを示す症例である。
光干渉断層計と網膜厚解析装置の比較
著者: 山口由美子 , 大谷倫裕 , 岸章治
ページ範囲:P.941 - P.945
(P−1-134) 黄斑病変を光干渉断層計(OCT)と網膜厚解析装置(RTA)で測定し,中心窩網膜厚(網膜表面から色素上皮までの距離)および網膜断層像を比較した。対象は黄斑病変がある37眼である。網膜内の混濁のため,RTAで中心窩網膜厚が測定できなかった症例は除外した。漿液性網膜剥離はOCTでは11眼が,RTAでは5眼(45%)が観察できた。嚢胞様変化は,OCTでは7眼が,RTAでは6眼(86%)が観察された。37眼中29眼(78%)は,中心窩網膜厚の測定値の差が50μm未満であった。測定値の差が50μm以上あった8眼は全例に漿液性網膜剥離があった。漿液性網膜剥離があると,RTAは神経網膜厚を測定していると考えられた。
網膜内境界膜下に滲出物が蓄積した感染性眼内炎の1例
著者: 中井正基 , 雑賀司珠也 , 岡田由香 , 大川記羊美 , 白井久美 , 宮本武 , 石田為久 , 大西克尚
ページ範囲:P.947 - P.950
(V−18) 50歳男性が左眼視力低下で受診した。2日前に鍬で土壌を耕していて左眼に異物感を自覚している。矯正視力は右1.5,左光覚弁,眼圧は左41mmHgであった。左眼に外傷性白内障と前房蓄膿があった。Bモードエコーとコンピュータ断層撮影で眼内に異物があり,同日,硝子体手術を行った。術中の所見として,内境界膜下に多量の滲出物があり,これの除去に内境界膜剥離が必要であった。眼内レーザーと拡張性ガスによるタンポナーデを行って手術を終わった。手術から4か月の現在,左眼矯正視力は0.08で,炎症所見はない。眼内異物が原因で受傷後早期に発症した眼内炎に対して,速やかな硝子体手術が有効であることを示す症例である。
黄斑部網膜前出血と網膜下出血合併例に対する網膜内境界膜切開と硝子体気体注入術
著者: 毛塚潤 , 中田安彦 , 岩崎琢也 , 臼井正彦
ページ範囲:P.951 - P.955
(P−2-133) 網膜細動脈瘤に続発した黄斑部網膜前と網膜下出血が同時にある3眼に,硝子体内気体注入と内境界膜切開術を行った。1眼では硝子体手術により後部硝子体剥離を作成し,t-PA(プラスミノーゲンアクチベータ)の滴下後にSF6ガスを注入したところ,網膜前出血が増強し,YAGレーザーで内境界膜切開を追加した。第2眼では硝子体手術で内境界膜を切開し,SF6ガスを注入した。両眼とも,出血と硝子体混濁が速やかに消失した。第3眼にはYAGレーザーによる内境界膜の切開とSF6ガスの注入を行ったが,硝子体混濁が長期間持続した。多量の網膜前と網膜下出血が同時にある場合には,早期の網膜内境界膜切開と気体注入術が出血除去に有効であること,術後の硝子体混濁を避けるには硝子体手術の併用が望ましいことが結論される。
硝子体切除術,組織プラスミノーゲンアクチベータとガス注入術を併用した黄斑下血腫移動術
著者: 久代正行 , 大矢佳美 , 小林和正 , 市辺幹雄 , 村上健治 , 斉藤暢子 , 今井和行 , 阿部春樹
ページ範囲:P.956 - P.960
(P−2-107) 黄斑下血腫に対し硝子体切除術,組織プラスミノーゲンアクチベータ(tPA)とガス注入術を併用した黄斑下血腫移動術を行った。対象は加齢黄斑変性症5眼,網膜細動脈瘤6眼で,術式は硝子体切除後,tPAを25〜62.5μg,SF6またはC3F8を硝子体腔に注入し,術後3時間仰臥位ののち24時間伏臥位を施行した。加齢黄斑変性症5眼の全例で血腫の移動が認められたが,網膜細動脈瘤3眼では移動がなかった。術翌日に加齢黄斑変性症1眼,網膜細動脈瘤5眼で硝子体出血が認められ,加齢黄斑変性症1眼,網膜細動脈瘤4眼に硝子体再手術を施行した。本術式では網膜細動脈瘤において術後硝子体出血が生じる可能性が高く,その適応は慎重に検討する必要がある。
外傷性黄斑円孔に対し内境界膜剥離が有効であった2症例
著者: 土田展生 , 西山功一 , 戸張幾生
ページ範囲:P.961 - P.964
(P−2-113) 鈍的外傷による黄斑円孔2眼に対して内境界膜剥離を併用する硝子体手術を,受傷後の5週と7週に行った。両眼とも網脈絡膜萎縮が残ったが円孔は閉鎖した。術前視力はそれぞれ0.4と0.2であり,術後には0.8と0.6に改善した。早期の内境界膜剥離が外傷性黄斑円孔に対して有効でありうることを示す症例である。
糖尿病網膜症と抗リン脂質抗体症候群網膜光凝固術後網膜動脈分枝閉塞症を繰り返した症例
著者: 河村美和 , 中沢陽子 , 鈴木伸
ページ範囲:P.965 - P.968
(P−2-132) 37歳男性が11年前からの糖尿病の眼合併症の検索のために受診した。矯正視力は各眼1.0であった。両眼に前増殖糖尿病網膜症があり,汎網膜光凝固を行った。その52日と57日後に右眼に網膜動脈分枝閉塞症が発症した。左眼には汎網膜光凝固追加の15日後に網膜動脈分枝閉塞症が発症した。全身検査で抗力ルジオリピン抗体が高値であり,抗リン脂質抗体症候群と診断した。両眼の網膜動脈分枝閉塞症は抗リン脂質抗体症候群を素因とし,急激な血糖コントロールと汎網膜光凝固によって誘発されたと解釈した。
連載 今月の話題
分子生物学による角膜疾患の診断
著者: 堀田喜裕
ページ範囲:P.749 - P.753
最近の分子生物学の進歩に伴って,角膜疾患の診断にも発展がみられた。本稿では臨床的に重要な角膜感染症と,遺伝性の角膜ジストロフィの診断の進歩について述べる。
眼の組織・病理アトラス・163
隅角の発育異常と緑内障
著者: 猪俣孟 , 田原昭彦
ページ範囲:P.754 - P.755
原発緑内障の病因は基本的に前眼部の発育異常である。隅角発育異常緑内障では,症例によって程度の差はあるが,一般に隅角陥凹の発育が悪い。また,40歳以降に発症する原発開放隅角緑内障でも軽度の隅角発育異常がみられることが多い。さらに,原発閉塞隅角緑内障は角膜径がやや小さい軽度の遠視眼に起こりやすい。
前眼部の発育状態,特に隅角陥凹の形成が前房隅角房水流出路の働きに密接に関係する。房水流出路には経シュレム管房水流出路と経ぶどう膜強膜房水流出路があるが,いずれの流出路でも隅角陥凹が十分に発育していることが大切である。
眼の遺伝病・9
ペリフェリン/RDS遺伝子異常による網膜色素変性(4)—Tyrl84Ser変異と常染色体優性錐体−桿体ジストロフィー
著者: 玉井信 , 和田裕子 , 中沢満
ページ範囲:P.757 - P.760
今回はペリフェリン/RDS遺伝子のコドン184の点突然変異による家系(図1)に示された3世代にわたる錐体—桿体ジストロフィの症例を紹介する。コドン184はTACで本来タイロシン(Tyr)をコードしているが,AからCに点突然変異を生じたため,TCCとなり,セリン(Ser)に代わった例である。
眼科図譜・369
MALTリンパ腫と診断された結膜腫瘍の1例
著者: 山田加奈子 , 田村卓彦 , 木村保孝 , 岸章治 , 平戸純子
ページ範囲:P.762 - P.764
緒言
Mucosa-associated lymphoid tissue(MALT)は,外界からの抗原刺激により粘膜下に後天的に形成されたリンパ組織を指す。MALTは局所免疫を司る粘膜固有のリンパ組織で,小腸粘膜におけるパイエル板がその典型で,他に呼吸器,泌尿器,唾液腺,結膜などが知られている1,2)。結膜には出生時にリンパ組織がないが,生後2〜3か月でリンパ組織が発達する。MALTを発生母地とする悪性リンパ腫は,1983年にIssacsonら2)により提唱された。この腫瘍の原発部位としては,消化管,甲状腺,唾液腺,肺などが知られているが,結膜の報告は少ない。筆者らは春季カタルとして3年以上経過観察され,生検によって結膜原発のMALTリンパ腫であることが判明した1例を報告する。
眼科手術のテクニック・125
網膜静脈分枝閉塞症に続発した黄斑浮腫に対する処理方法
著者: 石郷岡均
ページ範囲:P.766 - P.767
網膜静脈分枝閉塞症(branch retinal vein occlu-sion:BRVO)に続発した黄斑浮腫に対する硝子体手術は新しい治療方法であり,その手術手技や適応,奏効機序などを含めて現在検討中の部分が多く,明確な方針が示されていない。今回は現在筆者が考えているBRVO続発黄斑浮腫に対する硝子体手術のなかで,その手術操作における重要な基本ポイントとして,1)後部硝子体剥離(posteriorvitreous detachment:PVD)の作製,2)続発性網膜剥離の下液排出,3)網膜下出血の処理,4)術中・術後のレーザー凝固について示す。この他にも嚢胞状黄斑浮腫(cystoid macular edema:CME)に対する処理方法や内境界膜剥離の効果も検討されているが,その実際の有効性については今後の検討結果を待つ必要がある。
他科との連携
開口障害で初発し,耳鼻科から紹介された両眼性眼窩筋炎
著者: 牧野伸二 , 大石延正
ページ範囲:P.982 - P.984
はじめに
眼窩筋炎は外眼筋に限局した炎症性腫大を呈する疾患である。他覚的には結膜充血,結膜浮腫,眼球突出,眼瞼腫脹,眼球運動障害を,自覚的には眼痛,複視などをきたす。したがって,ほとんど眼科領域で診断,治療が行われる。今回,大学からの派遣先で,片側の咬筋炎,内側翼突筋炎による開口障害で初発し,耳鼻科から紹介を受けた両側性眼窩筋炎の診断,治療で,耳鼻科,放射線科との連携がうまくいった症例を経験したので報告する。
今月の表紙
PTK後のAvellino角膜ジストロフィ
著者: 山村麻里子 , 大野重昭
ページ範囲:P.761 - P.761
初診時4歳という若年期発症の症例で,両眼視力は0.15(矯正不能)であった。ケラトエピセリン関連角膜変性症であるAvellino角膜ジストロフィのホモ接合体症例と思われる。1994年に治療的レーザー角膜切除術(PTK)を両眼に施し,術後矯正視力は右0.7,左0.6と改善した。その後徐々に再発をきたし,術後5年の1999年には左眼の矯正視力は0.04まで低下した。再び左眼にPTKを施したところ,術後には視力は矯正で0.9に改善した。
撮影のカメラはコーワSC−1200PHOTO SLIT LAMP,フィルムはフジカラー400PROVIA,倍率は16倍で,拡散フィルターを使用した。
第53回日本臨床眼科学会専門別研究会1999.10.10東京
画像診断
著者: 中尾雄三
ページ範囲:P.972 - P.973
本年度の専門別研究会「画像診断」では8題の一般口演と1題の特別講演が行われた。一般口演はCTスキャン,ドップラー血流計,高周波超音波検査の症例への応用が発表された。いずれも病態の解析に優れた性能を有し,みごとに治療につなげる役割を果たしていた。特別講演は超音波ドップラー血流検査を用いた頸動脈循環障害の眼症状や所見をきめ細かく観察し,治療への応用を試みた内容で,大きな感銘を得た。
それぞれ座長を担当していただいた先生方に,その印象を述べてもらった。
眼先天異常
著者: 玉井信 , 野呂充
ページ範囲:P.974 - P.975
1.脳室上衣下石灰化を伴う家族性滲出性硝子体網
膜症の1例 斉藤 哲哉(北海道小児病院)
目的:先天性の脳室上衣下石灰化と網膜血管の発達異常を合併した1症例を経験したが,極めて稀と考えられるので,その所見と経過について報告する。
症例:在胎週数36週+4日,出生体重1,919gの低出生体重の女児において両側の脳室上衣下石灰化と脳室拡大が認められたが,先天感染は証明されなかった。第22日の眼底検査において両眼の網膜血管の走行異常と周辺部の無血管野を認め,最終的に家族性滲出性硝子体網膜症と診断した。脳室拡大は10か月時の脳室腹腔シャント術によって軽快した。1歳時から左網膜耳側周辺部の硬性白斑と硝子体への増殖が徐々に増加したため,1歳8か月時に左眼網膜耳側周辺部に対し光凝固を行った。その後,硬性白斑は次第に減少し,硝子体への増殖も停止した。4歳時に身長体重は正常であったが,軽度の精神運動発達遅滞が認められた。
やさしい目で きびしい目で・5
黙して観察
著者: 本村幸子
ページ範囲:P.977 - P.977
診療の場で患者さんを診察する場合には,まず確かな目でじっと観察することから始まる。眼科でも診療の出発点は視診である。ジュニアレジデントが研修を始めてまもなくは,患者さんと対面した時にどのような言動をとるか,じっと我慢の人になって見ている。どうしてああいう話し方をするのだろう,どうしてこういうことも聞かないのだろう,などなどである。新患の診療では,レジデントは予診をとり終わり,基本的診察を終えると診療担当責任者のところへチェックを受けるために持ってくる。いわゆるVorstellenである。レジデントの話を聞きながら,病歴を補足し,所見をチェックしていくが,なぜ,どうして,ここにある所見は何,などなどの連発となることもある。しかし,患者さんの前では,やさしく,ソフトタッチで,患者さんの不安を誘発しないように気配りながら,指摘すべきことはすべて行う。患者さんを前にして,強烈な指摘は避けるが,患者さんの退席を待って診療の問題点をすべて厳しく指導することになる。所見の見落としなどは見誤り以上に大きな問題であることを深く実感してもらわなければならない。このような経験を積み重ねて皆一人立ちしていく。今のレジデントの中には,厳しい言葉に耐えられない者も結構いるので,それぞれの性格などを見抜いて,ほどほどにと仏心が働くこともある。
手術でも同様に黙って観察することから始める。どのような手術でも,初めての執刀者となるときは,必ずその種の手術の助手を務め,直視下に見ているはずである。そして,手術の手順,それに伴う機器の使い方など一通りは心得ているはずである。鑷子,刀,剪刀など,ごくありふれた器具であっても目的にそって設計され,作られている。それらを理解して,合理的な使い方をすれば,安全に目的を達することができるし,器具も長持ちがする。本当に理解して手術を行なおうとしているのか否かは,黙って始めさせてみているとよい。とんでもないことをするようであったら,制しないといけないが,どうしてそうなのか,またそうするのかを問うと理解度を知ることができ,レジデントたちの指導に大変有益である。若き日に,私がフランス留学中にお世話になった先生方も,バックグランドがわからない人を教える場合には,まずその人の行為を黙って観察すると言っていらしたことを思い出す。当時,いきなり病棟で働かせて下さいと申し出て仕事を始めた自分が,先生方にどのように映り,理解されていたのか,今思っても顔が赤くなる思いである。
臨床報告
強膜穿孔および視神経萎縮のみられたParry-Romberg症候群の1例
著者: 川崎良 , 山口克宏 , 山下英俊 , 嘉山孝正
ページ範囲:P.985 - P.989
33歳男性が,左眼の視力低下と眼球陥凹で受診した。10歳の頃から前額,眼窩,頬部を含む左側の顔面萎縮があった。視力は右1.5,左光覚弁,眼圧は右12mmHg,左2mmHgであった。左側の眼球陥凹,眼瞼萎縮,眼瞼内反,睫毛脱落,散瞳,眼球運動障害,強膜穿孔によると推定される結膜濾過胞があり,眼底には視神経萎縮と乳頭周囲から下方に広がる網脈絡膜萎縮があった。本例は,半側顔面萎縮を中軸病変とするParry-Romberg症候群に視神経萎縮と強膜穿孔が併発したと解釈される。
急性腎不全に伴うuveal effusion syndrome
著者: 竹下孝之 , 阿部俊明 , 玉井信
ページ範囲:P.990 - P.992
53歳の男性が2週間前からの霧視で某医を受診した。矯正視力は右0.8,左0.3で,両眼に漿液性網膜剥離があった。病状が悪化し,その5日後に東北大学医学部附属病院眼科を受診した。視力は両眼とも手動弁,眼圧は右64mmHg,左58mmHgで前房はほとんど消失していた。両眼に脈絡膜剥離と広範な胞状網膜剥離があった。血圧は190/90mmHgで,血液検査などで急性腎不全の所見があり,これに続発したuveal effuslon syndromeと診断した。以後10日間に7回の血液透析を行い,眼圧は正常化し,脈絡膜剥離と網膜剥離は消退した。本症候群が急性腎不全で起こり得ることを示す症例である。
術中5-フルオロウラシル塗布併用線維柱帯切除術の成績
著者: 川添真理子 , 沖波聡 , 齋藤伊三雄 , 松井淑江 , 大野新治 , 石郷岡均
ページ範囲:P.993 - P.997
緑内障症例37例43眼に,術中5-フルオロウラシル(5-FU)塗布(50mg/ml,5分間)併用線維柱帯切除術を行い,その成績,併発症についてprospectiveに検討した。ハイリスク群26眼の術前眼圧は27.7±12.6mmHg,終診時眼圧は18.1±7.5mmHgで,ローリスク群17眼の術前眼圧は20.9±5.1mmHg,終診時眼圧は15.9±5.4mmHgであった。生命表法では,術後24か月で無治療で眼圧が20mmHg以下のものはハイリスク群で29.7±9.2%,ローリスク群で52.3±12.3%で,点眼治療を含めて眼圧が20mmHg以下のものはハイリスク群で53.9±9.8%,ローリスク群で63.6±16.6%であった。主な術後併発症は脈絡膜剥離23眼,点状表層角膜症16眼,低眼圧黄斑症7眼,晩期濾過胞漏孔1眼であった。術中5-FU塗布線維柱帯切除術はハイリスク群には不適当であると考えられた。
耳側から発生した翼状片の手術成績
著者: 入船元裕 , 福田昌彦 , 原英徳 , 妙中直子 , 三島弘 , 下村嘉一
ページ範囲:P.999 - P.1002
過去20年間に当科において手術を行い術後1年以上経過観察できた耳側発生の翼状片9例9眼について検討した。検討項目は年齢,性別,両眼の翼状片発生パターン,術式,再発,術後合併症である。年齢は38〜78歳で平均51歳であった。男性7例,女性2例と男性に多く認められた。耳側,鼻側の両方から発生していたのが7例,耳側からのみの発生が2例であった。初回手術術式はすべて強膜露出を伴う単純切除で,うち8例には術後Sr9050Gyの放射線照射を行った。再発は7例(78%)に認め,術後合併症は4例(57%)に瞼球癒着を認めた。耳側から発生した翼状片は若年発症で男性に多く,再発率が高く,高率に瞼球癒着を合併するため注意を要すると考えられた。
白色瞳孔を呈した脈絡膜コロボーマの1例
著者: 村田小夜子 , 中村礼恵 , 田淵昭雄 , 梶原康正 , 小田豪
ページ範囲:P.1003 - P.1007
1歳1か月の男児。左眼外斜視および白色瞳孔の精査目的で来院した。左眼底の後極部に視神経を中心とする広範囲の非定型的脈絡膜コロボーマがみられた。催眠下閃光刺激視覚誘発電位(FVEP)および網膜電位図(ERG)の同時記録においては,FVEPで左眼の主要成分の低振幅かつ潜時の延長がみられ,ERGでは左眼の反応は低振幅で基本波形がみられなかった。眼窩部CTでは左眼軸長は27mmと延長し,かつ脈絡膜コロボーマに一致した後極部の著しい菲薄像をみた。ヘリカルCTを用いた3D-CTではendoscopy像とvolume rendering像で欠損部の菲薄像が描出されたが,各組織のCT値の差が少ないため詳細な識別は困難であった。
基本情報
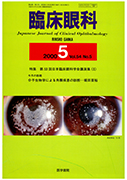
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
