(R1-7AM−6) 目的:後嚢混濁の定量的評価法について,徹照像所見の検討上で計測結果に支障をきたす因子を具体的に示した。
方法:徹照像の撮影には前眼部画像解析システム(EAS−1000,NIDEK)を用い,水晶体前嚢切除縁と後嚢部にフォーカスして撮影した。画像解析は一般的な二値化処理と画質のエンハンスを目的としたハイパスフィルター処理を行った。
結果:原画像の二値化処理のみでは,後嚢混濁による陰影か,それ以外の眼所見なのかを判別することは困難であった。フオーカスのわずかなずれで混濁陰影の様相が大きく変わった。
結論:徹照像は,後嚢混濁の定量的評価にあたって細隙灯顕微鏡検査所見を十分把握し,可能な限り混濁所見以外の陰影を取り除いた後に,二値化処理計測をすることが望ましい。
雑誌目次
臨床眼科54巻6号
2000年06月発行
雑誌目次
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
原著
眼内レンズ挿入眼の徹照像所見と後発白内障の定量限界
著者: 中泉裕子 , 坂本保夫
ページ範囲:P.1044 - P.1048
成熟白内障手術における術中・術後合併症
著者: 沼田愛 , 松場眞弓 , 藤澤直子 , 山崎啓祐
ページ範囲:P.1049 - P.1052
(R1-8PM−10) 1994年4月から1999年8月までの5年5か月間に,川崎病院眼科で白内障手術を行った成熟白内障105例109眼について検討した。比較的若年者の多い膨化白内障と,老年者を主体とする核硬化白内障では術中,術後の経過に大きな差異があることより,全体を膨化群と硬化群として分類し,術式,術中・術後合併症,術後視力について1,536眼の対照群と比較検討した。術中合併症の頻度は,膨化群2.8%,硬化群16.4%,対照群1.3%という結果であった。安全,安易に考えられがちな白内障手術だが,成熟白内障手術は術中・術後合併症頻度が高く,適切な手術時期や術式選択の必要があると考えられた。
小児眼内レンズ挿入術後の後発白内障対策
著者: 水谷英之 , 桜庭知己
ページ範囲:P.1053 - P.1056
(R1-8PM−11) 小児の白内障手術および眼内レンズ挿入術において,術中に施行した水晶体後嚢切開および前部硝子体切除の後発白内障予防への有効性について検討した。対象は,13例20眼(年齢は2歳から11歳)。水晶体後嚢を温存した11眼では,全例に瞳孔領にかかる後発白内障が発生した(平均発生期間は9か月)。白内障手術時に後嚢切開を施行した6眼では,5眼に後発白内障が発生した(平均期間は15か月)。後嚢切開に加え前部硝子体切除を施行した3眼中2眼では瞳孔領は透明に保たれていた。1眼は術後26か月目に後発白内障が発生した。単に水晶体後嚢を切開するだけでなく,前部硝子体切除も同時に行ったほうが,後発白内障予防に有効であると考えられた。
サルコイドぶどう膜炎に対する早期硝子体手術の試み—術後早期成績
著者: 宮本紀子 , 桐生純一 , 山城健児 , 田辺晶代 , 松村美代 , 喜多美穂里
ページ範囲:P.1057 - P.1060
(R2-7AM−2) サルコイドぶどう膜炎において,従来は手術の適応と考えられてこなかった比較的軽度な硝子体混濁や出血,黄斑浮腫,黄斑上膜に対する硝子体手術の成績を報告する。対象はサルコイドぶどう膜炎22症例31眼で,術前所見は黄斑浮腫18眼,硝子体混濁17眼、黄斑上膜9眼,硝子体出血5眼であった。眼底の炎症所見は28眼で改善し,術後2か月の視力は25眼で改善した。術前の黄斑浮腫の有無によって,視力の改善率に差が認められた。硝子体手術は比較的軽症のサルコイドぶどう膜炎の視力成績および炎症の軽減に対して有効であった。
アトピー性皮膚炎に発症した毛様体突起部無色素上皮剥離の検討
著者: 八木橋朋之 , 岩崎琢也 , 中田安彦 , 臼井正彦
ページ範囲:P.1062 - P.1066
(R2-7RM−17) アトピー性皮膚炎症例に発症した毛様体無色素上皮剥離のうち,毛様体突起部まで剥離がみられた11例11眼の手術成績を検討した。有水晶体眼は8眼で全てに自内障がみられ,偽水晶体眼は2眼,無水晶体眼は1眼であった。有水晶体眼に対しては白内障同時手術を行い,強膜バックリング術または硝子体手術を施行した。初回手術で水晶体切除または水晶体嚢切除を行った4眼では全例で復位が得られた。一方,後嚢を残した7眼のうち5眼は再手術を要し,4眼は水晶体嚢切除を,1眼は毛様体無色素上皮の部分切除を行い,全例で復位が得られた。術中所見では毛様体無色素上皮と水晶体嚢の癒着が6眼でみられ,これが剥離した網膜を牽引固定していた。
糖尿病網膜症に対する黄斑部同時汎網膜光凝固法の効果
著者: 野寄忍 , 大木隆太郎 , 針谷紀 , 佐野朱美 , 越川文 , 米谷新
ページ範囲:P.1067 - P.1070
(R2-7RM−21) 黄斑浮腫のある糖尿病網膜症77例118眼に汎網膜光凝固を行った。83眼では黄斑部光凝固を併用し,35眼では併用しなかった。汎網膜光凝固は3回に分け,3週間以上の間隔をおいた。平均14.6か月の経過で,黄斑部凝固を併用した83眼では視力の改善または不変が59眼(71%),悪化が24眼(29%)にあり,併用しない35眼では改善または不変が21眼(60%),悪化が14眼(40%)にあった。糖尿病網膜症への汎網膜光凝固では,黄斑部凝固を併用することで黄斑症の発症または悪化防止に有効であることを示す所見である。
緑内障眼における網膜神経線維層厚の経時的変化
著者: 高橋伊満子 , 田中稔
ページ範囲:P.1071 - P.1076
(D−7PM−11) 正常人14例24眼,正常眼圧緑内障(NTG)15例24眼,原発開放隅角緑内障(POAG)25例39眼に対して,初回,6か月後,12か月後にNerve Fiber Analyzer GDxTMを用いて網膜神経線維層厚(RNFLT)を測定し,各パラメーターに関して検討を加えた。さらに,初回,12か月後にハンフリー自動視野計で視野を測定し,MD値を解析した。全群で6か月後に全てのパラメーターに有意差はなく,12か月後に有意差が認められたのは,NTG群でSup.Max, POAG群ではInf.Max,Inf.Ratio,Max.Mであった。MD値は正常人,POAG群ともに12か月後に有意差を示さず,NTG群では有意な低下を示した。早期緑内障群(MD≧−5.0dB)ではNTG群,POAG群間で初回のMD値に有意差はなく,早期POAG群のみで12か月後にInf.Ratio, Max, Mが有意差を示した。以上より,POAGでは視野障害の進行に先行して下象限のRNFLTが減少する可能性が示唆された。
ラタノプロストとイソプロピルウノプロストン点眼による結膜充血
著者: 柳川秀雄 , 小早川信一郎 , 朽久保哲男
ページ範囲:P.1077 - P.1079
(D−7PM−14) ラタノプロスト(PhXA41)は優れた眼圧下降薬である。しかし多くの副作用が報告されており,中でも結膜充血は最も頻度が高い。そこで健常者38名を対象に,ラタノプロスト点眼により引き起こされる眼球結膜の充血について,イソプロピルウノプロストンと比較し検討した。ラタノプロスト点眼では38例中14例(36.8%),イソプロピルウノプロストン点眼では38例中2例(5.3%)に,肉眼で確認される程度の球結膜充血が認められた。ラタノプロストの初回処方においては,患者に対して十分に説明する必要があると考えられた。
原発閉塞隅角緑内障の角膜内皮障害
著者: 池田美砂 , 杉田美由紀 , 斎藤秀典 , 佐久間浩史 , 関本明世 , 棚橋玲子 , 大野重昭
ページ範囲:P.1081 - P.1084
(D−7PM−19) 原発閉塞隅角緑内障(primary angle closure glaucoma:PACG)における角膜内皮障害とその因子について検討した。緑内障発作眼25眼,非発作眼21眼,合計28例46眼についてアルゴンレーザー虹彩切開術(argon laser iridotomy:ALI)を行った6か月後の角膜内皮細胞密度を比較すると,緑内障発作眼では非発作眼に比べ有意に減少していた。年齢,前房深度,ALIのレーザー照射量と角膜内皮細胞密度との関係をみると,緑内障発作眼も非発作眼もいずれも相関はみられなかった。以上から,PACGの角膜内皮障害は緑内障発作自体による影響が大きいと考えられた。
血管新生緑内障発症の背景因子と手術予後
著者: 宮原晋介 , 広瀬文隆 , 武藤知之 , 谷原秀信 , 杉本琢二 , 栗本雅史 , 松村美代 , 米村昌宏 , 根木昭 , 小椋祐一郎 , 美川優子 , 沖波聡 , 白井美恵子 , 荻野誠周 , 川上淳子 , 永田誠
ページ範囲:P.1085 - P.1089
(D−7PM−21) 血管新生緑内障に対して,7施設で緑内障手術を行った92例111眼を解析した。原因疾患は,糖尿病網膜症82眼,網膜静脈閉塞症19眼,その他11眼であった。初回手術はマイトマイシンC併用トラベクレクトミー41眼,非穿孔トラベクレクトミー10眼,毛様体破壊術60眼であった。最終受診時に,92眼(83%)が20mmHg以下の眼圧であり,視力は23眼(21%)が0.2以上,26眼(23%)が失明していた。緑内障手術不成功の有意な因子は,術前の虹彩ルベオーシス(p=0.002)と周辺虹彩前癒着(p=0.021)であった。以上は,血管新生緑内障への治療法にまだ問題があることを示している。
済生会新潟第二病院における身体障害者手帳(視覚)該当者へのアンケート調査
著者: 田村久実子 , 小川佳子 , 畑山由比乃 , 長谷川百合子 , 安藤伸朗
ページ範囲:P.1091 - P.1094
(G−7AM−3) 1999年2月から5月の3か月間に,済生会新潟第二病院眼科外来通院患者3,790名のうち,身体障害者手帳(視覚)該当者に対しアンケート調査を行った。手帳該当者は42名(該当率1.1%)で,年齢・性差・原因疾患・等級による有意差はなかった。手帳取得者は24名で(取得率57.1%),5名(21%)が「メリットがない」,「体裁が悪い」などの理由で利用したことがなく,利用経験のある19名ではメリットとして交通費・税金などの控除を挙げていた。未取得者は18名で,過半数の10名が手帳を知らず,手帳のことを知っていた8名のうち半数が「手続きが面倒」という理由で取得していなかった。手帳の情報源は,手帳取得者は医師や病院スタッフからが多く,未取得者は友人・知人からが多かった。
ロービジョンエイド処方のための残存視機能評価方法の検討
著者: 米澤博文 , 栗本康夫 , 黒川徹 , 松野かおり , 吉村長久 , 小田浩一
ページ範囲:P.1095 - P.1098
(G−7AM−4) 信州大学医学部附属病院眼科ロービジョン外来を,1998年9月から1999年9月までの間に受診した患者36例を対象に,患者ニーズの聴取と種々の残存視機能評価のための検査を行い,実際に患者に対して処方された補助具との関係を検討した。患者のニーズ第1位は読書(26例)で,歩行(13例)がこれに次いだ。コントラスト感度の低下を認めた13例中6例と,グレア視力の低下を認めた5例中1例に遮光眼鏡の処方を行った。実施した視機能評価のための諸検査の中では,唯一MNREAD-Jにより得られた臨界文字サイズが,処方したルーペの倍率と統計学的に有意に相関していた。MNREAD—Jは読書のためのロービジョンエイド処方に有用な定量的検査方法と考えられた。
障害児・者の屈折異常の頻度
著者: 高橋広 , 周正喜 , 里村典子 , 小坂美樹 , 山城美和子 , 久保真奈子 , 玉谷晴代 , 大賀真由美
ページ範囲:P.1099 - P.1104
(G−7AM−6) 北九州市立総合療育センター眼科を受診した2,602名4,926眼を対象とし,ホマトロピン/シクロペントレート点眼後のレチノスコープによる他覚的屈折検査を施行し,±6D以上の高度遠視/近視および2D以上の乱視を屈折異常と判断し,その頻度を統計学的に検討した。
全身障害を有しない群は734例(28%),全身障害を有する群が1,868例(72%)であった。全身障害を有しない群の屈折異常の頻度は26%で,全身障害を有する群では28%と,その発生頻度には差はなかった。先天異常群では42%に屈折異常があり,特にダウン症では46%と有意に高頻度であった(p<0.01)。また,後遺症群では30%で,脳性麻痺でも31%と有意に多かった(p<0.01)。未熟児は全対象の10%を占めており,特に未熟児網膜症発症群では屈折異常がすでに3歳までに多く,4歳以後に異常者が多い他の障害児・者とは異なっていた。以上より,障害児・者においても早期からの他覚的屈折検査は重要な検査であることが示された。
Laser in situ keratomileusis(LASIK)の術後視覚障害を起こした4症例
著者: 下村直樹 , 天野史郎 , 大鹿哲郎 , 加治優一 , 臼井智彦 , 加賀谷文絵 , アレミンバスタンファルト , 神谷和孝 , 藤田南都也 , 吉田照宏
ページ範囲:P.1105 - P.1107
(G−7AM−14) 他施設でlaser in situ keratomileusis (LASIK)の屈折矯正手術を受け,術後に視力障害が生じた4例8眼を検査した。8眼の矯正視力は,0.02,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9,1.2であった。5眼に−3D (ジオプトリー)以上の乱視があった。5眼にフラップラインがあり,うち2眼では不整に彎曲していた。2眼に異物反応と考えられるフラップ下の水疱状の混濁があった。3眼ではフラップラインがなく,角膜中央部の菲薄化があることから,フラップの喪失または障害があったと推定された。LASIK術後の視力障害にはフラップ作成に関する問題が関与しやすい。
遺伝子解析による先天色覚異常保因者の診断
著者: 小田早苗 , 上山久雄 , 林幸子 , 山出新一
ページ範囲:P.1109 - P.1114
(G−7PM−11) 視色素遺伝子の解析により,先天色覚異常保因者の診断が可能かどうかを検討した。対象は,陽性対象群として家系的保因者38名とスクリーニング群として無作為に選んだ日本人女性104名である。視色素遺伝子配列の最上流の遺伝子,2番目以降の遺伝子,および最下流の遺伝子をそれぞれPCR法で増幅し,増幅されてきた各々の遺伝子の第5エキソンをさらにPCR法で増幅し,SSCP分析法により赤型か緑型かを判定した。陽性対象群はすべて保因者と診断できた。スクリーニング群で第1色覚異常保因者と診断できたのは5名(4.8%),第2色覚異常保因者と診断できたのは9名(8.7%)であった。これは従来いわれている色覚異常者の割合から推定される保因者の頻度よりも高い値を示した。
Erbium-YAGレーザーによる白内障手術の検討
著者: 魵沢伸介 , 土橋尊志 , 越川文 , 佐野朱美 , 村山耕一郎 , 米谷新 , 大木孝太郎
ページ範囲:P.1115 - P.1118
(V−3) Erbium-YAGレーザー(WaveLight社製)による白内障手術の可能性,安全性について実験モデルを使い検討した。摘出豚眼にアルコール,ホルマリン混合液の嚢内注入および電子レンジ処理した異なる硬度を持つ白内障を作製した。前嚢切開は出力5mJ,周波数35Hzで容易に連続した切開層が得られた。白内障では出力20mJ,周波数35Hzを標準の出力として破砕吸引が行えた。問題点として,核破砕時に前房中への飛散が挙げられたが,吸引圧を上げることにより改善され安全に手術を完遂することができた。Erbium-YAGレーザーによる白内障手術は可能であり,新しい白内障手術装置としての発展が期待される。
Open sky vitrectomyを行ったMMC併用トラベクレクトミー後に発生した蜂巣炎を伴う眼内炎
著者: 丸山幾代 , 鈴木純一 , 勝島晴美 , 長井伸二 , 木下貴正 , 前田貴美人 , 中川喬
ページ範囲:P.1119 - P.1122
(V−33) MMC併用トラベクレクトミー3年半後に,蜂巣炎を伴う重篤な眼内炎を発症した不幸な1例を経験した。抗生薬の全身および局所投与と硝子体手術を施行したが.光覚はもどらなかった。蜂巣炎を伴う重篤な眼内炎を発症した背景として,脆弱な濾過胞,糖尿病による易感染性,MMCによる強膜障害,強い毒性を有する病原菌の侵入などが考えられた。以上より,MMC併用トラベクレクトミー後の管理においては常に感染症を念頭におく必要があり,本症例のように易感染性疾患を有する場合には,特に注意が必要と思われた。
眼瞼痙攣に対するボツリヌス毒素投与前後のMRIによる検討
著者: 林田裕彦 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.1123 - P.1125
(P−1-10) 眼瞼痙攣に対するボツリヌス毒素注射を19例に行った。全例で症状が軽減した。副作用として,閉瞼不全が4例にあった。治療前後の磁気共鳴画像検査(MRI)では,外眼瞼または顔面筋に萎縮や炎症はなかった。以上の結果は,眼輪筋へのボツリヌス毒素注射が形態学的に安全であることを示している。
非接触式眼圧計とゴールドマン圧平式眼圧計の眼圧読み値の乖離に及ぼす角膜厚の影響
著者: 平野晋司 , 相良健 , 鈴木克佳 , 西田輝夫
ページ範囲:P.1127 - P.1130
(P−1-25) 緑内障または非緑内障の41例82眼について,中心角膜厚と眼圧を非接触式眼圧計(NCT),ゴールドマン圧平式眼圧計(GAT)を用いて測定した。NCTとGATの眼圧読み値の乖離と中心角膜厚は有意な相関を示し(単回帰分析:R=0.694,p<0.0001),回帰直線は,中心角膜厚(μm)=9.045×(NCT-GAT)+547.38であった。角膜が厚いほどNCTの眼圧読み値はGATに対して高値となり,薄いほど低値であった。中心角膜厚はNCTとGATの眼圧読み値の乖離の要因であると結論される。
先天眼振症例におけるアモバルビタール投与の社会的有用性
著者: 小山玲子 , 内海隆 , 奥英弘 , 菅澤淳
ページ範囲:P.1131 - P.1134
(P−1-26) 先天眼振がある16,18,22歳の3名にアモバルビタール(5mg/kg)を点滴静注した。3名とも視力のよい眼での矯正視力は0.5であった。点滴後に全例で0.7以上の視力が少なくとも1眼で得られた。この結果から気持ちをコントロールすることを教え,自信を持たせたうえで,薬物を使用しないで数回の視力検査練習を行わせた。その結果,1名は運転免許取得に成功し,2名は入学試験に合格した。アモバルビタールによる眼振抑制効果は,脳幹網様体への作用と,感情に関係する視床下部を介する可能性が考えられた。精神的に緊張しやすい先天眼振患者に対するアモバルビタール投与は,このような意味で社会的有用性があると結論される。
マイトマイシンC併用線維柱帯切除術の長期成績
著者: 今泉佳子 , 杉田美由紀 , 栗田正幸 , 斉藤秀典 , 大野重昭
ページ範囲:P.1135 - P.1138
(P−1-33) 1年以上眼圧コントロール良好であった症例におけるマイトマイシンC併用線維柱帯切除術の,長期眼圧調整率および晩期合併症について検討した。対象は99例113眼で,平均年齢は57歳,平均観察期間は32.7か月であった。Kaplan-Meier法による解析で,全症例の21mmHg未満への眼圧調整率は4年までは80%を超えていたが,以後はぶどう膜炎症例や手術既往例において低下がみられ,最終観察時では67.9%であった。長期観察中に低眼圧黄斑症が3眼みられたが,いずれも自然治癒した。
散瞳薬による開放隅角緑内障の眼圧上昇
著者: 市岡伊久子 , 市岡尚 , 市岡博
ページ範囲:P.1139 - P.1143
(P−1-43) 開放隅角緑内障のトロピカミド,フェニレフリン合剤(ミドリンP®)点眼後の眼圧変化につき調査した。点眼1時間後の眼圧上昇は開放隅角緑内障眼2.6±2.7mmHg,嚢性緑内障眼2.7±2.0mmHg,偽落屑(PE)のない非緑内障眼0.1±1.5mmHg,PEのある非緑内障眼0.5±1.6mmHgで,開放隅角緑内障眼嚢性緑内障眼では有意に眼圧上昇をきたした(p<0.0001)(student-t検定)。4mmHg以上の眼圧上昇をきたした例は開放隅角緑内障40眼中14眼(35%),嚢性緑内障16眼中6眼(38%)と高率であった。開放隅角緑内障,嚢性緑内障において,散瞳検査を要する場合は注意が必要であり,最初に点眼後の眼圧測定をしておくべきだと思われた。また眼圧上昇例では,より注意深い経過観察を要すると思われた。
眼内レンズ挿入眼の屈折値
著者: 渡辺三訓 , 市川一夫 , 斎藤裕
ページ範囲:P.1145 - P.1151
(P−1-54) 矯正視力が1.0以上ある両眼眼内レンズ(IOL)挿入患者297例に対し,近見および遠見の視活動についてのアンケートと術後屈折度を調査し,IOL挿入眼の目標とすべき屈折値を検討した。正視群(等価球面度数±1.0D以内),近視群(<−1.0D),遠視群(>+1.0D)がそれぞれ199例,86例,12例であった。正視群の近用眼鏡所有率は71.7%,遠用眼鏡所有率は24.9%であり,近視群はそれぞれ31.8%と62.8%であった。近用眼鏡なしでも正視群で約80%の患者が不自由を感じず,逆に近視群でも15%近くが不自由を感じており,術後目標屈折値を正視としても,読書など精密な近見作業以外は近用眼鏡を必要とせず,患者自身の満足が得られる可能性が高いと考えられた。
急性網膜壊死の1治療経験
著者: 西垣恵行 , 安積淳 , 中山伊知郎
ページ範囲:P.1153 - P.1156
(P−1-71) 急性網膜壊死の病態は,ウイルス増殖による急性網膜炎期,炎症が高度になる網膜壊死期,二次的病変が生じる寛解期の経時的な変化がある。53歳の女性が右眼の霧視を自覚し,その10日後に受診して急性網膜壊死と診断した。前房水から水痘・帯状疱疹ウイルスが検出された。急性期には,アシクロビル極量投与によるウイルス増殖抑制と病巣境界への光凝固を行い,初診6日目からの網膜壊死期にはステロイド薬投与による炎症のコントロール,5週後以降の寛解期の硝子体出血など続発病変に対しては,硝子体手術による観血的治療を順次行った。後極部網膜の温存に成功し,最終視力0.2を得た。本症の治療では,病期に応じた適切な対応が望ましいことを本例は示している。
両眼に左上四半盲を認めたSLEの1例
著者: 谷圭介 , 秋葉純 , 石丸浩平
ページ範囲:P.1157 - P.1159
(P−1-88) 全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus:SLE)の患者の両眼に左上四半盲を認め,脳神経外科にてSLE脳症と診断された症例を報告する。症例は53歳の女性。両眼の視力低下と下肢のしびれ感を訴え,王子総合病院眼科を初診した。初診時矯正視力は右1.0,左0.9と良好で,前眼部,中間透光体および眼底にも明らかな異常はなかった。ハンフリー視野検査で両眼に左上四半盲を認め,CT検査で右頭頂葉にlow density areaがみられたため,脳神経外科に紹介したところ,SLE脳症と診断された。ステロイドパルス療法にて脳病変は縮小し,視野異常が著しく改善した。SLEでは稀ではあるが脳症を合併し,視野異常をきたすことがあり,注意が必要である。
Erbium-YAGレーザーによる硝子体手術
著者: 村山耕一郎 , 魵澤伸介 , 土橋尊志 , 村田栄子 , 米谷新
ページ範囲:P.1160 - P.1163
(V−13) Erbium-YAGレーザーによる硝子体手術機器(WaveLight社製)の実用性と安全性を知るために,実験的に作製した増殖性網膜硝子体症および硝子体出血眼にて硝子体切除を施行し,その実用性を検討した。Erbium-YAGレーザーの波長は2.94μmで,レーザーの出力は5mJから40mJ,周波数は20Hzから70Hzの頻度を選択可能であった。正常硝子体線維は10mJ,20Hzの条件で切除・吸引でき,血液凝固塊および増殖組織は出力あるいは周波数を上げることでさらに効率的な切除が可能だった。Erbium-YAGレーザー硝子体切除装置は,切れ味の劣化はみられず十分に実用的であったが,今後その安全性についてさらに検討する必要があると考えられた。
線維柱帯部の炎症に続発したと思われる緑内障の1例
著者: 福井佳苗 , 木内良明 , 原周子 , 石本一郎
ページ範囲:P.1164 - P.1167
(P−1-36) 線維柱帯部の炎症に続発したと思われる緑内障を経験した。症例は67歳,女性。初診時,結膜の充血や前房中の細胞やフレアはなかったが,隅角に白色結節とテント状虹彩前癒着を伴っていた。両眼とも軽度な皮質白内障があるものの,硝子体に混濁はなかった。緑内障様の視神経乳頭の陥凹があり,眼圧は両眼とも20mmHg以上あった。ステロイド薬を点眼するだけで眼圧は下降し,隅角結節も消退した。線維柱帯部の炎症が眼圧上昇の原因であると思われ,隅角結節の原因としてサルコイドーシスが示唆された。本症と開放隅角緑内障の鑑別診断のためには詳細な隅角の観察が必要である。
内視鏡による術中眼内レンズループの固定位置の観察—術後屈折値に及ぼす影響
著者: 足立諭紀 , 吉村正美 , 小池昇 , 高橋春男
ページ範囲:P.1168 - P.1170
(P−1-59) 白内障手術の術中に,内視鏡を用いて毛様体および眼内レンズの固定位置を観察し,眼内レンズの固定位置が術後屈折値に与える影響について検討した。眼内レンズの固定位置は毛様体の上方が14例,中央が7例,下方が3例であった。毛様体の密度,太さや色調はさまざまであった。眼内レンズの固定位置と毛様体形態に有意な関係はみられなかった。術後の屈折値は術翌日,術後3か月目ともに下方固定群よりも上方固定群のほうが術前予測値よりも近視化し,誤差が大きく生じた。眼内レンズの固定位置を決定する要因について調べ,術中の眼内レンズの固定位置を一定化することができれば,術後屈折値の誤差を減少させることが可能と考える。
局所切除,白内障手術,眼内レンズ挿入,瞳孔形成術が奏効した毛様体腺腫の1症例
著者: 平石剛宏 , 戸塚清一 , 栗林秀治 , 根本裕次 , 石田康生
ページ範囲:P.1171 - P.1175
(P−1-77) 13歳男児が左眼の視力低下で受診した。褐色の腫瘍が虹彩の後方内側にあり,水晶体を圧迫し白内障が併発していた。腫瘍を局所切除し,白内障手術,眼内レンズ挿入,瞳孔形成術を行った。腫瘍は半球形で径は8mm,割面は嚢胞状であった。病理組織学的に悪性所見はなく,毛様体上皮に連なる腫瘍細胞が嚢胞状,腺状の構造を呈していた。手術後に重篤な合併症はなく,良好な視力が維持されている。
網膜動脈閉塞を発症した眼内異物の1例
著者: 高木史子 , 森秀夫
ページ範囲:P.1177 - P.1180
(P−1-105) 52歳の男性の左眼に異物が飛入した。初診時視力は眼前10cm指数弁で,9時の角膜,虹彩,水晶体に異物刺入創,軽度の外傷性白内障を認めた。眼底は硝子体出血により詳細不明であったが,超音波検査,CT検査にて,視神経乳頭近傍の網膜上に鉄片と思われる異物を認めた。明らかな網膜剥離などは認められなかった。翌日,超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入,硝子体手術,眼内異物摘出術を行った。術中,乳頭部から黄斑上半分を含み,耳側中間周辺部に至る帯状の網膜動脈閉塞を認めた。術後,黄斑前膜の形成をみ,再手術にて除去し,固視点直下に暗点を認めるものの視力0.9を得た。
特発性黄斑円孔に対する内境界膜除去手術による視力,網膜感度の変化
著者: 上田佳子 , 金沢佑隆 , 大庭啓介 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.1181 - P.1183
(P−1-140) 特発性黄斑円孔にて円孔閉鎖術施行時に内境膜除去を行い,内境膜除去を行わなかった群との間の視力,中心網膜感度を比較,検討した。対象は,黄斑円孔にて円孔閉鎖術施行時に内境界膜除去を行った女性8例8眼,対照は,黄斑円孔にて円孔閉鎖術施行時に内境界膜除去を行わなかった女性8例8眼である。内境界膜除去を施行した群では8例全例において視力が改善した。中心網膜感度は内境界膜除去を施行した群では8例中4例で変化はなかったが,2例は感度が上昇し,2例は感度が低下した。内境界膜除去を施行しなかった群では,視力は2例において改善し,中心網膜感度は8例中6例で変化はなかったが,2例では低下した。円孔閉鎖術施行時の内境界膜除去による機械的網膜損傷が,視力,中心網膜感度を低下させるかもしれないと予想されたが,内境界膜除去群と内境界膜非除去群の間に差はなかった。
公立みつぎ総合病院眼科における眼科救急患者の統計的観察
著者: 添田祐 , 新矢誠人 , 谷村尚俊 , 皆本敦 , 三嶋弘
ページ範囲:P.1185 - P.1190
(P−2-25) 1993年から1998年までの6年間に,公立みつぎ総合病院救急外来を受診した眼科救急患者370例の特徴について検討した。救急患者のうち74%(275例)が外傷性,26%(95例)が非外傷性であった。外傷性疾患のうち45例(16%)に手術処置を要した。外傷性疾患では非外傷性疾患に比較して,他科の医師が眼科医師に診察を要請した頻度が高かった。他科医師のみに診察を受けた例で,眼科的診断が不適切もしくは治療が不十分となっていた例が多くみられ,再診率も低くなっていた。これらの問題を改善するためには,他科医師に対する眼科救急疾患の啓蒙や,可能な限り二次的に眼科医師が診療する体制の整備が必要と考えられた。
6歳女児に生じた網膜動脈閉塞症の1例
著者: 朝比奈章子 , 小松崎優子 , 中山玲慧 , 横山利幸 , 大友義之
ページ範囲:P.1191 - P.1194
(P−1-142) 小児における網膜中心動脈閉塞症(central retinal artery occiusion:CRAO)は報告例が少なく,その原因としては血管腫,霰粒腫に対するステロイド薬注入が契機となった例や,外傷,血液疾患,先天性心疾患の合併例のほか原因不明な例もある。今回筆者らは,6歳女児に生じた網膜中心動脈閉塞症において.発症当時みられなかった抗カルジオリピン抗体が,発症後1年1か月後に初めて陽性化し,抗リン脂質症候群と診断された症例を経験した。抗リン脂質抗体症候群においては発症後数か月から数年を経た後,抗体価が陽性化する例も報告されており,今後原因不明の小児における網膜中心動脈閉塞症においては,抗リン脂質抗体症候群も念頭におかなければならない。
胞巣状軟部肉腫と診断した小児眼窩腫瘍の1例
著者: 赤木忠道 , 本田治
ページ範囲:P.1195 - P.1198
(P−2-3) 眼窩の胞巣状軟部肉腫は大変稀であり,世界的にも報告例は多くはない。眼瞼腫脹と流涙で発症し,急速に増大した1歳半女児の眼窩腫瘍を経験した。CTでは骨浸潤を伴わない眼球外後方の眼窩内腫瘍で,MRIでは腫瘍内にflow voidを認めた。病理組織学的には胞巣状構造を有し,明瞭な核小体を持つ類円形核を有する腫瘍細胞で,針状結晶は認められなかったが,その前駆物質と考えられているジアスターゼ耐性PAS陽性の顆粒をわずかに認めた。免疫組織化学的にはα-smooth muscle actin,desminなどの筋肉markerやHMB-45, S-100蛋白などが陰性であることより,横紋筋肉腫や明細胞肉腫を除外した。特徴的な針状結晶は確認できなかったが,臨床経過,画像および針状結晶以外の病理所見より胞巣状軟部肉腫と診断した。
強度近視に合併した黄斑円孔による網膜剥離眼の摘出網膜前膜の病理所見
著者: 森圭介 , 樺澤昌 , 米谷新
ページ範囲:P.1199 - P.1203
(P-1-114) 78歳の女性が,17か月前からの左眼視力低下で受診した。左眼の視力は,0.06×10.0Dであった。眼底には後部ぶどう腫とその範囲に一致する網膜剥離,黄斑円孔があった。手術中に除去した網膜前膜を除去し,病理的に検索した。ヘマトキシリン・エオジン染色では,主にエオジン好性の薄い線維絹織から成り,細胞成分を含んでいた。この線維成分を主体とする層は,Massonの膠原線維染色で膠原線維であると同定された。抗glial fibrillary acidic protein (GFAP)抗体による免疫組織化学染色で,細胞成分に富んだ層はGFAP陽性であった。以上の所見は特発性黄斑円孔のそれと同様であった。網膜前膜は硝子体膠原線維に由来し,網膜のグリア増殖で修飾されたと推定した。
再生不良性貧血に伴う網膜前出血に対してNd-YAGレーザー治療が奏効した1例
著者: 大井真愛 , 渡辺博 , 忍田拓哉 , 松橋正和 , 田冶えりか
ページ範囲:P.1205 - P.1209
(P−2-18) 両眼の網膜前出血をきたした再生不良性貧血の32歳女性の片眼に対して,Nd-YAG laserhyaloidotomyを施行した1例を報告した。突然の感冒症状から重症の再生不良性貧血を発症し,まもなく両黄斑部網膜前出血により急激な視力低下を自覚した。早期の視力回復を期待し,ドレナージ効果を得られると判断した片眼にのみNd-YAG laser hyaloidotomyを施行した。自然経過をみた左眼が矯正視力(1.0)に改善するのに約3か月を要したのに対して,YAGレーザー治療をした右眼は3週間で(1.0)に改善した。治療眼の出血の吸収は明らかに早まった。両眼性の黄斑部網膜前出血の場合,精神的にも不穏が強くなり,出血の早期吸収が望まれる。Nd-YAG laser hyaloidotomyは侵襲の小さい有効な方法であると思われた。
ロービジョンから見たバリアフリーの病院建築
著者: 西脇友紀 , 田中恵津子 , 小田浩一 , 平形明人 , 樋田哲夫 , 藤原隆明
ページ範囲:P.1211 - P.1216
公共建築物である病院が,ロービジョン患者(以下,LV患者)にとってバリアフリ自となるための要因を検討するため,LV患者に院内の移動に関してインタビューを行い,それに基づいて移動上重要な箇所の視認性を評価した。さらに現行の法令などがLVを考慮した内容であるか検討した。その結果,視認性が低いため利用しにくいと指摘された多くの場所は,認識しやすいと評価されたところに比べ,コントラストが明らかに低かった。したがって,LVにとってのバリアフリーには,聴覚や触覚情報による代替表示のほか,高いコントラストで視覚情報を提供する必要がある。また,本邦の法令にはLVに配慮した具体的な規定は少なく,規定のほとんどが強制力を伴わない努力規定だった。
角膜上皮肥厚の1例—病理所見の検討
著者: 芦忠陽 , 栄田裕子 , 雨宮次生
ページ範囲:P.1217 - P.1220
(P−2-41) 左眼角膜中央部に6×5mm白色隆起性病変と血管の進入がみられ,視力低下をきたした70歳女性に角膜移植術が施行された。光学顕微鏡では角膜上皮細胞は配列が不整で,基底細胞の丈が高く,ボウマン膜も不整であった。実質のコラーゲン線維は不規則で,炎症細胞の浸潤がみられ,血管も存在した。電子顕微鏡では複数の大きな核小体を持った核がみられた。上皮細胞質は小胞体が開存し,核が大きかった。デスモゾームは多数みられたが,一部には少ない細胞も存在した。上皮細胞の中には壊死細胞がみられ,細胞膜を失った線維細胞がみられた。以上より,本症例は角膜上皮細胞増殖であると診断した。このような病理所見は糸状角膜炎に極めて類似していた。ボウマン膜の近くの炎症性病変によって角膜上皮細胞の増殖を起こしたと推測した。
全層角膜移植術後拒絶反応に関与する因子の多変量解析
著者: 立原蘭 , 内尾英一 , 杉田美由紀 , 高野雅彦 , 樋口亮太郎 , 大野重昭
ページ範囲:P.1221 - P.1224
(P−2-54) 横浜市立大学医学部附属病院眼科で1991〜1998年に行われた全層角膜移植術(penetratingkeratoplasty:PKP)症例39例47眼を対象に生命表解析と多変量解析を組み合わせ,術後拒絶反応に関与する因子を検討した。拒絶反応に関与する要因として,性,年齢,原因疾患,術前角膜血管侵入,術前合併症,術式,術後ステロイド薬全身投与,術後シクロスポリン局所投与,術後眼圧上昇,縫合不全を用いた。Kaplan-Meier法による拒絶反応生存率は1年生存率74.1%,3年生存率58.4%であった。Cox比例ハザードモデルおよび多重ロジスティックモデルによる解析の結果,術後眼圧上昇,術前合併症,角膜血管侵入などが拒絶反応出現に強く関連していることが示され,中でも術後眼圧上昇が重要であると考えられた。一方,数量化理論II類では縫合不全,術前合併症などの異なった因子の関与も考えられた。
ピロカルピン,アプラクロニジン,ベタキソロールが実験的ぶどう膜炎を惹起した家兎の血液房水柵に及ぼす影響について
著者: 木内良明 , 板谷浩志 , 塩谷易之 , 中江一人 , 石本一郎 , 堀裕一 , 佐藤茂 , 原周子 , 福井佳苗 , 久保満 , 塚本裕次 , 森岡淳
ページ範囲:P.1225 - P.1229
(P−2-56) ピロカルピン,アプラクロニジン,ベタキソロールを健常家兎と実験的ぶどう膜炎を惹起した家兎に点眼して,血液房水柵の透過性の変化を検討した。大腸菌毒素(1μg/kg)を静脈内に注射してぶどう膜炎を発症させ,前房のフレア値を炎症の指標とした。いずれの点眼薬を健常眼に点眼しても前房フレア値は対照眼と差がなかった。2%ピロカルピンを炎症眼に点眼すると点眼側は対照側より1.7倍高いフレア値を示したものの,統計学的に有意な差はなかった。一方,1%アプラクロニジンは炎症眼の前房フレア値の上昇を有意に抑えた。0.5%ベタキソロールを炎症眼に点眼しても前房フレア値に変わりなかった。
悪性緑内障を生じた小眼球症の1例
著者: 森實祐基 , 永山幹夫 , 高須逸平 , 山口樹一郎 , 大月洋 , 河西葉子
ページ範囲:P.1230 - P.1234
(P−2-60) 小眼球に慢性閉塞隅角緑内障を伴った症例に対して,両眼に白内障手術を行い,右眼にピロカルピンを点眼し,悪性緑内障を発症した24歳男性の1例を経験した。発症後早期にアトロピン点眼を行うことで前房深度は深くなり,眼圧は正常化した。しかし眼内レンズの瞳孔捕獲が起こり,左眼に比べ前房深度は浅いままとなった。本症例はピロカルピン点眼によって毛様体—水晶体嚢ブロックが起こり,悪性緑内障を発症したと考えられる。また右眼に用いたアクリル3ピースレンズが,左眼に用いたPMMA1ピースレンズに比べて瞳孔捕獲や浅前房を容易にしたと考えた。したがって悪性緑内障を念頭におくべき症例では,眼内レンズの選択が重要であるといえる。
緑内障眼に網膜中心静脈閉塞症および網膜動脈分枝閉塞症が合併した2症例について
著者: 永木憲雄 , 半田幸子 , 良藤恵理子
ページ範囲:P.1235 - P.1239
(P−2-68) 緑内障眼に網膜静脈閉塞・網膜動脈閉塞が合併した2症例を経験した。症例1は76歳男性で,進行した緑内障眼に網膜静脈・網膜動脈閉塞症を合併し,最終視力は光覚となった。症例2は69歳男性で,緑内障に網膜静脈・網膜動脈閉塞症を合併した。黄斑浮腫が増悪し,硝子体手術を実施したが最終視力は0.3であった。緑内障による視野狭窄に加え,網膜血管閉塞による視力・視野障害も加わったため,視力予後は不良であった。緑内障眼に網膜血管閉塞が合併した場合,早期に積極的治療を行うことが必要と考えられた。
光干渉断層計による黄斑円孔の手術予後の検討
著者: 安齋要 , 森圭介 , 斉藤民也 , 村山耕一郎 , 米谷新
ページ範囲:P.1240 - P.1242
(P−2-81) 特発性全層黄斑円孔28例29眼を対象に,術前の円孔形態を光干渉断層計(OCT)で解析・定量し,罹病期間とともに術後視力との関係を統計学的に比較検討した。罹病期間が長いほど術前の円孔径,円孔底径,円孔係数(円孔底径から円孔の斜辺の和を引いたもの)は拡大し,統計学的に有意な正の相関がみられた。また,術前の円孔径,円孔底径,円孔係数が大きくなるほど術後視力は低く,統計学的に有意な負の相関がみられた。OCTによる術前の評価は客観的・定量的であるため,術後の視機能を予測するには従来の方法に比べより有用であると結論された。
網膜色素上皮剥離を伴った加齢黄斑変性へのインドシアニングリーン蛍光造影を指標とした光凝固
著者: 大澤松香 , 飯田知弘 , 中村研一 , 萩村徳一 , 佐藤拓 , 渡辺五郎 , 岸章治
ページ範囲:P.1243 - P.1246
(P−2-110) 網膜色素上皮剥離(PED)を伴った加齢黄斑変性(AMD)に対して,インドシアニングリーン蛍光造影(IA)を指標として光凝固を行った。光凝固後に6か月以上の経過観察ができた40例40眼では,32眼(80%)で視力の維持もしくは改善が得られた。また,追加凝固を含めて26眼(65%)で眼底所見が鎮静化した。40眼中28眼では光凝固後に1回以上IAを再検し,凝固前後の造影所見を比較した。28眼中13眼(46%)では初回の凝固後にfocal spotの消失が確認できたが,15眼(54%)ではfocal spotの遺残・再発がみられた。遺残・再発は11眼で凝固斑の中心窩側に検出された。初診時とは別の部位に再発したfocal spotは4眼あり,全てplaque内に出現した。Foca中spotが中心窩下に進展していた4眼以外では追加凝固を行い,11眼全例で消失した。PEDを伴ったAMDへの光凝固は,IAを指標にすることで治療成績が向上すること,脈絡膜新生血管の残存・再発への注意が必要なことが結論される。
網膜静脈分枝閉塞症の黄斑浮腫に対する柴苓湯の効果
著者: 岩下憲四郎 , 山岸和矢 , 弓削堅志 , 高橋愛 , 福井智恵子 , 津村晶子
ページ範囲:P.1247 - P.1251
(P−2-86) むくみ(浮腫)の改善に有用とされる柴苓湯を,網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫の症例に用い,その効果を検討した。対象は,1年以上経過観察できた柴苓湯(TJ114)を投与した投与群22例と投与しなかった非投与群29例である。柴苓湯の投与方法は,TJ114を毎食後3gずつ1日3回の服用とした。1年後の視力は,非投与群で55%が改善し21%に悪化がみられたのに対して,投与群では77%が改善し悪化はなかった。また,1年後の黄斑浮腫に関しては,非投与群で76%が改善,17%が不変,7%が悪化であったが,投与群では96%に改善が認められ,4%は不変であったが、悪化はなかった。従来の薬物療法および網膜光凝固療法では難治の症例に対して,柴苓湯の併用は有用と考えられた。
糖尿病黄斑浮腫とぶどう膜炎による黄斑浮腫に対する内境界膜切除を併用した硝子体手術
著者: 谷口亮 , 北岡隆 , 上田佳子 , 金沢祐隆 , 栄田裕子 , 大庭啓介 , 三島一晃 , 雨宮次生
ページ範囲:P.1252 - P.1254
(P−2-115) 糖尿病網膜症とぶどう膜炎による黄斑浮腫に対して,内境界膜切除を併用した硝子体手術を行った。糖尿病黄斑浮腫症例10例14眼,ぶどう膜炎による黄斑浮腫4例5眼に対して,浮腫消退を目的に硝子体手術を行った。手術施行後,浮腫は糖尿病網膜症症例の6眼(43%)で浮腫の消退をみたが,ぶどう膜炎症例では1例(20%)でのみ浮腫の消退をみた。視力は,糖尿病症例で,4眼(36%)で2段階以上の視力改善が得られたが,5眼で不変,2眼で低下した。ぶどう膜炎症例では,2眼(50%)で2段階以上の視力改善が得られ,2眼では低下した。糖尿病黄斑浮腫とぶどう膜炎による黄斑浮腫に対して,内境界膜切除を併用した硝子体手術を行ったが,視力の改善には統計学的に有意差はなかった。糖尿病網膜症症例とぶどう膜炎症例では黄斑浮腫の発症機序が異なる。糖尿病網膜症症例はぶどう膜炎症例より内境界膜切除を併用した硝子体手術が有効であると考えられた。
経強膜手術で治療した裂孔原性網膜剥離の長期予後
著者: 鳥居良彦 , 笹野久美子 , 京兼郁江 , 新城ゆかり , 安井修 , 安藤文隆
ページ範囲:P.1255 - P.1258
(P−2-124) 経強膜手術で治療した裂孔原性網膜剥離の術後5年以上経過の追えた症例の長期予後を検討した。症例は144眼,術式は輪状締結術+強膜内陥術85眼,強膜内陥術59眼で,研修医手術症例が89眼,指導医手術症例が55眼であった。研修医手術症例,指導医手術症例ともに長期経過後の視力は良好で,術後合併症の頻度も低く,術後長期予後に差はなかった。適切な指導のもとに行われる研修医の経強膜網膜剥離手術は有効で安全であると考えられた。また,黄斑剥離症例の71%が視力0.5以上に改善し,これらのうち64.3%は12か月以内に最高視力に達したが,35.7%は12か月以上たってから最高視力に達した。
裂孔原性網膜剥離に対する強膜インプラント手術の成績
著者: 田近智之 , 小木曽正博 , 松村香代子 , 井上慎三
ページ範囲:P.1259 - P.1262
(P−2-126) 1996年から1998年までの3年間に,国立善通寺病院眼科で裂孔原性網膜剥離に対し強膜インプラント法で初回手術を行った54例54眼について検討を行った。全例にジアテルミー凝固,シリコンインプラント,輪状締結を行い,40.7%(22眼)に硝子体内気体注入を併用した。初回復位率は81.5%(44眼),再手術では硝子体内気体注入を7眼,インプラント追加+硝子体内気体注入を2眼,硝子体手術を1眼に行い,最終復位率は100%と良好な成績を得ることができた。気体注入の併用が裂孔閉鎖の補助に有用であった。視力は多くの例で改善もしくは不変であったが低下が14.8%あり,術後合併症ではmacular puckerの頻度が高かった。
連載 今月の話題
ミュラー細胞とサイトカイン
著者: 池田恒彦
ページ範囲:P.1025 - P.1031
網膜固有のグリア細胞であるミュラー細胞は,感覚網膜における単なる支持組織としての機能だけでなく,種々のサイトカインや神経伝達物質を介して,周囲のニューロンとも密接な相互作用を有している。ミュラー細胞の機能を理解することは,眼内における細胞増殖,血管新生,神経保護をはじめ,種々の網膜硝子体疾患の病態を解明するうえで重要である。本稿では,ミュラー細胞とサイトカインに関する研究の現状および網膜硝子体疾患との関連を中心に述べる。
眼の組織・病理アトラス・164
ベルガー腔とウイガー靱帯
著者: 猪俣孟 , 吉富文昭 , 沖坂重邦
ページ範囲:P.1034 - P.1035
前硝子体の中央部は水晶体後面の彎曲に対応して浅く陥凹し,膝蓋窩を形成している。前硝子体は膝蓋窩の辺縁で厚くなり,前硝子体と水晶体後嚢とが直径は8〜9mmの大きさで輪状に堅固に接着している。これをウイガーの硝子体水晶体嚢靱帯hyaloideo-capsular ligament of Wiegerという(図1)。それより周辺側に,ガルニエル腔hyaloideo-orbital space of Garnierがあり,前硝子体と水晶体嚢との接着はない。ウイガー靱帯の接着は若年者では強く,高齢になるにつれて弱くなる。したがって,若年者では水晶体嚢内摘出に際して硝子体が牽引されて硝子体脱出を起こしやすいが,高齢者では硝子体が脱出することは少ない。
眼の遺伝病・10
ペリフェリン/RDS遺伝子異常による網膜色素変性(5)—Arg172Trp変異と常染色体優性黄斑ジストロフィ
著者: 玉井信 , 和田裕子 , 中沢満
ページ範囲:P.1037 - P.1039
ペリフェリン/RDS遺伝子のコドン172の点突然変異による常染色体優性錐体—桿体ジストロフィで,家系図に示すように4世代にわたっている(図1)。この家系の遺伝子異常は,コドン172のCGG(arginin)のシトシンがチミンに突然変異を起こしたもので,TGG (tryptophan)とアミノ酸が変異した。
眼科手術のテクニック・126
硝子体手術での内視鏡使用のコツ
著者: 小椋祐一郎
ページ範囲:P.1042 - P.1043
わが国で普及している内視鏡は,ファイバースコープ型のものであり,ハンドピースの先端は20ゲージで,通常の硝子体手術の強膜創から挿入可能である。また,キセノンランプを光源として用いているために照明も明るく,内視鏡の照明のみで十分に手術遂行が可能である。ハンドピースの大きさも,硝子体手術用のライトファイバーと比較してもそれほど大きくなく,慣れれば違和感もなくなる。
他科との連携
ちょっといい話(like a harpist)
著者: 橋本雅人
ページ範囲:P.1268 - P.1269
私は専門分野が神経眼科であるため他科にお世話になる機会が多く,日頃から他科との連携は重要なことだと感じています。特に脳神経外科,放射線科,神経内科,耳鼻科との協力は欠かすことができません。今回与えられたテーマは,これらの科とのつながりについてとのことですので,日常の臨床の場における状況を,脳神経外科と放射線科について,書いてみようと思った次第です。
今月の表紙
増殖性糖尿病網膜症
著者: 寺内渉 , 三宅養三
ページ範囲:P.1041 - P.1041
<撮影データ>
症例は36歳の女性。初診時視力は(0.8)で,汎網膜光凝固を施行し,1年後の現在,視力(1.0)を保っています。
写真(初診時)はコーワPROIIIを使い,十数方向より撮影した蛍光眼底写真をフィルムスキャナで取り込み,パソコンでパノラマに加工したものです。加工はPhotoshop5.0を使い,レイヤー機能で取り込んだ写真をそれぞれの部位に配置し,スタンプツールや消しゴムツールで修正しました。注意点としては,後極部と周辺部のコントラストを合わせること,スタンプツールや消しゴムツールの不透明度を30%前後に下げて修正すること,などがあります。
やさしい目で きびしい目で・6
『ひと呼吸おいて』
著者: 本村幸子
ページ範囲:P.1263 - P.1263
先に,教育の場での忍耐について触れたが,診療の場でも忍耐の一語に尽きる場面が増えてきたような気がする。患者さんが患者様と呼ばれる時代になって,医療を受ける側の患者が弱く,医療を行う側の医師,あるいは施設が決して強い立場ではなくなっている。しかし,これまで,医療従事者は,患者側の訴えや言い分に十分耳を傾けてはいたと思う。患者さんは,特に重篤な状態が急に起こった時には気持ちの整理が出来ていないことが多いので,訴えを整理しながら聞かねばならない。この場合,患者さんの話を決して制してはいけない。根気よく聞き取ることになる。紹介患者さんは,紹介状により病歴をほぼ把握できるが,前医でどのような説明を受けたのか,患者さんの言葉で話してもらうとその理解度を知ることができ,さらに詳細な病歴が得られ,その後の医療を進める上で有益である。しかし,高齢の患者さんが多くなり,病歴聴取は忍耐の一語に尽きる場面が少なくない。限られた診療時間内でのことで,医師側にもいらいらが出てくるが,“ひと呼吸おいて”病歴聴取を継続する。とにかく“納得のいく医療を受けていただければ”という思いに徹する。
つくば市は,研究学園都市として知られてきた。今もその色彩は強く,新しい住民には研究・教育職とその関係者が多い。今はインターネットで個人でもたくさんの情報を得ることができる。患者さんと家族は,病気についてたくさんの情報を引き出してきて,受診されることも少なくない。それゆえ,担当医としてもそれらをもとに発せられる質問にも答えてあげねばならない。医療職以外の方々にもわかるように,一般向けに話をするのには,結構な時間を割かねばならず,時にはうんざりすることもある。このような場面でも,“ひと呼吸おいて”気持ちを和らげ,穏やかな語調で再び話を始めることにしている。話の内容にどんなに不快になっても,一つ深呼吸をして,わずかの間をとると新しい気分になれ,やさしい目にもなれる。
第53回日本臨床眼科学会専門別研究会1999.10.10.10東京
地域予防眼科
著者: 赤松恒彦
ページ範囲:P.1270 - P.1271
1999年の研究会は自由演題形式で行い,眼寄生虫(眼科地理学),老人問題,学校保健,視覚障害者問題,知的障害者問題など多彩な演題がそろった。
第1席,小山泰良(六日市病院)らは「島根県西部において結膜嚢に東洋眼虫が見られた5例」について報告があった。東洋眼虫はインドから東の地域に広く分布するもので,中間宿主メマトイなど小さな昆虫内で感染幼虫となってイヌ,ネコ,人間にも寄生する。今回の症例はすべて結膜嚢に寄生し,結膜炎の症状にて眼科を訪問している。虫体を取り除き,抗菌薬点眼にて軽快したとのことであった。
臨床報告
ベーチェット病の併発白内障に対する手術成績
著者: 合田千穂 , 小竹聡 , 笹本洋一 , 寺山亜希子 , 松田英彦
ページ範囲:P.1272 - P.1276
北海道大学病院眼科で白内障手術を行ったベーチェット病患者の手術成績について検討した。対象は35例56眼で,平均経過観察期間は6年3か月,手術時の平均年齢は49.6歳であった。手術後,56眼中29眼に眼発作が生じ,最終眼発作から3か月以内に手術を行った症例では全例で術後眼発作がみられた。最終眼発作から6か月以内に手術した症例と7か月以上たって手術した症例では,術後眼発作の出現に有意差がみられた。視力予後は,術後3か月では88%の眼で2段階以上視力が上昇していたが,最終受診時に2段階以上視力が上昇していたのは68%であった。視力予後不良例において,手術の術式,眼内レンズ挿入の有無,術前後の投薬に差はなかった。
著明な網膜滲出性病変を呈した後部強膜炎の1例
著者: 林一 , 水澤志保子 , 中村誠 , 藤澤久美子
ページ範囲:P.1277 - P.1281
著明な網膜滲出性病変を呈した後部強膜炎の1例を経験した。症例は48歳女性,主訴は左眼視力低下である。汎ぶどう膜炎症状,硝子体出血および脈絡膜腫瘤形成と著明な網膜滲出性病変を左眼に認めた。特記すべき既往歴なく,当初,仮面症候群や眼悪性リンパ腫などの悪性腫瘍を疑ったが,CT,MRIにて特徴的な後部強膜の肥厚を認め,後部強膜炎と診断した。副腎皮質ステロイド薬の点眼およびプレドニゾロンの全身投与で次第に自覚症状,他覚所見の改善を認め,後部強膜の肥厚も消失した。しかし続発緑内障および併発白内障が生じたため,マイトマイシン併用線維柱帯切除術および超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術を施行し,良好な眼圧コントロールおよび視力を得た。
悪性リンパ腫によるparaneoplastic syndromeが疑われた外眼筋炎の1例
著者: 梅津秀夫 , 馬場哲也 , 野本浩之 , 多田寛
ページ範囲:P.1282 - P.1286
悪性リンパ腫の患者に合併した両眼の外眼筋炎の1症例を報告した。症例は60歳女性で悪性リンパ腫で加療中,眼球突出,眼球運動障害が出現した。CTにて両眼の4直筋肥厚を認めたが眼球内や視神経への浸潤は認めなかった。そして,化学療法にて外眼筋の肥厚は消退し,症状も改善した。腫瘍細胞の外眼筋への直接浸潤では,片眼の単独筋への浸潤が多く,両眼へ浸潤している場合は眼窩,視神経,眼球内にも浸潤していることが多い。このため外眼筋の肥厚は悪性リンパ腫による遠隔効果,すなわちparaneoplastic syndromeであることが疑われた。
著明な網膜および脈絡膜の循環障害を認めた樹氷状血管炎の1例
著者: 松田吉人 , 近藤由佳 , 尾関年則 , 小椋祐一郎
ページ範囲:P.1287 - P.1291
症例は24歳の男性で,2日前からの急激な視力低下を主訴として受診した。初診時,視力は両眼とも手動弁,両眼底には網膜血管の白鞘化,網膜出血,黄斑浮腫があり,樹氷状血管炎に相当する所見であった。フルオレセイン蛍光造影(FA)では,広範な毛細血管の閉塞網膜血管からの蛍光漏出,血管壁の染色がみられ,網膜血管の血流は周辺部で途絶し,インドシアニングリーン蛍光造影(IA)では造影される脈絡膜血管の数は後極部で少なく,脈絡膜は全体的に低蛍光を示した。アシクロビル,プレドニゾロン,アスピリンの全身投与を行ったが,網膜および脈絡膜の循環障害が進行したため汎網膜光凝固術を行い,眼底病変は鎮静化したが,初診2か月後の視力は右眼0.04,左眼0.03とわずかに改善したにとどまった。樹氷状血管炎でも本症例のように視力予後不良な症例もあり時その予後を判断するためにはFAだけでなくIAも必要と考える。
特発性黄斑円孔の術後経過
著者: 尾辻剛 , 岡田守生 , 内田璞
ページ範囲:P.1293 - P.1296
硝子体手術を行った特発性黄斑円孔35眼について,円孔閉鎖率,術後視力,合併症を検討した。12か月以上経過観察できた17眼の平均経過観察期間は19か月で,最長30か月であった。初回手術での閉鎖率は83%,最終的な円孔閉鎖率は89%であった。円孔の閉鎖した31眼では退院時にすべて術前以上の視力となり,その後も視力は徐々に回復した。35眼全例で,術後視力が術前より2段階以上低下した症例はなかった。術後,35眼中21眼(60%)に網膜前膜が形成された。それらの膜は菲薄なものが多く,視力に影響を与えることはなかった。
基本情報
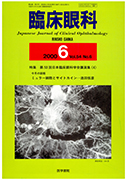
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
