はじめに
医学における古くて新しい課題は,やはり何といっても「感染症の克服」である。生物がこの地球上に誕生し,さらに人類が誕生して以来,感染症との壮絶な戦いは絶えることがなく,現在でも限りなく継続されている。
20世紀後半のある時期には,人類は一瞬「感染症を克服した」かのような錯覚に陥った時期があった。しかし,現実にはエイズの出現や病原性大腸菌感染の大流行によって,これらの空想はあっという間に瓦解してしまった。結局,感染症の克服はいかに大変な永遠の命題であるのかを改めて思い知らされる結果となった。
過去の眼科学の歴史を振り返ってみると,20世紀におけるホワイトアイ診療の進歩はまことにめざましいものであった。特に眼科手術をはじめとする眼外科領域の20世紀における進歩,発展は,後世の歴史に残るものであろう。しかし,現在でも眼感染症対策の重要性は相変わらず大きいものがあり,感染予防や術後感染治療の社会的ニーズはむしろ以前よりいっそう高まったといえるかもしれない。
雑誌目次
臨床眼科57巻11号
2003年10月発行
雑誌目次
特集 眼感染症診療ガイド
序文 フリーアクセス
著者: 大野重昭
ページ範囲:P.7 - P.8
I.眼感染症のトピックス
免疫不全と眼感染症
著者: 永田洋一
ページ範囲:P.10 - P.15
生体は細菌やウイルスなどの微生物による攻撃を受けているが,液性免疫や細胞性免疫,食細胞,補体からなる精巧な生体防御機構により絶えず撃退している。これが障害され易感染性を呈する状態を免疫不全といい,カリニ肺炎やサイトメガロウイルス(cytomegalovirus:CMV)肺炎,口腔内カンジダ症,帯状疱疹などの感染症を引き起こしていくが,特徴として,➀ 繰り返し起きる,➁ 重症化し難治である,➂ 病原性の弱い微生物による日和見感染症を起こす,などがある。原発性免疫不全症と続発性免疫不全症とに大別され(表1),後者ではヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus:HIV)感染による後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome:AIDS)と,悪性腫瘍や膠原病,臓器移植における抗癌薬や免疫抑制薬の投与による医原性のものが代表的である。近年の医療技術の飛躍的な進歩により,免疫能が極度に低下した状態でも生存できるようになってきているが,日和見感染症を起こす危険性が増えているのも事実である。
眼感染症としては,眼局所単独で生じることもあるが,全身感染症の一部分として起きることが多い(表2)。健常人に発症した場合と臨床像を異にすることがあり,また,同時に複数の微生物による感染症をきたすこともあるので,診断や治療にあたっては慎重に対処すべきである。本項では,免疫不全患者に合併しやすい感染症について概説した後に,最もよくみられるサイトメガロウイルス網膜炎について述べる。
性感染症と眼感染症
著者: 田川義継
ページ範囲:P.16 - P.20
はじめに
性感染症(sexually transmitted disease:STD)は,性行為により直接泌尿生殖器やその付属器を介し,また産道を介した母子の垂直感染などにより生じる感染症の総称で,古典的なSTDとして淋病,梅毒,軟性下疳,鼠径リンパ肉芽腫の4大性感染症がある。しかし,近年AIDS(HIV)の出現やHTLV-1,クラミジア,C型肝炎ウイルスなど多くの病原体が性行為を介して感染が生じることが明らかとなってきており,古典的な性感染症の概念は大きく変貌してきている。性感染症の原因病原体を表1に挙げたが,近年,このほかにも性行為で感染する可能性のある病原体としてアデノウイルス19型や37型など粘膜を介して感染する機会のある病原体の多くが挙げられている。ここでは,性感染症のなかで,眼科領域の疾患と関連の深い感染症について概説する。
院内感染
著者: 竹内聡
ページ範囲:P.22 - P.27
院内感染とは
院内感染とは,医療施設で治療を受けている患者が,原疾患とは別の新たな感染を院内で受けて発症することである。原疾患を治療するために医療施設にかかっているのにもかかわらず,新たな病気を与えてしまうことは,患者に精神的にも経済的にも苦痛を負わせることになる。
眼科領域で院内感染が話題となるとき,まず考えるのはウイルス性結膜炎,特にアデノウイルスによる結膜炎である。眼科日常診療において遭遇する機会も多いうえ,その感染力の強さから,一度院内感染が起きるとなかなか鎮静化できない。ほかに眼科院内感染には,急性出血性結膜炎やMRSA・MRSEによる結膜炎,術後感染症などが挙げられる(表1)。流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,MRSA感染症のいずれも,国の感染症新法で四類感染症に定められ,指定された医療機関からの届出報告から発生状況を分析し,拡大を防止すべき感染症とされている。
コンタクトレンズ角膜感染症―リスクファクターと予防
著者: 猪原博之
ページ範囲:P.28 - P.33
はじめに
現在わが国では1,000万人以上がコンタクトレンズを装用していると考えられている。今後遠近両用コンタクトレンズや虹彩付コンタクトレンズなどの普及とともに装用人口はさらに増加していくことが予測され,装用に伴う合併症の予防は重要である。特に角膜感染症は重症化すると重篤な視力障害を残すため,適切な装用指導や感染症予防の啓蒙は眼科医の社会的責務であると思われる。
PMMA(polymethyl methacrylate)レンズが主に処方された頃にはしばしば角膜上皮障害を生じていたが,重篤な角膜感染症の報告は少なかった。1980年代に入って連続装用ソフトコンタクトレンズが使用されるようになり,コンタクトレンズに起因する角膜感染症の報告が多くみられるようになった。これには,レンズ素材のガス透過性が比較的低く,それによる角膜上皮障害とレンズの汚れによる起因菌の持ち込みが考えられた。わが国では1991年代よりディスポーザブルコンタクトレンズ(disposable soft contact lens:DSCL)が,1994年より頻回交換コンタクトレンズ(frequent replacement soft contact lens:FRCL),1995年より毎日交換DSCL(daily-wear disposable soft contact lens:DWDSCL)の販売が開始された。これらの普及によりコンタクトレンズによる角膜感染症の発症率が減ることが期待されている。しかしFRCL,DWDSCLがわが国のコンタクトレンズのシェアに大きな比率を占めるに至った現在でも角膜感染症は後を絶たない。
眼感染症とバイオフィルム
著者: 三原悦子
ページ範囲:P.34 - P.39
バイオフィルムの概念
バイオフィルム(biofilm)はその言葉どおり「生物が作ったフィルム」で,菌自体の産生するグリコカリクス(glycocalyx)と呼ばれる菌体外多糖が細胞壁の周囲を取り囲むような粘液層を形成し,そのなかで細菌がコロニーを形成した状態である(図1)1)。
一般に細菌は自己の生息にとって不利な環境におかれた場合,周囲に多糖体(glycocalyx)を産生する。これを介して隣接した細菌が互いに凝集し,一塊となって付着表面に細菌の膜層,すなわちbioのfilm,biofilmを形成する2)。つまりバイオフィルムは住みにくい環境で生き残るために編み出された細菌の増殖様式なのである。このことは,例えば川底の石の表面などにみられるように,自然界に生息している細菌にみられる普遍的な姿として認識されている。
アトピー性皮膚炎と眼感染症
著者: 井上幸次
ページ範囲:P.40 - P.45
はじめに
アトピー性皮膚炎(atopic dermatitis:AD)は,アレルギー反応によって特徴的な慢性皮膚炎症の寛解と増悪を繰り返す疾患である。しばしば血清総IgEの上昇を伴っている。患者はそう痒感が強く,その閾値が低くなっている。そのため患者は皮膚をこすったり掻いたりするので皮膚炎症は悪化し,さらに強いそう痒感を起こす原因となるため悪循環が成立する。遺伝的素因と環境因子の両者がこの疾患の発症と関与している。わが国では最近アトピー性皮膚炎患者が非常に増加して世界でも有数の罹病率となっており,若年者に多い病気だけに社会的な問題となっている。
アトピー性皮膚炎は多くの眼合併症を併発してくることが知られている。アトピー性角結膜炎(atopic keratoconjunctivitis:AKC)はなかでも最も頻度が高く,眼瞼結膜の浮腫と乳頭増殖とともにそう痒と流涙を訴える。アトピー性角結膜炎の重症例ではシールド潰瘍(shield ulcer)やプラーク(epithelial plaque)を生じてくるため,これが瘢痕を残せば恒久的な視力障害につながる。
アトピー白内障・円錐角膜・網膜剝離もアトピー性皮膚炎の合併症としてよく知られているが,これらは眼科手術の対象になることも多く,アトピー性皮膚炎患者の眼科手術が増加すると,後述する術後感染症が非常に大きな問題となってくるのである。
このようなよく知られた眼合併症以外に,アトピー性皮膚炎では感染症を生じやすいことが知られており,それが眼感染症の発症にもつながってくる。本項では特に黄色ブドウ球菌と単純ヘルペスウイルスについて,眼感染症のみならず全身的な観点から解説し,そのような感染を起こしやすい機序についても考察したい。
アレルギー性結膜疾患とウイルス感染
著者: 藤島浩
ページ範囲:P.46 - P.49
はじめに
眼感染症でも特にウイルス感染によるアレルギー性結膜炎との因果関係というと不思議な感覚をもたれるかもしれない。眼表面は外来抗原に対するアレルギー疾患の標的となりやすい部位の1つであることからアレルギー反応を起こしやすい臓器であるといえるが,これはとりわけ環境因子の影響を受けやすいという意味でもある。アレルギーの環境因子としては紫外線やディーゼルガスなどが有名であるが,本項ではウイルス感染がアレルギー性結膜炎発症原因の環境因子の1つになっているのではないかというわれわれの検討報告をもとに,その可能性について考察を交えて紹介する。
屈折矯正手術後の感染症
著者: 堀裕一 , 渡辺仁
ページ範囲:P.50 - P.53
はじめに
屈折矯正術後の感染症は,合併症のなかでは比較的稀に起こるものであるが,その症例報告はいまだ後を絶たない。さらに,屈折矯正術後の感染症はいったん発生すると,たとえ治癒しても角膜混濁や不正乱視が残存する可能性が高く,重大な合併症につながるために厳重な注意を要する。最近では,両眼同日手術も多く行われていることから,両眼に同時に感染症を起こす例も報告されている1~3)。屈折矯正手術は眼科の手術のなかでも短時間で終了し,患者さんへの負担が少ない手術のため,術後感染症に対する注意が希薄になりがちであるが,手術である以上,常に感染症が起こりうることを,術者やスタッフをはじめ,医療機関全体で意識しておかなければならない。
マイボーム腺炎角膜上皮症
著者: 鈴木智
ページ範囲:P.54 - P.59
はじめに
日常臨床では,しばしばオキュラーサーフェス(ocular surface)に軽度の炎症を伴った角膜上皮障害を認める。このような場合,ドライアイ,アレルギー性結膜炎,ブドウ球菌性眼瞼結膜炎などを鑑別診断として考えながら診断していくことが多いが,診断に基づく治療が奏効せず,角膜上皮障害が遷延したり,寛解・増悪を繰り返す症例に悩むことがある。このような原因の明らかでない角膜上皮障害を生じる疾患のなかに,マイボーム腺の炎症が関連している疾患があると筆者らは考え,それを「マイボーム腺炎角膜上皮症」と呼ぶことを提唱した1)。McCulleyらの提唱している「閉塞性マイボーム腺機能不全に伴う蒸発亢進型ドライアイによって生じる角膜の点状表層角膜炎(meibomian keratoconjunctivitis)」2)とは異なり,「細菌感染に伴って生じるマイボーム腺そのものの炎症が角膜上皮障害と関連している」というのがこのコンセプトの基本である。このコンセプトを用いることによって,難治性の角膜上皮障害を的確に治療できることがあるので筆者らは正しいと信じているが,角膜専門医の間でも必ずしも広く認められたものではないということを付記しておく。
新興・再興感染症
著者: 林皓三郎
ページ範囲:P.60 - P.65
はじめに
新しいコロナウイルス(SARSウイルス)による肺炎は,病因ウイルスの迅速な伝播力と強い病原性によってすでに8,000人を超える感染患者と800人以上の死亡者を出している。各地で懸命の防疫対策が取られようやく終息したものの,次の流行がまたいつ起こるか予断を許さない状況である。原因病原体の同定・診断は極めて迅速に行われたが,その治療薬・ワクチンの開発はどんなにうまく事が進んだとしても2~3年はかかると考えられる。こうした情勢から国際的に旅行が制限され,旅客機の運行回数が減り,政治経済を含む社会生活全般にわたる大パニックが引き起こされていて,その影響はイラク戦争以上であるといわれている。本来鳥の感染ウイルスであったものが,何らかの機序でヒトに広がったものであるらしい。このことは感染症が過去の病気であるという思い込みが,いかに的はずれなものであったかをまことに如実に示している。
公衆衛生の改善,抗生物質・抗菌薬・抗ウイルス薬の発達,ワクチンの開発と普及,迅速かつ正確な診断法の進歩などが感染症の予防・治療に貢献してきたことは確かであるが,その一方では新たな感染症(新興感染症)が次々に報告され,いったん下火になっていた感染症がまた新たな装いで(薬剤耐性株として)現れている(再興感染症)のが現状である。
過去25年ほど(1970年頃以来)の間に新たに問題になってきたこうした疾患は40種類以上に上る(表1)。
耐性菌感染症
著者: 浅利誠志
ページ範囲:P.66 - P.74
はじめに
交通網の発達により,異なる地域で発生した新興感染症(emerging infectious disease:EID)や多剤耐性菌は瞬く間に世界中を駆け巡る時代となった。本年,東南アジアを中心に大問題となった重症急性呼吸器症候群(severe acute respiratory syndrome:SARS)がまさにそのものであるが,眼感染症の起因菌である多剤耐性菌も過去に生じSARSと同様に世界伝播したものである。
薬剤耐性菌が世界的に問題視されるなかで適切な眼感染症治療を行うには,耐性菌に関する理解を深め「耐性菌を生じにくい治療」を認識・実践することが大切である。
感染症に対する羊膜移植の実際とその効果
著者: 久保真人
ページ範囲:P.75 - P.80
はじめに
感染性角膜疾患に対する治療は,抗菌薬をはじめとする薬物療法が主体であるが,穿孔をきたした場合や強い眼表面の瘢痕化を呈している場合には外科的療法が必要である。穿孔例では閉鎖する移植材料の選択に苦慮する。代表的な術式として表層角膜移植術,結膜移植,羊膜移植が挙げられるが,表層角膜移植や治療的角膜移植は手技や移植片の入手が困難であり,結膜移植は,角膜病巣の炎症の波及により結膜の状態が不良な場合は不可能となる。また,ホスト角膜が融解しつつある例では縫合が容易ではなく,術後の病巣の透見も困難である。さらに,結膜を用いる際には僚眼の結膜の状態いかんによっては採取がむずかしく,瘢痕結膜を有する不良例などは適応から除外しなければならない。羊膜移植は保存が可能であることから緊急時の対応が容易であり,またこれまでに拒絶反応の報告はなく手技や入手も比較的容易であることから,穿孔に対する補填材料として有用であると考えられる。
感染症に対する羊膜移植については,移植羊膜の存在が病変部の視認性を悪くすることや,移植羊膜が新たな感染の土壌となる危険性などの理由から,禁忌と考えられてきた。しかし,羊膜のもつ細胞生物学的・免疫学的特殊性が次第に解明され1,5~17),羊膜移植が普及するにつれて臨床応用の範囲も拡大し,感染性眼表面疾患に対して羊膜移植を施行して奏効を得たとする報告が散見されるようになった2~4)。ここでは,感染性角膜疾患に対する羊膜移植の実際とその効果について述べる。
小児眼感染症の最近の動向
著者: 亀井裕子
ページ範囲:P.81 - P.85
はじめに
小児にみられる眼感染症は,結膜炎に代表される外眼部疾患が大半を占め,ほとんどが前眼部の疾患群であるという傾向は,過去から現在に至るまで大きな変化はない。しかしながら,原因微生物のパターンには若干の変化がある。いわゆる「新興感染症」「再興感染症」の存在がそれに相当する。例えば,細菌感染における起炎菌のパターンや,分離菌の薬剤感受性には変化がみられる。周知のように,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(meticilin resistant Stapylococcus aureus:MRSA)やペニシリン耐性肺炎球菌(penicillin resistant Streptococcus pneumoniae:PRSP)に代表される新たな耐性菌の出現は枚挙にいとまがないが,これらの菌による眼感染症は小児にも触手を伸ばしている。
また,近年の性感染症(sexually transmitted disease:STD)の蔓延に伴い,クラミジアや淋菌感染症の増加が懸念される。さらに,ペットとの接触や海外旅行の日常化により,トキソカラ症などの原虫感染症に代表される人畜共通感染症も問題視されている。
本項では最近の眼感染症の傾向を勘案して,外来診療で遭遇する頻度の高い眼感染症を中心にその概要を解説したい。
II.診断・治療のポイント 眼瞼・涙器・眼窩
【総論】眼瞼炎―感染か,非感染か
著者: 原二郎
ページ範囲:P.90 - P.94
眼瞼炎は解剖学的にanterior blepharitis(眼瞼炎),posterior blepharitis(マイボーム腺炎,内麦粒腫)と分類することがあるが(「マイボーム腺炎角膜上皮症」の項を参照),ここでは眼瞼皮膚を主として感染(細菌・ウイルスによる),非感染に分けて臨床診断の要点を述べる。一般的には,感染性のものでは炎症が強く結膜炎を伴うことが多い。非感染の場合には炎症は軽く痒みがあり,反復しやすい。
麦粒腫・霰粒腫
著者: 原二郎
ページ範囲:P.95 - P.99
麦粒腫
1.診断
3つのポイント
・眼瞼に限局性発赤・腫脹と圧痛がある。
・片眼性で急に発症し,初期は瞬目に伴う疼痛がある。
・末期には膿点を形成する。
多くは片眼のみにみられ,発症して1週間以内に受診する。眼瞼の限局性発赤・腫脹があり,その部に圧痛がある。自発痛もあるが,軽症では瞬目に伴う疼痛のみを訴える。ときに眼脂・涙流・結膜浮腫も伴う。進行すれば膿点を形成する。外麦粒腫(睫毛の皮脂腺〔ツァイツ腺〕や汗腺〔モル腺〕の急性化膿性炎症)と内麦粒腫(マイボーム腺の急性化膿性炎症)で病像が異なる1,2)。外麦粒腫では眼瞼の発赤・腫脹があり(図1),内麦粒腫では眼瞼を反転すると膿点を認める(図2)ことが多く,進行して眼瞼皮膚にも発赤をきたす例がある。
涙囊炎
著者: 栗橋克昭
ページ範囲:P.100 - P.105
はじめに
涙囊炎(dacryocystitis)1~9)の起炎菌についていろいろと報告されているが,涙囊鼻腔吻合術(dacryocystorhinostomy:DCR)が成功しドレナージが十分になされると,MRSAが起炎菌でも治癒してしまう。涙囊炎の起炎菌追求と保存的治療だけにとらわれず,できるだけ早期にDCRができる術者に主導権を渡すことが重要である。筆者らの施設では,ほとんどすべてのDCRを日帰り全身麻酔や局所麻酔で行っている。涙囊炎やそれに続発する眼窩膿瘍や眼球突出はブジーやシリコーンチューブ留置の合併症として挙げられるが,本項においては,ヌンチャク型シリコーンチューブ(NST)10),ブジー(probing),DCRに関連させて涙囊炎について述べてみたい。
涙小管炎
著者: 栗橋克昭
ページ範囲:P.107 - P.113
はじめに
涙小管炎1~10)(canaliculitis,図1,2)についてはその原因菌が精力的に追究され研究されているのは,涙小管炎が稀な疾患というだけでなく,従来の鋭匙による涙小管掻爬では涙石を取り残し再発することが稀でないという実情が関係しているであろう。KMTS(Kurihashi's multiple traction sutures)11,12)(図1c~f,2,3)をかけて涙小管水平部を切開し,その開いた部分からも涙石を直視下で完全に除去することが容易にできるようになった。涙石を完全に除去すると,どのような菌であれ涙小管炎は治癒し再発しなくなる。原因菌に対する追究,保存的治療,涙小管掻爬の繰り返しにこだわらず,KMTSをかけ直視下で完全に涙石を除去する必要がある。
本項においてはKMTSだけでなく,診断の一助として綿糸法,濾紙法,TMH,色素残留テストからなる精密涙分泌テスト10)を行い涙分泌速度だけでなく導涙速度(導涙機能)もチェックすることが重要と考えられるので,それについても触れる。
眼窩蜂巣炎
著者: 中尾雄三
ページ範囲:P.114 - P.116
診断のポイント
1.症状・所見
1)眼所見
眼窩蜂巣炎では眼瞼の浮腫と発赤がみられ,眼瞼下垂をみることが多い。眼球は突出し,眼球運動は全方向に障害され,痛みを感じ,流涙がみられる。眼球結膜は拡張・蛇行で発赤し,著しい結膜浮腫(chemosis)があり,このために閉瞼が不能なことがある。炎症による極端な眼窩内圧の上昇で眼圧は上昇し,視神経障害も加わると視力が低下することもある。眼底所見では網膜静脈が拡張し,視神経乳頭の軽い浮腫がみられる。眼球周囲から頭部にかけての痛みがあり,眼窩周囲の異常知覚を訴えることもある1~3)。
結膜
【総論】結膜炎―感染か,非感染か
著者: 内尾英一
ページ範囲:P.118 - P.121
結膜充血で感染・非感染が見分けられるか
ポイント
・結膜炎は充血だけで感染・非感染の鑑別を行うことは不可能である。
結膜炎は感染性,非感染性を含めて,日常臨床では非常に頻度の高い疾患であり,「目が赤くなりました」という主訴の患者は,毛様充血によるぶどう膜炎や,通常眼痛を伴う強膜炎を除くと,ほとんどが何らかの結膜炎である。感染性結膜炎には細菌,クラミジア,ウイルスによるそれぞれの結膜炎があり,非感染性結膜炎にはアレルギー性結膜炎などのアレルギー性結膜疾患や,頻度は高くないがフリクテン・瞼裂斑炎などの広義のアレルギー疾患というべきものがある。結膜は非角化重層扁平上皮におおわれ,下部の強膜と結合組織とにlooseに接合しており,血管が豊富な組織である。結膜炎はこの組織学的特徴から種々の臨床所見を示し,充血だけで感染・非感染の鑑別を行うことはまず不可能である。自覚症状やいくつかの臨床所見の組み合わせ,そして時には検査所見も併せて,感染性か非感染性かの判断を行わなくてはならないところに,結膜炎の診断のむずかしさがある。
アデノウイルス結膜炎
著者: 内尾英一
ページ範囲:P.122 - P.125
診断
3つのポイント
・臨床症状の重症度は,血清型よりも全身・局所の免疫状態に左右される。
・感染性は中和抗体価が上昇する発症後10日まで存在する。
・迅速診断キットはウイルス量に結果が左右される。陰性でもアデノウイルス感染を否定はできない。
1.臨床症状
アデノウイルス結膜炎は潜伏期7~10日で発症する。典型的な症例では急性濾胞性結膜炎(図1),角膜上皮下混濁(図2),耳前リンパ節腫脹がみられる。アデノウイルスには現在51の血清型があり,生物学的共通点からA~Fの6つの亜属に分類される(表1)。結膜炎はB,DおよびE亜属によるが,亜属により臨床像は特徴がある。かつて典型例は8型によるものに限られるとされてきたが,D亜属の19型や37型でも同様の所見を呈する。B亜属によるものでも,臨床症状ではD亜属による症例と区別できない例も多く,むしろ患者の年齢やアトピー性皮膚炎などの全身・局所の免疫状態により異なることが多い。アトピー性皮膚炎合併例などでは臨床症状も強く,角膜浮腫がみられることもあるが,結膜偽膜なども含め,永続的な合併症として残存することはまずない。発症早期にはしばしば点状表層角膜症を生じ,時に結膜偽膜(図3),結膜下出血や瞼球癒着のみられる症例もある。
臨床症状は発症後5~8日頃に最も強くなり,通常は発症後約2週間で自覚・他覚所見ともに軽快するが,感染性は血清中和抗体価が上昇する発症10日頃までと考えられるため,発症後7~10日間は登校や勤務を停止させることにより隔離すべきである。
エンテロウイルス結膜炎
著者: 中川尚
ページ範囲:P.126 - P.131
はじめに
エンテロウイルスによって起こる結膜炎は急性出血性結膜炎(acute hemorrhagic conjunctivitis:AHC)である。病原となるエンテロウイルスには,エンテロウイルス70(EV70)とコクサッキーウイルスA24変異株(CA24v)の2種類があり,臨床的には類似の症状・所見を示す。
急性出血性結膜炎は急性伝染性結膜炎の1つで,眼科領域ではアデノウイルスによる流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis:EKC)とともに厚生労働省の感染症サーベイランスの対象疾患になっている。現在,全国に約600の眼科観測定点があり,これらの定点からの報告数はインターネット上で閲覧できる。現在の流行状況を知ることも診断の一助になる(感染症情報センター:http://idsc.nih.go.jp/kanja/index-j.html)。
本項ではエンテロウイルス結膜炎の臨床診断,実験室診断,治療について解説する。
単純ヘルペスウイルス結膜炎
著者: 青木功喜
ページ範囲:P.132 - P.134
単純ヘルペスウイルスの組織親和性
ウイルスが特定の組織に親和性を示す原因はウイルス側と宿主側にあると考えられている。単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus:HSV)は眼瞼,角膜,結膜,網膜に病変を起こす。特に前眼部の結膜,角膜と眼瞼の病変はよく知られている。しかし,その理由について疑問なところも少なくない。
単純ヘルペスウイルスは皮膚,粘膜に親和性がある。角膜病変は視力という面からよく研究されてきたが,結膜炎についてはこのウイルスの初感染のときに多いと理解されている。しかしその疫学に対する記載は少ない。皮膚科でみられる単純ヘルペスウイルスの病変は眼病変よりも多い。私が札幌の同じ地域で皮膚科を開業している皮膚科医と一緒にその頻度を検討した際には,皮膚科では眼科より10倍以上多い患者を診察していた。また眼病変の頻度では眼瞼病変が最も高く,次いで結膜炎で,角膜炎は最も低かった。眼科外来で単純ヘルペスウイルスによる眼瞼炎(図1)が結膜炎を合併する頻度は30%である。結膜病変が角膜に及ぶのは20%である。眼瞼炎と角膜病変は一般的であるが結膜炎にも注目しておく必要がある。
クラミジア結膜炎
著者: 伊勢知弘 , 塩田洋
ページ範囲:P.137 - P.140
クラミジア結膜炎は主にChlamydia trachomatisによって起こる結膜感染症で,臨床的にトラコーマと封入体結膜炎に分けられる。
トラコーマは眼から眼へ伝播して起こる慢性の結膜炎で濾胞形成,乳頭増殖,パンヌスなどを特徴とし,瞼球癒着,角膜混濁といった後遺症を残し失明に至ることもあった。感染の反復による免疫機序の関与により,トラコーマの病像がつくられると考えられている。しかし,現在,先進国では衛生状態の改善などにより再感染の機会がなくなったため,ほとんどみられなくなった。
細菌性結膜炎
著者: 大橋秀行
ページ範囲:P.142 - P.147
起炎菌
細菌性結膜炎には好発年齢があり,小児と高齢者によく認められる。小児では急性カタル性結膜炎を呈し,インフルエンザ菌,肺炎球菌,ブドウ球菌が起炎菌である(表1)1~4)。季節的には冬季に多い。一方,高齢者では慢性結膜炎を呈することが多く,起炎菌として黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌を代表とするコアグラーゼ陰性ブドウ球菌などが挙げられる。また眼脂の性状によりある程度起炎菌の推測はできる(表2)。
角膜
【総論】角膜炎―感染か,非感染か
著者: 檜垣史郎
ページ範囲:P.149 - P.151
はじめに
角膜炎のうち,細菌性角膜炎,角膜真菌症,アカントアメーバ角膜炎,角膜ヘルペス,角膜実質炎,モーレン角膜潰瘍,膠原病に伴う周辺性角膜潰瘍,カタル性角膜潰瘍,角膜フリクテン,コンタクトレンズに関連するものなどが比較的,頻度が高いと考えられる。
感染に伴う角膜炎では黄色調の浸潤,膿性眼脂をしばしば認める。感染によるものか非感染かの鑑別に困るものとして,まず周辺性角膜炎が挙げられる。すなわちモーレン角膜潰瘍,膠原病に伴う周辺性角膜潰瘍,カタル性角膜潰瘍,ペルーシド角膜変性,テリエン周辺角膜変性,周辺部の角膜ヘルペスなどであろう。細菌性角膜炎,角膜真菌症,アカントアメーバ角膜炎,角膜ヘルペスについては他項に詳述されているので,以下,非感染の周辺性角膜炎を中心に述べたい。
角膜ヘルペス
著者: 檜垣史郎
ページ範囲:P.152 - P.155
単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus:HSV)によって生じる角膜炎を,一般に角膜ヘルペスと呼んでいる。また,HSV-1,2(単純ヘルペスウイルス1型,2型)による前眼部病変として,樹枝状角膜炎,地図状角膜炎,円板状角膜炎,壊死性角膜炎,栄養障害性角膜炎,角膜内皮炎,角膜ぶどう膜炎などが知られている。
眼部帯状疱疹
著者: 高村悦子
ページ範囲:P.156 - P.161
はじめに
水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella-zoster virus:VZV)は,初感染では水痘を発症しその後神経節の外套細胞に潜伏し,何らかの誘因でウイルスの再活性化が起こり,眼部帯状疱疹として再発する。健常人における再発の誘因は明らかではないが,若年者での再発やいくつかの神経節からの再発を短期間に起こす場合には,HIV感染など免疫機能が低下した状態が背景にある場合もある。
細菌性角膜潰瘍
著者: 庄司純
ページ範囲:P.162 - P.169
はじめに
細菌性角膜潰瘍は,角膜外傷,コンタクトレンズ障害などが誘因となって生じる角膜感染症である。原因菌は,ブドウ球菌・肺炎球菌・緑膿菌・セラチアなどに代表される細菌であるが,細菌の種類により病態や治療法が大きく異なる。したがって,細菌性角膜潰瘍に対する治療の第一歩は原因菌の診断であり,原因菌に対する治療法の選択や合併症対策が次のステップとなる。しかし,すべての症例で原因菌が確定できるとは限らない。このような原因菌不明の症例に対しては,感染症発症の誘因,細隙灯顕微鏡などによる角膜所見など,できる限りの情報から治療法を選択しなくてはならないことがたびたび経験される。本項では,これらのことを踏まえながら,細菌性角膜潰瘍の診断と治療のポイントについて述べる。
角膜真菌症
著者: 稲田紀子
ページ範囲:P.170 - P.175
はじめに
角膜真菌症は症例数としては少ない疾患ではあるが,診断や治療の遅れによって重症化する場合があり,角膜感染症が疑われたときには必ず鑑別しなければならない疾患である。
アカントアメーバ角膜炎
著者: 石橋康久
ページ範囲:P.176 - P.181
アカントアメーバ角膜炎は1974年に欧米で初めて報告され1),その後コンタクトレンズ装用との関連が注目され,話題となった疾患である。わが国では石橋ら2)が初めての症例を1988年に報告し,その後,2003年までに100例を超える症例が知られるようになっている。コンタクトレンズ装用の既往がなく,外傷によると考えられるものは10~15%と少なく,85~90%とほとんどの症例がコンタクトレンズ装用によるものである3)。ソフトコンタクトレンズ装用者,特にわが国では非含水性のソフトコンタクトレンズ(ソフィーナ)が症例の半数を占めているが,それ以外のすべての種類のコンタクトレンズに症例が報告され,安全であると宣伝されている使い捨てソフトコンタクトレンズも例外ではない4,5)。
本項では,本症の診断および治療におけるポイントについて述べる。
ぶどう膜・網膜
【総論】ぶどう膜炎―感染か,非感染か
著者: 望月啜
ページ範囲:P.183 - P.185
はじめに
ぶどう膜炎は,感染性ぶどう膜炎,非感染性ぶどう膜炎,特発性ぶどう膜炎の3つのカテゴリーに大別されるが,そのなかで感染性ぶどう膜炎が占める割合は10~30%である。筆者が関係している2つの医療施設における感染性ぶどう膜炎の内訳を表1に示す。これらのデータから,➀ 地域差があること,➁ ウイスル感染に関連する疾患(急性網膜壊死,ヘルペス性虹彩炎,サイトメガロウイスル網膜炎,HTLV-1ぶどう膜炎など)が大きな比重を占めること,➂ 人畜共通感染症(眼トキソカラ症,眼トキソプラズマ症,猫ひっかき病)も重要であること,➃ 古典的な梅毒や結核によるぶどう膜炎は少ないが,結核性網膜血管炎と診断される症例は少なくないこと,などが感染性ぶどう膜炎の特徴として挙げられる。
結核性ぶどう膜炎
著者: 後藤浩
ページ範囲:P.186 - P.190
最近の結核の動向
わが国における結核患者は1951年の結核予防法の制定,1961年の患者管理制度の強化などにより,着実に減少していった。1951年当時の新規登録患者数が60万人(対10万罹患率698),死亡者10万人(対10万110)であったのに対し,50年後の現在は新規登録患者4万人弱(対10万31),死亡者2,600人と激減している1)。しかし,近年になって欧米諸国において再興感染症として台頭してきた結核感染が日本でも同様の兆しを示すようになり,次第に罹患者の減少傾向に歯止めがかかってしまった。世界保健機構(WHO)による1993年の緊急事態宣言から4年経過した1997年には,わが国でも新規登録患者数と罹患率が増加に転じてしまい2),1999年に厚生省から同様の宣言が提起されたことは記憶に新しい。しかも,日本は先進国のなかでは死亡率が極めて高いのが特徴である。
わが国で結核が再び台頭してきた背景には,人口構成の高齢化やpatient's delay,doctor's delayといった患者発見の遅れ,すなわち,受診と診断の遅れによる感染の拡大が指摘されている3)。
従来行われていた小学校1年生および中学校1年生を対象としたツベルクリン反応検査はまもなく廃止となるが,一方で弱毒結核菌,リコンビナントBCG,サブユニットワクチン,DNAワクチンなどの開発が進められている4)。
梅毒性ぶどう膜炎
著者: 松尾俊彦
ページ範囲:P.191 - P.194
はじめに
梅毒は減少してきたが,なお注意しなければならない感染症である。最近,性生活の多様性から,一時期よりむしろ増加してきている。梅毒は,結核とともに非特異的な眼底病変を呈することが多いので,ぶどう膜炎および網膜病変の鑑別診断として常に梅毒,結核を念頭に置く必要がある。
眼科医が出会う梅毒病変としては,➀ 梅毒の初回感染時にみられる活動性のぶどう膜・網膜炎,➁ 以前,梅毒に感染し炎症自体は治まったが,そのなごりとしてみられる網膜変性,角膜混濁や続発閉塞隅角緑内障,➂ 先天梅毒,の3つの場合である。
猫ひっかき病
著者: 加島陽二
ページ範囲:P.195 - P.200
猫ひっかき病とは
猫ひっかき病は,その名の通りネコの爪・歯牙による皮膚外傷が原因で,発熱,感冒様症状,リンパ節腫脹を主症状にした疾患であり,主に小児科領域で扱われてきた1)。その合併症としては眼症状以外に,いずれも稀ではあるが痙攣を主とする中枢神経系障害,肝脾腫などの報告がある2,3)。眼合併症としては濾胞性結膜炎に耳前リンパ節腫脹を伴うParinaud oculo-glandular syndrome(パリノー症候群)および視神経網膜炎が有名である。近年,本症の原因菌としてグラム陰性桿菌であるBartonella henselaeが同定され,さらに血清学的診断法などの補助診断法が導入されたことで,いままで原因不明とされていた視神経網膜炎,ブドウ膜炎のなかに本症が埋もれていた可能性が指摘されている4)。
典型的な症例では,受傷後数日~2週間前後で受傷部位に赤紫色の丘疹が出現し,膿疱,痂皮の形成(初期皮膚病巣)をみる。軽い病変では,患者は普段より傷の治りが遅いと思う程度で終わることもある。皮膚病変が出現してからさらに2~3週間後に,受傷部位の所属リンパ節の疼痛を伴う腫脹が起こる(図1)。リンパ節は発赤・腫脹し,膿瘍を形成することもある。全身症状としては比較的軽く,数日程度の発熱などの感冒様症状が主体であり,多くの症例で合併症はなく,1週間以内に解熱する単峰性の経過をとる。
眼トキソプラズマ症
著者: 建林美佐子 , 大黒伸行
ページ範囲:P.202 - P.206
病原体と感染経路
病原体であるトキソプラズマ原虫(Toxoplasma gondii)は人畜共通感染性の細胞内寄生原虫でありネコを終宿主とする。ヒトへの感染はネコの糞便中の接合子囊,生肉中の増殖体や囊胞などが経口,経気道または経皮的に感染する後天感染と,妊婦の初感染の際に増殖体が経胎盤的に胎児に移行する先天感染とがある。
不顕性感染が多く,日本では成人の約3割が感染しているとされるが,その率は近年低下傾向にある。また,胎児感染の危険率は妊娠13週で6%,妊娠26週で40%,妊娠36週で72%と妊娠週数とともに上昇する一方,先天感染した場合に3歳までに臨床症状を呈する確率は妊娠13週で61%,妊娠26週で25%,妊娠36週で9%と,妊娠週数とともに低下する。したがって,先天性トキソプラズマ症の発症危険率は妊娠24~30週の初感染で最も高く約10%とされる。また,母体の初感染時期が妊娠初期であるほど児の症状は重篤である。
眼イヌ回虫症
著者: 佐藤達彦
ページ範囲:P.208 - P.211
はじめに
寄生虫にはおのおの固有の宿主特異性があり,通常その固有宿主(終宿主)の体内で成虫となり寄生する。しかし,本来ヒトを終宿主としない寄生虫が偶然にも虫卵や幼虫の段階でヒトの体内に迷入した場合,ヒトの体内で幼虫のまま長期間生存し,体内を移行することによりさまざまな臨床症状を示すことがあり,これを幼虫移行症(larva migrans)という。
イヌ回虫症とは仔犬を終宿主とするイヌ回虫(Toxocara canis)の第2期幼虫による幼虫移行症で,眼内へ幼虫が移行したものを眼イヌ回虫症という。1950年,Wilder1)により網膜芽細胞腫の診断で摘出された46例の小児眼球のうち24例から寄生虫が認められたことが初めて報告され,1956年にNicoles2)によりイヌ回虫の幼虫が同定された。わが国でも,1966年に吉岡3)が網膜膠腫と診断して摘出した眼球からイヌ回虫の幼虫を同定し,病理組織学的に確定診断がなされた貴重な報告がある。
現在,診断技術の向上に伴い,またペットブームや食生活の多様化に伴いイヌ回虫症と診断される症例は増加傾向にあり,注目すべき疾患の1つである。
急性網膜壊死
著者: 丸山耕一
ページ範囲:P.212 - P.217
はじめに
ヒトヘルペスウイルス属,特に単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus:HSV)と水痘・帯状疱疹ウイルス(varisella-zoster virus:VZV)は,急速に進行・増悪する網脈絡膜炎の1つである急性網膜壊死(acute retinal necrosis:ARN)に深く関与するウイルスとして知られており1,2),さらに原因ウイルスの違いによって病態に相違がみられる3)。抗ウイルス薬,光凝固術や硝子体手術による治療が主となるが,早期発見と診断がその予後を左右するといっても過言ではない。昨今の分子生物学的手法によって容易かつ迅速な原因ウイルスの検索が可能となったが,未だ良好な視力予後を得るまでに至らない例も多い。急性網膜壊死に加え,極めて稀ではあるがAIDSなどの免疫不全を有する患者が,同じヘルペスウイルス感染を原因とする進行性網膜外層壊死(progressive outer retinal necrosis:PORN)に罹患することもある。
本項では,急性網膜壊死の基礎的研究から実際の臨床における診断や必要な検査法,鑑別すべき疾患,そして治療手段と予後について述べてみたい。
サイトメガロウイルス網膜炎
著者: 山本成径
ページ範囲:P.219 - P.225
はじめに
サイトメガロウイルス(CMV)は全身の臓器に広く親和性をもち,全身感染症を起こす。眼科領域で問題になるのは網膜炎である。1980年初めまで,サイトメガロウイルス網膜炎は,多くの眼科医には非常に珍しい疾患であった。先天性サイトメガロウイルス感染症や免疫抑制薬による合併症としてのサイトメガロウイルス網膜炎に遭遇する機会があっても,その頻度は極めて稀なものであった。
しかし,AIDS(acquired immunodeficiency syndrome)が1981年に報告され,1982年にHollandら1)がAIDSに合併したと考えられたサイトメガロウイルス網膜炎を報告して以来,同様の報告は全世界からなされるようになった。現在,サイトメガロウイルス網膜炎は欧米をはじめとして最も一般的な感染性網膜炎となった。わが国においてもこの傾向は同様で,AIDS患者の増加とともにサイトメガロウイルス網膜炎の報告は増加し,稀な疾患ではなくなった。しかし1995年から導入されたHAART(highly active antiretroviral therapy)によりサイトメガロウイルス網膜炎の発症率は低下した。抗サイトメガロウイルス薬耐性患者の出現の報告もあり2),またHAARTも長期化するとさまざまな副作用を伴うため,眼科医は内科医と緊密に連絡をとり,また患者と十分なコミュニケーションをとりながら治療にあたる必要がある。
本項では,AIDSに合併するサイトメガロウイルス網膜炎を中心に述べる。
HTLV-I関連ぶどう膜炎
著者: 寺石友美子 , 松尾俊彦
ページ範囲:P.226 - P.229
HTLV-Iの特徴
HTLV-I(human T-lymphotropic virus typeI)1)はヒトレトロウイルス科オンコウイルス亜科に属するRNAウイルスである。ヒトでは成人T細胞白血病(adult T-cell leukemia:ATL),痙性脊髄麻痺(HTLV-I associated myelopathy:HAMまたはtropical spastic paraparesis:TSP),感染性皮膚炎(HTLV-I associated infective dermatitis)の原因ウイルスとして認知されており,肺炎,関節炎,自己免疫疾患との関連も注目されている(表1)2)。
眼科領域ではぶどう膜炎やシェーグレン症候群の関連ウイルスとして,近年関心を集めている。
眼内炎
【総論】眼内炎―感染か,非感染か
著者: 内藤毅
ページ範囲:P.231 - P.235
はじめに
眼内炎には外因性眼内炎と内因性眼内炎があり,感染か非感染かを検討する場合には,すべてのぶどう膜炎が鑑別診断の対象となりうる。特に感染性術後眼内炎は頻度は高くないが,場合によっては視力予後が不良となりかねないので的確な診断と慎重な対応が必要である。感染の確定診断には眼局所からの病原体の検出が必要であり,検査技術の進歩に伴い診断技術は向上している。しかし,病原体を証明することが困難な場合があり,感染か非感染かの判断に苦慮することがしばしばである。特に発症初期に感染か非感染かを判断することが重要であり,その結果が予後に大きく影響する。そこで症状・徴候を主な手がかりとして感染と判断する手順を考えてみることにする。
転移性眼内炎―細菌性眼内炎
著者: 阿部達也
ページ範囲:P.236 - P.240
疾患の特徴
1.概念
細菌性の転移性眼内炎は,眼以外の臓器の感染巣から血行性に細菌が播種されて眼内の感染症が起こる疾患で,内因性眼内炎とも呼ばれる。このため手術後や外傷による外因性眼内炎とは異なり,眼球の穿孔創がなくても発症する。病態は細菌感染で起こる眼内の急性,非肉芽腫性,化膿性炎症である。
転移性眼内炎―真菌性眼内炎
著者: 宮崎賢一
ページ範囲:P.242 - P.246
はじめに
眼内炎に至る真菌感染の経路は,内因性(血行性感染)と外因性(外傷や手術後)に大別できるが,本項では内因性真菌性眼内炎について扱う。医療水準の高度化に伴い増加している担癌患者などの免疫不全状態にある患者での発症が知られている1)。病歴聴取や臨床症状・所見から診断は困難ではない場合がほとんどであるが,治療が遅れると重篤な視力障害をきたしかねない。近年,有効性の高い抗真菌薬が各種開発され,一方では,硝子体手術の技術,機種の安全性も格段に向上したため,以前と比較して予後は格段に改善したといえる。以下,その診断方法と治療方針を記載したので,諸家の診療の一助となれば幸いである。
術後眼内炎―白内障術後眼内炎
著者: 安原徹
ページ範囲:P.248 - P.252
はじめに
術後眼内炎は,いうまでもなく,あらゆる手術合併症のうちで最も避けなければならない合併症であり,万が一発症した場合には可及的速やかに対応しなければならない。発症すればまず抗生物質投与を行い,無効なら硝子体手術,という治療の流れは一般に理解されていると思われるが,急性発症する強毒菌による眼内炎の場合には,時に経過観察の1~2日で予後不良へと至らしめるほどの著しい不可逆性変化をきたすことがある。しかし一方で,早期に適切な処置が施されれば良好な予後が得られることも多く,早期発見して的確な治療法を選択・実施することの重要性は極めて高いといえる。
白内障術後眼内炎は,早期眼内炎と晩発性眼内炎の2種類に分類される。起炎菌は,術後早期眼内炎ではグラム陽性のブドウ球菌や腸球菌,グラム陰性の緑膿菌,晩発性眼内炎では嫌気性菌のPropionibacterium acnesによるものが多い3,5~7)。それぞれ,睫毛や涙器などから手術時に眼内に迷入することにより発症すると考えられるが,眼内レンズに付着したP. acnesが眼内レンズと後囊の間に潜伏感染した場合に晩発性眼内炎が生じると考えられている9~11)。
近年,米国で行われたEndophthalmitis Vitrectomy Study(EVS)1)はわが国でも注目され,白内障術後眼内炎を論じる場合に頻繁に引用されている。ここでは,抗生物質の投与や硝子体手術の効果に関する非常に重要な見解が示されている1,4)。このstudyはわれわれが行っている治療法と単純に比較検討することはできないが,非常に多数例の検討であり,術後眼内炎の治療を考えるに際してその内容・結果を知っておく必要はあると思われる。表1にEVSの結果を簡単に紹介するが,プロトコールの内容など詳細は文献で確認していただきたい。
術後眼内炎―緑内障術後眼内炎
著者: 齋藤圭子
ページ範囲:P.253 - P.257
はじめに
緑内障手術後にみられる晩発性眼内炎は,20世紀の初めからElliot1)によって濾過手術の合併症として報告され,注意が喚起されていた。その後,緑内障手術はScheie法などの全層濾過手術法から線維柱帯切除術への手術法の変遷と線維芽細胞増殖阻害薬併用が行われるようになり,こうした併用療法を含む眼内炎の発症との関係について検討が行われるようになってきた。
緑内障術後の感染症は,bleb-related ocular infectionやbleb infectionといわれ,一般的には,緑内障術後しばらく経過した後,術後眼内炎として発症し予後が不良であるとされてきた。しかし,1994年にBrownら2)が病態と予後の関係から,➀ 濾過胞炎(blebitis)と,➁ 眼内炎(endophthalmitis)とに区別するよう提唱した。術後眼内炎は,手術中にその原因菌に感染し発症するものであると考えられるが,今回,濾過胞炎と眼内炎を広義の意味で緑内障術後感染症として扱い,臨床的特徴と治療について述べることとした。
III.検査・治療の基礎知識
最新の診断キット―その特徴,使用法,限界
著者: 木村泰朗
ページ範囲:P.260 - P.264
はじめに
感染症における微生物検出のための検査法は,近年の免疫学診断技術および遺伝子診断の進歩に伴い大きく変化,進歩している。従来の微生物学的検査の問題点は,検査の方法が微生物を培養することによっているために,すぐに臨床への反映に結びつきにくいということであった。しかし,生物学の技術革新によって,治療にすぐ反映できる迅速診断が多くの分野で可能になっている。その迅速診断をより速く,より単純化したものが検査キットといえる。検査キットは,特別な装置や器具を必要とすることなく,多くは数十分以内で結果を出せる。それだけ容易になった分,検出限界や偽陽性の問題などがあり,その特性と限界を理解しておく必要がある。
また,今回は触れないが,感染症領域では迅速診断という意味では,従来からの塗抹検査法が最も安価で,速くかつ確実な方法であることを忘れてはならない。グラム染色のみで,前眼部の起炎菌のかなりが確定できる。また,たとえ確定できなくても,背景として得られた細胞が,リンパ球が主体か,白血球が主体か,または上皮細胞かで,細菌性かウイルス性感染かの鑑別がつくし,観察された細菌が常在菌か否かの推定ができる1)。
一方,微生物の抗体や抗原の検出をする免疫学診断法は,培養の時間がかからない分だけ迅速性には優れているが,一般的に感度は低いが特異性は高いものが多い。そのため,偽陽性,偽陰性が認められることに注意をする。臨床検査としてキットが有用な場合は,➀ 本来無菌的である材料を対象とする場合,➁ 本来非常在性の微生物を対象とする場合,➂ 微生物由来の病原分子・毒素を検出した場合などが挙げられる。眼科でキット化された検査の対象はアデノウイルス,クラミジアであり,これは上記 2 にあたり,臨床検査キットとしては使いやすい。すなわち,眼科領域ではキットの結果が陽性(+)であればすべて病原微生物といえる。
点眼薬の自家調整法
著者: 林仁
ページ範囲:P.265 - P.269
ここ数年における点眼治療薬の新製品を振り返ってみると,抗アレルギー用薬や緑内障用薬が相次いで開発されたのが記憶に新しい。さて感染症対策としては,2000年にクラビット(R)点眼が開発されており,広範囲スペクトルと高い眼内移行性という特長から,今や抗菌薬としての第一選択肢として広く使われるようになってきている。しかし既製抗菌薬で感染症対策が万全かというと,まだまだ選択肢が不足しているといわざるをえない。遭遇した疾患に適用となる眼科用剤がない,あるいは薬剤耐性菌などの難治症例に対しては,今のところ自家調整点眼薬で立ち向かうしかない。本項ではその自家調整点眼薬の調整法と注意点について解説してみたい。
眼感染症の外科的治療
著者: 秦野寛
ページ範囲:P.270 - P.274
はじめに
眼感染症の外科的治療は,組織内の感染微生物の可及的除去による感染の終焉が最終目標である。次には炎症反応の軽減が目標になると思われる。ここでは改めて,眼感染症を全体的にみて,そもそも眼感染症のなかで外科的治療はどこの部位で,どこまで可能かを考えてみたい。結論的にいうと,緊急重篤性から外科的治療が不可欠なものは細菌性眼内炎(硝子体膿瘍)であり,慢性的難治性から最終的感染根治に外科的手段が不可欠なものが涙器感染症(涙小管炎,涙囊炎)である。それ以外の疾患は,必要性からは比較的に後順位である。
培地の選択
著者: 宮永嘉隆
ページ範囲:P.276 - P.282
眼感染症を疑ったときは
臨床症状や所見から感染症が疑われる疾患は,眼科領域においても少なくない。充血,疼痛,腫脹,分泌物(眼脂)などから眼感染症を疑っても,最終的にはその原因となる微生物を分離し,同定(identification)してはじめて確定診断となる。また原因微生物を同定するということは,診断のみならず,それに続く治療を行ううえでも非常に重要なものである。眼感染症といっても真核生物(動物)である原虫(アメーバなど)や真菌,原核生物である細菌,スピロヘータ,クラミジア,そしてDNA,RNAそのものであるウイルスまで種々の微生物感染がある。
さらにその微生物を証明する方法にも,➀ 形態学的に確認する方法,例えば細菌や真菌,アメーバなどならスメア(塗抹標本)を作製し顕微鏡などで確認する方法,➁ 病原微生物を同定するための培養検査,すなわち細菌や真菌では合成培地を用いて培養し,さらにその菌独特の培地で菌を同定する培養検査,➂ 病原微生物の抗原物質を確認する蛍光抗体法や酵素抗体法,ラジオイムノアッセイ(radio immunoassay:RIA),ELISA法などの免疫学的診断法もある。さらにまた,➃ 病原体の遺伝子を検出したり(Pars field immono erectro-phoresis),ウイルスなどではPCR(polymerase chain reaction)法を用いることにより極めて鋭敏に病原体の証明ができるものなどがある。このように,一口に病原微生物の証明といっても今日では種々の方法がある。
本項では「培地の選択」が主題となっており,さらに前後の項との関係から,細菌や真菌,アメーバなどの感染を疑ったときにどのような培地を選択し,どのように確定診断を進めていったらよいのかを主眼とした解説をしたい。
ウイルス学的検査法
著者: 薄井紀夫
ページ範囲:P.283 - P.287
はじめに
本項ではウイルス感染症に関する一般的な臨床検査法について述べる。検査の選択や結果の解釈に際しては,各ウイルス固有の感染様式や増殖形態を念頭に入れながら,さらにウイルスと宿主とのかかわりについても考慮する。検査法の誤りや結果の短絡的な判断は貴重な検体を無駄にするだけでなく,思わぬ誤診につながってしまうことに十分注意しなければならない。
PCRで検出できる眼感染症の病原体
著者: 伊藤典彦
ページ範囲:P.288 - P.293
はじめに
3つのポイント
・臨床症状の観察が重要である。
・前房水と硝子体にはPCRの阻害物質が混入している。
・1回の反応で1種類の病原体を検出するPCR(monoplex PCR)と1回の反応で複数の病原体を検出するPCR(multiplex PCR)がある。
1.何よりも臨床症状の観察が重要である
PCR(polymerase chain reaction)は万能の検査であると思われがちであるが,検出する対象を決定しなくては検査を行うことができない。SARS(severe acute respiratory syndrome)で思い知らされたように,この地球上でわれわれ人類が知っている病原体はほんの一握りである。また,検体の取得には侵襲が伴い,特に後眼部疾患ではより病巣に近い部位からの検出が望ましいが侵襲は強い。まずは臨床症状から可能な限り病原体を絞り込み,必要とあればPCRを行うことが望ましい。
βラクタム系抗菌薬の使い方
著者: 福田昌彦
ページ範囲:P.294 - P.297
βラクタム系抗菌薬とは
ペニシリン系抗生物質とセフェム系抗生物質は,両者とも化学構造式のなかに「βラクタム環」という構造を含んでいるためにβラクタム系抗生物質(抗菌薬)と総称される。抗生物質とは,種々の微生物種(細菌,真菌,放線菌)により生産され,他の微生物の発育を抑制する化学物質と定義されるが,最近では多くの抗生物質が微生物を介さずに合成でつくられるようになり,これらは抗菌薬(合成抗菌薬)と呼ばれる。つまり,広義の抗菌薬には抗生物質も含まれることになる。
ニューキノロン系抗菌薬の使い方
著者: 福田正道
ページ範囲:P.298 - P.303
はじめに
1963年に開発されたナリジクス酸(nalidixic acid:NA)はキノロン系抗菌薬の起源であり,その後,キノロン環骨格にフッ素を導入したノルフロキサシン(norfloxacin:NFLX)が開発され,緑膿菌をはじめグラム陽性菌にまで抗菌域を広げ,強い抗菌力を示した。NFLX以降に臨床応用されてたキノロン系抗菌薬は,その広い抗菌域と強い抗菌性から,以前のものと区別されニューキノロン系抗菌薬と呼ばれている。ニューキノロン系抗菌薬(フルオロキノロン系)は現在までにノルフロキサシン,オフロキサシン(ofloxacin:OFLX),エノキサシン(enoxacin:ENX),シプロフロキサシン(ciprofloxacin:CPFX),ロメフロキサシン(lomefloxacin:LFLX),トスフロキサシン(tosufloxacin:TFLX),スパルフロキサシン(sparfloxacin:SPFX),フレロキサシン(fleroxacin:FLRX),レボフロキサシン(levofloxacin:LVFX),ガチフロキサシン(gatifloxacin:GFLX),プルリフロキサシン(prulifloxacin:PUFX)などが経口剤として開発されている。現在臨床治験中の抗菌薬もあり,今後はさらに増える傾向にある。CPFLなどは注射剤として初めて臨床応用されている。点眼薬としてはOFLX,NFLX,LFLX,LVFX,CPFX(国外)の5種類の点眼薬がすでに臨床に用いられているが,新たに数種点眼薬の臨床治験が進行している。また眼軟膏剤としてはOFLX眼軟膏剤が臨床で広く使用されている。
その他の抗菌薬の使い方
著者: 岡本茂樹
ページ範囲:P.304 - P.307
キノロン系およびβラクタム系(ペニシリン系およびセフェム系)以外の抗菌薬で,眼科で使われる抗菌薬としては,蛋白合成阻害薬であるマクロライド系,アミノグリコシド系,およびテトラサイクリン系抗菌薬,そしてβラクタム系と同じく細胞壁合成阻害薬ではあるがβラクタム環をもたないバンコマイシンおよびホスホノマイシンが挙げられる。
現在,抗菌薬の第一選択はキノロン系抗菌薬およびβラクタム系抗菌薬であり,これ以外の薬剤はキノロン系やβラクタム系抗菌薬に耐性をもった菌,細菌以外のクラミジアなどに対する使用が主である。表1にキノロンおよびβラクタム系以外で,眼科で使用される頻度の高い抗菌薬について示す。
抗結核薬の使い方
著者: 小幡博人
ページ範囲:P.308 - P.310
はじめに
正しい診断があってはじめて正しい治療が行われる。しかし,結核の診断はしばしば容易ではない。本項では,まず結核とその診断について簡潔に整理し,結核の標準的治療法や副作用について概説する。
抗真菌薬の使い方
著者: 鈴木崇
ページ範囲:P.311 - P.316
はじめに
抗真菌薬は眼科領域において,角膜真菌症や真菌性眼内炎などの真菌による感染症だけでなく,アカントアメーバによる角膜炎に対しても有効であり,それらの治療においては必要不可欠な薬剤である。だが,抗真菌薬は薬剤数が限られていることから選択の幅が少なく,従来画一的な投与が行われてきた。特に一般眼科臨床医にとって抗真菌薬を用いるべき疾患がなじみの少ないこともあり,より使用薬剤や使用法が限られてきた。
しかしながら,最近新しい作用機序をもつ抗真菌薬が発売され,抗真菌薬の選択肢の幅が増えてきたため,今後は各抗真菌薬の特徴・抗真菌スペクトルなどを考慮し,各疾患・各症例について,より効果的で副作用の少ない適切な抗真菌薬の選択が必要となってきている。本項では,抗真菌薬の分類,各抗真菌薬の特徴・作用機序・副作用,抗真菌薬のスペクトル,抗真菌薬の薬剤感受性試験,眼科領域における疾患別の抗真菌薬の選択と使用法について説明する。
抗ウイルス薬の使い方
著者: 檜垣史郎
ページ範囲:P.318 - P.320
抗ウイルス薬としては,1962年に角膜ヘルペスの治療にイドクスウリジン(idoxuridine:IDU)が登場し,その後,1977年,Elionによってアシクロビル(acyclorvir:ACV)が開発され,その毒性の低さにより今日まで頻用されている。
抗寄生虫薬の使い方
著者: 横井克俊
ページ範囲:P.322 - P.325
寄生虫は大きく分類すると,多細胞生物(吸虫,条虫,線虫など)と単細胞生物(原虫)に分けられる。眼科領域で問題となる寄生虫疾患の大部分を占めるのが,線虫の幼虫移行症である眼トキソカラ症,原虫感染症であるアメーバ角膜炎,眼トキソプラズマ症の3疾患である。本項ではそれら3病原体に対する治療薬について述べるが,トキソカラに対する駆虫薬投与は統一されたプロトコールがなく,その有効性・必要性が疑問視されている。またトキソカラと比較してアメーバ,トキソプラズマは構造が単純であるため,抗菌薬や抗真菌薬の一部に駆虫薬としての有効性が報告されている。しかし基本的に各病原体に特異的な治療薬はなく,生物学的分類の近い他の病原体に対して本来の適応がある薬物を転用しているに過ぎない。
コラム 眼感染症への取り組み・いまむかし
単純ヘルペスウイルスの変異株
著者: 山本正洋
ページ範囲:P.27 - P.27
九州大学医学部ウイルス学教室に大学院を含め1982~1987年の約5年半在籍していた。単純ヘルペスウイルスの研究を主体としていた。当時のウイルス学教室森良一教授の意向もあり,眼科を含めいろいろな臨床科からのウイルス分離を行っていた。分離した臨床株の薬剤耐性やマウスを使い病原性を調べていた。
そういった臨床分離株のなかで,稀に変り種にでくわすことがある。そのなかで私自身が多少なりともかかわった2つの株について紹介する。それぞれの株の詳細に関しては論文1,2)を参照されたい。
イソジン点眼薬―過去と未来
著者: 原二郎
ページ範囲:P.39 - P.39
白内障術後眼内炎の発症抑制に関与する因子として,睫毛切除,抗菌薬投与,灌流液への抗菌薬添加などを文献的(1966~2000年の英文での論文88編)に考察し,イソジンによる術前洗眼のみが眼内炎の発症抑制に有効であったと2002年Ciullaらは報告している1)。
イソジン(ポビドンヨードpovidone-iodine,PVP-I:polyvinyl pyrrolidone iodine)液の眼科での使用を歴史的にみれば,1959年神谷ら2)が,治療(投薬用)には64倍希釈液,洗眼(処置用)には16倍希釈液を用いて,流行性角結膜炎を含めた急性結膜炎(約200例)の治療を行い,副作用や刺激作用はなく結膜炎の治療に有効であったと報告している。1981年中谷3),眼科手術領域でのイソジンによる消毒効果と家兎での眼障害を検討し,結膜囊消毒には8倍希釈液の使用を勧めている。
トラコーマとクラミジア
著者: 青木功喜
ページ範囲:P.58 - P.59
トラコーマという病気
トラコーマという名前は,臨床上結膜炎にみられる変化にその起原をもっている。一方,クラミジアは病原体の形にその語源がある。すなわちトラコーマは,結膜に観察されたtrachy(ざらざらな)+-oma(腫瘍)の合成語であり,いわゆる慢性な経過で産生されてくるトラコーマ顆粒の所見に与えられた名称である。小児期に初感染を起こし,再感染を繰り返しながら形成されて行く結膜所見にその語源をもっている。一方クラミジアは,その細胞内の封入体が外套(chlamys)のように細胞質内にあり,細胞核を外套のように取り囲むという,顕微鏡の所見にその語源を持っている。
トラコーマという病気は,紀元前27世紀から中国でトラコーマ治療記録として記載された長い歴史を持つ病気であり,世界の眼科医は,その研究と治療に昭和30年代前半まで多くの時間を割いていた。
角膜ヘルペスの治療・いまむかし
著者: 塩田洋
ページ範囲:P.80 - P.80
角膜ヘルペスの治療薬としては,現在アシクロビル(ACV)が第一選択薬として使用されています。ご承知のように本剤は優れた治療成績を収めています。そのため角膜ヘルペスの病像が,昔と今では少し変わってきているようです。病気の本質そのものは変わらないのですが,いわゆるよい薬の有無によって生じてきた差でしょうか。
私が医学部を卒業したのは1968年でした。翌年から眼科医としてスタートしましたが,当時角膜ヘルペスの治療薬としてはIDU(idoxuridine)しかありませんでした。IDUは核酸合成阻害薬の一種です。単純ヘルペスウイルスの核酸合成を阻害して治療効果を発揮するのはよいのですが,ヒトの正常細胞の核酸合成まで阻害するため,細胞毒性があります。細胞毒性があってもほかに角膜ヘルペスに効く薬がなかったので,局所投与剤として市販されました。細胞毒性のために点状角膜上皮症がよくみられ,またIDUが効かない症例もありました。当時IDUが効かない症例には,ヨードチンキを1~2滴角膜に滴下し生理食塩水で洗い流したり,楊枝の先にヨードチンキを浸してそれで樹枝状潰瘍の辺縁をつついたりしていました。
眼感染症―故きを温ねて
著者: 北野周作
ページ範囲:P.86 - P.88
はじめに
20世紀中頃より導入された抗菌薬の臨床応用は,眼感染症の領域にも革命的ともいえる変革をもたらし,病態や予後に著しい影響を及ぼした。それまで先人が苦心惨憺し,工夫をこらして行ってきた治療法は,いまや忘却の彼方に置かれつつある。
ここでは,トラコーマと細菌性角膜感染症を取り上げ,20世紀前半まではどのような治療が試みられていたか,故きを温ねてみたい。
病原体との和平交渉
著者: 今井由美
ページ範囲:P.112 - P.113
抗菌薬,抗ウイルス薬やワクチンの開発と改良により,確かに人間の歴史において長年の脅威であった感染症の危機は激減したといえるでしょう。医療現場にしても研究分野にしても,感染症は話題の中心から遠ざかっていた時期もあったかもしれません。しかしながら,近年ただならぬニュースが舞い込んできます。AIDS,エボラ,西ナイル,そして新型肺炎(SARS)といったように,一世代の人間の記憶のなかでも絶えず危機管理を警鐘する感染症の名が聞かれているように思います。ましてや彼ら病原体側の歴史からすれば,先進国の医療現場で影を潜めた時期なんて,とるに足らない「一休み」だったのではないでしょうか。というよりむしろ,休憩後の彼らの活動は局面を新たにしているように見受けます。
いま,まさしく日を追うごとにSARSに関するニュースが飛び込んできている時期ですが,先日テレビでここカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)内の研究者がインタビューに応じているのを見ました。誰が呼ぶのか知りませんがGene Hunterとかいう異名を持つ彼のところにも米国厚生省疾病管理・予防センター(CDC)から原因解明の依頼があり,コロナウイルスの新種あるいは変異株だと自作のgene arrayガラススライドを見せて説明しつつ,こんなことを言っていました。「現代の人間社会では抗菌薬などの過剰使用,人や物資の盛んな移動,未開発地域の開拓,これらによって変異株や新種株,さらにはまったく新しい病原体が出現・蔓延する可能性は大いにあり,感染症対策は新たな局面を迎えている。」近年の感染症の原因と対策を考えてみるとき,大概の人は彼と同様の視点を持つでしょうが,なかでも医療従事者あるいは医学研究者の直接的影響が大きいのは,やはり「変異」でしょう。
バイオハザード・いまむかし
著者: 宮永嘉隆
ページ範囲:P.117 - P.117
1974年夏,私は初めて流行性角結膜炎にかかった。ある公的病院の一人医長で頑張っていた私は,うっとうしい眼をしばたたき,これが「はやり目」か,二度とかかりたくないと思いながら,診療を数日休んでしまった。またその数年前から新しいウイルス性結膜炎がわが国でも流行しはじめていた。それはエンテロ70と名づけられたエンテロウイルスであることがわかった。ちょうどアポロ宇宙船が月に着陸し人間が初めて月面に立った感激にちなんで,この結膜炎はアポロ病と名づけられた。また,その頃からウイルスによる眼感染症が問題となりはじめ,「はやり目」の患者をみたあとは,何となく気をつけるようにしていたものである。一方で,ヘルペス角膜炎の研究が急速に発展してきたのもこの頃であろう。この頃はまた,細胞性免疫の幕開けでもあった。病院のような施設のなかで職員が感染し,また他の疾患で病院に来た患者さんが「はやり目」をもらって帰るという,今思うと当時の病院はバイオハザードの最たるものであった。
1980年代に入り,第3世代セフェム系抗生物質の開発と頃を同じくして,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が少しずつ問題となり,院内感染における新しい感染症として日和見感染(oportunistic infection)が院内感染の主役となり,MRSAががぜんクローズアップされてきた。しかし当時はまだMRSAの分離率は低かった。眼科医もMRSAの存在は知ってはいたが,あまり関心をもつこともなかったような気がする。
英国での見聞
著者: 松田彰
ページ範囲:P.125 - P.125
私は2001年4月から2年間,アトピー遺伝子研究で有名なJulian M Hopkin教授のラボに留学していました。Julianは11番染色体長腕とアトピー性疾患との関係を1989年に報告したオクスフォードグループのリーダーで,1997年に彼の故郷のウエールズに新設された医学部(University of Wales Swansea)にdirectorとして迎えられました。11番染色体説はその後,1994年に白川太郎先生(現京大教授)らによって,high affinity IgE receptorβ鎖(FcεRI-β)における遺伝子多型とアトピーとの相関という知見を加え,アトピー遺伝子研究の先駆けとなりました。
私自身は,白川教授のご紹介で,このFcεRI-βのアトピー性疾患における役割を研究するために,ウエールズに出発しました。いろいろなメディアにも紹介されていることですが,英国は個人主義の国,階級社会の国であり,さまざまな面で学ぶ点が多かったように思います。眼科などの専門医(consultantという階級に分類されます)の地位は非常に高く,公的保険であるNHSの患者のほかにプライベートの診療をすることが認められていますので,収入も平均的な労働者階級の3~5倍はあるようです。
急性出血性結膜炎ウイルスの発見
著者: 金子行子
ページ範囲:P.134 - P.134
新しいウイルスによる新型肺炎(SARS:重症急性呼吸器症候群)が今年世界を震撼させたが,その対応に苦慮している様子をみるにつけ,30数年前の急性出血性結膜炎(AHC)が同じように原因不明の新型ウイルス性結膜炎として世界中に猛威をふるった頃を思い出す。
1971年入局2年目の夏,私の所属していた東京女子医大眼科の内田幸男教授のもとに「潜伏期が1日しかないすごい“はやり目”が九州で大流行している」との情報が届いた。内田先生が「潜伏期がたった1日のウイルス結膜炎ねぇ」と首をかしげているうちに,この原因不明の結膜炎は野火の如く東京を通過し南から北へ日本列島を1年余で駆け巡り,世界的流行すなわちパンデミックの一部として日本全土への流行を認めるに至った。
悲しいアトピー白内障―治療の遅れた術後感染症
著者: 桜庭知己
ページ範囲:P.146 - P.147
TMさんは,21歳の学生だった。
幼少時からアトピー性の皮膚炎を患っていた。実家はH市だが,皮膚炎の治療のため,わざわざ隣県のM市のU病院まで治療に行っていた。そして,彼女が15歳の誕生日を迎えた頃から,なんとなく「視力が下がったかな?」と自覚するようになっていた。
受診した近くの開業医から白内障をいわれていたが,われわれの病院にやってきたのはそれから5年後だった。当科初診時の視力は,右眼0.3(矯正不能),左眼0.1(矯正不能)とかなり低下していた。両水晶体前囊には瞳孔領中央に石灰化を伴った混濁があり,いわゆるアトピー性の白内障を呈していて,これが視力低下の原因であった。そのため,眼底ははっきり透見できなかったが,網膜裂孔網膜剝離などの大きな異常はなさそうであった。早速,われわれは手術の有効性と必要性を語り,白内障手術をためらっていると眼底検査に支障をきたし,剝離の発見が遅れ,最悪の場合失明するかもしれないとも話した。しかし,この方が網膜剝離でなく眼内炎で失明に至るとは,その時点では誰も想像していなかった。
ヘルペスワクチン研究開発の問題点
著者: 井上智之
ページ範囲:P.151 - P.151
単純ヘルペスウイルス(HSV)によるヘルペス性角膜炎に対する主な治療は,抗ウイルス薬によるウイルス増殖抑制とステロイド薬による炎症の軽減である。現在の治療は対症的で,上皮型は治癒するが実質型の根本的治療は非常に困難であり,本病態の基幹をなしている再発に対する予防的治療法は確立されていない。ゆえに本症をワクチンによりコントロールすることが重要視され,活発に研究されてきた。われわれのグループ(現鳥取大学教授井上幸次先生のお仕事)は,HSVに特異的な膜抗原で免疫誘導能の高いグリコプロテインD(glycoprotein D:gD)蛋白に着目し,gD蛋白ワクチンのマウス角膜炎に対する抑制効果を見いだしていた。これに続く仕事として筆者がヘルペスワクチンに着手したが,そこにはいくつかの克服すべき問題点が存在していた。
一般に,蛋白ワクチンにおいては,液性免疫は誘導されるが細胞性免疫は得られにくいとされる。このことはgD蛋白ワクチン研究の結果にも一致していた。しかし,単純ヘルペスウイルスは細胞内に持続感染することを考え合わせると,理想的には細胞性免疫の誘導が望ましい。さらに,一般にサブユニットワクチンにおいては抗原性は通常弱いとされており,免疫にあたってアジュバントを必要とすることが多い。われわれは安全で有効なアジュバントの研究として,インターロイキン2(IL-2)が動物生体において,抗原とともに投与されると免疫反応が増強されうるという結果に着目した。このような背景から,蛋白ではなく細胞性免疫の誘導に優れているといわれるプラスミドDNAを投与する方法(DNAワクチネーション)を選択し,gD蛋白と,免疫効果増強に応用されているIL-2をgDに融合させたgD-IL-2蛋白をコードするプラスミドDNAを作製し,抑制効果の検討を試みた。
アデノウイルスとつきあって17年
著者: 日隈陸太郎
ページ範囲:P.160 - P.161
感染症サーベイランスの眼科定点医として観測を始めて17年が経過した。アデノウイルスが発見されて50年,その1/3の年数をこのウイルスとつきあってきたことになる。
サーベイランス事業における眼科対象疾患は流行性角結膜炎(EKC),咽頭結膜熱(数年前から小児科領域のみの対象になっている),急性出血性結膜炎であるが,全国307の定点において約60%が臨床所見のみによる診断となっている。しかしサーベイランス事業の目的が対象疾患の発生,流行を的確に把握し,その予防対策を立てることにあると考えると,ウイルス学的診断が是非必要であると考え,熊本県衛生公害研究所(現熊本県保健環境科学研究所)の協力のもと1987年から対象疾患におけるウイルスの分離培養を開始した。この調査によってアデノウイルスの各血清型には症状や発症の季節,年齢などに型特異的な特徴が認められる傾向があること,また従来述べられていた教科書的な臨床所見とウイルスの血清型には必ずしも整合性がみられないことなど興味ある結果が得られた。
アカントアメーバ角膜炎
著者: 石橋康久
ページ範囲:P.180 - P.181
私がアカントアメーバ角膜炎とわが国で初めて出会ったのは,1987年,留学から帰り,真菌の研究も一段落してこれから何をしようかと考えていたときである。コンタクトレンズで角膜に傷をつけ,2~3か所の眼科で治療を受けたが改善せず,紹介で筑波大の眼科を受診した患者である。それまでの経験から角膜真菌症であろうと当りを付け診察をしたが,角膜中央に白色円板状の病変がみられた(図1)。患者に角膜実質内の病原体を検索するためバイオプシーをすることを承諾してもらい,顕微鏡下に角膜実質を生検し,これをパーカーインクKOH法で直接鏡検した。
その日は時間がなくそのまま帰宅し,翌日早朝に大学に行き顕微鏡を覗いたところ,実質内に沢山の青く染まった丸いものが観察された(図2)。そのときは真菌を期待しており,青く細長いものがみえるものとばかり思っていたのでビックリした。一体これは何であるのかすぐには思いつかなかったが,ほどなくしてニューオリンズで見せてもらったアカントアメーバ角膜炎のことを思い出した。それを確認するためにはアメーバの培養が必要であり,すぐに筑波大の寄生虫学教室を訪ねた。患者からアメーバが培養されたとの報告を受けたのは1週間ほどしてからであった。
落下細菌への取り組み
著者: 佐々木香る
ページ範囲:P.190 - P.190
CDC(米国疾病管理・予防センター)のガイドラインによると,環境からすべての菌を除菌することは,不可能であり無意味だそうである。したがって,落下細菌についても,調べてどうこうするべきものではないとされている。しかし,予防医学,環境感染医学が叫ばれる21世紀,自分の勤務する病院内にどんな種類の菌がどの程度,浮遊しているのか,また手術室ではほんとうに落下細菌が少ないかどうかなど,知りたくなるのは人情である。そこで人情深い浪速っ子,佐々木は立ち上がった。
ちょうど院内感染対策委員を任されたこともあって,お金とマンパワーに差し障りが出ない限り,調べてみようと思って発表したのが,2002年の眼感染症学会である。「眼科専門病院各部署における落下細菌について」。こんな演題,あんまりメジャーじゃないなあ,と自分でも思いつつ,届いた抄録に目を通した。案の定,学会一般口演の最終演目である。事務局の方とて他の演題とグループ化できないこのような演題を,どの時間帯に配置しようか迷われたことだろう。結論としては,➀ 人の動線と検出菌数が比例する,➁ 手術室は少ないが,外来処置室は外来同様に検出菌数が多い,➂ ICT(infection control team)による啓蒙活動は効を奏するという,ごく当たり前のものである。
MRSAと向き合って
著者: 外園千恵
ページ範囲:P.207 - P.207
MRSA(methicillin-resistaut Staphylococcus aureus)という言葉を初めて聞いたのは研修医のとき(198? 年)です。それは「院内感染の起因菌として内科や外科で問題になっている菌」として若かりし私にインプットされました。その後,短期の外科研修でも,眼科臨床においてもMRSAには会うことなく月日は過ぎていきました。
1996年のこと,角膜上皮移植を行ったSteven-Johnson症候群の患者さんの医療用ソフトコンタクトレンズからMRSAを検出しました。眼脂もない,充血もない,角膜感染巣もないという状態です。自分が初めて出会ったMRSAに,どう対処したらよいのかわかりません。市販の抗生物質点眼薬をいろいろ変えてみたり,点眼回数を増やたりしてみましたが,MRSAは消えません。よくみると,角膜表面への血管侵入が少しずつ増強し,血管周囲の角膜上皮内に細胞浸潤があってわずかに曇ってみえます。「MRSAは,これらの所見と関係しているみたいだけど,どうしたら除菌できるのだろう。文献ではバンコマイシン(VCM)やアルベカシン(ABK)の点眼がよさそうだけど,上皮毒性が強そうだから上皮移植後にはまずいだろうなあ……。」1年くらいの経過ののち,思い切ってバンコマイシン点眼液を自家調整し恐る恐る使用しました。心配した上皮欠損は生じませんでした。でも夏のある日,突然に角膜感染症を発症し来院されました。アルベカシン点眼液と点滴を使い,約3か月で感染は治癒しました。
角膜移植と感染症
著者: 榛村重人
ページ範囲:P.235 - P.235
眼手術では,感染症という怖い合併症を完全に排除することは残念ながらできない。しかし,近代化に伴って人間も少しは賢くなり,抗生物質のおかげで手術を安全に行うことができるようになった。特に白内障などでは,小切開化や手術時間の短縮によって,術後眼内炎の発症率は0.05%前後まで下がっている。全層角膜移植(PKP)の場合も,open surgeryであるにもかかわらず,0.1%前後と報告されている。しかし,全層角膜移植で問題となるのは,術後しばらく経過してからの角膜感染症である。
全層角膜移植は,通常の眼手術よりはステロイド点眼を長期間使う場合が多い。術後経過が良好な低リスク症例でも,約20%に拒絶反応が認められる。拒絶反応は,そのままドナー角膜の内皮機能不全に陥る可能性があるため,徐々に濃度を下げながらステロイド点眼を1年以上続ける場合もある。ステロイドを使用しているため,真菌や弱毒菌による角膜潰瘍をきたすことがあるのが角膜移植後にみられる感染症の特徴である。また,原疾患がヘルペスの場合は,ステロイド点眼を使用している限りは再発の可能性がある。
術後眼内炎の治療経験から
著者: 平形明人
ページ範囲:P.258 - P.258
硝子体手術を専門領域にしているために眼内炎治療に携わる機会が多く,そのなかで術後眼内炎の治療経験から感じたことを記載する。
迅速で適切な対応
白内障術後眼内炎の治療として,米国のEVS(Endophthalmitis Vitrectomy Study)で,抗菌薬眼内投与の有用性が報告された。この検討は,硝子体手術が迅速にできない場合の対処方法にも有用な情報となっている。しかし実際には,まずは前房洗浄のみあるいは全身抗菌薬投与のみの対処などで経過をみて,その治療に抵抗性であるために本院を紹介される症例も少なくない。迅速な対応が遅れてしまっている。
患者さんへの説明(適切な病診連携が大切)
患者さん自体が,眼内炎治療の手術や予後を比較的深刻に捉えていなかったり,眼内炎治療手順を不適切に指導されていることがある。この原因は,紹介医の説明に基づいているように思われる。眼内炎治療は緊急の治療が大切であり,そのためには紹介先での良好な医師患者関係ができるように,紹介医には紹介先の対処を想定したていねいな説明をしていただきたい。紹介時の視力が良好でも,急速に悪化することは少なくない。紹介医と紹介先の密接な連絡が大切である。
眼内炎治療の私見
著者: 橋田正継
ページ範囲:P.268 - P.269
眼内炎の発症時には,しばしば患者も主治医もパニックになってしまって迅速で正確な対応ができなくなりがちですが,種々の検査データの集計と患者への告知,さらには観血的治療などを瞬時のうちに対応する必要があります。一般外来もストップしますし,他院へ転院となりますと連絡や転院の手配で天地をひっくり返したようになるでしょう。ほんとうに嫌なものです。
内科的治療や前眼部の洗浄で消炎が得られる症例もありますが,結局は硝子体手術が治療の中心となると思います。硝子体手術といいますと切り札という感じがありますが,かといって硝子体手術でもなかなか消炎が得られないケースもあるわけで,予後は起炎菌や菌体量,治療開始時期,患者因子などマルチファクターが関与していることはいうまでもありません。大切なことは初期治療が有効かどうかの判定を(特に硝子体手術を行わなかったとき)密にすることで,前房洗浄した直後はクリアでも数時間後に前房蓄膿,硝子体への炎症波及があることがありますので,応急処置を行ったまま翌日に外来受診してもらうような方針は賛成できません。
急性網膜壊死とウイルス
著者: 臼井正彦
ページ範囲:P.282 - P.282
1971年に初めて報告された桐沢型ぶどう膜炎は,当時その原因は不明であったが,この疾患と臨床所見が酷似し,欧米で報告された急性網膜壊死(acute retinal necrosis:ARN)の眼病理検査からヘルペスウイルス粒子が発見され,両疾患にヘルペス群ウイルスの関与が推測され始めた1982年以降,わが国においても桐沢型ぶどう膜炎の病因ウイルスの検索が始まった。1983年に月本らは,桐沢型ぶどう膜炎の硝子体手術時の眼内灌流液から高い単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus:HSV)抗体価を検出した。次いでわれわれも,1984年に29歳の両側性桐沢型ぶどう膜炎患者の眼内液から高い水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella-zoster virus:VZV)抗体価の存在を報告した。また1985年には,Witmerによる量的血清学の手法を用いて3例の桐沢型ぶどう膜炎の病因がVZVであることを間接的に証明した。そして,1986年にCulbertsonらがARNの網膜からVZVを分離同定するに至り,ARNの病因としてVZVが決定され注目された。
一方,HSVのARNにおける関与も明らかにされた。1984年にPeymanらは,2例のARNのうち1例からHSV-1の抗原陽性細胞を,他方からはHSV-2の陽性細胞を硝子体液より証明した。桐沢型ぶどう膜炎においても,1987年に高橋らは硝子体液よりHSVのDNAを検出し,1990年には原がHSVに対する高い抗体率を有する5症例を見いだした。その1年前の1989年には,Lewisらが27歳と37歳のARNの硝子体液からHSV-1を分離同定した。
むかしのトラコーマ治療とその意義
著者: 小林俊策
ページ範囲:P.287 - P.287
昔のトラコーマ薬物療法で広く用いられたのは,何といっても硝酸銀である。0.1~1.0%の硝酸銀溶液をつくる。上下眼瞼を反転して患者に眼をつぶるように指示すれば,瞼結膜と円蓋結膜が露出し角膜は隠れる。このとき,硝酸銀溶液を点眼し1.0%食塩水で洗う。1日1回でよい。使用する硝酸銀溶液の濃度は眼脂の多寡と炎症の強弱をみて決める。そのほか数種の薬物療法があるが,症状に応じて使用する。
慢性期トラコーマでは瞼結膜に乳頭と顆粒(濾胞ともいう),円蓋結膜に顆粒ができているので,薬物療法で眼脂が減り炎症が多少とも沈静化するのを待って,手術療法の1つであるカイニング法を施行する。カイニング法とは,まず硝子棒の先端部分に1.0%食塩水に浸した適当量の脱脂綿をしっかりと固く巻きつけた綿棒をつくっておき,次に患者に3.0~5.0%コカイン溶液を数回点眼して結膜を麻酔した後,硝酸銀を点眼するときの要領で瞼結膜と円蓋結膜を露出し,その結膜面を先につくっておいた綿棒でわずかに出血するまで摩擦するのである。上円蓋結膜に顆粒が簇生しているときは上眼瞼をデマル鉤で二重反転し,上円蓋結膜をていねいにすみずみまで摩擦する。1週に1回をめやすに行い,その間は薬物療法を続ける。
緑膿菌性角膜潰瘍の回想
著者: 大石正夫
ページ範囲:P.292 - P.293
はじめに
時は今から30数年前,1967(昭和42)年に,第17回日本医学会総会が名古屋市で開催された。その学術講演シンポジウムの主題49で,「グラム陰性桿菌感染症」が取り上げられた。当時,化学療法の開発,普及に伴ういわゆる「菌交代症」として,「グラム陰性桿菌感染症」が全科領域にわたって問題となっていた。
司会は,名古屋市立大学医学部第一外科,柴田清人教授で,眼科領域から新潟大学医学部眼科,三国政吉教授が指名された。参考までに他科領域のシンポジストの氏名を掲げる。基礎研究として桑原章吾(東邦大教授),臨床研究として内科:真下啓明(北大教授),小児科:藤井良知(東大助教授),外科:石山俊次(日大教授),婦人科:青河寛次(京都府立大講師),泌尿器科:石神譲次(神戸大教授),耳鼻科:高須照男(名市大教授),発言者:上田 泰(慈恵医大教授),白羽弥右衞門(大阪市大教授)。いずれも当時の日本感染症学会,日本化学療法学会の重鎮のメンバーであった。
当時,眼科領域では,グラム陰性桿菌といえば緑膿菌による角膜潰瘍が増加の傾向を示して問題となっていた。そこで「緑膿菌性角膜潰瘍」が主題として取り上げられることになった。新潟大学眼科教室では「細菌室グループ」が主体となって,発表準備にとりかかった。まず疫学として,全国眼科診療機関にアンケートを求めて,現況を把握することに努めた。治療実験として,周田茂雄先生が主体となって家兎眼に緑膿菌性角膜潰瘍をつくり,当時初めて登場した抗緑膿菌抗菌薬ゲンタマイシンを用いて,投与方法による発症予防,治療実験が精力的に行われた。医学会総会では三国教授によりそれらの成績が発表されて,多大の成果を収めた。
ここでその発表の概略1)を紹介して,当時の「緑膿菌性角膜潰瘍」の状況を回顧してみたい。
術後眼内炎との闘い
著者: 池田恒彦
ページ範囲:P.317 - P.317
筆者は網膜硝子体手術を専門にしている立場上,術後眼内炎の硝子体手術を数多く経験してきた。その大半は他院からご紹介いただいた白内障術後眼内炎である。いまさらいうまでもないが,術後眼内炎は弱毒菌によるものを除けば進行は極めて速く,視機能を保持できるかどうかはまさに時間との闘いである。紹介があと1日早ければ助かっていたかもしれない症例も何例か経験している。よって,筆者は術後眼内炎は原則的に即日手術の方針をとっている。予定していた業務をすべてキャンセルして緊急手術を施行しなければならないので,術者の負担は極端に大きくなる。しかし,それでも施行しなければならないのが術後眼内炎なのである。筆者は日頃,網膜硝子体手術に追われて多忙な日々を送っているが,どのような時でもあと1例は手術ができる体力を温存するように努めている。これはまさに眼内炎に即座に対応するためといってもよい。
眼科領域で緊急手術を必要とする疾患には外傷や網膜剝離など数多くのものがあるが,術後の細菌性眼内炎はそのどれよりも緊急性が高い。強毒菌による眼内炎は時々刻々と症状が悪化し,同一日でも朝と夕方では所見が大きく異なるこもしばしばある。最近の白内障手術は早期に視力改善が得られるのが当たり前という認識が医師側にも患者側にもあり,日帰り手術の件数も急増している。そのため,白内障手術を安易に考え,術後眼内炎の的確な診断や紹介が遅れるケースが増えているように思う。白内障術者は,術後眼内炎の可能性を常に念頭に置いて,発症時に迅速な対応ができる体制を普段から整えておく必要がある。それ以上に大切なのは,眼内炎が疑われたときに,早期に網膜硝子体術者に紹介する決断と勇気を持つことである。
基本情報
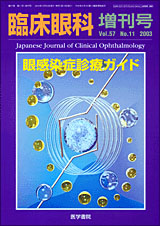
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
