要約 2眼の角膜潰瘍が,非ステロイド性抗炎症薬であるブロムフェナクナトリウム点眼後に生じた。1例は58歳男性で,水疱性角膜症に合併した強膜炎に対して本薬点眼と抗菌薬眼軟膏を点眼し,3日後に角膜中央部の実質深層に達する潰瘍が発症した。他の1例は71歳男性で,右翼状片の手術後に本薬点眼,抗菌薬点眼,ステロイド薬点眼を行い切除部が完全に上皮化したが,術後40日目に切除部の角膜輪部に潰瘍が生じた。両症例ともブロムフェナクナトリウム点眼を中止し,短期間で潰瘍が治癒した。ブロムフェナクナトリウムなどの非ステロイド性抗炎症薬点眼で,重篤な角膜障害が起こる可能性を示す症例であり,注意が望まれる。
雑誌目次
臨床眼科57巻5号
2003年05月発行
雑誌目次
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
円錐角膜患者における全層角膜移植後のステロイド点眼と眼圧
著者: 石岡みさき , 榛村重人 , 島崎潤 , 深川和己 , 坪田一男
ページ範囲:P.680 - P.682
要約 全層角膜移植を行った円錐角膜59例59眼について,術後の眼圧と副腎皮質ステロイド薬点眼の関係を検索した。男性46例,女性13例であり,平均年齢は33歳であった。術後のステロイド薬には0.1%ベタメタゾンを使い,1日5回の継続点眼を原則とした。全例で術後1年以上の経過を観察した。眼圧上昇は29眼(49%)に,術後平均4.4か月で生じた。27眼では,点眼を0.1%フルオロメトロンに変更するか,抗緑内障薬点眼の追加で眼圧コントロールができた。ステロイド薬に反応して眼圧が上昇しやすい若年者が多い円錐角膜であっても,眼圧に注意すれば,ステロイド薬点眼を角膜移植後に使うことが可能である。
裂孔原性網膜剝離への硝子体手術と強膜バックリングによる角膜内皮細胞の変化
著者: 岩崎明美 , 丸山泰弘 , 大谷倫裕 , 岸章治
ページ範囲:P.683 - P.686
要約 裂孔原性網膜剝離41眼に硝子体手術または強膜バックリングを行い,術後の角膜内皮細胞の変化を検索した。手術の内訳は,硝子体手術16眼,強膜バックリング20眼,硝子体手術に水晶体摘出を併用した5眼である。年齢は16~82歳,平均43歳である。手術から3か月後の角膜内皮細胞密度の減少率は,硝子体手術群0.5±9.3%,強膜バックリング群2.9±8.7%,水晶体摘出併用群22.0±13.0%であった。細胞密度が10%以上減少した症例では,術中の角膜上皮そう爬,水晶体後囊破損,虹彩リトラクターの使用,術後のフィブリン析出があり,前房内炎症の強さが角膜内皮細胞の減少に関係していることが推察された。
エタンブトール投与量と視神経症の発症率
著者: 竹下佳利 , 井上美奈香
ページ範囲:P.687 - P.690
要約 2000年までの7年間に当院で加療した結核患者について,エタンブトール視神経症の発症率を検索した。1996年までの3年間での発症率は投与を受けた129人中6人(4.7%)であり,1998年以後の3年間でのそれは237人中1人(0.4%)で有意差があった(p<0.01)。1996年の結核治療ガイドラインに伴い,当院ではエタンブトール投与量を変更した。1995年での平均投与量は17.0mg/kg/day,平均投与期間は4.6か月であり,2000年でのそれは13.6mg/kg/dayと3.8か月であった。視神経症の発症率が後半の3年間で低下した原因は,エタンブトール投与量が減ったためであると推定した。
白血病により視神経乳頭腫脹をきたした2例
著者: 平野佳男 , 滝昌弘 , 高木規夫
ページ範囲:P.691 - P.695
要約 白血病に視神経乳頭腫脹が併発した2例を経験した。1例は44歳男性で,3年前に急性骨髄性白血病が発症し,二度の化学療法で寛解していた。3週間前に両眼の視力障害を自覚した。受診時の視力は,右手動弁,左眼0.04であった。乳頭腫脹が両眼にあった。化学療法と放射線照射で乳頭腫脹が寛解し,視力は右0.4,左0.6に回復した。他の1例は16歳男性で,1か月前に風邪様の症状があり,右眼の眼瞼腫脹と複視が続発した。当科受診直前に急性リンパ性白血病と診断された。近見視力は右0.3,左0.6で,右眼に乳頭腫脹があり,両眼に網膜出血があった。磁気共鳴画像検査(MRI)で右の副鼻腔と眼窩に腫瘤があり,視神経が鼻側に圧排されていた。抗白血病薬の全身投与と髄腔内注入で,眼窩腫瘍と乳頭腫脹は寛解した。視神経乳頭腫脹の原因は,第1例では浸潤性視神経症,第2例では圧迫性視神経症と推定した。
ヌンチャク型シリコーンチューブの下鼻甲介穿孔例
著者: 五嶋摩理 , 三田哲子 , 新妻卓也 , 井藤紫朗 , 朝岡勇 , 松原正男
ページ範囲:P.697 - P.699
要約 70歳女性が右鼻涙管閉塞に対してヌンチャク型シリコーンチューブ挿入術を受けた。術直後は通水が良好であったが,2か月後から通水が不良となり,当科を受診した。鼻内視鏡検査で,下鼻甲介下部にチューブが2本穿孔,突出し,穿孔部位に発赤と隆起があった。チューブを抜去した直後に鼻涙管開口部から通水があった。20日後に仮道開口部は閉塞し,抜去から2か月後に鼻涙管開口部からの通水がなくなった。本手術では,通水があっても仮道に挿入されていることがあり,チューブ留置中に通水がなくなった場合にはその可能性が大きい。鼻涙管にチューブを留置する際に内視鏡で確認する必要がある。
未治療緑内障眼におけるラタノプロスト単剤投与による眼圧下降効果
著者: 木村英也 , 野崎実穂 , 小椋祐一郎 , 木村章 , 有村和枝 , 谷原秀信
ページ範囲:P.700 - P.704
要約 未治療の緑内障69例にラタノプロストを1日1回点眼し,眼圧下降効果を検索した。原発開放隅角緑内障26例と正常眼圧緑内障43例であり,基礎眼圧が高い各1眼を対象とした。原発開放隅角緑内障では,投薬前眼圧が22.6±3.6mmHg,3か月後眼圧が15.8±2.8mmHgであり,下降率29%であった。正常眼圧緑内障では,投薬前眼圧が16.4±2.5mmHg,3か月後眼圧が12.3±2.1mmHgであり,下降率24%であった。30%以上の眼圧下降は,前者では18眼(69%),後者では25眼(58%)で得られた。原発開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障に対するラタノプロスト単剤投与で,多くの症例で病期に応じた目標眼圧に到達することが可能であり,第1選択薬として有用であると結論される。
翼状片頭部におけるガングリオシドの検討
著者: 松本直 , 斉藤伸行 , 松橋正和
ページ範囲:P.705 - P.708
要約 手術で得られた7例7眼の翼状片頭部のガングリオシド含量を測定した。さらに2眼では翼状片再発に対する手術で検体を採取した。同一眼から正常と思われる球結膜を採取し,対照とした。ガングリオシド含量は,翼状片では対照よりも高く,再発例ではさらに高かった。薄層クロマトグラフィで,翼状片頭部は正常結膜にはない複数の分子種を含んでいた。再発翼状片頭部は,これに加え,Rf値が低いポリシアロガングリオシドを複数含んでいた。ガングリオシドはそれぞれの分子種単独でも生理活性がある。ガングリオシドの量的,質的変化が,翼状片の発生と再発に密接に関連している可能性を,上記の結果は示している。
カルテオロールとラタノプロストの併用による眼圧下降効果
著者: 河合裕美 , 林良子 , 庄司信行 , 森田哲也 , 平山さをり , 根本徹 , 兒玉安代 , 清水公也
ページ範囲:P.709 - P.713
要約 カルテオロールまたはラタノプロストを単独で使用していて,病期に応じた目標眼圧に達していない16例16眼に対し,もう一方の点眼薬を追加したときの眼圧下降効果と副作用をprospectiveに検索した。症例の内訳は,原発開放隅角緑内障12眼と正常眼圧緑内障4眼である。その結果,目標達成が,カルテオロール追加群8眼中4眼(50%),ラタノプロスト追加群8眼中5眼(63%)で得られた。6か月以上の最終観察時点での平均眼圧には,両群間に有意差がなかった。角膜障害が5眼(31%)に生じた以外には,特に副作用はなかった。以上の所見は,カルテオロールとラタノプロストの併用療法が良好な眼圧下降効果を示すことと,他の組み合わせよりも角膜障害の発生頻度が低いことを示している。
ボツリヌス毒素療法の成績
著者: 鈴木温 , 木村亜紀子 , 三村治
ページ範囲:P.715 - P.718
要約 過去5年間に412症例に対してボツリヌス毒素療法を行った。内訳は眼瞼痙攣172例と片側顔面痙攣240例で,男性122例,女性290例である。平均年齢は66±11歳,平均投与回数は7.4±5.7回であり,平均観察期間は2.0±1.6年である。投与のたびにアンケート調査を行い,81%の症例が治療に満足していた。効果持続期間は,眼瞼痙攣が2.4か月,片側顔面痙攣が3.5か月で,後者が有意に長かった(p<0.00000001)。治療の中断は,眼瞼痙攣では効果不十分,片側顔面痙攣では治療が奏効したことがその主な理由であった。23例で抗体検査を実施し,その全例で陰性であった。ボツリヌス毒素療法は,満足度が高く,全身的な副作用も皆無であった。発症初期に治療をすれば治癒の可能性が高くなると考えられるため,早期治療が望ましい。
白色発光ダイオードを用いた頭部搭載型網膜投影装置
著者: 白木邦彦 , 戒田真由美 , 安東孝久 , 中村肇 , 山口成志 , 田淵仁志 , 安成隆治 , 本山貴也 , 高橋秀也 , 志水英二
ページ範囲:P.719 - P.722
要約 空間光変調素子に表示された電子的映像を,赤色ダイオードレーザーを用いてマックスウエル視させることで,明瞭な像を網膜上に直接呈示する網膜投影装置を卓上視覚補助器として以前に作製した。今回,白色発光ダイオードを光源にして頭部に搭載できる小型な装置に改良した。重量は146gで,高さ,幅,奥行はそれぞれ13cm,3cm,3cmである。新しい光源にしたことで,完全なマックスウエル視ではなくなったが,光学的に瞳孔領に像を絞り込むことで焦点深度が深い明瞭な像を網膜に投影することができた。さらに,本装置ではフルカラー像の呈示が可能になった。
糖尿病黄斑浮腫の光干渉断層計による分類および硝子体手術の術後経過
著者: 木村徹志 , 高木均 , 加藤真理 , 桐生純一 , 西脇弘一 , 王英泰 , 鈴間潔 , 植村明嘉 , 渡部大介 , 菅波絵理 , 広瀬文隆 , 栗本雅史 , 本田孔士
ページ範囲:P.723 - P.728
要約 硝子体手術による後部硝子体剝離形成を糖尿病黄斑浮腫16眼に行い,その術後経過を術前の浮腫形態と比較した。浮腫の形態は光干渉断層計(OCT)で評価し,Kishiらの分類を用いた。術前の黄斑浮腫は,囊胞様黄斑浮腫にスポンジ様腫脹を伴うもの9眼,スポンジ様腫脹3眼,漿液性網膜剝離にスポンジ様腫脹を伴うもの4眼であった。それぞれの群の術前視力は0.15,0.25,0.35,術後視力は0.15,0.46,1.02であった。漿液性網膜剝離にスポンジ様腫脹を伴う群で視力の改善が顕著であり,この形の糖尿病黄斑浮腫に対して後部硝子体剝離形成術が特に奏効すると推定される。
網膜全周切開黄斑移動術の長期成績
著者: 出口裕子 , 北岡隆 , 宮村紀毅 , 宿輪恵子 , 雨宮次生
ページ範囲:P.729 - P.731
要約 周辺部網膜全周切開による黄斑移動術を行い,2年以上の経過が追跡できた19眼について,その長期経過を検索した。内訳は加齢黄斑変性13眼,近視性脈絡膜新生血管6眼である。術中と術直後の合併症が89%と高率で,術後早期の視力は不安定であった。3か月以降になると視力は安定し,最終視力は11眼(58%)で2段階以上改善し,4眼(21%)で不変,4眼(21%)で悪化した。各1眼で脈絡膜新生血管の再発と黄斑円孔が術後20か月以降に生じた。本手術後の長期経過は概して良好であったが,なお長期の経過観察が必要である。
鉄欠乏性貧血を伴った網膜中心動静脈閉塞症の3症例
著者: 川崎厚史 , 橋田徳康 , 金山慎太郎 , 小川憲治
ページ範囲:P.732 - P.736
要約 鉄欠乏性貧血の3症例に網膜中心動静脈閉塞症が併発した。いずれも女性で,年齢は29歳,44歳,51歳,すべて片眼発症である。受診の動機は急性の視力低下または霧視であり,初診時の患眼の矯正視力は,0.02,1.0,0.8であった。眼底所見として桜実紅斑,動脈周囲の糸状網膜浮腫または限局性浮腫があり,蛍光眼底造影で網膜内の循環遅延があり,一過性の網膜中心動脈閉塞症と診断した。その後,視神経乳頭の発赤浮腫,網膜静脈の拡張蛇行,火炎状の網膜出血が生じ,網膜中心静脈閉塞症の所見を呈した。全例に血清鉄,フェリチン,ヘモグロビン,ヘマトクリット値の低下があった。鉄欠乏性貧血の原因である拒食症,胃潰瘍,不正性器出血がそれぞれにあった。鉄剤などの投与で貧血は軽快した。これに続いて視力と眼底所見は速やかに改善し,最終視力として0.3,1.5,1.2を得た。初診時視力が良好なほど視力転帰がよかった。
透析患者の網膜静脈閉塞症
著者: 檀上陽子 , 佐藤圭子 , 池田誠宏 , 三村治 , 田畑勉 , 井上隆
ページ範囲:P.737 - P.739
要約 透析患者438例876眼について網膜静脈閉塞症の併発を検索した。原疾患は,慢性糸球体腎炎179例,糖尿病性腎症140例,その他119例であり,平均年齢は62.5歳であった。網膜静脈閉塞症は26例(5.9%)29眼にあった。平均年齢は62.2歳,透析期間は平均149か月であった。網膜静脈分枝閉塞症が21例24眼,網膜中心静脈閉塞症が5例5眼にあった。26例の全身因子として,高血圧が24例,糖尿病が3例,高脂血症と膠原病が各1例にあった。ヒトエリスロポエチンが21例で使用されていた。透析患者での網膜静脈閉塞症の発症率は0.3~1.0%とされているが,本症例群では5.9%と高率であった。高血圧と,血栓症を併発しやすいとされるエリスロポエチンの使用が危険因子として注目される。
裂孔原性網膜剝離に対する水晶体を温存した硝子体手術
著者: 櫻井寿也 , 前野貴俊 , 木下太賀 , 嶋元孝純 , 田野良太郎 , 吉田稔 , 川村博久 , 竹中久 , 佐々木香る , 小高隆平 , 真野富也
ページ範囲:P.740 - P.742
要約 裂孔原性網膜剝離36眼に対して硝子体手術を行った。全例が有水晶体眼で,手術の際に水晶体を温存した。原因裂孔は,弁状裂孔のみ11眼(30%),弁状裂孔とその他の象限に格子状変性がある20眼(56%),その他5眼(14%)であった。硝子体手術のみを6眼,硝子体手術と輪状締結を30眼に行った。初回手術で33眼(92%)に復位が得られ,再剝離した他の3眼も最終的に復位した。従来の報告とほぼ同様で良好な結果が得られたが,水晶体を温存する際には徹底した硝子体の切除が必要である。
耳側角膜小切開による日帰り白内障手術の術中合併症
著者: 原修哉 , 市川一夫 , 加賀達志 , 中村友昭 , 渡辺三訓 , 吉田則彦
ページ範囲:P.743 - P.746
要約 14施設で1年間に行われた角膜小切開日帰り白内障手術5,502眼を検討した。検討項目は,合併症の頻度,内訳と時期,術中処置,術前所見,術後の転帰である。術中合併症が63眼(1.15%)に生じ,後囊破損58眼,チン小帯断裂22眼,皮質残留5眼,核落下2眼である。術後視力は,合併症に対して適切な処置を行えば,合併症のない対照群と差がなかった。63眼中9眼では,眼内レンズの毛様溝縫着などの二次的処置が必要で,高核硬度や偽落屑症候群などが術前からあり,問題が予測されていた。角膜小切開日帰り白内障手術は処置を正しく行えば安全であるが,複数の危険因子がある場合には,当初から設備が整った二次施設での手術が望まれる。
硝子体腔内眼内レンズ落下症例の検討.二次縫着には専用レンズを用いるべし
著者: 日下野勉 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.747 - P.750
要約 挿入された眼内レンズが硝子体腔に落下した5例5眼を遡及的に検索した。年齢は63歳から86歳,平均75歳であった。眼内レンズは全例で囊外に固定されていた。2眼は無水晶体眼に対する二次挿入で,他の3眼中2眼には術中に後囊破損があり,1眼には術直前に穿孔性外傷があった。眼内レンズ脱臼の直接の原因は,転倒打撲1眼,大きな後囊破損2眼であり,さらに縫着用ではない眼内レンズの使用が2眼あった。硝子体切除の既往,高齢,術中の後囊の破損などが眼内レンズの硝子体腔落下の危険因子であり,挿入時に慎重な手術操作が望まれる。縫着用ではない眼内レンズの使用は新しい危険因子であり,避けるべきである。
白内障手術後にMRSA感染により敗血症性ショック・急性腎不全・DICに陥った1例
著者: 遠藤実
ページ範囲:P.751 - P.754
要約 66歳女性が右眼白内障手術を受けた。2か月前に左足関節骨折に対して骨接合術を受け,以後整形外科に入院中であった。抗生物質の点滴が術後8日間行われていた。白内障手術は術中・術後とも問題はなかった。フロモキセフナトリウム(フルマリン(R))の点滴を術後3日間行い,レボフロキサシン(クラビット(R))の内服に切り替えた。術後5日目に咽頭痛,悪心,発熱が起こった。3日後に体温が40℃になり,血圧が下降してショック状態になった。便からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が培養された。術後9日目に敗血症の状態になり,急性腎不全と播種性血管内凝固(DIC)が併発した。バンコマイシンの全身投与と持続的血液濾過透析を含む諸治療で全身状態は軽快した。白内障手術前の長期入院中にMRSAが定着し,術後の抗生物質投与でMRSA腸炎が発症したことが,一連の重篤な事態に至った理由と推定された。
各種アクリル製眼内レンズの家兎水晶体上皮培養細胞への影響
著者: 松島博之 , 向井公一郎 , 吉田紳一郎 , 吉田登茂子 , 澤野宗顕 , 妹尾正 , 小原喜隆
ページ範囲:P.755 - P.759
要約 目的:培養した水晶体上皮細胞に各種のアクリル製眼内レンズ(IOL)が及ぼす影響の検討。方法:生後8週の白色家兎から水晶体上皮細胞を採取し,IOL上にこれを播種した。96時間後に細胞の発育を停止させ,ヘマトキシリン・エオジンで染色し,コラーゲン膜上とIOL表面の細胞密度と性状を生体顕微鏡で観察した。アクリル製IOLには,疎水性3種と親水性1種を用いた。結果:親水性IOL表面には細胞付着が少なく,コラーゲン膜上には伸展していた。疎水性IOL表面には多数の細胞が付着し,コラーゲン膜上の伸展が少なかった。細胞の形状は,各IOL間で異なっていた。結論:親水性と疎水性アクリル製IOLでは,その種類により,後発白内障の発生頻度と伸展細胞の性状に特異性がある。
経瞳孔温熱療法後に異なる経過をとったポリープ状脈絡膜血管症の3症例
著者: 松本英孝 , 飯田知弘 , 佐藤拓 , 森本雅裕 , 岸章治
ページ範囲:P.763 - P.767
要約 臨床所見が似ている中心窩下のポリープ状脈絡膜血管症3例3眼に対して,同一条件で経瞳孔温熱療法(TTT)を行った。すべて男性で,年齢は68,76,79歳であった。治療前の視力は3眼とも0.5で,そのすべてに中心窩を含む漿液性網膜剝離があった。フルオレセイン蛍光造影でoccult CNVがあり,インドシアニングリーン蛍光造影でポリープ状異常血管が検出された。TTTにはダイオードレーザーを使い,直径3mmで1スポット,出力350mW,60秒照射とした。術後に1眼では網膜剝離が消失し,視力は0.9に改善した。1眼は術直後に網膜が白色化して視力が0.1に低下した。1眼では網膜剝離が増強し,最終的に黄斑萎縮が生じ,視力は0.2に低下した。これら3眼では治療前の臨床所見が類似していたにもかかわらず,術中と術後の反応が違った。TTTの照射条件の設定には,なお検討が必要である。
糖尿病網膜症のpigment epithelium-derived factorと血管内皮細胞増殖因子
著者: 緒方奈保子 , 西川真生 , 西村哲哉 , 松村美代
ページ範囲:P.769 - P.772
要約 糖尿病網膜症36眼につき,硝子体内のpigment epithelium-derived factor(PEDF)と血管内皮細胞増殖因子(VEGF)の濃度を測定した。症例の内訳は,増殖糖尿病網膜症32眼,非増殖糖尿病網膜症4眼であり,特発性黄斑円孔15眼を対照とした。PEDFとVEGFの濃度はELISAで測定した。対照群でPEDF値は1.62±0.23μg/ml,VEGF値は検出できなかった。増殖糖尿病網膜症のPEDFは平均0.84μg/mlと有意に低く(p=0.017),VEGFは平均1,871pg/mlと有意に高かった(p=0.026)。活動性が高い増殖糖尿病網膜症24眼のPEDFは平均0.76μg/mlとさらに低く,VEGFは平均2,341pg/mlとさらに高かった。PEDFには眼内血管新生阻害作用があるとされている。上記の結果は,高濃度のVEGFのみならず,低濃度のPEDFが網膜症の進展に関与している可能性を示している。
翼状片組織におけるヒアルロン酸合成酵素の発現について
著者: 岡野敬 , 村田正敏 , 白石久子 , 志和健吉 , 堀内三郎
ページ範囲:P.773 - P.776
要約 翼状片2眼から切除した組織を,ヒアルロン酸,ヒアルロン酸合成酵素,CD44について検索した。患者は70歳と76歳の女性である。ヒアルロン酸は細胞外マトリックスの構成要素であり,組織の立体構造の維持に関与する。これはヒアルロン酸合成酵素によって産出され,CD44はそのレセプターである。これら3者は,細胞の移動や増殖などの生物学的プロセスに関与している。ヒアルロン酸の定量にはELISAを用い,ヒアルロン酸合成酵素2とCD44の発現はRT-PCR法で確認した。1検体から1.0μg/mlのヒアルロン酸が検出され,両検体からヒアルロン酸合成酵素2とCD44の発現が認められた。以上の結果は,翼状片組織にはヒアルロン酸,ヒアルロン酸合成酵素,CD44が存在することと,これら3者からなる系が翼状片の病態に関与する可能性を示している。
Polymerase chain reaction法で診断されたアカントアメーバ角膜炎の1例
著者: 並木美夏 , 増田洋一郎 , 浦島容子 , 田中雄一郎 , 渡辺朗 , 鎌田芳夫 , 北原健二 , 中林條 , 小林かおり
ページ範囲:P.777 - P.780
要約 24歳女性が右眼の角膜潰瘍で紹介され受診した。ソフトコンタクトレンズを長期間使用していた。2週間前に右眼痛があり,樹枝状角膜炎の疑いで治療を受けたが無効であった。矯正視力は右0.06,左1.2であり,右角膜中央部にびらんを伴う径4mmの混濁があった。アカントアメーバ角膜炎を疑い,フルコナゾールとミコナゾール点眼を追加し角膜そう爬を繰り返したが,病変はさらに悪化した。初診から4か月後に,使用していたソフトコンタクトレンズとその保存液からアカントアメーバが培養され,角膜擦過物からもpolymerase chain reaction(PCR)法でアカントアメーバDNAが検出されて診断が確定した。本症に有効とされるクロルヘキシジンとポリヘキサメチレン・ビグアナイドの点眼を開始し,角膜病変は瘢痕治癒した。
閉塞隅角緑内障を合併した真性小眼球の1例
著者: 韓在元 , 加茂雅朗 , 佐井豊幸 , 稲田真紀子 , 小松敏郎 , 本山貴也 , 猪尾芳弘 , 白木邦彦
ページ範囲:P.781 - P.784
要約 60歳男性が緑内障のコントロール不良のため紹介され受診した。幼少時から両眼の視力が不良であり,同胞5名中3名が視力不良であった。視力は右0.08×+18D,左0.09×+17Dであり,眼圧は右21mmHg,左42mmHgであった。角膜径は左右とも11mmで,眼軸長は右15.4mm,左15.6mmであった。両眼とも前房が著しく浅く,狭隅角で,膨隆虹彩があった。以上のことから,閉塞隅角緑内障を伴う真性小眼球と診断した。右眼に周辺虹彩切除術,左眼に線維柱帯切除術,超音波乳化吸引術,眼内レンズ挿入術を行った。術後,右眼には合併症がなく,左眼には局所的な脈絡膜剝離が生じたが自然消退した。右眼は点眼併用,左眼は無治療で眼圧が正常化し,視野狭窄の進行はない。真性小眼球に内眼手術を行うと,uveal effusionが起こりやすいとされているが,ほぼ順調に経過した症例である。
治療が奏効した感染性強膜炎の2症例
著者: 間山夏子 , 佐藤章子 , 蔦祐人 , 三好永利子
ページ範囲:P.793 - P.797
要約 64歳男性が1週間前からの右眼痛と充血で受診した。右眼の矯正視力は0.5で,球結膜の充血と浮腫,デスメ膜皺襞,前房内炎症があった。ステロイド薬の減量と抗生物質などの全身投与は無効であった。初診から5週間後に強膜の生検を行った。強膜切開時に排膿があり,肺炎球菌が検出された。さらにステロイド薬の減量と抗生物質を投与し,病変は治癒した。44歳女性が右眼痛があり受診した。8年前に右眼の網膜剝離手術を受けており,球結膜鼻側にシリコーンスポンジが露出していた。視力は0.3であった。露出したスポンジを抜去した。その部の強膜は壊死により菲薄化し,ぶどう膜が透見されたので,他眼の球結膜を移植した。スポンジからグラム陽性菌が検出された。複数回の手術と抗生物質・消炎薬の投与で壊死強膜は結膜で被覆された。退院時視力は0.2であった。
角膜表面バイオフィルム形成から前房蓄膿性角膜潰瘍に至った兎眼の1症例
著者: 堅野比呂子 , 八田史郎 , 石倉涼子 , 井上幸次
ページ範囲:P.799 - P.803
要約 58歳男性が兎眼に伴う左眼角膜の菲薄化で紹介され受診した。32歳のとき,両眼に眼瞼下垂手術を受けていた。10年前に筋の生検でミトコンドリア筋症(Kearns-Sayre症候群)と診断された。矯正視力は右0.6,左手動弁であり,閉瞼に努力しても瞼裂幅が右2mm,左4mmであった。全眼筋麻痺があり,瞬目が不可能であった。左眼角膜は中央部で菲薄化し,突出していた。初診の2か月後に左眼角膜に白色塊が生じ,その3か月後に角膜が穿孔し,前房蓄膿が続発した。薬物治療では十分な効果が得られなかった。さらに増大した白色塊の組織学的検索でグラム陽性の桿菌が検出され,PAS染色陽性で,細菌によるバイオフィルムと考えられた。白色塊の除去で前房蓄膿は消退し,初診から18か月後の現在まで再発はない。全眼筋麻痺がある兎眠性角膜炎では,眼表面にもバイオマテリアルの介在なくバイオフィルム形成がありうることを示す症例である。
黄斑上膜に合併した黄斑円孔に対する硝子体手術後の後天青黄色覚異常
著者: 河野智子 , 中村かおる , 山本香織 , 河野千恵 , 堀貞夫
ページ範囲:P.804 - P.808
要約 目的:黄斑上膜を伴う黄斑円孔に対する硝子体手術後に後天青黄色覚異常が生じた症例の報告。症例:49歳女性。3年前からの右眼変視症が悪化し,黄斑円孔が発見され,硝子体手術を受けた。インドシアニングリーン(ICG)染色による内境界膜剝離を併用した。変視症が改善し,視力は1.0と不変であったが,色覚の左右差を訴えるようになった。所見:諸検査で青黄色覚異常が証明され,これに特有な色誤認があった。色覚異常は術後1年の現在まで続いている。結論:術後の青黄色覚異常が,内境界膜剝離による機械的損傷,ICGの毒性,青錐体系の脆弱性の個体差によって起こった可能性がある。ICG併用の黄斑手術では色覚異常が惹起されうることに留意する必要がある。
過去4年間の眼内悪性リンパ腫の検討
著者: 角環 , 福島敦樹 , 林暢紹 , 小浦裕治 , 小松丈記 , 橋田正継 , 政岡則夫 , 上野脩幸
ページ範囲:P.809 - P.813
要約 過去4年間に眼内悪性リンパ腫5例9眼を経験した。男性1例,女性4例で,年齢は59~81歳,平均70歳であった。受診の動機は,視力低下3例,霧視1例,飛蚊症1例であった。初診時の全身検査で,眼外に悪性リンパ腫の所見は5例すべてになかった。全例に遷延する硝子体混濁があった。全例に硝子体生検を行い,細胞診で診断が確定した。硝子体中のIL-10/IL-6比が,測定した4例すべてで高値であった。しかし,この値と以後の経過には明らかな関連はなかった。診断後4例に全眼球照射を行い,うち3例には化学療法を行った。4例で,眼症状出現から4~48か月,平均23か月後に頭蓋内転移が起こった。これら4例は不幸な転帰をとった。
両眼の脈絡膜新生血管に対し硝子体手術を行った真菌性網脈絡膜炎の1例
著者: 宮野良子 , 竹田宗泰 , 古庄史枝 , 斉藤秀文
ページ範囲:P.815 - P.819
要約 35歳女性が両眼の脈絡膜新生血管で紹介され受診した。2年前に卵巣奇形腫の手術を受け,術後の化学療法中,両眼に真菌性網脈絡膜炎と推定される病変が生じ,抗真菌薬投与で瘢痕治癒したが,ふたたび活性化した。視力は右0.8,左0.4であり,両眼黄斑部に漿液性網膜剝離があり,左眼に網膜下出血があった。蛍光眼底造影などで両眼の脈絡膜血管新生と診断した。初診から4か月後に,硝子体手術による脈絡膜新生血管抜去を左眼に行い,その10か月後に同様の手術を右眼に行った。経過は良好で,最終視力として右0.4,左0.8を得た。真菌性網脈絡膜炎による脈絡膜新生血管に対して血管抜去術が奏効した1例である。
全身転移を伴った眼窩内悪性リンパ腫に対して腫瘍摘出術を施行した1例
著者: 唐下千寿 , 山崎香織 , 三原悦子 , 八田史郎 , 井上幸次
ページ範囲:P.821 - P.824
要約 44歳男性が2週間前に左上眼瞼部に腫瘤を自覚した。その後さらに腫瘤が増大して開瞼不能になり,当科を受診した。2年前に頭蓋内悪性リンパ腫に対して放射線照射を受け,寛解している。初診時には眼位と眼球運動に異常がなかったが,1週間後に左眼の眼球運動障害が生じた。確定診断と整容上の改善,ならびに視機能改善を目的として,眼球を保存しながら眼窩腫瘤摘出術を行い,開瞼可能になった。摘出組織の病理所見は,悪性リンパ腫(diffuse large B cell lymphoma)であった。また全身的検査で他臓器への播種が認められたために,化学療法を開始し,眼局所を含めて著明な改善が得られた。全身転移があっても,眼窩腫瘍摘出で患者のQOLが向上した1例である。
眼窩先端部症候群で初発した蝶形骨洞原発悪性リンパ腫の1例
著者: 上原淳太郎 , 元木竜一 , 佐野信昭 , 武田憲夫 , 八代成子 , 上村敦子 , 三宮曜香 , 北橋正康
ページ範囲:P.825 - P.828
要約 57歳女性の左眼に霧視と鈍痛が8か月前からあった。2週前から増悪して受診した。右眼は外傷による無眼球であった。左眼矯正視力は0.8であったが,3日後に0.03に低下し,開瞼不能になった。全方向への眼球運動が高度に制限され,画像検査で蝶形骨洞腫瘍と左眼窩内浸潤が発見された。両側蝶形骨洞と篩骨洞の開放術に続き,プレドニゾロン点滴を行った。眼瞼下垂と眼球運動障害は速やかに改善した。病理組織学的診断はびまん性大細胞Bリンパ腫であった。視力は1.0にいったん回復したのち,視神経萎縮が生じ,0.03になった。両側蝶形骨洞に原発した悪性リンパ腫が眼窩先端部症候群で発見された稀な1例である。
眼窩内に発生したsolitary fibrous tumor
著者: 山下啓行 , 松本治恵 , 中塚和夫 , 榊保堅 , 前尾直子
ページ範囲:P.829 - P.832
要約 19歳男性が5か月前からの右眼球突出と流涙で受診した。矯正視力は右0.7,左1.2であり,眼球突出度は右20mm,左13mmであった。右眼底に脈絡膜皺襞があった。CT検査で右眼窩内に30×20mmの卵円形の腫瘤があり,これを摘出した。腫瘤は充実性で被膜に包まれていた。病理組織検査で,腫瘍細胞はpatternless patternの配列であった。免疫組織染色で,vimentinに陽性,CD34に強陽性を示した。これにより孤在性線維性腫瘍(solitary fibrous tumor)の診断が確定した。術前の磁気共鳴画像検査(MRI)で,腫瘍はT1強調画像で低信号,T2強調画像で不均一な高信号を示し,Gd-DTPAで腫瘍辺縁部に強い造影があった。摘出した腫瘍の被膜には血管成分があり,これが特徴的な画像所見を示した原因であると考えた。
外傷性眼球脱臼に対し眼球整復術を施行した1例
著者: 鈴木崇弘 , 山家麗 , 赤塚一子 , 松倉修司 , 河合憲司
ページ範囲:P.833 - P.835
要約 58歳女性が軽トラックを運転中に乗用車と正面衝突し,車内の突起物で顔面を強打し,その直後に受診した。矯正視力は右0,左1.2であった。右眼の球結膜が全周にわたって断裂し,前房出血があり,眼球が眼瞼前に脱臼していた。CT検査で右視神経の離断があった。眼窩骨折はなかった。即日全麻下で眼球の眼窩内への整復を行った。以後の経過は良好であり,受傷から約14か月後の現在,眼球は温存された状態にあり,中等度の眼球運動があり,整容的に患者は満足している。外傷性の眼球脱臼に対して眼窩内整復術が奏効した1例である。
著明な眼瞼,眼窩血腫をきたした小児眼窩血管腫の1症例
著者: 梅山圭以子 , 木本高志 , 小川豊 , 山内康雄 , 和田光正 , 国富薫 , 上原雅美
ページ範囲:P.836 - P.840
要約 5歳女児が3日前からの皮下出血を伴う強い右上眼瞼腫脹で受診した。複数の画像診断で,上眼瞼から眼窩にかけて血性の囊腫様病変があった。3週後に視力が低下し,眼圧が28mmHgに上昇した。眼瞼部の穿刺吸引で陳旧化した血液が得られ,眼窩血腫が疑われた。眼圧は正常化したが,眼瞼腫脹は持続した。まず経皮的,続いて経頭蓋的に腫瘤を摘出し,病理組織学的に海綿状血管腫と診断された。術後,眼瞼腫脹はほとんど消失し,視力も正常化した。本症例では,筋円錐外の海綿状血管腫が自然出血して血腫を形成したと推定された。
初発症状として前部ぶどう膜炎を呈し,サルコイドーシスの併発が疑われた全身性エリテマトーデスの1症例
著者: 堀尾和弘 , 西田保裕 , 岩崎博之 , 吉田健一 , 山出新一 , 小田早苗 , 可児一孝
ページ範囲:P.841 - P.845
要約 57歳男性が1週間前からの右眼視力障害で受診した。矯正視力は右0.01,左0.8であり,眼圧は右40mmHg,左12mmHgであった。右眼には豚脂様の角膜後面沈着物を多数伴う前部ぶどう膜炎があり,左眼にもやや軽症で同様な所見があった。右眼の眼底は透見不能であったが,その他は隅角を含め異常所見はなかった。ツベルクリン反応が陰性で,両側肺門リンパ節腫脹があり,眼サルコイドーシスが疑われた。副腎皮質ステロイド薬の局所と全身投与で軽快し,右眼視力は0.8に回復した。初診から6週間後に通院を中断したが,その6か月後に下痢と腹痛が生じた。内科で免疫性溶血性貧血と特発性血小板減少性紫斑病(Evans症候群)を伴う全身性エリテマトーデス(SLE)と診断された。両眼の前部ぶどう膜炎が再発,悪化し,眼底に軟性白斑と出血斑などSLE網膜症があった。眼病変は副腎皮質ステロイド薬の局所と全身投与で軽快した。本症例の前部ぶどう膜炎の原因として,SLEだけでなくサルコイドーシスの関与が推定された。
硝子体細胞診から診断された眼・中枢神経系悪性リンパ腫の1例
著者: 水野かほり , 保坂大輔 , 黒川克雄 , 郡司久人 , 河合一重
ページ範囲:P.847 - P.850
要約 32歳男性が2週間前からの左眼霧視で受診した。矯正視力は左右眼とも1.2であった。左眼の前房と硝子体に混濁があり,眼底は正常であった。硝子体混濁が悪化し,3か月後に左眼視力が30cm指数弁に低下したために硝子体手術を行った。初診から2年後に右眼に硝子体混濁が生じた。その10か月後に痙攣発作があり,画像検査で左側脳室に腫瘤が発見された。視野に右同名半盲があった。腫瘤生検でB細胞型悪性リンパ腫と診断された。頭部への放射線照射で右眼硝子体混濁は軽快したが,化学療法に切り替えると増悪した。右眼に硝子体手術を行い,細胞診でclassVの高度異型細胞が検出され,眼・中枢神経系悪性リンパ腫の診断が確定した。右眼には放射線照射を行い,経過は順調である。放射線照射と化学療法が無効であった眼・中枢神経系悪性リンパ腫に対し,硝子体手術による腫瘍細胞の除去と放射線照射の追加が奏効した1例である。
両眼性黄斑下脈絡膜新生血管を合併したEales病疑いの若年女子例
著者: 柴田佐和子 , 伊藤賢司 , 飯田知弘 , 岸章治
ページ範囲:P.851 - P.855
要約 16歳女子が1か月前からの両眼視力障害で受診した。矯正視力は両眼とも0.1であり,右に-12D,左に-11Dの近視があった。両眼に中心窩下の脈絡膜新生血管があり,網膜下出血と漿液性網膜剝離を伴っていた。両眼の耳側周辺部に網膜静脈周囲炎,血管の白鞘化,無血管野があった。ツベルクリン反応が強陽性で,サルコイドーシスよりもむしろEales病を疑った。高度近視が中心窩下の脈絡膜新生血管の誘因であると推測した。フルオレセイン蛍光造影による脈絡膜新生血管の活動性低下がないため,初診から10週後に左眼,4か月後に右眼の新生血管除去術を行った。術後1年の現在,両眼とも0.15~0.2の視力を維持し,網膜静脈周囲炎の悪化はない。
視機能障害にて発見された前交通動脈動脈瘤の1例
著者: 上野雅代 , 川添真理子 , 沖波聡 , 隈元真志 , 田渕和雄
ページ範囲:P.857 - P.860
要約 38歳女性が6週前からの左眼視力低下で受診した。4か月前から片頭痛があり,2か月前に脳神経外科でのCT検査で異常が発見されなかった。矯正視力は右1.5,左0.6で,左眼瞳孔の直接反応が遅鈍であった。左眼の中心と耳側視野に沈下があった。左眼の視神経症が疑われた。磁気共鳴画像検査(MRI)で脳内の動脈瘤が疑われた。血管造影で,左前大脳動脈と前交通動脈との分岐部に動脈瘤があった。動脈瘤のクリッピング術を行った。動脈瘤の大きさは3cmで血腫を伴い,左視神経を内側から前方に向かって圧迫していた。手術の1週後に左眼視力は1.0になり,その他の視機能も続いて回復した。脳動脈瘤が視神経障害を起こした稀な1例である。
外傷性隅角毛様体損傷の超音波生体顕微鏡による検討
著者: 和田園美 , 河野剛也 , 平林倫子 , 白木邦彦
ページ範囲:P.861 - P.865
要約 鈍的眼外傷後の29眼の隅角と毛様体を,超音波生体顕微鏡(UBM)で観察した。毛様体解離が4眼にあり,すべて強膜に沿う毛様体の裂隙を呈していた。この4眼中3眼には,眼圧が正常化したのちでも,隅角鏡では見えない限局性の毛様体解離ないし脈絡膜剝離があった。隅角後退が25眼にあり,さまざまな程度の毛様体実質への切れ込みの形を示した。受傷から10日以内の新鮮例12眼中4眼に,毛様体浮腫または脈絡膜剝離があった。鈍的外傷眼をUBMで観察することで,毛様体解離,隅角後退,毛様体浮腫,脈絡膜剝離などの客観的評価が可能であった。
多彩な眼症状を示した再発性多発性軟骨炎の症例
著者: 岡見豊一 , 松永裕史 , 白数純也 , 佐々木奈穂 , 畑埜浩子 , 三上義人
ページ範囲:P.867 - P.871
要約 再発性多発性軟骨炎がある48歳男性と65歳女性に眼病変が発症した。2症例に共通して,両側の耳介軟骨炎,多発性関節炎,強膜炎,虹彩毛様体炎があった。1例には両眼の視神経乳頭浮腫と網膜出血があった。他の1例には虹彩毛様体に前房蓄膿が併発し,角膜の浸潤と浮腫があった。副腎皮質ステロイド薬の局所投与は効果が不十分であり,これとコルヒチンの全身投与で著効が得られた。再発性多発性軟骨炎では眼病変の合併が多く,診断的価値があることを示す2症例である。
専門別研究会
眼先天異常
著者: 玉井信 , 野呂充
ページ範囲:P.872 - P.873
一般講演
1.Neurocristopathyを伴った第1番染色体異常のある先天緑内障の1例
初川嘉一・中尾武史・山岸智子・岡本伸彦(大阪府立母子保健総合医療センター眼科)
目的:近年,先天緑内障の遺伝子異常について多くの知見が得られている。われわれは先天緑内障の異常遺伝子座を含む領域の染色体異常とともに口蓋裂を伴った症例を経験した。この症例について神経堤細胞の異常であるneurocristopathyとの関連について報告したい。
症例:初診は1999年8月10日で,生後4日目の女児。在胎38週,出生体重1,604gで出生した。角膜径は右13mm,左13mm,催眠下眼圧は右37mmHg,左36mmHg,瞳孔は散大,前房は深く,隅角は虹彩の高位付着が認められた。ピロカルピン,βブロッカーの点眼とダイアモックス(R)の内服後,2日後に右眼,その翌日に左眼のトラベクロトミーを施行した。術後眼圧は正常化し,現在まで投薬なしで経過観察中である。全身合併症としては,口唇口蓋裂,小頭症,小顎症,四肢短縮,発達遅滞,体重増加不良が認められた。染色体検査にて1番染色体長腕の部分欠失46,XX,del(1)(q24.3q31.2)がみられた。家族歴には異常はなかった。
考按とまとめ:先天緑内障と口唇口蓋裂,小頭症,小顎症はneurocristopathyに相当すると考えられた。先天緑内障は染色体の欠失部が緑内障遺伝子座に一致しており,他の全身異常との関連性も考察した。
Evidence Based Eye Surgery(旧称:無水晶体眼JARG)
著者: 大木孝太郎
ページ範囲:P.874 - P.875
現在,多くの医療分野において,その医療行為の客観的有用性に基づく治療,いわゆるevidence based medicineが注目を集めている。われわれが行う手術という治療手段においても,今後はevidenceに基づく評価・議論が行われていくものと考えられるが,手術という外科的手段におけるevidence作りは容易なものではない。これまで本研究会は「無水晶体眼」の会名のもとで多くの情報交換を行ってきたが,今回から先に述べた現状認識のもとに,研究会の主題を眼科手術におけるevidenceにおくことにし,名前も「Evidence Based Eye Surgery」とし,今後活動していく。今回は,先述のEvidenceも含め,以下の5つのE(Ethics,Efficacy,Education,Economy)の視点から眼科手術について考え,われわれの持つ現実的な問題点と今後進むべき方向性をテーマにした。
色覚異常
著者: 市川一夫
ページ範囲:P.876 - P.878
学校保健における定期色覚検査が2003年度から廃止されることから,6演題のほかに,この問題にどのように対処するかについてのラウンドテーブル・ディスカッションを企画した。
1.微弱度色覚異常の1例:山出新一(滋賀医大),他
石原表の2桁の1表のみ誤読で,パネルD-15,ランタンテスト2回とも全部パスした22歳の第2色弱の症例を遺伝子解析結果も併せ報告した。その結果から石原表のスクリーニング能力の限界を指摘し,従来報告されている本邦の色覚異常の頻度5%はもう少し高いのではないかと報告した。
連載 今月の話題
翼状片の最近の知見
著者: 中神哲司
ページ範囲:P.651 - P.655
近年,翼状片の発生病理に関してさまざまな細胞生物学的研究が行われ,細胞レベルでの異常な性質が数多く報告されている。ここでは最近明らかにされた翼状片上皮細胞および線維芽細胞に関する報告をまとめ,その臨床的意味について考察する。また,現在注目されている手術法についても紹介する。
眼の遺伝病 45
PAX6遺伝子異常と無虹彩症(3)
著者: 鈴木健史 , 和田裕子 , 玉井信
ページ範囲:P.658 - P.661
今回紹介するのはPAX遺伝子のヌクレオチド498番目からイントロン5にかけて23塩基の欠失,2塩基の挿入変異をヘテロ接合体でもつ無虹彩症の1家系である。この変異によりsplicing errorが生じると考えられる。このような症例と家系は,現在までに報告がない新規変異であり,さらに1症例では眼底に網脈絡膜萎縮,精神発達遅延を伴っていたことがわかった。
日常みる角膜疾患 2
円錐角膜
著者: 柳井亮二 , 西田輝夫
ページ範囲:P.662 - P.664
症 例
患者:30歳,男性
主訴:右眼の視力低下と眼痛
現病歴:12~13年前,高校生のときから右眼の視力低下を自覚し,近医を受診し,右眼は円錐角膜と診断され,以後ハードコンタクトレンズを装用して視力補正を行い,経過を観察されていた。1998年ごろからは右眼に角膜上皮びらんを繰り返すようになり,すぐ脱落するためハードコンタクトレンズ装用も困難となってきた。2000年9月11日,精査と加療を目的として当科初診となった。
既往歴・家族歴:特記すべきことはない。アトピー素因もない。
初診時所見:視力は右0.02(矯正不能),左1.2で,眼圧は右眼が測定不能,左眼は9mmHg(NCT)であった。細隙灯顕微鏡検査において,右眼角膜中央部に著明な突出および角膜実質の混濁,菲薄化があり,左眼にも下方にわずかな突出を認めた(図1)。また,photokeratoscope(PKS)においても右眼の角膜中央部からやや下方を頂点としたプラチドリングの狭細化を認めた(図2)。TMS-2Nのkeratoconus screeningの値は両眼とも95%であった。中間透光体,眼底には異常はなかった。
治療・経過:右眼の治療目的で2001年2月13日に入院し,2月16日に右眼の全層角膜移植術を施行した。摘出した角膜のヘマトキシリン・エオジン染色では角膜中央部の菲薄化,角膜上皮の菲薄化および過形成,ボウマン膜の断裂が認められたが,炎症細胞の浸潤や内皮細胞の不整はみられなかった(図3)。術後の経過は良好で,感染や続発緑内障などはみられなかった。3月2日の退院時の視力は右0.2(0.5×S+3.0D)で,以後は外来で経過を観察中である。最近の視力は右0.3(0.9×S+5.0D()cyl-5.5D Ax180°)であった。
私のロービジョンケア・1
「医の心」から展開したロービジョンケア
著者: 高橋広
ページ範囲:P.666 - P.670
ロービジョンケアが最近注目されてきている。しかし,まだまだ発展途上の段階にある。私はロービジョンケアは決して特別なものではなく,眼科医が本来的にもっている「医の心」から考えれば自ずと行えるものであると信じている。事実,私は日常診療する患者からロービジョンケアの多くを学び,これを展開してきた。これから1年間,これらの経験を紹介しながら,どのように日常の診療から具体的実践に移すことができるのか考えていきたい。第1回は,私と視覚障害者との出会いと,私が取り組んできたロービジョンケアの変遷についてご紹介する。
あのころ あのとき 29
初めての論文の思い出
著者: 保坂明郎
ページ範囲:P.672 - P.674
私の青春時代を書くとき,どうしても昭和20(1945)年3月10日,同8月15日に触れないわけにはいかない。わが家はもちろん,十数軒の持ち家(貸家)を一挙に失って貧乏になった日,そして情けないながら,生命の助かったことにほっとした日である。耐乏生活にはどうやら慣らされた日々であったが,今度は経済の急激な悪化とものすごい円安で,旧紙幣の新円交換率は1/10以下で,通学どころか生活費の捻出自体が困難であった。
医学部2学年というのは,どうにも潰しのきかない立場であった。しばらく家庭教師をやっていたが,とても食えるものではなく,ふと思いついたのが英語の通訳であった。東京の中心,日本橋・京橋・銀座・新橋にかけて復興も早く,駐留軍(進駐軍といった)向けの店では通訳が不足していたのである。私は外語大卒の兄から,戦争が終われば絶対に必要になるからということで厳しく英語の訓練を受けていた。戦争中は英語の授業が減らされたため,意外に英語がしゃべれる人が少なく,私程度の会話力でも売り込めたのである。医学生であることを店主に明言し,午前中だけは通学し,午後1時から6時までの5時間勤務で採用してもらった。月給なんと300円(当時は大学卒の普通サラリーマンの初任給が50円程度)で昼食・夕食つきであったから,丸2年間の勤務で卒業までの学費と生活費がほぼ確保される収入が見込めた。「アルバイト」という語が流行する以前の元祖アルバイターでやってきたことを,今でも誇りに思っている。
他科との連携
全身麻酔下の眼科手術時に発見された第3の足
著者: 野田康雄 , 田中住美
ページ範囲:P.879 - P.880
医療の現場には,患者さんを含めて実に多くの人達が登場します。例えば,眼科の手術について考えてみると,受持眼科医師と患者以外に,執刀眼科医師,外来看護師,眼科検査員,病棟看護師,手術部看護師がいますし,手術が全身麻酔で行われる場合には麻酔科医師が,また患者さんに持病があれば,内科医師や当該科医師も関係してきます。これらの人々が眼科手術の安全な実施という目的のためにお互いに連携し合っています。
ごく当たり前のように行われているこれらの連携の危うさを気づかせ,また十分な連携のためには,普段から意識を持っておく必要があることを再認識させる出来事を当科で経験しましたので,ご紹介したいと思います。
臨床報告
電撃傷により著明なぶどう膜炎および白内障を発症した1例
著者: 福田由美 , 杉谷倫子 , 玉田裕治 , 河野吉喜
ページ範囲:P.881 - P.884
要約 33歳男性が釣りの最中に感電し,一時的に意識を消失した。顔面,左手,両足底に電撃傷があった。2週間後に左眼結膜が充血して受診した。右眼に異常はなく,左眼に球結膜充血と軽い虹彩炎があった。その8日後に右眼に眼痛が突発し,視力が手動弁に低下した。前房内にフィブリン塊形成を伴う急性ぶどう膜炎が右眼にあった。1か月後にぶどう膜炎は消退し,視力は1.0に回復した。受傷から3か月後に進行性の前囊下,後囊下白内障が両眼に生じ,矯正視力が右0.5,左0.3になった。白内障手術で視力が回復し,以後の経過は順調である。ぶどう膜炎が電撃によって発症した稀有な症例である。
カリジノゲナーゼの網脈絡膜血流に対する影響
著者: 小林ルミ , 森和彦 , 石橋健 , 足立和加子 , 成瀬繁太 , 池田陽子 , 南條由佳子 , 木下茂
ページ範囲:P.885 - P.888
要約 末梢循環改善薬であるカリジノゲナーゼが網脈絡膜血流に及ぼす影響を,眼疾患のない10人10眼について検索した。カリジノゲナーゼを1日量150IUとして4週間経口投与し,その前後で網脈絡膜血流量を測定した。測定には,走査レーザードップラー血流計(scanning laser doppler flowmeter)を使用した。血流パラメータの値は,投与前218.7±30.9,投与後262.3±49.3であり,両者間にpaired-t検定で有意差があった(p<0.01)。カリジノゲナーゼ内服で正常者の網脈絡膜血流が増加すると結論される。
Laser in situ keratomileusis後に発症した角膜拡張症の1例
著者: 安田明弘 , 山口達夫
ページ範囲:P.889 - P.892
要約 50歳女性が左眼に近視矯正手術を4年前に受けた。手術は屈折矯正専門クリニックで行われたが,その後視力が改善しないために当科を受診した。右眼は生来弱視であった。初診時の矯正視力は右0.06,左0.5であり,右眼は-24D,左眼は-22Dの矯正で最良視力が得られた。レーシック(LASIK)が左眼に行われたと推定された。術前の屈折値,視力,矯正量は不明であった。左眼の角膜中央部は菲薄化し,中央部の角膜厚は右眼514μm,左眼358μmであった。角膜形状解析で左眼の角膜前後面が前方に突出し,角膜拡張症と診断した。左眼に対してpiggybag法でのコンタクトレンズ矯正を行い,0.9pの視力が得られた。現在の手術適応の基準から考慮すると,本症例は過剰に切除を行ったことが角膜拡張症の原因であったと解釈される。
Wegener肉芽腫症に対する免疫抑制療法中にサイトメガロウイルス網膜炎が発症した2例
著者: 高橋知美 , 大沼郁子 , 高橋栄二 , 木村智華子 , 山下英俊
ページ範囲:P.893 - P.898
要約 Wegener肉芽腫症の2患者に網膜炎が発症した。1例は25歳男性で両眼発症,他の1例は52歳男性で片眼発症であった。肉芽腫症の診断から網膜炎発症までの期間は両名とも11年であり,免疫抑制療法を受けていた。両名とも,眼底に出血を伴う黄白色の滲出性病変があり,血液と前房水からサイトメガロウイルス(CMV)DNAが検出され,サイトメガロウイルス網膜炎と診断した。血液検査でCD4/8が低値であり,免疫不全状態にあると考えられた。ガンシクロビルの硝子体内注入と徐放性ガンシクロビル硝子体移植を1例に,ガンシクロビルの点滴静注と硝子体内注入を他の1例に行い,網膜炎は寛解した。免疫療法を行っているWegener肉芽腫症にはCMVなどの感染症が併発しやすく,注意が必要なことを示す例である。
今月の表紙
つた状血管腫
著者: 西村治子 , 西田輝夫
ページ範囲:P.656 - P.656
患者は35歳の男性。人間ドックにて右眼の眼底血管異常を指摘され,近医から当科を紹介され受診した。
初診時視力は右0.09(1.2),左0.08(1.2)であった。自覚症状はなく,眼底血管異常は片眼性で,眼底後極部に動静脈の吻合が認められた。中枢神経系の異常は認められなかった。蛍光眼底造影検査でも血管からの漏出はなかった。
撮影にはコーワ社製PROI眼底カメラを用い,フィルムはコニカクローム(ISO100)を使用した。(公立昭和病院眼科 西村治子)
やさしい目で きびしい目で 41
こども病院に勤務して
著者: 山田裕子
ページ範囲:P.785 - P.785
兵庫県立こども病院に勤務して3年余りが経とうとしている。とりあえず,自分なりには一生懸命働いているつもりでいる。正直なところ,医学部に入ったころから小児眼科医を志していたというわけではない。なんとなくというのは不真面目に聞こえるかもしれないが,その時々の心境や状況の必然性から現在に至っている(言葉を換えれば,ただ流されてきたということかもしれない)。
これまでに,医師やナースになろうと思った,あるいは眼科に進もうと思った動機といった話題は,学生のころや,働き出してからも何度となく繰り返され,適当な理由が本音や建前で語られてきた。そのようななかで,幼少のころから思春期にかけて,斜視や弱視といった疾患で,この病院の眼科外来に何年と通い,手術の経験をもつ人たちに数人出会った。彼(女)らは,その多感な時期に味わった入院生活や手術,親に連れられ年に何度と受診する眼科外来での診察や検査といった経験を通じて,何かしらの感銘(もしかするとある意味トラウマなのか?)を受け,将来の進路についての意志決定には大いなる影響を与えたと語っていた。もちろん,こどもの感受性は個人差も大きいだろうし,斜視の手術をする大人の患者さんに話を聞いてみても,小さいころの手術の記憶なんてほとんど残っていない人も大勢いる。彼らはそういった意味では治療を受けた時期や期間にもよるが,めずらしく感受性豊かな人たちで,また自分の目指す進路につくことができたといった点では幸運な人たちともいえるだろう。ふと最近,自分の今の外来や手術を振り返ってみて,果たしてそのような思いをめぐらせるこどもたちがこれから現れるのだろうかと考えた。
ことば・ことば・ことば
マゼンタ
ページ範囲:P.787 - P.787
カタカナ語がまだ氾濫していなかったその昔に,最初に覚えた色の名前はカーキ色でした。「柿色」かしらと思っていたら,ペルシャ語の「泥色」khakiでした。今ではアースカラーといいますが,兵隊さんの軍服を連想するので好きではありません。
「らくだ色」のベージュbeigeは,あまり英語らしくありません。これはフランス語から入ったためで,本来は「染めていない羊毛」のことでした。
基本情報
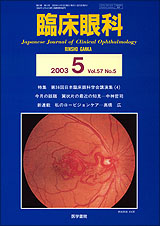
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
