白内障手術で使用する以下の3種類の灌流吸引チップを実験的に比較し,エピヌクレウスの吸引効率を評価した。ガルフチップは直径0.4mmの円形吸引孔を持ち,内径0.3mmで長さは35mmである。アスリートチップは0.2×0.5mmの長円形吸引孔を持ち,内径0.5mmで長さは47mmである。従来のチップは直径0.3mmの円形吸引孔を持ち,内径0.6mmで長さは35mmである。毎分灌流量はアスリートチップと従来のチップ間には差がなく,ガルフチップが有意に多かった(p<0.01)。毎分吸引量はガルフチップと従来のチップよりもアスリートチップが有意に多かった(p<0.01)。模擬前房での定常状態圧力値は,三者とも同じ程度に小さく低下した。吸引孔が最も大きく前房安定性を阻害しないガルフチップがエピヌクレウスの吸引に最も適していると結論される。
雑誌目次
臨床眼科58巻7号
2004年07月発行
雑誌目次
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
原著
超音波パルスモードでの創口温度に関与する因子と創口熱傷抑制に効果的な設定値の検討
著者: 石田佳子 , 西原仁 , 谷口重雄 , 中尾宗央 , 小田英夫 , 神田英典 , 松田秀幸
ページ範囲:P.1159 - P.1163
目的:頻回パルスモードでの水晶体乳化吸引術で,創口熱傷の抑制に有効な条件の設定。方法:豚眼の前房内で超音波を1分間発振し,創口付近のチップの最高温度を測定し,創口熱傷の程度を推定した。設定値は超音波出力60%,発振頻度は毎秒10~90回,超音波作動時間(デューティー)は18~100%(連続発振),吸引流量は0とした。結果:温度は超音波作動時間が上がるほど高くなり,発振頻度には関係しなかった。創口熱傷は温度が45℃以上で生じた。超音波作動時間が73%以下であると45℃には達しないか,または45℃に達するまで30秒以上を要した。結論:超音波作動時間を73%以下に設定すると,創口熱傷を抑制しやすい。
ポリープ状脈絡膜血管症(滲出型)の治療法による視力予後の比較
著者: 渡辺五郎 , 佐藤拓 , 岩崎明美 , 桜井健司 , 岸章治
ページ範囲:P.1165 - P.1169
滲出型ポリープ状脈絡膜血管症141例152眼の視力経過を検討した。男性111例122眼(78.7%),女性30例30眼(21.3%)であり,年齢は54~89歳,平均71.2±7.5歳,経過観察期間は6~72か月,平均29か月であった。111眼にレーザー光凝固を施行した。32眼ではポリープ状病巣のみを凝固し,79眼ではこれとともに異常血管網を凝固した。他の41眼には光凝固を行わなかった。対象とした152眼での最終視力は,0.5以上が78眼(51.3%),0.1~0.4が40眼(26.3%),0.1以下が34眼(22.4%)であった。最終視力と視力変化は,光凝固を行った111眼と行わない41眼との間,およびポリープ状病巣のみを凝固した32眼と異常血管網を合わせて凝固した79眼との間に,有意差はなかった。以上の結果から,滲出型ポリープ状脈絡膜血管症の視力転帰が比較的良好であり,ポリープ状病巣のみを凝固しても視力の維持改善が得られる場合があると結論される。
投影図からトレパンの位置と大きさを算出し良好な視力を得た自己角膜回転移植の1例
著者: 足羽孝治 , 目加田篤 , 長船嘉子 , 中室隆子
ページ範囲:P.1171 - P.1175
48歳男性の左眼に木片があたり,角膜中央部から周辺2方向に向かう裂傷が生じた。受傷の当日に裂傷を縫合したが,瞳孔領に角膜混濁が残った。7か月後の視力は0.2であり,自己角膜回転移植を企画した。瞳孔領に広い透明領域を得るために,前眼部写真から移植片の部位を選んだ。同様な方法に加えて縫合糸の幅を考慮し,角膜トレパンの直径を7.5mmに決定した。手術により角膜白斑は周辺部に移動し,透明な光学部が瞳孔領に確保できた。裸眼視力は2年後に1.0になり,以後3年間良好な視力を維持している。今回の方法は,自己角膜回転移植で有効な視機能を得るために有用であった。
眼脂培養によるキノロン耐性菌の検討
著者: 藤紀彦 , 田原昭彦
ページ範囲:P.1177 - P.1180
某病院の各科に入院した延べ402人の患者から眼脂を採取し,細菌を培養した。男性128人,女性274人で,平均年齢は84歳であった。細菌663株が同定され,キノロン系の抗生物質3薬剤に対する耐性を検索した。グラム陽性菌の耐性率は,対オフロキサシン60.7%,対シプロフロキサシン57.8%,対レボフロキサシン57.9%であった。グラム陰性菌の耐性率は,対オフロキサシン20.7%,対シプロフロキサシン19.8%,対レボフロキサシン10.3%であった。耐性率は3剤間に有意差がなかった。
慢性涙囊炎として加療されていた涙囊部悪性腫瘍の1例
著者: 岡奈央子 , 児玉俊夫 , 大橋裕一 , 兵頭政光 , 木藤克己
ページ範囲:P.1181 - P.1186
72歳女性が15か月前に涙囊部に腫瘤が生じ,慢性涙囊炎として治療されていた。涙囊部に腫瘍が発見されて当科を受診した。右涙囊部と右耳前部に無痛性の腫瘤があり,画像診断で涙囊部腫瘍は篩骨洞に浸潤し,ガリウムシンチグラフィで同部位に集積があった。摘出した涙囊部の腫瘍は,核異型を伴う扁平上皮様の腫瘍細胞が充実性胞巣を形成し,特殊染色で粘液産生細胞の混在があり,悪性度が高い粘液表皮癌と判断した。耳前部の腫瘍はその組織像からリンパ節転移と判断した。その2週間後に顎下リンパ節郭清術を行った。さらに放射線照射を行い,初診から17か月後の現在まで小康状態にある。急性炎症の既往がない涙囊部腫瘤では涙囊腫瘍の可能性があることを示す症例である。
ラタノプロストの副作用発現例のウノプロストンへの切り換えにおける有効性と安全性
著者: 久我紘子 , 宮内修 , 藤本尚也 , 佐藤栄寿 , 山本修一 , 武田憲夫 , 山崎広子 , 渡部美博 , 天谷健吾
ページ範囲:P.1187 - P.1191
ラタノプロスト点眼の結果として眼瞼色素沈着または多毛が生じた症例をウノプロストン点眼に切り換え,その効果と安全性を検索した。全例が原発開放隅角緑内障または正常眼圧緑内障であり,眼圧が20mmHg以下にコントロールされていた。薬剤切り換え後の経過観察は6か月以上とした。眼瞼色素沈着は,写真判定で19眼にあり,うち13眼で改善した。自覚的な色素沈着は11眼にあり,うち10眼で改善した。多毛は写真判定で13眼にあり,うち10眼で改善した。自覚的な多毛は7眼にあり,うち5眼で改善した。視力,眼圧,視野の平均値は,薬剤切り換え後の経過観察で有意な変化はなかった。ラタノプロスト点眼で生じた眼瞼色素沈着と多毛が,ウノプロストン点眼に切り換えることで改善する可能性がある。
緑内障患者の両眼開放視野における累加
著者: 山川弥生 , 庄司信行 , 河合裕美 , 筒井健太 , 清水公也
ページ範囲:P.1193 - P.1198
緑内障の両眼開放視野で累加が成立する条件を検索した。中心10°以内に視野障害があり,矯正視力が1.0以上の緑内障患者32名を対象とした。ハンフリー視野計10-2で,右眼,左眼,両眼開放それぞれにつき全点閾値を測定した。両眼開放時に重なる左右眼の各測定点の閾値を良好値と不良値とに分けた。良好値で予測した両眼視野は,両眼開放で測定した閾値と有意に相関した。不良値を5dB刻みで分け,それぞれの群で良好値と両眼開放視野の閾値を比較した。不良値が21dB以上のとき累加が生じた。左右差が4dB以内のとき,同様に累加が生じた。以上,緑内障の両眼開放視野で累加は特定の条件があるときに成立する。
8歳女児のpit macular syndromeにおける視力変化とOCT所見
著者: 鬼怒川次郎 , 志村雅彦 , 玉井信
ページ範囲:P.1199 - P.1203
8歳女児が3週間前からの左眼視力低下で受診した。7か月前の健康診断では,左右眼とも1.0の矯正視力があった。受診時の矯正視力は右1.2,左0.2であり,左眼に黄斑を中心とする漿液性網膜剝離と,乳頭に乳頭孔(pit)があった。蛍光眼底造影では,pitの部位に初期から後期にかけて過蛍光があり,網膜剝離の部位には色素貯留があった。光干渉断層計(OCT-3)で,網膜外層の網膜分離,中心窩の囊胞形成,700μmを超える漿液性網膜剝離があった。Pit-macular症候群と診断した。家族の希望で治療は行わなかった。6か月後に視力は0.5に改善し,OCTで網膜剝離と中心窩囊胞の残存と網膜分離の改善が認められた。OCTは非侵襲的であり,小児でも網膜の構造を検索することができ,本症候群では視力と関係がある網膜分離の所見を捉えることができた。
早期に手術に踏み切るべきと考えられた急激に進行したFusariumによる角膜潰瘍の1例
著者: 佐方弘哲 , 三宅太一郎 , 目加田篤
ページ範囲:P.1205 - P.1208
47歳男性に左眼眼痛が突発し,角膜異物が発見され除去した。角膜びらんが生じたが,点眼加療で6日後に軽快した。2週間後に左眼眼痛が再発し角膜びらんがあった。再発から14日目に菌糸が鏡検され,フルコナゾールとピマリシン点眼を開始した。20日目にFusarium sp.が同定され,24日目に角膜が穿孔した。40日目に保存強膜で穿孔部を被覆したが,網膜剝離と眼内炎になり内視鏡下で硝子体手術を行った。網膜は復位したが視力が光覚弁であり,角膜移植が検討されている。角膜異物後に発症した角膜炎または潰瘍では真菌感染の可能性があるので,早急に対処する必要がある。
ぶどう膜炎に対する硝子体手術成績
著者: 長澤利彦 , 内藤毅 , 四宮加容 , 塩田洋
ページ範囲:P.1209 - P.1212
過去40か月間に硝子体手術を行った非感染性ぶどう膜炎13症例17眼を回顧的に検索した。推定または確定した原因疾患は,サルコイドーシス6眼,トキソプラズマ症3眼,Vogt-小柳-原田病1眼,ベーチェット病1眼,原因不明6眼であるが,疑いを含んでいる。硝子体手術の適応になった状態は,囊胞様黄斑浮腫9眼,硝子体混濁3眼,新生血管黄斑症3眼,硝子体出血1眼,増殖性硝子体網膜症1眼であった。術後最高視力は13眼(76%)で改善し,術後最終視力は10眼(59%)で改善した。内科的療法が奏効しないぶどう膜炎に硝子体手術は有効であり,術後の消炎管理が重要であると結論される。
白内障硝子体同時手術におけるシングルピースアクリル眼内レンズの安全性
著者: 原信哉 , 櫻庭知己 , 三上尚子
ページ範囲:P.1213 - P.1217
139例193眼に,シングルピースアクリル眼内レンズを使って白内障硝子体同時手術を行った。原因疾患は増殖糖尿病網膜症,網膜静脈分枝閉塞症,黄斑円孔,網膜剝離などである。術後経過は平均8.7±6.2週観察した。192眼では眼内レンズは囊内に,1眼では毛様溝に固定された。術後の固定状態に問題はなく,炎症の程度も従来と差がなかった。後発白内障に対して後囊切開を要した症例はなかった。シングルピースアクリル眼内レンズは従来の眼内レンズの利点を保ちながら,さらに小切開創から挿入が可能であり,白内障硝子体同時手術でも安全に使用できた。
網膜細動脈瘤に対する硝子体手術および網膜光凝固術適応についての検討
著者: 加茂雅朗 , 戒田真由美 , 柏野緑 , 猪尾芳弘 , 本山貴也 , 白木邦彦
ページ範囲:P.1219 - P.1224
網膜出血が増強する傾向のない網膜細動脈瘤3例を検討し,次の結論を得た。初期出血が増加しなければ少なくとも1か月間は硝子体手術を控える。動脈瘤周囲に硬性白斑や出血が生じるか,インドシアニングリーン造影で動脈瘤に拍動があるときには,光凝固術が望ましい。出血が陳旧化して消退しないときには,内境界膜剝離を含めた硝子体手術を考慮する必要がある。
特発性黄斑円孔の臨床的特徴
著者: 大庭美智子 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.1225 - P.1229
手術を行った特発性黄斑円孔102例107眼につき,性別による病像などの違いを検索した。男性31例31眼,女性71例76眼で,有意差があった(p=0.004)。屈折値は男女とも0Dから+1.0Dが最も多く,その平均値は,男性+0.26±1.16D,女性+0.58±1.36Dで,有意差があった(p=0.0022)。男性には第3期が最も多く,女性との比較で有意差があった(p=0.0009)。SPP-Ⅱで評価した術前後の色覚には正の相関があった(p<0.0001)。年齢,術前後の視力,円孔径,眼軸長,初回閉鎖率については男女差がなかった。
眼内レンズ毛様溝縫着術7年後の遅発性眼内炎の1例
著者: 北澤憲孝 , 藤澤昇
ページ範囲:P.1231 - P.1233
85歳女性が右眼の眼痛と視力低下で緊急に受診した。22年前に白内障全摘術が行われ,7年前に毛様溝縫着による眼内レンズの2次挿入を受けていた。受診の5か月前の定期診察で1.2の矯正視力があった。緊急受診時には前房蓄膿を伴う眼内炎があり,遅発性であるにもかかわらず,自覚所見,多覚所見ともに急性術後眼内炎と同様な経過をとった。硝子体の培養で,インフルエンザ菌が分離された。感染の原因は,7年前の眼内レンズの2次挿入で使用し,8時の角膜輪部から1.5mm後方に通した10-0ポリプロピレン糸の断端が球結膜から露出していたためであると判断した。結膜上にポリプロピレン糸が露出しているときには,これを早期にレーザーで処理して断端を短くし,結膜で被覆されるような処置が望ましい。
加齢黄斑変性に対する経瞳孔温熱療法の治療成績
著者: 上松聖典 , 大庭啓介 , 北岡隆
ページ範囲:P.1235 - P.1239
加齢黄斑変性 8 眼に経瞳孔温熱療法(TTT)を行った。全例に中心窩下に脈絡膜新生血管があった。平均視力は術前 0.06,術後 0.07 であり,2 段階以上の改善が 2 眼,不変 5 眼,2 段階以上の低下が 1 眼にあった。中心窩厚は術前 535.8±58.0μm,術後 485.5±64.0μm で,有意に減少した(p<0.05)。2~6 か月,平均 4 か月の経過観察で,格別の合併症はなかった。経瞳孔温熱療法は視力を維持し,中心窩厚を減少させ,合併症がない点で有効であると評価した。視力が改善した 2 眼は発症 3 か月以内に本治療を受けていたことから,本療法を発症早期に実施すると視力改善効果が大きい可能性がある。
乳頭周囲ぶどう腫の光干渉断層計像
著者: 鈴木由美 , 川瀬英理子 , 仁科幸子 , 東範行
ページ範囲:P.1241 - P.1243
乳頭周囲ぶどう腫6眼6症例を検索した。年齢は6~18歳で,視力は0.04から1.5の範囲にあった。眼軸長は23~25mmで,乳頭陥凹の深さは2~4mmであった。光干渉断層計(OCT)では,全例で陥凹内に薄い感覚網膜があり,層構造の乱れがあった。網膜色素上皮には部分的な欠損ないし肥厚があった。従来の病理報告では,陥凹内の網膜は,朝顔症候群では肥厚し,乳頭コロボーマでは非薄であるとされている。今回のOCT所見は,乳頭周囲ぶどう腫が朝顔症候群よりもコロボーマに近いことを示している。
脈絡膜新生血管を伴った眼皮膚白子症の1例
著者: 新納麻理子 , 山口由美子 , 岸章治
ページ範囲:P.1245 - P.1249
49歳男性が5か月前からの左眼中心暗点で受診した。水平眼振,右-15D,左-11Dの近視があり,矯正視力は右0.08,左0.07であった。毛髪は白金色,虹彩は灰青色で,全身皮膚が淡紅白を呈し,眼皮膚白子症であった。左眼には後部ぶどう腫があり,出血を伴う1乳頭径大の脈絡膜新生血管が中心窩にあった。フルオレセイン蛍光造影で,新生血管は初期から過蛍光を呈し,網膜血管と脈絡膜大血管は見かけ上の低蛍光を示した。インドシアニングリーン造影で,新生血管は造影早期から後期にかけて境界明瞭な過蛍光を呈した。以後,新生血管は自然寛解の傾向を示した。初診から1年後,後部硝子体剝離に伴う裂孔原性網膜剝離が発症し,強膜内陥術を行った。その3か月後に新生血管は拡大し,黄斑出血が増強した。白子症に脈絡膜新生血管が発症した例は知られていない。本症は強度近視に続発したFuchs斑であると解釈した。
Punctate inner choroidopathyの1例
著者: 武末佳子 , 向野利寛 , 志賀宗佑
ページ範囲:P.1251 - P.1255
28歳女性が3週間前からの左眼の霧視と傍中心暗点で受診した。左右眼ともに約-6Dの近視で,矯正視力は左右とも1.5であった。左眼眼底の後極部一帯に黄白色小点が散在し,フルオレセイン蛍光造影で早期から晩期まで過蛍光を呈し,インドシアニングリーン造影では一貫して低蛍光であった。これらの所見からpunctate inner choroidopathyと診断した。1か月後に左眼視力が0.1に低下した。後極部の白点が増加し,その範囲が広がっていた。プレドニゾロン内服で視力は0.7に改善し,白色病変は瘢痕化した。初診から8か月間の観察で脈絡膜新生血管は生じていない。
結膜血管腫を合併したCrow-Fukase症候群の1例
著者: 宮河あやこ , 尾崎弘明 , 大島健司
ページ範囲:P.1267 - P.1271
47歳男性が10か月前からの右眼球結膜の腫瘤で受診した。約3年前に四肢に浮腫が生じ,さらに胸水が発見された。いったんは結核が疑われたが,全身に暗赤色の皮疹が出現し,生検でglomeruloid hemangiomaが確認された。全身的に髄液蛋白増加,甲状腺機能低下,肝腫大,血清蛋白異常などがあり,Crow-Fukase症候群と診断された。右球結膜の鼻側に,径1cm,有茎性で弾性軟の腫瘤があり,表面が痂皮で覆われていた。腫瘤切除を行い,病理学的にglomeruloid hemangiomaと診断された。本症候群で,皮膚と同じ血管腫が球結膜に生じた最初の報告例である。
硝子体腔注入シリコーンオイルの前房内への脱出をきたした症例の検討
著者: 谷口亮 , 吉田牧子 , 木下博文 , 宮村紀毅 , 北岡隆 , 雨宮次生
ページ範囲:P.1273 - P.1275
過去7年間にシリコーンオイル注入を併用した硝子体手術131眼を検討した。平均13か月間の術後観察で,前房へのシリコーンオイル脱出が39眼(29.8%)あった。原疾患は,裂孔原性網膜剝離17眼,増殖糖尿病網膜症9眼,加齢黄斑変性5眼,黄斑円孔網膜剝離2眼,穿孔性眼外傷2眼,その他4眼である。術後合併症は,シリコーンオイル脱出がある39眼では89.7%,脱出がない92眼では63.0%にあり,有意差があった(p=0.01)。続発性緑内障は脱出がある39眼では33.3%,脱出がない92眼では13.0%に生じ,有意差があった(p=0.03)。硝子体手術でシリコーンオイルタンポナーデを行うときには,前房と硝子体腔との交通を作らないことが望ましい。
シリコーンオイル注入眼のオイル貪食細胞のEDXAによる分析
著者: 岸川泰宏 , 高見由美子 , 北岡隆 , 雨宮次生 , 末松貴史 , 橋本恭子
ページ範囲:P.1277 - P.1279
シリコーンオイルを併用して硝子体手術が行われた6眼に,シリコーンオイル抜去を行い,その際に採取された増殖膜を検索した。シリコーンオイルが眼内にあった期間は3~14か月,平均9か月であった。原疾患は,加齢黄斑変性3眼,増殖糖尿病網膜症2眼,網膜剝離1眼である。増殖膜の中の貧食細胞中の空胞にX線元素分析で,そのほとんどに珪素に相当する所見が得られた。空胞付近の細胞質にはこの所見はなかった。貧食細胞に取り込まれたシリコーンオイルは分解されずに細胞内に存在し,眼内組織に影響を与え続ける可能性があると結論される。
線維柱帯切除術後裂孔原性網膜剝離に対してpneumatic retinopexyを施行した1例
著者: 藤田剛史 , 水野かほり , 中村曜祐 , 林敏信
ページ範囲:P.1281 - P.1284
77歳女性が右眼の眼圧上昇で紹介され受診した。2年前に両眼に白内障手術を受けている。矯正視力は右1.2,左1.0で,眼圧は右30mmHg,左20mmHgであった。薬物で眼圧コントロールが得られないので,マイトマイシンC併用線維柱帯切除術を行った。術後7日目に上方網膜に弁状裂孔を伴う網膜剝離が発見された。SF6によるpneumatic retinopexyを行い,網膜の復位と濾過胞の維持が得られた。Pneumatic retinopexyは,合併症と復位率について異論があるが,適応を選べば有効な治療法の1つになる。
両眼硝子体手術を行ったshaken baby syndromeの1例
著者: 川口一朗 , 白尾裕 , 小林顕 , 杉山和久 , 鳥崎真人 , 舘野靜佳 , 三浦正義 , 岡部敬 , 宮森正郎
ページ範囲:P.1285 - P.1289
生後6か月の男児に四肢硬直が突発し,画像診断で右硬膜下血腫が発見され,血腫除去が行われた。全身に外傷や骨折はなく,両親の態度にも不審がなかったので,shaken baby syndrome(揺さぶられっ子症候群)が疑われた。6日後の眼科診察で両眼に網膜と硝子体の出血が発見された。自然消退の傾向がなく,8週後に両眼に硝子体手術と水晶体切除術を行った。1年後の現在まで経過は良好である。乳幼児の眼内出血では,虐待がなく,あやしたつもりで本症候群が起こりうることを示す症例である。
黄斑下に迷入した眼内鉄片異物の1例
著者: 牛嶋美和 , 春藤真一郎 , 林一 , 松原令
ページ範囲:P.1291 - P.1293
52歳男性が草刈り機を操作中に,右眼に異物が飛入した。受傷当日の所見として,右眼視力は光覚弁で,角膜中央部に穿孔創があった。前房出血と硝子体出血のために眼底は透見不能であった。画像診断で眼内異物が同定された。硝子体手術と水晶体摘出術を行い,細長い異物が耳側上方の網膜経由で黄斑下に迷入していた。網膜裂孔の縁が不整で,その周囲に網膜下血腫があるため,裂孔経由での異物摘出は行わなかった。異物が大きいので硝子体鑷子では保持できなかった。黄斑部網膜の二次的損傷を避けるため,耳側下方の網膜に意図的に作った裂孔を経由し,眼内マグネットで異物を摘出した。異物は5×1.5×2mmの鉄片であった。眼内異物で網膜下に異物が迷入しているとき,眼内マグネットの操作は慎重に行う必要がある。
結膜悪性黒色腫の1例
著者: 平松彩子 , 四倉次郎 , 山本修一
ページ範囲:P.1295 - P.1298
56歳男性が6か月前からの左眼の腫瘤,異物感,眼痛で受診した。幼児期より左眼の球結膜に色素斑があったが,最近まで変化はなかった。左眼には,外下方の輪部に接する球結膜に茶褐色の結節性腫瘤,扁平な色素斑,色素沈着があった。これ以外には色素異常はなかった。切除した腫瘤は悪性黒色腫であることが病理組織学的に確定した。さらに広範囲球結膜切除術,冷凍凝固術,局所化学療法を行ったが,6か月後に局所再発した。再手術を行い,以後8か月間の経過は良好である。
良好な濾過胞をもつ術後50年の全層濾過手術の症例
著者: 帯刀真也 , 木許賢一 , 調枝聡治 , 中塚和夫
ページ範囲:P.1299 - P.1302
71歳男性と75歳男性が視力低下で受診した。1例は65年前に先天緑内障と診断された。1眼は摘出,他眼にはScheieの全層濾過手術が行われ,受診時の矯正視力は0.5であった。他の1例は58年前に不発弾が爆発し,1眼は失明し,他眼は5年後に外傷性緑内障と診断され,管錐術が行われた。受診時の矯正視力は手動弁であった。2例とも上方に濾過胞が形成され,白内障が進行していた。2例に白内障手術と眼内レンズ挿入術を行い,経過は良好である。過去の緑内障手術の具体像を知ることができた症例である。
男児に発症した全身性エリテマトーデスによる閉塞性網膜血管炎
著者: 大庭啓介 , 上松聖典 , 栗原潤子 , 計盛幸子 , 峰雅宣
ページ範囲:P.1303 - P.1307
14歳男児の左眼に視力低下が生じ,その当日に受診した。3日前から発熱,両足の関節痛と腫脹,顔面と足に紅色皮疹があった。矯正視力は右1.2,左0.03であり,両眼の眼底に綿花状白斑が多発していた。左眼の黄斑部に無灌流領域があった。血液検査を含む全身所見から全身性エリテマトーデス(SLE)と診断した。副腎皮質ステロイドの大量全身投与を行い,全身所見は軽快したが,眼底所見はすぐには改善しなかった。低投与量での内服を継続し,網膜血管炎は鎮静化し,側副血行路が形成され,発症から5か月後に左眼視力が0.8に回復した。男児にSLEが発症することは稀であり,重症化することがある。本症例は,抗リン脂質抗体が陰性で,亜急性型の紅斑であったことが重症化しなかった一因であると推定された。
シリコーンチューブを用いた網膜下血腫移動術
著者: 調枝聡治 , 中塚和夫 , 松本惣一 セルソ , 高木康宏
ページ範囲:P.1309 - P.1312
陳旧性の網膜下血腫4例4眼に対して,新しい手術器具を使って血腫移動術を行った。原因疾患は加齢黄斑変性症3例と網膜細動脈瘤1例で,年齢は78~91歳,すべてが女性であった。器具の先端にはJ字型のシリコーンチューブがついており,網膜上からなでるようにして血腫の移動を試みた。全症例で血腫は移動ないし減少した。視力は2例で向上し,2例では不変であった。術中,器具の操作による網膜裂孔の発生はなく,術後の重篤な合併症はなかった。本法は比較的安全で有効な術式であると結論される。
内境界膜下血腫を伴ったTerson症候群の1例
著者: 鎌田研太郎 , 阿川哲也 , 三浦雅博 , 尾﨏雅博 , 臼井正彦
ページ範囲:P.1313 - P.1317
43歳男性に左後下小脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血が発症し,クリッピング術が即日行われた。経過は良好であった。手術の翌日に両眼に硝子体出血が発見され,その5週後に当科を受診した。視力は右0.1,左手動弁であり,Terson症候群と診断した。発症から2か月後に両眼に硝子体手術を行った。左眼には陳旧性の内境界膜下血腫があり,右眼には網膜前に黄白色沈殿物があった。術後経過は良好で,左右とも1.2の最終視力を得た。Terson症候群では硝子体出血だけでなく内境界膜下に出血することがあり,これが長期化すると黄斑前膜の形成や血液分解産物による網膜機能障害が起こる可能性があるので,早期手術が望まれる。
超音波水晶体乳化吸引術中の眼内灌流液と気泡発生の検討
著者: 中静裕之 , 島田宏之 , 荒井真司 , 井上正教 , 西尾充平
ページ範囲:P.1319 - P.1323
超音波水晶体乳化吸引術中に前房に生じる気泡と灌流液との関係を検討した。灌流液にはオペガード(R)ネオキットを用い,その温度を10℃から5℃刻みで30℃までに設定し,37眼に手術を行った。気泡は3段階に分類した。温度が10℃のとき気泡が手術の障害になったが,15℃以上では軽度であった。実験的にも,灌流液の温度が低いほど気泡が多く発生した。灌流液が低温であると,使用時の温度上昇により空気の飽和溶解量が低下し,気泡が発生しやすくなると解釈した。本灌流液は15℃以上で保存して使用することが望ましいと結論される。
連載 今月の話題
黄斑部疾患に対するトリアムシノロン治療
著者: 野崎実穂 , 小椋祐一郎
ページ範囲:P.1125 - P.1131
はじめに
副腎皮質ステロイド剤は,抗炎症作用を持ち,古くから眼炎症疾患に使われていた薬剤であるが,近年,トリアムシノロンの眼局所への投与が黄斑浮腫や脈絡膜新生血管,増殖硝子体網膜症などの治療に有効と報告されてきている。ここでは,とくに従来の治療法では十分な効果がみられなかった黄斑部疾患に対するトリアムシノロン治療についてまとめる。
眼の遺伝病59
HPRP3遺伝子異常と網膜変性(1)
著者: 和田裕子 , 玉井信
ページ範囲:P.1132 - P.1134
HPRP3遺伝子は,2002年に常染色体優性網膜色素変性の原因遺伝子として報告された1,2)。この遺伝子はmRNAのsplicingに関与する遺伝子であり,HPRP3遺伝子の他にPRPF31遺伝子,PRPC8遺伝子がmRNAのsplicingに関与する常染色体優性網膜色素変性の原因遺伝子である。HPRP3遺伝子異常は,エクソン11に限局され,さらにThr494 Met変異が高頻度変異である。
今回は,Thr494 Met変異を認めた1家系を報告する。
日常みる角膜疾患16
Thygeson点状表層角膜炎
著者: 川本晃司 , 森重直行 , 西田輝夫
ページ範囲:P.1136 - P.1138
症例
患者:31歳,男性化
主訴:両眼羞明,流涙,異物感,瘙痒感
現病歴:2001年頃より両眼の羞明,流涙,異物感,瘙痒感を自覚した。近医を受診しThygeson点状表層角膜炎と診断された。0.02%フルオロメトロン点眼液(0.02%フルメトロン点眼液(R))およびヒアルロン酸ナトリウム点眼液(ヒアレイン点眼液(R))にて加療された。症状の改善が認められないため,2003年6月,当科を紹介され受診した。
既往歴・家族歴:特記すべきことはない。
初診時所見:視力は右眼0.2p(1.2×S-2.00D()C-1.00D Ax80°),左眼は0.2p(1.5×S-2.50D),眼圧は右眼9mmHg,左眼10mmHg(NCT)であった。細隙灯顕微鏡検査では両眼の角膜上皮から上皮下に及ぶ微小な点状混濁の集合体からなる混濁病変を認め(図1a,b),同部位に一致した点状のフルオレセイン染色像を認めた(図1c,d)。病巣間は透明であり,角膜実質内には細胞浸潤は認められなかった。また軽度の結膜充血を認めたものの,前房内に炎症所見は認められなかった。両眼の角膜知覚の低下は認められなかったが,涙液検査(シルマーⅠ法)では右眼4mm,左眼3mmと涙液分泌低下を認めた。フォトケラトスコープ(PKS)では角膜上皮病変部に一致してマイヤーリングの不整を認めた(図2)。共焦点角膜顕微鏡検査では,病巣に一致する角膜上皮層に高輝度・無定形の混濁病変を認めた(図3)。
臨床所見および病歴からThygeson点状表層角膜炎と診断し,0.01%リン酸ベタメタゾンナトリウム点眼液(リンデロン点眼液(R))を1日4回点眼により経過を観察した。点眼開始翌日より,病巣に一致した点状のフルオレセイン染色は減少し,病巣は徐々に上皮性の混濁を残して瘢痕化した。自覚症状も改善したことから,現在は0.02%フルオロメトロン点眼液(フルメトロン点眼液(R))の点眼で経過を観察している。
緑内障手術手技・13
周辺虹彩切除術
著者: 黒田真一郎
ページ範囲:P.1140 - P.1144
セッティング
ベッド・顕微鏡
基本的に周辺虹彩切除術(peripheral iridectomy:PI)は上方からのアプローチとなるため,ベッド,顕微鏡のセットは他の緑内障手術の上方アプローチの場合と同様に考えればよい。術野が確認しやすいように,やや顎を下げぎみに調節する。
制御糸
他の上方アプローチの緑内障手術の場合と同様,制御糸は上直筋付着部へかけ,開瞼器の上から手前に引き,眼球を下転させる(筋付着部へ制御糸を掛ける場合は,患者に下転してもらった状態で,血管の走行などから結膜を通して筋付着部を確認し,この部位を有鉤鑷子でつかみ,鑷子の下に針を通すようにすると確実である)。
あのころ あのとき42
網膜と取り組んだ40年(1)
著者: 安藤文隆
ページ範囲:P.1146 - P.1148
はじめに
私が眼科医になった昭和39年(1964)頃は,眼科医はまだ多くなく,ほとんどの医局関連病院は1人医長で運営されていた。入局して3週間経った4月下旬に,一関連病院の医長が病気で入院されたため,大学の講師と私がペアで隔日に代理診療に出向することになった。そして約1年後にはこの講師の先生が開業して名古屋を離れられたため,大学院生の身でありながら,朝,この代務病院に出かけて1日診療を行い,夕方家に帰って弁当を持ち,夜,名古屋大学の環境医学研究所に通って電気生理の勉強をする毎日となっていた。
当時は網膜剝離はまだ難病で,復位促進術には強膜短縮術が主に用いられており,術後の安静期間も長く,復位率もあまりよくはなかった。そんなある日,出張先の病院で網膜剝離症例を受け持った。気のよさそうなおばあさんで,大学に紹介すればこの人は何日も絶対安静で寝ていなければならないこと,それでも治らない場合が多いことを考えると,やるせない気持ちになった。
私は学生時代,S病院に頼まれて夜,自動車の運転手をし,眼球摘出に行くことがあった。そこで,その折など出発前の時間待ちの間に手術をみせていただいていた杉田慎一郎先生に相談してみた。そして,たまたま発行されたばかりであった“Highlight of Ophthalmology”の小冊子をいただいた。この小冊子を読んでいくうち,Custodisの強膜内陥術を知り,早速内陥材料を注文した。1966年当時はすでにCustodisが用いたPoliviorは副作用で使用されておらず,シリコーンラバーでできた太いシリコーンロッドが届けられた。このシリコーンロッドを用いて手術したところ,幸いに網膜は1度で復位した。このように,当時はまだ日本ではほとんど用いられていなかった強膜内陥術は網膜剝離の治療成績を一変させ,入局後2~3年の新人医師でも,単純症例であれば思いのままに治癒させうるとの実感を持つに至った。
他科との連携
脳神経外科との連携
著者: 宮本武
ページ範囲:P.1150 - P.1151
眼科を受診される患者さんは,当然のことですが主に視力障害の訴えで来院されます。白内障や緑内障など眼科疾患単独のことが多いのですが,糖尿病や高血圧,腎障害など全身的疾患の治療中の患者さんも多く含まれます。そのなかでも,患者さんの数としては,さほど多くはありませんが,脳神経系の疾患もかなりの関連性があることはみなさんもご存じのとおりです。そもそも眼球には視神経が網膜につながり,動眼神経,滑車神経,外転神経が外眼筋に分布し,三叉神経が知覚をつかさどり,眼瞼には顔面神経が分布しています。12の脳神経のうち,まさに半数の6つの脳神経がかかわっています。そのため,とくに脳神経外科の先生との連携は非常に大切であると考えています。
和歌山県立医科大学の眼科外来は,隣になんとその脳神経外科が位置しています。位置しているだけでは何の意味もないのですが,脳神経外科の先生はすごく親切な先生が多く,緊急の患者さんになればなるほど診察を快諾してくれます。眼科を受診された患者さんで脳腫瘍などが発見され,脳神経外科で加療していただくケースも多々あります。このようなケースを2例ほどお示しいたします。
臨床報告
ブロムフェナクナトリウムの白内障手術中の縮瞳抑制効果
著者: 大原國俊 , 大久保彰 , 宮本孝文 , 宮久保寛 , 禰津直久
ページ範囲:P.1325 - P.1328
0.1%ブロムフェナクナトリウム点眼の,白内障手術中の縮瞳抑制効果を5施設が共同して検索した。超音波乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行った32眼を対象とした。手術の2時間前から散瞳剤を30分間隔で点眼し,1時間前から30分間隔でブロムフェナクナトリウムを点眼した。術中の灌流液にはエピネフリンを加えなかった。0.1%ジクロフェナクナトリウム点眼液を同様に使用した26眼を対照とした。手術直前,超音波乳化吸引術の終了時,手術終了時の瞳孔径を手術顕微鏡下で0.25mm単位で測定した。測定した各時点の瞳孔径には両群で有意差はなく,超音波乳化吸引術終了時と手術終了時の縮瞳率にも有意差がなかった。術前に2回点眼したブロムフェナクナトリウムの手術中の縮瞳効果はジクロフェナクナトリウムと同等であると結論される。
アトピー性白内障手術4年後に眼内レンズの支持部が眼内で分離しレンズ偏位をきたした1例
著者: 河田博 , 土屋展生 , 幸田富士子 , 重枝崇志 , 征矢耕一
ページ範囲:P.1329 - P.1332
アトピー性皮膚炎がある14歳女性の右眼の過熟白内障に対して,水晶体吸引術と眼内レンズ挿入術による手術が行われた。眼内レンズは3ピースのアクリル製であった。白内障手術後の経過は良好であったが,18歳のとき,単眼複視で受診した。矯正視力は良好であった。右眼では,眼内レンズの光学部と眼支持部とが分離し,光学部が鼻下側に偏位していた。眼内レンズの入れ替え手術を行い,単眼複視は消失した。摘出した眼内レンズを走査電子顕微鏡で検索した。光学部の支持部との接合部に亀裂があり,支持部が抜け落ちたと判断された。若年者への眼内レンズ挿入術では,レンズの選択と挿入方法に慎重さが必要である。
網膜硝子体手術のクリニカルパス
著者: 中村顕彦 , 脇屋純子 , 望月泰敬 , 巣山弥生 , 久保田敏昭 , 宮崎美穂
ページ範囲:P.1333 - P.1340
網膜硝子体手術の医療チーム用クリニカルパスとして増殖糖尿病網膜症硝子体手術,網膜剝離硝子体手術,黄斑円孔手術,その他の硝子体手術,網膜剝離バックル手術の5種類のクリニカルパスを導入した。2003年1月までの1年間に,初回の網膜硝子体手術を行った患者は66名(69眼)で,クリニカルパスは69眼(100%)に使用されていた。クリニカルパス導入により術後在院日数の短縮が得られた。バリアンス(逸脱症例)は24眼(35%)に生じた。バリアンスは増殖糖尿病網膜症硝子体手術パスを用いたものが最も多く,バリアンスの原因で多かったのは硝子体出血の吸収遅延と術後眼圧上昇であった。
多剤耐性のCorynebacterium speciesが検出された角膜潰瘍の1例
著者: 岸本里栄子 , 田川義継 , 大野重昭
ページ範囲:P.1341 - P.1344
65歳,男性が左眼の視力低下と疼痛で受診した。6年前に左眼が角膜炎と診断され,以後再発を繰り返し,抗菌薬やステロイド薬の治療を受けていた。18日前に水疱性角膜症が発症していた。20年前に糖尿病が発見され加療中であったが,コントロールは不良であった。矯正視力は右1.0,左光覚弁であった。右眼に異常所見はなかった。左眼には角膜中央に円形の潰瘍があり,潰瘍底はデスメ膜瘤になっていた。眼脂と結膜充血が顕著であった。眼脂の培養でCorynebacterium sp.が検出された。薬剤感受性検査で,ペニシリン,セフェム,テトラサイクリン,グリコペプチド,クロラムフェニコール系に感受性があり,ニューキノロン,アミノグリコシド,マクロライド,リンコマイシン,ホスホマイシン系に耐性を示した。感受性のあるテトラサイクリン系の眼軟膏とセフェム系の点滴で眼脂が減少し,3か月後に角膜潰瘍は瘢痕治癒した。コントロール不良の糖尿病,ステロイド薬と抗菌薬の長期点眼,水疱性角膜症による局所のバリア機能低下が感染の誘因になったと推定された。
基本情報
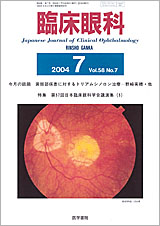
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
